複数辞典一括検索+![]()
![]()
会 あう🔗⭐🔉
【会】
 6画 人部 [二年]
区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF
【會】旧字旧字
6画 人部 [二年]
区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF
【會】旧字旧字
 13画 曰部
区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0
《常用音訓》エ/カイ/あ…う
《音読み》
13画 曰部
区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0
《常用音訓》エ/カイ/あ…う
《音読み》  カイ(ク
カイ(ク イ)
イ) /エ(
/エ( )
) 〈hu
〈hu 〉
〉 カイ(ク
カイ(ク イ)
イ) /ケ
/ケ 〈ku
〈ku i〉
《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず
《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち
《意味》
i〉
《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず
《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち
《意味》

 {名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」
{名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」
 カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕
カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕
 {動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」
{動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」
 {動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕
{動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕
 {名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」
{名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」
 {副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕
{副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕
 {副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕
{副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕
 「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕
「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕
 カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」
カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」
 {名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」
{名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」
 「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。
《解字》
「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。
《解字》
 会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。
《単語家族》
繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様)
会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。
《単語家族》
繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様) 膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。
《類義》
遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必
《異字同訓》
あう。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。
《類義》
遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必
《異字同訓》
あう。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 人部 [二年]
区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF
【會】旧字旧字
6画 人部 [二年]
区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF
【會】旧字旧字
 13画 曰部
区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0
《常用音訓》エ/カイ/あ…う
《音読み》
13画 曰部
区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0
《常用音訓》エ/カイ/あ…う
《音読み》  カイ(ク
カイ(ク イ)
イ) /エ(
/エ( )
) 〈hu
〈hu 〉
〉 カイ(ク
カイ(ク イ)
イ) /ケ
/ケ 〈ku
〈ku i〉
《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず
《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち
《意味》
i〉
《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず
《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち
《意味》

 {名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」
{名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」
 カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕
カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕
 {動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」
{動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」
 {動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕
{動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕
 {名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」
{名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」
 {副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕
{副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕
 {副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕
{副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕
 「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕
「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕
 カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」
カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」
 {名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」
{名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」
 「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。
《解字》
「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。
《解字》
 会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。
《単語家族》
繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様)
会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。
《単語家族》
繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様) 膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。
《類義》
遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必
《異字同訓》
あう。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。
《類義》
遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必
《異字同訓》
あう。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
値 あう🔗⭐🔉
【値】
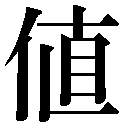 10画 人部 [六年]
区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C
《常用音訓》チ/あたい/ね
《音読み》
10画 人部 [六年]
区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C
《常用音訓》チ/あたい/ね
《音読み》  チ
チ /ジ(ヂ)
/ジ(ヂ) 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ジキ(ヂキ)
ジキ(ヂキ) /チョク
/チョク 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)
《名付け》 あう・あき・あきら
《意味》
〉
《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)
《名付け》 あう・あき・あきら
《意味》
 {名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」
{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

 {動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」
{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」
 {動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕
《解字》
会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+
{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕
《解字》
会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+ (かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる)
(かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる) 置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直
《類義》
→会・→価
《異字同訓》
あたい。 →価
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直
《類義》
→会・→価
《異字同訓》
あたい。 →価
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
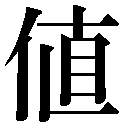 10画 人部 [六年]
区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C
《常用音訓》チ/あたい/ね
《音読み》
10画 人部 [六年]
区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C
《常用音訓》チ/あたい/ね
《音読み》  チ
チ /ジ(ヂ)
/ジ(ヂ) 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ジキ(ヂキ)
ジキ(ヂキ) /チョク
/チョク 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)
《名付け》 あう・あき・あきら
《意味》
〉
《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)
《名付け》 あう・あき・あきら
《意味》
 {名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」
{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

 {動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」
{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」
 {動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕
《解字》
会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+
{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕
《解字》
会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+ (かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる)
(かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる) 置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直
《類義》
→会・→価
《異字同訓》
あたい。 →価
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直
《類義》
→会・→価
《異字同訓》
あたい。 →価
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
合 あう🔗⭐🔉
【合】
 6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ
6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
 {動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
 {動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
 {動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
 {名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
 「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
 {単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
 {単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
 {助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
 {助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
 {名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
 会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱)
会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)
盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ
6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
 {動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
 {動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
 {動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
 {名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
 「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
 {単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
 {単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
 {助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
 {助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
 {名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
 会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱)
会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)
盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
契 あう🔗⭐🔉
【契】
 9画 大部 [常用漢字]
区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F
《常用音訓》ケイ/ちぎ…る
《音読み》
9画 大部 [常用漢字]
区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F
《常用音訓》ケイ/ちぎ…る
《音読み》  ケイ
ケイ /ケ
/ケ 〈q
〈q 〉/
〉/ ケツ
ケツ /ケチ
/ケチ 〈qi
〈qi 〉/
〉/ セツ
セツ /セチ
/セチ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ
《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ
《意味》
〉
《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ
《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ
《意味》

 {名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」
{名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」
 {動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」
{動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」
 {名}ちぎり。約束。誓い。「心契」
{名}ちぎり。約束。誓い。「心契」
 {名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕
{名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕
 {動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」
{動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」
 {動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕
{動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕
 {名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕
《解字》
{名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕
《解字》
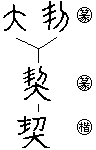 会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。
《単語家族》
割(切れ目をつける)
会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。
《単語家族》
割(切れ目をつける) 齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 大部 [常用漢字]
区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F
《常用音訓》ケイ/ちぎ…る
《音読み》
9画 大部 [常用漢字]
区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F
《常用音訓》ケイ/ちぎ…る
《音読み》  ケイ
ケイ /ケ
/ケ 〈q
〈q 〉/
〉/ ケツ
ケツ /ケチ
/ケチ 〈qi
〈qi 〉/
〉/ セツ
セツ /セチ
/セチ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ
《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ
《意味》
〉
《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ
《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ
《意味》

 {名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」
{名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」
 {動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」
{動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」
 {名}ちぎり。約束。誓い。「心契」
{名}ちぎり。約束。誓い。「心契」
 {名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕
{名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕
 {動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」
{動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」
 {動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕
{動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕
 {名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕
《解字》
{名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕
《解字》
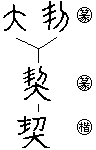 会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。
《単語家族》
割(切れ目をつける)
会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。
《単語家族》
割(切れ目をつける) 齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
媾 あう🔗⭐🔉
【媾】
 13画 女部
区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C
《音読み》 コウ
13画 女部
区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g u〉
《訓読み》 あう(あふ)/よしみ
《意味》
u〉
《訓読み》 あう(あふ)/よしみ
《意味》
 {動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」
{動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」
 {動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」
{動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」
 {名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。
《単語家族》
遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。
《単語家族》
遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 女部
区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C
《音読み》 コウ
13画 女部
区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g u〉
《訓読み》 あう(あふ)/よしみ
《意味》
u〉
《訓読み》 あう(あふ)/よしみ
《意味》
 {動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」
{動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」
 {動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」
{動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」
 {名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。
《単語家族》
遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。
《単語家族》
遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
晤 あう🔗⭐🔉
【晤】
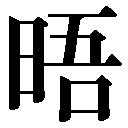 11画 日部
区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB
《音読み》 ゴ
11画 日部
区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB
《音読み》 ゴ /グ
/グ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる
《意味》
 {動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」
{動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」
 {形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」
《解字》
会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」
《解字》
会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
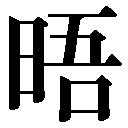 11画 日部
区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB
《音読み》 ゴ
11画 日部
区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB
《音読み》 ゴ /グ
/グ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる
《意味》
 {動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」
{動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」
 {形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」
《解字》
会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」
《解字》
会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
期 あう🔗⭐🔉
【期】
 12画 月部 [三年]
区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA
《常用音訓》キ/ゴ
《音読み》 キ
12画 月部 [三年]
区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA
《常用音訓》キ/ゴ
《音読み》 キ /ゴ
/ゴ 〈q
〈q 〉
《訓読み》 まつ/あう(あふ)
《名付け》 さね・とき・とし・のり
《意味》
〉
《訓読み》 まつ/あう(あふ)
《名付け》 さね・とき・とし・のり
《意味》
 {名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕
{名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕
 キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」
キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」
 キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕
キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕
 {名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕
{名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕
 {名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」
{名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」
 「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其
《単語家族》
旗(四角いはた)
「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其
《単語家族》
旗(四角いはた) 碁(四角いごばん)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
碁(四角いごばん)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 月部 [三年]
区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA
《常用音訓》キ/ゴ
《音読み》 キ
12画 月部 [三年]
区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA
《常用音訓》キ/ゴ
《音読み》 キ /ゴ
/ゴ 〈q
〈q 〉
《訓読み》 まつ/あう(あふ)
《名付け》 さね・とき・とし・のり
《意味》
〉
《訓読み》 まつ/あう(あふ)
《名付け》 さね・とき・とし・のり
《意味》
 {名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕
{名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕
 キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」
キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」
 キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕
キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕
 {名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕
{名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕
 {名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」
{名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」
 「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其
《単語家族》
旗(四角いはた)
「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其
《単語家族》
旗(四角いはた) 碁(四角いごばん)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
碁(四角いごばん)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
翕 あう🔗⭐🔉
荅 あう🔗⭐🔉
【荅】
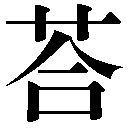 9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ)
9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)
/トウ(トフ) 〈d
〈d ・d
・d 〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
 {名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
 {動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
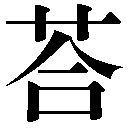 9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ)
9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)
/トウ(トフ) 〈d
〈d ・d
・d 〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
 {名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
 {動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
覯 あう🔗⭐🔉
【覯】
 17画 見部
区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651
《音読み》 コウ
17画 見部
区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g u〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
u〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
 {動}あう(アフ)。思いがけなくであう。
{動}あう(アフ)。思いがけなくであう。
 {動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。
《熟語》
→下付・中付語
{動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。
《熟語》
→下付・中付語
 17画 見部
区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651
《音読み》 コウ
17画 見部
区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g u〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
u〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
 {動}あう(アフ)。思いがけなくであう。
{動}あう(アフ)。思いがけなくであう。
 {動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。
《熟語》
→下付・中付語
{動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。
《熟語》
→下付・中付語
覿 あう🔗⭐🔉
逢 あう🔗⭐🔉
【逢】
 10画
10画  部
区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7
《音読み》 ホウ
部
区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7
《音読み》 ホウ /ブ
/ブ 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
 {動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕
{動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕
 ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕
ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕
 {動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」
{動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」
 「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp
「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、
ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、 (すすむ)を加えた字。
《単語家族》
峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山)
(すすむ)を加えた字。
《単語家族》
峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山) 縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画
10画  部
区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7
《音読み》 ホウ
部
区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7
《音読み》 ホウ /ブ
/ブ 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
 {動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕
{動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕
 ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕
ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕
 {動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」
{動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」
 「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp
「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、
ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、 (すすむ)を加えた字。
《単語家族》
峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山)
(すすむ)を加えた字。
《単語家族》
峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山) 縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遇 あう🔗⭐🔉
【遇】
 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6
《常用音訓》グウ
《音読み》 グウ
部 [常用漢字]
区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6
《常用音訓》グウ
《音読み》 グウ /グ
/グ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あう(あふ)/たまたま
《名付け》 あい・あう・はる
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/たまたま
《名付け》 あい・あう・はる
《意味》
 {動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕
{動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕
 グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」
グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」
 {名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」
{名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」
 {副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」
《解字》
会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「
{副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」
《解字》
会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「 (足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。
《単語家族》
偶グウ(ペアをなす二人)
(足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。
《単語家族》
偶グウ(ペアをなす二人) 隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6
《常用音訓》グウ
《音読み》 グウ
部 [常用漢字]
区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6
《常用音訓》グウ
《音読み》 グウ /グ
/グ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あう(あふ)/たまたま
《名付け》 あい・あう・はる
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/たまたま
《名付け》 あい・あう・はる
《意味》
 {動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕
{動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕
 グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」
グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」
 {名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」
{名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」
 {副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」
《解字》
会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「
{副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」
《解字》
会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「 (足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。
《単語家族》
偶グウ(ペアをなす二人)
(足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。
《単語家族》
偶グウ(ペアをなす二人) 隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。
《類義》
→会
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遘 あう🔗⭐🔉
遭 あう🔗⭐🔉
【遭】
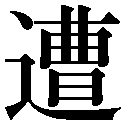 14画
14画  部 [常用漢字]
区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198
《常用音訓》ソウ/あ…う
《音読み》 ソウ(サウ)
部 [常用漢字]
区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198
《常用音訓》ソウ/あ…う
《音読み》 ソウ(サウ)
 〈z
〈z o〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
 {動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕
{動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕
 {単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」
{単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」
 {動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」
《解字》
会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「
{動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」
《解字》
会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「 (進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。
《単語家族》
糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 →合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
(進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。
《単語家族》
糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 →合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
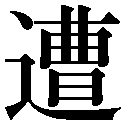 14画
14画  部 [常用漢字]
区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198
《常用音訓》ソウ/あ…う
《音読み》 ソウ(サウ)
部 [常用漢字]
区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198
《常用音訓》ソウ/あ…う
《音読み》 ソウ(サウ)
 〈z
〈z o〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 あう(あふ)
《意味》
 {動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕
{動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕
 {単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」
{単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」
 {動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」
《解字》
会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「
{動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」
《解字》
会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「 (進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。
《単語家族》
糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 →合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
(進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。
《単語家族》
糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 →合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
饗 あう🔗⭐🔉
【饗】
 20画 食部
区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0
《音読み》 キョウ(キャウ)
20画 食部
区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0
《音読み》 キョウ(キャウ) /コウ(カウ)
/コウ(カウ) 〈xi
〈xi ng〉
《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)
《意味》
ng〉
《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)
《意味》
 キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」
キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」
 キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕
キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕
 {動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。
《単語家族》
向
{動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。
《単語家族》
向 嚮キョウ(向かう)
嚮キョウ(向かう) 郷(向かいあった隣村)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
郷(向かいあった隣村)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 20画 食部
区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0
《音読み》 キョウ(キャウ)
20画 食部
区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0
《音読み》 キョウ(キャウ) /コウ(カウ)
/コウ(カウ) 〈xi
〈xi ng〉
《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)
《意味》
ng〉
《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)
《意味》
 キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」
キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」
 キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕
キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕
 {動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。
《単語家族》
向
{動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。
《単語家族》
向 嚮キョウ(向かう)
嚮キョウ(向かう) 郷(向かいあった隣村)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
郷(向かいあった隣村)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「あう」で完全一致するの検索結果 1-16。
 12画 羽部
区点=7037 16進=6645 シフトJIS=E3C3
《音読み》 キュウ(キフ)
12画 羽部
区点=7037 16進=6645 シフトJIS=E3C3
《音読み》 キュウ(キフ) 22画 見部
区点=7522 16進=6B36 シフトJIS=E655
《音読み》 テキ
22画 見部
区点=7522 16進=6B36 シフトJIS=E655
《音読み》 テキ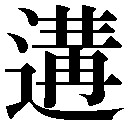 14画
14画