複数辞典一括検索+![]()
![]()
他端 タタン🔗⭐🔉
【他端】
タタン  物のほかのはし。
物のほかのはし。 ほかの端緒。物事がおこる別のきっかけのこと。
ほかの端緒。物事がおこる別のきっかけのこと。 それ以外のよい方針や手段。
それ以外のよい方針や手段。
 物のほかのはし。
物のほかのはし。 ほかの端緒。物事がおこる別のきっかけのこと。
ほかの端緒。物事がおこる別のきっかけのこと。 それ以外のよい方針や手段。
それ以外のよい方針や手段。
佇 たたずむ🔗⭐🔉
叩 たたく🔗⭐🔉
【叩】
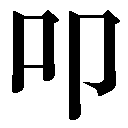 5画 口部
区点=3501 16進=4321 シフトJIS=9240
《音読み》 コウ
5画 口部
区点=3501 16進=4321 シフトJIS=9240
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈k
〈k u〉
《訓読み》 たたく/ひかえる(ひかふ)
《意味》
u〉
《訓読み》 たたく/ひかえる(ひかふ)
《意味》
 {動}たたく。こつこつとたたく。ノックする。〈類義語〉→敲コウ。「叩門=門ヲ叩ク」「我叩其両端=我ソノ両端ヲ叩ク」〔→論語〕
{動}たたく。こつこつとたたく。ノックする。〈類義語〉→敲コウ。「叩門=門ヲ叩ク」「我叩其両端=我ソノ両端ヲ叩ク」〔→論語〕
 {動}ひれ伏して、頭で地面をたたくようにおじぎする。「叩首コウシュ」「叩頭コウトウ」
{動}ひれ伏して、頭で地面をたたくようにおじぎする。「叩首コウシュ」「叩頭コウトウ」
 {動}ひかえる(ヒカフ)。ぐっと、うしろへ引く。〈類義語〉→控。▽扣コウ(ひかえる)に当てた用法。「伯夷叔斉叩馬而諫=伯夷、叔斉、馬ヲ叩ヘテ諫ム」〔→史記〕
《解字》
形声。卩印は、人間の動作を示す。叩は「卩(人のひざまずいた姿)+音符口」。扣コウと通用する。
《単語家族》
殻(こつこつとたたく)と同系。
《類義》
→打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ひかえる(ヒカフ)。ぐっと、うしろへ引く。〈類義語〉→控。▽扣コウ(ひかえる)に当てた用法。「伯夷叔斉叩馬而諫=伯夷、叔斉、馬ヲ叩ヘテ諫ム」〔→史記〕
《解字》
形声。卩印は、人間の動作を示す。叩は「卩(人のひざまずいた姿)+音符口」。扣コウと通用する。
《単語家族》
殻(こつこつとたたく)と同系。
《類義》
→打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
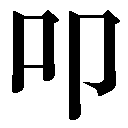 5画 口部
区点=3501 16進=4321 シフトJIS=9240
《音読み》 コウ
5画 口部
区点=3501 16進=4321 シフトJIS=9240
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈k
〈k u〉
《訓読み》 たたく/ひかえる(ひかふ)
《意味》
u〉
《訓読み》 たたく/ひかえる(ひかふ)
《意味》
 {動}たたく。こつこつとたたく。ノックする。〈類義語〉→敲コウ。「叩門=門ヲ叩ク」「我叩其両端=我ソノ両端ヲ叩ク」〔→論語〕
{動}たたく。こつこつとたたく。ノックする。〈類義語〉→敲コウ。「叩門=門ヲ叩ク」「我叩其両端=我ソノ両端ヲ叩ク」〔→論語〕
 {動}ひれ伏して、頭で地面をたたくようにおじぎする。「叩首コウシュ」「叩頭コウトウ」
{動}ひれ伏して、頭で地面をたたくようにおじぎする。「叩首コウシュ」「叩頭コウトウ」
 {動}ひかえる(ヒカフ)。ぐっと、うしろへ引く。〈類義語〉→控。▽扣コウ(ひかえる)に当てた用法。「伯夷叔斉叩馬而諫=伯夷、叔斉、馬ヲ叩ヘテ諫ム」〔→史記〕
《解字》
形声。卩印は、人間の動作を示す。叩は「卩(人のひざまずいた姿)+音符口」。扣コウと通用する。
《単語家族》
殻(こつこつとたたく)と同系。
《類義》
→打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ひかえる(ヒカフ)。ぐっと、うしろへ引く。〈類義語〉→控。▽扣コウ(ひかえる)に当てた用法。「伯夷叔斉叩馬而諫=伯夷、叔斉、馬ヲ叩ヘテ諫ム」〔→史記〕
《解字》
形声。卩印は、人間の動作を示す。叩は「卩(人のひざまずいた姿)+音符口」。扣コウと通用する。
《単語家族》
殻(こつこつとたたく)と同系。
《類義》
→打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
咤咤 タタ🔗⭐🔉
【咤咤】
タタ 怒る声の形容。
塔塔児 タタール🔗⭐🔉
【塔塔児】
タタール  中国北方にいて明ミン代に有力となったモンゴル系の遊牧民族の名。のちに、モンゴル族の総称ともなった。韃靼ダッタン。
中国北方にいて明ミン代に有力となったモンゴル系の遊牧民族の名。のちに、モンゴル族の総称ともなった。韃靼ダッタン。 中国の少数民族の名。新疆維吾爾シンキョウウイグル自治区に住む。塔塔児族。
中国の少数民族の名。新疆維吾爾シンキョウウイグル自治区に住む。塔塔児族。
 中国北方にいて明ミン代に有力となったモンゴル系の遊牧民族の名。のちに、モンゴル族の総称ともなった。韃靼ダッタン。
中国北方にいて明ミン代に有力となったモンゴル系の遊牧民族の名。のちに、モンゴル族の総称ともなった。韃靼ダッタン。 中国の少数民族の名。新疆維吾爾シンキョウウイグル自治区に住む。塔塔児族。
中国の少数民族の名。新疆維吾爾シンキョウウイグル自治区に住む。塔塔児族。
多多 タタ🔗⭐🔉
【多多】
タタ 数の多いこと。▽二字重ねて意味を強める。
多端 タタン🔗⭐🔉
【多端】
タタン こまごました仕事がたくさんあって忙しい。
戦 たたかい🔗⭐🔉
【戦】
 13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
 16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
 {動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
 {名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる)
{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる) 扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
13画 戈部 [四年]
区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED
【戰】旧字人名に使える旧字
 16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
16画 戈部
区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44
《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う
《音読み》 セン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
n〉
《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)
《意味》
 {動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕
 {名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる)
{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」
《解字》
会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。
→単
《単語家族》
殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる) 扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。
《類義》
→震・→闘
《異字同訓》
たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
扣 たたく🔗⭐🔉
【扣】
 6画
6画  部
区点=5711 16進=592B シフトJIS=9D4A
《音読み》 コウ
部
区点=5711 16進=592B シフトJIS=9D4A
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈k
〈k u〉
《訓読み》 ひかえる(ひかふ)/ひく/たたく
《意味》
u〉
《訓読み》 ひかえる(ひかふ)/ひく/たたく
《意味》
 {動}ひかえる(ヒカフ)。ひく。ひき止める。前進するものを押さえてうしろにひっぱる。〈類義語〉→控。「扣馬=馬ヲ扣フ」
{動}ひかえる(ヒカフ)。ひく。ひき止める。前進するものを押さえてうしろにひっぱる。〈類義語〉→控。「扣馬=馬ヲ扣フ」
 {動}たたく。こつこつと打つ。ノックする。〈同義語〉→叩コウ。「扣門=門ヲ扣ク」「扣舷而歌之=舷ヲ扣キテコレヲ歌フ」〔→蘇軾〕
{動}たたく。こつこつと打つ。ノックする。〈同義語〉→叩コウ。「扣門=門ヲ扣ク」「扣舷而歌之=舷ヲ扣キテコレヲ歌フ」〔→蘇軾〕
 {動・名}〔俗〕割りびく。また、割引。〈類義語〉→折。「折扣セッコウ(割引)」
{動・名}〔俗〕割りびく。また、割引。〈類義語〉→折。「折扣セッコウ(割引)」
 {名}〔俗〕ひっかけて止めるボタンや止め金。〈同義語〉→鉤コウ。「帯扣タイコウ(=帯鉤。帯の止め金)」
《解字》
会意兼形声。口は、くぼんだ穴。うしろや下にくぼむ意を含む。扣は「手+音符口」で、進むものを引き止めて、うしろにくぼませる。つまり、ひかえることをあらわす。▽控(ひかえる)はその語尾が伸びた語。また殻(かたい物でこつんとたたく)や叩コウ(こつんとたたく)に当てる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}〔俗〕ひっかけて止めるボタンや止め金。〈同義語〉→鉤コウ。「帯扣タイコウ(=帯鉤。帯の止め金)」
《解字》
会意兼形声。口は、くぼんだ穴。うしろや下にくぼむ意を含む。扣は「手+音符口」で、進むものを引き止めて、うしろにくぼませる。つまり、ひかえることをあらわす。▽控(ひかえる)はその語尾が伸びた語。また殻(かたい物でこつんとたたく)や叩コウ(こつんとたたく)に当てる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画
6画  部
区点=5711 16進=592B シフトJIS=9D4A
《音読み》 コウ
部
区点=5711 16進=592B シフトJIS=9D4A
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈k
〈k u〉
《訓読み》 ひかえる(ひかふ)/ひく/たたく
《意味》
u〉
《訓読み》 ひかえる(ひかふ)/ひく/たたく
《意味》
 {動}ひかえる(ヒカフ)。ひく。ひき止める。前進するものを押さえてうしろにひっぱる。〈類義語〉→控。「扣馬=馬ヲ扣フ」
{動}ひかえる(ヒカフ)。ひく。ひき止める。前進するものを押さえてうしろにひっぱる。〈類義語〉→控。「扣馬=馬ヲ扣フ」
 {動}たたく。こつこつと打つ。ノックする。〈同義語〉→叩コウ。「扣門=門ヲ扣ク」「扣舷而歌之=舷ヲ扣キテコレヲ歌フ」〔→蘇軾〕
{動}たたく。こつこつと打つ。ノックする。〈同義語〉→叩コウ。「扣門=門ヲ扣ク」「扣舷而歌之=舷ヲ扣キテコレヲ歌フ」〔→蘇軾〕
 {動・名}〔俗〕割りびく。また、割引。〈類義語〉→折。「折扣セッコウ(割引)」
{動・名}〔俗〕割りびく。また、割引。〈類義語〉→折。「折扣セッコウ(割引)」
 {名}〔俗〕ひっかけて止めるボタンや止め金。〈同義語〉→鉤コウ。「帯扣タイコウ(=帯鉤。帯の止め金)」
《解字》
会意兼形声。口は、くぼんだ穴。うしろや下にくぼむ意を含む。扣は「手+音符口」で、進むものを引き止めて、うしろにくぼませる。つまり、ひかえることをあらわす。▽控(ひかえる)はその語尾が伸びた語。また殻(かたい物でこつんとたたく)や叩コウ(こつんとたたく)に当てる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}〔俗〕ひっかけて止めるボタンや止め金。〈同義語〉→鉤コウ。「帯扣タイコウ(=帯鉤。帯の止め金)」
《解字》
会意兼形声。口は、くぼんだ穴。うしろや下にくぼむ意を含む。扣は「手+音符口」で、進むものを引き止めて、うしろにくぼませる。つまり、ひかえることをあらわす。▽控(ひかえる)はその語尾が伸びた語。また殻(かたい物でこつんとたたく)や叩コウ(こつんとたたく)に当てる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
摺 たたむ🔗⭐🔉
【摺】
 14画
14画  部
区点=3202 16進=4022 シフトJIS=90A0
《音読み》
部
区点=3202 16進=4022 シフトJIS=90A0
《音読み》  ショウ(セフ)
ショウ(セフ)
 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ロウ(ラフ)
ロウ(ラフ) /ロウ(ロフ)
/ロウ(ロフ) 《訓読み》 たたむ/ひしぐ/する/すり
《意味》
《訓読み》 たたむ/ひしぐ/する/すり
《意味》

 {動}たたむ。紙や布を折り重ねてたたむ。〈類義語〉→畳。
{動}たたむ。紙や布を折り重ねてたたむ。〈類義語〉→畳。
 {名}折りたたんだ文書。〈類義語〉→帖ジョウ。「手摺シュショウ(たたんだ文書)」「奏摺ソウショウ(上奏する文書)」
{名}折りたたんだ文書。〈類義語〉→帖ジョウ。「手摺シュショウ(たたんだ文書)」「奏摺ソウショウ(上奏する文書)」
 {動}ひしぐ。引っぱって折る。〈同義語〉→拉。「摺脇ロウキョウ(わきの骨をひしぐ)」
〔国〕する。すり。紙を重ねて印刷する。また、その物。〈類義語〉→刷。「石摺イシズリ」
《解字》
会意兼形声。習は、羽を重ねること。摺は「手+音符習」で、折り重ねること。
《単語家族》
畳(たたむ)
{動}ひしぐ。引っぱって折る。〈同義語〉→拉。「摺脇ロウキョウ(わきの骨をひしぐ)」
〔国〕する。すり。紙を重ねて印刷する。また、その物。〈類義語〉→刷。「石摺イシズリ」
《解字》
会意兼形声。習は、羽を重ねること。摺は「手+音符習」で、折り重ねること。
《単語家族》
畳(たたむ) 帖(紙をたたんだもの)
帖(紙をたたんだもの) 褶シュウ(たたんだひだ)と同系。
《熟語》
→熟語
褶シュウ(たたんだひだ)と同系。
《熟語》
→熟語
 14画
14画  部
区点=3202 16進=4022 シフトJIS=90A0
《音読み》
部
区点=3202 16進=4022 シフトJIS=90A0
《音読み》  ショウ(セフ)
ショウ(セフ)
 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ロウ(ラフ)
ロウ(ラフ) /ロウ(ロフ)
/ロウ(ロフ) 《訓読み》 たたむ/ひしぐ/する/すり
《意味》
《訓読み》 たたむ/ひしぐ/する/すり
《意味》

 {動}たたむ。紙や布を折り重ねてたたむ。〈類義語〉→畳。
{動}たたむ。紙や布を折り重ねてたたむ。〈類義語〉→畳。
 {名}折りたたんだ文書。〈類義語〉→帖ジョウ。「手摺シュショウ(たたんだ文書)」「奏摺ソウショウ(上奏する文書)」
{名}折りたたんだ文書。〈類義語〉→帖ジョウ。「手摺シュショウ(たたんだ文書)」「奏摺ソウショウ(上奏する文書)」
 {動}ひしぐ。引っぱって折る。〈同義語〉→拉。「摺脇ロウキョウ(わきの骨をひしぐ)」
〔国〕する。すり。紙を重ねて印刷する。また、その物。〈類義語〉→刷。「石摺イシズリ」
《解字》
会意兼形声。習は、羽を重ねること。摺は「手+音符習」で、折り重ねること。
《単語家族》
畳(たたむ)
{動}ひしぐ。引っぱって折る。〈同義語〉→拉。「摺脇ロウキョウ(わきの骨をひしぐ)」
〔国〕する。すり。紙を重ねて印刷する。また、その物。〈類義語〉→刷。「石摺イシズリ」
《解字》
会意兼形声。習は、羽を重ねること。摺は「手+音符習」で、折り重ねること。
《単語家族》
畳(たたむ) 帖(紙をたたんだもの)
帖(紙をたたんだもの) 褶シュウ(たたんだひだ)と同系。
《熟語》
→熟語
褶シュウ(たたんだひだ)と同系。
《熟語》
→熟語
攴 たたく🔗⭐🔉
【攴】
 4画 攴部
区点=5829 16進=5A3D シフトJIS=9DBB
《音読み》 ボク
4画 攴部
区点=5829 16進=5A3D シフトJIS=9DBB
《音読み》 ボク /ホク
/ホク
 〈p
〈p 〉
《訓読み》 うつ/たたく
《意味》
{動}うつ。たたく。ぽんとたたく。〈同義語〉→撲。
《解字》
〉
《訓読み》 うつ/たたく
《意味》
{動}うつ。たたく。ぽんとたたく。〈同義語〉→撲。
《解字》
 会意。「卜+又(て)」で、棒を手に持ってぽんとたたくさまを示す。のち、攵とも書く。改・教などの右側に含まれ、広く動詞を示す記号に用いられる。
会意。「卜+又(て)」で、棒を手に持ってぽんとたたくさまを示す。のち、攵とも書く。改・教などの右側に含まれ、広く動詞を示す記号に用いられる。
 4画 攴部
区点=5829 16進=5A3D シフトJIS=9DBB
《音読み》 ボク
4画 攴部
区点=5829 16進=5A3D シフトJIS=9DBB
《音読み》 ボク /ホク
/ホク
 〈p
〈p 〉
《訓読み》 うつ/たたく
《意味》
{動}うつ。たたく。ぽんとたたく。〈同義語〉→撲。
《解字》
〉
《訓読み》 うつ/たたく
《意味》
{動}うつ。たたく。ぽんとたたく。〈同義語〉→撲。
《解字》
 会意。「卜+又(て)」で、棒を手に持ってぽんとたたくさまを示す。のち、攵とも書く。改・教などの右側に含まれ、広く動詞を示す記号に用いられる。
会意。「卜+又(て)」で、棒を手に持ってぽんとたたくさまを示す。のち、攵とも書く。改・教などの右側に含まれ、広く動詞を示す記号に用いられる。
敲 たたく🔗⭐🔉
斗 たたかう🔗⭐🔉
【斗】
 4画 斗部 [常用漢字]
区点=3745 16進=454D シフトJIS=936C
《常用音訓》ト
《音読み》 ト
4画 斗部 [常用漢字]
区点=3745 16進=454D シフトJIS=936C
《常用音訓》ト
《音読み》 ト /ツ
/ツ /トウ
/トウ 〈d
〈d u・d
u・d u〉
《訓読み》 ひしゃく/にわかに(にはかに)/たたかう(たたかふ)
《名付け》 け・はかる・はるか・ほし・ます
《意味》
u〉
《訓読み》 ひしゃく/にわかに(にはかに)/たたかう(たたかふ)
《名付け》 け・はかる・はるか・ほし・ます
《意味》
 {名}ひしゃく。液体をすくう柄つきのひしゃく。また、転じて、液体の量をはかる角型・円型のます。「玉斗ギョクト(酒をくむ玉のひしゃく)」「熨斗ウット(ひのし)」
{名}ひしゃく。液体をすくう柄つきのひしゃく。また、転じて、液体の量をはかる角型・円型のます。「玉斗ギョクト(酒をくむ玉のひしゃく)」「熨斗ウット(ひのし)」
 {単位}容量の単位。一斗は十升。▽一斗は、周代には約一・九四リットル。隋ズイ・唐代には約六リットル。清シン代には約一〇リットル。日本の一斗は約一八リットル。「五斗米(わずかな俸禄ホウロクのたとえ)」
{単位}容量の単位。一斗は十升。▽一斗は、周代には約一・九四リットル。隋ズイ・唐代には約六リットル。清シン代には約一〇リットル。日本の一斗は約一八リットル。「五斗米(わずかな俸禄ホウロクのたとえ)」
 {名}ひしゃくの形をした星座。「北斗」「南斗」
{名}ひしゃくの形をした星座。「北斗」「南斗」
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のいて座にふくまれる。ひつき。
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のいて座にふくまれる。ひつき。
 {形}小さいさま。また、わずかなさま。「斗城トジョウ(小さな城)」
{形}小さいさま。また、わずかなさま。「斗城トジョウ(小さな城)」
 {副}にわかに(ニハカニ)。にわかに、はっとの意をあらわすことば。▽突に当てた用法。「斗然」
{副}にわかに(ニハカニ)。にわかに、はっとの意をあらわすことば。▽突に当てた用法。「斗然」
 {動}〔俗〕たたかう(タタカフ)。▽闘に当てた用法。
{動}〔俗〕たたかう(タタカフ)。▽闘に当てた用法。
 「科斗カト」とは、おたまじゃくしのこと。「科斗文字(初画がまるく、そのあとは尾を引いたおたまじゃくしのような形をした古代文字)」
《解字》
「科斗カト」とは、おたまじゃくしのこと。「科斗文字(初画がまるく、そのあとは尾を引いたおたまじゃくしのような形をした古代文字)」
《解字》
 象形。柄のたったひしゃくを描いたもの。柄がまっすぐたつさまに着目した、豆トウ(つきたつたかつき)
象形。柄のたったひしゃくを描いたもの。柄がまっすぐたつさまに着目した、豆トウ(つきたつたかつき) 頭トウ(まっすぐにたつあたま)などと同系とみてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
頭トウ(まっすぐにたつあたま)などと同系とみてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 4画 斗部 [常用漢字]
区点=3745 16進=454D シフトJIS=936C
《常用音訓》ト
《音読み》 ト
4画 斗部 [常用漢字]
区点=3745 16進=454D シフトJIS=936C
《常用音訓》ト
《音読み》 ト /ツ
/ツ /トウ
/トウ 〈d
〈d u・d
u・d u〉
《訓読み》 ひしゃく/にわかに(にはかに)/たたかう(たたかふ)
《名付け》 け・はかる・はるか・ほし・ます
《意味》
u〉
《訓読み》 ひしゃく/にわかに(にはかに)/たたかう(たたかふ)
《名付け》 け・はかる・はるか・ほし・ます
《意味》
 {名}ひしゃく。液体をすくう柄つきのひしゃく。また、転じて、液体の量をはかる角型・円型のます。「玉斗ギョクト(酒をくむ玉のひしゃく)」「熨斗ウット(ひのし)」
{名}ひしゃく。液体をすくう柄つきのひしゃく。また、転じて、液体の量をはかる角型・円型のます。「玉斗ギョクト(酒をくむ玉のひしゃく)」「熨斗ウット(ひのし)」
 {単位}容量の単位。一斗は十升。▽一斗は、周代には約一・九四リットル。隋ズイ・唐代には約六リットル。清シン代には約一〇リットル。日本の一斗は約一八リットル。「五斗米(わずかな俸禄ホウロクのたとえ)」
{単位}容量の単位。一斗は十升。▽一斗は、周代には約一・九四リットル。隋ズイ・唐代には約六リットル。清シン代には約一〇リットル。日本の一斗は約一八リットル。「五斗米(わずかな俸禄ホウロクのたとえ)」
 {名}ひしゃくの形をした星座。「北斗」「南斗」
{名}ひしゃくの形をした星座。「北斗」「南斗」
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のいて座にふくまれる。ひつき。
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のいて座にふくまれる。ひつき。
 {形}小さいさま。また、わずかなさま。「斗城トジョウ(小さな城)」
{形}小さいさま。また、わずかなさま。「斗城トジョウ(小さな城)」
 {副}にわかに(ニハカニ)。にわかに、はっとの意をあらわすことば。▽突に当てた用法。「斗然」
{副}にわかに(ニハカニ)。にわかに、はっとの意をあらわすことば。▽突に当てた用法。「斗然」
 {動}〔俗〕たたかう(タタカフ)。▽闘に当てた用法。
{動}〔俗〕たたかう(タタカフ)。▽闘に当てた用法。
 「科斗カト」とは、おたまじゃくしのこと。「科斗文字(初画がまるく、そのあとは尾を引いたおたまじゃくしのような形をした古代文字)」
《解字》
「科斗カト」とは、おたまじゃくしのこと。「科斗文字(初画がまるく、そのあとは尾を引いたおたまじゃくしのような形をした古代文字)」
《解字》
 象形。柄のたったひしゃくを描いたもの。柄がまっすぐたつさまに着目した、豆トウ(つきたつたかつき)
象形。柄のたったひしゃくを描いたもの。柄がまっすぐたつさまに着目した、豆トウ(つきたつたかつき) 頭トウ(まっすぐにたつあたま)などと同系とみてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
頭トウ(まっすぐにたつあたま)などと同系とみてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
湛 たたえる🔗⭐🔉
【湛】
 12画 水部
区点=3525 16進=4339 シフトJIS=9258
《音読み》
12画 水部
区点=3525 16進=4339 シフトJIS=9258
《音読み》  タン(タム)
タン(タム) /デン(デム)
/デン(デム) 〈zh
〈zh n〉/
n〉/ チン(チム)
チン(チム) /ジン(ヂム)
/ジン(ヂム)
 タン(タム)
タン(タム) /トン(トム)
/トン(トム) 《訓読み》 たたえる(たたふ)/ひたす/しずむ(しづむ)/ふかい(ふかし)/ふける
《意味》
《訓読み》 たたえる(たたふ)/ひたす/しずむ(しづむ)/ふかい(ふかし)/ふける
《意味》

 {動}たたえる(タタフ)。水がふかく満ちている。
{動}たたえる(タタフ)。水がふかく満ちている。
 {形}ふかくしずかなさま。ふかく澄んでいるさま。「清湛セイタン」
{形}ふかくしずかなさま。ふかく澄んでいるさま。「清湛セイタン」

 {動}ひたす。しずむ(シヅム)。ものをふかくしずめる。〈同義語〉→沈。〈対語〉→浮。「然則荊軻之湛七族=然ラバ則チ荊軻ノ七族ヲ湛メラル」〔→史記〕「湛諸美酒=コレヲ美酒ニ湛ス」〔→礼記〕
{動}ひたす。しずむ(シヅム)。ものをふかくしずめる。〈同義語〉→沈。〈対語〉→浮。「然則荊軻之湛七族=然ラバ則チ荊軻ノ七族ヲ湛メラル」〔→史記〕「湛諸美酒=コレヲ美酒ニ湛ス」〔→礼記〕
 {形}ふかい(フカシ)。〈類義語〉→深。
{形}ふかい(フカシ)。〈類義語〉→深。
 {動}ふける。酒色のふかみにはまりこむ。〈同義語〉→耽タン・→酖チン。「湛酒=酒ニ湛ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符甚(ふか入り)」。水がふかくたまることや、ものが水中ふかく沈むこと。
《単語家族》
探(ふか入りする)
{動}ふける。酒色のふかみにはまりこむ。〈同義語〉→耽タン・→酖チン。「湛酒=酒ニ湛ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符甚(ふか入り)」。水がふかくたまることや、ものが水中ふかく沈むこと。
《単語家族》
探(ふか入りする) 深
深 潭タンと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
潭タンと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 水部
区点=3525 16進=4339 シフトJIS=9258
《音読み》
12画 水部
区点=3525 16進=4339 シフトJIS=9258
《音読み》  タン(タム)
タン(タム) /デン(デム)
/デン(デム) 〈zh
〈zh n〉/
n〉/ チン(チム)
チン(チム) /ジン(ヂム)
/ジン(ヂム)
 タン(タム)
タン(タム) /トン(トム)
/トン(トム) 《訓読み》 たたえる(たたふ)/ひたす/しずむ(しづむ)/ふかい(ふかし)/ふける
《意味》
《訓読み》 たたえる(たたふ)/ひたす/しずむ(しづむ)/ふかい(ふかし)/ふける
《意味》

 {動}たたえる(タタフ)。水がふかく満ちている。
{動}たたえる(タタフ)。水がふかく満ちている。
 {形}ふかくしずかなさま。ふかく澄んでいるさま。「清湛セイタン」
{形}ふかくしずかなさま。ふかく澄んでいるさま。「清湛セイタン」

 {動}ひたす。しずむ(シヅム)。ものをふかくしずめる。〈同義語〉→沈。〈対語〉→浮。「然則荊軻之湛七族=然ラバ則チ荊軻ノ七族ヲ湛メラル」〔→史記〕「湛諸美酒=コレヲ美酒ニ湛ス」〔→礼記〕
{動}ひたす。しずむ(シヅム)。ものをふかくしずめる。〈同義語〉→沈。〈対語〉→浮。「然則荊軻之湛七族=然ラバ則チ荊軻ノ七族ヲ湛メラル」〔→史記〕「湛諸美酒=コレヲ美酒ニ湛ス」〔→礼記〕
 {形}ふかい(フカシ)。〈類義語〉→深。
{形}ふかい(フカシ)。〈類義語〉→深。
 {動}ふける。酒色のふかみにはまりこむ。〈同義語〉→耽タン・→酖チン。「湛酒=酒ニ湛ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符甚(ふか入り)」。水がふかくたまることや、ものが水中ふかく沈むこと。
《単語家族》
探(ふか入りする)
{動}ふける。酒色のふかみにはまりこむ。〈同義語〉→耽タン・→酖チン。「湛酒=酒ニ湛ル」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符甚(ふか入り)」。水がふかくたまることや、ものが水中ふかく沈むこと。
《単語家族》
探(ふか入りする) 深
深 潭タンと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
潭タンと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
琢 たたく🔗⭐🔉
【琢】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 玉部 [人名漢字]
区点=3486 16進=4276 シフトJIS=91F4
《音読み》 タク
11画 玉部 [人名漢字]
区点=3486 16進=4276 シフトJIS=91F4
《音読み》 タク
 〈zhu
〈zhu 〉
《訓読み》 みがく/たたく/えらぶ
《名付け》 あや・たか・みがく
《意味》
〉
《訓読み》 みがく/たたく/えらぶ
《名付け》 あや・たか・みがく
《意味》
 タクス{動}みがく。たたく。つちやのみで、とんとんと小まめにうってかどをとり玉を美しくする。「彫琢チョウタク」
タクス{動}みがく。たたく。つちやのみで、とんとんと小まめにうってかどをとり玉を美しくする。「彫琢チョウタク」
 タクス{動}みがく。努力して、学徳やわざをみがきあげる。「如切如磋、如琢如磨=切スルガゴトク磋スルガゴトク、琢スルガゴトク磨スルガゴトシ」〔→詩経〕
タクス{動}みがく。努力して、学徳やわざをみがきあげる。「如切如磋、如琢如磨=切スルガゴトク磋スルガゴトク、琢スルガゴトク磨スルガゴトシ」〔→詩経〕
 {動}えらぶ。選択する。選びとる。〈類義語〉→択。
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
啄タク(とんとんと口ばしでつつく)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}えらぶ。選択する。選びとる。〈類義語〉→択。
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
啄タク(とんとんと口ばしでつつく)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 玉部 [人名漢字]
区点=3486 16進=4276 シフトJIS=91F4
《音読み》 タク
11画 玉部 [人名漢字]
区点=3486 16進=4276 シフトJIS=91F4
《音読み》 タク
 〈zhu
〈zhu 〉
《訓読み》 みがく/たたく/えらぶ
《名付け》 あや・たか・みがく
《意味》
〉
《訓読み》 みがく/たたく/えらぶ
《名付け》 あや・たか・みがく
《意味》
 タクス{動}みがく。たたく。つちやのみで、とんとんと小まめにうってかどをとり玉を美しくする。「彫琢チョウタク」
タクス{動}みがく。たたく。つちやのみで、とんとんと小まめにうってかどをとり玉を美しくする。「彫琢チョウタク」
 タクス{動}みがく。努力して、学徳やわざをみがきあげる。「如切如磋、如琢如磨=切スルガゴトク磋スルガゴトク、琢スルガゴトク磨スルガゴトシ」〔→詩経〕
タクス{動}みがく。努力して、学徳やわざをみがきあげる。「如切如磋、如琢如磨=切スルガゴトク磋スルガゴトク、琢スルガゴトク磨スルガゴトシ」〔→詩経〕
 {動}えらぶ。選択する。選びとる。〈類義語〉→択。
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
啄タク(とんとんと口ばしでつつく)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}えらぶ。選択する。選びとる。〈類義語〉→択。
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
啄タク(とんとんと口ばしでつつく)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
畳 たたみ🔗⭐🔉
【畳】
 12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
 22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
 22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
 16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ)
16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)
/チョウ(テフ) 〈di
〈di 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
 {動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
 {単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
 {動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕
{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。
たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。
《解字》
じょう。たたみを数えることば。
《解字》
 会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる)
会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)
襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
 22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
 22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
 16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ)
16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)
/チョウ(テフ) 〈di
〈di 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
 {動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
 {単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
 {動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕
{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。
たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。
《解字》
じょう。たたみを数えることば。
《解字》
 会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる)
会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)
襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
祟 たたり🔗⭐🔉
【祟】
 10画 示部
区点=6714 16進=632E シフトJIS=E24D
《音読み》 スイ
10画 示部
区点=6714 16進=632E シフトJIS=E24D
《音読み》 スイ
 〈su
〈su 〉
《訓読み》 たたる/たたり
《意味》
{動・名}たたる。たたり。鬼神が人にえたいのしれない災いを及ぼす。また、その災い。「其鬼不祟=ソノ鬼祟ラズ」〔→荘子〕
〔国〕たたる。たたり。神仏・怨霊オンリョウから悪いむくいを受ける。また、受けること。
《解字》
会意兼形声。「示(かみ)+音符出」。神の出してくるたたりをあらわす。
〉
《訓読み》 たたる/たたり
《意味》
{動・名}たたる。たたり。鬼神が人にえたいのしれない災いを及ぼす。また、その災い。「其鬼不祟=ソノ鬼祟ラズ」〔→荘子〕
〔国〕たたる。たたり。神仏・怨霊オンリョウから悪いむくいを受ける。また、受けること。
《解字》
会意兼形声。「示(かみ)+音符出」。神の出してくるたたりをあらわす。
 10画 示部
区点=6714 16進=632E シフトJIS=E24D
《音読み》 スイ
10画 示部
区点=6714 16進=632E シフトJIS=E24D
《音読み》 スイ
 〈su
〈su 〉
《訓読み》 たたる/たたり
《意味》
{動・名}たたる。たたり。鬼神が人にえたいのしれない災いを及ぼす。また、その災い。「其鬼不祟=ソノ鬼祟ラズ」〔→荘子〕
〔国〕たたる。たたり。神仏・怨霊オンリョウから悪いむくいを受ける。また、受けること。
《解字》
会意兼形声。「示(かみ)+音符出」。神の出してくるたたりをあらわす。
〉
《訓読み》 たたる/たたり
《意味》
{動・名}たたる。たたり。鬼神が人にえたいのしれない災いを及ぼす。また、その災い。「其鬼不祟=ソノ鬼祟ラズ」〔→荘子〕
〔国〕たたる。たたり。神仏・怨霊オンリョウから悪いむくいを受ける。また、受けること。
《解字》
会意兼形声。「示(かみ)+音符出」。神の出してくるたたりをあらわす。
称 たたえる🔗⭐🔉
【称】
 10画 禾部 [常用漢字]
区点=3046 16進=3E4E シフトJIS=8FCC
【稱】旧字旧字
10画 禾部 [常用漢字]
区点=3046 16進=3E4E シフトJIS=8FCC
【稱】旧字旧字
 14画 禾部
区点=6742 16進=634A シフトJIS=E269
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ
14画 禾部
区点=6742 16進=634A シフトJIS=E269
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ
 〈ch
〈ch ng・ch
ng・ch ng・ch
ng・ch n〉
《訓読み》 はかる/となえる(となふ)/となえ(となへ)/ほめる(ほむ)/たたえる(たたふ)/あげる(あぐ)/はかり/かなう(かなふ)
《名付け》 あぐ・かみ・な・のり・みつ・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 はかる/となえる(となふ)/となえ(となへ)/ほめる(ほむ)/たたえる(たたふ)/あげる(あぐ)/はかり/かなう(かなふ)
《名付け》 あぐ・かみ・な・のり・みつ・よし
《意味》
 {動}はかる。物を持ちあげて重さをはかる。はかりの左右を平均させてはかる。転じて広く、なりゆきをはかりにかけて考えること。〈同義語〉→秤。〈類義語〉→量。「称量(はかる)」「称家之有亡=家之有亡ヲ称ル」〔→礼記〕
{動}はかる。物を持ちあげて重さをはかる。はかりの左右を平均させてはかる。転じて広く、なりゆきをはかりにかけて考えること。〈同義語〉→秤。〈類義語〉→量。「称量(はかる)」「称家之有亡=家之有亡ヲ称ル」〔→礼記〕
 ショウス{動}となえる(トナフ)。世間を相手にしておおっぴらにいう。〈類義語〉→唱・→号。「称呼」「称夫之母曰姑=夫ノ母ヲ称シテ姑ト曰フ」〔→爾雅〕
ショウス{動}となえる(トナフ)。世間を相手にしておおっぴらにいう。〈類義語〉→唱・→号。「称呼」「称夫之母曰姑=夫ノ母ヲ称シテ姑ト曰フ」〔→爾雅〕
 {名}となえ(トナヘ)。おおやけにいう名前。「尊称」「称号」
{名}となえ(トナヘ)。おおやけにいう名前。「尊称」「称号」
 ショウス{動}ほめる(ホム)。たたえる(タタフ)。わいわいと持ちあげる。おおっぴらにほめあげる。〈類義語〉→誉。「称誉」「驥不称其力、称其徳也=驥ハソノ力ヲ称セズ、ソノ徳ヲ称スルナリ」〔→論語〕
ショウス{動}ほめる(ホム)。たたえる(タタフ)。わいわいと持ちあげる。おおっぴらにほめあげる。〈類義語〉→誉。「称誉」「驥不称其力、称其徳也=驥ハソノ力ヲ称セズ、ソノ徳ヲ称スルナリ」〔→論語〕
 {動}あげる(アグ)。持ちあげる。「称爾戈=ナンヂノ戈ヲ称ゲヨ」〔→書経〕
{動}あげる(アグ)。持ちあげる。「称爾戈=ナンヂノ戈ヲ称ゲヨ」〔→書経〕
 {名}はかり。物をはかる道具。てんびんや棒のはかり。▽去声に読む。〈同義語〉→秤。
{名}はかり。物をはかる道具。てんびんや棒のはかり。▽去声に読む。〈同義語〉→秤。
 {動}かなう(カナフ)。はかりが左右平均するように、両方があい匹敵する。ちょうど対応しあう。▽去声に読む。「相称」「対称」「称意=意ニ称フ」
《解字》
{動}かなう(カナフ)。はかりが左右平均するように、両方があい匹敵する。ちょうど対応しあう。▽去声に読む。「相称」「対称」「称意=意ニ称フ」
《解字》
 会意兼形声。稱の右側(音ショウ)は「爪(手)+物が左右に平均してたれた姿」の会意文字で、左右平均してたれた物を手で持ちあげるさま。稱はそれを音符とし、禾(作物)を加えた字で、作物をぶらさげて重さをはかること。持ちあげる、はかるなどの意を含む。
《単語家族》
丞ジョウ(持ちあげる)
会意兼形声。稱の右側(音ショウ)は「爪(手)+物が左右に平均してたれた姿」の会意文字で、左右平均してたれた物を手で持ちあげるさま。稱はそれを音符とし、禾(作物)を加えた字で、作物をぶらさげて重さをはかること。持ちあげる、はかるなどの意を含む。
《単語家族》
丞ジョウ(持ちあげる) 勝(持ちあげる)
勝(持ちあげる) 昇(上にあげる)などと同系。
《類義》
唱は、はっきりととなえる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昇(上にあげる)などと同系。
《類義》
唱は、はっきりととなえる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 禾部 [常用漢字]
区点=3046 16進=3E4E シフトJIS=8FCC
【稱】旧字旧字
10画 禾部 [常用漢字]
区点=3046 16進=3E4E シフトJIS=8FCC
【稱】旧字旧字
 14画 禾部
区点=6742 16進=634A シフトJIS=E269
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ
14画 禾部
区点=6742 16進=634A シフトJIS=E269
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ
 〈ch
〈ch ng・ch
ng・ch ng・ch
ng・ch n〉
《訓読み》 はかる/となえる(となふ)/となえ(となへ)/ほめる(ほむ)/たたえる(たたふ)/あげる(あぐ)/はかり/かなう(かなふ)
《名付け》 あぐ・かみ・な・のり・みつ・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 はかる/となえる(となふ)/となえ(となへ)/ほめる(ほむ)/たたえる(たたふ)/あげる(あぐ)/はかり/かなう(かなふ)
《名付け》 あぐ・かみ・な・のり・みつ・よし
《意味》
 {動}はかる。物を持ちあげて重さをはかる。はかりの左右を平均させてはかる。転じて広く、なりゆきをはかりにかけて考えること。〈同義語〉→秤。〈類義語〉→量。「称量(はかる)」「称家之有亡=家之有亡ヲ称ル」〔→礼記〕
{動}はかる。物を持ちあげて重さをはかる。はかりの左右を平均させてはかる。転じて広く、なりゆきをはかりにかけて考えること。〈同義語〉→秤。〈類義語〉→量。「称量(はかる)」「称家之有亡=家之有亡ヲ称ル」〔→礼記〕
 ショウス{動}となえる(トナフ)。世間を相手にしておおっぴらにいう。〈類義語〉→唱・→号。「称呼」「称夫之母曰姑=夫ノ母ヲ称シテ姑ト曰フ」〔→爾雅〕
ショウス{動}となえる(トナフ)。世間を相手にしておおっぴらにいう。〈類義語〉→唱・→号。「称呼」「称夫之母曰姑=夫ノ母ヲ称シテ姑ト曰フ」〔→爾雅〕
 {名}となえ(トナヘ)。おおやけにいう名前。「尊称」「称号」
{名}となえ(トナヘ)。おおやけにいう名前。「尊称」「称号」
 ショウス{動}ほめる(ホム)。たたえる(タタフ)。わいわいと持ちあげる。おおっぴらにほめあげる。〈類義語〉→誉。「称誉」「驥不称其力、称其徳也=驥ハソノ力ヲ称セズ、ソノ徳ヲ称スルナリ」〔→論語〕
ショウス{動}ほめる(ホム)。たたえる(タタフ)。わいわいと持ちあげる。おおっぴらにほめあげる。〈類義語〉→誉。「称誉」「驥不称其力、称其徳也=驥ハソノ力ヲ称セズ、ソノ徳ヲ称スルナリ」〔→論語〕
 {動}あげる(アグ)。持ちあげる。「称爾戈=ナンヂノ戈ヲ称ゲヨ」〔→書経〕
{動}あげる(アグ)。持ちあげる。「称爾戈=ナンヂノ戈ヲ称ゲヨ」〔→書経〕
 {名}はかり。物をはかる道具。てんびんや棒のはかり。▽去声に読む。〈同義語〉→秤。
{名}はかり。物をはかる道具。てんびんや棒のはかり。▽去声に読む。〈同義語〉→秤。
 {動}かなう(カナフ)。はかりが左右平均するように、両方があい匹敵する。ちょうど対応しあう。▽去声に読む。「相称」「対称」「称意=意ニ称フ」
《解字》
{動}かなう(カナフ)。はかりが左右平均するように、両方があい匹敵する。ちょうど対応しあう。▽去声に読む。「相称」「対称」「称意=意ニ称フ」
《解字》
 会意兼形声。稱の右側(音ショウ)は「爪(手)+物が左右に平均してたれた姿」の会意文字で、左右平均してたれた物を手で持ちあげるさま。稱はそれを音符とし、禾(作物)を加えた字で、作物をぶらさげて重さをはかること。持ちあげる、はかるなどの意を含む。
《単語家族》
丞ジョウ(持ちあげる)
会意兼形声。稱の右側(音ショウ)は「爪(手)+物が左右に平均してたれた姿」の会意文字で、左右平均してたれた物を手で持ちあげるさま。稱はそれを音符とし、禾(作物)を加えた字で、作物をぶらさげて重さをはかること。持ちあげる、はかるなどの意を含む。
《単語家族》
丞ジョウ(持ちあげる) 勝(持ちあげる)
勝(持ちあげる) 昇(上にあげる)などと同系。
《類義》
唱は、はっきりととなえる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昇(上にあげる)などと同系。
《類義》
唱は、はっきりととなえる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
竚 たたずむ🔗⭐🔉
閧 たたかう🔗⭐🔉
闘 たたかい🔗⭐🔉
【闘】
 18画 門部 [常用漢字]
区点=3814 16進=462E シフトJIS=93AC
【鬪】旧字旧字
18画 門部 [常用漢字]
区点=3814 16進=462E シフトJIS=93AC
【鬪】旧字旧字
 20画 鬥部
区点=8212 16進=722C シフトJIS=E9AA
《常用音訓》トウ/たたか…う
《音読み》 トウ
20画 鬥部
区点=8212 16進=722C シフトJIS=E9AA
《常用音訓》トウ/たたか…う
《音読み》 トウ /ツ
/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)/たたかわす(たたかはす)/たたかい(たたかひ)
《意味》
u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)/たたかわす(たたかはす)/たたかい(たたかひ)
《意味》
 {動}たたかう(タタカフ)。たたかわす(タタカハス)。両方がたちはだかって、切りあいや組み打ちをする。互いに対抗してあらそう。〈類義語〉→戦・→争。「決闘」「闘智=智ヲ闘ハス」「闘妙争能爾不如=妙ヲ闘ハシ能ヲ争フナンヂモシカズ」〔→白居易〕
{動}たたかう(タタカフ)。たたかわす(タタカハス)。両方がたちはだかって、切りあいや組み打ちをする。互いに対抗してあらそう。〈類義語〉→戦・→争。「決闘」「闘智=智ヲ闘ハス」「闘妙争能爾不如=妙ヲ闘ハシ能ヲ争フナンヂモシカズ」〔→白居易〕
 {名}たたかい(タタカヒ)。互いに譲ろうとしないあらそい。「凡有闘怒者成之=オヨソ闘怒有ル者ハコレヲ成グ」〔→周礼〕
《解字》
会意兼形声。中の部分の字(音ジュ)は、たてる動作を示す。鬪は、それを音符とし、鬥(二人が武器を持ってたち、たたかうさま)を加えた字で、たちはだかって切りあうこと。闘は鬥を門にかえた俗字で、常用漢字に採用された。
《単語家族》
豆トウ(たつ)
{名}たたかい(タタカヒ)。互いに譲ろうとしないあらそい。「凡有闘怒者成之=オヨソ闘怒有ル者ハコレヲ成グ」〔→周礼〕
《解字》
会意兼形声。中の部分の字(音ジュ)は、たてる動作を示す。鬪は、それを音符とし、鬥(二人が武器を持ってたち、たたかうさま)を加えた字で、たちはだかって切りあうこと。闘は鬥を門にかえた俗字で、常用漢字に採用された。
《単語家族》
豆トウ(たつ) 逗トウ(たちどまる)
逗トウ(たちどまる) 豎ジュ(たつ)
豎ジュ(たつ) 樹ジュ(たつ)などと同系。
《類義》
戦は、もと、なぎたおして平らにすること。争は、とりあいをすること。
《異字同訓》
たたかう。 →戦
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
樹ジュ(たつ)などと同系。
《類義》
戦は、もと、なぎたおして平らにすること。争は、とりあいをすること。
《異字同訓》
たたかう。 →戦
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 18画 門部 [常用漢字]
区点=3814 16進=462E シフトJIS=93AC
【鬪】旧字旧字
18画 門部 [常用漢字]
区点=3814 16進=462E シフトJIS=93AC
【鬪】旧字旧字
 20画 鬥部
区点=8212 16進=722C シフトJIS=E9AA
《常用音訓》トウ/たたか…う
《音読み》 トウ
20画 鬥部
区点=8212 16進=722C シフトJIS=E9AA
《常用音訓》トウ/たたか…う
《音読み》 トウ /ツ
/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)/たたかわす(たたかはす)/たたかい(たたかひ)
《意味》
u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)/たたかわす(たたかはす)/たたかい(たたかひ)
《意味》
 {動}たたかう(タタカフ)。たたかわす(タタカハス)。両方がたちはだかって、切りあいや組み打ちをする。互いに対抗してあらそう。〈類義語〉→戦・→争。「決闘」「闘智=智ヲ闘ハス」「闘妙争能爾不如=妙ヲ闘ハシ能ヲ争フナンヂモシカズ」〔→白居易〕
{動}たたかう(タタカフ)。たたかわす(タタカハス)。両方がたちはだかって、切りあいや組み打ちをする。互いに対抗してあらそう。〈類義語〉→戦・→争。「決闘」「闘智=智ヲ闘ハス」「闘妙争能爾不如=妙ヲ闘ハシ能ヲ争フナンヂモシカズ」〔→白居易〕
 {名}たたかい(タタカヒ)。互いに譲ろうとしないあらそい。「凡有闘怒者成之=オヨソ闘怒有ル者ハコレヲ成グ」〔→周礼〕
《解字》
会意兼形声。中の部分の字(音ジュ)は、たてる動作を示す。鬪は、それを音符とし、鬥(二人が武器を持ってたち、たたかうさま)を加えた字で、たちはだかって切りあうこと。闘は鬥を門にかえた俗字で、常用漢字に採用された。
《単語家族》
豆トウ(たつ)
{名}たたかい(タタカヒ)。互いに譲ろうとしないあらそい。「凡有闘怒者成之=オヨソ闘怒有ル者ハコレヲ成グ」〔→周礼〕
《解字》
会意兼形声。中の部分の字(音ジュ)は、たてる動作を示す。鬪は、それを音符とし、鬥(二人が武器を持ってたち、たたかうさま)を加えた字で、たちはだかって切りあうこと。闘は鬥を門にかえた俗字で、常用漢字に採用された。
《単語家族》
豆トウ(たつ) 逗トウ(たちどまる)
逗トウ(たちどまる) 豎ジュ(たつ)
豎ジュ(たつ) 樹ジュ(たつ)などと同系。
《類義》
戦は、もと、なぎたおして平らにすること。争は、とりあいをすること。
《異字同訓》
たたかう。 →戦
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
樹ジュ(たつ)などと同系。
《類義》
戦は、もと、なぎたおして平らにすること。争は、とりあいをすること。
《異字同訓》
たたかう。 →戦
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
頌 たたえる🔗⭐🔉
【頌】
 13画 頁部 [人名漢字]
区点=8083 16進=7073 シフトJIS=E8F1
《音読み》 ショウ
13画 頁部 [人名漢字]
区点=8083 16進=7073 シフトJIS=E8F1
《音読み》 ショウ /ズ/ジュ
/ズ/ジュ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 となえる(となふ)/たたえる(たたふ)
《名付け》 うた・おと・つぐ・のぶ・よむ
《意味》
ng〉
《訓読み》 となえる(となふ)/たたえる(たたふ)
《名付け》 うた・おと・つぐ・のぶ・よむ
《意味》
 ショウス{動}となえる(トナフ)。始めから終わりまでとおしてとなえる。声をあげて読みとおす。〈同義語〉→誦。「吟頌ギンショウ」「読頌ドクショウ(=読誦)」「頌其詩=ソノ詩ヲ頌ス」〔→孟子〕
ショウス{動}となえる(トナフ)。始めから終わりまでとおしてとなえる。声をあげて読みとおす。〈同義語〉→誦。「吟頌ギンショウ」「読頌ドクショウ(=読誦)」「頌其詩=ソノ詩ヲ頌ス」〔→孟子〕
 ショウス{動}たたえる(タタフ)。功績や人がらをほめたことばをとなえる。「頌徳ショウトク」
ショウス{動}たたえる(タタフ)。功績や人がらをほめたことばをとなえる。「頌徳ショウトク」
 {名}「詩経」のジャンルを風・雅・頌にわけたうちの一つ。祭礼のとき、祖先の徳をたたえる歌のこと。▽一説に、容(容姿、振る舞い)に通じ、舞踊をともなった歌であるともいう。国別にわけて、魯頌ロショウ・周頌・商頌の三種がある。「頌者美盛徳之形容、以其成功、告於神明者也=頌トハ盛徳ノ形容ヲ美シ、ソノ成功ヲモッテ、神明ニ告グル者ナリ」〔→詩経〕
{名}「詩経」のジャンルを風・雅・頌にわけたうちの一つ。祭礼のとき、祖先の徳をたたえる歌のこと。▽一説に、容(容姿、振る舞い)に通じ、舞踊をともなった歌であるともいう。国別にわけて、魯頌ロショウ・周頌・商頌の三種がある。「頌者美盛徳之形容、以其成功、告於神明者也=頌トハ盛徳ノ形容ヲ美シ、ソノ成功ヲモッテ、神明ニ告グル者ナリ」〔→詩経〕
 {名}文体の一つ。功績や人がらをたたえるもの。「伯夷ハクイ頌」「酒徳頌」
{名}文体の一つ。功績や人がらをたたえるもの。「伯夷ハクイ頌」「酒徳頌」
 {名}姿。かたち。▽容ヨウに当てた用法。容((平)鍾)と同音に読む。「頌礼ヨウレイ」
{名}姿。かたち。▽容ヨウに当てた用法。容((平)鍾)と同音に読む。「頌礼ヨウレイ」
 {名}〔仏〕仏徳を賛美した教理を説く詩。「偈頌ゲジュ」
《解字》
会意兼形声。公は、さえぎることなく、あけすけに通す意を含み、松や頌においてはショウの音をあらわす。頌は「頁(あたま)+音符公」で、頭をふりつつ、よどみなく終わりまでとなえ通すことを示し、よどみなく、たてに通るとの意を含む。
《単語家族》
松ショウ(葉がたてに通ったまつ)
{名}〔仏〕仏徳を賛美した教理を説く詩。「偈頌ゲジュ」
《解字》
会意兼形声。公は、さえぎることなく、あけすけに通す意を含み、松や頌においてはショウの音をあらわす。頌は「頁(あたま)+音符公」で、頭をふりつつ、よどみなく終わりまでとなえ通すことを示し、よどみなく、たてに通るとの意を含む。
《単語家族》
松ショウ(葉がたてに通ったまつ) 鬆ショウ(たてに通る)
鬆ショウ(たてに通る) 縦ショウ・ジュウ(たてに通る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縦ショウ・ジュウ(たてに通る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 頁部 [人名漢字]
区点=8083 16進=7073 シフトJIS=E8F1
《音読み》 ショウ
13画 頁部 [人名漢字]
区点=8083 16進=7073 シフトJIS=E8F1
《音読み》 ショウ /ズ/ジュ
/ズ/ジュ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 となえる(となふ)/たたえる(たたふ)
《名付け》 うた・おと・つぐ・のぶ・よむ
《意味》
ng〉
《訓読み》 となえる(となふ)/たたえる(たたふ)
《名付け》 うた・おと・つぐ・のぶ・よむ
《意味》
 ショウス{動}となえる(トナフ)。始めから終わりまでとおしてとなえる。声をあげて読みとおす。〈同義語〉→誦。「吟頌ギンショウ」「読頌ドクショウ(=読誦)」「頌其詩=ソノ詩ヲ頌ス」〔→孟子〕
ショウス{動}となえる(トナフ)。始めから終わりまでとおしてとなえる。声をあげて読みとおす。〈同義語〉→誦。「吟頌ギンショウ」「読頌ドクショウ(=読誦)」「頌其詩=ソノ詩ヲ頌ス」〔→孟子〕
 ショウス{動}たたえる(タタフ)。功績や人がらをほめたことばをとなえる。「頌徳ショウトク」
ショウス{動}たたえる(タタフ)。功績や人がらをほめたことばをとなえる。「頌徳ショウトク」
 {名}「詩経」のジャンルを風・雅・頌にわけたうちの一つ。祭礼のとき、祖先の徳をたたえる歌のこと。▽一説に、容(容姿、振る舞い)に通じ、舞踊をともなった歌であるともいう。国別にわけて、魯頌ロショウ・周頌・商頌の三種がある。「頌者美盛徳之形容、以其成功、告於神明者也=頌トハ盛徳ノ形容ヲ美シ、ソノ成功ヲモッテ、神明ニ告グル者ナリ」〔→詩経〕
{名}「詩経」のジャンルを風・雅・頌にわけたうちの一つ。祭礼のとき、祖先の徳をたたえる歌のこと。▽一説に、容(容姿、振る舞い)に通じ、舞踊をともなった歌であるともいう。国別にわけて、魯頌ロショウ・周頌・商頌の三種がある。「頌者美盛徳之形容、以其成功、告於神明者也=頌トハ盛徳ノ形容ヲ美シ、ソノ成功ヲモッテ、神明ニ告グル者ナリ」〔→詩経〕
 {名}文体の一つ。功績や人がらをたたえるもの。「伯夷ハクイ頌」「酒徳頌」
{名}文体の一つ。功績や人がらをたたえるもの。「伯夷ハクイ頌」「酒徳頌」
 {名}姿。かたち。▽容ヨウに当てた用法。容((平)鍾)と同音に読む。「頌礼ヨウレイ」
{名}姿。かたち。▽容ヨウに当てた用法。容((平)鍾)と同音に読む。「頌礼ヨウレイ」
 {名}〔仏〕仏徳を賛美した教理を説く詩。「偈頌ゲジュ」
《解字》
会意兼形声。公は、さえぎることなく、あけすけに通す意を含み、松や頌においてはショウの音をあらわす。頌は「頁(あたま)+音符公」で、頭をふりつつ、よどみなく終わりまでとなえ通すことを示し、よどみなく、たてに通るとの意を含む。
《単語家族》
松ショウ(葉がたてに通ったまつ)
{名}〔仏〕仏徳を賛美した教理を説く詩。「偈頌ゲジュ」
《解字》
会意兼形声。公は、さえぎることなく、あけすけに通す意を含み、松や頌においてはショウの音をあらわす。頌は「頁(あたま)+音符公」で、頭をふりつつ、よどみなく終わりまでとなえ通すことを示し、よどみなく、たてに通るとの意を含む。
《単語家族》
松ショウ(葉がたてに通ったまつ) 鬆ショウ(たてに通る)
鬆ショウ(たてに通る) 縦ショウ・ジュウ(たてに通る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縦ショウ・ジュウ(たてに通る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鬥 たたかう🔗⭐🔉
【鬥】
 10画 鬥部
区点=8208 16進=7228 シフトJIS=E9A6
《音読み》 トウ
10画 鬥部
区点=8208 16進=7228 シフトJIS=E9A6
《音読み》 トウ /ツ
/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)
《意味》
{動}たたかう(タタカフ)。向かいあって、互いにゆずらずにたたかう。後へひかずにあらそう。
《解字》
u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)
《意味》
{動}たたかう(タタカフ)。向かいあって、互いにゆずらずにたたかう。後へひかずにあらそう。
《解字》
 象形。二人の人が手に武器をもち、たち向かってたたかう姿を描いたもの。鬪(=闘)の原字。
《単語家族》
逗トウ(たって動かない)と同系。
象形。二人の人が手に武器をもち、たち向かってたたかう姿を描いたもの。鬪(=闘)の原字。
《単語家族》
逗トウ(たって動かない)と同系。
 10画 鬥部
区点=8208 16進=7228 シフトJIS=E9A6
《音読み》 トウ
10画 鬥部
区点=8208 16進=7228 シフトJIS=E9A6
《音読み》 トウ /ツ
/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)
《意味》
{動}たたかう(タタカフ)。向かいあって、互いにゆずらずにたたかう。後へひかずにあらそう。
《解字》
u〉
《訓読み》 たたかう(たたかふ)
《意味》
{動}たたかう(タタカフ)。向かいあって、互いにゆずらずにたたかう。後へひかずにあらそう。
《解字》
 象形。二人の人が手に武器をもち、たち向かってたたかう姿を描いたもの。鬪(=闘)の原字。
《単語家族》
逗トウ(たって動かない)と同系。
象形。二人の人が手に武器をもち、たち向かってたたかう姿を描いたもの。鬪(=闘)の原字。
《単語家族》
逗トウ(たって動かない)と同系。
鬨 たたかう🔗⭐🔉
漢字源に「たた」で始まるの検索結果 1-25。
 7画 人部
区点=4842 16進=504A シフトJIS=98C8
《音読み》 チョ
7画 人部
区点=4842 16進=504A シフトJIS=98C8
《音読み》 チョ 〉
《訓読み》 たたずむ
《意味》
{動}たたずむ。じっと一か所にたちどまる。〈同義語〉
〉
《訓読み》 たたずむ
《意味》
{動}たたずむ。じっと一か所にたちどまる。〈同義語〉 14画 攴部
区点=5842 16進=5A4A シフトJIS=9DC8
《音読み》 コウ(カウ)
14画 攴部
区点=5842 16進=5A4A シフトJIS=9DC8
《音読み》 コウ(カウ) o〉
《訓読み》 たたく
《意味》
o〉
《訓読み》 たたく
《意味》
 10画 立部
区点=6776 16進=636C シフトJIS=E28C
《音読み》 チョ
10画 立部
区点=6776 16進=636C シフトJIS=E28C
《音読み》 チョ 14画 門部
区点=7966 16進=6F62 シフトJIS=E882
《音読み》 コウ(カウ)
14画 門部
区点=7966 16進=6F62 シフトJIS=E882
《音読み》 コウ(カウ) 16画 鬥部
区点=8210 16進=722A シフトJIS=E9A8
《音読み》 コウ
16画 鬥部
区点=8210 16進=722A シフトJIS=E9A8
《音読み》 コウ