複数辞典一括検索+![]()
![]()
じつ‐な・い【術無い】🔗⭐🔉
じつ‐な・い【術無い】
〔形〕[文]じつな・し(ク)
(ジュツナイの訛)仕方がない。困る。切ない。
じゅつ【術】🔗⭐🔉
じゅつ【術】
①わざ。技芸。学問。
②不思議なわざ。まじない。「―をかける」
③てだて。手段。すべ。
④はかりごと。たくらみ。「―を弄する」
じゅっ‐けい【術計】🔗⭐🔉
じゅっ‐けい【術計】
てだて。はかりごと。たくらみ。〈日葡辞書〉
じゅつ‐ご【術後】🔗⭐🔉
じゅつ‐ご【術後】
手術が完了したあと(の時期)。「―の経過は良好だ」
じゅつ‐ご【術語】🔗⭐🔉
じゅつ‐ご【術語】
(technical term)学術上で、特に限定された意味で用いる語。学術語。専門語。
じゅっ‐さく【術策】🔗⭐🔉
じゅっ‐さく【術策】
はかりごと。謀計。「―をめぐらす」
じゅつ‐し【術士】🔗⭐🔉
じゅつ‐し【術士】
巧みに計をめぐらす人。策士。
じゅつ‐しゃ【術者】🔗⭐🔉
じゅつ‐しゃ【術者】
手術・技術・忍術などを実際に施す人。
じゅっ‐すう【術数】🔗⭐🔉
じゅっ‐すう【術数】
①はかりごと。たくらみ。策略。計略。「権謀―」
②陰陽家・卜筮ぼくぜい家などの暦数の術。
じゅつ‐ぜん【術前】🔗⭐🔉
じゅつ‐ぜん【術前】
手術をする前。また、その時期。
じゅっ‐ちゅう【術中】🔗⭐🔉
じゅっ‐ちゅう【術中】
計略の中。てくだのうち。
⇒術中に陥る
○術中に陥るじゅっちゅうにおちいる
相手の作戦・計略にひっかかる。「まんまと敵の―」
⇒じゅっ‐ちゅう【術中】
○術中に陥るじゅっちゅうにおちいる🔗⭐🔉
○術中に陥るじゅっちゅうにおちいる
相手の作戦・計略にひっかかる。「まんまと敵の―」
⇒じゅっ‐ちゅう【術中】
しゅっ‐ちょう【出張】‥チヤウ
(一説に、「でばり(出張)」の音読)
①戦場に出て陣を張ること。
②用務のため、臨時にふだんの勤め先以外の所に出向くこと。「海外―」
⇒しゅっちょう‐こうせい【出張校正】
⇒しゅっちょう‐じょ【出張所】
⇒しゅっちょう‐てん【出張店】
しゅっ‐ちょう【出超】‥テウ
輸出超過の略。↔入超
しゅっちょう‐こうせい【出張校正】‥チヤウカウ‥
編集者・校正者・著者などが印刷所へ出向いて校正すること。
⇒しゅっ‐ちょう【出張】
しゅっちょう‐じょ【出張所】‥チヤウ‥
出張して事務を執る所。
⇒しゅっ‐ちょう【出張】
しゅっちょう‐てん【出張店】‥チヤウ‥
本店から派出した店。でみせ。
⇒しゅっ‐ちょう【出張】
しゅっちょう‐ときん【出長頭巾・出張頭巾】‥チヤウ‥
(→)首丁頭巾しゅちょうずきんに同じ。義経記2「―ひつかこみ」
しゅっ‐ちん【出陳】
展覧会などに物品を出して陳列すること。出品。
シュッチン【繻珍】
⇒シュチン
シュッツ【Alfred Schutz】
アメリカの社会学者。ウィーン生れ。ナチスに追われて亡命。M.ウェーバーの理解社会学とフッサールの現象学とを統合、現象学的社会学を築く。主著「社会的世界の意味構成」。(1899〜1959)
シュッツ【Heinrich Schütz】
ドイツの作曲家。ザクセン選帝侯の宮廷楽長。初期のドイツ‐バロック音楽における主要な作曲家。作品の多くは宗教音楽。「宗教的合唱曲集」など。(1585〜1672)
シュツットガルト【Stuttgart】
⇒シュトゥットガルト
じゅっ‐て【十手】
⇒じって
しゅっ‐てい【出廷】
法廷に出頭すること。「証人が―する」
じゅっ‐てき【怵惕】
恐れあやぶむこと。「―惻隠そくいん」
しゅっ‐てん【出典】
故事・成語・引用句などの出所である文献・書籍。また、その出所。典拠。「―を探す」
しゅっ‐てん【出店】
店を出すこと。新たに支店を作ったり売場を設けたりすること。「バザーに―する」
しゅっ‐てん【出展】
展覧会・展示会などに作品や製品を出すこと。出品。
しゅっ‐と【出途】
①旅立ち。門出。
②費用のでどころ。
しゅつ‐ど【出土】
古代の遺物などが土の中から出てくること。
⇒しゅつど‐ひん【出土品】
しゅっ‐とう【出頭】
①本人自ら、ある場所、特に役所など公の場に出向くこと。「警察に―する」
②他にぬきんでていること。立身出世や主君の寵愛において、他よりまさっていること。また、その人。浮世物語「主君の気に入りて知行をとり、―しけるほどに」
③出頭衆・出頭人の略。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「鎌倉殿の―を鼻にかけ」
⇒しゅっとう‐がろう【出頭家老】
⇒しゅっとう‐しゅう【出頭衆】
⇒しゅっとう‐だいいち【出頭第一】
⇒しゅっとう‐ち【出頭地】
⇒しゅっとう‐にん【出頭人】
⇒しゅっとう‐めいれい【出頭命令】
しゅつ‐どう【出動】
(隊をなすものが)他所へ出て行って活動すること。「捜索隊の―を要請する」
じゅつ‐どう【術道】‥ダウ
祈祷・まじないなどの術。
しゅっとう‐がろう【出頭家老】‥ラウ
権勢のある家老。一番家老。
⇒しゅっ‐とう【出頭】
しゅっとう‐しゅう【出頭衆】
(→)出頭人2に同じ。
⇒しゅっ‐とう【出頭】
しゅっとう‐だいいち【出頭第一】
出頭2のうち、第一の地位にあって権勢をふるう者。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―の高師直こうのもろなお」
⇒しゅっ‐とう【出頭】
しゅっとう‐ち【出頭地】
(「地」は助字)一頭地を出いだすこと。他よりもすぐれていること。
⇒しゅっ‐とう【出頭】
しゅっとう‐にん【出頭人】
①一定の場所に出頭した人。
②室町時代から江戸初期にかけて、幕府または大名の家で、君側に侍って政務に参与した人。三管領・四職と奉行または老臣の類。出頭衆。→近習きんじゅ出頭人。
⇒しゅっ‐とう【出頭】
しゅっとう‐めいれい【出頭命令】
裁判所が訴訟関係人に対して指定の場所に出頭を命ずること。
⇒しゅっ‐とう【出頭】
しゅつど‐ひん【出土品】
土中から出てきたもの。原始・古代の遺物や美術品など。↔伝世品
⇒しゅつ‐ど【出土】
じゅつ‐な・い【術無い】
〔形〕[文]じゅつな・し(ク)
(古くは、多くズチナシまたはズツナシ)なすべき方法がない。しかたがない。せつない。つらい。沙石集2「飢渇けかつの苦しみに責められて―・く候に」
じゅつ‐なが・る【術無がる】
〔自五〕
しかたがないと思う。つらく思う。苦しがる。
しゅつ‐にゅう【出入】‥ニフ
①出ることと入ること。でいり。ではいり。「―を許す」
②出すことと入れること。だしいれ。「預金の―」
⇒しゅつにゅうこう‐ぜい【出入港税】
⇒しゅつにゅう‐こく【出入国】
⇒しゅつにゅうこくかんり‐および‐なんみんにんてい‐ほう【出入国管理及び難民認定法】
しゅつにゅうこう‐ぜい【出入港税】‥ニフカウ‥
一定の港から移出し、または一定の港に移入する貨物に課する税。
⇒しゅつ‐にゅう【出入】
しゅつにゅう‐こく【出入国】‥ニフ‥
出国と入国。
⇒しゅつ‐にゅう【出入】
しゅつにゅうこくかんり‐および‐なんみんにんてい‐ほう【出入国管理及び難民認定法】‥ニフ‥クワン‥ハフ
外国人の出入国・在留資格・退去強制、入国管理局の役割、日本人の出国・帰国、および難民の認定などを定めた法律。1951年制定の出入国管理令を、81年日本の難民条約加入に伴って改定したもの。入管法。
⇒しゅつ‐にゅう【出入】
しゅつ‐のう【出納】‥ナフ
①⇒すいとう。
②寺院で、物品の出し入れをつかさどった役僧。
しゅつ‐ば【出馬】
①馬に乗って出かけること。特に、戦場に出ること。
②みずからすすんである場所に出たり、事に臨んだりすること。
③選挙に立候補すること。
しゅつ‐ばい【出梅】
梅雨の終わる日。つゆあがり。↔入梅
しゅっ‐ぱつ【出発】
①目的地に向かって出かけること。しゅったつ。
②何かをめざして始めること。「新たな研究の―」
⇒しゅっぱつ‐てん【出発点】
しゅっぱつ‐てん【出発点】
①出発する地点。
②事をはじめる初め。
⇒しゅっ‐ぱつ【出発】
じゅっぱ‐ひとからげ【十把一絡げ】
⇒じっぱひとからげ
しゅっ‐ぱん【出帆】
船舶が港を出ること。出港。出船。
しゅっ‐ぱん【出版】
文書・図画を印刷してこれを発売・頒布はんぷすること。「―社」
⇒しゅっぱん‐けいさつ【出版警察】
⇒しゅっぱん‐けいやく【出版契約】
⇒しゅっぱん‐けん【出版権】
⇒しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】
⇒しゅっぱん‐とりしまりれい【出版取締令】
⇒しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】
⇒しゅっぱん‐ぶつ【出版物】
⇒しゅっぱん‐ほう【出版法】
しゅっぱん‐けいさつ【出版警察】
公安保持のため、出版物の取締りを目的とする警察。明治憲法下では重要な警察活動の一部で、取り締まる主な法律には出版法・予約出版法・新聞紙法があった。
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐けいやく【出版契約】
著作権者が出版者に著作物を出版させることを約し、これに対して出版者はその著作物を出版することを約する契約。
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐けん【出版権】
著作物を出版する権利。著作権法では、出版者が著作権者による設定を受けて著作物の複製・頒布等について専有する準物権的権利。
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】‥デウ‥
書籍出版の取締りを目的とした法令。1869年(明治2)公布、93年に出版法に受けつがれた。
→文献資料[出版条例]
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐とりしまりれい【出版取締令】
江戸時代、幕府が発布した書物の出版と写本の流通に関する禁令。1657年(明暦3)京都所司代が命じた触れがもっとも早く、1722年(享保7)には全国触れが出され、その取締りは最初に書物問屋仲間が行なった。
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】‥イウ
(freedom of the press)思想・意見を出版によって発表する自由。日本国憲法第21条は、これを保障している。
→参照条文:日本国憲法第21条
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐ぶつ【出版物】
発売・頒布の目的で印刷された書物・図画。刊行物。
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっぱん‐ほう【出版法】‥ハフ
新聞・定期刊行雑誌を除く一切の出版物の取締りを目的とした法律。1893年(明治26)制定、1945年のGHQ覚書で効力を失い、49年廃止。
⇒しゅっ‐ぱん【出版】
しゅっ‐ぴ【出費】
費用を出すこと。また、その費用。かかり。「―がかさむ」「―をおさえる」
しゅっ‐ぴん【出品】
品物を提出すること。展覧会などに作品を出すこと。「見本市に新機種を―する」
しゅっ‐ぷ【出府】
①江戸時代、武家が幕府のある江戸に出ること。
②地方から都会に出ること。
じゅつ‐ぶ【述部】
文の構成部で、主部を説明する部分。述語とその修飾語とから成る。→主部2
しゅっ‐ぷう【出風】
能楽で、芸力が外に流れ出て観客の目に映る風趣。世阿弥の用語。
しゅっ‐ぺい【出兵】
軍隊を派遣すること。派兵。「シベリア―」
じゅっ‐ぺい【恤兵】
(「恤」は、めぐむ意)物品または金銭を寄贈して戦地の兵士を慰めること。「―金」
しゅつ‐ぼ【出母】
[礼記檀弓上]父に離縁されて家から出された実母。→十母じゅうぼ
しゅつ‐ぼつ【出没】
現れることと隠れること。出たり隠れたりすること。「賊が―する」「―自在」
しゅっ‐ぽん【出奔】
①逃げて跡をくらますこと。逐電。欠落ち。「恋人と―する」
②江戸時代、徒士かち以上の武士が逃亡して行方をくらますこと。
⇒しゅっぽん‐とどけ【出奔届】
しゅっぽん‐とどけ【出奔届】
江戸時代、出奔した者があった時、その旨を届け出ること。また、その書面。
⇒しゅっ‐ぽん【出奔】
じゅつ‐みん【恤民】
人民をあわれみめぐむこと。
しゅつ‐もん【出門】
門を出ること。また、外出すること。
しゅつ‐やく【出役】
①役目として出張すること。また、その役人。でやく。
②関東取締出役のこと。
しゅつ‐ゆう【出遊】‥イウ
①家を出て他所で遊ぶこと。
②他郷にさすらうこと。他国に遊学すること。
しゅつ‐よう【出要】‥エウ
〔仏〕生死を出離する要道。解脱げだつの道。
しゅつ‐らい【出来】
(シュッタイとも)
①現れること。出て来ること。今昔物語集19「新発意の―して」
②事件が起こること。天草本伊曾保物語「大事が―してから、悔むに益ない」
③物事のでき上がること。成就。ロドリーゲス大文典「天地―せしよりこの方」
しゅつ‐らん【出藍】
[荀子勧学「青は藍より出て藍より青し」]藍あいから採った青色は、藍よりも青い。弟子が師よりもまさりすぐれるたとえ。
⇒しゅつらん‐の‐ほまれ【出藍の誉れ】
しゅつらん‐の‐ほまれ【出藍の誉れ】
弟子がその師匠を越えてすぐれているという名声。
⇒しゅつ‐らん【出藍】
しゅつ‐り【出離】
①〔仏〕煩悩を去って悟りの境地に入ること。出家すること。今昔物語集7「仏法を修行して皆―の計を求む」
②〔天〕内惑星の太陽面経過の終止。出象。↔侵入。
⇒しゅつり‐しょうじ【出離生死】
しゅつり‐しょうじ【出離生死】‥シヤウ‥
〔仏〕生死の苦界を離脱して悟りの世界に入ること。源平盛衰記10「一切衆生―の期を失ふべし」
⇒しゅつ‐り【出離】
しゅつ‐りょう【出猟】‥レフ
狩猟に出ること。
しゅつ‐りょう【出漁】‥レフ
魚をとりに出ること。しゅつぎょ。
しゅつ‐りょく【出力】
(output)原動機・通信機・コンピューターなどの装置が入力を受けて仕事または情報を外部へ出すこと。また、その仕事または情報。アウトプット。↔入力。
⇒しゅつりょく‐そうち【出力装置】
しゅつりょく‐そうち【出力装置】‥サウ‥
コンピューターの出力のための装置。ディスプレー・プリンターなど。
⇒しゅつ‐りょく【出力】
しゅつ‐るい【出塁】
野球で、打者が塁に出ること。安打・四球・死球・打撃妨害などによる。
しゅつ‐れん【出輦】
天子のおでまし。
しゅつ‐ろ【出路】
出るべき路。のがれ出る路。
しゅつ‐ろ【出廬】
(諸葛孔明が劉備の三顧に感激して草廬を出て仕えたことから)隠遁いんとんしていた人が、再び世間で活動すること。
しゅつ‐ろう【出牢】‥ラウ
牢から出ること。出獄。
しゅ‐でい【朱泥】
中国江蘇省宜興窯ぎこうように産する、赤褐色で無釉むゆう締焼しめやきの陶器。土質緻密、炻器せっき質になるまで焼いたもので、多く急須にする。日本にも伝わり、常滑とこなめ焼・備前焼・万古ばんこ焼などで焼造。→紫泥→白泥
シュティール【Stil ドイツ】
①様式。
②文体。スタイル。
シュティフター【Adalbert Stifter】
オーストリアの小説家。精細な自然描写と運命観を特色とする。短編集「石さまざま」、長編「晩夏」など。(1805〜1868)
シュティムング【Stimmung ドイツ】
気分。情緒。情趣。
シュティルナー【Max Stirner】
ドイツの哲学者。ヘーゲル左派。あらゆる外的権威を排して、何ものにも縛られない唯一者としての自我の絶対性を主張し、個人の自由を抑圧する国家を否定して無政府主義に影響を与えた。主著「唯一者とその所有」。スチルネル。(1806〜1856)
シュテファン‐ボルツマン‐の‐ほうそく【シュテファンボルツマンの法則】‥ハフ‥
黒体放射で発する全エネルギーは絶対温度の4乗に比例するという法則。オーストリアの物理学者シュテファン(J.Stefan1835〜1893)が1879年に見出しボルツマンが84年に証明。
シュテム
(ドイツ語で「止める」意のstemmenから)スキーで、方向転換などのために、スキー板の先端をつけたまま、後端をV字形に開くこと。
⇒シュテム‐ターン
⇒シュテム‐ボーゲン【Stemmbogen ドイツ】
シュテム‐ターン
(和製語)スキーで、シュテムの技術を用いて方向を転換すること。
⇒シュテム
シュテム‐ボーゲン【Stemmbogen ドイツ】
スキーでシュテムの姿勢でする回転。制動回転。
⇒シュテム
シュテルン【Otto Stern】
アメリカの物理学者。ドイツ生れ。実験によって方向量子化を実証。また、陽子の磁気モーメントの測定に成功。ノーベル賞。(1888〜1969)
しゅ‐てん【主典】
①⇒さかん。
②旧官国幣社で、祢宜ねぎの下に属した神職。祭儀および庶務に従事し、判任官待遇。
⇒しゅてん‐だい【主典代】
しゅ‐てん【主点】
①大事な箇所。要点。眼目。
②〔理〕(principal point)レンズ系の軸上にあって、像の倍率が1になるような共役点。主点から焦点までの距離が焦点距離。薄いレンズではレンズ中心に一致。
しゅ‐てん【朱点】
①朱色の点。あかいしるし。
②朱で施された訓点。
しゅ‐てん【酒店】
①酒を売る店。さかや。さかみせ。
②中国で、旅館・ホテル。
しゅ‐でん【主殿】
①屋敷の中の主要な殿舎。寝殿または表座敷・客殿の称。室町時代に多く使う。義経記8「―の垂木に取りつきて」
②主殿寮とのもりょうの下司げす。とのも。
⇒しゅでん‐しょ【主殿署】
⇒しゅでん‐づくり【主殿造】
⇒しゅでん‐りょう【主殿寮】
しゅ‐でん【守殿】
(→)御守殿に同じ。
じゅ‐でん【受電】
①電信・電報などを受けること。
②送られてきた電力を受けること。
しゅでん‐しょ【主殿署】
律令制で、春宮とうぐう坊に属し、春宮の湯沐・灯燭・清掃・設営をつかさどった役所。とのもりのつかさ。
⇒しゅ‐でん【主殿】
しゅてん‐だい【主典代】
平安時代以降、院庁いんのちょうの記録・文書をつかさどった院司。朝廷の官と区別して「代」という。古今著聞集10「院の中門に―・庁官などが候ひける中に」
⇒しゅ‐てん【主典】
しゅでん‐づくり【主殿造】
書院造の初期形式。蔀しとみ戸などの寝殿造の要素を残しつつも、式台・角柱・付書院つけしょいん・畳敷など書院造の要素をもつ。室町末期から桃山時代にかけて造られ、園城寺光浄院・勧学院客殿などを典型とする。
⇒しゅ‐でん【主殿】
しゅてん‐どうじ【酒呑童子・酒顛童子】
鬼のすがたをまねて財を掠かすめ婦女子を掠奪した盗賊。丹波国大江山や近江国伊吹山に住んだといい、大江山のは源頼光が四天王と共に退治したという。絵巻・御伽草子・草双紙・浄瑠璃・歌舞伎などの題材となる。
しゅでん‐りょう【主殿寮】‥レウ
①明治時代、宮殿の監守および警察のことをつかさどった宮内省の一局。
②⇒とのもりょう
⇒しゅ‐でん【主殿】
しゅ‐と【主都】
省・道・州や植民地などの政庁があり中心となる都市。また、広く地方の中心都市。
しゅ‐と【首途】
出立すること。かどで。旅立ち。
しゅ‐と【首都】
その国の中央政府のある都市。首府。
⇒しゅと‐けん【首都圏】
⇒しゅと‐こうそくどうろ【首都高速道路】
⇒しゅとだいがく‐とうきょう【首都大学東京】
しゅ‐と【酒徒】
酒を飲む仲間。酒ずきの人々。
しゅ‐と【衆徒】
(シュウトとも)
①諸大寺の僧侶。院政期以降は僧兵をいう。僧の姿をした在地の武士もいる。
②中世の興福寺の僧兵。
⇒しゅと‐こくみん【衆徒国民】
しゅ‐ど【手弩】
小形のいしゆみ。
しゅ‐とう【手刀】‥タウ
空手の技の一つ。4指を密着させ、親指を曲げて手のひらにつけ、小指側で顔面・頸部等を攻撃し、また防御を行うもの。
しゅ‐とう【手灯】
仏道修行の一つ。手に脂燭しそくをかかげたり手のひらに灯心をともしたりすること。好色五人女1「夏中げちゅうは毎夜―かかげて大経の勤め怠らず」
しゅ‐とう【手套】‥タウ
てぶくろ。〈[季]冬〉
⇒手套を脱す
しゅ‐とう【主当】‥タウ
ある事を主として担当する職員の意。古代の諸官司や行事に関して用いる。専当せんとう。
しゅ‐とう【朱耷】‥タフ
清の画家、八大山人の本名。
しゅ‐とう【殊闘】
必死の覚悟でたたかうこと。命がけでたたかうこと。
しゅ‐とう【酒盗】‥タウ
(肴にすると酒が進むことからいう)カツオの内臓の塩辛。
しゅ‐とう【酒鐺】‥タウ
(→)燗鍋かんなべに同じ。
しゅ‐とう【種痘】
(vaccination)痘苗とうびょうを人体に接種し、天然痘に対する免疫性を得させ、感染を予防する方法。牛痘種痘法はジェンナーの発明。植え疱瘡ぼうそう。
⇒しゅとう‐じょ【種痘所】
しゅ‐どう【手動】
(機械などを)手で動かすこと。「―式」
しゅ‐どう【主動】
中心になって行動すること。主になって働きかけること。「―的」
しゅ‐どう【主導・首導】‥ダウ
主となって導くこと。
⇒しゅどう‐けん【主導権】
しゅ‐どう【朱銅】
銅器の面に現れた鮮明な朱色の斑文。松炭で銅器を赤熱し、真土・朴炭で研磨し、胆礬酢に投じ、鉄漿で塗抹して生じさせる技法は佐渡の鋳工初代本間琢斎(1809〜1891)の創始。
しゅ‐どう【修道】‥ダウ
〔仏〕
①仏道を修行すること。
②三道すなわち見・修・無学のうちの第2の段階。見道のあとで、具体的な事象に対処し、反復修習する段階をいう。
しゅ‐どう【衆道】‥ダウ
(若衆道の略)男色の道。美道。かげま。にゃくどう。じゃくどう。
じゅ‐とう【寿塔】‥タフ
生前に建てておく自分の塔婆とうば。
じゅ‐とう【授刀】‥タウ
刀を授けること。
⇒じゅとう‐えい【授刀衛】
⇒じゅとう‐とねり‐りょう【授刀舎人寮】
じゅ‐とう【樹頭】
木の上。木の枝の上。
じゅ‐どう【受動】
他からの働きかけを受けること。受身うけみ。↔能動。
⇒じゅどう‐きつえん【受動喫煙】
⇒じゅどう‐せい【受動性】
⇒じゅどう‐そし【受動素子】
⇒じゅどう‐たい【受動態】
⇒じゅどう‐てき【受動的】
⇒じゅどう‐ぶん【受動文】
⇒じゅどう‐めんえき【受動免疫】
⇒じゅどう‐ゆそう【受動輸送】
じゅ‐どう【豎童】
召使の少年。
じゅ‐どう【儒道】‥ダウ
①儒学の道。
②儒教と道教。
じゅとう‐えい【授刀衛】‥タウヱイ
「授刀舎人寮とねりりょう」参照。
⇒じゅ‐とう【授刀】
じゅどう‐きつえん【受動喫煙】
喫煙しない人が周囲の人の喫煙で害を受けること。
⇒じゅ‐どう【受動】
しゅどう‐けん【主導権】‥ダウ‥
物事を主導する権力。「―を握る」
⇒しゅ‐どう【主導・首導】
じゅどう‐じつげつ【寿同日月】
(謎語画題)日月に波、桃を描くもの。祝賀の図。
しゅとう‐じょ【種痘所】
江戸末期、江戸の神田お玉が池に創設された牛痘種痘法を施す施設。1857年(安政4)伊東玄朴ら蘭方医の願い出により、翌年開設。60年(万延1)幕府直轄。61年(文久1)西洋医学所、63年医学所と改称。東大医学部の前身の一つ。種痘館。
⇒しゅ‐とう【種痘】
じゅどう‐せい【受動性】
自発性に対し、他からの作用を受け入れる性質。
⇒じゅ‐どう【受動】
じゅどう‐そし【受動素子】
「素子」参照。
⇒じゅ‐どう【受動】
じゅどう‐たい【受動態】
〔言〕(passive voice)ボイス(態)の一つ。主語の指すものがある動作の対象となり、その作用を受けるという関係を示す動詞の形式。所相。受身。↔能動態。
⇒じゅ‐どう【受動】
シュトゥットガルト【Stuttgart】
ドイツ南西部、バーデン‐ヴュルテンベルク州の州都。ライン川の支流ネッカー川沿いの商工業の中心地。出版業も盛ん。中世にはヴュルテンベルク公の本拠地。人口58万2千(1999)。
じゅどう‐てき【受動的】
他から働きかけられて行動するさま。
⇒じゅ‐どう【受動】
じゅとう‐とねり‐りょう【授刀舎人寮】‥タウ‥レウ
古代、天皇の親衛の舎人(帯刀たちはき)を管掌した役所。707年(慶雲4)設置。一時中衛府に吸収、759年(天平宝字3)授刀衛となり、765年(天平神護1)近衛府、807年(大同2)左近衛府と改称。帯刀舎人寮。→帯刀
⇒じゅ‐とう【授刀】
しゅとう‐ぶん【主祷文】‥タウ‥
(→)「主の祈り」に同じ。
じゅどう‐ぶん【受動文】
(passive sentence)動詞が受動態である文。
⇒じゅ‐どう【受動】
じゅどう‐めんえき【受動免疫】
抗体を体外から与えることによって獲得される免疫。胎児が胎盤を通じて、また乳児が母乳を通じて抗体を得る類。血清療法もその応用。↔能動免疫。
⇒じゅ‐どう【受動】
じゅどう‐ゆそう【受動輸送】
〔生〕物質が細胞膜を透過する際、細胞の内外の濃度勾配に従って移動し、エネルギーを必要としない場合をいう。
⇒じゅ‐どう【受動】
シュトゥルム‐ウント‐ドラング【Sturm und Drang ドイツ】
(疾風怒濤と訳す)18世紀後半、若いゲーテらが興したドイツの文学革新運動。啓蒙主義の悟性偏重的側面に反対し、社会の旧習を主観的・感情的に激しく批判した。ドイツの劇作家クリンガー(Friedrich Maximilian von Klinger1752〜1831)の戯曲の題名に由来。
じゅつ‐どう【術道】‥ダウ🔗⭐🔉
じゅつ‐どう【術道】‥ダウ
祈祷・まじないなどの術。
じゅつ‐な・い【術無い】🔗⭐🔉
じゅつ‐な・い【術無い】
〔形〕[文]じゅつな・し(ク)
(古くは、多くズチナシまたはズツナシ)なすべき方法がない。しかたがない。せつない。つらい。沙石集2「飢渇けかつの苦しみに責められて―・く候に」
じゅつ‐なが・る【術無がる】🔗⭐🔉
じゅつ‐なが・る【術無がる】
〔自五〕
しかたがないと思う。つらく思う。苦しがる。
ずち‐な・し【術無し】🔗⭐🔉
ずち‐な・し【術無し】
〔形ク〕
(ズチは「術」の字音)なんともしようがない。困りはてたことだ。術すべなし。枕草子161「葛城の神、今ぞ―・き」。大鏡時平「けふは―・し。右の大臣にまかせ申す」
ずつ‐な・い【術無い】🔗⭐🔉
ずつ‐な・い【術無い】
〔形〕[文]ずつな・し(ク)
(ズチナシの転)処置のしようがない。苦しい。今昔物語集4「我等餓えつかれて―・し」。浄瑠璃、女殺油地獄「アア―・い、母様母様」
ずつ‐なが・る【術無がる】🔗⭐🔉
ずつ‐なが・る【術無がる】
〔自四〕
苦しがる。切せつながる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「イヤモウ細かには存ぜぬ、と―・る」
ずつ‐なし【術無し】🔗⭐🔉
ずつ‐なし【術無し】
はたらきのない者。無能者。
ずつ‐な・し【術無し】(形ク)🔗⭐🔉
ずつ‐な・し【術無し】
〔形ク〕
⇒ずつない
すべ‐な・し【術無し】🔗⭐🔉
すべ‐な・し【術無し】
〔形ク〕
ほどこす方法がなく切ない。万葉集5「かくばかり―・きものか」
すべ‐の‐たずき【術のたずき】‥タヅキ🔗⭐🔉
すべ‐の‐たずき【術のたずき】‥タヅキ
たよるべき手段。事をなす手がかり。万葉集13「思ひやる―も今はなし」
○術も術なさすべもすべなさ🔗⭐🔉
○術も術なさすべもすべなさ
どうにもしようがないことだ。万葉集18「君が心の―」
⇒すべ【術】
すべ‐やか【滑やか】
すべるさま。なめらか。すべすべ。すべらか。花鏡「五音正しく、句移りの文字ぐさりの―に聞きよくて」
すべ‐よく【術よく】
さっぱりと。手際よく。歌舞伎、三人吉三廓初買「―おれに渡さにやあ、腕づくでも取らにやあならねえ」
すべ‐ら【皇】
〔接頭〕
⇒すめら
ずべ‐ら
しまりのないこと。投げやり。ずぼら。「―なやり方」
⇒ずべら‐ぼう【ずべら坊】
すべら‐おおんかみ【皇大神】‥オホン‥
天照大神あまてらすおおみかみをいう語。後拾遺和歌集神祇「いただきまつる―」
すべ‐らか【滑らか】
すべすべしたさま。なめらか。
すべら‐かし
婦人のさげ髪の一種。髻もとどりの末を背後にすべらかし、長く垂れ下げるもの。すべしもとどり。おすべらかし。垂髪。好色一代男3「平もとゆひ太く―に結び下げ」
すべら‐か・す【滑らかす・辷らかす】
〔他五〕
すべらせる。ずらす。中務内侍日記「母屋のみす―・して」
すべら‐がみ【皇神】
(→)「すめがみ」に同じ。夫木和歌抄9「滝つ瀬に木綿ゆうかけ祈る―」
すべら‐ぎ【皇】
(スベラキとも)
⇒すめらぎ。古今和歌集序「今―の天の下しろしめすこと」
⇒すべらぎ‐の‐かみ【皇の神】
⇒すべらぎ‐の‐はな【皇の花】
すべらぎ‐の‐かみ【皇の神】
(→)「すめがみ」に同じ。相模集「祈りしぞかし―」
⇒すべら‐ぎ【皇】
すべらぎ‐の‐はな【皇の花】
牡丹ぼたんの異称。
⇒すべら‐ぎ【皇】
すべら・す【滑らす】
〔他五〕
①すべるようにする。すべらせる。「足を―・す」
②言わなくてよいこと、言ってはいけないことをうっかり言葉に出してしまう。「口を―・す」「筆を―・す」
ずべら‐ぼう【ずべら坊】‥バウ
①ずべらなこと。しまりのないこと。また、その人。
②のっぺらぼう。
⇒ずべ‐ら
すべら‐みこと【皇尊】
⇒すめらみこと。舒明紀「車駕すべらみこと、温湯ゆより還ります」
すべら‐よ【皇代】
天皇在位の代。すべらぎの代。謡曲、隠岐院「すべらぎの―なれど」
すべり【滑り・辷り】
①すべること。すべるさま。すべる程度。「―の悪い敷居」
②ふとん。おすべり。
⇒すべり‐ぎ【滑り木】
⇒すべり‐ぐるま【滑り車】
⇒すべり‐ごころ【辷り心】
⇒すべり‐こみ【滑り込み】
⇒すべり‐しんうけ【辷り心受け】
⇒すべり‐せん【滑り線】
⇒すべり‐だい【滑り台】
⇒すべり‐だし【滑り出し】
⇒すべり‐どめ【滑り止め】
⇒すべりは‐つぎ【滑り刃継ぎ】
⇒すべり‐ひゆ【滑莧】
⇒すべり‐ぶた【滑り蓋】
⇒すべり‐べん【滑り弁】
⇒すべり‐まさつ【滑り摩擦】
スペリー【Roger Wolcott Sperry】
アメリカの大脳生理学者。脳梁の切断実験により左右の大脳半球の機能分化を研究し、また、視神経の切断再生実験により、網膜の神経細胞が脳へ一対一対応で投射する機構を研究した。ノーベル賞。(1913〜1994)
すべり‐い・ず【滑り出づ】‥イヅ
〔自下二〕
①すべるようにして、そっと外に出る。源氏物語空蝉「単ひとえ一つを着て、―・でにけり」
②座ったまま前に出る。蜻蛉日記下「すのこに―・でて」
③洩れて出る。生まれ出る。浄瑠璃、曾我会稽山「風に乱るる下髪の―・でたは母の腹」
すべり‐い・る【滑り入る】
〔自五〕
①すべるようにして、そっと内に入る。大和物語「やをら―・りて此の人を奥にも入れず」
②すべって落ち込む。
すべり‐う・す【滑り失す】
〔自下二〕
すべり出て、見えなくなる。目立たないように退出する。枕草子161「細殿の四の口に殿上人あまた立てり。やうやう―・せなどして」
スペリオル‐こ【スペリオル湖】
(Lake Superior)北アメリカ五大湖の一つ。その西端に位置し、東に流れ出た水はヒューロン湖に注ぐ。淡水湖としては世界最大。面積8万2300平方キロメートル。→五大湖(図)
すべり‐ぎ【滑り木】
敷居の溝底に埋めこんだ樫の薄板。建具のすべりをよくし、敷居の摩耗を防ぐ。埋樫うめがし。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ぐるま【滑り車】
(→)戸車に同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ごころ【辷り心】
うわすべりしがちでおちつかない心。うつり気。為尹ためただ千首「うき名またおちぶれやせむ元結の―は衣きぬにたまらず」
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐こみ【滑り込み】
①野球で、走者が野手のタッチを避けるなどのため、すべって塁に入ること。スライディング。「―セーフ」
②辛うじて時刻に間に合うこと。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐こ・む【滑り込む】
〔自五〕
①滑って入る。滑るようにして入りこむ。「2塁に―・む」「列車がホームに―・む」
②辛うじて時刻に間に合う。「開演間際に―・む」
すべり‐しんうけ【辷り心受け】
〔機〕(→)心押台しんおしだいに同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐せん【滑り線】
〔機〕(slip band)表面をよく磨いた金属の試験片を引っ張って、降伏点に達すると、その力の方向に対して斜めに現れる細い線。リューダース線。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐だい【滑り台】
高い所からすべりおりる遊戯具。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐だし【滑り出し】
①すべりだすこと。
②物事が進行しはじめること。また、その時期。始動。でだし。「―好調」
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐どめ【滑り止め】
①すべらないようにする装置や材料。
②受験の際、志望する学校に入れなかった場合に備えて、入れそうな学校を志願して、すべてに不合格になることを避けること。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべりは‐つぎ【滑り刃継ぎ】
(→)「そぎつぎ」1に同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ひゆ【滑莧】
スベリヒユ科の一年草。世界の暖地に普通の雑草。茎は地をはい、暗紅色。葉は多肉で対生し、楕円形。夏、鮮黄色の5弁の小花を開く。果実は熟すと上半部が帽状にはずれ、種子を多数放出。茎・葉は食用、また、利尿・解毒剤にも用いる。イハイズル。漢名、馬歯莧。〈[季]夏〉
スベリヒユ
撮影:関戸 勇
 ⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ぶた【滑り蓋】
(→)スライド4に同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐べん【滑り弁】
蒸気機関で、蒸気口および排気口の開閉を行う箱形の弁。スライド‐バルブ。滑動弁。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐まさつ【滑り摩擦】
物体が、ある表面をすべる時、その物体に加えた力の、面に平行な成分と反対の向きに働く、面からの抵抗力。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐よ・る【滑り寄る】
〔自五〕
滑るようにして近寄る。すわったまま近寄る。にじりよる。枕草子76「蔭ながら―・りて聞く時もあり」
スペリング【spelling】
ヨーロッパ語のつづり字。綴字法。スペル。
す・べる【統べる・総べる】
〔他下一〕[文]す・ぶ(下二)
①個々のものを一つにする。別々のものをまとめる。大唐西域記長寛点「学ぶることは真俗を綜スヘ、信ずることは邪正を兼ねたり」。〈字鏡集〉
②支配する。管轄する。地蔵十輪経元慶点「輪王と作なりて四の洲渚を統スフべきひとなり」。「国を―・べる」
すべ・る【滑る・辷る】
〔自五〕
①物の上をなめらかに移行する。物の間を滞りなく通る。源氏物語夕顔「馬より―・りおりて」。狭衣物語4「御ぐし…取る手も―・るつやすぢの美しさなどの」。「スキーで雪山を―・る」「戸がよく―・る」
②にじり移る。すわったまますって行く。
③静かに退出する。源氏物語玉鬘「御使にかづけたる物を、いとわびしく傍痛しとおぼして、御気色あしければ、―・りまかでぬ」
④足がなめらかに動いて止まらない。古今著聞集16「あわて惑ひて出づとて、其の管の小竹に―・りてまろびにけり」。「雪道で―・った」
⑤位を降りる。退位する。平家物語1「位を―・らせ給ひて新院とぞ申しける」
⑥生まれおちる。傾城禁短気「何処の牛の骨やらしれぬ女の腹から―・つた餓鬼を」
⑦手に取ろうとしたものがすり抜ける。「手が―・って茶碗を落とす」
⑧思わず言う。「口が―・って秘密を漏らす」「筆が―・る」
⑨落第する。「入試に―・った」
⇒すべったの転んだの
スペル【spell】
(「字をつづる」の意)(→)スペリングに同じ。
⇒スペル‐チェック【spell-check】
スペル‐チェック【spell-check】
欧文の文書につづりの誤りがないか確認すること。
⇒スペル【spell】
スペルマ【sperma ラテン】
精子。精液。
スペルミン【spermine】
分子式C10H26N4 生体アミンの一種。ヒトの精子中から発見されたが、血清などほとんどすべての組織に存在する。精液の特異臭はその酸化生成物による。
すべろ‐ぎ【皇】
⇒すめろぎ
スペンサー【Herbert Spencer】
イギリスの哲学者・社会学者。ダーウィン進化論の影響のもとに、あらゆる事象を単純なものから複雑なものへの進化・発展として捉え、生物・心理・社会・道徳の諸現象を統一的に解明しようとした。その哲学思想は明治前半期の日本に大きな影響を与えた。主著「総合哲学体系」10巻。(1820〜1903)
スペンサー【Edmund Spenser】
イギリスの詩人。エリザベス朝文学の代表者の一人。キリスト教倫理を豊麗な詩語と多彩な詩型で歌う。エリザベス女王をも示唆する寓意的な叙事詩「妖精の女王」のほか、詩集「牧人の暦」など。(1552頃〜1599)
スペンダー【Stephen Spender】
イギリスの詩人・評論家。1930年代、オーデンを中心とする左翼詩人の一派に属した。53年「エンカウンター」誌の編集に参加。評論「破壊的要素」。(1909〜1995)
スペンディング‐ポリシー【spending policy】
不況期に大規模な財政支出を行なって景気回復を図る政策。アメリカでニュー‐ディールの一環として実施され、第二次大戦後も各国で財政による総需要の調整に用いる。
スポイト【spuit オランダ】
インクや液汁を少量吸いあげて他に移し入れるのに使う、一端にゴム製の袋が付いたガラスなどの管。液汁注入器。
スポイラー【spoiler】
①航空機で、気流を乱し、揚力を減少させて抗力を増加させる装置。翼の上面に設置され、一般には可動式の板状。速度を減じたり降下したりするために用いる。
②自動車で、空気流による揚力を減少させ、大きな駆動力でも空転しないようにするための翼。空力的固定板。
スポイル【spoil】
そこなうこと。台無しにすること。甘やかしてだめにすること。「子供を―する」
ず‐ほう【図法】ヅハフ
図形の作り方。特に、地球表面を地図に投影する方法。円筒図法・正射図法など。
ず‐ほう【修法】‥ホフ
〔仏〕(スホウとも)
⇒しゅほう
ず‐ぼう‥バウ
(「ぼうず」を倒置した隠語)坊主のこと。東海道中膝栗毛8「三すぢほどある薄鬢うすびんのあたま、やがて―に鳴る鐘ならば」
ず‐ぼうし【図法師】ヅボフ‥
治療法学習のために、身体各部を明らかに示した図。〈日葡辞書〉
スホーイ【Sukhoi ロシア】
(設計者の名に因む)ソ連・ロシアの戦闘機の機種の一つ。
スポーク【spoke】
車輪の軸受からリムに向かって放射状に出ている細長い棒。輻や。
スポークスマン【spokesman】
代弁者。特に、政府などの情報・見解を発表する担当者。
スポーツ【sport(s)】
陸上競技・野球・テニス・水泳・ボートレースなどから登山・狩猟などにいたるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。
⇒スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
⇒スポーツ‐ウェア【sportswear】
⇒スポーツ‐カー【sports car】
⇒スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
⇒スポーツ‐クラブ【sports club】
⇒スポーツ‐シャツ【sports shirt】
⇒スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
⇒スポーツ‐センター【sports center】
⇒スポーツ‐ドリンク
⇒スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
⇒スポーツ‐マン【sportsman】
⇒スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
スポーツの人体に及ぼす影響、競技者の健康管理などを研究・実践する医学。運動生理学・スポーツ臨床医学などを含む。体育運動医学。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ウェア【sportswear】
運動する時に着用する服の総称。また、競技の観戦者の服や活動的な服の意味にも用いる。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐カー【sports car】
運転を楽しむために作られた娯楽用乗用車。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
男性の髪型。前髪の輪郭を四角く刈り、両側と後ろを短く刈り上げたもの。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐クラブ【sports club】
①学校の運動部。また、企業や地域のスポーツ活動を行う組織。
②スポーツの講習や施設を提供する会員制組織。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐シャツ【sports shirt】
運動用のシャツ。また、軽快な感じのシャツの総称。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
スポーツ報道を中心に、娯楽・芸能関係の記事で構成される新聞。スポーツ紙。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐センター【sports center】
各種のスポーツができるように建設された総合スポーツ施設。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ドリンク
(sports drink)発汗によって失われた水分やミネラルなどを速やかに補給できるよう、成分を体液に近く調整してある清涼飲料。アイソトニック飲料。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
スポーツ用品を持ち運ぶための大型のかばん。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン【sportsman】
運動競技の選手。また、スポーツの得意な人。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
正々堂々と公明に勝負を争う、スポーツマンにふさわしい態度。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーティー【sporty】
スポーツ向き。服装・形などの軽快で活動的なさま。「―な乗用車」
ズボートー
(drop van zoet hout オランダの略訛)オランダから渡来した去痰きょたん薬。甘草を煎じつめて製したものという。オランダたんきり。ズドーボー。誹風柳多留12「平六がとこづぼうとうよく売れる」
ずほく‐めんさい‐うきょう‐が【頭北面西右脇臥】ヅ‥ウケフグワ
死者の頭を北に、顔を西に向け、右わきを下にして寝かせること。釈尊入滅の時の姿勢を模したもの。頭北西面右脇臥。謡曲、白髭「八十年の春のころ、―、抜提ばつだいの波と消え給ふ」
すぼけ
①ちぢむこと。狭くなること。
②まのぬけていること。また、その人。まぬけ。
③包茎の俗称。
す‐ぼし【角宿】
二十八宿の一つ。乙女座おとめざの首星スピカを含む部分。角かく。
す‐ぼし【素乾し】
日光または火にあてないで乾すこと。かげぼし。
すぼ・し【窄し】
〔形ク〕
①すぼんで細い。狭い。謡曲、清経「眼裏に塵あつて三界―・く」
②みすぼらしい。肩身が狭い。方丈記「朝夕―・き姿を恥ぢて」
ず‐ぼし【図星】ヅ‥
①的まとの中心の黒点。
②見込んだ所。人の思わくなどの、最も肝腎な所。急所。「―をつく」「どうだ、―だろう」
⇒図星を指される
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ぶた【滑り蓋】
(→)スライド4に同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐べん【滑り弁】
蒸気機関で、蒸気口および排気口の開閉を行う箱形の弁。スライド‐バルブ。滑動弁。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐まさつ【滑り摩擦】
物体が、ある表面をすべる時、その物体に加えた力の、面に平行な成分と反対の向きに働く、面からの抵抗力。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐よ・る【滑り寄る】
〔自五〕
滑るようにして近寄る。すわったまま近寄る。にじりよる。枕草子76「蔭ながら―・りて聞く時もあり」
スペリング【spelling】
ヨーロッパ語のつづり字。綴字法。スペル。
す・べる【統べる・総べる】
〔他下一〕[文]す・ぶ(下二)
①個々のものを一つにする。別々のものをまとめる。大唐西域記長寛点「学ぶることは真俗を綜スヘ、信ずることは邪正を兼ねたり」。〈字鏡集〉
②支配する。管轄する。地蔵十輪経元慶点「輪王と作なりて四の洲渚を統スフべきひとなり」。「国を―・べる」
すべ・る【滑る・辷る】
〔自五〕
①物の上をなめらかに移行する。物の間を滞りなく通る。源氏物語夕顔「馬より―・りおりて」。狭衣物語4「御ぐし…取る手も―・るつやすぢの美しさなどの」。「スキーで雪山を―・る」「戸がよく―・る」
②にじり移る。すわったまますって行く。
③静かに退出する。源氏物語玉鬘「御使にかづけたる物を、いとわびしく傍痛しとおぼして、御気色あしければ、―・りまかでぬ」
④足がなめらかに動いて止まらない。古今著聞集16「あわて惑ひて出づとて、其の管の小竹に―・りてまろびにけり」。「雪道で―・った」
⑤位を降りる。退位する。平家物語1「位を―・らせ給ひて新院とぞ申しける」
⑥生まれおちる。傾城禁短気「何処の牛の骨やらしれぬ女の腹から―・つた餓鬼を」
⑦手に取ろうとしたものがすり抜ける。「手が―・って茶碗を落とす」
⑧思わず言う。「口が―・って秘密を漏らす」「筆が―・る」
⑨落第する。「入試に―・った」
⇒すべったの転んだの
スペル【spell】
(「字をつづる」の意)(→)スペリングに同じ。
⇒スペル‐チェック【spell-check】
スペル‐チェック【spell-check】
欧文の文書につづりの誤りがないか確認すること。
⇒スペル【spell】
スペルマ【sperma ラテン】
精子。精液。
スペルミン【spermine】
分子式C10H26N4 生体アミンの一種。ヒトの精子中から発見されたが、血清などほとんどすべての組織に存在する。精液の特異臭はその酸化生成物による。
すべろ‐ぎ【皇】
⇒すめろぎ
スペンサー【Herbert Spencer】
イギリスの哲学者・社会学者。ダーウィン進化論の影響のもとに、あらゆる事象を単純なものから複雑なものへの進化・発展として捉え、生物・心理・社会・道徳の諸現象を統一的に解明しようとした。その哲学思想は明治前半期の日本に大きな影響を与えた。主著「総合哲学体系」10巻。(1820〜1903)
スペンサー【Edmund Spenser】
イギリスの詩人。エリザベス朝文学の代表者の一人。キリスト教倫理を豊麗な詩語と多彩な詩型で歌う。エリザベス女王をも示唆する寓意的な叙事詩「妖精の女王」のほか、詩集「牧人の暦」など。(1552頃〜1599)
スペンダー【Stephen Spender】
イギリスの詩人・評論家。1930年代、オーデンを中心とする左翼詩人の一派に属した。53年「エンカウンター」誌の編集に参加。評論「破壊的要素」。(1909〜1995)
スペンディング‐ポリシー【spending policy】
不況期に大規模な財政支出を行なって景気回復を図る政策。アメリカでニュー‐ディールの一環として実施され、第二次大戦後も各国で財政による総需要の調整に用いる。
スポイト【spuit オランダ】
インクや液汁を少量吸いあげて他に移し入れるのに使う、一端にゴム製の袋が付いたガラスなどの管。液汁注入器。
スポイラー【spoiler】
①航空機で、気流を乱し、揚力を減少させて抗力を増加させる装置。翼の上面に設置され、一般には可動式の板状。速度を減じたり降下したりするために用いる。
②自動車で、空気流による揚力を減少させ、大きな駆動力でも空転しないようにするための翼。空力的固定板。
スポイル【spoil】
そこなうこと。台無しにすること。甘やかしてだめにすること。「子供を―する」
ず‐ほう【図法】ヅハフ
図形の作り方。特に、地球表面を地図に投影する方法。円筒図法・正射図法など。
ず‐ほう【修法】‥ホフ
〔仏〕(スホウとも)
⇒しゅほう
ず‐ぼう‥バウ
(「ぼうず」を倒置した隠語)坊主のこと。東海道中膝栗毛8「三すぢほどある薄鬢うすびんのあたま、やがて―に鳴る鐘ならば」
ず‐ぼうし【図法師】ヅボフ‥
治療法学習のために、身体各部を明らかに示した図。〈日葡辞書〉
スホーイ【Sukhoi ロシア】
(設計者の名に因む)ソ連・ロシアの戦闘機の機種の一つ。
スポーク【spoke】
車輪の軸受からリムに向かって放射状に出ている細長い棒。輻や。
スポークスマン【spokesman】
代弁者。特に、政府などの情報・見解を発表する担当者。
スポーツ【sport(s)】
陸上競技・野球・テニス・水泳・ボートレースなどから登山・狩猟などにいたるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。
⇒スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
⇒スポーツ‐ウェア【sportswear】
⇒スポーツ‐カー【sports car】
⇒スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
⇒スポーツ‐クラブ【sports club】
⇒スポーツ‐シャツ【sports shirt】
⇒スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
⇒スポーツ‐センター【sports center】
⇒スポーツ‐ドリンク
⇒スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
⇒スポーツ‐マン【sportsman】
⇒スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
スポーツの人体に及ぼす影響、競技者の健康管理などを研究・実践する医学。運動生理学・スポーツ臨床医学などを含む。体育運動医学。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ウェア【sportswear】
運動する時に着用する服の総称。また、競技の観戦者の服や活動的な服の意味にも用いる。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐カー【sports car】
運転を楽しむために作られた娯楽用乗用車。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
男性の髪型。前髪の輪郭を四角く刈り、両側と後ろを短く刈り上げたもの。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐クラブ【sports club】
①学校の運動部。また、企業や地域のスポーツ活動を行う組織。
②スポーツの講習や施設を提供する会員制組織。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐シャツ【sports shirt】
運動用のシャツ。また、軽快な感じのシャツの総称。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
スポーツ報道を中心に、娯楽・芸能関係の記事で構成される新聞。スポーツ紙。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐センター【sports center】
各種のスポーツができるように建設された総合スポーツ施設。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ドリンク
(sports drink)発汗によって失われた水分やミネラルなどを速やかに補給できるよう、成分を体液に近く調整してある清涼飲料。アイソトニック飲料。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
スポーツ用品を持ち運ぶための大型のかばん。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン【sportsman】
運動競技の選手。また、スポーツの得意な人。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
正々堂々と公明に勝負を争う、スポーツマンにふさわしい態度。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーティー【sporty】
スポーツ向き。服装・形などの軽快で活動的なさま。「―な乗用車」
ズボートー
(drop van zoet hout オランダの略訛)オランダから渡来した去痰きょたん薬。甘草を煎じつめて製したものという。オランダたんきり。ズドーボー。誹風柳多留12「平六がとこづぼうとうよく売れる」
ずほく‐めんさい‐うきょう‐が【頭北面西右脇臥】ヅ‥ウケフグワ
死者の頭を北に、顔を西に向け、右わきを下にして寝かせること。釈尊入滅の時の姿勢を模したもの。頭北西面右脇臥。謡曲、白髭「八十年の春のころ、―、抜提ばつだいの波と消え給ふ」
すぼけ
①ちぢむこと。狭くなること。
②まのぬけていること。また、その人。まぬけ。
③包茎の俗称。
す‐ぼし【角宿】
二十八宿の一つ。乙女座おとめざの首星スピカを含む部分。角かく。
す‐ぼし【素乾し】
日光または火にあてないで乾すこと。かげぼし。
すぼ・し【窄し】
〔形ク〕
①すぼんで細い。狭い。謡曲、清経「眼裏に塵あつて三界―・く」
②みすぼらしい。肩身が狭い。方丈記「朝夕―・き姿を恥ぢて」
ず‐ぼし【図星】ヅ‥
①的まとの中心の黒点。
②見込んだ所。人の思わくなどの、最も肝腎な所。急所。「―をつく」「どうだ、―だろう」
⇒図星を指される
 ⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ぶた【滑り蓋】
(→)スライド4に同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐べん【滑り弁】
蒸気機関で、蒸気口および排気口の開閉を行う箱形の弁。スライド‐バルブ。滑動弁。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐まさつ【滑り摩擦】
物体が、ある表面をすべる時、その物体に加えた力の、面に平行な成分と反対の向きに働く、面からの抵抗力。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐よ・る【滑り寄る】
〔自五〕
滑るようにして近寄る。すわったまま近寄る。にじりよる。枕草子76「蔭ながら―・りて聞く時もあり」
スペリング【spelling】
ヨーロッパ語のつづり字。綴字法。スペル。
す・べる【統べる・総べる】
〔他下一〕[文]す・ぶ(下二)
①個々のものを一つにする。別々のものをまとめる。大唐西域記長寛点「学ぶることは真俗を綜スヘ、信ずることは邪正を兼ねたり」。〈字鏡集〉
②支配する。管轄する。地蔵十輪経元慶点「輪王と作なりて四の洲渚を統スフべきひとなり」。「国を―・べる」
すべ・る【滑る・辷る】
〔自五〕
①物の上をなめらかに移行する。物の間を滞りなく通る。源氏物語夕顔「馬より―・りおりて」。狭衣物語4「御ぐし…取る手も―・るつやすぢの美しさなどの」。「スキーで雪山を―・る」「戸がよく―・る」
②にじり移る。すわったまますって行く。
③静かに退出する。源氏物語玉鬘「御使にかづけたる物を、いとわびしく傍痛しとおぼして、御気色あしければ、―・りまかでぬ」
④足がなめらかに動いて止まらない。古今著聞集16「あわて惑ひて出づとて、其の管の小竹に―・りてまろびにけり」。「雪道で―・った」
⑤位を降りる。退位する。平家物語1「位を―・らせ給ひて新院とぞ申しける」
⑥生まれおちる。傾城禁短気「何処の牛の骨やらしれぬ女の腹から―・つた餓鬼を」
⑦手に取ろうとしたものがすり抜ける。「手が―・って茶碗を落とす」
⑧思わず言う。「口が―・って秘密を漏らす」「筆が―・る」
⑨落第する。「入試に―・った」
⇒すべったの転んだの
スペル【spell】
(「字をつづる」の意)(→)スペリングに同じ。
⇒スペル‐チェック【spell-check】
スペル‐チェック【spell-check】
欧文の文書につづりの誤りがないか確認すること。
⇒スペル【spell】
スペルマ【sperma ラテン】
精子。精液。
スペルミン【spermine】
分子式C10H26N4 生体アミンの一種。ヒトの精子中から発見されたが、血清などほとんどすべての組織に存在する。精液の特異臭はその酸化生成物による。
すべろ‐ぎ【皇】
⇒すめろぎ
スペンサー【Herbert Spencer】
イギリスの哲学者・社会学者。ダーウィン進化論の影響のもとに、あらゆる事象を単純なものから複雑なものへの進化・発展として捉え、生物・心理・社会・道徳の諸現象を統一的に解明しようとした。その哲学思想は明治前半期の日本に大きな影響を与えた。主著「総合哲学体系」10巻。(1820〜1903)
スペンサー【Edmund Spenser】
イギリスの詩人。エリザベス朝文学の代表者の一人。キリスト教倫理を豊麗な詩語と多彩な詩型で歌う。エリザベス女王をも示唆する寓意的な叙事詩「妖精の女王」のほか、詩集「牧人の暦」など。(1552頃〜1599)
スペンダー【Stephen Spender】
イギリスの詩人・評論家。1930年代、オーデンを中心とする左翼詩人の一派に属した。53年「エンカウンター」誌の編集に参加。評論「破壊的要素」。(1909〜1995)
スペンディング‐ポリシー【spending policy】
不況期に大規模な財政支出を行なって景気回復を図る政策。アメリカでニュー‐ディールの一環として実施され、第二次大戦後も各国で財政による総需要の調整に用いる。
スポイト【spuit オランダ】
インクや液汁を少量吸いあげて他に移し入れるのに使う、一端にゴム製の袋が付いたガラスなどの管。液汁注入器。
スポイラー【spoiler】
①航空機で、気流を乱し、揚力を減少させて抗力を増加させる装置。翼の上面に設置され、一般には可動式の板状。速度を減じたり降下したりするために用いる。
②自動車で、空気流による揚力を減少させ、大きな駆動力でも空転しないようにするための翼。空力的固定板。
スポイル【spoil】
そこなうこと。台無しにすること。甘やかしてだめにすること。「子供を―する」
ず‐ほう【図法】ヅハフ
図形の作り方。特に、地球表面を地図に投影する方法。円筒図法・正射図法など。
ず‐ほう【修法】‥ホフ
〔仏〕(スホウとも)
⇒しゅほう
ず‐ぼう‥バウ
(「ぼうず」を倒置した隠語)坊主のこと。東海道中膝栗毛8「三すぢほどある薄鬢うすびんのあたま、やがて―に鳴る鐘ならば」
ず‐ぼうし【図法師】ヅボフ‥
治療法学習のために、身体各部を明らかに示した図。〈日葡辞書〉
スホーイ【Sukhoi ロシア】
(設計者の名に因む)ソ連・ロシアの戦闘機の機種の一つ。
スポーク【spoke】
車輪の軸受からリムに向かって放射状に出ている細長い棒。輻や。
スポークスマン【spokesman】
代弁者。特に、政府などの情報・見解を発表する担当者。
スポーツ【sport(s)】
陸上競技・野球・テニス・水泳・ボートレースなどから登山・狩猟などにいたるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。
⇒スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
⇒スポーツ‐ウェア【sportswear】
⇒スポーツ‐カー【sports car】
⇒スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
⇒スポーツ‐クラブ【sports club】
⇒スポーツ‐シャツ【sports shirt】
⇒スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
⇒スポーツ‐センター【sports center】
⇒スポーツ‐ドリンク
⇒スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
⇒スポーツ‐マン【sportsman】
⇒スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
スポーツの人体に及ぼす影響、競技者の健康管理などを研究・実践する医学。運動生理学・スポーツ臨床医学などを含む。体育運動医学。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ウェア【sportswear】
運動する時に着用する服の総称。また、競技の観戦者の服や活動的な服の意味にも用いる。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐カー【sports car】
運転を楽しむために作られた娯楽用乗用車。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
男性の髪型。前髪の輪郭を四角く刈り、両側と後ろを短く刈り上げたもの。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐クラブ【sports club】
①学校の運動部。また、企業や地域のスポーツ活動を行う組織。
②スポーツの講習や施設を提供する会員制組織。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐シャツ【sports shirt】
運動用のシャツ。また、軽快な感じのシャツの総称。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
スポーツ報道を中心に、娯楽・芸能関係の記事で構成される新聞。スポーツ紙。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐センター【sports center】
各種のスポーツができるように建設された総合スポーツ施設。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ドリンク
(sports drink)発汗によって失われた水分やミネラルなどを速やかに補給できるよう、成分を体液に近く調整してある清涼飲料。アイソトニック飲料。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
スポーツ用品を持ち運ぶための大型のかばん。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン【sportsman】
運動競技の選手。また、スポーツの得意な人。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
正々堂々と公明に勝負を争う、スポーツマンにふさわしい態度。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーティー【sporty】
スポーツ向き。服装・形などの軽快で活動的なさま。「―な乗用車」
ズボートー
(drop van zoet hout オランダの略訛)オランダから渡来した去痰きょたん薬。甘草を煎じつめて製したものという。オランダたんきり。ズドーボー。誹風柳多留12「平六がとこづぼうとうよく売れる」
ずほく‐めんさい‐うきょう‐が【頭北面西右脇臥】ヅ‥ウケフグワ
死者の頭を北に、顔を西に向け、右わきを下にして寝かせること。釈尊入滅の時の姿勢を模したもの。頭北西面右脇臥。謡曲、白髭「八十年の春のころ、―、抜提ばつだいの波と消え給ふ」
すぼけ
①ちぢむこと。狭くなること。
②まのぬけていること。また、その人。まぬけ。
③包茎の俗称。
す‐ぼし【角宿】
二十八宿の一つ。乙女座おとめざの首星スピカを含む部分。角かく。
す‐ぼし【素乾し】
日光または火にあてないで乾すこと。かげぼし。
すぼ・し【窄し】
〔形ク〕
①すぼんで細い。狭い。謡曲、清経「眼裏に塵あつて三界―・く」
②みすぼらしい。肩身が狭い。方丈記「朝夕―・き姿を恥ぢて」
ず‐ぼし【図星】ヅ‥
①的まとの中心の黒点。
②見込んだ所。人の思わくなどの、最も肝腎な所。急所。「―をつく」「どうだ、―だろう」
⇒図星を指される
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐ぶた【滑り蓋】
(→)スライド4に同じ。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐べん【滑り弁】
蒸気機関で、蒸気口および排気口の開閉を行う箱形の弁。スライド‐バルブ。滑動弁。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐まさつ【滑り摩擦】
物体が、ある表面をすべる時、その物体に加えた力の、面に平行な成分と反対の向きに働く、面からの抵抗力。
⇒すべり【滑り・辷り】
すべり‐よ・る【滑り寄る】
〔自五〕
滑るようにして近寄る。すわったまま近寄る。にじりよる。枕草子76「蔭ながら―・りて聞く時もあり」
スペリング【spelling】
ヨーロッパ語のつづり字。綴字法。スペル。
す・べる【統べる・総べる】
〔他下一〕[文]す・ぶ(下二)
①個々のものを一つにする。別々のものをまとめる。大唐西域記長寛点「学ぶることは真俗を綜スヘ、信ずることは邪正を兼ねたり」。〈字鏡集〉
②支配する。管轄する。地蔵十輪経元慶点「輪王と作なりて四の洲渚を統スフべきひとなり」。「国を―・べる」
すべ・る【滑る・辷る】
〔自五〕
①物の上をなめらかに移行する。物の間を滞りなく通る。源氏物語夕顔「馬より―・りおりて」。狭衣物語4「御ぐし…取る手も―・るつやすぢの美しさなどの」。「スキーで雪山を―・る」「戸がよく―・る」
②にじり移る。すわったまますって行く。
③静かに退出する。源氏物語玉鬘「御使にかづけたる物を、いとわびしく傍痛しとおぼして、御気色あしければ、―・りまかでぬ」
④足がなめらかに動いて止まらない。古今著聞集16「あわて惑ひて出づとて、其の管の小竹に―・りてまろびにけり」。「雪道で―・った」
⑤位を降りる。退位する。平家物語1「位を―・らせ給ひて新院とぞ申しける」
⑥生まれおちる。傾城禁短気「何処の牛の骨やらしれぬ女の腹から―・つた餓鬼を」
⑦手に取ろうとしたものがすり抜ける。「手が―・って茶碗を落とす」
⑧思わず言う。「口が―・って秘密を漏らす」「筆が―・る」
⑨落第する。「入試に―・った」
⇒すべったの転んだの
スペル【spell】
(「字をつづる」の意)(→)スペリングに同じ。
⇒スペル‐チェック【spell-check】
スペル‐チェック【spell-check】
欧文の文書につづりの誤りがないか確認すること。
⇒スペル【spell】
スペルマ【sperma ラテン】
精子。精液。
スペルミン【spermine】
分子式C10H26N4 生体アミンの一種。ヒトの精子中から発見されたが、血清などほとんどすべての組織に存在する。精液の特異臭はその酸化生成物による。
すべろ‐ぎ【皇】
⇒すめろぎ
スペンサー【Herbert Spencer】
イギリスの哲学者・社会学者。ダーウィン進化論の影響のもとに、あらゆる事象を単純なものから複雑なものへの進化・発展として捉え、生物・心理・社会・道徳の諸現象を統一的に解明しようとした。その哲学思想は明治前半期の日本に大きな影響を与えた。主著「総合哲学体系」10巻。(1820〜1903)
スペンサー【Edmund Spenser】
イギリスの詩人。エリザベス朝文学の代表者の一人。キリスト教倫理を豊麗な詩語と多彩な詩型で歌う。エリザベス女王をも示唆する寓意的な叙事詩「妖精の女王」のほか、詩集「牧人の暦」など。(1552頃〜1599)
スペンダー【Stephen Spender】
イギリスの詩人・評論家。1930年代、オーデンを中心とする左翼詩人の一派に属した。53年「エンカウンター」誌の編集に参加。評論「破壊的要素」。(1909〜1995)
スペンディング‐ポリシー【spending policy】
不況期に大規模な財政支出を行なって景気回復を図る政策。アメリカでニュー‐ディールの一環として実施され、第二次大戦後も各国で財政による総需要の調整に用いる。
スポイト【spuit オランダ】
インクや液汁を少量吸いあげて他に移し入れるのに使う、一端にゴム製の袋が付いたガラスなどの管。液汁注入器。
スポイラー【spoiler】
①航空機で、気流を乱し、揚力を減少させて抗力を増加させる装置。翼の上面に設置され、一般には可動式の板状。速度を減じたり降下したりするために用いる。
②自動車で、空気流による揚力を減少させ、大きな駆動力でも空転しないようにするための翼。空力的固定板。
スポイル【spoil】
そこなうこと。台無しにすること。甘やかしてだめにすること。「子供を―する」
ず‐ほう【図法】ヅハフ
図形の作り方。特に、地球表面を地図に投影する方法。円筒図法・正射図法など。
ず‐ほう【修法】‥ホフ
〔仏〕(スホウとも)
⇒しゅほう
ず‐ぼう‥バウ
(「ぼうず」を倒置した隠語)坊主のこと。東海道中膝栗毛8「三すぢほどある薄鬢うすびんのあたま、やがて―に鳴る鐘ならば」
ず‐ぼうし【図法師】ヅボフ‥
治療法学習のために、身体各部を明らかに示した図。〈日葡辞書〉
スホーイ【Sukhoi ロシア】
(設計者の名に因む)ソ連・ロシアの戦闘機の機種の一つ。
スポーク【spoke】
車輪の軸受からリムに向かって放射状に出ている細長い棒。輻や。
スポークスマン【spokesman】
代弁者。特に、政府などの情報・見解を発表する担当者。
スポーツ【sport(s)】
陸上競技・野球・テニス・水泳・ボートレースなどから登山・狩猟などにいたるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。
⇒スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
⇒スポーツ‐ウェア【sportswear】
⇒スポーツ‐カー【sports car】
⇒スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
⇒スポーツ‐クラブ【sports club】
⇒スポーツ‐シャツ【sports shirt】
⇒スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
⇒スポーツ‐センター【sports center】
⇒スポーツ‐ドリンク
⇒スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
⇒スポーツ‐マン【sportsman】
⇒スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
スポーツ‐いがく【スポーツ医学】
スポーツの人体に及ぼす影響、競技者の健康管理などを研究・実践する医学。運動生理学・スポーツ臨床医学などを含む。体育運動医学。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ウェア【sportswear】
運動する時に着用する服の総称。また、競技の観戦者の服や活動的な服の意味にも用いる。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐カー【sports car】
運転を楽しむために作られた娯楽用乗用車。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐がり【スポーツ刈り】
男性の髪型。前髪の輪郭を四角く刈り、両側と後ろを短く刈り上げたもの。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐クラブ【sports club】
①学校の運動部。また、企業や地域のスポーツ活動を行う組織。
②スポーツの講習や施設を提供する会員制組織。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐シャツ【sports shirt】
運動用のシャツ。また、軽快な感じのシャツの総称。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐しんぶん【スポーツ新聞】
スポーツ報道を中心に、娯楽・芸能関係の記事で構成される新聞。スポーツ紙。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐センター【sports center】
各種のスポーツができるように建設された総合スポーツ施設。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐ドリンク
(sports drink)発汗によって失われた水分やミネラルなどを速やかに補給できるよう、成分を体液に近く調整してある清涼飲料。アイソトニック飲料。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐バッグ【sport(s) bag】
スポーツ用品を持ち運ぶための大型のかばん。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン【sportsman】
運動競技の選手。また、スポーツの得意な人。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーツ‐マン‐シップ【sportsmanship】
正々堂々と公明に勝負を争う、スポーツマンにふさわしい態度。
⇒スポーツ【sport(s)】
スポーティー【sporty】
スポーツ向き。服装・形などの軽快で活動的なさま。「―な乗用車」
ズボートー
(drop van zoet hout オランダの略訛)オランダから渡来した去痰きょたん薬。甘草を煎じつめて製したものという。オランダたんきり。ズドーボー。誹風柳多留12「平六がとこづぼうとうよく売れる」
ずほく‐めんさい‐うきょう‐が【頭北面西右脇臥】ヅ‥ウケフグワ
死者の頭を北に、顔を西に向け、右わきを下にして寝かせること。釈尊入滅の時の姿勢を模したもの。頭北西面右脇臥。謡曲、白髭「八十年の春のころ、―、抜提ばつだいの波と消え給ふ」
すぼけ
①ちぢむこと。狭くなること。
②まのぬけていること。また、その人。まぬけ。
③包茎の俗称。
す‐ぼし【角宿】
二十八宿の一つ。乙女座おとめざの首星スピカを含む部分。角かく。
す‐ぼし【素乾し】
日光または火にあてないで乾すこと。かげぼし。
すぼ・し【窄し】
〔形ク〕
①すぼんで細い。狭い。謡曲、清経「眼裏に塵あつて三界―・く」
②みすぼらしい。肩身が狭い。方丈記「朝夕―・き姿を恥ぢて」
ず‐ぼし【図星】ヅ‥
①的まとの中心の黒点。
②見込んだ所。人の思わくなどの、最も肝腎な所。急所。「―をつく」「どうだ、―だろう」
⇒図星を指される
すべ‐よく【術よく】🔗⭐🔉
すべ‐よく【術よく】
さっぱりと。手際よく。歌舞伎、三人吉三廓初買「―おれに渡さにやあ、腕づくでも取らにやあならねえ」
ばけ【術】🔗⭐🔉
ばけ【術】
(「化ばけ」と同源)てだて。はかりごと。神代紀下「必ず善き―有らむ、願はくは救ひたまへ」
[漢]術🔗⭐🔉
術 字形
 筆順
筆順
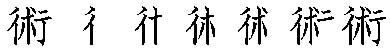 〔行部5画/11画/教育/2949・3D51〕
[
〔行部5画/11画/教育/2949・3D51〕
[ ] 字形
] 字形
 〔行部5画/11画〕
〔音〕ジュツ(呉)
〔訓〕すべ
[意味]
①わざ。技芸。「術を使う」「学術・技術・算術・剣術・医術・催眠術」
②手だて。手段。すべ。「秘術」
③はかりごと。「術策・術数」
[解字]
形声。「行」(=みち)+音符「朮」(=したがう)。人びとが通いなれた道、何かをするための手だて、の意。
[下ツキ
医術・学術・奇術・技術・弓術・芸術・剣術・幻術・詐術・算術・施術・射術・柔術・手術・呪術・心術・針術・鍼術・仁術・仙術・戦術・槍術・道術・読唇術・読心術・忍術・馬術・秘術・美術・腹話術・巫術・武術・方術・砲術・棒術・魔術・妖術・隆鼻術・錬金術・話術
〔行部5画/11画〕
〔音〕ジュツ(呉)
〔訓〕すべ
[意味]
①わざ。技芸。「術を使う」「学術・技術・算術・剣術・医術・催眠術」
②手だて。手段。すべ。「秘術」
③はかりごと。「術策・術数」
[解字]
形声。「行」(=みち)+音符「朮」(=したがう)。人びとが通いなれた道、何かをするための手だて、の意。
[下ツキ
医術・学術・奇術・技術・弓術・芸術・剣術・幻術・詐術・算術・施術・射術・柔術・手術・呪術・心術・針術・鍼術・仁術・仙術・戦術・槍術・道術・読唇術・読心術・忍術・馬術・秘術・美術・腹話術・巫術・武術・方術・砲術・棒術・魔術・妖術・隆鼻術・錬金術・話術
 筆順
筆順
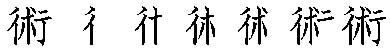 〔行部5画/11画/教育/2949・3D51〕
[
〔行部5画/11画/教育/2949・3D51〕
[ ] 字形
] 字形
 〔行部5画/11画〕
〔音〕ジュツ(呉)
〔訓〕すべ
[意味]
①わざ。技芸。「術を使う」「学術・技術・算術・剣術・医術・催眠術」
②手だて。手段。すべ。「秘術」
③はかりごと。「術策・術数」
[解字]
形声。「行」(=みち)+音符「朮」(=したがう)。人びとが通いなれた道、何かをするための手だて、の意。
[下ツキ
医術・学術・奇術・技術・弓術・芸術・剣術・幻術・詐術・算術・施術・射術・柔術・手術・呪術・心術・針術・鍼術・仁術・仙術・戦術・槍術・道術・読唇術・読心術・忍術・馬術・秘術・美術・腹話術・巫術・武術・方術・砲術・棒術・魔術・妖術・隆鼻術・錬金術・話術
〔行部5画/11画〕
〔音〕ジュツ(呉)
〔訓〕すべ
[意味]
①わざ。技芸。「術を使う」「学術・技術・算術・剣術・医術・催眠術」
②手だて。手段。すべ。「秘術」
③はかりごと。「術策・術数」
[解字]
形声。「行」(=みち)+音符「朮」(=したがう)。人びとが通いなれた道、何かをするための手だて、の意。
[下ツキ
医術・学術・奇術・技術・弓術・芸術・剣術・幻術・詐術・算術・施術・射術・柔術・手術・呪術・心術・針術・鍼術・仁術・仙術・戦術・槍術・道術・読唇術・読心術・忍術・馬術・秘術・美術・腹話術・巫術・武術・方術・砲術・棒術・魔術・妖術・隆鼻術・錬金術・話術
広辞苑に「術」で始まるの検索結果 1-27。