複数辞典一括検索+![]()
![]()
之 の🔗⭐🔉
【之】
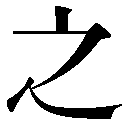 3画 丶部 [人名漢字]
区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456
《音読み》 シ
3画 丶部 [人名漢字]
区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 ゆく/これ/この/の
《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 ゆく/これ/この/の
《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より
《意味》
 {動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」
{動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」
 {指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕
{指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕
 {指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕
{指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕
 {助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕
{助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕
 {助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕
《解字》
{助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕
《解字》
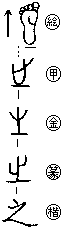 象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其
象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其 之、彼
之、彼 此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
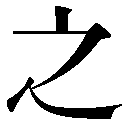 3画 丶部 [人名漢字]
区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456
《音読み》 シ
3画 丶部 [人名漢字]
区点=3923 16進=4737 シフトJIS=9456
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 ゆく/これ/この/の
《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 ゆく/これ/この/の
《名付け》 いたる・くに・これ・つな・の・のぶ・ひさ・ひで・ゆき・よし・より
《意味》
 {動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」
{動}ゆく。いく。…に至る。「孔子之衛=孔子衛ニ之ク」〔→礼記〕「之死=死ニ之ルマデ」
 {指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕
{指}これ。この。近いものをさし示すことば。「学而時習之=学ビテ時ニ之ヲ習フ」〔→論語〕「之子于帰=之ノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕
 {指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕
{指}これ。客語の位置にあって、上の語が動詞であることを示すことば。何をさすかは明示されない。「頃之=之ヲ頃クシテ」「知之為知之=之ヲ知ルヲ之ヲ知ルト為ス」〔→論語〕
 {助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕
{助}の。上の語句が下の語句を修飾することを示すことば。「古之君子仕乎=古之君子ハ仕ヘタルカ」〔→孟子〕
 {助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕
《解字》
{助}の。A。のB。すること(するさま、したとき)という意味の句をつくることば。「君子之於天下也=君子之天下ニ於ケルヤ」〔→論語〕
《解字》
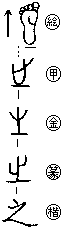 象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其
象形。足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。進みいく足の動作を意味する。先(跣センの原字。足さき)の字の上部は、この字の変形である。「これ」ということばに当てたのは音を利用した当て字。是シ・コレ、斯シ・コレ、此シ・コレなども当て字で之シに近いが、其 之、彼
之、彼 此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
乃 の🔗⭐🔉
【乃】
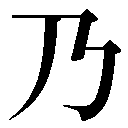 2画 丿部 [人名漢字]
区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454
《音読み》 ダイ
2画 丿部 [人名漢字]
区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454
《音読み》 ダイ /ナイ/ノ
/ナイ/ノ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の
《名付け》 いまし・おさむ・の
《意味》
i〉
《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の
《名付け》 いまし・おさむ・の
《意味》
 {接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕
{接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕
 {接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕
{接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕
 {代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕
〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」
《解字》
{代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕
〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」
《解字》
 指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
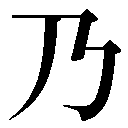 2画 丿部 [人名漢字]
区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454
《音読み》 ダイ
2画 丿部 [人名漢字]
区点=3921 16進=4735 シフトJIS=9454
《音読み》 ダイ /ナイ/ノ
/ナイ/ノ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の
《名付け》 いまし・おさむ・の
《意味》
i〉
《訓読み》 すなわち(すなはち)/なんじ(なんぢ)/の
《名付け》 いまし・おさむ・の
《意味》
 {接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕
{接続}すなわち(スナハチ)。ずばりと割り切らず、間をおいてつなげる気持ちをあらわすことば。そこでやっと。やむなく。〈同義語〉→迺。「乃許之=乃チコレヲ許セリ」〔→左伝〕
 {接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕
{接続}すなわち(スナハチ)。まずそれぐらい。まあそれが。「乃所謂善也=乃チイハユル善ナリ」〔→孟子〕
 {代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕
〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」
《解字》
{代}なんじ(ナンヂ)。第二人称の代名詞。▽女ナンジ・汝ナンジと同じ。「乃祖乃父=乃ノ祖乃ノ父」〔→書経〕
〔国〕の。助詞の「の」に当てた用法。「日乃丸ヒノマル」
《解字》
 指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
指事。耳たぶのようにぐにゃりと曲がったさまを示す。朶ダ(だらりとたれる)・仍ジョウ(やわらかくてなずむ)の音符となる。また、さっぱりと割り切れない気持ちをあらわす接続詞に転用され、迺とも書く。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
喃 のう🔗⭐🔉
【喃】
 12画 口部
区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66
《音読み》 ナン
12画 口部
区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66
《音読み》 ナン /ネン(ネム)
/ネン(ネム) /ダン(ダム)
/ダン(ダム) 〈n
〈n n〉
《訓読み》 のう(なう)
《意味》
n〉
《訓読み》 のう(なう)
《意味》
 {動}口ごもりつつしゃべる。
{動}口ごもりつつしゃべる。
 「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」
〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。
《解字》
会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。
《熟語》
→熟語
「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」
〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。
《解字》
会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。
《熟語》
→熟語
 12画 口部
区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66
《音読み》 ナン
12画 口部
区点=5139 16進=5347 シフトJIS=9A66
《音読み》 ナン /ネン(ネム)
/ネン(ネム) /ダン(ダム)
/ダン(ダム) 〈n
〈n n〉
《訓読み》 のう(なう)
《意味》
n〉
《訓読み》 のう(なう)
《意味》
 {動}口ごもりつつしゃべる。
{動}口ごもりつつしゃべる。
 「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」
〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。
《解字》
会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。
《熟語》
→熟語
「喃喃ナンナン」とは、もたもたといつまでも続けてしゃべるさま。「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」
〔国〕のう(ナウ)。人に呼びかける声。もしもし。
《解字》
会意兼形声。南は、納(中に入れる)と同系のことばで、中にこもる意を含む。喃は「口+音符南」で、口の中にこもってはっきり聞きとれないしゃべり方。
《熟語》
→熟語
嚢筐 ノウキョウ🔗⭐🔉
【嚢筐】
ノウキョウ 衣類や書類を入れる袋や、竹製のかご。
悩殺 ノウサツ🔗⭐🔉
【悩殺】
ノウサツ 非常に悩ます。特に、女が女の美しさなどで男の心をかき乱すこと。▽「殺」は、強めの助辞。
有能 ノウアリ🔗⭐🔉
【有能】
ユウノウ・ノウアリ 才能があること。また、その人。
濃厚 ノウコウ🔗⭐🔉
【濃厚】
ノウコウ 味・香り・色などが、こくてこってりしていること。〈対語〉淡泊。
濃艶 ノウエン🔗⭐🔉
【濃艶】
ノウエン あでやかで美しい。
直衣 ノウシ🔗⭐🔉
【直衣】
ノウシ〔国〕平安時代以後の天皇・貴族の平常服。袍ホウに似ているが、幅がせまく、たけがやや短い。
篦 の🔗⭐🔉
【篦】
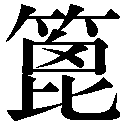 16画 竹部
区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2
【箆】異体字異体字
16画 竹部
区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2
【箆】異体字異体字
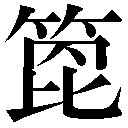 14画 竹部
区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD
《音読み》 ヘイ
14画 竹部
区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD
《音読み》 ヘイ /ヒ
/ヒ /ハイ
/ハイ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 くし/へら/の
《意味》
〉
《訓読み》 くし/へら/の
《意味》
 {名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。
〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」
〔国〕
{名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。
〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」
〔国〕 へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。
へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。 の。矢がら。
《解字》
会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。
《単語家族》
比(並ぶ)と同系。
《類義》
梳ソは、目のあらいすきぐし。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
の。矢がら。
《解字》
会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。
《単語家族》
比(並ぶ)と同系。
《類義》
梳ソは、目のあらいすきぐし。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
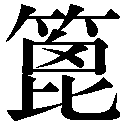 16画 竹部
区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2
【箆】異体字異体字
16画 竹部
区点=6836 16進=6444 シフトJIS=E2C2
【箆】異体字異体字
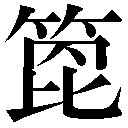 14画 竹部
区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD
《音読み》 ヘイ
14画 竹部
区点=4247 16進=4A4F シフトJIS=95CD
《音読み》 ヘイ /ヒ
/ヒ /ハイ
/ハイ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 くし/へら/の
《意味》
〉
《訓読み》 くし/へら/の
《意味》
 {名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。
〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」
〔国〕
{名}くし。節のびっしり並んだ竹ぐし。けすじたて。すじとおし。
〈類義語〉→梳。「梳篦ソヒ」
〔国〕 へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。
へら。細長く平たくけずってつくった竹の小刀。 の。矢がら。
《解字》
会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。
《単語家族》
比(並ぶ)と同系。
《類義》
梳ソは、目のあらいすきぐし。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
の。矢がら。
《解字》
会意兼形声。下部の字(音ヒ・ヘイ)は、びっしりと並ぶ意を含む。篦はそれを音符とし、竹を加えた字。
《単語家族》
比(並ぶ)と同系。
《類義》
梳ソは、目のあらいすきぐし。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
納会 ノウカイ🔗⭐🔉
【納会】
ノウカイ〔国〕 一年の最後の会合。おさめ会。
一年の最後の会合。おさめ会。 取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。
取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。
 一年の最後の会合。おさめ会。
一年の最後の会合。おさめ会。 取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。
取引所で、その月の最後のたちあい。▽十二月末の納会を年末納会・大納会という。
納吉 ノウキツ🔗⭐🔉
納采 ノウサイ🔗⭐🔉
納貢 ノウコウ🔗⭐🔉
【納貢】
ノウコウ みつぎ物をおさめる。
納骨 ノウコツ🔗⭐🔉
【納骨】
ノウコツ・ホネヲオサム 死んだ人の遺骨を寺や墓などにおさめる。
納経 ノウキョウ🔗⭐🔉
【納経】
ノウキョウ〔仏〕 書写した経典を寺に奉納すること。
書写した経典を寺に奉納すること。 寺で経をよむこと。
寺で経をよむこと。
 書写した経典を寺に奉納すること。
書写した経典を寺に奉納すること。 寺で経をよむこと。
寺で経をよむこと。
納款 ノウカン🔗⭐🔉
【納款】
ノウカン・カンヲイル 敵によしみを通ずる。敵に内通する。
能 のう🔗⭐🔉
【能】
 10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》
10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》  ノウ/ノ
ノウ/ノ /ドウ
/ドウ 〈n
〈n ng〉/
ng〉/ ダイ
ダイ /ナイ
/ナイ /タイ
/タイ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》

 {動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
 {名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
 {形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
 {動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕
{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

 {動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
 {名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
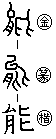 会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》
10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》  ノウ/ノ
ノウ/ノ /ドウ
/ドウ 〈n
〈n ng〉/
ng〉/ ダイ
ダイ /ナイ
/ナイ /タイ
/タイ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》

 {動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
 {名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
 {形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
 {動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕
{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

 {動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
 {名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
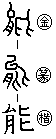 会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
能士 ノウシ🔗⭐🔉
【能士】
ノウシ 働きのある人。また、才能のある人物。
能化 ノウカ🔗⭐🔉
【能化】
 ノウカ 順調に変化する。
ノウカ 順調に変化する。 ノウゲ〔仏〕
ノウゲ〔仏〕 他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。
他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。 師である僧。人を教えみちびく人。
師である僧。人を教えみちびく人。
 ノウカ 順調に変化する。
ノウカ 順調に変化する。 ノウゲ〔仏〕
ノウゲ〔仏〕 他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。
他を教化するもの。▽衆生シュジョウに対しては仏、俗人に対しては、僧が能化である。 師である僧。人を教えみちびく人。
師である僧。人を教えみちびく人。
能言 ノウゲン🔗⭐🔉
【能弁】
ノウベン〔国〕弁舌がたっしゃである。〈類義語〉雄弁。『能言ノウゲン』
能官 ノウカン🔗⭐🔉
【能吏】
ノウリ 才能のある役人。物事を的確に処理する役人。『能官ノウカン』
能事 ノウジ🔗⭐🔉
【能事】
ノウジ  なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。
なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。 特別にすぐれたわざ。
特別にすぐれたわざ。 事をすることができる。
事をすることができる。
 なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。
なしうる事がら。また、しとげなければならない事がら。 特別にすぐれたわざ。
特別にすぐれたわざ。 事をすることができる。
事をすることができる。
能書 ノウガキ🔗⭐🔉
【能書】
 ノウショ「能筆」と同じ。
ノウショ「能筆」と同じ。 ノウガキ〔国〕
ノウガキ〔国〕 薬や商品などの効能をしるした文書。
薬や商品などの効能をしるした文書。 効能を宣伝することば。
効能を宣伝することば。
 ノウショ「能筆」と同じ。
ノウショ「能筆」と同じ。 ノウガキ〔国〕
ノウガキ〔国〕 薬や商品などの効能をしるした文書。
薬や商品などの効能をしるした文書。 効能を宣伝することば。
効能を宣伝することば。
能幹 ノウカン🔗⭐🔉
【能幹】
ノウカン  はたらき。
はたらき。 才能がある。
才能がある。
 はたらき。
はたらき。 才能がある。
才能がある。
脳溢血 ノウイッケツ🔗⭐🔉
【脳溢血】
ノウイッケツ 脳の血管が破れて脳の組織内に出血する病気。『脳出血ノウシュッケツ』
膿死 ノウシ🔗⭐🔉
【膿死】
ノウシ ただれ、腐って死ぬ。
衲衣 ノウエ🔗⭐🔉
【衲衣】
ノウエ  僧が着る衣。
僧が着る衣。 転じて、僧のこと。
転じて、僧のこと。
 僧が着る衣。
僧が着る衣。 転じて、僧のこと。
転じて、僧のこと。
農芸 ノウゲイ🔗⭐🔉
【農芸】
ノウゲイ  農業と園芸。
農業と園芸。 農業を行うための技術。
農業を行うための技術。
 農業と園芸。
農業と園芸。 農業を行うための技術。
農業を行うための技術。
農家 ノウカ🔗⭐🔉
農耕 ノウコウ🔗⭐🔉
【農耕】
ノウコウ 田畑を耕す。畑仕事。
農蚕 ノウサン🔗⭐🔉
【農蚕】
ノウサン 耕作の仕事と、かいこを飼う仕事。農業と養蚕。『農桑ノウソウ』
農期 ノウキ🔗⭐🔉
【農時】
ノウジ 田畑を耕す、草とりをする、作物をとり入れるなど、農業の仕事の忙しい時期。『農期ノウキ』「不違農時、穀不可勝食也=農時ヲ違ヘズンバ、穀ハ食ラフニ勝フベカラズ」〔→孟子〕
農園 ノウエン🔗⭐🔉
【農圃】
ノウホ 農作物を栽培するために区切った土地。『農園ノウエン・農場ノウジョウ』▽「圃」は、苗床。「且悲就行役、安得営農圃=カツ悲シンデ行役ニ就ク、イヅクンゾ農圃ヲ営ムヲ得ン」〔→李白〕
農業 ノウギョウ🔗⭐🔉
【農業】
ノウギョウ 生業として、田畑を耕し、作物を育てる仕事。
農稼 ノウカ🔗⭐🔉
【農稼】
ノウカ 田畑を耕し穀物をうえる。〈類義語〉耕稼コウカ。
野 の🔗⭐🔉
【野】
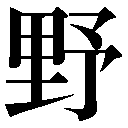 11画 里部 [二年]
区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC
【埜】異体字異体字
11画 里部 [二年]
区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC
【埜】異体字異体字
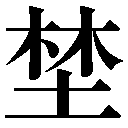 11画 土部
区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457
《常用音訓》ヤ/の
《音読み》
11画 土部
区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457
《常用音訓》ヤ/の
《音読み》  ヤ
ヤ
 〈y
〈y 〉/
〉/ ショ
ショ /ジョ
/ジョ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 の
《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ
《意味》
〉
《訓読み》 の
《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ
《意味》

 {名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕
{名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕
 {名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」
{名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」
 {名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」
{名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」
 ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕
ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕
 ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」
ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」
 {名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」
〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」
《解字》
{名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」
〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」
《解字》
 会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。
《単語家族》
豫ヨ(=予。のびのび)
会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。
《単語家族》
豫ヨ(=予。のびのび) 抒ジョ(のばす)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
抒ジョ(のばす)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
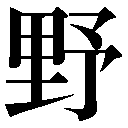 11画 里部 [二年]
区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC
【埜】異体字異体字
11画 里部 [二年]
区点=4478 16進=4C6E シフトJIS=96EC
【埜】異体字異体字
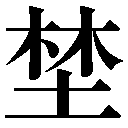 11画 土部
区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457
《常用音訓》ヤ/の
《音読み》
11画 土部
区点=3924 16進=4738 シフトJIS=9457
《常用音訓》ヤ/の
《音読み》  ヤ
ヤ
 〈y
〈y 〉/
〉/ ショ
ショ /ジョ
/ジョ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 の
《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ
《意味》
〉
《訓読み》 の
《名付け》 とお・なお・ぬ・の・ひろ
《意味》

 {名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕
{名}の。ひろくのびた大地。▽せま苦しい都市に対して、のび広がった郊外の地。「原野」「曠野コウヤ(広く何もないのはら)」「野有死麕=野ニ死セル麕有リ」〔→詩経〕
 {名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」
{名}天上の二十八宿に応じて、中国を二十八に区分したときのそれぞれの区域。また、のち、区分したそれぞれの範囲のこと。「分野」
 {名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」
{名・形}朝廷に対して、民間のこと。「在野」「朝野一致」
 ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕
ヤナリ{形}そぼくで洗練されていない。ひなびた。〈対語〉→雅ガ。「野人」「野性」「野哉由也=野ナルカナ由ヤ」〔→論語〕
 ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」
ヤナリ{形}おさえがきかずあらっぽい。かってな。「野心」
 {名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」
〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」
《解字》
{名}いなかにある家。畑の中の小屋。〈同義語〉→墅。「別野(=別墅)」
〔国〕野球のグラウンド。「外野」「野手」
《解字》
 会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。
《単語家族》
豫ヨ(=予。のびのび)
会意兼形声。予ヨは、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。▽古字の埜ヤは「林+土」の会意文字。
《単語家族》
豫ヨ(=予。のびのび) 抒ジョ(のばす)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
抒ジョ(のばす)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「の」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む