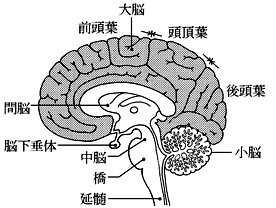複数辞典一括検索+![]()
![]()
の(音節)🔗⭐🔉
の
①舌尖を前硬口蓋に接して発する鼻子音〔n〕と母音〔o〕との結合した音節。〔no〕 上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔no〕乙〔nö〕2類の別があった。
②平仮名「の」は「乃」の草体。片仮名「ノ」は「乃」の最初の1画。
の【荷】🔗⭐🔉
の【荷】
荷にの古形。複合語に用いる。万葉集2「―前さきの篋はこの」
の【野】🔗⭐🔉
の【幅】🔗⭐🔉
の【幅】
①布の幅はばを数える語。一幅は普通鯨尺8寸ないし1尺(約30センチメートルないし38センチメートル)。「三み―ぶとん」
②一幅分の布。はぎ合わせたものの部分についていう。
の【箆】🔗⭐🔉
の【箆】
①ヤダケの古名。〈倭名類聚鈔20〉
②矢柄やがら。平家物語9「馬の額を―深に射させて」
の(助詞)🔗⭐🔉
の
〔助詞〕
➊(格助詞)
①連体格を示す。前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容を限定する。現代語では「の」の前後の内容に場面の差がない時に使われ、その差がある時は「…からの」「…までの」のように、その差を示す語を補って使うが、古代語では場面から理解できれば「…の」だけで使えた。後に付く体言が省略され、体言に準じて使われることもある。
㋐場所を示す。…にある。…にいる。…における。皇極紀「彼方おちかた―浅野―雉きぎし」。万葉集7「巻向―桧原の山を」。土佐日記「県あがた―四年五年果てて」。古今和歌集序「大空―月」。平家物語9「宇治川―先陣」。「東京―おじさん」
㋑時を示す。…における。万葉集2「秋―月夜は」。万葉集12「夕よい―物思ひ」。「昨日―出来事」
㋒位置・方角を示す。…に対する。万葉集2「御井―上より」。万葉集4「餓鬼―後しりえにぬかづくがごと」。「都―西北」
㋓向かって行く時・所を示す。…までの。…への。万葉集15「会はむ日―形見にせよと」。伊勢物語「都―つとにいざといはましを」。源氏物語若紫「朱雀院―行幸あるべし」
㋔対象を示す。…への。…との。…についての。源氏物語手習「山ごもり―御羨み」。源氏物語玉鬘「故少弐―仲悪しかりける国人」。「自動車―運転」「夫―操縦法」
㋕所有者を示す。「が」に比べ敬意をこめて使われると捉えられることもある。…のものである。…が持っている。古事記中「をとめ―床の辺」。万葉集1「采女―袖」。源氏物語葵「若君―御乳母」。史記抄「晋文公―夫人は繆公―女ぢや」。「私―本」「あなた―家」
㋖所属を示す。…に属している。万葉集1「珠裳たまも―裾に」。万葉集5「玉桙の道―隈廻くまみに」。万葉集5「天の下申し給ひし家―子と選び給ひて」。竹取物語「駿河の国にあなる山―頂き」。平家物語1「神祇官―官人」。「本校―生徒」「腕―付け根」「子供―手を引く」「5月―5日」「東京―世田谷」
㋗同格の関係であることを示す。…である。…で。…であり、かつ…である。万葉集9「見てしかといぶせむ時―垣ほなす人の問ふ時」。今昔物語集31「若き女―年二十余ばかりにていと清げなる出で来たり」。蒙求抄10「歩兵の官の人―厨に営む人あつて」。「弟―三郎」
㋘原料・材料を示す。…でできた。古事記上「玉―みすまる」。古今和歌集春「白 しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」
㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」
㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」
㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」
㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」
㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」
㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」
→が。
②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)
㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」
㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」
③体言を受け、連用修飾語を示す。
㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」
㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」
④もたらした主体を示す。
㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」
㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」
㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」
㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」
⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」
➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)
①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」
②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」
➌(終助詞)
①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」
②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」
➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」
しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」
㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」
㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」
㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」
㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」
㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」
㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」
→が。
②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)
㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」
㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」
③体言を受け、連用修飾語を示す。
㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」
㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」
④もたらした主体を示す。
㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」
㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」
㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」
㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」
⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」
➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)
①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」
②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」
➌(終助詞)
①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」
②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」
➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」
 しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」
㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」
㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」
㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」
㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」
㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」
㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」
→が。
②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)
㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」
㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」
③体言を受け、連用修飾語を示す。
㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」
㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」
④もたらした主体を示す。
㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」
㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」
㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」
㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」
⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」
➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)
①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」
②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」
➌(終助詞)
①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」
②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」
➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」
しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」
㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」
㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」
㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」
㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」
㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」
㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」
→が。
②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)
㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」
㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」
③体言を受け、連用修飾語を示す。
㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」
㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」
④もたらした主体を示す。
㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」
㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」
㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」
㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」
⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」
➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)
①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」
②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」
➌(終助詞)
①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」
②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」
➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」
ノア【NOAA】🔗⭐🔉
ノア【NOAA】
(National Oceanic and Atmospheric Administration)アメリカ国立海洋大気庁。
ノア【Noah】🔗⭐🔉
ノア【Noah】
旧約聖書創世記6章以下の洪水伝説中の主人公。人類の堕落がもとで起きた大洪水に、方舟はこぶねに乗って難を免れるよう神に命ぜられ、新しい契約を授かって、アダムにつぐ人類の第2の祖先になったという。→方舟
の‐あい【野合・野相】‥アヒ🔗⭐🔉
の‐あい【野合・野相】‥アヒ
戦いで、両軍が平地で出会うこと。新撰信長記「―の合戦なりとも」
の‐あえ【野饗】‥アヘ🔗⭐🔉
の‐あえ【野饗】‥アヘ
野原での饗応。多くは猟の獲物えものをその場で料理する。雄略紀「群臣と鮮なます割つくりて―せむとして」
の‐あざみ【野薊】🔗⭐🔉
の‐あざみ【野薊】
アザミ(キク科)の一種で、最も普通。北海道を除く各地の原野に自生。高さ約90センチメートル。5〜6月頃、紅紫色の頭状花をつけ、総苞の外面は粘質を帯びる。観賞用の改良品種は、ドイツアザミとよく誤称される。
のあざみ


の‐あずき【野小豆】‥アヅキ🔗⭐🔉
の‐あずき【野小豆】‥アヅキ
マメ科の多年草。山地に生え、蔓性。葉は3小葉で、クズの葉に似るが小形。夏、黄色の蝶形花を開く。ヒメクズ。
の‐あそび【野遊び】🔗⭐🔉
の‐あそび【野遊び】
①野に出て草をつみなどして遊ぶこと。〈[季]春〉。日葡辞書「ノアソビニヅ(出)ル」
②野で猟をすること。雄略紀「遊郊野のあそびせむと勧めて」
の‐あらし【野荒らし】🔗⭐🔉
の‐あらし【野荒らし】
田畑の作物などを荒らすこと。また、そういう人や獣など。
のあわせ‐いくさ【野合せ軍】‥アハセ‥🔗⭐🔉
のあわせ‐いくさ【野合せ軍】‥アハセ‥
平地での合戦。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の一番鑓」
ノイエ‐ザハリヒカイト【Neue Sachlichkeit ドイツ】🔗⭐🔉
ノイエ‐ザハリヒカイト【Neue Sachlichkeit ドイツ】
(→)新即物主義。
の‐いくさ【野戦】🔗⭐🔉
の‐いくさ【野戦】
平野でする戦い。やせん。
ノイジネス【noisiness】🔗⭐🔉
ノイジネス【noisiness】
騒音の不快感を評価する指標の一つ。音そのものに付随した聴覚上の不快感。大きさだけでなく、音色や発生頻度などと関連する。航空機騒音の評価などに用いられる。→アノイアンス
ノイズ【noise】🔗⭐🔉
ノイズ【noise】
①騒音。雑音。
②電気信号の乱れ。
⇒ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】
⇒ノイズ‐フィルター【noise filter】
ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】‥クワイ‥🔗⭐🔉
ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】‥クワイ‥
(noise squelch)無線の受信機で、到来電波がない時の雑音を消すための回路。
⇒ノイズ【noise】
ノイズ‐フィルター【noise filter】🔗⭐🔉
ノイズ‐フィルター【noise filter】
電子機器・ケーブルなどに外部から侵入する雑音を軽減・除去する機器。
⇒ノイズ【noise】
のい‐ずみ【芒墨・肉刺】🔗⭐🔉
のい‐ずみ【芒墨・肉刺】
(ノギズミの音便)はきものの固い部分にこすれて足にできる炎症。肉刺まめ。倭名類聚鈔3「肉刺、和名乃以須美」
の‐いた【野板】🔗⭐🔉
の‐いた【野板】
挽ひき割ったままで鉋かんなをかけてない板。粗板あらいた。
の‐いちご【野苺】🔗⭐🔉
の‐いちご【野苺】
野生のイチゴの総称。通常は草本の種類を指し、キイチゴ類は含まない。
の‐いぬ【野犬】🔗⭐🔉
の‐いぬ【野犬】
飼主のない犬。のらいぬ。やけん。浮世草子、傾城武道桜「―つきまとひてなきさけぶ」
の‐いね【野稲】🔗⭐🔉
の‐いね【野稲】
陸稲おかぼのこと。
の‐いばら【野薔薇・野茨】🔗⭐🔉
の‐いばら【野薔薇・野茨】
バラ科の落葉半蔓性低木。山野にごく普通。高さ約2メートル。茎にとげを散生。初夏、芳香のある白色花を多数開く。秋、赤色球形の小果実を結び、これを生薬の営実として利尿・瀉下しゃかに用いる。バラの台木に用いる。ノバラ。〈[季]夏〉
のいばら
 ノイバラ
提供:OPO
ノイバラ
提供:OPO

 ノイバラ
提供:OPO
ノイバラ
提供:OPO

のい‐ふ・す【偃す】🔗⭐🔉
のい‐ふ・す【偃す】
〔自四〕
(ノ(仰)キフスの音便)仰臥する。倒れ伏す。大鏡道長「やすらかに―・したれば」
ノイマン【John von Neumann】🔗⭐🔉
ノイマン【John von Neumann】
⇒フォン=ノイマン。
⇒ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】
ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】🔗⭐🔉
ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】
フォン=ノイマンの提案した原理に基づくコンピューター。ソフトウェアをメモリーに格納するプログラム内蔵方式と、プログラムから命令を順次読み出して実行する逐次制御方式とが特徴。
⇒ノイマン【John von Neumann】
ノイラート【Otto Neurath】🔗⭐🔉
ノイラート【Otto Neurath】
オーストリアの社会学者・哲学者。ウィーン学団の創設に中心的役割を果たした。(1882〜1945)
ノイローゼ【Neurose ドイツ】🔗⭐🔉
ノイローゼ【Neurose ドイツ】
(→)神経症に同じ。
ノイロン【Neuron ドイツ】🔗⭐🔉
ノイロン【Neuron ドイツ】
(→)神経細胞に同じ。
のう【衲】ナフ🔗⭐🔉
のう【衲】ナフ
(補綴の意)
①衲衣のうえ。枕草子123「暑げなるもの。…―の袈裟」
②僧の自称。「拙―」
のう【能】🔗⭐🔉
のう【脳】ナウ🔗⭐🔉
のう【農】🔗⭐🔉
のう【農】
田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。「―は国の本もと」
のう【濃】🔗⭐🔉
のう【濃】
美濃国みののくにの略。
のうナウ🔗⭐🔉
のうナウ
[一]〔感〕
(「喃」とも書く)人に呼びかけ、または同意を求める時に用いる。謡曲、隅田川「―舟人、あれに白き鳥の見えたるは」
[二]〔助詞〕
(「な」の転か)主として文末にあって感動の意を表す。閑吟集「たれも―、たれになりとも添うてみよ」。浄瑠璃、薩摩歌「ようもだまつてゐられた―」
のうあ【能阿】🔗⭐🔉
のうあ【能阿】
能阿弥の略。
ノヴァーリス【Novalis】🔗⭐🔉
ノヴァーリス【Novalis】
(本名Friedrich von Hardenberg)ドイツの詩人・作家。前期ロマン派の代表的小説「ハインリヒ=フォン=オフターディンゲン(青い花)」のほか、抒情詩文集「夜の讃歌」など。(1772〜1801)→青い花
ノヴァ‐スコシア【Nova Scotia】🔗⭐🔉
ノヴァ‐スコシア【Nova Scotia】
カナダ南東端の州。住民の大半はイギリス系で、特にスコットランド系が多い。製紙・木工・水産業が盛ん。旧称アカディア。州都ハリファックス。
のう‐あつ【脳圧】ナウ‥🔗⭐🔉
のう‐あつ【脳圧】ナウ‥
(→)脳内圧に同じ。
のうあみ【能阿弥】🔗⭐🔉
のうあみ【能阿弥】
室町中期の連歌師・画家。阿弥派の祖。真能とも称す。もと越前朝倉氏の被官で、水墨画をよくしたほか、鑑定・茶道・香道などにも通じた。足利義政の同朋衆。著に将軍家所蔵の中国画を列記した「御物御画目録」がある。その子に芸阿弥、孫に相阿弥があり、あわせて三阿弥という。(1397〜1471)
○能ある鷹は爪隠すのうあるたかはつめかくす
本当に実力のあるものは、やたらにそれを現さないものだというたとえ。
⇒のう【能】
ノー【no】🔗⭐🔉
ノー【no】
①否定・拒否を表す語。いや。いいえ。否。「―がなかなか言えない」↔イエス。
②(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐スリーブ」「―‐コメント」
🄰NOR回路🔗⭐🔉
NOR(ノア)回路
OR回路の出力にNOT回路を接続した論理回路.
広辞苑に「の」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む