複数辞典一括検索+![]()
![]()
一 ひと🔗⭐🔉
【一】
 1画 一部 [一年]
区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA
【弌】異体字異体字
1画 一部 [一年]
区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA
【弌】異体字異体字
 4画 弋部
区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F
《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ
《音読み》 イチ
4画 弋部
区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F
《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ
《音読み》 イチ /イツ
/イツ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし
《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ
《意味》
〉
《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし
《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ
《意味》
 {数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕
{数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕
 {数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」
{数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」
 イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕
イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕
 {形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕
{形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕
 イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕
イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕
 イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕
イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕
 イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕
イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕
 イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕
イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕
 イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕
イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕
 {副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕
{副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕
 {副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕
{副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕
 イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕
イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕
 {形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」
{形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」
 イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕
《解字》
イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕
《解字》
 指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。
《単語家族》
咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。
《単語家族》
咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
 1画 一部 [一年]
区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA
【弌】異体字異体字
1画 一部 [一年]
区点=1676 16進=306C シフトJIS=88EA
【弌】異体字異体字
 4画 弋部
区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F
《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ
《音読み》 イチ
4画 弋部
区点=4801 16進=5021 シフトJIS=989F
《常用音訓》イチ/イツ/ひと/ひと…つ
《音読み》 イチ /イツ
/イツ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし
《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ
《意味》
〉
《訓読み》 ひとつ/ひと/ひとつにする(ひとつにす)/ひとつとなる/もっぱら/ひとたび/すこし
《名付け》 おさむ・か・かず・かた・かつ・くに・さね・すすむ・たか・ただ・ち・のぶ・はじむ・はじめ・ひ・ひじ・ひで・ひと・ひとし・まこと・まさし・もと・もろ
《意味》
 {数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕
{数}ひとつ。〈同義語〉→壱。「一字」「定于一=一ニ定マラン」〔→孟子〕
 {数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」
{数}ひと。順番の一番め。〈同義語〉→壱。「一月一日」「一位」
 イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕
イツニス・イツトナル{動}ひとつにする(ヒトツニス)。ひとつとなる。「統一」「一意専心」「孰能一之=孰カ能クコレヲ一ニセン」〔→孟子〕
 {形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕
{形}(「一…」の形で)…じゅうすべて。…のすみからすみまで。「一天(空じゅう)」「一国慕之=一国コレヲ慕フ」〔→孟子〕
 イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕
イツナリ{形}同じであるさま。「其揆一也=其ノ揆一也」〔→孟子〕
 イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕
イツニス{動}同じくする。一致させる。「一致而百慮=致ヲ一ニシテ慮ヲ百ニス」〔→易経〕
 イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕
イツニス{動}ひとつのもの、また、同じものとして扱う。いっしょくたにする。「一死生為虚誕=死生ヲ一ニスルハ虚誕タリ」〔→王羲之〕
 イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕
イツニ{副}もっぱら。ひたすら。「欲一以窮之=一ニ以テコレヲ窮メンコトヲ欲ス」〔→礼記〕
 イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕
イツニ{副}なんと。「一至此乎=一ニ此ニ至ルカ」〔→呂覧〕
 {副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕
{副}ひとたび。一回。一度。「一戦勝斉=一タビ戦ヒテ斉ニ勝ツ」〔→孟子〕
 {副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕
{副}ひとたび。もしいちどでも…したら。「此地一為別=此ノ地一タビ別レヲ為セバ」〔→李白〕
 イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕
イツモ{副}すこし。ちょっと。わずかに。「一見」「不一動其心=一モ其ノ心ヲ動カサズ」〔→小学〕
 {形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」
{形}あるひとつの。また、あるひとりの。「一朝」「一少年」
 イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕
《解字》
イツニハ・イツハ{副}…したり…したり。▽「一…一…」の形で用いられる。「一則以喜、一則以懼=一ハ則チ以テ喜ビ、一ハ則チ以テ懼ル」〔→論語〕
《解字》
 指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。
《単語家族》
咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
指事。一本の横線で、ひとつを示す。ひとつの意のほか、全部をひとまとめにする、いっぱいに詰めるなどの意を含む。壱イチの原字壹は、壺ツボにいっぱい詰めて口をくびったさま。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、壱と書くことがある。
《単語家族》
咽エツ(のどがいっぱいに詰まる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
一入 ヒトシオ🔗⭐🔉
【一入】
ヒトシオ〔国〕 染め物を一度染め汁に浸すこと。
染め物を一度染め汁に浸すこと。 いっそう。ひときわ。
いっそう。ひときわ。
 染め物を一度染め汁に浸すこと。
染め物を一度染め汁に浸すこと。 いっそう。ひときわ。
いっそう。ひときわ。
一角 ヒトカド🔗⭐🔉
【一廉】
ヒトカド・イッカド〔国〕 きわだってすぐれているようす。
きわだってすぐれているようす。 その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』
その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』
 きわだってすぐれているようす。
きわだってすぐれているようす。 その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』
その名に値するだけの内容をそなえているようす。『一角ヒトカド・イッカド』
丕図 ヒト🔗⭐🔉
【丕図】
ヒト おおきな計画。▽ほめていうときに用いる。
人 ひと🔗⭐🔉
【人】
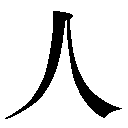 2画 人部 [一年]
区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C
《常用音訓》ジン/ニン/ひと
《音読み》 ジン
2画 人部 [一年]
区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C
《常用音訓》ジン/ニン/ひと
《音読み》 ジン /ニン
/ニン 〈r
〈r n〉
《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと
《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め
《意味》
n〉
《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと
《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め
《意味》
 {名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕
{名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕
 {名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕
{名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕
 {副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕
{副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕
 {単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕
《解字》
{単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕
《解字》
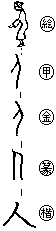 象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。
《単語家族》
二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ)
象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。
《単語家族》
二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ) 爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ)
爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ) 尼ニ(相並び親しむ人)
尼ニ(相並び親しむ人) 仁と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
仁と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
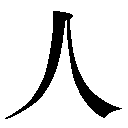 2画 人部 [一年]
区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C
《常用音訓》ジン/ニン/ひと
《音読み》 ジン
2画 人部 [一年]
区点=3145 16進=3F4D シフトJIS=906C
《常用音訓》ジン/ニン/ひと
《音読み》 ジン /ニン
/ニン 〈r
〈r n〉
《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと
《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め
《意味》
n〉
《訓読み》 ひと/ひとごとに/ひとびと
《名付け》 きよ・さね・たみ・と・ひこ・ひと・ひとし・ふと・むと・め
《意味》
 {名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕
{名}ひと。人間。「宋人ソウヒト(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人ニシテ信無クンバ、其ノ可ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→論語〕
 {名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕
{名}ひと。他人。〈対語〉→己オノレ・→我。「人我」「己欲立而立人=己立タント欲シテ人ヲ立ツ」〔→論語〕
 {副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕
{副}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ゴトニ給シ、家ゴトニ足ル」〔→史記〕
 {単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕
《解字》
{単位}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行ヘバ必ズ我ガ師有リ」〔→論語〕
《解字》
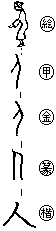 象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。
《単語家族》
二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ)
象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁ジン(ヒューマニズム)と名づけた。
《単語家族》
二ニ・ジ(二つくっついて並ぶ) 爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ)
爾ニ・ジ(そばにくっついている相手、なんじ) 尼ニ(相並び親しむ人)
尼ニ(相並び親しむ人) 仁と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
仁と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
人鬼 ヒトオニ🔗⭐🔉
【人鬼】
 ジンキ
ジンキ  死んだ人の魂。
死んだ人の魂。 人と鬼。
人と鬼。 ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。
ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。
 ジンキ
ジンキ  死んだ人の魂。
死んだ人の魂。 人と鬼。
人と鬼。 ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。
ヒトオニ〔国〕鬼のようにむごい人。
人衆者勝天 ヒトオオケレバテンニカツ🔗⭐🔉
【人衆者勝天】
ヒトオオケレバテンニカツ〈故事〉多数をたのめば、一時天道に勝って道理にはずれたこともできるが、天道が安定して道理が行われるようになると、そのような人間を破滅させてしまう。〔→史記〕
仁 ひと🔗⭐🔉
【仁】
 4画 人部 [六年]
区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D
《常用音訓》ジン/ニ
《音読み》 ジン
4画 人部 [六年]
区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D
《常用音訓》ジン/ニ
《音読み》 ジン /ニ/ニン
/ニ/ニン 〈r
〈r n〉
《訓読み》 ひと
《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 ひと
《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし
《意味》
 {名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕
{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕
 ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕
ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕
 {名}「仁
{名}「仁 」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕
」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕
 {名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」
{名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」
 「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。
《解字》
「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。
《解字》
 会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。
《単語家族》
人と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。
《単語家族》
人と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 4画 人部 [六年]
区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D
《常用音訓》ジン/ニ
《音読み》 ジン
4画 人部 [六年]
区点=3146 16進=3F4E シフトJIS=906D
《常用音訓》ジン/ニ
《音読み》 ジン /ニ/ニン
/ニ/ニン 〈r
〈r n〉
《訓読み》 ひと
《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 ひと
《名付け》 きみ・きん・さと・さね・しのぶ・ただし・と・とよ・にん・のぶ・のり・ひさし・ひと・ひとし・ひろし・まさ・まさし・み・めぐみ・めぐむ・やすし・よし
《意味》
 {名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕
{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。「井有仁焉=井ニ仁有リ」〔→論語〕
 ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕
ジンナリ{名・形}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁ナル者ハ人ヲ愛ス」〔→孟子〕
 {名}「仁
{名}「仁 」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕
」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過チヲ観レバ、斯ニ仁ヲ知ル」〔→論語〕
 {名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」
{名}柔らかい果物のたね。「杏仁キョウニン(あんずのたね)」
 「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。
《解字》
「不仁フジン」とは、手足の動かない病気のこと。
《解字》
 会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。
《単語家族》
人と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意兼形声。「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人ジン・ニンと二ジ・ニと、どちらを音符と考えてもよい。
《単語家族》
人と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
偏 ひとえに🔗⭐🔉
【偏】
 11画 人部 [常用漢字]
区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE
《常用音訓》ヘン/かたよ…る
《音読み》 ヘン
11画 人部 [常用漢字]
区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE
《常用音訓》ヘン/かたよ…る
《音読み》 ヘン
 〈pi
〈pi n〉
《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 つら・とも・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 つら・とも・ゆき
《意味》
 ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕
ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕
 ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕
ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕
 {副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕
{副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕
 {名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」
{名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」
 {副}〔俗〕あいにく。
《解字》
会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{副}〔俗〕あいにく。
《解字》
会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 人部 [常用漢字]
区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE
《常用音訓》ヘン/かたよ…る
《音読み》 ヘン
11画 人部 [常用漢字]
区点=4248 16進=4A50 シフトJIS=95CE
《常用音訓》ヘン/かたよ…る
《音読み》 ヘン
 〈pi
〈pi n〉
《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 つら・とも・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 かたよる/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 つら・とも・ゆき
《意味》
 ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕
ヘンス{動}かたよる。中心をそれて一方にかたよる。〈対語〉→正。「偏向」「雲髻半偏新睡覚=雲髻半バ偏シテ新睡覚ム」〔→白居易〕
 ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕
ヘンナリ{形}中央からそれて片すみに寄っているさま。片いなかであるさま。「偏僻ヘンペキ」「心遠地自偏=心遠クシテ地自ラ偏ナリ」〔→陶潜〕
 {副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕
{副}ひとえに(ヒトヘニ)。水準を越えて一方にかたよるさま。いやが上にも。そればかり。〈類義語〉→頗ハ(すこぶる)。「台上偏宜酩酊帰=台上偏ニ酩酊シテ帰ルニ宜シ」〔→高適〕
 {名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」
{名}漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる左側の部分。さんずい・にんべんなど。多くは、その字の意味する物事の種別をあらわす。▽右側の部分を傍という。〈同義語〉→扁。「偏傍(=扁旁)」
 {副}〔俗〕あいにく。
《解字》
会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{副}〔俗〕あいにく。
《解字》
会意兼形声。扁は「戸(平らな板)+冊(薄いたんざく)」の会意文字で、薄く平らにのびたの意を含む。平らにのびれば行き渡る(→遍)、また、周辺に行き渡ると、周辺は中央から離れるの意を派生する。偏は「人+音符扁」で、おもに扁の派生義、つまり、中心から離れてかたよった意をあらわす。→扁
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
儿 ひと🔗⭐🔉
【儿】
 2画 儿部
区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958
《音読み》 ニン
2画 儿部
区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958
《音読み》 ニン /ジン
/ジン 〈r
〈r n〉
《訓読み》 ひと
《意味》
{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。
《解字》
n〉
《訓読み》 ひと
《意味》
{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。
《解字》
 象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。
象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。
 2画 儿部
区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958
《音読み》 ニン
2画 儿部
区点=4925 16進=5139 シフトJIS=9958
《音読み》 ニン /ジン
/ジン 〈r
〈r n〉
《訓読み》 ひと
《意味》
{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。
《解字》
n〉
《訓読み》 ひと
《意味》
{名}ひと。人間。〈同義語〉→人。
《解字》
 象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。
象形。人間の下半身を描いたもの。人ニン・ジンと同じ。兄や允インなどの字に含まれ、人体を意味する。
匪徒 ヒト🔗⭐🔉
【匪徒】
ヒト 悪者の仲間。『匪党ヒトウ・匪類ヒルイ』
均 ひとしい🔗⭐🔉
【均】
 7画 土部 [五年]
区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF
《常用音訓》キン
《音読み》
7画 土部 [五年]
区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF
《常用音訓》キン
《音読み》  キン
キン
 〈j
〈j n〉/
n〉/ イン(
イン( ン)
ン) /ウン
/ウン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ
《意味》
n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ
《意味》

 {形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕
{形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕
 {動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕
{動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕
 {副}ひとしく。平均して。
{副}ひとしく。平均して。
 {名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」
《解字》
会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。
《類義》
→斉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」
《解字》
会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。
《類義》
→斉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 土部 [五年]
区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF
《常用音訓》キン
《音読み》
7画 土部 [五年]
区点=2249 16進=3651 シフトJIS=8BCF
《常用音訓》キン
《音読み》  キン
キン
 〈j
〈j n〉/
n〉/ イン(
イン( ン)
ン) /ウン
/ウン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ
《意味》
n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 お・ただ・なお・なり・ひとし・ひら・まさ
《意味》

 {形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕
{形}ひとしい(ヒトシ)。全部に公平に行き渡っているさま。「平均」「不患寡、而患不均=寡ナキヲ患ヘズ、均シカラザルヲ患フ」〔→論語〕
 {動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕
{動}ひとしくする(ヒトシクス)。公平に行き渡らせる。「願言均此施=願ハクハ言此ノ施シヲ均シウセン」〔→蘇軾〕
 {副}ひとしく。平均して。
{副}ひとしく。平均して。
 {名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」
《解字》
会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。
《類義》
→斉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}詩句の響きをあわせること。また、その調和のとれた部分。母音を含む音節の後半部。▽たとえば、単・干のanの部分。〈同義語〉→韻・→韵イン。「押均(=押韻)」
《解字》
会意兼形声。右側は「手をひと回りさせた姿+=印(そろえる)」の会意文字で、全部にそろえて平均させること。均はそれを音符とし、土をそえた字で、土をならして全部に行き渡らせることを示す。
《類義》
→斉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
埒 ひとしい🔗⭐🔉
【埒】
 10画 土部
区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD
【埓】異体字異体字
10画 土部
区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD
【埓】異体字異体字
 10画 土部
区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE
《音読み》 ラチ/ラツ
10画 土部
区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE
《音読み》 ラチ/ラツ /レチ
/レチ /レツ
/レツ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)
《意味》
〉
《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)
《意味》
 {名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」
{名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」
 {形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕
〔国〕
{形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕
〔国〕 「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」
「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」 「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。
《解字》
「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 土部
区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD
【埓】異体字異体字
10画 土部
区点=5231 16進=543F シフトJIS=9ABD
【埓】異体字異体字
 10画 土部
区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE
《音読み》 ラチ/ラツ
10画 土部
区点=5232 16進=5440 シフトJIS=9ABE
《音読み》 ラチ/ラツ /レチ
/レチ /レツ
/レツ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)
《意味》
〉
《訓読み》 かこい(かこひ)/ひとしい(ひとし)
《意味》
 {名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」
{名}かこい(カコヒ)。内と外をわけるための垣カキ。また、貯水池を囲う堤。「馬埒バラツ・バレツ(馬場の垣)」
 {形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕
〔国〕
{形}ひとしい(ヒトシ)。優劣がなくてひとしい。「富埒天子=富天子ニ埒シ」〔→史記〕
〔国〕 「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」
「不埒フラチ」とは、法の定めたわく(囲い)の中にはいらない→けしからぬの意。「不埒な奴ヤツ」 「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。
《解字》
「埒ラチがあかない」とは、事がもつれたままで、はかどらないこと。きまりがつかないこと。
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。右側の字(音ラツ)は、上の手と下の手とが、一線を境にして引っぱりあうさまを示す会意文字。↑と↓の逆方向に引きわけるので、内外をわかつ意となり、勝負がつかず引きわけとなるので、優劣がつけがたくてひとしい、の意となる。埒はそれを音符とし、土を加えた字で、内と外とをわける土べい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
壱 ひとえに🔗⭐🔉
【壱】
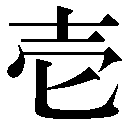 7画 士部 [常用漢字]
区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB
【壹】旧字旧字
7画 士部 [常用漢字]
区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB
【壹】旧字旧字
 12画 士部
区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3
《常用音訓》イチ
《音読み》 イチ
12画 士部
区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3
《常用音訓》イチ
《音読み》 イチ /イツ
/イツ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 かず・さね・もろ
《意味》
〉
《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 かず・さね・もろ
《意味》
 {数}ひとつ。〈同義語〉→一。
{数}ひとつ。〈同義語〉→一。
 {副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。
{副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。
 イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕
イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕
 イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕
《解字》
イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕
《解字》
 会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。
《単語家族》
噎イツ・エツ(詰まる)
会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。
《単語家族》
噎イツ・エツ(詰まる) 咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
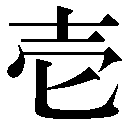 7画 士部 [常用漢字]
区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB
【壹】旧字旧字
7画 士部 [常用漢字]
区点=1677 16進=306D シフトJIS=88EB
【壹】旧字旧字
 12画 士部
区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3
《常用音訓》イチ
《音読み》 イチ
12画 士部
区点=5269 16進=5465 シフトJIS=9AE3
《常用音訓》イチ
《音読み》 イチ /イツ
/イツ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 かず・さね・もろ
《意味》
〉
《訓読み》 ひとつ/ひとたび/ひとえに(ひとへに)
《名付け》 かず・さね・もろ
《意味》
 {数}ひとつ。〈同義語〉→一。
{数}ひとつ。〈同義語〉→一。
 {副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。
{副}ひとたび。一度。いったん…すれば。〈同義語〉→一。
 イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕
イツニ{副}ひとえに(ヒトヘニ)。まったく。「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕
 イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕
《解字》
イツニ{副}ひたすら。「子卿壱聴陵言=子卿、壱ニ陵ノ言ヲ聴ケ」〔→漢書〕
《解字》
 会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。
《単語家族》
噎イツ・エツ(詰まる)
会意兼形声。吉キツは、結と同系で、口をかたく締めた意を含む。壹はもと「壺(つぼ)+音符吉」で、口を結んで締め、中にいっぱいにつめたつぼ。▽証文や契約書で、改竄カイザンや誤解をさけるために、「一」のかわりに、使うことがある。
《単語家族》
噎イツ・エツ(詰まる) 咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
咽エツと同系。その音を借りて、数詞の一に当てる。あるいはこぶしを握りしめて数詞の一をあらわしたため、一は壹(いっぱいつめる)と同系と考えてよい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
単 ひとえ🔗⭐🔉
【単】
 9画 ツ部 [四年]
区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250
【單】旧字人名に使える旧字
9画 ツ部 [四年]
区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250
【單】旧字人名に使える旧字
 12画 口部
区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64
《常用音訓》タン
《音読み》
12画 口部
区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64
《常用音訓》タン
《音読み》  タン
タン
 〈d
〈d n〉/
n〉/ ゼン
ゼン /セン
/セン 〈ch
〈ch n〉〈sh
n〉〈sh n〉
《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《名付け》 いち・ただ
《意味》
n〉
《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《名付け》 いち・ただ
《意味》

 タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕
タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕
 タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕
タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕
 {形}ただ一枚で薄い。「単薄」
{形}ただ一枚で薄い。「単薄」
 {名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」
{名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」
 タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。
タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。

 {動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」
{動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」
 「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。
「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。
 「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。
《解字》
「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。
《解字》
 象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。
《単語家族》
氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。
《単語家族》
氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 9画 ツ部 [四年]
区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250
【單】旧字人名に使える旧字
9画 ツ部 [四年]
区点=3517 16進=4331 シフトJIS=9250
【單】旧字人名に使える旧字
 12画 口部
区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64
《常用音訓》タン
《音読み》
12画 口部
区点=5137 16進=5345 シフトJIS=9A64
《常用音訓》タン
《音読み》  タン
タン
 〈d
〈d n〉/
n〉/ ゼン
ゼン /セン
/セン 〈ch
〈ch n〉〈sh
n〉〈sh n〉
《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《名付け》 いち・ただ
《意味》
n〉
《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《名付け》 いち・ただ
《意味》

 タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕
タンナリ{名・形}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえである。〈対語〉→複。「単衣(ひとえの着物)」「可憐身上衣正単=憐レムベシ身上ノ衣正ニ単ナリ」〔→白居易〕
 タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕
タンナリ{形}それだけで付加物がないさま。ただ一つである。〈対語〉→複・→双。〈類義語〉→隻・→独。「単数」「簡単」「両世一身形単影隻=両世一身ニシテ、形ハ単ニ、影ハ隻ナリ」〔→韓愈〕
 {形}ただ一枚で薄い。「単薄」
{形}ただ一枚で薄い。「単薄」
 {名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」
{名}薄い紙片。転じて、カード。札。「名単(名札)」
 タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。
タンニ{副}ただそれだけ、の意をあらわすことば。ひとえに。▽「不単…」とは、「不但…」と同じで、「単に…のみならず」と訓読する。

 {動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」
{動}たいらげる。なくなる。つきる。▽殫セン・タンに当てた用法。「単用」
 「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。
「単于ゼンウ」とは、匈奴キョウドの王の称号。▽匈奴語のtengrikoto(天のみ子)を略して音訳したもの。
 「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。
《解字》
「単父ゼンフ・ゼンホ」とは、中国の県の名。
《解字》
 象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。
《単語家族》
氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。籐トウのつるを編んでこしらえたはたきを描いたもの。はたきは両がわに耳があり、これでぱたぱたとたたき、ほこりを落としたり、鳥や小獣をたたき落としたりする。獸(=獣)の字に意符として含まれる。また、このはたきは薄く平らなので、一重であり薄い意を生じる。
《単語家族》
氈セン(薄く平らな敷物)と同系。また戦栗センリツの戦(平面が上下動する)や扇(薄く平らなとびらや、うちわ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
批答 ヒトウ🔗⭐🔉
【批答】
ヒトウ 臣下の提出した文書に対して、天子が自分の意見を書いて答えること。また、その文書。
比党 ヒトウ🔗⭐🔉
【比周】
ヒシュウ  かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。
かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。 かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕
かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕
 かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。
かたよった交わり(=比)と、公平な交わり(=周)。▽「論語」為政篇の「君子周而不比、小人比而不周=君子ハ周シテ比セズ、小人ハ比シテ周セズ」から。 かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕
かたよってくみする。徒党を組むこと。『比党ヒトウ』〔→左伝〕
秘匿 ヒトク🔗⭐🔉
【秘匿】
ヒトク〔国〕人に知られないようにかくす。
等 ひとしい🔗⭐🔉
【等】
 12画 竹部 [三年]
区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399
《常用音訓》トウ/ひと…しい
《音読み》 トウ
12画 竹部 [三年]
区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399
《常用音訓》トウ/ひと…しい
《音読み》 トウ
 〈d
〈d ng〉〈d
ng〉〈d i〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ
《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし
《意味》
i〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ
《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし
《意味》
 {形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」
{形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」
 {動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕
{動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕
 {名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」
{名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」
 {単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕
{単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕
 {助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」
{助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」
 {名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」
{名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」
 {疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕
{疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕
 {動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」
《解字》
形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。
《単語家族》
治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」
《解字》
形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。
《単語家族》
治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 竹部 [三年]
区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399
《常用音訓》トウ/ひと…しい
《音読み》 トウ
12画 竹部 [三年]
区点=3789 16進=4579 シフトJIS=9399
《常用音訓》トウ/ひと…しい
《音読み》 トウ
 〈d
〈d ng〉〈d
ng〉〈d i〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ
《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし
《意味》
i〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)/ひとしくする(ひとしくす)/たぐい(たぐひ)/ら/なに/まつ
《名付け》 しな・たか・とし・とも・ひとし
《意味》
 {形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」
{形}ひとしい(ヒトシ)。同じようにそろっている。〈類義語〉→斉。「斉等」「等分」
 {動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕
{動}ひとしくする(ヒトシクス)。そろえる。同じものをそろえて整理する。同じ等級にそろえる。ならべてくらべる。「等諸臣之爵=諸臣ノ爵ヲ等シクス」〔→周礼〕
 {名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」
{名}たぐい(タグヒ)。同じものをそろえてほかのものと区別した段階・順序。ランク。「等級」「同等」
 {単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕
{単位}階段の段を数えることば。また、転じて、物事の段階・順序を数えることば。「土階三等(土のきざはし三段。質素な住居のこと)」「出降一等=出デテ一等ヲ降ル」〔→論語〕
 {助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」
{助}ら。ほかにも同じものがあることをあらわすことば。「卿等ケイラ(あなた方)」「…等等トウトウ(…など)」
 {名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」
{名}同じ大きさをした、はかりの分銅。「等子」
 {疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕
{疑}〔俗〕なに。どんな。〈類義語〉→何。「死公云等道=死公ナニヲカ云フ」〔→後漢書〕
 {動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」
《解字》
形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。
《単語家族》
治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}〔俗〕まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→待。「等待トンタイ」
《解字》
形声。「竹+音符寺」で、もと竹の節、または、竹簡の長さがひとしくそろったこと。転じて、同じものをそろえて順序を整えるの意となった。寺の意味(役所、てら)とは直接の関係はない。
《単語家族》
治ジ・チ(でこぼこをそろえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
襌 ひとえ🔗⭐🔉
【襌】
 17画 衣部
区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9
【褝】異体字異体字
17画 衣部
区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9
【褝】異体字異体字
 14画 衣部
区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA
《音読み》 タン
14画 衣部
区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA
《音読み》 タン
 《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《意味》
{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。
《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《意味》
{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。
 17画 衣部
区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9
【褝】異体字異体字
17画 衣部
区点=7491 16進=6A7B シフトJIS=E5F9
【褝】異体字異体字
 14画 衣部
区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA
《音読み》 タン
14画 衣部
区点=7492 16進=6A7C シフトJIS=E5FA
《音読み》 タン
 《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《意味》
{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。
《訓読み》 ひとえ(ひとへ)
《意味》
{名}ひとえ(ヒトヘ)。ひとえの衣服。かたびら。〈同義語〉→単。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符單(ひとえ)」。
費途 ヒト🔗⭐🔉
【費途】
ヒト〔国〕金銭・財産の用途。
轡頭 ヒトウ🔗⭐🔉
【轡頭】
ヒトウ たづな。「南市買轡頭=南市ニ轡頭ヲ買フ」〔古楽府〕
避逃 ヒトウ🔗⭐🔉
【避逃】
ヒトウ 難儀を避けてのがれる。〈類義語〉逃避。
鈞 ひとしい🔗⭐🔉
【鈞】
 12画 金部
区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0
《音読み》 キン
12画 金部
区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0
《音読み》 キン
 〈j
〈j n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)
《意味》
n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)
《意味》
 {単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。
{単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。
 {名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」
{名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」
 {形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕
{形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕
 {形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」
《解字》
会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。
《単語家族》
均
{形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」
《解字》
会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。
《単語家族》
均 尹イン(平均をとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
尹イン(平均をとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 金部
区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0
《音読み》 キン
12画 金部
区点=7866 16進=6E62 シフトJIS=E7E0
《音読み》 キン
 〈j
〈j n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)
《意味》
n〉
《訓読み》 ひとしい(ひとし)
《意味》
 {単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。
{単位}重量の単位。一鈞は、三十斤。周代では七・六八キログラム。
 {名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」
{名}陶器をつくるときに使うろくろ。平均のとれた回転盤。転じて、天下の平均を保つ政治力。「国鈞コクキン」
 {形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕
{形}ひとしい(ヒトシ)。まんべんなくいきわたる。〈同義語〉→均。「鈞是人也=鈞シクコレ人ナリ」〔→孟子〕
 {形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」
《解字》
会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。
《単語家族》
均
{形}均斉がとれて、重々しい。▽尊敬の意をあらわすことば。「鈞令キンレイ」「鈞啓キンケイ」
《解字》
会意兼形声。「金+音符均キンの略体」。
《単語家族》
均 尹イン(平均をとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
尹イン(平均をとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
飛棟 ヒトウ🔗⭐🔉
【飛棟】
ヒトウ 高い屋根のむな木。〈類義語〉高棟・隆棟。
飛騰 ヒトウ🔗⭐🔉
【飛揚】
ヒヨウ  高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕
高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕 心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕
心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕 気ままにふるまうこと。
気ままにふるまうこと。
 高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕
高くとびあがる。舞いあがる。『飛騰ヒトウ』「大風起兮雲飛揚=大風ハ起コリテ雲ハ飛揚ス」〔漢高祖〕 心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕
心が落ち着かない。「趣舎滑心、使性飛揚=趣舎心ヲ滑シ、性ヲシテ飛揚セシム」〔→荘子〕 気ままにふるまうこと。
気ままにふるまうこと。
飛騰 ヒトウ🔗⭐🔉
【飛騰】
ヒトウ  「飛揚
「飛揚 」と同じ。
」と同じ。 〔俗〕暴騰する。
〔俗〕暴騰する。
 「飛揚
「飛揚 」と同じ。
」と同じ。 〔俗〕暴騰する。
〔俗〕暴騰する。
斉 ひとしい🔗⭐🔉
【斉】
 8画 齊部 [常用漢字]
区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4
【齊】旧字人名に使える旧字
8画 齊部 [常用漢字]
区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4
【齊】旧字人名に使える旧字
 14画 齊部
区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E
《常用音訓》セイ
《音読み》
14画 齊部
区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E
《常用音訓》セイ
《音読み》  セイ
セイ /ザイ
/ザイ /サイ
/サイ 〈q
〈q 〉/
〉/ ザイ
ザイ /セイ
/セイ /
/ シ
シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし
《意味》
〉
《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし
《意味》

 {動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」
{動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」
 {動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕
{動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕
 {名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕
{名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕
 {副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕
{副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕
 {名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。
{名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。
 {名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二
{名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二
 {名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七
{名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七
 {名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh
{名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕
iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕
 {名}層がきちんと重なった赤色の雲母。
{名}層がきちんと重なった赤色の雲母。
 {名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕
《解字》
{名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕
《解字》
 象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間)
象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間) 臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ)
臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ) 劑セイ(=剤。そろえて切る)
劑セイ(=剤。そろえて切る) 濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。
《類義》
均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。
《類義》
均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
 8画 齊部 [常用漢字]
区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4
【齊】旧字人名に使える旧字
8画 齊部 [常用漢字]
区点=3238 16進=4046 シフトJIS=90C4
【齊】旧字人名に使える旧字
 14画 齊部
区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E
《常用音訓》セイ
《音読み》
14画 齊部
区点=8378 16進=736E シフトJIS=EA8E
《常用音訓》セイ
《音読み》  セイ
セイ /ザイ
/ザイ /サイ
/サイ 〈q
〈q 〉/
〉/ ザイ
ザイ /セイ
/セイ /
/ シ
シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし
《意味》
〉
《訓読み》 ととのう(ととのふ)/ひとしい(ひとし)/ととのえる(ととのふ)/ひとしくする(ひとしくす)/ひとしく
《名付け》 きよ・ただ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし
《意味》

 {動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」
{動・形}ととのう(トトノフ)。ひとしい(ヒトシ)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」
 {動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕
{動}ととのえる(トトノフ)。ひとしくする(ヒトシクス)。きちんとそろえる。「斉駒並駕セイクヘイガ(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=コレヲ斉フルニ刑ヲモッテス」〔→論語〕
 {名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕
{名}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉ハッチンノセイ」〔→周礼〕
 {副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕
{副}ひとしく。そろって。みんな。〈類義語〉→均。「民不斉出於南畝=民ハ斉シク南畝ニ出デズ」〔→史記〕
 {名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。
{名}国名。周時代に太公望呂尚リョショウの封ぜられた国。今の山東省。桓公カンコウの代に覇者ハシャとなった。戦国時代には臣の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦シンに滅ぼされた。
 {名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二
{名}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭道成ショウドウセイが宋ソウから位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代二十四年で梁リヨウに滅ぼされた。四七九〜五〇二
 {名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七
{名}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高洋がたて五代二十八年で北周に滅ぼされた。五五〇〜五七七
 {名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh
{名}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕
iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒シテモッテ鬼神ニ事フ」〔→礼記〕
 {名}層がきちんと重なった赤色の雲母。
{名}層がきちんと重なった赤色の雲母。
 {名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕
《解字》
{名}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰シサイ(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉ヲ摂ゲテ堂ニ升ル」〔→論語〕
《解字》
 象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間)
象形。◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間) 臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ)
臍セイ(上下左右そろったまん中にあるへそ) 劑セイ(=剤。そろえて切る)
劑セイ(=剤。そろえて切る) 濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。
《類義》
均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
濟サイ(=済。水量をそろえる)などと同系。
《類義》
均キンは、まるく調和のとれること。整セイは、まっすぐにそろうこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
漢字源に「ひと」で始まるの検索結果 1-33。もっと読み込む