複数辞典一括検索+![]()
![]()
仍 かさなる🔗⭐🔉
【仍】
 4画 人部
区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9
《音読み》 ジョウ
4画 人部
区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9
《音読み》 ジョウ /ニョウ
/ニョウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)
《意味》
 {動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕
{動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕
 {動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕
{動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕
 「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。
「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。
 {副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」
《解字》
会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」
《解字》
会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 4画 人部
区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9
《音読み》 ジョウ
4画 人部
区点=4827 16進=503B シフトJIS=98B9
《音読み》 ジョウ /ニョウ
/ニョウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 よる/かさなる/かさねて/なお(なほ)
《意味》
 {動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕
{動}よる。ねばりついて離れない。なずむ。「仍旧貫=旧貫ニ仍ル」〔→論語〕
 {動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕
{動・副}かさなる。かさねて。もとの物事につけ加わる。また、そのさま。さらに。そのうえ。「饑饉仍臻=饑饉仍ネテ臻ル」〔→漢書〕
 「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。
「仍仍ジョウジョウ」とは、幾重にもかさなり、数多いさま。
 {副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」
《解字》
会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}なお(ナホ)。元どおり。依然として。「仍然ジョウゼン(元どおり)」
《解字》
会意兼形声。人の右に、乃(柔らかい耳たぶ)を加え、乃ナイの転音が音をあらわすもので、柔らかくねばりついて、なずむの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
佳作 カサク🔗⭐🔉
【佳作】
カサク  りっぱな詩文・芸術作品。
りっぱな詩文・芸術作品。 〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。
〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。
 りっぱな詩文・芸術作品。
りっぱな詩文・芸術作品。 〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。
〔国〕非常にすぐれてはいないが、かなりよくできた作品。
傘 かさ🔗⭐🔉
【傘】
 12画 人部 [常用漢字]
区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50
《常用音訓》サン/かさ
《音読み》 サン
12画 人部 [常用漢字]
区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50
《常用音訓》サン/かさ
《音読み》 サン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 かさ
《名付け》 かさ
《意味》
{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」
《解字》
n〉
《訓読み》 かさ
《名付け》 かさ
《意味》
{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」
《解字》
 象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺)
象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺) 散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。
《熟語》
→熟語
散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。
《熟語》
→熟語
 12画 人部 [常用漢字]
区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50
《常用音訓》サン/かさ
《音読み》 サン
12画 人部 [常用漢字]
区点=2717 16進=3B31 シフトJIS=8E50
《常用音訓》サン/かさ
《音読み》 サン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 かさ
《名付け》 かさ
《意味》
{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」
《解字》
n〉
《訓読み》 かさ
《名付け》 かさ
《意味》
{名}かさ。からかさ。▽今は広く、かさ、または、かさのようにおおうものをさす。〈同義語〉→繖。「傘下サンカ」「洋傘ヨウサン(こうもりがさ)」
《解字》
 象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺)
象形。漢代の「通俗文」の「御覧七〇二引」に「帛ヌノを張りて雨を避くるを繖蓋サンガイといふ」とある。繖は「糸+音符散」の会意兼形声文字で、これが古い字。俗字の傘サンは、かさの形を描いたもの。サンという音は、山(△型をしたやま、水がわかれ落ちる分水嶺) 散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。
《熟語》
→熟語
散(ばらばらにわかれちる)と同系で、傘は、雨水が△型のかさによってわかれちることに着目した命名である。
《熟語》
→熟語
因 かさねる🔗⭐🔉
【因】
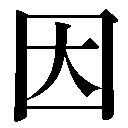 6画 囗部 [五年]
区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6
《常用音訓》イン/よ…る
《音読み》 イン
6画 囗部 [五年]
区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6
《常用音訓》イン/よ…る
《音読み》 イン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに
《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる
《意味》
n〉
《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに
《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる
《意味》
 {動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕
{動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕
 {動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕
{動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕
 {動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕
{動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕
 {名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」
{名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」
 {副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕
{副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕
 {副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕
{副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕
 {動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。
{動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。
 {名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。
《解字》
{名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。
《解字》
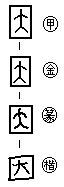 会意。「囗(ふとん)+
会意。「囗(ふとん)+ 印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。
《単語家族》
印(上から下を押さえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。
《単語家族》
印(上から下を押さえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
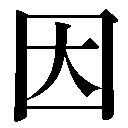 6画 囗部 [五年]
区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6
《常用音訓》イン/よ…る
《音読み》 イン
6画 囗部 [五年]
区点=1688 16進=3078 シフトJIS=88F6
《常用音訓》イン/よ…る
《音読み》 イン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに
《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる
《意味》
n〉
《訓読み》 よる/かさねる(かさぬ)/よりて/よって/ちなむ/ちなみに
《名付け》 ちなみ・なみ・ゆかり・よし・より・よる
《意味》
 {動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕
{動}よる。ふまえる。下になにかをふまえて、その上に乗る。「因循」「殷因於夏礼=殷ハ夏ノ礼ニ因ル」〔→論語〕
 {動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕
{動}よる。かさねる(カサヌ)。何かの下地の上に加わる。〈類義語〉→依。「因之以饑饉=コレニ因ヌルニ饑饉ヲモツテス」〔→論語〕
 {動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕
{動}よる。たよりにする。手づるにする。「因陳子而以告孟子=陳子ニ因リテモツテ孟子ニ告グ」〔→孟子〕
 {名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」
{名}おこった事のよりどころ。〈対語〉→果。「原因」「因由インユウ」
 {副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕
{副}よりて。よって。それにつれて。便乗して。「無恒産、因無恒心=恒産無ケレバ、因ッテ恒心無シ」〔→孟子〕
 {副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕
{副}よりて。よって。それが原因で。「余因得遍観群書=余因リテ遍ク群書ヲ観ルヲ得タリ」〔→宋濂〕
 {動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。
{動・副}ちなむ。ちなみに。ゆかりを持つ。機縁にする。何かを縁にして。
 {名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。
《解字》
{名}掛け算のこと。〈類義語〉→乗。
《解字》
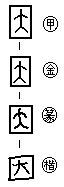 会意。「囗(ふとん)+
会意。「囗(ふとん)+ 印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。
《単語家族》
印(上から下を押さえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
印(乗せた物)、または大(ひと)」で、ふとんを下に敷いて、その上に大の字に乗ることを示す。下地をふまえて、その上に乗ること。茵イン(しとね)の原字。
《単語家族》
印(上から下を押さえる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
奕 かさなる🔗⭐🔉
套 かさね🔗⭐🔉
【套】
 10画 大部
区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385
《音読み》 トウ(タウ)
10画 大部
区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385
《音読み》 トウ(タウ)
 〈t
〈t o〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま
《意味》
o〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま
《意味》
 {動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」
{動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」
 {動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」
{動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」
 {単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。
{単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。
 {名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」
{名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」
 {名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」
{名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」
 「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。
《解字》
会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。
《単語家族》
韜トウ(外皮でつつみ隠す)
「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。
《解字》
会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。
《単語家族》
韜トウ(外皮でつつみ隠す) 疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 大部
区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385
《音読み》 トウ(タウ)
10画 大部
区点=3769 16進=4565 シフトJIS=9385
《音読み》 トウ(タウ)
 〈t
〈t o〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま
《意味》
o〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/つつむ/つつみ/かさね/くま
《意味》
 {動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」
{動・名}かさねる(カサヌ)。長く大きいカバーをかぶせる。また、かぶせてつつむもの。「外套ガイトウ」「套杯トウハイ(小杯を大杯の中に入れたひと組の酒杯)」
 {動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」
{動・名}つつむ。つつみ。外皮でつつみ隠す。また、つつみ隠したもの。「筆套ヒットウ(筆のさや)」「封套フウトウ(=封筒)」
 {単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。
{単位}かさね。衣服を数える単位。下衣の上に上衣をかさねることから。一套とは、衣服ひとかさねをいう。
 {名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」
{名}人をつつみこむ古い習慣。ありきたりのわく。「套語トウゴ」「脱套ダットウ(古い習慣から抜け出る)」
 {名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」
{名}くま。河川が曲がって岸をつつみこんだ所。「河套カトウ」
 「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。
《解字》
会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。
《単語家族》
韜トウ(外皮でつつみ隠す)
「圏套ケントウ」とは、人をつつみこむわなや、しかけ。また、悪だくみ。
《解字》
会意。「大+長」で、大きく長いカバーのこと。外からつつみこむ意を含む。
《単語家族》
韜トウ(外皮でつつみ隠す) 疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
疇チュウ(田を囲むあぜ→外わく)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
家宰 カサイ🔗⭐🔉
【家老】
カロウ  家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』
家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』 一族ちゅうの長老。
一族ちゅうの長老。 〔国〕大名・小名の家臣の長。
〔国〕大名・小名の家臣の長。
 家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』
家臣の長。『家宰カサイ・家相カショウ』 一族ちゅうの長老。
一族ちゅうの長老。 〔国〕大名・小名の家臣の長。
〔国〕大名・小名の家臣の長。
宴妻 カサイ🔗⭐🔉
層 かさなる🔗⭐🔉
【層】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 尸部 [六年]
区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177
《常用音訓》ソウ
《音読み》 ソウ
14画 尸部 [六年]
区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177
《常用音訓》ソウ
《音読み》 ソウ /ゾウ
/ゾウ 〈c
〈c ng〉
《訓読み》 かさなる
《意味》
ng〉
《訓読み》 かさなる
《意味》
 {動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」
{動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」
 {名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕
{名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕
 {名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」
《解字》
会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾
《単語家族》
増(土を何段もかさね増す)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」
《解字》
会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾
《単語家族》
増(土を何段もかさね増す)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 尸部 [六年]
区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177
《常用音訓》ソウ
《音読み》 ソウ
14画 尸部 [六年]
区点=3356 16進=4158 シフトJIS=9177
《常用音訓》ソウ
《音読み》 ソウ /ゾウ
/ゾウ 〈c
〈c ng〉
《訓読み》 かさなる
《意味》
ng〉
《訓読み》 かさなる
《意味》
 {動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」
{動}かさなる。上へ上へと幾段にもかさなる。「層累」「層次(かさなりの順序)」
 {名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕
{名・単位}何階にもかさなった建物。また階数を数えることば。〈類義語〉→楼・→階。「更上一層楼=更ニ上ル一層ノ楼」〔→王之渙〕
 {名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」
《解字》
会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾
《単語家族》
増(土を何段もかさね増す)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}社会や人々の階級。「中間層」「上層階級」
《解字》
会意兼形声。曾(=曽)の字の上部の八印は湯気の姿、中部はせいろう、下部はこんろの形で、何段にもせいろうをかさねて米をふかすこしき。甑ソウ(こしき)の原字。層は「尸(屋の字の上部。たれ幕、屋根)+音符曾ソウ」で、何段もやねをかさねた家。→曾
《単語家族》
増(土を何段もかさね増す)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
嵩 かさ🔗⭐🔉
【嵩】
 13画 山部 [人名漢字]
区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093
《音読み》 スウ
13画 山部 [人名漢字]
区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093
《音読み》 スウ /シュウ
/シュウ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 たかい(たかし)/かさ
《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ
《意味》
ng〉
《訓読み》 たかい(たかし)/かさ
《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ
《意味》
 {形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」
{形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」
 「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。
〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」
《解字》
会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。
〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」
《解字》
会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 山部 [人名漢字]
区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093
《音読み》 スウ
13画 山部 [人名漢字]
区点=3183 16進=3F73 シフトJIS=9093
《音読み》 スウ /シュウ
/シュウ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 たかい(たかし)/かさ
《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ
《意味》
ng〉
《訓読み》 たかい(たかし)/かさ
《名付け》 かさ・たか・たかし・たけ
《意味》
 {形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」
{形}たかい(タカシ)。山がたかくそびえたつさま。転じて、直立してそびえるさま。〈同義語〉→崇。「嵩高スウコウ(=崇高)」
 「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。
〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」
《解字》
会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「嵩山スウザン」とは、五岳の一つ。河南省登封トウホウ県の北にある。「中岳」「崇山スウザン」「嵩岳スウガク」「嵩丘スウキュウ」「嵩高スウコウ」とも。
〔国〕かさ。体積。「嵩がたかい」
《解字》
会意。「山+高」で、たかくそびえる山をあらわす。崇とまったく同じことばをあらわす異体の字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
暈 かさ🔗⭐🔉
【暈】
 13画 日部
区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2
《音読み》 ウン
13画 日部
区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2
《音読み》 ウン
 〈y
〈y n・y
n・y n〉
《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし
《意味》
n〉
《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし
《意味》
 {名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕
{名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕
 ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。
〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。
《解字》
会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。
〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。
《解字》
会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 日部
区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2
《音読み》 ウン
13画 日部
区点=5884 16進=5A74 シフトJIS=9DF2
《音読み》 ウン
 〈y
〈y n・y
n・y n〉
《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし
《意味》
n〉
《訓読み》 かさ/めまい(めまひ)/ぼかし
《意味》
 {名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕
{名}かさ。日や月の周りを、まるく取り巻いた光の輪。灯火の外側に生じたまるい光の輪。「日暈ニチウン(日がさ)」「灯生暈=灯暈ヲ生ズ」〔→韓愈〕
 ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。
〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。
《解字》
会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
ウンス{動・名}めまい(メマヒ)。目がぐるぐる回って、ぼうっとする。〈類義語〉→眩ゲン(くらむ)・→昏コン(暗くなる)。
〔国〕ぼかし。周囲をまるくなすりつつ、しだいに色を薄める絵画・染色の手法。
《解字》
会意兼形声。軍は、車を並べてまるく取り巻いた営舎のこと。まるく取り巻く意を含む。暈は「日+音符軍」で、日をまるく取り巻く光の輪。▽暉キは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枷鎖 カサ🔗⭐🔉
【枷鎖】
カサ 首かせと鎖。罪人の自由をうばう道具。
河朔 カサク🔗⭐🔉
【河北】
カホク  黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』
黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』 中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。
中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。
 黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』
黄河以北の地方。▽「朔」は北。『河朔カサク』 中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。
中国の現在の省の名。渤海ボツカイ湾に面し、黄河以北に位置する。省都は石家荘市。古くは、冀キ、幽、燕エンとよばれた。
沓 かさなる🔗⭐🔉
【沓】
 8画 水部
区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42
《音読み》 トウ(タフ)
8画 水部
区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42
《音読み》 トウ(タフ) /ドウ(ドフ)
/ドウ(ドフ) 〈d
〈d ・t
・t 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ
《意味》
 {動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕
{動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」
 {動}水が後から後からわきあふれる。
〔国〕くつ。履物のくつ。
《解字》
会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。
《単語家族》
踏(くりかえし足を動かす)
{動}水が後から後からわきあふれる。
〔国〕くつ。履物のくつ。
《解字》
会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。
《単語家族》
踏(くりかえし足を動かす) 畳(つみかさねる)
畳(つみかさねる) 習(くりかえし行う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
習(くりかえし行う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 水部
区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42
《音読み》 トウ(タフ)
8画 水部
区点=2303 16進=3723 シフトJIS=8C42
《音読み》 トウ(タフ) /ドウ(ドフ)
/ドウ(ドフ) 〈d
〈d ・t
・t 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/くつ
《意味》
 {動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕
{動}りゅうちょうにしゃべりまくる。「噂沓背憎=噂沓シテ背ニテ憎ム」〔→詩経〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。たくさんかさねあわせる。たくさんかさなりあう。また、そのさま。〈類義語〉→畳ジョウ。「重沓ジュウトウ」「雑沓ザットウ(=雑踏)」
 {動}水が後から後からわきあふれる。
〔国〕くつ。履物のくつ。
《解字》
会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。
《単語家族》
踏(くりかえし足を動かす)
{動}水が後から後からわきあふれる。
〔国〕くつ。履物のくつ。
《解字》
会意。「水+曰(いう)」で、流れるようにしゃべることをあらわす。かさねあわせる意味を含む。
《単語家族》
踏(くりかえし足を動かす) 畳(つみかさねる)
畳(つみかさねる) 習(くりかえし行う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
習(くりかえし行う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
畳 かさなる🔗⭐🔉
【畳】
 12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
 22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
 22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
 16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ)
16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)
/チョウ(テフ) 〈di
〈di 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
 {動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
 {単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
 {動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕
{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。
たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。
《解字》
じょう。たたみを数えることば。
《解字》
 会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる)
会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)
襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
12画 田部 [常用漢字]
区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4
【疊】旧字人名に使える旧字
 22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
22画 田部
区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167
【疉】異体字(A)異体字(A)
 22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
22画 田部
区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168
【疂】異体字(B)異体字(B)
 16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ)
16画 田部
区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169
《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む
《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)
/チョウ(テフ) 〈di
〈di 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう
《名付け》 あき
《意味》
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」
 {動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」
 {単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。
 {動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕
{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」
〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。
たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。
《解字》
じょう。たたみを数えることば。
《解字》
 会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる)
会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。
《単語家族》
沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)
襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
摺ショウ(かさねて折る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
疔 かさ🔗⭐🔉
【疔】
 7画
7画  部
区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A
《音読み》 チョウ(チャウ)
部
区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A
《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ
/テイ 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」
《解字》
会意兼形声。「
ng〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」
《解字》
会意兼形声。「 +音符丁(↑型につかえて出ない)」。
《熟語》
→下付・中付語
+音符丁(↑型につかえて出ない)」。
《熟語》
→下付・中付語
 7画
7画  部
区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A
《音読み》 チョウ(チャウ)
部
区点=6543 16進=614B シフトJIS=E16A
《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ
/テイ 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」
《解字》
会意兼形声。「
ng〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。できものの一種。顔面に生じることが多く、口が小さくて、うみが出にくい。めんちょうの類。「疔瘡チョウソウ」
《解字》
会意兼形声。「 +音符丁(↑型につかえて出ない)」。
《熟語》
→下付・中付語
+音符丁(↑型につかえて出ない)」。
《熟語》
→下付・中付語
疽 かさ🔗⭐🔉
瘍 かさ🔗⭐🔉
瘡 かさ🔗⭐🔉
禍災 カサイ🔗⭐🔉
【禍災】
カサイ 思いがけない災難。『禍殃カオウ・禍害カガイ・禍患カカン』
笠 かさ🔗⭐🔉
笠懸 カサガケ🔗⭐🔉
【笠懸】
カサガケ〔国〕射芸の一つ。馬に乗って綾藺笠アヤイガサを的にして遠くから弓を射るもの。後世はまるい板に皮をはり、中にわらなどを入れてふくらませた物を的として使った。鎌倉時代、武芸の修練のため盛んに行われた。
累 かさなる🔗⭐🔉
【累】
 11画 糸部 [常用漢字]
区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
11画 糸部 [常用漢字]
区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
 〈l
〈l i・l
i・l i・l
i・l i〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに
《名付け》 たか
《意味》
i〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに
《名付け》 たか
《意味》
 {動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」
{動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」
 {動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕
{動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕
 {名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」
{名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」
 {動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕
{動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕
 {副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕
《解字》
会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。
《単語家族》
壘ルイ(=塁。かさねた土)
{副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕
《解字》
会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。
《単語家族》
壘ルイ(=塁。かさねた土) 雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 糸部 [常用漢字]
区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
11画 糸部 [常用漢字]
区点=4663 16進=4E5F シフトJIS=97DD
《常用音訓》ルイ
《音読み》 ルイ
 〈l
〈l i・l
i・l i・l
i・l i〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに
《名付け》 たか
《意味》
i〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/わずらわす(わづらはす)/つなぐ/つながる/かさねて/しきりに
《名付け》 たか
《意味》
 {動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」
{動}かさなる。かさねる(カサヌ)。つながってかさなる。また、ほかの物事をかさね加える。▽上声に読む。〈類義語〉→積。「累代(なん世代もかさなって)」「積累」「家累千金=家ニ千金ヲ累ヌ」
 {動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕
{動}わずらわす(ワヅラハス)。めんどうな事につながりをもたせる。まきぞえをくわす。▽去声に読む。「願以竟内累矣=願ハクハ竟内ヲモッテ累ハサン」〔→荘子〕
 {名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」
{名}めんどうなかかわりあい。また、わずらわしい心配事。▽去声に読む。「家累(家庭内のごたごた)」「及累=累ヲ及ボス」
 {動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕
{動}つなぐ。つながる。つぎつぎとつなぐ。また、つぎつぎと縁がつながる。▽平声に読む。「係累其子弟=ソノ子弟ニ係累ス」〔→孟子〕
 {副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕
《解字》
会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。
《単語家族》
壘ルイ(=塁。かさねた土)
{副}かさねて。しきりに。なんども。▽上声に読む。〈類義語〉→屡ル/シバシバ。「累乞骸骨致仕=累ニ骸骨致仕ヲ乞フ」〔→徳川光圀〕
《解字》
会意兼形声。上部はもと田三つで、ごろごろとつみかさなったさまを描いた象形文字(音ルイ・ライ)。それを音符とし、糸を加えたのが累のもとの字で、糸でつなぐように、つぎつぎと連なってかさなること。
《単語家族》
壘ルイ(=塁。かさねた土) 雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
雷(電気のつらなりかさなったかみなり)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
繖 かさ🔗⭐🔉
【繖】
 18画 糸部
区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384
《音読み》 サン
18画 糸部
区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384
《音読み》 サン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。
n〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。
 18画 糸部
区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384
《音読み》 サン
18画 糸部
区点=6968 16進=6564 シフトJIS=E384
《音読み》 サン
 〈s
〈s n〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。
n〉
《訓読み》 かさ
《意味》
{名}かさ。きぬ張りのかさ。〈同義語〉→傘。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符散(ばらばらと水が四方にちる)」。
苛砕 カサイ🔗⭐🔉
【苛細】
カサイ 取り締まりがきつくて、わずらわしい。『苛砕カサイ』
華彩 カサイ🔗⭐🔉
【華采】
カサイ =華彩。はなやかな彩り。
蓋 かさ🔗⭐🔉
【蓋】
 13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
 12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
 11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》
11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》  ガイ
ガイ /カイ
/カイ
 〈g
〈g i〉/
i〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)
/ゴウ(ガフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》

 {動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
 {名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
 {単位}傘カサなどを数えることば。
{単位}傘カサなどを数えることば。
 {動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
 {動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
 {副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕
{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

 {名}草ぶきの屋根。とま。
{名}草ぶきの屋根。とま。
 {疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる)
{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
 12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
 11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》
11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》  ガイ
ガイ /カイ
/カイ
 〈g
〈g i〉/
i〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)
/ゴウ(ガフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》

 {動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
 {名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
 {単位}傘カサなどを数えることば。
{単位}傘カサなどを数えることば。
 {動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
 {動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
 {副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕
{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

 {名}草ぶきの屋根。とま。
{名}草ぶきの屋根。とま。
 {疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる)
{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
複 かさなる🔗⭐🔉
【複】
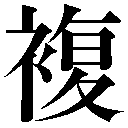 14画 衣部 [五年]
区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
14画 衣部 [五年]
区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)
《意味》
 {名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」
{名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」
 {形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。
《単語家族》
復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。
《単語家族》
復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
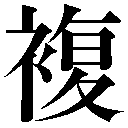 14画 衣部 [五年]
区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
14画 衣部 [五年]
区点=4203 16進=4A23 シフトJIS=95A1
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)
《意味》
 {名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」
{名}単衣(ひとえ)に対して、表だけでなく、裏がかさなって二重になったもの。あわせ。〈類義語〉→袷コウ。「複衣」
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。単に対して、物の上にさらに物が載る。物の上にさらに物を載せて積む。また、かさなっているさま。いくえにもなっているさま。「複沓フクトウ(かさなる)」「複雑」「重複」
 {形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。
《単語家族》
復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}単に対して、二つ以上の。また、数が多い。「複数」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は「はらのふくれたつぼ+夂(足)」で、中に物を入れて外からつつむ、かぶせるの意を含む。つつめば二重になる。往復して二重になることを示すため、夂(足)を加えた。複はそれを音符とし、衣を加えた字で、二重につつむ衣、つまりあわせのこと。
《単語家族》
復(同じ所を行き来する)と同系。また、反覆の覆(くり返す)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
襲 かさね🔗⭐🔉
【襲】
 22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ)
22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)
/ジュウ(ジフ) 〈x
〈x 〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
 {動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
 {単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
 {動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
 {動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる)
{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる) 習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ)
22画 衣部 [常用漢字]
区点=2917 16進=3D31 シフトJIS=8F50
《常用音訓》シュウ/おそ…う
《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)
/ジュウ(ジフ) 〈x
〈x 〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
〉
《訓読み》 かさねる(かさぬ)/かさね/おそう(おそふ)/つぐ
《名付け》 そ・つぎ・より
《意味》
 {動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
{動}かさねる(カサヌ)。衣服をかさねて着る。また、物事をかさねる。「襲衣=衣ヲ襲ヌ」「重仁襲義兮=仁ヲ重ネ義ヲ襲ヌ」〔→楚辞〕
 {単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
{単位}かさね。上下がそろった衣服を一セットとして数えるときのことば。〈類義語〉→套トウ。「一襲」
 {動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
{動}おそう(オソフ)。つぐ。今までのやり方やポストの上にかさなる。転じて、従来の方法や地位をそのまま引きつぐ。「世襲」「沿襲(従来の方法にそってつぐ)」「襲封=封ヲ襲グ」
 {動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる)
{動}おそう(オソフ)。不意に攻める。▽訓の「おそふ」は「おす(押)」の派生語で、相手に押しかかること。「非義襲而取之也=義、襲ヒテコレヲ取レルモノニハアラザルナリ」〔→孟子〕
〔国〕かさね。平安時代、袍ホウの下に着た衣服。
《解字》
会意兼形声。襲の上部は、もと龍を二つ並べた字(音トウ)で、かさねるの意をあらわす。襲はそれを音符とし、衣を加えた字で、衣服をかさねること。
《単語家族》
踏トウ(足ぶみをかさねる) 習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
習シュウ(かさねる)などと同系。
《類義》
→重
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
過差 カサ🔗⭐🔉
【過差】
カサ  あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。
あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。 身分不相応のぜいたく。
身分不相応のぜいたく。
 あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。
あやまち。過失。▽「差」は、くいちがい。しそこない。 身分不相応のぜいたく。
身分不相応のぜいたく。
重 かさなる🔗⭐🔉
【重】
 9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ
/チョウ 〈zh
〈zh ng〉〈ch
ng〉〈ch ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
 {形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
 {形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 {動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
 {単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
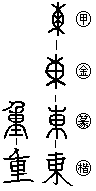 会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)
会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ
/チョウ 〈zh
〈zh ng〉〈ch
ng〉〈ch ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
 {形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
 {形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 {動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
 {単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
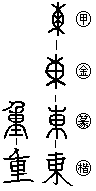 会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)
会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
量 かさ🔗⭐🔉
【量】
 12画 里部 [四年]
区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA
《常用音訓》リョウ/はか…る
《音読み》 リョウ(リャウ)
12画 里部 [四年]
区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA
《常用音訓》リョウ/はか…る
《音読み》 リョウ(リャウ) /ロウ(ラウ)
/ロウ(ラウ) 〈li
〈li ng・li
ng・li ng〉
《訓読み》 はかる/かさ/ます
《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる
《意味》
ng〉
《訓読み》 はかる/かさ/ます
《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる
《意味》

 {動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕
{動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕
 {名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」
{名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」
 {名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」
《解字》
{名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」
《解字》
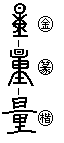 会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。
《単語家族》
両リョウ(天びんばかり)と同系。
《類義》
→測
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。
《単語家族》
両リョウ(天びんばかり)と同系。
《類義》
→測
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 里部 [四年]
区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA
《常用音訓》リョウ/はか…る
《音読み》 リョウ(リャウ)
12画 里部 [四年]
区点=4644 16進=4E4C シフトJIS=97CA
《常用音訓》リョウ/はか…る
《音読み》 リョウ(リャウ) /ロウ(ラウ)
/ロウ(ラウ) 〈li
〈li ng・li
ng・li ng〉
《訓読み》 はかる/かさ/ます
《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる
《意味》
ng〉
《訓読み》 はかる/かさ/ます
《名付け》 かず・さと・とも・はかり・はかる
《意味》

 {動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕
{動}はかる。かさ・重さ・大きさなどをはかる。転じて、物事のなりゆきをデータによって考え予測する。物色する。〈類義語〉→計・→測。「計量」「思量(考える)」「量力而行之=力ヲ量リテコレヲ行フ」〔→左伝〕
 {名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」
{名}かさ。ますや入れ物の容積。また、液体や粒状のものの体積や重さ。転じて、人間のもつ力や気持ちの大きさ。▽去声に読む。「容量」「力量」
 {名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」
《解字》
{名}ます。かさをはかるます。▽去声に読む。「量器」「度量衡(物さし・ます・はかり)」
《解字》
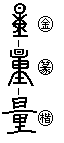 会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。
《単語家族》
両リョウ(天びんばかり)と同系。
《類義》
→測
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「穀物のしるし+重」で、穀物の重さを天びんではかることを示す。穀物や砂状のものは、はかりとますとのどちらでもはかる。のち、分量の意となる。
《単語家族》
両リョウ(天びんばかり)と同系。
《類義》
→測
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
霞彩 カサイ🔗⭐🔉
【霞彩】
カサイ 朝やけ・夕やけなどの美しい彩り。
漢字源に「カサ」で始まるの検索結果 1-35。もっと読み込む
 9画 大部
区点=5285 16進=5475 シフトJIS=9AF3
《音読み》 エキ
9画 大部
区点=5285 16進=5475 シフトJIS=9AF3
《音読み》 エキ 〉
《訓読み》 かさなる
《意味》
〉
《訓読み》 かさなる
《意味》
 10画
10画  14画
14画  15画
15画  ng〉
《訓読み》 かさ/きず
《意味》
ng〉
《訓読み》 かさ/きず
《意味》
 11画 竹部
区点=1962 16進=335E シフトJIS=8A7D
《音読み》 リュウ(リフ)
11画 竹部
区点=1962 16進=335E シフトJIS=8A7D
《音読み》 リュウ(リフ) {名}かさ。かぶりがさ。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符立(高さをそろえてたてる)」。平衡を保って頭上にたてるかさ。
《熟語》
{名}かさ。かぶりがさ。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符立(高さをそろえてたてる)」。平衡を保って頭上にたてるかさ。
《熟語》
 19画 鳥部
区点=8307 16進=7327 シフトJIS=EA46
《音読み》 ジャク
19画 鳥部
区点=8307 16進=7327 シフトJIS=EA46
《音読み》 ジャク