複数辞典一括検索+![]()
![]()
亭 とどまる🔗⭐🔉
【亭】
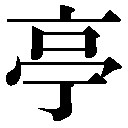 9画 亠部 [常用漢字]
区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
9画 亠部 [常用漢字]
区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)
/ジョウ(ヂャウ) /チン
/チン 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 とどまる
《名付け》 たかし
《意味》
ng〉
《訓読み》 とどまる
《名付け》 たかし
《意味》

 {名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕
{名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕 {名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。
{名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。
 {動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」
〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」
《解字》
{動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」
〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」
《解字》
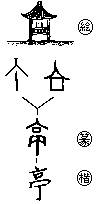 会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように
会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように 型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
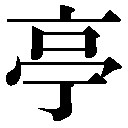 9画 亠部 [常用漢字]
区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
9画 亠部 [常用漢字]
区点=3666 16進=4462 シフトJIS=92E0
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)
/ジョウ(ヂャウ) /チン
/チン 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 とどまる
《名付け》 たかし
《意味》
ng〉
《訓読み》 とどまる
《名付け》 たかし
《意味》

 {名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕
{名}地上にすっくとたった建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休息所。あずまや。「駅亭エキテイ(街道ぞいの休息所)」「涼亭リョウテイ(遊覧地の休息所)」「列亭置郵=亭ヲ列ネ郵ヲ置ク」〔東観漢記〕 {名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。
{名}秦シン・漢代の行政区画の名。十里ごとを一亭とし、十亭を一郷として、亭長を置いた。
 {動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」
〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」
《解字》
{動}とどまる。ちょうどその点にあたってとまる。〈同義語〉→停。「亭年」
〔国〕あずまや式のしゃれたつくりの家。「料亭」
《解字》
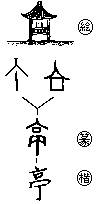 会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように
会意兼形声。「高の略体(楼閣)+音符丁テイ」で、地上に直角に釘クギのように 型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
型にたつ建物のこと。亭は停(ひと所に安定してじっとたつ)に含まれる。定(じっとひと所にたつ)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
住 とどまる🔗⭐🔉
【住】
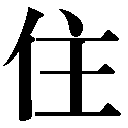 7画 人部 [三年]
区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A
《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
7画 人部 [三年]
区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A
《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チュウ
/チュウ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)
《名付け》 おき・すみ・もち・よし
《意味》
〉
《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)
《名付け》 おき・すみ・もち・よし
《意味》
 ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕
ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕
 {名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」
{名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕
 「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
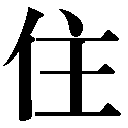 7画 人部 [三年]
区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A
《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
7画 人部 [三年]
区点=2927 16進=3D3B シフトJIS=8F5A
《常用音訓》ジュウ/す…まう/す…む
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チュウ
/チュウ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)
《名付け》 おき・すみ・もち・よし
《意味》
〉
《訓読み》 すまう/すむ/すまい(すまひ)/とどまる/とどめる(とどむ)
《名付け》 おき・すみ・もち・よし
《意味》
 ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕
ジュウス{動}すむ。居所を定めてそこで生活する。「妾住易州=妾ハ易州ニ住ム」〔→捜神記〕
 {名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」
{名}すまい(スマヒ)。すむこと。また、すむ所。住居。「衣食住」
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にじっととどまる。また、とどめる。「不為愁人住少時=愁人ノ為ニ少時モ住マラズ」〔戴叔倫〕
 「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「不住ヤマズ」とは、…してやめない、しつづけるの意。「両岸猿声啼不住=両岸ノ猿声啼イテ住マズ」〔→李白〕
《解字》
会意兼形声。丶印は、一か所にじっとたつ灯火を示す。主は、丶印(灯火)の下に燭台ショクダイを描いたさまで、定立して動かないの意を含む。住は「人+音符主」で、じっとたって動かないの意。→主
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
停 とどまる🔗⭐🔉
【停】
 11画 人部 [四年]
区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
11画 人部 [四年]
区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)
/ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)
/チョウ(チャウ) 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)
《名付け》 とどむ
《意味》
ng〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)
《名付け》 とどむ
《意味》
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
 {動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕
{動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕
 {単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」
《解字》
会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭
《単語家族》
定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」
《解字》
会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭
《単語家族》
定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 人部 [四年]
区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
11画 人部 [四年]
区点=3668 16進=4464 シフトJIS=92E2
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /ジョウ(ヂャウ)
/ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)
/チョウ(チャウ) 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)
《名付け》 とどむ
《意味》
ng〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)
《名付け》 とどむ
《意味》
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。一か所にとどまる。また、一か所にとどめる。「停滞」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ロニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
 {動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕
{動}やめる(ヤム)。しばらく中止する。「琵琶声停欲語遅=琵琶ノ声停ミ語ラント欲シテ遅シ」〔→白居易〕
 {単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」
《解字》
会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭
《単語家族》
定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{単位}〔俗〕十分の一を単位として、比率をあらわすことば。「九停(九割の人)」
《解字》
会意兼形声。丁は、釘テイ(くぎ)の原字で、ある点につんとささって動かないの意を含む。亭テイは「高(高い建物)の略体+音符丁」の会意兼形声文字で、建物の土台が棒をたてたように動かないさま。停は「人+音符亭」で、人がひと所にじっととまって動かないこと。→亭
《単語家族》
定テイ(足がひと所にとまって動かない)と同系。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
届 とどく🔗⭐🔉
【届】
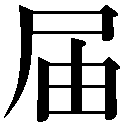 8画 尸部 [六年]
区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD
【屆】旧字旧字
8画 尸部 [六年]
区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD
【屆】旧字旧字
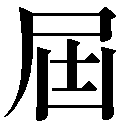 8画 尸部
区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C
《常用音訓》とど…く/とど…ける
《音読み》 カイ
8画 尸部
区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C
《常用音訓》とど…く/とど…ける
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)
《名付け》 あつ・いたる・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)
《名付け》 あつ・いたる・ゆき
《意味》
 {動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕
{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕
 {単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」
〔国〕
{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」
〔国〕 とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」
とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」 とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。
とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。 とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。
《解字》
会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。
とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。
《解字》
会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。
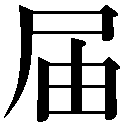 8画 尸部 [六年]
区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD
【屆】旧字旧字
8画 尸部 [六年]
区点=3847 16進=464F シフトJIS=93CD
【屆】旧字旧字
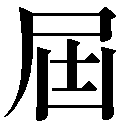 8画 尸部
区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C
《常用音訓》とど…く/とど…ける
《音読み》 カイ
8画 尸部
区点=5392 16進=557C シフトJIS=9B9C
《常用音訓》とど…く/とど…ける
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)
《名付け》 あつ・いたる・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/とどく/とどけ/とどける(とどく)
《名付け》 あつ・いたる・ゆき
《意味》
 {動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕
{動}いたる。とどく。決められた時刻・時期・場所にいたる。〈類義語〉→至・→到。「毎届初一=初一ニ届ルゴトニ」〔燕京歳時記〕
 {単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」
〔国〕
{単位}〔俗〕決められた会期になって開く会合を数えることば。「第一届会議(第一期会議のこと)」
〔国〕 とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」
とどけ。役所や監督者の手元に差し出す文書。「欠席届」 とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。
とどける(トドク)。決められた場所に物がつくようにする。また、役所などに申し出る。 とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。
《解字》
会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。
とどく。送ったものがそこに着く。また、声などがそこに達する。
《解字》
会意兼形声。屆の下部(音カイ)は「凵(あな)+土」の会意文字で、塊カイと同じく、まるい土のかたまりや穴のこと。屆はそれを音符とし、尸(からだ)を加えた字。もと、ずんぐりとまるく太いからだで、動作がにぶくとまりがちなこと。転じて、一定の場所までとどいてとまること。
底 とどまる🔗⭐🔉
【底】
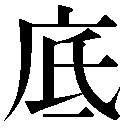 8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ
8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
 {名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
 {名}文書の下書き。「底稿」
{名}文書の下書き。「底稿」
 {動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
 「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
 {疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
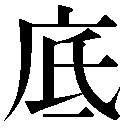 8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ
8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
 {名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
 {名}文書の下書き。「底稿」
{名}文書の下書き。「底稿」
 {動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
 「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
 {疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
扈 とどめる🔗⭐🔉
【扈】
 11画 戸部
区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB
《音読み》 コ
11画 戸部
区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB
《音読み》 コ /グ/ゴ
/グ/ゴ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)
《意味》
〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)
《意味》
 {動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」
{動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」
 {動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。
{動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。
 {名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。
{名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。
 {名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」
{名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」
 「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。
「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。
 「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。
《解字》
会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。
《単語家族》
戸(出入りを制止するとびら)
「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。
《解字》
会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。
《単語家族》
戸(出入りを制止するとびら) 雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 戸部
区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB
《音読み》 コ
11画 戸部
区点=7829 16進=6E3D シフトJIS=E7BB
《音読み》 コ /グ/ゴ
/グ/ゴ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)
《意味》
〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/とどめる(とどむ)
《意味》
 {動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」
{動}したがう(シタガフ)。主君のあとにつきしたがう。主君のお供をする。「扈従コジュウ」
 {動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。
{動}とどめる(トドム)。行動を束縛する。
 {名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。
{名}主君に使われている従者。役目にしばられる雇い人。
 {名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」
{名}鳥。人間になつく鳥。▽雇に当てた用法。「九扈キュウコ(時節を告げる鳥の総称)」「桑扈ソウコ(桑つみの時を知らせる鳥)」「春扈シュンコ(春告げ鳥。うぐいすのこと)」
 「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。
「扈扈ココ」とは、おだやかなさま。おっとりしたさま。
 「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。
《解字》
会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。
《単語家族》
戸(出入りを制止するとびら)
「跋扈バッコ」とは、わくをはずしてかってにはびこること。
《解字》
会意兼形声。邑ユウは「口印(領地)+人のひざまずいたさま」からなり、服従する領民のこと。扈は「邑+音符戸(出入りを制止するとびら)」で、行動を制限されて服従する従者のこと。
《単語家族》
戸(出入りを制止するとびら) 雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
雇(行動をおさえた飼い鳥)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
止 とどまる🔗⭐🔉
【止】
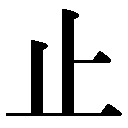 4画 止部 [二年]
区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E
《常用音訓》シ/と…まる/と…める
《音読み》 シ
4画 止部 [二年]
区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E
《常用音訓》シ/と…まる/と…める
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ
《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと
《意味》
〉
《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ
《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと
《意味》
 {動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕
{動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕
 {動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕
{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕
 {動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕
{動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕
 {名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕
{名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕
 {副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕
{副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕
 {助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕
《解字》
{助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕
《解字》
 象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。
《単語家族》
歯(ものをかんでとめる前歯)
象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。
《単語家族》
歯(ものをかんでとめる前歯) 阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。
《類義》
留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁
《異字同訓》
とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。
《類義》
留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁
《異字同訓》
とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
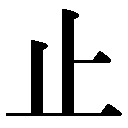 4画 止部 [二年]
区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E
《常用音訓》シ/と…まる/と…める
《音読み》 シ
4画 止部 [二年]
区点=2763 16進=3B5F シフトJIS=8E7E
《常用音訓》シ/と…まる/と…める
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ
《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと
《意味》
〉
《訓読み》 とまる/とどまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/やめる(やむ)/ただ
《名付け》 おる・ただ・と・とどむ・とまる・とめ・とも・もと
《意味》
 {動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕
{動}とまる。とどまる。じっとひと所にとまる。〈対語〉→進。〈類義語〉→留・→滞。「停止」「或五十歩而後止=或イハ五十歩ニシテ後ニ止マル」〔→孟子〕「知止而后有定=止マルヲ知リテ后ニ定マル有リ」〔→大学〕
 {動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕
{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。じっとひと所にとめる。行こうとするのを押さえてとめる。「制止」「止子路宿=子路ヲ止メテ宿セシム」〔→論語〕
 {動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕
{動}やめる(ヤム)。進行をやめる。仕事をとりやめる。役目をやめる。〈類義語〉→已。「中止」「止吾止也=止ムハ吾ガ止ムナリ」〔→論語〕
 {名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕
{名}たちどまった姿。転じて、姿。「容姿」「人而無止=人ニシテ止無シ」〔→詩経〕
 {副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕
{副}ただ。それだけ、わずかにの意をあらわすことば。▽それだけにとどまるの意から。〈類義語〉→只タダ。「止一人耳=止ダ一人ノミ」「止可以一宿=止ダモッテ一宿スベシ」〔→荘子〕
 {助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕
《解字》
{助}句末にそえることば。「百室盈止、婦子寧止=百室盈チテ、婦子寧シ」〔→詩経〕
《解字》
 象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。
《単語家族》
歯(ものをかんでとめる前歯)
象形。足の形を描いたもので、足がじっとひと所にとまることを示す。趾シ(あし)の原字。
《単語家族》
歯(ものをかんでとめる前歯) 阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。
《類義》
留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁
《異字同訓》
とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
阯シ・址シ(じっととどまったあと)などと同系。
《類義》
留は、溜リュウ(たまる)と同系で、一時そこにとまること。滞は、帯(長いおび)と同系で、長びくこと。停は、棒だちにたちどまること。泊は、舟がひと所にとまること。→禁
《異字同訓》
とまる/とめる。 止まる/止める「交通が止まる。水道が止まる。笑いが止まらない。息を止める。通行止め」留まる/留める「小鳥が木の枝に留(止)まる。ボタンを留める。留め置く/書留」泊まる/泊める「船が港に泊まる。宿直室に泊まる。友達を家に泊める」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
知止 トドマルヲシル🔗⭐🔉
注 とどめる🔗⭐🔉
【注】
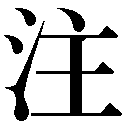 8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ
8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ /ス
/ス /シュ
/シュ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
 {動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
 {動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
 {動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
 チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
 {動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
 チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
 {名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ)
{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ) 柱(はしら)
柱(はしら) 住(一か所にとどまる→すむ)
住(一か所にとどまる→すむ) 駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
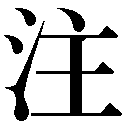 8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ
8画 水部 [三年]
区点=3577 16進=436D シフトJIS=928D
《常用音訓》チュウ/そそ…ぐ
《音読み》 チュウ /ス
/ス /シュ
/シュ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
〉
《訓読み》 そそぐ/つぐ/つける(つく)/とどめる(とどむ)/しるす
《意味》
 {動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
{動}そそぐ。つぐ。水が柱のようにたってそそぐ。「雨下如注=雨ノ下ルコト注グガ如シ」〔→後漢書〕
 {動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
{動}そそぐ。目や心を一か所に集中させる。「引領注目=領ヲ引キテ注目ス」
 {動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
{動}つける(ツク)。一か所にくっつける。「烏膏注脣脣似泥=烏膏脣ニ注ケ脣ハ泥ニ似タリ」〔→白居易〕
 チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
チュウス{動}とどめる(トドム)。一か所にとまるようにねらいをつけてなげる。〈同義語〉→投。「以瓦注者巧、以鉤注者憚=瓦ヲモッテ注スル者ハ巧ミニ、鉤ヲモッテ注スル者ハ憚ス」〔→荘子〕
 {動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
{動・名}しるす。書きとめる。記載する。また、書きとめたもの。〈同義語〉→註。「注記」
 チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
チュウス{動}文章の意味を解釈したり説明したりする。〈同義語〉→註。「注釈」
 {名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ)
{名}文章につけられたその文章の意味の解釈や説明。〈同義語〉→註。「脚注」
《解字》
会意兼形声。「水+音符主」。→主
《単語家族》
主(じっとたって燃える灯火の炎→一か所に居続けるあるじ) 柱(はしら)
柱(はしら) 住(一か所にとどまる→すむ)
住(一か所にとどまる→すむ) 駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
駐(一か所にとどまる)などと同系。
《類義》
→漑
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
淤 とどこおる🔗⭐🔉
【淤】
 11画 水部
区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9
《音読み》 オ
11画 水部
区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9
《音読み》 オ /ヨ
/ヨ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ
《意味》
〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ
《意味》
 {動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」
{動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」
 {名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」
《解字》
会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於
《単語家族》
塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」
《解字》
会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於
《単語家族》
塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 水部
区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9
《音読み》 オ
11画 水部
区点=6243 16進=5E4B シフトJIS=9FC9
《音読み》 オ /ヨ
/ヨ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ
《意味》
〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)/にごる/どろ
《意味》
 {動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」
{動・形}とどこおる(トドコホル)。にごる。水や血液がつまって流れない。また、そのさま。「淤塞オソク(つまってたまる)」「淤血オケツ(たまった血)」
 {名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」
《解字》
会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於
《単語家族》
塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}どろ。つまったどろ。どろのたまり。「淤泥オデイ」
《解字》
会意兼形声。於オは「はた+=印(かさなる)」の会意文字で、旗がなびかずに垂れて止まったさま。「説文解字」が烏オ(からす)を於の原字とするは誤り。淤は「水+音符於(とまる)」で、水が止まって流れないこと。→於
《単語家族》
塢オ・ウ(流れを止める堤)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
渟 とどまる🔗⭐🔉
滞 とどこおる🔗⭐🔉
【滞】
 13画 水部 [常用漢字]
区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8
【滯】旧字人名に使える旧字
13画 水部 [常用漢字]
区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8
【滯】旧字人名に使える旧字
 14画 水部
区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA
《常用音訓》タイ/とどこお…る
《音読み》 タイ
14画 水部
区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA
《常用音訓》タイ/とどこお…る
《音読み》 タイ /テイ
/テイ /ダイ
/ダイ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)
《意味》
〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)
《意味》
 {動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」
{動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」
 {動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。
《単語家族》
帶(=帯)
{動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。
《単語家族》
帶(=帯) 池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 水部 [常用漢字]
区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8
【滯】旧字人名に使える旧字
13画 水部 [常用漢字]
区点=3458 16進=425A シフトJIS=91D8
【滯】旧字人名に使える旧字
 14画 水部
区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA
《常用音訓》タイ/とどこお…る
《音読み》 タイ
14画 水部
区点=6292 16進=5E7C シフトJIS=9FFA
《常用音訓》タイ/とどこお…る
《音読み》 タイ /テイ
/テイ /ダイ
/ダイ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)
《意味》
〉
《訓読み》 とどこおる(とどこほる)
《意味》
 {動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」
{動}とどこおる(トドコホル)。ひと所にとまっていつまでも動かない。〈類義語〉→留。「滞在」「太史公、留滞周南=太史公、周南ニ留滞ス」
 {動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。
《単語家族》
帶(=帯)
{動}とどこおる(トドコホル)。進行がとまってはかどらない。〈対語〉→滑。「渋滞(しぶってとまる)」「是何濡滞也=コレナンゾ濡滞ナルヤ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。帶タイ(=帯)は「おびに佩玉ハイギョクのついた形+布かざりの垂れた形」の会意文字で、腰につけておくおび。滯は「水+音符帶」で、帯が長くのびて腰にまといついているように、水が定着して動かないこと。
《単語家族》
帶(=帯) 池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
池(水が平らにのびてたまって動かぬいけ)などと同系。池は、滞の語尾が転じたことば。
《類義》
→止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
留 とどまる🔗⭐🔉
【留】
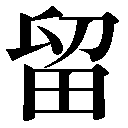 10画 田部 [五年]
区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF
【畄】異体字異体字
10画 田部 [五年]
区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF
【畄】異体字異体字
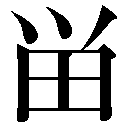 8画 田部
区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156
《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める
《音読み》 リュウ(リウ)
8画 田部
区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156
《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める
《音読み》 リュウ(リウ) /ル
/ル 〈li
〈li 〉
《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる
《名付け》 たね・と・とめ・ひさ
《意味》
〉
《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる
《名付け》 たね・と・とめ・ひさ
《意味》
 {動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕
{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕
 {動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」
{動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」
 {動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」
{動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」
 {名}星座の名。すばる。昴ボウとも。
{名}星座の名。すばる。昴ボウとも。
 {単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。
《解字》
{単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。
《解字》
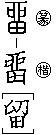 会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。
《単語家族》
溜リュウ(とどまって流れない水)
会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。
《単語家族》
溜リュウ(とどまって流れない水) 瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。
《類義》
→止
《異字同訓》
とまる/とめる。 →止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。
《類義》
→止
《異字同訓》
とまる/とめる。 →止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
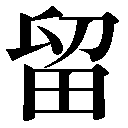 10画 田部 [五年]
区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF
【畄】異体字異体字
10画 田部 [五年]
区点=4617 16進=4E31 シフトJIS=97AF
【畄】異体字異体字
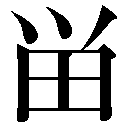 8画 田部
区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156
《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める
《音読み》 リュウ(リウ)
8画 田部
区点=6523 16進=6137 シフトJIS=E156
《常用音訓》リュウ/ル/と…まる/と…める
《音読み》 リュウ(リウ) /ル
/ル 〈li
〈li 〉
《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる
《名付け》 たね・と・とめ・ひさ
《意味》
〉
《訓読み》 とまる/とめる(とむ)/とどめる(とどむ)/とどまる
《名付け》 たね・と・とめ・ひさ
《意味》
 {動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕
{動}とめる(トム)。とどめる(トドム)。いきかけるのをとめる。「慰留イリュウ」「挽留バンリュウ(引きとめる)」「留意=意ヲ留ム」「因留沛公与飲=因リテ沛公ヲ留メテトモニ飲ス」〔→史記〕
 {動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」
{動}とどめる(トドム)。あとに残す。「留名=名ヲ留ム」「不留影=影ヲ留メズ」
 {動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」
{動}とどまる。いきかけてとまる。また、とどこおる。「逗留トウリュウ」「留滞」
 {名}星座の名。すばる。昴ボウとも。
{名}星座の名。すばる。昴ボウとも。
 {単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。
《解字》
{単位}ソ連の貨幣の単位。ルーブルに当てたことば。
《解字》
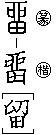 会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。
《単語家族》
溜リュウ(とどまって流れない水)
会意。上部はもと戸を押しあけるさまの上に―印を加えて、あきそうになる戸や窓を押さえてとめることを示す。留はそれに田(一定の面積の地)を加えた字で、動きやすいものをある場所の中にしばらくとどめることを示す。
《単語家族》
溜リュウ(とどまって流れない水) 瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。
《類義》
→止
《異字同訓》
とまる/とめる。 →止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
瘤リュウ(血液がとどまって生じるこぶ)などと同系。
《類義》
→止
《異字同訓》
とまる/とめる。 →止
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
禁 とどめる🔗⭐🔉
【禁】
 13画 示部 [五年]
区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6
《常用音訓》キン
《音読み》 キン(キム)
13画 示部 [五年]
区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6
《常用音訓》キン
《音読み》 キン(キム) /コン(コム)
/コン(コム) 〈j
〈j n・j
n・j n〉
《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ
《意味》
n〉
《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ
《意味》
 キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕
キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕
 {名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕
{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕
 {名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」
{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」
 {動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」
{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」
 {動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」
{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」
 {動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」
{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」
 「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。
《解字》
「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。
《単語家族》
噤キン(口をふさぐ)
「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。
《解字》
「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。
《単語家族》
噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。
《類義》
止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。
《類義》
止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 示部 [五年]
区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6
《常用音訓》キン
《音読み》 キン(キム)
13画 示部 [五年]
区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6
《常用音訓》キン
《音読み》 キン(キム) /コン(コム)
/コン(コム) 〈j
〈j n・j
n・j n〉
《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ
《意味》
n〉
《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ
《意味》
 キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕
キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕
 {名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕
{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕
 {名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」
{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」
 {動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」
{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」
 {動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」
{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」
 {動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」
{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」
 「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。
《解字》
「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。
《単語家族》
噤キン(口をふさぐ)
「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。
《解字》
「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。
《単語家族》
噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。
《類義》
止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。
《類義》
止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
稽 とどまる🔗⭐🔉
【稽】
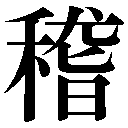 15画 禾部
区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D
《音読み》 ケイ
15画 禾部
区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D
《音読み》 ケイ /ケ
/ケ 〈j
〈j ・q
・q 〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)
《意味》
〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)
《意味》
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕
 {動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」
{動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」
 {動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
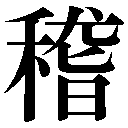 15画 禾部
区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D
《音読み》 ケイ
15画 禾部
区点=2346 16進=374E シフトJIS=8C6D
《音読み》 ケイ /ケ
/ケ 〈j
〈j ・q
・q 〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)
《意味》
〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)/かんがえる(かんがふ)/くらべる(くらぶ)
《意味》
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。一定のところまでとどいてとまる。とどこおる。ためらう。「稽留ケイリュウ」「稽首ケイシュ」「何足久稽天下士乎=ナンゾ久シク天下ノ士ヲ稽マルニ足ランヤ」〔→後漢書〕
 {動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」
{動}かんがえる(カンガフ)。よせあわせてかんがえる。〈類義語〉→考・→計。「稽古=古ヲ稽フ」「無稽ムケイ(根拠がない)」
 {動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}くらべる(クラブ)。比較する。〈類義語〉→計。「反脣而相稽=脣ヲ反シテアヒ稽ブ」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。もと「禾(作物)+音符耆キ(長くたくわえる)」で、久しくとどめおいた収穫物。のち計(あわせてはかる)に当て、次々とかんがえあわせること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
紮 とどまる🔗⭐🔉
蠹毒 トドク🔗⭐🔉
【蠹害】
トガイ  しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。
しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。 物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』
物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』
 しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。
しみ(虫の名)が衣服や書物を食い破る害。 物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』
物事を害すること。またその害。『蠹毒トドク』
轟 とどろく🔗⭐🔉
【轟】
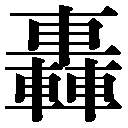 21画 車部
区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C
【軣】異体字異体字
21画 車部
区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C
【軣】異体字異体字
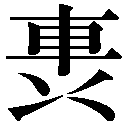 11画 車部
区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763
《音読み》 ゴウ(ガウ)
11画 車部
区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763
《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(ク
/コウ(ク ウ)
ウ)
 〈h
〈h ng〉
《訓読み》 とどろく
《意味》
ng〉
《訓読み》 とどろく
《意味》
 {形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。
{形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。
 {形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」
{形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」
 {形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」
{形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」
 {形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。
〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。
《解字》
会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。
〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。
《解字》
会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
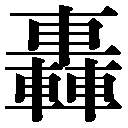 21画 車部
区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C
【軣】異体字異体字
21画 車部
区点=2576 16進=396C シフトJIS=8D8C
【軣】異体字異体字
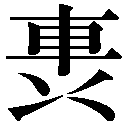 11画 車部
区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763
《音読み》 ゴウ(ガウ)
11画 車部
区点=7736 16進=6D44 シフトJIS=E763
《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(ク
/コウ(ク ウ)
ウ)
 〈h
〈h ng〉
《訓読み》 とどろく
《意味》
ng〉
《訓読み》 とどろく
《意味》
 {形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。
{形・名}ごろごろととどろく音の形容。多くの車の往来する音。
 {形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」
{形・名}地ひびきのする大きな音の形容。どんととどろく音。ざわざわとさわぎみだれる音。「轟音ゴウオン」「喧轟ケンゴウ」
 {形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」
{形}物事が盛んで激しいさま。「轟轟烈烈ゴウゴウレツレツ」
 {形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。
〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。
《解字》
会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}〔俗〕火薬の爆発する音の形容。
〔国〕とどろく。(イ)音が鳴り響く。(ロ)名まえが世間に知れわたる。
《解字》
会意。「車+車+車」で、多くの車が往来することをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
逗 とどまる🔗⭐🔉
【逗】
 10画
10画  部
区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080
《音読み》 トウ
部
区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080
《音読み》 トウ /ズ(ヅ)
/ズ(ヅ) 〈d
〈d u〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
u〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」
{動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」
 トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」
トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」
 トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。「
トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。
《単語家族》
住(とまる)
+音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。
《単語家族》
住(とまる) 注(ひと所にそそぐ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
注(ひと所にそそぐ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画
10画  部
区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080
《音読み》 トウ
部
区点=3164 16進=3F60 シフトJIS=9080
《音読み》 トウ /ズ(ヅ)
/ズ(ヅ) 〈d
〈d u〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
u〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」
{動}とどまる。とどめる(トドム)。じっとたちどまる。しばらくそこにとどまって動かない。しばらくそこに足をとめる。〈同義語〉→投。〈類義語〉→住・→駐。「逗留トウリュウ」「逗宿トウシュク」
 トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」
トウズ{動}ねらいをつけて投げる。目標にぴたりとあうように与える。〈同義語〉→投。「逗薬(=投薬。病気にあわせて薬を与える)」
 トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。「
トウズ{動}じっとひと所にしたたる。そそぐ。〈類義語〉→注。「桂露対仙娥、星星下雲逗=桂露仙娥ニ対シ、星星トシテ雲ヨリ下リテ逗ズ」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。
《単語家族》
住(とまる)
+音符豆(じっとひと所にたつたかつき)」。
《単語家族》
住(とまる) 注(ひと所にそそぐ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
注(ひと所にそそぐ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遏 とどめる🔗⭐🔉
【遏】
 13画
13画  部
区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F
《音読み》 アツ
部
区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F
《音読み》 アツ /アチ
/アチ 〈
〈 〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす
《意味》
〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす
《意味》
 {動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕
{動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕
 {動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率
{動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率 テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。「
テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。
《単語家族》
謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
+音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。
《単語家族》
謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画
13画  部
区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F
《音読み》 アツ
部
区点=7801 16進=6E21 シフトJIS=E79F
《音読み》 アツ /アチ
/アチ 〈
〈 〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす
《意味》
〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/さえぎる(さへぎる)/つくす
《意味》
 {動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕
{動}とどめる(トドム)。さえぎる(サヘギル)。おしとどめる。おさえて防ぐ。「遏止アツシ」「作尹并州遏戎虜=并州ニ尹ト作リテ戎虜ヲ遏ム」〔→李白〕
 {動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率
{動}つくす。からからになるまで出しつくす。▽竭ケツに当てた用法。「夏王率遏衆力=夏王率 テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。「
テ衆力ヲ遏ス」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。
《単語家族》
謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
+音符曷カツ(=喝。はっと声をかけておしとどめる)」。
《単語家族》
謁エツ(おしとどめて直訴する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
邸 とどめる🔗⭐🔉
【邸】
 8画 邑部 [常用漢字]
区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
8画 邑部 [常用漢字]
区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる
《名付け》 いえ
《意味》
〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる
《名付け》 いえ
《意味》
 {名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」
{名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」
 {名}宿屋。旅館。「邸舎」
{名}宿屋。旅館。「邸舎」
 {動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕
{動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕
 {動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。
《単語家族》
柢テイ(とまっている根もと)
{動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。
《単語家族》
柢テイ(とまっている根もと) 底(根が生えたように固着する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
底(根が生えたように固着する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 邑部 [常用漢字]
区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
8画 邑部 [常用漢字]
区点=3701 16進=4521 シフトJIS=9340
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる
《名付け》 いえ
《意味》
〉
《訓読み》 とどめる(とどむ)/いたる
《名付け》 いえ
《意味》
 {名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」
{名}もと、諸侯が都に来た時にとまる宿舎。転じて、貴族のやしき。りっぱなやしき。▽何々王という代わりに何々邸ということがある。〈同義語〉→第。「邸宅」「官邸」
 {名}宿屋。旅館。「邸舎」
{名}宿屋。旅館。「邸舎」
 {動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕
{動}とどめる(トドム)。そこにとまっていさせる。〈同義語〉→底。「邸余車兮方林=余ガ車ヲ方林ニ邸ム」〔→楚辞〕
 {動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。
《単語家族》
柢テイ(とまっている根もと)
{動}いたる。そこまでとどく。触れる。▽抵に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。左側の字(音テイ)は、ひくい、下底にとどくの意をふくむ。邸はそれを音符とし、邑を加えた字で、都に定置してとめおく諸侯のやしき。あるいは、低い平屋と解してもよい。
《単語家族》
柢テイ(とまっている根もと) 底(根が生えたように固着する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
底(根が生えたように固着する)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
閼 とどめる🔗⭐🔉
集 とどまる🔗⭐🔉
【集】
 12画 隹部 [三年]
区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57
《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う
《音読み》 シュウ(シフ)
12画 隹部 [三年]
区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57
《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う
《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)
/ジュウ(ジフ) 〈j
〈j 〉
《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり
《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい
《意味》
〉
《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり
《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい
《意味》
 {動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」
{動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕
 {動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕
{動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕
 {動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕
{動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕
 {名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」
{名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」
 {名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。
〔国〕
{名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。
〔国〕 つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。
つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。 あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。
《解字》
あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。
《解字》
 会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。
《単語家族》
雑(いろいろな色をあつめた衣)
会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。
《単語家族》
雑(いろいろな色をあつめた衣) 緝(繊維をあつめあわせて糸にする)
緝(繊維をあつめあわせて糸にする) 輯シュウ(まとめる)と同系。
《類義》
→斂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
輯シュウ(まとめる)と同系。
《類義》
→斂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 12画 隹部 [三年]
区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57
《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う
《音読み》 シュウ(シフ)
12画 隹部 [三年]
区点=2924 16進=3D38 シフトJIS=8F57
《常用音訓》シュウ/あつ…まる/あつ…める/つど…う
《音読み》 シュウ(シフ) /ジュウ(ジフ)
/ジュウ(ジフ) 〈j
〈j 〉
《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり
《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい
《意味》
〉
《訓読み》 あつまる/つどう(つどふ)/あつめる(あつむ)/とどまる/とどめる(とどむ)/いたる/なす/なる/つどい(つどひ)/あつまり
《名付け》 あい・い・ため・ち・ちか・つどい
《意味》
 {動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」
{動}あつまる。つどう(ツドフ)。あつめる(アツム)。たくさんの物や人が、ひと所に寄りあう。また、寄せあつめる。〈同義語〉→輯。〈対語〉→散。「集中」「集散」
 {動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕
{動}とどまる。とどめる(トドム)。ひと所にとまる。とめる。「翔而後集=翔リテシカル後ニ集マル」〔→論語〕「親集矢於其目=親ラ矢ヲソノ目ニ集ム」〔→左伝〕
 {動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕
{動}いたる。なす。なる。まとめる。ある状態に達する。また、物事をなしとげる。物事ができあがる。〈類義語〉→蒐シュウ・→就。「集成」「集事=事ヲ集ス」「我行既集=我ガ行既ニ集ル」〔→詩経〕
 {動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕
{動}なる。ひとつにまとまる。なつく。まとまって調和する。〈類義語〉→輯シュウ・→緝シュウ。「集睦シュウボク」「天下未集=天下イマダ集ラズ」〔→漢書〕
 {名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」
{名}詩文をあつめてつくった書物。また、そのシリーズ。▽四部(書籍の四つの分類)の一つとしても用いる。「詩集」「陶淵明集」
 {名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。
〔国〕
{名}常設でない市場イチバ。郷村にたつ市イチ。▽転じて、市のたつ村落の地名にそえることば。
〔国〕 つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。
つどい(ツドヒ)。あつまり。会合。集会。 あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。
《解字》
あつまり。たくさんのものがあつまったもの。また、あつまり方。
《解字》
 会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。
《単語家族》
雑(いろいろな色をあつめた衣)
会意。もとは「三つの隹(とり)+木」の会意文字で、たくさんの鳥が木の上にあつまることをあらわす。現在の字体は隹を二つ省略した略字体。
《単語家族》
雑(いろいろな色をあつめた衣) 緝(繊維をあつめあわせて糸にする)
緝(繊維をあつめあわせて糸にする) 輯シュウ(まとめる)と同系。
《類義》
→斂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
輯シュウ(まとめる)と同系。
《類義》
→斂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
頓 とどまる🔗⭐🔉
【頓】
 13画 頁部
区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA
《音読み》 トン
13画 頁部
区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA
《音読み》 トン
 〈d
〈d n・d
n・d 〉
《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに
《意味》
〉
《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに
《意味》
 トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」
トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」
 トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」
トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」
 トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」
トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」
 {名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。
{名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。
 {副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」
{副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」
 {単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」
{単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」
 「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。
《解字》
会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。
《単語家族》
敦トン(ずしんと重い)
「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。
《解字》
会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。
《単語家族》
敦トン(ずしんと重い) 屯チュン(ずしんと重い)
屯チュン(ずしんと重い) 豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 頁部
区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA
《音読み》 トン
13画 頁部
区点=3860 16進=465C シフトJIS=93DA
《音読み》 トン
 〈d
〈d n・d
n・d 〉
《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに
《意味》
〉
《訓読み》 ぬかずく(ぬかづく)/とどまる/とどめる(とどむ)/とみに
《意味》
 トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」
トンス{動}ぬかずく(ヌカヅク)。ずしんと頭を地につけておじぎをする。「頓首トンシュ」
 トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」
トンス{動}とどまる。とどめる(トドム)。ずしんと腰をおろす。腰をおろして動かない。とんとおく。とんととまる。「困頓コントン(疲れてとまり、動きがとれない)」「整頓セイトン(ととのえておちつける)」「頓躓トンチ」
 トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」
トンス{動}どんと重みをかける。とんと急に動く。とっさに変化する。「頓足=足ヲ頓ス」「頓仆トンボク」
 {名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。
{名・単位}腰をおちつける休み所や宿。転じて、休み所で一食するのを一頓という。〈類義語〉→屯トン/チュン。
 {副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」
{副}とみに。ずしんと。どんと。にわかに。「頓挫トンザ(ずしんとくじける)」「頓死トンシ(急死)」
 {単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」
{単位}〔俗〕ずしんと重くこたえる動作、とんととまる動作を数える単位。「罵一頓マアイイトン(いちどひどくののしる)」
 「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。
《解字》
会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。
《単語家族》
敦トン(ずしんと重い)
「冒頓ボクトツ」とは、匈奴キョウドの王の名。▽突と同音に読む。
《解字》
会意兼形声。屯トン・チュンは、草の芽が出ようとして、ずっしりと地中に根をはるさま。頓は「頁(あたま)+音符屯」で、ずしんと重く頭を地につけること。
《単語家族》
敦トン(ずしんと重い) 屯チュン(ずしんと重い)
屯チュン(ずしんと重い) 豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
豚トン(ずっしりと重いぶた)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
駐 とどまる🔗⭐🔉
【駐】
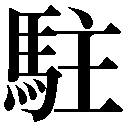 15画 馬部 [常用漢字]
区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
15画 馬部 [常用漢字]
区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
 {動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」
{動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」
 {動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕
《解字》
会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。
《単語家族》
主(じっととまってもえる灯火)
{動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕
《解字》
会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。
《単語家族》
主(じっととまってもえる灯火) 柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。
《熟語》
→熟語
柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。
《熟語》
→熟語
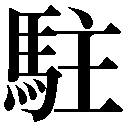 15画 馬部 [常用漢字]
区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
15画 馬部 [常用漢字]
区点=3583 16進=4373 シフトJIS=9293
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
〉
《訓読み》 とどまる/とどめる(とどむ)
《意味》
 {動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」
{動}とどまる。じっとそこにとどまる。〈類義語〉→住・→止。「駐在」
 {動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕
《解字》
会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。
《単語家族》
主(じっととまってもえる灯火)
{動}とどめる(トドム)。歩いてきた足をとめてたちどまる。また、乗って来た馬や車をとめておく。〈類義語〉→住・→止。「駐車」「行人駐足聴=行人足ヲ駐メテ聴ク」〔古楽府〕
《解字》
会意兼形声。「馬+音符主(=住。とまる)」。
《単語家族》
主(じっととまってもえる灯火) 柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。
《熟語》
→熟語
柱(ひとところにじっとたっているはしら)と同系。
《熟語》
→熟語
椴 とどまつ🔗⭐🔉
【椴】
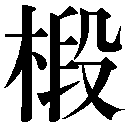 13画 木部
区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC
《音読み》 タン
13画 木部
区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC
《音読み》 タン /ダン
/ダン 《訓読み》 とどまつ
《意味》
《訓読み》 とどまつ
《意味》
 木の名。白楊ハクヨウに似た高木。
木の名。白楊ハクヨウに似た高木。 むくげ。木の名。
〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。
むくげ。木の名。
〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。
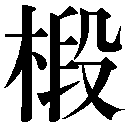 13画 木部
区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC
《音読み》 タン
13画 木部
区点=3846 16進=464E シフトJIS=93CC
《音読み》 タン /ダン
/ダン 《訓読み》 とどまつ
《意味》
《訓読み》 とどまつ
《意味》
 木の名。白楊ハクヨウに似た高木。
木の名。白楊ハクヨウに似た高木。 むくげ。木の名。
〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。
むくげ。木の名。
〔国〕とどまつ。木の名。松の一種。
驫 とどろき🔗⭐🔉
【驫】
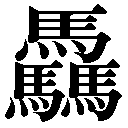 30画 馬部
区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A
《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ
30画 馬部
区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A
《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ /ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク
/ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク 《訓読み》 とどろき
《意味》
《訓読み》 とどろき
《意味》
 たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。
〔国〕とどろき。姓に使う。
たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。
〔国〕とどろき。姓に使う。
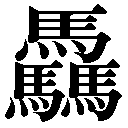 30画 馬部
区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A
《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ
30画 馬部
区点=8174 16進=716A シフトJIS=E98A
《音読み》 ヒュウ/シュウ/キュウ /ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク
/ヒュ/ヒュウ/ジュウ/ク 《訓読み》 とどろき
《意味》
《訓読み》 とどろき
《意味》
 たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。
〔国〕とどろき。姓に使う。
たくさんの馬。たくさんの馬の走るようす。
〔国〕とどろき。姓に使う。
漢字源に「とど」で始まるの検索結果 1-28。
 12画 水部
区点=6259 16進=5E5B シフトJIS=9FD9
《音読み》 テイ
12画 水部
区点=6259 16進=5E5B シフトJIS=9FD9
《音読み》 テイ 11画 糸部
区点=6907 16進=6527 シフトJIS=E346
《音読み》 サツ
11画 糸部
区点=6907 16進=6527 シフトJIS=E346
《音読み》 サツ ・z
・z 16画 門部
区点=7968 16進=6F64 シフトJIS=E884
《音読み》
16画 門部
区点=7968 16進=6F64 シフトJIS=E884
《音読み》  アツ
アツ エン
エン