複数辞典一括検索+![]()
![]()
冷 ひえる🔗⭐🔉
【冷】
 7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ
7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
 {動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
 {形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
 レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ
7画 冫部 [四年]
区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2
《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)
《名付け》 すずし
《意味》
 {動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕
 {形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕
 {形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」
 レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕
《解字》
会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令
《類義》
→寒
《異字同訓》
さます/さめる。→覚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
卑下 ヒカ🔗⭐🔉
【卑下】
 ヒゲ
ヒゲ  必要以上にへりくだる。
必要以上にへりくだる。 他人を見下す。いやしめる。さげすむ。
他人を見下す。いやしめる。さげすむ。 〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。
〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。 ヒカ 土地・地位などが低いさま。
ヒカ 土地・地位などが低いさま。
 ヒゲ
ヒゲ  必要以上にへりくだる。
必要以上にへりくだる。 他人を見下す。いやしめる。さげすむ。
他人を見下す。いやしめる。さげすむ。 〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。
〔国〕自分を実際より価値のないものと思いこむ。 ヒカ 土地・地位などが低いさま。
ヒカ 土地・地位などが低いさま。
卑汚 ヒオ🔗⭐🔉
【卑汚】
ヒオ  いやしみ汚す。人を見下げること。
いやしみ汚す。人を見下げること。 身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。
身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。
 いやしみ汚す。人を見下げること。
いやしみ汚す。人を見下げること。 身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。
身分がひくくいやしいこと。下賤ゲセン。
否運 ヒウン🔗⭐🔉
【否運】
ヒウン よくない巡りあわせ。不運。
彼我 ヒガ🔗⭐🔉
【彼我】
ヒガ 彼と我。相手がわと自分のがわ。
悲笳 ヒカ🔗⭐🔉
【悲笳】
ヒカ もの悲しい音色のする胡笳コカ(あし笛)。また、その音色。
悲運 ヒウン🔗⭐🔉
【悲運】
ヒウン〔国〕ふしあわせ。不運。
披閲 ヒエツ🔗⭐🔉
【披閲】
ヒエツ 書物・書類などをひらいて読む。『披見ヒケン・披読ヒドク・披覧ヒラン・披繙ヒハン』
日 ひ🔗⭐🔉
【日】
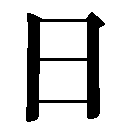 4画 日部 [一年]
区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA
《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ
《音読み》 ニチ
4画 日部 [一年]
区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA
《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ
《音読み》 ニチ /ジツ
/ジツ 〈r
〈r 〉
《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち
《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる
《意味》
〉
《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち
《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる
《意味》
 {名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕
{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕
 {名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕
{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕
 {名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」
{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」
 {単位}か。日数をかぞえることば。
{単位}か。日数をかぞえることば。
 {副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕
{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕
 {副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕
{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕
 {名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕
{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕
 {名}「日本」の略。
〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。
《解字》
{名}「日本」の略。
〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。
《解字》
 象形。太陽の姿を描いたもの。
《単語家族》
ニチ・ジツということばは、尼(近づく)
象形。太陽の姿を描いたもの。
《単語家族》
ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)
昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
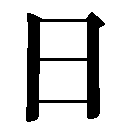 4画 日部 [一年]
区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA
《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ
《音読み》 ニチ
4画 日部 [一年]
区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA
《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ
《音読み》 ニチ /ジツ
/ジツ 〈r
〈r 〉
《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち
《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる
《意味》
〉
《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち
《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる
《意味》
 {名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕
{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕
 {名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕
{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕
 {名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」
{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」
 {単位}か。日数をかぞえることば。
{単位}か。日数をかぞえることば。
 {副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕
{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕
 {副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕
{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕
 {名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕
{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕
 {名}「日本」の略。
〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。
《解字》
{名}「日本」の略。
〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。
《解字》
 象形。太陽の姿を描いたもの。
《単語家族》
ニチ・ジツということばは、尼(近づく)
象形。太陽の姿を描いたもの。
《単語家族》
ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)
昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
暘 ひ🔗⭐🔉
【暘】
 13画 日部
区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
13画 日部
区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 ひ/ひので/はれ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひ/ひので/はれ
《意味》
 {名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」
{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」
 {動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。
{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。
 {名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。
《単語家族》
陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。
《熟語》
→下付・中付語
{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。
《単語家族》
陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。
《熟語》
→下付・中付語
 13画 日部
区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
13画 日部
区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 ひ/ひので/はれ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひ/ひので/はれ
《意味》
 {名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」
{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」
 {動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。
{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。
 {名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。
《単語家族》
陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。
《熟語》
→下付・中付語
{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。
《単語家族》
陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。
《熟語》
→下付・中付語
曦 ひ🔗⭐🔉
杼 ひ🔗⭐🔉
【杼】
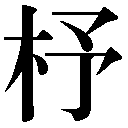 8画 木部
区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60
《音読み》
8画 木部
区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60
《音読み》  ジョ(ヂョ)
ジョ(ヂョ) /チョ
/チョ 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ジョ
ジョ /ショ
/ショ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 ひ
《意味》
〉
《訓読み》 ひ
《意味》
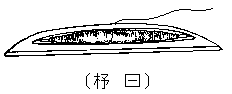
 {名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕
{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕
 {名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」
《解字》
会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予
《単語家族》
舒ジョ(のびのびする)
{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」
《解字》
会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予
《単語家族》
舒ジョ(のびのびする) 抒ジョ(のばす)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
抒ジョ(のばす)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
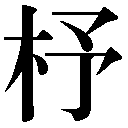 8画 木部
区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60
《音読み》
8画 木部
区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60
《音読み》  ジョ(ヂョ)
ジョ(ヂョ) /チョ
/チョ 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ジョ
ジョ /ショ
/ショ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 ひ
《意味》
〉
《訓読み》 ひ
《意味》
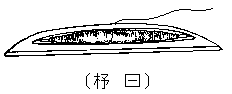
 {名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕
{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕
 {名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」
《解字》
会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予
《単語家族》
舒ジョ(のびのびする)
{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」
《解字》
会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予
《単語家族》
舒ジョ(のびのびする) 抒ジョ(のばす)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
抒ジョ(のばす)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
柊 ひいらぎ🔗⭐🔉
【柊】
 9画 木部 [人名漢字]
区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541
《音読み》 シュウ
9画 木部 [人名漢字]
区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541
《音読み》 シュウ /シュ
/シュ 《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)
《名付け》 ひいらぎ
《意味》
《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)
《名付け》 ひいらぎ
《意味》
 つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。
つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。
 「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。
〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符冬」。
「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。
〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符冬」。
 9画 木部 [人名漢字]
区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541
《音読み》 シュウ
9画 木部 [人名漢字]
区点=4102 16進=4922 シフトJIS=9541
《音読み》 シュウ /シュ
/シュ 《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)
《名付け》 ひいらぎ
《意味》
《訓読み》 ひいらぎ(ひひらぎ)
《名付け》 ひいらぎ
《意味》
 つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。
つち、さいづちなど、まるいこぶ状の握りを持つ道具を示す言葉に使う。
 「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。
〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符冬」。
「柊葉シュウヨウ」とは、中国南部産のしょうがの一種。葉が大きく、食物を包んでおくと長もちする。ちまきを包むのに用いる。
〔国〕ひいらぎ(ヒヒラギ)。もくせい科の常緑の小高木。葉は堅く、つやがあり、ふちは切れこみがあって、とげのようになっている。材は細工物などに用いる。
《解字》
会意兼形声。「木+音符冬」。
梭 ひ🔗⭐🔉
樋 ひ🔗⭐🔉
【樋】
 14画 木部
区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3
《音読み》 ツウ
14画 木部
区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3
《音読み》 ツウ /トウ
/トウ 《訓読み》 ひ
《意味》
{名}木の名。
〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。
《解字》
会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。
《訓読み》 ひ
《意味》
{名}木の名。
〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。
《解字》
会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。
 14画 木部
区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3
《音読み》 ツウ
14画 木部
区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3
《音読み》 ツウ /トウ
/トウ 《訓読み》 ひ
《意味》
{名}木の名。
〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。
《解字》
会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。
《訓読み》 ひ
《意味》
{名}木の名。
〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。
《解字》
会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。
比屋 ヒオク🔗⭐🔉
【比屋】
ヒオク  家並み。軒並み。
家並み。軒並み。 家を連ねる。
家を連ねる。
 家並み。軒並み。
家並み。軒並み。 家を連ねる。
家を連ねる。
毘益 ヒエキ🔗⭐🔉
【毘益】
ヒエキ そばからたすけて利益があるようにする。『毘補ビホ』
氷 ひ🔗⭐🔉
【氷】
 5画 水部 [三年]
区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558
【冰】異体字異体字
5画 水部 [三年]
区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558
【冰】異体字異体字
 6画 冫部
区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975
《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ
《音読み》 ヒョウ
6画 冫部
区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975
《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ
《音読み》 ヒョウ
 〈b
〈b ng〉
《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)
《名付け》 きよ・ひ
《意味》
ng〉
《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)
《名付け》 きよ・ひ
《意味》
 {名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕
{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕
 {動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」
{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」
 {形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」
{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」
 {形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」
《解字》
会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。
《単語家族》
馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける)
{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」
《解字》
会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。
《単語家族》
馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける) 崩(ばさりとくずれる)などと同系。
《異字同訓》
こおる/こおり。 →凍
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
崩(ばさりとくずれる)などと同系。
《異字同訓》
こおる/こおり。 →凍
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 5画 水部 [三年]
区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558
【冰】異体字異体字
5画 水部 [三年]
区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558
【冰】異体字異体字
 6画 冫部
区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975
《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ
《音読み》 ヒョウ
6画 冫部
区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975
《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ
《音読み》 ヒョウ
 〈b
〈b ng〉
《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)
《名付け》 きよ・ひ
《意味》
ng〉
《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)
《名付け》 きよ・ひ
《意味》
 {名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕
{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕
 {動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」
{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」
 {形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」
{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」
 {形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」
《解字》
会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。
《単語家族》
馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける)
{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」
《解字》
会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。
《単語家族》
馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける) 崩(ばさりとくずれる)などと同系。
《異字同訓》
こおる/こおり。 →凍
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
崩(ばさりとくずれる)などと同系。
《異字同訓》
こおる/こおり。 →凍
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
氷魚 ヒウオ🔗⭐🔉
【氷魚】
 ヒョウギョ
ヒョウギョ  氷の下にいる淡水魚。
氷の下にいる淡水魚。 魚の名。
魚の名。 ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。
ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。
 ヒョウギョ
ヒョウギョ  氷の下にいる淡水魚。
氷の下にいる淡水魚。 魚の名。
魚の名。 ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。
ヒウオ・ヒオ〔国〕あゆの稚魚。
火 ひ🔗⭐🔉
【火】
 4画 火部 [一年]
区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE
《常用音訓》カ/ひ/ほ
《音読み》 カ(ク
4画 火部 [一年]
区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE
《常用音訓》カ/ひ/ほ
《音読み》 カ(ク )
)
 /コ
/コ 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)
《名付け》 ひ・ほ
《意味》
〉
《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)
《名付け》 ひ・ほ
《意味》
 {名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕
{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕
 {名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕
{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕
 {名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。
{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。
 {名}火星。
{名}火星。
 {名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕
{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕
 {名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」
{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」
 {形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」
{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」
 {形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」
{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」
 {名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」
〔国〕か(ク
{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」
〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。
《解字》
)。七曜の一つ。火曜日。
《解字》
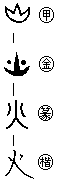 象形。火が燃えるさまを描いたもの。
《単語家族》
毀キ(形がなくなる)
象形。火が燃えるさまを描いたもの。
《単語家族》
毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。
《類義》
炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。
《異字同訓》
ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
燬(やけてなくなる)などと同系。
《類義》
炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。
《異字同訓》
ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 4画 火部 [一年]
区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE
《常用音訓》カ/ひ/ほ
《音読み》 カ(ク
4画 火部 [一年]
区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE
《常用音訓》カ/ひ/ほ
《音読み》 カ(ク )
)
 /コ
/コ 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)
《名付け》 ひ・ほ
《意味》
〉
《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)
《名付け》 ひ・ほ
《意味》
 {名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕
{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕
 {名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕
{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕
 {名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。
{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。
 {名}火星。
{名}火星。
 {名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕
{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕
 {名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」
{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」
 {形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」
{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」
 {形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」
{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」
 {名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」
〔国〕か(ク
{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」
〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。
《解字》
)。七曜の一つ。火曜日。
《解字》
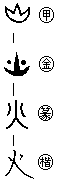 象形。火が燃えるさまを描いたもの。
《単語家族》
毀キ(形がなくなる)
象形。火が燃えるさまを描いたもの。
《単語家族》
毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。
《類義》
炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。
《異字同訓》
ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
燬(やけてなくなる)などと同系。
《類義》
炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。
《異字同訓》
ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
灯 ひ🔗⭐🔉
【灯】
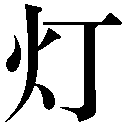 6画 火部 [四年]
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
【燈】旧字(A)人名に使える旧字
6画 火部 [四年]
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
【燈】旧字(A)人名に使える旧字
 16画 火部
区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395
【灯】旧字(B)旧字(B)
16画 火部
区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395
【灯】旧字(B)旧字(B)
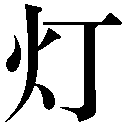 6画 火部
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
《常用音訓》トウ/ひ
《音読み》 (A)トウ
6画 火部
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
《常用音訓》トウ/ひ
《音読み》 (A)トウ
 /(B)チョウ(チャウ)
/(B)チョウ(チャウ) /テイ
/テイ /チン
/チン 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 ともしび/あかし/ひ
《意味》
(A)【燈】
ng〉
《訓読み》 ともしび/あかし/ひ
《意味》
(A)【燈】 {名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕
{名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕
 {名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」
(B)【灯】
{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」
(B)【灯】 {名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。
{名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。
 {名}「燈」と同じ。
《解字》
(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。
(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。
《異字同訓》
ひ。→火
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}「燈」と同じ。
《解字》
(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。
(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。
《異字同訓》
ひ。→火
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
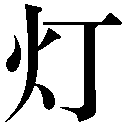 6画 火部 [四年]
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
【燈】旧字(A)人名に使える旧字
6画 火部 [四年]
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
【燈】旧字(A)人名に使える旧字
 16画 火部
区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395
【灯】旧字(B)旧字(B)
16画 火部
区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395
【灯】旧字(B)旧字(B)
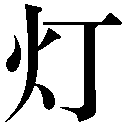 6画 火部
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
《常用音訓》トウ/ひ
《音読み》 (A)トウ
6画 火部
区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394
《常用音訓》トウ/ひ
《音読み》 (A)トウ
 /(B)チョウ(チャウ)
/(B)チョウ(チャウ) /テイ
/テイ /チン
/チン 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 ともしび/あかし/ひ
《意味》
(A)【燈】
ng〉
《訓読み》 ともしび/あかし/ひ
《意味》
(A)【燈】 {名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕
{名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕
 {名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」
(B)【灯】
{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」
(B)【灯】 {名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。
{名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。
 {名}「燈」と同じ。
《解字》
(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。
(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。
《異字同訓》
ひ。→火
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}「燈」と同じ。
《解字》
(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。
(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。
《異字同訓》
ひ。→火
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
燧 ひうち🔗⭐🔉
【燧】
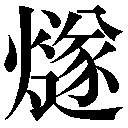 17画 火部
区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C
《音読み》 スイ
17画 火部
区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C
《音読み》 スイ /ズイ
/ズイ 〈su
〈su 〉
《訓読み》 ひうち
《意味》
〉
《訓読み》 ひうち
《意味》
 {名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」
{名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」
 {名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」
《解字》
会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂
《単語家族》
邃スイ(奥深い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」
《解字》
会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂
《単語家族》
邃スイ(奥深い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
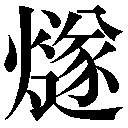 17画 火部
区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C
《音読み》 スイ
17画 火部
区点=6392 16進=5F7C シフトJIS=E09C
《音読み》 スイ /ズイ
/ズイ 〈su
〈su 〉
《訓読み》 ひうち
《意味》
〉
《訓読み》 ひうち
《意味》
 {名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」
{名}ひうち。火を得るために用いる道具。「石燧セキスイ(火打ち石。石と金とを打ちあわせて発火させるもの)」「木燧モクスイ(木をきりでもんで発火させるもの)」「鑽燧=燧ヲ鑽ツ」
 {名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」
《解字》
会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂
《単語家族》
邃スイ(奥深い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}のろし。〈類義語〉→烽ホウ。「燧烽スイホウ」
《解字》
会意兼形声。遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+音符遂」で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること。→遂
《単語家族》
邃スイ(奥深い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
碑陰 ヒイン🔗⭐🔉
【碑陰】
ヒイン  石碑の裏。〈対語〉碑表。
石碑の裏。〈対語〉碑表。 石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。
石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。
 石碑の裏。〈対語〉碑表。
石碑の裏。〈対語〉碑表。 石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。
石碑の背にきざみつけた文章。また、その文体。
秀 ひいでる🔗⭐🔉
【秀】
 7画 禾部 [常用漢字]
区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47
《常用音訓》シュウ/ひい…でる
《音読み》 シュウ(シウ)
7画 禾部 [常用漢字]
区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47
《常用音訓》シュウ/ひい…でる
《音読み》 シュウ(シウ) /シュ
/シュ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 ひいでる(ひいづ)
《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし
《意味》
〉
《訓読み》 ひいでる(ひいづ)
《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし
《意味》
 シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕
シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕
 {動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」
《解字》
{動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」
《解字》
 会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。
《単語家族》
修(すらりと形の整った)
会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。
《単語家族》
修(すらりと形の整った) 脩シュウ(細長い干し肉)
脩シュウ(細長い干し肉) 蕭ショウ(ほそい)などと同系。
《類義》
優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
蕭ショウ(ほそい)などと同系。
《類義》
優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 禾部 [常用漢字]
区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47
《常用音訓》シュウ/ひい…でる
《音読み》 シュウ(シウ)
7画 禾部 [常用漢字]
区点=2908 16進=3D28 シフトJIS=8F47
《常用音訓》シュウ/ひい…でる
《音読み》 シュウ(シウ) /シュ
/シュ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 ひいでる(ひいづ)
《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし
《意味》
〉
《訓読み》 ひいでる(ひいづ)
《名付け》 さかえ・しげる・すえ・ひいず・ひで・ひでし・ほ・ほず・ほら・みつ・みのる・よし
《意味》
 シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕
シュウス{動・名}すらりと高く穂や花になる芽が出る。また、すらりとぬきんでた穂。「秀而不実者、有矣夫=秀シテ実ラザル者、有ルカナ」〔→論語〕
 {動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」
《解字》
{動・形・名}ひいでる(ヒイヅ)。すらりと高く出る。また、ほかの人よりすぐれる。目だってすぐれたさま。すらりとして美しいさま。また、すぐれたもの。▽訓の「ひいづ」は「ひ(穂)+いづ(出)」から。「秀逸」「秀才」「眉目秀麗ビモクシュウレイ」
《解字》
 会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。
《単語家族》
修(すらりと形の整った)
会意。「禾(禾本科の植物)+乃(なよなよ)」で、なよなよした稲の穂がすらりと伸びることを示す。
《単語家族》
修(すらりと形の整った) 脩シュウ(細長い干し肉)
脩シュウ(細長い干し肉) 蕭ショウ(ほそい)などと同系。
《類義》
優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
蕭ショウ(ほそい)などと同系。
《類義》
優は、しなやかなしぐさをする人で、エレガントなこと。俊は、すらりとひいでた人で、スマートなこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
秘蘊 ヒウン🔗⭐🔉
【秘蘊】
ヒウン 学芸などの奥深い要点・奥義。『秘奥ヒオウ』
稗 ひえ🔗⭐🔉
【稗】
 14画 禾部
区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542
《音読み》 ハイ
14画 禾部
区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542
《音読み》 ハイ /ベ
/ベ 〈b
〈b i〉
《訓読み》 ひえ
《意味》
i〉
《訓読み》 ひえ
《意味》
 {名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。
{名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。
 {形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」
《解字》
会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。
《単語家族》
婢ヒ(小者の女)と同系。
《熟語》
→熟語
{形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」
《解字》
会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。
《単語家族》
婢ヒ(小者の女)と同系。
《熟語》
→熟語
 14画 禾部
区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542
《音読み》 ハイ
14画 禾部
区点=4103 16進=4923 シフトJIS=9542
《音読み》 ハイ /ベ
/ベ 〈b
〈b i〉
《訓読み》 ひえ
《意味》
i〉
《訓読み》 ひえ
《意味》
 {名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。
{名}ひえ。穀物の一種。稲科の一年生植物。稲に比べて、背が低く粒が小さい。
 {形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」
《解字》
会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。
《単語家族》
婢ヒ(小者の女)と同系。
《熟語》
→熟語
{形・名}こまかいさま。また、ひえのように小さいもの。「稗官ハイカン」「稗史ハイシ」
《解字》
会意兼形声。「禾(いね)+音符卑(せが低い、小さい)」。
《単語家族》
婢ヒ(小者の女)と同系。
《熟語》
→熟語
緋縅 ヒオドシ🔗⭐🔉
【緋縅】
ヒオドシ〔国〕緋色のなめし革で作った縅オドシ(よろいのさねを、糸・革でつづりあわせたもの)。
被衣 ヒイ🔗⭐🔉
【被衣】
 ヒイ
ヒイ  きもの。
きもの。 きものをはおっただけで帯をしないこと。
きものをはおっただけで帯をしないこと。 カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。
カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。
 ヒイ
ヒイ  きもの。
きもの。 きものをはおっただけで帯をしないこと。
きものをはおっただけで帯をしないこと。 カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。
カズキ〔国〕昔、女が外出するとき、顔をかくすため、頭からかぶったおおい。
裨益 ヒエキ🔗⭐🔉
【裨益】
ヒエキ おぎない、役だつ。たすけとなって役だつこと。
費隠 ヒイン🔗⭐🔉
【費隠】
ヒイン 君子が踏み行うべき道は骨が折れるが、人目にはつきにくいこと。▽一説に、費隠フツインと読み、世の中が正道にもとっていれば、隠退するの意とする。「中庸」の「君子之道、費而隠=君子ノ道ハ費ニシテシカモ隠ナリ」から。
跛倚 ヒイ🔗⭐🔉
【跛倚】
ヒイ  片足でたって物によりかかる。
片足でたって物によりかかる。 物事が一方に片よっていること。
物事が一方に片よっていること。
 片足でたって物によりかかる。
片足でたって物によりかかる。 物事が一方に片よっていること。
物事が一方に片よっていること。
僻遠 ヒエン🔗⭐🔉
【辟遠】
 ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。
ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。 ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。
ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。
 ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。
ヘキエン =僻遠。土地などが、中央からかたよっていて遠い。 ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。
ヒエン =避遠。しりぞけて遠ざける。さけて遠ざかる。
避遠 ヒエン🔗⭐🔉
【避遠】
ヒエン  わきに避けて遠ざかる。
わきに避けて遠ざかる。 しりぞけて遠ざける。
しりぞけて遠ざける。
 わきに避けて遠ざかる。
わきに避けて遠ざかる。 しりぞけて遠ざける。
しりぞけて遠ざける。
鄙穢 ヒアイ🔗⭐🔉
【鄙穢】
ヒアイ・ヒワイ ことばや文章がいやしくて下品である。
陽 ひ🔗⭐🔉
【陽】
 12画 阜部 [三年]
区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
12画 阜部 [三年]
区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)
《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)
《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や
《意味》
 {名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。
{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。
 {名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」
{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」
 {名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕
{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕
 ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕
ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕
 {名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」
{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」
 {名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」
{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」
 {動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」
{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」
 {名}男の生殖器。「陽道」
{名}男の生殖器。「陽道」
 ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。
《単語家族》
昌(明るい)
ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。
《単語家族》
昌(明るい) 彰(明るい、あざやか)
彰(明るい、あざやか) 章(あざやかで、目だつ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
章(あざやかで、目だつ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 12画 阜部 [三年]
区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
12画 阜部 [三年]
区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ(ヤウ)
 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)
《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)
《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や
《意味》
 {名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。
{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。
 {名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」
{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」
 {名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕
{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕
 ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕
ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕
 {名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」
{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」
 {名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」
{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」
 {動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」
{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」
 {名}男の生殖器。「陽道」
{名}男の生殖器。「陽道」
 ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。
《単語家族》
昌(明るい)
ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。
《単語家族》
昌(明るい) 彰(明るい、あざやか)
彰(明るい、あざやか) 章(あざやかで、目だつ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
章(あざやかで、目だつ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
非意 ヒイ🔗⭐🔉
【非意】
ヒイ 思いもよらず。だしぬけに。心ならずも。不意。考えてもいなかったことがおこったときのことば。
非違 ヒイ🔗⭐🔉
【非違】
ヒイ 法やおきてにそむくこと。
飛宇 ヒウ🔗⭐🔉
【飛宇】
ヒウ 屋根のすそのほうがそりあがっているもの。『飛檐ヒエン・飛軒ヒケン』
飛舸 ヒカ🔗⭐🔉
【飛舟】
ヒシュウ とぶようにはやい舟・速力のはやい舟。『飛舸ヒカ』
飛花 ヒカ🔗⭐🔉
【飛花】
ヒカ 散る花。『飛華ヒカ』
飛燕 ヒエン🔗⭐🔉
【飛燕】
ヒエン  とぶつばめ。
とぶつばめ。 前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。
前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。
 とぶつばめ。
とぶつばめ。 前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。
前漢の成帝の趙チョウ皇后の号。舞がじょうずであったという。「趙飛燕」とも。
漢字源に「ひ」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む
 20画 日部
区点=5907 16進=5B27 シフトJIS=9E46
《音読み》 ギ
20画 日部
区点=5907 16進=5B27 シフトJIS=9E46
《音読み》 ギ /キ
/キ 11画 木部
区点=5972 16進=5B68 シフトJIS=9E88
《音読み》 サ
11画 木部
区点=5972 16進=5B68 シフトJIS=9E88
《音読み》 サ 〉
《訓読み》 ひ
《意味》
{名}ひ。機織りの道具。横糸を通す管のついているもの。▽細長い0型をしていて、その中に糸巻きをおさめる。
《解字》
会意「木+すらりと細長い」で、すらりと細長い木製のひ。
《熟語》
〉
《訓読み》 ひ
《意味》
{名}ひ。機織りの道具。横糸を通す管のついているもの。▽細長い0型をしていて、その中に糸巻きをおさめる。
《解字》
会意「木+すらりと細長い」で、すらりと細長い木製のひ。
《熟語》