複数辞典一括検索+![]()
![]()
依託 イタク🔗⭐🔉
【依託】
イタク  責任や原因をある物のせいにする。かこつける。
責任や原因をある物のせいにする。かこつける。 たよる。
たよる。 〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。
〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。
 責任や原因をある物のせいにする。かこつける。
責任や原因をある物のせいにする。かこつける。 たよる。
たよる。 〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。
〔国〕ほかの人に物事の処理や世話をすっかり任せて頼むこと。
傷 いたむ🔗⭐🔉
【傷】
 13画 人部 [六年]
区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D
《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず
《音読み》 ショウ(シャウ)
13画 人部 [六年]
区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D
《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず
《音読み》 ショウ(シャウ)
 〈sh
〈sh ng〉
《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ
《意味》
ng〉
《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ
《意味》
 {名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」
{名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」
 {動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕
{動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕
 {動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」
{動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」
 {動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。
《単語家族》
當(=当。あたる)と同系。
《類義》
創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。
《異字同訓》
いたむ/いためる。→痛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。
《単語家族》
當(=当。あたる)と同系。
《類義》
創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。
《異字同訓》
いたむ/いためる。→痛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 人部 [六年]
区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D
《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず
《音読み》 ショウ(シャウ)
13画 人部 [六年]
区点=2993 16進=3D7D シフトJIS=8F9D
《常用音訓》ショウ/いた…む/いた…める/きず
《音読み》 ショウ(シャウ)
 〈sh
〈sh ng〉
《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ
《意味》
ng〉
《訓読み》 いためる/きず/きずつく/きずつける(きずつく)/やぶる/いたむ
《意味》
 {名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」
{名}きず。皮膚や肉をそこなうこと。また、その部分。「負傷」「創傷(きりきず)」「火傷(やけど)」
 {動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕
{動}きずつく。きずつける(キズツク)。けがをする。また、けがをさせる。「傷害」「傷人乎=人ヲ傷ツケタルカ」〔→論語〕
 {動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」
{動}やぶる。ぶちあたってきずをつける。「中傷(悪口をいって人をきずつける)」
 {動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。
《単語家族》
當(=当。あたる)と同系。
《類義》
創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。
《異字同訓》
いたむ/いためる。→痛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}いたむ。心配する。「傷心(つらく思う)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ心ヲ傷マシムル色」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。昜ヨウは、太陽の陽(暘)の原字。傷は「人+音符殤ショウの略体」。傷・殤ともに昜が音をあらわすが、昜(太陽)とは関係はない。強く物にぶちあたってきずつくこと。
《単語家族》
當(=当。あたる)と同系。
《類義》
創ソウは、切りきず。疵シは、ぎざぎざのかすりきず。
《異字同訓》
いたむ/いためる。→痛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
効 いたす🔗⭐🔉
【効】
 8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
 10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ)
10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)
/ギョウ(ゲウ) 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
 {名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
 コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
 {動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
 {動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
 10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ)
10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)
/ギョウ(ゲウ) 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
 {名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
 コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
 {動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
 {動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
委托 イタク🔗⭐🔉
【委託】
イタク =委托。ゆだねまかせる。『委嘱イショク』
巓 いただき🔗⭐🔉
徒 いたずらに🔗⭐🔉
【徒】
 10画 彳部 [四年]
区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B
《常用音訓》ト
《音読み》 ト
10画 彳部 [四年]
区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B
《常用音訓》ト
《音読み》 ト /ズ(ヅ)/ド
/ズ(ヅ)/ド 〈t
〈t 〉
《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ
《名付け》 かち・ただ・とも
《意味》
〉
《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ
《名付け》 かち・ただ・とも
《意味》
 {動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕
{動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕
 {名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕
{名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕
 {名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」
{名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」
 {名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕
{名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕
 {形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」
{形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」
 {副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」
{副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」
 {副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕
{副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕
 「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕
《解字》
「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕
《解字》
 形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。
《単語家族》
渡ト(水を一歩一歩わたる)
形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。
《単語家族》
渡ト(水を一歩一歩わたる) 度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 彳部 [四年]
区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B
《常用音訓》ト
《音読み》 ト
10画 彳部 [四年]
区点=3744 16進=454C シフトJIS=936B
《常用音訓》ト
《音読み》 ト /ズ(ヅ)/ド
/ズ(ヅ)/ド 〈t
〈t 〉
《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ
《名付け》 かち・ただ・とも
《意味》
〉
《訓読み》 かちありきする(かちありきす)/かち/ともがら/むなしい(むなし)/いたずらに(いたづらに)/ただ
《名付け》 かち・ただ・とも
《意味》
 {動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕
{動}かちありきする(カチアリキス)。一歩一歩と歩く。「徒歩」「徒渉トショウ(歩いて川を渡る)」「舎車而徒=車ヲ舎テテ徒ス」〔→易経〕
 {名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕
{名}かち。歩いて行く兵隊。歩兵。足軽。〈対語〉→騎(馬に乗った兵)。「公徒三万(歩兵三万)」〔→詩経〕
 {名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」
{名}ともがら。下級の仲間。▽数多い歩兵の意から。「衆徒」「徒党」
 {名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕
{名}門下のでし。「徒弟」「非吾徒也=吾ガ徒ニアラザルナリ」〔→論語〕
 {形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」
{形}むなしい(ムナシ)。何も物を持たないさま。▽車も馬もない意から。「徒搏トハク(素手でうちかかる、すもう)」
 {副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」
{副}いたずらに(イタヅラニ)。何も得ることなしに。むだに。「徒労」「徒自苦耳=イタヅラニミヅカラ苦シムノミ」
 {副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕
{副}ただ。…だけ。「徒善不足以為政=タダ善ナルノミナラバ、モッテ政ヲ為スニ足ラズ」〔→孟子〕
 「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕
《解字》
「不徒…タダニ…ノミナラズ」「非徒…タダニ…ノミニアラズ」とは、単にAだけでなく(またBである)との意に用いることば。「非徒無益=タダニ益ナキノミニアラズ」〔→孟子〕
《解字》
 形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。
《単語家族》
渡ト(水を一歩一歩わたる)
形声。「止(あし)+彳(いく)+音符土」で、陸地を一歩一歩とあゆむことで、ポーズをおいて、一つ一つ進む意を含む。
《単語家族》
渡ト(水を一歩一歩わたる) 度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
度ド(手尺で一さし一さしとわたってはかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
徒事 イタズラゴト🔗⭐🔉
【徒事】
 トジ 役にたたないこと。
トジ 役にたたないこと。 イタズラゴト〔国〕
イタズラゴト〔国〕 役にたたないこと。
役にたたないこと。 みだらなこと。
みだらなこと。
 トジ 役にたたないこと。
トジ 役にたたないこと。 イタズラゴト〔国〕
イタズラゴト〔国〕 役にたたないこと。
役にたたないこと。 みだらなこと。
みだらなこと。
徒爾 イタヅラニ🔗⭐🔉
【徒爾】
トジ・イタヅラニ むだに。無意味に。
慇 いたむ🔗⭐🔉
憖 いたむ🔗⭐🔉
【憖】
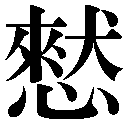 16画 心部
区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9
《音読み》 ギン
16画 心部
区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9
《音読み》 ギン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ
《意味》
 {動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕
{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕
 ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕
ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕
 {動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。
{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。
 {動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」
《解字》
会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」
《解字》
会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
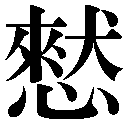 16画 心部
区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9
《音読み》 ギン
16画 心部
区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9
《音読み》 ギン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ
《意味》
 {動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕
{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕
 ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕
ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕
 {動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。
{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。
 {動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」
《解字》
会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」
《解字》
会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
怛 いたむ🔗⭐🔉
恫 いたむ🔗⭐🔉
惨 いたむ🔗⭐🔉
【惨】
 11画
11画  部 [常用漢字]
区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53
【慘】旧字旧字
部 [常用漢字]
区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53
【慘】旧字旧字
 14画
14画  部
区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC
《常用音訓》サン/ザン/みじ…め
《音読み》 サン(サム)
部
区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC
《常用音訓》サン/ザン/みじ…め
《音読み》 サン(サム) /ザン
/ザン /ソン(ソム)
/ソン(ソム) 〈c
〈c n〉
《訓読み》 みじめ/いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 みじめ/いたむ
《意味》
 サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕
サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕
 {動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕
《解字》
形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。
《単語家族》
浸シン(しみこむ)
{動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕
《解字》
形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。
《単語家族》
浸シン(しみこむ) 滲シン(しみこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
滲シン(しみこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画
11画  部 [常用漢字]
区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53
【慘】旧字旧字
部 [常用漢字]
区点=2720 16進=3B34 シフトJIS=8E53
【慘】旧字旧字
 14画
14画  部
区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC
《常用音訓》サン/ザン/みじ…め
《音読み》 サン(サム)
部
区点=5646 16進=584E シフトJIS=9CCC
《常用音訓》サン/ザン/みじ…め
《音読み》 サン(サム) /ザン
/ザン /ソン(ソム)
/ソン(ソム) 〈c
〈c n〉
《訓読み》 みじめ/いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 みじめ/いたむ
《意味》
 サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕
サンタリ{形}みじめでいたいたしい。むごい。心にしみ入るようにつらい。じめじめと気がめいるような。「悲惨」「酔不成歓惨将別=酔ウテ歓ヲ成サズ、惨トシテマサニ別レントス」〔→白居易〕
 {動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕
《解字》
形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。
《単語家族》
浸シン(しみこむ)
{動}いたむ。つらい思いをする。心の底にしみいるようなつらい思いをする。「傷心惨目=心ヲ傷メ、目ヲ惨マシム」〔→李華〕
《解字》
形声。「心+音符參サン」で、心の中へ深くしみこんでつらい思いを与えること。
《単語家族》
浸シン(しみこむ) 滲シン(しみこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
滲シン(しみこむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
悽 いたむ🔗⭐🔉
悵 いたむ🔗⭐🔉
悼 いたむ🔗⭐🔉
惻 いたむ🔗⭐🔉
愴 いたむ🔗⭐🔉
戴 いただく🔗⭐🔉
【戴】
 17画 戈部
区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5
《音読み》 タイ
17画 戈部
区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5
《音読み》 タイ
 〈d
〈d i〉
《訓読み》 いただく
《意味》
i〉
《訓読み》 いただく
《意味》
 {動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕
{動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕
 {動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕
{動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕
 「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。
〔国〕
「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。
〔国〕 いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。
いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。 いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。
いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。 いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」
《解字》
形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。
《単語家族》
待(じっと止まる)
いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」
《解字》
形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。
《単語家族》
待(じっと止まる) 臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 17画 戈部
区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5
《音読み》 タイ
17画 戈部
区点=3455 16進=4257 シフトJIS=91D5
《音読み》 タイ
 〈d
〈d i〉
《訓読み》 いただく
《意味》
i〉
《訓読み》 いただく
《意味》
 {動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕
{動}いただく。じっと頭の上にのせておく。「戴冠タイカン」「頌白者不負戴於道路矣=頌白ノ者、道路ニ負戴セズ」〔→孟子〕「戴歩揺=歩揺ヲ戴ク」〔陳鴻〕
 {動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕
{動}いただく。君主として、上におしいただく。また、君主からありがたくもらう。「愛戴アイタイ」「四海之内、咸戴帝舜之功=四海ノ内、ミナ帝舜ノ功ヲ戴ク」〔→史記〕
 「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。
〔国〕
「頂戴テイタイ」とは、頭上におしいただく。また、その冠。
〔国〕 いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。
いただく。他人、特に、目上の人から物品をありがたくもらう。 いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。
いただく。「飲む」「食う」をへりくだっていうことば。 いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」
《解字》
形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。
《単語家族》
待(じっと止まる)
いただく。「…してもらう」をへりくだっていうことば。「話していただく」
《解字》
形声。異を除いた部分は、在ザイ(切りとめる)の原字で切り止めること。戴はそれに異を音符としてそえた字で、じっと頭の頂上に止めおくこと。異の古い音は、タイの音をあらわすことができた。
《単語家族》
待(じっと止まる) 臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
臺(=台。じっと建物をのせる高台)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
抵 いたす🔗⭐🔉
【抵】
 8画
8画  部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
 {動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
 {動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
 {動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
 {動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
 「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
 {動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く)
{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画
8画  部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ
部 [常用漢字]
区点=3681 16進=4471 シフトJIS=92EF
《常用音訓》テイ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたす/あたる/あてる(あつ)
《名付け》 あつ・やす・ゆき
《意味》
 {動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
{動}いたる。そこまでぴたりと届く。そこまで行く。〈類義語〉→至。「抵至(いたる)」「抵昭王幸姫=昭王ノ幸姫ニ抵ル」〔→史記〕
 {動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
{動}いたす。ぬきさしならぬよう押しつける。〈類義語〉→致。「傷人及盗、抵罪=人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ、罪ニ抵サン」〔→史記〕
 {動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
{動}あたる。あてる(アツ)。それにぴたりとあたる。そこまで届いてくっつく。つかえる。「抵法=法ニ抵ル」「抵抗」
 {動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
{動}あたる。値うちがそれだけに相当する。〈類義語〉→当・→値(あたる)。「抵当」「家書抵万金=家書、万金ニ抵ル」〔→杜甫〕
 「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
「大抵タイテイ」とは、およそそれに該当する意から、ほぼという意の副詞に用いることば。
 {動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く)
{動}うつ。「抵掌而談=掌ヲ抵チテ談ズ」〔→国策〕
《解字》
形声。右側の字(ひくい)は、音を示すだけで、意味には関係がない。抵は間隙カンゲキなく届いて、ぬきさしならないこと。
《単語家族》
至シ(いたる、ぴたりと届く) 致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
致チ(いたす、そこまでぴたりと届ける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枉 いたずらに🔗⭐🔉
【枉】
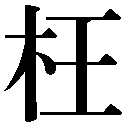 8画 木部
区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D
《音読み》 オウ(ワウ)
8画 木部
区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D
《音読み》 オウ(ワウ)
 〈w
〈w ng〉
《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)
《意味》
ng〉
《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)
《意味》
 {動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕
{動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕
 {形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」
{形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」
 {動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」
{動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」
 {副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」
《解字》
形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。
《単語家族》
汚(
{副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」
《解字》
形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。
《単語家族》
汚( 型にくぼんだ水たまり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
型にくぼんだ水たまり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
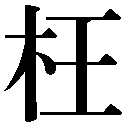 8画 木部
区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D
《音読み》 オウ(ワウ)
8画 木部
区点=5930 16進=5B3E シフトJIS=9E5D
《音読み》 オウ(ワウ)
 〈w
〈w ng〉
《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)
《意味》
ng〉
《訓読み》 まげる(まぐ)/まがる/まげて/いたずらに(いたづらに)
《意味》
 {動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕
{動}まげる(マグ)。まがる。まっすぐな線や面をゆるやかな曲線をなすようにおしまげる。また、道理をおしまげる。〈対語〉→直。「枉道オウドウ(道理をおしまげる)」「挙直、錯諸枉=直キヲ挙ゲテ、諸ヲ枉レルニ錯ク」〔→論語〕
 {形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」
{形}道理をゆがめた。また、罪をむりやりにおしつけた。〈類義語〉→冤エン。「枉死オウシ」「冤枉エンオウ(無実)」
 {動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」
{動}まげて。面子メンツをむりにおしまげて…してくださった、との意をあらわすていねいなことば。「枉顧オウコ・マゲテカエリミル(わざわざ立ち寄ってくださる)」「枉駕オウガ」
 {副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」
《解字》
形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。
《単語家族》
汚(
{副}いたずらに(イタヅラニ)。むりをして。役にもたたないのに。「枉費精神=枉ラニ精神ヲ費ヤス」
《解字》
形声。「木+音符王」。王(おうさま)の原義とは関係がない。
《単語家族》
汚( 型にくぼんだ水たまり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
型にくぼんだ水たまり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
板 いた🔗⭐🔉
【板】
 8画 木部 [三年]
区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2
《常用音訓》ハン/バン/いた
《音読み》 ハン
8画 木部 [三年]
区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2
《常用音訓》ハン/バン/いた
《音読み》 ハン /バン
/バン /ヘン
/ヘン 〈b
〈b n〉
《訓読み》 いた
《名付け》 いた
《意味》
n〉
《訓読み》 いた
《名付け》 いた
《意味》
 {名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」
{名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」
 {名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」
{名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」
 {名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。
{名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。
 {名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」
{名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」
 {名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」
{名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」
 (形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」
(形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」
 「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。
「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。
 {単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。
《解字》
会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反
《単語家族》
版ハン(平らないた)
{単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。
《解字》
会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反
《単語家族》
版ハン(平らないた) 番ハン(平らにひらく)
番ハン(平らにひらく) 盤(平らなさら)
盤(平らなさら) 繙ハン(平らに開く)
繙ハン(平らに開く) 返(そりかえる、はねもどる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
返(そりかえる、はねもどる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 8画 木部 [三年]
区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2
《常用音訓》ハン/バン/いた
《音読み》 ハン
8画 木部 [三年]
区点=4036 16進=4844 シフトJIS=94C2
《常用音訓》ハン/バン/いた
《音読み》 ハン /バン
/バン /ヘン
/ヘン 〈b
〈b n〉
《訓読み》 いた
《名付け》 いた
《意味》
n〉
《訓読み》 いた
《名付け》 いた
《意味》
 {名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」
{名}いた。平らで薄い木のいた。転じて、いた状の平らで薄い形のもの。〈同義語〉→版。「鉄板」
 {名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」
{名}刷るための字や絵をほりこんだいた。版木。〈同義語〉→版。「原板(=原版)」「板画(=版画)」
 {名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。
{名}文字を書いたいた。▽昔は、木版に詔勅や告示を書いた。
 {名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」
{名}歌曲の間びょうしのこと。▽いたをうって、拍子をとることから。「板眼(間びょうし)」
 {名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」
{名・単位}〔俗〕刑具に用いるむち。また、むち打つ回数をかぞえる単位。「小板子(小さいむち)」
 (形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」
(形)いたのように張ったまま動かないさま。「呆板タイパン(融通がきかない)」
 「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。
「板板ハンハン」とは、反対にそりかえるさま。道理にそむくさま。
 {単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。
《解字》
会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反
《単語家族》
版ハン(平らないた)
{単位}長さの単位。一板は十尺、または八尺。▽周代の一尺は二二・五センチメートル。長い板をはめて土壁を築いたため、長さをはかる単位として用いる。
《解字》
会意兼形声。反は「厂(たれた布)+又(手)」からなり、手で布をそり返らせることを示す。板は「木+音符反」で、そり返って張った木のいた。→反
《単語家族》
版ハン(平らないた) 番ハン(平らにひらく)
番ハン(平らにひらく) 盤(平らなさら)
盤(平らなさら) 繙ハン(平らに開く)
繙ハン(平らに開く) 返(そりかえる、はねもどる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
返(そりかえる、はねもどる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
格 いたす🔗⭐🔉
【格】
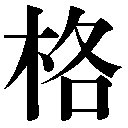 10画 木部 [五年]
区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69
《常用音訓》カク/コウ
《音読み》 カク
10画 木部 [五年]
区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69
《常用音訓》カク/コウ
《音読み》 カク /コウ(カウ)
/コウ(カウ) /キャク
/キャク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 いたる/いたす/ただす
《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたす/ただす
《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ
《意味》
 {名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」
{名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」
 {名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕
{名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕
 {名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」
{名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」
 {動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」
{動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」
 {動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」
{動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」
 {動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕
{動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕
 {動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕
{動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕
 {名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」
〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」
《解字》
会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各
《単語家族》
客(一軒の家につかえて止まった人)
{名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」
〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」
《解字》
会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各
《単語家族》
客(一軒の家につかえて止まった人) 閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石)
閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石) 擱カク(つかえて止まる)
擱カク(つかえて止まる) 挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
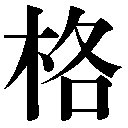 10画 木部 [五年]
区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69
《常用音訓》カク/コウ
《音読み》 カク
10画 木部 [五年]
区点=1942 16進=334A シフトJIS=8A69
《常用音訓》カク/コウ
《音読み》 カク /コウ(カウ)
/コウ(カウ) /キャク
/キャク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 いたる/いたす/ただす
《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたす/ただす
《名付け》 いたる・きわめ・ただ・ただし・ただす・つとむ・のり・まさ
《意味》
 {名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」
{名}こつんとつかえるかたいしんや、しん棒。人間が、しんにもつ本質。「人格」「骨格」
 {名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕
{名}こつんとつかえるかたいかどや、わく。物事を制限するきまり。法則。「格式」「及格(=合格)」「言有物、而行有格也=言ニ物有リテ、行ニ格有ルナリ」〔→礼記〕
 {名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」
{名}かたい材料でつくった、物を止めておく道具。また、四角くくぎったますがた。「書格(本だな)」「格子」
 {動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」
{動・形}こつんとつかえる。つかえてとめる。また、そのさま。「扞格カンカク(つかえる)」「支格(つかえる)」「格格不入=格格トシテ入ラズ」
 {動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」
{動}こつんと打ち当てる。かたい物にぶつかる。〈同義語〉→挌。「格闘」「格殺」
 {動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕
{動}いたる。いたす。かたい本質につき当たる。物事のしんにつき当たるまでつきつめる。きわめる。とどく。「致知在格物=知ヲ致スハ格物ニ在リ」〔→大学〕
 {動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕
{動}ただす。かたいかどめをつける。わくにはめてただす。あやまちをただしくする。「惟大人為能格君心之非=タダ大人ノミヨク君心ノ非ヲ格スヲ為ス」〔→孟子〕
 {名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」
〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」
《解字》
会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各
《単語家族》
客(一軒の家につかえて止まった人)
{名}体言(名詞)が他の語に対する関係をあらわす文法学の用語。ケース。「主格」
〔国〕平安時代の、制度に関する勅令や、きまり。「格式キャクシキ」
《解字》
会意兼形声。各は、夂(あし)と四角い石を組みあわせて、足がかたい石につかえて止まったさまを示す。格は「木+音符各」で、つかえて止めるかたい棒、ひっかかる木。→各
《単語家族》
客(一軒の家につかえて止まった人) 閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石)
閣(とびらにつかえて止めるとびらどめの石) 擱カク(つかえて止まる)
擱カク(つかえて止まる) 挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
挌(つきあたる、ひっかかる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
版 いた🔗⭐🔉
【版】
 8画 片部 [五年]
区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン
8画 片部 [五年]
区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン /ヘン
/ヘン 〈b
〈b n〉
《訓読み》 ふだ/いた
《意味》
n〉
《訓読み》 ふだ/いた
《意味》
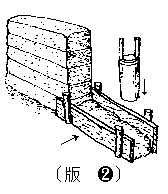
 {名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」
{名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」
 {名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」
{名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」
 {名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」
{名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」
 {単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」
{単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」
 {単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。
《解字》
会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。
《単語家族》
反(表面をそらせてのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。
《解字》
会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。
《単語家族》
反(表面をそらせてのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 片部 [五年]
区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン
8画 片部 [五年]
区点=4039 16進=4847 シフトJIS=94C5
《常用音訓》ハン
《音読み》 ハン /ヘン
/ヘン 〈b
〈b n〉
《訓読み》 ふだ/いた
《意味》
n〉
《訓読み》 ふだ/いた
《意味》
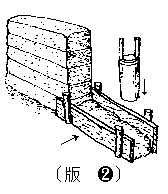
 {名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」
{名}ふだ。木のふだ。「版籍(戸籍や土地区分を書いたふだ)」「手版(姓名・略歴などを書いた名刺のふだ)」
 {名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」
{名}いた。平らにしたいた。土壁を築くとき両側に張って、その間に土を入れてかためるためにも用いた。〈同義語〉→板。「版築」
 {名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」
{名}もと、字を刻んだ印刷用のいた。また、のち印刷の原版のこと。〈同義語〉→板。「原版」
 {単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」
{単位}出版物の刊行の回数を数えることば。「初版」
 {単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。
《解字》
会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。
《単語家族》
反(表面をそらせてのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{単位}長さの単位。版築に用いる板の長さを基準とし、一版は、周代の一丈(二・二五メートル)または八尺(一・八メートル)。〈同義語〉→板。
《解字》
会意兼形声。版は「片(木のきれはし)+音符反」で、板とほとんど同じ。
《単語家族》
反(表面をそらせてのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
異体 イタイ🔗⭐🔉
【異体】
イタイ  タイヲコトニス形を異にする。
タイヲコトニス形を異にする。 異なった形。
異なった形。 異様な形。
異様な形。
 タイヲコトニス形を異にする。
タイヲコトニス形を異にする。 異なった形。
異なった形。 異様な形。
異様な形。
異体字 イタイジ🔗⭐🔉
【異体字】
イタイジ 発音・意味は同じであるが、字形が異なる二種類以上の漢字があるとき、一方を、他の異体字という。
異態 イタイ🔗⭐🔉
【異態】
イタイ  地形や風景などが異なる。
地形や風景などが異なる。 地形・風景などのすぐれた状態。
地形・風景などのすぐれた状態。
 地形や風景などが異なる。
地形や風景などが異なる。 地形・風景などのすぐれた状態。
地形・風景などのすぐれた状態。
疼 いたい🔗⭐🔉
痛 いたい🔗⭐🔉
【痛】
 12画
12画  部 [六年]
区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9
《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める
《音読み》 ツウ
部 [六年]
区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9
《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める
《音読み》 ツウ /トウ
/トウ 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)
《意味》
ng〉
《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)
《意味》
 {動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」
{動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」
 {動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」
{動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」
 {副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕
〔国〕
{副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕
〔国〕 いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。
いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。 いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。
《解字》
会意兼形声。「
いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。
《解字》
会意兼形声。「 +音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。
《単語家族》
通と同系。
《異字同訓》
いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
+音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。
《単語家族》
通と同系。
《異字同訓》
いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画
12画  部 [六年]
区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9
《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める
《音読み》 ツウ
部 [六年]
区点=3643 16進=444B シフトJIS=92C9
《常用音訓》ツウ/いた…い/いた…む/いた…める
《音読み》 ツウ /トウ
/トウ 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)
《意味》
ng〉
《訓読み》 いたむ/いたい(いたし)/いたみ/いたます/いためる(いたむ)/いたく/いたましい(いたまし)
《意味》
 {動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」
{動・形・名}いたむ。いたい(イタシ)。いたみ。つきとおるようにいたい。ずきずきといたむ。また、そのようないたみ。〈同義語〉→疼。「激痛」「疼痛トウツウ」
 {動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」
{動}いたむ。いたます。いためる(イタム)。心がつきぬけるようにつらい思いをする。悲しみなげく。苦しむ。「痛嘆」「常痛於心=常ニ心ニ痛ム」
 {副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕
〔国〕
{副}いたく。とことんまで。力の限り。非常に。「痛飲」「痛折節=痛ク節ヲ折ク」〔→史記〕
〔国〕 いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。
いたむ。果物がくさる。また、器物・建物が破損する。▽現在では「傷」を使う。 いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。
《解字》
会意兼形声。「
いたましい(イタマシ)。かわいそうであるさま。
《解字》
会意兼形声。「 +音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。
《単語家族》
通と同系。
《異字同訓》
いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
+音符甬ヨウ・トウ(つきぬける、つきとおる)」。
《単語家族》
通と同系。
《異字同訓》
いたむ/いためる。 痛む/痛める「足が痛む。腰を痛める」傷む/傷める「家が傷む。傷んだ果物。建物を傷める」悼む「死を悼む。故人を悼む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
至 いたって🔗⭐🔉
【至】
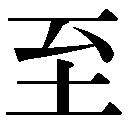 6画 至部 [六年]
区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A
《常用音訓》シ/いた…る
《音読み》 シ
6画 至部 [六年]
区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A
《常用音訓》シ/いた…る
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり
《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり
《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし
《意味》
 {動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕
{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕
 {形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕
{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕
 {接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕
{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕
 {名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。
{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。
 {名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」
《解字》
{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」
《解字》
 会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。
《単語家族》
室(いきづまりの奥のへや)
会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。
《単語家族》
室(いきづまりの奥のへや) 抵(いたる)
抵(いたる) 致(そこまでとどける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
致(そこまでとどける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
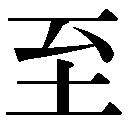 6画 至部 [六年]
区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A
《常用音訓》シ/いた…る
《音読み》 シ
6画 至部 [六年]
区点=2774 16進=3B6A シフトJIS=8E8A
《常用音訓》シ/いた…る
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり
《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いたる/いたれる/いたって/いたるまで/いたり
《名付け》 いたり・いたる・ちか・のり・みち・むね・ゆき・よし
《意味》
 {動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕
{動}いたる。目ざす所までとどく。また、自分の所までやってくる。〈類義語〉→到。「必至(必ずそうなる)」「風雨驟至=風雨驟ニ至ル」「斯天下之民至焉=ココニ天下ノ民至ラン」〔→孟子〕
 {形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕
{形・副}いたれる。いたって。ぎりぎりの線までとどいたさま。最高の。このうえなく。「至大」「至聖」「中庸之為徳也、其至矣乎=中庸ノ徳タルヤ、ソレ至レルカナ」〔→論語〕
 {接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕
{接続}いたるまで。「以至A=以テAニ至ルマデ」「乃至A=乃チAニ至ルマデ」「至若A=Aノ若キニ至ルマデ」などの形で用い、Aまでも含めてそこまでの意。「自耕稼陶漁、以至為帝=耕稼陶漁ヨリ、モッテ帝タルモノニ至ルマデ」〔→孟子〕
 {名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。
{名}太陽がぎりぎりの線までとどいた日。夏至ゲシ・冬至トウジを至日という。
 {名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」
《解字》
{名}いたり。「…之至」という形で用い、手紙や奏上文に用いられる。「恐懼之至=恐懼ノ至リナリ」
《解字》
 会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。
《単語家族》
室(いきづまりの奥のへや)
会意。「矢が下方に進むさま+ー印(目ざす線)」で、矢が目標線までとどくさまを示す。
《単語家族》
室(いきづまりの奥のへや) 抵(いたる)
抵(いたる) 致(そこまでとどける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
致(そこまでとどける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
致 いたす🔗⭐🔉
【致】
 10画 至部 [常用漢字]
区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276
《常用音訓》チ/いた…す
《音読み》 チ
10画 至部 [常用漢字]
区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276
《常用音訓》チ/いた…す
《音読み》 チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 いたす
《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いたす
《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし
《意味》
 {動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕
{動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕
 {動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」
{動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」
 {動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕
{動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕
 {動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」
{動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」
 {動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」
{動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」
 {名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ
{名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕
ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕
 {名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」
〔国〕いたす。「する」の謙譲語。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。
《類義》
効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」
〔国〕いたす。「する」の謙譲語。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。
《類義》
効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 至部 [常用漢字]
区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276
《常用音訓》チ/いた…す
《音読み》 チ
10画 至部 [常用漢字]
区点=3555 16進=4357 シフトJIS=9276
《常用音訓》チ/いた…す
《音読み》 チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 いたす
《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いたす
《名付け》 いたす・いたる・おき・おきかず・かず・とも・のり・むね・ゆき・よし
《意味》
 {動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕
{動}いたす。目ざす所までとどける。「致書=書ヲ致ス」「又不致膰爼於大夫=マタ膰爼ヲ大夫ニ致サズ」〔→史記〕
 {動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」
{動}いたす。こちらまで来させる。そこまでいたらせる。「招致」「致賢=賢ヲ致ス」「致之死地=コレヲ死地ニ致ス」
 {動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕
{動}いたす。ぎりぎりの線まで力を尽くす。「致力」「事君能致其身=君ニ事ヘテヨクソノ身ヲ致ス」〔→論語〕
 {動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」
{動}いたす。役を返上して、役人をやめる。▽役目を返上して、お上に送りとどけるの意から。「致仕チシ(役人をやめる)」「致事=事ヲ致ス」
 {動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」
{動}いたす。ある結果をまねきよせる。「致禍=禍ヲ致ス」「致病=病ヲ致ス」
 {名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ
{名}気持ちのいたるところ。おもむき。「意致」「情致(気持ち)」「所以興懐、其致一也=懐ヲ興スユ ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕
ンハ、ソノ致一ナリ」〔→王羲之〕
 {名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」
〔国〕いたす。「する」の謙譲語。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。
《類義》
効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}いきつくところの意より、転じて、物事の方向と結果。「一致」「大致(物事のおよその方向)」
〔国〕いたす。「する」の謙譲語。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がー線までとどくさまをあらわす会意文字。夂は「夂(あし)+音符至(いたる)」で、足で歩いて目標までとどくこと。自動詞の「至」に対して、他動詞として用いる。
《類義》
効コウ(いたす)は、力をしぼり出すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
不解衣帯 イタイヲトカズ🔗⭐🔉
【不解衣帯】
イタイヲトカズ 帯をとかない。忙しくて寝るひまもないことのたとえ。〔→漢書〕
軫 いたむ🔗⭐🔉
【軫】
 12画 車部
区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766
《音読み》 シン
12画 車部
区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766
《音読み》 シン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 よこぎ/いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 よこぎ/いたむ
《意味》
 {名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。
{名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。
 {名}琴の弦を巻いて調節する軸木。
{名}琴の弦を巻いて調節する軸木。
 {動}車がぐるぐるまわる。
{動}車がぐるぐるまわる。
 {動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」
{動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。
《単語家族》
診(ようすを細かくみて調べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。
《単語家族》
診(ようすを細かくみて調べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 車部
区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766
《音読み》 シン
12画 車部
区点=7739 16進=6D47 シフトJIS=E766
《音読み》 シン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 よこぎ/いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 よこぎ/いたむ
《意味》
 {名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。
{名}よこぎ。車の後部の下にあるよこぎ。また、車台を組みたてるきめ細かい材木。
 {名}琴の弦を巻いて調節する軸木。
{名}琴の弦を巻いて調節する軸木。
 {動}車がぐるぐるまわる。
{動}車がぐるぐるまわる。
 {動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」
{動}いたむ。うれえる。ようすをきめ細かくみて心配する。〈類義語〉→診。「軫恤シンジュツ」
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。
《単語家族》
診(ようすを細かくみて調べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のからす座に含まれる。みつうち。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シン)は、きめ細かいの意を含む。軫はそれを音符とし、車をそえた字。きめ細かい木でつくったよこぎや柱。
《単語家族》
診(ようすを細かくみて調べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
輸 いたす🔗⭐🔉
【輸】
 16画 車部 [五年]
区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741
《常用音訓》ユ
《音読み》 ユ
16画 車部 [五年]
区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741
《常用音訓》ユ
《音読み》 ユ /シュ
/シュ /ス
/ス 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)
《意味》
〉
《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)
《意味》
 シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕
シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕
 シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」
シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」
 シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」
シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」
 {名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。
《解字》
会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。
《単語家族》
偸トウ(ぬきとる)
{名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。
《解字》
会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。
《単語家族》
偸トウ(ぬきとる) 癒ユ(病をぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
癒ユ(病をぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 16画 車部 [五年]
区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741
《常用音訓》ユ
《音読み》 ユ
16画 車部 [五年]
区点=4502 16進=4D22 シフトJIS=9741
《常用音訓》ユ
《音読み》 ユ /シュ
/シュ /ス
/ス 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)
《意味》
〉
《訓読み》 うつす/いたす/まける(まく)
《意味》
 シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕
シュス・ユス{動}うつす。中みをそっくりとり出して他の所へ運ぶ。〈類義語〉→運。「運輸」「輸送」「楽輸ラクユ(よろこんで人に物をやる)」「輸積聚以貸=積聚ヲ輸シテモッテ貸ス」〔→左伝〕
 シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」
シュス・ユス{動}いたす。中みをすっかりとり出す。出しつくす。力をとり出して相手にわたす。「輸誠=誠ヲ輸ス」「輸力=力ヲ輸ス」
 シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」
シュス・ユス{動}まける(マク)。かけごとでまけて、かけ金をすっかりもっていかれる。やられる。劣る。〈対語〉→贏エイ。「輸一籌=一籌ヲ輸ス」
 {名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。
《解字》
会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。
《単語家族》
偸トウ(ぬきとる)
{名}送ったり運んだりする品物。▽去声に読む。
《解字》
会意兼形声。兪ユは「舟+くりぬく刀」から成り、丸木舟の中みをすっかりくりぬくさま。輸は「車+音符兪(ぬきとる)」で、ある所の品をそっくりぬき出して車で運ぶこと。
《単語家族》
偸トウ(ぬきとる) 癒ユ(病をぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
癒ユ(病をぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
遺体 イタイ🔗⭐🔉
遺託 イタク🔗⭐🔉
【遺託】
イタク あとにいいのこした頼みごと。死後におこる問題の処理や子どもの後見を頼むこと。
鈑 いたがね🔗⭐🔉
【鈑】
 12画 金部
区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5
《音読み》 ハン
12画 金部
区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5
《音読み》 ハン /ヘン
/ヘン 〈b
〈b n〉
《訓読み》 いたがね/ふだ
《意味》
n〉
《訓読み》 いたがね/ふだ
《意味》
 {名}いたがね。金属ののべいた。板金。
{名}いたがね。金属ののべいた。板金。
 {名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。
《解字》
会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。
《単語家族》
板や版と同系。
{名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。
《解字》
会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。
《単語家族》
板や版と同系。
 12画 金部
区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5
《音読み》 ハン
12画 金部
区点=7871 16進=6E67 シフトJIS=E7E5
《音読み》 ハン /ヘン
/ヘン 〈b
〈b n〉
《訓読み》 いたがね/ふだ
《意味》
n〉
《訓読み》 いたがね/ふだ
《意味》
 {名}いたがね。金属ののべいた。板金。
{名}いたがね。金属ののべいた。板金。
 {名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。
《解字》
会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。
《単語家族》
板や版と同系。
{名}ふだ。平らな金属のふだ。〈同義語〉→版。
《解字》
会意兼形声。「金+音符反(平らにのびる)」。
《単語家族》
板や版と同系。
閔 いたむ🔗⭐🔉
【閔】
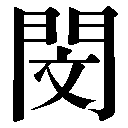 12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン
12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン /ミン
/ミン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
 {動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
 {動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
 {動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
 {動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
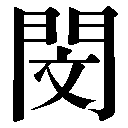 12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン
12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン /ミン
/ミン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
 {動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
 {動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
 {動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
 {動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
隠 いたむ🔗⭐🔉
【隠】
 14画 阜部 [常用漢字]
区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942
【隱】旧字旧字
14画 阜部 [常用漢字]
区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942
【隱】旧字旧字
 17画 阜部
区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA
《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる
《音読み》 イン
17画 阜部
区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA
《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる
《音読み》 イン /オン
/オン 〈y
〈y n・y
n・y n〉
《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる
《名付け》 やす
《意味》
n〉
《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる
《名付け》 やす
《意味》
 {動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕
{動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕
 {動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕
{動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕
 {動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕
{動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕
 {動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕
{動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕
 {名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」
{名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」
 インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕
インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕
 {形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」
{形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」
 {動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕
《解字》
{動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕
《解字》
 会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。
《単語家族》
穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか)
会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。
《単語家族》
穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか) 湮イン(かくす)
湮イン(かくす) 殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。
《類義》
→蔵
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。
《類義》
→蔵
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 14画 阜部 [常用漢字]
区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942
【隱】旧字旧字
14画 阜部 [常用漢字]
区点=1703 16進=3123 シフトJIS=8942
【隱】旧字旧字
 17画 阜部
区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA
《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる
《音読み》 イン
17画 阜部
区点=8012 16進=702C シフトJIS=E8AA
《常用音訓》イン/かく…す/かく…れる
《音読み》 イン /オン
/オン 〈y
〈y n・y
n・y n〉
《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる
《名付け》 やす
《意味》
n〉
《訓読み》 かくれる(かくる)/かくす/いたむ/よる
《名付け》 やす
《意味》
 {動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕
{動・形}かくれる(カクル)。かくす。外から見えなくなる。また、何かでおおって見えなくする。おおわれて見えないさま。〈対語〉→顕。「隠匿」「隠微」「隠悪而揚善=悪ヲ隠シテ善ヲ揚グ」〔→中庸〕
 {動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕
{動}かくす。人に知れないようにする。秘密にする。「父為子隠=父ハ子ノ為ニ隠ス」〔→論語〕
 {動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕
{動・形}かくれる(カクル)。出世を求めず、人目からかくれる。目だたない所に退いている。「隠民」「隠士」「隠居放言=隠居シテ放ニ言フ」〔→論語〕
 {動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕
{動}いたむ。相手の身により添って考える。親身になって心配する。おしはかる。〈類義語〉→依。「惻隠ソクイン」「王若隠其無罪而就死地、則牛羊何択焉=王モシソノ罪無クシテ死地ニ就クヲ隠マバ、スナハチ牛羊ナンゾ択バン」〔→孟子〕
 {名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」
{名}人知れぬ悩み。その身になってみてわかる苦労。「民隠(人民の苦しみ)」
 インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕
インタリ・イントシテ{形}おおわれてぼんやりしたさま。なんとなく。▽去声に読む。「隠若白虹起=隠トシテ白虹ノ起ツガゴトシ」〔→李白〕
 {形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」
{形}はででなく、ずっしりと中にこもっているさま。落ち着いているさま。▽去声に読む。〈類義語〉→穏。「隠隠」
 {動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕
《解字》
{動}よる。よりかかる。また、何かをたよりにする。何かのかげにかくれる。▽去声に読む。〈類義語〉→依イ・→倚イ。「隠几而臥=几ニ隠リテ臥ス」〔→孟子〕
《解字》
 会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。
《単語家族》
穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか)
会意兼形声。隱の右側の上部は「爪(手)+工印+ヨ(手)」の会意文字で、工形の物を上下の手で、おおいかくすさまをあらわす。隱はそれに心をそえた字を音符とし、阜(壁や、土べい)を加えた字で、壁でかくして見えなくすることをあらわす。隠は工印をはぶいた略字。
《単語家族》
穩オン(=穏。動きをかくす→おだやか) 湮イン(かくす)
湮イン(かくす) 殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。
《類義》
→蔵
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
殷イン(かくして中にこもる)などと同系。衣(からだをかくすころも)・依は、その語尾が転じたことば。
《類義》
→蔵
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
頂 いただき🔗⭐🔉
【頂】
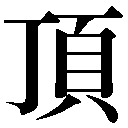 11画 頁部 [六年]
区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8
《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く
《音読み》 チョウ(チャウ)
11画 頁部 [六年]
区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8
《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く
《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ
/テイ 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 いただき/いただく
《名付け》 かみ
《意味》
ng〉
《訓読み》 いただき/いただく
《名付け》 かみ
《意味》
 {名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕
{名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕
 {動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」
{動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」
 {動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」
{動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」
 {動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」
{動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」
 {副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」
〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。
《解字》
会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。
《単語家族》
釘(T型のくぎ)
{副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」
〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。
《解字》
会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。
《単語家族》
釘(T型のくぎ) 打(平面を直角にうちあてる)
打(平面を直角にうちあてる) 亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
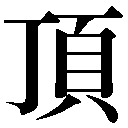 11画 頁部 [六年]
区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8
《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く
《音読み》 チョウ(チャウ)
11画 頁部 [六年]
区点=3626 16進=443A シフトJIS=92B8
《常用音訓》チョウ/いただき/いただ…く
《音読み》 チョウ(チャウ) /テイ
/テイ 〈d
〈d ng〉
《訓読み》 いただき/いただく
《名付け》 かみ
《意味》
ng〉
《訓読み》 いただき/いただく
《名付け》 かみ
《意味》
 {名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕
{名}いただき。頭のてっぺん。直線がT型につかえた上方の面。たっているもののいちばん高い所。「山頂」「頂上」「觝頂交跖=頂ニ觝レ跖ヲ交フ」〔→韓愈〕
 {動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」
{動}いただく。頭上にのせる。下にたって物を上にのせる。「頂天立地=天ヲ頂キ地ニ立ツ」
 {動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」
{動}つっかえ棒をしてささえる。正面からつきあたる。「頂衝」
 {動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」
{動}代わりにささえる。肩代わりする。「頂替」
 {副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」
〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。
《解字》
会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。
《単語家族》
釘(T型のくぎ)
{副}〔俗〕いちばん。とびきり。〈類義語〉→最。「頂好ティンハオ」
〔国〕いただく。「もらう」「食べる」のていねいないい方。
《解字》
会意兼形声。「頁(あたま)+音符丁(直線がてっぺんにつかえる、てっぺん)」。胴体の直線が直角につかえる脳天。
《単語家族》
釘(T型のくぎ) 打(平面を直角にうちあてる)
打(平面を直角にうちあてる) 亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
亭(地面に直角にたつ望楼)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
顛 いただき🔗⭐🔉
【顛】
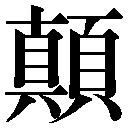 19画 頁部
区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E
《音読み》 テン
19画 頁部
区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E
《音読み》 テン
 〈di
〈di n〉
《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)
《意味》
n〉
《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)
《意味》
 {名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕
{名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕
 {名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」
{名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」
 {動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕
{動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕
 {形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」
{形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」
 {動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
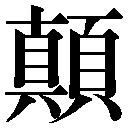 19画 頁部
区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E
《音読み》 テン
19画 頁部
区点=3731 16進=453F シフトJIS=935E
《音読み》 テン
 〈di
〈di n〉
《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)
《意味》
n〉
《訓読み》 いただき/たおれる(たふる)/たおす(たふす)
《意味》
 {名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕
{名}いただき。頭のてっぺん。転じて、山や物の上のはし。〈同義語〉→巓。〈類義語〉→頂チョウ/テイ。「有馬白顛=馬有リ白顛ナリ」〔→詩経〕「頭髪未長顛已朽=頭髪イマダ長ゼザルニ顛スデニ朽チヌ」〔→袁宏道〕
 {名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」
{名}物の先端。また、はじめ。「顛末テンマツ(事がらのはじめから終わりまでの事情)」
 {動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕
{動}たおれる(タフル)。たおす(タフス)。さかさまになる。頭のてっぺんを地につける。〈類義語〉→倒。「顛倒テントウ」「顛覆厥徳=ソノ徳ヲ顛覆ス」〔→詩経〕「顛而不扶=顛ルルモ扶ケズ」〔→論語〕
 {形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」
{形・名}気が狂って正気でない。また、そのようになる病気。〈同義語〉→癲。「狂顛キョウテン」
 {動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}欠けめをつめて、いっぱいにみたす。▽填テンに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。眞(=真)は「匕(さじ)+鼎」の会意文字。鼎(かなえ)の中にさじで物をみたすことをあらわす。また、のち「人+首の逆形」の会意文字となり、人が首をさかさにして頭のいただきを地につけ、たおれることを示す。顛は「頁(あたま)+音符眞(さかさにしてみたす、たおれる)」で、真の本来の意味をあらわす。▽山のいただきなら、特に巓テンと書く。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鼬 いたち🔗⭐🔉
【鼬】
 18画 鼠部
区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C
《音読み》 ユウ(イウ)
18画 鼠部
区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 いたち
《意味》
{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」
《解字》
会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。
《単語家族》
抽(抜け出る)と同系。
u〉
《訓読み》 いたち
《意味》
{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」
《解字》
会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。
《単語家族》
抽(抜け出る)と同系。
 18画 鼠部
区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C
《音読み》 ユウ(イウ)
18画 鼠部
区点=8376 16進=736C シフトJIS=EA8C
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 いたち
《意味》
{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」
《解字》
会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。
《単語家族》
抽(抜け出る)と同系。
u〉
《訓読み》 いたち
《意味》
{名}いたち。ねずみより大きく、むささびに似た動物。動作がすばしこく、細いすきまから抜け出て、出入する。夜、ねずみ・鶏などを捕食する。敵に追いつめられると悪臭を放つ。「鼬鼠ユウソ」
《解字》
会意兼形声。「鼠+音符由(細い穴から抜け出る)」。
《単語家族》
抽(抜け出る)と同系。
漢字源に「いた」で始まるの検索結果 1-44。もっと読み込む
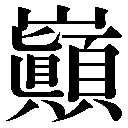 22画 山部
区点=5460 16進=565C シフトJIS=9BDA
《音読み》 テン
22画 山部
区点=5460 16進=565C シフトJIS=9BDA
《音読み》 テン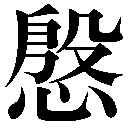 14画 心部
区点=5632 16進=5840 シフトJIS=9CBE
《音読み》 イン
14画 心部
区点=5632 16進=5840 シフトJIS=9CBE
《音読み》 イン n〉
《訓読み》 いたむ
《意味》
n〉
《訓読み》 いたむ
《意味》
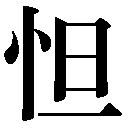 8画
8画  〉
《訓読み》 いたむ/おどろく
《意味》
{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」
《解字》
形声。「心+音符旦タン」。
《単語家族》
憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。
《熟語》
〉
《訓読み》 いたむ/おどろく
《意味》
{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」
《解字》
形声。「心+音符旦タン」。
《単語家族》
憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。
《熟語》
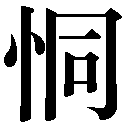 9画
9画  11画
11画  11画
11画 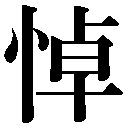 11画
11画  12画
12画  〉
《訓読み》 いたむ
《意味》
{動}いたむ。いつも心について離れない。ひしひしと心に迫る。「惻然ソクゼン」「惻惻ソクソク」
《解字》
会意兼形声。則は「鼎(かなえ)+刀」からなる会意文字で、食器のそばに刀をくっつけて置いたさま。側ソバにくっつく意を含む。惻は「心+音符則」で、心にひしひしとくっついて離れないこと。
〉
《訓読み》 いたむ
《意味》
{動}いたむ。いつも心について離れない。ひしひしと心に迫る。「惻然ソクゼン」「惻惻ソクソク」
《解字》
会意兼形声。則は「鼎(かなえ)+刀」からなる会意文字で、食器のそばに刀をくっつけて置いたさま。側ソバにくっつく意を含む。惻は「心+音符則」で、心にひしひしとくっついて離れないこと。 13画
13画 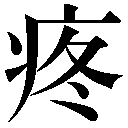 10画
10画