複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぶつ【物】🔗⭐🔉
ぶつ【物】
(慣用音はモツ)
①もの。ことがら。
②金品を指していう俗語。現物。「―がない」
ぶっ‐か【物化】‥クワ🔗⭐🔉
ぶっ‐か【物化】‥クワ
①[荘子斉物論]物が変化すること。
②天命を終えて死ぬこと。物故。
ぶっ‐か【物価】🔗⭐🔉
ぶっ‐か【物価】
諸商品の市価。商品の価格を総合的・平均的に見たものをいう。「―騰貴」
⇒ぶっか‐しすう【物価指数】
⇒ぶっか‐すいじゅん【物価水準】
⇒ぶっか‐たいけい【物価体系】
⇒ぶっか‐だか【物価高】
⇒ぶっか‐ていし‐れい【物価停止令】
⇒ぶっか‐とうせい【物価統制】
ぶつ‐が【物我】🔗⭐🔉
ぶつ‐が【物我】
外物と自我。客観と主観。
ぶっか‐しすう【物価指数】🔗⭐🔉
ぶっか‐しすう【物価指数】
物価の変動を表示する統計数字。一定の場所、一定の時期における一定の商品の価格を100とし、その後のある時における価格の変動状態を指数で表したもの。企業物価指数・消費者物価指数など。
⇒ぶっ‐か【物価】
ぶっか‐すいじゅん【物価水準】🔗⭐🔉
ぶっか‐すいじゅん【物価水準】
さまざまな財・サービスの価格をその取引額に応じて平均して得られる社会全体の物価の平均。
⇒ぶっ‐か【物価】
ぶっか‐たいけい【物価体系】🔗⭐🔉
ぶっか‐たいけい【物価体系】
①重要商品の価格を統一的な原則によって組み立てた系列。
②諸個別価格の相対的関係。相対価格体系。
⇒ぶっ‐か【物価】
ぶっか‐だか【物価高】🔗⭐🔉
ぶっか‐だか【物価高】
物価の高いこと。高物価。
⇒ぶっ‐か【物価】
ぶっか‐ていし‐れい【物価停止令】🔗⭐🔉
ぶっか‐ていし‐れい【物価停止令】
物価・賃金・給料などをその時現在の価格以上に引き上げることを禁止した法令。価格等統制令など一連の法令の俗称。国家総動員法により、1939年(昭和14)10月に公布。九‐一八停止令。
⇒ぶっ‐か【物価】
ぶっか‐とうせい【物価統制】🔗⭐🔉
ぶっか‐とうせい【物価統制】
物資需給の円滑化のために国家機関が物価を統制すること。日中戦争以降に本格化し、戦後も1940年代末まで続いた。
⇒ぶっ‐か【物価】
ぶつぶつ‐こうかん【物物交換】‥カウクワン🔗⭐🔉
ぶつぶつ‐こうかん【物物交換】‥カウクワン
交換の原始的形態で、品物を貨幣などの媒介物によらず、直接他の品物と交換すること。バーター。
もっ‐け【物怪・勿怪】🔗⭐🔉
もっ‐け【物怪・勿怪】
①異変。災害。不幸。今昔物語集14「様々の―あるに占卜うらなはするに」
②思いもうけぬこと。意外。浄瑠璃、女殺油地獄「たつた今飛脚の状に、―な事がいうて来ました」
⇒もっけ‐がお【物怪顔】
⇒もっけ‐の‐さいわい【物怪の幸い】
もっけ‐の‐さいわい【物怪の幸い】‥サイハヒ🔗⭐🔉
もっけ‐の‐さいわい【物怪の幸い】‥サイハヒ
思いがけない幸せ。意外な幸運。
⇒もっ‐け【物怪・勿怪】
もの【物】🔗⭐🔉
もの【物】
[一]〔名〕
➊形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。また、対象を特定の言葉で指し示さず漠然ととらえて表現するのにも用いる。
①物体。物品。万葉集2「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」。「―がなくなる」「他人の―」「時代―」
②仏・神・鬼・魂など、霊妙な作用をもたらす存在。妖怪。邪神。物のけ。源氏物語帚木「―におそはるる心地して」。「―に憑つかれる」「―詣で」
③物事。源氏物語桐壺「―の心知り給ふ人」。源氏物語帚木「まことの―の上手」。源氏物語若紫「―のはじめ」。「―のついでに伝える」
④世間で知られている内容。世間一般の事柄。普通の物。源氏物語初音「御簾の内の追風、なまめかしく吹き匂はして、―より殊にけだかくおぼさる」。「―を知らない」
⑤取り立てて言うべきほどのこと。物の数。貫之集「桜よりまさる色なき春なればあだし草木を―とやは見る」。「―ともしない」「―になる」
⑥動作・作用・心情の対象となる事柄。
㋐言語。言葉。古事記下「山城のつつきの宮に―申すあが兄せの君は」。源氏物語桐壺「母君もとみにえ―ものたまはず」。「―をあまり言わない子」
㋑飲食物。おもの。源氏物語桐壺「―などもきこしめさず、朝がれひのけしきばかり触れさせ給ひて」
㋒着物。衣服。源氏物語若紫「―縫ひ営むけはひなど」
㋓楽器。源氏物語桐壺「心ことなる―の音をかき鳴らし」
⑦それと言いにくいことを漠然と示す語。源氏物語若紫「―よりおはすれば、まづ出でむかひて」
➋(形式名詞)
①そうあって当然のこと。徒然草「あまりに興あらんとする事は、必ずあいなき―なり」。「親には従う―だ」「悲しい時は泣く―」
②感嘆の意。万葉集15「ほととぎす物思ふ時に鳴くべき―か」。「ばかなことをした―だ」
③(終助詞的に)少し感情をこめて理由をのべる。「行きたいんだ―」
➌〔哲〕(thing イギリス・Ding ドイツ)
①広義には、思考の対象としての意識的存在であれ、現実に存在する事物であれ、何らかの存在・対象・判断の主語となる一切。
②狭義には、外界に在り、感覚によって知覚しうる事物。感性的性質の統一的担い手としての個物。時間・空間中に在る物体的・物質的なもの。
➍〔法〕民法上、有体物。私権の客体たりうるもの。
[二]〔接頭〕
状態を表す名詞・形容詞の語頭に添えて、何とはなしにそうである、の意を表す。「―静か」「―悲しい」
⇒物覚ゆ
⇒物が無い
⇒物がわかる
⇒物ともせず
⇒物ならず
⇒物に当たる
⇒物に掛かる
⇒物にする
⇒物になる
⇒物に似ず
⇒物には七十五度
⇒物にもあらず
⇒物の先を折る
⇒物の上手
⇒物は言いよう
⇒物は考えよう
⇒物は相談
⇒物は試し
⇒物は使いよう
⇒物も言いようで角が立つ
⇒物を言う
⇒物を言わす
もの‐あき【物厭き】🔗⭐🔉
もの‐あき【物厭き】
物事にあきること。浮世風呂前「おのしがやうな―をする者は万一に飽きツぽくて」
もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ🔗⭐🔉
もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ
何となくあわれなこと。何となく感慨深いさま。源氏物語賢木「はるけき野辺を分け入り給ふよりいと―なり」
もの‐あんじ【物案じ】🔗⭐🔉
もの‐あんじ【物案じ】
心配すること。物思い。狂言、千鳥「幾瀬の―をする事ぢや」
もの‐えんじ【物怨じ】‥ヱンジ🔗⭐🔉
もの‐えんじ【物怨じ】‥ヱンジ
物事をうらむこと。嫉妬。ものうらみ。枕草子125「人の妻のすずろなる―して」
もの‐おと【物音】🔗⭐🔉
もの‐おと【物音】
物のたてる音。何かの音。「不審な―」「―一つしない」
もの‐がくし【物隠し】🔗⭐🔉
もの‐がくし【物隠し】
物事をつつみ隠すこと。かくしだて。源氏物語紅葉賀「―は懲りぬらむかし」
もの‐かげ【物陰】🔗⭐🔉
もの‐かげ【物陰】
物のかげ。物にかくれて見えない所。「―にかくれる」
もの‐かげ【物影】🔗⭐🔉
もの‐かげ【物影】
物の形。何かの姿。
○物が無いものがない🔗⭐🔉
○物が無いものがない
①身も蓋もない。つまらない。浮世草子、好色敗毒散「人のそしりをうけてからは―」
②命がない。浄瑠璃、博多小女郎波枕「この中のこと一言いうても―ぞ」
⇒もの【物】
もの‐がなし・い【物悲しい】
〔形〕[文]ものがな・し(シク)
何となく悲しい。うらがなし。万葉集19「春まけて―・しきに」。「―・い気分」「―・い夕暮」
もの‐がなし‐ら【物悲しら】
(ラは状態を表す接尾語)何となく悲しそうなさま。万葉集4「―に思へりしわが児の刀自を」
もの‐か‐は
(名詞モノに助詞カ・ハの付いたもの)
[一]大したことではない。ものの数ではない。後撰和歌集恋「憂きは―恋ひしきよりは」。「豪雨も―、出発した」
[二]〔助詞〕
(終助詞)
①強い感動の意を表す。大鏡道長「おなじものを中心なからにはあたる―」
②強い反語の意を表す。徒然草「花はさかりに月はくまなきをのみ見る―」
もの‐がま・し【物がまし】
〔形シク〕
とりたてて言うべき物のようである。重大らしい。一言芳談「生死界の事を―・しくおもふべからざるなり」
モノガミー【monogamy】
一夫一妻いっぷいっさい。単婚。
ものから
〔助詞〕
(接続助詞。形式名詞モノに格助詞カラの付いたもの)
①対立・矛盾する状況を示す。…ではあるが。…ものの。万葉集6「見渡せば近き―石いわ隠りかがよふ珠を」
②理由を示す。(中世に始まり、近世で一般化した)…だから。…ので。奥の細道「さすがに辺土の遺風忘れざる―殊勝に覚えらる」
もの‐がら【物柄】
品質。しながら。徒然草「費えもなくて―のよきがよきなり」
もの‐がら【物殻】
(渥美半島で)土間敷きのこと。
モノカルチャー【monoculture】
①特定の一種類の農作物を栽培すること。単作。
②植民地時代の影響による、単一または少数の一次産品に依存する、発展途上国に多く見られる経済構造。キューバの砂糖、スリランカの茶など。
もの‐がま・し【物がまし】🔗⭐🔉
もの‐がま・し【物がまし】
〔形シク〕
とりたてて言うべき物のようである。重大らしい。一言芳談「生死界の事を―・しくおもふべからざるなり」
○物がわかるものがわかる🔗⭐🔉
○物がわかるものがわかる
物事の道理や人情がよくわかっている。「物のわかる人」
⇒もの【物】
もの‐ぎ【物着】
①衣服を着ること。
②能楽で、演技者が退場せずに舞台で扮装を変えること。
⇒ものぎ‐の‐あいかた【物着の合方】
もの‐ぎき【物聞き】
様子を探り聞くこと。また、その人。遠聞き。しのび。探偵。枕草子25「―に宵より寒がりわななきをりける下衆げす男」
もの‐きこ・ゆ【物聞ゆ】
〔自下二〕
(「きこゆ」は「言う」の謙譲語)お話しする。伊勢物語「人の御もとに忍びて―・えて」
もの‐ぎせ【物着せ】
能および狂言の演技者に装束を着せる人。江戸時代には専門の者がいたが、今は後見が担当する。
もの‐ぎたな・し【物穢し】
〔形ク〕
何となくきたない。なんとなく卑しい。源氏物語東屋「上達部かんだちめの筋にてなからひも―・き人ならず」
ものぎ‐の‐あいかた【物着の合方】‥アヒ‥
歌舞伎下座音楽の一つ。時代物で着物を舞台で着替える時につなぎに弾く三味線。多く小太鼓を入れる。別称、鎧三重よろいさんじゅう。
⇒もの‐ぎ【物着】
ものき‐ぼし【物着星】
爪にできた白い点。女は衣服を得る前兆として喜ぶ。誹風柳多留23「―かたみをもらうなさけなさ」
もの‐きょうじ【物興じ】
物事に興じること。面白がること。栄華物語耀く藤壺「あまり―する程に」
もの‐きよ・し【物清し】
〔形ク〕
何となくきよい。源氏物語総角「まことに―・く推し量りきこゆる人も侍らじ」
もの‐きらぎら・し【物端正し】
〔形シク〕
目立ってはっきりしている。源氏物語常夏「いと―・しくかひある所つき給へる人にて」
もの‐きれ【物切れ】
①(モノギレとも)品物のきれてなくなること。しなぎれ。洒落本、当世繁栄通宝「はけ方がたくさん故…―だのとことわりを言ひ」
②切れ味のよい刃物。狂言、武悪「是は―ぢや程に心安思うてどこからなり共きれ」
もの‐ぎわ【物際】‥ギハ
①行うべき物事のまぎわ。せとぎわ。三河物語「はやりて鑓を入れば―にて精が抜けて鑓が弱きものなり」
②盆・正月などの前の多忙な時。節季前。傾城禁短気「―に肴屋呼びつけ」
もの‐ぐさ【懶・物臭】
(古くは清音)
①無精ぶしょうなこと。また、その性質の人。徳和歌後万載集雑「人とはぬ庭も我が身もあかつきて苔むしけりな―の庵」。「―な男」
②懶草履の略。一遍上人語録「―といふものを四十八作りて」
⇒ものぐさ‐ぞうり【懶草履】
⇒ものぐさ‐どうしん【懶道心】
もの‐ぐさ【物種】
もののたねとなるべきもの。物の材料。拾遺和歌集雑春「なき―は思はざらまし」
もの‐ぐさ・い【懶い】
〔形〕[文]ものぐさ・し(ク)
(古くは清音)
①物事をするのがいやで気が進まない。無精ぶしょうである。おっくうである。
②気分がすぐれない。からだの工合が悪い。〈日葡辞書〉
③うさんくさい。疑わしい。浄瑠璃、碁盤太平記「この内は―・し。さがせやさがせ」
④とるに足りない。幸若舞曲、高館「今はむかふかたきのあらざれば、ええ―・い戦かな」
もの‐ぐさし【懶】
(古くは清音)物ぐさ者。無精者ぶしょうもの。御伽草子、物くさ太郎「国にならびなき程の―なり」
ものぐさ‐ぞうり【懶草履】‥ザウ‥
短くて、かかとのない、普通の半分ぐらいの草履。足半あしなか。尻切れ草履。御伽草子、物くさ太郎「―のやぶれたるをはき」
⇒もの‐ぐさ【懶・物臭】
ものくさたろう【物くさ太郎】‥ラウ
御伽草子23編の一つ。1冊。成立は室町時代か。信濃国の物臭太郎という無精者ぶしょうものが歌才によって宮中に召され、貴族の出身で善光寺如来の申子もうしごとわかって出世するという筋。「おたがの本地」ともいう。
→文献資料[物くさ太郎]
ものぐさ‐どうしん【懶道心】‥ダウ‥
生活の苦労を厭って出家した僧。
⇒もの‐ぐさ【懶・物臭】
もの‐ぐねり【物ぐねり】
意地悪をすること。また、すねること。愚痴。松の葉1「ともすれば何ぞよそなたの―」
もの‐ぐら・し【物暗し】
〔形ク〕
何となく暗い。うすぐらい。能因本枕草子物くらうなりて「―・うなりて文字も書かれずなりにたり」
モノグラフ【monograph】
一つの特定の問題を詳細に取り扱った研究論文。モノグラフィー。
モノグラフィー【monographie フランス】
⇒モノグラフ
モノグラム【monogram】
2個以上の文字を1字状に図案化したもの。組字。合一文字。
モノクル【monocle】
片眼鏡かためがね。単眼鏡。
もの‐ぐるい【物狂い】‥グルヒ
①何かの原因で正常な判断ができなくなること。乱心。また、その人。枕草子267「誰てふ―か我人にさ思はれんとは思はん」
②神の乗り移った者。平家物語2「此の―走りまはつて」
③能楽で、悲嘆のあまり心の正常さを失って舞い歌いなどする人物。また、その芸。
もの‐ぐるおし・い【物狂おしい】‥グルホシイ
〔形〕[文]ものぐるほ・し(シク)
心が異常な状態に陥りそうである。ものぐるわしい。枕草子142「ものにあたるばかりさわぐも、いといと―・し」
もの‐ぐるわし・い【物狂わしい】‥グルハシイ
〔形〕
(→)「ものぐるおしい」に同じ。
モノクロ
モノクロームの略。
モノクローナル‐こうたい【モノクローナル抗体】‥カウ‥
〔生〕(monoclonal antibody)(→)単一クローン抗体に同じ。
モノクローム【monochrome】
①単色画。単彩画。
②白黒の写真や映画。モノクロ。
もの‐けざやか【物けざやか】
はっきりしているさま。栄華物語日蔭のかづら「更衣ころもがえなどの有様も―に」
もの‐けたまわる【物承る】‥ケタマハル
(モノウケタマワルの約。物を伺いますの意)人に物を言う最初の語。もしもし。源氏物語帚木「―、いづくにおはしますぞ」
ものげ‐な・し【物気無し】
〔形ク〕
それと認めるほどの事もない。あまり目立たない。源氏物語帚木「―・き程を見すぐして」
もの‐ごい【物乞い】‥ゴヒ
①物を乞いもとめること。
②こじき。
ものご・い
〔形〕
(福井県で)つらい。悲しい。
もの‐こい・し【物恋し】‥コヒシ
〔形シク〕
何となく恋しい。玉葉集恋「―・しらにさ夜ぞふけ行く」
もの‐こお・し【物恋ほし】‥コホシ
〔形シク〕
何となく恋しい。万葉集3「旅にして―・しきに」
モノコード【monochord】
古代ギリシアから伝わる1弦の楽器・器具。共鳴箱の上に一本の弦を張り、駒を動かしてさまざまな音を得る。音の高さの研究・教育、弦に関する実験に19世紀末まで使用。
モノコード
 もの‐ごころ【物心】
人情・世態などを理解する心。「―がつく」
もの‐こころづきな・し【物心付きなし】
〔形シク〕
何となく気に入らない。源氏物語真木柱「―・き御けしき絶えず」
もの‐こころぼそ・し【物心細し】
〔形ク〕
何となく心細い。源氏物語明石「重くならせ給ひて―・く思されければ」
も‐の‐こし【裳の腰】
裳の腰帯。源氏物語宿木「三重がさねの唐衣、―もみなけぢめあるべし」
もの‐ごし【物越し】
(几帳・すだれなど)物を隔てていること。伊勢物語「―に対面して」
もの‐ごし【物腰】
①物のいいぶり。ことばつき。好色一代女1「―程かはいらしきはなし」
②身のこなし方。態度。好色一代男3「色白く髪うるはしく―やさしく」。「品のよい―」
もの‐ごと【物事】
物と事。一切の事柄。事物。「―には限度がある」「―を苦にしない」
もの‐ごと‐に【物毎に】
それぞれの物に。物のあるたびごとに。ことごとに。中務内侍日記「―面白きこと限りなし」
もの‐ごのみ【物好み】
ある種の物事をえりごのみすること。源氏物語梅枝「―し艶えんがりおはするみこにて」
もの‐ごり【物懲り】
物事にこりること。源氏物語夕顔「危かりし―に」
もの‐ごわ・し【物強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
かたくるしいさまである。うちとけないさまである。源氏物語若紫「―・きさまし給へれば」
もの‐さし【物差し・物指し】
物の長さを差しはかる道具。直尺・曲尺・巻尺など。直尺は竹・鉄・セルロイド・プラスチックなどで細長く作り、長さの単位の目盛を付けたもの。さし。尺しゃく。転じて、物の価値をはかる基準。「かの人物たるや、世間一般の―でははかれない」
もの‐さた【物沙汰】
訴訟などを受理して裁くこと。
もの‐さだめ【物定め】
物事のよしあしを判定すること。しなさだめ。源氏物語帚木「馬の頭、―の博士になりて」
もの‐ざね【物実】
(→)物種ものだねに同じ。古事記上「三柱の女子は―汝が物に因りて成れり」
もの‐さびし・い【物淋しい】
〔形〕[文]ものさび・し(シク)
何となく淋しい。うらさびしい。源氏物語橋姫「宮のうち―・しくのみなりまさる」
もの‐さ・びる【物寂びる】
〔自上一〕[文]ものさ・ぶ(上二)
①どことなくすさび衰える。謡曲、夜討曾我「われら兄弟が幕の内ほど―・びたるは候はじ」
②古びて趣がある。十訓抄「いと―・びたる家のすのこの下に遣水の音たえだえ聞えて」
もの‐さわがし・い【物騒がしい】
〔形〕[文]ものさわが・し(シク)
①物音がして騒がしい。源氏物語末摘花「遊びののしり給ふに、―・しけれど」
②世の中が穏やかでない。物騒である。太平記3「―・しく候ふ間、夜討や忍び入り候はんずらん」。「―・い世相」
③気が早い。せっかちである。平家物語2「入道腹の立ちのままに―・しき事し給ひては」
もの‐さわ‐に【物多に】‥サハニ
〔枕〕
物が多い意で、「大宅おおやけ」にかかる。武烈紀「―大宅過ぎ」
もの‐し【物仕・物師】
①物事をよく心得てする人。巧者な人。落窪物語1「いみじき―ぞ、まろは」
②物事を手早く整える人。世事に馴れた人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「長者もさすが―にて」
③裁縫女。世間胸算用2「内義に腰元・中居女・―を添へて」
もの・し【物し】
〔形シク〕
物々しく厭わしい。気障りである。不愉快だ。大和物語「人もなしと思ひつるに―・しきさまをみえぬることとおもひて」
もの‐しずか【物静か】‥シヅカ
①何となくしずかなさま。「―な夜」
②言語・動作などのおちついて穏やかなさま。「―な態度」「―に語る」
もの‐じたい【物自体】
〔哲〕(Ding an sich ドイツ)カントの哲学で、認識主観に現れた現象としての物ではなくて、認識主観とは独立にそれ自体として存在すると考えられた物。経験の彼方にありながら、現象の究極原因・真実在と考えられるもの。感官を触発することによって認識の素材としての感覚を生み出す。物自体は、考えることはできても認識することはできない。↔現象
もの‐しらず【物知らず】
物事を知らないこと。物の道理をわきまえないこと。また、その人。わからず屋。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―と縁を組み」
もの‐しり【物知り・物識り】
①ひろく物事を知っていること。博識。また、その人。
②(秋田県や奄美諸島・沖縄で)祈祷や占いを職とする者。
⇒ものしり‐がお【物知り顔】
⇒ものしり‐だて【物識り立て】
ものしり‐がお【物知り顔】‥ガホ
物事を知っているような顔つき。
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
ものしり‐だて【物識り立て】
物識りの風をすること。知ったかぶり。狂言、右流左止うるさし「いらぬ―をいうて」
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
もの‐しろ【物代】
物のもととなるもの。材料。物実ものざね。物種ものだね。〈崇神紀訓注〉
もの・す【物す】
[一]〔自サ変〕
「居る」「行く」などの動作を婉曲えんきょくにいう語。源氏物語夕顔「そこに―・する程ならば此処に来べき由」
[二]〔他サ変〕
⇒ものする(サ変)
もの‐ずき【物好き・物数奇】
①特殊の物事を好むこと。また、その性質・人。狂言、棒縛「それはわごりよの―にさしめ」。「世の中には―もいる」「―な趣味」
②好奇心が強く、新奇なことを好むこと。また、その人。ものごのみ。好事こうず。狂言、察化「お―をなさるる体じやが」。「―にもわざわざ見に行く」
⇒ものずき‐しゃ【物好者】
ものずき‐しゃ【物好者】
好事家こうずか。狂言、萩大名「亭主は―と見えた」
⇒もの‐ずき【物好き・物数奇】
もの‐すご・い【物凄い】
〔形〕[文]ものすご・し(ク)
①何となく気味がわるい。また、何となくさびしい。好色一代男1「次第に月さへ―・く、『一羽の声はつまなし鳥か』となほ淋しく」
②非常におそろしい。「―・い形相ぎょうそう」
③非常に際立っている。はなはだしい。「―・い人出」「―・く腹が立つ」
もの‐すさま・じ【物凄じ】
〔形シク〕
物事に興味も感じられない。なんとなくさびしい。荒涼とした心境である。源氏物語賢木「今よりはかくこそはと思ひやられて―・じくなむ」
もの・する【物する】
〔他サ変〕[文]もの・す(サ変)
ある動作をする。ある物事を行う。「言う」「食べる」「書く」など種々の動作を婉曲にいう語。源氏物語桐壺「宮仕への本意深く―・したりしよろこびは」。「俳句を―・する」
モノ‐セックス
(和製語mono sex)風俗や生活において男女の区別がないこと。ユニセックス。
もの‐ぞ
(形式名詞モノに助詞ゾの付いたもの。古くは清音)
①断定の意を表す。…ものだ。万葉集12「紫は灰さすものそ」
②強意を表す。…にちがいない。万葉集11「秋風の立ち来る時に物思ふものそ」
もの‐ぞこない【物損い】‥ゾコナヒ
物事をきずつけ、そこなうこと。興をさますこと。枕草子83「袿姿うちきすがたにてゐたるこそ―にて口惜しけれ」
モノタイプ【Monotype】
キーボード・文字盤の操作によって1字ずつの活字を自動的に鋳造植字する機械。商品名。
もの‐だくみ【物工・物匠】
物を作ることを職とする人。工匠。
もの‐たしなみ【物嗜み】
物事に嗜みのあること。狂言、岡太夫「―な人ぢや程にさうもあらう」
もの‐たち【物断ち】
神仏に願がんをかけるなどで、ある飲食物を断ってとらないこと。断物たちものをすること。
もの‐たち【物裁ち】
①布帛を裁つこと。転じて、裁縫。源氏物語野分「―などするねび御達ごたち」
②「ものたちがたな」の略。
⇒ものたち‐がたな【物裁ち刀】
ものたち‐がたな【物裁ち刀】
(→)裁物庖丁たちものぼうちょうに同じ。〈倭名類聚鈔14〉
⇒もの‐たち【物裁ち】
もの‐だね【物種】
①物のもととなるもの。材料。ものざね。ものしろ。狂言、武悪「命が―ぢや」。「命あっての―」
②草木の種。特に野菜・草花の種。たねもの。〈[季]春〉。「―の袋ぬらしつ春の雨」(蕪村)
⇒物種は盗まれず
⇒物種蒔く
もの‐ごころ【物心】
人情・世態などを理解する心。「―がつく」
もの‐こころづきな・し【物心付きなし】
〔形シク〕
何となく気に入らない。源氏物語真木柱「―・き御けしき絶えず」
もの‐こころぼそ・し【物心細し】
〔形ク〕
何となく心細い。源氏物語明石「重くならせ給ひて―・く思されければ」
も‐の‐こし【裳の腰】
裳の腰帯。源氏物語宿木「三重がさねの唐衣、―もみなけぢめあるべし」
もの‐ごし【物越し】
(几帳・すだれなど)物を隔てていること。伊勢物語「―に対面して」
もの‐ごし【物腰】
①物のいいぶり。ことばつき。好色一代女1「―程かはいらしきはなし」
②身のこなし方。態度。好色一代男3「色白く髪うるはしく―やさしく」。「品のよい―」
もの‐ごと【物事】
物と事。一切の事柄。事物。「―には限度がある」「―を苦にしない」
もの‐ごと‐に【物毎に】
それぞれの物に。物のあるたびごとに。ことごとに。中務内侍日記「―面白きこと限りなし」
もの‐ごのみ【物好み】
ある種の物事をえりごのみすること。源氏物語梅枝「―し艶えんがりおはするみこにて」
もの‐ごり【物懲り】
物事にこりること。源氏物語夕顔「危かりし―に」
もの‐ごわ・し【物強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
かたくるしいさまである。うちとけないさまである。源氏物語若紫「―・きさまし給へれば」
もの‐さし【物差し・物指し】
物の長さを差しはかる道具。直尺・曲尺・巻尺など。直尺は竹・鉄・セルロイド・プラスチックなどで細長く作り、長さの単位の目盛を付けたもの。さし。尺しゃく。転じて、物の価値をはかる基準。「かの人物たるや、世間一般の―でははかれない」
もの‐さた【物沙汰】
訴訟などを受理して裁くこと。
もの‐さだめ【物定め】
物事のよしあしを判定すること。しなさだめ。源氏物語帚木「馬の頭、―の博士になりて」
もの‐ざね【物実】
(→)物種ものだねに同じ。古事記上「三柱の女子は―汝が物に因りて成れり」
もの‐さびし・い【物淋しい】
〔形〕[文]ものさび・し(シク)
何となく淋しい。うらさびしい。源氏物語橋姫「宮のうち―・しくのみなりまさる」
もの‐さ・びる【物寂びる】
〔自上一〕[文]ものさ・ぶ(上二)
①どことなくすさび衰える。謡曲、夜討曾我「われら兄弟が幕の内ほど―・びたるは候はじ」
②古びて趣がある。十訓抄「いと―・びたる家のすのこの下に遣水の音たえだえ聞えて」
もの‐さわがし・い【物騒がしい】
〔形〕[文]ものさわが・し(シク)
①物音がして騒がしい。源氏物語末摘花「遊びののしり給ふに、―・しけれど」
②世の中が穏やかでない。物騒である。太平記3「―・しく候ふ間、夜討や忍び入り候はんずらん」。「―・い世相」
③気が早い。せっかちである。平家物語2「入道腹の立ちのままに―・しき事し給ひては」
もの‐さわ‐に【物多に】‥サハニ
〔枕〕
物が多い意で、「大宅おおやけ」にかかる。武烈紀「―大宅過ぎ」
もの‐し【物仕・物師】
①物事をよく心得てする人。巧者な人。落窪物語1「いみじき―ぞ、まろは」
②物事を手早く整える人。世事に馴れた人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「長者もさすが―にて」
③裁縫女。世間胸算用2「内義に腰元・中居女・―を添へて」
もの・し【物し】
〔形シク〕
物々しく厭わしい。気障りである。不愉快だ。大和物語「人もなしと思ひつるに―・しきさまをみえぬることとおもひて」
もの‐しずか【物静か】‥シヅカ
①何となくしずかなさま。「―な夜」
②言語・動作などのおちついて穏やかなさま。「―な態度」「―に語る」
もの‐じたい【物自体】
〔哲〕(Ding an sich ドイツ)カントの哲学で、認識主観に現れた現象としての物ではなくて、認識主観とは独立にそれ自体として存在すると考えられた物。経験の彼方にありながら、現象の究極原因・真実在と考えられるもの。感官を触発することによって認識の素材としての感覚を生み出す。物自体は、考えることはできても認識することはできない。↔現象
もの‐しらず【物知らず】
物事を知らないこと。物の道理をわきまえないこと。また、その人。わからず屋。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―と縁を組み」
もの‐しり【物知り・物識り】
①ひろく物事を知っていること。博識。また、その人。
②(秋田県や奄美諸島・沖縄で)祈祷や占いを職とする者。
⇒ものしり‐がお【物知り顔】
⇒ものしり‐だて【物識り立て】
ものしり‐がお【物知り顔】‥ガホ
物事を知っているような顔つき。
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
ものしり‐だて【物識り立て】
物識りの風をすること。知ったかぶり。狂言、右流左止うるさし「いらぬ―をいうて」
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
もの‐しろ【物代】
物のもととなるもの。材料。物実ものざね。物種ものだね。〈崇神紀訓注〉
もの・す【物す】
[一]〔自サ変〕
「居る」「行く」などの動作を婉曲えんきょくにいう語。源氏物語夕顔「そこに―・する程ならば此処に来べき由」
[二]〔他サ変〕
⇒ものする(サ変)
もの‐ずき【物好き・物数奇】
①特殊の物事を好むこと。また、その性質・人。狂言、棒縛「それはわごりよの―にさしめ」。「世の中には―もいる」「―な趣味」
②好奇心が強く、新奇なことを好むこと。また、その人。ものごのみ。好事こうず。狂言、察化「お―をなさるる体じやが」。「―にもわざわざ見に行く」
⇒ものずき‐しゃ【物好者】
ものずき‐しゃ【物好者】
好事家こうずか。狂言、萩大名「亭主は―と見えた」
⇒もの‐ずき【物好き・物数奇】
もの‐すご・い【物凄い】
〔形〕[文]ものすご・し(ク)
①何となく気味がわるい。また、何となくさびしい。好色一代男1「次第に月さへ―・く、『一羽の声はつまなし鳥か』となほ淋しく」
②非常におそろしい。「―・い形相ぎょうそう」
③非常に際立っている。はなはだしい。「―・い人出」「―・く腹が立つ」
もの‐すさま・じ【物凄じ】
〔形シク〕
物事に興味も感じられない。なんとなくさびしい。荒涼とした心境である。源氏物語賢木「今よりはかくこそはと思ひやられて―・じくなむ」
もの・する【物する】
〔他サ変〕[文]もの・す(サ変)
ある動作をする。ある物事を行う。「言う」「食べる」「書く」など種々の動作を婉曲にいう語。源氏物語桐壺「宮仕への本意深く―・したりしよろこびは」。「俳句を―・する」
モノ‐セックス
(和製語mono sex)風俗や生活において男女の区別がないこと。ユニセックス。
もの‐ぞ
(形式名詞モノに助詞ゾの付いたもの。古くは清音)
①断定の意を表す。…ものだ。万葉集12「紫は灰さすものそ」
②強意を表す。…にちがいない。万葉集11「秋風の立ち来る時に物思ふものそ」
もの‐ぞこない【物損い】‥ゾコナヒ
物事をきずつけ、そこなうこと。興をさますこと。枕草子83「袿姿うちきすがたにてゐたるこそ―にて口惜しけれ」
モノタイプ【Monotype】
キーボード・文字盤の操作によって1字ずつの活字を自動的に鋳造植字する機械。商品名。
もの‐だくみ【物工・物匠】
物を作ることを職とする人。工匠。
もの‐たしなみ【物嗜み】
物事に嗜みのあること。狂言、岡太夫「―な人ぢや程にさうもあらう」
もの‐たち【物断ち】
神仏に願がんをかけるなどで、ある飲食物を断ってとらないこと。断物たちものをすること。
もの‐たち【物裁ち】
①布帛を裁つこと。転じて、裁縫。源氏物語野分「―などするねび御達ごたち」
②「ものたちがたな」の略。
⇒ものたち‐がたな【物裁ち刀】
ものたち‐がたな【物裁ち刀】
(→)裁物庖丁たちものぼうちょうに同じ。〈倭名類聚鈔14〉
⇒もの‐たち【物裁ち】
もの‐だね【物種】
①物のもととなるもの。材料。ものざね。ものしろ。狂言、武悪「命が―ぢや」。「命あっての―」
②草木の種。特に野菜・草花の種。たねもの。〈[季]春〉。「―の袋ぬらしつ春の雨」(蕪村)
⇒物種は盗まれず
⇒物種蒔く
 もの‐ごころ【物心】
人情・世態などを理解する心。「―がつく」
もの‐こころづきな・し【物心付きなし】
〔形シク〕
何となく気に入らない。源氏物語真木柱「―・き御けしき絶えず」
もの‐こころぼそ・し【物心細し】
〔形ク〕
何となく心細い。源氏物語明石「重くならせ給ひて―・く思されければ」
も‐の‐こし【裳の腰】
裳の腰帯。源氏物語宿木「三重がさねの唐衣、―もみなけぢめあるべし」
もの‐ごし【物越し】
(几帳・すだれなど)物を隔てていること。伊勢物語「―に対面して」
もの‐ごし【物腰】
①物のいいぶり。ことばつき。好色一代女1「―程かはいらしきはなし」
②身のこなし方。態度。好色一代男3「色白く髪うるはしく―やさしく」。「品のよい―」
もの‐ごと【物事】
物と事。一切の事柄。事物。「―には限度がある」「―を苦にしない」
もの‐ごと‐に【物毎に】
それぞれの物に。物のあるたびごとに。ことごとに。中務内侍日記「―面白きこと限りなし」
もの‐ごのみ【物好み】
ある種の物事をえりごのみすること。源氏物語梅枝「―し艶えんがりおはするみこにて」
もの‐ごり【物懲り】
物事にこりること。源氏物語夕顔「危かりし―に」
もの‐ごわ・し【物強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
かたくるしいさまである。うちとけないさまである。源氏物語若紫「―・きさまし給へれば」
もの‐さし【物差し・物指し】
物の長さを差しはかる道具。直尺・曲尺・巻尺など。直尺は竹・鉄・セルロイド・プラスチックなどで細長く作り、長さの単位の目盛を付けたもの。さし。尺しゃく。転じて、物の価値をはかる基準。「かの人物たるや、世間一般の―でははかれない」
もの‐さた【物沙汰】
訴訟などを受理して裁くこと。
もの‐さだめ【物定め】
物事のよしあしを判定すること。しなさだめ。源氏物語帚木「馬の頭、―の博士になりて」
もの‐ざね【物実】
(→)物種ものだねに同じ。古事記上「三柱の女子は―汝が物に因りて成れり」
もの‐さびし・い【物淋しい】
〔形〕[文]ものさび・し(シク)
何となく淋しい。うらさびしい。源氏物語橋姫「宮のうち―・しくのみなりまさる」
もの‐さ・びる【物寂びる】
〔自上一〕[文]ものさ・ぶ(上二)
①どことなくすさび衰える。謡曲、夜討曾我「われら兄弟が幕の内ほど―・びたるは候はじ」
②古びて趣がある。十訓抄「いと―・びたる家のすのこの下に遣水の音たえだえ聞えて」
もの‐さわがし・い【物騒がしい】
〔形〕[文]ものさわが・し(シク)
①物音がして騒がしい。源氏物語末摘花「遊びののしり給ふに、―・しけれど」
②世の中が穏やかでない。物騒である。太平記3「―・しく候ふ間、夜討や忍び入り候はんずらん」。「―・い世相」
③気が早い。せっかちである。平家物語2「入道腹の立ちのままに―・しき事し給ひては」
もの‐さわ‐に【物多に】‥サハニ
〔枕〕
物が多い意で、「大宅おおやけ」にかかる。武烈紀「―大宅過ぎ」
もの‐し【物仕・物師】
①物事をよく心得てする人。巧者な人。落窪物語1「いみじき―ぞ、まろは」
②物事を手早く整える人。世事に馴れた人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「長者もさすが―にて」
③裁縫女。世間胸算用2「内義に腰元・中居女・―を添へて」
もの・し【物し】
〔形シク〕
物々しく厭わしい。気障りである。不愉快だ。大和物語「人もなしと思ひつるに―・しきさまをみえぬることとおもひて」
もの‐しずか【物静か】‥シヅカ
①何となくしずかなさま。「―な夜」
②言語・動作などのおちついて穏やかなさま。「―な態度」「―に語る」
もの‐じたい【物自体】
〔哲〕(Ding an sich ドイツ)カントの哲学で、認識主観に現れた現象としての物ではなくて、認識主観とは独立にそれ自体として存在すると考えられた物。経験の彼方にありながら、現象の究極原因・真実在と考えられるもの。感官を触発することによって認識の素材としての感覚を生み出す。物自体は、考えることはできても認識することはできない。↔現象
もの‐しらず【物知らず】
物事を知らないこと。物の道理をわきまえないこと。また、その人。わからず屋。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―と縁を組み」
もの‐しり【物知り・物識り】
①ひろく物事を知っていること。博識。また、その人。
②(秋田県や奄美諸島・沖縄で)祈祷や占いを職とする者。
⇒ものしり‐がお【物知り顔】
⇒ものしり‐だて【物識り立て】
ものしり‐がお【物知り顔】‥ガホ
物事を知っているような顔つき。
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
ものしり‐だて【物識り立て】
物識りの風をすること。知ったかぶり。狂言、右流左止うるさし「いらぬ―をいうて」
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
もの‐しろ【物代】
物のもととなるもの。材料。物実ものざね。物種ものだね。〈崇神紀訓注〉
もの・す【物す】
[一]〔自サ変〕
「居る」「行く」などの動作を婉曲えんきょくにいう語。源氏物語夕顔「そこに―・する程ならば此処に来べき由」
[二]〔他サ変〕
⇒ものする(サ変)
もの‐ずき【物好き・物数奇】
①特殊の物事を好むこと。また、その性質・人。狂言、棒縛「それはわごりよの―にさしめ」。「世の中には―もいる」「―な趣味」
②好奇心が強く、新奇なことを好むこと。また、その人。ものごのみ。好事こうず。狂言、察化「お―をなさるる体じやが」。「―にもわざわざ見に行く」
⇒ものずき‐しゃ【物好者】
ものずき‐しゃ【物好者】
好事家こうずか。狂言、萩大名「亭主は―と見えた」
⇒もの‐ずき【物好き・物数奇】
もの‐すご・い【物凄い】
〔形〕[文]ものすご・し(ク)
①何となく気味がわるい。また、何となくさびしい。好色一代男1「次第に月さへ―・く、『一羽の声はつまなし鳥か』となほ淋しく」
②非常におそろしい。「―・い形相ぎょうそう」
③非常に際立っている。はなはだしい。「―・い人出」「―・く腹が立つ」
もの‐すさま・じ【物凄じ】
〔形シク〕
物事に興味も感じられない。なんとなくさびしい。荒涼とした心境である。源氏物語賢木「今よりはかくこそはと思ひやられて―・じくなむ」
もの・する【物する】
〔他サ変〕[文]もの・す(サ変)
ある動作をする。ある物事を行う。「言う」「食べる」「書く」など種々の動作を婉曲にいう語。源氏物語桐壺「宮仕への本意深く―・したりしよろこびは」。「俳句を―・する」
モノ‐セックス
(和製語mono sex)風俗や生活において男女の区別がないこと。ユニセックス。
もの‐ぞ
(形式名詞モノに助詞ゾの付いたもの。古くは清音)
①断定の意を表す。…ものだ。万葉集12「紫は灰さすものそ」
②強意を表す。…にちがいない。万葉集11「秋風の立ち来る時に物思ふものそ」
もの‐ぞこない【物損い】‥ゾコナヒ
物事をきずつけ、そこなうこと。興をさますこと。枕草子83「袿姿うちきすがたにてゐたるこそ―にて口惜しけれ」
モノタイプ【Monotype】
キーボード・文字盤の操作によって1字ずつの活字を自動的に鋳造植字する機械。商品名。
もの‐だくみ【物工・物匠】
物を作ることを職とする人。工匠。
もの‐たしなみ【物嗜み】
物事に嗜みのあること。狂言、岡太夫「―な人ぢや程にさうもあらう」
もの‐たち【物断ち】
神仏に願がんをかけるなどで、ある飲食物を断ってとらないこと。断物たちものをすること。
もの‐たち【物裁ち】
①布帛を裁つこと。転じて、裁縫。源氏物語野分「―などするねび御達ごたち」
②「ものたちがたな」の略。
⇒ものたち‐がたな【物裁ち刀】
ものたち‐がたな【物裁ち刀】
(→)裁物庖丁たちものぼうちょうに同じ。〈倭名類聚鈔14〉
⇒もの‐たち【物裁ち】
もの‐だね【物種】
①物のもととなるもの。材料。ものざね。ものしろ。狂言、武悪「命が―ぢや」。「命あっての―」
②草木の種。特に野菜・草花の種。たねもの。〈[季]春〉。「―の袋ぬらしつ春の雨」(蕪村)
⇒物種は盗まれず
⇒物種蒔く
もの‐ごころ【物心】
人情・世態などを理解する心。「―がつく」
もの‐こころづきな・し【物心付きなし】
〔形シク〕
何となく気に入らない。源氏物語真木柱「―・き御けしき絶えず」
もの‐こころぼそ・し【物心細し】
〔形ク〕
何となく心細い。源氏物語明石「重くならせ給ひて―・く思されければ」
も‐の‐こし【裳の腰】
裳の腰帯。源氏物語宿木「三重がさねの唐衣、―もみなけぢめあるべし」
もの‐ごし【物越し】
(几帳・すだれなど)物を隔てていること。伊勢物語「―に対面して」
もの‐ごし【物腰】
①物のいいぶり。ことばつき。好色一代女1「―程かはいらしきはなし」
②身のこなし方。態度。好色一代男3「色白く髪うるはしく―やさしく」。「品のよい―」
もの‐ごと【物事】
物と事。一切の事柄。事物。「―には限度がある」「―を苦にしない」
もの‐ごと‐に【物毎に】
それぞれの物に。物のあるたびごとに。ことごとに。中務内侍日記「―面白きこと限りなし」
もの‐ごのみ【物好み】
ある種の物事をえりごのみすること。源氏物語梅枝「―し艶えんがりおはするみこにて」
もの‐ごり【物懲り】
物事にこりること。源氏物語夕顔「危かりし―に」
もの‐ごわ・し【物強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
かたくるしいさまである。うちとけないさまである。源氏物語若紫「―・きさまし給へれば」
もの‐さし【物差し・物指し】
物の長さを差しはかる道具。直尺・曲尺・巻尺など。直尺は竹・鉄・セルロイド・プラスチックなどで細長く作り、長さの単位の目盛を付けたもの。さし。尺しゃく。転じて、物の価値をはかる基準。「かの人物たるや、世間一般の―でははかれない」
もの‐さた【物沙汰】
訴訟などを受理して裁くこと。
もの‐さだめ【物定め】
物事のよしあしを判定すること。しなさだめ。源氏物語帚木「馬の頭、―の博士になりて」
もの‐ざね【物実】
(→)物種ものだねに同じ。古事記上「三柱の女子は―汝が物に因りて成れり」
もの‐さびし・い【物淋しい】
〔形〕[文]ものさび・し(シク)
何となく淋しい。うらさびしい。源氏物語橋姫「宮のうち―・しくのみなりまさる」
もの‐さ・びる【物寂びる】
〔自上一〕[文]ものさ・ぶ(上二)
①どことなくすさび衰える。謡曲、夜討曾我「われら兄弟が幕の内ほど―・びたるは候はじ」
②古びて趣がある。十訓抄「いと―・びたる家のすのこの下に遣水の音たえだえ聞えて」
もの‐さわがし・い【物騒がしい】
〔形〕[文]ものさわが・し(シク)
①物音がして騒がしい。源氏物語末摘花「遊びののしり給ふに、―・しけれど」
②世の中が穏やかでない。物騒である。太平記3「―・しく候ふ間、夜討や忍び入り候はんずらん」。「―・い世相」
③気が早い。せっかちである。平家物語2「入道腹の立ちのままに―・しき事し給ひては」
もの‐さわ‐に【物多に】‥サハニ
〔枕〕
物が多い意で、「大宅おおやけ」にかかる。武烈紀「―大宅過ぎ」
もの‐し【物仕・物師】
①物事をよく心得てする人。巧者な人。落窪物語1「いみじき―ぞ、まろは」
②物事を手早く整える人。世事に馴れた人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「長者もさすが―にて」
③裁縫女。世間胸算用2「内義に腰元・中居女・―を添へて」
もの・し【物し】
〔形シク〕
物々しく厭わしい。気障りである。不愉快だ。大和物語「人もなしと思ひつるに―・しきさまをみえぬることとおもひて」
もの‐しずか【物静か】‥シヅカ
①何となくしずかなさま。「―な夜」
②言語・動作などのおちついて穏やかなさま。「―な態度」「―に語る」
もの‐じたい【物自体】
〔哲〕(Ding an sich ドイツ)カントの哲学で、認識主観に現れた現象としての物ではなくて、認識主観とは独立にそれ自体として存在すると考えられた物。経験の彼方にありながら、現象の究極原因・真実在と考えられるもの。感官を触発することによって認識の素材としての感覚を生み出す。物自体は、考えることはできても認識することはできない。↔現象
もの‐しらず【物知らず】
物事を知らないこと。物の道理をわきまえないこと。また、その人。わからず屋。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―と縁を組み」
もの‐しり【物知り・物識り】
①ひろく物事を知っていること。博識。また、その人。
②(秋田県や奄美諸島・沖縄で)祈祷や占いを職とする者。
⇒ものしり‐がお【物知り顔】
⇒ものしり‐だて【物識り立て】
ものしり‐がお【物知り顔】‥ガホ
物事を知っているような顔つき。
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
ものしり‐だて【物識り立て】
物識りの風をすること。知ったかぶり。狂言、右流左止うるさし「いらぬ―をいうて」
⇒もの‐しり【物知り・物識り】
もの‐しろ【物代】
物のもととなるもの。材料。物実ものざね。物種ものだね。〈崇神紀訓注〉
もの・す【物す】
[一]〔自サ変〕
「居る」「行く」などの動作を婉曲えんきょくにいう語。源氏物語夕顔「そこに―・する程ならば此処に来べき由」
[二]〔他サ変〕
⇒ものする(サ変)
もの‐ずき【物好き・物数奇】
①特殊の物事を好むこと。また、その性質・人。狂言、棒縛「それはわごりよの―にさしめ」。「世の中には―もいる」「―な趣味」
②好奇心が強く、新奇なことを好むこと。また、その人。ものごのみ。好事こうず。狂言、察化「お―をなさるる体じやが」。「―にもわざわざ見に行く」
⇒ものずき‐しゃ【物好者】
ものずき‐しゃ【物好者】
好事家こうずか。狂言、萩大名「亭主は―と見えた」
⇒もの‐ずき【物好き・物数奇】
もの‐すご・い【物凄い】
〔形〕[文]ものすご・し(ク)
①何となく気味がわるい。また、何となくさびしい。好色一代男1「次第に月さへ―・く、『一羽の声はつまなし鳥か』となほ淋しく」
②非常におそろしい。「―・い形相ぎょうそう」
③非常に際立っている。はなはだしい。「―・い人出」「―・く腹が立つ」
もの‐すさま・じ【物凄じ】
〔形シク〕
物事に興味も感じられない。なんとなくさびしい。荒涼とした心境である。源氏物語賢木「今よりはかくこそはと思ひやられて―・じくなむ」
もの・する【物する】
〔他サ変〕[文]もの・す(サ変)
ある動作をする。ある物事を行う。「言う」「食べる」「書く」など種々の動作を婉曲にいう語。源氏物語桐壺「宮仕への本意深く―・したりしよろこびは」。「俳句を―・する」
モノ‐セックス
(和製語mono sex)風俗や生活において男女の区別がないこと。ユニセックス。
もの‐ぞ
(形式名詞モノに助詞ゾの付いたもの。古くは清音)
①断定の意を表す。…ものだ。万葉集12「紫は灰さすものそ」
②強意を表す。…にちがいない。万葉集11「秋風の立ち来る時に物思ふものそ」
もの‐ぞこない【物損い】‥ゾコナヒ
物事をきずつけ、そこなうこと。興をさますこと。枕草子83「袿姿うちきすがたにてゐたるこそ―にて口惜しけれ」
モノタイプ【Monotype】
キーボード・文字盤の操作によって1字ずつの活字を自動的に鋳造植字する機械。商品名。
もの‐だくみ【物工・物匠】
物を作ることを職とする人。工匠。
もの‐たしなみ【物嗜み】
物事に嗜みのあること。狂言、岡太夫「―な人ぢや程にさうもあらう」
もの‐たち【物断ち】
神仏に願がんをかけるなどで、ある飲食物を断ってとらないこと。断物たちものをすること。
もの‐たち【物裁ち】
①布帛を裁つこと。転じて、裁縫。源氏物語野分「―などするねび御達ごたち」
②「ものたちがたな」の略。
⇒ものたち‐がたな【物裁ち刀】
ものたち‐がたな【物裁ち刀】
(→)裁物庖丁たちものぼうちょうに同じ。〈倭名類聚鈔14〉
⇒もの‐たち【物裁ち】
もの‐だね【物種】
①物のもととなるもの。材料。ものざね。ものしろ。狂言、武悪「命が―ぢや」。「命あっての―」
②草木の種。特に野菜・草花の種。たねもの。〈[季]春〉。「―の袋ぬらしつ春の雨」(蕪村)
⇒物種は盗まれず
⇒物種蒔く
ものくさたろう【物くさ太郎】‥ラウ🔗⭐🔉
ものくさたろう【物くさ太郎】‥ラウ
御伽草子23編の一つ。1冊。成立は室町時代か。信濃国の物臭太郎という無精者ぶしょうものが歌才によって宮中に召され、貴族の出身で善光寺如来の申子もうしごとわかって出世するという筋。「おたがの本地」ともいう。
→文献資料[物くさ太郎]
もの‐ぐねり【物ぐねり】🔗⭐🔉
もの‐ぐねり【物ぐねり】
意地悪をすること。また、すねること。愚痴。松の葉1「ともすれば何ぞよそなたの―」
もの‐ぐら・し【物暗し】🔗⭐🔉
もの‐ぐら・し【物暗し】
〔形ク〕
何となく暗い。うすぐらい。能因本枕草子物くらうなりて「―・うなりて文字も書かれずなりにたり」
もの‐けざやか【物けざやか】🔗⭐🔉
もの‐けざやか【物けざやか】
はっきりしているさま。栄華物語日蔭のかづら「更衣ころもがえなどの有様も―に」
もの‐ごし【物越し】🔗⭐🔉
もの‐ごし【物越し】
(几帳・すだれなど)物を隔てていること。伊勢物語「―に対面して」
もの・し【物し】🔗⭐🔉
もの・し【物し】
〔形シク〕
物々しく厭わしい。気障りである。不愉快だ。大和物語「人もなしと思ひつるに―・しきさまをみえぬることとおもひて」
もの・す【物す】🔗⭐🔉
もの・す【物す】
[一]〔自サ変〕
「居る」「行く」などの動作を婉曲えんきょくにいう語。源氏物語夕顔「そこに―・する程ならば此処に来べき由」
[二]〔他サ変〕
⇒ものする(サ変)
もの・する【物する】🔗⭐🔉
もの・する【物する】
〔他サ変〕[文]もの・す(サ変)
ある動作をする。ある物事を行う。「言う」「食べる」「書く」など種々の動作を婉曲にいう語。源氏物語桐壺「宮仕への本意深く―・したりしよろこびは」。「俳句を―・する」
もの‐どお【物遠】‥ドホ🔗⭐🔉
もの‐どお【物遠】‥ドホ
疎遠。無沙汰。狂言、素襖落「其の後はお―にこそござれ」
もの‐どお・し【物遠し】‥ドホシ🔗⭐🔉
もの‐どお・し【物遠し】‥ドホシ
〔形ク〕
①物事がとおい。離れている。源氏物語須磨「かやうの人もおのづから―・からでほの見たてまつる御さまかたちを」
②疎遠である。他人行儀である。源氏物語紅葉賀「―・きさましておはするに」
○物ともせずものともせず🔗⭐🔉
○物ともせずものともせず
困難や障害を何とも思わない。問題としない。「敵の攻撃を―突進する」
⇒もの【物】
モノドラマ【monodrama】
一人の俳優が演ずる劇。また、ある人物の内面の動きを象徴的に表現する劇。ロシアのエウレイノフ(N. Evreinov1879〜1953)が唱え、代表作は「心の劇場」。独演劇。独白劇。ひとり芝居。
もの‐とり【物取り】
人の物を盗み取ること。また、盗人。今昔物語集29「盗人の―に入りたるか」
もの‐なげか・し【物嘆かし】
〔形シク〕
なんとなく嘆かわしい。源氏物語明石「―・しうてうちとけぬ心ざまを」
もの‐なげき【物嘆き】
悲嘆。心配。栄華物語浦々別「公家おおやけ・私、今の―にして」
もの‐なつか・し【物懐かし】
〔形シク〕
何となく懐かしい。
もの‐なら【物なら】
(モノに指定の助動詞ナリの未然形の付いたもの)
①(物でいうならの意)どうせ。せいぜい。浄瑠璃、大経師昔暦「―たつた二十日の間お気遣なされますな」
②(連体形に付いて)仮定の条件を表す。また、不可能と思われる前提や、「う」「よう」を受けて重大な結果をもたらす場合の前提につかう。…なら。もんなら。「やれる―やってみな」「そんなことしよう―大変なことになる」
もの‐ならい【物習い】‥ナラヒ
物事をならうこと。学問すること。学問。公任集「三井寺に―に入り給ふとて」
もの‐なら【物なら】🔗⭐🔉
もの‐なら【物なら】
(モノに指定の助動詞ナリの未然形の付いたもの)
①(物でいうならの意)どうせ。せいぜい。浄瑠璃、大経師昔暦「―たつた二十日の間お気遣なされますな」
②(連体形に付いて)仮定の条件を表す。また、不可能と思われる前提や、「う」「よう」を受けて重大な結果をもたらす場合の前提につかう。…なら。もんなら。「やれる―やってみな」「そんなことしよう―大変なことになる」
○物ならずものならず🔗⭐🔉
○物ならずものならず
たいしたことではない。問題にならない。土佐日記「今は和泉国に来ぬれば、海賊―」。「箱根の山は天下の険、函谷関も―」
⇒もの【物】
もの‐なら‐ず【物ならず】
⇒もの(物)(成句)
もの‐ならわし【物習わし】‥ナラハシ
物事をならわせること。学問させること。古今和歌集旅「仲麿をもろこしに―に遣はしたりけるに」
もの‐なり【物成】
①田畑から産出した農作物。
②収穫の一部で納める年貢。取箇とりか。成箇なりか。本年貢。江戸時代には、小物成こものなり(雑税)に対して、特に本途ほんと物成(地租)を指した。
③領主や家臣の禄高の基礎である1年の年貢米の収入高。
もの‐なれ【物馴れ】
物事に馴れていること。熟練すること。世故せこにたけていること。源氏物語横笛「あざれがましうすきずきしき気色などに―などもし侍らぬに」
もの‐な・れる【物馴れる】
〔自下一〕[文]ものな・る(下二)
①物事に馴れて巧みになる。熟練する。世故せこにたける。「―・れた手さばき」
②馴れ馴れしくする。源氏物語浮舟「―・れても、え申し出でず」
もの‐なら‐ず【物ならず】🔗⭐🔉
もの‐なら‐ず【物ならず】
⇒もの(物)(成句)
○物に当たるものにあたる🔗⭐🔉
○物に当たるものにあたる
物につき当たってうろうろする。あわてるさまにいう。源氏物語葵「殿の内の人、物にぞあたる」
⇒もの【物】
○物に掛かるものにかかる🔗⭐🔉
○物に掛かるものにかかる
何事にもうるさく口を出す。あれやこれやに手を出す。浮世草子、新可笑記「夫婦いさかひのことまでもあつかひにかかり…―を」
⇒もの【物】
もの‐にくみ【物悪み】
物事をにくむこと。憎悪。嫉妬。源氏物語澪標「―はいつ習ふべきにかと怨じ給へば」
もの‐にくみ【物悪み】🔗⭐🔉
もの‐にくみ【物悪み】
物事をにくむこと。憎悪。嫉妬。源氏物語澪標「―はいつ習ふべきにかと怨じ給へば」
○物にするものにする
自分の所有物にする。目的を達する。自分の思い通りの結果や状態にする。狂言、萩大名「あれをものにせう」。「英会話を―」
⇒もの【物】
○物になるものになる
ちゃんとしたものになる。一かどのものとなる。自分の意図したようになる。「弟だけは物になって欲しい」「てんで物にならない」
⇒もの【物】
○物に似ずものににず
くらべるものがない。たとえようもない。大和物語「かなしきこと―」
⇒もの【物】
○物には七十五度ものにはしちじゅうごど
物には限度があるの意。世間胸算用4「―とて必ずあらはるる時節あり」
⇒もの【物】
○物にもあらずものにもあらず
それと認めるべき程のものでもない。何でもない。気にかけるに及ばない。源氏物語桐壺「右のおとどの御いきほひは、―おされ給へり」
⇒もの【物】
○物にするものにする🔗⭐🔉
○物にするものにする
自分の所有物にする。目的を達する。自分の思い通りの結果や状態にする。狂言、萩大名「あれをものにせう」。「英会話を―」
⇒もの【物】
○物になるものになる🔗⭐🔉
○物になるものになる
ちゃんとしたものになる。一かどのものとなる。自分の意図したようになる。「弟だけは物になって欲しい」「てんで物にならない」
⇒もの【物】
○物に似ずものににず🔗⭐🔉
○物に似ずものににず
くらべるものがない。たとえようもない。大和物語「かなしきこと―」
⇒もの【物】
○物には七十五度ものにはしちじゅうごど🔗⭐🔉
○物には七十五度ものにはしちじゅうごど
物には限度があるの意。世間胸算用4「―とて必ずあらはるる時節あり」
⇒もの【物】
○物にもあらずものにもあらず🔗⭐🔉
○物にもあらずものにもあらず
それと認めるべき程のものでもない。何でもない。気にかけるに及ばない。源氏物語桐壺「右のおとどの御いきほひは、―おされ給へり」
⇒もの【物】
ものによせて‐おもいをのぶる‐うた【寄物陳思歌】‥オモヒ‥
万葉集で相聞そうもんの小分類。表現手法による部立の一つ。直接ではなく、ある物事に寄せて自分の心情を述べた歌。巻11「をとめらを袖振る山の瑞垣みずかきの久しき時ゆ思ひけり吾は」はその例。→正述心緒歌ただにおもいをのぶるうた
もの‐ぬい【物縫い】‥ヌヒ
裁縫をすること。また、その人。源氏物語早蕨「―いとなみつつ」
⇒ものぬい‐おんな【物縫い女】
ものぬい‐おんな【物縫い女】‥ヌヒヲンナ
裁縫を業とする女。
⇒もの‐ぬい【物縫い】
もの‐ぬし【物主】
①物のもちぬし。物持。
②(→)物頭ものがしら2に同じ。天正記「羽柴孫七郎秀次、江州の―として」
もの‐ねがい【物願い】‥ネガヒ
物事を願うこと。また、その願い。宇津保物語藤原君「苦しげなる御―かな」
もの‐ねたみ【物妬み】
物事をねたむこと。何かと嫉妬すること。源氏物語若菜下「腹あしくて―打ちしたる」
もの‐ねんじ【物念じ】
物事を堪え忍ぶこと。こらえること。我慢。源氏物語浮舟「昔も今も―して」
もの‐の
(名詞モノに助詞ノの付いたもの)
[一](副詞的に用いて)たかだか。せいぜい。「―五分もすれば」
[二]〔助詞〕
(接続助詞)連体形に付いて、対立・矛盾する関係を示すのに用いる。…のであるが。ものから。ものながら。源氏物語夕顔「つれなくねたき―忘れがたきにおぼす」。「来るには来た―成果はなかった」「知らなかったとは言う―気の毒なことをした」「無事でよかった―気をつけなさい」
もの‐の‐あなた【物の彼方】
①物の向う側。
②来世。後の世。源氏物語鈴虫「―思ひ給へやらざりけるが」
もの‐の‐あわれ【物の哀れ】‥アハレ
①平安時代の文学およびそれを生んだ貴族生活の中心をなす理念。本居宣長が「源氏物語」を通して指摘。「もの」すなわち対象客観と、「あはれ」すなわち感情主観の一致する所に生ずる調和的情趣の世界。優美・繊細・沈静・観照的の理念。
②人生の機微やはかなさなどに触れた時に感ずる、しみじみとした情趣。「―を解する」
もの‐の‐かい【債】‥カヒ
借財。負債。持統紀「―負へる者」
もの‐の‐かず【物の数】
数えたてるほどのもの。多く打消の語を伴う。文鏡秘府論保延点「此の事を屑モノノカスニセず」。「―ではない」
もの‐の‐きこえ【物の聞え】
世間の噂。評判。源氏物語関屋「―に憚りて」
もの‐の‐ぐ【物の具】
①調度。道具。枕草子87「御―ども運び、いみじうさわがしきにあはせて」
②武具。具足ぐそく。甲冑。今昔物語集5「万の―・腹帯・手綱・鞦しりかい等」
③朝服。男子は束帯そくたい。女子は普通、唐衣・裳も・表着うわぎ・五衣いつつぎぬをつける礼装。建礼門院右京大夫集「宮の御―召したりし御さまなど」
もの‐の‐け【物の怪・物の気】
死霊・生霊などが祟たたること。また、その死霊・生霊。邪気。源氏物語葵「―いきすだまなどいふものおほく出で来て」。「―に取りつかれる」
⇒もののけ‐だ・つ【物の怪だつ】
もののけ‐だ・つ【物の怪だつ】
〔自四〕
物の怪が取りついたようにみえる。源氏物語浮舟「―・ちて悩み侍れば」
⇒もの‐の‐け【物の怪・物の気】
もの‐の‐あなた【物の彼方】🔗⭐🔉
もの‐の‐あなた【物の彼方】
①物の向う側。
②来世。後の世。源氏物語鈴虫「―思ひ給へやらざりけるが」
もの‐の‐あわれ【物の哀れ】‥アハレ🔗⭐🔉
もの‐の‐あわれ【物の哀れ】‥アハレ
①平安時代の文学およびそれを生んだ貴族生活の中心をなす理念。本居宣長が「源氏物語」を通して指摘。「もの」すなわち対象客観と、「あはれ」すなわち感情主観の一致する所に生ずる調和的情趣の世界。優美・繊細・沈静・観照的の理念。
②人生の機微やはかなさなどに触れた時に感ずる、しみじみとした情趣。「―を解する」
もの‐の‐かず【物の数】🔗⭐🔉
もの‐の‐かず【物の数】
数えたてるほどのもの。多く打消の語を伴う。文鏡秘府論保延点「此の事を屑モノノカスニセず」。「―ではない」
もの‐の‐きこえ【物の聞え】🔗⭐🔉
もの‐の‐きこえ【物の聞え】
世間の噂。評判。源氏物語関屋「―に憚りて」
もの‐の‐ぐ【物の具】🔗⭐🔉
もの‐の‐ぐ【物の具】
①調度。道具。枕草子87「御―ども運び、いみじうさわがしきにあはせて」
②武具。具足ぐそく。甲冑。今昔物語集5「万の―・腹帯・手綱・鞦しりかい等」
③朝服。男子は束帯そくたい。女子は普通、唐衣・裳も・表着うわぎ・五衣いつつぎぬをつける礼装。建礼門院右京大夫集「宮の御―召したりし御さまなど」
もの‐の‐け【物の怪・物の気】🔗⭐🔉
もの‐の‐け【物の怪・物の気】
死霊・生霊などが祟たたること。また、その死霊・生霊。邪気。源氏物語葵「―いきすだまなどいふものおほく出で来て」。「―に取りつかれる」
⇒もののけ‐だ・つ【物の怪だつ】
もののけ‐だ・つ【物の怪だつ】🔗⭐🔉
もののけ‐だ・つ【物の怪だつ】
〔自四〕
物の怪が取りついたようにみえる。源氏物語浮舟「―・ちて悩み侍れば」
⇒もの‐の‐け【物の怪・物の気】
○物の先を折るもののさきをおる
出鼻をくじく。狂言、千鳥「そちの様に―様に云うてはならぬ」
⇒もの【物】
○物の先を折るもののさきをおる🔗⭐🔉
○物の先を折るもののさきをおる
出鼻をくじく。狂言、千鳥「そちの様に―様に云うてはならぬ」
⇒もの【物】
もの‐の‐さとし【物の諭し】
神仏のお告げ。また、天変地異などによる凶事の予兆。源氏物語薄雲「―しげくのどかならで」
もの‐の‐し【物の師】
ある学芸を専門とする人。源氏物語橋姫「雅楽寮うたづかさの―どもなどやうのすぐれたるを」
もの‐の‐さとし【物の諭し】🔗⭐🔉
もの‐の‐さとし【物の諭し】
神仏のお告げ。また、天変地異などによる凶事の予兆。源氏物語薄雲「―しげくのどかならで」
もの‐の‐し【物の師】🔗⭐🔉
もの‐の‐し【物の師】
ある学芸を専門とする人。源氏物語橋姫「雅楽寮うたづかさの―どもなどやうのすぐれたるを」
○物の上手もののじょうず
芸道の達人。源氏物語帚木「まことの―は様ことに見え分れ侍る」
⇒もの【物】
○物の上手もののじょうず🔗⭐🔉
○物の上手もののじょうず
芸道の達人。源氏物語帚木「まことの―は様ことに見え分れ侍る」
⇒もの【物】
もの‐のぞき【物覘き】
物事をのぞいて見ること。源氏物語夕顔「―の心もさめぬめり」
もの‐の‐ついで【物の序で】
他の物事を行う、そのついで。ことのついで。
もの‐の‐どうり【物の道理】‥ダウ‥
物事のあるべき筋道。
もの‐の‐な【物の名】
①物事の名称。ぶつめい。
②和歌や俳諧で、1首の中に物の名を他の語句に隠して詠むこと。「杣人そまびとは宮木ひくらし足ひきの山の山彦よびとよむなり」に「ひぐらし」を隠した類。隠題かくしだい。
もの‐の‐ね【物の音】
物のおと。特に楽器の音ね。音楽。源氏物語桐壺「心ことなる―をかき鳴らし」
もの‐の‐はじめ【物の始め】
物事の始め。特に縁組の始め。初縁。源氏物語若紫「たはぶれにても―にこの御事よ」
もの‐の‐はずみ【物の弾み】‥ハヅミ
その場のなりゆき。ことの勢い。「―でそう言ったまでだ」
もの‐の‐ふ【武士】
①上代、朝廷に仕えた官人。万葉集18「―の八十氏人も」
②武勇をもって仕え、戦陣に立つ武人。武者。つわもの。ぶし。宇津保物語俊蔭「―の寝しづまるを窺ひて」
⇒もののふ‐の【武士の】
もの‐の‐ふし【物の節】
近衛の舎人とねりその他の役人の中で雅楽の技能のあるもの。春日祭・賀茂祭などに奉仕。源氏物語松風「近衛づかさの名高き舎人、―どもなどさぶらふに」
もののふ‐の【武士の】
〔枕〕
「やそ(八十)」「宇治川」「磐瀬」「矢野」「弓削ゆげ」などにかかる。
⇒もの‐の‐ふ【武士】
もの‐の‐べ【物部】
①大和政権で、軍事・警察・裁判を担当した品部しなべ。
②律令制で、刑部省囚獄司・衛門府・東西市司いちのつかさに属し、刑罰を担当した下級官人。
もののべ【物部】
古代の大豪族。姓かばねは連むらじ。饒速日命にぎはやひのみことの子孫と称し、天皇の親衛軍を率い、連姓諸氏の中では大伴氏と共に最有力となって、族長は代々大連おおむらじに就任したが、6世紀半ば仏教受容に反対、大連の守屋は大臣の蘇我馬子および皇族らの連合軍と戦って敗死。律令時代には、一族の石上いそのかみ・榎井えのい氏らが朝廷に復帰。
⇒もののべ‐の‐おこし【物部尾輿】
⇒もののべ‐の‐もりや【物部守屋】
もののべ‐じんじゃ【物部神社】
島根県大田市川合町にある元国幣小社。祭神は宇摩志麻遅命うましまじのみことほか。石見いわみ国一の宮。
もののべ‐の‐おこし【物部尾輿】‥ヲ‥
欽明天皇朝の大連。任那みまなに対する政策をめぐって大連大伴金村を失脚させ、また日本に仏教伝来の際は蘇我稲目に反対し、排仏を主張したという。生没年未詳。
⇒もののべ【物部】
もののべ‐の‐もりや【物部守屋】
敏達・用明天皇朝の大連。尾輿の子。仏教を排斥して蘇我氏と争い、塔を壊し仏像を焼く。用明天皇の没後、穴穂部あなほべ皇子を奉じて兵を挙げたが、蘇我氏のために滅ぼされた。( 〜587)
⇒もののべ【物部】
もの‐の‐ほん【物の本】
本。書物。また、草紙に対して、然るべきことの書いてある本。学問的な本。梅暦「徒然をなぐさむ為の―」。「―に書いてある」
⇒もののほん‐みせ【物の本店】
もののほん‐みせ【物の本店】
書店。狂言、長光「是は―でござる」
⇒もの‐の‐ほん【物の本】
もの‐の‐まぎれ【物の紛れ】
①物事がごたごたすること。どさくさまぎれ。源氏物語賢木「―にも左の大臣の御有様ふと思しくらべられて」
②男女間の間違い。密会。源氏物語若菜下「心を交しそめ―多かりぬべきわざなり」
もの‐の‐みごと【物の見事】
あざやかなさま。みごとなさま。「―に合格する」「―にころんだ」
もの‐の‐め【物の芽】
いろいろな草木の芽。〈[季]春〉
もの‐の‐よう【物の用】
何かの役。薄雪物語「―に立たぬものは手かきなり」
もの‐は【もの派】
1960年代末から70年代初頭にかけて起こった美術動向。木・石・鉄などの物質や物体をインスタレーションに用いる美術家たちを指す。
もの‐の‐ついで【物の序で】🔗⭐🔉
もの‐の‐ついで【物の序で】
他の物事を行う、そのついで。ことのついで。
もの‐の‐どうり【物の道理】‥ダウ‥🔗⭐🔉
もの‐の‐どうり【物の道理】‥ダウ‥
物事のあるべき筋道。
もの‐の‐な【物の名】🔗⭐🔉
もの‐の‐な【物の名】
①物事の名称。ぶつめい。
②和歌や俳諧で、1首の中に物の名を他の語句に隠して詠むこと。「杣人そまびとは宮木ひくらし足ひきの山の山彦よびとよむなり」に「ひぐらし」を隠した類。隠題かくしだい。
もの‐の‐ね【物の音】🔗⭐🔉
もの‐の‐ね【物の音】
物のおと。特に楽器の音ね。音楽。源氏物語桐壺「心ことなる―をかき鳴らし」
もの‐の‐はじめ【物の始め】🔗⭐🔉
もの‐の‐はじめ【物の始め】
物事の始め。特に縁組の始め。初縁。源氏物語若紫「たはぶれにても―にこの御事よ」
もの‐の‐はずみ【物の弾み】‥ハヅミ🔗⭐🔉
もの‐の‐はずみ【物の弾み】‥ハヅミ
その場のなりゆき。ことの勢い。「―でそう言ったまでだ」
もの‐の‐ふし【物の節】🔗⭐🔉
もの‐の‐ふし【物の節】
近衛の舎人とねりその他の役人の中で雅楽の技能のあるもの。春日祭・賀茂祭などに奉仕。源氏物語松風「近衛づかさの名高き舎人、―どもなどさぶらふに」
もの‐の‐ほん【物の本】🔗⭐🔉
もの‐の‐ほん【物の本】
本。書物。また、草紙に対して、然るべきことの書いてある本。学問的な本。梅暦「徒然をなぐさむ為の―」。「―に書いてある」
⇒もののほん‐みせ【物の本店】
もののほん‐みせ【物の本店】🔗⭐🔉
もののほん‐みせ【物の本店】
書店。狂言、長光「是は―でござる」
⇒もの‐の‐ほん【物の本】
もの‐の‐まぎれ【物の紛れ】🔗⭐🔉
もの‐の‐まぎれ【物の紛れ】
①物事がごたごたすること。どさくさまぎれ。源氏物語賢木「―にも左の大臣の御有様ふと思しくらべられて」
②男女間の間違い。密会。源氏物語若菜下「心を交しそめ―多かりぬべきわざなり」
もの‐の‐みごと【物の見事】🔗⭐🔉
もの‐の‐みごと【物の見事】
あざやかなさま。みごとなさま。「―に合格する」「―にころんだ」
もの‐の‐め【物の芽】🔗⭐🔉
もの‐の‐め【物の芽】
いろいろな草木の芽。〈[季]春〉
もの‐の‐よう【物の用】🔗⭐🔉
もの‐の‐よう【物の用】
何かの役。薄雪物語「―に立たぬものは手かきなり」
○物は言いようものはいいよう🔗⭐🔉
○物は言いようものはいいよう
同じ物事も話し方によってよくも悪くも聞こえるものだ。
⇒もの【物】
もの‐はかな・し【物果無し】
〔形ク〕
何となくはかない。頼りない。源氏物語賢木「いと―・き御程なれば」
もの‐はかな・し【物果無し】🔗⭐🔉
もの‐はかな・し【物果無し】
〔形ク〕
何となくはかない。頼りない。源氏物語賢木「いと―・き御程なれば」
○物は考えようものはかんがえよう
物事は考え方ひとつでよくも悪くも解釈できるものだ。
⇒もの【物】
○物は考えようものはかんがえよう🔗⭐🔉
○物は考えようものはかんがえよう
物事は考え方ひとつでよくも悪くも解釈できるものだ。
⇒もの【物】
もの‐はじ【物恥じ】‥ハヂ
物事をはじること。はずかしいと思うこと。源氏物語帚木「艶に―して」
もの‐はじめ【物始め】
物事を始めること。事始め。手始め。
もの‐はずか・し【物恥かし】‥ハヅカシ
〔形シク〕
きまりがわるい。何となくはずかしい。源氏物語少女「かたみに―・しく胸つぶれて」
○物は相談ものはそうだん🔗⭐🔉
○物は相談ものはそうだん
むずかしそうに見える事も、人と相談をすれば意外に解決法が得られるものだ、の意。また、他人に相談を切り出すときにいう語。「物は談合」とも。「―だが、手伝ってくれないか」
⇒もの【物】
○物は試しものはためし🔗⭐🔉
○物は試しものはためし
物事は1度試みない限り成否はわからない。やってみないであきらめることはない。
⇒もの【物】
○物は使いようものはつかいよう🔗⭐🔉
○物は使いようものはつかいよう
物は使い方ひとつで、つまらない物が役立ったり、良い物を損ねてしまったりするものである。
⇒もの【物】
ものは‐づくし【物は尽し】
(→)「ものづくし」に同じ。
ものは‐づけ【物は付け】
雑俳の一種。点者が出した「…物は」「…する物は」などという題に応じて答句を付けるもの。寛保(1741〜1744)頃から江戸に起こった。
も‐の‐はな【藻の花】
湖や沼に生ずる淡水藻の花。夏、水面に出て葉の間に淡黄緑や白色の小さい花をつける。〈[季]夏〉
もの‐はみ【膆・物食み】
鳥の胃。えぶくろ。〈倭名類聚鈔18〉
もの‐はゆ・し【物映し】
〔形ク〕
まばゆい。きまり悪い。おもはゆい。〈名語記〉
もの‐はり【物張り】
衣の染色・洗張り、また、その裁ち縫いをすること。また、その人。今昔物語集24「故宰相殿の―にてなむ侍りし」
もの‐び【物日】
①祭日・祝日など特別な事の行われる日。
②遊郭で、五節句などの祝日や、毎月の朔日・15日など特に定めてあった日。この日は遊女は休むことが許されず、休むときは、客のない場合でも身揚みあがりをしなければならなかった。紋日。売り日。役日。
モノフォニー【monophony】
(→)単声音楽に同じ。
もの‐ふか・し【物深し】
〔形ク〕
①奥ふかい。深い。枕草子73「いみじう―・く遠きが」
②趣が深い。おくゆかしい。源氏物語椎本「耳なれぬけにやあらむいと―・くおもしろしと」
③縁故がふかい。栄華物語初花「―・からぬ人も涙留め難し」
もの‐ふ・る【物古る・物旧る】
〔自上二〕
何となく古くなる。古びる。源氏物語若紫「こよなう荒れまさり、広う―・りたる所」
モノ‐ポール【monopole】
磁極のN極またはS極のどちらか一方だけをもつとされる仮想的な粒子。1934年ディラックが理論的にその存在を予想したが、未発見。磁気単極子。
もの‐ほけん【物保険】
⇒ぶつほけん
もの‐ほこりらか【物誇りらか】
得意そうなさま。蜻蛉日記中「―に言ひののしるほどに」
もの‐ほし【物干し】
洗った衣類・布帛などを乾すこと。また、その場所。「―場」
⇒ものほし‐ざお【物干し竿】
⇒ものほし‐だい【物干し台】
もの‐ほし・い【物欲しい】
〔形〕[文]ものほ・し(シク)
何かほしい。何か手に入れたい。
ものほし‐げ【物欲しげ】
(→)「物欲しそう」に同じ。「―な顔つき」
ものほし‐ざお【物干し竿】‥ザヲ
洗い物などをかけて干す竿。
⇒もの‐ほし【物干し】
ものほし‐そう【物欲しそう】‥サウ
何かほしそうなさま。ものほしげ。「―な口ぶり」「―にふるまう」
ものほし‐だい【物干し台】
洗濯物を干す場所として屋根などに設けた台。
⇒もの‐ほし【物干し】
モノポリー【monopoly】
①独占。専売。
②独占権。専売権。
③独占会社。専売公社。
モノマー【monomer】
〔化〕(→)単量体のこと。
もの‐まいり【物参り】‥マヰリ
社寺に参詣さんけいすること。ものもうで。建礼門院右京大夫集「ゆかりある人の―すとて」
もの‐まえ【物前】‥マヘ
①戦が始まる前。戦のまぎわ。甲陽軍鑑6「―にて腰立たず無性になる人は本の臆病者とて」
②盆・正月・節句などの前。節季。日本永代蔵5「今日と明日との―さもいそがはしき片手に」
もの‐まお・す【物申す】‥マヲス
〔自四〕
(→)「ものもうす」に同じ。仁徳紀「―・す我が兄せを見れば」
もの‐まさ【尸者】
祖先の祭に、神霊の代りに立って祭を受ける者。また葬儀で、死人に代わって弔問を受ける人。神代紀下「鴗そびを以て―とす」
もの‐まなび【物学び】
物事を学ぶこと。学問。
モノマニア【monomania】
偏執狂。偏狂。凝り症。
もの‐まね【物真似】
①人や動物その他の態度・声音などをまねること。また、それをする興行物。狂言、柿山伏「―の上手な奴でござる」
②ある人物に扮してそれらしく姿態・行動を再現すること。猿楽の能では舞歌ぶがとともに技法の基礎とする。
もの‐まねび【物学び】
ものまねをすること。人まね。源氏物語手習「所につけたる―しつつ」
もの‐まめやか
実直なさま。まじめ。源氏物語帚木「思ひとまる人は―なりと見え」
もの‐み【物見】
①物事を見ること。見物けんぶつ。源氏物語花宴「―にはえ過ぐし給はでまゐり給ふ」
②敵の様子などを見張ること。また、その役の人。斥候。「―番」「―船」
③外部や遠方を見るための設備。
㋐牛車ぎっしゃの左右の立板にある窓。→牛車(図)。
㋑物見窓。
㋒物見櫓やぐら。
㋓編笠などで、目の前に当たる透かして編んだ部分。
④みごとなこと。みもの。醒睡笑「松茸の―なるを一折」
⇒ものみ‐がさ【物見笠】
⇒ものみ‐ぐさ【物見草】
⇒ものみ‐ぐるま【物見車】
⇒ものみ‐すだれ【物見簾】
⇒ものみ‐だい【物見台】
⇒ものみ‐ぶね【物見船】
⇒ものみ‐まど【物見窓】
⇒ものみ‐やく【物見役】
⇒ものみ‐やぐら【物見櫓】
⇒ものみ‐ゆさん【物見遊山】
ものみ‐がさ【物見笠】
見物する人のかぶる編笠。
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐ぐさ【物見草】
松の異称。蔵玉集「―袖にかざさむ折々に涙をだにも花と思へば」
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐ぐるま【物見車】
祭礼などを見物する人の乗る牛車ぎっしゃ。源氏物語葵「かねてより―心づかひしけり」
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐すだれ【物見簾】
車の物見にかけるすだれ。
⇒もの‐み【物見】
ものみせ‐だて【物見せ立て】
目に物見せようとするさまをすること。狂言、鴈盗人「こなたの―いらぬこと」
ものみ‐だい【物見台】
遠方を見るために設けた高い台。
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐だか・い【物見高い】
〔形〕[文]ものみだか・し(ク)
なんでも見たがる風がある。ものみだけし。「―・いは江戸の常」「―・い野次馬」
ものみ‐だけ・し【物見猛し】
〔形ク〕
「ものみだかし」に同じ。狂言、八幡の前「ことにやわたは人おほい所で、―・いほどに」
ものみ‐ぶね【物見船】
見物するために乗る船。
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐まど【物見窓】
物見のために設けた窓。のぞき窓。物見の窓。
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐やく【物見役】
敵の動静を探る役の人。
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐やぐら【物見櫓】
遠望するために設けた櫓。
⇒もの‐み【物見】
ものみ‐ゆさん【物見遊山】
物見と遊山。見物して遊びまわること。
⇒もの‐み【物見】
もの‐むつか・し【物難し】
〔形シク〕
何となくいとわしい。気がむさくさする。源氏物語若紫「―・しくおぼえ給ひて」
もの‐むつかり【物憤り】
物事に腹をたてること。栄華物語玉飾「―などせさせ給はざりつれば」
もの‐めか・し【物めかし】
〔形シク〕
目立つさまである。ひとかどのものに見える。源氏物語若菜上「位など今少し―・しき程になりなば」
もの‐めか・す【物めかす】
〔他四〕
目立つようにする。源氏物語松風「―・さむほども憚り多かるに」
もの‐めずらし・い【物珍しい】‥メヅラシイ
〔形〕[文]ものめづら・し(シク)
物事がめずらしい。何となくめずらしい。「田舎出なので、都会のすべてが―・い」「―・そうに眺める」
もの‐めで【物愛で】
①物事を深く愛めでること。物事に感動すること。源氏物語須磨「―する若き人にて」
②物好みすること。物好き。
もの‐も
〔感〕
(→)「ものもう」(感)に同じ。
もの‐もい【物思ひ】‥モヒ
モノオモイの約。万葉集20「防人に行くは誰が夫せと問ふ人を見るが羨ともしさ―もせず」
ものは‐づくし【物は尽し】🔗⭐🔉
ものは‐づくし【物は尽し】
(→)「ものづくし」に同じ。
ものは‐づけ【物は付け】🔗⭐🔉
ものは‐づけ【物は付け】
雑俳の一種。点者が出した「…物は」「…する物は」などという題に応じて答句を付けるもの。寛保(1741〜1744)頃から江戸に起こった。
もの‐はゆ・し【物映し】🔗⭐🔉
もの‐はゆ・し【物映し】
〔形ク〕
まばゆい。きまり悪い。おもはゆい。〈名語記〉
もの‐めか・し【物めかし】🔗⭐🔉
もの‐めか・し【物めかし】
〔形シク〕
目立つさまである。ひとかどのものに見える。源氏物語若菜上「位など今少し―・しき程になりなば」
もの‐めか・す【物めかす】🔗⭐🔉
もの‐めか・す【物めかす】
〔他四〕
目立つようにする。源氏物語松風「―・さむほども憚り多かるに」
もの‐めで【物愛で】🔗⭐🔉
もの‐めで【物愛で】
①物事を深く愛めでること。物事に感動すること。源氏物語須磨「―する若き人にて」
②物好みすること。物好き。
○物も言いようで角が立つものもいいようでかどがたつ🔗⭐🔉
○物も言いようで角が立つものもいいようでかどがたつ
さほどでもない事も話の仕様で人の感情をきずつける。
⇒もの【物】
もの‐も・う【物思ふ】‥モフ
〔他四〕
モノオモウの約。万葉集15「―・ふと人には見えじ」
もの‐もう‥マウ
〔感〕
(「物申す」の略)他人の家に行って案内を請う語。たのもう。狂言、福の神「―案内もう」
もの‐もうし【物申し・謁者】‥マウシ
①ものを申し上げること。取りついで上に伝えること。また、その人。顕宗紀「謁者ものもうしひとに労いたわること無かれ」
②案内を請うこと。
③祝詞を奏すること。春雨物語「―の声皺ぶる人なれば」
もの‐もう・す【物申す】‥マウス
〔自五〕
①ものを申し上げる。天武紀下「納言ものもうすつかさ兼かねて宮内卿みやのうちのつかさのきみ」。古今和歌集雑体「をち方人に―・す」
②案内を請う。
③注文をつける。抗議する。「一筆―・す」
もの‐もうで【物詣で】‥マウデ
社寺にまいること。ものまいり。参詣。枕草子25「出で入る車の轅もひまなく見え、―する供に」
モノモタパ【Monomotapa】
アフリカ南部、現在のジンバブエを中心に、11〜19世紀に栄えたショナ人・ロズウィ人などの王国。インド洋交易・内陸交易を支配。
もの‐もち【物持】
①多くの財産を所持する人。財産家。富豪。徳冨蘆花、灰燼「此辺きつての素封家ものもち上田久吾と云ふ人の居なり」。「村一番の―」
②品物を大切に長く使うこと。「―がいい」
もの‐もどき【物抵牾】
何かにつけて非難すること。紫式部日記「―うちし」
ものもの‐し・い【物物しい】
〔形〕[文]ものもの・し(シク)
①いかめしい。おごそかである。堂々としている。源氏物語葵「御年の加はるけにや―・しきけさへ添ひ給ひて」
②仰山らしい。大層らしい。謡曲、景清「―・しやと夕日影に打ち物閃かいて斬つて掛かれば」。「―・い警戒」「―・いいでたち」
もの‐もらい【物貰い】‥モラヒ
①食物などを人からもらって生活する者。こじき。かたい。
②麦粒腫ばくりゅうしゅの俗称。「―ができる」
もの‐やみ【物病み】
病気。やまい。伊勢物語「―になりて死ぬべき時に」
もの‐やわらか【物柔らか】‥ヤハラカ
何となくやわらかなさま。しとやかなさま。おだやか。源氏物語帚木「―に掻き鳴らして」。「―な人柄」
ものゆえ‥ユヱ
〔助詞〕
(接続助詞。形式名詞モノにユエの付いたもの)
①確定の逆接条件を示すのに用いる。…であるのに。…にもかかわらず。ものから。万葉集19「毎年としのはに来鳴く―ほととぎす聞けば慕しのはく逢はぬ日を多み」
②確定の順接条件を示すのに用いる。現代語では書き言葉、または演説調の言葉。…ので。…のだから。万葉集15「我が故に思ひな痩せそ秋風の吹かむその月逢はむ―」。「知らなかった―失礼した」
もの‐ゆか・し【物床し】
〔形シク〕
何となく心ひかれる。何となく慕わしい。能因本枕草子文ことばなめき人こそ「女房の―・しうする」
もの‐よし【物吉】
①めでたいこと。
②祝い詞や雑芸をもって門に立ち、物乞いする者。〈[季]新年〉
③江戸時代、ハンセン病患者をいった語。醒睡笑「わが身に癩瘡らいそういできたる体を見…かれをば―といふなれば」
もの‐よみ【物読み】
書物を読むこと。特に漢籍を読むこと。好色五人女5「此の客僧は我が―のお師匠なり」
もの‐ら・し【物らし】
〔形シク〕
ものものしい。大げさである。浄瑠璃、義経千本桜「味うまい盛りの振袖が、釣瓶鮨とは―・しし」
モノラル【monaural】
単一の録音・再生装置を用いる音響方式。また、その装置。「―‐レコード」↔ステレオ
モノリシック‐アイシー【monolithic IC】
集積回路(IC)のうち、シリコン基板上にトランジスター・ダイオード・抵抗・コンデンサーを一体構造として構成するもの。
モノレール【monorail】
1本のレールに沿って走る鉄道。レールをまたぐ跨座こざ式と、レールに吊り下がる懸垂式とがある。単軌鉄道。
モノローグ【monologue】
①自問自答したり相手なしに述懐したりする台詞せりふ。独白。↔ダイアローグ。
②独演劇。→モノドラマ
もの‐わかり【物分り】
事情・状況、人の立場などを理解すること。また、その能力。のみこみ。「―のよい人」
もの‐わかれ【物別れ・物分れ】
双方の意見が一致しないで別れること。「交渉が―に終わる」
もの‐わすれ【物忘れ】
物事を忘れること。失念。「―が激しい」「よく―する」
もの‐わびし・い【物侘しい】
〔形〕[文]ものわび・し(シク)
何となくわびしい。うらさびしい。源氏物語明石「いとど―・しきこと数知らず」
ものわびし‐ら【物侘しら】
ものわびしいさま。ものわびしそう。古今和歌集物名「―になくのべのむし」
もの‐わらい【物笑い】‥ワラヒ
①物事を笑うこと。源氏物語少女「―などすまじくすぐしつつ」
②他人の言行を見聞してあざけり笑うこと。また、その対象。笑いぐさ。「―の種」「世間の―になる」
ものを
〔助詞〕
(形式名詞モノに助詞ヲの付いたもの)活用語の連体形から続く。ただし、口語の「だ」には終止形にも付く。
➊(接続助詞)
①逆接を表す。…のであるが。…であるのに。源氏物語桐壺「年頃嬉しくおもだたしきついでにて立寄り給ひし―、かかる御せうそこにて見奉る、かへすがへすつれなき命にも侍るかな」。「あきらめればいい―、いつまでもこだわる」
②順接を表す。…のであるから。…だから。もの。浄瑠璃、心中宵庚申「明日は未来で添ふ―、別は暫しの此の世の名残」。「いい人だ―、断ることはできない」
➋(終助詞)詠嘆的に悔恨・愛惜・不満などの気持を表す。…であるなあ。…であるのにな。万葉集2「吾を待つと君がぬれけむあしひきの山のしづくにならまし―」。「もっと早くすればいい―」
ものもの‐し・い【物物しい】🔗⭐🔉
ものもの‐し・い【物物しい】
〔形〕[文]ものもの・し(シク)
①いかめしい。おごそかである。堂々としている。源氏物語葵「御年の加はるけにや―・しきけさへ添ひ給ひて」
②仰山らしい。大層らしい。謡曲、景清「―・しやと夕日影に打ち物閃かいて斬つて掛かれば」。「―・い警戒」「―・いいでたち」
もの‐ら・し【物らし】🔗⭐🔉
もの‐ら・し【物らし】
〔形シク〕
ものものしい。大げさである。浄瑠璃、義経千本桜「味うまい盛りの振袖が、釣瓶鮨とは―・しし」
○物を言うものをいう🔗⭐🔉
○物を言うものをいう
好結果をあらわす。効果がある。役に立つ。「経験が―」「金が―世の中」
⇒もの【物】
○物を言わすものをいわす🔗⭐🔉
○物を言わすものをいわす
その効果を十分に発揮させる。「腕力に―」
⇒もの【物】
も‐は【藻葉】
藻の古語。祝詞、祈年祭「沖つ―、辺つ―に至るまでに」
も‐は
〔副〕
最早もはやの略。好色一代女1「―一つもならぬ」
も‐ば【藻場】
海底にコンブ・ホンダワラ・アマモなどの藻が繁茂しているところ。ホンダワラが密生するガラモ場、アマモが密生するアマモ場がある。魚介類が集まる。→海中林
モバイル【mobile】
「動かしやすい」「移動できる」の意。軽量化や無線通信機能の装備によって機器を自由な場所で利用できること。「―‐コミュニケーション」
⇒モバイル‐コンピューティング【mobile computing】
モバイル‐コンピューティング【mobile computing】
携帯用小型コンピューターと通信回線を利用し、外出先で情報の処理や送受信を行うこと。
⇒モバイル【mobile】
モハメッド【Mohammed】
⇒ムハンマド
も‐はや【最早】
〔副〕
今となっては。もう。すでに。狂言、末広がり「―かう参りまする」。「―時代遅れである」「―5年も前のことになってしまった」
もは・ゆ【思はゆ】
〔自下二〕
(オモハユの約)思われる。万葉集20「袖もしほほに泣きしそ―・ゆ」
も‐はら【専ら】
〔副〕
①もっぱら。古事記上「此の鏡は―我が御魂として」
②(下に打消の語を伴って)まったく。ちっとも。竹取物語「―さやうの宮仕へ仕うまつらじと思ふを」
もばら【茂原】
千葉県中部、九十九里平野南端の市。近世の市場町から発達し、1930年代に開発された天然ガスを基礎に機械・化学工業が発展。人口9万3千。
も‐はん【模範】
①(「模」は木製の型、「範」は竹製の型)器物をつくるのに用いる型。
②見ならうべき手本。規範。「―を示す」
⇒もはん‐ぎかい【模範議会】
⇒もはん‐じあい【模範試合】
⇒もはん‐せい【模範生】
⇒もはん‐てき【模範的】
もはん‐ぎかい【模範議会】‥クワイ
(Model Parliament)イギリスで1295年エドワード1世が召集した議会。大貴族のほか、騎士・市民・下級聖職者の代表も参加した身分制議会。19世紀の学説で議会の模範的形態とされた。
⇒も‐はん【模範】
もはん‐じあい【模範試合】‥アヒ
スポーツ・武芸の分野で、熟練した者同士が紹介・普及の目的で行う模範的な試合。
⇒も‐はん【模範】
もはん‐せい【模範生】
品行方正・学術優秀で他の模範とすべき学生・生徒。
⇒も‐はん【模範】
もはん‐てき【模範的】
模範となるようなさま。「―な演技」
⇒も‐はん【模範】
モヒ
モルヒネの略。
モビール【mobile】
(動く物体(objet mobile フランス)の意)細い針金・糸などでさまざまな形の金属片・木片を吊り、微妙な均衡を保たせた造形品。室内装飾などに用いる。コールダーが創始。
モヒカン‐がり【モヒカン刈り】
(モヒカン(Mohican)はアメリカ先住民の一部族の名)髪型の一つ。頭部の左右を剃り、中央に一直線に髪を残したもの。
も‐びき【裳引き】
裳裾を後ろへ引くこと。万葉集10「―しるけむ雪な降りそね」
も‐び・く【裳引く】
〔他四〕
裳裾を後ろへ引く。万葉集20「―・き平ならしし菅原の里」
も‐ひめ【最姫】
大嘗祭だいじょうさいの神事に奉仕する采女うねめの最上位。主に御親供ごしんくの介錯かいしゃくに当たる。陪膳。
も‐ひも【裳紐】
裳の紐。神代紀下「―を臍ほその下しもに抑おしたれき」
も‐ふく【喪服】
喪中の人または弔問者が着る薄墨色・墨色の服。ふじごろも。もぎぬ。凶服。服衣ぶくえ。「―に身を包む」
もふし‐つかふな【藻臥束鮒】
藻の中にひそむ1束(握った拳の小指から人差指までの長さ、約2寸5分)の鮒。また、河内国藻伏産の鮒ともいう。万葉集4「吾が漁すなどれる―」
も‐ふね【喪船】
棺をのせた船。古事記中「御子を其の―に載せ」
モヘア【mohair】
アンゴラ山羊やぎの毛。また、その織物。光沢があり、毛足は長く柔らかい。モヘヤ。モヘル。
⇒モヘア‐プラッシュ【mohair plush】
モヘア‐プラッシュ【mohair plush】
ビロードの一種。地のたてよこを木綿糸にし、けばになる糸をモヘア糸にした、荒くてけばの長いもの。
⇒モヘア【mohair】
もへ‐ばこ【もへ箱】
(東北地方で)女が私物を入れておく箱。ざもばこ。
モヘル【Mohär ドイツ】
⇒モヘア
モヘンジョ‐ダロ【Mohenjo-daro】
パキスタン南部、インダス川下流右岸にあるインダス文明の遺跡。紀元前2300〜前1800年頃に栄えた6〜7層の都市遺跡が発掘された。→ハラッパー
モ‐ボ
(昭和初期の造語)モダンボーイの略。↔モガ
も‐ほう【模倣・摸倣】‥ハウ
自分で創り出すのではなく、すでにあるものをまねならうこと。他者と類似あるいは同一の行動をとること。幼児の学習過程、社会的流行、さらには高度の文化活動など、文化的・社会的に重要な意義をもつ。「―癖」↔創造。
⇒もほう‐げいじゅつ【模倣芸術】
⇒もほう‐せつ【模倣説】
⇒もほう‐はん【模倣犯】
もほう‐げいじゅつ【模倣芸術】‥ハウ‥
自然の姿を写す絵画・彫刻などを指す語。建築・工芸のように自然描写を行わない芸術と区別していう。
⇒も‐ほう【模倣・摸倣】
もほう‐せつ【模倣説】‥ハウ‥
あらゆる社会現象の根源が模倣にあると説く社会学説。代表はタルドの人間心理学的見解。
⇒も‐ほう【模倣・摸倣】
もほう‐はん【模倣犯】‥ハウ‥
すでに起きた犯罪をまねて同じような犯罪をおかす者。
⇒も‐ほう【模倣・摸倣】
モホリ‐ナジ【László Moholy-Nagy】
アメリカの画家・映像作家。ハンガリー生れ。バウハウスで教授。抽象絵画・彫刻・工芸・建築・写真など多方面に活動。キネティック‐アート・環境芸術などの先駆。モホリ‐ナギ。(1895〜1946)
モホロヴィチッチ‐ふれんぞく‐めん【モホロヴィチッチ不連続面】
地殻とマントルとの境界面。地震波の速さがこの面で急に変わる(地殻で小、マントルで大)。大陸域では地表から30〜60キロメートル、海洋域では海底から約7キロメートルの深さにある。ユーゴスラヴィアの地震学者モホロヴィチッチ(A. Mohorovičić1857〜1936)が1909年のバルカン地震により発見。モホ面。
も‐ほん【模本・摸本・摹本】
①模写した書物。
②習字・図画などの手本。臨本。
も‐また【亦】
上を受けて「これもまた」の意を表す漢字「亦」の称。「又」「復」などと区別していう。
も‐また【も又】
〔副〕
もはや。もう既に。好色一代女3「―其の年も年なるに」
もま・れる【揉まれる】
⇒もむ(揉)9
もみ【籾】
①穂から扱こいたままで、まだ脱穀しない米。もみごめ。〈[季]秋〉。天智紀「―と塩とを積む」
②「もみがら」の略。
もみ【紅・紅絹】
(ベニバナを揉んで染めるからいう)紅べにで無地に染めた絹布。ほんもみ。
もみ【樅】
マツ科の常緑針葉樹。本州・四国・九州に自生。日本の特産種。高さ30メートル内外。樹皮は暗灰色、葉は線形で密生。初夏、雌雄花を同株に開き、円柱形緑褐色の球果を結ぶ。庭木やオウシュウモミの代りにクリスマス‐ツリーとする。材は建築材・船材・経木材・製紙原料。もみそ。とうもみ。もむのき。〈倭名類聚鈔20〉
もみ
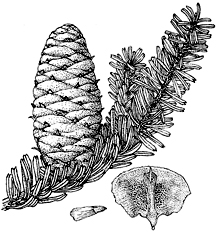 もみ【蝦蟇】
アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」
もみ【鼯鼠】
ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉
もみ‐あい【揉合い】‥アヒ
もみあうこと。「―になる」
もみ‐あい【揉藍】‥アヰ
藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。
もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ
〔他五〕
①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」
②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。
もみ‐あげ【揉上げ】
鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。
もみ‐あし【揉足】
足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。
もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ
手でもんで洗うこと。
もみ‐いた【揉板】
衣服をもみつけて洗濯する板。
もみ‐うす【籾臼】
籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉
もみ‐うら【紅裏】
紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」
もみ‐うり【揉瓜】
①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉
②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉
もみ‐えぼし【揉烏帽子】
揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。
もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ
衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき
もみ‐がみ【揉紙】
和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」
揉紙
撮影:関戸 勇
もみ【蝦蟇】
アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」
もみ【鼯鼠】
ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉
もみ‐あい【揉合い】‥アヒ
もみあうこと。「―になる」
もみ‐あい【揉藍】‥アヰ
藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。
もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ
〔他五〕
①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」
②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。
もみ‐あげ【揉上げ】
鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。
もみ‐あし【揉足】
足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。
もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ
手でもんで洗うこと。
もみ‐いた【揉板】
衣服をもみつけて洗濯する板。
もみ‐うす【籾臼】
籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉
もみ‐うら【紅裏】
紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」
もみ‐うり【揉瓜】
①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉
②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉
もみ‐えぼし【揉烏帽子】
揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。
もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ
衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき
もみ‐がみ【揉紙】
和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」
揉紙
撮影:関戸 勇
 もみ‐がら【籾殻】
籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。
もみ‐かわ【揉革】‥カハ
なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。
もみ‐ぎり【揉錐】
(→)「きり」1に同じ。
もみ‐くじ【揉鬮】
数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。
もみ‐くた【揉みくた】
(→)「もみくちゃ」に同じ。
もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】
ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」
もみ‐ぐら【籾蔵】
凶年に備えて籾米を入れておく蔵。
もみ‐ぐるま【籾車】
穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。
もみ‐け・す【揉み消す】
〔他五〕
①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」
②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」
③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」
もみ‐こ・む【揉み込む】
〔他五〕
①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」
②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」
もみ‐ごめ【籾米】
皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。
もみ‐し【紅師】
紅もみを染める職人。
もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ
(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)
①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。
②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉
③「もみじば」の略。
④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。
⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」
⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。
⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」
⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】
⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】
⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】
⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】
⇒もみじ‐がい【紅葉貝】
⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】
⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】
⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】
⇒もみじ‐がり【紅葉狩】
⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】
⇒もみじ‐づき【紅葉月】
⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】
⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】
⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】
⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】
⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】
⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】
⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】
⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】
⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】
⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】
⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】
⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】
⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】
⇒もみじ‐み【紅葉見】
⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】
⇒紅葉散る
⇒紅葉のような手
⇒紅葉を散らす
もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ
(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ
アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。
もみじあおい
もみ‐がら【籾殻】
籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。
もみ‐かわ【揉革】‥カハ
なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。
もみ‐ぎり【揉錐】
(→)「きり」1に同じ。
もみ‐くじ【揉鬮】
数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。
もみ‐くた【揉みくた】
(→)「もみくちゃ」に同じ。
もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】
ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」
もみ‐ぐら【籾蔵】
凶年に備えて籾米を入れておく蔵。
もみ‐ぐるま【籾車】
穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。
もみ‐け・す【揉み消す】
〔他五〕
①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」
②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」
③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」
もみ‐こ・む【揉み込む】
〔他五〕
①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」
②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」
もみ‐ごめ【籾米】
皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。
もみ‐し【紅師】
紅もみを染める職人。
もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ
(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)
①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。
②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉
③「もみじば」の略。
④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。
⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」
⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。
⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」
⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】
⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】
⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】
⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】
⇒もみじ‐がい【紅葉貝】
⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】
⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】
⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】
⇒もみじ‐がり【紅葉狩】
⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】
⇒もみじ‐づき【紅葉月】
⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】
⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】
⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】
⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】
⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】
⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】
⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】
⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】
⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】
⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】
⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】
⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】
⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】
⇒もみじ‐み【紅葉見】
⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】
⇒紅葉散る
⇒紅葉のような手
⇒紅葉を散らす
もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ
(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ
アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。
もみじあおい
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥
バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。
モミジイチゴ
提供:OPO
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥
バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。
モミジイチゴ
提供:OPO
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥
大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ
モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥
①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。
②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」
③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。
モミジガサ
提供:OPO
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥
大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ
モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥
①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。
②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」
③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。
モミジガサ
提供:OPO
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥
(→)「もみじ」4に同じ。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥
キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。
モミジカラマツ
提供:OPO
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥
(→)「もみじ」4に同じ。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥
キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。
モミジカラマツ
提供:OPO
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥
山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥
①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。
②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。
③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。
④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。
もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥
紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥
山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥
①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。
②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。
③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。
④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。
もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥
紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
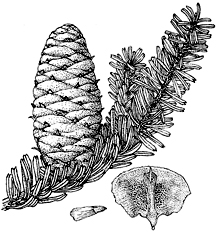 もみ【蝦蟇】
アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」
もみ【鼯鼠】
ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉
もみ‐あい【揉合い】‥アヒ
もみあうこと。「―になる」
もみ‐あい【揉藍】‥アヰ
藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。
もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ
〔他五〕
①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」
②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。
もみ‐あげ【揉上げ】
鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。
もみ‐あし【揉足】
足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。
もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ
手でもんで洗うこと。
もみ‐いた【揉板】
衣服をもみつけて洗濯する板。
もみ‐うす【籾臼】
籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉
もみ‐うら【紅裏】
紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」
もみ‐うり【揉瓜】
①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉
②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉
もみ‐えぼし【揉烏帽子】
揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。
もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ
衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき
もみ‐がみ【揉紙】
和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」
揉紙
撮影:関戸 勇
もみ【蝦蟇】
アカガエルの異称。また、アカガエルを料理して煮たもの。応神紀「蝦蟆かえるを煮て上味よきあじわいとす、名づけて―と曰ふ」
もみ【鼯鼠】
ムササビ・モモンガの類の古名。〈本草和名〉
もみ‐あい【揉合い】‥アヒ
もみあうこと。「―になる」
もみ‐あい【揉藍】‥アヰ
藍の葉を乾かし砕いてつくった藍色の染料。
もみ‐あ・う【揉み合う】‥アフ
〔他五〕
①互いに強く擦れ合って争う。「入口で―・う」
②取引市場で、相場が小幅の変動をくりかえす。
もみ‐あげ【揉上げ】
鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。
もみ‐あし【揉足】
足と足とをすり合わせて洗うこと。葬式から帰った人はこうして洗うので平常は忌む。
もみ‐あらい【揉洗い】‥アラヒ
手でもんで洗うこと。
もみ‐いた【揉板】
衣服をもみつけて洗濯する板。
もみ‐うす【籾臼】
籾摺もみすり用の臼。すりうす。〈[季]秋〉
もみ‐うら【紅裏】
紅もみを衣服の裏とすること。また、その裏地。木下尚江、良人の自白「燃へ立つような紅絹裏もみうらの夜具を、胸も腹も露はに、ポンとはね除けた」
もみ‐うり【揉瓜】
①シロウリの異称。もみふり。〈運歩色葉集〉
②(→)「瓜もみ」に同じ。〈[季]夏〉
もみ‐えぼし【揉烏帽子】
揉んで柔らかく作った烏帽子。鎌倉時代から多く軍陣に用いられた。梨子打なしうち烏帽子。
もみ‐がえし【紅返し】‥ガヘシ
衣服で、紅裏もみうらを表に返して縁どりしたもの。べにがえし。好色一代女1「―の下着」→袘ふき
もみ‐がみ【揉紙】
和紙を揉んだり、筆軸など丸い棒に巻きつけて端から押しつぶしたりして、皺しぼを立てたもの。手遊びの人形の髪などを作る。縮緬ちりめん紙。浮世風呂2「―でこしらへた島田・丸まげ・島田くづし」
揉紙
撮影:関戸 勇
 もみ‐がら【籾殻】
籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。
もみ‐かわ【揉革】‥カハ
なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。
もみ‐ぎり【揉錐】
(→)「きり」1に同じ。
もみ‐くじ【揉鬮】
数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。
もみ‐くた【揉みくた】
(→)「もみくちゃ」に同じ。
もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】
ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」
もみ‐ぐら【籾蔵】
凶年に備えて籾米を入れておく蔵。
もみ‐ぐるま【籾車】
穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。
もみ‐け・す【揉み消す】
〔他五〕
①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」
②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」
③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」
もみ‐こ・む【揉み込む】
〔他五〕
①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」
②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」
もみ‐ごめ【籾米】
皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。
もみ‐し【紅師】
紅もみを染める職人。
もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ
(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)
①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。
②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉
③「もみじば」の略。
④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。
⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」
⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。
⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」
⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】
⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】
⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】
⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】
⇒もみじ‐がい【紅葉貝】
⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】
⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】
⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】
⇒もみじ‐がり【紅葉狩】
⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】
⇒もみじ‐づき【紅葉月】
⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】
⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】
⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】
⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】
⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】
⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】
⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】
⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】
⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】
⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】
⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】
⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】
⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】
⇒もみじ‐み【紅葉見】
⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】
⇒紅葉散る
⇒紅葉のような手
⇒紅葉を散らす
もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ
(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ
アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。
もみじあおい
もみ‐がら【籾殻】
籾米の外皮。また、その米から摺り落としたもの。あらぬか。すりぬか。もみ。籾糠もみぬか。
もみ‐かわ【揉革】‥カハ
なめし皮の上面を削り揉んで柔らかにしたもの。おしかわ。
もみ‐ぎり【揉錐】
(→)「きり」1に同じ。
もみ‐くじ【揉鬮】
数枚の細長い紙片に別々のことを書いてひねり、その中から引き抜いて吉凶を占うくじ。拈書ひねりぶみ。
もみ‐くた【揉みくた】
(→)「もみくちゃ」に同じ。
もみ‐くちゃ【揉みくちゃ】
ひどく揉まれること。揉まれて皺になるさま。もみくしゃ。もみくた。「満員電車で―になる」
もみ‐ぐら【籾蔵】
凶年に備えて籾米を入れておく蔵。
もみ‐ぐるま【籾車】
穀物の実と粃しいなまたは籾殻もみがらとを吹き分ける農具。唐箕とうみ。
もみ‐け・す【揉み消す】
〔他五〕
①火のついたものを手で揉んで消す。「煙草を―・す」
②自分の不利益なことや悪い評判の起こりかけたのを、抑えたり打ち消したりして大事に至らないようにする。「悪事を―・す」
③攻め滅ぼす。日葡辞書「テキヲヒトカッセンニモミケス」
もみ‐こ・む【揉み込む】
〔他五〕
①一緒にしてよく揉み、混ぜ合わせる。浄瑠璃、女殺油地獄「解櫛に色香―・む梅花の油」。「きゅうりに塩を―・む」
②きたえて身につけさせる。仕込む。傾城禁短気「顔色すぐれたるにはさのみ諸芸は―・まず」
もみ‐ごめ【籾米】
皮を取り去る前の米。もみよね。あらしね。もみ。かちしね。
もみ‐し【紅師】
紅もみを染める職人。
もみじ【紅葉・黄葉】モミヂ
(上代にはモミチと清音。上代は「黄葉」、平安時代以後「紅葉」と書く例が多い)
①秋に、木の葉が赤や黄色に色づくこと。また、その葉。〈[季]秋〉。万葉集15「秋山の―をかざし」→紅葉こうよう→黄葉こうよう。
②(→)カエデの別称。〈[季]秋〉
③「もみじば」の略。
④襲かさねの色目。「雑事鈔ぞうじしょう」によると、表は紅、裏は濃い蘇芳すおう。「雁衣鈔」では表は赤、裏は濃い赤。もみじがさね。
⑤(鹿にはもみじが取り合わされるところから)鹿の肉。「―鍋」
⑥(関西で)麦のふすま。もみじご。
⑦茶を濃く味よくたてること。「紅葉こうよう」を「濃う好う」にかけたしゃれ。醒睡笑「お茶を―にたてよ。…ただこうようにといふ事なり」
⇒もみじ‐あえ【紅葉和え】
⇒もみじ‐あおい【紅葉葵】
⇒もみじ‐いちご【紅葉苺】
⇒もみじ‐おろし【紅葉卸し】
⇒もみじ‐がい【紅葉貝】
⇒もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】
⇒もみじ‐がさね【紅葉襲】
⇒もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】
⇒もみじ‐がり【紅葉狩】
⇒もみじ‐ごろも【紅葉衣】
⇒もみじ‐づき【紅葉月】
⇒もみじ‐どり【紅葉鳥】
⇒もみじ‐の‐が【紅葉賀】
⇒もみじ‐の‐かさ【紅葉の笠】
⇒もみじ‐の‐ころも【紅葉の衣】
⇒もみじ‐の‐とばり【紅葉の帳】
⇒もみじ‐の‐にしき【紅葉の錦】
⇒もみじ‐の‐はし【紅葉の橋】
⇒もみじ‐ば【紅葉・黄葉】
⇒もみじば‐の【紅葉の・黄葉の】
⇒もみじば‐ふう【紅葉楓】
⇒もみじ‐ぶくろ【紅葉袋】
⇒もみじ‐ぶな【紅葉鮒】
⇒もみじ‐マーク【紅葉マーク】
⇒もみじ‐み【紅葉見】
⇒もみじ‐むしろ【紅葉蓆】
⇒紅葉散る
⇒紅葉のような手
⇒紅葉を散らす
もみじ‐あえ【紅葉和え】モミヂアヘ
(赤色を紅葉にたとえた名)赤みのある和え物。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐あおい【紅葉葵】モミヂアフヒ
アオイ科の多年草。北アメリカの原産。高さは1.5メートルに達し、葉は掌状で深く5〜7裂。夏から秋に大形緋色の美花を開く。観賞用。紅蜀葵こうしょっき。
もみじあおい
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥
バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。
モミジイチゴ
提供:OPO
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐いちご【紅葉苺】モミヂ‥
バラ科の落葉低木で山地に普通。木苺の一種。高さ約1メートル。茎に毛と刺とげがある。葉は卵形で、掌状に3〜5裂。春、白色のヤマブキに似た花を開き、夏、黄色の果実を結ぶ。甘味があり、生食。
モミジイチゴ
提供:OPO
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥
大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ
モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥
①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。
②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」
③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。
モミジガサ
提供:OPO
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐おろし【紅葉卸し】モミヂ‥
大根おろしの一種。大根に赤唐辛子を差し込んで共におろしたもの。また、人参をすりおろして加えたもの。たつたおろし。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がい【紅葉貝】モミヂガヒ
モミジガイ科のヒトデ。体は星形で腕は5本。背面は灰青色か淡褐色。腕は長さ5〜6センチメートルで、側面に細い刺とげが多く並ぶ。体を砂中に浅くうずめてすべるように動き、小さな貝や動物の死骸を食う。北海道南部以南に分布。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさ【紅葉笠・紅葉傘】モミヂ‥
①(古今集秋に「雨降れば笠取山のもみぢばは行きかふ人の袖さへぞ照る」とあるのに基づく)菅笠の一種、日照笠ひでりがさのこと。
②中心部分を丸く青土佐紙で張り、外側は白紙で張った雨傘。貞享(1684〜1688)頃から江戸に流行、初めは日傘にしたという。歌舞伎、韓人漢文手管始「傾城と―は新しい内が賞翫じや」
③〔植〕キク科の多年草。山地の林下に自生。高さ約1メートル。葉は大きく掌状中裂、夏、帯紫白色の細長い頭状花を、総状花序に開く。若芽は山菜の「しとぎ」で、食用。
モミジガサ
提供:OPO
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥
(→)「もみじ」4に同じ。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥
キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。
モミジカラマツ
提供:OPO
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がさね【紅葉襲】モミヂ‥
(→)「もみじ」4に同じ。
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐からまつ【紅葉唐松・槭唐松】モミヂ‥
キンポウゲ科の多年草。日本の中部・北部の高山に自生。掌状の葉をつけ、夏、茎頭にカラマツソウに似た多数の白花を開く。雄しべも白色で目立つ。モミジショウマ。
モミジカラマツ
提供:OPO
 ⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥
山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥
①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。
②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。
③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。
④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。
もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥
紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじ‐がり【紅葉狩】モミヂ‥
山野に紅葉をたずねて観賞すること。もみじみ。観楓。〈[季]秋〉。(曲名別項)
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もみじがり【紅葉狩】モミヂ‥
①能。観世信光作。平維茂が戸隠山で、美女に化けて紅葉狩する鬼女にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに退治する。
②舞踊劇。義太夫・常磐津・長唄の三方掛合。河竹黙阿弥作詞。能の舞踊化。1887年(明治20)初演。新歌舞伎十八番の一つ。
③長唄。本名題「色見草月盃」。腰元秋篠が色仕掛で盗賊雲井太郎から名笛を奪い返す場に用いた。
④荻江節。能の文句を郭くるわ気分に改めたもの。ほかに地唄・一中節にも同名の曲がある。
もみじ‐ごろも【紅葉衣】モミヂ‥
紅葉襲もみじがさねの衣服。陰暦9月から11月まで用いる。〈[季]秋〉
⇒もみじ【紅葉・黄葉】
もん【物】🔗⭐🔉
もん【物】
モノの音便。浮世風呂3「白玉と金鍔焼をひとつ竹の皮に包んだ―だらう」
[漢]物🔗⭐🔉
物 字形
 筆順
筆順
 〔牛(牜)部4画/8画/教育/4210・4A2A〕
〔音〕ブツ(漢) モツ(呉)
〔訓〕もの
[意味]
宇宙間にある(形ある)存在。もの。「万物・生物・物質・物価・食物しょくもつ・進物しんもつ・書物しょもつ」。特に、
㋐(世間に存在する)人。「人物・愚物・俗物・物議」
㋑事柄。「物理・事物・禁物きんもつ」
[解字]
形声。「牛」+音符「勿」。一定の特色のないさまざまなものの意。一説に、「勿」は切りきざむ意で、「物」は切って神に供える牛の肉と解する。
[下ツキ
阿堵物・一物・逸物・遺物・異物・音物・詠物・汚物・怪物・格物致知・貨物・奸物・換物・乾物・贋物・官物・器物・偽物・旧物・御物・禁物・愚物・供物・景物・傑物・原物・現物・見物・献物・監物・好物・鉱物・穀物・個物・古物・才物・賽物・財物・作物・雑物・産物・残物・質物・実物・死物・私物・事物・什物・呪物・腫物・抄物・植物・食物・庶物・書物・人物・進物・生物・静物・贅物・施物・造物・贓物・臓物・俗物・代物・炭水化物・地物・長物・珍物・典物・天物・動物・唐物・毒物・鈍物・難物・廃物・博物・万物・風物・文物・幣物・変物・抛物線・放物線・宝物・無生物・名物・薬物・唯物論・有体物・尤物・陽物・利物・礼物・禄物・果物くだもの
〔牛(牜)部4画/8画/教育/4210・4A2A〕
〔音〕ブツ(漢) モツ(呉)
〔訓〕もの
[意味]
宇宙間にある(形ある)存在。もの。「万物・生物・物質・物価・食物しょくもつ・進物しんもつ・書物しょもつ」。特に、
㋐(世間に存在する)人。「人物・愚物・俗物・物議」
㋑事柄。「物理・事物・禁物きんもつ」
[解字]
形声。「牛」+音符「勿」。一定の特色のないさまざまなものの意。一説に、「勿」は切りきざむ意で、「物」は切って神に供える牛の肉と解する。
[下ツキ
阿堵物・一物・逸物・遺物・異物・音物・詠物・汚物・怪物・格物致知・貨物・奸物・換物・乾物・贋物・官物・器物・偽物・旧物・御物・禁物・愚物・供物・景物・傑物・原物・現物・見物・献物・監物・好物・鉱物・穀物・個物・古物・才物・賽物・財物・作物・雑物・産物・残物・質物・実物・死物・私物・事物・什物・呪物・腫物・抄物・植物・食物・庶物・書物・人物・進物・生物・静物・贅物・施物・造物・贓物・臓物・俗物・代物・炭水化物・地物・長物・珍物・典物・天物・動物・唐物・毒物・鈍物・難物・廃物・博物・万物・風物・文物・幣物・変物・抛物線・放物線・宝物・無生物・名物・薬物・唯物論・有体物・尤物・陽物・利物・礼物・禄物・果物くだもの
 筆順
筆順
 〔牛(牜)部4画/8画/教育/4210・4A2A〕
〔音〕ブツ(漢) モツ(呉)
〔訓〕もの
[意味]
宇宙間にある(形ある)存在。もの。「万物・生物・物質・物価・食物しょくもつ・進物しんもつ・書物しょもつ」。特に、
㋐(世間に存在する)人。「人物・愚物・俗物・物議」
㋑事柄。「物理・事物・禁物きんもつ」
[解字]
形声。「牛」+音符「勿」。一定の特色のないさまざまなものの意。一説に、「勿」は切りきざむ意で、「物」は切って神に供える牛の肉と解する。
[下ツキ
阿堵物・一物・逸物・遺物・異物・音物・詠物・汚物・怪物・格物致知・貨物・奸物・換物・乾物・贋物・官物・器物・偽物・旧物・御物・禁物・愚物・供物・景物・傑物・原物・現物・見物・献物・監物・好物・鉱物・穀物・個物・古物・才物・賽物・財物・作物・雑物・産物・残物・質物・実物・死物・私物・事物・什物・呪物・腫物・抄物・植物・食物・庶物・書物・人物・進物・生物・静物・贅物・施物・造物・贓物・臓物・俗物・代物・炭水化物・地物・長物・珍物・典物・天物・動物・唐物・毒物・鈍物・難物・廃物・博物・万物・風物・文物・幣物・変物・抛物線・放物線・宝物・無生物・名物・薬物・唯物論・有体物・尤物・陽物・利物・礼物・禄物・果物くだもの
〔牛(牜)部4画/8画/教育/4210・4A2A〕
〔音〕ブツ(漢) モツ(呉)
〔訓〕もの
[意味]
宇宙間にある(形ある)存在。もの。「万物・生物・物質・物価・食物しょくもつ・進物しんもつ・書物しょもつ」。特に、
㋐(世間に存在する)人。「人物・愚物・俗物・物議」
㋑事柄。「物理・事物・禁物きんもつ」
[解字]
形声。「牛」+音符「勿」。一定の特色のないさまざまなものの意。一説に、「勿」は切りきざむ意で、「物」は切って神に供える牛の肉と解する。
[下ツキ
阿堵物・一物・逸物・遺物・異物・音物・詠物・汚物・怪物・格物致知・貨物・奸物・換物・乾物・贋物・官物・器物・偽物・旧物・御物・禁物・愚物・供物・景物・傑物・原物・現物・見物・献物・監物・好物・鉱物・穀物・個物・古物・才物・賽物・財物・作物・雑物・産物・残物・質物・実物・死物・私物・事物・什物・呪物・腫物・抄物・植物・食物・庶物・書物・人物・進物・生物・静物・贅物・施物・造物・贓物・臓物・俗物・代物・炭水化物・地物・長物・珍物・典物・天物・動物・唐物・毒物・鈍物・難物・廃物・博物・万物・風物・文物・幣物・変物・抛物線・放物線・宝物・無生物・名物・薬物・唯物論・有体物・尤物・陽物・利物・礼物・禄物・果物くだもの
広辞苑に「物」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む