複数辞典一括検索+![]()
![]()
不屑 イサギヨシトセズ🔗⭐🔉
争 いさめる🔗⭐🔉
【争】
 6画 亅部 [四年]
区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188
【爭】旧字人名に使える旧字
6画 亅部 [四年]
区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188
【爭】旧字人名に使える旧字
 8画 爪部
区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5
《常用音訓》ソウ/あらそ…う
《音読み》 ソウ(サウ)
8画 爪部
区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5
《常用音訓》ソウ/あらそ…う
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)
《意味》
 {動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕
{動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕
 {助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕
{助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕
 {動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」
《解字》
{動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」
《解字》
 会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。
《単語家族》
諍ソウ(言いあってあらそう)
会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。
《単語家族》
諍ソウ(言いあってあらそう) 箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。
《類義》
→闘
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。
《類義》
→闘
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画 亅部 [四年]
区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188
【爭】旧字人名に使える旧字
6画 亅部 [四年]
区点=3372 16進=4168 シフトJIS=9188
【爭】旧字人名に使える旧字
 8画 爪部
区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5
《常用音訓》ソウ/あらそ…う
《音読み》 ソウ(サウ)
8画 爪部
区点=6407 16進=6027 シフトJIS=E0A5
《常用音訓》ソウ/あらそ…う
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/いかでか/いさめる(いさむ)
《意味》
 {動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕
{動}あらそう(アラソフ)。両方からとりあいをする。力ずくであらそう。「争奪」「君子無所争=君子ハ争フ所無シ」〔→論語〕
 {助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕
{助}いかでか。疑問・反語をあらわす助詞。どうして。▽やや口語的なことば。「誠知老去風情少、見此争無一句詩=誠ニ老イ去リテハ風情ノ少ナキヲ知ルモ、コレヲ見テハイカデカ一句ノ詩無カランヤ」〔→白居易〕
 {動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」
《解字》
{動}いさめる(イサム)。あやまちを改めるようにいう。▽諍ソウに当てた用法。「争臣(=諍臣)」
《解字》
 会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。
《単語家族》
諍ソウ(言いあってあらそう)
会意。「爪(手)+ー印+手」で、ある物を両者が手で引っぱりあうさまを示す。反対の方向に引っぱりあう、の意を含む。
《単語家族》
諍ソウ(言いあってあらそう) 箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。
《類義》
→闘
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
箏ソウ(両方から引きあって弦を張った琴)などと同系。
《類義》
→闘
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
些 いささか🔗⭐🔉
【些】
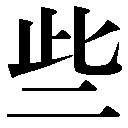 7画 二部
区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1
《音読み》 サ
7画 二部
区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1
《音読み》 サ /シャ
/シャ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 いささか
《意味》
〉
《訓読み》 いささか
《意味》
 {形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」
{形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」
 {助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕
《解字》
会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。
《単語家族》
煩瑣ハンサの瑣(こまごま)
{助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕
《解字》
会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。
《単語家族》
煩瑣ハンサの瑣(こまごま) 砂(細かいすな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
砂(細かいすな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
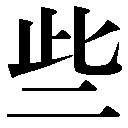 7画 二部
区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1
《音読み》 サ
7画 二部
区点=2619 16進=3A33 シフトJIS=8DB1
《音読み》 サ /シャ
/シャ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 いささか
《意味》
〉
《訓読み》 いささか
《意味》
 {形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」
{形}いささか。少しであるさま。細かい。「些少サショウ」
 {助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕
《解字》
会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。
《単語家族》
煩瑣ハンサの瑣(こまごま)
{助}楚ソの国の歌で、句末の間拍子マビョウシに用いる助詞。▽この場合は、サ((去)箇sa)と読む。「何為乎四方些=何ヲカ四方ニ為スヤ」〔→楚辞〕
《解字》
会意。此シは、「止(あし)+比(ならべる)の略体」から成り、足をちぐはぐに並べること。些は「此+二印(並べる)」でいくつかのものをざっと並べるの意を示す。こまかくて数多いの意を含む。
《単語家族》
煩瑣ハンサの瑣(こまごま) 砂(細かいすな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
砂(細かいすな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
偉才 イサイ🔗⭐🔉
【偉才】
イサイ =偉材。普通の人以上にすぐれた才能。また、それを持っている人。『偉器イキ』
功 いさお🔗⭐🔉
【功】
 5画 力部 [四年]
区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7
《常用音訓》ク/コウ
《音読み》 コウ
5画 力部 [四年]
区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7
《常用音訓》ク/コウ
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g ng〉
《訓読み》 いさお(いさを)
《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり
《意味》
ng〉
《訓読み》 いさお(いさを)
《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり
《意味》
 {名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
{名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
 コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕
コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕
 {名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕
{名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕
 {名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕
{名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕
 {名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕
{名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕
 「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。
「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。
 {名}〔仏〕よい行い。「功徳」
《解字》
会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。
《単語家族》
攻(あなをあけて突き抜く)
{名}〔仏〕よい行い。「功徳」
《解字》
会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。
《単語家族》
攻(あなをあけて突き抜く) 孔(突き抜けたあな)
孔(突き抜けたあな) 空(突き抜けたあな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
空(突き抜けたあな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 5画 力部 [四年]
区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7
《常用音訓》ク/コウ
《音読み》 コウ
5画 力部 [四年]
区点=2489 16進=3879 シフトJIS=8CF7
《常用音訓》ク/コウ
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g ng〉
《訓読み》 いさお(いさを)
《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり
《意味》
ng〉
《訓読み》 いさお(いさを)
《名付け》 あう・あつ・いさ・いさお・いさおし・かた・かつ・こと・つとむ・つとめ・なり・なる・のり
《意味》
 {名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
{名}いさお(イサヲ)。てがら。やりばえ。「論功=功ヲ論ズ」「功績」「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
 コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕
コウトス{動}てがらと考える。功績とみなす。「公子乃自驕而功之=公子スナハチミヅカラ驕リテコレヲ功トス」〔→史記〕
 {名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕
{名}働きの結果。成し遂げた仕事。「成功=功ヲ成ス」「功遂身退天之道=功遂ゲ身退クハ天ノ道ナリ」〔→老子〕
 {名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕
{名}ききめ。実り。「奏功=功ヲ奏ス」「夫伐深根者難為功=ソレ深根ヲ伐ル者ハ功ヲ為シ難シ」〔曹冏〕
 {名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕
{名}努力。または、工夫。「用功=功ヲ用フ」「人不暇施功=人功ヲ施スニ暇アラズ」〔→司馬相如〕
 「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。
「功服」とは、喪服の一種。大功と小功がある。
 {名}〔仏〕よい行い。「功徳」
《解字》
会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。
《単語家族》
攻(あなをあけて突き抜く)
{名}〔仏〕よい行い。「功徳」
《解字》
会意兼形声。工は、上下両面にあなをあけること。功は「力+音符工」。あなをあけるのはむずかしい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえを功という。
《単語家族》
攻(あなをあけて突き抜く) 孔(突き抜けたあな)
孔(突き抜けたあな) 空(突き抜けたあな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
空(突き抜けたあな)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
勇 いさましい🔗⭐🔉
【勇】
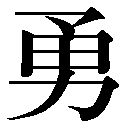 9画 力部 [四年]
区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745
《常用音訓》ユウ/いさ…む
《音読み》 ユウ/ユ
9画 力部 [四年]
区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745
《常用音訓》ユウ/いさ…む
《音読み》 ユウ/ユ /ヨウ
/ヨウ 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ
《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ
《意味》
ng〉
《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ
《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ
《意味》
 ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕
ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕
 {名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕
{名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕
 {動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕
{動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕
 {名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」
《解字》
会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」
《解字》
会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
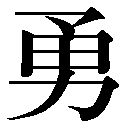 9画 力部 [四年]
区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745
《常用音訓》ユウ/いさ…む
《音読み》 ユウ/ユ
9画 力部 [四年]
区点=4506 16進=4D26 シフトJIS=9745
《常用音訓》ユウ/いさ…む
《音読み》 ユウ/ユ /ヨウ
/ヨウ 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ
《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ
《意味》
ng〉
《訓読み》 いさましい(いさまし)/いさむ
《名付け》 いさ・いさお・いさまし・いさみ・いさむ・お・さ・そよ・たけ・たけし・とし・はや・よ
《意味》
 ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕
ユウナリ{形}いさましい(イサマシ)。もと、足ぶみして奮いたつさま。のち、気力が盛んで強いさま。〈対語〉→怯キョウ。〈類義語〉→壮・→孟。「勇者」「民勇於公戦、怯於私闘=民公戦ニ勇ニシテ、私闘ニ怯ナリ」〔→史記〕
 {名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕
{名}まともに事にぶつかる気構え。「勇気」「見義不為、無勇也=義ヲ見テ為ザルハ、勇無キナリ」〔→論語〕
 {動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕
{動}いさむ。心が奮いたつ。いさみたつ。「勇於為人、不自貴重顧藉=人ノ為ニスルニ勇ミ、ミヅカラ貴重顧藉セズ」〔→韓愈〕
 {名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」
《解字》
会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}中国の民間の自警団。義勇兵。「民勇」「郷勇」
《解字》
会意兼形声。甬ヨウは「人+音符用」から成り、用はつき通す意を含む。足でとんとんと突き通すように足踏みするのを甬ヨウ・踊ヨウという。勇は「力+音符甬ヨウ」で、力があふれ足踏みして奮いたつ意。また、衝(まともに直進して突き当たる)とも縁が近い。→甬
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
勲 いさお🔗⭐🔉
【勲】
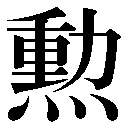 15画 力部 [常用漢字]
区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D
【勳】旧字人名に使える旧字
15画 力部 [常用漢字]
区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D
【勳】旧字人名に使える旧字
 16画 力部
区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
16画 力部
区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
 〈x
〈x n〉
《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)
《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ
《意味》
n〉
《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)
《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ
《意味》
 {名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕
{名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕
 {名}てがらをたてた人。「元勲」
《解字》
会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}てがらをたてた人。「元勲」
《解字》
会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
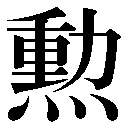 15画 力部 [常用漢字]
区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D
【勳】旧字人名に使える旧字
15画 力部 [常用漢字]
区点=2314 16進=372E シフトJIS=8C4D
【勳】旧字人名に使える旧字
 16画 力部
区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
16画 力部
区点=5014 16進=522E シフトJIS=99AC
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
 〈x
〈x n〉
《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)
《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ
《意味》
n〉
《訓読み》 いさお(いさを)/いさおし(いさをし)
《名付け》 いさ・いさお・いそ・こと・つとむ・ひろ
《意味》
 {名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕
{名}いさお(イサヲ)。いさおし(イサヲシ)。かぐわしいてがら。「勲功」「興功立勲=功ヲ興シ勲ヲ立ツ」〔曹冏〕
 {名}てがらをたてた人。「元勲」
《解字》
会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}てがらをたてた人。「元勲」
《解字》
会意兼形声。熏クンは、炎の上に煙突があり、煙がこもるさまを示す会意文字。薫クン(かぐわしい草)・醺クン(かぐわしい酒のかおり)の原字で、よいにおいのこもること。勳は「力+音符熏」で、かぐわしい努力の実り、つまり賞賛されるてがらのこと。→熏
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
委細 イサイ🔗⭐🔉
【委細】
イサイ こまごまと詳しいこと。『委悉イシツ・委備イビ』
廉 いさぎよい🔗⭐🔉
【廉】
 13画 广部 [常用漢字]
区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5
《常用音訓》レン
《音読み》 レン(レム)
13画 广部 [常用漢字]
区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5
《常用音訓》レン
《音読み》 レン(レム)
 〈li
〈li n〉
《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)
《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)
《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき
《意味》
 {名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」
{名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」
 {名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」
{名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」
 {形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕
{形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕
 {形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」
{形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」
 「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。
「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。
 「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。
〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」
《解字》
会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。
〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」
《解字》
会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 13画 广部 [常用漢字]
区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5
《常用音訓》レン
《音読み》 レン(レム)
13画 广部 [常用漢字]
区点=4687 16進=4E77 シフトJIS=97F5
《常用音訓》レン
《音読み》 レン(レム)
 〈li
〈li n〉
《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)
《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 かど/いさぎよい(いさぎよし)/やすい(やすし)
《名付け》 おさ・かど・きよ・きよし・すが・すなお・ただし・やす・ゆき
《意味》
 {名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」
{名}かど。一つ一つの境め。「堂廉ドウレン(建物の境め)」
 {名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」
{名}かど。物事のけじめ・折りめ。「廉隅レングウ(けじめ)」
 {形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕
{形}いさぎよい(イサギヨシ)。善悪のけじめがたっているさま。欲につられてけじめを失わないさま。〈類義語〉→潔。「廉潔レンケツ」「豈不誠廉士哉=アニ誠ノ廉士ナラズヤ」〔→孟子〕
 {形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」
{形}やすい(ヤスシ)。けじめをたてて暴利をおさえたさま。欲ばらないさま。「廉価」
 「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。
「廉訪使レンポウシ」とは、行政を監察してけじめをつける役目。元ゲン代、粛政廉訪司の長官。
 「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。
〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」
《解字》
会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「養廉銀ヨウレンギン」とは、官兵に不正を行わせないように待遇を改善する加俸のこと。清シン代、地方官に支給された。
〔国〕かど。(イ)箇条。(ロ)理由。「窃盗の廉により処罰」
《解字》
会意兼形声。兼は「禾二本+手のかたち」の会意文字で、別々の物をかねまとめて持つこと。廉は「广(いえ)+音符兼」で、家の中に寄せあわせた物の一つ一つを区別する意を示す。転じて、物事のけじめをつけること。→兼
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
彙纂 イサン🔗⭐🔉
【彙纂】
イサン いろいろの事がらをあつめ、分類して編集する。『彙集イシュウ』
愎諫 イサメニモトル🔗⭐🔉
【愎諫】
フッカン・イサメニモトル ずぶとくて、いさめるのをきかない。〔→左伝〕
涓 いさぎよい🔗⭐🔉
【涓】
 10画 水部
区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0
《音読み》 ケン
10画 水部
区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0
《音読み》 ケン
 〈ju
〈ju n〉
《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)
《意味》
n〉
《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)
《意味》
 {名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。
{名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。
 {名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」
{名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」
 {動}おちる(オツ)。しずくがおちる。
{動}おちる(オツ)。しずくがおちる。
 {動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」
{動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」
 {形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 10画 水部
区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0
《音読み》 ケン
10画 水部
区点=6218 16進=5E32 シフトJIS=9FB0
《音読み》 ケン
 〈ju
〈ju n〉
《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)
《意味》
n〉
《訓読み》 しずく(しづく)/おちる(おつ)/えらぶ/いさぎよい(いさぎよし)
《意味》
 {名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。
{名}ちょろちょろ流れる水。細いからだをひねったようにして流れる細流。
 {名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」
{名}しずく(シヅク)。わずかなこと、小さいことのたとえ。「涓滴ケンテキ」「涓埃ケンアイ」
 {動}おちる(オツ)。しずくがおちる。
{動}おちる(オツ)。しずくがおちる。
 {動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」
{動}えらぶ。細かくよりわける。「涓選ケンセン」「涓吉ケンキツ(吉日をえらぶ)」
 {形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{形}いさぎよい(イサギヨシ)。意地をはっても、不潔なことはしないさま。清潔である。〈同義語〉→狷。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エン・ケン)は、まるくからだをひねるぼうふら。涓はそれを音符とし、水を加えた字で、細くひねるの意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
潔 いさぎよい🔗⭐🔉
【潔】
 15画 水部 [五年]
区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89
《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い
《音読み》 ケツ
15画 水部 [五年]
区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89
《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い
《音読み》 ケツ /ケチ
/ケチ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)
《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)
《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし
《意味》
 {形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」
{形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」
 {形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」
{形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」
 {動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 水部 [五年]
区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89
《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い
《音読み》 ケツ
15画 水部 [五年]
区点=2373 16進=3769 シフトJIS=8C89
《常用音訓》ケツ/いさぎよ…い
《音読み》 ケツ /ケチ
/ケチ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)
《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 いさぎよい(いさぎよし)/きよい(きよし)/いさぎよくする(いさぎよくす)/きよめる(きよむ)
《名付け》 きよ・きよし・ゆき・よし
《意味》
 {形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」
{形・名}いさぎよい(イサギヨシ)。きよい(キヨシ)。さっぱりとしたさま。けじめただしいこと。「潔浄」「清潔」
 {形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」
{形}きよい(キヨシ)。さっぱりしていて、欲がないさま。「清廉潔白」
 {動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}いさぎよくする(イサギヨクス)。きよめる(キヨム)。さっぱりときよらかにする。きっぱりと、けじめをつける。引き締める。「欲潔其身而乱大倫=其ノ身ヲ潔クセント欲シテ大倫ヲ乱ル」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ケツ)は、ぐっと引き締める意を含む。潔はそれを音符とし、水をそえた字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
異才 イサイ🔗⭐🔉
【異才】
イサイ =異材。人なみすぐれた才能。また、人なみすぐれた才能を持った人。
縊殺 イサツ🔗⭐🔉
【縊殺】
イサツ 首をしめて殺す。
績 いさお🔗⭐🔉
【績】
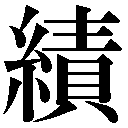 17画 糸部 [五年]
区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ
17画 糸部 [五年]
区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ /シャク
/シャク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)
《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり
《意味》
〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)
《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり
《意味》
 {動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕
{動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕
 {動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。
{動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。
 {名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。
《単語家族》
積セキ(つみ重ね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。
《単語家族》
積セキ(つみ重ね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
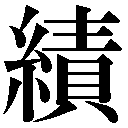 17画 糸部 [五年]
区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ
17画 糸部 [五年]
区点=3251 16進=4053 シフトJIS=90D1
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ /シャク
/シャク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)
《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり
《意味》
〉
《訓読み》 つむぐ/うむ/いさお(いさを)
《名付け》 いさ・いさお・さね・つみ・なり・のり・もり
《意味》
 {動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕
{動}つむぐ。縦糸を張った間に、横糸をだんだん積み重ねていく。布を織る。〈類義語〉→紡。「紡績」「績麻=麻ヲ績グ」「孟母方績=孟母マサニ績グ」〔→列女〕
 {動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。
{動}うむ。麻の長い繊維をよりながら、一段一段とつぎたして、糸をつくる。
 {名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。
《単語家族》
積セキ(つみ重ね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}いさお(イサヲ)。一段一段と積みかさねてきた仕事。また、そのよい結果。てがら。〈類義語〉→功。「功績」「成績」「九載績用弗成=九載ニシテ績用成ラズ」〔→書経〕
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、ぎざぎざにとがったとげを描いた象形文字。責セキは「貝(財貨)+音符朿」の会意兼形声文字で、借金の積みかさなりを示す。績は「糸+音符責」で、横糸を積み重ねて布を織ること。
《単語家族》
積セキ(つみ重ね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
聊 いささか🔗⭐🔉
【聊】
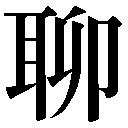 11画 耳部
区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6
《音読み》 リョウ(レウ)
11画 耳部
区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6
《音読み》 リョウ(レウ)
 〈li
〈li o〉
《訓読み》 いささか
《意味》
o〉
《訓読み》 いささか
《意味》
 {副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍
{副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍 以相羊=聊カ逍
以相羊=聊カ逍 シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕
シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕
 リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」
リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」
 「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕
「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕
 {動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」
《解字》
会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。
《単語家族》
留(つかえる)
{動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」
《解字》
会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。
《単語家族》
留(つかえる) 瘤リュウ(しこる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
瘤リュウ(しこる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
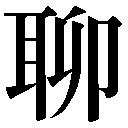 11画 耳部
区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6
《音読み》 リョウ(レウ)
11画 耳部
区点=7056 16進=6658 シフトJIS=E3D6
《音読み》 リョウ(レウ)
 〈li
〈li o〉
《訓読み》 いささか
《意味》
o〉
《訓読み》 いささか
《意味》
 {副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍
{副}いささか。とりあえず。今しばらく。わりきれないままに。なんとはなしに。〈類義語〉→且ショ。「聊逍 以相羊=聊カ逍
以相羊=聊カ逍 シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕
シテモッテ相羊ス」〔→楚辞〕
 リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」
リョウス{動}どうにか事が運ぶ。やっとしまつする。「民、不聊生=民、生ヲ聊セズ」
 「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕
「無聊ブリョウ」とは、事がわりきれず不快なこと。また、気持ちの晴れないこと。「意無聊=意無聊ナリ」〔→楚辞〕
 {動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」
《解字》
会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。
《単語家族》
留(つかえる)
{動・形}耳鳴りがする。また、どうにか耳が通るが、よく聞こえないさま。「聊啾リョウシュウ(かすかに耳が鳴る)」
《解字》
会意兼形声。「耳+音符卯リュウ(つかえる、しこる)」で、耳がつかえて音がよく通らないこと。しばらくつかえて、とどまるの意から。一時のしのぎに(とりあえず)の意となる。▽この音符は、のち卯ボウ・モウと混同された。
《単語家族》
留(つかえる) 瘤リュウ(しこる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
瘤リュウ(しこる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
諍 いさめる🔗⭐🔉
【諍】
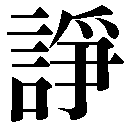 15画 言部
区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679
《音読み》 ソウ(サウ)
15画 言部
区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)
《意味》
 {動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。
{動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。
 {動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」
{動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」
 {動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」
《解字》
会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」
《解字》
会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
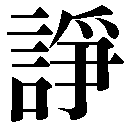 15画 言部
区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679
《音読み》 ソウ(サウ)
15画 言部
区点=7558 16進=6B5A シフトJIS=E679
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/いさめる(いさむ)
《意味》
 {動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。
{動}あらそう(アラソフ)。いさかいをする。いいあらそう。論争する。〈同義語〉→争。
 {動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」
{動}うったえる(ウツタフ)。うったえていいあらそう。〈類義語〉→訟。「諍訟ソウショウ」
 {動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」
《解字》
会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}いさめる(イサム)。きつくいさめてやめさせる。〈類義語〉→諫カン。「諍臣ソウシン」「諫諍カンソウ」
《解字》
会意兼形声。爭ソウ(=争)は、一つのものを両方にひっぱりあうことを示す会意文字。諍ソウは「言+音符爭」で、ことばで両方からとりあいをすること。いさめる、うったえる、などというのは、その派生義である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
諫 いさめ🔗⭐🔉
【諫】
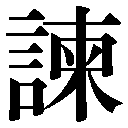 16画 言部
区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C
【諌】異体字異体字
16画 言部
区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C
【諌】異体字異体字
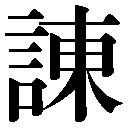 15画 言部
区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0
《音読み》 カン
15画 言部
区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0
《音読み》 カン /ケン
/ケン 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ
《意味》
n〉
《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ
《意味》
 {動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕
{動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕
 {動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。
《単語家族》
欄ラン(さえぎりとめる囲い)
{動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。
《単語家族》
欄ラン(さえぎりとめる囲い) 扞カン(相手をおさえとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
扞カン(相手をおさえとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
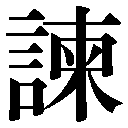 16画 言部
区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C
【諌】異体字異体字
16画 言部
区点=7561 16進=6B5D シフトJIS=E67C
【諌】異体字異体字
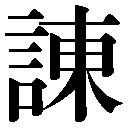 15画 言部
区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0
《音読み》 カン
15画 言部
区点=2050 16進=3452 シフトJIS=8AD0
《音読み》 カン /ケン
/ケン 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ
《意味》
n〉
《訓読み》 いさめる(いさむ)/いさめ
《意味》
 {動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕
{動・名}いさめる(イサム)。いさめ。目上の人の不正をおさえとどめるために意見する。いさめることば。「信而後諫=信ゼラレテ、シカウシテ後ニ諫ム」〔→論語〕
 {動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。
《単語家族》
欄ラン(さえぎりとめる囲い)
{動}いさめる(イサム)。過ちを正す。よしあしをわけてとがめる。してしまったあとから文句をつける。「逐事不諫=逐事ハ諫メズ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。「言+音符柬カン(よしあしをわける、おさえる)」。
《単語家族》
欄ラン(さえぎりとめる囲い) 扞カン(相手をおさえとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
扞カン(相手をおさえとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
諷 いさめる🔗⭐🔉
違算 イサン🔗⭐🔉
【違算】
イサン〔国〕 計算ちがい。
計算ちがい。 はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。
はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。
 計算ちがい。
計算ちがい。 はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。
はじめの計画とあわないこと。もくろみちがい。
遺産 イサン🔗⭐🔉
【遺産】
イサン 故人が家族にのこしおいた財産。
遺策 イサク🔗⭐🔉
【遺策】
イサク  ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」
ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」 先人ののこしたはかりごと。
先人ののこしたはかりごと。 散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。
散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。
 ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」
ておちや、見落としのあったはかりごと。失計。『遺計イケイ』「無遺策=遺策無シ」 先人ののこしたはかりごと。
先人ののこしたはかりごと。 散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。
散逸した部分のある、昔から伝えられた書物。▽「策」は、竹札・木札に書いた書物。
遺算 イサン🔗⭐🔉
【遺算】
イサン 物事を行うのに不完全であること。計算違い。みこみちがい。
閥 いさお🔗⭐🔉
【閥】
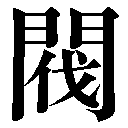 14画 門部 [常用漢字]
区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4
《常用音訓》バツ
《音読み》 バツ
14画 門部 [常用漢字]
区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4
《常用音訓》バツ
《音読み》 バツ /ボチ
/ボチ /ハツ
/ハツ 〈f
〈f 〉
《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ
《名付け》 いさお
《意味》
〉
《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ
《名付け》 いさお
《意味》
 {名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。
{名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。
 {名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」
{名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」
 {名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。
〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」
《解字》
会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。
〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」
《解字》
会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
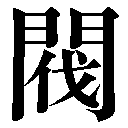 14画 門部 [常用漢字]
区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4
《常用音訓》バツ
《音読み》 バツ
14画 門部 [常用漢字]
区点=4022 16進=4836 シフトJIS=94B4
《常用音訓》バツ
《音読み》 バツ /ボチ
/ボチ /ハツ
/ハツ 〈f
〈f 〉
《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ
《名付け》 いさお
《意味》
〉
《訓読み》 いさお(いさを)/ばつ
《名付け》 いさお
《意味》
 {名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。
{名}いさお(イサヲ)。てがら。誇らしげな功績。〈類義語〉→伐。
 {名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」
{名}外にむけて勢いを誇る家がら。家の社会的な地位。門地。「門閥」
 {名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。
〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」
《解字》
会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}家がらの高い家の門の左側の柱にかざす札。また、その柱。▽右側にたてる柱、およびそこにかける札を閲エツという。
〔国〕ばつ。党派・出身・利害など何らかの点で同じくする者が結んで、排他的な立場をとるグループ。「学閥」「財閥」
《解字》
会意兼形声。「門+音符伐(力を誇る、ひけらかす)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「いさ」で始まるの検索結果 1-27。
 16画 言部
区点=7569 16進=6B65 シフトJIS=E685
《音読み》 フウ/フ
16画 言部
区点=7569 16進=6B65 シフトJIS=E685
《音読み》 フウ/フ ng〉
《訓読み》 うたう(うたふ)/いさめる(いさむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 うたう(うたふ)/いさめる(いさむ)
《意味》