複数辞典一括検索+![]()
![]()
丼 い🔗⭐🔉
【丼】
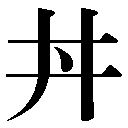 5画 丶部
区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5
《音読み》 セイ
5画 丶部
区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5
《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 い/どんぶり
《意味》
{名}い(
ng〉
《訓読み》 い/どんぶり
《意味》
{名}い( )。いど。〈同義語〉→井。
〔国〕
)。いど。〈同義語〉→井。
〔国〕 どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。
どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。 どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。
《解字》
会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青
どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。
《解字》
会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青
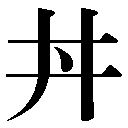 5画 丶部
区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5
《音読み》 セイ
5画 丶部
区点=4807 16進=5027 シフトJIS=98A5
《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 い/どんぶり
《意味》
{名}い(
ng〉
《訓読み》 い/どんぶり
《意味》
{名}い( )。いど。〈同義語〉→井。
〔国〕
)。いど。〈同義語〉→井。
〔国〕 どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。
どんぶり。厚みのある深い陶製のはち。どんぶりばち。また、それに飯を盛り、種をのせた料理。 どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。
《解字》
会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青
どんぶり。職人などが着る腹がけの前部につけた物入れ。
《解字》
会意。「井(四角い井戸のわく)+・印(清い水のたまったさま)」で、清らかな水をあらわす。青(すみきってあおい)の下部に含まれる。ただし、のちには、井戸の清水を示す丼セイは井と書かれるようになった。わくを示す井ケイは、かたちを変えて形・型に含まれる。→青
云 いう🔗⭐🔉
【云】
 4画 二部
区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D
《音読み》 ウン
4画 二部
区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D
《音読み》 ウン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 いう(いふ)/ここに
《意味》
n〉
《訓読み》 いう(いふ)/ここに
《意味》
 {動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。
{動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。
 {助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕
{助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕
 「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。
《解字》
「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。
《解字》
 指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 4画 二部
区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D
《音読み》 ウン
4画 二部
区点=1730 16進=313E シフトJIS=895D
《音読み》 ウン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 いう(いふ)/ここに
《意味》
n〉
《訓読み》 いう(いふ)/ここに
《意味》
 {動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。
{動}いう(イフ)。口ごもって声を出す。転じて、ものをいう。
 {助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕
{助}ここに。文中・文末にあって、語調を整えたり、上の文をおさめたりすることば。「道之云遠、曷云能来=道ノ云ニ遠キ、曷カ云ニ能ク来タラン」〔→詩経〕「則可謂云爾已矣=則チ謂フベキノミ」〔→論語〕
 「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。
《解字》
「…云云ウンヌン・ウンウン」とは、それ以下を省略する場合に用いることば。
《解字》
 指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
指事。息や空気が曲折してたちあがるさまを示す。もと、口の中に息がとぐろを巻いて口ごもること。雲(もくもくとあがる水気)の原字。耘ウン(土をもくもくとこね返す)・魂(もやもやした亡霊)に音符として含まれる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
井 い🔗⭐🔉
【井】
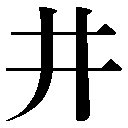 4画 二部 [常用漢字]
区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4
《常用音訓》ショウ/セイ/い
《音読み》 セイ
4画 二部 [常用漢字]
区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4
《常用音訓》ショウ/セイ/い
《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 い
《名付け》 い・きよ
《意味》
ng〉
《訓読み》 い
《名付け》 い・きよ
《意味》
 {名}い(
{名}い( )。いど。
)。いど。
 {名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。
{名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。
 {形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」
{形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」
 {名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕
{名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。
 {名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。
《解字》
{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。
《解字》
 象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
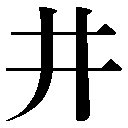 4画 二部 [常用漢字]
区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4
《常用音訓》ショウ/セイ/い
《音読み》 セイ
4画 二部 [常用漢字]
区点=1670 16進=3066 シフトJIS=88E4
《常用音訓》ショウ/セイ/い
《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 い
《名付け》 い・きよ
《意味》
ng〉
《訓読み》 い
《名付け》 い・きよ
《意味》
 {名}い(
{名}い( )。いど。
)。いど。
 {名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。
{名}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。
 {形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」
{形}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」
 {名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕
{名}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里ニシテ井ナリ、井ハ九百畝ナリ」〔→孟子〕
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。
 {名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。
《解字》
{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下坎上ソンカカンショウ。
《解字》
 象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
亥 い🔗⭐🔉
【亥】
 6画 亠部 [人名漢字]
区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5
《音読み》 ガイ
6画 亠部 [人名漢字]
区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5
《音読み》 ガイ /カイ
/カイ 〈h
〈h i〉
《訓読み》 い(ゐ)
《名付け》 い・り
《意味》
{名}い(
i〉
《訓読み》 い(ゐ)
《名付け》 い・り
《意味》
{名}い( )。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」
《解字》
)。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」
《解字》
 象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 亠部 [人名漢字]
区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5
《音読み》 ガイ
6画 亠部 [人名漢字]
区点=1671 16進=3067 シフトJIS=88E5
《音読み》 ガイ /カイ
/カイ 〈h
〈h i〉
《訓読み》 い(ゐ)
《名付け》 い・り
《意味》
{名}い(
i〉
《訓読み》 い(ゐ)
《名付け》 い・り
《意味》
{名}い( )。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」
《解字》
)。十二支の第十二番。▽時刻では午後十時およびその前後二時間、方角では北北西、動物ではいのししに当てる。「辛亥シンガイ・カノトイ」
《解字》
 象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
象形。いのしし、または豚の骨格をたてに描いたもので、骨組み、骨組みができあがるの意を含む。豕シ(豚)の字と似ているが、亥は豚そのものではなく、豚の骨組みを示す。骸ガイ(骨組み)・孩ガイ(骨格のできた幼児)・核(果実の骨組み→かたいからや、しん)に含まれる。また、十二進法の体系(骨組み)が全部張りわたった所に位置する数だから、十二番めを亥ガイという。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
伊尹 イイン🔗⭐🔉
【伊尹】
イイン〈人名〉殷インの知恵者。湯トウ王を助けて世の中を調和しておさめた。伝説では代表的な上古の賢人とされる。
依阿 イア🔗⭐🔉
【依阿】
イア こびへつらう。▽「阿」は、迎合する。
依倚 イイ🔗⭐🔉
【依倚】
イイ『依憑イヒョウ』よりかかる。たよること。
依違 イイ🔗⭐🔉
【依違】
イイ ぐずぐずして態度がはっきりしないさま。
舎 いえ🔗⭐🔉
【舎】
 8画 人部 [五年]
区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9
【舍】旧字旧字
8画 人部 [五年]
区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9
【舍】旧字旧字
 8画 舌部
区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
8画 舌部
区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
 〈sh
〈sh ・sh
・sh 〉
《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 いえ・や・やどる
《意味》
〉
《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 いえ・や・やどる
《意味》
 {名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕
{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕
 シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕
シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕
 {動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕
{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕
 {動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」
{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」
 {動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」
{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」
 {動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」
{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」
 {単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」
{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」
 {形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」
《解字》
会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余
《単語家族》
捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく)
{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」
《解字》
会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余
《単語家族》
捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく) 赦シャ(ゆるめてはなす)
赦シャ(ゆるめてはなす) 舒ジョ(のばす)
舒ジョ(のばす) 射シャ(張った矢をはなす)などと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
射シャ(張った矢をはなす)などと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 8画 人部 [五年]
区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9
【舍】旧字旧字
8画 人部 [五年]
区点=2843 16進=3C4B シフトJIS=8EC9
【舍】旧字旧字
 8画 舌部
区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
8画 舌部
区点=7150 16進=6752 シフトJIS=E471
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
 〈sh
〈sh ・sh
・sh 〉
《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 いえ・や・やどる
《意味》
〉
《訓読み》 やど/いえ(いへ)/やどる/やどす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 いえ・や・やどる
《意味》
 {名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕
{名}やど。いえ(イヘ)。手足をのばしてくつろぐいえ。ひと休みするやど。「宿舎」「其舎近墓=其ノ舎墓ニ近シ」〔→列女伝〕
 シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕
シャス{動}やどる。やどす。からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。いえをかまえて住む。「出舎於郊=出デテ郊ニ舎ル」〔→孟子〕「乃去舎市傍=乃チ去リテ市ノ傍ニ舎ス」〔→列女〕
 {動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕
{動}おく。すてる(スツ)。手をゆるめてはなしおく。また、すておく。はなす。▽上声に読む。〈同義語〉→捨。「舎箸=箸ヲ舎ク」「舎而不問=舎キテ問ハズ」「山川其舎諸=山川其レ諸ヲ舎テンヤ」〔→論語〕
 {動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」
{動}ゆるしてはなす。▽上声に読む。〈同義語〉→赦。「饒舎ジョウシャ(ゆるして放免する)」
 {動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」
{動}持っていた物をはなして人にやる。▽上声に読む。「施舎」
 {動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」
{動}そなえ物をならべておく。▽釈セキに当てた用法。「舎奠セキテン(=釈奠)」「舎采セキサイ(=釈采)」
 {単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」
{単位}軍隊の行軍の距離をあらわすことば。一舎は、周代、三十里。約一二キロメートル。▽昔の軍隊が大休止(舎)するまでの行程を基準とした。「退辟三舎=退辟スルコト三舎」
 {形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」
《解字》
会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余
《単語家族》
捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく)
{形}自分の身うちや自分が所有するものを謙そんしていうことば。▽自分のうちの、の意。「舎弟(わたしの弟)」
《解字》
会意兼形声。余の原字は、土を伸ばすスコップのさま。舍は「口(ある場所)+音符余」で、手足を伸ばす場所。つまり、休み所や宿舎のこと。→余
《単語家族》
捨(つかんだ指を伸ばす→はなしてそのままにしておく) 赦シャ(ゆるめてはなす)
赦シャ(ゆるめてはなす) 舒ジョ(のばす)
舒ジョ(のばす) 射シャ(張った矢をはなす)などと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
射シャ(張った矢をはなす)などと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
唯唯諾諾 イイダクダク🔗⭐🔉
【唯唯諾諾】
イイダクダク〈故事〉事のよしあしにかかわらず他人のいうとおりになるさま。〔→韓非〕
坊 いえ🔗⭐🔉
【坊】
 7画 土部 [常用漢字]
区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656
《常用音訓》ボウ/ボッ
《音読み》 ボウ(バウ)
7画 土部 [常用漢字]
区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656
《常用音訓》ボウ/ボッ
《音読み》 ボウ(バウ) /ボッ
/ボッ /ホウ(ハウ)
/ホウ(ハウ) 〈f
〈f ng・f
ng・f ng〉
《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)
《意味》
ng〉
《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)
《意味》
 {名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」
{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」
 {名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」
{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」
 {名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」
{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」
 {動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕
〔国〕
{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕
〔国〕 「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」
「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」 ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」
《解字》
会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」
《解字》
会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 土部 [常用漢字]
区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656
《常用音訓》ボウ/ボッ
《音読み》 ボウ(バウ)
7画 土部 [常用漢字]
区点=4323 16進=4B37 シフトJIS=9656
《常用音訓》ボウ/ボッ
《音読み》 ボウ(バウ) /ボッ
/ボッ /ホウ(ハウ)
/ホウ(ハウ) 〈f
〈f ng・f
ng・f ng〉
《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)
《意味》
ng〉
《訓読み》 まち/へや/いえ(いへ)/ふせぐ/ぼう(ばう)
《意味》
 {名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」
{名}まち。方形に区切った街路。転じて、市街地の区画の名。「街坊」「坊廂ボウショウ(市街地)」
 {名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」
{名}孝子や節婦を記念するため、街路の入り口にたてた門や建物。「孝坊」
 {名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」
{名}へや。いえ(イヘ)。住居。〈同義語〉→房。「春坊(皇太子の居所)」「僧坊(僧の住む家)」
 {動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕
〔国〕
{動・名}ふせぐ。さえぎる。さえぎるもの。▽防に当てた用法。「因人之情而為之節文、以為民坊者也=人ノ情ニ因リテコレガ節文ヲ為シ、モツテ民ノ坊ギト為ス者ナリ」〔→礼記〕
〔国〕 「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」
「坊主ボウズ」の略。僧。「武蔵坊ムサシボウ」 ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」
《解字》
会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
ぼう(バウ)。(イ)幼い男の子を親しんで呼ぶことば。「坊や」(ロ)他人を親しみ、また、軽んじていうことば。「朝寝坊」「けちん坊」
《解字》
会意兼形声。方は、左と右に張り出たすきの柄を描いた象形文字。坊は「土+音符方」。もと堤防の防と同じで、両側に張り出した堤や壁。のち、四角く区切った街路の意に用いる。▽方(四角い)からの派生義である。→方
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
威圧 イアツ🔗⭐🔉
【威圧】
イアツ 勢力で人をおさえつけること。
宇 いえ🔗⭐🔉
【宇】
 6画 宀部 [六年]
区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946
《常用音訓》ウ
《音読み》 ウ
6画 宀部 [六年]
区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946
《常用音訓》ウ
《音読み》 ウ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 いえ(いへ)
《名付け》 うま・たか・ね・のき
《意味》
〉
《訓読み》 いえ(いへ)
《名付け》 うま・たか・ね・のき
《意味》
 {名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕
{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕
 {名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」
{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」
 {名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」
{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」
 {名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。
《単語家族》
迂ウ(大きくまわる)
{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。
《単語家族》
迂ウ(大きくまわる) 盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 6画 宀部 [六年]
区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946
《常用音訓》ウ
《音読み》 ウ
6画 宀部 [六年]
区点=1707 16進=3127 シフトJIS=8946
《常用音訓》ウ
《音読み》 ウ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 いえ(いへ)
《名付け》 うま・たか・ね・のき
《意味》
〉
《訓読み》 いえ(いへ)
《名付け》 うま・たか・ね・のき
《意味》
 {名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕
{名}いえ(イヘ)。大きな屋根でおおったいえ。また住居をおおうひさし。また、軒下。転じて、大きな建物。「玉宇(大理石の大きな建物)」「香茅結為宇=香茅結ンデ宇ト為ス」〔→王維〕
 {名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」
{名}大きい屋根のような大空におおわれた世界。すべての空間。「宇宙」「寰宇カンウ」「宇内ウダイ(天下)」
 {名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」
{名}空間的なスケール。大きさ。「気宇」
 {名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。
《単語家族》
迂ウ(大きくまわる)
{名}天子の統治する世界。「御宇ギョウ」「御宇多年求不得=御宇多年求ムレドモ得ズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。于は大きく曲がるさまを示す。宇は「宀(やね)+音符于ウ」で、大きくてまるい屋根のこと。
《単語家族》
迂ウ(大きくまわる) 盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
盂ウ(まるくくぼんだ大ざら)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
室 いえ🔗⭐🔉
【室】
 9画 宀部 [二年]
区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA
《常用音訓》シツ/むろ
《音読み》 シツ
9画 宀部 [二年]
区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA
《常用音訓》シツ/むろ
《音読み》 シツ /シチ
/シチ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや
《名付け》 いえ・むろ・や
《意味》
〉
《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや
《名付け》 いえ・むろ・や
《意味》
 {名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕
{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕
 {名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」
{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」
 {名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕
{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕
 {単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕
{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕
 {名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕
{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕
 {名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕
{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕
 {名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。
《単語家族》
窒チツ(いきづまり)
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。
《単語家族》
窒チツ(いきづまり) 膣チツと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
膣チツと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 宀部 [二年]
区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA
《常用音訓》シツ/むろ
《音読み》 シツ
9画 宀部 [二年]
区点=2828 16進=3C3C シフトJIS=8EBA
《常用音訓》シツ/むろ
《音読み》 シツ /シチ
/シチ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや
《名付け》 いえ・むろ・や
《意味》
〉
《訓読み》 へや/むろ/いえ(いへ)/さや
《名付け》 いえ・むろ・や
《意味》
 {名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕
{名}へや。奥まったへや。〈対語〉→堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂ニ升レリ、イマダ室ニ入ラザルナリ」〔→論語〕
 {名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」
{名}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室ヒムロ」
 {名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕
{名}いえ(イヘ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗ハソノ室ヲ愛シテ、ソノ異室ヲ愛セズ」〔→墨子〕
 {単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕
{単位}家の戸数を数えることば。〈類義語〉→戸。「千室之邑=千室ノ邑」〔→論語〕
 {名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕
{名}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長シソノ室ヲ操ル」〔→史記〕
 {名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕
{名}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功、漢室ニ顕カナリ」〔→漢書〕
 {名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
{名}奥べやに住む夫人。〈対語〉→家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫、生マレテハコレガ為ニ室有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。
《単語家族》
窒チツ(いきづまり)
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。
《解字》
会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづきり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+音符至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。
《単語家族》
窒チツ(いきづまり) 膣チツと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
膣チツと同系。
《類義》
→家
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
帷幄之臣 イアクノシン🔗⭐🔉
【帷幄之臣】
イアクノシン〈故事〉陣営にいて、作戦計画をたてる臣下。転じて、参謀。〔→漢書〕
幃幄 イアク🔗⭐🔉
【幃幄】
イアク  たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』
たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』 戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。
戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。
 たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』
たれぎぬ。とばり。『幃帳イチョウ・幃幕イマク』 戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。
戦場で、幕を張りめぐらし、作戦計画をたてる所。〈同義語〉帷幄。
慰安 イアン🔗⭐🔉
【慰安】
イアン 慰めて心安らかにさせる。
惟惟 イイ🔗⭐🔉
【惟惟】
イイ =唯唯。はいはいと承諾するさま。「惟惟諾諾」
曰 いう🔗⭐🔉
【曰】
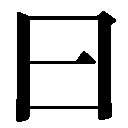 4画 曰部
区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48
《音読み》 エツ(
4画 曰部
区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48
《音読み》 エツ( ツ)
ツ) /オチ(ヲチ)
/オチ(ヲチ) 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに
《意味》
〉
《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに
《意味》
 {動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕
{動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕
 {動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」
{動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」
 {助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕
〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」
《解字》
{助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕
〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」
《解字》
 会意。「口+
会意。「口+ 印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう)
印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう) 話(はなす)
話(はなす) 聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。
《類義》
謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。
《熟語》
→熟語
聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。
《類義》
謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。
《熟語》
→熟語
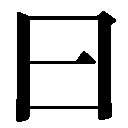 4画 曰部
区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48
《音読み》 エツ(
4画 曰部
区点=5909 16進=5B29 シフトJIS=9E48
《音読み》 エツ( ツ)
ツ) /オチ(ヲチ)
/オチ(ヲチ) 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに
《意味》
〉
《訓読み》 いう(いふ)/いわく(いはく)/のたまわく(のたまはく)/ここに
《意味》
 {動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕
{動}いう(イフ)。口をあけてものをいう。発言した内容を、次に導くときに用いる。名づけて…という。〈類義語〉→謂(いう)。「君称之曰夫人=君、コレヲ称シテ夫人ト曰フ」〔→論語〕
 {動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」
{動}いわく(イハク)。のたまわく(ノタマハク)。いうことには。▽「いはく」は、「おそらく」と同じく、動詞「いふ」の未然形に「く」をつけた奈良時代の言い方。「問之曰=コレニ問ヒテ曰ク」「答曰=答ヘテ曰ク」
 {助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕
〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」
《解字》
{助}ここに。さて。そこで。「曰為改歳=曰ニ改歳ト為ス」〔→詩経〕
〔国〕いわく(イハク)。理由。わけ。「曰くがある」
《解字》
 会意。「口+
会意。「口+ 印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう)
印」で、口の中からことばが出てくることを示す。謂イ(口をまるくあけて物をいう) 話(はなす)
話(はなす) 聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。
《類義》
謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。
《熟語》
→熟語
聒カツ(口を開いてしゃべる)などと同系で、口にまるくゆとりをあけてことばを出す意。漢字を組みたてるさい、曰印は、いうの意に限らず、広く人間の行為を示す意符として用いられる。
《類義》
謂は、話しかける、名づけるなどの意に用い、発言内容をじかに導くには「曰……」を用いる。
《熟語》
→熟語
猗違 イイ🔗⭐🔉
【猗違】
イイ ぐずつく。はっきりときまらない。〈同義語〉依違。
猗蔚 イイ🔗⭐🔉
【猗蔚】
イイ 草木のしげるさま。
猪 い🔗⭐🔉
【猪】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 犬部 [人名漢字]
区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296
《音読み》 チョ
11画 犬部 [人名漢字]
区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296
《音読み》 チョ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)
《名付け》 い・しし
《意味》
{名}い(
〉
《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)
《名付け》 い・しし
《意味》
{名}い( )。いのしし(
)。いのしし( ノシシ)。いのこ(
ノシシ)。いのこ( ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」
《解字》
会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。
《単語家族》
貯(中が充実する)と同系。
《類義》
→豕
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」
《解字》
会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。
《単語家族》
貯(中が充実する)と同系。
《類義》
→豕
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 犬部 [人名漢字]
区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296
《音読み》 チョ
11画 犬部 [人名漢字]
区点=3586 16進=4376 シフトJIS=9296
《音読み》 チョ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)
《名付け》 い・しし
《意味》
{名}い(
〉
《訓読み》 い/いのしし(ゐのしし)/いのこ(ゐのこ)
《名付け》 い・しし
《意味》
{名}い( )。いのしし(
)。いのしし( ノシシ)。いのこ(
ノシシ)。いのこ( ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」
《解字》
会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。
《単語家族》
貯(中が充実する)と同系。
《類義》
→豕
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
ノコ)。獣の名。からだの太ったいのしし。転じて、ぶた。〈同義語〉→豬。「野猪ヤチョ(いのしし)」
《解字》
会意兼形声。「犬+音符者(充実する、太る)」。太ったいのしし。その家畜となったのがぶた。猪は、豬の俗字。
《単語家族》
貯(中が充実する)と同系。
《類義》
→豕
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
畏愛 イアイ🔗⭐🔉
【畏愛】
イアイ 敬服して親愛する。
異意 イイ🔗⭐🔉
異域之鬼 イイキノキ🔗⭐🔉
【異域之鬼】
イイキノキ 外国で死んだ人。「生為別世之人、死為異域之鬼、長与足下、生死辞矣=生キテハ別世ノ人ト為リ、死シテハ異域ノ鬼ト為リ、長ニ足下ト、生死辞セン」〔→李陵〕
緯 イ🔗⭐🔉
【緯】
イ〈書物〉『詩経』『書経』『易経』『春秋』『礼記ライキ』『楽経』『孝経』などにかこつけて、占いや予言を記した漢代の書。陰陽五行説の影響が強い。『緯書』『讖緯シンイ(予言のことばを含む緯書)』ともいう。
莞 い🔗⭐🔉
藺 い🔗⭐🔉
【藺】
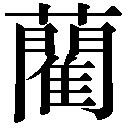 19画 艸部
区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561
《音読み》 リン
19画 艸部
区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561
《音読み》 リン
 〈l
〈l n〉
《訓読み》 い(ゐ)
《意味》
n〉
《訓読み》 い(ゐ)
《意味》
 {名}い(
{名}い( )。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」
)。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」
 「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。
《解字》
形声。下部の字が音をあらわす。
《熟語》
→主要人名
「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。
《解字》
形声。下部の字が音をあらわす。
《熟語》
→主要人名
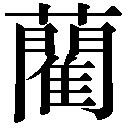 19画 艸部
区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561
《音読み》 リン
19画 艸部
区点=7334 16進=6942 シフトJIS=E561
《音読み》 リン
 〈l
〈l n〉
《訓読み》 い(ゐ)
《意味》
n〉
《訓読み》 い(ゐ)
《意味》
 {名}い(
{名}い( )。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」
)。草の名。湿地に生じる。茎は織ってむしろをつくる。いぐさ。「灯心草」とも。「藺席リンセキ(むしろ)」
 「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。
《解字》
形声。下部の字が音をあらわす。
《熟語》
→主要人名
「藺石リンセキ」とは、城の上から、敵を防ぐために投げおとす石のこと。
《解字》
形声。下部の字が音をあらわす。
《熟語》
→主要人名
見説 イウナラク🔗⭐🔉
【見説】
ミルナラク・キクナラク・イウナラク 世間でいうところによれば。▽「聞説キクナラク」と同じ。「見説蚕叢路、崎嶇不易行=キクナラク蚕叢ノ路、崎嶇トシテ行キ易カラズ」〔→李白〕
言 いう🔗⭐🔉
【言】
 7画 言部 [二年]
区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE
《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと
《音読み》 ゲン
7画 言部 [二年]
区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE
《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと
《音読み》 ゲン /ゴン
/ゴン 〈y
〈y n〉
《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん
《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん
《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき
《意味》
 {動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕
{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕
 {名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕
{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕
 {単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕
{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕
 {代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕
{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕
 「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。
〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。
《解字》
「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。
〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。
《解字》
 会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。
《単語家族》
彦ゲン(かどめのついた顔)
会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。
《単語家族》
彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。
《類義》
謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
岸ガン(かどだったきし)などと同系。
《類義》
謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 7画 言部 [二年]
区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE
《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと
《音読み》 ゲン
7画 言部 [二年]
区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE
《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと
《音読み》 ゲン /ゴン
/ゴン 〈y
〈y n〉
《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん
《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき
《意味》
n〉
《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん
《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき
《意味》
 {動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕
{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕
 {名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕
{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕
 {単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕
{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕
 {代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕
{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕
 「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。
〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。
《解字》
「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。
〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。
《解字》
 会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。
《単語家族》
彦ゲン(かどめのついた顔)
会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。
《単語家族》
彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。
《類義》
謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
岸ガン(かどだったきし)などと同系。
《類義》
謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
謂 いい🔗⭐🔉
【謂】
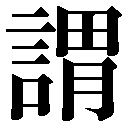 16画 言部
区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0
《音読み》 イ(
16画 言部
区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0
《音読み》 イ( )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)
《意味》
i〉
《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)
《意味》
 {動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕
{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕
 {動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕
{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕
 {動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕
{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕
 {動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕
{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕
 {名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」
{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」
 {名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕
{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕
 「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。
《単語家族》
囲イ(めぐってとりまく)
「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。
《単語家族》
囲イ(めぐってとりまく) 蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。
《類義》
→言
《熟語》
→下付・中付語
蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。
《類義》
→言
《熟語》
→下付・中付語
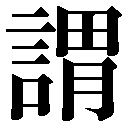 16画 言部
区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0
《音読み》 イ(
16画 言部
区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0
《音読み》 イ( )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)
《意味》
i〉
《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)
《意味》
 {動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕
{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕
 {動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕
{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕
 {動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕
{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕
 {動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕
{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕
 {名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」
{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」
 {名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕
{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕
 「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。
《単語家族》
囲イ(めぐってとりまく)
「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。
《単語家族》
囲イ(めぐってとりまく) 蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。
《類義》
→言
《熟語》
→下付・中付語
蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。
《類義》
→言
《熟語》
→下付・中付語
諤 いう🔗⭐🔉
豬 い🔗⭐🔉
道 いう🔗⭐🔉
【道】
 12画
12画  部 [二年]
区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9
《常用音訓》トウ/ドウ/みち
《音読み》 ドウ(ダウ)
部 [二年]
区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9
《常用音訓》トウ/ドウ/みち
《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)
/トウ(タウ) 〈d
〈d o〉
《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく
《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる
《意味》
o〉
《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく
《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる
《意味》
 {名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕
{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕
 {副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕
{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕
 {名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕
{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕
 {名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」
{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」
 {名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」
{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」
 {名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」
{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」
 {名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」
{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」
 {動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。
{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。
 {動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕
〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」
《解字》
会意兼形声。「
{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕
〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」
《解字》
会意兼形声。「 (足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。
《類義》
路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
(足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。
《類義》
路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 12画
12画  部 [二年]
区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9
《常用音訓》トウ/ドウ/みち
《音読み》 ドウ(ダウ)
部 [二年]
区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9
《常用音訓》トウ/ドウ/みち
《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)
/トウ(タウ) 〈d
〈d o〉
《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく
《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる
《意味》
o〉
《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく
《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる
《意味》
 {名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕
{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕
 {副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕
{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕
 {名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕
{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕
 {名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」
{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」
 {名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」
{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」
 {名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」
{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」
 {名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」
{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」
 {動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。
{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。
 {動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕
〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」
《解字》
会意兼形声。「
{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕
〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」
《解字》
会意兼形声。「 (足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。
《類義》
路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
(足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。
《類義》
路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
遺音 イイン🔗⭐🔉
【遺音】
イイン・イオン  奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。
奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。 心のこりの悲しげな声。
心のこりの悲しげな声。 古人が後世にのこした音楽のしらべ。
古人が後世にのこした音楽のしらべ。 いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕
いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕
 奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。
奏し終えたあとまでのこっている楽器などの響き。余韻。 心のこりの悲しげな声。
心のこりの悲しげな声。 古人が後世にのこした音楽のしらべ。
古人が後世にのこした音楽のしらべ。 いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕
いいのこしたいことば。伝言。「翹思慕遠人、願欲託遺言=思ヒヲ翹ゲテ遠人ヲ慕ヒ、願ハクハ遺言ヲ託セント欲ス」〔→曹植〕
遺韻 イイン🔗⭐🔉
【遺風】
イフウ  死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕
死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕 昔から伝えられている風習。余風。
昔から伝えられている風習。余風。 さっとすぎさるはやい風。
さっとすぎさるはやい風。 足のはやい馬。駿馬シュンメ。
足のはやい馬。駿馬シュンメ。
 死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕
死後にまで影響が及んでいる、故人の感化・やり方。『遺韻イイン』「昔嘗詠遺風、著為十六篇=昔カツテ遺風ヲ詠ジ、著シテ十六篇ト為シヌ」〔→白居易〕 昔から伝えられている風習。余風。
昔から伝えられている風習。余風。 さっとすぎさるはやい風。
さっとすぎさるはやい風。 足のはやい馬。駿馬シュンメ。
足のはやい馬。駿馬シュンメ。
遺愛 イアイ🔗⭐🔉
食 いい🔗⭐🔉
【食】
 9画 食部 [二年]
区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048
《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる
《音読み》
9画 食部 [二年]
区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048
《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる
《音読み》  ショク
ショク /ジキ
/ジキ 〈sh
〈sh 〉/
〉/ シ
シ /ジ
/ジ 〈s
〈s 〉
〉 イ
イ
 《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし
《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ
《意味》
《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし
《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ
《意味》

 ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕
ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕
 {名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕
{名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕
 {名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕
{名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕
 ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕
ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕
 ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕
ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕
 {動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕
{動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕

 {動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」
{動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」
 {名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕
{名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕
 {名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。
《解字》
{名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。
《解字》
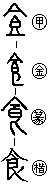 会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。
《単語家族》
飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ)
会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。
《単語家族》
飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ) 飼(柔らかくしたえさ)
飼(柔らかくしたえさ) 式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。
《類義》
咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。
《類義》
咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 9画 食部 [二年]
区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048
《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる
《音読み》
9画 食部 [二年]
区点=3109 16進=3F29 シフトJIS=9048
《常用音訓》ショク/ジキ/く…う/く…らう/た…べる
《音読み》  ショク
ショク /ジキ
/ジキ 〈sh
〈sh 〉/
〉/ シ
シ /ジ
/ジ 〈s
〈s 〉
〉 イ
イ
 《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし
《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ
《意味》
《訓読み》 たべる/くらう(くらふ)/くう(くふ)/はむ/くらわす(くらはす)/はます/やしなう(やしなふ)/いい(いひ)/めし
《名付け》 あき・あきら・うけ・くら・け・みけ
《意味》

 ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕
ショクス{動}くらう(クラフ)。くう(クフ)。はむ。もと、穀物を柔らかくしてたべること。のち、広くたべる意に用いる。「飲食」「食糧」「食而不知其味=食ラヘドモソノ味ヲ知ラズ」〔→大学〕
 {名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕
{名}たべもの。たべること。「断食」「配食」「甘其食=ソノ食ヲ甘シトス」〔→老子〕
 {名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕
{名}くいぶち。「食禄ショクロク」「君子謀道、不謀食=君子ハ道ヲ謀リ、食ヲ謀ラズ」〔→論語〕
 ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕
ショクス{動・名}くいこむ。虫がくいこんだように、日や月が欠ける。また、そのこと。〈同義語〉→蝕。「月食(=月蝕)」「日有食之=日コレヲ食スル有リ」〔→春秋〕
 ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕
ショクス{動}たべたようになくしてしまう。くいものにする。「食言=言ヲ食ス」「言不可食=言ハ食ス可カラズ」〔→国語〕
 {動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕
{動}くらう(クラフ)。打撃をうける。ひどい仕打ちをくらう。「不食膚受之愬=膚受ノ愬ヲ食ラハズ」〔→漢書〕

 {動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」
{動}くらわす(クラハス)。はます。やしなう(ヤシナフ)。たべさせる。食物を与えてやしなう。〈同義語〉→飼シ。「飲之食之=コレニ飲マセコレニ食ラハス」〔→詩経〕「食我以其食=我ニ食ラハスニソノ食ヲモッテス」
 {名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕
{名}いい(イヒ)。めし。〈同義語〉→飼。「一箪食、一瓢飲=一箪ノ食、一瓢ノ飲」〔→論語〕
 {名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。
《解字》
{名}「審食其シンイキ」など人名に用いる読み方。
《解字》
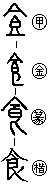 会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。
《単語家族》
飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ)
会意。「あつめて、ふたをするしるし+穀物を盛ったさま」をあわせたもの。容器に入れて手を加え、柔らかくしてたべることを意味する。
《単語家族》
飴イ(穀物に加工して柔らかくしたあめ) 飼(柔らかくしたえさ)
飼(柔らかくしたえさ) 式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。
《類義》
咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
式ショク(作為を加える)などと同系。蝕ショク(くいこむ、むしばむ)と最も近い。
《類義》
咀ソは、舌にのせてたべる。嚼シャクは、小さくかみくだいてたべる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
飯 いい🔗⭐🔉
【飯】
 12画 食部 [四年]
区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1
《常用音訓》ハン/めし
《音読み》 ハン
12画 食部 [四年]
区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1
《常用音訓》ハン/めし
《音読み》 ハン /ボン
/ボン 〈f
〈f n〉
《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)
《名付け》 いい
《意味》
n〉
《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)
《名付け》 いい
《意味》
 {名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。
{名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。
 ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕
ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕
 ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢
ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢 タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。
《単語家族》
播(ばらまく)
タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。
《単語家族》
播(ばらまく) 販(商品をひろげて売る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
販(商品をひろげて売る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 食部 [四年]
区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1
《常用音訓》ハン/めし
《音読み》 ハン
12画 食部 [四年]
区点=4051 16進=4853 シフトJIS=94D1
《常用音訓》ハン/めし
《音読み》 ハン /ボン
/ボン 〈f
〈f n〉
《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)
《名付け》 いい
《意味》
n〉
《訓読み》 めし/いい(いひ)/くらう(くらふ)/くらわす(くらはす)
《名付け》 いい
《意味》
 {名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。
{名}めし。いい(イヒ)。米その他の穀物を煮てふやかし、食べられるようにしたもの。また、食事。
 ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕
ハンス{動}くらう(クラフ)。めしを食べる。「飯疏食、飲水=疏食ヲ飯ヒ、水ヲ飲ム」〔→論語〕「侍食於君、君祭先飯=君ニ侍食スルニ、君祭レバ先ヅ飯ス」〔→論語〕
 ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢
ハンス{動}くらわす(クラハス)。めしを食べさせる。▽上声に読む。「見信飢飯信=信ノ飢 タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。
《単語家族》
播(ばらまく)
タルヲ見テ信ニ飯ハス」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「食+音符反(ばらばらになる→ふやける、ふくれる)」で、粒がふやけてばらばらに煮えた玄米のめし。
《単語家族》
播(ばらまく) 販(商品をひろげて売る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
販(商品をひろげて売る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「い」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む
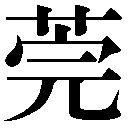 10画 艸部 [人名漢字]
区点=2048 16進=3450 シフトJIS=8ACE
《音読み》 カン(ク
10画 艸部 [人名漢字]
区点=2048 16進=3450 シフトJIS=8ACE
《音読み》 カン(ク ン)
ン) n〉〈hu
n〉〈hu ン」〔
ン」〔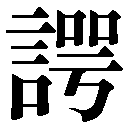 16画 言部
区点=7564 16進=6B60 シフトJIS=E680
《音読み》 ガク
16画 言部
区点=7564 16進=6B60 シフトJIS=E680
《音読み》 ガク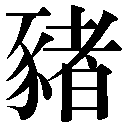 16画 豕部
区点=7623 16進=6C37 シフトJIS=E6B5
《音読み》 チョ
16画 豕部
区点=7623 16進=6C37 シフトJIS=E6B5
《音読み》 チョ