複数辞典一括検索+![]()
![]()
しゅん‐い【春衣】🔗⭐🔉
しゅん‐い【春衣】
春(正月)に着る衣服。春服。はるぎ。
しゅん‐い【春意】🔗⭐🔉
しゅん‐い【春意】
①春ののどかな心地。
②情欲。
しゅん‐いん【春陰】🔗⭐🔉
しゅん‐いん【春陰】
春の曇りがちな天候。〈[季]春〉
しゅん‐う【春雨】🔗⭐🔉
しゅん‐う【春雨】
春降る雨。はるさめ。
しゅん‐うん【春雲】🔗⭐🔉
しゅん‐うん【春雲】
①春の雲。
②茶の異称。
しゅん‐えん【春怨】‥ヱン🔗⭐🔉
しゅん‐えん【春怨】‥ヱン
若い女性が春にいだく物思い。また、過去の恋の思い。
しゅんおうでん【春鶯囀】‥アウ‥🔗⭐🔉
しゅんおうでん【春鶯囀】‥アウ‥
⇒しゅんのうでん
しゅんおく‐みょうは【春屋妙葩】‥ヲクメウ‥🔗⭐🔉
しゅんおく‐みょうは【春屋妙葩】‥ヲクメウ‥
南北朝時代の臨済宗の僧。号は不軽子。甲斐の人。叔父の夢窓疎石に師事。等持寺・天竜寺・南禅寺に歴住し、足利義満の帰依を受けて僧録となる。相国寺開創に際しては疎石を勧請開山として自らは第2世となり、ほかに多く寺を開く。五山文学代表者の一人。諡号しごうは普明国師。(1311〜1388)
しゅん‐か【春花】‥クワ🔗⭐🔉
しゅん‐か【春花】‥クワ
春の花。
⇒しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】
しゅん‐か【春歌】🔗⭐🔉
しゅん‐か【春歌】
①春を歌った歌。
②性に関することを露骨に歌った歌。
しゅん‐か【春霞】🔗⭐🔉
しゅん‐か【春霞】
春立つ霞。はるがすみ。
しゅん‐が【春画】‥グワ🔗⭐🔉
しゅん‐が【春画】‥グワ
男女の秘戯を描いた絵。おそくずの絵。枕絵。笑い絵。わ印。枕草紙。
しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】‥クワシウ‥🔗⭐🔉
しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】‥クワシウ‥
春の花と秋の月。すなわち、自然の美観。
⇒しゅん‐か【春花】
しゅん‐か‐しゅう‐とう【春夏秋冬】‥シウ‥🔗⭐🔉
しゅん‐か‐しゅう‐とう【春夏秋冬】‥シウ‥
春と夏と秋と冬。四時。四季。「―を通じて」
しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】‥シウ‥(作品名)🔗⭐🔉
しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】‥シウ‥
正岡子規一門の代表句集。4冊。1901〜03年(明治34〜36)刊。春の部は子規編、夏の部以下は高浜虚子・河東碧梧桐共編。
しゅんか‐しょり【春化処理】‥クワ‥🔗⭐🔉
しゅんか‐しょり【春化処理】‥クワ‥
〔農〕植物が自然の中で経過する条件を人為的に与えて、播種の時期をかえても正常に生育できるようにする処理。秋播き植物の種子を春に播いて発芽・結実させるなど。バーナリゼーション。ヤロビザーチヤ。
しゅんか‐もん【春華門・春花門】‥クワ‥🔗⭐🔉
しゅんか‐もん【春華門・春花門】‥クワ‥
平安京内裏の外郭門の一つ。南面の東端にあって、西端の修明門に対する。左馬の陣。枇杷陣。左廂僻仗門。→内裏(図)
しゅんか‐もんいん【春華門院】‥クワ‥ヰン🔗⭐🔉
しゅんか‐もんいん【春華門院】‥クワ‥ヰン
後鳥羽天皇の皇女。名は昇子。1196年(建久7)准三后。1208年(承元2)順徳天皇准母。翌年院号宣下。(1195〜1211)
しゅん‐かん【春官】‥クワン🔗⭐🔉
しゅん‐かん【春官】‥クワン
①周代の六官の一つ。祭祀・礼法をつかさどる。大宗伯から家宗に至るまで官属69。
②唐代以降、礼部の雅称。
③治部省の唐名。
しゅん‐かん【春寒】🔗⭐🔉
しゅん‐かん【春寒】
春になっても残る寒さ。はるさむ。余寒。残寒。〈[季]春〉
しゅん‐き【春気】🔗⭐🔉
しゅん‐き【春気】
春の気配。春げしき。
しゅん‐き【春季】🔗⭐🔉
しゅん‐き【春季】
①春のすえ。
②春の季節。
⇒しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】
しゅん‐き【春期】🔗⭐🔉
しゅん‐き【春期】
春のあいだ。春の期間。「―講習会」
しゅん‐き【春機】🔗⭐🔉
しゅん‐き【春機】
性的な情念。色情。
⇒しゅんき‐はつどうき【春機発動期】
しゅん‐ぎく【春菊】🔗⭐🔉
しゅん‐ぎく【春菊】
キク科の一年生または二年生作物。地中海地方原産。葉は香気が強い。茎葉を食用。漢名、茼蒿。
しゅんぎく
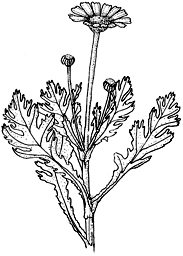
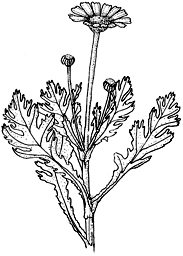
しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】‥クワウ‥🔗⭐🔉
しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】‥クワウ‥
天皇が毎年春分の日に、皇霊殿で歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祭る祭祀。旧制の祭日の一つ。今は「春分の日」といい、国民の祝日。樋口一葉、日記「廿日、晴天、今日はむさしの発行とかきくに―にもあればとてすしなど調す」
⇒しゅん‐き【春季】
しゅんき‐はつどうき【春機発動期】🔗⭐🔉
しゅんき‐はつどうき【春機発動期】
(→)思春期に同じ。
⇒しゅん‐き【春機】
しゅん‐きゅう【春宮】🔗⭐🔉
しゅん‐きゅう【春宮】
①皇太子。東宮。はるのみや。
②春の神の宮殿。
しゅん‐きょう【春興】🔗⭐🔉
しゅん‐きょう【春興】
①春の興趣。
②俳諧で、新年の会席で詠まれた三物みつものや発句。→歳旦2。
⇒しゅんきょう‐ちょう【春興帖】
しゅんのうでん【春鶯囀】‥アウ‥🔗⭐🔉
しゅんのうでん【春鶯囀】‥アウ‥
(囀は、さえずる意)雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの大曲。8部から成る華麗な曲。管弦では颯踏さっとうと入破じゅはの2部だけが奏される。四または六人舞。舞人は襲かさね装束に特異の甲を用いる。梅花春鶯囀。天長宝寿楽。天寿楽。
春鶯囀


しゅんぼう‐いっそく【春茅一束】‥バウ‥🔗⭐🔉
しゅんぼう‐いっそく【春茅一束】‥バウ‥
(謎語画題)松・蝋梅・水仙を描くもの。
とう‐ぐう【東宮・春宮】🔗⭐🔉
とう‐ぐう【東宮・春宮】
(東方は春に配し、万物生成の意を含み、また、易で東を震とし、震は長男であり、かつ昔はその宮殿が皇居の東にあったからいう)
①皇太子の宮殿。
②皇太子の称。はるのみや。
⇒とうぐう‐がくし【東宮学士】
⇒とうぐう‐ごしょ【東宮御所】
⇒とうぐう‐しょく【東宮職】
⇒とうぐう‐だいぶ【東宮大夫】
⇒とうぐう‐たてわき【東宮帯刀】
⇒とうぐう‐の‐だいぶ【春宮大夫】
⇒とうぐう‐の‐にょうご【東宮女御】
⇒とうぐう‐ふ【東宮傅】
⇒とうぐう‐ぼう【春宮坊】
とうぐう‐の‐だいぶ【春宮大夫】🔗⭐🔉
とうぐう‐の‐だいぶ【春宮大夫】
春宮坊の長官。
⇒とう‐ぐう【東宮・春宮】
とうぐう‐ぼう【春宮坊】‥バウ🔗⭐🔉
とうぐう‐ぼう【春宮坊】‥バウ
①律令制以後明治維新前まで、皇太子に奉仕し、その内政をつかさどった官司。職員に大夫だいぶ・亮すけ・大少進じょう・大少属さかんなどがあった。
②皇太子の事務をつかさどった役所。1869年(明治2)に設け、72年廃止。のち、東宮職となる。
⇒とう‐ぐう【東宮・春宮】
はる【春】🔗⭐🔉
はる‐いちばん【春一番】🔗⭐🔉
はる‐いちばん【春一番】
立春後、はじめて吹く強い南寄りの風。はるいち。〈[季]春〉
▷天気予報では、立春から春分までの間に広い範囲ではじめて吹く、暖かく強い南寄りの風をいう。
はる‐いとなみ【春営み】🔗⭐🔉
はる‐いとなみ【春営み】
春を迎えるための用意をすること。夫木和歌抄18「―にみ山出づなり」
はる‐いのこ【春亥の子】‥ヰ‥🔗⭐🔉
はる‐いのこ【春亥の子】‥ヰ‥
旧暦2月の初亥の日。東日本で、田の神を祭り農耕の予祝をする。→亥の子2
はる‐がすみ【春霞】🔗⭐🔉
はる‐がすみ【春霞】
[一]〔名〕
春の季節に立つかすみ。春靄しゅんあい。〈[季]春〉
[二]〔枕〕
「春日かすが」「立つ」「ゐる」「おほ」などにかかる。
はる‐きょうげん【春狂言】‥キヤウ‥🔗⭐🔉
はる‐きょうげん【春狂言】‥キヤウ‥
歌舞伎で、新春に上演する狂言。江戸では初期は正月2日、後に15日を初日とし、曾我物を吉例とした。京阪では二の替りといった。初春狂言。
はる‐さむ【春寒】🔗⭐🔉
はる‐さむ【春寒】
立春の後の寒さ。〈[季]春〉
はる‐さめ【春雨】🔗⭐🔉
はる‐さめ【春雨】
①春降る雨。特に若芽の出る頃、静かに降る細かい雨。〈[季]春〉。万葉集17「赤裳の裾の―ににほひひづちて」
②(その形状から名づけた)緑豆りょくとうまたはジャガイモ・サツマイモの澱粉から作った透明・線状の食品。とうめん。
③うた沢・端唄。二上りで、最も流行した曲の一つ。
はるさめものがたり【春雨物語】🔗⭐🔉
はるさめものがたり【春雨物語】
読本よみほん。10巻。上田秋成作。古典的教養を基礎にして、作者の歴史観・芸術観・人生観などを盛った小説。1808〜09年(文化5〜6)成る。
→文献資料[春雨物語]
はる‐さ・る【春さる】🔗⭐🔉
はる‐さ・る【春さる】
〔自四〕
(サルは移動する意)春がくる。春になる。万葉集5「―・ればまづ咲く宿の梅の花」
はる‐ざれ【春ざれ】🔗⭐🔉
はる‐ざれ【春ざれ】
(ハルサレとも。ハルサルの名詞形ハルサリの転)春が来てうららかな景色になること。春色。浮世草子、好色産毛「野山の―眺めにあかぬ身となりて」
はる‐つ‐かた【春つ方】🔗⭐🔉
はる‐つ‐かた【春つ方】
(ツは格助詞)春の季節。春の頃。和泉式部集「―人の来りければ」
はる‐なが【春永】🔗⭐🔉
はる‐なが【春永】
①昼間の長い春の季節。日永。永陽。多く、年の初めをたたえていう。〈[季]新年〉。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「五穀豊饒ぶにょうの―になほ新春の御吉慶と」
②(「―に」の形で)いずれひまな時に。また、ゆっくりと。浮世風呂3「言はれずは―におつしやいまし」
はる‐なぐさみ【春慰み】🔗⭐🔉
はる‐なぐさみ【春慰み】
正月のたのしみごと。また、春の野遊び。好色五人女2「正月廿二日の夜、恋は引く手の宝引縄、女子の―」
○春に三日の晴れなしはるにみっかのはれなし🔗⭐🔉
○春に三日の晴れなしはるにみっかのはれなし
春は天候が安定せず、晴天が三日も続くことはない。
⇒はる【春】
はる‐にれ【春楡】
ニレ科の落葉高木。北海道・本州北部の山地に自生。高さ30メートル、周囲6メートルに達する。葉は楕円形。3〜4月頃、葉に先だって帯紫淡緑色の小花を密生。花後、扁円形で膜質の翼果を結ぶ。材は器具用。若枝の繊維で縄を作る。にれ。ねり。古名、やにれ。
バルネラビリティー【vulnerability】
⇒ヴァルネラビリティー
はる‐の【春野】
春の季節の野。万葉集1「巨勢こせの―は」
はる‐の‐いろ【春の色】
春らしい様子。春色。〈[季]春〉
はる‐の‐うみ【春の海】
春のおだやかでのどかな海。〈[季]春〉。「―終日ひねもすのたりのたりかな」(蕪村)
はるのうみ【春の海】
箏と尺八の二重奏曲。1929年宮城道雄作曲。翌年の歌御会始うたごかいはじめの勅題に因む。瀬戸内海の船旅の印象を作品化。フランスのルネ=シュメー(Renée Chemet)の編曲で海外にも知られる。
ハル‐ノート【Hull Note】
1941年11月、日米交渉で米国務長官ハルが提示したアメリカ側の対日提案。日本軍の中国・インドシナからの完全な撤退、中華民国国民政府以外の中国における政府・政権の否認などを主張。日本側はアメリカの最後通牒とみなし、太平洋戦争に突入。
はる‐の‐かぎり【春の限り】
春の終り。春のはて。〈[季]春〉。伊勢物語「惜しめども―のけふの日の夕暮にさへなりにけるかな」
はるのきょく【春の曲】
箏曲。古今組こきんぐみの一曲。2世吉沢検校作曲。古今集の春の部の和歌6首を歌詞とする。のちに松阪春栄が手事と替手を補作。
はる‐の‐くれ【春の暮】
①春の終わるころ。晩春。暮春。くれのはる。
②春の日の夕暮れ。〈[季]春〉
はる‐の‐こころ【春の心】
①春を人に見立てていう時の、その心。また、春の季節ののどかな人心。古今和歌集春「―はのどけからまし」。風雅和歌集春「飛鳥井の―は知らねども」
②春情。恋心。人情本、出世娘「たがひの眼もとに秋の浪、―おこれども」
はる‐の‐ころも【春の衣】
①春に着る衣服。はるぎ。
②霞を衣に見立てていう語。
はる‐の‐さかずき【春の杯】‥サカヅキ
①春の頃、酒を飲む杯。
②3月上巳じょうしの曲水の宴に、水に浮かべる杯。
はる‐の‐じもく【春の除目】‥ヂ‥
(春、行われたからいう)(→)県召除目あがためしのじもくのこと。↔秋の除目
はる‐の‐しらべ【春の調】
雅楽などにおける春の調子。双調そうじょう。古今和歌集物名「浪の音のけさからことに聞ゆるは―やあらたまるらん」
はる‐の‐つかい【春の使】‥ツカヒ
ウグイスの異称。五社百首「関越ゆる―や行きやらぬ」
はる‐の‐つき【春の月】
春の、いくぶんぼんやりとして、ほのぼのとした風情の月。〈[季]春〉
はるのつじ‐いせき【原の辻遺跡】‥ヰ‥
長崎県壱岐島の南東部にある弥生時代の大集落遺跡。1991年以来の発掘で多くの遺構・遺物を出土・発見。「魏志倭人伝」の一支いき国の中心と推定されている。
はる‐の‐と【春の戸】
春をとざしこめている戸。聞書集「―あくる鶯の声」
はる‐の‐となり【春の隣】
春に近いことを空間的に隣と表現したもの。晩冬、春の近づくのにいう。古今和歌集雑体「冬ながら―の近ければ」
はる‐の‐とり【春の鳥】
春に鳴く鳥。特に、鶯。〈[季]春〉。源氏物語若菜上「―の、桜一つにとまらぬ心よ」
はる‐の‐なさけ【春の情】
春のおもむき。風雅和歌集春「花の後も―は残りけり」
はる‐の‐ななくさ【春の七草】
正月7日に摘み採って七草粥に入れる若菜。芹せり・薺なずな・御形ごぎょう・蘩蔞はこべ・仏座ほとけのざ・菘すずな・蘿蔔すずしろの7種。↔秋の七草
はる‐の‐にしき【春の錦】
春の時節に、百花が錦を織ったように美しく咲くさま。古今和歌集春「都ぞ―なりける」
はる‐の‐の【春の野】
春ののどかな野原。〈[季]春〉
はる‐の‐ひ【春の日】
春の一日。また、春の太陽。春日。春陽。〈[季]春〉
はるのひ【春の日】
俳諧集。1冊。山本荷兮かけい編。1686年(貞享3)刊。荷兮・野水・越人ら蕉門の連句・発句を集めたもの。格調は平板だが安らか。俳諧七部集の一つ。
→文献資料[春の日]
はるのべ‐の‐こめ【春延べの米】
年末に翌年3月払いの約束で借りる米。他に転売して資金を調達するために行われた。世間胸算用4「―を、…毎年のくれに借入の肝煎して」→延米のべごめ
はる‐の‐ほし【春の星】
春の夜空の星。代表的な星座は大熊座・獅子座・蟹座・海蛇座・乙女座・牛飼座など。春星しゅんせい。〈[季]春〉
はる‐の‐みず【春の水】‥ミヅ
春の、水量の多くなった川や湖沼の水。〈[季]春〉
はる‐の‐みなと【春の湊】
春の行き止まるところ。船のゆき泊まる港にたとえていう。春の泊とまり。〈[季]春〉。新古今和歌集春「暮れてゆく―は知らねども」
はる‐の‐みや【春の宮】
(「春宮とうぐう」の訓読)皇太子の称。東宮。
⇒はるのみや‐びと【春の宮人】
はるのみや‐びと【春の宮人】
東宮坊に仕える役人。後拾遺和歌集春「うらやまし―うち群れて」
⇒はる‐の‐みや【春の宮】
はる‐の‐みやま【春の深山】
春のころの深山。歌で多く「春の宮」にかけていう。古今和歌集雑「―の蔭をこひつつ」
はる‐の‐めざめ【春の目覚め】
思春期に達して、性の欲望がきざすこと。
はるのめざめ【春の目ざめ】
(Frühlings Erwachen ドイツ)ウェデキントの戯曲。1906年初演。思春期の少年少女が性的無知のために陥る悲劇を描き、うわべを取り繕う社会の偽善に抗議。表現主義の先駆。
はるのや‐おぼろ【春廼舎朧】
(→)坪内逍遥の別号。
はる‐の‐やま【春の山】
春になって、木の芽がもえ、花が咲き、霞んで見える山。〈[季]春〉
はる‐の‐ゆき【春の雪】
春になって降る雪。大きな雪片の牡丹ぼたん雪になることが多く、淡く消えやすい。春雪しゅんせつ。〈[季]春〉
はる‐の‐よ【春の夜】
春の短い夜。〈[季]春〉
⇒はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】
はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】
春の夜に見るゆめ。短くはかないことのたとえ。後撰和歌集哀傷「―の中にも思ひきや」
⇒はる‐の‐よ【春の夜】
ハルハ【喀爾喀・Khalkha】
明代の韃靼だったん部、すなわち東モンゴル族の一部。清の康 こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。
ハルバースタム【David Halberstam】
米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)
はる‐ばしょ【春場所】
大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。
バルバドス【Barbados】
カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)
はるはな‐の【春花の】
〔枕〕
「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。
はる‐はやて【春疾風】
春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉
バルパライソ【Valparaíso】
チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。
はる‐ばる【遥遥】
〔副〕
距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」
バルバロイ【barbaroi ギリシア】
古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス
はるび【腹帯】
(ハラオビの約転)
①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。
②長持につける白布の緒。
はる‐び【春日】
(古くはハルヒ)
[一]〔名〕
春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」
[二]〔枕〕
(→)「はるびを」に同じ。
⇒はるび‐の【春日の】
⇒はるび‐を【春日を】
はる‐ひかげ【春日影】
春の日の光。〈[季]春〉
バルビゾン‐は【バルビゾン派】
19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派
バルビタール【barbital】
ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。
バルビツール‐さん【バルビツール酸】
(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール
はるび‐の【春日の】
〔枕〕
「かすが(春日)」にかかる。
⇒はる‐び【春日】
バルビュス【Henri Barbusse】
フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)
はるび‐を【春日を】
〔枕〕
(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」
⇒はる‐び【春日】
ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】
(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。
バルブ【bulb】
①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。
②電球。閃光電球。
③鱗茎。球根。
バルブ【valve】
①(→)弁(瓣)3に同じ。
②(→)真空管に同じ。
パルプ【pulp】
木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。
バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】
イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)
こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。
ハルバースタム【David Halberstam】
米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)
はる‐ばしょ【春場所】
大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。
バルバドス【Barbados】
カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)
はるはな‐の【春花の】
〔枕〕
「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。
はる‐はやて【春疾風】
春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉
バルパライソ【Valparaíso】
チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。
はる‐ばる【遥遥】
〔副〕
距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」
バルバロイ【barbaroi ギリシア】
古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス
はるび【腹帯】
(ハラオビの約転)
①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。
②長持につける白布の緒。
はる‐び【春日】
(古くはハルヒ)
[一]〔名〕
春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」
[二]〔枕〕
(→)「はるびを」に同じ。
⇒はるび‐の【春日の】
⇒はるび‐を【春日を】
はる‐ひかげ【春日影】
春の日の光。〈[季]春〉
バルビゾン‐は【バルビゾン派】
19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派
バルビタール【barbital】
ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。
バルビツール‐さん【バルビツール酸】
(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール
はるび‐の【春日の】
〔枕〕
「かすが(春日)」にかかる。
⇒はる‐び【春日】
バルビュス【Henri Barbusse】
フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)
はるび‐を【春日を】
〔枕〕
(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」
⇒はる‐び【春日】
ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】
(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。
バルブ【bulb】
①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。
②電球。閃光電球。
③鱗茎。球根。
バルブ【valve】
①(→)弁(瓣)3に同じ。
②(→)真空管に同じ。
パルプ【pulp】
木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。
バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】
イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)
 こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。
ハルバースタム【David Halberstam】
米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)
はる‐ばしょ【春場所】
大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。
バルバドス【Barbados】
カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)
はるはな‐の【春花の】
〔枕〕
「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。
はる‐はやて【春疾風】
春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉
バルパライソ【Valparaíso】
チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。
はる‐ばる【遥遥】
〔副〕
距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」
バルバロイ【barbaroi ギリシア】
古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス
はるび【腹帯】
(ハラオビの約転)
①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。
②長持につける白布の緒。
はる‐び【春日】
(古くはハルヒ)
[一]〔名〕
春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」
[二]〔枕〕
(→)「はるびを」に同じ。
⇒はるび‐の【春日の】
⇒はるび‐を【春日を】
はる‐ひかげ【春日影】
春の日の光。〈[季]春〉
バルビゾン‐は【バルビゾン派】
19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派
バルビタール【barbital】
ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。
バルビツール‐さん【バルビツール酸】
(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール
はるび‐の【春日の】
〔枕〕
「かすが(春日)」にかかる。
⇒はる‐び【春日】
バルビュス【Henri Barbusse】
フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)
はるび‐を【春日を】
〔枕〕
(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」
⇒はる‐び【春日】
ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】
(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。
バルブ【bulb】
①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。
②電球。閃光電球。
③鱗茎。球根。
バルブ【valve】
①(→)弁(瓣)3に同じ。
②(→)真空管に同じ。
パルプ【pulp】
木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。
バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】
イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)
こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。
ハルバースタム【David Halberstam】
米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)
はる‐ばしょ【春場所】
大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。
バルバドス【Barbados】
カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)
はるはな‐の【春花の】
〔枕〕
「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。
はる‐はやて【春疾風】
春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉
バルパライソ【Valparaíso】
チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。
はる‐ばる【遥遥】
〔副〕
距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」
バルバロイ【barbaroi ギリシア】
古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス
はるび【腹帯】
(ハラオビの約転)
①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。
②長持につける白布の緒。
はる‐び【春日】
(古くはハルヒ)
[一]〔名〕
春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」
[二]〔枕〕
(→)「はるびを」に同じ。
⇒はるび‐の【春日の】
⇒はるび‐を【春日を】
はる‐ひかげ【春日影】
春の日の光。〈[季]春〉
バルビゾン‐は【バルビゾン派】
19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派
バルビタール【barbital】
ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。
バルビツール‐さん【バルビツール酸】
(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール
はるび‐の【春日の】
〔枕〕
「かすが(春日)」にかかる。
⇒はる‐び【春日】
バルビュス【Henri Barbusse】
フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)
はるび‐を【春日を】
〔枕〕
(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」
⇒はる‐び【春日】
ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】
(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。
バルブ【bulb】
①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。
②電球。閃光電球。
③鱗茎。球根。
バルブ【valve】
①(→)弁(瓣)3に同じ。
②(→)真空管に同じ。
パルプ【pulp】
木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。
バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】
イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)
はる‐の‐いろ【春の色】🔗⭐🔉
はる‐の‐いろ【春の色】
春らしい様子。春色。〈[季]春〉
はる‐の‐うみ【春の海】🔗⭐🔉
はる‐の‐うみ【春の海】
春のおだやかでのどかな海。〈[季]春〉。「―終日ひねもすのたりのたりかな」(蕪村)
はるのうみ【春の海】(作品名)🔗⭐🔉
はるのうみ【春の海】
箏と尺八の二重奏曲。1929年宮城道雄作曲。翌年の歌御会始うたごかいはじめの勅題に因む。瀬戸内海の船旅の印象を作品化。フランスのルネ=シュメー(Renée Chemet)の編曲で海外にも知られる。
はる‐の‐かぎり【春の限り】🔗⭐🔉
はる‐の‐かぎり【春の限り】
春の終り。春のはて。〈[季]春〉。伊勢物語「惜しめども―のけふの日の夕暮にさへなりにけるかな」
はるのきょく【春の曲】🔗⭐🔉
はるのきょく【春の曲】
箏曲。古今組こきんぐみの一曲。2世吉沢検校作曲。古今集の春の部の和歌6首を歌詞とする。のちに松阪春栄が手事と替手を補作。
はる‐の‐くれ【春の暮】🔗⭐🔉
はる‐の‐くれ【春の暮】
①春の終わるころ。晩春。暮春。くれのはる。
②春の日の夕暮れ。〈[季]春〉
はる‐の‐こころ【春の心】🔗⭐🔉
はる‐の‐こころ【春の心】
①春を人に見立てていう時の、その心。また、春の季節ののどかな人心。古今和歌集春「―はのどけからまし」。風雅和歌集春「飛鳥井の―は知らねども」
②春情。恋心。人情本、出世娘「たがひの眼もとに秋の浪、―おこれども」
はる‐の‐ころも【春の衣】🔗⭐🔉
はる‐の‐ころも【春の衣】
①春に着る衣服。はるぎ。
②霞を衣に見立てていう語。
はる‐の‐さかずき【春の杯】‥サカヅキ🔗⭐🔉
はる‐の‐さかずき【春の杯】‥サカヅキ
①春の頃、酒を飲む杯。
②3月上巳じょうしの曲水の宴に、水に浮かべる杯。
はる‐の‐じもく【春の除目】‥ヂ‥🔗⭐🔉
はる‐の‐じもく【春の除目】‥ヂ‥
(春、行われたからいう)(→)県召除目あがためしのじもくのこと。↔秋の除目
はる‐の‐しらべ【春の調】🔗⭐🔉
はる‐の‐しらべ【春の調】
雅楽などにおける春の調子。双調そうじょう。古今和歌集物名「浪の音のけさからことに聞ゆるは―やあらたまるらん」
はる‐の‐つかい【春の使】‥ツカヒ🔗⭐🔉
はる‐の‐つかい【春の使】‥ツカヒ
ウグイスの異称。五社百首「関越ゆる―や行きやらぬ」
はる‐の‐つき【春の月】🔗⭐🔉
はる‐の‐つき【春の月】
春の、いくぶんぼんやりとして、ほのぼのとした風情の月。〈[季]春〉
はる‐の‐と【春の戸】🔗⭐🔉
はる‐の‐と【春の戸】
春をとざしこめている戸。聞書集「―あくる鶯の声」
はる‐の‐となり【春の隣】🔗⭐🔉
はる‐の‐となり【春の隣】
春に近いことを空間的に隣と表現したもの。晩冬、春の近づくのにいう。古今和歌集雑体「冬ながら―の近ければ」
はる‐の‐とり【春の鳥】🔗⭐🔉
はる‐の‐とり【春の鳥】
春に鳴く鳥。特に、鶯。〈[季]春〉。源氏物語若菜上「―の、桜一つにとまらぬ心よ」
はる‐の‐なさけ【春の情】🔗⭐🔉
はる‐の‐なさけ【春の情】
春のおもむき。風雅和歌集春「花の後も―は残りけり」
はる‐の‐ななくさ【春の七草】🔗⭐🔉
はる‐の‐ななくさ【春の七草】
正月7日に摘み採って七草粥に入れる若菜。芹せり・薺なずな・御形ごぎょう・蘩蔞はこべ・仏座ほとけのざ・菘すずな・蘿蔔すずしろの7種。↔秋の七草
はる‐の‐にしき【春の錦】🔗⭐🔉
はる‐の‐にしき【春の錦】
春の時節に、百花が錦を織ったように美しく咲くさま。古今和歌集春「都ぞ―なりける」
はる‐の‐の【春の野】🔗⭐🔉
はる‐の‐の【春の野】
春ののどかな野原。〈[季]春〉
はる‐の‐ひ【春の日】🔗⭐🔉
はる‐の‐ひ【春の日】
春の一日。また、春の太陽。春日。春陽。〈[季]春〉
はるのひ【春の日】(作品名)🔗⭐🔉
はるのひ【春の日】
俳諧集。1冊。山本荷兮かけい編。1686年(貞享3)刊。荷兮・野水・越人ら蕉門の連句・発句を集めたもの。格調は平板だが安らか。俳諧七部集の一つ。
→文献資料[春の日]
はるのべ‐の‐こめ【春延べの米】🔗⭐🔉
はるのべ‐の‐こめ【春延べの米】
年末に翌年3月払いの約束で借りる米。他に転売して資金を調達するために行われた。世間胸算用4「―を、…毎年のくれに借入の肝煎して」→延米のべごめ
はる‐の‐ほし【春の星】🔗⭐🔉
はる‐の‐ほし【春の星】
春の夜空の星。代表的な星座は大熊座・獅子座・蟹座・海蛇座・乙女座・牛飼座など。春星しゅんせい。〈[季]春〉
はる‐の‐みず【春の水】‥ミヅ🔗⭐🔉
はる‐の‐みず【春の水】‥ミヅ
春の、水量の多くなった川や湖沼の水。〈[季]春〉
はる‐の‐みなと【春の湊】🔗⭐🔉
はる‐の‐みなと【春の湊】
春の行き止まるところ。船のゆき泊まる港にたとえていう。春の泊とまり。〈[季]春〉。新古今和歌集春「暮れてゆく―は知らねども」
はる‐の‐みや【春の宮】🔗⭐🔉
はる‐の‐みや【春の宮】
(「春宮とうぐう」の訓読)皇太子の称。東宮。
⇒はるのみや‐びと【春の宮人】
はるのみや‐びと【春の宮人】🔗⭐🔉
はるのみや‐びと【春の宮人】
東宮坊に仕える役人。後拾遺和歌集春「うらやまし―うち群れて」
⇒はる‐の‐みや【春の宮】
はる‐の‐みやま【春の深山】🔗⭐🔉
はる‐の‐みやま【春の深山】
春のころの深山。歌で多く「春の宮」にかけていう。古今和歌集雑「―の蔭をこひつつ」
はる‐の‐めざめ【春の目覚め】🔗⭐🔉
はる‐の‐めざめ【春の目覚め】
思春期に達して、性の欲望がきざすこと。
はるのめざめ【春の目ざめ】🔗⭐🔉
はるのめざめ【春の目ざめ】
(Frühlings Erwachen ドイツ)ウェデキントの戯曲。1906年初演。思春期の少年少女が性的無知のために陥る悲劇を描き、うわべを取り繕う社会の偽善に抗議。表現主義の先駆。
はる‐の‐やま【春の山】🔗⭐🔉
はる‐の‐やま【春の山】
春になって、木の芽がもえ、花が咲き、霞んで見える山。〈[季]春〉
はる‐の‐ゆき【春の雪】🔗⭐🔉
はる‐の‐ゆき【春の雪】
春になって降る雪。大きな雪片の牡丹ぼたん雪になることが多く、淡く消えやすい。春雪しゅんせつ。〈[季]春〉
はる‐の‐よ【春の夜】🔗⭐🔉
はる‐の‐よ【春の夜】
春の短い夜。〈[季]春〉
⇒はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】
はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】🔗⭐🔉
はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】
春の夜に見るゆめ。短くはかないことのたとえ。後撰和歌集哀傷「―の中にも思ひきや」
⇒はる‐の‐よ【春の夜】
はるはな‐の【春花の】🔗⭐🔉
はるはな‐の【春花の】
〔枕〕
「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。
はる‐まき【春巻】🔗⭐🔉
はる‐まき【春巻】
小麦粉で作った薄い皮で具を包み、揚げた中国料理の点心。
はる‐め・く【春めく】🔗⭐🔉
はる‐め・く【春めく】
〔自五〕
春の気候らしくなる。春らしい気配になる。〈[季]春〉。拾遺和歌集雑秋「霜がれの野原のけぶり―・きにけり」
はる‐やすみ【春休み】🔗⭐🔉
はる‐やすみ【春休み】
学校の春の休暇。学年末から4月の始業日までのあいだ。
みこ‐の‐みや【東宮・春宮】🔗⭐🔉
みこ‐の‐みや【東宮・春宮】
皇太子。とうぐう。持統紀「―大傅おおきかしずきとす」
[漢]春🔗⭐🔉
春 字形
 筆順
筆順
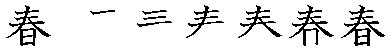 〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕
〔音〕シュン(呉)(漢)
〔訓〕はる
[意味]
①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。
②若く元気な年ごろ。「青春」
③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」
[解字]
もと[
〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕
〔音〕シュン(呉)(漢)
〔訓〕はる
[意味]
①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。
②若く元気な年ごろ。「青春」
③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」
[解字]
もと[ ]と書く。形声。音符「
]と書く。形声。音符「 」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[
」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[ ]は異体字。
[下ツキ
回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春
[難読]
春日かすが
]は異体字。
[下ツキ
回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春
[難読]
春日かすが
 筆順
筆順
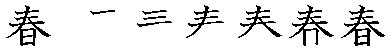 〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕
〔音〕シュン(呉)(漢)
〔訓〕はる
[意味]
①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。
②若く元気な年ごろ。「青春」
③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」
[解字]
もと[
〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕
〔音〕シュン(呉)(漢)
〔訓〕はる
[意味]
①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。
②若く元気な年ごろ。「青春」
③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」
[解字]
もと[ ]と書く。形声。音符「
]と書く。形声。音符「 」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[
」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[ ]は異体字。
[下ツキ
回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春
[難読]
春日かすが
]は異体字。
[下ツキ
回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春
[難読]
春日かすが
広辞苑に「春」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む
 部4画〕
部4画〕