複数辞典一括検索+![]()
![]()
屠狗 トク🔗⭐🔉
【屠狗】
トク  イヌヲホフル犬を殺す。
イヌヲホフル犬を殺す。 犬を殺し、その肉を売るのを職業とする人。犬殺し。
犬を殺し、その肉を売るのを職業とする人。犬殺し。 転じて、いやしい職業に従事する者のたとえ。
転じて、いやしい職業に従事する者のたとえ。
 イヌヲホフル犬を殺す。
イヌヲホフル犬を殺す。 犬を殺し、その肉を売るのを職業とする人。犬殺し。
犬を殺し、その肉を売るのを職業とする人。犬殺し。 転じて、いやしい職業に従事する者のたとえ。
転じて、いやしい職業に従事する者のたとえ。
抒 とく🔗⭐🔉
【抒】
 7画
7画  部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ
部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
 ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
 ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
 {動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける)
{動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける) 捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画
7画  部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ
部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
 ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
 ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
 {動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける)
{動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける) 捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
溶 とく🔗⭐🔉
【溶】
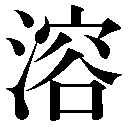 13画 水部 [常用漢字]
区点=4547 16進=4D4F シフトJIS=976E
《常用音訓》ヨウ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》 ヨウ
13画 水部 [常用漢字]
区点=4547 16進=4D4F シフトJIS=976E
《常用音訓》ヨウ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》 ヨウ /ユウ
/ユウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/とかす
《意味》
ng〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/とかす
《意味》
 {動}とける(トク)。とかす。中に入れてまぜこむ。とけこむ。〈同義語〉→熔ヨウ・→鎔ヨウ。「溶解」
{動}とける(トク)。とかす。中に入れてまぜこむ。とけこむ。〈同義語〉→熔ヨウ・→鎔ヨウ。「溶解」
 「溶溶ヨウヨウ」とは、水がゆったりと多いさま。また、気持ちのゆったりと広いさま。「心溶溶其不可量兮=心溶溶トシテソレ量ルベカラズ」〔→楚辞〕
《解字》
会意兼形声。谷は、口(あな)があいて、水の八型に流れ出るたに間をあらわす会意文字。容は「宀(やね)+谷」から成り、穴があいていて中に物を入れこむ家や入れもの。溶は「水+音符容」で、水の中に物を入れてまぜこむこと。→谷
《単語家族》
浴(水の中に体を入れる)と溶は、語尾のあい転じた形で同系。また、収容の容(中に入れこむ)
「溶溶ヨウヨウ」とは、水がゆったりと多いさま。また、気持ちのゆったりと広いさま。「心溶溶其不可量兮=心溶溶トシテソレ量ルベカラズ」〔→楚辞〕
《解字》
会意兼形声。谷は、口(あな)があいて、水の八型に流れ出るたに間をあらわす会意文字。容は「宀(やね)+谷」から成り、穴があいていて中に物を入れこむ家や入れもの。溶は「水+音符容」で、水の中に物を入れてまぜこむこと。→谷
《単語家族》
浴(水の中に体を入れる)と溶は、語尾のあい転じた形で同系。また、収容の容(中に入れこむ) 融ユウ(とけこむ)とは最も近い。
《類義》
→融
《異字同訓》
とく/とける。 →解
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
融ユウ(とけこむ)とは最も近い。
《類義》
→融
《異字同訓》
とく/とける。 →解
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
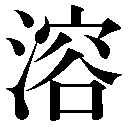 13画 水部 [常用漢字]
区点=4547 16進=4D4F シフトJIS=976E
《常用音訓》ヨウ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》 ヨウ
13画 水部 [常用漢字]
区点=4547 16進=4D4F シフトJIS=976E
《常用音訓》ヨウ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》 ヨウ /ユウ
/ユウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/とかす
《意味》
ng〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/とかす
《意味》
 {動}とける(トク)。とかす。中に入れてまぜこむ。とけこむ。〈同義語〉→熔ヨウ・→鎔ヨウ。「溶解」
{動}とける(トク)。とかす。中に入れてまぜこむ。とけこむ。〈同義語〉→熔ヨウ・→鎔ヨウ。「溶解」
 「溶溶ヨウヨウ」とは、水がゆったりと多いさま。また、気持ちのゆったりと広いさま。「心溶溶其不可量兮=心溶溶トシテソレ量ルベカラズ」〔→楚辞〕
《解字》
会意兼形声。谷は、口(あな)があいて、水の八型に流れ出るたに間をあらわす会意文字。容は「宀(やね)+谷」から成り、穴があいていて中に物を入れこむ家や入れもの。溶は「水+音符容」で、水の中に物を入れてまぜこむこと。→谷
《単語家族》
浴(水の中に体を入れる)と溶は、語尾のあい転じた形で同系。また、収容の容(中に入れこむ)
「溶溶ヨウヨウ」とは、水がゆったりと多いさま。また、気持ちのゆったりと広いさま。「心溶溶其不可量兮=心溶溶トシテソレ量ルベカラズ」〔→楚辞〕
《解字》
会意兼形声。谷は、口(あな)があいて、水の八型に流れ出るたに間をあらわす会意文字。容は「宀(やね)+谷」から成り、穴があいていて中に物を入れこむ家や入れもの。溶は「水+音符容」で、水の中に物を入れてまぜこむこと。→谷
《単語家族》
浴(水の中に体を入れる)と溶は、語尾のあい転じた形で同系。また、収容の容(中に入れこむ) 融ユウ(とけこむ)とは最も近い。
《類義》
→融
《異字同訓》
とく/とける。 →解
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
融ユウ(とけこむ)とは最も近い。
《類義》
→融
《異字同訓》
とく/とける。 →解
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
税 とく🔗⭐🔉
【税】
 12画 禾部 [五年]
区点=3239 16進=4047 シフトJIS=90C5
《常用音訓》ゼイ
《音読み》 ゼイ
12画 禾部 [五年]
区点=3239 16進=4047 シフトJIS=90C5
《常用音訓》ゼイ
《音読み》 ゼイ /セイ
/セイ /セ
/セ 〈shu
〈shu 〉
《訓読み》 みつぎ/とく/ぬく
《名付け》 おさむ・ちから・みつぎ
《意味》
〉
《訓読み》 みつぎ/とく/ぬく
《名付け》 おさむ・ちから・みつぎ
《意味》
 {名}みつぎ。国家や支配者が、人民の収入や収穫のうちからぬきとって徴収するもの。年貢。▽近世では田畑や土地から徴収するのを租といい、品物や収入からとるのを税という。「国税」「租税」
{名}みつぎ。国家や支配者が、人民の収入や収穫のうちからぬきとって徴収するもの。年貢。▽近世では田畑や土地から徴収するのを租といい、品物や収入からとるのを税という。「国税」「租税」
 ゼイス{動}税をかける。年貢をとりたてる。▽昔は一割を理想としたが、現実には田租は五割から六割にも達し、税は多方面に及んだ。「什一而税=什一ニシテ税ス」
ゼイス{動}税をかける。年貢をとりたてる。▽昔は一割を理想としたが、現実には田租は五割から六割にも達し、税は多方面に及んだ。「什一而税=什一ニシテ税ス」
 ゼイス{動}とく。ぬく。ぬきとる。はがす。自分の持ち物をぬきとって人にあたえる。〈類義語〉→脱。「税駕=駕ヲ税ク」「未仕者不敢税人=イマダ仕ヘザル者ハアヘテ人ニ税セズ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「八(はぎとる)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をはがしてぬきとるさま。脱衣の脱の原字。税は「禾(作物)+音符兌」で、収穫の一部をぬきとること。
《単語家族》
脱(はぎとる)
ゼイス{動}とく。ぬく。ぬきとる。はがす。自分の持ち物をぬきとって人にあたえる。〈類義語〉→脱。「税駕=駕ヲ税ク」「未仕者不敢税人=イマダ仕ヘザル者ハアヘテ人ニ税セズ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「八(はぎとる)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をはがしてぬきとるさま。脱衣の脱の原字。税は「禾(作物)+音符兌」で、収穫の一部をぬきとること。
《単語家族》
脱(はぎとる) 奪(ぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
奪(ぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 禾部 [五年]
区点=3239 16進=4047 シフトJIS=90C5
《常用音訓》ゼイ
《音読み》 ゼイ
12画 禾部 [五年]
区点=3239 16進=4047 シフトJIS=90C5
《常用音訓》ゼイ
《音読み》 ゼイ /セイ
/セイ /セ
/セ 〈shu
〈shu 〉
《訓読み》 みつぎ/とく/ぬく
《名付け》 おさむ・ちから・みつぎ
《意味》
〉
《訓読み》 みつぎ/とく/ぬく
《名付け》 おさむ・ちから・みつぎ
《意味》
 {名}みつぎ。国家や支配者が、人民の収入や収穫のうちからぬきとって徴収するもの。年貢。▽近世では田畑や土地から徴収するのを租といい、品物や収入からとるのを税という。「国税」「租税」
{名}みつぎ。国家や支配者が、人民の収入や収穫のうちからぬきとって徴収するもの。年貢。▽近世では田畑や土地から徴収するのを租といい、品物や収入からとるのを税という。「国税」「租税」
 ゼイス{動}税をかける。年貢をとりたてる。▽昔は一割を理想としたが、現実には田租は五割から六割にも達し、税は多方面に及んだ。「什一而税=什一ニシテ税ス」
ゼイス{動}税をかける。年貢をとりたてる。▽昔は一割を理想としたが、現実には田租は五割から六割にも達し、税は多方面に及んだ。「什一而税=什一ニシテ税ス」
 ゼイス{動}とく。ぬく。ぬきとる。はがす。自分の持ち物をぬきとって人にあたえる。〈類義語〉→脱。「税駕=駕ヲ税ク」「未仕者不敢税人=イマダ仕ヘザル者ハアヘテ人ニ税セズ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「八(はぎとる)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をはがしてぬきとるさま。脱衣の脱の原字。税は「禾(作物)+音符兌」で、収穫の一部をぬきとること。
《単語家族》
脱(はぎとる)
ゼイス{動}とく。ぬく。ぬきとる。はがす。自分の持ち物をぬきとって人にあたえる。〈類義語〉→脱。「税駕=駕ヲ税ク」「未仕者不敢税人=イマダ仕ヘザル者ハアヘテ人ニ税セズ」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「八(はぎとる)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をはがしてぬきとるさま。脱衣の脱の原字。税は「禾(作物)+音符兌」で、収穫の一部をぬきとること。
《単語家族》
脱(はぎとる) 奪(ぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
奪(ぬきとる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
解 とく🔗⭐🔉
【解】
 13画 角部 [五年]
区点=1882 16進=3272 シフトJIS=89F0
【觧】異体字異体字
13画 角部 [五年]
区点=1882 16進=3272 シフトJIS=89F0
【觧】異体字異体字
 13画 角部
区点=7527 16進=6B3B シフトJIS=E65A
《常用音訓》カイ/ゲ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》
13画 角部
区点=7527 16進=6B3B シフトJIS=E65A
《常用音訓》カイ/ゲ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》  カイ
カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉/
〉/ ゲ
ゲ /カイ
/カイ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 とかす/とく/とける(とく)/つかわす(つかはす)/さとる
《名付け》 ざ・さとる・とき・ひろ
《意味》
〉
《訓読み》 とかす/とく/とける(とく)/つかわす(つかはす)/さとる
《名付け》 ざ・さとる・とき・ひろ
《意味》

 {動}とく。とける(トク)。一体をなしたものを、ばらばらにわける。また、一体をなしていたものが離れわかれる。「分解」「瓦解」「解其左肩=ソノ左肩ヲ解ク」〔→左伝〕
{動}とく。とける(トク)。一体をなしたものを、ばらばらにわける。また、一体をなしていたものが離れわかれる。「分解」「瓦解」「解其左肩=ソノ左肩ヲ解ク」〔→左伝〕
 {動}とく。とける(トク)。結びめやしこりを、ばらばらにしてときほぐす。「勧解(すすめて仲なおりさせる)」「和解」
{動}とく。とける(トク)。結びめやしこりを、ばらばらにしてときほぐす。「勧解(すすめて仲なおりさせる)」「和解」
 カイス{動}とく。禁じたことや束縛をときはなす。役目や責任をときはずす。釈放する。「解禁=禁ヲ解ク」「解放」「解任=任ヲ解ク」
カイス{動}とく。禁じたことや束縛をときはなす。役目や責任をときはずす。釈放する。「解禁=禁ヲ解ク」「解放」「解任=任ヲ解ク」
 {動}からだのしこりや熱などをときほぐしてとり除く。「解熱ゲネツ」「大解(大便)」「小解(小便)」
{動}からだのしこりや熱などをときほぐしてとり除く。「解熱ゲネツ」「大解(大便)」「小解(小便)」
 {名}文章の様式の一つ。理由や見解をのべた文章。「進学解シンガクノカイ」
{名}文章の様式の一つ。理由や見解をのべた文章。「進学解シンガクノカイ」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。坎下震上カンカシンショウの形で、困難がとけてなくなることをあらわす。
{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下震上カンカシンショウの形で、困難がとけてなくなることをあらわす。
 {単位}楽曲または古詩の節を数えることば。
{単位}楽曲または古詩の節を数えることば。
 {動}つかわす(ツカハス)。人や金品を護送する。また、人を派遣する。▽去声に読む。「解支」
{動}つかわす(ツカハス)。人や金品を護送する。また、人を派遣する。▽去声に読む。「解支」
 「解額カイガク」とは、地方から進士の受験者の名簿を届けること。「発解」とは、郷試の試験に合格すること。▽去声に読む。
「解額カイガク」とは、地方から進士の受験者の名簿を届けること。「発解」とは、郷試の試験に合格すること。▽去声に読む。

 カイス{動・名}とく。不明な点や理由を明らかにする。ときあかす。また、不明な点や理由についての説明。〈類義語〉→釈。「弁解」「解釈」「詳解」「略解リャクカイ/リャクゲ」「閉約而無解=閉約シテ解スル無シ」〔→荀子〕
カイス{動・名}とく。不明な点や理由を明らかにする。ときあかす。また、不明な点や理由についての説明。〈類義語〉→釈。「弁解」「解釈」「詳解」「略解リャクカイ/リャクゲ」「閉約而無解=閉約シテ解スル無シ」〔→荀子〕
 カイス{動・名}とける(トク)。さとる。ほぐれてわかる。また、ときほぐした考え。「理解」「見解」
カイス{動・名}とける(トク)。さとる。ほぐれてわかる。また、ときほぐした考え。「理解」「見解」
 {名}からだの各部が牛・羊・馬・鹿シカに似ているという動物の名。「解豸カイチ」
{名}からだの各部が牛・羊・馬・鹿シカに似ているという動物の名。「解豸カイチ」
 {動・形}おこたる。だらける。また、そのさま。▽懈カイに当てた用法。「解怠」
《解字》
会意。「角+刀+牛」で、刀で牛のからだやつのをばらばらに分解することを示す。
《単語家族》
蟹カイ(からだが分解するかに)
{動・形}おこたる。だらける。また、そのさま。▽懈カイに当てた用法。「解怠」
《解字》
会意。「角+刀+牛」で、刀で牛のからだやつのをばらばらに分解することを示す。
《単語家族》
蟹カイ(からだが分解するかに) 懈カイ(心がばらばらにとける、だらける)
懈カイ(心がばらばらにとける、だらける) 隔カク(べつべつになる)などと同系。
《類義》
→剖・→釈
《異字同訓》
とく/とける。 解く/解ける「結び目を解く。包囲を解く。問題を解く。会長の任を解かれる。ひもが解ける。雪解け。疑いが解ける」溶く/溶ける「絵の具を溶く。砂糖が水に溶ける。地域社会に溶け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
隔カク(べつべつになる)などと同系。
《類義》
→剖・→釈
《異字同訓》
とく/とける。 解く/解ける「結び目を解く。包囲を解く。問題を解く。会長の任を解かれる。ひもが解ける。雪解け。疑いが解ける」溶く/溶ける「絵の具を溶く。砂糖が水に溶ける。地域社会に溶け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 13画 角部 [五年]
区点=1882 16進=3272 シフトJIS=89F0
【觧】異体字異体字
13画 角部 [五年]
区点=1882 16進=3272 シフトJIS=89F0
【觧】異体字異体字
 13画 角部
区点=7527 16進=6B3B シフトJIS=E65A
《常用音訓》カイ/ゲ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》
13画 角部
区点=7527 16進=6B3B シフトJIS=E65A
《常用音訓》カイ/ゲ/と…かす/と…く/と…ける
《音読み》  カイ
カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉/
〉/ ゲ
ゲ /カイ
/カイ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 とかす/とく/とける(とく)/つかわす(つかはす)/さとる
《名付け》 ざ・さとる・とき・ひろ
《意味》
〉
《訓読み》 とかす/とく/とける(とく)/つかわす(つかはす)/さとる
《名付け》 ざ・さとる・とき・ひろ
《意味》

 {動}とく。とける(トク)。一体をなしたものを、ばらばらにわける。また、一体をなしていたものが離れわかれる。「分解」「瓦解」「解其左肩=ソノ左肩ヲ解ク」〔→左伝〕
{動}とく。とける(トク)。一体をなしたものを、ばらばらにわける。また、一体をなしていたものが離れわかれる。「分解」「瓦解」「解其左肩=ソノ左肩ヲ解ク」〔→左伝〕
 {動}とく。とける(トク)。結びめやしこりを、ばらばらにしてときほぐす。「勧解(すすめて仲なおりさせる)」「和解」
{動}とく。とける(トク)。結びめやしこりを、ばらばらにしてときほぐす。「勧解(すすめて仲なおりさせる)」「和解」
 カイス{動}とく。禁じたことや束縛をときはなす。役目や責任をときはずす。釈放する。「解禁=禁ヲ解ク」「解放」「解任=任ヲ解ク」
カイス{動}とく。禁じたことや束縛をときはなす。役目や責任をときはずす。釈放する。「解禁=禁ヲ解ク」「解放」「解任=任ヲ解ク」
 {動}からだのしこりや熱などをときほぐしてとり除く。「解熱ゲネツ」「大解(大便)」「小解(小便)」
{動}からだのしこりや熱などをときほぐしてとり除く。「解熱ゲネツ」「大解(大便)」「小解(小便)」
 {名}文章の様式の一つ。理由や見解をのべた文章。「進学解シンガクノカイ」
{名}文章の様式の一つ。理由や見解をのべた文章。「進学解シンガクノカイ」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。坎下震上カンカシンショウの形で、困難がとけてなくなることをあらわす。
{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下震上カンカシンショウの形で、困難がとけてなくなることをあらわす。
 {単位}楽曲または古詩の節を数えることば。
{単位}楽曲または古詩の節を数えることば。
 {動}つかわす(ツカハス)。人や金品を護送する。また、人を派遣する。▽去声に読む。「解支」
{動}つかわす(ツカハス)。人や金品を護送する。また、人を派遣する。▽去声に読む。「解支」
 「解額カイガク」とは、地方から進士の受験者の名簿を届けること。「発解」とは、郷試の試験に合格すること。▽去声に読む。
「解額カイガク」とは、地方から進士の受験者の名簿を届けること。「発解」とは、郷試の試験に合格すること。▽去声に読む。

 カイス{動・名}とく。不明な点や理由を明らかにする。ときあかす。また、不明な点や理由についての説明。〈類義語〉→釈。「弁解」「解釈」「詳解」「略解リャクカイ/リャクゲ」「閉約而無解=閉約シテ解スル無シ」〔→荀子〕
カイス{動・名}とく。不明な点や理由を明らかにする。ときあかす。また、不明な点や理由についての説明。〈類義語〉→釈。「弁解」「解釈」「詳解」「略解リャクカイ/リャクゲ」「閉約而無解=閉約シテ解スル無シ」〔→荀子〕
 カイス{動・名}とける(トク)。さとる。ほぐれてわかる。また、ときほぐした考え。「理解」「見解」
カイス{動・名}とける(トク)。さとる。ほぐれてわかる。また、ときほぐした考え。「理解」「見解」
 {名}からだの各部が牛・羊・馬・鹿シカに似ているという動物の名。「解豸カイチ」
{名}からだの各部が牛・羊・馬・鹿シカに似ているという動物の名。「解豸カイチ」
 {動・形}おこたる。だらける。また、そのさま。▽懈カイに当てた用法。「解怠」
《解字》
会意。「角+刀+牛」で、刀で牛のからだやつのをばらばらに分解することを示す。
《単語家族》
蟹カイ(からだが分解するかに)
{動・形}おこたる。だらける。また、そのさま。▽懈カイに当てた用法。「解怠」
《解字》
会意。「角+刀+牛」で、刀で牛のからだやつのをばらばらに分解することを示す。
《単語家族》
蟹カイ(からだが分解するかに) 懈カイ(心がばらばらにとける、だらける)
懈カイ(心がばらばらにとける、だらける) 隔カク(べつべつになる)などと同系。
《類義》
→剖・→釈
《異字同訓》
とく/とける。 解く/解ける「結び目を解く。包囲を解く。問題を解く。会長の任を解かれる。ひもが解ける。雪解け。疑いが解ける」溶く/溶ける「絵の具を溶く。砂糖が水に溶ける。地域社会に溶け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
隔カク(べつべつになる)などと同系。
《類義》
→剖・→釈
《異字同訓》
とく/とける。 解く/解ける「結び目を解く。包囲を解く。問題を解く。会長の任を解かれる。ひもが解ける。雪解け。疑いが解ける」溶く/溶ける「絵の具を溶く。砂糖が水に溶ける。地域社会に溶け込む」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
詮 とく🔗⭐🔉
【詮】
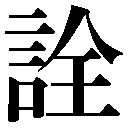 13画 言部
区点=3307 16進=4127 シフトJIS=9146
《音読み》 セン
13画 言部
区点=3307 16進=4127 シフトJIS=9146
《音読み》 セン
 〈qu
〈qu n〉
《訓読み》 とく/そなわる(そなはる)/えらぶ/せんずる(せんず)/せん
《意味》
n〉
《訓読み》 とく/そなわる(そなはる)/えらぶ/せんずる(せんず)/せん
《意味》
 {動}とく。物事の道理をつまびらかにとく。ときあかす。「詮解センカイ」「詮釈センシャク」
{動}とく。物事の道理をつまびらかにとく。ときあかす。「詮解センカイ」「詮釈センシャク」
 {動・名}そなわる(ソナハル)。ことばや物の道理が整然とそろっている。また、物事にそなわった道理。「真詮シンセン」
{動・名}そなわる(ソナハル)。ことばや物の道理が整然とそろっている。また、物事にそなわった道理。「真詮シンセン」
 {動}えらぶ。ことばや物事をきれいにそろえて、よいもの、正しいものをえらびとる。〈同義語〉→銓。「詮衡センコウ」
〔国〕
{動}えらぶ。ことばや物事をきれいにそろえて、よいもの、正しいものをえらびとる。〈同義語〉→銓。「詮衡センコウ」
〔国〕 せんずる(センズ)。よくつきつめて考える。「詮じつめる」
せんずる(センズ)。よくつきつめて考える。「詮じつめる」 せん。なすべき手段。すべ。「詮も尽き果てぬ」
せん。なすべき手段。すべ。「詮も尽き果てぬ」 せん。物事をしたかい。「詮なきこと」
せん。物事をしたかい。「詮なきこと」 「所詮ショセン・センズルトコロ」とは、要するに。結局。
《解字》
会意兼形声。全センは「集めるしるし+工または玉」の会意文字で、物を程よくそろえること。詮は「言+音符全」で、ことばを整然ととりそろえて、物事の道理を明らかにすること。
《単語家族》
そろえたものを調整して、不要なものをおとすという点で、選セン(物をとりそろえて、必要なものをえらぶ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「所詮ショセン・センズルトコロ」とは、要するに。結局。
《解字》
会意兼形声。全センは「集めるしるし+工または玉」の会意文字で、物を程よくそろえること。詮は「言+音符全」で、ことばを整然ととりそろえて、物事の道理を明らかにすること。
《単語家族》
そろえたものを調整して、不要なものをおとすという点で、選セン(物をとりそろえて、必要なものをえらぶ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
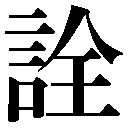 13画 言部
区点=3307 16進=4127 シフトJIS=9146
《音読み》 セン
13画 言部
区点=3307 16進=4127 シフトJIS=9146
《音読み》 セン
 〈qu
〈qu n〉
《訓読み》 とく/そなわる(そなはる)/えらぶ/せんずる(せんず)/せん
《意味》
n〉
《訓読み》 とく/そなわる(そなはる)/えらぶ/せんずる(せんず)/せん
《意味》
 {動}とく。物事の道理をつまびらかにとく。ときあかす。「詮解センカイ」「詮釈センシャク」
{動}とく。物事の道理をつまびらかにとく。ときあかす。「詮解センカイ」「詮釈センシャク」
 {動・名}そなわる(ソナハル)。ことばや物の道理が整然とそろっている。また、物事にそなわった道理。「真詮シンセン」
{動・名}そなわる(ソナハル)。ことばや物の道理が整然とそろっている。また、物事にそなわった道理。「真詮シンセン」
 {動}えらぶ。ことばや物事をきれいにそろえて、よいもの、正しいものをえらびとる。〈同義語〉→銓。「詮衡センコウ」
〔国〕
{動}えらぶ。ことばや物事をきれいにそろえて、よいもの、正しいものをえらびとる。〈同義語〉→銓。「詮衡センコウ」
〔国〕 せんずる(センズ)。よくつきつめて考える。「詮じつめる」
せんずる(センズ)。よくつきつめて考える。「詮じつめる」 せん。なすべき手段。すべ。「詮も尽き果てぬ」
せん。なすべき手段。すべ。「詮も尽き果てぬ」 せん。物事をしたかい。「詮なきこと」
せん。物事をしたかい。「詮なきこと」 「所詮ショセン・センズルトコロ」とは、要するに。結局。
《解字》
会意兼形声。全センは「集めるしるし+工または玉」の会意文字で、物を程よくそろえること。詮は「言+音符全」で、ことばを整然ととりそろえて、物事の道理を明らかにすること。
《単語家族》
そろえたものを調整して、不要なものをおとすという点で、選セン(物をとりそろえて、必要なものをえらぶ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「所詮ショセン・センズルトコロ」とは、要するに。結局。
《解字》
会意兼形声。全センは「集めるしるし+工または玉」の会意文字で、物を程よくそろえること。詮は「言+音符全」で、ことばを整然ととりそろえて、物事の道理を明らかにすること。
《単語家族》
そろえたものを調整して、不要なものをおとすという点で、選セン(物をとりそろえて、必要なものをえらぶ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
説 とく🔗⭐🔉
【説】
 14画 言部 [四年]
区点=3266 16進=4062 シフトJIS=90E0
《常用音訓》セツ/ゼイ/と…く
《音読み》
14画 言部 [四年]
区点=3266 16進=4062 シフトJIS=90E0
《常用音訓》セツ/ゼイ/と…く
《音読み》  セツ
セツ /セチ
/セチ 〈shu
〈shu 〉/
〉/ ゼイ/セツ
ゼイ/セツ /セイ
/セイ
 〈shu
〈shu 〉/
〉/ エツ
エツ /エチ
/エチ 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 とく/よろこぶ/よろこばしい(よろこばし)
《名付け》 あき・かぬ・かね・こと・つぐ・とき・とく・のぶ・ひさ
《意味》
〉
《訓読み》 とく/よろこぶ/よろこばしい(よろこばし)
《名付け》 あき・かぬ・かね・こと・つぐ・とき・とく・のぶ・ひさ
《意味》

 {動}とく。しこりや難点を、ことばでときあかす。〈類義語〉→釈シャク。「解説」「説明」「説之不以道、不説也=コレヲ説クニ道ヲモッテセザルハ、説バザルナリ」〔→論語〕
{動}とく。しこりや難点を、ことばでときあかす。〈類義語〉→釈シャク。「解説」「説明」「説之不以道、不説也=コレヲ説クニ道ヲモッテセザルハ、説バザルナリ」〔→論語〕
 {動}とく。結んでしばってあったものを、ときはなす。〈類義語〉→解。
{動}とく。結んでしばってあったものを、ときはなす。〈類義語〉→解。
 {名}いわれや理屈をときあかした意見・主張。また、議論や解説をもりこんだ文章。「邪説」「異説」
{名}いわれや理屈をときあかした意見・主張。また、議論や解説をもりこんだ文章。「邪説」「異説」
 {動}〔俗〕はなす。また、ものがたる。「説書(講談)」「説白(せりふ)」
{動}〔俗〕はなす。また、ものがたる。「説書(講談)」「説白(せりふ)」
 {動}とく。相手に説明して自分の意見に従わせる。▽「説得セットク」「説伏セップク」などは、今ではセツと読む。「遊説ユウゼイ」「説大人則藐之=大人ニ説クニハスナハチコレヲ藐ンゼヨ」〔→孟子〕
{動}とく。相手に説明して自分の意見に従わせる。▽「説得セットク」「説伏セップク」などは、今ではセツと読む。「遊説ユウゼイ」「説大人則藐之=大人ニ説クニハスナハチコレヲ藐ンゼヨ」〔→孟子〕
 {動・形}よろこぶ。よろこばしい(ヨロコバシ)。心のしこりがとけてよろこぶ。はればれするさま。〈同義語〉→悦。「喜説キエツ(=喜悦)」「学而時習之、不亦説乎=学ビテ時ニコレヲ習フ、マタ説バシカラズヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「ハ(ときはなす)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をときはなすこと。脱の原字。説は「言+音符兌」で、ことばでしこりをときはなすこと。→兌
《単語家族》
脱(ときはがす)
{動・形}よろこぶ。よろこばしい(ヨロコバシ)。心のしこりがとけてよろこぶ。はればれするさま。〈同義語〉→悦。「喜説キエツ(=喜悦)」「学而時習之、不亦説乎=学ビテ時ニコレヲ習フ、マタ説バシカラズヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「ハ(ときはなす)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をときはなすこと。脱の原字。説は「言+音符兌」で、ことばでしこりをときはなすこと。→兌
《単語家族》
脱(ときはがす) 税(収穫物をはがしてとる)などと同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
税(収穫物をはがしてとる)などと同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 14画 言部 [四年]
区点=3266 16進=4062 シフトJIS=90E0
《常用音訓》セツ/ゼイ/と…く
《音読み》
14画 言部 [四年]
区点=3266 16進=4062 シフトJIS=90E0
《常用音訓》セツ/ゼイ/と…く
《音読み》  セツ
セツ /セチ
/セチ 〈shu
〈shu 〉/
〉/ ゼイ/セツ
ゼイ/セツ /セイ
/セイ
 〈shu
〈shu 〉/
〉/ エツ
エツ /エチ
/エチ 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 とく/よろこぶ/よろこばしい(よろこばし)
《名付け》 あき・かぬ・かね・こと・つぐ・とき・とく・のぶ・ひさ
《意味》
〉
《訓読み》 とく/よろこぶ/よろこばしい(よろこばし)
《名付け》 あき・かぬ・かね・こと・つぐ・とき・とく・のぶ・ひさ
《意味》

 {動}とく。しこりや難点を、ことばでときあかす。〈類義語〉→釈シャク。「解説」「説明」「説之不以道、不説也=コレヲ説クニ道ヲモッテセザルハ、説バザルナリ」〔→論語〕
{動}とく。しこりや難点を、ことばでときあかす。〈類義語〉→釈シャク。「解説」「説明」「説之不以道、不説也=コレヲ説クニ道ヲモッテセザルハ、説バザルナリ」〔→論語〕
 {動}とく。結んでしばってあったものを、ときはなす。〈類義語〉→解。
{動}とく。結んでしばってあったものを、ときはなす。〈類義語〉→解。
 {名}いわれや理屈をときあかした意見・主張。また、議論や解説をもりこんだ文章。「邪説」「異説」
{名}いわれや理屈をときあかした意見・主張。また、議論や解説をもりこんだ文章。「邪説」「異説」
 {動}〔俗〕はなす。また、ものがたる。「説書(講談)」「説白(せりふ)」
{動}〔俗〕はなす。また、ものがたる。「説書(講談)」「説白(せりふ)」
 {動}とく。相手に説明して自分の意見に従わせる。▽「説得セットク」「説伏セップク」などは、今ではセツと読む。「遊説ユウゼイ」「説大人則藐之=大人ニ説クニハスナハチコレヲ藐ンゼヨ」〔→孟子〕
{動}とく。相手に説明して自分の意見に従わせる。▽「説得セットク」「説伏セップク」などは、今ではセツと読む。「遊説ユウゼイ」「説大人則藐之=大人ニ説クニハスナハチコレヲ藐ンゼヨ」〔→孟子〕
 {動・形}よろこぶ。よろこばしい(ヨロコバシ)。心のしこりがとけてよろこぶ。はればれするさま。〈同義語〉→悦。「喜説キエツ(=喜悦)」「学而時習之、不亦説乎=学ビテ時ニコレヲ習フ、マタ説バシカラズヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「ハ(ときはなす)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をときはなすこと。脱の原字。説は「言+音符兌」で、ことばでしこりをときはなすこと。→兌
《単語家族》
脱(ときはがす)
{動・形}よろこぶ。よろこばしい(ヨロコバシ)。心のしこりがとけてよろこぶ。はればれするさま。〈同義語〉→悦。「喜説キエツ(=喜悦)」「学而時習之、不亦説乎=学ビテ時ニコレヲ習フ、マタ説バシカラズヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。兌タイ・ダは「ハ(ときはなす)+兄(頭の大きい人)」の会意文字で、人の着物をときはなすこと。脱の原字。説は「言+音符兌」で、ことばでしこりをときはなすこと。→兌
《単語家族》
脱(ときはがす) 税(収穫物をはがしてとる)などと同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
税(収穫物をはがしてとる)などと同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
釈 とく🔗⭐🔉
【釈】
 11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
 20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク
20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク /セキ
/セキ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
 {動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
{動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
 {動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
{動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
 {動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
{動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
 {名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す)
{名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す) 驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場)
驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場) 譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
 20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク
20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク /セキ
/セキ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
 {動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
{動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
 {動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
{動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
 {動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
{動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
 {名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す)
{名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す) 驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場)
驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場) 譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
漢字源に「とく」で完全一致するの検索結果 1-8。