複数辞典一括検索+![]()
![]()
些些 ササ🔗⭐🔉
【些些】
ササ 物事がわずかであること。
些細 ササイ🔗⭐🔉
【些細】
ササイ その物事がとるに足りないつまらないこと。わずか。いささか。〈同義語〉瑣細。
刺 ささる🔗⭐🔉
【刺】
 8画 リ部 [常用漢字]
区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68
《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す
《音読み》 シ
8画 リ部 [常用漢字]
区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68
《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す
《音読み》 シ
 /セキ
/セキ /シャク
/シャク 〈c
〈c 〉
《訓読み》 ささる/さす/とげ
《名付け》 さし・さす
《意味》
〉
《訓読み》 ささる/さす/とげ
《名付け》 さし・さす
《意味》
 {動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕
{動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕
 {名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」
{名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」
 {動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」
{動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」
 {動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」
{動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」
 {名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕
{名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕
 {名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」
{名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」
 「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿
《異字同訓》
さす。→差
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿
《異字同訓》
さす。→差
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 8画 リ部 [常用漢字]
区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68
《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す
《音読み》 シ
8画 リ部 [常用漢字]
区点=2741 16進=3B49 シフトJIS=8E68
《常用音訓》シ/さ…さる/さ…す
《音読み》 シ
 /セキ
/セキ /シャク
/シャク 〈c
〈c 〉
《訓読み》 ささる/さす/とげ
《名付け》 さし・さす
《意味》
〉
《訓読み》 ささる/さす/とげ
《名付け》 さし・さす
《意味》
 {動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕
{動}さす。とがった物でちくりとさす。さおさす。「刺繍シシュウ」「刺殺」「能死刺我=能ク死サバ我ヲ刺セ」〔→漢書〕
 {名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」
{名}とげ。細くとがったとげや、はり。「茫刺ボウシ(細いとげ)」「魚刺(魚のとげ)」
 {動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」
{動}さす。痛いところをちくりとつつく。相手の弱みをせめる。「諷刺フウシ(=風刺)」
 {動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」
{動}探る。「刺探(漢方で針をさして病気の所在を探る)」
 {名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕
{名}まず相手に名を知らせて都合を探るのを「刺を通ず」といい、その名札を「名刺」という。「生因投刺謁於郵亭=生因リテ刺ヲ投ジテ郵亭ニ謁ス」〔李娃伝〕
 {名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」
{名}民情を探る役目の意から、州の長官のこと。「刺史」
 「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿
《異字同訓》
さす。→差
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「刺刺シシ」とは、身にこたえるほど、うるさくしゃべるさま。
《解字》
会意兼形声。朿シの原字は、四方に鋭いとげの出た姿を描いた象形文字。刺は「刀+音符朿(とげ)」。刀でとげのようにさすこと。また、ちくりとさす針。その左は朿であり、束ではない。もとおもに名詞にはシ、動詞にはセキの音を用いたが、のち混用して多く、シの音を用いる。▽剌ラツは、別字。→朿
《異字同訓》
さす。→差
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
囁 ささやく🔗⭐🔉
【囁】
 21画 口部
区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91
《音読み》
21画 口部
区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91
《音読み》  ショウ(セフ)
ショウ(セフ)
 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ジョウ(ゼフ)
ジョウ(ゼフ) /ニョウ(ネフ)
/ニョウ(ネフ) 〈ni
〈ni 〉
《訓読み》 ささやく
《意味》
{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。
《解字》
会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。
〉
《訓読み》 ささやく
《意味》
{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。
《解字》
会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。
 21画 口部
区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91
《音読み》
21画 口部
区点=5181 16進=5371 シフトJIS=9A91
《音読み》  ショウ(セフ)
ショウ(セフ)
 〈zh
〈zh 〉/
〉/ ジョウ(ゼフ)
ジョウ(ゼフ) /ニョウ(ネフ)
/ニョウ(ネフ) 〈ni
〈ni 〉
《訓読み》 ささやく
《意味》
{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。
《解字》
会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。
〉
《訓読み》 ささやく
《意味》
{動}ささやく。そっと話す。〈同義語〉→聶ジョウ/ニョウ。
《解字》
会意兼形声。聶は、耳に口を寄せてささやくこと。囁は「口+音符聶ジョウ・ニョウ」で、口を寄せてそっとささやくこと。
差錯 ササク🔗⭐🔉
【差錯】
ササク じぐざぐになる。入り乱れる。
捧 ささげる🔗⭐🔉
【捧】
 11画
11画  部
区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9
《音読み》 ホウ
部
区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9
《音読み》 ホウ /フ
/フ 〈p
〈p ng〉
《訓読み》 ささげる(ささぐ)
《意味》
{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」
〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。
《解字》
会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり
ng〉
《訓読み》 ささげる(ささぐ)
《意味》
{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」
〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。
《解字》
会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり 型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で
型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で 型に出あうささげ方のこと。→奉
《単語家族》
逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で
型に出あうささげ方のこと。→奉
《単語家族》
逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で 型に出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
型に出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画
11画  部
区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9
《音読み》 ホウ
部
区点=4291 16進=4A7B シフトJIS=95F9
《音読み》 ホウ /フ
/フ 〈p
〈p ng〉
《訓読み》 ささげる(ささぐ)
《意味》
{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」
〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。
《解字》
会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり
ng〉
《訓読み》 ささげる(ささぐ)
《意味》
{動}ささげる(ササグ)。両手で胸の前に持ちあげて持つ。〈同義語〉→奉。〈対語〉→負(せなかにせおう)。「捧持ホウジ」「捧心=心ヲ捧グ」
〔国〕ささげる(ササグ)。神仏などにさしあげる。
《解字》
会意兼形声。奉ホウは「お供え+両手」からなる会意文字で、お供え物を両手でささげたさま。捧は「手+音符奉」で、両手をあげてその頂点に物をのせる、つまり 型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で
型にささげること。奉の原義をあらわす。両手がその頂点で 型に出あうささげ方のこと。→奉
《単語家族》
逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で
型に出あうささげ方のこと。→奉
《単語家族》
逢ホウ(両方から山を登り、峠の頂点で 型に出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
型に出あう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
支 ささえ🔗⭐🔉
【支】
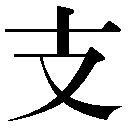 4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
 {名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
 {名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
 {動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
 シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
 {名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕
{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕 「支那シナ」の略。
「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
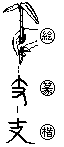 会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ)
会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
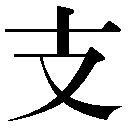 4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
 {名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
 {名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
 {動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
 シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
 {名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕
{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕 「支那シナ」の略。
「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
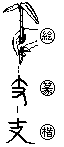 会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ)
会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
査察 ササツ🔗⭐🔉
【査察】
ササツ とりしらべる。調査。
瑣砕 ササイ🔗⭐🔉
【瑣砕】
ササイ  こまごましている。
こまごましている。 くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』
くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』
 こまごましている。
こまごましている。 くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』
くだくだしくめんどうなこと。『瑣屑サセツ』
瑣細 ササイ🔗⭐🔉
【瑣細】
ササイ こまかくて重要でないこと。『瑣小サショウ・瑣末サマツ』〈同義語〉些細。
笹 ささ🔗⭐🔉
【笹】
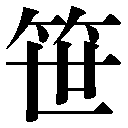 11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕
区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9
《訓読み》 ささ
《名付け》 ささ
《意味》
ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。
《解字》
「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。
11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕
区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9
《訓読み》 ささ
《名付け》 ささ
《意味》
ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。
《解字》
「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。
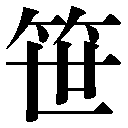 11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕
区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9
《訓読み》 ささ
《名付け》 ささ
《意味》
ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。
《解字》
「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。
11画 竹部 [人名漢字] 〔国〕
区点=2691 16進=3A7B シフトJIS=8DF9
《訓読み》 ささ
《名付け》 ささ
《意味》
ささ。くまざさ・ちまきざさなど、小形の竹の総称。
《解字》
「竹+世(何代もはえる)」の会意文字か。▽一説に、「竹+葉(小さな竹の葉)の略体」の会意文字とも。
筅 ささら🔗⭐🔉
【筅】
 12画 竹部
区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4
《音読み》 セン
12画 竹部
区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4
《音読み》 セン
 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 ささら
《意味》
n〉
《訓読み》 ささら
《意味》
 {名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。
{名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。
 「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。
《熟語》
→下付・中付語
「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。
《熟語》
→下付・中付語
 12画 竹部
区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4
《音読み》 セン
12画 竹部
区点=6806 16進=6426 シフトJIS=E2A4
《音読み》 セン
 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 ささら
《意味》
n〉
《訓読み》 ささら
《意味》
 {名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。
{名}ささら。先端が細かくわかれた小さな竹製のほうき。鍋ナベや釜カマを洗うのに使う。
 「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。
《熟語》
→下付・中付語
「茶筅チャセン」とは、茶をかきまわしてあわをたてる道具。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符先(=跣。細かく指がわかれているつまさき)」。足のつま先のように、先端のわかれたささら。
《熟語》
→下付・中付語
簓 ささら🔗⭐🔉
【簓】
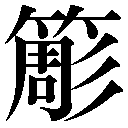 17画 竹部 〔国〕
区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7
《訓読み》 ささら
《意味》
17画 竹部 〔国〕
区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7
《訓読み》 ささら
《意味》
 ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。
ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。 ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。
《解字》
会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。
ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。
《解字》
会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。
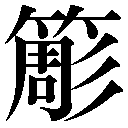 17画 竹部 〔国〕
区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7
《訓読み》 ささら
《意味》
17画 竹部 〔国〕
区点=6841 16進=6449 シフトJIS=E2C7
《訓読み》 ささら
《意味》
 ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。
ささら。楽器の一種。竹の先を細かく割った物。田楽舞に用いる。 ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。
《解字》
会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。
ささら。食器などを洗うのに使う道具。竹を細かく割って束ねた物。
《解字》
会意。「竹+彫(細かくきざむ)」。
細 ささ🔗⭐🔉
【細】
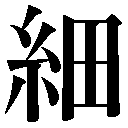 11画 糸部 [二年]
区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7
《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る
《音読み》 サイ
11画 糸部 [二年]
区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7
《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る
《音読み》 サイ /セイ
/セイ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ
《名付け》 くわし・ほそ
《意味》
〉
《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ
《名付け》 くわし・ほそ
《意味》
 {形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕
{形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕
 {形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」
{形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」
 〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。
〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。
《単語家族》
先(小さく分離した足さき)
〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。
〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。
《単語家族》
先(小さく分離した足さき) 洗(水をほそく分離して流す)
洗(水をほそく分離して流す) 私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。
《類義》
繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。
《類義》
繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
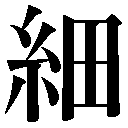 11画 糸部 [二年]
区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7
《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る
《音読み》 サイ
11画 糸部 [二年]
区点=2657 16進=3A59 シフトJIS=8DD7
《常用音訓》サイ/こま…か/こま…かい/ほそ…い/ほそ…る
《音読み》 サイ /セイ
/セイ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ
《名付け》 くわし・ほそ
《意味》
〉
《訓読み》 ほそる/こまか/ほそい(ほそし)/こまかい(こまかし)/ささ
《名付け》 くわし・ほそ
《意味》
 {形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕
{形}ほそい(ホソシ)。〈類義語〉→小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾ハ細キヲ厭ハズ」〔→論語〕
 {形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」
{形・名}こまかい(コマカシ)。こまごましたさま。また、小さい事がら。〈対語〉→粗・→略。〈類義語〉→些サ。「細密」「詳細」
 〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。
〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。
《単語家族》
先(小さく分離した足さき)
〔俗〕「細作」「奸細カンサイ」とは、スパイのこと。
〔国〕ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。右側の田の形は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+音符田シン・セイ」で、小さくこまかく分離していること。
《単語家族》
先(小さく分離した足さき) 洗(水をほそく分離して流す)
洗(水をほそく分離して流す) 私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。
《類義》
繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
私(小さくわける)などと同系。センとセイの音は、語尾の転じた形で、もと同系。
《類義》
繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
蓑蓑 ササ🔗⭐🔉
【蓑蓑】
サイサイ・ササ  →〈意味〉
→〈意味〉
 草木の葉が茂るさま。
草木の葉が茂るさま。
 →〈意味〉
→〈意味〉
 草木の葉が茂るさま。
草木の葉が茂るさま。
漢字源に「ささ」で始まるの検索結果 1-17。
 玉の小さい音の形容。
玉の小さい音の形容。