複数辞典一括検索+![]()
![]()
州 す🔗⭐🔉
【州】
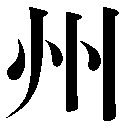 6画 巛部 [三年]
区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42
《常用音訓》シュウ/す
《音読み》 シュウ(シウ)
6画 巛部 [三年]
区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42
《常用音訓》シュウ/す
《音読み》 シュウ(シウ) /ス
/ス 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 す/しま
《名付け》 くに
《意味》
u〉
《訓読み》 す/しま
《名付け》 くに
《意味》
 {名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」
{名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」
 {名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」
{名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」
 {名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。
{名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。
 {名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕
{名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕
 {形}なかすのように、まとまっているさま。
《解字》
{形}なかすのように、まとまっているさま。
《解字》
 象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。
《単語家族》
周囲の周(まわりをとり巻く)
象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。
《単語家族》
周囲の周(まわりをとり巻く) 舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。
《類義》
洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。
《類義》
洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
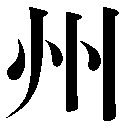 6画 巛部 [三年]
区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42
《常用音訓》シュウ/す
《音読み》 シュウ(シウ)
6画 巛部 [三年]
区点=2903 16進=3D23 シフトJIS=8F42
《常用音訓》シュウ/す
《音読み》 シュウ(シウ) /ス
/ス 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 す/しま
《名付け》 くに
《意味》
u〉
《訓読み》 す/しま
《名付け》 くに
《意味》
 {名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」
{名}す。しま。なかす。砂がたまって、水面に出た陸地。〈同義語〉→洲。「三角州サンカクス」
 {名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」
{名}大陸。〈同義語〉→洲。「アジア州」「欧州」
 {名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。
{名}上古の中国では、名山大川にちなんで、全国を九つの州にわけた、その一つ。▽九州とは、冀キ州・[エン]州・青州・幽州・揚州・荊ケイ州・予州・并ヘイ州・雍ヨウ州をいう。▽異説もある。
 {名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕
{名}地方の行政区画。周代では、約二千五百戸を州といい、明ミン・清シン時代には一省を数十にわけ、大きいのを州、小さいのを県といった。「州郡」「跨州連郡=州ニ跨リ、郡ニ連ナル」〔→蜀志〕
 {形}なかすのように、まとまっているさま。
《解字》
{形}なかすのように、まとまっているさま。
《解字》
 象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。
《単語家族》
周囲の周(まわりをとり巻く)
象形。川の中になかすのできたさまを描いたもので、砂地の周囲を、水がとり巻くことを示す。欠けめなくとり巻く意を含む。
《単語家族》
周囲の周(まわりをとり巻く) 舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。
《類義》
洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
舟(周囲をとり巻いて水のはいらぬふね)などと同系。
《類義》
洲は、州にさんずいを添えた字。大陸のことを、特にアジア洲のように書いたこともあるが、州・洲は区別するに及ばない。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
巣 す🔗⭐🔉
【巣】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
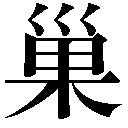 11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ)
11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)
/ジョウ(ゼウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
 {名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
 {動}すくう(スクフ)。巣
{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
 {名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
 会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも)
会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)
剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
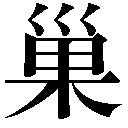 11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ)
11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)
/ジョウ(ゼウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
 {名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
 {動}すくう(スクフ)。巣
{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
 {名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
 会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも)
会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)
剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
推引 スイイン🔗⭐🔉
【推引】
スイイン 人を引き立てて用いる。「推引後進=後進ヲ推引ス」
栖 す🔗⭐🔉
【栖】
 10画 木部
区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2
《音読み》 セイ
10画 木部
区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2
《音読み》 セイ /サイ
/サイ 〈x
〈x ・q
・q 〉
《訓読み》 す/すむ
《意味》
〉
《訓読み》 す/すむ
《意味》
 {名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。
{名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。
 {動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」
{動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」
 「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。
《類義》
住は、ひと所に定着してすむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【棲】を見よ。
「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。
《類義》
住は、ひと所に定着してすむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【棲】を見よ。
 10画 木部
区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2
《音読み》 セイ
10画 木部
区点=3220 16進=4034 シフトJIS=90B2
《音読み》 セイ /サイ
/サイ 〈x
〈x ・q
・q 〉
《訓読み》 す/すむ
《意味》
〉
《訓読み》 す/すむ
《意味》
 {名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。
{名}す。ざる状をした、鳥のすみか。〈同義語〉→棲セイ。
 {動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」
{動}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。〈同義語〉→棲。「栖息セイソク(=棲息)」
 「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。
《類義》
住は、ひと所に定着してすむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【棲】を見よ。
「栖栖セイセイ」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。〈同義語〉棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子ニ謂ヒテ曰ハク、丘ナンスレゾカク栖栖タルヤ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+音符西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。
《類義》
住は、ひと所に定着してすむこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【棲】を見よ。
棲 す🔗⭐🔉
【棲】
 12画 木部
区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1
《音読み》 セイ
12画 木部
区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1
《音読み》 セイ /サイ
/サイ 〈x
〈x ・q
・q 〉
《訓読み》 すむ/す
《意味》
〉
《訓読み》 すむ/す
《意味》
 {動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」
{動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」
 {名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕
{名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕
 「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。
《解字》
形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。
《解字》
形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 木部
区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1
《音読み》 セイ
12画 木部
区点=3219 16進=4033 シフトJIS=90B1
《音読み》 セイ /サイ
/サイ 〈x
〈x ・q
・q 〉
《訓読み》 すむ/す
《意味》
〉
《訓読み》 すむ/す
《意味》
 {動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」
{動}すむ。ねぐらにいこうように、ゆっくりとやすむ。ねぐらを設けてすむ。〈同義語〉→栖。「棲遅セイチ(ゆっくりやすむ、おくれる)」「同棲ドウセイ」
 {名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕
{名}す。鳥のねぐら。すみか。転じて、すまい。ねどこ。〈同義語〉栖。「二嫂、使治朕棲=二嫂ニハ、朕ガ棲ヲ治メシム」〔→孟子〕
 「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。
《解字》
形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「棲棲セイセイ」とは、息づかいのせわしいさま。つぎつぎと事におわれて忙しいさま。〈同義語〉栖栖。
《解字》
形声。「木+音符妻セイ・サイ」。妻(つま)の原義とは関係がない。栖セイが本字で、西はざる状をした鳥のす。転じて、ねぐら、すまいの意となる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
水 すい🔗⭐🔉
【水】
 4画 水部 [一年]
区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085
《常用音訓》スイ/みず
《音読み》 スイ
4画 水部 [一年]
区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085
《常用音訓》スイ/みず
《音読み》 スイ
 〈shu
〈shu 〉
《訓読み》 みず(みづ)/すい
《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 みず(みづ)/すい
《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく
《意味》
 {名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕
{名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕
 {名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」
{名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」
 {名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」
{名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」
 {名}「水星」の略。
{名}「水星」の略。
 {名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。
{名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。
 {名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」
〔国〕
{名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」
〔国〕 「水素」の略。「水爆」
「水素」の略。「水爆」 みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。
みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。 すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。
《解字》
すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。
《解字》
 象形。みずの流れの姿を描いたもの。
《単語家族》
追(ルートについて進む)
象形。みずの流れの姿を描いたもの。
《単語家族》
追(ルートについて進む) 遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
 4画 水部 [一年]
区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085
《常用音訓》スイ/みず
《音読み》 スイ
4画 水部 [一年]
区点=3169 16進=3F65 シフトJIS=9085
《常用音訓》スイ/みず
《音読み》 スイ
 〈shu
〈shu 〉
《訓読み》 みず(みづ)/すい
《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 みず(みづ)/すい
《名付け》 お・たいら・な・なか・み・みず・みな・ゆ・ゆく
《意味》
 {名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕
{名}みず(ミヅ)。外わくに従って形をかえ、低い所に流れる性質をもつ液体の代表。▽火に対して水といい、湯に対して水(特に冷たいみず)という。また柔弱なものの代表。「水火(みずと、ひ。生活の基本条件)」「知者楽水=知者ハ水ヲ楽シム」〔→論語〕
 {名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」
{名}みず(ミヅ)。川や湖などのある場所。「滄浪水ソウロウノミズ(清らかな流れ。また滄浪という川の名)」「洞庭水ドウテイノミズ(洞庭湖)」「水陸」
 {名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」
{名}河川の名につけることば。「洛水ラクスイ」
 {名}「水星」の略。
{名}「水星」の略。
 {名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。
{名}五行の一つ。方角では北、色では黒、時節では冬、十干ジッカンでは壬ジンと癸キ、五音では羽に当てる。
 {名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」
〔国〕
{名}〔俗〕割増金や、手当。「貼水テンスイ(割増金)」
〔国〕 「水素」の略。「水爆」
「水素」の略。「水爆」 みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。
みず(ミヅ)。相撲で、勝負が長びき力士が疲れたとき、しばらく引き離して休ませること。 すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。
《解字》
すい。七曜の一つ。「水曜日」の略。
《解字》
 象形。みずの流れの姿を描いたもの。
《単語家族》
追(ルートについて進む)
象形。みずの流れの姿を描いたもの。
《単語家族》
追(ルートについて進む) 遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
遂(ルートに従ってどこまでも進む)と同系。その語尾がnとなったのは順や巡(従う)、循(ルートに従う)などである。平准の准ジュン(平らに落ち着く)と同系だと考える説もある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
水火 スイカ🔗⭐🔉
水花 スイカ🔗⭐🔉
【水花】
スイカ  うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。
うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。 はすの花の別名。『水華スイカ』
はすの花の別名。『水華スイカ』
 うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。
うきくさ。萍ヘイ・ビョウ。 はすの花の別名。『水華スイカ』
はすの花の別名。『水華スイカ』
水陰 スイイン🔗⭐🔉
【水陰】
スイイン  水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。
水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。 川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。
川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。
 水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。
水のこと。▽水は陰陽のうち陰に属する。 川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。
川の南岸。▽川の南を陰、川の北を陽とする。山の場合はその反対。
水雲 スイウン🔗⭐🔉
【水雲】
スイウン  水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」
水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」 水上にあらわれた雲。
水上にあらわれた雲。 海藻の名。もずくのこと。
海藻の名。もずくのこと。
 水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」
水と雲。雲水。「鳳簫吹断水雲間=鳳簫吹断シテ水雲間カナリ」 水上にあらわれた雲。
水上にあらわれた雲。 海藻の名。もずくのこと。
海藻の名。もずくのこと。
水運 スイウン🔗⭐🔉
【水運】
スイウン 陸運に対して、船で物資を運ぶこと。
水煙 スイエン🔗⭐🔉
【水煙】
 スイエン
スイエン  水上にたつもや。
水上にたつもや。 水たばこ。
水たばこ。 塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。
塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。 ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。
ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。
 スイエン
スイエン  水上にたつもや。
水上にたつもや。 水たばこ。
水たばこ。 塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。
塔の九輪の上についている炎の形をした飾り。▽「火」を忌みきらったことから。 ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。
ミズケムリ〔国〕水がこまかく飛びちって煙のようになったもの。しぶき。
水駅 スイエキ🔗⭐🔉
【水駅】
スイエキ 船着き場。
水甕 スイオウ🔗⭐🔉
【水甕】
スイオウ 水がめ。『水缸スイコウ』
洲 す🔗⭐🔉
炊煙 スイエン🔗⭐🔉
【炊煙】
スイエン 炊事をするかまどから出る煙。『炊烟スイエン』
笊 す🔗⭐🔉
【笊】
 10画 竹部
区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295
《音読み》 ソウ(サウ)
10画 竹部
区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(セウ)
/ショウ(セウ) 〈zh
〈zh o〉
《訓読み》 ざる/す
《意味》
o〉
《訓読み》 ざる/す
《意味》
 {名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」
{名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」
 {名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。
{名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。
 10画 竹部
区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295
《音読み》 ソウ(サウ)
10画 竹部
区点=6785 16進=6375 シフトJIS=E295
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(セウ)
/ショウ(セウ) 〈zh
〈zh o〉
《訓読み》 ざる/す
《意味》
o〉
《訓読み》 ざる/す
《意味》
 {名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」
{名}ざる。割った竹であんだかご。「笊籬ソウリ(ざる)」
 {名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。
{名}す。ざるの形をした鳥のす。〈類義語〉→巣。
《解字》
会意兼形声。「竹+音符爪ソウ(ひっかく、さらえる)」。
簀 す🔗⭐🔉
素足 スアシ🔗⭐🔉
【素足】
 ソソク 白い足。
ソソク 白い足。 スアシ〔国〕
スアシ〔国〕 はきものをはいていない足。はだし。
はきものをはいていない足。はだし。 たび・くつしたをはいていない足。
たび・くつしたをはいていない足。
 ソソク 白い足。
ソソク 白い足。 スアシ〔国〕
スアシ〔国〕 はきものをはいていない足。はだし。
はきものをはいていない足。はだし。 たび・くつしたをはいていない足。
たび・くつしたをはいていない足。
綏遠 スイエン🔗⭐🔉
【綏遠】
スイエン 遠い地方をおさめて静める。
綏安 スイアン🔗⭐🔉
【綏寧】
スイネイ 人民をおさめてやすらかにする。『綏安スイアン』▽「寧」も、やすらか。
翠羽 スイウ🔗⭐🔉
【翠羽】
スイウ かわせみの羽。珍しいものとされ、装飾品の材料とされた。
翠雨 スイウ🔗⭐🔉
【翠雨】
スイウ  青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。
青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。 穀物の生長を助ける雨。
穀物の生長を助ける雨。 美しい黒髪に降りかかる雨。
美しい黒髪に降りかかる雨。
 青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。
青葉に降る雨。〈類義語〉緑雨。 穀物の生長を助ける雨。
穀物の生長を助ける雨。 美しい黒髪に降りかかる雨。
美しい黒髪に降りかかる雨。
翠華 スイカ🔗⭐🔉
【翠華】
スイカ かわせみの羽で飾った天子の旗。「翠華南幸=翠華南幸ス」〔陳鴻〕
翠幄 スイアク🔗⭐🔉
【翠帷】
スイイ みどり色のとばり。『翠幄スイアク・翠帳スイチョウ』
翠蔭 スイイン🔗⭐🔉
【翠陰】
スイイン =翠蔭。青葉のかげ。〈類義語〉緑陰。
翠煙 スイエン🔗⭐🔉
【翠煙】
スイエン  青みを帯びた煙。
青みを帯びた煙。 青みを帯びたもや。
青みを帯びたもや。 遠くの青々とした森にかかっているもや。
遠くの青々とした森にかかっているもや。
 青みを帯びた煙。
青みを帯びた煙。 青みを帯びたもや。
青みを帯びたもや。 遠くの青々とした森にかかっているもや。
遠くの青々とした森にかかっているもや。
翠蛾 スイガ🔗⭐🔉
【翠蛾】
スイガ =翠娥。 青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。
青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。 転じて、美人のこと。
転じて、美人のこと。
 青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。
青黒い三日月形の眉マユ。美人の美しい眉のこと。 転じて、美人のこと。
転じて、美人のこと。
翠靄 スイアイ🔗⭐🔉
【翠靄】
スイアイ 青みを帯びたもや。
衰運 スイウン🔗⭐🔉
【衰勢】
スイセイ おとろえる運命。物事がおとろえていく傾向のこと。『衰運スイウン』
酔歌 スイカ🔗⭐🔉
【酔吟】
スイギン 酒に酔って詩や歌を口ずさむ。『酔歌スイカ』
酔臥 スイガ🔗⭐🔉
【酔臥】
スイガ 酒に酔ってねころぶ。また、酒に酔って眠る。
酔翁 スイオウ🔗⭐🔉
【酔翁】
スイオウ  酒に酔った老人。
酒に酔った老人。 宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。
宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。
 酒に酔った老人。
酒に酔った老人。 宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。
宋ソウの文人、欧陽脩オウヨウシュウの号。
酢 す🔗⭐🔉
【酢】
 12画 酉部 [常用漢字]
区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C
《常用音訓》サク/す
《音読み》
12画 酉部 [常用漢字]
区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C
《常用音訓》サク/す
《音読み》  サク
サク /ソ
/ソ /ス
/ス 〈c
〈c 〉/
〉/ サク
サク /ザク
/ザク 〈zu
〈zu 〉
《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《名付け》 す
《意味》
〉
《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《名付け》 す
《意味》

 {名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。
{名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。
 {形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。
{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。
 サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕
《解字》
形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし)
サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕
《解字》
形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし) 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 酉部 [常用漢字]
区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C
《常用音訓》サク/す
《音読み》
12画 酉部 [常用漢字]
区点=3161 16進=3F5D シフトJIS=907C
《常用音訓》サク/す
《音読み》  サク
サク /ソ
/ソ /ス
/ス 〈c
〈c 〉/
〉/ サク
サク /ザク
/ザク 〈zu
〈zu 〉
《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《名付け》 す
《意味》
〉
《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《名付け》 す
《意味》

 {名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。
{名}す。すっぱい味の液体。長くすえおいて酸味をつけた汁のこと。〈同義語〉→醋。
 {形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。
{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酸。
 サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕
《解字》
形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし)
サクス{動}むくいる(ムクユ)。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒を進める)に対することば。〈同義語〉→醋。〈類義語〉→酬。「酬酢(酒のやりとりを重ねる)」「或献或酢=或イハ献ジ或イハ酢ス」〔→詩経〕
《解字》
形声。「酉+音符乍」。醋(月日を重ねて、発酵した汁をねかせておく)と同じ。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし) 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
酸 す🔗⭐🔉
【酸】
 14画 酉部 [五年]
区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F
《常用音訓》サン/す…い
《音読み》 サン
14画 酉部 [五年]
区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F
《常用音訓》サン/す…い
《音読み》 サン
 〈su
〈su n〉
《訓読み》 す/すい(すし)
《意味》
n〉
《訓読み》 す/すい(すし)
《意味》
 {名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」
{名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」
 {形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。
{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。
 {名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」
{名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」
 {形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」
{形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」
 {形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。
《類義》
醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。
《類義》
醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 14画 酉部 [五年]
区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F
《常用音訓》サン/す…い
《音読み》 サン
14画 酉部 [五年]
区点=2732 16進=3B40 シフトJIS=8E5F
《常用音訓》サン/す…い
《音読み》 サン
 〈su
〈su n〉
《訓読み》 す/すい(すし)
《意味》
n〉
《訓読み》 す/すい(すし)
《意味》
 {名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」
{名}す。すっぱい液体。穀物や乳を発酵させたり、果物の汁をとったりしてつくる。筋骨をスマートにし、からだを柔らげる作用があるとされた。〈類義語〉→醋ソ/サク・→酢ソ/サク。「乳酸」「果酸」
 {形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。
{形}すい(スシ)。酢のような味がする。すっぱい。五味(辛・酸・苦・甘・鹹カン)の一つ。
 {名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」
{名}酸性をおびた水素化合物。水にとけると水素イオンを生じ、リトマス試験紙を赤くする。「塩酸」「酸性」
 {形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」
{形・名}つんと鼻をついて涙をうながすようなつらい感じがするさま。つらさ。わびしさ。「酸鼻(鼻につんとこたえて涙をさそうような)」「寒酸(貧しくてわびしい)」「辛酸(つらさ)」
 {形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。
《類義》
醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}〔俗〕だるくてつらい。「腰酸ヤオスワン(こしがだるい)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音シュン)は、「允イン(すらりとした柔らかい人の姿)+夂(足)」で、スマートにたった人をあらわす。酸はそれを音符とし、酉(さけ)を加えた字で、筋骨を柔らげ、スマートにする発酵液のこと。
《類義》
醋と酢とは、発酵した汁を長くすえおいて、すっぱい味を出したもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
醋 す🔗⭐🔉
【醋】
 15画 酉部
区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA
《音読み》
15画 酉部
区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA
《音読み》  サク
サク /ソ
/ソ /ス
/ス 〈c
〈c 〉/
〉/ サク
サク /ザク
/ザク 《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《意味》
《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《意味》

 {名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。
{名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。
 {形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。
{形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。
 {動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。
《解字》
会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし)
{動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。
《解字》
会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし) 昨
昨 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 酉部
区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA
《音読み》
15画 酉部
区点=7844 16進=6E4C シフトJIS=E7CA
《音読み》  サク
サク /ソ
/ソ /ス
/ス 〈c
〈c 〉/
〉/ サク
サク /ザク
/ザク 《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《意味》
《訓読み》 す/すい(すし)/むくいる(むくゆ)
《意味》

 {名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。
{名}す。すっぱい味の液体。酒、または酒かすを長くねかせて、発酵させたもの。
 {形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。
{形}すい(スシ)。すっぱい。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酸。
 {動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。
《解字》
会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし)
{動}むくいる(ムクユ)。杯をやりとりして応対する。客が主人に杯を返す。▽献(主人が客に酒をすすめる)に対することば。〈同義語〉→酢。〈類義語〉→酬。
《解字》
会意兼形声。「酉+音符昔(日を重ねる)」で、月日を重ねて、発酵した汁をねかせておくこと。
《単語家族》
昔(月日を重ねたむかし) 昨
昨 錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
錯(金属を上に重ねてめっきする)と同系。
《類義》
→酸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「す」で始まるの検索結果 1-43。もっと読み込む
 水におぼれ、火に焼かれるような苦しみ。「救民於水火之中=民ヲ水火ノ中ヨリ救フ」〔
水におぼれ、火に焼かれるような苦しみ。「救民於水火之中=民ヲ水火ノ中ヨリ救フ」〔 危険なもののたとえ。(6)水と火は性質が相反することから、仲の悪いことのたとえ。〔
危険なもののたとえ。(6)水と火は性質が相反することから、仲の悪いことのたとえ。〔 9画 水部 [人名漢字]
区点=2907 16進=3D27 シフトJIS=8F46
《音読み》 シュウ(シウ)
9画 水部 [人名漢字]
区点=2907 16進=3D27 シフトJIS=8F46
《音読み》 シュウ(シウ) 17画 竹部
区点=6839 16進=6447 シフトJIS=E2C5
《音読み》 サク
17画 竹部
区点=6839 16進=6447 シフトJIS=E2C5
《音読み》 サク 〉
《訓読み》 す
《意味》
〉
《訓読み》 す
《意味》
 18画 髟部
区点=8202 16進=7222 シフトJIS=E9A0
《音読み》 ショウ
18画 髟部
区点=8202 16進=7222 シフトJIS=E9A0
《音読み》 ショウ