複数辞典一括検索+![]()
![]()
不遇 アワズ🔗⭐🔉
【不遇】
フグウ・アワズ すぐれた才能・能力を持っていながら、運が悪くて世間に認められないこと。また、そのためによい待遇を受けないこと。
併 あわせる🔗⭐🔉
【併】
 8画 人部 [常用漢字]
区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9
《常用音訓》ヘイ/あわ…せる
《音読み》 ヘイ
8画 人部 [常用漢字]
区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9
《常用音訓》ヘイ/あわ…せる
《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)
/ヒョウ(ヒャウ) 〈b
〈b ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし
《意味》
 {動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕
{動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕
 {動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」
〔国〕しかし。けれども。しかしながら。
《解字》
会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并
《単語家族》
餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品)
{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」
〔国〕しかし。けれども。しかしながら。
《解字》
会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并
《単語家族》
餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品) 屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。
《類義》
→並
《異字同訓》
あわせる。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。
《類義》
→並
《異字同訓》
あわせる。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 人部 [常用漢字]
区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9
《常用音訓》ヘイ/あわ…せる
《音読み》 ヘイ
8画 人部 [常用漢字]
区点=4227 16進=4A3B シフトJIS=95B9
《常用音訓》ヘイ/あわ…せる
《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)
/ヒョウ(ヒャウ) 〈b
〈b ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/しかし
《意味》
 {動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕
{動}あわせる(アハス)。二つ以上のものをいっしょにする。「合併」「併気積力、運兵計謀=気ヲ併セ力ヲ積ミ、兵ヲ計謀ニ運ラス」〔→孫子〕
 {動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」
〔国〕しかし。けれども。しかしながら。
《解字》
会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并
《単語家族》
餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品)
{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。并ヘイ・併(あわせる)と並(ならぶ)は、本来意味が異なり別字であるが、のち混用された。▽並ヘイに当てた用法。「併立(=並立)」
〔国〕しかし。けれども。しかしながら。
《解字》
会意兼形声。并ヘイは、二人の人と二印とをあわせて、二人または二個を合併することを示す会意文字。併は「人+音符并」。→并
《単語家族》
餅ヘイ(蒸し米をあわせひっつけた食品) 屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。
《類義》
→並
《異字同訓》
あわせる。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
屏ヘイ(幕や板をあわせたついたて)と同系。
《類義》
→並
《異字同訓》
あわせる。→合
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
勠 あわせる🔗⭐🔉
協 あわせる🔗⭐🔉
【協】
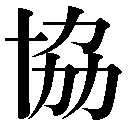 8画 十部 [四年]
区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6
【恊】異体字異体字
8画 十部 [四年]
区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6
【恊】異体字異体字
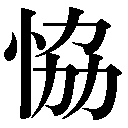 9画
9画  部
区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ケフ)
部
区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)
/ギョウ(ゲフ) 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)
《名付け》 かな・かなう・かのう・やす
《意味》
〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)
《名付け》 かな・かなう・かのう・やす
《意味》
 キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率
キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率 怠リテ協セズ」〔→書経〕
怠リテ協セズ」〔→書経〕
 {動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」
{動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」
 {名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」
《解字》
会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」
《解字》
会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
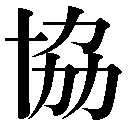 8画 十部 [四年]
区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6
【恊】異体字異体字
8画 十部 [四年]
区点=2208 16進=3628 シフトJIS=8BA6
【恊】異体字異体字
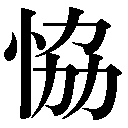 9画
9画  部
区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ケフ)
部
区点=5580 16進=5770 シフトJIS=9C90
《常用音訓》キョウ
《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)
/ギョウ(ゲフ) 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)
《名付け》 かな・かなう・かのう・やす
《意味》
〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/かなう(かなふ)
《名付け》 かな・かなう・かのう・やす
《意味》
 キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率
キョウス{動}あわせる(アハス)。力を一つにあわせる。「協議」「有衆率怠弗協=有衆、率 怠リテ協セズ」〔→書経〕
怠リテ協セズ」〔→書経〕
 {動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」
{動}かなう(カナフ)。多くのものが一つにあわさる。〈同義語〉→叶。「協議」
 {名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」
《解字》
会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}清シン朝の軍団の名。旅団に当たる。「協台(副将)」
《解字》
会意兼形声。右側は、力を三つあわせた会意文字(音キョウ)で、多くの力をあわせること。協はそれを音符とし、十印(ひとまとめ)を加えた字。▽叶は、協の異体字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
可憐 アワレムベシ🔗⭐🔉
合 あわす🔗⭐🔉
【合】
 6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ
6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
 {動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
 {動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
 {動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
 {名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
 「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
 {単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
 {単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
 {助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
 {助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
 {名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
 会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱)
会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)
盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ
6画 口部 [二年]
区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87
《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる
《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
〉
《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし
《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし
《意味》
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕
 {動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕
 {動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」
 {動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」
 {名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」
 「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。
 {単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕
 {単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。
 {助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕
 {助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」
 {名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕
〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」
《解字》
 会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱)
会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。
《単語家族》
盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)
盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
含(ふくむ)と同系。
《類義》
→会
《異字同訓》
あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
哀 あわれ🔗⭐🔉
【哀】
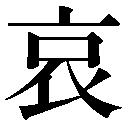 9画 口部 [常用漢字]
区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3
《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ
《音読み》 アイ
9画 口部 [常用漢字]
区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3
《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ
《音読み》 アイ /オ/アイ
/オ/アイ 〈
〈 i〉
《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)
《意味》
i〉
《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)
《意味》
 {形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」
{形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」
 {動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕
{動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕
 {名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕
{名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕
 {名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」
《解字》
会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。
《単語家族》
愛(せつない思いをこらえる)
{名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」
《解字》
会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。
《単語家族》
愛(せつない思いをこらえる) 噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
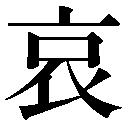 9画 口部 [常用漢字]
区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3
《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ
《音読み》 アイ
9画 口部 [常用漢字]
区点=1605 16進=3025 シフトJIS=88A3
《常用音訓》アイ/あわ…れ/あわ…れむ
《音読み》 アイ /オ/アイ
/オ/アイ 〈
〈 i〉
《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)
《意味》
i〉
《訓読み》 あわれ(あはれ)/あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/かなしみ/かなしい(かなし)
《意味》
 {形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」
{形・名}あわれ(アハレ)。せつないさま。悲しいさま。また、その感情。▽もと、ある思いのために胸のつかえたような気持ちをいう。〈対語〉→喜。「哀切」
 {動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕
{動・名}あわれむ(アハレム)。あわれみ(アハレミ)。かわいそうで、胸が詰まるような気持ちになる。かわいそうになる。また、そのような気持ち。〈類義語〉→憐レン。「可哀=哀レムベシ」「乞哀=哀レミヲ乞フ」「吾哀王孫而進食=吾、王孫ヲ哀レンデ食ヲ進ム」〔→史記〕
 {名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕
{名・形}かなしみ。かなしい(カナシ)。つらくて胸のつかえたような気持ち。また、そのような気持ちであるさま。「悲哀」「喜怒哀楽」「嗚呼哀哉=アア哀シイカナ」〔→韓愈〕
 {名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」
《解字》
会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。
《単語家族》
愛(せつない思いをこらえる)
{名}父母の喪。「哀子(父母の喪に服する子)」
《解字》
会意兼形声。衣は、かぶせて隠す意を含む。哀は「口+音符衣」で、思いを胸中におさえ、口を隠してむせぶこと。
《単語家族》
愛(せつない思いをこらえる) 噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
噫アイ(胸がつかえて声が漏れる)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
天晴 アワレ🔗⭐🔉
【天晴】
アッパレ・アワレ〔国〕 すぐれてみごとなこと。
すぐれてみごとなこと。 ほめるときにいうことば。
ほめるときにいうことば。
 すぐれてみごとなこと。
すぐれてみごとなこと。 ほめるときにいうことば。
ほめるときにいうことば。
夾 あわせ🔗⭐🔉
【夾】
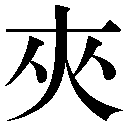 7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ)
7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
 {動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
 {形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
 {名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
 {名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
 会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ)
会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)
峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
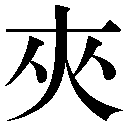 7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ)
7画 大部
区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1
《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)
《意味》
 {動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕
 {形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。
 {名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」
 {名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」
《解字》
 会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ)
会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。
《単語家族》
挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)
峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
并 あわせる🔗⭐🔉
【并】
 6画 干部
区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3
《音読み》 ヘイ
6画 干部
区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3
《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)
/ヒョウ(ヒャウ) 〈b
〈b ng・b
ng・b ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに
《意味》
 {動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」
{動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」
 {動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。
{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。
 {接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」
{接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」
 {名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。
《解字》
{名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。
《解字》
 会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。
《単語家族》
竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。
《単語家族》
竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画 干部
区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3
《音読み》 ヘイ
6画 干部
区点=5485 16進=5675 シフトJIS=9BF3
《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)
/ヒョウ(ヒャウ) 〈b
〈b ng・b
ng・b ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわせる(あはす)/ならぶ/ならべる(ならぶ)/ならびに
《意味》
 {動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」
{動}あわせる(アハス)。一つにする。〈同義語〉→併。「合并ガッペイ(=合併)」
 {動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。
{動}ならぶ。ならべる(ナラブ)。〈同義語〉→併。
 {接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」
{接続}ならびに。それにまた、の意をあらわすことば。「并且ナラビニカツ(その上)」
 {名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。
《解字》
{名}山西省太原地方の別称。▽平声に読む。
《解字》
 会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。
《単語家族》
竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。もとの字は、「人二人+干を二つ」。同じように肩をならべてひっつけたさま。
《単語家族》
竝ヘイ(=並。ならぶ)と近く、屏ヘイ(ならべてたてたついたて)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
悲 あわれみ🔗⭐🔉
【悲】
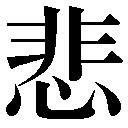 12画 心部 [三年]
区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF
《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ
《音読み》 ヒ
12画 心部 [三年]
区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF
《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ
《音読み》 ヒ
 〈b
〈b i〉
《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)
《意味》
i〉
《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)
《意味》
 {形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。
{形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。
 {動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕
{動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕
 {名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕
{名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕
 {名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」
《解字》
会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。
《単語家族》
扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」
《解字》
会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。
《単語家族》
扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
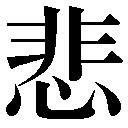 12画 心部 [三年]
区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF
《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ
《音読み》 ヒ
12画 心部 [三年]
区点=4065 16進=4861 シフトJIS=94DF
《常用音訓》ヒ/かな…しい/かな…しむ
《音読み》 ヒ
 〈b
〈b i〉
《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)
《意味》
i〉
《訓読み》 かなしい(かなし)/かなしむ/かなしみ/あわれみ(あはれみ)
《意味》
 {形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。
{形}かなしい(カナシ)。胸がさけるようにせつない。〈対語〉→楽。
 {動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕
{動}かなしむ。〈対語〉→楽。「奚惆悵而独悲=ナンゾ惆悵トシテ独リ悲シマン」〔→陶潜〕
 {名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕
{名}かなしみ。〈対語〉→楽。「楽尽悲来=楽シミ尽キテ、悲シミ来タル」〔陳鴻〕
 {名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」
《解字》
会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。
《単語家族》
扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}〔仏〕あわれみ(アハレミ)。衆生シュジョウの苦しみを除こうとする心。「慈悲」
《解字》
会意兼形声。非は、羽が左右に反対に開いたさま。両方に割れる意を含む。悲は「心+音符非」で、心が調和統一を失って裂けること。胸が裂けるようなせつない感じのこと。
《単語家族》
扉ヒ(両方に開くとびら)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
愍 あわれむ🔗⭐🔉
怜 あわれむ🔗⭐🔉
【怜】
 8画
8画  部 [人名漢字]
区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5
《音読み》 レイ
部 [人名漢字]
区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)
《名付け》 さと・さとし・とき
《意味》
《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)
《名付け》 さと・さとし・とき
《意味》
 {形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」
{形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」
 {動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。
《解字》
会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま)
{動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。
《解字》
会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま) 霊(澄みきった神のお告げ)
霊(澄みきった神のお告げ) 玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。
《類義》
→賢
《熟語》
→熟語
玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。
《類義》
→賢
《熟語》
→熟語
 8画
8画  部 [人名漢字]
区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5
《音読み》 レイ
部 [人名漢字]
区点=4671 16進=4E67 シフトJIS=97E5
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)
《名付け》 さと・さとし・とき
《意味》
《訓読み》 さとい(さとし)/あわれむ(あはれむ)
《名付け》 さと・さとし・とき
《意味》
 {形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」
{形}さとい(サトシ)。心が澄んでいて賢い。悟りがよい。〈類義語〉→賢。「怜悧レイリ(さとい)」
 {動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。
《解字》
会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま)
{動}あわれむ(アハレム)。▽憐レンの俗字として用いる。(平)先韻に読む。
《解字》
会意兼形声。令は、澄みきって清らかな神の命令。冷(つめたく澄んださま) 霊(澄みきった神のお告げ)
霊(澄みきった神のお告げ) 玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。
《類義》
→賢
《熟語》
→熟語
玲レイ(清らかに澄んだ玉)などと同系。怜は「心+音符令」で、心が澄みきったさま。
《類義》
→賢
《熟語》
→熟語
恤 あわれむ🔗⭐🔉
【恤】
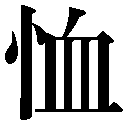 9画
9画  部
区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95
《音読み》 ジュツ
部
区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95
《音読み》 ジュツ /シュツ
/シュツ /シュチ
/シュチ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)
《意味》
〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)
《意味》
 {動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕
{動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕
 {動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕
{動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕
 {動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」
《解字》
会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」
《解字》
会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
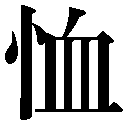 9画
9画  部
区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95
《音読み》 ジュツ
部
区点=5585 16進=5775 シフトJIS=9C95
《音読み》 ジュツ /シュツ
/シュツ /シュチ
/シュチ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)
《意味》
〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/うれえる(うれふ)
《意味》
 {動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕
{動}あわれむ(アハレム)。気の毒な人に思いをめぐらす。情けをめぐらす。「我后不恤我衆=我ガ后我ガ衆ヲ恤マズ」〔→書経〕
 {動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕
{動}うれえる(ウレフ)。気を配る。いろいろと心配する。「遑恤我後=我ガ後ヲ恤フルニ遑アランヤ」〔→詩経〕
 {動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」
《解字》
会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}人の難儀を気の毒がって金品を恵む。「賑恤シンジュツ」「救恤品キュウジュツヒン」
《解字》
会意兼形声。血は、全身くまなく巡るちのこと。恤は「心+音符血」で、心をすみずみまで思い巡らせること。▽巡や徇ジュン(めぐる)はその語尾が鼻音となったことば。ことに恂ジュン(心をすべての面に行き巡らすこと)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
慌 あわただしい🔗⭐🔉
【慌】
 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51
《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる
《音読み》 コウ(クワウ)
部 [常用漢字]
区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51
《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる
《音読み》 コウ(クワウ)
 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」
{形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」
 {動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」
{動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」
 {形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」
{形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」
 {動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」
《解字》
会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」
《解字》
会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51
《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる
《音読み》 コウ(クワウ)
部 [常用漢字]
区点=2518 16進=3932 シフトJIS=8D51
《常用音訓》コウ/あわ…ただしい/あわ…てる
《音読み》 コウ(クワウ)
 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/あわてる(あわつ)/くらい(くらし)/おそれる(おそる)
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」
{形}あわただしい(アワタダシ)。そわそわと落ち着かない。「慌忙コウボウ」
 {動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」
{動}あわてる(アワツ)。動揺して何をしてよいかわからないほどにうろたえる。〈類義語〉→惶。「慌乱コウラン」
 {形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」
{形}くらい(クラシ)。ぼんやりしている。〈同義語〉→恍。「慌忽コウコツ(=恍忽)」
 {動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」
《解字》
会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}おそれる(オソル)。おそれておどおどする。〈同義語〉→惶。「恐慌キョウコウ」
《解字》
会意兼形声。荒コウは、あれてむなしく何もないさま。また広(ひろい)や徨コウ(さまよう)に通じて、あてどもなく広がるさま。慌は「心+音符荒」で、心中がむなしくて自信をなくし落ち着かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
慥 あわただしい🔗⭐🔉
【慥】
 14画
14画  部
区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2
《音読み》 ゾウ(ザウ)
部
区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2
《音読み》 ゾウ(ザウ) /ソウ(サウ)
/ソウ(サウ)
 〈c
〈c o・z
o・z o〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか
《意味》
o〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。
{形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。
 「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕
〔国〕
「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕
〔国〕 こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」
こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」 たしか。おそらく。多分。
《解字》
会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。
たしか。おそらく。多分。
《解字》
会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。
 14画
14画  部
区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2
《音読み》 ゾウ(ザウ)
部
区点=5652 16進=5854 シフトJIS=9CD2
《音読み》 ゾウ(ザウ) /ソウ(サウ)
/ソウ(サウ)
 〈c
〈c o・z
o・z o〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか
《意味》
o〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/こしらえる(こしらふ)/たしか
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。
{形}あわただしい(アワタダシ)。とりあえず急場にまにあわせるさま。まにあわせにつくろうさま。
 「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕
〔国〕
「慥慥ゾウゾウ」「慥慥爾ゾウゾウジ」とは、いったことをすぐ実行するさま。「君子胡不慥慥爾=君子ナンゾ慥慥タラザランヤ」〔→中庸〕
〔国〕 こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」
こしらえる(コシラフ)。ありあわせの材料で組み立てる。「急慥キュウゴシラえ」 たしか。おそらく。多分。
《解字》
会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。
たしか。おそらく。多分。
《解字》
会意兼形声。造次ゾウジ(急ごしらえ)の造は、あわただしく寄せ集めること。慥は「心+音符造」で、そそくさと急場をつくろう気持ちのこと。
憫 あわれみ🔗⭐🔉
【憫】
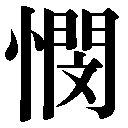 15画
15画  部
区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0
《音読み》 ビン
部
区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0
《音読み》 ビン /ミン
/ミン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)
《意味》
n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)
《意味》
 {動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」
{動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」
 {名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。
{名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。
 {動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。
《単語家族》
問モン・ブン(隠れたことを尋ねる)
{動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。
《単語家族》
問モン・ブン(隠れたことを尋ねる) 聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。
《類義》
憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。
《類義》
憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
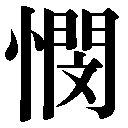 15画
15画  部
区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0
《音読み》 ビン
部
区点=5666 16進=5862 シフトJIS=9CE0
《音読み》 ビン /ミン
/ミン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)
《意味》
n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)/あわれみ(あはれみ)/うれえる(うれふ)
《意味》
 {動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」
{動}あわれむ(アハレム)。見えないところまで、こまごまと思いやる。気の毒に思う。「憐憫レンビン」「憫農=農ヲ憫ム」
 {名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。
{名}あわれみ(アハレミ)。同情の気持ち。細かい思いやり。
 {動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。
《単語家族》
問モン・ブン(隠れたことを尋ねる)
{動}うれえる(ウレフ)。こまごまと心配して心を痛める。また、人知れず気にやむ。「阨窮而不憫=阨窮スルモ憫ヘズ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。閔ビンは「門+文」からなり、門(隠す)と文(細かいあや)のどちらを音符と考えてもよい。憫は「心+音符閔」で、心印を加えて閔の原義をより明白に示したもの。隠れた点まで思いやること。
《単語家族》
問モン・ブン(隠れたことを尋ねる) 聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。
《類義》
憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
聞モン・ブン(隠されたことをきく)と同系。
《類義》
憐レンは、心が引かれて絶ち切れないこと。哀アイは、胸が詰まってせつない感じのすること。悲は、心が裂けるように痛むこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
憐 あわれむ🔗⭐🔉
【憐】
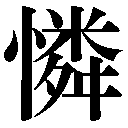 15画
15画  部
区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7
《音読み》 レン
部
区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7
《音読み》 レン
 〈li
〈li n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)
《意味》
n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)
《意味》
 {動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」
{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」
 {動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕
{動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕
 {動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」
《解字》
{動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」
《解字》
 会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。
《単語家族》
隣(次々と続くとなり家)
会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。
《単語家族》
隣(次々と続くとなり家) 燐(続いてたえない鬼火)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
燐(続いてたえない鬼火)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
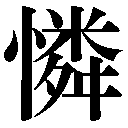 15画
15画  部
区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7
《音読み》 レン
部
区点=4689 16進=4E79 シフトJIS=97F7
《音読み》 レン
 〈li
〈li n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)
《意味》
n〉
《訓読み》 あわれむ(あはれむ)
《意味》
 {動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」
{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思って、いつまでも心が引かれる。「可憐=憐レムベシ」「同病相憐=同病アヒ憐レム」
 {動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕
{動}あわれむ(アハレム)。ああと感じ入って心が引かれる。「可憐光彩生門戸=憐レムベシ、光彩、門戸ニ生ズ」〔→白居易〕
 {動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」
《解字》
{動}あわれむ(アハレム)。いとおしむ。「自憐=ミヅカラ憐レム」
《解字》
 会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。
《単語家族》
隣(次々と続くとなり家)
会意兼形声。右側の部分は「炎(ひ)+舛(足がよろめく)」の会意文字で、よろよろとしているが、たえずに続いて燃える鬼火(燐リン)のこと。次々と続いてたえない意を含む。憐はそれを音符とし、心を加えた字で、心がある対象に引かれて、つらつらと思いがたえないこと。
《単語家族》
隣(次々と続くとなり家) 燐(続いてたえない鬼火)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
燐(続いてたえない鬼火)と同系。
《類義》
→憫
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
戮 あわせる🔗⭐🔉
【戮】
 15画 戈部
区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43
《音読み》 リク
15画 戈部
区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43
《音読み》 リク /ロク
/ロク 〈l
〈l 〉
《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)
《意味》
〉
《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)
《意味》
 リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕
リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕
 {名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」
{名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」
 {名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕
{名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕
 {動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。
《単語家族》
寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。
《単語家族》
寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 戈部
区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43
《音読み》 リク
15画 戈部
区点=5704 16進=5924 シフトJIS=9D43
《音読み》 リク /ロク
/ロク 〈l
〈l 〉
《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)
《意味》
〉
《訓読み》 ころす/あわせる(あはす)
《意味》
 リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕
リクス{動}ころす。ばらばらに切ってころす。敵を残酷なやり方でころす。また、罪人を残酷なやり方で死刑にする。「殺戮サツリク」「駆飛廉於海隅而戮之=飛廉ヲ海隅ニ駆リテ、コレヲ戮ス」〔→孟子〕
 {名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」
{名}死刑。また、殺害。「刑戮ケイリク」「就戮=戮ニ就ク」
 {名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕
{名}恥。はずかしめ。「従耳目之欲以為父母戮=耳目ノ欲ニ従ヒテ、モッテ父母ノ戮ヲ為ス」〔→孟子〕
 {動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。
《単語家族》
寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}あわせる(アハス)。力をあわせること。▽勠リクに当てた用法。「臣与将軍戮力而攻秦=臣、将軍ト力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。左側の字(音リョウ)とは、鳥がわかれて高く飛ぶさま。複数に分ける意を含む。戮はそれを音符とし、戈(ほこ)を加えた字で、刃物でいくつにも切り離すこと。
《単語家族》
寥リョウ(ばらばらにわかれる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
泡 あわ🔗⭐🔉
沫雪 アワユキ🔗⭐🔉
【沫雪】
アワユキ〔国〕溶けやすい雪。〈同義語〉泡雪。
淡 あわい🔗⭐🔉
【淡】
 11画 水部 [常用漢字]
区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257
《常用音訓》タン/あわ…い
《音読み》 タン(タム)
11画 水部 [常用漢字]
区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257
《常用音訓》タン/あわ…い
《音読み》 タン(タム) /ダン(ダム)
/ダン(ダム) 〈d
〈d n〉
《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)
《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう
《意味》
n〉
《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)
《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう
《意味》
 {形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」
{形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」
 タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」
タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」
 タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」
《解字》
形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」
《解字》
形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 11画 水部 [常用漢字]
区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257
《常用音訓》タン/あわ…い
《音読み》 タン(タム)
11画 水部 [常用漢字]
区点=3524 16進=4338 シフトJIS=9257
《常用音訓》タン/あわ…い
《音読み》 タン(タム) /ダン(ダム)
/ダン(ダム) 〈d
〈d n〉
《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)
《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう
《意味》
n〉
《訓読み》 あわい(あはし)/うすい(うすし)
《名付け》 あう・あわ・あわし・あわじ・おう
《意味》
 {形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」
{形}あわい(アハシ)。うすい(ウスシ)。刺激がないさま。色や味がうすいさま。〈同義語〉→澹タン。〈対語〉→濃。「濃淡」「淡青(うすい青色)」
 タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」
タンナリ{形・名}あわい(アハシ)。あっさりしたさま。あっさりしたもの。「君子之道、淡而不厭=君子之道ハ、淡ニシテシカモ厭ハズ」〔→中庸〕「君子之交淡若水=君子ノ交ハリハ淡キコト水ノゴトシ」〔→荘子〕「食淡=淡ヲ食ラフ」
 タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」
《解字》
形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
タンナリ{形}欲望がうすいさま。〈同義語〉→澹。「淡泊」「恬淡テンタン(欲がなくあっさりしている)」
《解字》
形声。右側の炎はもと、火を三つあわせた会意文字。淡は、水にそれを単なる音符としてそえた字で、火が盛んにもえるという原義には関係がない。澹と同じく、静かに安定して、刺激のないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
淡雪 アワユキ🔗⭐🔉
【淡雪】
アワユキ〔国〕 うっすらと降りつもった雪。
うっすらと降りつもった雪。 春になって降る、とけやすい雪。
春になって降る、とけやすい雪。
 うっすらと降りつもった雪。
うっすらと降りつもった雪。 春になって降る、とけやすい雪。
春になって降る、とけやすい雪。
澹 あわい🔗⭐🔉
【澹】
 16画 水部
区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057
《音読み》
16画 水部
区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057
《音読み》  タン(タム)
タン(タム) /ダン(ダム)
/ダン(ダム) 〈d
〈d n〉/
n〉/ セン(セム)
セン(セム) /ゼン(ゼム)
/ゼン(ゼム) 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)
《意味》
n〉
《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)
《意味》

 タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕
タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕
 タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕
タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕
 {形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。
{形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。
 {動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 16画 水部
区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057
《音読み》
16画 水部
区点=6324 16進=5F38 シフトJIS=E057
《音読み》  タン(タム)
タン(タム) /ダン(ダム)
/ダン(ダム) 〈d
〈d n〉/
n〉/ セン(セム)
セン(セム) /ゼン(ゼム)
/ゼン(ゼム) 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)
《意味》
n〉
《訓読み》 しずか(しづかなり)/やすらか(やすらかなり)/あわい(あはし)/たりる(たる)
《意味》

 タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕
タンタリ{形}水がゆったりたゆたうさま。「水澹澹兮生煙=水ハ澹澹トシテ煙ヲ生ズ」〔→李白〕
 タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕
タンタリ{形}しずか(シヅカナリ)。やすらか(ヤスラカナリ)。ゆったりと落ち着いたさま。しずかで穏やかなさま。〈同義語〉→憺。〈類義語〉→恬テン。「澹兮其若海=澹トシテソレ海ノゴトシ」〔→老子〕
 {形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。
{形}あわい(アハシ)。あっさりしているさま。さっぱりしているさま。〈同義語〉→淡。〈対語〉→濃。
 {動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動}たりる(タル)。じゅうぶんである。また、たっぷりとみたす。▽贍センに当てた用法。「物不能澹則必争=物澹ルコトアタハザレバスナハチ必ズ争フ」〔→荀子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音セン・タン)は、ずっしりと下がる、重い、落ち着くなどの意をあらわす。澹はそれを音符とし、水を加えた字。穏やかで、起伏がないことから、淡(あわい)と同じ意にも用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
矜 あわれむ🔗⭐🔉
【矜】
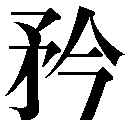 9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》
9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》  キン
キン /ゴン
/ゴン 〈q
〈q n〉/
n〉/ キョウ
キョウ
 /キン
/キン 〈j
〈j ng・j
ng・j n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》
n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》

 {名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
 {動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
 {名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu
{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」
n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

 {動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
 {動}かたくまもる。
{動}かたくまもる。
 「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
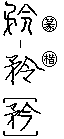 形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
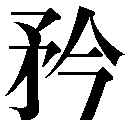 9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》
9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》  キン
キン /ゴン
/ゴン 〈q
〈q n〉/
n〉/ キョウ
キョウ
 /キン
/キン 〈j
〈j ng・j
ng・j n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》
n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》

 {名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
 {動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
 {名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu
{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」
n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

 {動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
 {動}かたくまもる。
{動}かたくまもる。
 「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
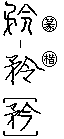 形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
粟 あわ🔗⭐🔉
【粟】
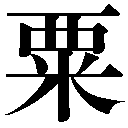 12画 米部
区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE
《音読み》 ゾク
12画 米部
区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE
《音読み》 ゾク /ショク
/ショク /ソク
/ソク 〈s
〈s 〉
《訓読み》 あわ(あは)
《意味》
〉
《訓読み》 あわ(あは)
《意味》
 {名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。
{名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。
 {名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」
{名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」
 {名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕
《解字》
会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。
《単語家族》
縮(小さくちぢむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕
《解字》
会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。
《単語家族》
縮(小さくちぢむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
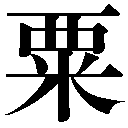 12画 米部
区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE
《音読み》 ゾク
12画 米部
区点=1632 16進=3040 シフトJIS=88BE
《音読み》 ゾク /ショク
/ショク /ソク
/ソク 〈s
〈s 〉
《訓読み》 あわ(あは)
《意味》
〉
《訓読み》 あわ(あは)
《意味》
 {名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。
{名}穀物の総称。稲・きびなどの外皮のついたままの実。
 {名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」
{名}あわ(アハ)。穀物の名。実は黄色で小さくてまるい。畑でつくる。中国北部で産する穀物のうち、もっとも主要なもの。▽小さいものにたとえる。「滄海一粟ソウカイノイチゾク」
 {名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕
《解字》
会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。
《単語家族》
縮(小さくちぢむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}穀物。食糧。また、俸禄ホウロク。「義不食周粟=義トシテ周ノ粟ヲ食マズ」〔→史記〕
《解字》
会意。「西(ばらばらになる)+米」。小さくて、ぱらぱらした穀物をあらわす。
《単語家族》
縮(小さくちぢむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
荅 あわせる🔗⭐🔉
【荅】
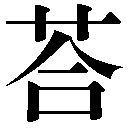 9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ)
9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)
/トウ(トフ) 〈d
〈d ・d
・d 〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
 {名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
 {動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
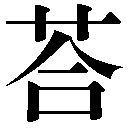 9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ)
9画 艸部
区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7
《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)
/トウ(トフ) 〈d
〈d ・d
・d 〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
〉
《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)
《意味》
 {名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。
 {動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」
 {動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。
《解字》
会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。
蚫 あわび🔗⭐🔉
【蚫】
 11画 虫部
区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A
《音読み》 ホウ(ハウ)
11画 虫部
区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A
《音読み》 ホウ(ハウ) /ビョウ(ベウ)
/ビョウ(ベウ) 《訓読み》 あわび(あはび)
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。
《訓読み》 あわび(あはび)
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。
 11画 虫部
区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A
《音読み》 ホウ(ハウ)
11画 虫部
区点=7359 16進=695B シフトJIS=E57A
《音読み》 ホウ(ハウ) /ビョウ(ベウ)
/ビョウ(ベウ) 《訓読み》 あわび(あはび)
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。
《訓読み》 あわび(あはび)
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の名。食用にする。「鮑魚ホウギョ」とも。〈同義語〉→鮑。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符包ホウ(からでからだをつつむ)」。貝がらで包まれたかい。▽もと、国字。
袷 あわせ🔗⭐🔉
【袷】
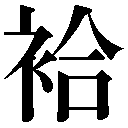 11画 衣部
区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF
《音読み》
11画 衣部
区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF
《音読み》  コウ(カフ)
コウ(カフ) /キョウ(ケフ)
/キョウ(ケフ) 〈ji
〈ji ・qi
・qi 〉/
〉/ キョウ(ケフ)
キョウ(ケフ) /コウ(コフ)
/コウ(コフ) 《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)
《意味》
《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)
《意味》
 {名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」
{名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」

 {名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」
{名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」
 {名}えり。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。
{名}えり。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。
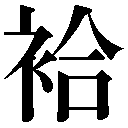 11画 衣部
区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF
《音読み》
11画 衣部
区点=1633 16進=3041 シフトJIS=88BF
《音読み》  コウ(カフ)
コウ(カフ) /キョウ(ケフ)
/キョウ(ケフ) 〈ji
〈ji ・qi
・qi 〉/
〉/ キョウ(ケフ)
キョウ(ケフ) /コウ(コフ)
/コウ(コフ) 《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)
《意味》
《訓読み》 あわせ(あはせ)/つぎ/ひかえ(ひかへ)
《意味》
 {名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」
{名}あわせ(アハセ)。裏地と表地とをあわせた衣。裏のついたきもの。「袷衣コウイ」

 {名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」
{名}つぎ。ひかえ(ヒカヘ)。主に対する副。「袷輅コウロ(ひかえぐるま。副車)」
 {名}えり。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。
{名}えり。
《解字》
会意兼形声。「衣+音符合(あわす)」。
遑 あわただしい🔗⭐🔉
【遑】
 13画
13画  部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク
部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
 {形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢
{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「
テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。
+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。
の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画
13画  部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク
部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
 {形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢
{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「
テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。
+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。
の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遽 あわただしい🔗⭐🔉
【遽】
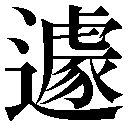 17画
17画  部
区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF
《音読み》 キョ
部
区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF
《音読み》 キョ /ゴ
/ゴ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)
《意味》
〉
《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)
《意味》
 {名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。
{名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。
 {形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕
{形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕
 {動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」
{動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」
 「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、
「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、 を加えたもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
を加えたもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
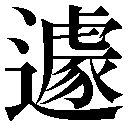 17画
17画  部
区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF
《音読み》 キョ
部
区点=7817 16進=6E31 シフトJIS=E7AF
《音読み》 キョ /ゴ
/ゴ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)
《意味》
〉
《訓読み》 にわか(にはかなり)/あわただしい(あわただし)/おそれる(おそる)
《意味》
 {名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。
{名}馬を使った駅伝。はや馬の使い。▽車によるものを伝デンという。
 {形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕
{形}にわか(ニハカナリ)。あわただしい(アワタダシ)。はげしく急に。ぎくっとしてあわてるさま。「遽契其舟曰=遽ニソノ舟ヲ契ミテ曰ハク」〔→呂覧〕「心遽脚忙=心遽シク脚忙シ」〔柴野邦彦〕
 {動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」
{動}おそれる(オソル)。うろたえる。「骸遽ガイキョ」
 「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、
「何遽ナンゾ・ナンゾニワカニ」とは、「どうして」「なんで」と反問する気持ちをあらわすことば。〈同義語〉何渠ナンゾ。「此何遽不為福乎=コレ何遽福ト為ラザランヤ」〔→淮南子〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キョ)は、はげしく争う、きつくてはやいとの意を含む。遽はそれを音符とし、 を加えたもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
を加えたもの。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
閔 あわれむ🔗⭐🔉
【閔】
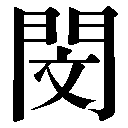 12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン
12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン /ミン
/ミン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
 {動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
 {動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
 {動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
 {動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
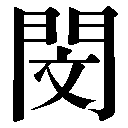 12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン
12画 門部
区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B
《音読み》 ビン /ミン
/ミン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
n〉
《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)
《意味》
 {動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。
 {動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕
 {動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」
 {動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。
《単語家族》
問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
鮑 あわび🔗⭐🔉
鰒 あわび🔗⭐🔉
【鰒】
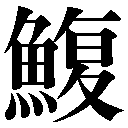 20画 魚部
区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6
《音読み》 フク
20画 魚部
区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6
《音読み》 フク /ブク
/ブク 〈f
〈f 〉
《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の一種。
〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。
《単語家族》
腹(ふくれたはら)と同系。
〉
《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の一種。
〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。
《単語家族》
腹(ふくれたはら)と同系。
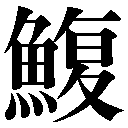 20画 魚部
区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6
《音読み》 フク
20画 魚部
区点=8256 16進=7258 シフトJIS=E9D6
《音読み》 フク /ブク
/ブク 〈f
〈f 〉
《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の一種。
〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。
《単語家族》
腹(ふくれたはら)と同系。
〉
《訓読み》 あわび(あはび)/ふぐ
《意味》
{名}あわび(アハビ)。貝の一種。
〔国〕ふぐ。海にすむ魚の一種。河豚。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音フク)は、ふっくらとふくれたとの基本義をもつ。鰒はそれを音符とし、魚をそえた字。
《単語家族》
腹(ふくれたはら)と同系。
漢字源に「あわ」で始まるの検索結果 1-35。
 13画 力部
区点=5013 16進=522D シフトJIS=99AB
《音読み》 リク
13画 力部
区点=5013 16進=522D シフトJIS=99AB
《音読み》 リク かわいそうだ。あわれだ。「可憐王孫泣路隅=憐レムベシ、王孫ノ路隅ニ泣クヲ」〔
かわいそうだ。あわれだ。「可憐王孫泣路隅=憐レムベシ、王孫ノ路隅ニ泣クヲ」〔 美しくてかわいらしい。「可憐飛燕倚新粧=可憐ノ飛燕新粧ニ倚ル」〔
美しくてかわいらしい。「可憐飛燕倚新粧=可憐ノ飛燕新粧ニ倚ル」〔 13画 心部
区点=5630 16進=583E シフトJIS=9CBC
《音読み》 ビン
13画 心部
区点=5630 16進=583E シフトJIS=9CBC
《音読み》 ビン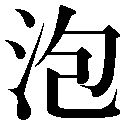 8画 水部 [常用漢字]
区点=4302 16進=4B22 シフトJIS=9641
《常用音訓》ホウ/あわ
《音読み》 ホウ(ハウ)
8画 水部 [常用漢字]
区点=4302 16進=4B22 シフトJIS=9641
《常用音訓》ホウ/あわ
《音読み》 ホウ(ハウ) 16画 魚部
区点=8226 16進=723A シフトJIS=E9B8
《音読み》 ホウ(ハウ)
16画 魚部
区点=8226 16進=723A シフトJIS=E9B8
《音読み》 ホウ(ハウ)