複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (68)
いら・う【借ふ】イラフ🔗⭐🔉
いら・う【借ふ】イラフ
〔自下二〕
「借りる」の古語。(甲斐・駿河などには後世も残存)天武紀下「稲と資財たからとを貸いらへし者」↔貸いらす
かし‐あげ【借上】🔗⭐🔉
かし‐あげ【借上】
鎌倉時代〜室町初期、高利貸をすること。また、その業者。かりあげ。
かり【借り】🔗⭐🔉
かり【借り】
①借りること。また、借りた物。特に、借金。比喩的に、まだ返していない恩や恨み。「助けてもらった―がある」「この―は必ず返す」
②簿記上の借方かりかたの略。
かり‐あげ【借上げ】🔗⭐🔉
かり‐あげ【借上げ】
①政府などが民間から土地や物品を借り受けること。
②江戸時代に、諸藩が財政窮乏のため、家臣に対して知行ちぎょう高や扶持ふち高をへらしたこと。
③⇒かしあげ
かり‐あ・げる【借り上げる】🔗⭐🔉
かり‐あ・げる【借り上げる】
〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)
目上の者が目下の者から金品を借りる。
かり‐いえ【借家】‥イヘ🔗⭐🔉
かり‐いえ【借家】‥イヘ
借りて住む家。しゃくや。
かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ🔗⭐🔉
かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ
借りること、また互いに貸借すること。炭俵「中よくて傍輩合ほうばいあいの―」(野坡)
かり‐い・れる【借り入れる】🔗⭐🔉
かり‐い・れる【借り入れる】
〔他下一〕
借りて自分の方へ取り入れる。「資金を―・れる」
かり‐う・ける【借り受ける】🔗⭐🔉
かり‐う・ける【借り受ける】
〔他下一〕
「借りる」の改まった言い方。借りて受け取る。
かり‐かえ【借換え】‥カヘ🔗⭐🔉
かり‐かえ【借換え】‥カヘ
①新たに借りて、前に借りたものを返却すること。
②新起債をもって既発公社債の償還に充当すること。
⇒かりかえ‐こうさい【借換公債】
かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥🔗⭐🔉
かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥
公債の償還期が来たときに、償還の財源として新たに発行する公債。
⇒かり‐かえ【借換え】
かり‐か・える【借り換える】‥カヘル🔗⭐🔉
かり‐か・える【借り換える】‥カヘル
〔他下一〕
前の借りを返して新たに借りる。
かり‐かし【借り貸し】🔗⭐🔉
かり‐かし【借り貸し】
借りと貸し。かしかり。
かり‐き・る【借り切る】🔗⭐🔉
かり‐き・る【借り切る】
〔他五〕
(個人または団体で)全部を借りる。「全館―・る」「住宅資金を限度いっぱい―・る」
かり‐くだ・す【借り下す】🔗⭐🔉
かり‐くだ・す【借り下す】
〔他四〕
目下の人が目上の人のものを借りる。拝借する。
かり‐けん【借券】🔗⭐🔉
かり‐けん【借券】
金銀財物の借用証書。
かり‐こし【借越】🔗⭐🔉
かり‐こし【借越】
①一定の限度以上に借りること。また、その借りたもの。
②貸してあるものより、借りの方が多いこと。特に、当座預金についていう。
かり‐じ【借字】🔗⭐🔉
かり‐じ【借字】
字義によらず、音または訓の同じものをあてて用いた字。「参議」を「三木」、「めでたく」を「目出度」と書く類。あて字。
かり‐ずまい【借住い】‥ズマヒ🔗⭐🔉
かり‐ずまい【借住い】‥ズマヒ
借家して住むこと。また、その住居。
かり‐たお・す【借り倒す】‥タフス🔗⭐🔉
かり‐たお・す【借り倒す】‥タフス
〔他五〕
借りて返さず、先方に損をかける。「借金を―・す」
かり‐だ・す【借り出す】🔗⭐🔉
かり‐だ・す【借り出す】
〔他五〕
①借りて持ち出す。「図書館から本を―・す」
②借りはじめる。
かり‐ち【借地】🔗⭐🔉
かり‐ち【借地】
借りている土地。しゃくち。
かり‐つぎ【借次ぎ】🔗⭐🔉
かり‐つぎ【借次ぎ】
金銭貸借の周旋。また、その周旋人。
かりっ‐ぱなし【借りっ放し】🔗⭐🔉
かりっ‐ぱなし【借りっ放し】
借りたまま返さずにおくこと。
かり‐て【借り手】🔗⭐🔉
かり‐て【借り手】
金銭・品物などを借りる人。かりぬし。
○借りて来た猫のようかりてきたねこのよう🔗⭐🔉
○借りて来た猫のようかりてきたねこのよう
ふだんと違って非常におとなしくしているさま。
⇒か・りる【借りる】
かり‐とうき【仮登記】
本登記をなすべき実質的または形式的要件が完備しない場合に、将来なされるべき本登記の順位を保全するためになされる登記。
⇒かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】
かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】
金銭債務を返済しない場合に債務者の所有物が債権者に移転する旨を合意し、仮登記をした担保。仮登記担保契約法で規律される。
⇒かり‐とうき【仮登記】
かり‐とうひょう【仮投票】‥ヘウ
投票所で、投票管理者の投票拒否の決定に対し、その決定を受けた選挙人または投票立会人が異議を申し立てた場合に、投票管理者がその選挙人に仮にさせる投票。
かり‐どこ【仮床】
仮に設けた床。
かり‐とじ【仮綴じ】‥トヂ
(→)仮製本に同じ。
かり‐どの【仮殿・権殿】
(→)移殿うつしどのに同じ。
⇒かりどの‐せんぐう【仮殿遷宮】
かりどの‐せんぐう【仮殿遷宮】
「遷宮」参照。
⇒かり‐どの【仮殿・権殿】
かり‐とり【刈取り】
稲・麦や牧草などを刈り取ること。かりいれ。
⇒かりとり‐き【刈取り機】
⇒かりとり‐けっそく‐き【刈取り結束機】
かり‐どり【借り取り】
借りたまま返さずに、自分の物とすること。
かりとり‐き【刈取り機】
稲・麦や牧草などを刈るのに用いる機械。稲・麦類用のリーパー、牧草用のモアーなどの類。
⇒かり‐とり【刈取り】
かりとり‐けっそく‐き【刈取り結束機】
(→)バインダー2に同じ。
⇒かり‐とり【刈取り】
かり‐と・る【刈り取る】
〔他五〕
①稲・麦や牧草などを刈って取り入れる。収穫する。
②刈って取り除く。切って取る。また、比喩的に、悪いものなどを取り除く。平治物語「―・りし鎌田が首の報にや」。「悪の芽を―・る」
かり‐な【仮名】
①(仮の文字の意)かな。↔まな(真名)。
②仮につけておく名。
かり‐な【借名】
他人の名を借りること。また、その名。
かり‐に【仮に】
〔副〕
①一時のまにあわせとして。暫定的に。大唐西域記長寛点「樹陰こかげに仮寝カリニネタリ」。「―付けた名前」
②現実ではないが、もしあったとして。もしも。「―雨が降るとしても」
⇒かりに‐も【仮にも】
カリニ‐はいえん【カリニ肺炎】
(carinii pneumonia)ニューモシスチス‐カリニという原虫の感染による肺炎。未熟児、免疫抑制剤や抗癌剤の使用後あるいはエイズ患者など、抵抗力の低下時に発症し、呼吸困難・チアノーゼなどを起こす。肺胞内滲出しんしゅつ液にまじって卵円形・半月状など種々の形態のカリニ嚢子のうしが見られる。
かりに‐も【仮にも】
〔副〕
①(多く下に否定の語を伴って)どんなことがあっても。決して。いささかでも。「―死ぬなんて口にするな」
②内実はともかく。いやしくも。「―教師たる者のすることか」
⇒かり‐に【仮に】
かり‐にわ【狩場】‥ニハ
かりば。古事記下「―に幸いでますべしと」
かり‐ぬい【仮縫い】‥ヌヒ
①まにあわせに縫っておくこと。
②洋服などの本仕立の前に、体型にあわせて仮に縫うこと。また、それを補正すること。したぬい。
かり‐ぬし【借り主】
借りている人。借用主。↔貸し主
かり‐ね【刈根】
刈った草木の根。和歌で多く「仮寝」にかけていう。千載和歌集恋「難波江の蘆の―の一よゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき」
かり‐ね【仮寝】
仮に寝ること。うたたね。かりぶし。また、旅寝をさすことが多い。かりまくら。かりのやどり。源氏物語夕霧「―の枕結びやはせし」。玉葉集旅「草枕―は同じ夜な夜なのつゆ」
かり‐の‐いけ【雁の池】
(梁の孝王の苑に雁池があったことに基づく)親王の異称。
かり‐の‐いのち【仮の命】
現世のはかない生命。
かり‐の‐うきよ【仮の憂き世】
はかなくつらい現世。仮の世。夫木和歌抄23「つれもなきすがたの池のまこも草―になほ乱れつつ」
かり‐の‐うつつ【仮の現】
(仏説に、現世は仮のものであるというによる)一時的なはかない現世。
かり‐の‐おや【仮の親】
⇒かりおや
かり‐の‐ぎむづけ【仮の義務付け】
義務付け訴訟の提起があった場合に、裁判所が行政庁に対し、仮の救済として仮処分をすべき旨を命ずる決定。
かり‐の‐こ【雁の子】
①雁のひな。また、コは愛称で、雁や鴨などの水鳥の称。万葉集2「とぐら立て飼ひし―巣立ちなば」
②水鳥の卵。水鳥は、カルガモ・アヒル・ガチョウなど諸説ある。蜻蛉日記上「―の見ゆるを、これ十づつ重ぬるわざを」
かり‐の‐ことじ【雁の琴柱】‥ヂ
雁の列を琴柱の並んださまにたとえていう語。夫木和歌抄12「たまづさのかきあはせたるしらべかな―に峰の松風」
かり‐の‐さしとめ【仮の差止め】
差止め訴訟の提起があった場合に、裁判所が行政庁に対し、仮の救済として仮処分をしてはならない旨を命ずる決定。
かり‐の‐ずいじん【仮の随身】
臨時に命じた近衛の随身。仮御随身かりみずいじん。源氏物語葵「大将の御―に殿上のぞうなどのすることは常の事にもあらず」
かり‐の‐たまずさ【雁の玉章】‥ヅサ
(→)「雁の使」に同じ。
かり‐の‐たより【雁の便り】
(→)「雁の使」に同じ。
かり‐の‐つかい【狩の使】‥ツカヒ
平安初期、朝廷の用にあてるため諸国へ鳥獣を狩りに遣わされた使者。伊勢物語「伊勢の国に―に行きけるに」
かり‐の‐つかい【雁の使】‥ツカヒ
[漢書蘇武伝](前漢の蘇武が匈奴に使者として行き久しく囚われた時、蘇武を帰国させるために、「蘇武からの手紙が天子の射止めた雁の脚に結ばれていた」と使者に言わせて交渉したという故事から)消息をもたらす使いの雁。転じて、おとずれ。たより。手紙。消息。雁書がんしょ。万葉集8「九月ながつきのその初―にも思ふ心は聞え来ぬかも」
かり‐の‐つて【雁の伝】
(→)「雁の使」に同じ。
かり‐の‐ふみ【雁の文】
(→)「雁の使」に同じ。
かり‐の‐ま【雁の間】
江戸城内の表座敷の一つ。襖ふすまに、刈田に雁の絵を描く高家衆こうけしゅうおよび譜代大名城主らが登城した時の詰所。等級は柳の間の次。
かり‐の‐まくら【仮の枕】
(→)仮寝かりねに同じ。
かり‐の‐もの【仮の物】
化け物。変化へんげ。源氏物語手習「人の心惑はさむとて出で来たる―にや」
かり‐の‐やど【仮の宿】
①一時のすまい。旅のやどり。堀河百首春「草の枕に行きかへる―にもとまる心ぞ」
②無常な世。現世。かりのやどり。新古今和歌集旅「―に心とむなと思ふばかりぞ」
かり‐の‐よ【仮の世】
無常な現世。はかないこの世。源氏物語幻「―はいづくもつひの常世とこよならぬに」
かり‐ば【狩場・猟場】
狩をする場所。遊猟の場所。かりくら。かりやま。かりにわ。
⇒かりば‐の‐きじ【狩場の雉】
⇒かりば‐の‐とり【狩場の鳥】
ガリバー【Gulliver】
⇒ガリヴァー
かり‐ばか【刈ばか】
稲や草などを刈るのに定めた土地の範囲。または刈り取る量ともいう。万葉集4「秋の田の穂田の―か縁りあはば」
かり‐ばかま【狩袴】
地下じげの狩衣着用の時につけた袴。堂上とうしょう所用の狩衣付属の八幅やのの指貫さしぬきに対し、六幅むのに仕立てたものをいう。
かり‐ばし【仮橋】
①橋の工事中などに、一時的に架ける代りの橋。
②転じて、臨時の出し物。浮世風呂前「先斗町が口づいて大丈夫だといふから、―を出した」
カリパス【callipers】
⇒キャリパス
カリバ‐ダム【Kariba Dam】
アフリカ南部、ザンビア・ジンバブエ国境のザンベジ川中流にあるダム。1959年完成のアーチ式ダムで、堤高128メートル。電力は銅精錬に利用。
かり‐はな【雁鼻】
「雁鼻の沓」の略。
⇒かりはな‐の‐くつ【雁鼻の沓】
かりはな‐の‐くつ【雁鼻の沓】
鼻高履びこうりの先端を切りそいだ形の沓。はなきれぐつ。かりはな。
⇒かり‐はな【雁鼻】
かり‐はなみち【仮花道】
「花道1」参照。
かり‐ばね【刈ばね】
竹や木などを刈り取ってあとに残った株。切り株。万葉集14「信濃路は今のはり道―に足踏ましなむ沓はけ我が背」
かりば‐の‐きじ【狩場の雉】
とても助からない命のたとえ。浄瑠璃、心中天の網島「―の妻ゆゑ我も首しめくくるなわ結び」
⇒かり‐ば【狩場・猟場】
かりば‐の‐とり【狩場の鳥】
鷹狩の語で、キジのこと。
⇒かり‐ば【狩場・猟場】
かり‐はや・す【刈り生やす】
〔他四〕
草木の枝葉を刈りこんで、新たによい枝葉を生じさせる。堀河百首夏「―・すま菰をさへに根こじつるかな」
かり‐ばら【借り腹】
(host mother)不妊夫婦の受精卵を妻以外の女性の子宮に移植して出産してもらうこと。→代理母
かり‐ばらい【仮払い】‥バラヒ
金額が未確定な段階で、暫定的に概算で支払うこと。仮渡し。
かりはらい‐き【刈払い機】‥ハラヒ‥
小形のエンジンで小径の丸鋸やワイヤーを回転させ、雑草などを刈り払うための機械。肩から吊し、振るようにして使う。
かり‐ばり【仮貼り】
①かりにはること。また、そのはったもの。
②表具または日本画を描く際、しわがよらないように紙・絹布を水張りにする時に用いる道具。表面に柿渋を塗った襖ふすまのようなもの。
がり‐はり【がり張り】
我がを張り通すこと。また、そのような性質の人。がむしゃ。「―者」
ガリバルディ【Giuseppe Garibaldi】
イタリアの愛国者。マッツィーニと共に政治結社「青年イタリア」で活躍。1859年、サルデーニャのイタリア統一戦争に参加、翌年千人隊(赤シャツ隊)を率いて進撃、南イタリアの統一に道を開いた。(1807〜1882)
がり‐ばん【がり版】
(ガリは鉄筆で原紙を切る音から)謄写版の俗称。「―刷」
かり‐び【借り火】
煙草を吸う時などに火を借りること。また、その火。
かり‐びし【雁菱】
(→)「かりがねびし」に同じ。
かり‐びと【猟人・狩人】
かりうど。万葉集6「あしひきの山にも野にもみ―さつ矢手挟みさわきたり見ゆ」
カリ‐ひりょう【加里肥料】‥レウ
カリウムを比較的多く含む肥料。草木灰・硫酸カリ・塩化カリの類。
かり‐ふ【刈生】
草などを刈った後に、再び芽の生えること。また、その生え出た所。夫木和歌抄22「しひてこそなほ刈り行かめいはせ野の萩の―は雪深くとも」
カリフ【calif; caliph】
(khalīfah アラビアは後継者・代理者の意)ムハンマドの後継者として、全イスラム教徒の指導者であり、教徒の共同体(ウンマ)の政治的支配者でもあるものの呼称。カリフ制は13世紀半ばに崩壊、称号としてのカリフは1924年まで用いられた。ハリーファ。
カリブー【caribou】
(アメリカ先住民の語から)北アメリカのトナカイ。
カリフォルニア【California】
アメリカ合衆国太平洋岸の州。州都サクラメント。経済規模は合衆国の州のうち最大。農業のほか電子工業・航空宇宙産業が盛ん。加州。→アメリカ合衆国(図)。
⇒カリフォルニア‐こうか‐だいがく【カリフォルニア工科大学】
⇒カリフォルニア‐だいがく【カリフォルニア大学】
⇒カリフォルニア‐はんとう【カリフォルニア半島】
⇒カリフォルニア‐ポピー【California poppy】
カリフォルニア‐こうか‐だいがく【カリフォルニア工科大学】‥クワ‥
(California Institute of Technology)カリフォルニア州パサデナにある私立大学。1891年創設。科学・技術の研究・教育の世界的な中心の一つ。略称、Caltech
⇒カリフォルニア【California】
カリフォルニア‐だいがく【カリフォルニア大学】
(The University of California)カリフォルニア州の州立総合大学群。1855年創立の私立カレッジを68年州立総合大学に改める。バークレー・ロサンゼルス・サンタ‐バーバラなど10キャンパスから成る。UC
⇒カリフォルニア【California】
カリフォルニア‐はんとう【カリフォルニア半島】‥タウ
北アメリカ大陸西岸に南南東に伸び、カリフォルニア湾を抱く半島。面積14万3000平方キロメートル。メキシコ領。アメリカ合衆国のカリフォルニア地方に対して、下カリフォルニア(Lower C.)と称する。
⇒カリフォルニア【California】
カリフォルニア‐ポピー【California poppy】
(→)ハナビシソウ。
⇒カリフォルニア【California】
カリブ‐かい【カリブ海】
(Caribbean Sea)中央アメリカ・西インド諸島・南アメリカ大陸に囲まれる大西洋の付属海。
カリブ海
撮影:小松義夫
 かり‐ぶき【仮葺き】
①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。
②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。
かり‐ふ・く【刈り葺く】
〔他四〕
草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」
かり‐ぶし【仮臥し】
かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」
かり‐ぶしん【仮普請】
一時のまにあわせにする普請。↔本普請
カリプソ【calypso】
西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。
カリフラワー【cauliflower】
キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。
カリフラワー
撮影:関戸 勇
かり‐ぶき【仮葺き】
①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。
②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。
かり‐ふ・く【刈り葺く】
〔他四〕
草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」
かり‐ぶし【仮臥し】
かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」
かり‐ぶしん【仮普請】
一時のまにあわせにする普請。↔本普請
カリプソ【calypso】
西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。
カリフラワー【cauliflower】
キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。
カリフラワー
撮影:関戸 勇
 がり‐べん【我利勉】
(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。
かり‐ほ【刈穂】
刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」
かり‐ほ【仮庵・仮廬】
(カリイホの約)
⇒かりいお
かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥
短く刈り揃えた馬のたてがみ。
かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥
戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。
かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥
①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。
②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。
かり‐ほこ【狩鉾】
狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」
かりぼしきり‐うた【刈干切唄】
宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。
→文献資料[刈干切唄]
かり‐ほ・す【刈り干す】
〔他五〕
草木を刈って日にほす。
カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ
紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。
カリホルニウム【californium】
(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。
かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ
本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。
かり‐まくら【仮枕】
(→)仮寝かりねに同じ。
カリマコス【Kallimachos】
ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。
かり‐また【狩股・雁股】
先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。
⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】
かりまた‐の‐や【狩股の矢】
鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。
⇒かり‐また【狩股・雁股】
カリマンタン【Kalimantan】
ボルネオのインドネシア語名。
かり‐みや【仮宮】
①仮に造った宮殿。
②(→)行宮あんぐうに同じ。
③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。
かり‐むしゃ【駆武者】
かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」
かり‐めんきょ【仮免許】
一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。
かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ
本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。
かり‐も【釭】
車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉
かり‐もがり【殯】
死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」
かり‐もの【借り物】
①人から借りた物。
②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」
⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】
かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ
室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。
⇒かり‐もの【借り物】
かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス
〔他四〕
催促して諸方からかり集める。寄せ集める。
かり‐もり
瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。
かりや【刈谷】
愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。
かり‐や【仮屋】
①仮に造った小屋。
②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。
③産屋うぶや。
④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。
⑤御旅所おたびしょ。
かり‐や【狩矢】
狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。
かりや【狩谷】
姓氏の一つ。
⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
かり‐や【借家】
借りた家。しゃくや。
かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)
⇒かりや【狩谷】
か‐りゃく【下略】
⇒げりゃく(下略)
かりゃく【嘉暦】
[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。
かり‐やく【仮役】
①仮の役目。臨時の職。
②見習役。試補。権官。
が‐りゃく【瓦礫】グワ‥
⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉
かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ
本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。
かり‐やくそく【仮約束】
仮の約束。仮契約。
かり‐やぐら【仮櫓】
(→)代櫓かえやぐらに同じ。
かり‐やす【刈安・青茅】
①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉
②コブナグサの別称。
③刈安染の略。
⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】
かりやす‐ぞめ【刈安染】
カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。
⇒かり‐やす【刈安・青茅】
かり‐やど【仮宿】
かりのやど。かりずまい。
かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ
洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。
かり‐やま【狩山】
①狩場かりば。
②山で鳥獣を狩ること。山狩り。
か‐りゅう【下流】‥リウ
①川の流れのしもの方。かわしも。
②下の地位。下の階級。下層。
か‐りゅう【加硫】‥リウ
〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。
⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】
か‐りゅう【花柳】クワリウ
①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。
②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。
⇒かりゅう‐かい【花柳界】
⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】
⇒かりゅう‐びょう【花柳病】
か‐りゅう【河流】‥リウ
河のながれ。
か‐りゅう【渦流】クワリウ
うずまくながれ。
か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ
①粒。「―状」
②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。
③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。
⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】
⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】
が‐りゅう【我流】‥リウ
自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」
が‐りゅう【画竜】グワ‥
⇒がりょう
が‐りゅう【賀竜】
(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)
かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥
芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ
細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥
加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム
⇒か‐りゅう【加硫】
か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥
ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸
かりゅうど【猟人・狩人】カリウド
⇒かりうど
かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥
遊里。色里。花柳界。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ
(→)顆粒球に同じ。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ
(花柳界で感染する病の意)性病。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゆし
(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。
カリュプソ【Kalypsō】
ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。
カリュブディス【Charybdis】
「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。
か‐りょ【過慮】クワ‥
思いすごし。考え過ぎ。
か‐りょう【下僚】‥レウ
下役したやく。部下の役人。
か‐りょう【火竜】クワ‥
火を負う竜。炎天の形容。
か‐りょう【加療】‥レウ
病気や傷を治療すること。
か‐りょう【佳良】‥リヤウ
よいこと。普通よりまさっていること。
か‐りょう【河梁】‥リヤウ
河にかけた橋。
か‐りょう【科料】クワレウ
①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉
②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料
か‐りょう【家領】‥リヤウ
家に属する土地。家門の領地。
か‐りょう【過料】クワレウ
過失罪科に科する金品。
①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。
②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。
かりょう【訶陵】
ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。
が‐りょう【画料】グワレウ
①絵をかくための材料。画材。
②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。
が‐りょう【画竜】グワ‥
画にかいた竜。↔真竜。
⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】
⇒画竜点睛を欠く
が‐りょう【臥竜】グワ‥
①臥している竜。
②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。
⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】
⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】
が‐りょう【雅量】‥リヤウ
広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」
かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥
江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」
がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥
[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。
⇒が‐りょう【画竜】
がり‐べん【我利勉】
(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。
かり‐ほ【刈穂】
刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」
かり‐ほ【仮庵・仮廬】
(カリイホの約)
⇒かりいお
かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥
短く刈り揃えた馬のたてがみ。
かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥
戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。
かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥
①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。
②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。
かり‐ほこ【狩鉾】
狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」
かりぼしきり‐うた【刈干切唄】
宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。
→文献資料[刈干切唄]
かり‐ほ・す【刈り干す】
〔他五〕
草木を刈って日にほす。
カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ
紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。
カリホルニウム【californium】
(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。
かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ
本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。
かり‐まくら【仮枕】
(→)仮寝かりねに同じ。
カリマコス【Kallimachos】
ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。
かり‐また【狩股・雁股】
先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。
⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】
かりまた‐の‐や【狩股の矢】
鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。
⇒かり‐また【狩股・雁股】
カリマンタン【Kalimantan】
ボルネオのインドネシア語名。
かり‐みや【仮宮】
①仮に造った宮殿。
②(→)行宮あんぐうに同じ。
③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。
かり‐むしゃ【駆武者】
かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」
かり‐めんきょ【仮免許】
一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。
かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ
本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。
かり‐も【釭】
車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉
かり‐もがり【殯】
死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」
かり‐もの【借り物】
①人から借りた物。
②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」
⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】
かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ
室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。
⇒かり‐もの【借り物】
かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス
〔他四〕
催促して諸方からかり集める。寄せ集める。
かり‐もり
瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。
かりや【刈谷】
愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。
かり‐や【仮屋】
①仮に造った小屋。
②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。
③産屋うぶや。
④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。
⑤御旅所おたびしょ。
かり‐や【狩矢】
狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。
かりや【狩谷】
姓氏の一つ。
⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
かり‐や【借家】
借りた家。しゃくや。
かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)
⇒かりや【狩谷】
か‐りゃく【下略】
⇒げりゃく(下略)
かりゃく【嘉暦】
[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。
かり‐やく【仮役】
①仮の役目。臨時の職。
②見習役。試補。権官。
が‐りゃく【瓦礫】グワ‥
⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉
かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ
本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。
かり‐やくそく【仮約束】
仮の約束。仮契約。
かり‐やぐら【仮櫓】
(→)代櫓かえやぐらに同じ。
かり‐やす【刈安・青茅】
①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉
②コブナグサの別称。
③刈安染の略。
⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】
かりやす‐ぞめ【刈安染】
カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。
⇒かり‐やす【刈安・青茅】
かり‐やど【仮宿】
かりのやど。かりずまい。
かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ
洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。
かり‐やま【狩山】
①狩場かりば。
②山で鳥獣を狩ること。山狩り。
か‐りゅう【下流】‥リウ
①川の流れのしもの方。かわしも。
②下の地位。下の階級。下層。
か‐りゅう【加硫】‥リウ
〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。
⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】
か‐りゅう【花柳】クワリウ
①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。
②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。
⇒かりゅう‐かい【花柳界】
⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】
⇒かりゅう‐びょう【花柳病】
か‐りゅう【河流】‥リウ
河のながれ。
か‐りゅう【渦流】クワリウ
うずまくながれ。
か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ
①粒。「―状」
②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。
③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。
⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】
⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】
が‐りゅう【我流】‥リウ
自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」
が‐りゅう【画竜】グワ‥
⇒がりょう
が‐りゅう【賀竜】
(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)
かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥
芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ
細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥
加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム
⇒か‐りゅう【加硫】
か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥
ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸
かりゅうど【猟人・狩人】カリウド
⇒かりうど
かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥
遊里。色里。花柳界。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ
(→)顆粒球に同じ。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ
(花柳界で感染する病の意)性病。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゆし
(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。
カリュプソ【Kalypsō】
ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。
カリュブディス【Charybdis】
「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。
か‐りょ【過慮】クワ‥
思いすごし。考え過ぎ。
か‐りょう【下僚】‥レウ
下役したやく。部下の役人。
か‐りょう【火竜】クワ‥
火を負う竜。炎天の形容。
か‐りょう【加療】‥レウ
病気や傷を治療すること。
か‐りょう【佳良】‥リヤウ
よいこと。普通よりまさっていること。
か‐りょう【河梁】‥リヤウ
河にかけた橋。
か‐りょう【科料】クワレウ
①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉
②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料
か‐りょう【家領】‥リヤウ
家に属する土地。家門の領地。
か‐りょう【過料】クワレウ
過失罪科に科する金品。
①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。
②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。
かりょう【訶陵】
ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。
が‐りょう【画料】グワレウ
①絵をかくための材料。画材。
②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。
が‐りょう【画竜】グワ‥
画にかいた竜。↔真竜。
⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】
⇒画竜点睛を欠く
が‐りょう【臥竜】グワ‥
①臥している竜。
②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。
⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】
⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】
が‐りょう【雅量】‥リヤウ
広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」
かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥
江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」
がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥
[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。
⇒が‐りょう【画竜】
 かり‐ぶき【仮葺き】
①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。
②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。
かり‐ふ・く【刈り葺く】
〔他四〕
草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」
かり‐ぶし【仮臥し】
かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」
かり‐ぶしん【仮普請】
一時のまにあわせにする普請。↔本普請
カリプソ【calypso】
西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。
カリフラワー【cauliflower】
キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。
カリフラワー
撮影:関戸 勇
かり‐ぶき【仮葺き】
①仮に屋根をふくこと。また、その屋根。
②板ぶきのままで、まだ瓦をのせてない屋根。
かり‐ふ・く【刈り葺く】
〔他四〕
草を刈って屋根をふく。万葉集1「秋の野のみ草―・き宿れりし」
かり‐ぶし【仮臥し】
かりね。うたたね。夫木和歌抄34「神垣のいはほの上の―にまろねの足を洗ふみやつこ」
かり‐ぶしん【仮普請】
一時のまにあわせにする普請。↔本普請
カリプソ【calypso】
西インド諸島トリニダード‐トバゴで生まれたポピュラー音楽。諷刺に富む歌と踊りやすい2拍子の演奏が特徴。
カリフラワー【cauliflower】
キャベツの一変種。葉球を結ばず、中心部に白色の蕾つぼみが大きな扁球状にかたまって現れ、これを食用にする。花甘藍はなかんらん。花椰菜はなやさい。花キャベツ。
カリフラワー
撮影:関戸 勇
 がり‐べん【我利勉】
(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。
かり‐ほ【刈穂】
刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」
かり‐ほ【仮庵・仮廬】
(カリイホの約)
⇒かりいお
かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥
短く刈り揃えた馬のたてがみ。
かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥
戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。
かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥
①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。
②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。
かり‐ほこ【狩鉾】
狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」
かりぼしきり‐うた【刈干切唄】
宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。
→文献資料[刈干切唄]
かり‐ほ・す【刈り干す】
〔他五〕
草木を刈って日にほす。
カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ
紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。
カリホルニウム【californium】
(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。
かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ
本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。
かり‐まくら【仮枕】
(→)仮寝かりねに同じ。
カリマコス【Kallimachos】
ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。
かり‐また【狩股・雁股】
先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。
⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】
かりまた‐の‐や【狩股の矢】
鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。
⇒かり‐また【狩股・雁股】
カリマンタン【Kalimantan】
ボルネオのインドネシア語名。
かり‐みや【仮宮】
①仮に造った宮殿。
②(→)行宮あんぐうに同じ。
③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。
かり‐むしゃ【駆武者】
かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」
かり‐めんきょ【仮免許】
一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。
かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ
本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。
かり‐も【釭】
車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉
かり‐もがり【殯】
死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」
かり‐もの【借り物】
①人から借りた物。
②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」
⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】
かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ
室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。
⇒かり‐もの【借り物】
かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス
〔他四〕
催促して諸方からかり集める。寄せ集める。
かり‐もり
瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。
かりや【刈谷】
愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。
かり‐や【仮屋】
①仮に造った小屋。
②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。
③産屋うぶや。
④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。
⑤御旅所おたびしょ。
かり‐や【狩矢】
狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。
かりや【狩谷】
姓氏の一つ。
⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
かり‐や【借家】
借りた家。しゃくや。
かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)
⇒かりや【狩谷】
か‐りゃく【下略】
⇒げりゃく(下略)
かりゃく【嘉暦】
[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。
かり‐やく【仮役】
①仮の役目。臨時の職。
②見習役。試補。権官。
が‐りゃく【瓦礫】グワ‥
⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉
かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ
本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。
かり‐やくそく【仮約束】
仮の約束。仮契約。
かり‐やぐら【仮櫓】
(→)代櫓かえやぐらに同じ。
かり‐やす【刈安・青茅】
①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉
②コブナグサの別称。
③刈安染の略。
⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】
かりやす‐ぞめ【刈安染】
カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。
⇒かり‐やす【刈安・青茅】
かり‐やど【仮宿】
かりのやど。かりずまい。
かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ
洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。
かり‐やま【狩山】
①狩場かりば。
②山で鳥獣を狩ること。山狩り。
か‐りゅう【下流】‥リウ
①川の流れのしもの方。かわしも。
②下の地位。下の階級。下層。
か‐りゅう【加硫】‥リウ
〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。
⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】
か‐りゅう【花柳】クワリウ
①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。
②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。
⇒かりゅう‐かい【花柳界】
⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】
⇒かりゅう‐びょう【花柳病】
か‐りゅう【河流】‥リウ
河のながれ。
か‐りゅう【渦流】クワリウ
うずまくながれ。
か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ
①粒。「―状」
②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。
③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。
⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】
⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】
が‐りゅう【我流】‥リウ
自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」
が‐りゅう【画竜】グワ‥
⇒がりょう
が‐りゅう【賀竜】
(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)
かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥
芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ
細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥
加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム
⇒か‐りゅう【加硫】
か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥
ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸
かりゅうど【猟人・狩人】カリウド
⇒かりうど
かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥
遊里。色里。花柳界。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ
(→)顆粒球に同じ。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ
(花柳界で感染する病の意)性病。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゆし
(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。
カリュプソ【Kalypsō】
ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。
カリュブディス【Charybdis】
「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。
か‐りょ【過慮】クワ‥
思いすごし。考え過ぎ。
か‐りょう【下僚】‥レウ
下役したやく。部下の役人。
か‐りょう【火竜】クワ‥
火を負う竜。炎天の形容。
か‐りょう【加療】‥レウ
病気や傷を治療すること。
か‐りょう【佳良】‥リヤウ
よいこと。普通よりまさっていること。
か‐りょう【河梁】‥リヤウ
河にかけた橋。
か‐りょう【科料】クワレウ
①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉
②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料
か‐りょう【家領】‥リヤウ
家に属する土地。家門の領地。
か‐りょう【過料】クワレウ
過失罪科に科する金品。
①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。
②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。
かりょう【訶陵】
ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。
が‐りょう【画料】グワレウ
①絵をかくための材料。画材。
②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。
が‐りょう【画竜】グワ‥
画にかいた竜。↔真竜。
⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】
⇒画竜点睛を欠く
が‐りょう【臥竜】グワ‥
①臥している竜。
②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。
⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】
⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】
が‐りょう【雅量】‥リヤウ
広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」
かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥
江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」
がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥
[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。
⇒が‐りょう【画竜】
がり‐べん【我利勉】
(「我利」は当て字)他のことには全く目も向けず、ひたすら勉強だけをすること。多く、あざけりの気持をこめていう。
かり‐ほ【刈穂】
刈った稲の穂。夫木和歌抄20「積める―を見るがうれしさ」
かり‐ほ【仮庵・仮廬】
(カリイホの約)
⇒かりいお
かり‐ぼうし【刈法師】‥ボフ‥
短く刈り揃えた馬のたてがみ。
かり‐ほうたいしょ【仮繃帯所】‥ハウ‥
戦場で負傷者に応急手当を施す所で、戦線のまぢかな後方に設けるもの。
かり‐ほうめん【仮放免】‥ハウ‥
①容疑者などの情状その他を考慮して、一応放免すること。
②中世の糾問手続における法定証拠主義のもとで、有罪の証拠が十分そろわないとき仮に放免し、証拠が発見されたとき再び公訴の提起を許す制度。1848年までドイツに存続。
かり‐ほこ【狩鉾】
狩猟用のほこ。浄瑠璃、国性爺合戦「―数鑓かずやり手にあたるを幸ひに投げつけ」
かりぼしきり‐うた【刈干切唄】
宮崎県の民謡。高千穂町など西臼杵地方の萱を刈り取るときの作業唄。萱刈節。
→文献資料[刈干切唄]
かり‐ほ・す【刈り干す】
〔他五〕
草木を刈って日にほす。
カリポス‐ほう【カリポス法】‥ハフ
紀元前4世紀、ギリシアの天文学者カリポス(Kallippos)が考案したという太陰暦法。メトン期の4倍から1日を減じた期間(2万7759日)を940月(76年)とし、これを1期とする。閏月のおき方はメトンと同じ。この暦法によれば1年の長さは平均365.25日となる。古代中国でもこれに相当する四分法が行われていた。
カリホルニウム【californium】
(カリフォルニア大学で発見されたことに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Cf 原子番号98。1950年、キュリウムにアルファ線を当てて、人工的につくられた。
かり‐まいそう【仮埋葬】‥サウ
本葬を営めない場合に、死体を一時仮に埋めておくこと。かりうめ。
かり‐まくら【仮枕】
(→)仮寝かりねに同じ。
カリマコス【Kallimachos】
ヘレニズム期ギリシアの学者詩人。前4世紀末〜前3世紀半ばの人。アレクサンドリア図書館の文献目録を完成。叙事詩・抒情詩・讃歌・縁起譚などの作品を遺す。
かり‐また【狩股・雁股】
先が叉またの形に開き、その内側に刃のある鏃やじり。また、それを付けた矢。太平記12「流鏑にすげたる―を抜て」→鏃(図)。
⇒かりまた‐の‐や【狩股の矢】
かりまた‐の‐や【狩股の矢】
鏑かぶらをつけず狩股の鏃やじりだけをつけた矢。
⇒かり‐また【狩股・雁股】
カリマンタン【Kalimantan】
ボルネオのインドネシア語名。
かり‐みや【仮宮】
①仮に造った宮殿。
②(→)行宮あんぐうに同じ。
③神輿渡御の時の御旅所おたびしょ。
かり‐むしゃ【駆武者】
かり集めた武者。平治物語(金刀比羅本)「是は諸国の―どもにて候ふが」
かり‐めんきょ【仮免許】
一定の資格を得た者が、免許の確認手続がすむまで、仮に与えられる免許。仮免。
かり‐めんじょう【仮免状】‥ジヤウ
本免状を渡すまで、仮に渡しておく免状。
かり‐も【釭】
車の轂こしきの孔にはめた鉄の管。かも。〈倭名類聚鈔11〉
かり‐もがり【殯】
死人を埋葬する前、しばらくその死骸を棺に入れて安置すること。もがり。今昔物語集3「仏、涅槃ねはんに入り給ひぬれば、阿難、仏の御身を―し奉りて」
かり‐もの【借り物】
①人から借りた物。
②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」
⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】
かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】‥ギヤウ
室町時代、将軍を自邸に迎えるに当たり、諸大名が臨時に任命して、茶器・屏風びょうぶなど当日入用の器具を借り集めることをつかさどらせた役。
⇒かり‐もの【借り物】
かり‐もよお・す【駆り催す】‥モヨホス
〔他四〕
催促して諸方からかり集める。寄せ集める。
かり‐もり
瓜のすえなり。(和訓栞)また、白瓜しろうりともいう。
かりや【刈谷】
愛知県中央部の市。もと水野氏の城下町。自動車産業を中心とする機械工業都市。人口14万2千。
かり‐や【仮屋】
①仮に造った小屋。
②鳥取県で、雁木造がんぎづくりをいう。
③産屋うぶや。
④月経の時に入っている仮小屋。他家たや。
⑤御旅所おたびしょ。
かり‐や【狩矢】
狩に用いる矢。多くは鏑かぶらのついた狩股かりまたを用いる。野矢。
かりや【狩谷】
姓氏の一つ。
⇒かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
かり‐や【借家】
借りた家。しゃくや。
かりや‐えきさい【狩谷棭斎】
江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。和漢の古典の本文考証・注解、また金石文の蒐集に力を注ぐ。著「箋注倭名類聚抄」「日本霊異記攷証」「古京遺文」「本朝度量権衡攷」など。(1775〜1835)
⇒かりや【狩谷】
か‐りゃく【下略】
⇒げりゃく(下略)
かりゃく【嘉暦】
[旧唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。正中3年4月26日(1326年5月28日)改元、嘉暦4年8月29日(1329年9月22日)元徳に改元。
かり‐やく【仮役】
①仮の役目。臨時の職。
②見習役。試補。権官。
が‐りゃく【瓦礫】グワ‥
⇒がれき。〈伊呂波字類抄〉
かり‐やくじょう【仮約定】‥ヂヤウ
本約定を締結するまで、仮に結ぶ約束。
かり‐やくそく【仮約束】
仮の約束。仮契約。
かり‐やぐら【仮櫓】
(→)代櫓かえやぐらに同じ。
かり‐やす【刈安・青茅】
①イネ科の多年草。山地・草原に自生。細い茎が直立し、高さ約1メートル。葉は線形で、カヤに似、秋、花穂を出す。穂は3〜5分岐。茎・葉は乾して黄色の染料、また、藍と併用し緑色染料を製する。ヤマカリヤス。オウミカリヤス。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔14〉
②コブナグサの別称。
③刈安染の略。
⇒かりやす‐ぞめ【刈安染】
かりやす‐ぞめ【刈安染】
カリヤスで染めること。また、そのもの。かりやす。
⇒かり‐やす【刈安・青茅】
かり‐やど【仮宿】
かりのやど。かりずまい。
かり‐やなぐい【狩胡簶】‥ヤナグヒ
洛外の野行幸の供奉ぐぶや遊猟の時、狩猟用の野矢を盛って帯びるやなぐい。
かり‐やま【狩山】
①狩場かりば。
②山で鳥獣を狩ること。山狩り。
か‐りゅう【下流】‥リウ
①川の流れのしもの方。かわしも。
②下の地位。下の階級。下層。
か‐りゅう【加硫】‥リウ
〔化〕(vulcanization)生ゴムに硫黄をまぜて加熱し、目的に応じた弾性をもつゴムを製する操作。より一般的に高分子鎖を架橋する反応をいう。硫化。和硫。
⇒かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】
か‐りゅう【花柳】クワリウ
①[王勃、詩]紅花と緑柳。美しさの形容。
②[李白、詩]遊里。いろざと。また、芸者や遊女。
⇒かりゅう‐かい【花柳界】
⇒かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】
⇒かりゅう‐びょう【花柳病】
か‐りゅう【河流】‥リウ
河のながれ。
か‐りゅう【渦流】クワリウ
うずまくながれ。
か‐りゅう【顆粒・粿粒】クワリフ
①粒。「―状」
②〔生〕細胞内の微小な粒子の総称。
③〔医〕トラコーマにかかった時、結膜に生じる水泡状の粒。
⇒かりゅう‐きゅう【顆粒球】
⇒かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】
が‐りゅう【我流】‥リウ
自分勝手の流儀。自分独自のやりかた。自己流。「―の書き方」
が‐りゅう【画竜】グワ‥
⇒がりょう
が‐りゅう【賀竜】
(He Long)中国の軍人。湖南桑植の人。北伐に参加、1927年、南昌蜂起に加わり共産党に入党。紅軍の幹部として活躍し、55年元帥、また国務院副総理となる。文化大革命中迫害され没。82年名誉回復。(1896〜1969)
かりゅう‐かい【花柳界】クワリウ‥
芸娼妓の社会。花柳の巷。田山花袋、東京の三十年「紅葉が柳橋あたりの―に遊んだことは」
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐きゅう【顆粒球】クワリフキウ
細胞質内に多数の顆粒を含む多核白血球。顆粒の染色性により好中球・好酸球・好塩基球に分ける。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】‥リウ‥
加硫操作を加えたゴム。含硫ゴム。→弾性ゴム
⇒か‐りゅう【加硫】
か‐りゅうさん【過硫酸】クワリウ‥
ペルオキソ二硫酸の俗称。→ペルオキソ硫酸
かりゅうど【猟人・狩人】カリウド
⇒かりうど
かりゅう‐の‐ちまた【花柳の巷】クワリウ‥
遊里。色里。花柳界。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゅう‐はっけっきゅう【顆粒白血球】クワリフハク‥キウ
(→)顆粒球に同じ。
⇒か‐りゅう【顆粒・粿粒】
かりゅう‐びょう【花柳病】クワリウビヤウ
(花柳界で感染する病の意)性病。
⇒か‐りゅう【花柳】
かりゆし
(嘉例吉の意)沖縄で、めでたいことや幸せをいう語。
カリュプソ【Kalypsō】
ギリシア神話で海のニンフ。トロイアから帰国するオデュッセウスを引き止め同棲した。
カリュブディス【Charybdis】
「オデュッセイア」に現れる、海の渦巻を擬人化した怪物。1日に3度船を呑み込み吐き出した。
か‐りょ【過慮】クワ‥
思いすごし。考え過ぎ。
か‐りょう【下僚】‥レウ
下役したやく。部下の役人。
か‐りょう【火竜】クワ‥
火を負う竜。炎天の形容。
か‐りょう【加療】‥レウ
病気や傷を治療すること。
か‐りょう【佳良】‥リヤウ
よいこと。普通よりまさっていること。
か‐りょう【河梁】‥リヤウ
河にかけた橋。
か‐りょう【科料】クワレウ
①罪科をあがなうための金品。〈運歩色葉集〉
②刑法の規定する主刑の一種で、軽微な犯罪に科する財産刑。現行刑法では千円以上1万円未満。とがりょう。→罰金→過料
か‐りょう【家領】‥リヤウ
家に属する土地。家門の領地。
か‐りょう【過料】クワレウ
過失罪科に科する金品。
①江戸時代、庶民の刑として過失の償いに出させた金銭。
②現刑法で、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰としての過料がある。科料と違って刑法上の刑罰ではない。あやまちりょう。
かりょう【訶陵】
ジャワ島のシャイレンドラ朝のこと。通典つでん・唐書などに見える。
が‐りょう【画料】グワレウ
①絵をかくための材料。画材。
②絵をかいてもらったことに対する謝礼。画稿料。
が‐りょう【画竜】グワ‥
画にかいた竜。↔真竜。
⇒がりょう‐てんせい【画竜点睛】
⇒画竜点睛を欠く
が‐りょう【臥竜】グワ‥
①臥している竜。
②[三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明なる者は臥竜也」]野やに隠れて世に知られていない大人物。
⇒がりょう‐ばい【臥竜梅】
⇒がりょう‐ほうすう【臥竜鳳雛】
が‐りょう【雅量】‥リヤウ
広く、おおらかな度量。「敵の健闘をたたえる―がほしい」「―を示す」
かり‐ようし【仮養子】‥ヤウ‥
江戸時代、武士が公用で遠国に旅する時、道中の不慮の変に備え、あらかじめ幕府に願い出た仮の養子。鶉衣「仮親―も勝手次第にて」
がりょう‐てんせい【画竜点睛】グワ‥
[歴代名画記7](梁の画家張僧繇ちょうそうようが金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛ひとみを書きこんだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体がひきたつたとえ。
⇒が‐りょう【画竜】
かり‐どり【借り取り】🔗⭐🔉
かり‐どり【借り取り】
借りたまま返さずに、自分の物とすること。
かり‐ぬし【借り主】🔗⭐🔉
かり‐ぬし【借り主】
借りている人。借用主。↔貸し主
かり‐ばら【借り腹】🔗⭐🔉
かり‐ばら【借り腹】
(host mother)不妊夫婦の受精卵を妻以外の女性の子宮に移植して出産してもらうこと。→代理母
かり‐び【借り火】🔗⭐🔉
かり‐び【借り火】
煙草を吸う時などに火を借りること。また、その火。
かり‐もの【借り物】🔗⭐🔉
かり‐もの【借り物】
①人から借りた物。
②形だけ取り入れ、まだ自分のものになっていない、考えや意見など。「―の知識」
⇒かりもの‐ぶぎょう【借物奉行】
かり‐や【借家】🔗⭐🔉
かり‐や【借家】
借りた家。しゃくや。
か・りる【借りる】🔗⭐🔉
か・りる【借りる】
〔他上一〕
(近世後期ごろから江戸で使われ始めた語形。古くは四段活用)
①他人のものを、あとで返す約束で使う。借用する。浮世風呂3「内で給金を―・りようと言へば」。「部屋を―・りる」
②仮に他のものをある目的に使う。代用する。「この席を―・りてお礼を申し上げる」「文字を―・りて音声をうつす」
③他の助力・協力を受ける。「知恵を―・りる」「猫の手も―・りたい忙しさ」
→借る
⇒借りて来た猫のよう
⇒借りる八合済す一升
○借りる八合済す一升かりるはちごうなすいっしょう🔗⭐🔉
○借りる八合済す一升かりるはちごうなすいっしょう
(「済す」は返済する意)8合借りたら1升(10合)にして返すように、人にものを返すときにはお礼をせよということ。
⇒か・りる【借りる】
ガリレイ【Galileo Galilei】
イタリアの天文学者・物理学者・哲学者。近代科学の父。力学上の諸法則の発見、太陽黒点の発見、望遠鏡による天体の研究など、功績が多い。また、アリストテレスの自然哲学を否定し、分析と統合との経験的・実証的方法を用いる近代科学の方法論の端緒を開く。コペルニクスの地動説を是認したため、宗教裁判に付された。著「新科学対話」「天文対話」など。(1564〜1642)
⇒ガリレイしき‐ぼうえんきょう【ガリレイ式望遠鏡】
⇒ガリレイ‐の‐そうたいせいげんり【ガリレイの相対性原理】
⇒ガリレイ‐へんかん【ガリレイ変換】
ガリレイしき‐ぼうえんきょう【ガリレイ式望遠鏡】‥バウヱンキヤウ
対物レンズに凸レンズを、接眼レンズに凹レンズを用いた望遠鏡。1609年ガリレイが製作し、木星の衛星や土星の環などを発見。正立像が得られる。オランダ式望遠鏡。→木星。
⇒ガリレイ【Galileo Galilei】
ガリレイ‐の‐そうたいせいげんり【ガリレイの相対性原理】‥サウ‥
一つの慣性系で成り立つニュートンの運動法則が、その慣性系に対して等速度で平行移動している他の座標系でも同じ形で成り立つという原理。
⇒ガリレイ【Galileo Galilei】
ガリレイ‐へんかん【ガリレイ変換】‥クワン
慣性系に属する二つの座標系が互いに等速運動をしているとき、それらの座標系を結びつける変換。
⇒ガリレイ【Galileo Galilei】
ガリレオ【Galileo】
⇒ガリレイ
かりろく【訶梨勒】
(梵語harītakī)
①シクンシ科の高木。インド・インドシナ地方に産し、高さ約30メートル。葉は長楕円形、花は白色で穂状。初秋、乾果を結ぶ。材は器具用、果実は薬用にする。
②室町時代に座敷の柱飾りに用いた具。象牙・銅・石でカリロクの果実に似た卵形に造り、長さ20センチメートル、径8センチメートル。美しい白緞子・白綾の袋に入れて緋色の緒で吊る。もとカリロクの果実が眼病・風邪・便通に有効とされ邪気を払う具として柱に掛けたことに始まる。
かり‐わく【仮枠】
①コンクリートを一定の型に固まらせるために用いる板や支え。型枠。
②アーチを作る時に一時仮に受ける枠。
③日本画用の絹・絖ぬめを張る木製の枠。
かり‐わけ【刈分け】
刈分小作の略。日葡辞書「カリワケニスル」
⇒かりわけ‐こさく【刈分け小作】
かりわけ‐こさく【刈分け小作】
小作料の額を予め一定せず、毎年その小作地の収穫物を一定の割合で、現物のまま、地主・小作人間に分配する小作関係。分作ぶつくり。
⇒かり‐わけ【刈分け】
かり‐わたし【仮渡し】
①(→)「仮払い」に同じ。
②短期の清算取引で、売方が買方より少なく、渡株不足の場合、代行者が株を立て替えて渡すこと。代渡だいわたし。
か‐りん【下臨】
①見おろすこと。
②貴人が身分低い者の所に尋ねて行くこと。
か‐りん【火輪】クワ‥
①火の輪のように見えるもの。
②太陽。日輪。
③〔仏〕五輪の一種。
⇒かりん‐しゃ【火輪車】
⇒かりん‐せん【火輪船】
か‐りん【花櫚】クワ‥
マメ科の高木。高さ40メートルに達し、東南アジアに分布。材は美しく、花櫚材として細工物・建具などに重用。インド紫檀。
か‐りん【榠樝】クワ‥
(「花梨」とも書く)
①バラ科の落葉高木。中国大陸の原産。古く日本に渡来した。高さ約6メートル。周囲2メートルに及ぶ。樹皮は毎年剥脱し、幹に青褐色の雲紋をあらわす。春の末、枝端に淡紅色5弁の花を開く。果実は黄色となり、芳香は強いが全体が木化して生食はできない。カラナシ。キボケ。
かりん
 カリン(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
カリン(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 カリン(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
カリン(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ②マルメロの別称。
⇒かりん‐あたま【花梨頭】
が‐りん【芽鱗】
冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。
かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥
カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。
⇒か‐りん【榠樝】
カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】
古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯
②マルメロの別称。
⇒かりん‐あたま【花梨頭】
が‐りん【芽鱗】
冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。
かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥
カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。
⇒か‐りん【榠樝】
カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】
古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯 伽国かつりょうがこく。
かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ
リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。
かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥
汽車の旧称。
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐せん【火輪船】クワ‥
汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ
古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。
花林糖
撮影:関戸 勇
伽国かつりょうがこく。
かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ
リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。
かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥
汽車の旧称。
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐せん【火輪船】クワ‥
汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ
古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。
花林糖
撮影:関戸 勇
 かる【軽】
奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。
か・る【上る】
〔自他四〕
音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり
か・る【刈る・苅る】
〔他五〕
①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」
②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」
か・る【狩る・猟る】
〔他五〕
①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」
②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」
③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」
か・る【借る】
〔他五〕
(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)
①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」
②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」
③他の助力・協力を受ける。
④(遊里語)
㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」
㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」
⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔
か・る【涸る・枯る・嗄る】
〔自下二〕
⇒かれる(下一)
か・る【駆る・駈る】
〔他五〕
①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」
②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」
③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」
か・る【離る】
〔自下二〕
(「か(涸・枯)れる」と同源)
①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」
②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」
かる【着る】
(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」
ガル【gal】
(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal
が・る
〔接尾〕
形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。
①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」
②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」
か‐るい【家累】
①家族または家事上のわずらい。
②一家の係累。家族。
かる・い【軽い】
〔形〕[文]かる・し(ク)
①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」
②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」
③動きが軽快である。「足取りが―・い」
④軽率である。「口が―・い」
⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」
⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」
⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」
↔重い
かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ
長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。
軽井沢 塩沢湖と浅間山
撮影:佐藤 尚
かる【軽】
奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。
か・る【上る】
〔自他四〕
音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり
か・る【刈る・苅る】
〔他五〕
①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」
②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」
か・る【狩る・猟る】
〔他五〕
①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」
②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」
③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」
か・る【借る】
〔他五〕
(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)
①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」
②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」
③他の助力・協力を受ける。
④(遊里語)
㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」
㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」
⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔
か・る【涸る・枯る・嗄る】
〔自下二〕
⇒かれる(下一)
か・る【駆る・駈る】
〔他五〕
①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」
②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」
③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」
か・る【離る】
〔自下二〕
(「か(涸・枯)れる」と同源)
①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」
②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」
かる【着る】
(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」
ガル【gal】
(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal
が・る
〔接尾〕
形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。
①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」
②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」
か‐るい【家累】
①家族または家事上のわずらい。
②一家の係累。家族。
かる・い【軽い】
〔形〕[文]かる・し(ク)
①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」
②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」
③動きが軽快である。「足取りが―・い」
④軽率である。「口が―・い」
⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」
⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」
⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」
↔重い
かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ
長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。
軽井沢 塩沢湖と浅間山
撮影:佐藤 尚
 かる‐いし【軽石】
火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」
軽石
撮影:関戸 勇
かる‐いし【軽石】
火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」
軽石
撮影:関戸 勇
 かる・うカルフ
〔他四〕
(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」
ガルヴァーニ【Luigi Galvani】
イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)
カルヴァン【Jean Calvin】
フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)
⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。
⇒カルヴァン【Jean Calvin】
カルヴィーノ【Italo Calvino】
イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)
カルヴィニズム【Calvinism】
(→)カルヴァン主義に同じ。
カルヴィン【J. Calvin】
⇒カルヴァン
カルヴィン【Melvin Calvin】
アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)
⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】
カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥
光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。
⇒カルヴィン【Melvin Calvin】
かる‐うす【唐臼】
カラウスの転。
カルーソー【Enrico Caruso】
イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)
カルーソー
提供:毎日新聞社
かる・うカルフ
〔他四〕
(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」
ガルヴァーニ【Luigi Galvani】
イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)
カルヴァン【Jean Calvin】
フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)
⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。
⇒カルヴァン【Jean Calvin】
カルヴィーノ【Italo Calvino】
イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)
カルヴィニズム【Calvinism】
(→)カルヴァン主義に同じ。
カルヴィン【J. Calvin】
⇒カルヴァン
カルヴィン【Melvin Calvin】
アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)
⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】
カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥
光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。
⇒カルヴィン【Melvin Calvin】
かる‐うす【唐臼】
カラウスの転。
カルーソー【Enrico Caruso】
イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)
カルーソー
提供:毎日新聞社
 ガルーダ【Garuḍa 梵】
⇒ガルダ
かるか
(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。
ガルーダ【Garuḍa 梵】
⇒ガルダ
かるか
(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。 杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」
カルカッタ【Calcutta】
コルカタの旧称。
かる‐がも【軽鴨】
カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。
カルガモ
撮影:小宮輝之
杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」
カルカッタ【Calcutta】
コルカタの旧称。
かる‐がも【軽鴨】
カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。
カルガモ
撮影:小宮輝之
 かる‐かや【刈茅・刈草】
屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」
⇒かるかや‐の【刈茅の】
かる‐かや【刈萱】
①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」
かるかや
かる‐かや【刈茅・刈草】
屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」
⇒かるかや‐の【刈茅の】
かる‐かや【刈萱】
①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」
かるかや
 ②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉
⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】
かるかや【苅萱】
苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。
⇒かるかや‐どう【苅萱堂】
⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】
⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫
②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉
⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】
かるかや【苅萱】
苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。
⇒かるかや‐どう【苅萱堂】
⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】
⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】
かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ
刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。
⇒かる‐かや【刈萱】
かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ
苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥
石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。
⇒かるかや【苅萱】
かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫
】
かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ
刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。
⇒かる‐かや【刈萱】
かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ
苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥
石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。
⇒かるかや【苅萱】
かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】‥ダウ‥イヘ‥
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐の【刈茅の】
〔枕〕
「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。
⇒かる‐かや【刈茅・刈草】
かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥
〔接続〕
(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉
カルガリー【Calgary】
カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。
かる‐がる【軽軽】
軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」
かるがる‐し・い【軽軽しい】
〔形〕[文]かるがる・し(シク)
①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」
②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」
③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい
かる‐かん【軽羹】
すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。
軽羹
撮影:関戸 勇
】‥ダウ‥イヘ‥
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐の【刈茅の】
〔枕〕
「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。
⇒かる‐かや【刈茅・刈草】
かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥
〔接続〕
(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉
カルガリー【Calgary】
カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。
かる‐がる【軽軽】
軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」
かるがる‐し・い【軽軽しい】
〔形〕[文]かるがる・し(シク)
①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」
②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」
③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい
かる‐かん【軽羹】
すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。
軽羹
撮影:関戸 勇
 ガルガンチュア【Gargantua】
ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。
カルキ【kalk オランダ】
①石灰。
②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」
⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】
カルキ‐ながし【カルキ流し】
石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。
⇒カルキ【kalk オランダ】
カルク
(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。
カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】
(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩
かる‐くち【軽口】
①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」
②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。
③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」
④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。
⇒かるくち‐だて【軽口立て】
⇒かるくち‐ばなし【軽口話】
かるくち‐だて【軽口立て】
得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」
⇒かる‐くち【軽口】
かるくち‐ばなし【軽口話】
軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。
⇒かる‐くち【軽口】
カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥
(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。
カルケミッシュ【Carchemish】
トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。
かる‐こ【軽子】
①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。
②江戸深川の遊里の仲居女。
⇒かるこ‐ちん【軽子賃】
かる‐こ【軽籠】
縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。
カルコ【Francis Carco】
フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)
カルコゲン【chalcogen】
(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。
かるこ‐ちん【軽子賃】
(→)軽子1を使役して与える賃銭。
⇒かる‐こ【軽子】
カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】
江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。
カルサン【calção ポルトガル・軽衫】
袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)
軽衫
ガルガンチュア【Gargantua】
ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。
カルキ【kalk オランダ】
①石灰。
②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」
⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】
カルキ‐ながし【カルキ流し】
石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。
⇒カルキ【kalk オランダ】
カルク
(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。
カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】
(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩
かる‐くち【軽口】
①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」
②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。
③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」
④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。
⇒かるくち‐だて【軽口立て】
⇒かるくち‐ばなし【軽口話】
かるくち‐だて【軽口立て】
得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」
⇒かる‐くち【軽口】
かるくち‐ばなし【軽口話】
軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。
⇒かる‐くち【軽口】
カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥
(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。
カルケミッシュ【Carchemish】
トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。
かる‐こ【軽子】
①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。
②江戸深川の遊里の仲居女。
⇒かるこ‐ちん【軽子賃】
かる‐こ【軽籠】
縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。
カルコ【Francis Carco】
フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)
カルコゲン【chalcogen】
(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。
かるこ‐ちん【軽子賃】
(→)軽子1を使役して与える賃銭。
⇒かる‐こ【軽子】
カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】
江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。
カルサン【calção ポルトガル・軽衫】
袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)
軽衫
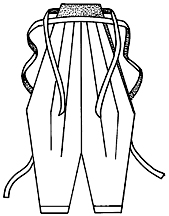 軽衫(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
軽衫(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 かる・し【軽し】
〔形ク〕
⇒かるい
ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】
コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)
ガルシア‐マルケス
提供:ullstein bild/APL
かる・し【軽し】
〔形ク〕
⇒かるい
ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】
コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)
ガルシア‐マルケス
提供:ullstein bild/APL
 ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】
スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)
カルシウム【calcium】
(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。
⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素
⇒カルシウム【calcium】
カルシトニン【calcitonin】
甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。
カルシフェロール【calciferol】
ビタミンD2・D3のこと。
ガルシン【Vsevolod M. Garshin】
ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)
カルス【callus】
〔生〕
①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。
②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。
③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。
カルスト‐ちけい【カルスト地形】
(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。
カルセオラリア【Calceolaria ラテン】
ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。
カルセオラリア
提供:OPO
ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】
スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)
カルシウム【calcium】
(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。
⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素
⇒カルシウム【calcium】
カルシトニン【calcitonin】
甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。
カルシフェロール【calciferol】
ビタミンD2・D3のこと。
ガルシン【Vsevolod M. Garshin】
ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)
カルス【callus】
〔生〕
①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。
②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。
③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。
カルスト‐ちけい【カルスト地形】
(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。
カルセオラリア【Calceolaria ラテン】
ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。
カルセオラリア
提供:OPO
 ガルソン【garçon フランス】
⇒ギャルソン
カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。
⇒カルタ‐かい【カルタ会】
⇒カルタ‐とり【カルタ取り】
⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】
⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】
ガルダ【Garuḍa 梵】
ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。
カルダーノ【Girolamo Cardano】
イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)
かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】
(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。
カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ
カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタゴ【Carthago】
アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。
カルタゴの遺跡
撮影:田沼武能
ガルソン【garçon フランス】
⇒ギャルソン
カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。
⇒カルタ‐かい【カルタ会】
⇒カルタ‐とり【カルタ取り】
⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】
⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】
ガルダ【Garuḍa 梵】
ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。
カルダーノ【Girolamo Cardano】
イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)
かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】
(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。
カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ
カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタゴ【Carthago】
アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。
カルタゴの遺跡
撮影:田沼武能
 カルタ‐とり【カルタ取り】
カルタを取る遊び。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐ばこ【骨牌函】
①カルタを入れる箱。
②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐むすび【骨牌結び】
帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」
骨牌結び
カルタ‐とり【カルタ取り】
カルタを取る遊び。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐ばこ【骨牌函】
①カルタを入れる箱。
②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐むすび【骨牌結び】
帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」
骨牌結び
 ⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルダモン【cardamon】
〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。
カルタン【Elie Cartan】
フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)
ガルダン【噶爾丹・Galdan】
ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルダモン【cardamon】
〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。
カルタン【Elie Cartan】
フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)
ガルダン【噶爾丹・Galdan】
ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康 こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)
カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】
(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。
カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】
パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)
カルチノイド【carcinoid】
胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。
カルチベーター【cultivator】
畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。
カルチャー【culture】
教養。文化。カルチュア。
⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】
⇒カルチャー‐ショック【culture shock】
⇒カルチャー‐センター
カルチャー‐ギャップ【culture gap】
文化による違い。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐ショック【culture shock】
異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐センター
(和製語culture center)
①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。
②主に社会人を対象とした教養講座。
⇒カルチャー【culture】
カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】
民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。
カルテ【Karte ドイツ】
(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。
カルデア‐じん【カルデア人】
(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア
カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】
フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)
カルディナル【kardinaal オランダ】
枢機卿。カーディナル。
カルテット【quartetto イタリア】
①四重奏。四重唱。
②四重奏曲。四重唱曲。
③四重奏団。四重唱団。
カルデラ【caldera】
(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。
⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。
⇒カルデラ【caldera】
カルテル【Kartell ドイツ】
同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合
カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】
スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)
カルト【cult】
①崇拝。
②狂信的な崇拝。「―集団」
③少数の人々の熱狂的支持。
⇒カルト‐えいが【カルト映画】
カルドア【Nicholas Kaldor】
ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)
カルトゥーシュ【cartouche フランス】
①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。
②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。
カルドゥッチ【Giosuè Carducci】
イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)
カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ
一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。
⇒カルト【cult】
こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)
カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】
(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。
カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】
パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)
カルチノイド【carcinoid】
胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。
カルチベーター【cultivator】
畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。
カルチャー【culture】
教養。文化。カルチュア。
⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】
⇒カルチャー‐ショック【culture shock】
⇒カルチャー‐センター
カルチャー‐ギャップ【culture gap】
文化による違い。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐ショック【culture shock】
異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐センター
(和製語culture center)
①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。
②主に社会人を対象とした教養講座。
⇒カルチャー【culture】
カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】
民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。
カルテ【Karte ドイツ】
(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。
カルデア‐じん【カルデア人】
(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア
カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】
フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)
カルディナル【kardinaal オランダ】
枢機卿。カーディナル。
カルテット【quartetto イタリア】
①四重奏。四重唱。
②四重奏曲。四重唱曲。
③四重奏団。四重唱団。
カルデラ【caldera】
(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。
⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。
⇒カルデラ【caldera】
カルテル【Kartell ドイツ】
同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合
カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】
スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)
カルト【cult】
①崇拝。
②狂信的な崇拝。「―集団」
③少数の人々の熱狂的支持。
⇒カルト‐えいが【カルト映画】
カルドア【Nicholas Kaldor】
ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)
カルトゥーシュ【cartouche フランス】
①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。
②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。
カルドゥッチ【Giosuè Carducci】
イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)
カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ
一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。
⇒カルト【cult】
 カリン(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
カリン(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 カリン(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
カリン(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ②マルメロの別称。
⇒かりん‐あたま【花梨頭】
が‐りん【芽鱗】
冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。
かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥
カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。
⇒か‐りん【榠樝】
カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】
古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯
②マルメロの別称。
⇒かりん‐あたま【花梨頭】
が‐りん【芽鱗】
冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。
かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥
カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。
⇒か‐りん【榠樝】
カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】
古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯 伽国かつりょうがこく。
かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ
リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。
かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥
汽車の旧称。
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐せん【火輪船】クワ‥
汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ
古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。
花林糖
撮影:関戸 勇
伽国かつりょうがこく。
かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ
リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。
かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥
汽車の旧称。
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐せん【火輪船】クワ‥
汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」
⇒か‐りん【火輪】
かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ
古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。
花林糖
撮影:関戸 勇
 かる【軽】
奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。
か・る【上る】
〔自他四〕
音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり
か・る【刈る・苅る】
〔他五〕
①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」
②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」
か・る【狩る・猟る】
〔他五〕
①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」
②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」
③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」
か・る【借る】
〔他五〕
(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)
①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」
②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」
③他の助力・協力を受ける。
④(遊里語)
㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」
㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」
⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔
か・る【涸る・枯る・嗄る】
〔自下二〕
⇒かれる(下一)
か・る【駆る・駈る】
〔他五〕
①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」
②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」
③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」
か・る【離る】
〔自下二〕
(「か(涸・枯)れる」と同源)
①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」
②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」
かる【着る】
(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」
ガル【gal】
(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal
が・る
〔接尾〕
形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。
①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」
②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」
か‐るい【家累】
①家族または家事上のわずらい。
②一家の係累。家族。
かる・い【軽い】
〔形〕[文]かる・し(ク)
①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」
②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」
③動きが軽快である。「足取りが―・い」
④軽率である。「口が―・い」
⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」
⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」
⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」
↔重い
かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ
長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。
軽井沢 塩沢湖と浅間山
撮影:佐藤 尚
かる【軽】
奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。
か・る【上る】
〔自他四〕
音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり
か・る【刈る・苅る】
〔他五〕
①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」
②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」
か・る【狩る・猟る】
〔他五〕
①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」
②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」
③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」
か・る【借る】
〔他五〕
(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)
①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」
②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」
③他の助力・協力を受ける。
④(遊里語)
㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」
㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」
⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔
か・る【涸る・枯る・嗄る】
〔自下二〕
⇒かれる(下一)
か・る【駆る・駈る】
〔他五〕
①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」
②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」
③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」
か・る【離る】
〔自下二〕
(「か(涸・枯)れる」と同源)
①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」
②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」
かる【着る】
(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」
ガル【gal】
(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal
が・る
〔接尾〕
形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。
①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」
②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」
か‐るい【家累】
①家族または家事上のわずらい。
②一家の係累。家族。
かる・い【軽い】
〔形〕[文]かる・し(ク)
①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」
②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」
③動きが軽快である。「足取りが―・い」
④軽率である。「口が―・い」
⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」
⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」
⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」
↔重い
かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ
長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。
軽井沢 塩沢湖と浅間山
撮影:佐藤 尚
 かる‐いし【軽石】
火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」
軽石
撮影:関戸 勇
かる‐いし【軽石】
火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」
軽石
撮影:関戸 勇
 かる・うカルフ
〔他四〕
(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」
ガルヴァーニ【Luigi Galvani】
イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)
カルヴァン【Jean Calvin】
フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)
⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。
⇒カルヴァン【Jean Calvin】
カルヴィーノ【Italo Calvino】
イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)
カルヴィニズム【Calvinism】
(→)カルヴァン主義に同じ。
カルヴィン【J. Calvin】
⇒カルヴァン
カルヴィン【Melvin Calvin】
アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)
⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】
カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥
光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。
⇒カルヴィン【Melvin Calvin】
かる‐うす【唐臼】
カラウスの転。
カルーソー【Enrico Caruso】
イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)
カルーソー
提供:毎日新聞社
かる・うカルフ
〔他四〕
(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」
ガルヴァーニ【Luigi Galvani】
イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)
カルヴァン【Jean Calvin】
フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)
⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】
(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。
⇒カルヴァン【Jean Calvin】
カルヴィーノ【Italo Calvino】
イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)
カルヴィニズム【Calvinism】
(→)カルヴァン主義に同じ。
カルヴィン【J. Calvin】
⇒カルヴァン
カルヴィン【Melvin Calvin】
アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)
⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】
カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥
光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。
⇒カルヴィン【Melvin Calvin】
かる‐うす【唐臼】
カラウスの転。
カルーソー【Enrico Caruso】
イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)
カルーソー
提供:毎日新聞社
 ガルーダ【Garuḍa 梵】
⇒ガルダ
かるか
(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。
ガルーダ【Garuḍa 梵】
⇒ガルダ
かるか
(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。 杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」
カルカッタ【Calcutta】
コルカタの旧称。
かる‐がも【軽鴨】
カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。
カルガモ
撮影:小宮輝之
杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」
カルカッタ【Calcutta】
コルカタの旧称。
かる‐がも【軽鴨】
カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。
カルガモ
撮影:小宮輝之
 かる‐かや【刈茅・刈草】
屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」
⇒かるかや‐の【刈茅の】
かる‐かや【刈萱】
①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」
かるかや
かる‐かや【刈茅・刈草】
屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」
⇒かるかや‐の【刈茅の】
かる‐かや【刈萱】
①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」
かるかや
 ②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉
⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】
かるかや【苅萱】
苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。
⇒かるかや‐どう【苅萱堂】
⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】
⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫
②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉
⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】
かるかや【苅萱】
苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。
⇒かるかや‐どう【苅萱堂】
⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】
⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】
かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ
刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。
⇒かる‐かや【刈萱】
かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ
苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥
石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。
⇒かるかや【苅萱】
かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫
】
かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ
刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。
⇒かる‐かや【刈萱】
かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ
苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥
石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。
⇒かるかや【苅萱】
かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】‥ダウ‥イヘ‥
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐の【刈茅の】
〔枕〕
「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。
⇒かる‐かや【刈茅・刈草】
かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥
〔接続〕
(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉
カルガリー【Calgary】
カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。
かる‐がる【軽軽】
軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」
かるがる‐し・い【軽軽しい】
〔形〕[文]かるがる・し(シク)
①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」
②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」
③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい
かる‐かん【軽羹】
すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。
軽羹
撮影:関戸 勇
】‥ダウ‥イヘ‥
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。
⇒かるかや【苅萱】
かるかや‐の【刈茅の】
〔枕〕
「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。
⇒かる‐かや【刈茅・刈草】
かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥
〔接続〕
(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉
カルガリー【Calgary】
カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。
かる‐がる【軽軽】
軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」
かるがる‐し・い【軽軽しい】
〔形〕[文]かるがる・し(シク)
①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」
②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」
③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい
かる‐かん【軽羹】
すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。
軽羹
撮影:関戸 勇
 ガルガンチュア【Gargantua】
ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。
カルキ【kalk オランダ】
①石灰。
②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」
⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】
カルキ‐ながし【カルキ流し】
石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。
⇒カルキ【kalk オランダ】
カルク
(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。
カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】
(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩
かる‐くち【軽口】
①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」
②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。
③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」
④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。
⇒かるくち‐だて【軽口立て】
⇒かるくち‐ばなし【軽口話】
かるくち‐だて【軽口立て】
得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」
⇒かる‐くち【軽口】
かるくち‐ばなし【軽口話】
軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。
⇒かる‐くち【軽口】
カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥
(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。
カルケミッシュ【Carchemish】
トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。
かる‐こ【軽子】
①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。
②江戸深川の遊里の仲居女。
⇒かるこ‐ちん【軽子賃】
かる‐こ【軽籠】
縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。
カルコ【Francis Carco】
フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)
カルコゲン【chalcogen】
(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。
かるこ‐ちん【軽子賃】
(→)軽子1を使役して与える賃銭。
⇒かる‐こ【軽子】
カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】
江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。
カルサン【calção ポルトガル・軽衫】
袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)
軽衫
ガルガンチュア【Gargantua】
ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。
カルキ【kalk オランダ】
①石灰。
②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」
⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】
カルキ‐ながし【カルキ流し】
石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。
⇒カルキ【kalk オランダ】
カルク
(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。
カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】
(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩
かる‐くち【軽口】
①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」
②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。
③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」
④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。
⇒かるくち‐だて【軽口立て】
⇒かるくち‐ばなし【軽口話】
かるくち‐だて【軽口立て】
得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」
⇒かる‐くち【軽口】
かるくち‐ばなし【軽口話】
軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。
⇒かる‐くち【軽口】
カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥
(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。
カルケミッシュ【Carchemish】
トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。
かる‐こ【軽子】
①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。
②江戸深川の遊里の仲居女。
⇒かるこ‐ちん【軽子賃】
かる‐こ【軽籠】
縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。
カルコ【Francis Carco】
フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)
カルコゲン【chalcogen】
(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。
かるこ‐ちん【軽子賃】
(→)軽子1を使役して与える賃銭。
⇒かる‐こ【軽子】
カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】
江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。
カルサン【calção ポルトガル・軽衫】
袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)
軽衫
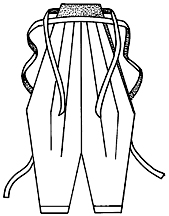 軽衫(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
軽衫(長野)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 かる・し【軽し】
〔形ク〕
⇒かるい
ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】
コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)
ガルシア‐マルケス
提供:ullstein bild/APL
かる・し【軽し】
〔形ク〕
⇒かるい
ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】
コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)
ガルシア‐マルケス
提供:ullstein bild/APL
 ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】
スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)
カルシウム【calcium】
(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。
⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素
⇒カルシウム【calcium】
カルシトニン【calcitonin】
甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。
カルシフェロール【calciferol】
ビタミンD2・D3のこと。
ガルシン【Vsevolod M. Garshin】
ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)
カルス【callus】
〔生〕
①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。
②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。
③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。
カルスト‐ちけい【カルスト地形】
(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。
カルセオラリア【Calceolaria ラテン】
ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。
カルセオラリア
提供:OPO
ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】
スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)
カルシウム【calcium】
(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。
⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】
化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素
⇒カルシウム【calcium】
カルシトニン【calcitonin】
甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。
カルシフェロール【calciferol】
ビタミンD2・D3のこと。
ガルシン【Vsevolod M. Garshin】
ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)
カルス【callus】
〔生〕
①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。
②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。
③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。
カルスト‐ちけい【カルスト地形】
(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。
カルセオラリア【Calceolaria ラテン】
ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。
カルセオラリア
提供:OPO
 ガルソン【garçon フランス】
⇒ギャルソン
カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。
⇒カルタ‐かい【カルタ会】
⇒カルタ‐とり【カルタ取り】
⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】
⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】
ガルダ【Garuḍa 梵】
ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。
カルダーノ【Girolamo Cardano】
イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)
かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】
(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。
カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ
カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタゴ【Carthago】
アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。
カルタゴの遺跡
撮影:田沼武能
ガルソン【garçon フランス】
⇒ギャルソン
カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。
⇒カルタ‐かい【カルタ会】
⇒カルタ‐とり【カルタ取り】
⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】
⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】
ガルダ【Garuḍa 梵】
ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。
カルダーノ【Girolamo Cardano】
イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)
かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】
(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。
カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ
カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタゴ【Carthago】
アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。
カルタゴの遺跡
撮影:田沼武能
 カルタ‐とり【カルタ取り】
カルタを取る遊び。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐ばこ【骨牌函】
①カルタを入れる箱。
②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐むすび【骨牌結び】
帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」
骨牌結び
カルタ‐とり【カルタ取り】
カルタを取る遊び。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐ばこ【骨牌函】
①カルタを入れる箱。
②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルタ‐むすび【骨牌結び】
帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」
骨牌結び
 ⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルダモン【cardamon】
〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。
カルタン【Elie Cartan】
フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)
ガルダン【噶爾丹・Galdan】
ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康
⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】
カルダモン【cardamon】
〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。
カルタン【Elie Cartan】
フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)
ガルダン【噶爾丹・Galdan】
ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康 こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)
カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】
(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。
カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】
パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)
カルチノイド【carcinoid】
胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。
カルチベーター【cultivator】
畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。
カルチャー【culture】
教養。文化。カルチュア。
⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】
⇒カルチャー‐ショック【culture shock】
⇒カルチャー‐センター
カルチャー‐ギャップ【culture gap】
文化による違い。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐ショック【culture shock】
異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐センター
(和製語culture center)
①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。
②主に社会人を対象とした教養講座。
⇒カルチャー【culture】
カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】
民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。
カルテ【Karte ドイツ】
(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。
カルデア‐じん【カルデア人】
(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア
カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】
フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)
カルディナル【kardinaal オランダ】
枢機卿。カーディナル。
カルテット【quartetto イタリア】
①四重奏。四重唱。
②四重奏曲。四重唱曲。
③四重奏団。四重唱団。
カルデラ【caldera】
(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。
⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。
⇒カルデラ【caldera】
カルテル【Kartell ドイツ】
同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合
カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】
スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)
カルト【cult】
①崇拝。
②狂信的な崇拝。「―集団」
③少数の人々の熱狂的支持。
⇒カルト‐えいが【カルト映画】
カルドア【Nicholas Kaldor】
ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)
カルトゥーシュ【cartouche フランス】
①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。
②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。
カルドゥッチ【Giosuè Carducci】
イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)
カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ
一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。
⇒カルト【cult】
こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)
カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】
(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。
カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】
パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)
カルチノイド【carcinoid】
胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。
カルチベーター【cultivator】
畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。
カルチャー【culture】
教養。文化。カルチュア。
⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】
⇒カルチャー‐ショック【culture shock】
⇒カルチャー‐センター
カルチャー‐ギャップ【culture gap】
文化による違い。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐ショック【culture shock】
異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。
⇒カルチャー【culture】
カルチャー‐センター
(和製語culture center)
①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。
②主に社会人を対象とした教養講座。
⇒カルチャー【culture】
カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】
民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。
カルテ【Karte ドイツ】
(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。
カルデア‐じん【カルデア人】
(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア
カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】
フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)
カルディナル【kardinaal オランダ】
枢機卿。カーディナル。
カルテット【quartetto イタリア】
①四重奏。四重唱。
②四重奏曲。四重唱曲。
③四重奏団。四重唱団。
カルデラ【caldera】
(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。
⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラ‐こ【カルデラ湖】
カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。
⇒カルデラ【caldera】
カルテル【Kartell ドイツ】
同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合
カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】
スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)
カルト【cult】
①崇拝。
②狂信的な崇拝。「―集団」
③少数の人々の熱狂的支持。
⇒カルト‐えいが【カルト映画】
カルドア【Nicholas Kaldor】
ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)
カルトゥーシュ【cartouche フランス】
①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。
②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。
カルドゥッチ【Giosuè Carducci】
イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)
カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ
一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。
⇒カルト【cult】
か・る【借る】🔗⭐🔉
か・る【借る】
〔他五〕
(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)
①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」
②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」
③他の助力・協力を受ける。
④(遊里語)
㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」
㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」
⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔
○借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔かるときのじぞうがおなすときのえんまがお🔗⭐🔉
○借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔かるときのじぞうがおなすときのえんまがお
物を借りる時はにこにこ愛想よくするのに、返す時は無愛想なこわい顔になる人間の心理をいう。「地蔵顔」は「恵比寿顔えびすがお」とも。
⇒か・る【借る】
ガルドス【Galdós】
⇒ペレス=ガルドス
カルトン【carton フランス】
①油絵を描くための厚手のボール紙。
②原画大の厚紙の上に描いた素描による画稿。これを壁面にあてて図様を転写し、壁画の下図とする。
③大形のボール紙でつくった紙ばさみ。デッサンなどを入れるのに用いる。
④銀行・商店などで支払金・釣銭などを入れる盆。
カルナータカ【Karnataka】
インド南部の州。アラビア海に面する。州都ベンガルール。旧称、マイソール。
⇒カルナータカ‐おんがく【カルナータカ音楽】
カルナータカ‐おんがく【カルナータカ音楽】
南インド音楽の総称。北インドのヒンドスターニーの音楽とともに、インド古典音楽の二つの伝統を作る。
⇒カルナータカ【Karnataka】
カルナップ【Rudolf Carnap】
ドイツ生れの哲学者。言語の論理的分析および科学哲学において指導的役割を果たす。ウィーン学団の中心の一人であったが、ナチス台頭によりシカゴ大学に移り、「ウィーン‐シカゴ学派」を形成して統一科学運動を指導した。著「世界の論理的構築」「意味と必然性」など。(1891〜1970)
カルナティック【Carnatic】
インド南部、タミルナドゥ州の東海岸の地方。18世紀中葉の英仏抗争の地。
かる‐に【軽荷】
①軽い荷物。
②船の荷が軽く、喫水きっすいの浅い時に船底に積む石。バラスト。
カルニチン【carnitine】
分子式C7H15NO3 アミノ酸の一種。すべての生物組織に存在し、脂肪酸代謝で重要。強心剤など医薬品として使用される。
カルネ【Marcel Carné】
フランスの映画監督。作「霧の波止場」「北ホテル」「悪魔が夜来る」「天井桟敷の人々」など。(1909〜1996)
カルネアデス【Karneadēs】
古代ギリシアの哲学者。新アカデメイア派に属し、懐疑主義を奉じた。(前214〜前129)
⇒カルネアデス‐の‐いた【カルネアデスの板】
カルネアデス‐の‐いた【カルネアデスの板】
カルネアデスが提示した問題。難船の後、1枚の板に弱い者がすがりついている時、強い者はどう行動するのが正義に叶うかを問う。
⇒カルネアデス【Karneadēs】
カルノー【Nicolas Léonard Sadi Carnot】
フランスの物理学者。熱力学を研究。(1796〜1832)
⇒カルノー‐サイクル【Carnot's cycle】
カルノー‐サイクル【Carnot's cycle】
19世紀初頭カルノーの考案した、熱機関の効率が最大になるような理想的な可逆サイクル。作業物質(変化の過程を調べる対象物質)が高温度と低温度間に等温膨張・断熱膨張・等温圧縮・断熱圧縮の4行程で1循環するとき、その効率は作業物質には無関係に、高温度と低温度とによって定まるというもの。熱力学第2法則の基礎となった。
⇒カルノー【Nicolas Léonard Sadi Carnot】
かる‐の‐こ【軽鳧の子】
カルガモの子。〈[季]夏〉
かる‐はずみ【軽はずみ】‥ハヅミ
①軽妙なこと。野郎立役舞台大鏡「今までのもやうさらりとかへわつさりと―に出てみまひか」
②深く考えずに、調子にのって言ったりしたりすること。軽率。かろはずみ。「―な行動」
カルバゾール【carbazole】
分子式C12H9N 環中に窒素原子1個を含む三環複素環式化合物。コールタール中に含まれる。無色の結晶。染料の原料。
カルパチア【Carpathia】
スロヴァキア東部から東に弧状に延び、ルーマニア北部に至る山脈。延長約1500キロメートル。最高峰ゲルラホフカ山は標高2663メートル。銅・鉄・石油・岩塩などを産出。ロシア語名カルパート。
カルパチア山脈
撮影:小松義夫
 カルパッチオ【Vittore Carpaccio】
イタリア、ヴェネツィア派の画家。ベッリーニ兄弟の門人。風景描写にすぐれた。作「聖女ウルスラ物語」など。(1455頃〜1525頃)
カルパッチオ
提供:Maxppp/APL
カルパッチオ【Vittore Carpaccio】
イタリア、ヴェネツィア派の画家。ベッリーニ兄弟の門人。風景描写にすぐれた。作「聖女ウルスラ物語」など。(1455頃〜1525頃)
カルパッチオ
提供:Maxppp/APL
 「エルサレムで説教する聖エティエンヌ」
提供:Photos12/APL
「エルサレムで説教する聖エティエンヌ」
提供:Photos12/APL
 カルパッチョ【carpaccio イタリア】
(画家カルパッチオに因む)生の牛肉を薄切りにし、ソースやドレッシングで調味したイタリア料理。牛以外の肉や魚でも作る。
カルバドス【calvados フランス】
リンゴから作るブランデー。フランス、ノルマンディー地方カルヴァドス県で生産されるのでこの名がある。
ガルバノメーター【galvanometer】
(→)検流計のこと。
カルバラー【Karbalā'】
イラク中央部の都市。ナジャフとならぶイスラム教シーア派の聖地。680年アリーの息子フサインが殺された地。人口29万6千(1987)。
ガルバンソ【garbanzo スペイン】
〔植〕(→)ひよこまめ。
カルビ
(朝鮮語kalbi)ばら肉のこと。焼肉・煮込みなどに用いる。
カルピーニ【Giovanni de Piano Carpini】
イタリア人。フランシスコ会修道士。1245年、教皇の命をうけモンゴルに赴き、47年リヨンに帰着。その旅行記がある。(1182頃〜1252)
カルピス【Calpis】
乳酸菌飲料の一種。脱脂乳を乳酸発酵させ、砂糖・香料などを加えたもの。希釈して飲む。商標名。
かる・ぶ【軽ぶ】
〔自上二〕
「かろぶ」に同じ。
ガルブレイス【John Kenneth Galbraith】
制度学派の流れをひくアメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。全米経済学会会長。著「ゆたかな社会」「新しい産業国家」「満足の文化」など。(1908〜2006)
カルペンティエール【Alejo Carpentier】
キューバの作家。時間の魔術師と呼ばれる。作「失われた足跡」「光の世紀」など。(1904〜1980)
ガルボ【Greta Garbo】
スウェーデン生れの女優。「肉体と悪魔」「アンナ=カレーニナ」などアメリカ映画に出演。36歳で引退、伝説的存在となる。(1905〜1990)
カルポー【Jean Baptiste Carpeaux】
フランス、ロマン派の彫刻家。リュードの後継者。(1827〜1875)
カルボキシ‐き【カルボキシ基】
〔化〕(carboxyl group)1価の基。化学式‐COOH カルボキシル基。
カルホス【Karphos】
有機燐系殺虫剤イソキサチオン剤の商品名。劇物。急性経口毒性(マウス)LD50は242。アオムシ・カイガラムシ・ヨトウムシなど幅広く害虫に用いる。
カルボナード【carbonado スペイン】
ブラジル産の暗灰色または黒色ダイヤモンド。不純物を含み、主に削岩機に使う。
カルボナーラ【carbonara イタリア】
ベーコン・チーズ・卵などで作るソースであえ、黒胡椒をふったイタリア料理。「スパゲッティ‐―」
カルボナリ【Carbonari フランス】
(炭焼すみやきの意)19世紀前半のイタリアの秘密結社。ナポリを中心に南イタリアに広がり、オーストリアに抗して祖国の統一と独立を目ざし、反乱を起こした。
カルボニル‐き【カルボニル基】
〔化〕(carbonyl group)2価の官能基>C=Oをいう。この基に二つの炭化水素基が結合した化合物をケトン、水素原子と炭化水素基が結合した化合物をアルデヒドと総称する。
カルボン‐さん【カルボン酸】
(carboxylic acid)カルボキシ基をもつ有機酸の総称。酢酸・安息香酸の類。カルボキシ酸。
カルマ【karman 梵】
〔仏〕
⇒ごう(業)
カルマル‐どうめい【カルマル同盟】
中世、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン三国の同君連合。1389年、スウェーデン南部の都市カルマル(Kalmar)で三国の貴族が同一の国王を選出したのが正式の始まりで、15世紀前半まで続く。カルマル連合。
カルマン‐うず【カルマン渦】‥ウヅ
流体中で柱状物体を動かすとき、物体の両側から交互に反対向きに生じて規則正しく並ぶ渦。風の吹く日に電線がうなりを生ずる原因。アメリカの航空力学者カルマン(T. von Kármán1881〜1963)が理論的に研究。
かる‐み【軽み】
蕉風俳諧で重んじた作風の一つ。移り行く現実に応じた、とどこおらない軽やかさを把握しようとする理念。去来抄「そこもと随分―をとり失ふべからず」
カルミア【Kalmia ラテン】
広義にはツツジ科の一属(その学名)。北アメリカ原産。また、同属の観賞用常緑低木。シャクナゲに似た葉を枝先に輪生。初夏に枝端に多数の白花を束状につける。花冠は盃状で赤紫の斑点がめだつ。アメリカシャクナゲ。
カルミア(花)
撮影:関戸 勇
カルパッチョ【carpaccio イタリア】
(画家カルパッチオに因む)生の牛肉を薄切りにし、ソースやドレッシングで調味したイタリア料理。牛以外の肉や魚でも作る。
カルバドス【calvados フランス】
リンゴから作るブランデー。フランス、ノルマンディー地方カルヴァドス県で生産されるのでこの名がある。
ガルバノメーター【galvanometer】
(→)検流計のこと。
カルバラー【Karbalā'】
イラク中央部の都市。ナジャフとならぶイスラム教シーア派の聖地。680年アリーの息子フサインが殺された地。人口29万6千(1987)。
ガルバンソ【garbanzo スペイン】
〔植〕(→)ひよこまめ。
カルビ
(朝鮮語kalbi)ばら肉のこと。焼肉・煮込みなどに用いる。
カルピーニ【Giovanni de Piano Carpini】
イタリア人。フランシスコ会修道士。1245年、教皇の命をうけモンゴルに赴き、47年リヨンに帰着。その旅行記がある。(1182頃〜1252)
カルピス【Calpis】
乳酸菌飲料の一種。脱脂乳を乳酸発酵させ、砂糖・香料などを加えたもの。希釈して飲む。商標名。
かる・ぶ【軽ぶ】
〔自上二〕
「かろぶ」に同じ。
ガルブレイス【John Kenneth Galbraith】
制度学派の流れをひくアメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。全米経済学会会長。著「ゆたかな社会」「新しい産業国家」「満足の文化」など。(1908〜2006)
カルペンティエール【Alejo Carpentier】
キューバの作家。時間の魔術師と呼ばれる。作「失われた足跡」「光の世紀」など。(1904〜1980)
ガルボ【Greta Garbo】
スウェーデン生れの女優。「肉体と悪魔」「アンナ=カレーニナ」などアメリカ映画に出演。36歳で引退、伝説的存在となる。(1905〜1990)
カルポー【Jean Baptiste Carpeaux】
フランス、ロマン派の彫刻家。リュードの後継者。(1827〜1875)
カルボキシ‐き【カルボキシ基】
〔化〕(carboxyl group)1価の基。化学式‐COOH カルボキシル基。
カルホス【Karphos】
有機燐系殺虫剤イソキサチオン剤の商品名。劇物。急性経口毒性(マウス)LD50は242。アオムシ・カイガラムシ・ヨトウムシなど幅広く害虫に用いる。
カルボナード【carbonado スペイン】
ブラジル産の暗灰色または黒色ダイヤモンド。不純物を含み、主に削岩機に使う。
カルボナーラ【carbonara イタリア】
ベーコン・チーズ・卵などで作るソースであえ、黒胡椒をふったイタリア料理。「スパゲッティ‐―」
カルボナリ【Carbonari フランス】
(炭焼すみやきの意)19世紀前半のイタリアの秘密結社。ナポリを中心に南イタリアに広がり、オーストリアに抗して祖国の統一と独立を目ざし、反乱を起こした。
カルボニル‐き【カルボニル基】
〔化〕(carbonyl group)2価の官能基>C=Oをいう。この基に二つの炭化水素基が結合した化合物をケトン、水素原子と炭化水素基が結合した化合物をアルデヒドと総称する。
カルボン‐さん【カルボン酸】
(carboxylic acid)カルボキシ基をもつ有機酸の総称。酢酸・安息香酸の類。カルボキシ酸。
カルマ【karman 梵】
〔仏〕
⇒ごう(業)
カルマル‐どうめい【カルマル同盟】
中世、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン三国の同君連合。1389年、スウェーデン南部の都市カルマル(Kalmar)で三国の貴族が同一の国王を選出したのが正式の始まりで、15世紀前半まで続く。カルマル連合。
カルマン‐うず【カルマン渦】‥ウヅ
流体中で柱状物体を動かすとき、物体の両側から交互に反対向きに生じて規則正しく並ぶ渦。風の吹く日に電線がうなりを生ずる原因。アメリカの航空力学者カルマン(T. von Kármán1881〜1963)が理論的に研究。
かる‐み【軽み】
蕉風俳諧で重んじた作風の一つ。移り行く現実に応じた、とどこおらない軽やかさを把握しようとする理念。去来抄「そこもと随分―をとり失ふべからず」
カルミア【Kalmia ラテン】
広義にはツツジ科の一属(その学名)。北アメリカ原産。また、同属の観賞用常緑低木。シャクナゲに似た葉を枝先に輪生。初夏に枝端に多数の白花を束状につける。花冠は盃状で赤紫の斑点がめだつ。アメリカシャクナゲ。
カルミア(花)
撮影:関戸 勇
 カルミナ‐ブラーナ【Carmina Burana ラテン】
(ボイレンの歌の意)
①ラテン語と一部ドイツ語で書かれた13世紀の世俗歌集。恋・酒・賭事・諷刺を題材とする遍歴学生の歌など約300を収録。南ドイツのボイレンのベネディクト修道院で発見されたので、こう呼ばれる。
②ドイツのオルフが1936年に、1の歌集から24編の詩を選んで作曲した舞台形式オラトリオ。
カルミン【karmijn オランダ】
中南米の砂漠地に産するサボテンに寄生するコチニール虫(エンジムシの一種)の雌の体から製した鮮麗な紅色の色素。その成分であるカルミン酸はアントラキノン誘導体である。日本画の絵具、赤インクの製造または飲食物の着色、また、友禅染の染料、化粧料に用いる。また生物学などで組織染色に使用。洋紅。コチニール。カーミン。
かる・む【軽む】
〔他下二・自四〕
「かろむ」に同じ。
かる‐め【軽目】
①目方の軽いこと。
②軽目墨の略。
③⇒カルメ。
⇒かるめ‐きん【軽目金】
⇒かるめ‐ずみ【軽目墨】
⇒かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】
⇒かるめ‐やき【軽目焼】
カルメ
「カルメラ」「カルメル」の略。「軽目」と当てる。
かるめ‐きん【軽目金】
量目の減った小判や一分金。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐ずみ【軽目墨】
掃墨はいずみに豆汁ごじるをまぜ、藍鼠色の染料としたもの。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】‥ヘ
目方の軽い羽二重。片羽二重。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐やき【軽目焼】
⇒カルメラ
⇒かる‐め【軽目】
カルメラ【caramelo ポルトガル・ スペイン】
氷砂糖に卵の白身を加え、煮て泡立たせ、そのまま固まらせた軽石状の菓子。今はざらめ糖に重曹を加えて作る。軽目焼。浮石糖。泡糖。カルメル。カルメロ。カルメ。カルメイラ。
カルメル
⇒カルメラ
カルメル‐かい【カルメル会】‥クワイ
(Ordo Fratrum Carmelitarum ラテン)カトリック観想修道会の一つ。12世紀以来パレスチナのカルメル山に住み始めたラテン系隠修士団が托鉢修道会として認可され、1238年頃西欧へ移住したもの。16世紀アビラのテレサと十字架の聖ヨハネの刷新運動の結果、跣足せんそくカルメル会が創立。
カルメン【Carmen】
①メリメの小説。1845年刊。スペインを舞台に、ジプシー女カルメンと竜騎隊の伍長ドン=ホセとの恋愛葛藤の悲劇を描く。
②1によってビゼーが作曲した歌劇。4幕。1875年パリで初演。
ビゼー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
カルミナ‐ブラーナ【Carmina Burana ラテン】
(ボイレンの歌の意)
①ラテン語と一部ドイツ語で書かれた13世紀の世俗歌集。恋・酒・賭事・諷刺を題材とする遍歴学生の歌など約300を収録。南ドイツのボイレンのベネディクト修道院で発見されたので、こう呼ばれる。
②ドイツのオルフが1936年に、1の歌集から24編の詩を選んで作曲した舞台形式オラトリオ。
カルミン【karmijn オランダ】
中南米の砂漠地に産するサボテンに寄生するコチニール虫(エンジムシの一種)の雌の体から製した鮮麗な紅色の色素。その成分であるカルミン酸はアントラキノン誘導体である。日本画の絵具、赤インクの製造または飲食物の着色、また、友禅染の染料、化粧料に用いる。また生物学などで組織染色に使用。洋紅。コチニール。カーミン。
かる・む【軽む】
〔他下二・自四〕
「かろむ」に同じ。
かる‐め【軽目】
①目方の軽いこと。
②軽目墨の略。
③⇒カルメ。
⇒かるめ‐きん【軽目金】
⇒かるめ‐ずみ【軽目墨】
⇒かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】
⇒かるめ‐やき【軽目焼】
カルメ
「カルメラ」「カルメル」の略。「軽目」と当てる。
かるめ‐きん【軽目金】
量目の減った小判や一分金。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐ずみ【軽目墨】
掃墨はいずみに豆汁ごじるをまぜ、藍鼠色の染料としたもの。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】‥ヘ
目方の軽い羽二重。片羽二重。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐やき【軽目焼】
⇒カルメラ
⇒かる‐め【軽目】
カルメラ【caramelo ポルトガル・ スペイン】
氷砂糖に卵の白身を加え、煮て泡立たせ、そのまま固まらせた軽石状の菓子。今はざらめ糖に重曹を加えて作る。軽目焼。浮石糖。泡糖。カルメル。カルメロ。カルメ。カルメイラ。
カルメル
⇒カルメラ
カルメル‐かい【カルメル会】‥クワイ
(Ordo Fratrum Carmelitarum ラテン)カトリック観想修道会の一つ。12世紀以来パレスチナのカルメル山に住み始めたラテン系隠修士団が托鉢修道会として認可され、1238年頃西欧へ移住したもの。16世紀アビラのテレサと十字架の聖ヨハネの刷新運動の結果、跣足せんそくカルメル会が創立。
カルメン【Carmen】
①メリメの小説。1845年刊。スペインを舞台に、ジプシー女カルメンと竜騎隊の伍長ドン=ホセとの恋愛葛藤の悲劇を描く。
②1によってビゼーが作曲した歌劇。4幕。1875年パリで初演。
ビゼー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
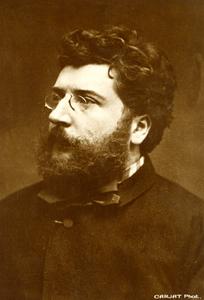 →歌劇「カルメン」 闘牛士
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
かる‐も【刈藻】
刈り取った藻。伊勢物語「恋ひわびぬ蜑あまの―に宿るてふわれから身をもくだきつるかな」
かる‐も【枯草】
かれくさ。夫木和歌抄27「秋の野の―がしたに月もりて」
⇒かるも‐かく【枯草掻く】
かるも‐かく【枯草掻く】
〔枕〕
(猪が枯草を集めて寝床とすることから)「ゐ(猪)」にかかる。
⇒かる‐も【枯草】
カルモジュリン【calmodulin】
真核細胞に存在し、カルシウム‐イオンと特異的に結合する蛋白質の一つ。垣内史朗(1929〜1984)らが発見。カルシウムを結合したカルモジュリンは細胞内のさまざまな酵素に結合し、それを活性化する。
カルモチン【Calmotin】
鎮静催眠剤として用いられたブロムワレリル尿素の商品名。
かる‐もの【軽物】
目方が軽い物の意で、絹布の称。今昔物語集28「粮かても少し有り、―も人要すばかりのものは少々有り」
⇒かるもの‐ぐら【軽物蔵】
かるもの‐ぐら【軽物蔵】
軽物を入れる蔵。狂言、三人片輪「汝が前に有るは―ぢや」
⇒かる‐もの【軽物】
かる‐やか【軽やか】
(→)「かろやか」に同じ。
かる‐やき【軽焼】
軽焼煎餅の略。
⇒かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
糯米もちごめの粉に砂糖を加え、いったん蒸して乾燥させ、これを焼いてふくれるようにした煎餅。
⇒かる‐やき【軽焼】
かる‐ゆき【軽行き】
手軽なこと。たやすく事が進むこと。好色一代女1「一人を金一角に定め置きしは―なる呼びものなり」
かるら【迦楼羅】
(梵語Garuḍa)インド神話における巨鳥で、竜を憎んで食べるという。仏教に入って天竜八部衆の一つとして、仏法の守護神とされる。翼は金色、頭には如意珠があり、常に口から火焔を吐く。金翅こんじ鳥。妙翅鳥。→ガルダ→伎楽面ぎがくめん(図)。
迦楼羅
→歌劇「カルメン」 闘牛士
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
かる‐も【刈藻】
刈り取った藻。伊勢物語「恋ひわびぬ蜑あまの―に宿るてふわれから身をもくだきつるかな」
かる‐も【枯草】
かれくさ。夫木和歌抄27「秋の野の―がしたに月もりて」
⇒かるも‐かく【枯草掻く】
かるも‐かく【枯草掻く】
〔枕〕
(猪が枯草を集めて寝床とすることから)「ゐ(猪)」にかかる。
⇒かる‐も【枯草】
カルモジュリン【calmodulin】
真核細胞に存在し、カルシウム‐イオンと特異的に結合する蛋白質の一つ。垣内史朗(1929〜1984)らが発見。カルシウムを結合したカルモジュリンは細胞内のさまざまな酵素に結合し、それを活性化する。
カルモチン【Calmotin】
鎮静催眠剤として用いられたブロムワレリル尿素の商品名。
かる‐もの【軽物】
目方が軽い物の意で、絹布の称。今昔物語集28「粮かても少し有り、―も人要すばかりのものは少々有り」
⇒かるもの‐ぐら【軽物蔵】
かるもの‐ぐら【軽物蔵】
軽物を入れる蔵。狂言、三人片輪「汝が前に有るは―ぢや」
⇒かる‐もの【軽物】
かる‐やか【軽やか】
(→)「かろやか」に同じ。
かる‐やき【軽焼】
軽焼煎餅の略。
⇒かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
糯米もちごめの粉に砂糖を加え、いったん蒸して乾燥させ、これを焼いてふくれるようにした煎餅。
⇒かる‐やき【軽焼】
かる‐ゆき【軽行き】
手軽なこと。たやすく事が進むこと。好色一代女1「一人を金一角に定め置きしは―なる呼びものなり」
かるら【迦楼羅】
(梵語Garuḍa)インド神話における巨鳥で、竜を憎んで食べるという。仏教に入って天竜八部衆の一つとして、仏法の守護神とされる。翼は金色、頭には如意珠があり、常に口から火焔を吐く。金翅こんじ鳥。妙翅鳥。→ガルダ→伎楽面ぎがくめん(図)。
迦楼羅
 ⇒かるら‐えん【迦楼羅炎】
⇒かるら‐ほう【迦楼羅法】
かるら‐えん【迦楼羅炎】
不動明王の光背の名称。カルラの羽根をひろげた形に似るからいう。
⇒かるら【迦楼羅】
かる‐らか【軽らか】
(→)「かろらか」に同じ。
かるら‐ほう【迦楼羅法】‥ホフ
密教で、迦楼羅を本尊とし、病苦・風雨・雷などを除くことを祈願する修法しゅほう。
⇒かるら【迦楼羅】
カルルス‐せんえん【カルルス泉塩】
(Karlsbader Salz ドイツ)チェコ西部カールスバート(現、カルロヴィ‐ヴァリ)の鉱泉(カルルス水)を結晶させた薬品。また、人工的には、硫酸ナトリウムに重曹・食塩・硫酸カリウムを加えて製した白色の粉末。緩下剤・消化剤。
カルルス‐せんべい【カルルス煎餅】
カルルス泉塩を加えて製した煎餅。
カルルック【Qarluq・葛邏禄】
古トルコ系民族の一つ。主に7〜12世紀に中央アジアで活躍。カルルク。
カルロヴィ‐ヴァリ【Karlovy Vary チェコ】
チェコ西部ボヘミアの都市。温泉とガラス細工で有名な観光地。ドイツ語名カールスバート。
かる‐わざ【軽業】
①困難なことや危険なことを身軽にやりこなすこと。尤之双紙もっとものそうし「あぶなき物のしなじな…老人の―」
②危険な曲芸を身軽に演じるもの。綱渡り・籠抜け・梯子はしご乗りの類。
③比喩的に、はなはだしく冒険的な計画または事業。「そんな―はやめろ」
⇒かるわざ‐し【軽業師】
⇒かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】
かるわざ‐し【軽業師】
①軽業2を職業として演ずる人。
②比喩的に、軽業3をする人。
⇒かる‐わざ【軽業】
かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】‥ギヤウ
紙製の人形を絓糸すがいとで操り、自然に動くように見せたもの。
⇒かる‐わざ【軽業】
かれ【枯れ】
草木が枯れること。万葉集16「海は潮干て山は―すれ」
かれ【涸れ】
水が涸れること。乾燥。
かれ【嗄れ】
声が嗄れること。しわがれ。
かれ【彼】
〔代〕
①あれ。あのもの。古くは人をも人以外のものをもさした。人の場合、男女ともにさした。万葉集11「たそ―と問はば答へむ」。万葉集18「わが思ふ君が御船かも―」
②(「かのじょ」に対し特に)あの男。その男。泉鏡花、妙の宮「士官は心剛ごうなりき。渠かれはつかつかと寄添ひぬ」
③転じて、愛人である男性。彼氏。
⇒彼と言い此れと言い
⇒彼も一時此れも一時
⇒彼も人なり我も人なり
⇒彼を知り己を知れば百戦殆からず
かれ【故】
〔接続〕
(カ(此)アレ(有リの已然形)の約、「かあれば」の意)
①(前段を承けて)こういうわけで。ゆえに。因明論疏四相違略註釈天永点「二他に通して用せらるとい、故カレ今臥具を以て」
②(段落の初めにおいて)さて。そこで。古事記上「―此の大国主神の兄弟あにおと、八十やそ神坐ましき」
がれ
谷川ぞいの路、あるいは山崩れで崖になった、石塊のがらがらした急斜面。なぎ。がれ場。
ガレ【Émile Gallé】
フランスの工芸家。アール‐ヌーヴォーを代表する一人。彩色・象眼等を施したガラス工芸と、寄木細工による優美な家具で知られる。(1846〜1904)
かれ‐あし【枯葦・枯蘆】
枯れた葦。特に、冬枯れした葦。〈[季]冬〉
かれい【鰈】カレヒ
(カラエイの転)カレイ科の硬骨魚の総称。体は扁平で卵形、頭部はねじれて、眼は普通、体の右側に集まる(ヒラメでは、眼は左側)。眼のある側は褐色で海底の色に似、眼のない側は白色。砂底に生息。多くの種類がある。食用。倭名類聚鈔19「王余魚、和名加良衣比、俗云加礼比」
かれ‐い【餉】‥ヒ
(カレイヒ(乾飯)の約)旅行のときなどに携帯した干した飯。転じて、広く携帯用食料にもいう。万葉集5「いかにか行かむ―はなしに」
⇒かれい‐け【餉笥・樏子】
⇒かれい‐つけ【餉付】
か‐れい【下隷】
しもべ。
か‐れい【加齢】
①新年または誕生日を迎えて年齢を増すこと。加年。
②年老いること。
か‐れい【花翎】クワ‥
中国清朝で、皇族または官吏に与えた、帽子の後に垂れる孔雀の羽根の装飾。
か‐れい【佳麗】
①美しいこと。きれいなこと。「―を競う」
②[白楽天、長恨歌]美女。
か‐れい【苛令】
きびしい法令。むごいおきて。
か‐れい【家令】
①(ケリョウとも)律令制で、親王・内親王・三位以上などの家で家務・会計を管理した人。のち家司けいしが置かれてからは有名無実となった。
②明治以後、宮家や華族の家務を管理し、家扶以下を監督した者。
か‐れい【家例】
その家に代々伝わるしきたり。
か‐れい【家隷】
一家に隷属する者。けらい。しもべ。
か‐れい【華麗】クワ‥
はなやかで美しいこと。「―な演技」
か‐れい【遐齢】
長生き。長寿。「―延年」
か‐れい【嘉礼】
めでたい礼式。
か‐れい【嘉例・佳例】
①めでたい先例。吉例。嘉躅かちょく。
②通例。例。狂言、宗論「―の情ごはでござる」
か‐れい【嘉齢】
めでたい長寿。
かれ‐いい【餉・乾飯】‥イヒ
(→)「かれい」に同じ。伊勢物語「―の上に涙おとしてほとびにけり」
か‐れいきゃく【過冷却】クワ‥
気体や液体をその沸点や融点以下に冷やしてもなお気体や液体の状態にあること。過冷。
かれい‐け【餉笥・樏子】‥ヒ‥
餉を入れる笥け。弁当箱。わりご。〈倭名類聚鈔14〉
⇒かれ‐い【餉】
かれい‐つけ【餉付】‥ヒ‥
(旅行の際、餉を結びつけたからいう)鞍の後輪しずわの左右の四緒手しおでに付けた長い紐。ものつけ。〈倭名類聚鈔15〉
⇒かれ‐い【餉】
かれ‐いばら【枯茨】
冬になって葉が枯れ落ちた茨。〈[季]冬〉
かれ‐いろ【枯色】
①草木などの枯れた色。
Munsell color system: 10YR7.5/4.5
②襲かさねの色目。表は白、裏は薄紫、あるいは中倍なかべに朽葉を入れる。または、表は香こう、裏は青。
かれ‐うお【涸魚】‥ウヲ
日に干した魚。ひもの。ほしうお。
カレー【Calais】
フランス北部の都市。ドーヴァー海峡に臨むイギリスとの連絡港。レースの産地。
カレー【curry】
(タミール語でソースの意のkariから)
①(→)カレー粉に同じ。
②カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。「ビーフ‐―」
③「カレーライス」「ライスカレー」の略。
⇒カレー‐こ【カレー粉】
⇒カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
ガレー【galley】
古代から近代まで地中海で使用された軍船。両舷に多数の櫂かいを出して漕ぎ、櫂を2段・3段に配置することもあった。帆を備えた船もある。ガリー。ガレー船。
カレー‐こ【カレー粉】
黄褐色で粉末状の、辛味の強い混合香辛料。ウコン・コエンドロ・コショウ・ショウガ・トウガラシ・カラシ・オールスパイス・チョウジなど多種の香辛料を配合して作る。インドが主産地。カレー。カリー。
⇒カレー【curry】
ガレージ【garage】
自動車の車庫。ギャレージ。
⇒ガレージ‐セール【garage sale】
ガレージ‐セール【garage sale】
家庭で不用な品を自宅のガレージなどで売ること。
⇒ガレージ【garage】
カレーズ【karēz ペルシア】
(→)カナートに同じ。
かれ‐えだ【枯枝】
枯れた木の枝。また、葉の落ちてしまった木の枝。〈[季]冬〉
カレードスコープ【kaleidoscope】
万華鏡まんげきょう。百色めがね。
カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
肉・野菜などをカレーの風味をつけて煮込み、飯の上にかけた料理。本来インドの料理であるカレーが、日本独自の料理として定着したもの。ライスカレー。
⇒カレー【curry】
かれ‐おばな【枯尾花】‥ヲ‥
すすきの穂が枯れたもの。〈[季]冬〉。「狐火の燃えつくばかり―」(蕪村)
枯尾花
撮影:関戸 勇
⇒かるら‐えん【迦楼羅炎】
⇒かるら‐ほう【迦楼羅法】
かるら‐えん【迦楼羅炎】
不動明王の光背の名称。カルラの羽根をひろげた形に似るからいう。
⇒かるら【迦楼羅】
かる‐らか【軽らか】
(→)「かろらか」に同じ。
かるら‐ほう【迦楼羅法】‥ホフ
密教で、迦楼羅を本尊とし、病苦・風雨・雷などを除くことを祈願する修法しゅほう。
⇒かるら【迦楼羅】
カルルス‐せんえん【カルルス泉塩】
(Karlsbader Salz ドイツ)チェコ西部カールスバート(現、カルロヴィ‐ヴァリ)の鉱泉(カルルス水)を結晶させた薬品。また、人工的には、硫酸ナトリウムに重曹・食塩・硫酸カリウムを加えて製した白色の粉末。緩下剤・消化剤。
カルルス‐せんべい【カルルス煎餅】
カルルス泉塩を加えて製した煎餅。
カルルック【Qarluq・葛邏禄】
古トルコ系民族の一つ。主に7〜12世紀に中央アジアで活躍。カルルク。
カルロヴィ‐ヴァリ【Karlovy Vary チェコ】
チェコ西部ボヘミアの都市。温泉とガラス細工で有名な観光地。ドイツ語名カールスバート。
かる‐わざ【軽業】
①困難なことや危険なことを身軽にやりこなすこと。尤之双紙もっとものそうし「あぶなき物のしなじな…老人の―」
②危険な曲芸を身軽に演じるもの。綱渡り・籠抜け・梯子はしご乗りの類。
③比喩的に、はなはだしく冒険的な計画または事業。「そんな―はやめろ」
⇒かるわざ‐し【軽業師】
⇒かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】
かるわざ‐し【軽業師】
①軽業2を職業として演ずる人。
②比喩的に、軽業3をする人。
⇒かる‐わざ【軽業】
かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】‥ギヤウ
紙製の人形を絓糸すがいとで操り、自然に動くように見せたもの。
⇒かる‐わざ【軽業】
かれ【枯れ】
草木が枯れること。万葉集16「海は潮干て山は―すれ」
かれ【涸れ】
水が涸れること。乾燥。
かれ【嗄れ】
声が嗄れること。しわがれ。
かれ【彼】
〔代〕
①あれ。あのもの。古くは人をも人以外のものをもさした。人の場合、男女ともにさした。万葉集11「たそ―と問はば答へむ」。万葉集18「わが思ふ君が御船かも―」
②(「かのじょ」に対し特に)あの男。その男。泉鏡花、妙の宮「士官は心剛ごうなりき。渠かれはつかつかと寄添ひぬ」
③転じて、愛人である男性。彼氏。
⇒彼と言い此れと言い
⇒彼も一時此れも一時
⇒彼も人なり我も人なり
⇒彼を知り己を知れば百戦殆からず
かれ【故】
〔接続〕
(カ(此)アレ(有リの已然形)の約、「かあれば」の意)
①(前段を承けて)こういうわけで。ゆえに。因明論疏四相違略註釈天永点「二他に通して用せらるとい、故カレ今臥具を以て」
②(段落の初めにおいて)さて。そこで。古事記上「―此の大国主神の兄弟あにおと、八十やそ神坐ましき」
がれ
谷川ぞいの路、あるいは山崩れで崖になった、石塊のがらがらした急斜面。なぎ。がれ場。
ガレ【Émile Gallé】
フランスの工芸家。アール‐ヌーヴォーを代表する一人。彩色・象眼等を施したガラス工芸と、寄木細工による優美な家具で知られる。(1846〜1904)
かれ‐あし【枯葦・枯蘆】
枯れた葦。特に、冬枯れした葦。〈[季]冬〉
かれい【鰈】カレヒ
(カラエイの転)カレイ科の硬骨魚の総称。体は扁平で卵形、頭部はねじれて、眼は普通、体の右側に集まる(ヒラメでは、眼は左側)。眼のある側は褐色で海底の色に似、眼のない側は白色。砂底に生息。多くの種類がある。食用。倭名類聚鈔19「王余魚、和名加良衣比、俗云加礼比」
かれ‐い【餉】‥ヒ
(カレイヒ(乾飯)の約)旅行のときなどに携帯した干した飯。転じて、広く携帯用食料にもいう。万葉集5「いかにか行かむ―はなしに」
⇒かれい‐け【餉笥・樏子】
⇒かれい‐つけ【餉付】
か‐れい【下隷】
しもべ。
か‐れい【加齢】
①新年または誕生日を迎えて年齢を増すこと。加年。
②年老いること。
か‐れい【花翎】クワ‥
中国清朝で、皇族または官吏に与えた、帽子の後に垂れる孔雀の羽根の装飾。
か‐れい【佳麗】
①美しいこと。きれいなこと。「―を競う」
②[白楽天、長恨歌]美女。
か‐れい【苛令】
きびしい法令。むごいおきて。
か‐れい【家令】
①(ケリョウとも)律令制で、親王・内親王・三位以上などの家で家務・会計を管理した人。のち家司けいしが置かれてからは有名無実となった。
②明治以後、宮家や華族の家務を管理し、家扶以下を監督した者。
か‐れい【家例】
その家に代々伝わるしきたり。
か‐れい【家隷】
一家に隷属する者。けらい。しもべ。
か‐れい【華麗】クワ‥
はなやかで美しいこと。「―な演技」
か‐れい【遐齢】
長生き。長寿。「―延年」
か‐れい【嘉礼】
めでたい礼式。
か‐れい【嘉例・佳例】
①めでたい先例。吉例。嘉躅かちょく。
②通例。例。狂言、宗論「―の情ごはでござる」
か‐れい【嘉齢】
めでたい長寿。
かれ‐いい【餉・乾飯】‥イヒ
(→)「かれい」に同じ。伊勢物語「―の上に涙おとしてほとびにけり」
か‐れいきゃく【過冷却】クワ‥
気体や液体をその沸点や融点以下に冷やしてもなお気体や液体の状態にあること。過冷。
かれい‐け【餉笥・樏子】‥ヒ‥
餉を入れる笥け。弁当箱。わりご。〈倭名類聚鈔14〉
⇒かれ‐い【餉】
かれい‐つけ【餉付】‥ヒ‥
(旅行の際、餉を結びつけたからいう)鞍の後輪しずわの左右の四緒手しおでに付けた長い紐。ものつけ。〈倭名類聚鈔15〉
⇒かれ‐い【餉】
かれ‐いばら【枯茨】
冬になって葉が枯れ落ちた茨。〈[季]冬〉
かれ‐いろ【枯色】
①草木などの枯れた色。
Munsell color system: 10YR7.5/4.5
②襲かさねの色目。表は白、裏は薄紫、あるいは中倍なかべに朽葉を入れる。または、表は香こう、裏は青。
かれ‐うお【涸魚】‥ウヲ
日に干した魚。ひもの。ほしうお。
カレー【Calais】
フランス北部の都市。ドーヴァー海峡に臨むイギリスとの連絡港。レースの産地。
カレー【curry】
(タミール語でソースの意のkariから)
①(→)カレー粉に同じ。
②カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。「ビーフ‐―」
③「カレーライス」「ライスカレー」の略。
⇒カレー‐こ【カレー粉】
⇒カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
ガレー【galley】
古代から近代まで地中海で使用された軍船。両舷に多数の櫂かいを出して漕ぎ、櫂を2段・3段に配置することもあった。帆を備えた船もある。ガリー。ガレー船。
カレー‐こ【カレー粉】
黄褐色で粉末状の、辛味の強い混合香辛料。ウコン・コエンドロ・コショウ・ショウガ・トウガラシ・カラシ・オールスパイス・チョウジなど多種の香辛料を配合して作る。インドが主産地。カレー。カリー。
⇒カレー【curry】
ガレージ【garage】
自動車の車庫。ギャレージ。
⇒ガレージ‐セール【garage sale】
ガレージ‐セール【garage sale】
家庭で不用な品を自宅のガレージなどで売ること。
⇒ガレージ【garage】
カレーズ【karēz ペルシア】
(→)カナートに同じ。
かれ‐えだ【枯枝】
枯れた木の枝。また、葉の落ちてしまった木の枝。〈[季]冬〉
カレードスコープ【kaleidoscope】
万華鏡まんげきょう。百色めがね。
カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
肉・野菜などをカレーの風味をつけて煮込み、飯の上にかけた料理。本来インドの料理であるカレーが、日本独自の料理として定着したもの。ライスカレー。
⇒カレー【curry】
かれ‐おばな【枯尾花】‥ヲ‥
すすきの穂が枯れたもの。〈[季]冬〉。「狐火の燃えつくばかり―」(蕪村)
枯尾花
撮影:関戸 勇
 かれおばな【枯尾華】‥ヲ‥
俳諧集。宝井其角編。2冊。1694年(元禄7)刊。其角の「芭蕉翁終焉記」および芭蕉門人の追善句・連句などを収める。
ガレオン【galleon】
16世紀からスペインなどで外国貿易に使用した典型的帆船。ガリアン船。
かれ‐がし【彼某】
〔代〕
(不定称)名を知らない人、名を言う必要のない人にいう語。宇治拾遺物語14「また何者か候といへば、それがし―といふ」
かれ‐がた【枯れ方】
草木の枯れかかる頃。
かれ‐がた【離れ方】
とだえがちになる頃。多く、男女の仲についていう。古今和歌集恋「あひしりて侍りけるを―になりにければ」
かれ‐がれ【枯れ枯れ】
草木の枯れようとするさま。狭衣物語4「野辺の草どもも皆―になりて」
かれ‐がれ【涸れ涸れ】
水などのかれたさま。夫木和歌抄27「小車のわだちの水の―に」
かれ‐がれ【嗄れ嗄れ】
声のしわがれたさま。続拾遺和歌集秋「虫のねも―になるながつきの」
かれ‐がれ【離れ離れ】
交際が疎遠になるさま。源氏物語帚木「うち頼むべくも見えず、―にのみ見せ侍るほどに」
かれ‐がわ【涸れ川】‥ガハ
降雨のとき以外は水が流れない川。水無し川。
かれ‐き【枯木】
枯れた木。また、落葉した樹木。〈[季]冬〉
⇒枯木に花
⇒枯木も山の賑わい
が‐れき【瓦礫】グワ‥
①瓦と小石。「―の山」「―と化す」
②価値のないもののたとえ。
かれき‐がく【花暦学】クワ‥
(phenology)気候・気象の時期的変化を、自然界における生物現象と関連づけて研究する学問。生物季節学。
かれ‐ぎく【枯菊】
冬枯れした菊。〈[季]冬〉
かれおばな【枯尾華】‥ヲ‥
俳諧集。宝井其角編。2冊。1694年(元禄7)刊。其角の「芭蕉翁終焉記」および芭蕉門人の追善句・連句などを収める。
ガレオン【galleon】
16世紀からスペインなどで外国貿易に使用した典型的帆船。ガリアン船。
かれ‐がし【彼某】
〔代〕
(不定称)名を知らない人、名を言う必要のない人にいう語。宇治拾遺物語14「また何者か候といへば、それがし―といふ」
かれ‐がた【枯れ方】
草木の枯れかかる頃。
かれ‐がた【離れ方】
とだえがちになる頃。多く、男女の仲についていう。古今和歌集恋「あひしりて侍りけるを―になりにければ」
かれ‐がれ【枯れ枯れ】
草木の枯れようとするさま。狭衣物語4「野辺の草どもも皆―になりて」
かれ‐がれ【涸れ涸れ】
水などのかれたさま。夫木和歌抄27「小車のわだちの水の―に」
かれ‐がれ【嗄れ嗄れ】
声のしわがれたさま。続拾遺和歌集秋「虫のねも―になるながつきの」
かれ‐がれ【離れ離れ】
交際が疎遠になるさま。源氏物語帚木「うち頼むべくも見えず、―にのみ見せ侍るほどに」
かれ‐がわ【涸れ川】‥ガハ
降雨のとき以外は水が流れない川。水無し川。
かれ‐き【枯木】
枯れた木。また、落葉した樹木。〈[季]冬〉
⇒枯木に花
⇒枯木も山の賑わい
が‐れき【瓦礫】グワ‥
①瓦と小石。「―の山」「―と化す」
②価値のないもののたとえ。
かれき‐がく【花暦学】クワ‥
(phenology)気候・気象の時期的変化を、自然界における生物現象と関連づけて研究する学問。生物季節学。
かれ‐ぎく【枯菊】
冬枯れした菊。〈[季]冬〉
 カルパッチオ【Vittore Carpaccio】
イタリア、ヴェネツィア派の画家。ベッリーニ兄弟の門人。風景描写にすぐれた。作「聖女ウルスラ物語」など。(1455頃〜1525頃)
カルパッチオ
提供:Maxppp/APL
カルパッチオ【Vittore Carpaccio】
イタリア、ヴェネツィア派の画家。ベッリーニ兄弟の門人。風景描写にすぐれた。作「聖女ウルスラ物語」など。(1455頃〜1525頃)
カルパッチオ
提供:Maxppp/APL
 「エルサレムで説教する聖エティエンヌ」
提供:Photos12/APL
「エルサレムで説教する聖エティエンヌ」
提供:Photos12/APL
 カルパッチョ【carpaccio イタリア】
(画家カルパッチオに因む)生の牛肉を薄切りにし、ソースやドレッシングで調味したイタリア料理。牛以外の肉や魚でも作る。
カルバドス【calvados フランス】
リンゴから作るブランデー。フランス、ノルマンディー地方カルヴァドス県で生産されるのでこの名がある。
ガルバノメーター【galvanometer】
(→)検流計のこと。
カルバラー【Karbalā'】
イラク中央部の都市。ナジャフとならぶイスラム教シーア派の聖地。680年アリーの息子フサインが殺された地。人口29万6千(1987)。
ガルバンソ【garbanzo スペイン】
〔植〕(→)ひよこまめ。
カルビ
(朝鮮語kalbi)ばら肉のこと。焼肉・煮込みなどに用いる。
カルピーニ【Giovanni de Piano Carpini】
イタリア人。フランシスコ会修道士。1245年、教皇の命をうけモンゴルに赴き、47年リヨンに帰着。その旅行記がある。(1182頃〜1252)
カルピス【Calpis】
乳酸菌飲料の一種。脱脂乳を乳酸発酵させ、砂糖・香料などを加えたもの。希釈して飲む。商標名。
かる・ぶ【軽ぶ】
〔自上二〕
「かろぶ」に同じ。
ガルブレイス【John Kenneth Galbraith】
制度学派の流れをひくアメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。全米経済学会会長。著「ゆたかな社会」「新しい産業国家」「満足の文化」など。(1908〜2006)
カルペンティエール【Alejo Carpentier】
キューバの作家。時間の魔術師と呼ばれる。作「失われた足跡」「光の世紀」など。(1904〜1980)
ガルボ【Greta Garbo】
スウェーデン生れの女優。「肉体と悪魔」「アンナ=カレーニナ」などアメリカ映画に出演。36歳で引退、伝説的存在となる。(1905〜1990)
カルポー【Jean Baptiste Carpeaux】
フランス、ロマン派の彫刻家。リュードの後継者。(1827〜1875)
カルボキシ‐き【カルボキシ基】
〔化〕(carboxyl group)1価の基。化学式‐COOH カルボキシル基。
カルホス【Karphos】
有機燐系殺虫剤イソキサチオン剤の商品名。劇物。急性経口毒性(マウス)LD50は242。アオムシ・カイガラムシ・ヨトウムシなど幅広く害虫に用いる。
カルボナード【carbonado スペイン】
ブラジル産の暗灰色または黒色ダイヤモンド。不純物を含み、主に削岩機に使う。
カルボナーラ【carbonara イタリア】
ベーコン・チーズ・卵などで作るソースであえ、黒胡椒をふったイタリア料理。「スパゲッティ‐―」
カルボナリ【Carbonari フランス】
(炭焼すみやきの意)19世紀前半のイタリアの秘密結社。ナポリを中心に南イタリアに広がり、オーストリアに抗して祖国の統一と独立を目ざし、反乱を起こした。
カルボニル‐き【カルボニル基】
〔化〕(carbonyl group)2価の官能基>C=Oをいう。この基に二つの炭化水素基が結合した化合物をケトン、水素原子と炭化水素基が結合した化合物をアルデヒドと総称する。
カルボン‐さん【カルボン酸】
(carboxylic acid)カルボキシ基をもつ有機酸の総称。酢酸・安息香酸の類。カルボキシ酸。
カルマ【karman 梵】
〔仏〕
⇒ごう(業)
カルマル‐どうめい【カルマル同盟】
中世、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン三国の同君連合。1389年、スウェーデン南部の都市カルマル(Kalmar)で三国の貴族が同一の国王を選出したのが正式の始まりで、15世紀前半まで続く。カルマル連合。
カルマン‐うず【カルマン渦】‥ウヅ
流体中で柱状物体を動かすとき、物体の両側から交互に反対向きに生じて規則正しく並ぶ渦。風の吹く日に電線がうなりを生ずる原因。アメリカの航空力学者カルマン(T. von Kármán1881〜1963)が理論的に研究。
かる‐み【軽み】
蕉風俳諧で重んじた作風の一つ。移り行く現実に応じた、とどこおらない軽やかさを把握しようとする理念。去来抄「そこもと随分―をとり失ふべからず」
カルミア【Kalmia ラテン】
広義にはツツジ科の一属(その学名)。北アメリカ原産。また、同属の観賞用常緑低木。シャクナゲに似た葉を枝先に輪生。初夏に枝端に多数の白花を束状につける。花冠は盃状で赤紫の斑点がめだつ。アメリカシャクナゲ。
カルミア(花)
撮影:関戸 勇
カルパッチョ【carpaccio イタリア】
(画家カルパッチオに因む)生の牛肉を薄切りにし、ソースやドレッシングで調味したイタリア料理。牛以外の肉や魚でも作る。
カルバドス【calvados フランス】
リンゴから作るブランデー。フランス、ノルマンディー地方カルヴァドス県で生産されるのでこの名がある。
ガルバノメーター【galvanometer】
(→)検流計のこと。
カルバラー【Karbalā'】
イラク中央部の都市。ナジャフとならぶイスラム教シーア派の聖地。680年アリーの息子フサインが殺された地。人口29万6千(1987)。
ガルバンソ【garbanzo スペイン】
〔植〕(→)ひよこまめ。
カルビ
(朝鮮語kalbi)ばら肉のこと。焼肉・煮込みなどに用いる。
カルピーニ【Giovanni de Piano Carpini】
イタリア人。フランシスコ会修道士。1245年、教皇の命をうけモンゴルに赴き、47年リヨンに帰着。その旅行記がある。(1182頃〜1252)
カルピス【Calpis】
乳酸菌飲料の一種。脱脂乳を乳酸発酵させ、砂糖・香料などを加えたもの。希釈して飲む。商標名。
かる・ぶ【軽ぶ】
〔自上二〕
「かろぶ」に同じ。
ガルブレイス【John Kenneth Galbraith】
制度学派の流れをひくアメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。全米経済学会会長。著「ゆたかな社会」「新しい産業国家」「満足の文化」など。(1908〜2006)
カルペンティエール【Alejo Carpentier】
キューバの作家。時間の魔術師と呼ばれる。作「失われた足跡」「光の世紀」など。(1904〜1980)
ガルボ【Greta Garbo】
スウェーデン生れの女優。「肉体と悪魔」「アンナ=カレーニナ」などアメリカ映画に出演。36歳で引退、伝説的存在となる。(1905〜1990)
カルポー【Jean Baptiste Carpeaux】
フランス、ロマン派の彫刻家。リュードの後継者。(1827〜1875)
カルボキシ‐き【カルボキシ基】
〔化〕(carboxyl group)1価の基。化学式‐COOH カルボキシル基。
カルホス【Karphos】
有機燐系殺虫剤イソキサチオン剤の商品名。劇物。急性経口毒性(マウス)LD50は242。アオムシ・カイガラムシ・ヨトウムシなど幅広く害虫に用いる。
カルボナード【carbonado スペイン】
ブラジル産の暗灰色または黒色ダイヤモンド。不純物を含み、主に削岩機に使う。
カルボナーラ【carbonara イタリア】
ベーコン・チーズ・卵などで作るソースであえ、黒胡椒をふったイタリア料理。「スパゲッティ‐―」
カルボナリ【Carbonari フランス】
(炭焼すみやきの意)19世紀前半のイタリアの秘密結社。ナポリを中心に南イタリアに広がり、オーストリアに抗して祖国の統一と独立を目ざし、反乱を起こした。
カルボニル‐き【カルボニル基】
〔化〕(carbonyl group)2価の官能基>C=Oをいう。この基に二つの炭化水素基が結合した化合物をケトン、水素原子と炭化水素基が結合した化合物をアルデヒドと総称する。
カルボン‐さん【カルボン酸】
(carboxylic acid)カルボキシ基をもつ有機酸の総称。酢酸・安息香酸の類。カルボキシ酸。
カルマ【karman 梵】
〔仏〕
⇒ごう(業)
カルマル‐どうめい【カルマル同盟】
中世、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン三国の同君連合。1389年、スウェーデン南部の都市カルマル(Kalmar)で三国の貴族が同一の国王を選出したのが正式の始まりで、15世紀前半まで続く。カルマル連合。
カルマン‐うず【カルマン渦】‥ウヅ
流体中で柱状物体を動かすとき、物体の両側から交互に反対向きに生じて規則正しく並ぶ渦。風の吹く日に電線がうなりを生ずる原因。アメリカの航空力学者カルマン(T. von Kármán1881〜1963)が理論的に研究。
かる‐み【軽み】
蕉風俳諧で重んじた作風の一つ。移り行く現実に応じた、とどこおらない軽やかさを把握しようとする理念。去来抄「そこもと随分―をとり失ふべからず」
カルミア【Kalmia ラテン】
広義にはツツジ科の一属(その学名)。北アメリカ原産。また、同属の観賞用常緑低木。シャクナゲに似た葉を枝先に輪生。初夏に枝端に多数の白花を束状につける。花冠は盃状で赤紫の斑点がめだつ。アメリカシャクナゲ。
カルミア(花)
撮影:関戸 勇
 カルミナ‐ブラーナ【Carmina Burana ラテン】
(ボイレンの歌の意)
①ラテン語と一部ドイツ語で書かれた13世紀の世俗歌集。恋・酒・賭事・諷刺を題材とする遍歴学生の歌など約300を収録。南ドイツのボイレンのベネディクト修道院で発見されたので、こう呼ばれる。
②ドイツのオルフが1936年に、1の歌集から24編の詩を選んで作曲した舞台形式オラトリオ。
カルミン【karmijn オランダ】
中南米の砂漠地に産するサボテンに寄生するコチニール虫(エンジムシの一種)の雌の体から製した鮮麗な紅色の色素。その成分であるカルミン酸はアントラキノン誘導体である。日本画の絵具、赤インクの製造または飲食物の着色、また、友禅染の染料、化粧料に用いる。また生物学などで組織染色に使用。洋紅。コチニール。カーミン。
かる・む【軽む】
〔他下二・自四〕
「かろむ」に同じ。
かる‐め【軽目】
①目方の軽いこと。
②軽目墨の略。
③⇒カルメ。
⇒かるめ‐きん【軽目金】
⇒かるめ‐ずみ【軽目墨】
⇒かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】
⇒かるめ‐やき【軽目焼】
カルメ
「カルメラ」「カルメル」の略。「軽目」と当てる。
かるめ‐きん【軽目金】
量目の減った小判や一分金。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐ずみ【軽目墨】
掃墨はいずみに豆汁ごじるをまぜ、藍鼠色の染料としたもの。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】‥ヘ
目方の軽い羽二重。片羽二重。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐やき【軽目焼】
⇒カルメラ
⇒かる‐め【軽目】
カルメラ【caramelo ポルトガル・ スペイン】
氷砂糖に卵の白身を加え、煮て泡立たせ、そのまま固まらせた軽石状の菓子。今はざらめ糖に重曹を加えて作る。軽目焼。浮石糖。泡糖。カルメル。カルメロ。カルメ。カルメイラ。
カルメル
⇒カルメラ
カルメル‐かい【カルメル会】‥クワイ
(Ordo Fratrum Carmelitarum ラテン)カトリック観想修道会の一つ。12世紀以来パレスチナのカルメル山に住み始めたラテン系隠修士団が托鉢修道会として認可され、1238年頃西欧へ移住したもの。16世紀アビラのテレサと十字架の聖ヨハネの刷新運動の結果、跣足せんそくカルメル会が創立。
カルメン【Carmen】
①メリメの小説。1845年刊。スペインを舞台に、ジプシー女カルメンと竜騎隊の伍長ドン=ホセとの恋愛葛藤の悲劇を描く。
②1によってビゼーが作曲した歌劇。4幕。1875年パリで初演。
ビゼー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
カルミナ‐ブラーナ【Carmina Burana ラテン】
(ボイレンの歌の意)
①ラテン語と一部ドイツ語で書かれた13世紀の世俗歌集。恋・酒・賭事・諷刺を題材とする遍歴学生の歌など約300を収録。南ドイツのボイレンのベネディクト修道院で発見されたので、こう呼ばれる。
②ドイツのオルフが1936年に、1の歌集から24編の詩を選んで作曲した舞台形式オラトリオ。
カルミン【karmijn オランダ】
中南米の砂漠地に産するサボテンに寄生するコチニール虫(エンジムシの一種)の雌の体から製した鮮麗な紅色の色素。その成分であるカルミン酸はアントラキノン誘導体である。日本画の絵具、赤インクの製造または飲食物の着色、また、友禅染の染料、化粧料に用いる。また生物学などで組織染色に使用。洋紅。コチニール。カーミン。
かる・む【軽む】
〔他下二・自四〕
「かろむ」に同じ。
かる‐め【軽目】
①目方の軽いこと。
②軽目墨の略。
③⇒カルメ。
⇒かるめ‐きん【軽目金】
⇒かるめ‐ずみ【軽目墨】
⇒かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】
⇒かるめ‐やき【軽目焼】
カルメ
「カルメラ」「カルメル」の略。「軽目」と当てる。
かるめ‐きん【軽目金】
量目の減った小判や一分金。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐ずみ【軽目墨】
掃墨はいずみに豆汁ごじるをまぜ、藍鼠色の染料としたもの。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐はぶたえ【軽目羽二重】‥ヘ
目方の軽い羽二重。片羽二重。
⇒かる‐め【軽目】
かるめ‐やき【軽目焼】
⇒カルメラ
⇒かる‐め【軽目】
カルメラ【caramelo ポルトガル・ スペイン】
氷砂糖に卵の白身を加え、煮て泡立たせ、そのまま固まらせた軽石状の菓子。今はざらめ糖に重曹を加えて作る。軽目焼。浮石糖。泡糖。カルメル。カルメロ。カルメ。カルメイラ。
カルメル
⇒カルメラ
カルメル‐かい【カルメル会】‥クワイ
(Ordo Fratrum Carmelitarum ラテン)カトリック観想修道会の一つ。12世紀以来パレスチナのカルメル山に住み始めたラテン系隠修士団が托鉢修道会として認可され、1238年頃西欧へ移住したもの。16世紀アビラのテレサと十字架の聖ヨハネの刷新運動の結果、跣足せんそくカルメル会が創立。
カルメン【Carmen】
①メリメの小説。1845年刊。スペインを舞台に、ジプシー女カルメンと竜騎隊の伍長ドン=ホセとの恋愛葛藤の悲劇を描く。
②1によってビゼーが作曲した歌劇。4幕。1875年パリで初演。
ビゼー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
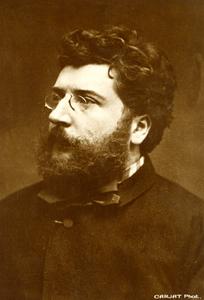 →歌劇「カルメン」 闘牛士
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
かる‐も【刈藻】
刈り取った藻。伊勢物語「恋ひわびぬ蜑あまの―に宿るてふわれから身をもくだきつるかな」
かる‐も【枯草】
かれくさ。夫木和歌抄27「秋の野の―がしたに月もりて」
⇒かるも‐かく【枯草掻く】
かるも‐かく【枯草掻く】
〔枕〕
(猪が枯草を集めて寝床とすることから)「ゐ(猪)」にかかる。
⇒かる‐も【枯草】
カルモジュリン【calmodulin】
真核細胞に存在し、カルシウム‐イオンと特異的に結合する蛋白質の一つ。垣内史朗(1929〜1984)らが発見。カルシウムを結合したカルモジュリンは細胞内のさまざまな酵素に結合し、それを活性化する。
カルモチン【Calmotin】
鎮静催眠剤として用いられたブロムワレリル尿素の商品名。
かる‐もの【軽物】
目方が軽い物の意で、絹布の称。今昔物語集28「粮かても少し有り、―も人要すばかりのものは少々有り」
⇒かるもの‐ぐら【軽物蔵】
かるもの‐ぐら【軽物蔵】
軽物を入れる蔵。狂言、三人片輪「汝が前に有るは―ぢや」
⇒かる‐もの【軽物】
かる‐やか【軽やか】
(→)「かろやか」に同じ。
かる‐やき【軽焼】
軽焼煎餅の略。
⇒かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
糯米もちごめの粉に砂糖を加え、いったん蒸して乾燥させ、これを焼いてふくれるようにした煎餅。
⇒かる‐やき【軽焼】
かる‐ゆき【軽行き】
手軽なこと。たやすく事が進むこと。好色一代女1「一人を金一角に定め置きしは―なる呼びものなり」
かるら【迦楼羅】
(梵語Garuḍa)インド神話における巨鳥で、竜を憎んで食べるという。仏教に入って天竜八部衆の一つとして、仏法の守護神とされる。翼は金色、頭には如意珠があり、常に口から火焔を吐く。金翅こんじ鳥。妙翅鳥。→ガルダ→伎楽面ぎがくめん(図)。
迦楼羅
→歌劇「カルメン」 闘牛士
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
かる‐も【刈藻】
刈り取った藻。伊勢物語「恋ひわびぬ蜑あまの―に宿るてふわれから身をもくだきつるかな」
かる‐も【枯草】
かれくさ。夫木和歌抄27「秋の野の―がしたに月もりて」
⇒かるも‐かく【枯草掻く】
かるも‐かく【枯草掻く】
〔枕〕
(猪が枯草を集めて寝床とすることから)「ゐ(猪)」にかかる。
⇒かる‐も【枯草】
カルモジュリン【calmodulin】
真核細胞に存在し、カルシウム‐イオンと特異的に結合する蛋白質の一つ。垣内史朗(1929〜1984)らが発見。カルシウムを結合したカルモジュリンは細胞内のさまざまな酵素に結合し、それを活性化する。
カルモチン【Calmotin】
鎮静催眠剤として用いられたブロムワレリル尿素の商品名。
かる‐もの【軽物】
目方が軽い物の意で、絹布の称。今昔物語集28「粮かても少し有り、―も人要すばかりのものは少々有り」
⇒かるもの‐ぐら【軽物蔵】
かるもの‐ぐら【軽物蔵】
軽物を入れる蔵。狂言、三人片輪「汝が前に有るは―ぢや」
⇒かる‐もの【軽物】
かる‐やか【軽やか】
(→)「かろやか」に同じ。
かる‐やき【軽焼】
軽焼煎餅の略。
⇒かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
かるやき‐せんべい【軽焼煎餅】
糯米もちごめの粉に砂糖を加え、いったん蒸して乾燥させ、これを焼いてふくれるようにした煎餅。
⇒かる‐やき【軽焼】
かる‐ゆき【軽行き】
手軽なこと。たやすく事が進むこと。好色一代女1「一人を金一角に定め置きしは―なる呼びものなり」
かるら【迦楼羅】
(梵語Garuḍa)インド神話における巨鳥で、竜を憎んで食べるという。仏教に入って天竜八部衆の一つとして、仏法の守護神とされる。翼は金色、頭には如意珠があり、常に口から火焔を吐く。金翅こんじ鳥。妙翅鳥。→ガルダ→伎楽面ぎがくめん(図)。
迦楼羅
 ⇒かるら‐えん【迦楼羅炎】
⇒かるら‐ほう【迦楼羅法】
かるら‐えん【迦楼羅炎】
不動明王の光背の名称。カルラの羽根をひろげた形に似るからいう。
⇒かるら【迦楼羅】
かる‐らか【軽らか】
(→)「かろらか」に同じ。
かるら‐ほう【迦楼羅法】‥ホフ
密教で、迦楼羅を本尊とし、病苦・風雨・雷などを除くことを祈願する修法しゅほう。
⇒かるら【迦楼羅】
カルルス‐せんえん【カルルス泉塩】
(Karlsbader Salz ドイツ)チェコ西部カールスバート(現、カルロヴィ‐ヴァリ)の鉱泉(カルルス水)を結晶させた薬品。また、人工的には、硫酸ナトリウムに重曹・食塩・硫酸カリウムを加えて製した白色の粉末。緩下剤・消化剤。
カルルス‐せんべい【カルルス煎餅】
カルルス泉塩を加えて製した煎餅。
カルルック【Qarluq・葛邏禄】
古トルコ系民族の一つ。主に7〜12世紀に中央アジアで活躍。カルルク。
カルロヴィ‐ヴァリ【Karlovy Vary チェコ】
チェコ西部ボヘミアの都市。温泉とガラス細工で有名な観光地。ドイツ語名カールスバート。
かる‐わざ【軽業】
①困難なことや危険なことを身軽にやりこなすこと。尤之双紙もっとものそうし「あぶなき物のしなじな…老人の―」
②危険な曲芸を身軽に演じるもの。綱渡り・籠抜け・梯子はしご乗りの類。
③比喩的に、はなはだしく冒険的な計画または事業。「そんな―はやめろ」
⇒かるわざ‐し【軽業師】
⇒かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】
かるわざ‐し【軽業師】
①軽業2を職業として演ずる人。
②比喩的に、軽業3をする人。
⇒かる‐わざ【軽業】
かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】‥ギヤウ
紙製の人形を絓糸すがいとで操り、自然に動くように見せたもの。
⇒かる‐わざ【軽業】
かれ【枯れ】
草木が枯れること。万葉集16「海は潮干て山は―すれ」
かれ【涸れ】
水が涸れること。乾燥。
かれ【嗄れ】
声が嗄れること。しわがれ。
かれ【彼】
〔代〕
①あれ。あのもの。古くは人をも人以外のものをもさした。人の場合、男女ともにさした。万葉集11「たそ―と問はば答へむ」。万葉集18「わが思ふ君が御船かも―」
②(「かのじょ」に対し特に)あの男。その男。泉鏡花、妙の宮「士官は心剛ごうなりき。渠かれはつかつかと寄添ひぬ」
③転じて、愛人である男性。彼氏。
⇒彼と言い此れと言い
⇒彼も一時此れも一時
⇒彼も人なり我も人なり
⇒彼を知り己を知れば百戦殆からず
かれ【故】
〔接続〕
(カ(此)アレ(有リの已然形)の約、「かあれば」の意)
①(前段を承けて)こういうわけで。ゆえに。因明論疏四相違略註釈天永点「二他に通して用せらるとい、故カレ今臥具を以て」
②(段落の初めにおいて)さて。そこで。古事記上「―此の大国主神の兄弟あにおと、八十やそ神坐ましき」
がれ
谷川ぞいの路、あるいは山崩れで崖になった、石塊のがらがらした急斜面。なぎ。がれ場。
ガレ【Émile Gallé】
フランスの工芸家。アール‐ヌーヴォーを代表する一人。彩色・象眼等を施したガラス工芸と、寄木細工による優美な家具で知られる。(1846〜1904)
かれ‐あし【枯葦・枯蘆】
枯れた葦。特に、冬枯れした葦。〈[季]冬〉
かれい【鰈】カレヒ
(カラエイの転)カレイ科の硬骨魚の総称。体は扁平で卵形、頭部はねじれて、眼は普通、体の右側に集まる(ヒラメでは、眼は左側)。眼のある側は褐色で海底の色に似、眼のない側は白色。砂底に生息。多くの種類がある。食用。倭名類聚鈔19「王余魚、和名加良衣比、俗云加礼比」
かれ‐い【餉】‥ヒ
(カレイヒ(乾飯)の約)旅行のときなどに携帯した干した飯。転じて、広く携帯用食料にもいう。万葉集5「いかにか行かむ―はなしに」
⇒かれい‐け【餉笥・樏子】
⇒かれい‐つけ【餉付】
か‐れい【下隷】
しもべ。
か‐れい【加齢】
①新年または誕生日を迎えて年齢を増すこと。加年。
②年老いること。
か‐れい【花翎】クワ‥
中国清朝で、皇族または官吏に与えた、帽子の後に垂れる孔雀の羽根の装飾。
か‐れい【佳麗】
①美しいこと。きれいなこと。「―を競う」
②[白楽天、長恨歌]美女。
か‐れい【苛令】
きびしい法令。むごいおきて。
か‐れい【家令】
①(ケリョウとも)律令制で、親王・内親王・三位以上などの家で家務・会計を管理した人。のち家司けいしが置かれてからは有名無実となった。
②明治以後、宮家や華族の家務を管理し、家扶以下を監督した者。
か‐れい【家例】
その家に代々伝わるしきたり。
か‐れい【家隷】
一家に隷属する者。けらい。しもべ。
か‐れい【華麗】クワ‥
はなやかで美しいこと。「―な演技」
か‐れい【遐齢】
長生き。長寿。「―延年」
か‐れい【嘉礼】
めでたい礼式。
か‐れい【嘉例・佳例】
①めでたい先例。吉例。嘉躅かちょく。
②通例。例。狂言、宗論「―の情ごはでござる」
か‐れい【嘉齢】
めでたい長寿。
かれ‐いい【餉・乾飯】‥イヒ
(→)「かれい」に同じ。伊勢物語「―の上に涙おとしてほとびにけり」
か‐れいきゃく【過冷却】クワ‥
気体や液体をその沸点や融点以下に冷やしてもなお気体や液体の状態にあること。過冷。
かれい‐け【餉笥・樏子】‥ヒ‥
餉を入れる笥け。弁当箱。わりご。〈倭名類聚鈔14〉
⇒かれ‐い【餉】
かれい‐つけ【餉付】‥ヒ‥
(旅行の際、餉を結びつけたからいう)鞍の後輪しずわの左右の四緒手しおでに付けた長い紐。ものつけ。〈倭名類聚鈔15〉
⇒かれ‐い【餉】
かれ‐いばら【枯茨】
冬になって葉が枯れ落ちた茨。〈[季]冬〉
かれ‐いろ【枯色】
①草木などの枯れた色。
Munsell color system: 10YR7.5/4.5
②襲かさねの色目。表は白、裏は薄紫、あるいは中倍なかべに朽葉を入れる。または、表は香こう、裏は青。
かれ‐うお【涸魚】‥ウヲ
日に干した魚。ひもの。ほしうお。
カレー【Calais】
フランス北部の都市。ドーヴァー海峡に臨むイギリスとの連絡港。レースの産地。
カレー【curry】
(タミール語でソースの意のkariから)
①(→)カレー粉に同じ。
②カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。「ビーフ‐―」
③「カレーライス」「ライスカレー」の略。
⇒カレー‐こ【カレー粉】
⇒カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
ガレー【galley】
古代から近代まで地中海で使用された軍船。両舷に多数の櫂かいを出して漕ぎ、櫂を2段・3段に配置することもあった。帆を備えた船もある。ガリー。ガレー船。
カレー‐こ【カレー粉】
黄褐色で粉末状の、辛味の強い混合香辛料。ウコン・コエンドロ・コショウ・ショウガ・トウガラシ・カラシ・オールスパイス・チョウジなど多種の香辛料を配合して作る。インドが主産地。カレー。カリー。
⇒カレー【curry】
ガレージ【garage】
自動車の車庫。ギャレージ。
⇒ガレージ‐セール【garage sale】
ガレージ‐セール【garage sale】
家庭で不用な品を自宅のガレージなどで売ること。
⇒ガレージ【garage】
カレーズ【karēz ペルシア】
(→)カナートに同じ。
かれ‐えだ【枯枝】
枯れた木の枝。また、葉の落ちてしまった木の枝。〈[季]冬〉
カレードスコープ【kaleidoscope】
万華鏡まんげきょう。百色めがね。
カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
肉・野菜などをカレーの風味をつけて煮込み、飯の上にかけた料理。本来インドの料理であるカレーが、日本独自の料理として定着したもの。ライスカレー。
⇒カレー【curry】
かれ‐おばな【枯尾花】‥ヲ‥
すすきの穂が枯れたもの。〈[季]冬〉。「狐火の燃えつくばかり―」(蕪村)
枯尾花
撮影:関戸 勇
⇒かるら‐えん【迦楼羅炎】
⇒かるら‐ほう【迦楼羅法】
かるら‐えん【迦楼羅炎】
不動明王の光背の名称。カルラの羽根をひろげた形に似るからいう。
⇒かるら【迦楼羅】
かる‐らか【軽らか】
(→)「かろらか」に同じ。
かるら‐ほう【迦楼羅法】‥ホフ
密教で、迦楼羅を本尊とし、病苦・風雨・雷などを除くことを祈願する修法しゅほう。
⇒かるら【迦楼羅】
カルルス‐せんえん【カルルス泉塩】
(Karlsbader Salz ドイツ)チェコ西部カールスバート(現、カルロヴィ‐ヴァリ)の鉱泉(カルルス水)を結晶させた薬品。また、人工的には、硫酸ナトリウムに重曹・食塩・硫酸カリウムを加えて製した白色の粉末。緩下剤・消化剤。
カルルス‐せんべい【カルルス煎餅】
カルルス泉塩を加えて製した煎餅。
カルルック【Qarluq・葛邏禄】
古トルコ系民族の一つ。主に7〜12世紀に中央アジアで活躍。カルルク。
カルロヴィ‐ヴァリ【Karlovy Vary チェコ】
チェコ西部ボヘミアの都市。温泉とガラス細工で有名な観光地。ドイツ語名カールスバート。
かる‐わざ【軽業】
①困難なことや危険なことを身軽にやりこなすこと。尤之双紙もっとものそうし「あぶなき物のしなじな…老人の―」
②危険な曲芸を身軽に演じるもの。綱渡り・籠抜け・梯子はしご乗りの類。
③比喩的に、はなはだしく冒険的な計画または事業。「そんな―はやめろ」
⇒かるわざ‐し【軽業師】
⇒かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】
かるわざ‐し【軽業師】
①軽業2を職業として演ずる人。
②比喩的に、軽業3をする人。
⇒かる‐わざ【軽業】
かるわざ‐にんぎょう【軽業人形】‥ギヤウ
紙製の人形を絓糸すがいとで操り、自然に動くように見せたもの。
⇒かる‐わざ【軽業】
かれ【枯れ】
草木が枯れること。万葉集16「海は潮干て山は―すれ」
かれ【涸れ】
水が涸れること。乾燥。
かれ【嗄れ】
声が嗄れること。しわがれ。
かれ【彼】
〔代〕
①あれ。あのもの。古くは人をも人以外のものをもさした。人の場合、男女ともにさした。万葉集11「たそ―と問はば答へむ」。万葉集18「わが思ふ君が御船かも―」
②(「かのじょ」に対し特に)あの男。その男。泉鏡花、妙の宮「士官は心剛ごうなりき。渠かれはつかつかと寄添ひぬ」
③転じて、愛人である男性。彼氏。
⇒彼と言い此れと言い
⇒彼も一時此れも一時
⇒彼も人なり我も人なり
⇒彼を知り己を知れば百戦殆からず
かれ【故】
〔接続〕
(カ(此)アレ(有リの已然形)の約、「かあれば」の意)
①(前段を承けて)こういうわけで。ゆえに。因明論疏四相違略註釈天永点「二他に通して用せらるとい、故カレ今臥具を以て」
②(段落の初めにおいて)さて。そこで。古事記上「―此の大国主神の兄弟あにおと、八十やそ神坐ましき」
がれ
谷川ぞいの路、あるいは山崩れで崖になった、石塊のがらがらした急斜面。なぎ。がれ場。
ガレ【Émile Gallé】
フランスの工芸家。アール‐ヌーヴォーを代表する一人。彩色・象眼等を施したガラス工芸と、寄木細工による優美な家具で知られる。(1846〜1904)
かれ‐あし【枯葦・枯蘆】
枯れた葦。特に、冬枯れした葦。〈[季]冬〉
かれい【鰈】カレヒ
(カラエイの転)カレイ科の硬骨魚の総称。体は扁平で卵形、頭部はねじれて、眼は普通、体の右側に集まる(ヒラメでは、眼は左側)。眼のある側は褐色で海底の色に似、眼のない側は白色。砂底に生息。多くの種類がある。食用。倭名類聚鈔19「王余魚、和名加良衣比、俗云加礼比」
かれ‐い【餉】‥ヒ
(カレイヒ(乾飯)の約)旅行のときなどに携帯した干した飯。転じて、広く携帯用食料にもいう。万葉集5「いかにか行かむ―はなしに」
⇒かれい‐け【餉笥・樏子】
⇒かれい‐つけ【餉付】
か‐れい【下隷】
しもべ。
か‐れい【加齢】
①新年または誕生日を迎えて年齢を増すこと。加年。
②年老いること。
か‐れい【花翎】クワ‥
中国清朝で、皇族または官吏に与えた、帽子の後に垂れる孔雀の羽根の装飾。
か‐れい【佳麗】
①美しいこと。きれいなこと。「―を競う」
②[白楽天、長恨歌]美女。
か‐れい【苛令】
きびしい法令。むごいおきて。
か‐れい【家令】
①(ケリョウとも)律令制で、親王・内親王・三位以上などの家で家務・会計を管理した人。のち家司けいしが置かれてからは有名無実となった。
②明治以後、宮家や華族の家務を管理し、家扶以下を監督した者。
か‐れい【家例】
その家に代々伝わるしきたり。
か‐れい【家隷】
一家に隷属する者。けらい。しもべ。
か‐れい【華麗】クワ‥
はなやかで美しいこと。「―な演技」
か‐れい【遐齢】
長生き。長寿。「―延年」
か‐れい【嘉礼】
めでたい礼式。
か‐れい【嘉例・佳例】
①めでたい先例。吉例。嘉躅かちょく。
②通例。例。狂言、宗論「―の情ごはでござる」
か‐れい【嘉齢】
めでたい長寿。
かれ‐いい【餉・乾飯】‥イヒ
(→)「かれい」に同じ。伊勢物語「―の上に涙おとしてほとびにけり」
か‐れいきゃく【過冷却】クワ‥
気体や液体をその沸点や融点以下に冷やしてもなお気体や液体の状態にあること。過冷。
かれい‐け【餉笥・樏子】‥ヒ‥
餉を入れる笥け。弁当箱。わりご。〈倭名類聚鈔14〉
⇒かれ‐い【餉】
かれい‐つけ【餉付】‥ヒ‥
(旅行の際、餉を結びつけたからいう)鞍の後輪しずわの左右の四緒手しおでに付けた長い紐。ものつけ。〈倭名類聚鈔15〉
⇒かれ‐い【餉】
かれ‐いばら【枯茨】
冬になって葉が枯れ落ちた茨。〈[季]冬〉
かれ‐いろ【枯色】
①草木などの枯れた色。
Munsell color system: 10YR7.5/4.5
②襲かさねの色目。表は白、裏は薄紫、あるいは中倍なかべに朽葉を入れる。または、表は香こう、裏は青。
かれ‐うお【涸魚】‥ウヲ
日に干した魚。ひもの。ほしうお。
カレー【Calais】
フランス北部の都市。ドーヴァー海峡に臨むイギリスとの連絡港。レースの産地。
カレー【curry】
(タミール語でソースの意のkariから)
①(→)カレー粉に同じ。
②カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。「ビーフ‐―」
③「カレーライス」「ライスカレー」の略。
⇒カレー‐こ【カレー粉】
⇒カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
ガレー【galley】
古代から近代まで地中海で使用された軍船。両舷に多数の櫂かいを出して漕ぎ、櫂を2段・3段に配置することもあった。帆を備えた船もある。ガリー。ガレー船。
カレー‐こ【カレー粉】
黄褐色で粉末状の、辛味の強い混合香辛料。ウコン・コエンドロ・コショウ・ショウガ・トウガラシ・カラシ・オールスパイス・チョウジなど多種の香辛料を配合して作る。インドが主産地。カレー。カリー。
⇒カレー【curry】
ガレージ【garage】
自動車の車庫。ギャレージ。
⇒ガレージ‐セール【garage sale】
ガレージ‐セール【garage sale】
家庭で不用な品を自宅のガレージなどで売ること。
⇒ガレージ【garage】
カレーズ【karēz ペルシア】
(→)カナートに同じ。
かれ‐えだ【枯枝】
枯れた木の枝。また、葉の落ちてしまった木の枝。〈[季]冬〉
カレードスコープ【kaleidoscope】
万華鏡まんげきょう。百色めがね。
カレー‐ライス【curry and rice; curried rice】
肉・野菜などをカレーの風味をつけて煮込み、飯の上にかけた料理。本来インドの料理であるカレーが、日本独自の料理として定着したもの。ライスカレー。
⇒カレー【curry】
かれ‐おばな【枯尾花】‥ヲ‥
すすきの穂が枯れたもの。〈[季]冬〉。「狐火の燃えつくばかり―」(蕪村)
枯尾花
撮影:関戸 勇
 かれおばな【枯尾華】‥ヲ‥
俳諧集。宝井其角編。2冊。1694年(元禄7)刊。其角の「芭蕉翁終焉記」および芭蕉門人の追善句・連句などを収める。
ガレオン【galleon】
16世紀からスペインなどで外国貿易に使用した典型的帆船。ガリアン船。
かれ‐がし【彼某】
〔代〕
(不定称)名を知らない人、名を言う必要のない人にいう語。宇治拾遺物語14「また何者か候といへば、それがし―といふ」
かれ‐がた【枯れ方】
草木の枯れかかる頃。
かれ‐がた【離れ方】
とだえがちになる頃。多く、男女の仲についていう。古今和歌集恋「あひしりて侍りけるを―になりにければ」
かれ‐がれ【枯れ枯れ】
草木の枯れようとするさま。狭衣物語4「野辺の草どもも皆―になりて」
かれ‐がれ【涸れ涸れ】
水などのかれたさま。夫木和歌抄27「小車のわだちの水の―に」
かれ‐がれ【嗄れ嗄れ】
声のしわがれたさま。続拾遺和歌集秋「虫のねも―になるながつきの」
かれ‐がれ【離れ離れ】
交際が疎遠になるさま。源氏物語帚木「うち頼むべくも見えず、―にのみ見せ侍るほどに」
かれ‐がわ【涸れ川】‥ガハ
降雨のとき以外は水が流れない川。水無し川。
かれ‐き【枯木】
枯れた木。また、落葉した樹木。〈[季]冬〉
⇒枯木に花
⇒枯木も山の賑わい
が‐れき【瓦礫】グワ‥
①瓦と小石。「―の山」「―と化す」
②価値のないもののたとえ。
かれき‐がく【花暦学】クワ‥
(phenology)気候・気象の時期的変化を、自然界における生物現象と関連づけて研究する学問。生物季節学。
かれ‐ぎく【枯菊】
冬枯れした菊。〈[季]冬〉
かれおばな【枯尾華】‥ヲ‥
俳諧集。宝井其角編。2冊。1694年(元禄7)刊。其角の「芭蕉翁終焉記」および芭蕉門人の追善句・連句などを収める。
ガレオン【galleon】
16世紀からスペインなどで外国貿易に使用した典型的帆船。ガリアン船。
かれ‐がし【彼某】
〔代〕
(不定称)名を知らない人、名を言う必要のない人にいう語。宇治拾遺物語14「また何者か候といへば、それがし―といふ」
かれ‐がた【枯れ方】
草木の枯れかかる頃。
かれ‐がた【離れ方】
とだえがちになる頃。多く、男女の仲についていう。古今和歌集恋「あひしりて侍りけるを―になりにければ」
かれ‐がれ【枯れ枯れ】
草木の枯れようとするさま。狭衣物語4「野辺の草どもも皆―になりて」
かれ‐がれ【涸れ涸れ】
水などのかれたさま。夫木和歌抄27「小車のわだちの水の―に」
かれ‐がれ【嗄れ嗄れ】
声のしわがれたさま。続拾遺和歌集秋「虫のねも―になるながつきの」
かれ‐がれ【離れ離れ】
交際が疎遠になるさま。源氏物語帚木「うち頼むべくも見えず、―にのみ見せ侍るほどに」
かれ‐がわ【涸れ川】‥ガハ
降雨のとき以外は水が流れない川。水無し川。
かれ‐き【枯木】
枯れた木。また、落葉した樹木。〈[季]冬〉
⇒枯木に花
⇒枯木も山の賑わい
が‐れき【瓦礫】グワ‥
①瓦と小石。「―の山」「―と化す」
②価値のないもののたとえ。
かれき‐がく【花暦学】クワ‥
(phenology)気候・気象の時期的変化を、自然界における生物現象と関連づけて研究する学問。生物季節学。
かれ‐ぎく【枯菊】
冬枯れした菊。〈[季]冬〉
しゃく‐い【借位】‥ヰ🔗⭐🔉
しゃく‐い【借位】‥ヰ
①古代、位の低い者が仮に位階を授けられること。貴人との謁見、外国派遣、外使接伴などの際に行う。
②勅許を受けるまでの間、国司が仮にその管内の神社に位階を授けること。
しゃく‐おん【借音】🔗⭐🔉
しゃく‐おん【借音】
漢字を、意味に関係なく音だけを借りて日本語の表記に使用すること。「やま(山)」を「夜麻」と書く類。→万葉仮名
しゃく‐ぎん【借銀】🔗⭐🔉
しゃく‐ぎん【借銀】
銀子ぎんすすなわち金銭を借りること。また、借りた銀子。借金。狂言、胸突「―を負ひ」
しゃく‐けい【借景】🔗⭐🔉
しゃく‐けい【借景】
⇒しゃっけい
しゃく‐けん【借券】🔗⭐🔉
しゃく‐けん【借券】
⇒しゃっけん
しゃく‐ざい【借財】🔗⭐🔉
しゃく‐ざい【借財】
借金。借銭。「巨額の―を負う」
しゃく‐しょ【借書】🔗⭐🔉
しゃく‐しょ【借書】
借用の証書。太平記35「―を調へ判形を加へて」
しゃく‐じょう【借状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
しゃく‐じょう【借状】‥ジヤウ
借用の証書。狂言、八句連歌「それはそなたの書いた―ぢや」
しゃく‐せん【借銭】🔗⭐🔉
しゃく‐せん【借銭】
借金。借財。
⇒しゃくせん‐こい【借銭乞い】
しゃくせん‐こい【借銭乞い】‥コヒ🔗⭐🔉
しゃくせん‐こい【借銭乞い】‥コヒ
借金取り。
⇒しゃく‐せん【借銭】
しゃく‐たい【借貸】🔗⭐🔉
しゃく‐たい【借貸】
①かりかし。貸借。
②無利息で貸すこと。特に律令時代の朝廷が窮民救済のために農民に官稲を無利息で貸したこと。賑貸しんたい。↔出挙すいこ
しゃく‐たく【借宅】🔗⭐🔉
しゃく‐たく【借宅】
借家。かりや。武家義理物語「此所に―をもして」
しゃく‐ち【借地】🔗⭐🔉
しゃく‐ち【借地】
土地を借りること。また、借りた土地。
⇒しゃくち‐けん【借地権】
⇒しゃくち‐しゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】
⇒しゃくち‐しゃっか‐ほう【借地借家法】
⇒しゃくち‐ほう【借地法】
しゃく‐ま【借間】🔗⭐🔉
しゃく‐ま【借間】
部屋を借りること。また、借りた部屋。
しゃく‐や【借家・借屋】🔗⭐🔉
○借家栄えて母屋倒れるしゃくやさかえておもやたおれる🔗⭐🔉
○借家栄えて母屋倒れるしゃくやさかえておもやたおれる
恩徳をこうむった人が栄えて、恩徳を施した方の人がおちぶれる。「廂ひさしを貸して母屋を取られる」の類。
⇒しゃく‐や【借家・借屋】
しゃくや‐にん【借家人】
家主から家屋を借りて住んでいる人。店子たなこ。しゃっかにん。
⇒しゃく‐や【借家・借屋】
しゃくや‐ほう【借家法】‥ハフ
借家人の居住の安定を図るため1921年(大正10)に制定された法律。92年借地借家法の施行に伴い廃止。
⇒しゃく‐や【借家・借屋】
しゃく‐ゆう【爵邑】‥イフ
爵位と封邑ほうゆう。身分と領地。
しゃく‐よう【借用】
借りて使うこと。借りること。「無断で―する」「―金」
⇒しゃくよう‐ご【借用語】
⇒しゃくよう‐しょうしょ【借用証書】
しゃくよう‐ご【借用語】
(Lehnwort ドイツ)ある言語体系から別の言語体系へ取り入れられ、日常的に使われる外国語・古語・方言など。外来語と同義にも用いる。
⇒しゃく‐よう【借用】
しゃくよう‐しょうしょ【借用証書】
金銭または物品の借用を証明する証書。借用証。
⇒しゃく‐よう【借用】
じゃく‐ら【雀羅】
雀などを捕らえる網。とりあみ。「門前―を張る」
しゃく‐らん【灼爛】
あかくやけただれること。
しゃく‐らん【借覧】
書物などを借りて見ること。「秘蔵本を―する」「―に供する」
じゃくらん‐はん【雀卵斑】
そばかす。
しゃくり
(サクリ(決)の転)
①しゃくること。刳くること。
②そそのかすこと。おだてること。人情本、春色辰巳園「さし込むひとの―(癪をかける)をば口でけなして」
⇒しゃくり‐づり【しゃくり釣り】
⇒しゃくり‐びき【しゃくり引き】
しゃくり【噦り・吃逆】
(サクリの転)
①(→)「しゃっくり」に同じ。正法眼蔵随聞記6「世間に―する人」
②泣く時に声をひき入れるさま。すすりなき。
⇒しゃくり‐なき【噦り泣き】
しゃく‐り【赤痢】
⇒せきり。日葡辞書「ビャクリ(白痢)シャクリ」
しゃくり‐あ・げる【噦り上げる】
〔自下一〕[文]しゃくりあ・ぐ(下二)
息を急に吸い込むような声で、肩をふるわせて泣く。「いつまでも―・げる」
しゃくり‐づり【しゃくり釣り】
短い竿をしゃくりあげるように動かして魚を釣る方法。真鯛の代表的な釣り方の一つ。
⇒しゃくり
しゃくり‐なき【噦り泣き】
しゃくりあげて泣くこと。すすりなき。
⇒しゃくり【噦り・吃逆】
しゃくり‐びき【しゃくり引き】
すくい取るようにして引くこと。狂言、膏薬煉「―にしてやらう」
⇒しゃくり
しゃく‐りょう【借料】‥レウ
借り賃。
しゃく‐りょう【酌量】‥リヤウ
事情をくみとって同情すること。斟酌しんしゃくすること。「情状―」
⇒しゃくりょう‐げんけい【酌量減軽】
しゃく‐りょう【爵料】‥レウ
平安時代以降、栄爵(五位)を得るために出した料金。栄爵料。
しゃくりょう‐げんけい【酌量減軽】‥リヤウ‥
裁判所が犯罪の情状を酌量して、その刑を減軽すること。→情状
⇒しゃく‐りょう【酌量】
ジャグリング【juggling】
多くの玉や輪などを巧みに投げたり取ったりする曲芸。
しゃく・る【決る・刳る】
〔他五〕
(サク(決)ルの転)
①中がくぼむように刳くる。
②すくうように引き上げる。すくうように動かす。西鶴織留3「糸をしめてしづかに―・りける程に」。「あごを―・る」
③そそのかす。おだてる。洒落本、客衆肝照子きゃくしゅきもかがみ「アノ吉やらうが―・つたさうで、とんだあつくなつて来たから」
しゃく・る【噦る】
〔自五〕
(サクルの転)
①しゃっくりをする。
②すすり泣きをする。
シャクルトン【Ernest Henry Shackleton】
イギリスの南極探検家。1914〜16年、探検失敗とその後の奇跡的な生還で有名。(1874〜1922)
じゃく‐れい【弱齢・若齢】
年が若いこと。弱年。
しゃく・れる
〔自下一〕
中くぼみになっている。「―・れた顔」
じゃく‐れん【若恋】
若道じゃくどうの恋。若衆に対する恋。男色の恋。男色大鑑「―を忘れもやらず」
じゃくれん【寂蓮】
鎌倉初期の歌僧。俗名、藤原定長。叔父俊成の養子となったが、のち出家。歌合作者として活躍、撰者に選ばれながら新古今集撰進に先立って没。優美繊細で静寂を兼ねた巧緻な秀歌が多い。家集「寂蓮法師集」。( 〜1202)
じゃくろ【石榴】
⇒ざくろ。
⇒じゃくろ‐ざか【石榴ざか】
しゃく‐ろく【尺六】
1尺6寸(約48センチメートル)。また、その幅や長さのもの。「―の板」
しゃく‐ろく【爵禄】
爵位と俸禄。
⇒しゃくろく‐ほうこう【爵禄封侯】
しゃくろく‐ほうこう【爵禄封侯】
(謎語画題)雀と爵、鹿と禄、蜂と封、猴と侯とが各字音の通ずるところから、これらの動物を描いて出世を祝う意をこめた絵。
⇒しゃく‐ろく【爵禄】
じゃくろ‐ざか【石榴ざか】
ざくろの実に似た形の、鶏のとさか。〈日葡辞書〉
⇒じゃくろ【石榴】
しゃくろん【釈論】
「釈摩訶衍論しゃくまかえんろん」の略称。
しゃくや‐にん【借家人】🔗⭐🔉
しゃくや‐にん【借家人】
家主から家屋を借りて住んでいる人。店子たなこ。しゃっかにん。
⇒しゃく‐や【借家・借屋】
しゃくや‐ほう【借家法】‥ハフ🔗⭐🔉
しゃくや‐ほう【借家法】‥ハフ
借家人の居住の安定を図るため1921年(大正10)に制定された法律。92年借地借家法の施行に伴い廃止。
⇒しゃく‐や【借家・借屋】
しゃっ‐か【借家】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっ‐か【借家】シヤク‥
⇒しゃくや。
⇒しゃっか‐にん【借家人】
しゃっか‐にん【借家人】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっか‐にん【借家人】シヤク‥
⇒しゃくやにん。「―組合」
⇒しゃっ‐か【借家】
しゃっ‐かん【借款】シヤククワン🔗⭐🔉
しゃっ‐かん【借款】シヤククワン
(「款」は契約の条項の意)国際間の資金の貸借。政府借款と民間借款とに分ける。
しゃっ‐きょ【借居】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっ‐きょ【借居】シヤク‥
借家ずまい。
しゃっきん‐こい【借金乞い】シヤク‥コヒ🔗⭐🔉
しゃっきん‐こい【借金乞い】シヤク‥コヒ
借金取り。借銭乞い。
⇒しゃっ‐きん【借金】
しゃっきん‐とう【借金党】シヤク‥タウ🔗⭐🔉
しゃっきん‐とう【借金党】シヤク‥タウ
困民党こんみんとうの別称。
⇒しゃっ‐きん【借金】
しゃっきん‐とり【借金取り】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっきん‐とり【借金取り】シヤク‥
借金の返済を求めて取り立てに来る人。
⇒しゃっ‐きん【借金】
○借金を質に置くしゃっきんをしちにおく
(借金を質にしてまた借金をする意)無理な金銭の工面をする。
⇒しゃっ‐きん【借金】
○借金を質に置くしゃっきんをしちにおく🔗⭐🔉
○借金を質に置くしゃっきんをしちにおく
(借金を質にしてまた借金をする意)無理な金銭の工面をする。
⇒しゃっ‐きん【借金】
しゃっ‐く【赤口】シヤク‥
⇒しゃっこう
じゃっ‐く【惹句】ジヤク‥
(キャッチ‐フレーズの訳語)宣伝・広告などで人を引きつける文句。
ジャック【jack】
①トランプの絵札の一つ。兵士の姿を画いたもの。
②電気器具のさしこみ。また、さしこみ口。
③⇒ジャッキ。
⇒ジャック‐ナイフ【jackknife】
ジャック‐ダルクローズ【Émile Jaques-Dalcroze】
⇒ダルクローズ
ジャック‐ナイフ【jackknife】
①海軍ナイフ。大形の折畳み式ナイフ。
②棒高跳および水泳の飛び込みの型の一つ。海老えびとび。
⇒ジャック【jack】
しゃっくり【噦り・吃逆】
横隔膜の不時の収縮によって、空気が急に吸い込まれる時に発する特殊な音声。さくり。しゃくり。「―が止まらない」
ジャックリー‐の‐らん【ジャックリーの乱】
1358年フランスの北東部で起きた農民・都市民衆の一揆。百年戦争のなか、略奪や領主の戦時徴税に不満をもつ農民が蜂起し、一時パリ民衆とも合流したが、貴族軍に鎮圧された。ジャックリー(Jacquerie)は貴族の農民に対する蔑称ジャックに由来。
ジャッグル【juggle】
(「お手玉のような曲芸をする」の意から)野球で、野手が捕球する際、ボールを確実につかめずグラブやミットの中ではずませてしまうこと。
しゃっく‐るいとく【積功累徳】シヤク‥
〔仏〕悟りを求めるために、常に仏道修行をなし、功徳を積むこと。
しゃっ‐くん【借訓】シヤク‥
漢字の訓を、本来の意味に関係なく、同音の別語に転用すること。詠嘆の終助詞「かも」を「鴨」と書く類。→万葉仮名
しゃっ‐け【釈家】シヤク‥
①僧侶。また、仏門。仏家。
②経論の文義を解釈する学問僧。
しゃっ‐けい【借景】シヤク‥
庭園外の遠山や樹木をその庭のものであるかのように利用してあること。また、そのような造園法。
じゃっ‐けい【若契】ジヤク‥
若道じゃくどうの契り。男色の関係を結ぶこと。傾城禁短気「―浅からずして」
しゃっ‐けん【借券】シヤク‥
動産・不動産借用の証文。借状。借書。借用証文。
しゃっ‐こう【赤口】シヤク‥
①暦注の六輝の一つ。大凶の日。午うまの刻のみ吉という。
②(→)赤口日に同じ。
⇒しゃっこう‐にち【赤口日】
しゃっこう【赤光】シヤククワウ
斎藤茂吉の第1歌集。1913年(大正2)刊。近代的な抒情を緊密な調べに盛って、画期的な歌集といわれる。
→文献資料[赤光]
しゃっ‐こう【釈講】シヤクカウ
意義をときあかして聞かすこと。講釈。
じゃっ‐こう【弱行】ジヤクカウ
実行力の弱いこと。「薄志―」
じゃっ‐こう【寂光】ジヤククワウ
〔仏〕
①静寂な涅槃の境地から発する智慧の光。
②常寂光土じょうじゃっこうどの略。
⇒じゃっこう‐じょうど【寂光浄土】
⇒じゃっこう‐ど【寂光土】
じゃっこう‐いん【寂光院】ジヤククワウヰン
京都市左京区大原にある天台宗の尼寺。聖徳太子の創建という。平家滅亡後、安徳天皇の母建礼門院が隠棲して高倉・安徳両天皇および平家一門の冥福を祈った所。慶長(1596〜1615)年間淀君の本願で再興。2000年本堂が焼失したが、復元。
じゃっこう‐じょうど【寂光浄土】ジヤククワウジヤウ‥
(→)常寂光土に同じ。
⇒じゃっ‐こう【寂光】
じゃっこう‐ど【寂光土】ジヤククワウ‥
常寂光土の略。
⇒じゃっ‐こう【寂光】
しゃっこう‐にち【赤口日】シヤク‥
暦注で、各月の定日から8日ごとに繰り返し、公事・訴訟・契約などに凶という日。大赤たいしゃく。赤口。
⇒しゃっ‐こう【赤口】
じゃっ‐こく【弱国】ジヤク‥
国力の弱い国。
しゃっ‐こつ【尺骨】シヤク‥
前腕にある2本の骨のうち、小指側のもの。上腕骨と橈骨とうこつに連接。→骨格(図)
しゃっ‐こつ【灼骨】シヤク‥
(→)卜骨ぼっこつに同じ。
ジャッジ【judge】
①審判員。審査員。ボクシングやレスリングでは、レフェリーに対して副審をいう。
②審判。審査。判定。
⇒ジャッジ‐ペーパー【judge paper】
ジャッジ‐ペーパー【judge paper】
ボクシングやレスリングで審判が記入する採点用紙。スコアリング‐ペーパー。
⇒ジャッジ【judge】
ジャッジメント【judgment】
判断。審判。ジャッジ。
シャッター【shutter】
(閉じるものの意)
①防寒・防火・防盗・日除けなどのため、窓または入口の戸障子の外側または内側に設ける遮断扉。一般に、簾すだれ状で巻込み可能な金属製の鎧戸よろいどをいう。「―を下ろす」
②カメラで、感光材料に露光するために開閉する装置。「―を切る」
⇒シャッター‐チャンス
⇒シャッター‐どおり【シャッター通り】
シャッター‐チャンス
(和製語shutter chance)撮影で、シャッターを切るのに最もよい機会。特に、動作や表情の最もよい場面を捕らえる瞬間。「―をのがす」
⇒シャッター【shutter】
シャッター‐どおり【シャッター通り】‥ドホリ
(シャッターを下ろしたまま営業していない店舗が多いことから)さびれた商店街。
⇒シャッター【shutter】
しゃっちょこ‐だち【鯱立ち】
「しゃちほこだち」の転。
しゃっちょこ‐ば・る【鯱張る】
〔自五〕
「しゃちほこばる」の転。
しゃっ‐つら【しゃっ面】
(シャツラの促音化)顔をあしざまにいう語。浮世風呂4「家台やていぼねへ地震といふ―が」
しゃっ‐と
〔副〕
(→)「しゃんと」に同じ。閑吟集「―しておりやるこそ底は深けれ」
シャット‐アウト【shutout】
①閉めだすこと。「部外者を―する」
②野球で相手方を零敗させること。完封。
シャット‐ダウン【shutdown】
コンピューターで、システムを終了すること。
シャットル【shuttle】
(→)梭ひ。
じゃっぱ‐じる【じゃっぱ汁】
鱈のあら(じゃっぱ)に大根やねぎを加えた味噌や塩仕立ての汁物。青森県津軽地方の郷土料理。
しゃつ‐ばら【奴原】
数多くの者をののしっていう語。やつら。やつばら。太平記26「夫ぶを労らば、―を使ふべしとて」
⇒しゃつ【奴】
ジャップ【Jap】
(Japaneseの略)英語で、日本人を卑しめて呼ぶ語。
シャツ‐ブラウス
(shirt blouse)襟や袖口などを男物のワイシャツのように仕立てたブラウス。
⇒シャツ【shirt・襯衣】
しゃっぷり
水などを注ぎかけるさま。ざぶり。浄瑠璃、曾我会稽山「左手ゆんでへ回つて―、右手めてへ回つて又―」
シャッフル【shuffle】
トランプで、カードを切り混ぜること。
シャッポ【chapeau フランス】
つばのついた、多くはラシャの帽子。また、単に帽子。シャポー。福地桜痴、もしや草紙「其料見りょうけんまでが帽子シャッポの角やフロツクコートの襟先と同じ様に角ばつて」
⇒シャッポを脱ぐ
しゃっ‐くん【借訓】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっ‐くん【借訓】シヤク‥
漢字の訓を、本来の意味に関係なく、同音の別語に転用すること。詠嘆の終助詞「かも」を「鴨」と書く類。→万葉仮名
しゃっ‐けい【借景】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっ‐けい【借景】シヤク‥
庭園外の遠山や樹木をその庭のものであるかのように利用してあること。また、そのような造園法。
しゃっ‐けん【借券】シヤク‥🔗⭐🔉
しゃっ‐けん【借券】シヤク‥
動産・不動産借用の証文。借状。借書。借用証文。
[漢]借🔗⭐🔉
借 字形
 筆順
筆順
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部8画/10画/教育/2858・3C5A〕
〔音〕シャク(呉) シャ(呉)(漢)
〔訓〕かりる
[意味]
[一]シャク
①かりる。他人の物を一時使用する。(対)貸。「借金・借款・拝借・賃借」
②ゆるす。「仮借かしゃく」
[二]シャ他のもので間に合わせる。「仮借かしゃ」。かりに。「借問しゃもん」
[解字]
形声。「人」+音符「昔」(=日かずを重ねる)。何かが不足している時、その上に人の力を重ねる意。
[下ツキ
恩借・家借・仮借・寸借・前借・租借・貸借・賃借・転借・内借・拝借・馬借
)部8画/10画/教育/2858・3C5A〕
〔音〕シャク(呉) シャ(呉)(漢)
〔訓〕かりる
[意味]
[一]シャク
①かりる。他人の物を一時使用する。(対)貸。「借金・借款・拝借・賃借」
②ゆるす。「仮借かしゃく」
[二]シャ他のもので間に合わせる。「仮借かしゃ」。かりに。「借問しゃもん」
[解字]
形声。「人」+音符「昔」(=日かずを重ねる)。何かが不足している時、その上に人の力を重ねる意。
[下ツキ
恩借・家借・仮借・寸借・前借・租借・貸借・賃借・転借・内借・拝借・馬借
 筆順
筆順
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部8画/10画/教育/2858・3C5A〕
〔音〕シャク(呉) シャ(呉)(漢)
〔訓〕かりる
[意味]
[一]シャク
①かりる。他人の物を一時使用する。(対)貸。「借金・借款・拝借・賃借」
②ゆるす。「仮借かしゃく」
[二]シャ他のもので間に合わせる。「仮借かしゃ」。かりに。「借問しゃもん」
[解字]
形声。「人」+音符「昔」(=日かずを重ねる)。何かが不足している時、その上に人の力を重ねる意。
[下ツキ
恩借・家借・仮借・寸借・前借・租借・貸借・賃借・転借・内借・拝借・馬借
)部8画/10画/教育/2858・3C5A〕
〔音〕シャク(呉) シャ(呉)(漢)
〔訓〕かりる
[意味]
[一]シャク
①かりる。他人の物を一時使用する。(対)貸。「借金・借款・拝借・賃借」
②ゆるす。「仮借かしゃく」
[二]シャ他のもので間に合わせる。「仮借かしゃ」。かりに。「借問しゃもん」
[解字]
形声。「人」+音符「昔」(=日かずを重ねる)。何かが不足している時、その上に人の力を重ねる意。
[下ツキ
恩借・家借・仮借・寸借・前借・租借・貸借・賃借・転借・内借・拝借・馬借
大辞林の検索結果 (82)
かし-あげ【借上】🔗⭐🔉
かし-あげ 【借上】
鎌倉時代から室町時代初期,高利貸し業者の称。のちの土倉(ドソウ)。かりあげ。
かり【借り】🔗⭐🔉
かり [0] 【借り】
〔「借る」「借りる」の連用形から〕
(1)借りること。また,借りたもの。特に借金。
(2)相手から受けて,報いなければならないと感ずる利益・恩恵。負い目。または,恨み。「一つ―ができた」「この―は必ず返す」
(3)「借り方」の略。
⇔貸し
かり-あげ【借(り)上げ】🔗⭐🔉
かり-あげ [0] 【借(り)上げ】
(1)借り上げること。
(2)江戸時代,各藩で財政に困窮して,家臣から借りる形式で,俸禄(ホウロク)を減らしたこと。借知(カリチ)。
(3)「貸し上げ」に同じ。
かり-あ・げる【借(り)上げる】🔗⭐🔉
かり-あ・げる [4][0] 【借(り)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 かりあ・ぐ
目上の者が目下の者から,または官庁が民間から金品を借りる。「民家を―・げて宿舎にあてる」
かり-いえ【借(り)家】🔗⭐🔉
かり-いえ ―イヘ [0] 【借(り)家】
⇒しゃくや(借家)
かり-いれ【借(り)入れ】🔗⭐🔉
かり-いれ [0] 【借(り)入れ】 (名)スル
借り入れること。しゃくにゅう。
⇔貸し出し
「資金を―する」
かり-い・れる【借(り)入れる】🔗⭐🔉
かり-い・れる [4][0] 【借(り)入れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 かりい・る
金銭や商品を他から借りて自分の使用にあてる。借りる。「銀行から資金を―・れる」
かり-う・ける【借(り)受ける】🔗⭐🔉
かり-う・ける [4] 【借(り)受ける】 (動カ下一)[文]カ下二 かりう・く
「借りる」のやや改まった言い方。借りて受け取る。「ホテルを―・けて保養所とする」
かり-かえ【借(り)換え】🔗⭐🔉
かり-かえ ―カヘ [0] 【借(り)換え】 (名)スル
(1)新たに金を借りて,今までの借金の返却にあてること。「期末に―する」
(2)新しく公社債を発行して,以前に発行した公社債の償還にあてること。
かりかえ-さい【借換債】🔗⭐🔉
かりかえ-さい ―カヘ― [4] 【借換債】
満期のきた債券を償還する資金の調達のために新たに発行される債券。
かり-か・える【借(り)換える】🔗⭐🔉
かり-か・える ―カヘル [3][4] 【借(り)換える】 (動ア下一)[文]ハ下二 かりか・ふ
前に借りた分を返して,新しくまた借りる。「図書館の本を―・える」「利率の低いローンに―・える」
かり-かた【借(り)方】🔗⭐🔉
かり-かた [0] 【借(り)方】
(1)物を借りる方法。「―がうまい」
(2)借りた側の人。借り手。「―にまわる」
(3)複式簿記で,資産の増加,負債・資本の減少,損失の発生などを記入する勘定口座の左側の欄。借り。
⇔貸方(カシカタ)
かり-ぎ【借(り)着】🔗⭐🔉
かり-ぎ [0] 【借(り)着】 (名)スル
衣服を借りて着ること。また,その衣服。
かり-き・る【借(り)切る】🔗⭐🔉
かり-き・る [3] 【借(り)切る】 (動ラ五[四])
ある期間,特定の人が全部借りてしまう。
⇔貸し切る
「研修会でホテルを一週間―・る」「バス一台を―・る」
[可能] かりきれる
かり-こし【借(り)越し】🔗⭐🔉
かり-こし [0] 【借(り)越し】
(1)一定限度以上に借りること。
(2)貸しよりも,借りが多いこと。また,その金。特に,当座預金についていう。
⇔貸し越し
かり-こ・す【借(り)越す】🔗⭐🔉
かり-こ・す [3] 【借(り)越す】 (動サ五[四])
一定の限度以上に借りる。
かり-じ【借(り)字】🔗⭐🔉
かり-じ [0] 【借(り)字】
「当(ア)て字(ジ)」に同じ。
かり-ずまい【借り住(ま)い】🔗⭐🔉
かり-ずまい ―ズマヒ [3] 【借り住(ま)い】 (名)スル
家を賃借して住むこと。また,その家。借屋住まい。
かり-たお・す【借(り)倒す】🔗⭐🔉
かり-たお・す ―タフス [4] 【借(り)倒す】 (動サ五[四])
金品を借りたまま返さないですます。踏み倒す。「借金を―・す」
かり-だ・す【借(り)出す】🔗⭐🔉
かり-だ・す [3][0] 【借(り)出す】 (動サ五[四])
借りて持ち出す。「図書館から本を―・す」
[可能] かりだせる
かり-だな【借(り)店】🔗⭐🔉
かり-だな 【借(り)店】
店賃(タナチン)を出して借りた家。借家(シヤクヤ)。
かり-ち【借(り)地】🔗⭐🔉
かり-ち [0] 【借(り)地】
借りた土地。しゃくち。
かり-ちん【借(り)賃】🔗⭐🔉
かり-ちん [2] 【借(り)賃】
物を借りて支払う料金。
⇔貸し賃
かりっ-ぱなし【借りっ放し】🔗⭐🔉
かりっ-ぱなし [0] 【借りっ放し】
借りたままで返さないこと。「本を―にする」
かり-て【借(り)手】🔗⭐🔉
かり-て [0] 【借(り)手】
金や物を借りる人。借り主。
⇔貸し手
かり-どり【借り取り】🔗⭐🔉
かり-どり 【借り取り】
借りた物を自分の物にしてしまうこと。「何も―にするといふではあるまいし/歌舞伎・四谷怪談」
かり-ぬし【借(り)主】🔗⭐🔉
かり-ぬし [2] 【借(り)主】
金や物を借りる方の人。借り手。
⇔貸し主
かり-もの【借(り)物】🔗⭐🔉
かり-もの [0] 【借(り)物】
(1)人から借りたもの。
(2)人真似で,本当に自分のものになっていない物事。「―の思想」
かり-や【借(り)家】🔗⭐🔉
かり-や [0] 【借(り)家】
借りた家。しゃくや。
か・りる【借りる】🔗⭐🔉
か・りる [0] 【借りる】 (動ラ上一)
〔四段動詞「借る」の上一段化。近世江戸語以降のもの〕
(1)あとで返す約束で,他人の品物や金銭を自分の用に使う。有償にも無償にも言う。借用する。
⇔貸す
「本を―・りる」「銀行から資金を―・りる」「事務所を―・りる」
(2)他人の能力などを使わせてもらう。「知恵を―・りる」「猫の手も―・りたいくらい忙しい」「兄弟子の胸を―・りる」
(3)仮に他のものを使う。臨時にある用途に当てる。「ゲーテの言葉を―・りれば,…」「この場を―・りて」「名を―・りる」
借りて来た猫(ネコ)のよう🔗⭐🔉
借りて来た猫(ネコ)のよう
ふだんと違っておとなしくかしこまっている様子をいう言葉。
か・る【借る】🔗⭐🔉
か・る 【借る】 (動ラ四)
(1)「借りる{(1)}」に同じ。「車なども誰にか―・らむ/堤中納言(はいずみ)」
(2)「借りる{(2)}」に同じ。「いかが他の力を―・るべき/方丈記」
(3)「借りる{(3)}」に同じ。「をとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ/平家 4」
(4)別の座敷に出ている遊女を呼ぶ。また,遊女を見立てるために揚屋から呼ぶ。「まづ大橋(=遊女ノ名)を―・る約にさつしやりませい/歌舞伎・幼稚子敵討」
〔近世江戸語以降,上一段化して「借りる」の形が用いられるようになる。ただし西日本では現代も用いられている。「本をかった(=借リタ)」〕
借る時の=地蔵顔(ジゾウガオ)(=恵比寿顔(エビスガオ))済(ナ)す時の閻魔顔(エンマガオ)🔗⭐🔉
借る時の=地蔵顔(ジゾウガオ)(=恵比寿顔(エビスガオ))済(ナ)す時の閻魔顔(エンマガオ)
物を借りる時には,にこにこするが,それを返済する時には渋い顔をすることのたとえ。
しゃく-い【借位】🔗⭐🔉
しゃく-い ― [1] 【借位】
(1)仮に授けられた位階。古代,無位の者が,貴人に謁見,または外国に派遣されるときなどに行われた。
(2)勅許を受けるまでの間,国司がその管内の神社に仮に授けた位階。
[1] 【借位】
(1)仮に授けられた位階。古代,無位の者が,貴人に謁見,または外国に派遣されるときなどに行われた。
(2)勅許を受けるまでの間,国司がその管内の神社に仮に授けた位階。
 [1] 【借位】
(1)仮に授けられた位階。古代,無位の者が,貴人に謁見,または外国に派遣されるときなどに行われた。
(2)勅許を受けるまでの間,国司がその管内の神社に仮に授けた位階。
[1] 【借位】
(1)仮に授けられた位階。古代,無位の者が,貴人に謁見,または外国に派遣されるときなどに行われた。
(2)勅許を受けるまでの間,国司がその管内の神社に仮に授けた位階。
しゃく-おん【借音】🔗⭐🔉
しゃく-おん [0] 【借音】
国語を漢字で表記する際,漢字の本来の意義と関係なく,その字音を借りて当てはめたもの。主として上代のものについていう。万葉仮名で,「らむ」を「濫」,「はな」を「波奈」と書く類。
→借訓
しゃく-ぎん【借銀】🔗⭐🔉
しゃく-ぎん 【借銀】
かねを借りること。また,借りたかね。借金。「八百五十貫目の―といふ/浮世草子・胸算用 2」
しゃく-けい【借景】🔗⭐🔉
しゃく-けい [0] 【借景】
⇒しゃっけい(借景)
しゃく-ざい【借財】🔗⭐🔉
しゃく-ざい [0] 【借財】 (名)スル
借金をすること。また,借金。
しゃく-しょ【借書】🔗⭐🔉
しゃく-しょ [0] 【借書】
借用の証文。
しゃく-じょう【借状】🔗⭐🔉
しゃく-じょう ―ジヤウ [0] 【借状】
借用の証文。
しゃく-せん【借銭】🔗⭐🔉
しゃく-せん [3][0] 【借銭】
(1)金を借りること。借金。借財。
(2)「借銭乞い」の略。
しゃくせん-こい【借銭乞ひ】🔗⭐🔉
しゃくせん-こい ―コヒ 【借銭乞ひ】
借金取り。
しゃく-たい【借貸】🔗⭐🔉
しゃく-たい [0] 【借貸】
(1)かしかり。
(2)奈良・平安時代,貧民救済などのために官稲を無利息で貸したこと。賑貸(シンタイ)。
→出挙(スイコ)
しゃく-たく【借宅】🔗⭐🔉
しゃく-たく [0] 【借宅】
家を借りること。また,その家。
しゃく-ち【借地】🔗⭐🔉
しゃく-ち [0] 【借地】 (名)スル
土地を借りること。また,借りた土地。
しゃく-ま【借間】🔗⭐🔉
しゃく-ま [0] 【借間】 (名)スル
部屋を借りること。また,借りた部屋。
しゃく-や【借家】🔗⭐🔉
しゃく-や [0] 【借家】 (名)スル
人から家を借りること。また,借りた家。しゃっか。「―住まい」
しゃくや=栄えて母屋(オモヤ)倒る🔗⭐🔉
――栄えて母屋(オモヤ)倒る
恩恵を受けた人が栄えて,恩恵を施した人が落ちぶれるたとえ。
しゃくや-けん【借家権】🔗⭐🔉
しゃくや-けん [3] 【借家権】
借家人がその建物に継続的に居住することができる等の借家人の権利。主に借地借家法により保護されている。
しゃくや-にん【借家人】🔗⭐🔉
しゃくや-にん [0] 【借家人】
家を借りている人。店子(タナコ)。
しゃくや-ほう【借家法】🔗⭐🔉
しゃくや-ほう ―ハフ 【借家法】
〔「しゃっかほう」とも〕
借家人の権利の保護を目的とする法律。1921年(大正10)制定。91年(平成3)借地借家法に吸収廃止。
しゃっ-か【借家】🔗⭐🔉
しゃっ-か シヤク― [0] 【借家】 (名)スル
「しゃくや(借家)」に同じ。
しゃっか-ほう【借家法】🔗⭐🔉
しゃっか-ほう シヤク―ハフ [0] 【借家法】
⇒しゃくやほう(借家法)
しゃっ-かん【借款】🔗⭐🔉
しゃっ-かん シヤククワン [0] 【借款】
金銭の貸借。特に,政府または公的機関同士の国際的な長期資金の貸借。
しゃっかん-さい【借換債】🔗⭐🔉
しゃっかん-さい シヤククワン― [3] 【借換債】
⇒かりかえさい(借換債)
しゃっ-きん【借金】🔗⭐🔉
しゃっ-きん シヤク― [3] 【借金】 (名)スル
金を借りること。また,その借りた金。「知人から―する」
しゃっきん=を質(シチ)に置・く🔗⭐🔉
――を質(シチ)に置・く
(1)借金以外に質ぐさがないほど貧乏する。
(2)無理な算段をして現金を集める。
しゃっきん-とう【借金党】🔗⭐🔉
しゃっきん-とう シヤク―タウ 【借金党】
⇒困民党(コンミントウ)
しゃっきん-とり【借金取り】🔗⭐🔉
しゃっきん-とり シヤク― [3] 【借金取り】
借金を取りたてること。また,その人。借金乞い。
しゃっ-くん【借訓】🔗⭐🔉
しゃっ-くん シヤク― [0] 【借訓】
万葉仮名などで,漢字の「訓」の読みをその意味に関係なく,同音の別語に転用したもの。助動詞「つ」の連体形「つる」を「鶴」と書く類。
→借音
しゃっ-けい【借景】🔗⭐🔉
しゃっ-けい シヤク― [0] 【借景】
庭園外にある山などの景物を,庭園の構成要素として取り入れること。
しゃっ-けん【借券】🔗⭐🔉
しゃっ-けん シヤク― [0] 【借券】
借用証書。借用証文。
かり【借り】(和英)🔗⭐🔉
かりうけにん【借受人】(和英)🔗⭐🔉
かりうけにん【借受人】
⇒借主.
かりうける【借り受ける】(和英)🔗⭐🔉
かりうける【借り受ける】
⇒借りる.
かりかし【借り貸し】(和英)🔗⭐🔉
かりかし【借り貸し】
⇒貸し借り.
かりぎ【借り着】(和英)🔗⭐🔉
かりぎ【借り着】
borrowed clothes.
かりきり【借切りの】(和英)🔗⭐🔉
かりきり【借切りの】
reserved.客車を〜にする engage a whole car.
かりだす【借り出す】(和英)🔗⭐🔉
かりだす【借り出す】
take out (本などを).
かりて【借手】(和英)🔗⭐🔉
かりて【借手】
⇒借主.
かりにげ【借り逃げする】(和英)🔗⭐🔉
かりにげ【借り逃げする】
run away without paying one's debt.
かりぬし【借主】(和英)🔗⭐🔉
かりる【借りる】(和英)🔗⭐🔉
しゃくざい【借財】(和英)🔗⭐🔉
しゃくざい【借財】
⇒借金.
しゃくや【借家】(和英)🔗⭐🔉
しゃくや【借家】
a rented house.→英和
〜する rent a house.‖借家人 a tenant.借家料 a house rent.
しゃっかん【借款】(和英)🔗⭐🔉
しゃっかん【借款】
a loan.→英和
〜する obtain a loan.
広辞苑+大辞林に「借」で始まるの検索結果。もっと読み込む