複数辞典一括検索+![]()
![]()
劈 さく🔗⭐🔉
【劈】
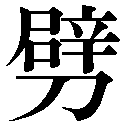 15画 刀部
区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C
《音読み》 ヘキ
15画 刀部
区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C
《音読み》 ヘキ /ヒャク
/ヒャク 〈p
〈p ・p
・p 〉
《訓読み》 さく
《意味》
〉
《訓読み》 さく
《意味》
 {動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」
{動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」
 「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。
「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。
 「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。
《解字》
会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。
《単語家族》
避ヒ(横にかわしてさける)
「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。
《解字》
会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。
《単語家族》
避ヒ(横にかわしてさける) 璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。
《類義》
→剖
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。
《類義》
→剖
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
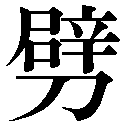 15画 刀部
区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C
《音読み》 ヘキ
15画 刀部
区点=4992 16進=517C シフトJIS=999C
《音読み》 ヘキ /ヒャク
/ヒャク 〈p
〈p ・p
・p 〉
《訓読み》 さく
《意味》
〉
《訓読み》 さく
《意味》
 {動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」
{動}さく。刃物で二つに切り開く。なたでまきを左右にさく動作はその一例。〈類義語〉→裂。「劈開ヘキカイ」
 「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。
「劈面ヘキメン」とは、顔の正面にまっこうからあたること。
 「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。
《解字》
会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。
《単語家族》
避ヒ(横にかわしてさける)
「劈頭ヘキトウ」とは、まっこうから一撃を加える意から、転じて、物事の最初のこと。
《解字》
会意兼形声。辟は、からだを横に引きさく刑罰で、横に開く意を含む。劈は「刀+音符辟ヘキ」で、左右に横に切りさくこと。
《単語家族》
避ヒ(横にかわしてさける) 璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。
《類義》
→剖
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
璧ヘキ(横に開いた平らな玉)と同系。
《類義》
→剖
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
刳 さく🔗⭐🔉
剖 さく🔗⭐🔉
【剖】
 10画 リ部 [常用漢字]
区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ
10画 リ部 [常用漢字]
区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ /ホウ
/ホウ /フ
/フ 〈p
〈p u〉
《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)
《意味》
u〉
《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)
《意味》
 {動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕
{動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕
 {動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕
{動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕
 {動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」
《解字》
会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。
《単語家族》
倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。
《類義》
裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」
《解字》
会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。
《単語家族》
倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。
《類義》
裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 リ部 [常用漢字]
区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ
10画 リ部 [常用漢字]
区点=4322 16進=4B36 シフトJIS=9655
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ /ホウ
/ホウ /フ
/フ 〈p
〈p u〉
《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)
《意味》
u〉
《訓読み》 さく/わかれる(わかる)/さける(さく)
《意味》
 {動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕
{動}さく。二つに切りわける。〈対語〉→合。〈類義語〉→判。「解剖」「剖之以為瓢=コレヲ剖キテモッテ瓢ト為ス」〔→荘子〕
 {動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕
{動}わかれる(ワカル)。さける(サク)。二つにわかれる。割れる。「天地剖判=天地剖判ス」〔→史記〕
 {動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」
《解字》
会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。
《単語家族》
倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。
《類義》
裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}黒と白、善と悪とをわけて判定する。「剖断」「剖析」
《解字》
会意兼形声。左側の字(音ホウ)は、否の変形で、拒否し、背を向け、離れる意を含む。剖はそれを音符とし、刀を加えた字で、刀で切って二つにし、背中あわせに分離させること。
《単語家族》
倍(二つにわける→個数がばいになる)と同系。また、北(背中あわせ、そむく)や、背とも縁が近い。
《類義》
裂は、ずるずると細く小さく引きさくこと。解は、ばらばらに分解すること。劈ヘキは、左右に横に切りさくこと。割は、刃物で二つに切りさくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
副 さく🔗⭐🔉
【副】
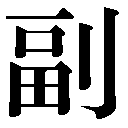 11画 リ部 [四年]
区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
11画 リ部 [四年]
区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ
《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます
《意味》
〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ
《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます
《意味》
 {動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕
{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕
 {名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕
{名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕
 {動}さく。二つに切りさく。「剖副」
{動}さく。二つに切りさく。「剖副」
 {単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。
〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。
《解字》
{単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。
〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。
《解字》
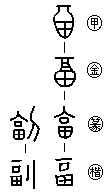 形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍
形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍 逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく)
逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく) 富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。
《類義》
→就
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。
《類義》
→就
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
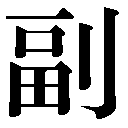 11画 リ部 [四年]
区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
11画 リ部 [四年]
区点=4191 16進=497B シフトJIS=959B
《常用音訓》フク
《音読み》 フク
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ
《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます
《意味》
〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)/さく/すけ
《名付け》 すえ・すけ・そえ・つぎ・ます
《意味》
 {動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕
{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。主となるものにぴったりと寄りそって対をなす。そばにくっついて助ける。「副以桜桃=副フルニ桜桃ヲモッテス」〔燕京歳時記〕
 {名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕
{名}そえ役。控え。▽正使のそえ役を「副使」といい、正本の控えを「副本」という。「令秦舞陽為副=秦舞陽ヲシテ副ト為ラシム」〔→史記〕
 {動}さく。二つに切りさく。「剖副」
{動}さく。二つに切りさく。「剖副」
 {単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。
〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。
《解字》
{単位}寄りあって一組をなす物。▽中国の書画は多く二枚で対をなすので、書副・画副といい、書画を一副、二副と数える。転じて、書画一枚(一面)をも「一副」という。
〔国〕すけ。四等官で、神祇官の第二位。
《解字》
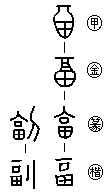 形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍
形声。左側の字(音フク)は、腹がふくれ、いっぱい酒のはいるとっくりを描いた象形文字。副は刀にそれを単なる音符としてそえたもので、原義とは関係はない。剖ホウと同じく、もと二つに切りわけることであるが、むしろその二つがぴたりとくっついてペアをなす意に専用される。倍 逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく)
逼ヒョク・ヒツ(ぴたりとくっつく) 富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。
《類義》
→就
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
富(財貨がびっしりつまっている)とも縁が近い。
《類義》
→就
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
割 さく🔗⭐🔉
【割】
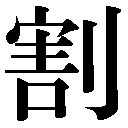 12画 リ部 [六年]
区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84
《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる
《音読み》 カツ
12画 リ部 [六年]
区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84
《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる
《音読み》 カツ /カチ
/カチ 〈g
〈g 〉
《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり
《名付け》 さき
《意味》
〉
《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり
《名付け》 さき
《意味》
 {動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。
{動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。
 {動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕
{動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕
 {動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」
〔国〕
{動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」
〔国〕 わる。計算で、除法を行う。「割り算」
わる。計算で、除法を行う。「割り算」 わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」
わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」 わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。
《解字》
形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害
《単語家族》
契ケイ(きる)
わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。
《解字》
形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害
《単語家族》
契ケイ(きる) 介カイ(二つにわける)
介カイ(二つにわける) 界(二つにわける)と同系。
《類義》
→剖
《異字同訓》
さく。 →裂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
界(二つにわける)と同系。
《類義》
→剖
《異字同訓》
さく。 →裂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
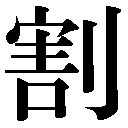 12画 リ部 [六年]
区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84
《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる
《音読み》 カツ
12画 リ部 [六年]
区点=1968 16進=3364 シフトJIS=8A84
《常用音訓》カツ/さ…く/わり/わ…る/わ…れる
《音読み》 カツ /カチ
/カチ 〈g
〈g 〉
《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり
《名付け》 さき
《意味》
〉
《訓読み》 われる/わる/さく/きる/わり
《名付け》 さき
《意味》
 {動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。
{動}わる。さく。刀で二つにきりさく。転じて、広く、二つにわること。▽漢文では「わる」という訓は用いず「さく」という。
 {動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕
{動}さく。分割する。「割地=地ヲ割ク」「令楚王割東国以与斉=楚王ヲシテ東国ヲ割キモッテ斉ニ与ヘシム」〔→史記〕
 {動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」
〔国〕
{動}〔俗〕きる。途中できってとる。「割麦(麦の穂をきりとる)」
〔国〕 わる。計算で、除法を行う。「割り算」
わる。計算で、除法を行う。「割り算」 わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」
わる。標準と考えられる一定の限度をはずれて下まわる。「百円の大台を割る」 わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。
《解字》
形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害
《単語家族》
契ケイ(きる)
わり。比率をあらわすことば。一割は、十分の一のこと。
《解字》
形声。害ガイは、かご状のふたを口の上にかぶせることを示し、遏アツと同じくふさぎ止めること。割は「刀+音符害」で害の原義とは関係がない。→害
《単語家族》
契ケイ(きる) 介カイ(二つにわける)
介カイ(二つにわける) 界(二つにわける)と同系。
《類義》
→剖
《異字同訓》
さく。 →裂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
界(二つにわける)と同系。
《類義》
→剖
《異字同訓》
さく。 →裂
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
咲 さく🔗⭐🔉
【咲】
 9画 口部 [常用漢字]
区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7
《常用音訓》さ…く
《音読み》 ショウ(セウ)
9画 口部 [常用漢字]
区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7
《常用音訓》さ…く
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく
《名付け》 さき
《意味》
{動}わらう(ワラフ)。えむ(
o〉
《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく
《名付け》 さき
《意味》
{動}わらう(ワラフ)。えむ( ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕
〔国〕さく。花がさく。
《解字》
ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕
〔国〕さく。花がさく。
《解字》
 会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。
会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。
 9画 口部 [常用漢字]
区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7
《常用音訓》さ…く
《音読み》 ショウ(セウ)
9画 口部 [常用漢字]
区点=2673 16進=3A69 シフトJIS=8DE7
《常用音訓》さ…く
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく
《名付け》 さき
《意味》
{動}わらう(ワラフ)。えむ(
o〉
《訓読み》 わらう(わらふ)/えむ(ゑむ)/さく
《名付け》 さき
《意味》
{動}わらう(ワラフ)。えむ( ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕
〔国〕さく。花がさく。
《解字》
ム)。口をすぼめてほほとわらう。〈同義語〉→笑。「八百万神ヤオヨロズノカミ共に咲ひき」〔→記〕
〔国〕さく。花がさく。
《解字》
 会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。
会意兼形声。夭ヨウは、なよなよと細い姿の人を描いた象形文字。笑ショウは、細い竹。細い意を含む。咲はもと、「口+音符笑」で、口を細めてほほとわらうこと。咲は、それが変形した俗字。日本では、「鳥鳴き花笑ふ」という慣用句から、花がさく意に転用された。「わらう」意には笑の字を用い、この字を用いない。
宰 さく🔗⭐🔉
【宰】
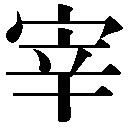 10画 宀部 [常用漢字]
区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ
10画 宀部 [常用漢字]
区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ
 〈z
〈z i〉
《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる
《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ
《意味》
i〉
《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる
《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ
《意味》
 サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕
サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕
 サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」
サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」
 「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。
「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。
 {名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕
{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕
 {動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。
《解字》
会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。
《単語家族》
栽(木をきる)
{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。
《解字》
会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。
《単語家族》
栽(木をきる) 裁(衣をきる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
裁(衣をきる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
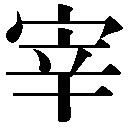 10画 宀部 [常用漢字]
区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ
10画 宀部 [常用漢字]
区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9
《常用音訓》サイ
《音読み》 サイ
 〈z
〈z i〉
《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる
《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ
《意味》
i〉
《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる
《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ
《意味》
 サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕
サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕
 サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」
サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」
 「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。
「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。
 {名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕
{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕
 {動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。
《解字》
会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。
《単語家族》
栽(木をきる)
{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。
《解字》
会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。
《単語家族》
栽(木をきる) 裁(衣をきる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
裁(衣をきる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
擘 さく🔗⭐🔉
【擘】
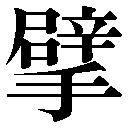 17画 手部
区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4
《音読み》
17画 手部
区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4
《音読み》  ハク
ハク /ヒャク
/ヒャク 〈b
〈b 〉〈b
〉〈b i〉/
i〉/ ヘキ
ヘキ /ヒャク
/ヒャク 〈b
〈b 〉
《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび
《意味》
〉
《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび
《意味》

 {動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕
{動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕
 {動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」
{動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」
 {名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟
《単語家族》
闢ヘキ(左右に開く)
{名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟
《単語家族》
闢ヘキ(左右に開く) 避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉)
避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉) 卑ヒ(たけが低い)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
卑ヒ(たけが低い)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
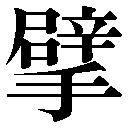 17画 手部
区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4
《音読み》
17画 手部
区点=5806 16進=5A26 シフトJIS=9DA4
《音読み》  ハク
ハク /ヒャク
/ヒャク 〈b
〈b 〉〈b
〉〈b i〉/
i〉/ ヘキ
ヘキ /ヒャク
/ヒャク 〈b
〈b 〉
《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび
《意味》
〉
《訓読み》 さく/さける(さく)/おやゆび
《意味》

 {動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕
{動}さく。さける(サク)。左と右とに、さっとさける。また、左右二つにさく。〈類義語〉→劈ヘキ(さく)。「擘裂ハクレツ」「釵擘黄金合分鈿=釵ハ黄金ヲ擘キ、合ハ鈿ヲ分カツ」〔→白居易〕
 {動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」
{動}弓のつるを引き開いて張る。「擘張ハクチョウ(弓を張る)」
 {名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟
《単語家族》
闢ヘキ(左右に開く)
{名}おやゆび。たけの低いおやゆび。また、転じて親分のこと。▽これに対してたけの長い中指を将指ショウシという。「巨擘キョヘキ(大親分)」
《解字》
会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刑具)+口」からなる会意文字で、人のからだを刑具で横ざきにすることを示す。擘は「手+音符辟」で、横にさくこと。横に開けば平らになる。そこで、たけが低く平らなおやゆびのこと。→辟
《単語家族》
闢ヘキ(左右に開く) 避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉)
避ヒ(横にさける)と同系。また璧ヘキ(平らな玉) 卑ヒ(たけが低い)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
卑ヒ(たけが低い)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拆 さく🔗⭐🔉
【拆】
 8画
8画  部
区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D
《音読み》 タク
部
区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D
《音読み》 タク /チャク
/チャク 〈ch
〈ch i・ch
i・ch 〉
《訓読み》 ひらく/さく/やぶる
《意味》
〉
《訓読み》 ひらく/さく/やぶる
《意味》
 {動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕
{動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕
 {動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕
《解字》
会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。
《単語家族》
柝タク(打ちたたく拍子木)
{動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕
《解字》
会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。
《単語家族》
柝タク(打ちたたく拍子木) 拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画
8画  部
区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D
《音読み》 タク
部
区点=5730 16進=593E シフトJIS=9D5D
《音読み》 タク /チャク
/チャク 〈ch
〈ch i・ch
i・ch 〉
《訓読み》 ひらく/さく/やぶる
《意味》
〉
《訓読み》 ひらく/さく/やぶる
《意味》
 {動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕
{動}ひらく。さく。打ち割って二つにさく。〈同義語〉→拓タク。「開拆カイタク」「声拆江河、勢崩雷電=声ハ江河ヲ拆キ、勢ヒハ雷電ヲ崩ス」〔→李華〕
 {動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕
《解字》
会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。
《単語家族》
柝タク(打ちたたく拍子木)
{動}やぶる。打ちやぶる。相手の説を論破する。「請余代拆之=請フ、余代ハリテコレヲ拆ラン」〔→原善〕
《解字》
会意兼形声。斥セキは「斤(おの)+丶(きる)」からなり、斧オノでたたき割るさま。拆は「手+音符斥」で、たたき割ること。
《単語家族》
柝タク(打ちたたく拍子木) 拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拓タク(打ちひらく)などと同系。傷ショウ(やぶる)は、その語尾が伸びたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
斯 さく🔗⭐🔉
【斯】
 12画 斤部
区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A
《音読み》 シ
12画 斤部
区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)
《意味》
〉
《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)
《意味》
 {動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕
{動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕
 {指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕
{指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕
 {接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕
{接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕
 {助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕
{助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕
 {形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕
{形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕
 {名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕
《解字》
{名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕
《解字》
 会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。
《単語家族》
分析の析(細かくさく)
会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。
《単語家族》
分析の析(細かくさく) 撕シ(引きさく)などと同系。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
撕シ(引きさく)などと同系。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 斤部
区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A
《音読み》 シ
12画 斤部
区点=2759 16進=3B5B シフトJIS=8E7A
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)
《意味》
〉
《訓読み》 きる/さく/これ/この/すなわち(すなはち)/ここに/しろい(しろし)
《意味》
 {動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕
{動}きる。さく。ばらばらにきり離す。〈類義語〉→析。「墓門有棘、斧以斯之=墓門ニ棘有リ、斧ヲモッテコレヲ斯ク」〔→詩経〕
 {指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕
{指}これ。この。▽近称の指示詞にあてた用法。〈類義語〉→此・→是コレ・→之コレ。「斯人也而有斯疾也=コノ人ニシテコノ疾有ルヤ」〔→論語〕
 {接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕
{接続}すなわち(スナハチ)。ここに。AならBだと、上下の句の内容をつなぐことば。〈類義語〉→則。「清斯濯纓、濁斯濯足矣=清ミテハスナハチ纓ヲ濯ヒ、濁リテハスナハチ足ヲ濯フ」〔→孟子〕
 {助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕
{助}詩のリズムを整えることば。「彼、何人斯=彼、何人ゾヤ」〔→詩経〕
 {形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕
{形}しろい(シロシ)。▽鮮に当てた用法。「有兔斯首=兔有リ、斯首ナリ」〔→詩経〕
 {名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕
《解字》
{名}小者。また、雑役夫。▽廝シに当てた用法。「厮(=斯)徒十万」〔→史記〕
《解字》
 会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。
《単語家族》
分析の析(細かくさく)
会意。「其(=箕。穀物のごみなどをよりわける四角いあみかご)+斤(おの)」で、刃物で箕ミをばらばらにさくことを示す。「爾雅」釈言篇に「斯とは離なり」とあり、また「広雅」釈詁篇に「斯とは裂なり」とある。
《単語家族》
分析の析(細かくさく) 撕シ(引きさく)などと同系。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
撕シ(引きさく)などと同系。
《類義》
→則
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
析 さく🔗⭐🔉
柝 さく🔗⭐🔉
磔 さく🔗⭐🔉
【磔】
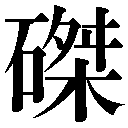 15画 石部
区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7
《音読み》 タク
15画 石部
区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7
《音読み》 タク /チャク
/チャク 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 はりつけ/さく
《意味》
〉
《訓読み》 はりつけ/さく
《意味》
 {名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。
{名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。
 タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。
タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。
 {名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。
{名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。
 {名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。
{名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。
 「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。
〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。
《解字》
会意。「石+桀(はりつけ)」。
《単語家族》
拓(うちひらく)
「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。
〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。
《解字》
会意。「石+桀(はりつけ)」。
《単語家族》
拓(うちひらく) 拆タク(うちわる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拆タク(うちわる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
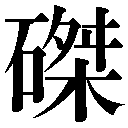 15画 石部
区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7
《音読み》 タク
15画 石部
区点=6689 16進=6279 シフトJIS=E1F7
《音読み》 タク /チャク
/チャク 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 はりつけ/さく
《意味》
〉
《訓読み》 はりつけ/さく
《意味》
 {名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。
{名}はりつけ。死体をはりつけ、市中にさらすこと。
 タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。
タクス{動・名}さく。からだをさく。ひきさいて内臓を開く。また、刑の一つ。罪人のからだをひきさくもの。車ざき・牛ざきなど。
 {名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。
{名}祭りの名。風の神をまつる祭り。▽犬をはりつけにして風神をふせぐことから。
 {名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。
{名}永字八法の一つ。右ななめ下にさげる筆法。▽今は捺ナツという。
 「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。
〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。
《解字》
会意。「石+桀(はりつけ)」。
《単語家族》
拓(うちひらく)
「磔磔タクタク」とは、(イ)ことこととたたく音。(ロ)鳥の羽ばたく音。また、鳥の鳴く声。
〔国〕はりつけ。刑の一つ。罪人を柱にしばりつけ、やりで突きさすこと。
《解字》
会意。「石+桀(はりつけ)」。
《単語家族》
拓(うちひらく) 拆タク(うちわる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拆タク(うちわる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
裂 さく🔗⭐🔉
【裂】
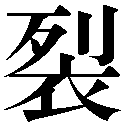 12画 衣部 [常用漢字]
区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4
《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける
《音読み》 レツ
12画 衣部 [常用漢字]
区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4
《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける
《音読み》 レツ /レチ
/レチ 〈li
〈li 〉
《訓読み》 さく/さける(さく)
《意味》
〉
《訓読み》 さく/さける(さく)
《意味》
 {動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕
{動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕
 {動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕
{動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕
 {名}さいた布ぎれ。切れはし。
《解字》
会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。
《単語家族》
烈レツ(木がさけてもえる)
{名}さいた布ぎれ。切れはし。
《解字》
会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。
《単語家族》
烈レツ(木がさけてもえる) 例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。
《類義》
→剖・→破
《異字同訓》
さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。
《類義》
→剖・→破
《異字同訓》
さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
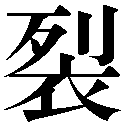 12画 衣部 [常用漢字]
区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4
《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける
《音読み》 レツ
12画 衣部 [常用漢字]
区点=4686 16進=4E76 シフトJIS=97F4
《常用音訓》レツ/さ…く/さ…ける
《音読み》 レツ /レチ
/レチ 〈li
〈li 〉
《訓読み》 さく/さける(さく)
《意味》
〉
《訓読み》 さく/さける(さく)
《意味》
 {動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕
{動}さく。さける(サク)。引っぱってやぶる。二つにさきはなす。〈類義語〉→割。「割裂」「裂帛=帛ヲ裂ク」「車裂(車ざきの刑)」「裂裳帛而与之=裳帛ヲ裂キテコレヲ与フ」〔→左伝〕
 {動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕
{動}ばらばらに離れる。また、物事が破れてだめになる。「分裂」「支離滅裂(ばらばらでまとまりがない)」「道術将為天下裂=道術マサニ天下ノ為ニ裂カレントス」〔→荘子〕
 {名}さいた布ぎれ。切れはし。
《解字》
会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。
《単語家族》
烈レツ(木がさけてもえる)
{名}さいた布ぎれ。切れはし。
《解字》
会意兼形声。歹ガツは、関節の骨の一片。それに刀をそえて、列レツ(骨を刀で切り離す→切り離したものがずるずると並ぶ)となる。裂は「衣+音符列」で、布地を切りさくこと。
《単語家族》
烈レツ(木がさけてもえる) 例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。
《類義》
→剖・→破
《異字同訓》
さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
例レイ(引きさく→さいた物を並べてみせる)などと同系。
《類義》
→剖・→破
《異字同訓》
さく。 裂く「布を裂く。仲を裂く。引き裂く」割く「時間を割く。紙面を割く。人手を割く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「さく」で完全一致するの検索結果 1-14。
 8画 リ部
区点=4974 16進=516A シフトJIS=998A
《音読み》 コ
8画 リ部
区点=4974 16進=516A シフトJIS=998A
《音読み》 コ 〉
《訓読み》 さく/えぐる(ゑぐる)
《意味》
{動}さく。えぐる(
〉
《訓読み》 さく/えぐる(ゑぐる)
《意味》
{動}さく。えぐる( 型に左右に大きくさく。また
型に左右に大きくさく。また 型にえぐりとる。「刳腹=腹ヲ刳ク」「刳木為舟=木ヲ刳リテ舟ト為ス」〔
型にえぐりとる。「刳腹=腹ヲ刳ク」「刳木為舟=木ヲ刳リテ舟ト為ス」〔 型にひらく)」で、股を開くように刀で
型にひらく)」で、股を開くように刀で 8画 木部 [常用漢字]
区点=3247 16進=404F シフトJIS=90CD
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ
8画 木部 [常用漢字]
区点=3247 16進=404F シフトJIS=90CD
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ 9画 木部
区点=5949 16進=5B51 シフトJIS=9E70
《音読み》 タク
9画 木部
区点=5949 16進=5B51 シフトJIS=9E70
《音読み》 タク