複数辞典一括検索+![]()
![]()
伊藤仁斎 イトウジンサイ🔗⭐🔉
【伊藤仁斎】
イトウジンサイ〔日〕〈人名〉1627〜1705 江戸時代初期の儒学者。字アザナは源佐ゲンスケ、仁斎は号。朱熹シュキの儒学に対し、原始儒教に帰るという古義学を主唱し、京都の堀川に塾を開いた。著に『童子問』『語孟ゴモウ字義』『論語古義』『孟子古義』などがある。
伊藤東涯 イトウトウガイ🔗⭐🔉
【伊藤東涯】
イトウトウガイ〔日〕〈人名〉1670〜1736 江戸時代中期の儒学者。伊藤仁斎の長男。名は長胤ナガタネ、字アザナは原蔵、東涯は号。父のあとを継ぎ古義学を大成した。修辞・制度に詳しく、『制度通』のほか、著書が多い。
仮 いとま🔗⭐🔉
【仮】
 6画 人部 [五年]
区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC
【假】旧字旧字
6画 人部 [五年]
区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC
【假】旧字旧字
 11画 人部
区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF
《常用音訓》カ/ケ/かり
《音読み》 カ
11画 人部
区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF
《常用音訓》カ/ケ/かり
《音読み》 カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉
《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま
《意味》
〉
《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま
《意味》
 {名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」
{名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」
 {動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕
{動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕
 {動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕
{動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕
 {動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕
{動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕
 {副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。
{副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。
 {接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。
{接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。
 {名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕
{名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕
 {形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」
《解字》
{形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」
《解字》
 会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。
《単語家族》
家(屋根で豚をおおう小屋)
会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。
《単語家族》
家(屋根で豚をおおう小屋) 廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画 人部 [五年]
区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC
【假】旧字旧字
6画 人部 [五年]
区点=1830 16進=323E シフトJIS=89BC
【假】旧字旧字
 11画 人部
区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF
《常用音訓》カ/ケ/かり
《音読み》 カ
11画 人部
区点=4881 16進=5071 シフトJIS=98EF
《常用音訓》カ/ケ/かり
《音読み》 カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji ・ji
・ji 〉
《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま
《意味》
〉
《訓読み》 かり/かりる(かる)/かす/かりに/もし/たとい(たとひ)/いとま
《意味》
 {名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」
{名・形}かり。内容を見せないようにカバーをかけてあること。みせかけ。また、一時だけのまにあわせであるさま。「仮面」「仮定」
 {動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕
{動}かりる(カル)。うわべをつくろう。「以力仮仁者覇=力ヲ以テ仁ヲ仮ル者ハ覇ナリ」〔→孟子〕
 {動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕
{動}かりる(カル)。一時借用する。また、利用する。▽みせかけの意から。〈類義語〉→借。「仮道于衛=道ヲ衛ニ仮ル」〔→左伝〕
 {動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕
{動}かす。一時だけかし与える。「仮我以文章=我ニ仮スニ文章ヲ以テス」〔→李白〕
 {副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。
{副}かりに。永久的にではなく一時だけ。とりあえず。
 {接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。
{接続}もし。たとい(タトヒ)。かりに…だとすると。▽「仮令」「仮使」「仮如」「仮若」などの形で用いる。
 {名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕
{名}いとま。仕事のないあいた時間のこと。▽内容がないの意から。去声に読む。〈同義語〉→暇。「因求仮暫帰=因リテ仮ヲ求メテ暫ク帰ル」〔古楽府〕
 {形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」
《解字》
{形}ひまなさま。〈同義語〉→暇。「仮楽カラク/ケラク(ひまで楽しい)」
《解字》
 会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。
《単語家族》
家(屋根で豚をおおう小屋)
会意兼形声。假カの右側は「たれたおおい+=印(そろえる意を示す)+手」の会意文字で、手でおおいをあしらい、かぶることをあらわす。假はそれを音符とし人を加えた字で、仮面をかぶる人間の動作をあらわす。▽真(中身がつまっている)・填テンの反対で、中身がからで表面だけ、一時だけ、みせかけなどの意を含む。
《単語家族》
家(屋根で豚をおおう小屋) 廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
廈カ(屋根でおおった家)などと同系。庫(屋根で車をおおう車庫)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
依投 イトウ🔗⭐🔉
【依投】
イトウ たよりにする。▽「投」は、一か所にとどまる。
偉徳 イトク🔗⭐🔉
【偉徳】
イトク りっぱな徳。
厭 いとう🔗⭐🔉
【厭】
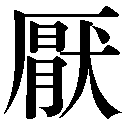 14画 厂部
区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D
《音読み》
14画 厂部
区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D
《音読み》  エン(エム)
エン(エム)
 /オン(オム)
/オン(オム) 〈y
〈y n〉/
n〉/ ヨウ(エフ)
ヨウ(エフ)
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)
《意味》
〉
《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)
《意味》

 {動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕
{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕
 {動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕
{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕
 {副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕
{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

 {動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」
{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」
 {動}隠す。上から下のものをおおい隠す。
{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。
 {動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。
《解字》
{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。
《解字》
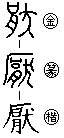 会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。
《単語家族》
壓(=圧。上からおさえつける)と同系。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。
《単語家族》
壓(=圧。上からおさえつける)と同系。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
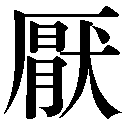 14画 厂部
区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D
《音読み》
14画 厂部
区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D
《音読み》  エン(エム)
エン(エム)
 /オン(オム)
/オン(オム) 〈y
〈y n〉/
n〉/ ヨウ(エフ)
ヨウ(エフ)
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)
《意味》
〉
《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)
《意味》

 {動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕
{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕
 {動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕
{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕
 {副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕
{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

 {動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」
{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」
 {動}隠す。上から下のものをおおい隠す。
{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。
 {動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。
《解字》
{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。
《解字》
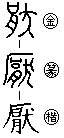 会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。
《単語家族》
壓(=圧。上からおさえつける)と同系。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。
《単語家族》
壓(=圧。上からおさえつける)と同系。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
夷塗 イト🔗⭐🔉
【夷道】
イドウ たいらな道。『夷塗イト・夷路イロ』
委頓 イトン🔗⭐🔉
【委頓】
イトン ぐったりと力が抜ける。衰え弱る。
威徳 イトク🔗⭐🔉
【威徳】
イトク  おごそかで、おかしがたい徳。
おごそかで、おかしがたい徳。 軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』
軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』
 おごそかで、おかしがたい徳。
おごそかで、おかしがたい徳。 軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』
軍事的な威力と、徳(恩恵)によって人を従わせる力。『威恩イオン』
嫌 いとう🔗⭐🔉
【嫌】
 13画 女部 [常用漢字]
区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99
《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う
《音読み》 ケン(ケム)
13画 女部 [常用漢字]
区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99
《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う
《音読み》 ケン(ケム) /ゲン(ゲム)
/ゲン(ゲム) 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)
《意味》
n〉
《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)
《意味》
 {動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕
{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕
 ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」
ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」
 {名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 女部 [常用漢字]
区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99
《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う
《音読み》 ケン(ケム)
13画 女部 [常用漢字]
区点=2389 16進=3779 シフトJIS=8C99
《常用音訓》ケン/ゲン/いや/きら…う
《音読み》 ケン(ケム) /ゲン(ゲム)
/ゲン(ゲム) 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)
《意味》
n〉
《訓読み》 いや/きらう(きらふ)/いとう(いとふ)/うたがう(うたがふ)/きらい(きらひ)/うたがい(うたがひ)
《意味》
 {動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕
{動}きらう(キラフ)。いとう(イトフ)。いやがる。しぶる。憎みきらう。「嫌悪ケンオ」「大人故嫌遅=大人故ニ遅キヲ嫌フ」〔古楽府〕
 ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」
ケンス{動}うたがう(ウタガフ)。こうではないかと気を回して思う。悪いほうへと連想する。「嫌疑ケンギ」
 {名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}きらい(キラヒ)。うたがい(ウタガヒ)。よくないことについてそうではないかと思われるふし。また、そう思う気持ち。「使民無嫌=民ヲシテ嫌無カラシム」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。兼ケンは、禾イネを二つ並べ持つ姿。いくつも連続する意を含む。嫌は「女+音符兼」で、女性にありがちな、あれこれと気がねし、思いが連続して実行をしぶることを示す。
《類義》
→忌
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
射 いとう🔗⭐🔉
【射】
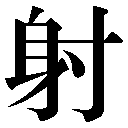 10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》
10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》  シャ
シャ /ジャ
/ジャ 〈sh
〈sh 〉/
〉/ ヤ
ヤ
 〈y
〈y 〉/
〉/ エキ
エキ /ヤク
/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》
《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》

 {動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
 {名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
 {動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
 「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。
「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

 {動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
 「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
 会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる)
会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
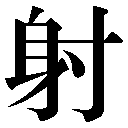 10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》
10画 寸部 [六年]
区点=2845 16進=3C4D シフトJIS=8ECB
《常用音訓》シャ/い…る
《音読み》  シャ
シャ /ジャ
/ジャ 〈sh
〈sh 〉/
〉/ ヤ
ヤ
 〈y
〈y 〉/
〉/ エキ
エキ /ヤク
/ヤク 《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》
《訓読み》 いる/あてる(あつ)/いとう(いとふ)/あきる(あく)
《名付け》 い・いり
《意味》

 {動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
{動}いる。弓を張って矢をいる。「射雉=雉ヲ射ル」「弋射ヨクシャ(いぐるみ)」「弋不射宿=弋スルニハ宿ヲ射ズ」〔→論語〕
 {名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
{名}弓をいる術。弓術。▽古代には礼・楽・射・御(乗馬)・書・数を「六芸リクゲイ」といい、男子の教養の主要課目であった。「射有似乎君子=射ハ君子ニ似タルコト有リ」〔→中庸〕
 {動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
{動}あてる(アツ)。ねらって的にあてる。また一点めざして光や弾をあてる。「照射ショウシャ」「射利シャリ(もうけをねらう)」「射倖心シャコウシン(=射幸心。まぐれをねらう心)」
 「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。
「僕射ボクヤ」とは、秦シン代以後の官名。左僕射・右僕射があった。▽唐・宋ソウ代は、宰相のこと。

 {動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
{動}いとう(イトフ)。あきる(アク)。ありすぎていやになる。ありすぎてだれる。〈類義語〉→厭エン。「無射=射イトフコト無シ・射アクコト無シ」
 「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
「無射ブエキ」とは、音階の十二律の一つ。また、季節では九月に当たることから、九月の別名。
《解字》
 会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる)
会意。原字は、弓に矢をつがえている姿。のち寸(て)を添えたものとなる。張った弓の弦を放して、緊張を解くこと。
《単語家族》
赦シャ(ゆるめる) 捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨(ゆるめて放す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
弦 いと🔗⭐🔉
【弦】
 8画 弓部 [常用漢字]
区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7
《常用音訓》ゲン/つる
《音読み》 ゲン
8画 弓部 [常用漢字]
区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7
《常用音訓》ゲン/つる
《音読み》 ゲン /ケン
/ケン 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 つる/いと
《名付け》 いと・お・つる・ふさ
《意味》
n〉
《訓読み》 つる/いと
《名付け》 いと・お・つる・ふさ
《意味》
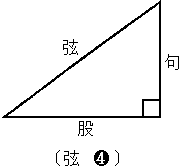
 {名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕
{名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕
 {名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕
{名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕
 {名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」
{名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」
 {名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。
{名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。
 {名}円周上の二点を結ぶ直線。
{名}円周上の二点を結ぶ直線。
 {名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」
{名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」
 {名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。
《解字》
会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄
《単語家族》
幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。
《解字》
会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄
《単語家族》
幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 弓部 [常用漢字]
区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7
《常用音訓》ゲン/つる
《音読み》 ゲン
8画 弓部 [常用漢字]
区点=2425 16進=3839 シフトJIS=8CB7
《常用音訓》ゲン/つる
《音読み》 ゲン /ケン
/ケン 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 つる/いと
《名付け》 いと・お・つる・ふさ
《意味》
n〉
《訓読み》 つる/いと
《名付け》 いと・お・つる・ふさ
《意味》
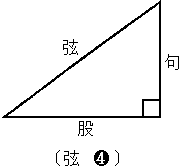
 {名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕
{名}つる。弓のつる。▽もと、絹糸や麻糸をより、にかわを塗ってつくった。「引弦而戦=弦ヲ引キテ戦フ」〔→淮南子〕
 {名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕
{名}いと。琴などの楽器に張ったいと。〈同義語〉→絃。「管弦(笛や琴)」「聞弦歌之声=弦歌ノ声ヲ聞ク」〔→論語〕
 {名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」
{名}半月に欠けた月の直径。▽弓の弦にあたる線のこと。「上弦(陰暦七、八日ごろの月)」「下弦(陰暦二十二、三日ごろの月)」
 {名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。
{名}直角三角形の斜辺のこと。〈対語〉→句・→股コ。
 {名}円周上の二点を結ぶ直線。
{名}円周上の二点を結ぶ直線。
 {名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」
{名}病人の脈で、弱くかつ急で、弓の弦のように震える打ち方のこと。「弦脈」
 {名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。
《解字》
会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄
《単語家族》
幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}夫婦の縁。▽昔は夫婦を琴瑟キンシツ(琴)にたとえたので、「断弦」とは、妻に死なれること。「続弦」とは、後妻をめとること。
《解字》
会意兼形声。玄は、一線の上に細いいとの端がのぞいた姿で、いとの細いこと。弦は「弓+音符玄」で、弓の細いいと。のち楽器につけた細いいとは絃とも書いた。→玄
《単語家族》
幻ゲン(細くて見えにくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
営 いとなむ🔗⭐🔉
【営】
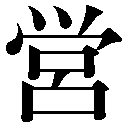 12画 ツ部 [五年]
区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963
【營】旧字旧字
12画 ツ部 [五年]
区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963
【營】旧字旧字
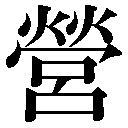 17画 火部
区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A
《常用音訓》エイ/いとな…む
《音読み》 エイ
17画 火部
区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A
《常用音訓》エイ/いとな…む
《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)
/ヨウ(ヤウ) 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 いとなむ
《名付け》 のり・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 いとなむ
《名付け》 のり・よし
《意味》
 {名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」
{名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」
 {名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」
{名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」
 エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
 {動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」
{動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」
 {動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕
{動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕
 {名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」
{名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」
 「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕
「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕
 「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。
《解字》
会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。
《単語家族》
螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる)
「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。
《解字》
会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。
《単語家族》
螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる) 榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
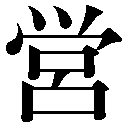 12画 ツ部 [五年]
区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963
【營】旧字旧字
12画 ツ部 [五年]
区点=1736 16進=3144 シフトJIS=8963
【營】旧字旧字
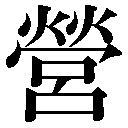 17画 火部
区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A
《常用音訓》エイ/いとな…む
《音読み》 エイ
17画 火部
区点=5159 16進=535B シフトJIS=9A7A
《常用音訓》エイ/いとな…む
《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)
/ヨウ(ヤウ) 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 いとなむ
《名付け》 のり・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 いとなむ
《名付け》 のり・よし
《意味》
 {名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」
{名}ぐるりをとり巻いて守った陣屋。「兵営」「営舎」
 {名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」
{名}軍隊で、大隊のこと。一営は約五百人からなる部隊。また、転じて、軍隊。「第一営(第一大隊)」「緑営(清シン朝の緑旗兵の軍隊)」
 エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
エイス{動}周囲をとり巻く。▽直線の区画を切るのを経ケイといい、外がわをとり巻く区画をつけるのを営エイという。あわせて、荒地を開拓して畑をくぎるのを「経営」といい、転じて、仕事を切り盛りするのを「経営」という。「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
 {動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」
{動}周囲にまといつく。からまる。「営惑」
 {動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕
{動}いとなむ。仕事を切り盛りする。「営造」「売炭得銭何所営=炭ヲ売リ銭ヲ得テ、ナンノ営ムトコロゾ」〔→白居易〕
 {名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」
{名}漢方の医学で、食べ物から得られたエネルギーによる活力のこと。〈類義語〉→栄。「営気(=栄気)」「営養」
 「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕
「営営」とは、ぐるぐる周囲を巡るさま。また、せっせと働くさま。「営営青蠅止于棘=営営タル青蠅ハ棘ニ止マル」〔→詩経〕
 「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。
《解字》
会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。
《単語家族》
螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる)
「営州エイシュウ」とは、古代の十二州の一つ。今の河北・遼寧リョウネイ省から朝鮮までの間の地。
《解字》
会意兼形声。營の上部は炎が周囲をとり巻くこと。營はそれを音符とし、宮(連なった建物)の略体を加えた字で、周囲をたいまつでとり巻いた陣屋のこと。
《単語家族》
螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとり巻いたほたる) 榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
榮(=栄。まるくとり巻いて咲く花)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
愛 いとおしむ🔗⭐🔉
【愛】
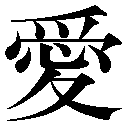 13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ
13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ /オ/アイ
/オ/アイ 〈
〈 i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
 アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
 アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
 アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
 {名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
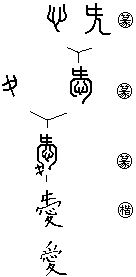 会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである)
会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
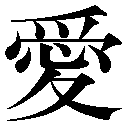 13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ
13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ /オ/アイ
/オ/アイ 〈
〈 i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
 アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
 アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
 アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
 {名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
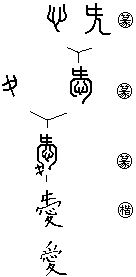 会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである)
会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
意図 イト🔗⭐🔉
【意図】
イト  物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。
物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。 心中で計画する。
心中で計画する。
 物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。
物事をするとき、めざしている事がら。ねらい。 心中で計画する。
心中で計画する。
懶 いとう🔗⭐🔉
暇 いとま🔗⭐🔉
【暇】
 13画 日部 [常用漢字]
区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9
《常用音訓》カ/ひま
《音読み》 カ
13画 日部 [常用漢字]
区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9
《常用音訓》カ/ひま
《音読み》 カ /ゲ
/ゲ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 ひま/いとま
《意味》
〉
《訓読み》 ひま/いとま
《意味》
 {名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕
{名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕
 {名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」
{名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」
 「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。
《単語家族》
假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。
《単語家族》
假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 日部 [常用漢字]
区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9
《常用音訓》カ/ひま
《音読み》 カ
13画 日部 [常用漢字]
区点=1843 16進=324B シフトJIS=89C9
《常用音訓》カ/ひま
《音読み》 カ /ゲ
/ゲ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 ひま/いとま
《意味》
〉
《訓読み》 ひま/いとま
《意味》
 {名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕
{名・形}ひま。仕事がなくて余った時間。仕事がなくてひまなさま。〈類義語〉→閑・→間。「閑暇カンカ(ひま)」「暇日」「以暇日修其孝悌忠信=暇日ヲモッテソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕
 {名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」
{名}いとま。官職や奉公をやめて、ひまな身分になること。「乞暇=暇ヲ乞フ」
 「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。
《単語家族》
假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「不暇…」とは、「…するにいとまあらず」と訓読し、そうするひま・ゆとりがないこと。「我則不暇=我ハ則チ暇アラズ」〔→論語〕「不暇及他=他ニ及ブニ暇アラズ」〔→白居易〕
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カ)は「かぶせる物+=印(下においた物)」の会意文字で、下に物をおいて、上にベールをかぶせるさま。暇はそれを音符とし、日を加えた字で、所要の日時の上にかぶせたよけいな日時のこと。
《単語家族》
假(=仮。本物の上にかぶせたよけいな水増し)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
沖 いとけない🔗⭐🔉
【沖】
 7画 水部 [常用漢字]
区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB
《常用音訓》チュウ/おき
《音読み》 チュウ
7画 水部 [常用漢字]
区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB
《常用音訓》チュウ/おき
《音読み》 チュウ /ジュウ(ヂュウ)
/ジュウ(ヂュウ) 〈ch
〈ch ng〉
《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき
《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし
《意味》
ng〉
《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき
《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし
《意味》
 {動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」
{動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」
 チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」
チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」
 {形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」
{形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」
 チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕
〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。
《解字》
会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕
〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。
《解字》
会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 水部 [常用漢字]
区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB
《常用音訓》チュウ/おき
《音読み》 チュウ
7画 水部 [常用漢字]
区点=1813 16進=322D シフトJIS=89AB
《常用音訓》チュウ/おき
《音読み》 チュウ /ジュウ(ヂュウ)
/ジュウ(ヂュウ) 〈ch
〈ch ng〉
《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき
《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし
《意味》
ng〉
《訓読み》 むなしくする(むなしくす)/むなしい(むなし)/いとけない(いとけなし)/おき
《名付け》 おき・とおる・なか・ふかし
《意味》
 {動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」
{動・形}むなしくする(ムナシクス)。むなしい(ムナシ)。心をむなしくする。また、中がむなしい。「沖譲チュウジョウ」
 チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」
チュウタリ{形}性格や態度がおだやかである。片よらない。〈同義語〉→中。「沖和チュウワ」
 {形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」
{形}いとけない(イトケナシ)。からだがまだ柔らかい。幼い。〈類義語〉→僮ドウ。「沖齢チュウレイ」「沖人チュウジン」
 チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕
〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。
《解字》
会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
チュウス{動}すっとまっすぐに高くあがる。つきあたる。〈類義語〉→衝。「一飛沖天=一タビ飛ビテ天ニ沖ス」〔→史記〕
〔国〕おき。海や湖の陸から遠く離れた水面。
《解字》
会意兼形声。「水+音符中(なか、片よらない、中和)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
猗頓之富 イトンノトミ🔗⭐🔉
【猗頓之富】
イトンノトミ〈故事〉巨万の富のこと。▽猗頓は、春秋時代、魯ロの大富豪。「倚頓」とも。〔→賈誼〕
異図 イト🔗⭐🔉
【異図】
イト むほんをおこそうとするたくらみ。
稚 いとけない🔗⭐🔉
【稚】
 13画 禾部 [常用漢字]
区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274
【穉】異体字異体字
13画 禾部 [常用漢字]
区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274
【穉】異体字異体字
 17画 禾部
区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F
《常用音訓》チ
《音読み》 チ
17画 禾部
区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F
《常用音訓》チ
《音読み》 チ /ジ(ヂ)
/ジ(ヂ) 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)
《名付け》 のり・わか・わく
《意味》
〉
《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)
《名付け》 のり・わか・わく
《意味》
 {形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」
{形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」
 {名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。
《解字》
会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。
《解字》
会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 禾部 [常用漢字]
区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274
【穉】異体字異体字
13画 禾部 [常用漢字]
区点=3553 16進=4355 シフトJIS=9274
【穉】異体字異体字
 17画 禾部
区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F
《常用音訓》チ
《音読み》 チ
17画 禾部
区点=6748 16進=6350 シフトJIS=E26F
《常用音訓》チ
《音読み》 チ /ジ(ヂ)
/ジ(ヂ) 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)
《名付け》 のり・わか・わく
《意味》
〉
《訓読み》 いとけない(いとけなし)/おさない(をさなし)/わかい(わかし)
《名付け》 のり・わか・わく
《意味》
 {形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」
{形}いとけない(イトケナシ)。おさない(ヲサナシ)。わかい(ワカシ)。まだのびきらないで、たけが小さい。年が少ない。〈対語〉→壮・→老。「幼稚」
 {名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。
《解字》
会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}おさない子ども。〈類義語〉→幼・→児。
《解字》
会意。もと「禾(作物)+遲チ(成長がおそい)」で、稚はその俗字。生長がおくれて小さい作物。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
糸 いと🔗⭐🔉
【糸】
 6画 糸部 [一年]
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
【絲】旧字(A)旧字(A)
6画 糸部 [一年]
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
【絲】旧字(A)旧字(A)
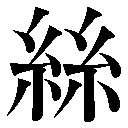 12画 糸部
区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E
【糸】旧字(B)旧字(B)
12画 糸部
区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E
【糸】旧字(B)旧字(B)
 6画 糸部
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
《常用音訓》シ/いと
《音読み》 (A)シ
6画 糸部
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
《常用音訓》シ/いと
《音読み》 (A)シ
 〈s
〈s 〉/(B)ベキ
〉/(B)ベキ /ミャク
/ミャク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より
《意味》
(A)【絲】
〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より
《意味》
(A)【絲】 {名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」
{名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」
 {名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」
{名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」
 {名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕
{名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕
 {単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」
(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。
〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。
《解字》
{単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」
(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。
〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。
《解字》
 会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。
《単語家族》
子(小さいこども)
会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。
《単語家族》
子(小さいこども) 巳シ(小さい胎児)
巳シ(小さい胎児) 思(こまごまと考える)などと同系。
《類義》
縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
思(こまごまと考える)などと同系。
《類義》
縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 糸部 [一年]
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
【絲】旧字(A)旧字(A)
6画 糸部 [一年]
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
【絲】旧字(A)旧字(A)
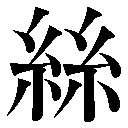 12画 糸部
区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E
【糸】旧字(B)旧字(B)
12画 糸部
区点=6915 16進=652F シフトJIS=E34E
【糸】旧字(B)旧字(B)
 6画 糸部
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
《常用音訓》シ/いと
《音読み》 (A)シ
6画 糸部
区点=2769 16進=3B65 シフトJIS=8E85
《常用音訓》シ/いと
《音読み》 (A)シ
 〈s
〈s 〉/(B)ベキ
〉/(B)ベキ /ミャク
/ミャク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より
《意味》
(A)【絲】
〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・たえ・ため・つら・より
《意味》
(A)【絲】 {名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」
{名}いと。もと、蚕の繭の繊維をよったもの。きぬいと。のち、織物の原料になるよりいとをすべて糸という。「絹糸」「抽糸=糸ヲ抽ク」「乱如糸=乱レテ糸ノゴトシ」
 {名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」
{名}いと。いとのように細い線をなしたもの。〈類義語〉→条。「柳糸(柳の細い枝)」「菌糸」「雨糸(細い雨)」
 {名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕
{名}管楽器に対して琴や琵琶ビワなど、弦楽器のこと。〈類義語〉→絃。「糸竹(弦楽器と管楽器。楽器)」「宴酣之楽非糸非竹=宴酣ナルノ楽ハ糸ニアラズ竹ニアラズ」〔→欧陽脩〕
 {単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」
(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。
〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。
《解字》
{単位}割合をあらわすことば。一糸は、一毫ゴウの十分の一で、一の一万分の一。「糸毫」
(B)【糸】{名}蚕の繭からとった細い原糸。
〔国〕いと。ぬいいと。▽中国では、綫セン・線といい、糸シとはいわない。
《解字》
 会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。
《単語家族》
子(小さいこども)
会意。絲は、糸ベキを二つ並べたもので、よりいとのこと。いま、ベキ(糸)をシ(絲)の略字に使って、シと読む。小さく細かい意を含む。
《単語家族》
子(小さいこども) 巳シ(小さい胎児)
巳シ(小さい胎児) 思(こまごまと考える)などと同系。
《類義》
縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
思(こまごまと考える)などと同系。
《類義》
縷ルは、ほそぼそと連なった糸。絮ジョ・ショは、やわらかい綿の繊維。線は、細長いいと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
糸遊 イトユウ🔗⭐🔉
【糸遊】
イトユウ〔国〕春や夏、日光が照りつけて地面からたちのぼる気。かげろう。陽炎。
紀 いとぐち🔗⭐🔉
【紀】
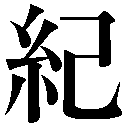 9画 糸部 [四年]
区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49
《常用音訓》キ
《音読み》 キ
9画 糸部 [四年]
区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49
《常用音訓》キ
《音読み》 キ /コ
/コ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き
《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし
《意味》
〉
《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き
《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし
《意味》
 キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」
キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」
 {名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」
{名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」
 {名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」
{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」
 「世紀」とは、年代の百年間。
「世紀」とは、年代の百年間。
 キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕
キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕
 {名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」
〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」
《解字》
会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。
《単語家族》
起(おこす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」
〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」
《解字》
会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。
《単語家族》
起(おこす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
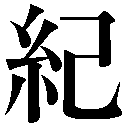 9画 糸部 [四年]
区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49
《常用音訓》キ
《音読み》 キ
9画 糸部 [四年]
区点=2110 16進=352A シフトJIS=8B49
《常用音訓》キ
《音読み》 キ /コ
/コ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き
《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし
《意味》
〉
《訓読み》 おさめる(おさむ)/のり/いとぐち/しるす/き
《名付け》 あき・おさ・おさむ・かず・かなめ・こと・しるす・すみ・ただ・ただし・つぐ・つな・とし・のり・はじめ・もと・よし
《意味》
 キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」
キス{動}おさめる(オサム)。物事のおこりを定める。また、はじめをきめて順序よく仕事を進める。「経紀(出発点と、それから後のすじ道をたてて仕事を進める。転じて、事業や商売の進め方。経営のしかた)」
 {名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」
{名}のり。いとぐち。物事のはじめ。また、はじめから順序よく整理するための手順。すじ道。〈類義語〉→綱。「紀律」「綱紀(すじ道)」
 {名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」
{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ…の十二支のひと回りの十二年間。▽道家では、一千五百二十年を一紀という。「一紀(十二年)」「年紀」
 「世紀」とは、年代の百年間。
「世紀」とは、年代の百年間。
 キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕
キス{動}しるす。物事の順序を追って書きしるす。〈同義語〉→記。「紀念(=記念)」「咸用紀宗存主=咸モッテ宗ヲ紀シ主ヲ存ス」〔→張衡〕
 {名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」
〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」
《解字》
会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。
《単語家族》
起(おこす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}順序よく、または年を追って書きしるした書。また、歴史書の帝王に関する記述。「紀行」「本紀」「紀年(年を追ってしるした歴史書)」
〔国〕き。「日本書紀」の略。「記紀」
《解字》
会意兼形声。己キとは、曲がっておきたつさま。または、曲がった目じるし。紀は「糸+音符己」で、糸のはじめを求め、目じるしをつけ、そこから巻く、織るなどの動作をおこすこと。
《単語家族》
起(おこす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
絃 いと🔗⭐🔉
【絃】
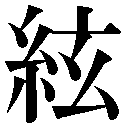 11画 糸部 [人名漢字]
区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC
《音読み》 ゲン
11画 糸部 [人名漢字]
区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC
《音読み》 ゲン /ケン
/ケン 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・お・つる
《意味》
{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。
《単語家族》
玄(宙づりであいまい)
n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・お・つる
《意味》
{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。
《単語家族》
玄(宙づりであいまい) 牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【弦】を見よ。
牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【弦】を見よ。
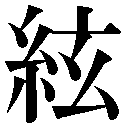 11画 糸部 [人名漢字]
区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC
《音読み》 ゲン
11画 糸部 [人名漢字]
区点=2430 16進=383E シフトJIS=8CBC
《音読み》 ゲン /ケン
/ケン 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・お・つる
《意味》
{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。
《単語家族》
玄(宙づりであいまい)
n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 いと・お・つる
《意味》
{名}いと。琴や胡弓コキュウなどの楽器のいと。はじいたりこすったりして音を出す。また、それを用いた楽器のこと。「管絃カンゲン」「断絃ダンゲン(いとが切れる→夫婦を琴瑟キンシツにたとえることから、妻に死なれること)」「続絃ゾクゲン(いとをつぐ→夫婦を琴瑟にたとえることから、後妻をめとること)」〈同義語〉→弦。
《解字》
会意兼形声。「糸+音符玄(宙ぶらりの細いいと)」。
《単語家族》
玄(宙づりであいまい) 牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【弦】を見よ。
牽ケン(綱をつけて引っぱり、綱が宙にかかった形になる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
〈注〉熟語は→【弦】を見よ。
統 いとぐち🔗⭐🔉
【統】
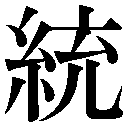 12画 糸部 [五年]
区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D
《常用音訓》トウ/す…べる
《音読み》 トウ
12画 糸部 [五年]
区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D
《常用音訓》トウ/す…べる
《音読み》 トウ
 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて
《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと
《意味》
ng〉
《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて
《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと
《意味》
 {名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」
{名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」
 {名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕
{名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕
 {動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕
{動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕
 「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕
「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕
 {副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。
{副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。
 「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」
《解字》
会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」
《解字》
会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
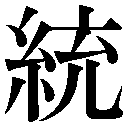 12画 糸部 [五年]
区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D
《常用音訓》トウ/す…べる
《音読み》 トウ
12画 糸部 [五年]
区点=3793 16進=457D シフトJIS=939D
《常用音訓》トウ/す…べる
《音読み》 トウ
 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて
《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと
《意味》
ng〉
《訓読み》 いとぐち/すじ(すぢ)/すべる(すぶ)/おさめる(をさむ)/すべて
《名付け》 おさ・おさむ・かね・すぶる・すみ・すめる・つづき・つな・つね・のり・むね・もと
《意味》
 {名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」
{名}いとぐち。全体につながる糸のすじ。もとづな。〈類義語〉→紀。「統紀」
 {名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕
{名}すじ(スヂ)。全体につながるすじ。「系統」「伝統」「君子創業垂統=君子ハ業ヲ創メ統ヲ垂ル」〔→孟子〕
 {動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕
{動}すべる(スブ)。おさめる(ヲサム)。全体をひとすじにまとめる。〈類義語〉→治。「統一」「統治」「統率」「統楫群元=群元ヲ統楫ス」〔→漢書〕
 「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕
「一統イットウ」とは、ひとすじにまとまったもの。「大一統也=一統ヲ大ブナリ」〔→公羊〕
 {副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。
{副}すべて。全体で。とりまとめて。〈類義語〉→全・→総。
 「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」
《解字》
会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「三統サントウ」とは、世界をつくるという天・地・人の三つの系統。「三統暦サントウレキ(前漢代末期に劉向リュウキョウがつくったこよみ)」
《解字》
会意兼形声。充ジュウは、子どもが充実して育つこと。全体にゆきわたる意を含む。統は「糸+音符充」で、糸すじが端から全体へとゆきわたること。▽通トウ・ツウ(全体にゆきわたる)と縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
緒 いとぐち🔗⭐🔉
【緒】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 糸部 [常用漢字]
区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F
《常用音訓》ショ/チョ/お
《音読み》 ショ
14画 糸部 [常用漢字]
区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F
《常用音訓》ショ/チョ/お
《音読み》 ショ /チョ
/チョ /ジョ
/ジョ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 いとぐち/お(を)
《名付け》 お・つぐ
《意味》
〉
《訓読み》 いとぐち/お(を)
《名付け》 お・つぐ
《意味》
 {名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕
{名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕
 {名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」
{名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」
 {名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」
{名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」
 {名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」
〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。
《単語家族》
紵チョ(糸をたくわえる糸巻き)
{名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」
〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。
《単語家族》
紵チョ(糸をたくわえる糸巻き) 貯チョ(中にたくわえる)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
貯チョ(中にたくわえる)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 糸部 [常用漢字]
区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F
《常用音訓》ショ/チョ/お
《音読み》 ショ
14画 糸部 [常用漢字]
区点=2979 16進=3D6F シフトJIS=8F8F
《常用音訓》ショ/チョ/お
《音読み》 ショ /チョ
/チョ /ジョ
/ジョ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 いとぐち/お(を)
《名付け》 お・つぐ
《意味》
〉
《訓読み》 いとぐち/お(を)
《名付け》 お・つぐ
《意味》
 {名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕
{名}いとぐち。糸巻きにまいた糸のはし。転じて、物事を引き出す手口。物事のはじめ。〈類義語〉→端。「端緒」「千頭万緒セントウバンショ(事がもつれていとぐちがわからない)」「就緒=緒ニ就ク」「探礼楽之緒=礼楽ノ緒ヲ探ル」〔→司馬光〕
 {名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」
{名}長く続いた物事のつながり。系統を引くもの。「宗緒ソウショ(家系)」「由緒ユイショ・ユウショ(系統を引く事がらのおこり)」
 {名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」
{名}はみ出た部分。たまった心からはみ出た感情。あるきっかけからつぎつぎと引き出される思い。「情緒」
 {名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」
〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。
《単語家族》
紵チョ(糸をたくわえる糸巻き)
{名}事をのべるいとぐち。はしがき。「緒言ショゲン(はしがき)」
〔国〕お(ヲ)。細長いひも。「鼻緒」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符者シャ(集まる、つめこむ)」。転じて糸巻きにたくわえた糸のはみ出たはし、の意となった。
《単語家族》
紵チョ(糸をたくわえる糸巻き) 貯チョ(中にたくわえる)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
貯チョ(中にたくわえる)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
綸 いと🔗⭐🔉
【綸】
 14画 糸部 [人名漢字]
区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364
《音読み》
14画 糸部 [人名漢字]
区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364
《音読み》  リン
リン
 〈l
〈l n〉/
n〉/ カン(ク
カン(ク ン)
ン) /ケン
/ケン 〈gu
〈gu n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 お・くみ
《意味》
n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 お・くみ
《意味》

 {名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。
{名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。
 {名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。
{名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。
 {名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」
{名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」
 「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 14画 糸部 [人名漢字]
区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364
《音読み》
14画 糸部 [人名漢字]
区点=6937 16進=6545 シフトJIS=E364
《音読み》  リン
リン
 〈l
〈l n〉/
n〉/ カン(ク
カン(ク ン)
ン) /ケン
/ケン 〈gu
〈gu n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 お・くみ
《意味》
n〉
《訓読み》 いと
《名付け》 お・くみ
《意味》

 {名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。
{名}青い印綬インジュ。▽カンとも読む。
 {名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。
{名}いと。絹糸十本をきちんとよりあわせたひも。「王言如糸、其出如綸、=王言ハ糸ノゴトクナレドモ、ソノ出ヅルヤ綸ノゴトシ」〔→礼記〕▽この「礼記」の文句から、詔勅のことを、「綸言リンゲン」という。
 {名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」
{名}いと。釣りいと。「垂綸=綸ヲ垂ル」「収綸=綸ヲ収ム」
 「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「綸巾カンキン」とは、(青い)絹の組みひもでつくったずきん。ふだん着用のかぶりもの。▽諸葛ショカツ孔明は青いのを、漢・魏ギ時代の風流人は白いのを使ったという。「半脱綸巾臥翠籐=半バ綸巾ヲ脱シテ翠籐ニ臥ス」〔→陸游〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符侖(きちんとそろう)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
縷 いと🔗⭐🔉
【縷】
 17画 糸部
区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E
《音読み》
17画 糸部
区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E
《音読み》  ル
ル
 〈l
〈l 〉/
〉/ ル
ル /ロウ
/ロウ 《訓読み》 いと
《意味》
《訓読み》 いと
《意味》

 {名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕
{名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕
 ルス{動}縫いとりをする。
ルス{動}縫いとりをする。
 {形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」
{形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」
 {名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。
《単語家族》
樓(=楼。つらなる高殿)と同系。
《類義》
→糸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。
《単語家族》
樓(=楼。つらなる高殿)と同系。
《類義》
→糸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 17画 糸部
区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E
《音読み》
17画 糸部
区点=6963 16進=655F シフトJIS=E37E
《音読み》  ル
ル
 〈l
〈l 〉/
〉/ ル
ル /ロウ
/ロウ 《訓読み》 いと
《意味》
《訓読み》 いと
《意味》

 {名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕
{名}いと。細ぼそとつらなるいと。また縫いいと。〈類義語〉→線・→糸。「余音嫋嫋、不絶如縷=余音嫋嫋トシテ、絶エザルコト縷ノゴトシ」〔→蘇軾〕
 ルス{動}縫いとりをする。
ルス{動}縫いとりをする。
 {形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」
{形}いとのように細長くつらなるさま。くどくどとしているさま。「縷説ルセツ」
 {名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。
《単語家族》
樓(=楼。つらなる高殿)と同系。
《類義》
→糸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}つづれ。破れ布をつないだぼろ。「襤縷ランル」
《解字》
会意兼形声。「糸+音符婁ロウ・ル(細くつらなる)」。
《単語家族》
樓(=楼。つらなる高殿)と同系。
《類義》
→糸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遑 いとまあり🔗⭐🔉
【遑】
 13画
13画  部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク
部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
 {形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢
{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「
テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。
+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。
の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画
13画  部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク
部
区点=7803 16進=6E23 シフトJIS=E7A1
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
ng〉
《訓読み》 あわただしい(あわただし)/いとまあり
《意味》
 {形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
{形}あわただしい(アワタダシ)。うろうろして落ち着けない。〈同義語〉→惶。
 {形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢
{形}いとまあり。ゆとりがある。ひまである。「飢不遑食=飢 テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「
テ食ラフニ遑アラズ」〔→曹植〕「不遑寧処=寧処スルニ遑アラズ」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「 +音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。
+音符皇(大きく広がる)」で、大きい意を含む。 の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。
の意味は、大きいことから、むやみに動きまわる、うろうろする意になったもので、狂(むてっぽうな犬)・往(むやみに前進する)と近い。 は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
は、広い、ゆったりしているという方向に派生した意味で、ゆとりがあること。
《単語家族》
皇(大きい巨人)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「いと」で始まるの検索結果 1-36。
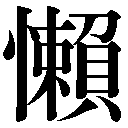 19画
19画  部
区点=5681 16進=5871 シフトJIS=9CEF
《音読み》
部
区点=5681 16進=5871 シフトJIS=9CEF
《音読み》