複数辞典一括検索+![]()
![]()
好 すく🔗⭐🔉
【好】
 6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
 〈h
〈h o・h
o・h o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
 {動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
 {形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
 {形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
 {名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
 {動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
 {名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
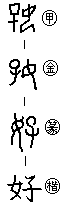 会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする)
会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)
畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
 〈h
〈h o・h
o・h o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
 {動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
 {形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
 {形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
 {名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
 {動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
 {名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
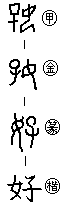 会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする)
会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)
畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
宿世 スクセ🔗⭐🔉
【宿世】
シュクセ・スクセ〔仏〕 現世にうまれる前の世。前世。
現世にうまれる前の世。前世。 前世からの因縁、また、運命。
前世からの因縁、また、運命。
 現世にうまれる前の世。前世。
現世にうまれる前の世。前世。 前世からの因縁、また、運命。
前世からの因縁、また、運命。
宿禰 スクネ🔗⭐🔉
【宿禰】
スクネ〔国〕 昔、臣下を親しんで呼んだことば。
昔、臣下を親しんで呼んだことば。 八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。
八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。
 昔、臣下を親しんで呼んだことば。
昔、臣下を親しんで呼んだことば。 八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。
八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの三番め。
寡 すくない🔗⭐🔉
【寡】
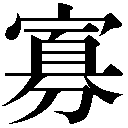 14画 宀部 [常用漢字]
区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7
《常用音訓》カ
《音読み》 カ(ク
14画 宀部 [常用漢字]
区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7
《常用音訓》カ
《音読み》 カ(ク )
) /ケ
/ケ 〈gu
〈gu 〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ
《意味》
〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ
《意味》
 {形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕
{形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕
 {動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕
{動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕
 {名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕
{名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕
 {名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」
{名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」
 {形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕
《解字》
会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。
《単語家族》
孤と同系。
《類義》
少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕
《解字》
会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。
《単語家族》
孤と同系。
《類義》
少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
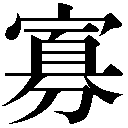 14画 宀部 [常用漢字]
区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7
《常用音訓》カ
《音読み》 カ(ク
14画 宀部 [常用漢字]
区点=1841 16進=3249 シフトJIS=89C7
《常用音訓》カ
《音読み》 カ(ク )
) /ケ
/ケ 〈gu
〈gu 〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ
《意味》
〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/すくなくする(すくなくす)/やもめ
《意味》
 {形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕
{形}すくない(スクナシ)。ひとりぼっちで、味方や財産がすくない。▽下に補足語があれば、前に返って訓読する。〈対語〉→衆・→多。〈類義語〉→孤・→少。「寡尢=尢寡ナシ」〔→論語〕
 {動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕
{動}すくなくする(スクナクス)。減らす。「欲寡其過而未能也=ソノ過チヲ寡ナクセント欲シテ、イマダアタハザルナリ」〔→論語〕
 {名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕
{名}小人数。また、わずかな力。〈対語〉→衆。「寡固不可以敵衆=寡ハ固ヨリモツテ衆ニ敵スベカラズ」〔→孟子〕
 {名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」
{名}やもめ。夫に死なれた女。女が夫に死なれたこと。「寡婦」「守寡=寡ヲ守ル」
 {形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕
《解字》
会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。
《単語家族》
孤と同系。
《類義》
少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}徳のすくない意から、諸侯がみずからを謙そんしていうことば。「寡人願安承教=寡人、願ハクハ安ンジテ教ヘヲ承ケン」〔→孟子〕
《解字》
会意。宀(やね)の下に頭だけ大きいひとりの子が残された姿を示すもので、ひとりぼっちのさまを示す。たよるべき人や力のないこと。
《単語家族》
孤と同系。
《類義》
少は、削られて減ること。鮮センは、めったにないこと。稀は、わずかで目につかないこと。孤も、寡と同系で、ひとりぼっちの子どものこと。独は、一定の場所にくっついて、それだけ動かないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
少 すくない🔗⭐🔉
【少】
 4画 小部 [二年]
区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD
《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し
《音読み》 ショウ(セウ)
4画 小部 [二年]
区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD
《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈sh
〈sh o・sh
o・sh o〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)
《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ
《意味》
o〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)
《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ
《意味》
 {形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕
{形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕
 {名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕
{名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕
 {動}かく。足りない。「欠少」
{動}かく。足りない。「欠少」
 {副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕
{副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕
 {副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕
{副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕
 {形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕
{形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕
 {名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。
《解字》
{名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。
《解字》
 会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。
《単語家族》
抄ショウ(さっとかすめる)と同系。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。
《単語家族》
抄ショウ(さっとかすめる)と同系。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 4画 小部 [二年]
区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD
《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し
《音読み》 ショウ(セウ)
4画 小部 [二年]
区点=3015 16進=3E2F シフトJIS=8FAD
《常用音訓》ショウ/すく…ない/すこ…し
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈sh
〈sh o・sh
o・sh o〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)
《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ
《意味》
o〉
《訓読み》 すくない(すくなし)/かく/すこし/すこしく/しばらく/わかい(わかし)
《名付け》 お・すく・すくな・つぎ・まさ・まれ
《意味》
 {形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕
{形}すくない(スクナシ)。たくさんない。わずかな。▽後に名詞を伴うときは、前に返って訓読する。〈対語〉→多・→衆。〈類義語〉→寡・→稀。「兵少食尽=兵少ナク食尽ク」〔→史記〕「峨嵋山下少人行=峨嵋山下人行少ナシ」〔→白居易〕
 {名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕
{名}少数。また、少数の人。〈対語〉→衆。「与少楽楽=少ト楽ヲ楽シム」〔→孟子〕
 {動}かく。足りない。「欠少」
{動}かく。足りない。「欠少」
 {副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕
{副}すこし。すこしく。程度・数量がすくないこと。わずかに。「少光王室=少シク王室ヲ光カス」〔→国語〕
 {副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕
{副}しばらく。すこしの間たって。しばし。「少則洋洋焉=シバラクスレバスナハチ洋洋タリ」〔→孟子〕
 {形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕
{形・名}わかい(ワカシ)。年がわかい。わかい者。▽去声に読む。〈対語〉→長・→老。「少年」「少時(わかい時)」「人少則慕父母=人少ケレバスナハチ父母ヲ慕フ」〔→孟子〕「比少已憔悴=少ニクラブレバスデニ憔悴ス」〔→袁宏道〕
 {名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。
《解字》
{名}添え役。▽「太師」「太傅タイフ」に対して、そのわき役を「少師」「少傅」という。去声に読む。
《解字》
 会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。
《単語家族》
抄ショウ(さっとかすめる)と同系。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
会意。「小(ちいさくけずる)+ノ印(そぎとる)」で、削って減らすこと。のち、分量や数が満ち足りない意に用い、年齢の満ち足りないのを少年という。
《単語家族》
抄ショウ(さっとかすめる)と同系。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
尠 すくない🔗⭐🔉
【尠】
 13画 小部
区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96
《音読み》 セン
13画 小部
区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96
《音読み》 セン
 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」
《解字》
会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。
n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」
《解字》
会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。
 13画 小部
区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96
《音読み》 セン
13画 小部
区点=5386 16進=5576 シフトJIS=9B96
《音読み》 セン
 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」
《解字》
会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。
n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。ひじょうにすくない。また、まばらである。〈同義語〉→鮮。「尠少センショウ」
《解字》
会意。「甚(はなはだしい)+少(すくない)」。
巣 すくう🔗⭐🔉
【巣】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
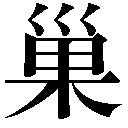 11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ)
11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)
/ジョウ(ゼウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
 {名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
 {動}すくう(スクフ)。巣
{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
 {名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
 会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも)
会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)
剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
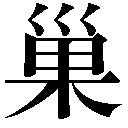 11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ)
11画 ツ部 [四年]
区点=3367 16進=4163 シフトJIS=9183
《常用音訓》ソウ/す
《音読み》 ソウ(サウ) /ジョウ(ゼウ)
/ジョウ(ゼウ) 〈ch
〈ch o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
o〉
《訓読み》 す/すくう(すくふ)
《名付け》 す
《意味》
 {名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
{名}す。木の上に構えた鳥のす。〈類義語〉→栖セイ。「下者為巣=下キ者ハ巣ヲ為ル」〔→孟子〕
 {動}すくう(スクフ)。巣
{動}すくう(スクフ)。巣 をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
をつくる。「越鳥巣南枝=越鳥、南枝ニ巣クフ」〔→古詩十九首〕
 {名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
{名}盗賊のかくれがを鳥のすにたとえていう。「巣穴」「賊巣」
《解字》
 会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも)
会意。「鳥のすのかたち(のち西と書く)+木」で、高い木の上の鳥のすのこと。高く浮いて見える意を含む。
《単語家族》
藻ソウ(上に浮いたも) 剿ソウ(表面をかすめとる)
剿ソウ(表面をかすめとる) 抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
抄(表面をかすめとる)と同系。
《類義》
栖セイは、ざる状をした、す。おもにすにすむ意に用い、棲セイとも書く。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は11画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
戔 すくない🔗⭐🔉
【戔】
 8画 戈部
区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB
《音読み》 セン
8画 戈部
区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB
《音読み》 セン
 /サン
/サン /ザン
/ザン 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」
《解字》
n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」
《解字》
 会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。
《単語家族》
殘(=残。わずかなのこり)
会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。
《単語家族》
殘(=残。わずかなのこり) 淺(=浅。水が少ない→あさい)
淺(=浅。水が少ない→あさい) 賤(財貨がすくない→いやしい)
賤(財貨がすくない→いやしい) 盞サン(小さいさかずき)などと同系。
盞サン(小さいさかずき)などと同系。
 8画 戈部
区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB
《音読み》 セン
8画 戈部
区点=5693 16進=587D シフトJIS=9CFB
《音読み》 セン
 /サン
/サン /ザン
/ザン 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」
《解字》
n〉
《訓読み》 すくない(すくなし)
《意味》
{形}すくない(スクナシ)。小さい。また、すくない。「戔戔センセン(わずか)」
《解字》
 会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。
《単語家族》
殘(=残。わずかなのこり)
会意。「戈(ほこ)+戈(ほこ)」で、刃物で削りに削って残りすくない意を示す。小さい、すくないの意を含む。
《単語家族》
殘(=残。わずかなのこり) 淺(=浅。水が少ない→あさい)
淺(=浅。水が少ない→あさい) 賤(財貨がすくない→いやしい)
賤(財貨がすくない→いやしい) 盞サン(小さいさかずき)などと同系。
盞サン(小さいさかずき)などと同系。
抔 すくい🔗⭐🔉
【抔】
 7画
7画  部
区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57
《音読み》 ホウ
部
区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57
《音読み》 ホウ /ブ
/ブ 〈p
〈p u〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など
《意味》
{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」
〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不
《単語家族》
杯(まるくふくれたさかずき)
u〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など
《意味》
{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」
〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不
《単語家族》
杯(まるくふくれたさかずき) 胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画
7画  部
区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57
《音読み》 ホウ
部
区点=5724 16進=5938 シフトJIS=9D57
《音読み》 ホウ /ブ
/ブ 〈p
〈p u〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など
《意味》
{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」
〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不
《単語家族》
杯(まるくふくれたさかずき)
u〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)/など
《意味》
{動・単位}すくう(スクフ)。すくい(スクヒ)。両手をまるくあわせてすくう。また、その単位。「抔土ホウド」「一抔土イッポウノド(手ですくった土、転じてまるく土を盛りあげた墓のつか)」
〔国〕など。それだけに限らないがという気持ちをふくめて、例示することをあらわすことば。
《解字》
会意兼形声。不は、まるくふくれたつぼみの形を描いた象形文字。抔は「手+音符不」で、両手をまるくふくらませてすくうこと。▽杯・坏ハイは、別字。→不
《単語家族》
杯(まるくふくれたさかずき) 胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
胚ハイ(まるくふくれた胚芽)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
拯 すくう🔗⭐🔉
振 すくう🔗⭐🔉
【振】
 10画
10画  部 [常用漢字]
区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055
《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう
《音読み》 シン
部 [常用漢字]
区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055
《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう
《音読み》 シン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり
《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる
《意味》
n〉
《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり
《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる
《意味》
 {動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕
{動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕
 {動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」
{動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」
 {動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕
{動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕
 {動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」
{動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」
 {動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」
〔国〕
{動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」
〔国〕 ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」
ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」 ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」
《解字》
会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰
《単語家族》
震(ふるえる)と同系。
《類義》
→揮
《異字同訓》
ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」
《解字》
会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰
《単語家族》
震(ふるえる)と同系。
《類義》
→揮
《異字同訓》
ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画
10画  部 [常用漢字]
区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055
《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう
《音読み》 シン
部 [常用漢字]
区点=3122 16進=3F36 シフトJIS=9055
《常用音訓》シン/ふ…る/ふ…るう
《音読み》 シン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり
《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる
《意味》
n〉
《訓読み》 ふる/ふるう(ふるふ)/すくう(すくふ)/ふり
《名付け》 とし・のぶ・ふり・ふる
《意味》
 {動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕
{動}ふる。ふるう(フルフ)。ゆすって動かす。びりびりと小きざみにふる。「振鈴=鈴ヲ振ル」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕
 {動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」
{動}ふるう(フルフ)。沈滞したものにショックを与えて動き出させる。ふるいおこす。ふるいたつ。活発に活動する。「不振=振ルハズ」「振興」「振作シンサ・シンサク(ふるいおこす)」
 {動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕
{動}ふるう(フルフ)。人々を恐れさせる。耳目を驚かす。〈同義語〉→震。「威振四海=威四海ニ振ルフ」〔→史記〕
 {動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」
{動}すくう(スクフ)。災害にあった者や貧困者に施しをして、元気づける。〈同義語〉→賑。「振救(=賑救)」「振済(=賑済)」
 {動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」
〔国〕
{動}疲れたもの、たるんだものをはげます。「振旅」
〔国〕 ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」
ふり。(イ)身のこなしや手足の動かしかた。「手振り」「なり振りかまわず」(ロ)芝居や踊りのしぐさ。「振り付け」 ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」
《解字》
会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰
《単語家族》
震(ふるえる)と同系。
《類義》
→揮
《異字同訓》
ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
ふり。刀剣を数えるときのことば。「名刀一振り」
《解字》
会意兼形声。辰シンは、蜃シン(はまぐり)の原字で、貝が開いてぴらぴらとふるう舌の出たさまを描いた象形文字。振は「手+音符辰」で、貝の舌のように、小きざみにふるえ動くこと。→辰
《単語家族》
震(ふるえる)と同系。
《類義》
→揮
《異字同訓》
ふるう。 振るう「士気が振るう。事業が振るわない。刀を振るう」震う「声を震わせる。身震い。武者震い」奮う「勇気を奮って立ち向かう。奮って参加する。奮い立つ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
掬 すくう🔗⭐🔉
【掬】
 11画
11画  部
区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64
《音読み》 キク
部
区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64
《音読み》 キク
 〈j
〈j 〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
 キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕
キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕
 「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕
「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕
 {単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。
《単語家族》
菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花)
{単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。
《単語家族》
菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花) 鞠キク(まるいたま)
鞠キク(まるいたま) 球と同系。
《類義》
→汲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
球と同系。
《類義》
→汲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画
11画  部
区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64
《音読み》 キク
部
区点=2137 16進=3545 シフトJIS=8B64
《音読み》 キク
 〈j
〈j 〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
 キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕
キクス{動}すくう(スクフ)。片手または両手をまるくして、その中へ水をすくいとる。また、手のひらをまるめて、その中にのせる。「掬水=水ヲ掬フ」「流花去難掬=流花去リテ掬シ難シ」〔→高啓〕
 「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕
「可掬キクスベシ」とは、手にすくうほど多いこと。手にとって見るほど明らかである。「饑寒之色可掬=饑寒ノ色、掬スベシ」〔→杜子春〕「舟中之指可掬也=舟中ノ指掬スベシ」〔→左伝〕
 {単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。
《単語家族》
菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花)
{単位}両手一ぱいほどの量。▽春秋・戦国時代の一掬は、約〇・二リットル。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音キク)は「勹(つつむ)+米」からなる会意文字で、手をまるめて米や水をつつむようにすくうこと。のち、手をそえた掬の字で、その原義をあらわす。また、まるくつつんだ意を含む。
《単語家族》
菊(まるくつつんだ形をした球状のきくの花) 鞠キク(まるいたま)
鞠キク(まるいたま) 球と同系。
《類義》
→汲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
球と同系。
《類義》
→汲
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
掏 すくう🔗⭐🔉
【掏】
 11画
11画  部
区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A
《音読み》 トウ(タウ)
部
区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈t
〈t o〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
 {動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。
{動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。
 {動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。
《単語家族》
搗トウ(こねる)
{動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。
《単語家族》
搗トウ(こねる) 陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。
《熟語》
→熟語
陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。
《熟語》
→熟語
 11画
11画  部
区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A
《音読み》 トウ(タウ)
部
区点=5759 16進=595B シフトJIS=9D7A
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈t
〈t o〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
 {動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。
{動}すくう(スクフ)。手をまるくまるめて器の中から物をすくい出す。
 {動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。
《単語家族》
搗トウ(こねる)
{動}〔俗〕他人のふところから、物をすくいとる。「掏児タオル(すり)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「手をまるく曲げた形+缶(ほとぎ)」からなり、器の中に手をまるくして入れて、こねるさま。掏はそれを音符とし、手を加えた字で、土をこねるような手つきで、物を器の中からすくって外に出すこと。
《単語家族》
搗トウ(こねる) 陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。
《熟語》
→熟語
陶トウ(粘土をこねてつくった陶器)と同系。
《熟語》
→熟語
撈 すくう🔗⭐🔉
救 すくい🔗⭐🔉
【救】
 11画 攴部 [四年]
区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E
《常用音訓》キュウ/すく…う
《音読み》 キュウ(キウ)
11画 攴部 [四年]
区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E
《常用音訓》キュウ/すく…う
《音読み》 キュウ(キウ) /ク
/ク 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)
《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす
《意味》
〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)
《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす
《意味》
 {動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕
{動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕
 {名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕
《解字》
会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求
《単語家族》
糾キュウ(ぐいと引き締める)
{名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕
《解字》
会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求
《単語家族》
糾キュウ(ぐいと引き締める) 球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。
《類義》
→助
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。
《類義》
→助
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 攴部 [四年]
区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E
《常用音訓》キュウ/すく…う
《音読み》 キュウ(キウ)
11画 攴部 [四年]
区点=2163 16進=355F シフトJIS=8B7E
《常用音訓》キュウ/すく…う
《音読み》 キュウ(キウ) /ク
/ク 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)
《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす
《意味》
〉
《訓読み》 すくう(すくふ)/すくい(すくひ)
《名付け》 すけ・たすく・なり・ひら・やす
《意味》
 {動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕
{動}すくう(スクフ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。〈類義語〉→助。「救助」「救死=死ヲ救フ」「女弗能救与=ナンヂ救フコトアタハザルカ」〔→論語〕
 {名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕
《解字》
会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求
《単語家族》
糾キュウ(ぐいと引き締める)
{名}すくい(スクヒ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ヒヲ斉ニ求ム」〔→国策〕
《解字》
会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘キュウ(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+音符求」で、引き締めて食い止めること。 →求
《単語家族》
糾キュウ(ぐいと引き締める) 球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。
《類義》
→助
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。
《類義》
→助
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
済 すくう🔗⭐🔉
【済】
 11画 水部 [六年]
区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF
【濟】旧字旧字
11画 水部 [六年]
区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF
【濟】旧字旧字
 17画 水部
区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A
《常用音訓》サイ/す…ます/す…む
《音読み》 サイ
17画 水部
区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A
《常用音訓》サイ/す…ます/す…む
《音読み》 サイ /セイ
/セイ /ザイ
/ザイ 〈j
〈j ・j
・j 〉
《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ
《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる
《意味》
〉
《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ
《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる
《意味》
 {動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕
{動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕
 {動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」
{動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」
 {動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。
{動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。
 セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕
セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕
 {名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕
{名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕
 {名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。
{名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。
 「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕
「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕
 〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。
〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。
《解字》
会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間)
〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。
〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。
《解字》
会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間) 劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る)
劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る) 齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。
《類義》
→渡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。
《類義》
→渡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 水部 [六年]
区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF
【濟】旧字旧字
11画 水部 [六年]
区点=2649 16進=3A51 シフトJIS=8DCF
【濟】旧字旧字
 17画 水部
区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A
《常用音訓》サイ/す…ます/す…む
《音読み》 サイ
17画 水部
区点=6327 16進=5F3B シフトJIS=E05A
《常用音訓》サイ/す…ます/す…む
《音読み》 サイ /セイ
/セイ /ザイ
/ザイ 〈j
〈j ・j
・j 〉
《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ
《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる
《意味》
〉
《訓読み》 すます/すくう(すくふ)/なす/わたる/わたす/すむ
《名付け》 いつき・お・かた・さだ・さとる・すみ・ただ・とおる・なり・なる・まさ・ます・やす・よし・わたす・わたり・わたる
《意味》
 {動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕
{動}すくう(スクフ)。不足を補って、平等にならす。困っている者に当てがって、水準の線までそろえてやる。「救済」「経世済民ケイセイサイミン(世の中を調整して人民の生活のでこぼこをなくする)」「博施於民而能済衆=博ク民ニ施シテヨク衆ヲ済フ」〔→論語〕
 {動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」
{動}なす。でこぼこや過不足を調整する。ととのえてまとめあげる。「済美=美ヲ済ス」「無済於事=事ニ済ス無シ」
 {動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。
{動}わたる。わたす。川や難路を無事に通り切る。また、通す。
 セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕
セイス{動}障害を除いてうまく調整する。「鑿河八十里以済不通=河ヲ鑿ツコト八十里モッテ不通ヲ済ス」〔→枕中記〕
 {名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕
{名}やりくり。「取済於一時=済ヲ一時ニ取ル」〔→欧陽脩〕
 {名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。
{名}川名。済水。河南省済源県に源を発し東南に流れて黄河にはいる。下流は大小の支流にわかれる。昔は黄河本流と並行して東流し、渤海ボッカイに注いだ。▽河水を調整して流したので済という。
 「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕
「済済セイセイ・サイサイ」とは、数多くそろっていてりっぱなさま。「済済多士=済済タル多士」〔→詩経〕
 〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。
〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。
《解字》
会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間)
〔仏〕「済度サイド」とは、仏道によって人を極楽へわたすこと。
〔国〕すむ。終わる。また、うまくやりすごす。
《解字》
会意兼形声。齊(=斉)の原字は、物がでこぼこなくそろったさまをあらわす象形文字。濟は「水+音符齊」で、川の水量を過不足なく調整すること。調整してそろえる意を含む。→斉
《単語家族》
儕セイ(そろった仲間) 劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る)
劑サイ・セイ(=剤。そろえて切る) 齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。
《類義》
→渡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
齋サイ(=斎。起居をきちんとととのえる)などと同系。
《類義》
→渡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
淘 すくう🔗⭐🔉
【淘】
 11画 水部
区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391
《音読み》 トウ(タウ)
11画 水部
区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈t
〈t o〉
《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)
《意味》
 {動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」
{動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」
 {動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。
《熟語》
→熟語
{動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。
《熟語》
→熟語
 11画 水部
区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391
《音読み》 トウ(タウ)
11画 水部
区点=3781 16進=4571 シフトJIS=9391
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈t
〈t o〉
《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 とぐ/よなげる(よなぐ)/すくう(すくふ)
《意味》
 {動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」
{動}とぐ。よなげる(ヨナグ)。たらいやおけに水を入れ、かきまわして米をとぐ。水洗いしてすくうようによりわける。「淘金トウキン」「淘汰トウタ」
 {動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。
《熟語》
→熟語
{動}すくう(スクフ)。水中をさらって、物をすくい出す。〈同義語〉→掏トウ。「淘井トウセイ(=掏井。井戸さらえ)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音トウ)は「勹(つつむ)+缶(ほとぎ、つぼ型の土器)」の会意文字で、土器をつくるとき、外わくで包んで、その中でねん土をこねること。搗トウ(まんべんなくこねる)と同系のことばで、容器の中に手を入れ、すくうようにこねまわすこと。淘はそれを音符とし、水を加えた字で、水にはいった容器に手を入れ、こねまわして中の米や砂金だけをすくいあげること。掏(こねる、すくい出す)と最も近い。
《熟語》
→熟語
漉 すく🔗⭐🔉
犂 すく🔗⭐🔉
【犂】
 12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
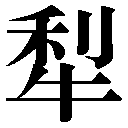 11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》
11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》  レイ
レイ /ライ
/ライ /
/ リ
リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
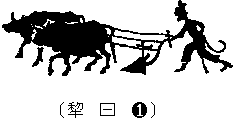

 {名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
 {動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕
{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

 {名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
 {形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
 {動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
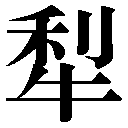 11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》
11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》  レイ
レイ /ライ
/ライ /
/ リ
リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
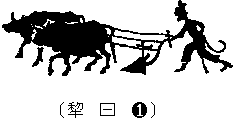

 {名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
 {動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕
{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

 {名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
 {形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
 {動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
竦 すくむ🔗⭐🔉
【竦】
 12画 立部
区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290
《音読み》 ショウ
12画 立部
区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290
《音読み》 ショウ /シュ
/シュ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)
《意味》
 ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕
ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕
 {動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束
《単語家族》
縦(たてに細長い)
{動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束
《単語家族》
縦(たてに細長い) 嵩スウ(細長く高い)
嵩スウ(細長く高い) 粛シュク(細くしまる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
粛シュク(細くしまる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 立部
区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290
《音読み》 ショウ
12画 立部
区点=6780 16進=6370 シフトJIS=E290
《音読み》 ショウ /シュ
/シュ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 そばだつ/すくむ/つつしむ/おそれる(おそる)
《意味》
 ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕
ショウス{動}そばだつ。すくむ。二本の足をたばねたように棒だちになる。棒だちになって背伸びする。そびえたつ。〈同義語〉→聳。「竦立ショウリツ(たちすくむ)」「竦竦ショウショウ(細く高く棒だちとなるさま)」「竦而望帰=竦シテ帰ルヲ望ム」〔→漢書〕
 {動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束
《単語家族》
縦(たてに細長い)
{動}つつしむ。おそれる(オソル)。ぞっとして棒だちとなる。また、身を引きしめてかしこまる。〈類義語〉→粛。「竦然ショウゼン(ぞっとするさま)」「寡人将竦意而覧焉=寡人マサニ意ヲ竦ンデコレヲ覧ントス」〔→漢書〕
《解字》
会意兼形声。束ソクは「木+○印」の会意文字で、まきを集め、まるいわくで細長くたばねることを示す。竦ショウは「立+音符束」で、二本の足を細くたばねたように、棒だちになること。束の語尾がのびたことば。→束
《単語家族》
縦(たてに細長い) 嵩スウ(細長く高い)
嵩スウ(細長く高い) 粛シュク(細くしまる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
粛シュク(細くしまる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
籍 すく🔗⭐🔉
【籍】
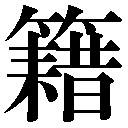 20画 竹部 [常用漢字]
区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ
20画 竹部 [常用漢字]
区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ /ジャク
/ジャク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 ふみ/すく
《名付け》 ふみ・もり・より
《意味》
〉
《訓読み》 ふみ/すく
《名付け》 ふみ・もり・より
《意味》
 {名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」
{名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」
 {名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」
{名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」
 セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕
セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕
 セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」
セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」
 セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕
セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕
 「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕
「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕
 {動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
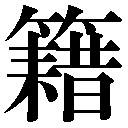 20画 竹部 [常用漢字]
区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ
20画 竹部 [常用漢字]
区点=3250 16進=4052 シフトJIS=90D0
《常用音訓》セキ
《音読み》 セキ /ジャク
/ジャク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 ふみ/すく
《名付け》 ふみ・もり・より
《意味》
〉
《訓読み》 ふみ/すく
《名付け》 ふみ・もり・より
《意味》
 {名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」
{名}ふみ。昔、紙のないころ、竹のふだに文字を書いて、それを重ねて保存したことから、文書・書物のこと。〈類義語〉→簡。「書籍」「典籍(古典)」
 {名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」
{名}人別・戸別・地別等を書きつけた役所のふだや文書。人別帳。「戸籍コセキ」「籍貫(原籍・戸籍のあるうまれ故郷)」
 セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕
セキス{動}書きつける。記入する。「勿籍=籍スルナカレ」〔→左伝〕
 セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」
セキス{動}家産を没収して帳簿に記入する。「籍没」
 セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕
セキス{動}すく。田畑を農具ですく。〈類義語〉→耡ジョ(すく)。「籍田(天子自ら耕す田)」「宣王、不脩籍於千畝=宣王、千畝ニ籍スルヲ脩メズ」〔→史記〕
 「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕
「籍籍セキセキ」とは、ごたごたと重なること。また、やかましいさま。〈同義語〉藉藉。「国中口語籍籍=国中ノ口語スルヤ籍籍タリ」〔→漢書〕
 {動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}下にしく。▽藉セキ・シャに当てた用法。「狼籍ロウゼキ(=狼藉。おおかみがしき草を荒らしたように、乱れたさま)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔(日数の重なったむかし)」からなり、すきで土をおこして重ねること。籍はそれを音符とし、竹を加えた字で、文字を書いた竹札を重ねて保存したもの。→昔
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
耡 すく🔗⭐🔉
【耡】
 13画 耒部
区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2
《音読み》 ジョ
13画 耒部
区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2
《音読み》 ジョ /ソ
/ソ 〈ch
〈ch 〉
《訓読み》 すく/すき
《意味》
〉
《訓読み》 すく/すき
《意味》
 {動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。
{動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。
 {名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。
{名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。
 ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。
《解字》
会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。
ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。
《解字》
会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。
 13画 耒部
区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2
《音読み》 ジョ
13画 耒部
区点=7052 16進=6654 シフトJIS=E3D2
《音読み》 ジョ /ソ
/ソ 〈ch
〈ch 〉
《訓読み》 すく/すき
《意味》
〉
《訓読み》 すく/すき
《意味》
 {動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。
{動}すく。すきぐわで、田畑の土をすき返す。
 {名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。
{名}すき。土の下にしき入れるすきぐわ。〈同義語〉→鋤ジョ。
 ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。
《解字》
会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。
ジョス{名・動}殷イン代の田畑に対する税法。また、税をかける。税をとりたてる。▽助の字で代用する。
《解字》
会意兼形声。「耒(すき)+音符助」で、助はかさね加えること。ここでは、下の土をおこして表土に重ねる、土の下にしきこむ意か。
透 すく🔗⭐🔉
【透】
 10画
10画  部 [常用漢字]
区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7
《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける
《音読み》
部 [常用漢字]
区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7
《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける
《音読み》  トウ
トウ /ツ
/ツ 〈t
〈t u〉
u〉 シュク
シュク
 /トウ
/トウ 《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)
《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき
《意味》
《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)
《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき
《意味》

 {動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」
{動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」
 {動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」
{動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」
 {副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」
{副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」
 {動}はっとしてとびあがる。「驚透」
《解字》
会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「
{動}はっとしてとびあがる。「驚透」
《解字》
会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「 (すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
(すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画
10画  部 [常用漢字]
区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7
《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける
《音読み》
部 [常用漢字]
区点=3809 16進=4629 シフトJIS=93A7
《常用音訓》トウ/す…かす/す…く/す…ける
《音読み》  トウ
トウ /ツ
/ツ 〈t
〈t u〉
u〉 シュク
シュク
 /トウ
/トウ 《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)
《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき
《意味》
《訓読み》 すかす/すく/すける(すく)/とおる(とほる)
《名付け》 すき・すく・とおる・ゆき
《意味》

 {動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」
{動・形}すく。すける(スク)。すきとおる。すきとおっている。つきぬけてみえるさま。「透明」「透視(すかしてみる)」
 {動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」
{動・形}とおる(トホル)。他のものの中を、それだけがぬけてとおる。すきとおるほどの。〈類義語〉→通。「透徹」
 {副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」
{副}〔俗〕とびぬけてはなはだしい。非常に。「透亮トウリョウ(とびぬけてあかるい)」
 {動}はっとしてとびあがる。「驚透」
《解字》
会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「
{動}はっとしてとびあがる。「驚透」
《解字》
会意。秀シュウは「禾(稲のほ)+乃(なよなよ)」から成る会意文字で、なよなよとした穂がそれだけぬけ出たさま。透は「 (すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
(すすむ)+秀(ぬけ出る)」で、それだけがぬけとおる、すきとおるの意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鋤 すく🔗⭐🔉
鮮 すくない🔗⭐🔉
【鮮】
 17画 魚部 [常用漢字]
区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E
《常用音訓》セン/あざ…やか
《音読み》
17画 魚部 [常用漢字]
区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E
《常用音訓》セン/あざ…やか
《音読み》  セン
セン
 〈xi
〈xi n〉/
n〉/ セン
セン
 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)
《名付け》 あきら・き・まれ・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)
《名付け》 あきら・き・まれ・よし
《意味》

 {名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕
{名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕
 {名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕
{名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕
 {形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」
{形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」
 {形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」
{形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」
 {形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕
〔国〕朝鮮の略。
《解字》
会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕
〔国〕朝鮮の略。
《解字》
会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 17画 魚部 [常用漢字]
区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E
《常用音訓》セン/あざ…やか
《音読み》
17画 魚部 [常用漢字]
区点=3315 16進=412F シフトJIS=914E
《常用音訓》セン/あざ…やか
《音読み》  セン
セン
 〈xi
〈xi n〉/
n〉/ セン
セン
 〈xi
〈xi n〉
《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)
《名付け》 あきら・き・まれ・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 あたらしい(あたらし)/あざやか(あざやかなり)/すくない(すくなし)
《名付け》 あきら・き・まれ・よし
《意味》

 {名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕
{名}なまの魚。「鮮魚」「治大国若烹小鮮=大国ヲ治ムルニハ小鮮ヲ烹ルガゴトクス」〔→老子〕
 {名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕
{名}新しいなま肉。殺したての鳥獣。「肥鮮」「割鮮野食=鮮ヲ割キ野ニ食ス」〔→班固〕
 {形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」
{形}あたらしい(アタラシ)。できたてである。古びていない。みずみずしい。「新鮮」「鮮果」
 {形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」
{形}あざやか(アザヤカナリ)。境めがはっきりしている。できたてのようにけがれがない。すっきりした色合いで美しい。「鮮明」「鮮紅」
 {形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕
〔国〕朝鮮の略。
《解字》
会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}すくない(スクナシ)。ごたごたとしていない。それだけが目だつさま。めったにない。「巧言令色、鮮矣仁=巧言令色、鮮ナシ仁」〔→論語〕
〔国〕朝鮮の略。
《解字》
会意。「魚(さかな)+羊(ひつじ)」で、なま肉の意味をあらわす。なまの、切りたての、切りめがはっきりしたなどの意を含む。
《類義》
→寡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
粭 すくも🔗⭐🔉
【粭】
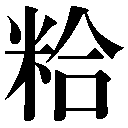 12画 米部 〔国〕
区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4
《訓読み》 すくも
《意味》
12画 米部 〔国〕
区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4
《訓読み》 すくも
《意味》
 すくも。あし、かやなどの枯れたもの。
すくも。あし、かやなどの枯れたもの。 地名に使われる。
地名に使われる。
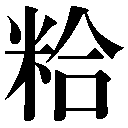 12画 米部 〔国〕
区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4
《訓読み》 すくも
《意味》
12画 米部 〔国〕
区点=6870 16進=6466 シフトJIS=E2E4
《訓読み》 すくも
《意味》
 すくも。あし、かやなどの枯れたもの。
すくも。あし、かやなどの枯れたもの。 地名に使われる。
地名に使われる。
糘 すくも🔗⭐🔉
【糘】
 16画 米部 〔国〕
区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2
《訓読み》 すくも
《意味》
16画 米部 〔国〕
区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2
《訓読み》 すくも
《意味》
 すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。
すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。 地名に使う。
地名に使う。
 16画 米部 〔国〕
区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2
《訓読み》 すくも
《意味》
16画 米部 〔国〕
区点=6884 16進=6474 シフトJIS=E2F2
《訓読み》 すくも
《意味》
 すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。
すくも。葦や茅などの枯れたもの。またはもみがら。 地名に使う。
地名に使う。
漢字源に「すく」で始まるの検索結果 1-27。
 9画
9画  ng〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
{動}すくう(スクフ)。水中に落ちたり、災難にあったりした者をすくいあげる。「拯救ジョウキュウ」「将拯己於水火之中也=マサニ己ヲ水火ノ中ヨリ拯ハントス」〔
ng〉
《訓読み》 すくう(すくふ)
《意味》
{動}すくう(スクフ)。水中に落ちたり、災難にあったりした者をすくいあげる。「拯救ジョウキュウ」「将拯己於水火之中也=マサニ己ヲ水火ノ中ヨリ拯ハントス」〔 15画
15画  14画 水部
区点=2587 16進=3977 シフトJIS=8D97
《音読み》 ロク
14画 水部
区点=2587 16進=3977 シフトJIS=8D97
《音読み》 ロク 15画 金部
区点=2991 16進=3D7B シフトJIS=8F9B
《音読み》 ジョ
15画 金部
区点=2991 16進=3D7B シフトJIS=8F9B
《音読み》 ジョ