複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (91)
き‐あ・う【来合ふ】‥アフ🔗⭐🔉
き‐あ・う【来合ふ】‥アフ
〔自四〕
たまたま来て出合う。来合わせる。源氏物語帚木「ある上人―・ひて、この車に相乗り」
き‐あわ・せる【来合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉
き‐あわ・せる【来合わせる】‥アハセル
〔自下一〕[文]きあは・す(下二)
たまたま来て出合う。期せずして出合う。「―・せたバスに乗る」
き・いる【来居る】‥ヰル🔗⭐🔉
き・いる【来居る】‥ヰル
〔自上一〕
来ている。万葉集20「蘆が散る難波に―・ゐて」
き‐かか・る【来掛かる】🔗⭐🔉
き‐かか・る【来掛かる】
〔自五〕
ちょうどそこへ来る。さしかかる。
○気が軽いきがかるい
そのことが負担に感じられず、気持が晴れ晴れとしている。↔気が重い
⇒き【気】
き‐がけ【来掛け】🔗⭐🔉
き‐がけ【来掛け】
①来る途中。来るついで。↔行き掛け。
②来るとすぐ。着く早々。歌舞伎、東海道四谷怪談「これは―からの御挨拶」
き‐し‐かた【来し方】🔗⭐🔉
き‐し‐かた【来し方】
(「き」は動詞「く」の連用形、「し」は過去の助動詞「き」の連体形。「こしかた」とも)
①過ぎ去った時。過去。源氏物語若菜上「さまざまに世の中を思ひ知り、―をくやしく」
②過ぎて来た方。通過した所。後拾遺和歌集旅「須磨の浦を今過ぎゆけど―へ」
⇒きしかた‐ゆくさき【来し方行く先】
⇒きしかた‐ゆくすえ【来し方行く末】
きしかた‐ゆくさき【来し方行く先】🔗⭐🔉
きしかた‐ゆくさき【来し方行く先】
(→)「きしかたゆくすえ」に同じ。
⇒き‐し‐かた【来し方】
きしかた‐ゆくすえ【来し方行く末】‥スヱ🔗⭐🔉
きしかた‐ゆくすえ【来し方行く末】‥スヱ
過去と未来。きしかたゆくさき。源氏物語明石「―思し合はせて」
⇒き‐し‐かた【来し方】
き‐し・く【来及く】🔗⭐🔉
き‐し・く【来及く】
〔自四〕
しきりに来る。重ねて来る。万葉集4「百重ももえにも―・かぬかもと思へかも」
き‐しな【来しな】🔗⭐🔉
き‐しな【来しな】
(「しな」は接尾語)来る途中。来ようとする時。また、来たばかりの時。きがけ。
きた・す【来す】🔗⭐🔉
きた・す【来す】
〔他五〕
来るようにする。結果としてある事態を生じさせる。もたらす。三蔵法師伝承徳点「請ふ、附け来キタスことを為せ」。「支障を―・す」
きた・る【来る】(自四)🔗⭐🔉
きた・る【来る】
〔自四〕
(キ(来)イタ(到)ルの約。古くは主に漢文訓読の語)
①くる。やってくる。白氏文集天永点「潜ひそかに来キタリて更に消息を通やらず」。「冬―・りなば春遠からじ」↔去る。
②物などが古くなっていたむ。使いものにならなくなる。また、人が年をとって弱ってくる。錦之裏「こいつもすこし―・つた小袖をうちかけ」。浮世風呂4「大きに―・りましたテ。世の中に老耄おいこんで能いものはごぜへませんが」
③ほれる。まいる。滑稽本、妙竹林話七偏人「お麦めは自己おいらに九分九厘―・つて居て」
きたる【来る】(連体詞)🔗⭐🔉
きたる【来る】
〔連体〕
近いうちにくる意を表す語。「―三月一日開店」↔去る
きたる‐べき【来るべき】🔗⭐🔉
きたる‐べき【来るべき】
近い将来に来るはずの。「―災害に備える」
き‐て【来手】🔗⭐🔉
き‐て【来手】
来る人。来てくれる人。「嫁に―がない」
き・ふ【来経】🔗⭐🔉
き・ふ【来経】
〔自下二〕
年月が来て過ぎ去る。古事記中「あらたまの年が―・ふれば」
き‐へな・る【来隔る】🔗⭐🔉
き‐へな・る【来隔る】
〔自四〕
来て遠くへだたる。万葉集17「あしひきの山―・りて遠けども」
き‐へゆ・く【来経行く】🔗⭐🔉
き‐へゆ・く【来経行く】
〔自四〕
年月が来て過ぎ去る。万葉集5「―・く年の限り知らずて」
き‐むか・う【来向かふ】‥ムカフ🔗⭐🔉
き‐むか・う【来向かふ】‥ムカフ
〔自四〕
やって来る。近づく。万葉集1「み猟立たしし時は―・ふ」
き‐よ・す【来寄す】🔗⭐🔉
き‐よ・す【来寄す】
〔自下二〕
寄せて来る。万葉集7「住吉の奥つ白浪風吹けば―・する浜をみれば清しも」
き‐よ・る【来寄る】🔗⭐🔉
き‐よ・る【来寄る】
〔自四〕
寄せて来る。土佐日記「―・る浪をもあはれとぞ見る」
くらく【来らく】🔗⭐🔉
くらく【来らく】
(「来く」のク語法)来ること。万葉集13「古ゆ言ひつぎ―恋すれば安からぬものと」
くる【来る】🔗⭐🔉
くる【来る】
〔自カ変〕[文]く(カ変)
地点・事物・人・時など中心になる点に向かって何かが近づき寄る動作を、中心になる側からいう語。(命令形は古くは「こ」)
①㋐人・事物がこちらに向かって近づく。古事記中「島つ鳥鵜飼が伴とも今助すけに来こね」。万葉集15「吾妹子わぎもこが待たむといひし時そ来きにける」。「客がくる」「手紙がくる」「電車がくる」
㋑その日時・季節になったり、順番が近づいたりする。「春がきた」「試合の日がくる」
②行く。目的地へ自己を置いた心でいう。万葉集1「大和には鳴きてか来くらむ呼子鳥象きさの中山呼びそ越ゆなる」。源氏物語浮舟「見奉らぬがいとおぼつかなく覚え侍るを、しばしも参り来こまほしくこそ」
③慕う心が、意中の人に向けられる。ほれる。まいる。古くは女から男への場合にいう。好色一代女1「此の程つかへたる肩までひねらせた。これほど我等にくること、何とも合点がゆかぬ」
④古くなっていたむ。通言総籬つうげんそうまがき「つむぎじまの袖口のちときた裏襟うらえりの小袖」
⑤(「腹がくる」の形で)腹がへる。腹がすく。通言総籬「少し腹がきたはへ。さつきそこにあつたのはなんだ」
⑥ある状態に立ち至る。
㋐(「…とくる」の形で)…といった状態なのである。浮世風呂3「こちとらはどうで着たきり雀ときてゐるから、気に入つた着物をさつさつと着殺すがいいのさ」。「それが面白いときている」
㋑(「…とくると」「…ときては」などの形で)…を取り上げて言うと。特に…の場合には。浮世風呂4「越後の雪ときたら大層さネ」。「野球とくると飯より好きだ」
㋒ある事がもとで、その状態になる。「過労からきた病気」
㋓ある事態が立ち現れる。また、自分の心に生じる。「体力が限界にきた」「がたがくる」「そうこなくちゃ面白くない」「ぴんとくる」「頭にくる」
⑦(動詞の連用形に付いて)ある動作・状態が以前から現在まで続いている意を表す。今まで…する。ずっと…する。源氏物語帚木「憂きふしを心ひとつに数へ来きてこや君が手をわかるべき折」。「今日まで続けてきた仕事」
⑧(動詞の連用形またはそれに「て」を添えた形に付いて)
㋐次第にそうなる、また、そういう状態が出現する意を表す。万葉集14「遠き吾妹が着せし衣たもとのくだり紕まよひ来きにけり」。「胸がわくわくしてきた」「生まれてくる子供のために」「良い考えが浮かんでこない」
㋑その動作・作用を済ませて立ち戻る意を表す。「行ってきます」「事情を話してきます」
⇒来る者は拒まず
くる‐とし【来る年】🔗⭐🔉
くる‐とし【来る年】
新たに迎える年。明年。
くる‐ひ【来る日】🔗⭐🔉
くる‐ひ【来る日】
新しくやって来る日。明日。翌日。
○来る者は拒まずくるものはこばまず🔗⭐🔉
○来る者は拒まずくるものはこばまず
向うから自分のところにやって来る者は誰でも拒むことなく、快く受け入れて仲間に入れるの意。きたる者は拒まず。→去る者は追わず(「去る」成句)
⇒くる【来る】
くるり【矪】
矪矢の略。古今著聞集20「をしどり一つがひゐたりけるを、―を持ちて射たりければ」
⇒くるり‐や【矪矢】
くるり【転】
①身軽く、回転するさま。「―と向きをかえる」
②物事が反転したように、すっかりかわるさま。「言う事が―と変わる」
③まわりを取り巻くさま。丸めたり包んだりするさま。ぐるり。
④唐棹からさおのこと。くるり棒。
⇒くるり‐くるり【転転】
ぐるり【周】
めぐり。まわり。四辺。周囲。「―を海で囲まれている」
⇒ぐるり‐おとし【周落】
⇒ぐるり‐だか【周高】
ぐるり【転】
①一回転するさま。「腕を―と回す」
②まわりを取りまくさま。くるり。「―と囲まれる」
⇒ぐるり‐ぐるり【転転】
ぐるり‐おとし【周落】
女の髪の結い方。鬢びんと髱たぼとを一つに出した落し散毛ばらげ。洒落本、仕懸文庫「髪は―のつり舟」
⇒ぐるり【周】
くるり‐くるり【転転】
幾回となく回転し、または変化するさま。くるくる。ぐるりぐるり。
⇒くるり【転】
ぐるり‐ぐるり【転転】
⇒くるりくるり
⇒ぐるり【転】
くるり‐じょう【久留里城】‥ジヤウ
戦国時代に里見氏が、現在の千葉県君津市久留里に築いた城。江戸時代、久留里藩主として大須賀・土屋・黒田の諸氏が入る。
ぐるり‐だか【周高】
まわりが高いこと。鼻の低い顔をいう。傾城禁短気「是れは若旦那様御機嫌でござりますと、―な顔をほむれば」↔中高なかだか
⇒ぐるり【周】
くるり‐や【矪矢】
水鳥を射るのに用いた矢。半月形の小さい雁股かりまたで、桐・桧製の小鏑こかぶらを付ける。
矪矢
 ⇒くるり【矪】
くるる【枢】
①扉の端の上下につけた突起(とまら)をかまちの穴(とぼそ)にさし込んで開閉させるための装置。くる。くろろ。拾玉集4「納殿の―の妻戸おし開けて」
②戸の桟。さる。
③回転装置の心棒。枢軸。
⇒くるる‐ぎ【枢木】
⇒くるる‐ど【枢戸】
くるる‐ぎ【枢木】
(→)「くるる」に同じ。
⇒くるる【枢】
くるる‐ど【枢戸】
くるるによって開閉する戸。源氏物語花宴「奥の―もあきて人音もせず」↔引戸
⇒くるる【枢】
くる‐わ【曲輪・郭・廓】
①城・砦など、一定の区域の周囲に築いた土や石のかこい。
②遊女屋の集まっている所。遊郭。遊里。
⇒くるわ‐がよい【郭通い】
⇒くるわ‐ことば【郭詞】
⇒くるわ‐ざた【郭沙汰】
⇒くるわ‐さんがい【郭三界】
⇒くるわ‐づとめ【郭勤め】
⇒くるわ‐の‐あみ【郭の網】
⇒くるわ‐もの【郭者】
⇒くるわ‐もよう【郭模様】
⇒くるわ‐よう【郭様】
⇒くるわ‐よすじ【郭四筋】
くるわ‐か・す【狂はかす】クルハカス
〔他四〕
①くるわす。くるわせる。
②だます。たぶらかす。住吉物語「侍従に―・されて」
くるわ‐がよい【郭通い】‥ガヨヒ
遊郭へたびたびゆくこと。悪所がよい。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ことば【郭詞】
遊郭で遊女の使用することば。田舎詞を使わせないために定めたものという。「ありんす」の類。さとことば。遊里語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ざた【郭沙汰】
遊郭中の評判になること。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐さんがい【郭三界】
遊里全体。浄瑠璃、冥途飛脚「この忠兵衛が五十両損かけうかと気遣ひさに―披露して、男の一分捨てさする」
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわし・い【狂わしい】クルハシイ
〔形〕[文]くるは・し(シク)
(→)「くるおしい」に同じ。
くるわ・す【狂わす】クルハス
[一]〔他五〕
(→)「くるわせる」に同じ。
[二]〔他下二〕
⇒くるわせる(下一)
くるわ・せる【狂わせる】クルハセル
〔他下一〕[文]くるは・す(下二)
①くるうようにする。
②合わないようにする。正確さを失わせる。
③心を乱れさせる。
くるわ‐づとめ【郭勤め】
遊里で働くこと。また、その身。遊女。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐の‐あみ【郭の網】
郭づとめで身の自由を束縛されることを、鳥が網にかかったのにたとえていう語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわぶんしょう【廓文章】‥シヤウ
浄瑠璃。「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」吉田屋の段の改作。また、歌舞伎での同場面の通称。
くるわ‐もの【郭者】
遊里で生計を立てている人。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐もよう【郭模様】‥ヤウ
遊里で流行する模様。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よう【郭様】‥ヤウ
遊郭に独特の風俗。遊里風。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よすじ【郭四筋】‥スヂ
(四筋の通りから成ることから)大坂新町の遊里。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
グルント【Grund ドイツ】
(地面の意)基礎。根底。根拠。論拠。
⇒グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
ドイツの小学校。4年制で、国民一般に共通の基礎教育を行う。基礎学校。
⇒グルント【Grund ドイツ】
くれ【呉】
①中国南北朝時代の南朝およびその支配した江南の地域を日本でいう称。また、広く中国の称。
②呉と通交して以来、中国伝来の事物に添えていう語。「―ない(呉の藍の意)」「―の母おも」「―楽」
くれ【呉】
広島県南西部、広島市の南東にある市。江田島・能美島・倉橋島を望む。もと軍港・海軍工廠があり、現在は造船所がある。人口25万1千。
くれ【呉】
姓氏の一つ。
⇒くれ‐しげいち【呉茂一】
⇒くれ‐しゅうぞう【呉秀三】
くれ【塊】
かたまり。「土―」
くれ【暗れ】
①暗いこと。万葉集20「木この―の繁き尾の上をほととぎす鳴きて越ゆなり」
②不安なさま。万葉集10「春日はるひも―に恋ひわたるかも」
③混乱。五代帝王物語「京中おびただしき―にてぞありし」
くれ【暮れ】
①暮れること。日が入ろうとしてあたりの暗くなる時。日暮れ。夕。晩。「日の―」↔明け。
②すえ。おわり。「年の―」「―の春」
③1年の終り。歳暮。年末。「―の大掃除」
⇒暮れ遅し
⇒暮れ早し
くれ【榑】
①山出しの板材。平安時代の規格では長さ12尺、幅6寸、厚さ4寸。くれき。宇津保物語祭使「浅き世になげきてわたる筏師はいくらの―か流れきぬらん」
②薄板。へぎいた。
③薪。
④(→)背板せいた1に同じ。
くれ【某】
〔代〕
(不定称)「何」という語と並べて用い、不明・不定の人や事物に代えていう語。源氏物語少女「何の御子みこ、―の源氏など数へたまひて」
ぐれ
(「ぐれはま」の略)物事のくいちがうこと。ぐりはま。浄瑠璃、新版歌祭文「―の来ぬ内サアござんせと」
ぐれ
〔動〕メジナの俗称。
グレア【glare】
輝度分布の偏りや極端な輝度対比などによって感じられるまぶしさ。
くれ‐あい【暮合】‥アヒ
暮れようとする頃。日暮れがた。三河物語「―になりければ御門の鍵を渡させ給へといふ」
クレアチニン【creatinine】
クレアチン燐酸の分解最終産物で、筋肉内で非酵素的につくられ、尿中に排泄される。クレアチニンの尿中排泄は糸球体濾過値(GFR)の臨床検査に用いる。
⇒クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
糸球体濾過値検査法の一種。クレアチニンの単位時間内尿中排泄量を血中濃度で除した値。1分間に糸球体で濾過される水分量を表す。
⇒クレアチニン【creatinine】
クレアチン【creatine】
筋肉、特に随意筋に、単独または燐酸と結合した形(クレアチン燐酸)で存在する化合物。生体内では主としてアデノシン三燐酸(ATP)と反応して高いエネルギーをもったクレアチン燐酸として存在し、筋肉の運動の際に分解して大量のエネルギーを放出する。
グレアム【Thomas Graham】
イギリスの化学者。同じ条件のもとで気体が細孔を通って流出する速度はその分子量の平方根に逆比例するというグレアムの法則を発見。コロイド化学の祖。(1805〜1869)
グレイ【gray】
放射線の吸収線量の単位。国際単位系の組立単位。物質1キログラム当り1ジュールのときが1グレイ。100ラドに等しい。記号Gy
クレイグ【Edward Gordon Craig】
イギリスの演劇理論家・舞台美術家。演劇における演出家の絶対的権限を主張し大きな影響を与えた。(1872〜1966)
クレイステネス【Kleisthenēs】
前6世紀末のアテナイの政治家。部族制度の改革を行い、アテナイ民主政治の基礎をおいた。オストラシズム(陶片追放)の発案者。クリステネス。
くれ‐いた【榑板】
①榑の薄板。
②榑縁くれえんに張った板。
クレイトン‐ほう【クレイトン法】‥ハフ
(Clayton Act)アメリカの独占禁止法の中心で、価格協定や合併など企業間の競争制限的行為を規制するための法律。1941年制定。シャーマン法を補完。
くれ‐うち【塊打ち】
田畑を鋤すきで起こしたのち、土塊を塊割りなどでうち砕くこと。
くれ‐うり【榑売】
榑木を売ること。また、その人。
クレー【clay】
①粘土。陶土。また、それで作った皿など。
②クレー射撃で、的として飛ばす素焼の皿。また、クレー射撃の略。
③テニスなどのクレーコートの略。
⇒クレー‐コート【clay court】
⇒クレー‐しゃげき【クレー射撃】
クレー【Paul Klee】
スイス生れのドイツ人画家。初め線描中心で諷刺的人間像を描いたが、のち、自然・都市・人間を記号化・単純化して詩的幻想とユーモアにみちた抽象的絵画を描く。(1879〜1940)
クレー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
⇒くるり【矪】
くるる【枢】
①扉の端の上下につけた突起(とまら)をかまちの穴(とぼそ)にさし込んで開閉させるための装置。くる。くろろ。拾玉集4「納殿の―の妻戸おし開けて」
②戸の桟。さる。
③回転装置の心棒。枢軸。
⇒くるる‐ぎ【枢木】
⇒くるる‐ど【枢戸】
くるる‐ぎ【枢木】
(→)「くるる」に同じ。
⇒くるる【枢】
くるる‐ど【枢戸】
くるるによって開閉する戸。源氏物語花宴「奥の―もあきて人音もせず」↔引戸
⇒くるる【枢】
くる‐わ【曲輪・郭・廓】
①城・砦など、一定の区域の周囲に築いた土や石のかこい。
②遊女屋の集まっている所。遊郭。遊里。
⇒くるわ‐がよい【郭通い】
⇒くるわ‐ことば【郭詞】
⇒くるわ‐ざた【郭沙汰】
⇒くるわ‐さんがい【郭三界】
⇒くるわ‐づとめ【郭勤め】
⇒くるわ‐の‐あみ【郭の網】
⇒くるわ‐もの【郭者】
⇒くるわ‐もよう【郭模様】
⇒くるわ‐よう【郭様】
⇒くるわ‐よすじ【郭四筋】
くるわ‐か・す【狂はかす】クルハカス
〔他四〕
①くるわす。くるわせる。
②だます。たぶらかす。住吉物語「侍従に―・されて」
くるわ‐がよい【郭通い】‥ガヨヒ
遊郭へたびたびゆくこと。悪所がよい。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ことば【郭詞】
遊郭で遊女の使用することば。田舎詞を使わせないために定めたものという。「ありんす」の類。さとことば。遊里語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ざた【郭沙汰】
遊郭中の評判になること。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐さんがい【郭三界】
遊里全体。浄瑠璃、冥途飛脚「この忠兵衛が五十両損かけうかと気遣ひさに―披露して、男の一分捨てさする」
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわし・い【狂わしい】クルハシイ
〔形〕[文]くるは・し(シク)
(→)「くるおしい」に同じ。
くるわ・す【狂わす】クルハス
[一]〔他五〕
(→)「くるわせる」に同じ。
[二]〔他下二〕
⇒くるわせる(下一)
くるわ・せる【狂わせる】クルハセル
〔他下一〕[文]くるは・す(下二)
①くるうようにする。
②合わないようにする。正確さを失わせる。
③心を乱れさせる。
くるわ‐づとめ【郭勤め】
遊里で働くこと。また、その身。遊女。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐の‐あみ【郭の網】
郭づとめで身の自由を束縛されることを、鳥が網にかかったのにたとえていう語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわぶんしょう【廓文章】‥シヤウ
浄瑠璃。「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」吉田屋の段の改作。また、歌舞伎での同場面の通称。
くるわ‐もの【郭者】
遊里で生計を立てている人。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐もよう【郭模様】‥ヤウ
遊里で流行する模様。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よう【郭様】‥ヤウ
遊郭に独特の風俗。遊里風。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よすじ【郭四筋】‥スヂ
(四筋の通りから成ることから)大坂新町の遊里。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
グルント【Grund ドイツ】
(地面の意)基礎。根底。根拠。論拠。
⇒グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
ドイツの小学校。4年制で、国民一般に共通の基礎教育を行う。基礎学校。
⇒グルント【Grund ドイツ】
くれ【呉】
①中国南北朝時代の南朝およびその支配した江南の地域を日本でいう称。また、広く中国の称。
②呉と通交して以来、中国伝来の事物に添えていう語。「―ない(呉の藍の意)」「―の母おも」「―楽」
くれ【呉】
広島県南西部、広島市の南東にある市。江田島・能美島・倉橋島を望む。もと軍港・海軍工廠があり、現在は造船所がある。人口25万1千。
くれ【呉】
姓氏の一つ。
⇒くれ‐しげいち【呉茂一】
⇒くれ‐しゅうぞう【呉秀三】
くれ【塊】
かたまり。「土―」
くれ【暗れ】
①暗いこと。万葉集20「木この―の繁き尾の上をほととぎす鳴きて越ゆなり」
②不安なさま。万葉集10「春日はるひも―に恋ひわたるかも」
③混乱。五代帝王物語「京中おびただしき―にてぞありし」
くれ【暮れ】
①暮れること。日が入ろうとしてあたりの暗くなる時。日暮れ。夕。晩。「日の―」↔明け。
②すえ。おわり。「年の―」「―の春」
③1年の終り。歳暮。年末。「―の大掃除」
⇒暮れ遅し
⇒暮れ早し
くれ【榑】
①山出しの板材。平安時代の規格では長さ12尺、幅6寸、厚さ4寸。くれき。宇津保物語祭使「浅き世になげきてわたる筏師はいくらの―か流れきぬらん」
②薄板。へぎいた。
③薪。
④(→)背板せいた1に同じ。
くれ【某】
〔代〕
(不定称)「何」という語と並べて用い、不明・不定の人や事物に代えていう語。源氏物語少女「何の御子みこ、―の源氏など数へたまひて」
ぐれ
(「ぐれはま」の略)物事のくいちがうこと。ぐりはま。浄瑠璃、新版歌祭文「―の来ぬ内サアござんせと」
ぐれ
〔動〕メジナの俗称。
グレア【glare】
輝度分布の偏りや極端な輝度対比などによって感じられるまぶしさ。
くれ‐あい【暮合】‥アヒ
暮れようとする頃。日暮れがた。三河物語「―になりければ御門の鍵を渡させ給へといふ」
クレアチニン【creatinine】
クレアチン燐酸の分解最終産物で、筋肉内で非酵素的につくられ、尿中に排泄される。クレアチニンの尿中排泄は糸球体濾過値(GFR)の臨床検査に用いる。
⇒クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
糸球体濾過値検査法の一種。クレアチニンの単位時間内尿中排泄量を血中濃度で除した値。1分間に糸球体で濾過される水分量を表す。
⇒クレアチニン【creatinine】
クレアチン【creatine】
筋肉、特に随意筋に、単独または燐酸と結合した形(クレアチン燐酸)で存在する化合物。生体内では主としてアデノシン三燐酸(ATP)と反応して高いエネルギーをもったクレアチン燐酸として存在し、筋肉の運動の際に分解して大量のエネルギーを放出する。
グレアム【Thomas Graham】
イギリスの化学者。同じ条件のもとで気体が細孔を通って流出する速度はその分子量の平方根に逆比例するというグレアムの法則を発見。コロイド化学の祖。(1805〜1869)
グレイ【gray】
放射線の吸収線量の単位。国際単位系の組立単位。物質1キログラム当り1ジュールのときが1グレイ。100ラドに等しい。記号Gy
クレイグ【Edward Gordon Craig】
イギリスの演劇理論家・舞台美術家。演劇における演出家の絶対的権限を主張し大きな影響を与えた。(1872〜1966)
クレイステネス【Kleisthenēs】
前6世紀末のアテナイの政治家。部族制度の改革を行い、アテナイ民主政治の基礎をおいた。オストラシズム(陶片追放)の発案者。クリステネス。
くれ‐いた【榑板】
①榑の薄板。
②榑縁くれえんに張った板。
クレイトン‐ほう【クレイトン法】‥ハフ
(Clayton Act)アメリカの独占禁止法の中心で、価格協定や合併など企業間の競争制限的行為を規制するための法律。1941年制定。シャーマン法を補完。
くれ‐うち【塊打ち】
田畑を鋤すきで起こしたのち、土塊を塊割りなどでうち砕くこと。
くれ‐うり【榑売】
榑木を売ること。また、その人。
クレー【clay】
①粘土。陶土。また、それで作った皿など。
②クレー射撃で、的として飛ばす素焼の皿。また、クレー射撃の略。
③テニスなどのクレーコートの略。
⇒クレー‐コート【clay court】
⇒クレー‐しゃげき【クレー射撃】
クレー【Paul Klee】
スイス生れのドイツ人画家。初め線描中心で諷刺的人間像を描いたが、のち、自然・都市・人間を記号化・単純化して詩的幻想とユーモアにみちた抽象的絵画を描く。(1879〜1940)
クレー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 「鍛冶屋KN」
提供:Photos12/APL
「鍛冶屋KN」
提供:Photos12/APL
 「子どものいる風景」
提供:Photos12/APL
「子どものいる風景」
提供:Photos12/APL
 グレー【grey; gray】
①灰色。ねずみ色。
Munsell color system: N5.5
②銀髪。「ロマンス‐―」
③(白と黒の中間の色であることから)あいまいなこと。どっちつかずであること。
⇒グレー‐カラー【grey-collar】
⇒グレー‐ゾーン【grey zone】
グレー【Alasdair Gray】
スコットランドの小説家。実験的な手法の小説「ラナーク」など。(1934〜)
グレー【Thomas Gray】
イギリスの詩人・学者。詩「墓畔の哀歌」の憂愁趣味や古詩の翻訳を通じてロマン主義の先駆となり、新体詩訳を通じて明治文学に影響を与えた。(1716〜1771)
クレーヴのおくがた【クレーヴの奥方】
(La Princesse de Clèves フランス)ラ=ファイエット夫人の小説。1678年刊。古典的文体とこまやかな心理分析に秀でた近代小説の先駆。
グレー‐カラー【grey-collar】
(灰色の作業服を着ることから)修理・整備など技術関係の労働者。ホワイト‐カラー・ブルー‐カラーに対していう。
⇒グレー【grey; gray】
クレー‐コート【clay court】
テニスで、粘土などで固めたコート。→グラスコート。
⇒クレー【clay】
グレーザー【Donald Arthur Glaser】
アメリカの実験物理学者。カリフォルニア大学教授。高速荷電粒子の飛跡を観測する泡箱を発明。ノーベル賞。(1926〜)
クレージー【crazy】
常軌を逸しているさま。熱狂的なさま。「―な演奏」
グレーシャー【glacier】
(→)氷河。
クレー‐しゃげき【クレー射撃】
素焼の皿を飛ばし、これを標的として散弾銃でねらいうちする射撃競技。トラップ競技とスキート競技とがある。クレー。
⇒クレー【clay】
グレー‐ゾーン【grey zone】
どちらとも判別できない領域。どっちつかずの領域。
⇒グレー【grey; gray】
クレーター【crater】
惑星や衛星の表面の円形にくぼんだ地形。火山活動の跡や隕石孔いんせきこうとされる。
月のクレーター
撮影:NASA
グレー【grey; gray】
①灰色。ねずみ色。
Munsell color system: N5.5
②銀髪。「ロマンス‐―」
③(白と黒の中間の色であることから)あいまいなこと。どっちつかずであること。
⇒グレー‐カラー【grey-collar】
⇒グレー‐ゾーン【grey zone】
グレー【Alasdair Gray】
スコットランドの小説家。実験的な手法の小説「ラナーク」など。(1934〜)
グレー【Thomas Gray】
イギリスの詩人・学者。詩「墓畔の哀歌」の憂愁趣味や古詩の翻訳を通じてロマン主義の先駆となり、新体詩訳を通じて明治文学に影響を与えた。(1716〜1771)
クレーヴのおくがた【クレーヴの奥方】
(La Princesse de Clèves フランス)ラ=ファイエット夫人の小説。1678年刊。古典的文体とこまやかな心理分析に秀でた近代小説の先駆。
グレー‐カラー【grey-collar】
(灰色の作業服を着ることから)修理・整備など技術関係の労働者。ホワイト‐カラー・ブルー‐カラーに対していう。
⇒グレー【grey; gray】
クレー‐コート【clay court】
テニスで、粘土などで固めたコート。→グラスコート。
⇒クレー【clay】
グレーザー【Donald Arthur Glaser】
アメリカの実験物理学者。カリフォルニア大学教授。高速荷電粒子の飛跡を観測する泡箱を発明。ノーベル賞。(1926〜)
クレージー【crazy】
常軌を逸しているさま。熱狂的なさま。「―な演奏」
グレーシャー【glacier】
(→)氷河。
クレー‐しゃげき【クレー射撃】
素焼の皿を飛ばし、これを標的として散弾銃でねらいうちする射撃競技。トラップ競技とスキート競技とがある。クレー。
⇒クレー【clay】
グレー‐ゾーン【grey zone】
どちらとも判別できない領域。どっちつかずの領域。
⇒グレー【grey; gray】
クレーター【crater】
惑星や衛星の表面の円形にくぼんだ地形。火山活動の跡や隕石孔いんせきこうとされる。
月のクレーター
撮影:NASA
 グレーダー【grader】
土掻き板を備えた地ならし用の建設機械。道路工事などに用いる。
グレート【great】
大きいさま。偉大なさま。
グレード【grade】
等級。段階。品等。
⇒グレード‐アップ
グレード‐アップ
(和製語grade up)等級や格を上げること。「―した装い」
⇒グレード【grade】
グレート‐ソルト‐こ【グレートソルト湖】
(Great Salt Lake)アメリカ西部、ユタ州の大きな内陸湖。面積4700平方キロメートル。湖水1リットル中に約200グラムの塩分を含む。大塩湖。
グレート‐デーン【Great Dane】
(偉大なデンマーク犬の意)イヌの一品種。最大犬種の一つで、体高75センチメートルほど。耳介を一部切り、人工的に耳を直立させることが多い。毛色は黄、黒、また白に黒の斑点など。ドイツ犬とされるが、イギリスへはデンマークから紹介された。元来は狩猟犬であったが、現在は番犬・愛玩用。
グレート‐バリア‐リーフ【Great Barrier Reef】
オーストラリア大陸北東岸沖にある世界最大の珊瑚礁さんごしょう。長さ2000キロメートル以上。海洋生物の宝庫で、観光地。大堡礁だいほしょう。
グレート・バリア・リーフ
提供:NHK
グレート‐ブリテン【Great Britain】
イギリスを構成する諸島中の主島。イングランド・ウェールズ・スコットランドを含む。大ブリテン島。
グレート‐ベア‐こ【グレートベア湖】
(Great Bear Lake)カナダ最大の淡水湖。北西部にあり、極地に接する。面積約3万2000平方キロメートル。最大深度82メートル。
グレーバー【graver】
(→)彫器ちょうきに同じ。
グレーハウンド【greyhound】
イヌの一品種。やせて四肢の長い体形で、原産地はエジプトといわれる。体高70センチメートルほどで、走るのが早い。古代は狩猟に用いたが、現在はドッグレースや愛玩用。
クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
①強撚糸を用いて縮緬ちりめん風に縮らせ皺しぼを出した織物。縮地ちぢみじ綿布。クレップ。
②小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの。ジャム・チーズ・ハムなどを挟んで食べる。
⇒クレープ‐シャツ
⇒クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
⇒クレープ‐ペーパー【crape paper】
グレープ【grape】
ブドウ。
⇒グレープ‐ジュース【grape juice】
⇒グレープ‐フルーツ【grapefruit】
クレープ‐シャツ
(和製語crêpe shirt)クレープ地の夏用シャツ。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐ジュース【grape juice】
ブドウのジュース。
⇒グレープ【grape】
クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
女性用の洋服生地。錦紗きんしゃに似た平織の薄地縮緬ちりめん。元来中国産の縮緬に模してフランスで織り出したもの。フランス縮緬。デシン。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐フルーツ【grapefruit】
ミカン科ザボン類の大形柑橘類。果序がブドウのように総状なのでこの名がある。アメリカで作出された栽培品種。形は夏蜜柑なつみかんほどで、皮は黄色。味は夏蜜柑より酸味が少なく、生食・ジュース用。北米南部やイスラエルで大規模に栽培。
グレープフルーツ
撮影:関戸 勇
グレーダー【grader】
土掻き板を備えた地ならし用の建設機械。道路工事などに用いる。
グレート【great】
大きいさま。偉大なさま。
グレード【grade】
等級。段階。品等。
⇒グレード‐アップ
グレード‐アップ
(和製語grade up)等級や格を上げること。「―した装い」
⇒グレード【grade】
グレート‐ソルト‐こ【グレートソルト湖】
(Great Salt Lake)アメリカ西部、ユタ州の大きな内陸湖。面積4700平方キロメートル。湖水1リットル中に約200グラムの塩分を含む。大塩湖。
グレート‐デーン【Great Dane】
(偉大なデンマーク犬の意)イヌの一品種。最大犬種の一つで、体高75センチメートルほど。耳介を一部切り、人工的に耳を直立させることが多い。毛色は黄、黒、また白に黒の斑点など。ドイツ犬とされるが、イギリスへはデンマークから紹介された。元来は狩猟犬であったが、現在は番犬・愛玩用。
グレート‐バリア‐リーフ【Great Barrier Reef】
オーストラリア大陸北東岸沖にある世界最大の珊瑚礁さんごしょう。長さ2000キロメートル以上。海洋生物の宝庫で、観光地。大堡礁だいほしょう。
グレート・バリア・リーフ
提供:NHK
グレート‐ブリテン【Great Britain】
イギリスを構成する諸島中の主島。イングランド・ウェールズ・スコットランドを含む。大ブリテン島。
グレート‐ベア‐こ【グレートベア湖】
(Great Bear Lake)カナダ最大の淡水湖。北西部にあり、極地に接する。面積約3万2000平方キロメートル。最大深度82メートル。
グレーバー【graver】
(→)彫器ちょうきに同じ。
グレーハウンド【greyhound】
イヌの一品種。やせて四肢の長い体形で、原産地はエジプトといわれる。体高70センチメートルほどで、走るのが早い。古代は狩猟に用いたが、現在はドッグレースや愛玩用。
クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
①強撚糸を用いて縮緬ちりめん風に縮らせ皺しぼを出した織物。縮地ちぢみじ綿布。クレップ。
②小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの。ジャム・チーズ・ハムなどを挟んで食べる。
⇒クレープ‐シャツ
⇒クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
⇒クレープ‐ペーパー【crape paper】
グレープ【grape】
ブドウ。
⇒グレープ‐ジュース【grape juice】
⇒グレープ‐フルーツ【grapefruit】
クレープ‐シャツ
(和製語crêpe shirt)クレープ地の夏用シャツ。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐ジュース【grape juice】
ブドウのジュース。
⇒グレープ【grape】
クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
女性用の洋服生地。錦紗きんしゃに似た平織の薄地縮緬ちりめん。元来中国産の縮緬に模してフランスで織り出したもの。フランス縮緬。デシン。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐フルーツ【grapefruit】
ミカン科ザボン類の大形柑橘類。果序がブドウのように総状なのでこの名がある。アメリカで作出された栽培品種。形は夏蜜柑なつみかんほどで、皮は黄色。味は夏蜜柑より酸味が少なく、生食・ジュース用。北米南部やイスラエルで大規模に栽培。
グレープフルーツ
撮影:関戸 勇
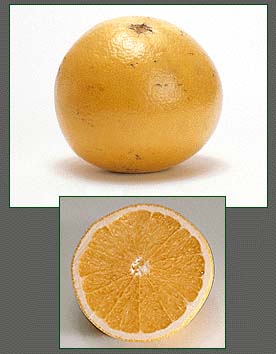 ⇒グレープ【grape】
クレープ‐ペーパー【crape paper】
縮緬ちりめん状の細かい皺しわをつけた紙。包装・手芸・ナプキンなどに使用。縮緬紙。しわ紙。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
クレーマー【claimer】
(原告・請求人の意)企業に対して常習的に苦情を訴える人。
クレーム【claim】
①売買契約で、違約があった場合、売手に損害賠償を請求すること。
②異議。苦情。文句。「―をつける」
⇒クレーム‐タグ【claim tag】
クレーム【crème フランス】
⇒クリーム
⇒クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
クレーム‐タグ【claim tag】
航空機の乗客が預けた荷物の照合に用いる預かり証。
⇒クレーム【claim】
クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
カシスをアルコールに漬けて作る甘いリキュール。
⇒クレーム【crème フランス】
クレール【René Clair】
フランスの映画監督。無声映画時代に前衛映画「眠る巴里」によって監督となり、パリ情緒ものと諷刺喜劇でフランス映画史に一時期を画した。作「巴里の屋根の下」「ル‐ミリオン」「自由を我等に」など。(1898〜1981)
くれ‐えん【榑縁】
細長い板を敷居と平行に並べて張った縁側。↔切目縁きりめえん
クレーン【crane】
(鶴の意)重量物をつり上げて垂直または水平方向に移動させる機械の総称。起重機。
⇒クレーン‐しゃ【クレーン車】
グレーン【grain】
①穀物の粒、また穀物の意。
②(小麦1粒の質量に由来)ヤード‐ポンド法で、質量の単位。1ポンドの7000分の1。0.0648グラムに当たる。ゲレイン。
⇒グレーン‐ドリル【grain drill】
クレーン‐しゃ【クレーン車】
クレーンを搭載した自動車。
⇒クレーン【crane】
グレーン‐ドリル【grain drill】
条播じょうは機。種子を筋状に播まく農業機械。→点播てんぱ機
⇒グレーン【grain】
クレオール【créole フランス】
①中南米やカリブ海の植民地生れのヨーロッパ人、特にスペイン人の称。クリオーリョ。
②米国南部にみられるフランスやスペインの影響を受けた混交的な文化。音楽・料理などにいう。
③広く、植民地支配によって生まれた言語や文化の複合的・雑種的なあり方。
⇒クレオール‐ご【クレオール語】
クレオール‐ご【クレオール語】
主として旧植民地で、植民者の言語が先住民の言語と混ざって独自の言語となり、その土地の母語となったもの。フランス語系・英語系・スペイン語系・ポルトガル語系・オランダ語系のものがある。→ピジン語
⇒クレオール【créole フランス】
クレオソート【creosote】
①イヌブナなどの木材を乾留して得られる油状の液体。淡黄色で強い刺激性の臭気がある。グアヤコール・クレオソールなどのフェノール類およびそのエーテルの混合物。殺菌力が強く消化管内の異常発酵を抑制する。
②(→)クレオソート油に同じ。
⇒クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】
⇒クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】‥ニフハフ
木材の防腐・防虫のため、クレオソートまたはその混和液を注入する方法。電柱や枕木に多く利用された。
⇒クレオソート【creosote】
クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
コールタールのセ氏230〜270度の留分。主成分はナフタレン・クレゾール・高級フェノール類・ナフトール類など。木材の防腐剤に用いる。
⇒クレオソート【creosote】
⇒グレープ【grape】
クレープ‐ペーパー【crape paper】
縮緬ちりめん状の細かい皺しわをつけた紙。包装・手芸・ナプキンなどに使用。縮緬紙。しわ紙。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
クレーマー【claimer】
(原告・請求人の意)企業に対して常習的に苦情を訴える人。
クレーム【claim】
①売買契約で、違約があった場合、売手に損害賠償を請求すること。
②異議。苦情。文句。「―をつける」
⇒クレーム‐タグ【claim tag】
クレーム【crème フランス】
⇒クリーム
⇒クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
クレーム‐タグ【claim tag】
航空機の乗客が預けた荷物の照合に用いる預かり証。
⇒クレーム【claim】
クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
カシスをアルコールに漬けて作る甘いリキュール。
⇒クレーム【crème フランス】
クレール【René Clair】
フランスの映画監督。無声映画時代に前衛映画「眠る巴里」によって監督となり、パリ情緒ものと諷刺喜劇でフランス映画史に一時期を画した。作「巴里の屋根の下」「ル‐ミリオン」「自由を我等に」など。(1898〜1981)
くれ‐えん【榑縁】
細長い板を敷居と平行に並べて張った縁側。↔切目縁きりめえん
クレーン【crane】
(鶴の意)重量物をつり上げて垂直または水平方向に移動させる機械の総称。起重機。
⇒クレーン‐しゃ【クレーン車】
グレーン【grain】
①穀物の粒、また穀物の意。
②(小麦1粒の質量に由来)ヤード‐ポンド法で、質量の単位。1ポンドの7000分の1。0.0648グラムに当たる。ゲレイン。
⇒グレーン‐ドリル【grain drill】
クレーン‐しゃ【クレーン車】
クレーンを搭載した自動車。
⇒クレーン【crane】
グレーン‐ドリル【grain drill】
条播じょうは機。種子を筋状に播まく農業機械。→点播てんぱ機
⇒グレーン【grain】
クレオール【créole フランス】
①中南米やカリブ海の植民地生れのヨーロッパ人、特にスペイン人の称。クリオーリョ。
②米国南部にみられるフランスやスペインの影響を受けた混交的な文化。音楽・料理などにいう。
③広く、植民地支配によって生まれた言語や文化の複合的・雑種的なあり方。
⇒クレオール‐ご【クレオール語】
クレオール‐ご【クレオール語】
主として旧植民地で、植民者の言語が先住民の言語と混ざって独自の言語となり、その土地の母語となったもの。フランス語系・英語系・スペイン語系・ポルトガル語系・オランダ語系のものがある。→ピジン語
⇒クレオール【créole フランス】
クレオソート【creosote】
①イヌブナなどの木材を乾留して得られる油状の液体。淡黄色で強い刺激性の臭気がある。グアヤコール・クレオソールなどのフェノール類およびそのエーテルの混合物。殺菌力が強く消化管内の異常発酵を抑制する。
②(→)クレオソート油に同じ。
⇒クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】
⇒クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】‥ニフハフ
木材の防腐・防虫のため、クレオソートまたはその混和液を注入する方法。電柱や枕木に多く利用された。
⇒クレオソート【creosote】
クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
コールタールのセ氏230〜270度の留分。主成分はナフタレン・クレゾール・高級フェノール類・ナフトール類など。木材の防腐剤に用いる。
⇒クレオソート【creosote】
 ⇒くるり【矪】
くるる【枢】
①扉の端の上下につけた突起(とまら)をかまちの穴(とぼそ)にさし込んで開閉させるための装置。くる。くろろ。拾玉集4「納殿の―の妻戸おし開けて」
②戸の桟。さる。
③回転装置の心棒。枢軸。
⇒くるる‐ぎ【枢木】
⇒くるる‐ど【枢戸】
くるる‐ぎ【枢木】
(→)「くるる」に同じ。
⇒くるる【枢】
くるる‐ど【枢戸】
くるるによって開閉する戸。源氏物語花宴「奥の―もあきて人音もせず」↔引戸
⇒くるる【枢】
くる‐わ【曲輪・郭・廓】
①城・砦など、一定の区域の周囲に築いた土や石のかこい。
②遊女屋の集まっている所。遊郭。遊里。
⇒くるわ‐がよい【郭通い】
⇒くるわ‐ことば【郭詞】
⇒くるわ‐ざた【郭沙汰】
⇒くるわ‐さんがい【郭三界】
⇒くるわ‐づとめ【郭勤め】
⇒くるわ‐の‐あみ【郭の網】
⇒くるわ‐もの【郭者】
⇒くるわ‐もよう【郭模様】
⇒くるわ‐よう【郭様】
⇒くるわ‐よすじ【郭四筋】
くるわ‐か・す【狂はかす】クルハカス
〔他四〕
①くるわす。くるわせる。
②だます。たぶらかす。住吉物語「侍従に―・されて」
くるわ‐がよい【郭通い】‥ガヨヒ
遊郭へたびたびゆくこと。悪所がよい。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ことば【郭詞】
遊郭で遊女の使用することば。田舎詞を使わせないために定めたものという。「ありんす」の類。さとことば。遊里語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ざた【郭沙汰】
遊郭中の評判になること。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐さんがい【郭三界】
遊里全体。浄瑠璃、冥途飛脚「この忠兵衛が五十両損かけうかと気遣ひさに―披露して、男の一分捨てさする」
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわし・い【狂わしい】クルハシイ
〔形〕[文]くるは・し(シク)
(→)「くるおしい」に同じ。
くるわ・す【狂わす】クルハス
[一]〔他五〕
(→)「くるわせる」に同じ。
[二]〔他下二〕
⇒くるわせる(下一)
くるわ・せる【狂わせる】クルハセル
〔他下一〕[文]くるは・す(下二)
①くるうようにする。
②合わないようにする。正確さを失わせる。
③心を乱れさせる。
くるわ‐づとめ【郭勤め】
遊里で働くこと。また、その身。遊女。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐の‐あみ【郭の網】
郭づとめで身の自由を束縛されることを、鳥が網にかかったのにたとえていう語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわぶんしょう【廓文章】‥シヤウ
浄瑠璃。「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」吉田屋の段の改作。また、歌舞伎での同場面の通称。
くるわ‐もの【郭者】
遊里で生計を立てている人。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐もよう【郭模様】‥ヤウ
遊里で流行する模様。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よう【郭様】‥ヤウ
遊郭に独特の風俗。遊里風。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よすじ【郭四筋】‥スヂ
(四筋の通りから成ることから)大坂新町の遊里。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
グルント【Grund ドイツ】
(地面の意)基礎。根底。根拠。論拠。
⇒グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
ドイツの小学校。4年制で、国民一般に共通の基礎教育を行う。基礎学校。
⇒グルント【Grund ドイツ】
くれ【呉】
①中国南北朝時代の南朝およびその支配した江南の地域を日本でいう称。また、広く中国の称。
②呉と通交して以来、中国伝来の事物に添えていう語。「―ない(呉の藍の意)」「―の母おも」「―楽」
くれ【呉】
広島県南西部、広島市の南東にある市。江田島・能美島・倉橋島を望む。もと軍港・海軍工廠があり、現在は造船所がある。人口25万1千。
くれ【呉】
姓氏の一つ。
⇒くれ‐しげいち【呉茂一】
⇒くれ‐しゅうぞう【呉秀三】
くれ【塊】
かたまり。「土―」
くれ【暗れ】
①暗いこと。万葉集20「木この―の繁き尾の上をほととぎす鳴きて越ゆなり」
②不安なさま。万葉集10「春日はるひも―に恋ひわたるかも」
③混乱。五代帝王物語「京中おびただしき―にてぞありし」
くれ【暮れ】
①暮れること。日が入ろうとしてあたりの暗くなる時。日暮れ。夕。晩。「日の―」↔明け。
②すえ。おわり。「年の―」「―の春」
③1年の終り。歳暮。年末。「―の大掃除」
⇒暮れ遅し
⇒暮れ早し
くれ【榑】
①山出しの板材。平安時代の規格では長さ12尺、幅6寸、厚さ4寸。くれき。宇津保物語祭使「浅き世になげきてわたる筏師はいくらの―か流れきぬらん」
②薄板。へぎいた。
③薪。
④(→)背板せいた1に同じ。
くれ【某】
〔代〕
(不定称)「何」という語と並べて用い、不明・不定の人や事物に代えていう語。源氏物語少女「何の御子みこ、―の源氏など数へたまひて」
ぐれ
(「ぐれはま」の略)物事のくいちがうこと。ぐりはま。浄瑠璃、新版歌祭文「―の来ぬ内サアござんせと」
ぐれ
〔動〕メジナの俗称。
グレア【glare】
輝度分布の偏りや極端な輝度対比などによって感じられるまぶしさ。
くれ‐あい【暮合】‥アヒ
暮れようとする頃。日暮れがた。三河物語「―になりければ御門の鍵を渡させ給へといふ」
クレアチニン【creatinine】
クレアチン燐酸の分解最終産物で、筋肉内で非酵素的につくられ、尿中に排泄される。クレアチニンの尿中排泄は糸球体濾過値(GFR)の臨床検査に用いる。
⇒クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
糸球体濾過値検査法の一種。クレアチニンの単位時間内尿中排泄量を血中濃度で除した値。1分間に糸球体で濾過される水分量を表す。
⇒クレアチニン【creatinine】
クレアチン【creatine】
筋肉、特に随意筋に、単独または燐酸と結合した形(クレアチン燐酸)で存在する化合物。生体内では主としてアデノシン三燐酸(ATP)と反応して高いエネルギーをもったクレアチン燐酸として存在し、筋肉の運動の際に分解して大量のエネルギーを放出する。
グレアム【Thomas Graham】
イギリスの化学者。同じ条件のもとで気体が細孔を通って流出する速度はその分子量の平方根に逆比例するというグレアムの法則を発見。コロイド化学の祖。(1805〜1869)
グレイ【gray】
放射線の吸収線量の単位。国際単位系の組立単位。物質1キログラム当り1ジュールのときが1グレイ。100ラドに等しい。記号Gy
クレイグ【Edward Gordon Craig】
イギリスの演劇理論家・舞台美術家。演劇における演出家の絶対的権限を主張し大きな影響を与えた。(1872〜1966)
クレイステネス【Kleisthenēs】
前6世紀末のアテナイの政治家。部族制度の改革を行い、アテナイ民主政治の基礎をおいた。オストラシズム(陶片追放)の発案者。クリステネス。
くれ‐いた【榑板】
①榑の薄板。
②榑縁くれえんに張った板。
クレイトン‐ほう【クレイトン法】‥ハフ
(Clayton Act)アメリカの独占禁止法の中心で、価格協定や合併など企業間の競争制限的行為を規制するための法律。1941年制定。シャーマン法を補完。
くれ‐うち【塊打ち】
田畑を鋤すきで起こしたのち、土塊を塊割りなどでうち砕くこと。
くれ‐うり【榑売】
榑木を売ること。また、その人。
クレー【clay】
①粘土。陶土。また、それで作った皿など。
②クレー射撃で、的として飛ばす素焼の皿。また、クレー射撃の略。
③テニスなどのクレーコートの略。
⇒クレー‐コート【clay court】
⇒クレー‐しゃげき【クレー射撃】
クレー【Paul Klee】
スイス生れのドイツ人画家。初め線描中心で諷刺的人間像を描いたが、のち、自然・都市・人間を記号化・単純化して詩的幻想とユーモアにみちた抽象的絵画を描く。(1879〜1940)
クレー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
⇒くるり【矪】
くるる【枢】
①扉の端の上下につけた突起(とまら)をかまちの穴(とぼそ)にさし込んで開閉させるための装置。くる。くろろ。拾玉集4「納殿の―の妻戸おし開けて」
②戸の桟。さる。
③回転装置の心棒。枢軸。
⇒くるる‐ぎ【枢木】
⇒くるる‐ど【枢戸】
くるる‐ぎ【枢木】
(→)「くるる」に同じ。
⇒くるる【枢】
くるる‐ど【枢戸】
くるるによって開閉する戸。源氏物語花宴「奥の―もあきて人音もせず」↔引戸
⇒くるる【枢】
くる‐わ【曲輪・郭・廓】
①城・砦など、一定の区域の周囲に築いた土や石のかこい。
②遊女屋の集まっている所。遊郭。遊里。
⇒くるわ‐がよい【郭通い】
⇒くるわ‐ことば【郭詞】
⇒くるわ‐ざた【郭沙汰】
⇒くるわ‐さんがい【郭三界】
⇒くるわ‐づとめ【郭勤め】
⇒くるわ‐の‐あみ【郭の網】
⇒くるわ‐もの【郭者】
⇒くるわ‐もよう【郭模様】
⇒くるわ‐よう【郭様】
⇒くるわ‐よすじ【郭四筋】
くるわ‐か・す【狂はかす】クルハカス
〔他四〕
①くるわす。くるわせる。
②だます。たぶらかす。住吉物語「侍従に―・されて」
くるわ‐がよい【郭通い】‥ガヨヒ
遊郭へたびたびゆくこと。悪所がよい。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ことば【郭詞】
遊郭で遊女の使用することば。田舎詞を使わせないために定めたものという。「ありんす」の類。さとことば。遊里語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐ざた【郭沙汰】
遊郭中の評判になること。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐さんがい【郭三界】
遊里全体。浄瑠璃、冥途飛脚「この忠兵衛が五十両損かけうかと気遣ひさに―披露して、男の一分捨てさする」
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわし・い【狂わしい】クルハシイ
〔形〕[文]くるは・し(シク)
(→)「くるおしい」に同じ。
くるわ・す【狂わす】クルハス
[一]〔他五〕
(→)「くるわせる」に同じ。
[二]〔他下二〕
⇒くるわせる(下一)
くるわ・せる【狂わせる】クルハセル
〔他下一〕[文]くるは・す(下二)
①くるうようにする。
②合わないようにする。正確さを失わせる。
③心を乱れさせる。
くるわ‐づとめ【郭勤め】
遊里で働くこと。また、その身。遊女。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐の‐あみ【郭の網】
郭づとめで身の自由を束縛されることを、鳥が網にかかったのにたとえていう語。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわぶんしょう【廓文章】‥シヤウ
浄瑠璃。「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」吉田屋の段の改作。また、歌舞伎での同場面の通称。
くるわ‐もの【郭者】
遊里で生計を立てている人。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐もよう【郭模様】‥ヤウ
遊里で流行する模様。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よう【郭様】‥ヤウ
遊郭に独特の風俗。遊里風。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
くるわ‐よすじ【郭四筋】‥スヂ
(四筋の通りから成ることから)大坂新町の遊里。
⇒くる‐わ【曲輪・郭・廓】
グルント【Grund ドイツ】
(地面の意)基礎。根底。根拠。論拠。
⇒グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
グルント‐シューレ【Grundschule ドイツ】
ドイツの小学校。4年制で、国民一般に共通の基礎教育を行う。基礎学校。
⇒グルント【Grund ドイツ】
くれ【呉】
①中国南北朝時代の南朝およびその支配した江南の地域を日本でいう称。また、広く中国の称。
②呉と通交して以来、中国伝来の事物に添えていう語。「―ない(呉の藍の意)」「―の母おも」「―楽」
くれ【呉】
広島県南西部、広島市の南東にある市。江田島・能美島・倉橋島を望む。もと軍港・海軍工廠があり、現在は造船所がある。人口25万1千。
くれ【呉】
姓氏の一つ。
⇒くれ‐しげいち【呉茂一】
⇒くれ‐しゅうぞう【呉秀三】
くれ【塊】
かたまり。「土―」
くれ【暗れ】
①暗いこと。万葉集20「木この―の繁き尾の上をほととぎす鳴きて越ゆなり」
②不安なさま。万葉集10「春日はるひも―に恋ひわたるかも」
③混乱。五代帝王物語「京中おびただしき―にてぞありし」
くれ【暮れ】
①暮れること。日が入ろうとしてあたりの暗くなる時。日暮れ。夕。晩。「日の―」↔明け。
②すえ。おわり。「年の―」「―の春」
③1年の終り。歳暮。年末。「―の大掃除」
⇒暮れ遅し
⇒暮れ早し
くれ【榑】
①山出しの板材。平安時代の規格では長さ12尺、幅6寸、厚さ4寸。くれき。宇津保物語祭使「浅き世になげきてわたる筏師はいくらの―か流れきぬらん」
②薄板。へぎいた。
③薪。
④(→)背板せいた1に同じ。
くれ【某】
〔代〕
(不定称)「何」という語と並べて用い、不明・不定の人や事物に代えていう語。源氏物語少女「何の御子みこ、―の源氏など数へたまひて」
ぐれ
(「ぐれはま」の略)物事のくいちがうこと。ぐりはま。浄瑠璃、新版歌祭文「―の来ぬ内サアござんせと」
ぐれ
〔動〕メジナの俗称。
グレア【glare】
輝度分布の偏りや極端な輝度対比などによって感じられるまぶしさ。
くれ‐あい【暮合】‥アヒ
暮れようとする頃。日暮れがた。三河物語「―になりければ御門の鍵を渡させ給へといふ」
クレアチニン【creatinine】
クレアチン燐酸の分解最終産物で、筋肉内で非酵素的につくられ、尿中に排泄される。クレアチニンの尿中排泄は糸球体濾過値(GFR)の臨床検査に用いる。
⇒クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
クレアチニン‐クリアランス【creatinine clearance】
糸球体濾過値検査法の一種。クレアチニンの単位時間内尿中排泄量を血中濃度で除した値。1分間に糸球体で濾過される水分量を表す。
⇒クレアチニン【creatinine】
クレアチン【creatine】
筋肉、特に随意筋に、単独または燐酸と結合した形(クレアチン燐酸)で存在する化合物。生体内では主としてアデノシン三燐酸(ATP)と反応して高いエネルギーをもったクレアチン燐酸として存在し、筋肉の運動の際に分解して大量のエネルギーを放出する。
グレアム【Thomas Graham】
イギリスの化学者。同じ条件のもとで気体が細孔を通って流出する速度はその分子量の平方根に逆比例するというグレアムの法則を発見。コロイド化学の祖。(1805〜1869)
グレイ【gray】
放射線の吸収線量の単位。国際単位系の組立単位。物質1キログラム当り1ジュールのときが1グレイ。100ラドに等しい。記号Gy
クレイグ【Edward Gordon Craig】
イギリスの演劇理論家・舞台美術家。演劇における演出家の絶対的権限を主張し大きな影響を与えた。(1872〜1966)
クレイステネス【Kleisthenēs】
前6世紀末のアテナイの政治家。部族制度の改革を行い、アテナイ民主政治の基礎をおいた。オストラシズム(陶片追放)の発案者。クリステネス。
くれ‐いた【榑板】
①榑の薄板。
②榑縁くれえんに張った板。
クレイトン‐ほう【クレイトン法】‥ハフ
(Clayton Act)アメリカの独占禁止法の中心で、価格協定や合併など企業間の競争制限的行為を規制するための法律。1941年制定。シャーマン法を補完。
くれ‐うち【塊打ち】
田畑を鋤すきで起こしたのち、土塊を塊割りなどでうち砕くこと。
くれ‐うり【榑売】
榑木を売ること。また、その人。
クレー【clay】
①粘土。陶土。また、それで作った皿など。
②クレー射撃で、的として飛ばす素焼の皿。また、クレー射撃の略。
③テニスなどのクレーコートの略。
⇒クレー‐コート【clay court】
⇒クレー‐しゃげき【クレー射撃】
クレー【Paul Klee】
スイス生れのドイツ人画家。初め線描中心で諷刺的人間像を描いたが、のち、自然・都市・人間を記号化・単純化して詩的幻想とユーモアにみちた抽象的絵画を描く。(1879〜1940)
クレー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 「鍛冶屋KN」
提供:Photos12/APL
「鍛冶屋KN」
提供:Photos12/APL
 「子どものいる風景」
提供:Photos12/APL
「子どものいる風景」
提供:Photos12/APL
 グレー【grey; gray】
①灰色。ねずみ色。
Munsell color system: N5.5
②銀髪。「ロマンス‐―」
③(白と黒の中間の色であることから)あいまいなこと。どっちつかずであること。
⇒グレー‐カラー【grey-collar】
⇒グレー‐ゾーン【grey zone】
グレー【Alasdair Gray】
スコットランドの小説家。実験的な手法の小説「ラナーク」など。(1934〜)
グレー【Thomas Gray】
イギリスの詩人・学者。詩「墓畔の哀歌」の憂愁趣味や古詩の翻訳を通じてロマン主義の先駆となり、新体詩訳を通じて明治文学に影響を与えた。(1716〜1771)
クレーヴのおくがた【クレーヴの奥方】
(La Princesse de Clèves フランス)ラ=ファイエット夫人の小説。1678年刊。古典的文体とこまやかな心理分析に秀でた近代小説の先駆。
グレー‐カラー【grey-collar】
(灰色の作業服を着ることから)修理・整備など技術関係の労働者。ホワイト‐カラー・ブルー‐カラーに対していう。
⇒グレー【grey; gray】
クレー‐コート【clay court】
テニスで、粘土などで固めたコート。→グラスコート。
⇒クレー【clay】
グレーザー【Donald Arthur Glaser】
アメリカの実験物理学者。カリフォルニア大学教授。高速荷電粒子の飛跡を観測する泡箱を発明。ノーベル賞。(1926〜)
クレージー【crazy】
常軌を逸しているさま。熱狂的なさま。「―な演奏」
グレーシャー【glacier】
(→)氷河。
クレー‐しゃげき【クレー射撃】
素焼の皿を飛ばし、これを標的として散弾銃でねらいうちする射撃競技。トラップ競技とスキート競技とがある。クレー。
⇒クレー【clay】
グレー‐ゾーン【grey zone】
どちらとも判別できない領域。どっちつかずの領域。
⇒グレー【grey; gray】
クレーター【crater】
惑星や衛星の表面の円形にくぼんだ地形。火山活動の跡や隕石孔いんせきこうとされる。
月のクレーター
撮影:NASA
グレー【grey; gray】
①灰色。ねずみ色。
Munsell color system: N5.5
②銀髪。「ロマンス‐―」
③(白と黒の中間の色であることから)あいまいなこと。どっちつかずであること。
⇒グレー‐カラー【grey-collar】
⇒グレー‐ゾーン【grey zone】
グレー【Alasdair Gray】
スコットランドの小説家。実験的な手法の小説「ラナーク」など。(1934〜)
グレー【Thomas Gray】
イギリスの詩人・学者。詩「墓畔の哀歌」の憂愁趣味や古詩の翻訳を通じてロマン主義の先駆となり、新体詩訳を通じて明治文学に影響を与えた。(1716〜1771)
クレーヴのおくがた【クレーヴの奥方】
(La Princesse de Clèves フランス)ラ=ファイエット夫人の小説。1678年刊。古典的文体とこまやかな心理分析に秀でた近代小説の先駆。
グレー‐カラー【grey-collar】
(灰色の作業服を着ることから)修理・整備など技術関係の労働者。ホワイト‐カラー・ブルー‐カラーに対していう。
⇒グレー【grey; gray】
クレー‐コート【clay court】
テニスで、粘土などで固めたコート。→グラスコート。
⇒クレー【clay】
グレーザー【Donald Arthur Glaser】
アメリカの実験物理学者。カリフォルニア大学教授。高速荷電粒子の飛跡を観測する泡箱を発明。ノーベル賞。(1926〜)
クレージー【crazy】
常軌を逸しているさま。熱狂的なさま。「―な演奏」
グレーシャー【glacier】
(→)氷河。
クレー‐しゃげき【クレー射撃】
素焼の皿を飛ばし、これを標的として散弾銃でねらいうちする射撃競技。トラップ競技とスキート競技とがある。クレー。
⇒クレー【clay】
グレー‐ゾーン【grey zone】
どちらとも判別できない領域。どっちつかずの領域。
⇒グレー【grey; gray】
クレーター【crater】
惑星や衛星の表面の円形にくぼんだ地形。火山活動の跡や隕石孔いんせきこうとされる。
月のクレーター
撮影:NASA
 グレーダー【grader】
土掻き板を備えた地ならし用の建設機械。道路工事などに用いる。
グレート【great】
大きいさま。偉大なさま。
グレード【grade】
等級。段階。品等。
⇒グレード‐アップ
グレード‐アップ
(和製語grade up)等級や格を上げること。「―した装い」
⇒グレード【grade】
グレート‐ソルト‐こ【グレートソルト湖】
(Great Salt Lake)アメリカ西部、ユタ州の大きな内陸湖。面積4700平方キロメートル。湖水1リットル中に約200グラムの塩分を含む。大塩湖。
グレート‐デーン【Great Dane】
(偉大なデンマーク犬の意)イヌの一品種。最大犬種の一つで、体高75センチメートルほど。耳介を一部切り、人工的に耳を直立させることが多い。毛色は黄、黒、また白に黒の斑点など。ドイツ犬とされるが、イギリスへはデンマークから紹介された。元来は狩猟犬であったが、現在は番犬・愛玩用。
グレート‐バリア‐リーフ【Great Barrier Reef】
オーストラリア大陸北東岸沖にある世界最大の珊瑚礁さんごしょう。長さ2000キロメートル以上。海洋生物の宝庫で、観光地。大堡礁だいほしょう。
グレート・バリア・リーフ
提供:NHK
グレート‐ブリテン【Great Britain】
イギリスを構成する諸島中の主島。イングランド・ウェールズ・スコットランドを含む。大ブリテン島。
グレート‐ベア‐こ【グレートベア湖】
(Great Bear Lake)カナダ最大の淡水湖。北西部にあり、極地に接する。面積約3万2000平方キロメートル。最大深度82メートル。
グレーバー【graver】
(→)彫器ちょうきに同じ。
グレーハウンド【greyhound】
イヌの一品種。やせて四肢の長い体形で、原産地はエジプトといわれる。体高70センチメートルほどで、走るのが早い。古代は狩猟に用いたが、現在はドッグレースや愛玩用。
クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
①強撚糸を用いて縮緬ちりめん風に縮らせ皺しぼを出した織物。縮地ちぢみじ綿布。クレップ。
②小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの。ジャム・チーズ・ハムなどを挟んで食べる。
⇒クレープ‐シャツ
⇒クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
⇒クレープ‐ペーパー【crape paper】
グレープ【grape】
ブドウ。
⇒グレープ‐ジュース【grape juice】
⇒グレープ‐フルーツ【grapefruit】
クレープ‐シャツ
(和製語crêpe shirt)クレープ地の夏用シャツ。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐ジュース【grape juice】
ブドウのジュース。
⇒グレープ【grape】
クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
女性用の洋服生地。錦紗きんしゃに似た平織の薄地縮緬ちりめん。元来中国産の縮緬に模してフランスで織り出したもの。フランス縮緬。デシン。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐フルーツ【grapefruit】
ミカン科ザボン類の大形柑橘類。果序がブドウのように総状なのでこの名がある。アメリカで作出された栽培品種。形は夏蜜柑なつみかんほどで、皮は黄色。味は夏蜜柑より酸味が少なく、生食・ジュース用。北米南部やイスラエルで大規模に栽培。
グレープフルーツ
撮影:関戸 勇
グレーダー【grader】
土掻き板を備えた地ならし用の建設機械。道路工事などに用いる。
グレート【great】
大きいさま。偉大なさま。
グレード【grade】
等級。段階。品等。
⇒グレード‐アップ
グレード‐アップ
(和製語grade up)等級や格を上げること。「―した装い」
⇒グレード【grade】
グレート‐ソルト‐こ【グレートソルト湖】
(Great Salt Lake)アメリカ西部、ユタ州の大きな内陸湖。面積4700平方キロメートル。湖水1リットル中に約200グラムの塩分を含む。大塩湖。
グレート‐デーン【Great Dane】
(偉大なデンマーク犬の意)イヌの一品種。最大犬種の一つで、体高75センチメートルほど。耳介を一部切り、人工的に耳を直立させることが多い。毛色は黄、黒、また白に黒の斑点など。ドイツ犬とされるが、イギリスへはデンマークから紹介された。元来は狩猟犬であったが、現在は番犬・愛玩用。
グレート‐バリア‐リーフ【Great Barrier Reef】
オーストラリア大陸北東岸沖にある世界最大の珊瑚礁さんごしょう。長さ2000キロメートル以上。海洋生物の宝庫で、観光地。大堡礁だいほしょう。
グレート・バリア・リーフ
提供:NHK
グレート‐ブリテン【Great Britain】
イギリスを構成する諸島中の主島。イングランド・ウェールズ・スコットランドを含む。大ブリテン島。
グレート‐ベア‐こ【グレートベア湖】
(Great Bear Lake)カナダ最大の淡水湖。北西部にあり、極地に接する。面積約3万2000平方キロメートル。最大深度82メートル。
グレーバー【graver】
(→)彫器ちょうきに同じ。
グレーハウンド【greyhound】
イヌの一品種。やせて四肢の長い体形で、原産地はエジプトといわれる。体高70センチメートルほどで、走るのが早い。古代は狩猟に用いたが、現在はドッグレースや愛玩用。
クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
①強撚糸を用いて縮緬ちりめん風に縮らせ皺しぼを出した織物。縮地ちぢみじ綿布。クレップ。
②小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの。ジャム・チーズ・ハムなどを挟んで食べる。
⇒クレープ‐シャツ
⇒クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
⇒クレープ‐ペーパー【crape paper】
グレープ【grape】
ブドウ。
⇒グレープ‐ジュース【grape juice】
⇒グレープ‐フルーツ【grapefruit】
クレープ‐シャツ
(和製語crêpe shirt)クレープ地の夏用シャツ。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐ジュース【grape juice】
ブドウのジュース。
⇒グレープ【grape】
クレープ‐デ‐シン【crêpe de Chine フランス】
女性用の洋服生地。錦紗きんしゃに似た平織の薄地縮緬ちりめん。元来中国産の縮緬に模してフランスで織り出したもの。フランス縮緬。デシン。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
グレープ‐フルーツ【grapefruit】
ミカン科ザボン類の大形柑橘類。果序がブドウのように総状なのでこの名がある。アメリカで作出された栽培品種。形は夏蜜柑なつみかんほどで、皮は黄色。味は夏蜜柑より酸味が少なく、生食・ジュース用。北米南部やイスラエルで大規模に栽培。
グレープフルーツ
撮影:関戸 勇
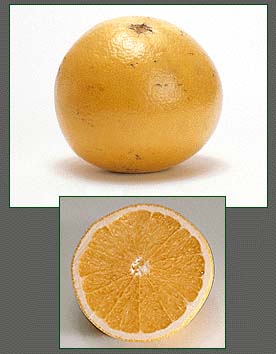 ⇒グレープ【grape】
クレープ‐ペーパー【crape paper】
縮緬ちりめん状の細かい皺しわをつけた紙。包装・手芸・ナプキンなどに使用。縮緬紙。しわ紙。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
クレーマー【claimer】
(原告・請求人の意)企業に対して常習的に苦情を訴える人。
クレーム【claim】
①売買契約で、違約があった場合、売手に損害賠償を請求すること。
②異議。苦情。文句。「―をつける」
⇒クレーム‐タグ【claim tag】
クレーム【crème フランス】
⇒クリーム
⇒クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
クレーム‐タグ【claim tag】
航空機の乗客が預けた荷物の照合に用いる預かり証。
⇒クレーム【claim】
クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
カシスをアルコールに漬けて作る甘いリキュール。
⇒クレーム【crème フランス】
クレール【René Clair】
フランスの映画監督。無声映画時代に前衛映画「眠る巴里」によって監督となり、パリ情緒ものと諷刺喜劇でフランス映画史に一時期を画した。作「巴里の屋根の下」「ル‐ミリオン」「自由を我等に」など。(1898〜1981)
くれ‐えん【榑縁】
細長い板を敷居と平行に並べて張った縁側。↔切目縁きりめえん
クレーン【crane】
(鶴の意)重量物をつり上げて垂直または水平方向に移動させる機械の総称。起重機。
⇒クレーン‐しゃ【クレーン車】
グレーン【grain】
①穀物の粒、また穀物の意。
②(小麦1粒の質量に由来)ヤード‐ポンド法で、質量の単位。1ポンドの7000分の1。0.0648グラムに当たる。ゲレイン。
⇒グレーン‐ドリル【grain drill】
クレーン‐しゃ【クレーン車】
クレーンを搭載した自動車。
⇒クレーン【crane】
グレーン‐ドリル【grain drill】
条播じょうは機。種子を筋状に播まく農業機械。→点播てんぱ機
⇒グレーン【grain】
クレオール【créole フランス】
①中南米やカリブ海の植民地生れのヨーロッパ人、特にスペイン人の称。クリオーリョ。
②米国南部にみられるフランスやスペインの影響を受けた混交的な文化。音楽・料理などにいう。
③広く、植民地支配によって生まれた言語や文化の複合的・雑種的なあり方。
⇒クレオール‐ご【クレオール語】
クレオール‐ご【クレオール語】
主として旧植民地で、植民者の言語が先住民の言語と混ざって独自の言語となり、その土地の母語となったもの。フランス語系・英語系・スペイン語系・ポルトガル語系・オランダ語系のものがある。→ピジン語
⇒クレオール【créole フランス】
クレオソート【creosote】
①イヌブナなどの木材を乾留して得られる油状の液体。淡黄色で強い刺激性の臭気がある。グアヤコール・クレオソールなどのフェノール類およびそのエーテルの混合物。殺菌力が強く消化管内の異常発酵を抑制する。
②(→)クレオソート油に同じ。
⇒クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】
⇒クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】‥ニフハフ
木材の防腐・防虫のため、クレオソートまたはその混和液を注入する方法。電柱や枕木に多く利用された。
⇒クレオソート【creosote】
クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
コールタールのセ氏230〜270度の留分。主成分はナフタレン・クレゾール・高級フェノール類・ナフトール類など。木材の防腐剤に用いる。
⇒クレオソート【creosote】
⇒グレープ【grape】
クレープ‐ペーパー【crape paper】
縮緬ちりめん状の細かい皺しわをつけた紙。包装・手芸・ナプキンなどに使用。縮緬紙。しわ紙。
⇒クレープ【crêpe フランス・crape イギリス】
クレーマー【claimer】
(原告・請求人の意)企業に対して常習的に苦情を訴える人。
クレーム【claim】
①売買契約で、違約があった場合、売手に損害賠償を請求すること。
②異議。苦情。文句。「―をつける」
⇒クレーム‐タグ【claim tag】
クレーム【crème フランス】
⇒クリーム
⇒クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
クレーム‐タグ【claim tag】
航空機の乗客が預けた荷物の照合に用いる預かり証。
⇒クレーム【claim】
クレーム‐ド‐カシス【crème de cassis フランス】
カシスをアルコールに漬けて作る甘いリキュール。
⇒クレーム【crème フランス】
クレール【René Clair】
フランスの映画監督。無声映画時代に前衛映画「眠る巴里」によって監督となり、パリ情緒ものと諷刺喜劇でフランス映画史に一時期を画した。作「巴里の屋根の下」「ル‐ミリオン」「自由を我等に」など。(1898〜1981)
くれ‐えん【榑縁】
細長い板を敷居と平行に並べて張った縁側。↔切目縁きりめえん
クレーン【crane】
(鶴の意)重量物をつり上げて垂直または水平方向に移動させる機械の総称。起重機。
⇒クレーン‐しゃ【クレーン車】
グレーン【grain】
①穀物の粒、また穀物の意。
②(小麦1粒の質量に由来)ヤード‐ポンド法で、質量の単位。1ポンドの7000分の1。0.0648グラムに当たる。ゲレイン。
⇒グレーン‐ドリル【grain drill】
クレーン‐しゃ【クレーン車】
クレーンを搭載した自動車。
⇒クレーン【crane】
グレーン‐ドリル【grain drill】
条播じょうは機。種子を筋状に播まく農業機械。→点播てんぱ機
⇒グレーン【grain】
クレオール【créole フランス】
①中南米やカリブ海の植民地生れのヨーロッパ人、特にスペイン人の称。クリオーリョ。
②米国南部にみられるフランスやスペインの影響を受けた混交的な文化。音楽・料理などにいう。
③広く、植民地支配によって生まれた言語や文化の複合的・雑種的なあり方。
⇒クレオール‐ご【クレオール語】
クレオール‐ご【クレオール語】
主として旧植民地で、植民者の言語が先住民の言語と混ざって独自の言語となり、その土地の母語となったもの。フランス語系・英語系・スペイン語系・ポルトガル語系・オランダ語系のものがある。→ピジン語
⇒クレオール【créole フランス】
クレオソート【creosote】
①イヌブナなどの木材を乾留して得られる油状の液体。淡黄色で強い刺激性の臭気がある。グアヤコール・クレオソールなどのフェノール類およびそのエーテルの混合物。殺菌力が強く消化管内の異常発酵を抑制する。
②(→)クレオソート油に同じ。
⇒クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】
⇒クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
クレオソート‐ちゅうにゅうほう【クレオソート注入法】‥ニフハフ
木材の防腐・防虫のため、クレオソートまたはその混和液を注入する方法。電柱や枕木に多く利用された。
⇒クレオソート【creosote】
クレオソート‐ゆ【クレオソート油】
コールタールのセ氏230〜270度の留分。主成分はナフタレン・クレゾール・高級フェノール類・ナフトール類など。木材の防腐剤に用いる。
⇒クレオソート【creosote】
け【来】🔗⭐🔉
け【来】
(上代東国方言)動詞「き(来)」(連用形)に同じ。万葉集20「父母に物言ものわず―にて今ぞくやしき」
け・り【来り】🔗⭐🔉
け・り【来り】
〔自ラ変〕
(「来く」の連用形キにアリの付いたキアリの約)来ている。来た。万葉集3「雪消げの道をなづみ―・るかも」
こ【来】🔗⭐🔉
こ【来】
カ変動詞「く」の未然形・命令形。命令形は後世、「こよ」とも。更級日記「いづら猫は。こちゐて―」
こ‐し‐かた【来し方】🔗⭐🔉
こ‐し‐かた【来し方】
(「こ」は動詞「く」の未然形、「し」は過去の助動詞「き」の連体形。「きしかた」とも)
①すぎてきた時。過去。新古今和歌集雑「―をさながら夢になしつれば」
②過ぎて来た方向、また、その場所。源氏物語須磨「―の山は霞はるかにて」
⇒こしかた‐ゆくすえ【来し方行く末】
こしかた‐ゆくすえ【来し方行く末】‥スヱ🔗⭐🔉
こしかた‐ゆくすえ【来し方行く末】‥スヱ
過去と未来。栄華物語玉飾「―思し続けらるることも」
⇒こ‐し‐かた【来し方】
○腰が強いこしがつよい
①たやすく人に屈しない。気がつよい。
②(餅・麺めんなどの)ねばりや弾力性が強い。
⇒こし【腰】
○腰がないこしがない
麺めん類などに、しっかりした粘りや弾力性がない。
⇒こし【腰】
○腰が抜けて一生立居のならぬ法もあれこしがぬけていっしょうたちいのならぬほうもあれ
もし違約したら一生腰抜けになりましょうという誓いの詞。狂言、六人僧「身どもは腹をたてたれば、―。腹は立てますまい」
⇒こし【腰】
○腰が抜けるこしがぬける
驚いて立ち上がる力がなくなる。また、激しい打撃を受けて気力がなくなる。
⇒こし【腰】
○腰が低いこしがひくい
他人に対して態度が謙虚である。
⇒こし【腰】
こ‐ね【来ね】🔗⭐🔉
こ‐ね【来ね】
(ネは願望の意を表す助詞)こい。来てくれ。万葉集10「風に副たぐひてここに散り―」
こん‐とし【来ん年】🔗⭐🔉
こん‐とし【来ん年】
(「ん(む)」は推量の助動詞)今年の次に来るべき年。らいねん。
こん‐よ【来ん世】🔗⭐🔉
こん‐よ【来ん世】
(「ん(む)」は推量の助動詞)来世。万葉集3「来む世には虫に鳥にも吾はなりなむ」
こん‐よ【来ん夜】🔗⭐🔉
こん‐よ【来ん夜】
(「ん(む)」は推量の助動詞)
①あすの夜。明晩。
②今晩。
らい【来】🔗⭐🔉
らい【来】
①これから来る時。次にくること。つぎの。「―学年」
②このかた。そののち。「昨年―」
らい【来】(姓氏)🔗⭐🔉
らい‐い【来意】🔗⭐🔉
らい‐い【来意】
①来訪の趣意。「―を告げる」
②手紙で言って来た趣意。申し越しの趣旨。
らい‐えつ【来謁】🔗⭐🔉
らい‐えつ【来謁】
来てお目にかかること。
らい‐えん【来援】‥ヱン🔗⭐🔉
らい‐えん【来援】‥ヱン
来てたすけること。
らい‐えん【来演】🔗⭐🔉
らい‐えん【来演】
その土地に来て、音楽・劇などを演ずること。
らい‐おう【来往】‥ワウ🔗⭐🔉
らい‐おう【来往】‥ワウ
行ったり来たりすること。往来。
らい‐が【来賀】🔗⭐🔉
らい‐が【来賀】
来てよろこびを述べること。
らい‐が【来駕】🔗⭐🔉
らい‐が【来駕】
(古くはライカとも)他人の来訪の尊敬語。「御―を賜り光栄に存じます」
らい‐かい【来会】‥クワイ🔗⭐🔉
らい‐かい【来会】‥クワイ
来て一緒になること。会に出席すること。
らい‐かく【来格】🔗⭐🔉
らい‐かく【来格】
(「格」は至る意)祭祀などに、神霊の降り来ること。源平盛衰記45「鏡璽―の報賽」
らい‐がくねん【来学年】🔗⭐🔉
らい‐がくねん【来学年】
この次に来る学年。
らい‐がっき【来学期】‥ガク‥🔗⭐🔉
らい‐がっき【来学期】‥ガク‥
この次に来る学期。
らい‐かん【来簡・来翰】🔗⭐🔉
らい‐かん【来簡・来翰】
他から来た手紙。来信。来書。来状。
らい‐かん【来観】‥クワン🔗⭐🔉
らい‐かん【来観】‥クワン
来て、みること。「―者」
らい‐き【来期】🔗⭐🔉
らい‐き【来期】
この次の期。今の時期が済んだ次の期間。「―の予算」
らい‐ぎ【来儀】🔗⭐🔉
らい‐ぎ【来儀】
(「儀」も来る意)来ることの尊敬語。狂言、鳳凰の風流「唯今目出度き舞の囃子の音に引かれ、これまで―仕りて候」。日葡辞書「ライギ。即ち、ヲンイデ」
らい‐きゃく【来客】🔗⭐🔉
らい‐きゃく【来客】
訪れてきた客。また、客が訪ねてくること。らいかく。「―中」
らい‐きょ【来去】🔗⭐🔉
らい‐きょ【来去】
行ったり来たりすること。去来。
らい‐くにつぐ【来国次】🔗⭐🔉
らい‐くにつぐ【来国次】
鎌倉後期の刀工。国俊の女婿。相模に出て正宗の門に入り十哲の一人。世に鎌倉来という。ほかに同名異人がある。(1247〜1324?)
⇒らい【来】
らい‐くにとし【来国俊】🔗⭐🔉
らい‐くにとし【来国俊】
鎌倉後期、山城の刀工。国行の子。俗に二字国俊と称。ほかに同名異人がある。
⇒らい【来】
らい‐くにゆき【来国行】🔗⭐🔉
らい‐くにゆき【来国行】
鎌倉中期の刀工。通称、来太郎。山城の来派の刀工国吉の子で、名工といわれた。
⇒らい【来】
らい‐げ【来下】🔗⭐🔉
らい‐げ【来下】
くだり来ること。
らい‐けい【来詣】🔗⭐🔉
らい‐けい【来詣】
(「詣」は至る意)来ることをうやうやしくいう語。
らい‐げつ【来月】🔗⭐🔉
らい‐げつ【来月】
今月の次の月。
らい‐けん【来県】🔗⭐🔉
らい‐けん【来県】
他からその県に来ること。
らい‐けん【来献】🔗⭐🔉
らい‐けん【来献】
来て物を献ずること。
らい‐げん【来現】🔗⭐🔉
らい‐げん【来現】
来りあらわれること。あらわれ来ること。
らい‐こう【来光】‥クワウ🔗⭐🔉
らい‐こう【来光】‥クワウ
①高山に登っておがむ日の出。
②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。
らい‐こう【来迎】‥カウ🔗⭐🔉
らい‐こう【来迎】‥カウ
⇒らいごう
らい‐こう【来航】‥カウ🔗⭐🔉
らい‐こう【来航】‥カウ
船や航空機で外国から来ること。
らい‐こう【来貢】🔗⭐🔉
らい‐こう【来貢】
外国の使者が来て貢物みつぎものを献ずること。
らい‐ごう【来迎】‥ガウ🔗⭐🔉
らい‐ごう【来迎】‥ガウ
(ライコウとも)
①〔仏〕臨終の際、仏・菩薩がこれを迎えに来ること。特に浄土門でいう。末灯鈔「臨終をまつことなし。―をたのむことなし」
②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。
⇒らいごう‐いんじょう【来迎引接】
⇒らいごう‐かべ【来迎壁】
⇒らいごう‐ず【来迎図】
⇒らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】
⇒らいごう‐ばしら【来迎柱】
らい‐ごう【来降】‥ガウ🔗⭐🔉
らい‐ごう【来降】‥ガウ
(ライコウとも)神仏が地上に降りてくること。降臨。
らいごう‐いん【来迎院】‥ガウヰン🔗⭐🔉
らいごう‐いん【来迎院】‥ガウヰン
京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号は魚山。別称、大原寺。仁寿(851〜854)年間円仁の創建と伝え、天台声明しょうみょうの発祥地。1094年(嘉保1)融通念仏宗開祖の良忍が隠棲して再興。
らいごう‐いんじょう【来迎引接】‥ガウ‥ゼフ🔗⭐🔉
らいごう‐いんじょう【来迎引接】‥ガウ‥ゼフ
阿弥陀仏が来迎して、衆生を救いとって極楽浄土に導くこと。迎接ごうしょう。引接。梁塵秘抄「一度御名を称となふれば、―疑はず」
⇒らい‐ごう【来迎】
らいごう‐かべ【来迎壁】‥ガウ‥🔗⭐🔉
らいごう‐かべ【来迎壁】‥ガウ‥
仏堂内で、本尊を安置する仏壇の後方にある壁。
⇒らい‐ごう【来迎】
らいごう‐じ【来迎寺】‥ガウ‥🔗⭐🔉
らいごう‐じ【来迎寺】‥ガウ‥
滋賀県大津市にある天台宗の寺。790年(延暦9)最澄開創の地蔵教院を、1001年(長保3)源信が再興して改称したと伝える。鎌倉後期の六道絵をはじめ名宝が多い。聖衆しょうじゅ来迎寺。
らいごう‐ず【来迎図】‥ガウヅ🔗⭐🔉
らいごう‐ず【来迎図】‥ガウヅ
平安中期からの浄土信仰に基づく仏画で、西方浄土の阿弥陀如来が衆生を救うため諸菩薩すなわち聖衆しょうじゅや天人を従えて人間世界へ下降するさまを描いたもの。阿弥陀来迎図。ほかに弥勒来迎図などもある。
⇒らい‐ごう【来迎】
らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】‥ガウ‥🔗⭐🔉
らいごう‐の‐さんぞん【来迎の三尊】‥ガウ‥
来迎する阿弥陀仏と観音・勢至せいしの二菩薩。
⇒らい‐ごう【来迎】
らいごう‐ばしら【来迎柱】‥ガウ‥🔗⭐🔉
らいごう‐ばしら【来迎柱】‥ガウ‥
仏堂内で、来迎壁の左右にある柱。
⇒らい‐ごう【来迎】
らい‐こん【来今】🔗⭐🔉
らい‐こん【来今】
将来と今。また、今から後。今後。自今。以後。
らい‐さい【来歳】🔗⭐🔉
らい‐さい【来歳】
次に来る年。来年。
らい‐さつ【来札】🔗⭐🔉
らい‐さつ【来札】
よそから来た手紙。来状。来翰。来書。来信。
らいざん【来山】🔗⭐🔉
らいざん【来山】
⇒こにしらいざん(小西来山)
らい‐し【来旨】🔗⭐🔉
らい‐し【来旨】
他人から言ってよこした趣旨。来意。
らい‐じ【来示】🔗⭐🔉
らい‐じ【来示】
(ライシとも)書状で書きよこしたことがらを尊敬していう語。来諭。来命。「御―の件」
らい‐しゃ【来社】🔗⭐🔉
らい‐しゃ【来社】
会社などへ人が訪ねて来ること。
らい‐しゃ【来車】🔗⭐🔉
らい‐しゃ【来車】
乗物に乗って来ること。転じて、他人の来訪を尊敬していう語。来駕らいが。
らい‐しゃ【来者】🔗⭐🔉
らい‐しゃ【来者】
①来た人。来訪の人。
②自分より後に生まれて来る人。後進の徒。
③将来のこと。未来。「―知るべからず」↔往者
らい‐しゅう【来週】‥シウ🔗⭐🔉
らい‐しゅう【来週】‥シウ
今週の次の週。次週。
らい‐しゅう【来襲】‥シフ🔗⭐🔉
らい‐しゅう【来襲】‥シフ
おそってくること。攻めこんで来ること。「台風が―する」「敵機―」
らいらい‐せせ【来来世世】🔗⭐🔉
らいらい‐せせ【来来世世】
来世のまたその次の来世。生きかわり死にかわりする長い未来。
[漢]来🔗⭐🔉
来 字形
 筆順
筆順
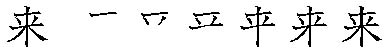 〔木部3画/7画/教育/4572・4D68〕
[來] 字形
〔木部3画/7画/教育/4572・4D68〕
[來] 字形
 〔人部6画/8画/4852・5054〕
〔音〕ライ(漢)
〔訓〕くる・きたる・きたす
[意味]
①こちらに近づく。くる。(対)往・去。「来客・来訪・到来・舶来・未来」
②物事がおこる。きたす。「出来しゅったい・来由・来歴」
③今の次にくる。きたる(べき)。「来年・来春・来世・来学年」
④それよりこのかた。「以来・古来・生来・昨夜来」
⑤文末について、「いざ…しよう」という語気を示す助字。漢文訓読では特定な読みならわしがあるとき以外には読まない。「帰去来兮=帰りなんいざ」〔帰去来の辞〕
[解字]
象形。ライむぎの形にかたどる。「夂」(=歩く)を加えた「麥(=麦)」が本来は「歩いてくる」意であったが、誤用されて、逆に「麥」が「むぎ」、「來」が「くる」意となった。[徠][
〔人部6画/8画/4852・5054〕
〔音〕ライ(漢)
〔訓〕くる・きたる・きたす
[意味]
①こちらに近づく。くる。(対)往・去。「来客・来訪・到来・舶来・未来」
②物事がおこる。きたす。「出来しゅったい・来由・来歴」
③今の次にくる。きたる(べき)。「来年・来春・来世・来学年」
④それよりこのかた。「以来・古来・生来・昨夜来」
⑤文末について、「いざ…しよう」という語気を示す助字。漢文訓読では特定な読みならわしがあるとき以外には読まない。「帰去来兮=帰りなんいざ」〔帰去来の辞〕
[解字]
象形。ライむぎの形にかたどる。「夂」(=歩く)を加えた「麥(=麦)」が本来は「歩いてくる」意であったが、誤用されて、逆に「麥」が「むぎ」、「來」が「くる」意となった。[徠][ ][耒]は異体字。
[下ツキ
以来・遠来・往来・外来・元来・帰去来・客来・旧来・向来・去来・帰来・近来・月来・家来・巻土重来・捲土重来・後来・光来・古往今来・古来・在来・再来・山帰来・襲来・従来・出来・将来・招来・請来・爾来・新来・生来・千客万来・尊来・朝来・天来・伝来・到来・当来・渡来・入来・如来・年来・舶来・飛来・風来・本来・未来・夜来・由来・老来
][耒]は異体字。
[下ツキ
以来・遠来・往来・外来・元来・帰去来・客来・旧来・向来・去来・帰来・近来・月来・家来・巻土重来・捲土重来・後来・光来・古往今来・古来・在来・再来・山帰来・襲来・従来・出来・将来・招来・請来・爾来・新来・生来・千客万来・尊来・朝来・天来・伝来・到来・当来・渡来・入来・如来・年来・舶来・飛来・風来・本来・未来・夜来・由来・老来
 筆順
筆順
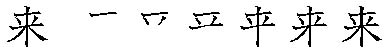 〔木部3画/7画/教育/4572・4D68〕
[來] 字形
〔木部3画/7画/教育/4572・4D68〕
[來] 字形
 〔人部6画/8画/4852・5054〕
〔音〕ライ(漢)
〔訓〕くる・きたる・きたす
[意味]
①こちらに近づく。くる。(対)往・去。「来客・来訪・到来・舶来・未来」
②物事がおこる。きたす。「出来しゅったい・来由・来歴」
③今の次にくる。きたる(べき)。「来年・来春・来世・来学年」
④それよりこのかた。「以来・古来・生来・昨夜来」
⑤文末について、「いざ…しよう」という語気を示す助字。漢文訓読では特定な読みならわしがあるとき以外には読まない。「帰去来兮=帰りなんいざ」〔帰去来の辞〕
[解字]
象形。ライむぎの形にかたどる。「夂」(=歩く)を加えた「麥(=麦)」が本来は「歩いてくる」意であったが、誤用されて、逆に「麥」が「むぎ」、「來」が「くる」意となった。[徠][
〔人部6画/8画/4852・5054〕
〔音〕ライ(漢)
〔訓〕くる・きたる・きたす
[意味]
①こちらに近づく。くる。(対)往・去。「来客・来訪・到来・舶来・未来」
②物事がおこる。きたす。「出来しゅったい・来由・来歴」
③今の次にくる。きたる(べき)。「来年・来春・来世・来学年」
④それよりこのかた。「以来・古来・生来・昨夜来」
⑤文末について、「いざ…しよう」という語気を示す助字。漢文訓読では特定な読みならわしがあるとき以外には読まない。「帰去来兮=帰りなんいざ」〔帰去来の辞〕
[解字]
象形。ライむぎの形にかたどる。「夂」(=歩く)を加えた「麥(=麦)」が本来は「歩いてくる」意であったが、誤用されて、逆に「麥」が「むぎ」、「來」が「くる」意となった。[徠][ ][耒]は異体字。
[下ツキ
以来・遠来・往来・外来・元来・帰去来・客来・旧来・向来・去来・帰来・近来・月来・家来・巻土重来・捲土重来・後来・光来・古往今来・古来・在来・再来・山帰来・襲来・従来・出来・将来・招来・請来・爾来・新来・生来・千客万来・尊来・朝来・天来・伝来・到来・当来・渡来・入来・如来・年来・舶来・飛来・風来・本来・未来・夜来・由来・老来
][耒]は異体字。
[下ツキ
以来・遠来・往来・外来・元来・帰去来・客来・旧来・向来・去来・帰来・近来・月来・家来・巻土重来・捲土重来・後来・光来・古往今来・古来・在来・再来・山帰来・襲来・従来・出来・将来・招来・請来・爾来・新来・生来・千客万来・尊来・朝来・天来・伝来・到来・当来・渡来・入来・如来・年来・舶来・飛来・風来・本来・未来・夜来・由来・老来
大辞林の検索結果 (95)
き-あわ・せる【来合(わ)せる】🔗⭐🔉
き-あわ・せる ―アハセル [4][0] 【来合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 きあは・す
たまたまそこへ来て出会う。都合よく,そこに来る。「ちょうどそこへ兄が―・せた」
き-かか・る【来掛(か)る】🔗⭐🔉
き-かか・る [3] 【来掛(か)る】 (動ラ五[四])
(1)こちらへ向かって来始める。
(2)ちょうどその場所へ来る。さしかかる。
き-し-かた【来し方】🔗⭐🔉
き-し-かた 【来し方】 (連語)
〔「き」は動詞「く(来)」の連用形,「し」は過去の助動詞「き」の連体形〕
(1)過ぎ去った時。過去。こしかた。「―の事なども人知れず思ひ出でけり/源氏(夕顔)」
(2)やってきた方向・経路。「住吉の―慕ふあとの白波/新千載(雑上)」
→こしかた
きしかた-ゆくすえ【来し方行く末】🔗⭐🔉
きしかた-ゆくすえ ―ス 【来し方行く末】
(1)過ごしてきた日々とこれから先の日々。「―おもひ続け給ふに/源氏(須磨)」
(2)来た方向とこれから行く方向。「ある時には,―も知らず,海にまぎれむとしき/竹取」
【来し方行く末】
(1)過ごしてきた日々とこれから先の日々。「―おもひ続け給ふに/源氏(須磨)」
(2)来た方向とこれから行く方向。「ある時には,―も知らず,海にまぎれむとしき/竹取」
 【来し方行く末】
(1)過ごしてきた日々とこれから先の日々。「―おもひ続け給ふに/源氏(須磨)」
(2)来た方向とこれから行く方向。「ある時には,―も知らず,海にまぎれむとしき/竹取」
【来し方行く末】
(1)過ごしてきた日々とこれから先の日々。「―おもひ続け給ふに/源氏(須磨)」
(2)来た方向とこれから行く方向。「ある時には,―も知らず,海にまぎれむとしき/竹取」
き-しな【来しな】🔗⭐🔉
き-しな [0] 【来しな】
〔「しな」は接尾語〕
来るとき。来るついで。きがけ。「―に立ち寄る」
きた・す【来す】🔗⭐🔉
きた・す [2][0] 【来す】 (動サ五[四])
(1)ある結果を招く。ある事態を生じさせる。好ましくないことについていうことが多い。「運営に支障を―・す」
(2)来るようにする。招く。「法門を皆―・して我が所に持し奉らむ/今昔 1」
〔漢文訓読系の語。「きたる」に対する他動詞〕
きた・る【来る】🔗⭐🔉
きた・る [2] 【来る】 (動ラ五[四])
〔「来(キ)到(イタ)る」の転か。「来たる」とも書く〕
(1)くる。やってくる。「我が町へ首相―・る」「韓国を如何に言(フ)ことそ目頬子(メズラコ)―・る/日本書紀(継体)」
(2)古くなって役に立たなくなる。傷む。「少し―・つた小袖をうちかけ/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」
(3)異性に心を奪われる。ほれこむ。参る。「年増のお麦めは自己(オイラ)に九分九厘―・つてゐて/滑稽本・七偏人」
〔漢文訓読系の語。「きたす」に対する自動詞〕
来りなば🔗⭐🔉
来りなば
〔「な」は完了の助動詞「ぬ」の未然形〕
来たらば。「冬―春遠からじ」
来るべき🔗⭐🔉
来るべき
これから来るはずの。今度の。「―選挙」
来る者は拒(コバ)まず🔗⭐🔉
来る者は拒(コバ)まず
仲間になりたい,行動をともにしたいと寄ってくる者はだれでも迎え入れる,ということ。「―去る者は追わず」
き-て【来手】🔗⭐🔉
き-て [2] 【来手】
来る人。来てくれる人。「嫁の―がない」
き・ふ【来経】🔗⭐🔉
き・ふ 【来経】 (動ハ下二)
年月が経過してゆく。「あらたまの年が―・ふれば/古事記(中)」
き-むか・う【来向かふ】🔗⭐🔉
き-むか・う ―ムカフ 【来向かふ】 (動ハ四)
(時などが)近づく。(人などが)やってくる。「春過ぎて夏―・へば/万葉 4180」
くる【来る】🔗⭐🔉
くる [1] 【来る】 (動カ変)[文]カ変 く
(1)話し手のいる方へ近づく。(ア)(話し手と動作者とが別の場合)話し手が今いる場所,または話し手の領域にやってくる。自分のいる方に接近・到着する。「こっちへ〈こい〉」「客が〈くる〉」「やっと電車が〈き〉た」(イ)(話し手と動作者とが同一の場合)話し手の今いる地点を現在以外の時に訪れる。やってくる。「一〇年前に一度〈き〉たことがある」「この道はいつか〈き〉た道」「あしたまた〈くる〉よ」
(2)動作者が,話し手とともに移動する。目的地に自分を置いた気持ちでいう場合には「行く」で表現することも可能。「映画を見にいく所なんだけど一緒に〈こ〉ないか」「あしたのハイキング,あの人も〈くる〉の」
(3)物が運ばれて,話し手のもとに到達する。「ミロのビーナスが今度また日本に〈くる〉そうだ」「やっと返事が〈き〉た」「先月発注した品物がまだ〈こ〉ない」
(4)風・光などが話し手の方に到達・接近する。また,地震・雨などの自然現象が話し手のいる場所に起こる。「いい風が〈くる〉」「電波の〈くる〉方向にアンテナを向ける」「このへんで一雨〈き〉てくれるといいのだが」
(5)時間が経過して,その季節・時期・順番になる。「春が〈き〉た」「もうすぐ返済の期限が〈くる〉」「やっと私の番が〈き〉た」
(6)ある事態が出現する。(ア)事態が進行して,ある段階にたち至る。「体力はもう限界に〈き〉ている」「交渉は土壇場に〈き〉て難航している」(イ)(「そこへきて」「…の所へきて」の形で)ある悪い事態の上にさらによくない事態が積み重なる。そこへ持って来て。「毎晩残業でくたくただ。そこへ〈き〉てこの暑さだから参った」「もともと二月は客の少ないところへ〈き〉てこの大雪だ」
(7)(「…からくる」の形で)…がその由来・原因となっている。…のために生ずる。「心のゆるみから〈くる〉事故」「風俗習慣の違いから〈くる〉誤解」「英語から〈き〉た外来語」
(8)ある特定の位置を占める。「句読点が行の頭に〈こ〉ないようにする」「本の目次は普通最初に〈くる〉」
(9)病気・故障・劣化などの異常が肉体や物のある部分にあらわれる。「しびれが〈くる〉」「今年の風邪は胃腸に〈くる〉」「体のあちこちにガタが〈くる〉」「飽きの〈こ〉ない色と柄」「かびが〈き〉た餅」
(10)電気・電話・鉄道・水道などが話し手の方へ通じる。「村に電気が〈くる〉」
(11)ある知覚・感覚が生じる。「鼻にツンと〈くる〉におい」「手にびりっと〈き〉た」「頭にぴんと〈き〉た」「胸にじいんと〈くる〉」「かちんと〈くる〉物の言い方」「どうもしっくり〈こ〉ない」
(12)(「よしきた」の形で)承知した。「よし〈き〉た,まかせておけ」
(13)(「…ときたら」「…ときた日には」「…ときているから」などの形で)あるものを話題にとりあげて示す。「うちの亭主と〈き〉たら」「うまい上に安いと〈き〉ているから,いつも満席だ」「鯛の刺身に灘の生一本と〈き〉た日には,こたえられないね」
(14)(「頭にくる」の形で)立腹することを俗にいう。「また遅れてきたので頭に〈き〉た」
(15)(「…にくる」の形で)ある人を慕う気持ちがおこる。「是れ程我等に〈くる〉事,何とも合点がゆかぬ/浮世草子・一代女 1」
(16)(「腹がくる」の形で)空腹になる。「少し腹が〈き〉たわえ/洒落本・通言総籬」
(17)(補助動詞)
動詞の連用形またはこれに「て(で)」の付いた形に付いて,動作が進行し,また,事態が推移する意を表す。(ア)話し手の方へ向かって動作が行われ,その話し手の方へ近づく意を表す。「少年がこっちへ走って〈き〉た」「蜂が飛んで〈き〉た」(イ)(戻ることを前提にして)動作が行われる意を表す。動作の実現・完了に重点が置かれる場合もある。「ちょっと見て〈くる〉よ」「うちへ帰ってカバンを置いて〈くる〉よ」(ウ)ある事態が出現し,またある現象が現れる意を表す。「生まれて〈くる〉子供のために」「なくした本が出て〈き〉た」(エ)動作が継続・反復されて現在に至るまで続く意を表す。「生まれてからずうっとこの村で暮らして〈き〉た」「いつも,ひとに迷惑をかけるな,といって〈き〉たはずだ」(オ)事態が進行してある段階に至る意を表す。「眠くなって〈き〉た」「沖へより潮満ち〈く〉らし/万葉 3642」
(18)行く。目的地を基準にしていう。「富士の山びに我が〈き〉なばいづち向きてか妹が嘆かむ/万葉 3357」
来(キ)と来(ク)🔗⭐🔉
来(キ)と来(ク)
(1)遠い地を急いでやって来る。遠い所からせっせと来る。「きときては川のぼりぢの水を浅み舟も我が身もなづむ今日かな/土左」
(2)次々に来る。「春ごとの花の盛りは我が宿にきとくる人の長居せぬなし/和泉式部集」
くる-とし【来る年】🔗⭐🔉
くる-とし [1] 【来る年】
新しくやってくる年。「行く年 ―」
くる-ひ【来る日】🔗⭐🔉
くる-ひ [1] 【来る日】
新しくやってくる日。翌日。明くる日。「―も―も(=毎日)」
け【来】🔗⭐🔉
け 【来】 (動)
カ変動詞「来(ク)」の連用形「き」の上代東国方言。「父母にもの言はず―にて今ぞ悔しき/万葉 4337」
け・り【来り】🔗⭐🔉
け・り 【来り】 (動ラ変)
〔カ変動詞「く(来)」の連用形「き」に「あり」の付いた「きあり」の転〕
来ている。「玉梓(タマズサ)の使ひの―・れば嬉しみと/万葉 3957」
こ【来】🔗⭐🔉
こ 【来】
カ行変格活用動詞「く」の命令形の古形。こい。「旅にても喪なくはや〈こ〉と我妹子が結びし紐はなれにけるかも/万葉 3717」「こち〈こ〉,と言ひて/大和 103」
〔平安中期以降には,「かしこに物して整へむ,装束(ソウズク)して〈こよ〉/蜻蛉(中)」「こち〈こよ〉,と呼びよせて/宇治拾遺 5」のように間投助詞「よ」を添えた「こよ」の形も用いられるようになり,以後「こよ」が次第に優勢になってゆく〕
→来る
こ-しかた【来し方】🔗⭐🔉
こ-しかた 【来し方】 (連語)
〔「こ」は動詞「来(ク)」の未然形,「し」は助動詞「き」の連体形〕
(1)通ってきた所・方向。「―の山は霞み,はるかにて/源氏(須磨)」
(2)過ごしてきた時間。過去。「身の罪を白状して,其―の事実を語りぬ/当世書生気質(逍遥)」
〔平安時代中期までは(1)は「こしかた」,(2)は「きしかた」と区別されていたが,平安末期から乱れた〕
こしかた-ゆくすえ【来し方行く末】🔗⭐🔉
こしかた-ゆくすえ ―ス 【来し方行く末】
(1)過去と未来。前後。「心の内は―の事も,来ん世の闇もよろづ思ひ忘れて/とはずがたり 4」
(2)通り過ぎてきた方向と,これからの行く先。「はるばる一通りは―野原なり/とはずがたり 4」
【来し方行く末】
(1)過去と未来。前後。「心の内は―の事も,来ん世の闇もよろづ思ひ忘れて/とはずがたり 4」
(2)通り過ぎてきた方向と,これからの行く先。「はるばる一通りは―野原なり/とはずがたり 4」
 【来し方行く末】
(1)過去と未来。前後。「心の内は―の事も,来ん世の闇もよろづ思ひ忘れて/とはずがたり 4」
(2)通り過ぎてきた方向と,これからの行く先。「はるばる一通りは―野原なり/とはずがたり 4」
【来し方行く末】
(1)過去と未来。前後。「心の内は―の事も,来ん世の闇もよろづ思ひ忘れて/とはずがたり 4」
(2)通り過ぎてきた方向と,これからの行く先。「はるばる一通りは―野原なり/とはずがたり 4」
こ-ちょう【来てふ】🔗⭐🔉
こ-ちょう ―テフ 【来てふ】 (連語)
〔動詞「来(ク)」の命令形「こ」に,「と言ふ」の転じた「てふ」が付いたもの〕
来いという。「胡蝶(コチヨウ)」に掛けて用いられる。「月夜よし夜よしと人につげやらば―に似たり待たずしもあらず/古今(恋四)」
こ・れる【来れる】🔗⭐🔉
こ・れる [2] 【来れる】 (動ラ下一)
来ることができる。五段動詞「書く」「読む」の可能動詞「書ける」「読める」などからの類推でできた語。「こられる」が本来の形。
こん-とし【来ん年】🔗⭐🔉
こん-とし 【来ん年】 (連語)
次に来る年。来年。こむとし。「人々は―を北伊太利にて暮さんと/即興詩人(鴎外)」
らい【来】🔗⭐🔉
らい 【来】
(1)時などを表す名詞の上に付いて,次の,来たる,の意を表す。「―学期の計画」「―年度」「―場所」
(2)時などを表す名詞の下に付いて,その時から今まで,それ以来,の意を表す。「昨年―の懸案」「先週―,気分がすぐれない」
らい【来】🔗⭐🔉
らい 【来】
姓氏の一。鎌倉中期から南北朝時代にかけて栄えた,京都の刀工群の家名。国行(クニユキ)・国俊(クニトシ)・国光(クニミツ)・国次(クニツグ)らがおり,山城(ヤマシロ)物を代表する。
らい-い【来意】🔗⭐🔉
らい-い [1] 【来意】
(1)客がたずねて来たわけ。「―を告げる」「―を伺う」
(2)手紙の趣旨。
らい-いん【来院】🔗⭐🔉
らい-いん ― ン [0] 【来院】 (名)スル
病院など「院」と名のつく所へ来ること。
ン [0] 【来院】 (名)スル
病院など「院」と名のつく所へ来ること。
 ン [0] 【来院】 (名)スル
病院など「院」と名のつく所へ来ること。
ン [0] 【来院】 (名)スル
病院など「院」と名のつく所へ来ること。
らい-えつ【来謁】🔗⭐🔉
らい-えつ [0] 【来謁】 (名)スル
来て貴人に面会すること。「国事の為めに―せる人ありと承りしに/経国美談(竜渓)」
らい-えん【来援】🔗⭐🔉
らい-えん ― ン [0] 【来援】 (名)スル
応援に来ること。来て援助すること。「急報で友軍が―した」
ン [0] 【来援】 (名)スル
応援に来ること。来て援助すること。「急報で友軍が―した」
 ン [0] 【来援】 (名)スル
応援に来ること。来て援助すること。「急報で友軍が―した」
ン [0] 【来援】 (名)スル
応援に来ること。来て援助すること。「急報で友軍が―した」
らい-えん【来園】🔗⭐🔉
らい-えん ― ン [0] 【来園】 (名)スル
学園・幼稚園・動物園など「園」と名のつく所に来ること。
ン [0] 【来園】 (名)スル
学園・幼稚園・動物園など「園」と名のつく所に来ること。
 ン [0] 【来園】 (名)スル
学園・幼稚園・動物園など「園」と名のつく所に来ること。
ン [0] 【来園】 (名)スル
学園・幼稚園・動物園など「園」と名のつく所に来ること。
らい-えん【来演】🔗⭐🔉
らい-えん [0] 【来演】 (名)スル
その土地にやって来て演ずること。「オーケストラが―する」
らい-おう【来往】🔗⭐🔉
らい-おう ―ワウ [0] 【来往】 (名)スル
行ったり来たりすること。往来。ゆきき。「市街を―する西人子女/浮城物語(竜渓)」
らい-か【来夏】🔗⭐🔉
らい-か [1] 【来夏】
来年の夏。
らい-が【来賀】🔗⭐🔉
らい-が [1] 【来賀】 (名)スル
来て,祝いの言葉を述べること。
らい-が【来駕】🔗⭐🔉
らい-が [1] 【来駕】 (名)スル
〔「らいか」とも〕
貴人や尊敬する人がやって来ることを敬っていう語。「―を請う」
らい-かい【来会】🔗⭐🔉
らい-かい ―クワイ [0] 【来会】 (名)スル
会合に集まって来ること。「―者」「諸県より―せし有名の姉妹等に/蜃中楼(柳浪)」
らい-がっき【来学期】🔗⭐🔉
らい-がっき ―ガクキ [3] 【来学期】
次の学期。
らい-かん【来館】🔗⭐🔉
らい-かん ―クワン [0] 【来館】 (名)スル
図書館・博物館などに来ること。「―者」「本日―した人数」
らい-かん【来簡・来翰】🔗⭐🔉
らい-かん [0] 【来簡・来翰】
人から来た手紙。来書。来信。
らい-かん【来観】🔗⭐🔉
らい-かん ―クワン [0] 【来観】 (名)スル
来て,見ること。見物するために来ること。「―者」
らい-き【来季】🔗⭐🔉
らい-き [1] 【来季】
(1)次の季節。
(2)スポーツで,次の開催期間。来シーズン。
らい-き【来期】🔗⭐🔉
らい-き [1] 【来期】
この次の期。「―の予算」
らい-きゃく【来客】🔗⭐🔉
らい-きゃく [0] 【来客】
訪ねて来る客。らいかく。「―中で手が離せない」
らい-きょう【来京】🔗⭐🔉
らい-きょう ―キヤウ [0] 【来京】 (名)スル
(1)都へ来ること。
(2)東京,または京都へ来ること。
らい-きょく【来局】🔗⭐🔉
らい-きょく [0] 【来局】 (名)スル
郵便局・放送局など「局」と名のつく機関・建物へ来ること。
らい-げつ【来月】🔗⭐🔉
らい-げつ [1] 【来月】
今月の次の月。
らい-けん【来県】🔗⭐🔉
らい-けん [0] 【来県】 (名)スル
その県へ来ること。「首相―」
らい-こう【来光】🔗⭐🔉
らい-こう ―クワウ [0] 【来光】
⇒御来光(ゴライコウ)
らい-こう【来行】🔗⭐🔉
らい-こう ―カウ [0] 【来行】 (名)スル
銀行へ来ること。
らい-こう【来攻】🔗⭐🔉
らい-こう [0] 【来攻】 (名)スル
敵が攻めて来ること。
らい-こう【来校】🔗⭐🔉
らい-こう ―カウ [0] 【来校】 (名)スル
よそからその学校に来ること。「参観日に父兄が―する」
らい-こう【来航】🔗⭐🔉
らい-こう ―カウ [0] 【来航】 (名)スル
船に乗って外国から来ること。「洋艦―せしより以来(コノカタ)/近世紀聞(延房)」
らい-こう【来貢】🔗⭐🔉
らい-こう [0] 【来貢】 (名)スル
外国から使者が貢(ミツ)ぎ物を持って来ること。入貢。
らい-ごう【来迎】🔗⭐🔉
らい-ごう ―ガウ [0] 【来迎】
〔「らいこう」とも〕
(1)浄土教で,人が死ぬ際に一心に念仏すると,阿弥陀仏や菩薩が迎えにやって来ることをいう。
→臨終正念
(2)
⇒御来迎(ゴライゴウ)(3)
らいごう-いんじょう【来迎引接】🔗⭐🔉
らいごう-いんじょう ―ガウ―ゼフ [0] 【来迎引接】
阿弥陀仏や菩薩が来迎し,衆生(シユジヨウ)を極楽へ導き,救済すること。
らいごう-え【来迎会】🔗⭐🔉
らいごう-え ―ガウ [3] 【来迎会】
〔仏〕 浄土信仰で,阿弥陀仏が死者を救済するために来迎する様を演ずる法会。迎え講。
→練(ネ)り供養(クヨウ)
[3] 【来迎会】
〔仏〕 浄土信仰で,阿弥陀仏が死者を救済するために来迎する様を演ずる法会。迎え講。
→練(ネ)り供養(クヨウ)
 [3] 【来迎会】
〔仏〕 浄土信仰で,阿弥陀仏が死者を救済するために来迎する様を演ずる法会。迎え講。
→練(ネ)り供養(クヨウ)
[3] 【来迎会】
〔仏〕 浄土信仰で,阿弥陀仏が死者を救済するために来迎する様を演ずる法会。迎え講。
→練(ネ)り供養(クヨウ)
らいごう-かべ【来迎壁】🔗⭐🔉
らいごう-かべ ―ガウ― [3] 【来迎壁】
仏堂で,本尊を安置する須弥壇(シユミダン)の後ろにある壁。
らいごう-ず【来迎図】🔗⭐🔉
らいごう-ず ―ガウヅ [3] 【来迎図】
平安中期の浄土信仰に基づく仏画。主に阿弥陀仏が諸菩薩を従えて衆生(シユジヨウ)を極楽浄土に救うため,人間世界へ迎えに下降して来る姿を描いたもの。
らいごう-の-さんぞん【来迎の三尊】🔗⭐🔉
らいごう-の-さんぞん ―ガウ― 【来迎の三尊】
浄土から来迎した姿をとった阿弥陀三尊。
らいごう-ばしら【来迎柱】🔗⭐🔉
らいごう-ばしら ―ガウ― [5] 【来迎柱】
仏堂で,来迎壁の左右にある柱。古くは須弥壇の四隅にあった柱をいった。
らいごう-わさん【来迎和讃】🔗⭐🔉
らいごう-わさん ―ガウ― [5] 【来迎和讃】
三尊の来迎を讃談し,念仏を勧めた和讃。源信の作と伝える。
らい-ごう【来降】🔗⭐🔉
らい-ごう ―ガウ [0] 【来降】 (名)スル
神仏がこの世に降りて来ること。「耶蘇(ヤソ)が天堂から―なし/当世書生気質(逍遥)」
らいごう-いん【来迎院】🔗⭐🔉
らいごう-いん ライガウ ン 【来迎院】
京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号,魚山。仁寿年間(851-854)円仁の開創。1095年良忍の中興。梵唄(ボンバイ)声明の発祥地として有名。
ン 【来迎院】
京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号,魚山。仁寿年間(851-854)円仁の開創。1095年良忍の中興。梵唄(ボンバイ)声明の発祥地として有名。
 ン 【来迎院】
京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号,魚山。仁寿年間(851-854)円仁の開創。1095年良忍の中興。梵唄(ボンバイ)声明の発祥地として有名。
ン 【来迎院】
京都市左京区大原にある天台宗の寺。山号,魚山。仁寿年間(851-854)円仁の開創。1095年良忍の中興。梵唄(ボンバイ)声明の発祥地として有名。
らいごう-じ【来迎寺】🔗⭐🔉
らいごう-じ ライガウ― 【来迎寺】
大津市下坂本にある天台宗の寺。山号,紫雲山。790年最澄が開創した地蔵教院に始まる。1001年源信が当寺で水想観により聖衆来迎(シヨウジユライゴウ)を感得し現寺名に改称。以後,専修念仏道場として栄えた。聖衆来迎寺。
らい-さつ【来札】🔗⭐🔉
らい-さつ [0] 【来札】
人から来た手紙。来簡。来書。来状。
らいざん【来山】🔗⭐🔉
らいざん 【来山】
⇒小西(コニシ)来山
らい-し【来旨】🔗⭐🔉
らい-し [1] 【来旨】
他人の言ってよこした事柄の趣旨。また,来訪の趣旨。来意。「―を告げる」
らい-じ【来示】🔗⭐🔉
らい-じ [0][1] 【来示】
〔「らいし」とも〕
相手のよこした書状の内容を敬っていう語。「御―の趣」
らい-しつ【来室】🔗⭐🔉
らい-しつ [0] 【来室】 (名)スル
部屋,または「室」と名のつく部署に来ること。
らい-しゃ【来社】🔗⭐🔉
らい-しゃ [0] 【来社】 (名)スル
会社などにやって来ること。「先生が―される」
らい-しゃ【来車】🔗⭐🔉
らい-しゃ [0][1] 【来車】 (名)スル
(1)車で来ること。
(2)訪ねて来ることを敬っていう語。来駕。多く手紙や挨拶(アイサツ)などで用いる。「諸君の御―を請ひましたところ/花間鶯(鉄腸)」
らい-しゅう【来秋】🔗⭐🔉
らい-しゅう ―シウ [0] 【来秋】
来年の秋。
らい-しゅう【来週】🔗⭐🔉
らい-しゅう ―シウ [0] 【来週】
この次の週。
らい-しゅう【来襲】🔗⭐🔉
らい-しゅう ―シフ [0] 【来襲】 (名)スル
襲って来ること。突然,攻めて来ること。「イナゴの大群が―する」「敵機の―」
らい-はん【来阪】🔗⭐🔉
らい-はん [0] 【来阪】 (名)スル
大阪へ来ること。
きあわせる【来合わせる】(和英)🔗⭐🔉
きあわせる【来合わせる】
come by chance;happen to be present.
きがけ【来掛に】(和英)🔗⭐🔉
きがけ【来掛に】
on one's way here.
きたす【来たす】(和英)🔗⭐🔉
きたる【来たる】(和英)🔗⭐🔉
くる【来る】(和英)🔗⭐🔉
らい−【来−】(和英)🔗⭐🔉
らいきゃく【来客(がある)】(和英)🔗⭐🔉
らいきゃく【来客(がある)】
(have) a visitor.→英和
らいげつ【来月】(和英)🔗⭐🔉
らいげつ【来月】
next month.〜の今日 this day next month.
らいこう【来航する】(和英)🔗⭐🔉
らいこう【来航する】
visit.→英和
らいしゅう【来週】(和英)🔗⭐🔉
らいしゅう【来週】
next week.〜の今日<米>a week from today;<英>this day[today](next) week.
広辞苑+大辞林に「来」で始まるの検索結果。もっと読み込む