複数辞典一括検索+![]()
![]()
咢 おどろく🔗⭐🔉
【咢】
 9画 口部
区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6
《音読み》 ガク
9画 口部
区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6
《音読み》 ガク
 〈
〈 〉
《訓読み》 おどろく
《意味》
〉
《訓読み》 おどろく
《意味》
 {動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」
{動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」
 ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕
ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕
 「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」
《解字》
「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」
《解字》
 会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。
《単語家族》
逆ギャク
会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。
《単語家族》
逆ギャク 牙ガ(交差してかみあう)と同系。
《類義》
予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚
《熟語》
→下付・中付語
牙ガ(交差してかみあう)と同系。
《類義》
予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚
《熟語》
→下付・中付語
 9画 口部
区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6
《音読み》 ガク
9画 口部
区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6
《音読み》 ガク
 〈
〈 〉
《訓読み》 おどろく
《意味》
〉
《訓読み》 おどろく
《意味》
 {動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」
{動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」
 ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕
ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕
 「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」
《解字》
「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」
《解字》
 会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。
《単語家族》
逆ギャク
会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。
《単語家族》
逆ギャク 牙ガ(交差してかみあう)と同系。
《類義》
予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚
《熟語》
→下付・中付語
牙ガ(交差してかみあう)と同系。
《類義》
予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚
《熟語》
→下付・中付語
嚇 おどす🔗⭐🔉
【嚇】
 17画 口部 [常用漢字]
区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64
《常用音訓》カク
《音読み》 カク
17画 口部 [常用漢字]
区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64
《常用音訓》カク
《音読み》 カク /キャク
/キャク 〈xi
〈xi 〉〈h
〉〈h 〉
《訓読み》 いかる/おどす
《意味》
〉
《訓読み》 いかる/おどす
《意味》
 {動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」
{動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」
 {動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」
{動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」
 「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。
《解字》
会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。
《類義》
→怒
《熟語》
→下付・中付語
「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。
《解字》
会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。
《類義》
→怒
《熟語》
→下付・中付語
 17画 口部 [常用漢字]
区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64
《常用音訓》カク
《音読み》 カク
17画 口部 [常用漢字]
区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64
《常用音訓》カク
《音読み》 カク /キャク
/キャク 〈xi
〈xi 〉〈h
〉〈h 〉
《訓読み》 いかる/おどす
《意味》
〉
《訓読み》 いかる/おどす
《意味》
 {動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」
{動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」
 {動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」
{動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」
 「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。
《解字》
会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。
《類義》
→怒
《熟語》
→下付・中付語
「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。
《解字》
会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。
《類義》
→怒
《熟語》
→下付・中付語
威 おどし🔗⭐🔉
【威】
 9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ(
9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ( )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
 {名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
 イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
 イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく)
「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)
熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ(
9画 女部 [常用漢字]
区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0
《常用音訓》イ
《音読み》 イ( )
)
 〈w
〈w i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
i〉
《訓読み》 おどし/おどす/たけし
《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり
《意味》
 {名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕
 イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕
 イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく)
「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。
《解字》
会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。
《単語家族》
畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)
熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
鬱ウツ(押さえこめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
怛 おどろく🔗⭐🔉
恫 おどす🔗⭐🔉
愕 おどろく🔗⭐🔉
【愕】
 12画
12画  部
区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1
《音読み》 ガク
部
区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1
《音読み》 ガク
 《訓読み》 おどろく
《意味》
《訓読み》 おどろく
《意味》
 {動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕
{動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕
 {動}がみがみいう。
《解字》
会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢
《単語家族》
逆(さからう)
{動}がみがみいう。
《解字》
会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢
《単語家族》
逆(さからう) 忤ゴ(さからう)
忤ゴ(さからう) 顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。
《類義》
→驚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。
《類義》
→驚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画
12画  部
区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1
《音読み》 ガク
部
区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1
《音読み》 ガク
 《訓読み》 おどろく
《意味》
《訓読み》 おどろく
《意味》
 {動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕
{動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕
 {動}がみがみいう。
《解字》
会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢
《単語家族》
逆(さからう)
{動}がみがみいう。
《解字》
会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢
《単語家族》
逆(さからう) 忤ゴ(さからう)
忤ゴ(さからう) 顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。
《類義》
→驚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。
《類義》
→驚
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縅 おどし🔗⭐🔉
【縅】
 15画 糸部 〔国〕
区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E
《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)
《意味》
15画 糸部 〔国〕
区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E
《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)
《意味》
 おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。
おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。 おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。
《解字》
会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。
《熟語》
→下付・中付語
おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。
《解字》
会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。
《熟語》
→下付・中付語
 15画 糸部 〔国〕
区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E
《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)
《意味》
15画 糸部 〔国〕
区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E
《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)
《意味》
 おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。
おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。 おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。
《解字》
会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。
《熟語》
→下付・中付語
おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。
《解字》
会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。
《熟語》
→下付・中付語
脅 おどかす🔗⭐🔉
【脅】
 10画 肉部 [常用漢字]
区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA
《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす
《音読み》 キョウ(ケフ)
10画 肉部 [常用漢字]
区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA
《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす
《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(コフ)
/コウ(コフ) 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき
《意味》
〉
《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき
《意味》
 {動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」
{動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」
 {動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」
{動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」
 {名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。
《解字》
{名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。
《解字》
 会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。
《単語家族》
協(はさんで力をあわす)
会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。
《単語家族》
協(はさんで力をあわす) 挾キョウ(=挟。はさむ)
挾キョウ(=挟。はさむ) 鋏キョウ(はさみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鋏キョウ(はさみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 肉部 [常用漢字]
区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA
《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす
《音読み》 キョウ(ケフ)
10画 肉部 [常用漢字]
区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA
《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす
《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(コフ)
/コウ(コフ) 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき
《意味》
〉
《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき
《意味》
 {動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」
{動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」
 {動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」
{動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」
 {名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。
《解字》
{名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。
《解字》
 会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。
《単語家族》
協(はさんで力をあわす)
会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。
《単語家族》
協(はさんで力をあわす) 挾キョウ(=挟。はさむ)
挾キョウ(=挟。はさむ) 鋏キョウ(はさみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鋏キョウ(はさみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
跳 おどる🔗⭐🔉
【跳】
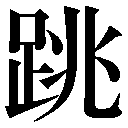 13画 足部 [常用漢字]
区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5
《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる
《音読み》 チョウ(テウ)
13画 足部 [常用漢字]
区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5
《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる
《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈ti
〈ti o〉
《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)
《意味》
o〉
《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)
《意味》
 {動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」
{動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」
 {動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」
{動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」
 {動}はねとばす。「跳丸」
《解字》
会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。
《単語家族》
桃(割れるもも)
{動}はねとばす。「跳丸」
《解字》
会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。
《単語家族》
桃(割れるもも) 挑(ひっかけてはなす)
挑(ひっかけてはなす) 眺(視線を左右にひらく)
眺(視線を左右にひらく) 逃(ぱっと離れてさる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
とぶ。 →飛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
逃(ぱっと離れてさる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
とぶ。 →飛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
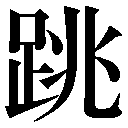 13画 足部 [常用漢字]
区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5
《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる
《音読み》 チョウ(テウ)
13画 足部 [常用漢字]
区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5
《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる
《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈ti
〈ti o〉
《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)
《意味》
o〉
《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)
《意味》
 {動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」
{動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」
 {動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」
{動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」
 {動}はねとばす。「跳丸」
《解字》
会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。
《単語家族》
桃(割れるもも)
{動}はねとばす。「跳丸」
《解字》
会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。
《単語家族》
桃(割れるもも) 挑(ひっかけてはなす)
挑(ひっかけてはなす) 眺(視線を左右にひらく)
眺(視線を左右にひらく) 逃(ぱっと離れてさる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
とぶ。 →飛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
逃(ぱっと離れてさる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
とぶ。 →飛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
踊 おどり🔗⭐🔉
【踊】
 14画 足部 [常用漢字]
区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778
【踴】異体字異体字
14画 足部 [常用漢字]
区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778
【踴】異体字異体字
 16画 足部
区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB
《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る
《音読み》 ヨウ
16画 足部
区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB
《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る
《音読み》 ヨウ /ユ/ユウ
/ユ/ユウ 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)
《名付け》 おどり
《意味》
ng〉
《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)
《名付け》 おどり
《意味》
 {動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」
{動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」
 ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕
ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕
 {動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」
{動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」
 {名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」
〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。
《解字》
会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。
《単語家族》
涌ヨウ(水がとびあがる→わく)
{名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」
〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。
《解字》
会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。
《単語家族》
涌ヨウ(水がとびあがる→わく) 勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。
《類義》
跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。
《異字同訓》
おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。
《類義》
跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。
《異字同訓》
おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 14画 足部 [常用漢字]
区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778
【踴】異体字異体字
14画 足部 [常用漢字]
区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778
【踴】異体字異体字
 16画 足部
区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB
《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る
《音読み》 ヨウ
16画 足部
区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB
《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る
《音読み》 ヨウ /ユ/ユウ
/ユ/ユウ 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)
《名付け》 おどり
《意味》
ng〉
《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)
《名付け》 おどり
《意味》
 {動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」
{動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」
 ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕
ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕
 {動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」
{動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」
 {名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」
〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。
《解字》
会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。
《単語家族》
涌ヨウ(水がとびあがる→わく)
{名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」
〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。
《解字》
会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。
《単語家族》
涌ヨウ(水がとびあがる→わく) 勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。
《類義》
跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。
《異字同訓》
おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。
《類義》
跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。
《異字同訓》
おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
躍 おどらす🔗⭐🔉
【躍】
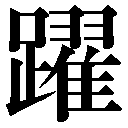 21画 足部 [常用漢字]
区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4
《常用音訓》ヤク/おど…る
《音読み》 ヤク
21画 足部 [常用漢字]
区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4
《常用音訓》ヤク/おど…る
《音読み》 ヤク
 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)
《意味》
〉
《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)
《意味》
 {動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕
{動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕
 {動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕
{動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕
 {形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」
{形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」
 {動}とびあがって走る。
{動}とびあがって走る。
 「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。
《単語家族》
擢テキ(高く抜きあげる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
おどる。 →踊
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。
《単語家族》
擢テキ(高く抜きあげる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
おどる。 →踊
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
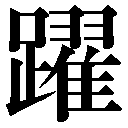 21画 足部 [常用漢字]
区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4
《常用音訓》ヤク/おど…る
《音読み》 ヤク
21画 足部 [常用漢字]
区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4
《常用音訓》ヤク/おど…る
《音読み》 ヤク
 〈yu
〈yu 〉
《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)
《意味》
〉
《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)
《意味》
 {動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕
{動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕
 {動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕
{動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕
 {形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」
{形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」
 {動}とびあがって走る。
{動}とびあがって走る。
 「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。
《単語家族》
擢テキ(高く抜きあげる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
おどる。 →踊
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。
《単語家族》
擢テキ(高く抜きあげる)と同系。
《類義》
→踊
《異字同訓》
おどる。 →踊
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
駭 おどろかす🔗⭐🔉
驚 おどろかす🔗⭐🔉
【驚】
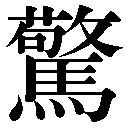 22画 馬部 [常用漢字]
区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1
《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く
《音読み》 キョウ(キャウ)
22画 馬部 [常用漢字]
区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1
《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く
《音読み》 キョウ(キャウ) /ケイ
/ケイ 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)
《名付け》 とし
《意味》
ng〉
《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)
《名付け》 とし
《意味》
 {動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕
{動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕
 {名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」
{名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」
 {動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕
{動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕
 {名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。
《解字》
会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬
《単語家族》
敬
{名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。
《解字》
会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬
《単語家族》
敬 警(はっと用心する)
警(はっと用心する) 檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。
《類義》
駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。
《類義》
駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
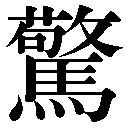 22画 馬部 [常用漢字]
区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1
《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く
《音読み》 キョウ(キャウ)
22画 馬部 [常用漢字]
区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1
《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く
《音読み》 キョウ(キャウ) /ケイ
/ケイ 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)
《名付け》 とし
《意味》
ng〉
《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)
《名付け》 とし
《意味》
 {動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕
{動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕
 {名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」
{名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」
 {動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕
{動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕
 {名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。
《解字》
会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬
《単語家族》
敬
{名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。
《解字》
会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬
《単語家族》
敬 警(はっと用心する)
警(はっと用心する) 檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。
《類義》
駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。
《類義》
駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「おど」で始まるの検索結果 1-13。
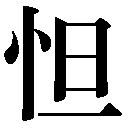 8画
8画  /タツ
/タツ 〉
《訓読み》 いたむ/おどろく
《意味》
{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」
《解字》
形声。「心+音符旦タン」。
《単語家族》
憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。
《熟語》
〉
《訓読み》 いたむ/おどろく
《意味》
{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」
《解字》
形声。「心+音符旦タン」。
《単語家族》
憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。
《熟語》
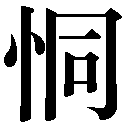 9画
9画  ドウ
ドウ ng〉/
ng〉/ トウ
トウ 16画 馬部
区点=8147 16進=714F シフトJIS=E96E
《音読み》 ガイ
16画 馬部
区点=8147 16進=714F シフトJIS=E96E
《音読み》 ガイ