複数辞典一括検索+![]()
![]()
おこ【△痴・×烏×滸・尾×籠】をこ🔗⭐🔉
おこ【△痴・×烏×滸・尾×籠】をこ
[名・形動]愚かなこと。ばかげていること。また、そのさま。「―の者」「退(すさ)れ卑きもの、魔道呼わり―なり」〈露伴・新浦島〉
お‐こう【△御講】🔗⭐🔉
お‐こう【△御講】
 寺院での読経、説経の集まり。
寺院での読経、説経の集まり。 宮中などで行われた法華八講(ほつけはつこう)などの法会。
宮中などで行われた法華八講(ほつけはつこう)などの法会。 仏教各宗で、開祖の忌日などに行う仏事。報恩講。御正忌(ごしようき)。
仏教各宗で、開祖の忌日などに行う仏事。報恩講。御正忌(ごしようき)。
 寺院での読経、説経の集まり。
寺院での読経、説経の集まり。 宮中などで行われた法華八講(ほつけはつこう)などの法会。
宮中などで行われた法華八講(ほつけはつこう)などの法会。 仏教各宗で、開祖の忌日などに行う仏事。報恩講。御正忌(ごしようき)。
仏教各宗で、開祖の忌日などに行う仏事。報恩講。御正忌(ごしようき)。
お‐こう【汚行】ヲカウ🔗⭐🔉
お‐こう【汚行】ヲカウ
道徳に外れた不名誉な行い。
お‐こうこう【△御香香】‐カウカウ🔗⭐🔉
お‐こうこう【△御香香】‐カウカウ
「香香」の丁寧な言い方。漬物。香のもの。おこうこ。
おこう‐びより【△御講日‐和】🔗⭐🔉
おこう‐びより【△御講日‐和】
報恩講の行われる一一月の末ごろは好天気が続くこと。御講なぎ。《季 冬》
おこ‐え【△痴絵・×烏×滸絵】をこヱ🔗⭐🔉
おこ‐え【△痴絵・×烏×滸絵】をこヱ
滑稽(こつけい)あるいは風刺を目的とした絵。戯画。
おこえ‐がかり【△御声掛(か)り】おこゑ‐🔗⭐🔉
おこえ‐がかり【△御声掛(か)り】おこゑ‐
「声掛かり」に同じ。「社長の―で抜擢(ばつてき)する」
おこ‐がまし・い【△痴がましい・×烏×滸がましい】をこ‐🔗⭐🔉
おこ‐がまし・い【△痴がましい・×烏×滸がましい】をこ‐
[形] をこがま・し[シク]
をこがま・し[シク] 身の程をわきまえない。差し出がましい。なまいきだ。「先輩をさしおいて―・いのですが…」
身の程をわきまえない。差し出がましい。なまいきだ。「先輩をさしおいて―・いのですが…」 いかにもばかばかしい。ばかげている。「世俗のそらごとを、ねんごろに信じたるも―・しく」〈徒然・七三〉
[派生]おこがましげ[形動]おこがましさ[名]
いかにもばかばかしい。ばかげている。「世俗のそらごとを、ねんごろに信じたるも―・しく」〈徒然・七三〉
[派生]おこがましげ[形動]おこがましさ[名]
 をこがま・し[シク]
をこがま・し[シク] 身の程をわきまえない。差し出がましい。なまいきだ。「先輩をさしおいて―・いのですが…」
身の程をわきまえない。差し出がましい。なまいきだ。「先輩をさしおいて―・いのですが…」 いかにもばかばかしい。ばかげている。「世俗のそらごとを、ねんごろに信じたるも―・しく」〈徒然・七三〉
[派生]おこがましげ[形動]おこがましさ[名]
いかにもばかばかしい。ばかげている。「世俗のそらごとを、ねんごろに信じたるも―・しく」〈徒然・七三〉
[派生]おこがましげ[形動]おこがましさ[名]
おこ‐が・る【△痴がる】をこ‐🔗⭐🔉
おこ‐が・る【△痴がる】をこ‐
[動ラ四]ばからしいと思う。ばかにする。「この聞く男ども、―・りあざけりて」〈宇治拾遺・二〉
お‐こげ【△御焦げ】🔗⭐🔉
お‐こげ【△御焦げ】
炊いた釜(かま)の底に焦げついた飯。こげめし。
おこさこ【右近左近】🔗⭐🔉
おこさこ【右近左近】
狂言「内沙汰(うちざた)」の、大蔵流での名称。
おこ‐さま【△御子様】🔗⭐🔉
おこ‐さま【△御子様】
 相手を敬ってその子供をいう語。「―はおいくつですか」
相手を敬ってその子供をいう語。「―はおいくつですか」 子供。「―用品」
子供。「―用品」
 相手を敬ってその子供をいう語。「―はおいくつですか」
相手を敬ってその子供をいう語。「―はおいくつですか」 子供。「―用品」
子供。「―用品」
おこさま‐ランチ【△御子様ランチ】🔗⭐🔉
おこさま‐ランチ【△御子様ランチ】
子供の好む食べ物が一皿に盛り付けられた定食。
おこし【起(こ)し】🔗⭐🔉
おこし【起(こ)し】
 起こすこと。
起こすこと。 田畑を耕すこと。
田畑を耕すこと。 花札で、めくり札を開くこと。また、その札。
花札で、めくり札を開くこと。また、その札。
 起こすこと。
起こすこと。 田畑を耕すこと。
田畑を耕すこと。 花札で、めくり札を開くこと。また、その札。
花札で、めくり札を開くこと。また、その札。
おこし【 =
= ・興】🔗⭐🔉
・興】🔗⭐🔉
おこし【 =
= ・興】
米・粟(あわ)などで作ったおこし種を水飴(みずあめ)と砂糖で固めた菓子。大豆・ピーナッツなどをまぜることもある。
・興】
米・粟(あわ)などで作ったおこし種を水飴(みずあめ)と砂糖で固めた菓子。大豆・ピーナッツなどをまぜることもある。
 =
= ・興】
米・粟(あわ)などで作ったおこし種を水飴(みずあめ)と砂糖で固めた菓子。大豆・ピーナッツなどをまぜることもある。
・興】
米・粟(あわ)などで作ったおこし種を水飴(みずあめ)と砂糖で固めた菓子。大豆・ピーナッツなどをまぜることもある。
お‐こし【△御越し】🔗⭐🔉
お‐こし【△御越し】
「行くこと」「来ること」の意の尊敬語。「―を願う」
お‐こし【△御腰】🔗⭐🔉
お‐こし【△御腰】
 「腰」をいう尊敬語。
「腰」をいう尊敬語。 「腰巻き」の女性語。
「腰巻き」の女性語。
 「腰」をいう尊敬語。
「腰」をいう尊敬語。 「腰巻き」の女性語。
「腰巻き」の女性語。
おこし‐え【起(こ)し絵】‐ヱ🔗⭐🔉
おこし‐え【起(こ)し絵】‐ヱ
建物・樹木・人物などを切り抜いて枠の中に立てると、風景・舞台などが立体的に再現されるようになっている絵。茶室の絵図面などに用いられたが、もともとは子供のおもちゃ。組立灯籠(くみたてとうろう)。立版古(たてばんこ)。《季 夏》
おこし‐がね【起(こ)し金】🔗⭐🔉
おこし‐がね【起(こ)し金】
鮑(あわび)などを岩からはがすために用いる鉄製の漁具。海女金(あまがね)。
おこし‐ごめ【 =
= 米】🔗⭐🔉
米】🔗⭐🔉
おこし‐ごめ【 =
= 米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
 =
= 米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
おこし‐ずみ【×熾し炭】🔗⭐🔉
おこし‐ずみ【×熾し炭】
赤くおこした炭火。
おこし‐だね【 =
= 種】🔗⭐🔉
種】🔗⭐🔉
おこし‐だね【 =
= 種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
 =
= 種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
おこし‐び【×熾し火】🔗⭐🔉
おこし‐び【×熾し火】
真っ赤におこった炭火。
おこじょ🔗⭐🔉
おこじょ

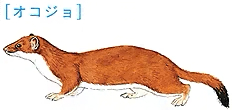 イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。
イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。

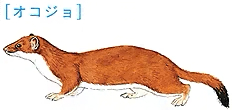 イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。
イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。
おこ・す【起(こ)す】🔗⭐🔉
おこ・す【起(こ)す】
[動サ五(四)] 横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」
横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」 目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」
目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」 今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」
今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」 新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
 自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」
自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」 平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」
平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」 静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」
静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」 ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」
ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」 表面に現れるようにする。
表面に現れるようにする。 土を掘り返す。「畑を―・す」
土を掘り返す。「畑を―・す」 へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」
へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」 伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。
伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。 隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」
隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」 速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
 横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」
横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」 目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」
目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」 今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」
今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」 新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
 自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」
自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」 平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」
平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」 静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」
静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」 ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」
ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」 表面に現れるようにする。
表面に現れるようにする。 土を掘り返す。「畑を―・す」
土を掘り返す。「畑を―・す」 へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」
へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」 伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。
伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。 隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」
隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」 速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
おこ・す【×熾す】🔗⭐🔉
おこ・す【×熾す】
[動サ五(四)]《「起こす」と同語源》炭火などの勢いを盛んにする。また、炭などに火をつける。「火吹き竹で火を―・す」
[可能]おこせる
おこ・す【興す】🔗⭐🔉
おこ・す【興す】
[動サ五(四)]《「起こす」と同語源》 ひっそりしていたものを目立つ状態にする。衰えていたものを再び勢いづかせる。「家を―・す」「国を―・す」「弓道を―・す」
ひっそりしていたものを目立つ状態にする。衰えていたものを再び勢いづかせる。「家を―・す」「国を―・す」「弓道を―・す」 「起こす
「起こす 」に同じ。「俳句の革新運動を―・す」
」に同じ。「俳句の革新運動を―・す」 気力を充実させる。奮い立たせる。「君もしひて御心を―・して、心の内に仏を念じ給ひて」〈源・夕顔〉
気力を充実させる。奮い立たせる。「君もしひて御心を―・して、心の内に仏を念じ給ひて」〈源・夕顔〉 大挙して立ち上がらせる。「十八日辰(たつ)の一点に大衆(だいしゆ)を―・し」〈平家・四〉
[可能]おこせる
大挙して立ち上がらせる。「十八日辰(たつ)の一点に大衆(だいしゆ)を―・し」〈平家・四〉
[可能]おこせる
 ひっそりしていたものを目立つ状態にする。衰えていたものを再び勢いづかせる。「家を―・す」「国を―・す」「弓道を―・す」
ひっそりしていたものを目立つ状態にする。衰えていたものを再び勢いづかせる。「家を―・す」「国を―・す」「弓道を―・す」 「起こす
「起こす 」に同じ。「俳句の革新運動を―・す」
」に同じ。「俳句の革新運動を―・す」 気力を充実させる。奮い立たせる。「君もしひて御心を―・して、心の内に仏を念じ給ひて」〈源・夕顔〉
気力を充実させる。奮い立たせる。「君もしひて御心を―・して、心の内に仏を念じ給ひて」〈源・夕顔〉 大挙して立ち上がらせる。「十八日辰(たつ)の一点に大衆(だいしゆ)を―・し」〈平家・四〉
[可能]おこせる
大挙して立ち上がらせる。「十八日辰(たつ)の一点に大衆(だいしゆ)を―・し」〈平家・四〉
[可能]おこせる
おこ・す【△遣す・△致す】🔗⭐🔉
おこ・す【△遣す・△致す】
 [動サ下二]
[動サ下二] よこす。届けてくる。「講師、もの、酒―・せたり」〈土佐〉
よこす。届けてくる。「講師、もの、酒―・せたり」〈土佐〉 (動詞の連用形に付いて)その動作が自分の方へ及ぶことを表す。こちらへ…する。…してくる。「空合はせ(=夢判断)にあらず、いひ―・せたる僧の疑はしきなり」〈かげろふ・下〉
(動詞の連用形に付いて)その動作が自分の方へ及ぶことを表す。こちらへ…する。…してくる。「空合はせ(=夢判断)にあらず、いひ―・せたる僧の疑はしきなり」〈かげろふ・下〉 [動サ四]《
[動サ四]《 の四段活用化》
の四段活用化》
 に同じ。「極道めが―・しをらぬわい」〈滑・浮世床・初〉
に同じ。「極道めが―・しをらぬわい」〈滑・浮世床・初〉
 [動サ下二]
[動サ下二] よこす。届けてくる。「講師、もの、酒―・せたり」〈土佐〉
よこす。届けてくる。「講師、もの、酒―・せたり」〈土佐〉 (動詞の連用形に付いて)その動作が自分の方へ及ぶことを表す。こちらへ…する。…してくる。「空合はせ(=夢判断)にあらず、いひ―・せたる僧の疑はしきなり」〈かげろふ・下〉
(動詞の連用形に付いて)その動作が自分の方へ及ぶことを表す。こちらへ…する。…してくる。「空合はせ(=夢判断)にあらず、いひ―・せたる僧の疑はしきなり」〈かげろふ・下〉 [動サ四]《
[動サ四]《 の四段活用化》
の四段活用化》
 に同じ。「極道めが―・しをらぬわい」〈滑・浮世床・初〉
に同じ。「極道めが―・しをらぬわい」〈滑・浮世床・初〉
おこぜ【× ・虎=魚】をこぜ🔗⭐🔉
・虎=魚】をこぜ🔗⭐🔉
おこぜ【× ・虎=魚】をこぜ
オニオコゼの別名。また、ハオコゼ・ダルマオコゼなどを含めていうこともあり、一般に頭は凹凸が激しく、背びれのとげが強大で、奇異な姿をしている。《季 夏》
・虎=魚】をこぜ
オニオコゼの別名。また、ハオコゼ・ダルマオコゼなどを含めていうこともあり、一般に頭は凹凸が激しく、背びれのとげが強大で、奇異な姿をしている。《季 夏》
 ・虎=魚】をこぜ
オニオコゼの別名。また、ハオコゼ・ダルマオコゼなどを含めていうこともあり、一般に頭は凹凸が激しく、背びれのとげが強大で、奇異な姿をしている。《季 夏》
・虎=魚】をこぜ
オニオコゼの別名。また、ハオコゼ・ダルマオコゼなどを含めていうこともあり、一般に頭は凹凸が激しく、背びれのとげが強大で、奇異な姿をしている。《季 夏》
おこそ‐ずきん【△御△高祖頭×巾】‐ヅキン🔗⭐🔉
おこそ‐ずきん【△御△高祖頭×巾】‐ヅキン
《日蓮上人の像の頭巾に似るところから》縮緬(ちりめん)などの四角い布にひもをつけ、目だけを出して頭・顔を包む婦人の防寒用頭巾。袖頭巾(そでずきん)。《季 冬》
お‐こた🔗⭐🔉
お‐こた
「炬燵(こたつ)」を丁寧にいう女性語。
おこたり【怠り】🔗⭐🔉
おこたり【怠り】
 なまけること。怠慢。「―なく励む」
なまけること。怠慢。「―なく励む」 怠慢から生じる過失。手落ち。「わが―にて流され給ふにしもあらず」〈大鏡・道隆〉
怠慢から生じる過失。手落ち。「わが―にて流され給ふにしもあらず」〈大鏡・道隆〉 過失をわびること。謝罪。「泣く泣く―を言へど」〈堤・はいずみ〉
過失をわびること。謝罪。「泣く泣く―を言へど」〈堤・はいずみ〉
 なまけること。怠慢。「―なく励む」
なまけること。怠慢。「―なく励む」 怠慢から生じる過失。手落ち。「わが―にて流され給ふにしもあらず」〈大鏡・道隆〉
怠慢から生じる過失。手落ち。「わが―にて流され給ふにしもあらず」〈大鏡・道隆〉 過失をわびること。謝罪。「泣く泣く―を言へど」〈堤・はいずみ〉
過失をわびること。謝罪。「泣く泣く―を言へど」〈堤・はいずみ〉
おこたり‐ぶみ【怠り文】🔗⭐🔉
おこたり‐ぶみ【怠り文】
謝罪の手紙。わび状。怠状(たいじよう)。「―を書きてたてまつりてん」〈今昔・二八・三六〉
おこた・る【怠る】🔗⭐🔉
おこた・る【怠る】
[動ラ五(四)] すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。「学業を―・る」「注意を―・る」
すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。「学業を―・る」「注意を―・る」 病気がよくなる。快方に向かう。「発作が、夏が来ると共に、漸く―・り出したのを喜こんだ」〈芥川・忠義〉「読経、修法(ずほふ)などして、いささか―・りたるやうなれば」〈かげろふ・上〉
病気がよくなる。快方に向かう。「発作が、夏が来ると共に、漸く―・り出したのを喜こんだ」〈芥川・忠義〉「読経、修法(ずほふ)などして、いささか―・りたるやうなれば」〈かげろふ・上〉 過ちを犯す。「みづから―・ると思ひ給ふること侍らねど」〈栄花・浦々の別れ〉
過ちを犯す。「みづから―・ると思ひ給ふること侍らねど」〈栄花・浦々の別れ〉 中断する。休む。「(水ガ)―・る間(ま)なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」〈徒然・一三七〉
[可能]おこたれる
中断する。休む。「(水ガ)―・る間(ま)なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」〈徒然・一三七〉
[可能]おこたれる
 すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。「学業を―・る」「注意を―・る」
すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。「学業を―・る」「注意を―・る」 病気がよくなる。快方に向かう。「発作が、夏が来ると共に、漸く―・り出したのを喜こんだ」〈芥川・忠義〉「読経、修法(ずほふ)などして、いささか―・りたるやうなれば」〈かげろふ・上〉
病気がよくなる。快方に向かう。「発作が、夏が来ると共に、漸く―・り出したのを喜こんだ」〈芥川・忠義〉「読経、修法(ずほふ)などして、いささか―・りたるやうなれば」〈かげろふ・上〉 過ちを犯す。「みづから―・ると思ひ給ふること侍らねど」〈栄花・浦々の別れ〉
過ちを犯す。「みづから―・ると思ひ給ふること侍らねど」〈栄花・浦々の別れ〉 中断する。休む。「(水ガ)―・る間(ま)なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」〈徒然・一三七〉
[可能]おこたれる
中断する。休む。「(水ガ)―・る間(ま)なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」〈徒然・一三七〉
[可能]おこたれる
おこ‐づ・く🔗⭐🔉
おこ‐づ・く
[動カ四] ひくひく動かす。ぴくつかす。「鼻のわたり―・きて、語りなす」〈源・帚木〉
ひくひく動かす。ぴくつかす。「鼻のわたり―・きて、語りなす」〈源・帚木〉 勢いづく。調子づく。「大石はづんで二つ三つ、どうどうどうと―・きて」〈浄・虎が磨〉
勢いづく。調子づく。「大石はづんで二つ三つ、どうどうどうと―・きて」〈浄・虎が磨〉 力む。「さは言へ、とちょっと―・く」〈伎・韓人漢文〉
力む。「さは言へ、とちょっと―・く」〈伎・韓人漢文〉 ずきずき痛む。「合戦のきず口―・き」〈浄・千本桜〉
ずきずき痛む。「合戦のきず口―・き」〈浄・千本桜〉
 ひくひく動かす。ぴくつかす。「鼻のわたり―・きて、語りなす」〈源・帚木〉
ひくひく動かす。ぴくつかす。「鼻のわたり―・きて、語りなす」〈源・帚木〉 勢いづく。調子づく。「大石はづんで二つ三つ、どうどうどうと―・きて」〈浄・虎が磨〉
勢いづく。調子づく。「大石はづんで二つ三つ、どうどうどうと―・きて」〈浄・虎が磨〉 力む。「さは言へ、とちょっと―・く」〈伎・韓人漢文〉
力む。「さは言へ、とちょっと―・く」〈伎・韓人漢文〉 ずきずき痛む。「合戦のきず口―・き」〈浄・千本桜〉
ずきずき痛む。「合戦のきず口―・き」〈浄・千本桜〉
おこ‐づ・く【△痴付く・×烏×滸付く】をこ‐🔗⭐🔉
おこ‐づ・く【△痴付く・×烏×滸付く】をこ‐
[動カ四] 愚かしく見える。「腰かがまりて―・きてなんありし」〈今昔・二八・二六〉
愚かしく見える。「腰かがまりて―・きてなんありし」〈今昔・二八・二六〉 ばかにする。「男どもこれを聞きて―・き嘲(あざけ)りて」〈今昔・一〇・三六〉
ばかにする。「男どもこれを聞きて―・き嘲(あざけ)りて」〈今昔・一〇・三六〉
 愚かしく見える。「腰かがまりて―・きてなんありし」〈今昔・二八・二六〉
愚かしく見える。「腰かがまりて―・きてなんありし」〈今昔・二八・二六〉 ばかにする。「男どもこれを聞きて―・き嘲(あざけ)りて」〈今昔・一〇・三六〉
ばかにする。「男どもこれを聞きて―・き嘲(あざけ)りて」〈今昔・一〇・三六〉
おこつ・る【△誘る】🔗⭐🔉
おこつ・る【△誘る】
[動ラ四]だまして人をさそう。また、機嫌をとる。「このふみの、けしきなく―・り取らむの心にて、あざむき申し給へば」〈源・夕霧〉◆仮名遣いは「おこつる」か「をこつる」か不明。
お‐こと【△御事】🔗⭐🔉
お‐こと【△御事】
 [名]「御事始め」または「御事納め」の略。
[名]「御事始め」または「御事納め」の略。 [代]二人称の人代名詞。あなた。親しみを込めていう語。主に中世・近世に用いた。「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」〈保元・中〉
[代]二人称の人代名詞。あなた。親しみを込めていう語。主に中世・近世に用いた。「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」〈保元・中〉
 [名]「御事始め」または「御事納め」の略。
[名]「御事始め」または「御事納め」の略。 [代]二人称の人代名詞。あなた。親しみを込めていう語。主に中世・近世に用いた。「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」〈保元・中〉
[代]二人称の人代名詞。あなた。親しみを込めていう語。主に中世・近世に用いた。「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」〈保元・中〉
おこと‐おさめ【△御事納め】‐をさめ🔗⭐🔉
おこと‐おさめ【△御事納め】‐をさめ
 江戸時代、陰暦二月八日に年神の棚を取り外したりして、正月の行事の終わりとしたこと。事納め。御事。
江戸時代、陰暦二月八日に年神の棚を取り外したりして、正月の行事の終わりとしたこと。事納め。御事。 東国で、陰暦一二月八日に行った、その年の農事の終わりの行事。この日は、「目一つ小僧」の魔物が来るので、目の多い籠(かご)を掲げ、追い払うもの。事納め。御事。→事八日(ことようか)
東国で、陰暦一二月八日に行った、その年の農事の終わりの行事。この日は、「目一つ小僧」の魔物が来るので、目の多い籠(かご)を掲げ、追い払うもの。事納め。御事。→事八日(ことようか)
 江戸時代、陰暦二月八日に年神の棚を取り外したりして、正月の行事の終わりとしたこと。事納め。御事。
江戸時代、陰暦二月八日に年神の棚を取り外したりして、正月の行事の終わりとしたこと。事納め。御事。 東国で、陰暦一二月八日に行った、その年の農事の終わりの行事。この日は、「目一つ小僧」の魔物が来るので、目の多い籠(かご)を掲げ、追い払うもの。事納め。御事。→事八日(ことようか)
東国で、陰暦一二月八日に行った、その年の農事の終わりの行事。この日は、「目一つ小僧」の魔物が来るので、目の多い籠(かご)を掲げ、追い払うもの。事納め。御事。→事八日(ことようか)
おこと‐じる【△御事汁】🔗⭐🔉
おこと‐じる【△御事汁】
御事始め・御事納めの日にこしらえた味噌汁。里芋・ごぼう・大根・小豆・人参・くわい・焼き栗・焼き豆腐などを入れたもの。御事煮。
おこと‐てん【×乎古△止点】をこと‐🔗⭐🔉
おこと‐てん【×乎古△止点】をこと‐
 をことてん
をことてん
 をことてん
をことてん
おこと‐はじめ【△御事始め】🔗⭐🔉
おこと‐はじめ【△御事始め】
 江戸時代、陰暦一二月八日にすす払いなどをして、正月の準備を始めたこと。事始め。御事。
江戸時代、陰暦一二月八日にすす払いなどをして、正月の準備を始めたこと。事始め。御事。 東国で、陰暦二月八日に行った、その年の農事の始めの行事。事始め。御事。→事八日(ことようか)
東国で、陰暦二月八日に行った、その年の農事の始めの行事。事始め。御事。→事八日(ことようか)
 江戸時代、陰暦一二月八日にすす払いなどをして、正月の準備を始めたこと。事始め。御事。
江戸時代、陰暦一二月八日にすす払いなどをして、正月の準備を始めたこと。事始め。御事。 東国で、陰暦二月八日に行った、その年の農事の始めの行事。事始め。御事。→事八日(ことようか)
東国で、陰暦二月八日に行った、その年の農事の始めの行事。事始め。御事。→事八日(ことようか)
おこない【行い(行ない)】おこなひ🔗⭐🔉
おこない【行い(行ない)】おこなひ
 物事をすること。振る舞い。行為。行動。「万が一君にどんな間違った―があったとしても」〈里見
物事をすること。振る舞い。行為。行動。「万が一君にどんな間違った―があったとしても」〈里見 ・多情仏心〉
・多情仏心〉 日常の生活態度。身持ち。品行。行状。「―を慎む」「平素の―が物を言う」
日常の生活態度。身持ち。品行。行状。「―を慎む」「平素の―が物を言う」 仏道の修行。また、勤行(ごんぎよう)。「阿闍梨(あざり)などにもなるべきものにこそあなれ。―の労は積もりて」〈源・若紫〉
仏道の修行。また、勤行(ごんぎよう)。「阿闍梨(あざり)などにもなるべきものにこそあなれ。―の労は積もりて」〈源・若紫〉 近畿地方を中心に、年頭または春先に行われる祈祷(きとう)行事。主に寺堂などで行われるが、元来は農事祈願の神事。
近畿地方を中心に、年頭または春先に行われる祈祷(きとう)行事。主に寺堂などで行われるが、元来は農事祈願の神事。
 物事をすること。振る舞い。行為。行動。「万が一君にどんな間違った―があったとしても」〈里見
物事をすること。振る舞い。行為。行動。「万が一君にどんな間違った―があったとしても」〈里見 ・多情仏心〉
・多情仏心〉 日常の生活態度。身持ち。品行。行状。「―を慎む」「平素の―が物を言う」
日常の生活態度。身持ち。品行。行状。「―を慎む」「平素の―が物を言う」 仏道の修行。また、勤行(ごんぎよう)。「阿闍梨(あざり)などにもなるべきものにこそあなれ。―の労は積もりて」〈源・若紫〉
仏道の修行。また、勤行(ごんぎよう)。「阿闍梨(あざり)などにもなるべきものにこそあなれ。―の労は積もりて」〈源・若紫〉 近畿地方を中心に、年頭または春先に行われる祈祷(きとう)行事。主に寺堂などで行われるが、元来は農事祈願の神事。
近畿地方を中心に、年頭または春先に行われる祈祷(きとう)行事。主に寺堂などで行われるが、元来は農事祈願の神事。
おこない‐がち【行ひ勝ち】おこなひ‐🔗⭐🔉
おこない‐がち【行ひ勝ち】おこなひ‐
[形動ナリ]仏道修行に専念するさま。「―に、口ひひらかし、数珠の音高きなど」〈紫式部日記〉
おこない‐すま・す【行い澄ます】おこなひ‐🔗⭐🔉
おこない‐すま・す【行い澄ます】おこなひ‐
[動サ五(四)] 自分だけが悟っているかのように振る舞う。もっともらしく、殊勝に振る舞う。気どる。「すっかり、―・した顔でいる」
自分だけが悟っているかのように振る舞う。もっともらしく、殊勝に振る舞う。気どる。「すっかり、―・した顔でいる」 ひたすら仏道を修行する。「尼が人の世に橋を隔て門を鎖して、斯る寒き雪の日をも―・しているのか」〈虚子・俳諧師〉
ひたすら仏道を修行する。「尼が人の世に橋を隔て門を鎖して、斯る寒き雪の日をも―・しているのか」〈虚子・俳諧師〉
 自分だけが悟っているかのように振る舞う。もっともらしく、殊勝に振る舞う。気どる。「すっかり、―・した顔でいる」
自分だけが悟っているかのように振る舞う。もっともらしく、殊勝に振る舞う。気どる。「すっかり、―・した顔でいる」 ひたすら仏道を修行する。「尼が人の世に橋を隔て門を鎖して、斯る寒き雪の日をも―・しているのか」〈虚子・俳諧師〉
ひたすら仏道を修行する。「尼が人の世に橋を隔て門を鎖して、斯る寒き雪の日をも―・しているのか」〈虚子・俳諧師〉
おこない‐びと【行ひ人】おこなひ‐🔗⭐🔉
おこない‐びと【行ひ人】おこなひ‐
《「行人(ぎようにん)」を訓読みにした語》仏道を修行する人。行者。修行僧。「若くより(鞍馬ニ)籠もれる―の」〈宇津保・忠こそ〉
おこな・う【行う(行なう)】おこなふ🔗⭐🔉
おこな・う【行う(行なう)】おこなふ
[動ワ五(ハ四)] 物事をする。なす。やる。実施する。「儀式を―・う」「合同演習を―・う」「四月五日に入学式が―・われる」
物事をする。なす。やる。実施する。「儀式を―・う」「合同演習を―・う」「四月五日に入学式が―・われる」 仏道を修行する。勤行(ごんぎよう)する。「いみじう額(ぬか)づき―・ひて寝たりしかば」〈更級〉
仏道を修行する。勤行(ごんぎよう)する。「いみじう額(ぬか)づき―・ひて寝たりしかば」〈更級〉 処理する。指図する。「世の人の飢ゑず、寒からぬやうに、世をば―・はまほしきなり」〈徒然・一四二〉
処理する。指図する。「世の人の飢ゑず、寒からぬやうに、世をば―・はまほしきなり」〈徒然・一四二〉 (「…におこなう」の形で)処する。付する。「死罪に―・はるべかりし人の」〈平家・二〉◆一定の手順を経て、または慣習・方式に従って何かをするのがもとの意。現在もその含みが残る。
[可能]おこなえる
[類語](
(「…におこなう」の形で)処する。付する。「死罪に―・はるべかりし人の」〈平家・二〉◆一定の手順を経て、または慣習・方式に従って何かをするのがもとの意。現在もその含みが残る。
[可能]おこなえる
[類語]( )する・なす・やる・営む・催す・執り行う・施(ほどこ)す・実施する・施行する・執行する・挙行する・敢行する・決行する・断行する・実行する・実践する・履行する・励行する
)する・なす・やる・営む・催す・執り行う・施(ほどこ)す・実施する・施行する・執行する・挙行する・敢行する・決行する・断行する・実行する・実践する・履行する・励行する
 物事をする。なす。やる。実施する。「儀式を―・う」「合同演習を―・う」「四月五日に入学式が―・われる」
物事をする。なす。やる。実施する。「儀式を―・う」「合同演習を―・う」「四月五日に入学式が―・われる」 仏道を修行する。勤行(ごんぎよう)する。「いみじう額(ぬか)づき―・ひて寝たりしかば」〈更級〉
仏道を修行する。勤行(ごんぎよう)する。「いみじう額(ぬか)づき―・ひて寝たりしかば」〈更級〉 処理する。指図する。「世の人の飢ゑず、寒からぬやうに、世をば―・はまほしきなり」〈徒然・一四二〉
処理する。指図する。「世の人の飢ゑず、寒からぬやうに、世をば―・はまほしきなり」〈徒然・一四二〉 (「…におこなう」の形で)処する。付する。「死罪に―・はるべかりし人の」〈平家・二〉◆一定の手順を経て、または慣習・方式に従って何かをするのがもとの意。現在もその含みが残る。
[可能]おこなえる
[類語](
(「…におこなう」の形で)処する。付する。「死罪に―・はるべかりし人の」〈平家・二〉◆一定の手順を経て、または慣習・方式に従って何かをするのがもとの意。現在もその含みが残る。
[可能]おこなえる
[類語]( )する・なす・やる・営む・催す・執り行う・施(ほどこ)す・実施する・施行する・執行する・挙行する・敢行する・決行する・断行する・実行する・実践する・履行する・励行する
)する・なす・やる・営む・催す・執り行う・施(ほどこ)す・実施する・施行する・執行する・挙行する・敢行する・決行する・断行する・実行する・実践する・履行する・励行する
おこなわ・れる【行われる(行なわれる)】おこなはれる🔗⭐🔉
おこなわ・れる【行われる(行なわれる)】おこなはれる
[動ラ下一] おこなは・る[ラ下二]《動詞「おこな(行)う」の未然形に受身の助動詞「れる」の付いたものから》世間に広く用いられる。通用する。また、流行する。「昔の風習が今も―・れている」
おこなは・る[ラ下二]《動詞「おこな(行)う」の未然形に受身の助動詞「れる」の付いたものから》世間に広く用いられる。通用する。また、流行する。「昔の風習が今も―・れている」
 おこなは・る[ラ下二]《動詞「おこな(行)う」の未然形に受身の助動詞「れる」の付いたものから》世間に広く用いられる。通用する。また、流行する。「昔の風習が今も―・れている」
おこなは・る[ラ下二]《動詞「おこな(行)う」の未然形に受身の助動詞「れる」の付いたものから》世間に広く用いられる。通用する。また、流行する。「昔の風習が今も―・れている」
お‐このみ【△御好み】🔗⭐🔉
お‐このみ【△御好み】
「好み」の尊敬語・丁寧語。
おこのみ‐しょくどう【△御好み食堂】‐シヨクダウ🔗⭐🔉
おこのみ‐しょくどう【△御好み食堂】‐シヨクダウ
和食・洋食・中国料理など献立を幅広くとりそろえて、客が好みのものを選べるようにした食堂。
おこのみ‐やき【△御好み焼(き)】🔗⭐🔉
おこのみ‐やき【△御好み焼(き)】
水と卵で溶いた小麦粉にイカ・牛肉・豚肉や刻みキャベツなどの野菜を好みによってまぜ、熱した鉄板の上で焼き、ソース・青海苔(あおのり)などで味つけをして食べるもの。
お‐こぼれ【△御△零れ】🔗⭐🔉
お‐こぼれ【△御△零れ】
「零(こぼ)れ 」に同じ。「―にあずかる」
」に同じ。「―にあずかる」
 」に同じ。「―にあずかる」
」に同じ。「―にあずかる」
おこま‐さいざ【お駒才三】🔗⭐🔉
おこま‐さいざ【お駒才三】
浄瑠璃「恋娘昔八丈(こいむすめむかしはちじよう)」などの男女の主人公。城木屋の娘お駒と髪結い才三郎。
おこ‐め・く【△痴めく・×烏×滸めく】をこ‐🔗⭐🔉
おこ‐め・く【△痴めく・×烏×滸めく】をこ‐
[動カ四]愚かなようすをする。ばかげている。ふざける。「昔物語などに、ことさらに―・きて作り出でたる物の譬に」〈源・総角〉
お‐こも【△御△薦】🔗⭐🔉
お‐こも【△御△薦】
《こもをかぶっていたところから》乞食(こじき)。ものもらい。
お‐こもり【△御×籠もり】🔗⭐🔉
お‐こもり【△御×籠もり】
[名]スル神仏に祈願するため一定の期間、神社・仏寺にこもること。参籠(さんろう)。
おこら‐ご【△御子△良子】🔗⭐🔉
おこら‐ご【△御子△良子】
伊勢神宮で、神饌(しんせん)を調える子良(こら)の館(たち)に仕える少女。おくらご。
おこり【怒り】🔗⭐🔉
おこり【怒り】
いかり。立腹。「他の人ならば一通りの―では有るまじと」〈一葉・たけくらべ〉
おこり【起(こ)り】🔗⭐🔉
おこり【起(こ)り】
物事の始まり。もと。起源。また、原因。「宗教の―」「争いの―」
おこり【×瘧】🔗⭐🔉
おこり【×瘧】
《隔日また周期的に起こる意》間欠的に発熱し、悪感(おかん)や震えを発する病気。主にマラリアの一種、三日熱をさした。えやみ。わらわやみ。瘧(ぎやく)。《季 夏》
おこり‐じょうご【怒り上戸】‐ジヤウゴ🔗⭐🔉
おこり‐じょうご【怒り上戸】‐ジヤウゴ
酒に酔うと怒りっぽくなる性質。また、そういう人。
おこりっ‐ぽ・い【怒りっぽい】🔗⭐🔉
おこりっ‐ぽ・い【怒りっぽい】
[形]ちょっとしたことに腹を立てやすい性質である。「疲れてくると―・くなる」
おこりん‐ぼう【怒りん坊】‐バウ🔗⭐🔉
おこりん‐ぼう【怒りん坊】‐バウ
少しのことでもすぐ怒る人。怒りっぽい人。気短な人。おこりんぼ。
おこ・る【怒る】🔗⭐🔉
おこ・る【怒る】
[動ラ五(四)]《「起こる」と同語源。感情が高まるところから》 不満・不快なことがあって、がまんできない気持ちを表す。腹を立てる。いかる。「真っ赤になって―・る」
不満・不快なことがあって、がまんできない気持ちを表す。腹を立てる。いかる。「真っ赤になって―・る」 よくない言動を強くとがめる。しかる。「へまをして―・られた」
[可能]おこれる
[用法]おこる・いかる――「父親は息子のうそにおこって(いかって)殴りつけた」のように、日常的な怒りが行為や表情となって外に現れる場合には、ほぼ共通して使える。◇抽象的ないかりの場合は「政界汚職にいかる」のように用い、「おこる」はふつう使わない。また、「いかる」は文章語的でもある。「いかった肩」◇類似の語「しかる」は、相手の言動やあやまちなどを強い調子で責めること。「父親はうそをついた息子をしかった」のように用いる。
よくない言動を強くとがめる。しかる。「へまをして―・られた」
[可能]おこれる
[用法]おこる・いかる――「父親は息子のうそにおこって(いかって)殴りつけた」のように、日常的な怒りが行為や表情となって外に現れる場合には、ほぼ共通して使える。◇抽象的ないかりの場合は「政界汚職にいかる」のように用い、「おこる」はふつう使わない。また、「いかる」は文章語的でもある。「いかった肩」◇類似の語「しかる」は、相手の言動やあやまちなどを強い調子で責めること。「父親はうそをついた息子をしかった」のように用いる。
 不満・不快なことがあって、がまんできない気持ちを表す。腹を立てる。いかる。「真っ赤になって―・る」
不満・不快なことがあって、がまんできない気持ちを表す。腹を立てる。いかる。「真っ赤になって―・る」 よくない言動を強くとがめる。しかる。「へまをして―・られた」
[可能]おこれる
[用法]おこる・いかる――「父親は息子のうそにおこって(いかって)殴りつけた」のように、日常的な怒りが行為や表情となって外に現れる場合には、ほぼ共通して使える。◇抽象的ないかりの場合は「政界汚職にいかる」のように用い、「おこる」はふつう使わない。また、「いかる」は文章語的でもある。「いかった肩」◇類似の語「しかる」は、相手の言動やあやまちなどを強い調子で責めること。「父親はうそをついた息子をしかった」のように用いる。
よくない言動を強くとがめる。しかる。「へまをして―・られた」
[可能]おこれる
[用法]おこる・いかる――「父親は息子のうそにおこって(いかって)殴りつけた」のように、日常的な怒りが行為や表情となって外に現れる場合には、ほぼ共通して使える。◇抽象的ないかりの場合は「政界汚職にいかる」のように用い、「おこる」はふつう使わない。また、「いかる」は文章語的でもある。「いかった肩」◇類似の語「しかる」は、相手の言動やあやまちなどを強い調子で責めること。「父親はうそをついた息子をしかった」のように用いる。
おこ・る【起(こ)る】🔗⭐🔉
おこ・る【起(こ)る】
[動ラ五(四)] 今までなかったものが新たに生じる。おきる。「静電気が―・る」「さざ波が―・る」
今までなかったものが新たに生じる。おきる。「静電気が―・る」「さざ波が―・る」
 自然が働きや動きを示す。おきる。「地震が―・る」「洪水が―・る」
自然が働きや動きを示す。おきる。「地震が―・る」「洪水が―・る」 平常と異なる状態や、好ましくない事態が生じる。おきる。「事件が―・る」「戦争が―・る」
平常と異なる状態や、好ましくない事態が生じる。おきる。「事件が―・る」「戦争が―・る」 ある感情・欲望が生じる。また、からだの働きがある状態を示す。おきる。「疑いが―・る」「仏ごころが―・る」「発作が―・る」
ある感情・欲望が生じる。また、からだの働きがある状態を示す。おきる。「疑いが―・る」「仏ごころが―・る」「発作が―・る」 大ぜいの人が出てくる。大挙する。「大衆(だいしゆ)―・って西坂本より皆おっかへす」〈平家・一〉
[類語](
大ぜいの人が出てくる。大挙する。「大衆(だいしゆ)―・って西坂本より皆おっかへす」〈平家・一〉
[類語](
 )起きる・生ずる・生まれる・兆(きざ)す・発する・生起する・発生する/(
)起きる・生ずる・生まれる・兆(きざ)す・発する・生起する・発生する/(
 )起きる・持ち上がる・出来(しゆつたい)する・勃発(ぼつぱつ)する・突発する・偶発する
)起きる・持ち上がる・出来(しゆつたい)する・勃発(ぼつぱつ)する・突発する・偶発する
 今までなかったものが新たに生じる。おきる。「静電気が―・る」「さざ波が―・る」
今までなかったものが新たに生じる。おきる。「静電気が―・る」「さざ波が―・る」
 自然が働きや動きを示す。おきる。「地震が―・る」「洪水が―・る」
自然が働きや動きを示す。おきる。「地震が―・る」「洪水が―・る」 平常と異なる状態や、好ましくない事態が生じる。おきる。「事件が―・る」「戦争が―・る」
平常と異なる状態や、好ましくない事態が生じる。おきる。「事件が―・る」「戦争が―・る」 ある感情・欲望が生じる。また、からだの働きがある状態を示す。おきる。「疑いが―・る」「仏ごころが―・る」「発作が―・る」
ある感情・欲望が生じる。また、からだの働きがある状態を示す。おきる。「疑いが―・る」「仏ごころが―・る」「発作が―・る」 大ぜいの人が出てくる。大挙する。「大衆(だいしゆ)―・って西坂本より皆おっかへす」〈平家・一〉
[類語](
大ぜいの人が出てくる。大挙する。「大衆(だいしゆ)―・って西坂本より皆おっかへす」〈平家・一〉
[類語](
 )起きる・生ずる・生まれる・兆(きざ)す・発する・生起する・発生する/(
)起きる・生ずる・生まれる・兆(きざ)す・発する・生起する・発生する/(
 )起きる・持ち上がる・出来(しゆつたい)する・勃発(ぼつぱつ)する・突発する・偶発する
)起きる・持ち上がる・出来(しゆつたい)する・勃発(ぼつぱつ)する・突発する・偶発する
おこ・る【×熾る】🔗⭐🔉
おこ・る【×熾る】
[動ラ五(四)]《「起こる」と同語源》火が炭に燃え移って、火勢が強くなる。また、炭に火がつく。おきる。「火鉢の炭火が―・る」
おこ・る【興る】🔗⭐🔉
おこ・る【興る】
[動ラ五(四)]《「起こる」と同語源》新しいものが生じ、勢いが盛んになる。また、ひっそりしていたものが目立つ状態になる。「新分野の学問が―・る」「志気が―・る」「国が―・る」
おころり‐よ🔗⭐🔉
おころり‐よ
〔連語〕子供を寝かしつけるときにいう語。おねんねしなさい。「ねんねんよ―」
お‐こわ【△御△強】‐こは🔗⭐🔉
お‐こわ【△御△強】‐こは
 《「こわめし」をいう女房詞から》赤飯(せきはん)。
《「こわめし」をいう女房詞から》赤飯(せきはん)。 人をだますこと。特に、「つつもたせ」にいうことが多い。「それはてっきり悪者の兄めが衒(かた)りの―であらふ」〈浄・前太平記〉
人をだますこと。特に、「つつもたせ」にいうことが多い。「それはてっきり悪者の兄めが衒(かた)りの―であらふ」〈浄・前太平記〉
 《「こわめし」をいう女房詞から》赤飯(せきはん)。
《「こわめし」をいう女房詞から》赤飯(せきはん)。 人をだますこと。特に、「つつもたせ」にいうことが多い。「それはてっきり悪者の兄めが衒(かた)りの―であらふ」〈浄・前太平記〉
人をだますこと。特に、「つつもたせ」にいうことが多い。「それはてっきり悪者の兄めが衒(かた)りの―であらふ」〈浄・前太平記〉
オコンナー【Feargus O'Connor】🔗⭐🔉
オコンナー【Feargus O'Connor】
[一七九四〜一八五五]英国のチャーチスト運動の指導者。アイルランド出身で、左派の実力行動派を指導して暴力革命を主張した。
オコンネル【Daniel O'Connell】🔗⭐🔉
オコンネル【Daniel O'Connell】
[一七七五〜一八四七]アイルランド解放運動の指導者。英国の支配に反対し、カトリック教徒の被選挙権獲得運動、アイルランドの分離独立運動を進めた。
衣🔗⭐🔉
衣
 [音]イ
エ
[訓]ころも
きぬ
き‐る
よ‐る
おこな‐う
[部首]衣
[総画数]6
[コード]区点 1665
JIS 3061
S‐JIS 88DF
[分類]常用漢字
[難読語]
→あか‐はとり【明衣】
→いだし‐ぎぬ【出衣】
→いほ‐かく【衣鉢閣】
→うえ‐の‐おんぞ【表御衣・上御衣】
→うえ‐の‐きぬ【表衣・上衣】
→うち‐ごろも【裏衣】
→えい【
[音]イ
エ
[訓]ころも
きぬ
き‐る
よ‐る
おこな‐う
[部首]衣
[総画数]6
[コード]区点 1665
JIS 3061
S‐JIS 88DF
[分類]常用漢字
[難読語]
→あか‐はとり【明衣】
→いだし‐ぎぬ【出衣】
→いほ‐かく【衣鉢閣】
→うえ‐の‐おんぞ【表御衣・上御衣】
→うえ‐の‐きぬ【表衣・上衣】
→うち‐ごろも【裏衣】
→えい【 衣・
衣・ 被】
→えい‐こう【
被】
→えい‐こう【 衣香・
衣香・ 被香】
→え‐こう【衣桁】
→え‐な【胞衣】
→え‐はつ【衣鉢】
→えび【
被香】
→え‐こう【衣桁】
→え‐な【胞衣】
→え‐はつ【衣鉢】
→えび【 衣・
衣・ 被】
→え‐もん【衣紋・衣文】
→おおん‐ぞ【御衣】
→おそ‐き【襲着・襲衣】
→おん‐ぞ【御衣】
→かき‐そ【柿衣・柿麻】
→かずき【被・被衣】
→かち‐え【褐衣】
→かつぎ【被・被衣】
→かみ‐こ【紙子・紙衣】
→かり‐ぎぬ【狩衣】
→きさらぎ【如月・更衣・衣更着】
→きぬ‐かずき【衣被】
→きぬ‐ぎぬ【衣衣・後朝】
→きょう‐え【経衣】
→くぬえ‐こう【薫衣香】
→くのえ‐こう【薫衣香・薫香】
→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】
→くろ‐ご【黒衣・黒子】
→け‐ごろも【褻衣】
→ころもがえ【更衣】
→さ‐ごろも【狭衣】
→さん‐ね【三衣】
→し‐い【緇衣】
→し‐え【緇衣】
→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】
→シャツ【shirt】
→じゅ‐え【受衣】
→しゅく‐え【宿衣】
→じゅん‐い【鶉衣】
→せつ‐い【褻衣】
→そとおり‐ひめ【衣通姫】
→だし‐ぎぬ【出衣】
→とう‐い【擣衣・搗衣】
→どう‐ぎ【胴着・胴衣】
→なおし【直衣】
→のう‐え【衲衣・納衣】
→のうし【直衣】
→のみ【衣
被】
→え‐もん【衣紋・衣文】
→おおん‐ぞ【御衣】
→おそ‐き【襲着・襲衣】
→おん‐ぞ【御衣】
→かき‐そ【柿衣・柿麻】
→かずき【被・被衣】
→かち‐え【褐衣】
→かつぎ【被・被衣】
→かみ‐こ【紙子・紙衣】
→かり‐ぎぬ【狩衣】
→きさらぎ【如月・更衣・衣更着】
→きぬ‐かずき【衣被】
→きぬ‐ぎぬ【衣衣・後朝】
→きょう‐え【経衣】
→くぬえ‐こう【薫衣香】
→くのえ‐こう【薫衣香・薫香】
→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】
→くろ‐ご【黒衣・黒子】
→け‐ごろも【褻衣】
→ころもがえ【更衣】
→さ‐ごろも【狭衣】
→さん‐ね【三衣】
→し‐い【緇衣】
→し‐え【緇衣】
→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】
→シャツ【shirt】
→じゅ‐え【受衣】
→しゅく‐え【宿衣】
→じゅん‐い【鶉衣】
→せつ‐い【褻衣】
→そとおり‐ひめ【衣通姫】
→だし‐ぎぬ【出衣】
→とう‐い【擣衣・搗衣】
→どう‐ぎ【胴着・胴衣】
→なおし【直衣】
→のう‐え【衲衣・納衣】
→のうし【直衣】
→のみ【衣 ・船
・船 ・
・ ・
・ 】
→はですがたおんなまいぎぬ【艶容女舞衣】
→ひいな‐ぎぬ【雛衣】
→ひこばえ【比古婆衣】
→ふんぞう‐え【糞掃衣】
→ほ‐い【布衣】
→ほう‐い【布衣】
→ほう‐え【法衣】
→ほう‐え【胞衣】
→ほろ【幌・母衣】
→み‐けし【御衣】
→み‐そ【御衣】
→ゆ‐かた【浴衣】
→ゆ‐こう【衣桁】
→らん‐い【襤衣】
】
→はですがたおんなまいぎぬ【艶容女舞衣】
→ひいな‐ぎぬ【雛衣】
→ひこばえ【比古婆衣】
→ふんぞう‐え【糞掃衣】
→ほ‐い【布衣】
→ほう‐い【布衣】
→ほう‐え【法衣】
→ほう‐え【胞衣】
→ほろ【幌・母衣】
→み‐けし【御衣】
→み‐そ【御衣】
→ゆ‐かた【浴衣】
→ゆ‐こう【衣桁】
→らん‐い【襤衣】
 [音]イ
エ
[訓]ころも
きぬ
き‐る
よ‐る
おこな‐う
[部首]衣
[総画数]6
[コード]区点 1665
JIS 3061
S‐JIS 88DF
[分類]常用漢字
[難読語]
→あか‐はとり【明衣】
→いだし‐ぎぬ【出衣】
→いほ‐かく【衣鉢閣】
→うえ‐の‐おんぞ【表御衣・上御衣】
→うえ‐の‐きぬ【表衣・上衣】
→うち‐ごろも【裏衣】
→えい【
[音]イ
エ
[訓]ころも
きぬ
き‐る
よ‐る
おこな‐う
[部首]衣
[総画数]6
[コード]区点 1665
JIS 3061
S‐JIS 88DF
[分類]常用漢字
[難読語]
→あか‐はとり【明衣】
→いだし‐ぎぬ【出衣】
→いほ‐かく【衣鉢閣】
→うえ‐の‐おんぞ【表御衣・上御衣】
→うえ‐の‐きぬ【表衣・上衣】
→うち‐ごろも【裏衣】
→えい【 衣・
衣・ 被】
→えい‐こう【
被】
→えい‐こう【 衣香・
衣香・ 被香】
→え‐こう【衣桁】
→え‐な【胞衣】
→え‐はつ【衣鉢】
→えび【
被香】
→え‐こう【衣桁】
→え‐な【胞衣】
→え‐はつ【衣鉢】
→えび【 衣・
衣・ 被】
→え‐もん【衣紋・衣文】
→おおん‐ぞ【御衣】
→おそ‐き【襲着・襲衣】
→おん‐ぞ【御衣】
→かき‐そ【柿衣・柿麻】
→かずき【被・被衣】
→かち‐え【褐衣】
→かつぎ【被・被衣】
→かみ‐こ【紙子・紙衣】
→かり‐ぎぬ【狩衣】
→きさらぎ【如月・更衣・衣更着】
→きぬ‐かずき【衣被】
→きぬ‐ぎぬ【衣衣・後朝】
→きょう‐え【経衣】
→くぬえ‐こう【薫衣香】
→くのえ‐こう【薫衣香・薫香】
→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】
→くろ‐ご【黒衣・黒子】
→け‐ごろも【褻衣】
→ころもがえ【更衣】
→さ‐ごろも【狭衣】
→さん‐ね【三衣】
→し‐い【緇衣】
→し‐え【緇衣】
→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】
→シャツ【shirt】
→じゅ‐え【受衣】
→しゅく‐え【宿衣】
→じゅん‐い【鶉衣】
→せつ‐い【褻衣】
→そとおり‐ひめ【衣通姫】
→だし‐ぎぬ【出衣】
→とう‐い【擣衣・搗衣】
→どう‐ぎ【胴着・胴衣】
→なおし【直衣】
→のう‐え【衲衣・納衣】
→のうし【直衣】
→のみ【衣
被】
→え‐もん【衣紋・衣文】
→おおん‐ぞ【御衣】
→おそ‐き【襲着・襲衣】
→おん‐ぞ【御衣】
→かき‐そ【柿衣・柿麻】
→かずき【被・被衣】
→かち‐え【褐衣】
→かつぎ【被・被衣】
→かみ‐こ【紙子・紙衣】
→かり‐ぎぬ【狩衣】
→きさらぎ【如月・更衣・衣更着】
→きぬ‐かずき【衣被】
→きぬ‐ぎぬ【衣衣・後朝】
→きょう‐え【経衣】
→くぬえ‐こう【薫衣香】
→くのえ‐こう【薫衣香・薫香】
→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】
→くろ‐ご【黒衣・黒子】
→け‐ごろも【褻衣】
→ころもがえ【更衣】
→さ‐ごろも【狭衣】
→さん‐ね【三衣】
→し‐い【緇衣】
→し‐え【緇衣】
→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】
→シャツ【shirt】
→じゅ‐え【受衣】
→しゅく‐え【宿衣】
→じゅん‐い【鶉衣】
→せつ‐い【褻衣】
→そとおり‐ひめ【衣通姫】
→だし‐ぎぬ【出衣】
→とう‐い【擣衣・搗衣】
→どう‐ぎ【胴着・胴衣】
→なおし【直衣】
→のう‐え【衲衣・納衣】
→のうし【直衣】
→のみ【衣 ・船
・船 ・
・ ・
・ 】
→はですがたおんなまいぎぬ【艶容女舞衣】
→ひいな‐ぎぬ【雛衣】
→ひこばえ【比古婆衣】
→ふんぞう‐え【糞掃衣】
→ほ‐い【布衣】
→ほう‐い【布衣】
→ほう‐え【法衣】
→ほう‐え【胞衣】
→ほろ【幌・母衣】
→み‐けし【御衣】
→み‐そ【御衣】
→ゆ‐かた【浴衣】
→ゆ‐こう【衣桁】
→らん‐い【襤衣】
】
→はですがたおんなまいぎぬ【艶容女舞衣】
→ひいな‐ぎぬ【雛衣】
→ひこばえ【比古婆衣】
→ふんぞう‐え【糞掃衣】
→ほ‐い【布衣】
→ほう‐い【布衣】
→ほう‐え【法衣】
→ほう‐え【胞衣】
→ほろ【幌・母衣】
→み‐けし【御衣】
→み‐そ【御衣】
→ゆ‐かた【浴衣】
→ゆ‐こう【衣桁】
→らん‐い【襤衣】
解🔗⭐🔉
解
 [音]カイ
ゲ
[訓]と‐く
と‐ける
と‐かす
ほど‐く
ほぐ‐す
わか‐る
ほつ‐れ
おこた‐る
めぐりあ‐う
[部首]角
[総画数]13
[コード]区点 1882
JIS 3272
S‐JIS 89F0
[分類]常用漢字
[難読語]
→え‐げ【慧解】
→かい‐い【解頤】
→かい‐らん【解纜】
→か‐げゆ【勘解由】
→ぎ‐げ【義解】
→げ‐あき【夏解・夏明き】
→げ‐かん【解官】
→げじんみっきょう【解深密経】
→けん‐げ【見解】
→こう‐かい【叩解】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しゅう‐げ【集解】
→ゆき‐げ【雪解・雪消】
→ろんごしっかい【論語集解】
→わくげ【和句解】
→わ‐げ【和解】
[音]カイ
ゲ
[訓]と‐く
と‐ける
と‐かす
ほど‐く
ほぐ‐す
わか‐る
ほつ‐れ
おこた‐る
めぐりあ‐う
[部首]角
[総画数]13
[コード]区点 1882
JIS 3272
S‐JIS 89F0
[分類]常用漢字
[難読語]
→え‐げ【慧解】
→かい‐い【解頤】
→かい‐らん【解纜】
→か‐げゆ【勘解由】
→ぎ‐げ【義解】
→げ‐あき【夏解・夏明き】
→げ‐かん【解官】
→げじんみっきょう【解深密経】
→けん‐げ【見解】
→こう‐かい【叩解】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しゅう‐げ【集解】
→ゆき‐げ【雪解・雪消】
→ろんごしっかい【論語集解】
→わくげ【和句解】
→わ‐げ【和解】
 [音]カイ
ゲ
[訓]と‐く
と‐ける
と‐かす
ほど‐く
ほぐ‐す
わか‐る
ほつ‐れ
おこた‐る
めぐりあ‐う
[部首]角
[総画数]13
[コード]区点 1882
JIS 3272
S‐JIS 89F0
[分類]常用漢字
[難読語]
→え‐げ【慧解】
→かい‐い【解頤】
→かい‐らん【解纜】
→か‐げゆ【勘解由】
→ぎ‐げ【義解】
→げ‐あき【夏解・夏明き】
→げ‐かん【解官】
→げじんみっきょう【解深密経】
→けん‐げ【見解】
→こう‐かい【叩解】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しゅう‐げ【集解】
→ゆき‐げ【雪解・雪消】
→ろんごしっかい【論語集解】
→わくげ【和句解】
→わ‐げ【和解】
[音]カイ
ゲ
[訓]と‐く
と‐ける
と‐かす
ほど‐く
ほぐ‐す
わか‐る
ほつ‐れ
おこた‐る
めぐりあ‐う
[部首]角
[総画数]13
[コード]区点 1882
JIS 3272
S‐JIS 89F0
[分類]常用漢字
[難読語]
→え‐げ【慧解】
→かい‐い【解頤】
→かい‐らん【解纜】
→か‐げゆ【勘解由】
→ぎ‐げ【義解】
→げ‐あき【夏解・夏明き】
→げ‐かん【解官】
→げじんみっきょう【解深密経】
→けん‐げ【見解】
→こう‐かい【叩解】
→こころのなぞとけたいろいと【心謎解色糸】
→しゅう‐げ【集解】
→ゆき‐げ【雪解・雪消】
→ろんごしっかい【論語集解】
→わくげ【和句解】
→わ‐げ【和解】
起🔗⭐🔉
興🔗⭐🔉
興
 [音]キョウ
コウ
[訓]おこ‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]臼
[総画数]16
[コード]区点 2229
JIS 363D
S‐JIS 8BBB
[分類]常用漢字
[難読語]
→おきつ【興津】
→がご‐じ【元興寺】
→がんごう‐じ【元興寺】
→こうけい【興京】
→こう‐こう【黄興】
→こうしょう‐じ【興正寺】
→こうしょう‐じ【興聖寺】
→シャオシンチュー【紹興酒】
→じゅ‐きょう【入興】
→しゅく‐こう【夙興】
→しゅっ‐こう【夙興】
[音]キョウ
コウ
[訓]おこ‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]臼
[総画数]16
[コード]区点 2229
JIS 363D
S‐JIS 8BBB
[分類]常用漢字
[難読語]
→おきつ【興津】
→がご‐じ【元興寺】
→がんごう‐じ【元興寺】
→こうけい【興京】
→こう‐こう【黄興】
→こうしょう‐じ【興正寺】
→こうしょう‐じ【興聖寺】
→シャオシンチュー【紹興酒】
→じゅ‐きょう【入興】
→しゅく‐こう【夙興】
→しゅっ‐こう【夙興】
 [音]キョウ
コウ
[訓]おこ‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]臼
[総画数]16
[コード]区点 2229
JIS 363D
S‐JIS 8BBB
[分類]常用漢字
[難読語]
→おきつ【興津】
→がご‐じ【元興寺】
→がんごう‐じ【元興寺】
→こうけい【興京】
→こう‐こう【黄興】
→こうしょう‐じ【興正寺】
→こうしょう‐じ【興聖寺】
→シャオシンチュー【紹興酒】
→じゅ‐きょう【入興】
→しゅく‐こう【夙興】
→しゅっ‐こう【夙興】
[音]キョウ
コウ
[訓]おこ‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]臼
[総画数]16
[コード]区点 2229
JIS 363D
S‐JIS 8BBB
[分類]常用漢字
[難読語]
→おきつ【興津】
→がご‐じ【元興寺】
→がんごう‐じ【元興寺】
→こうけい【興京】
→こう‐こう【黄興】
→こうしょう‐じ【興正寺】
→こうしょう‐じ【興聖寺】
→シャオシンチュー【紹興酒】
→じゅ‐きょう【入興】
→しゅく‐こう【夙興】
→しゅっ‐こう【夙興】
行🔗⭐🔉
行
 [音]コウ
ギョウ
アン
[訓]ゆ‐く
い‐く
めぐ‐る
ゆくゆく
さ‐る
や‐る
おこな‐う
の‐びる
みち
おこな‐い
くだり
[部首]行
[総画数]6
[コード]区点 2552
JIS 3954
S‐JIS 8D73
[分類]常用漢字
[難読語]
→あがた‐ありき【県歩行】
→あて‐おこない【充行・宛行】
→あて‐がい【宛てがい・宛行・充行】
→あん‐か【行火】
→あん‐ぎゃ【行脚】
→あん‐じゃ【行者】
→あん‐どう【行灯】
→あん‐どん【行灯】
→あん‐り【行履】
→いぎょう‐ほん【易行品】
→い‐ざ・る【躄る・膝行る】
→おさ‐むし【歩行虫・筬虫】
→かく‐ぎょう【角行】
→かち【徒・徒歩・歩・歩行】
→がち‐ぎょうじ【月行事・月行司】
→ぎょう‐け【行化】
→ぎょう‐ごう【行香】
→ぎょう‐そう【行装・行粧】
→きん‐ひん【経行】
→くばり‐ぶぎょう【賦奉行】
→け‐ぎょう【加行】
→こうし‐そうにく【行尸走肉】
→こう‐のう【行嚢】
→ごみ‐むし【塵芥虫・歩行虫】
→しゅ‐ぎょう【執行】
→じょう‐ごう【長行】
→す‐ぎょう【修行】
→たそや‐あんどん【誰哉行灯】
→にわ‐たずみ【潦・行潦】
→はばき【脛巾・行纏】
→はやり【流行り】
→はり‐ゆき【梁行】
→ひと‐くだり【一行】
→ひと‐つら【一連・一行】
→ふじ‐ごうり【藤行李】
→ふじ‐ごり【藤行李】
→ほか‐い【外居・行器】
→みくだり‐はん【三行半・三下り半】
→み‐ゆき【行幸・御幸】
→むか‐ばき【行縢・行騰】
→めし‐ごり【飯行李】
→やさすかり【八道行成】
→ゆき‐ひら【行平・雪平】
→ゆくはし【行橋】
[音]コウ
ギョウ
アン
[訓]ゆ‐く
い‐く
めぐ‐る
ゆくゆく
さ‐る
や‐る
おこな‐う
の‐びる
みち
おこな‐い
くだり
[部首]行
[総画数]6
[コード]区点 2552
JIS 3954
S‐JIS 8D73
[分類]常用漢字
[難読語]
→あがた‐ありき【県歩行】
→あて‐おこない【充行・宛行】
→あて‐がい【宛てがい・宛行・充行】
→あん‐か【行火】
→あん‐ぎゃ【行脚】
→あん‐じゃ【行者】
→あん‐どう【行灯】
→あん‐どん【行灯】
→あん‐り【行履】
→いぎょう‐ほん【易行品】
→い‐ざ・る【躄る・膝行る】
→おさ‐むし【歩行虫・筬虫】
→かく‐ぎょう【角行】
→かち【徒・徒歩・歩・歩行】
→がち‐ぎょうじ【月行事・月行司】
→ぎょう‐け【行化】
→ぎょう‐ごう【行香】
→ぎょう‐そう【行装・行粧】
→きん‐ひん【経行】
→くばり‐ぶぎょう【賦奉行】
→け‐ぎょう【加行】
→こうし‐そうにく【行尸走肉】
→こう‐のう【行嚢】
→ごみ‐むし【塵芥虫・歩行虫】
→しゅ‐ぎょう【執行】
→じょう‐ごう【長行】
→す‐ぎょう【修行】
→たそや‐あんどん【誰哉行灯】
→にわ‐たずみ【潦・行潦】
→はばき【脛巾・行纏】
→はやり【流行り】
→はり‐ゆき【梁行】
→ひと‐くだり【一行】
→ひと‐つら【一連・一行】
→ふじ‐ごうり【藤行李】
→ふじ‐ごり【藤行李】
→ほか‐い【外居・行器】
→みくだり‐はん【三行半・三下り半】
→み‐ゆき【行幸・御幸】
→むか‐ばき【行縢・行騰】
→めし‐ごり【飯行李】
→やさすかり【八道行成】
→ゆき‐ひら【行平・雪平】
→ゆくはし【行橋】
 [音]コウ
ギョウ
アン
[訓]ゆ‐く
い‐く
めぐ‐る
ゆくゆく
さ‐る
や‐る
おこな‐う
の‐びる
みち
おこな‐い
くだり
[部首]行
[総画数]6
[コード]区点 2552
JIS 3954
S‐JIS 8D73
[分類]常用漢字
[難読語]
→あがた‐ありき【県歩行】
→あて‐おこない【充行・宛行】
→あて‐がい【宛てがい・宛行・充行】
→あん‐か【行火】
→あん‐ぎゃ【行脚】
→あん‐じゃ【行者】
→あん‐どう【行灯】
→あん‐どん【行灯】
→あん‐り【行履】
→いぎょう‐ほん【易行品】
→い‐ざ・る【躄る・膝行る】
→おさ‐むし【歩行虫・筬虫】
→かく‐ぎょう【角行】
→かち【徒・徒歩・歩・歩行】
→がち‐ぎょうじ【月行事・月行司】
→ぎょう‐け【行化】
→ぎょう‐ごう【行香】
→ぎょう‐そう【行装・行粧】
→きん‐ひん【経行】
→くばり‐ぶぎょう【賦奉行】
→け‐ぎょう【加行】
→こうし‐そうにく【行尸走肉】
→こう‐のう【行嚢】
→ごみ‐むし【塵芥虫・歩行虫】
→しゅ‐ぎょう【執行】
→じょう‐ごう【長行】
→す‐ぎょう【修行】
→たそや‐あんどん【誰哉行灯】
→にわ‐たずみ【潦・行潦】
→はばき【脛巾・行纏】
→はやり【流行り】
→はり‐ゆき【梁行】
→ひと‐くだり【一行】
→ひと‐つら【一連・一行】
→ふじ‐ごうり【藤行李】
→ふじ‐ごり【藤行李】
→ほか‐い【外居・行器】
→みくだり‐はん【三行半・三下り半】
→み‐ゆき【行幸・御幸】
→むか‐ばき【行縢・行騰】
→めし‐ごり【飯行李】
→やさすかり【八道行成】
→ゆき‐ひら【行平・雪平】
→ゆくはし【行橋】
[音]コウ
ギョウ
アン
[訓]ゆ‐く
い‐く
めぐ‐る
ゆくゆく
さ‐る
や‐る
おこな‐う
の‐びる
みち
おこな‐い
くだり
[部首]行
[総画数]6
[コード]区点 2552
JIS 3954
S‐JIS 8D73
[分類]常用漢字
[難読語]
→あがた‐ありき【県歩行】
→あて‐おこない【充行・宛行】
→あて‐がい【宛てがい・宛行・充行】
→あん‐か【行火】
→あん‐ぎゃ【行脚】
→あん‐じゃ【行者】
→あん‐どう【行灯】
→あん‐どん【行灯】
→あん‐り【行履】
→いぎょう‐ほん【易行品】
→い‐ざ・る【躄る・膝行る】
→おさ‐むし【歩行虫・筬虫】
→かく‐ぎょう【角行】
→かち【徒・徒歩・歩・歩行】
→がち‐ぎょうじ【月行事・月行司】
→ぎょう‐け【行化】
→ぎょう‐ごう【行香】
→ぎょう‐そう【行装・行粧】
→きん‐ひん【経行】
→くばり‐ぶぎょう【賦奉行】
→け‐ぎょう【加行】
→こうし‐そうにく【行尸走肉】
→こう‐のう【行嚢】
→ごみ‐むし【塵芥虫・歩行虫】
→しゅ‐ぎょう【執行】
→じょう‐ごう【長行】
→す‐ぎょう【修行】
→たそや‐あんどん【誰哉行灯】
→にわ‐たずみ【潦・行潦】
→はばき【脛巾・行纏】
→はやり【流行り】
→はり‐ゆき【梁行】
→ひと‐くだり【一行】
→ひと‐つら【一連・一行】
→ふじ‐ごうり【藤行李】
→ふじ‐ごり【藤行李】
→ほか‐い【外居・行器】
→みくだり‐はん【三行半・三下り半】
→み‐ゆき【行幸・御幸】
→むか‐ばき【行縢・行騰】
→めし‐ごり【飯行李】
→やさすかり【八道行成】
→ゆき‐ひら【行平・雪平】
→ゆくはし【行橋】
作🔗⭐🔉
作
 [音]サク
サ
ソ
[訓]つく‐る
な‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]人
[総画数]7
[コード]区点 2678
JIS 3A6E
S‐JIS 8DEC
[分類]常用漢字
[難読語]
→け‐さ【化作】
→げ‐さく【戯作】
→さく‐しき【作職】
→さくなみ‐おんせん【作並温泉】
→しょあく‐まくさ【諸悪莫作】
→そも‐さん【作麼生・怎麼生・什麼生】
→つぐのい‐びと【償い人・客作児】
→つくも‐どころ【作物所】
→みまさか【美作】
→や‐はぎ【矢作・矢矧】
[音]サク
サ
ソ
[訓]つく‐る
な‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]人
[総画数]7
[コード]区点 2678
JIS 3A6E
S‐JIS 8DEC
[分類]常用漢字
[難読語]
→け‐さ【化作】
→げ‐さく【戯作】
→さく‐しき【作職】
→さくなみ‐おんせん【作並温泉】
→しょあく‐まくさ【諸悪莫作】
→そも‐さん【作麼生・怎麼生・什麼生】
→つぐのい‐びと【償い人・客作児】
→つくも‐どころ【作物所】
→みまさか【美作】
→や‐はぎ【矢作・矢矧】
 [音]サク
サ
ソ
[訓]つく‐る
な‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]人
[総画数]7
[コード]区点 2678
JIS 3A6E
S‐JIS 8DEC
[分類]常用漢字
[難読語]
→け‐さ【化作】
→げ‐さく【戯作】
→さく‐しき【作職】
→さくなみ‐おんせん【作並温泉】
→しょあく‐まくさ【諸悪莫作】
→そも‐さん【作麼生・怎麼生・什麼生】
→つぐのい‐びと【償い人・客作児】
→つくも‐どころ【作物所】
→みまさか【美作】
→や‐はぎ【矢作・矢矧】
[音]サク
サ
ソ
[訓]つく‐る
な‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]人
[総画数]7
[コード]区点 2678
JIS 3A6E
S‐JIS 8DEC
[分類]常用漢字
[難読語]
→け‐さ【化作】
→げ‐さく【戯作】
→さく‐しき【作職】
→さくなみ‐おんせん【作並温泉】
→しょあく‐まくさ【諸悪莫作】
→そも‐さん【作麼生・怎麼生・什麼生】
→つぐのい‐びと【償い人・客作児】
→つくも‐どころ【作物所】
→みまさか【美作】
→や‐はぎ【矢作・矢矧】
惰🔗⭐🔉
惰
[音]ダ
タ
[訓]おこた‐る
[部首]心
[総画数]12
[コード]区点 3438
JIS 4246
S‐JIS 91C4
[分類]常用漢字
[難読語]
→らん‐だ【懶惰・嬾惰】
怠🔗⭐🔉
怠
[音]タイ
[訓]おこた‐る
なま‐ける
あなど‐る
おこた‐り
[部首]心
[総画数]9
[コード]区点 3453
JIS 4255
S‐JIS 91D3
[分類]常用漢字
怒🔗⭐🔉
怒
[音]ド
ヌ
[訓]いか‐る
おこ‐る
はげ‐む
はげ‐しい
[部首]心
[総画数]9
[コード]区点 3760
JIS 455C
S‐JIS 937B
[分類]常用漢字
[難読語]
→きぬ‐がわ【鬼怒川】
→どっちょう‐ごえ【怒張声】
慢🔗⭐🔉
慢
[音]バン
マン
ベン
[訓]おこた‐る
おご‐る
あなど‐る
[部首]心
[総画数]14
[コード]区点 4393
JIS 4B7D
S‐JIS 969D
[分類]常用漢字
[難読語]
→マンマンデ【慢慢的】
做🔗⭐🔉
做
[音]サク
サ
ソ
[訓]つく‐る
な‐す
おこ‐る
た‐つ
[部首]人
[総画数]11
[コード]区点 4886
JIS 5076
S‐JIS 98F4
懈🔗⭐🔉
懈
[音]カイ
ケ
ゲ
[訓]おこた‐る
[部首]心
[総画数]16
[コード]区点 5672
JIS 5868
S‐JIS 9CE6
懶🔗⭐🔉
懶
[音]ラン
ライ
[訓]ものう‐い
おこた‐る
[部首]心
[総画数]19
[コード]区点 5681
JIS 5871
S‐JIS 9CEF
[難読語]
→なまけ‐ぐま【懶熊】
→なまけ‐もの【樹懶】
→らん‐だ【懶惰・嬾惰】
瘧🔗⭐🔉
瘧
[音]ギャク
[訓]おこり
[部首] [総画数]15
[コード]区点 6574
JIS 616A
S‐JIS E18A
[総画数]15
[コード]区点 6574
JIS 616A
S‐JIS E18A
 [総画数]15
[コード]区点 6574
JIS 616A
S‐JIS E18A
[総画数]15
[コード]区点 6574
JIS 616A
S‐JIS E18A
觧🔗⭐🔉
觧
[音]カイ
ゲ
[訓]と‐く
と‐ける
と‐かす
ほど‐く
ほぐ‐す
わか‐る
ほつ‐れ
おこた‐る
めぐりあ‐う
[部首]角
[総画数]13
[コード]区点 7527
JIS 6B3B
S‐JIS E65A
大辞泉に「おこ」で始まるの検索結果 1-87。