複数辞典一括検索+![]()
![]()
允 ゆるす🔗⭐🔉
【允】
 4画 儿部 [人名漢字]
区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2
《音読み》 イン
4画 儿部 [人名漢字]
区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2
《音読み》 イン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう
《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう
《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし
《意味》
 {形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕
{形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕
 {副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕
{副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕
 {動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」
〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。
《解字》
{動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」
〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。
《解字》
 会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。
《単語家族》
尹イン(調和をとる)
会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。
《単語家族》
尹イン(調和をとる) 均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 4画 儿部 [人名漢字]
区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2
《音読み》 イン
4画 儿部 [人名漢字]
区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2
《音読み》 イン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう
《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう
《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし
《意味》
 {形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕
{形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕
 {副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕
{副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕
 {動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」
〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。
《解字》
{動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」
〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。
《解字》
 会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。
《単語家族》
尹イン(調和をとる)
会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。
《単語家族》
尹イン(調和をとる) 均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
准 ゆるす🔗⭐🔉
【准】
 10画 冫部 [常用漢字]
区点=2958 16進=3D5A シフトJIS=8F79
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン
10画 冫部 [常用漢字]
区点=2958 16進=3D5A シフトJIS=8F79
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 なぞらえる(なぞらふ)/ゆるす
《名付け》 のり
《意味》
n〉
《訓読み》 なぞらえる(なぞらふ)/ゆるす
《名付け》 のり
《意味》
 {動・名}平らにならすこと。〈同義語〉→準。「標准(=標準)」
{動・名}平らにならすこと。〈同義語〉→準。「標准(=標準)」
 ジュンス{動}なぞらえる(ナゾラフ)。規準となる事がらに、比べあわせる。▽平均する意から、同等にそろえて扱う意となる。〈同義語〉→準。「准用(=準用)」
ジュンス{動}なぞらえる(ナゾラフ)。規準となる事がらに、比べあわせる。▽平均する意から、同等にそろえて扱う意となる。〈同義語〉→準。「准用(=準用)」
 {動}ゆるす。全体を見渡してバランスをとって認める。▽允イン(ゆるす)に近い。「准許」「批准(裁断を下してゆるす)」
{動}ゆるす。全体を見渡してバランスをとって認める。▽允イン(ゆるす)に近い。「准許」「批准(裁断を下してゆるす)」
 {動}〔俗〕…により。…によれば。▽中世以後の公文書用語。「准…部咨行シコウ(…部の通告によれば)」
《解字》
会意兼形声。準は「水+十(集めそろえる)+音符隹スイ(ずっしり、落ち着く)」の会意兼形声文字。水を落ち着けて水面を平らにそろえること。水準・平均の意を含む。准はその略字。▽淮ワイは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}〔俗〕…により。…によれば。▽中世以後の公文書用語。「准…部咨行シコウ(…部の通告によれば)」
《解字》
会意兼形声。準は「水+十(集めそろえる)+音符隹スイ(ずっしり、落ち着く)」の会意兼形声文字。水を落ち着けて水面を平らにそろえること。水準・平均の意を含む。准はその略字。▽淮ワイは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 冫部 [常用漢字]
区点=2958 16進=3D5A シフトJIS=8F79
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン
10画 冫部 [常用漢字]
区点=2958 16進=3D5A シフトJIS=8F79
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 なぞらえる(なぞらふ)/ゆるす
《名付け》 のり
《意味》
n〉
《訓読み》 なぞらえる(なぞらふ)/ゆるす
《名付け》 のり
《意味》
 {動・名}平らにならすこと。〈同義語〉→準。「標准(=標準)」
{動・名}平らにならすこと。〈同義語〉→準。「標准(=標準)」
 ジュンス{動}なぞらえる(ナゾラフ)。規準となる事がらに、比べあわせる。▽平均する意から、同等にそろえて扱う意となる。〈同義語〉→準。「准用(=準用)」
ジュンス{動}なぞらえる(ナゾラフ)。規準となる事がらに、比べあわせる。▽平均する意から、同等にそろえて扱う意となる。〈同義語〉→準。「准用(=準用)」
 {動}ゆるす。全体を見渡してバランスをとって認める。▽允イン(ゆるす)に近い。「准許」「批准(裁断を下してゆるす)」
{動}ゆるす。全体を見渡してバランスをとって認める。▽允イン(ゆるす)に近い。「准許」「批准(裁断を下してゆるす)」
 {動}〔俗〕…により。…によれば。▽中世以後の公文書用語。「准…部咨行シコウ(…部の通告によれば)」
《解字》
会意兼形声。準は「水+十(集めそろえる)+音符隹スイ(ずっしり、落ち着く)」の会意兼形声文字。水を落ち着けて水面を平らにそろえること。水準・平均の意を含む。准はその略字。▽淮ワイは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}〔俗〕…により。…によれば。▽中世以後の公文書用語。「准…部咨行シコウ(…部の通告によれば)」
《解字》
会意兼形声。準は「水+十(集めそろえる)+音符隹スイ(ずっしり、落ち着く)」の会意兼形声文字。水を落ち着けて水面を平らにそろえること。水準・平均の意を含む。准はその略字。▽淮ワイは、別字。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
原 ゆるす🔗⭐🔉
【原】
 10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン
10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン /ゴン
/ゴン /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) 〈yu
〈yu n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
 {名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
 {名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
 {名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
 {副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
 {動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
 {形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
 {動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
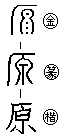 会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)
会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン
10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン /ゴン
/ゴン /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) 〈yu
〈yu n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
 {名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
 {名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
 {名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
 {副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
 {動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
 {形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
 {動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
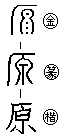 会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)
会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
宥 ゆるす🔗⭐🔉
【宥】
 9画 宀部 [人名漢字]
区点=4508 16進=4D28 シフトJIS=9747
《音読み》 ユウ(イウ)
9画 宀部 [人名漢字]
区点=4508 16進=4D28 シフトJIS=9747
《音読み》 ユウ(イウ) /ウ
/ウ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 ゆるす/なだめる(なだむ)
《名付け》 すけ・ひろ
《意味》
u〉
《訓読み》 ゆるす/なだめる(なだむ)
《名付け》 すけ・ひろ
《意味》
 {動}ゆるす。ゆとりを持つ。ゆとりをおき、責めないでおく。大目に見てかばう。「寛宥カンユウ」「宥恕ユウジョ」「宥罪挙職=罪ヲ宥シテ職ヲ挙グ」〔→左伝〕
{動}ゆるす。ゆとりを持つ。ゆとりをおき、責めないでおく。大目に見てかばう。「寛宥カンユウ」「宥恕ユウジョ」「宥罪挙職=罪ヲ宥シテ職ヲ挙グ」〔→左伝〕
 {動}なだめる(ナダム)。気持ちにゆとりを持たせる。
《解字》
会意兼形声。有は、手でかばって肉を持つ姿で、周囲をわくで囲んで中をかばい、ゆとりを設ける意を含む。域と同系。宥は「宀(やね)+音符有」で、屋根で囲って中の物をかばうこと。→有
《単語家族》
祐ユウ(神のかばい)
{動}なだめる(ナダム)。気持ちにゆとりを持たせる。
《解字》
会意兼形声。有は、手でかばって肉を持つ姿で、周囲をわくで囲んで中をかばい、ゆとりを設ける意を含む。域と同系。宥は「宀(やね)+音符有」で、屋根で囲って中の物をかばうこと。→有
《単語家族》
祐ユウ(神のかばい) 友(かばいあうともだち)
友(かばいあうともだち) 佑ユウ(かばいたすける)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
佑ユウ(かばいたすける)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 宀部 [人名漢字]
区点=4508 16進=4D28 シフトJIS=9747
《音読み》 ユウ(イウ)
9画 宀部 [人名漢字]
区点=4508 16進=4D28 シフトJIS=9747
《音読み》 ユウ(イウ) /ウ
/ウ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 ゆるす/なだめる(なだむ)
《名付け》 すけ・ひろ
《意味》
u〉
《訓読み》 ゆるす/なだめる(なだむ)
《名付け》 すけ・ひろ
《意味》
 {動}ゆるす。ゆとりを持つ。ゆとりをおき、責めないでおく。大目に見てかばう。「寛宥カンユウ」「宥恕ユウジョ」「宥罪挙職=罪ヲ宥シテ職ヲ挙グ」〔→左伝〕
{動}ゆるす。ゆとりを持つ。ゆとりをおき、責めないでおく。大目に見てかばう。「寛宥カンユウ」「宥恕ユウジョ」「宥罪挙職=罪ヲ宥シテ職ヲ挙グ」〔→左伝〕
 {動}なだめる(ナダム)。気持ちにゆとりを持たせる。
《解字》
会意兼形声。有は、手でかばって肉を持つ姿で、周囲をわくで囲んで中をかばい、ゆとりを設ける意を含む。域と同系。宥は「宀(やね)+音符有」で、屋根で囲って中の物をかばうこと。→有
《単語家族》
祐ユウ(神のかばい)
{動}なだめる(ナダム)。気持ちにゆとりを持たせる。
《解字》
会意兼形声。有は、手でかばって肉を持つ姿で、周囲をわくで囲んで中をかばい、ゆとりを設ける意を含む。域と同系。宥は「宀(やね)+音符有」で、屋根で囲って中の物をかばうこと。→有
《単語家族》
祐ユウ(神のかばい) 友(かばいあうともだち)
友(かばいあうともだち) 佑ユウ(かばいたすける)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
佑ユウ(かばいたすける)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
容 ゆるす🔗⭐🔉
【容】
 10画 宀部 [五年]
区点=4538 16進=4D46 シフトJIS=9765
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ
10画 宀部 [五年]
区点=4538 16進=4D46 シフトJIS=9765
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ /ユウ
/ユウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 いれる(いる)/かたち/すがた/ゆるす
《名付け》 いるる・おさ・かた・なり・ひろ・ひろし・まさ・もり・やす・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 いれる(いる)/かたち/すがた/ゆるす
《名付け》 いるる・おさ・かた・なり・ひろ・ひろし・まさ・もり・やす・よし
《意味》
 {動}いれる(イル)。中に物をいれる。また、とりこむ。「収容」「瓠落無所容=瓠落トシテ容ルルトコロ無シ」〔→荘子〕
{動}いれる(イル)。中に物をいれる。また、とりこむ。「収容」「瓠落無所容=瓠落トシテ容ルルトコロ無シ」〔→荘子〕
 {名}中身。中にはいっているもの。またその量。「内容」
{名}中身。中にはいっているもの。またその量。「内容」
 {名}かたち。すがた。わくの中におさまった全体のようす。かっこう。「容貌ヨウボウ」「斂容=容ヲ斂ム」「女容甚麗=女ノ容甚ダ麗シ」〔→枕中記〕
{名}かたち。すがた。わくの中におさまった全体のようす。かっこう。「容貌ヨウボウ」「斂容=容ヲ斂ム」「女容甚麗=女ノ容甚ダ麗シ」〔→枕中記〕
 {動}かたちづくる。すがたを整える。また、化粧する。「転側為君容=転側シテ君ガ為ニ容ル」〔→蘇軾〕
{動}かたちづくる。すがたを整える。また、化粧する。「転側為君容=転側シテ君ガ為ニ容ル」〔→蘇軾〕
 {動}ゆるす。いれる(イル)。ゆるす。また、ききいれる。受けいれる。「許容」「不容=容サズ」
{動}ゆるす。いれる(イル)。ゆるす。また、ききいれる。受けいれる。「許容」「不容=容サズ」
 {形}ゆとりがあるさま。「容与」
《解字》
会意兼形声。谷は、中がくぼんで水のはいるたに。容は「宀(いえ)+音符谷」で、からのわくの中に物を入れること。またその中身。人間のからだの輪郭の中におさまったすがたも容姿という。ヨウの音はヨクの語尾が鼻音となって伸びたもの。
《単語家族》
浴(水の中にからだを入れる)
{形}ゆとりがあるさま。「容与」
《解字》
会意兼形声。谷は、中がくぼんで水のはいるたに。容は「宀(いえ)+音符谷」で、からのわくの中に物を入れること。またその中身。人間のからだの輪郭の中におさまったすがたも容姿という。ヨウの音はヨクの語尾が鼻音となって伸びたもの。
《単語家族》
浴(水の中にからだを入れる) 慾・欲(中がくぼんで、物を入れたくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
慾・欲(中がくぼんで、物を入れたくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 10画 宀部 [五年]
区点=4538 16進=4D46 シフトJIS=9765
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ
10画 宀部 [五年]
区点=4538 16進=4D46 シフトJIS=9765
《常用音訓》ヨウ
《音読み》 ヨウ /ユウ
/ユウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 いれる(いる)/かたち/すがた/ゆるす
《名付け》 いるる・おさ・かた・なり・ひろ・ひろし・まさ・もり・やす・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 いれる(いる)/かたち/すがた/ゆるす
《名付け》 いるる・おさ・かた・なり・ひろ・ひろし・まさ・もり・やす・よし
《意味》
 {動}いれる(イル)。中に物をいれる。また、とりこむ。「収容」「瓠落無所容=瓠落トシテ容ルルトコロ無シ」〔→荘子〕
{動}いれる(イル)。中に物をいれる。また、とりこむ。「収容」「瓠落無所容=瓠落トシテ容ルルトコロ無シ」〔→荘子〕
 {名}中身。中にはいっているもの。またその量。「内容」
{名}中身。中にはいっているもの。またその量。「内容」
 {名}かたち。すがた。わくの中におさまった全体のようす。かっこう。「容貌ヨウボウ」「斂容=容ヲ斂ム」「女容甚麗=女ノ容甚ダ麗シ」〔→枕中記〕
{名}かたち。すがた。わくの中におさまった全体のようす。かっこう。「容貌ヨウボウ」「斂容=容ヲ斂ム」「女容甚麗=女ノ容甚ダ麗シ」〔→枕中記〕
 {動}かたちづくる。すがたを整える。また、化粧する。「転側為君容=転側シテ君ガ為ニ容ル」〔→蘇軾〕
{動}かたちづくる。すがたを整える。また、化粧する。「転側為君容=転側シテ君ガ為ニ容ル」〔→蘇軾〕
 {動}ゆるす。いれる(イル)。ゆるす。また、ききいれる。受けいれる。「許容」「不容=容サズ」
{動}ゆるす。いれる(イル)。ゆるす。また、ききいれる。受けいれる。「許容」「不容=容サズ」
 {形}ゆとりがあるさま。「容与」
《解字》
会意兼形声。谷は、中がくぼんで水のはいるたに。容は「宀(いえ)+音符谷」で、からのわくの中に物を入れること。またその中身。人間のからだの輪郭の中におさまったすがたも容姿という。ヨウの音はヨクの語尾が鼻音となって伸びたもの。
《単語家族》
浴(水の中にからだを入れる)
{形}ゆとりがあるさま。「容与」
《解字》
会意兼形声。谷は、中がくぼんで水のはいるたに。容は「宀(いえ)+音符谷」で、からのわくの中に物を入れること。またその中身。人間のからだの輪郭の中におさまったすがたも容姿という。ヨウの音はヨクの語尾が鼻音となって伸びたもの。
《単語家族》
浴(水の中にからだを入れる) 慾・欲(中がくぼんで、物を入れたくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
慾・欲(中がくぼんで、物を入れたくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
寛 ゆるくする🔗⭐🔉
【寛】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 13画 宀部 [常用漢字]
区点=2018 16進=3432 シフトJIS=8AB0
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク
13画 宀部 [常用漢字]
区点=2018 16進=3432 シフトJIS=8AB0
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク ン)
ン)
 〈ku
〈ku n〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるす/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 お・おき・ちか・とお・とみ・とも・とら・のぶ・のり・ひと・ひろ・ひろし・むね・もと・ゆたか・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるす/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 お・おき・ちか・とお・とみ・とも・とら・のぶ・のり・ひと・ひろ・ひろし・むね・もと・ゆたか・よし
《意味》
 {形}ひろい(ヒロシ)。スペースがひろい。気持ちにゆったりとゆとりがあるさま。〈対語〉→狭。「寛容」「居上不寛=上ニ居リテ寛カラズ」〔→論語〕
{形}ひろい(ヒロシ)。スペースがひろい。気持ちにゆったりとゆとりがあるさま。〈対語〉→狭。「寛容」「居上不寛=上ニ居リテ寛カラズ」〔→論語〕
 カンナリ{形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。おおまかであるさま。差し迫った用がなくて、のんびりしているさま。〈対語〉→急・→厳。「急則人習騎射、寛則人楽無事=急ナレバスナハチ人騎射ヲ習ヒ、寛ナレバスナハチ人無事ヲ楽シム」〔→史記〕
カンナリ{形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。おおまかであるさま。差し迫った用がなくて、のんびりしているさま。〈対語〉→急・→厳。「急則人習騎射、寛則人楽無事=急ナレバスナハチ人騎射ヲ習ヒ、寛ナレバスナハチ人無事ヲ楽シム」〔→史記〕
 {動}くつろぐ。ゆったりする。ゆとりをもつ。
{動}くつろぐ。ゆったりする。ゆとりをもつ。
 {名}はば。「寛三尺」
{名}はば。「寛三尺」
 {動}ゆるす。ゆるくする(ユルクス)。大目に見て、きびしく責めない。ゆるめる。「寛赦」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音カン)は、からだのまるいやぎを描いた象形文字。まるい意を含む。寛はそれを音符とし、宀(いえ)を加えた字で、中がまるくゆとりがあって、自由に動ける大きい家。転じて、ひろく中にゆとりのある意を示す。
《単語家族》
緩と同系。
《類義》
→広
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ゆるす。ゆるくする(ユルクス)。大目に見て、きびしく責めない。ゆるめる。「寛赦」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音カン)は、からだのまるいやぎを描いた象形文字。まるい意を含む。寛はそれを音符とし、宀(いえ)を加えた字で、中がまるくゆとりがあって、自由に動ける大きい家。転じて、ひろく中にゆとりのある意を示す。
《単語家族》
緩と同系。
《類義》
→広
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 13画 宀部 [常用漢字]
区点=2018 16進=3432 シフトJIS=8AB0
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク
13画 宀部 [常用漢字]
区点=2018 16進=3432 シフトJIS=8AB0
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(ク ン)
ン)
 〈ku
〈ku n〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるす/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 お・おき・ちか・とお・とみ・とも・とら・のぶ・のり・ひと・ひろ・ひろし・むね・もと・ゆたか・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるす/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 お・おき・ちか・とお・とみ・とも・とら・のぶ・のり・ひと・ひろ・ひろし・むね・もと・ゆたか・よし
《意味》
 {形}ひろい(ヒロシ)。スペースがひろい。気持ちにゆったりとゆとりがあるさま。〈対語〉→狭。「寛容」「居上不寛=上ニ居リテ寛カラズ」〔→論語〕
{形}ひろい(ヒロシ)。スペースがひろい。気持ちにゆったりとゆとりがあるさま。〈対語〉→狭。「寛容」「居上不寛=上ニ居リテ寛カラズ」〔→論語〕
 カンナリ{形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。おおまかであるさま。差し迫った用がなくて、のんびりしているさま。〈対語〉→急・→厳。「急則人習騎射、寛則人楽無事=急ナレバスナハチ人騎射ヲ習ヒ、寛ナレバスナハチ人無事ヲ楽シム」〔→史記〕
カンナリ{形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。おおまかであるさま。差し迫った用がなくて、のんびりしているさま。〈対語〉→急・→厳。「急則人習騎射、寛則人楽無事=急ナレバスナハチ人騎射ヲ習ヒ、寛ナレバスナハチ人無事ヲ楽シム」〔→史記〕
 {動}くつろぐ。ゆったりする。ゆとりをもつ。
{動}くつろぐ。ゆったりする。ゆとりをもつ。
 {名}はば。「寛三尺」
{名}はば。「寛三尺」
 {動}ゆるす。ゆるくする(ユルクス)。大目に見て、きびしく責めない。ゆるめる。「寛赦」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音カン)は、からだのまるいやぎを描いた象形文字。まるい意を含む。寛はそれを音符とし、宀(いえ)を加えた字で、中がまるくゆとりがあって、自由に動ける大きい家。転じて、ひろく中にゆとりのある意を示す。
《単語家族》
緩と同系。
《類義》
→広
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ゆるす。ゆるくする(ユルクス)。大目に見て、きびしく責めない。ゆるめる。「寛赦」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音カン)は、からだのまるいやぎを描いた象形文字。まるい意を含む。寛はそれを音符とし、宀(いえ)を加えた字で、中がまるくゆとりがあって、自由に動ける大きい家。転じて、ひろく中にゆとりのある意を示す。
《単語家族》
緩と同系。
《類義》
→広
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
弛 ゆるむ🔗⭐🔉
【弛】
 6画 弓部
区点=3548 16進=4350 シフトJIS=926F
《音読み》 シ
6画 弓部
区点=3548 16進=4350 シフトJIS=926F
《音読み》 シ
 /チ
/チ 〈sh
〈sh ・ch
・ch 〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるめる(ゆるむ)
《意味》
{動}ゆるむ。ゆるめる(ユルム)。張っていた力が抜けてだれる。〈対語〉→張。〈類義語〉→緩。「弛張シチョウ/チチョウ(張りとゆるみ)」「摂帽弛帯=帽ヲ摂リ帯ヲ弛ム」〔→枕中記〕
《解字》
会意兼形声。也は、平らに長く伸びたさそりを描いた象形文字。弛は「弓+音符也」で、ぴんと張った弓がだらりと長く伸びること。→也
《単語家族》
地(平らに伸びたち)
〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるめる(ゆるむ)
《意味》
{動}ゆるむ。ゆるめる(ユルム)。張っていた力が抜けてだれる。〈対語〉→張。〈類義語〉→緩。「弛張シチョウ/チチョウ(張りとゆるみ)」「摂帽弛帯=帽ヲ摂リ帯ヲ弛ム」〔→枕中記〕
《解字》
会意兼形声。也は、平らに長く伸びたさそりを描いた象形文字。弛は「弓+音符也」で、ぴんと張った弓がだらりと長く伸びること。→也
《単語家族》
地(平らに伸びたち) 紙(平らに伸びたかみ)と同系。
《類義》
緩は、間にゆとりを持つこと。徐ジョは、ゆるゆると歩みをのばすことから、ゆとりがある意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
紙(平らに伸びたかみ)と同系。
《類義》
緩は、間にゆとりを持つこと。徐ジョは、ゆるゆると歩みをのばすことから、ゆとりがある意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画 弓部
区点=3548 16進=4350 シフトJIS=926F
《音読み》 シ
6画 弓部
区点=3548 16進=4350 シフトJIS=926F
《音読み》 シ
 /チ
/チ 〈sh
〈sh ・ch
・ch 〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるめる(ゆるむ)
《意味》
{動}ゆるむ。ゆるめる(ユルム)。張っていた力が抜けてだれる。〈対語〉→張。〈類義語〉→緩。「弛張シチョウ/チチョウ(張りとゆるみ)」「摂帽弛帯=帽ヲ摂リ帯ヲ弛ム」〔→枕中記〕
《解字》
会意兼形声。也は、平らに長く伸びたさそりを描いた象形文字。弛は「弓+音符也」で、ぴんと張った弓がだらりと長く伸びること。→也
《単語家族》
地(平らに伸びたち)
〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるめる(ゆるむ)
《意味》
{動}ゆるむ。ゆるめる(ユルム)。張っていた力が抜けてだれる。〈対語〉→張。〈類義語〉→緩。「弛張シチョウ/チチョウ(張りとゆるみ)」「摂帽弛帯=帽ヲ摂リ帯ヲ弛ム」〔→枕中記〕
《解字》
会意兼形声。也は、平らに長く伸びたさそりを描いた象形文字。弛は「弓+音符也」で、ぴんと張った弓がだらりと長く伸びること。→也
《単語家族》
地(平らに伸びたち) 紙(平らに伸びたかみ)と同系。
《類義》
緩は、間にゆとりを持つこと。徐ジョは、ゆるゆると歩みをのばすことから、ゆとりがある意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
紙(平らに伸びたかみ)と同系。
《類義》
緩は、間にゆとりを持つこと。徐ジョは、ゆるゆると歩みをのばすことから、ゆとりがある意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
従 ゆるめる🔗⭐🔉
【従】
 10画 彳部 [六年]
区点=2930 16進=3D3E シフトJIS=8F5D
【從】旧字人名に使える旧字
10画 彳部 [六年]
区点=2930 16進=3D3E シフトJIS=8F5D
【從】旧字人名に使える旧字
 11画 彳部
区点=5547 16進=574F シフトJIS=9C6E
【从】異体字異体字
11画 彳部
区点=5547 16進=574F シフトJIS=9C6E
【从】異体字異体字
 4画 人部
区点=4826 16進=503A シフトJIS=98B8
《常用音訓》ショウ/ジュ/ジュウ/したが…う/したが…える
《音読み》
4画 人部
区点=4826 16進=503A シフトJIS=98B8
《常用音訓》ショウ/ジュ/ジュウ/したが…う/したが…える
《音読み》  ジュウ/ジュ
ジュウ/ジュ /ショウ
/ショウ 〈c
〈c ng〉/
ng〉/ ジュ/ジュウ
ジュ/ジュウ /ショウ
/ショウ 〈z
〈z ng〉/
ng〉/ シュ
シュ /ショウ
/ショウ /ジュウ
/ジュウ /
/ ショウ
ショウ /シュ
/シュ 〈c
〈c ng〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/したがえる(したがふ)/したがって/より/ゆるめる(ゆるむ)
《名付け》 しげ・つぐ・より
《意味》
ng〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/したがえる(したがふ)/したがって/より/ゆるめる(ゆるむ)
《名付け》 しげ・つぐ・より
《意味》

 {動}したがう(シタガフ)。したがえる(シタガフ)。前のもののあとについて行く。あとに引き連れる。「従属」「従駕=駕ニ従フ」
{動}したがう(シタガフ)。したがえる(シタガフ)。前のもののあとについて行く。あとに引き連れる。「従属」「従駕=駕ニ従フ」
 {動}したがう(シタガフ)。ある仕事につく。「従事」「従政=政ニ従フ」
{動}したがう(シタガフ)。ある仕事につく。「従事」「従政=政ニ従フ」
 {接続}したがって。そのあとに引き続いて。「然後従而刑之=シカルノチ従ッテコレヲ刑ス」〔→孟子〕
{接続}したがって。そのあとに引き続いて。「然後従而刑之=シカルノチ従ッテコレヲ刑ス」〔→孟子〕
 {前}より。…からという起点をあらわす。場所にも時間にも用いる。〈類義語〉→自。「憂従中来=憂ヒ、中ヨリ来タル」〔→曹操〕
{前}より。…からという起点をあらわす。場所にも時間にも用いる。〈類義語〉→自。「憂従中来=憂ヒ、中ヨリ来タル」〔→曹操〕

 {名}つきしたがう人。〈対語〉→主。「主従シュジュウ/シュジュ」
{名}つきしたがう人。〈対語〉→主。「主従シュジュウ/シュジュ」
 {助}親族の名称につけて、主なものの次にあることを示すことば。「従兄」「再従兄弟(またいとこ)」
{助}親族の名称につけて、主なものの次にあることを示すことば。「従兄」「再従兄弟(またいとこ)」
 {助}官位の正式なものに対して、それに次ぐ官位をあらわすことば。「従三位」
{助}官位の正式なものに対して、それに次ぐ官位をあらわすことば。「従三位」
 {名}たて。南北のこと。▽東西は衡コウ。〈同義語〉→縦。「従横家」「合従(南北の同盟)」
{名}たて。南北のこと。▽東西は衡コウ。〈同義語〉→縦。「従横家」「合従(南北の同盟)」
 {動}ゆるめる(ユルム)。束縛をといてのばす。存分に手足をのばす。〈同義語〉→縦。「従容ショウヨウ」
〔国〕したがって。それだから。
《解字》
{動}ゆるめる(ユルム)。束縛をといてのばす。存分に手足をのばす。〈同義語〉→縦。「従容ショウヨウ」
〔国〕したがって。それだから。
《解字》
 会意兼形声。从ジュウは、前の人のあとにうしろの人がつきしたがうさま。從は「止(あし)+彳(いく)+音符从」で、つきしたがうこと。AのあとにBがしたがえば長い縦隊となるので、長く縦に伸びる意となった。
《類義》
→随
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。从ジュウは、前の人のあとにうしろの人がつきしたがうさま。從は「止(あし)+彳(いく)+音符从」で、つきしたがうこと。AのあとにBがしたがえば長い縦隊となるので、長く縦に伸びる意となった。
《類義》
→随
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 彳部 [六年]
区点=2930 16進=3D3E シフトJIS=8F5D
【從】旧字人名に使える旧字
10画 彳部 [六年]
区点=2930 16進=3D3E シフトJIS=8F5D
【從】旧字人名に使える旧字
 11画 彳部
区点=5547 16進=574F シフトJIS=9C6E
【从】異体字異体字
11画 彳部
区点=5547 16進=574F シフトJIS=9C6E
【从】異体字異体字
 4画 人部
区点=4826 16進=503A シフトJIS=98B8
《常用音訓》ショウ/ジュ/ジュウ/したが…う/したが…える
《音読み》
4画 人部
区点=4826 16進=503A シフトJIS=98B8
《常用音訓》ショウ/ジュ/ジュウ/したが…う/したが…える
《音読み》  ジュウ/ジュ
ジュウ/ジュ /ショウ
/ショウ 〈c
〈c ng〉/
ng〉/ ジュ/ジュウ
ジュ/ジュウ /ショウ
/ショウ 〈z
〈z ng〉/
ng〉/ シュ
シュ /ショウ
/ショウ /ジュウ
/ジュウ /
/ ショウ
ショウ /シュ
/シュ 〈c
〈c ng〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/したがえる(したがふ)/したがって/より/ゆるめる(ゆるむ)
《名付け》 しげ・つぐ・より
《意味》
ng〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/したがえる(したがふ)/したがって/より/ゆるめる(ゆるむ)
《名付け》 しげ・つぐ・より
《意味》

 {動}したがう(シタガフ)。したがえる(シタガフ)。前のもののあとについて行く。あとに引き連れる。「従属」「従駕=駕ニ従フ」
{動}したがう(シタガフ)。したがえる(シタガフ)。前のもののあとについて行く。あとに引き連れる。「従属」「従駕=駕ニ従フ」
 {動}したがう(シタガフ)。ある仕事につく。「従事」「従政=政ニ従フ」
{動}したがう(シタガフ)。ある仕事につく。「従事」「従政=政ニ従フ」
 {接続}したがって。そのあとに引き続いて。「然後従而刑之=シカルノチ従ッテコレヲ刑ス」〔→孟子〕
{接続}したがって。そのあとに引き続いて。「然後従而刑之=シカルノチ従ッテコレヲ刑ス」〔→孟子〕
 {前}より。…からという起点をあらわす。場所にも時間にも用いる。〈類義語〉→自。「憂従中来=憂ヒ、中ヨリ来タル」〔→曹操〕
{前}より。…からという起点をあらわす。場所にも時間にも用いる。〈類義語〉→自。「憂従中来=憂ヒ、中ヨリ来タル」〔→曹操〕

 {名}つきしたがう人。〈対語〉→主。「主従シュジュウ/シュジュ」
{名}つきしたがう人。〈対語〉→主。「主従シュジュウ/シュジュ」
 {助}親族の名称につけて、主なものの次にあることを示すことば。「従兄」「再従兄弟(またいとこ)」
{助}親族の名称につけて、主なものの次にあることを示すことば。「従兄」「再従兄弟(またいとこ)」
 {助}官位の正式なものに対して、それに次ぐ官位をあらわすことば。「従三位」
{助}官位の正式なものに対して、それに次ぐ官位をあらわすことば。「従三位」
 {名}たて。南北のこと。▽東西は衡コウ。〈同義語〉→縦。「従横家」「合従(南北の同盟)」
{名}たて。南北のこと。▽東西は衡コウ。〈同義語〉→縦。「従横家」「合従(南北の同盟)」
 {動}ゆるめる(ユルム)。束縛をといてのばす。存分に手足をのばす。〈同義語〉→縦。「従容ショウヨウ」
〔国〕したがって。それだから。
《解字》
{動}ゆるめる(ユルム)。束縛をといてのばす。存分に手足をのばす。〈同義語〉→縦。「従容ショウヨウ」
〔国〕したがって。それだから。
《解字》
 会意兼形声。从ジュウは、前の人のあとにうしろの人がつきしたがうさま。從は「止(あし)+彳(いく)+音符从」で、つきしたがうこと。AのあとにBがしたがえば長い縦隊となるので、長く縦に伸びる意となった。
《類義》
→随
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。从ジュウは、前の人のあとにうしろの人がつきしたがうさま。從は「止(あし)+彳(いく)+音符从」で、つきしたがうこと。AのあとにBがしたがえば長い縦隊となるので、長く縦に伸びる意となった。
《類義》
→随
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
徐 ゆるやか🔗⭐🔉
【徐】
 10画 彳部 [常用漢字]
区点=2989 16進=3D79 シフトJIS=8F99
《常用音訓》ジョ
《音読み》 ジョ
10画 彳部 [常用漢字]
区点=2989 16進=3D79 シフトJIS=8F99
《常用音訓》ジョ
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 おもむろ/ゆるやか(ゆるやかなり)
《名付け》 やす・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 おもむろ/ゆるやか(ゆるやかなり)
《名付け》 やす・ゆき
《意味》
 {形}おもむろ。ゆっくり。そろそろと。〈対語〉→疾。〈類義語〉→緩。「徐歩(ゆっくり歩く)」「清風徐来=清風徐ロニ来タル」〔→蘇軾〕
{形}おもむろ。ゆっくり。そろそろと。〈対語〉→疾。〈類義語〉→緩。「徐歩(ゆっくり歩く)」「清風徐来=清風徐ロニ来タル」〔→蘇軾〕
 {形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。ゆとりがある。
{形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。ゆとりがある。
 {名}地名。(イ)古代、九州の一つ。今の山東省の東南部から江蘇コウソ・安徽アンキ両省の北部にかけての地域。(ロ)後漢時代以来の州・路・府名。今の江蘇省の北西部を中心とする地域にあたる。治所は今の徐州市など。(ハ)漢代から南北朝時代まで置かれた県。今の江蘇省泗洪シコウ県にあたる。
《解字》
会意兼形声。余は両手でスコップを押し、土を向こうにゆるゆると延ばしやるさま。徐は「彳(いく)+音符余」で、ゆるゆると歩みを伸ばすこと。→余
《単語家族》
舒ジョ(伸ばす)と同系。また、舎シャ(ゆったりとくつろぐ所)・赦シャ(ゆるめる)とも近い。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}地名。(イ)古代、九州の一つ。今の山東省の東南部から江蘇コウソ・安徽アンキ両省の北部にかけての地域。(ロ)後漢時代以来の州・路・府名。今の江蘇省の北西部を中心とする地域にあたる。治所は今の徐州市など。(ハ)漢代から南北朝時代まで置かれた県。今の江蘇省泗洪シコウ県にあたる。
《解字》
会意兼形声。余は両手でスコップを押し、土を向こうにゆるゆると延ばしやるさま。徐は「彳(いく)+音符余」で、ゆるゆると歩みを伸ばすこと。→余
《単語家族》
舒ジョ(伸ばす)と同系。また、舎シャ(ゆったりとくつろぐ所)・赦シャ(ゆるめる)とも近い。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 10画 彳部 [常用漢字]
区点=2989 16進=3D79 シフトJIS=8F99
《常用音訓》ジョ
《音読み》 ジョ
10画 彳部 [常用漢字]
区点=2989 16進=3D79 シフトJIS=8F99
《常用音訓》ジョ
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 おもむろ/ゆるやか(ゆるやかなり)
《名付け》 やす・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 おもむろ/ゆるやか(ゆるやかなり)
《名付け》 やす・ゆき
《意味》
 {形}おもむろ。ゆっくり。そろそろと。〈対語〉→疾。〈類義語〉→緩。「徐歩(ゆっくり歩く)」「清風徐来=清風徐ロニ来タル」〔→蘇軾〕
{形}おもむろ。ゆっくり。そろそろと。〈対語〉→疾。〈類義語〉→緩。「徐歩(ゆっくり歩く)」「清風徐来=清風徐ロニ来タル」〔→蘇軾〕
 {形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。ゆとりがある。
{形}ゆるやか(ユルヤカナリ)。ゆとりがある。
 {名}地名。(イ)古代、九州の一つ。今の山東省の東南部から江蘇コウソ・安徽アンキ両省の北部にかけての地域。(ロ)後漢時代以来の州・路・府名。今の江蘇省の北西部を中心とする地域にあたる。治所は今の徐州市など。(ハ)漢代から南北朝時代まで置かれた県。今の江蘇省泗洪シコウ県にあたる。
《解字》
会意兼形声。余は両手でスコップを押し、土を向こうにゆるゆると延ばしやるさま。徐は「彳(いく)+音符余」で、ゆるゆると歩みを伸ばすこと。→余
《単語家族》
舒ジョ(伸ばす)と同系。また、舎シャ(ゆったりとくつろぐ所)・赦シャ(ゆるめる)とも近い。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}地名。(イ)古代、九州の一つ。今の山東省の東南部から江蘇コウソ・安徽アンキ両省の北部にかけての地域。(ロ)後漢時代以来の州・路・府名。今の江蘇省の北西部を中心とする地域にあたる。治所は今の徐州市など。(ハ)漢代から南北朝時代まで置かれた県。今の江蘇省泗洪シコウ県にあたる。
《解字》
会意兼形声。余は両手でスコップを押し、土を向こうにゆるゆると延ばしやるさま。徐は「彳(いく)+音符余」で、ゆるゆると歩みを伸ばすこと。→余
《単語家族》
舒ジョ(伸ばす)と同系。また、舎シャ(ゆったりとくつろぐ所)・赦シャ(ゆるめる)とも近い。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
忽 ゆるがせにする🔗⭐🔉
【忽】
 8画 心部
区点=2590 16進=397A シフトJIS=8D9A
《音読み》 コツ
8画 心部
区点=2590 16進=397A シフトJIS=8D9A
《音読み》 コツ /コチ
/コチ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 たちまち/ゆるがせにする(ゆるがせにす)
《意味》
〉
《訓読み》 たちまち/ゆるがせにする(ゆるがせにす)
《意味》
 {副}たちまち。いつのまにか。うっかりしているまに。〈類義語〉→俄ガ/ニワカ。「忽然」「忽聞=忽チ聞ク」「歳月忽已晩=歳月、忽チスデニ晩シ」〔→古詩十九首〕
{副}たちまち。いつのまにか。うっかりしているまに。〈類義語〉→俄ガ/ニワカ。「忽然」「忽聞=忽チ聞ク」「歳月忽已晩=歳月、忽チスデニ晩シ」〔→古詩十九首〕
 {形}心がうつろなさま。よく見定められないさま。とりとめのないさま。〈同義語〉→惚。
{形}心がうつろなさま。よく見定められないさま。とりとめのないさま。〈同義語〉→惚。
 {形・動}ゆるがせにする(ユルガセニス)。気にとめないさま。気にとめずにほうっておく。しっかりととらえずに放置する。「忽略コツリャク」「禍乱生於所忽=禍乱ハ、忽ニスル所ヨリ生ズ」〔→通鑑〕
{形・動}ゆるがせにする(ユルガセニス)。気にとめないさま。気にとめずにほうっておく。しっかりととらえずに放置する。「忽略コツリャク」「禍乱生於所忽=禍乱ハ、忽ニスル所ヨリ生ズ」〔→通鑑〕
 {単位}数の単位。一の十万分の一。糸の十分の一。微の十倍。
《解字》
会意兼形声。勿ブツは、吹き流しがゆらゆらして、はっきりと見えないさまを描いた象形文字。忽は「心+音符勿」で、心がそこに存在せず、はっきりしないまま見すごしていること。→勿
《単語家族》
勿(ない)
{単位}数の単位。一の十万分の一。糸の十分の一。微の十倍。
《解字》
会意兼形声。勿ブツは、吹き流しがゆらゆらして、はっきりと見えないさまを描いた象形文字。忽は「心+音符勿」で、心がそこに存在せず、はっきりしないまま見すごしていること。→勿
《単語家族》
勿(ない) 没(見えなくなる)などと同系。
《類義》
俄ガは、きわだった断層が生じる意を含み、がくっと驚く、にわかに変化するなどの場合の副詞に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
没(見えなくなる)などと同系。
《類義》
俄ガは、きわだった断層が生じる意を含み、がくっと驚く、にわかに変化するなどの場合の副詞に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 8画 心部
区点=2590 16進=397A シフトJIS=8D9A
《音読み》 コツ
8画 心部
区点=2590 16進=397A シフトJIS=8D9A
《音読み》 コツ /コチ
/コチ 〈h
〈h 〉
《訓読み》 たちまち/ゆるがせにする(ゆるがせにす)
《意味》
〉
《訓読み》 たちまち/ゆるがせにする(ゆるがせにす)
《意味》
 {副}たちまち。いつのまにか。うっかりしているまに。〈類義語〉→俄ガ/ニワカ。「忽然」「忽聞=忽チ聞ク」「歳月忽已晩=歳月、忽チスデニ晩シ」〔→古詩十九首〕
{副}たちまち。いつのまにか。うっかりしているまに。〈類義語〉→俄ガ/ニワカ。「忽然」「忽聞=忽チ聞ク」「歳月忽已晩=歳月、忽チスデニ晩シ」〔→古詩十九首〕
 {形}心がうつろなさま。よく見定められないさま。とりとめのないさま。〈同義語〉→惚。
{形}心がうつろなさま。よく見定められないさま。とりとめのないさま。〈同義語〉→惚。
 {形・動}ゆるがせにする(ユルガセニス)。気にとめないさま。気にとめずにほうっておく。しっかりととらえずに放置する。「忽略コツリャク」「禍乱生於所忽=禍乱ハ、忽ニスル所ヨリ生ズ」〔→通鑑〕
{形・動}ゆるがせにする(ユルガセニス)。気にとめないさま。気にとめずにほうっておく。しっかりととらえずに放置する。「忽略コツリャク」「禍乱生於所忽=禍乱ハ、忽ニスル所ヨリ生ズ」〔→通鑑〕
 {単位}数の単位。一の十万分の一。糸の十分の一。微の十倍。
《解字》
会意兼形声。勿ブツは、吹き流しがゆらゆらして、はっきりと見えないさまを描いた象形文字。忽は「心+音符勿」で、心がそこに存在せず、はっきりしないまま見すごしていること。→勿
《単語家族》
勿(ない)
{単位}数の単位。一の十万分の一。糸の十分の一。微の十倍。
《解字》
会意兼形声。勿ブツは、吹き流しがゆらゆらして、はっきりと見えないさまを描いた象形文字。忽は「心+音符勿」で、心がそこに存在せず、はっきりしないまま見すごしていること。→勿
《単語家族》
勿(ない) 没(見えなくなる)などと同系。
《類義》
俄ガは、きわだった断層が生じる意を含み、がくっと驚く、にわかに変化するなどの場合の副詞に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
没(見えなくなる)などと同系。
《類義》
俄ガは、きわだった断層が生じる意を含み、がくっと驚く、にわかに変化するなどの場合の副詞に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
恕 ゆるす🔗⭐🔉
【恕】
 10画 心部 [人名漢字]
区点=2990 16進=3D7A シフトJIS=8F9A
《音読み》 ジョ
10画 心部 [人名漢字]
区点=2990 16進=3D7A シフトJIS=8F9A
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 ゆるす
《名付け》 くに・しのぶ・ただし・のぶ・のり・はかる・ひろ・ひろし・ひろむ・みち・もろ・ゆき・ゆるす・よし
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす
《名付け》 くに・しのぶ・ただし・のぶ・のり・はかる・ひろ・ひろし・ひろむ・みち・もろ・ゆき・ゆるす・よし
《意味》
 {動・名}自分を思うのと同じように相手を思いやる。思いやり。「其恕乎、己所不欲勿施於人=ソレ恕カ、己ノ欲セザルトコロハ、人ニ施スコトナカレ」〔→論語〕
{動・名}自分を思うのと同じように相手を思いやる。思いやり。「其恕乎、己所不欲勿施於人=ソレ恕カ、己ノ欲セザルトコロハ、人ニ施スコトナカレ」〔→論語〕
 {動}ゆるす。自分に引き比べてみて、他人を寛大に扱う。また、同情して相手をとがめずにおく。「寛恕カンジョ」「宥恕ユウジョ」
《解字》
会意兼形声。如は、汝ジョ(自分とペアをなす相手)と同系のことば。自分と同じような対者という意味を含む。恕は「心+音符如ジョ」で、相手を自分と同じように見る心のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ゆるす。自分に引き比べてみて、他人を寛大に扱う。また、同情して相手をとがめずにおく。「寛恕カンジョ」「宥恕ユウジョ」
《解字》
会意兼形声。如は、汝ジョ(自分とペアをなす相手)と同系のことば。自分と同じような対者という意味を含む。恕は「心+音符如ジョ」で、相手を自分と同じように見る心のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 心部 [人名漢字]
区点=2990 16進=3D7A シフトJIS=8F9A
《音読み》 ジョ
10画 心部 [人名漢字]
区点=2990 16進=3D7A シフトJIS=8F9A
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 ゆるす
《名付け》 くに・しのぶ・ただし・のぶ・のり・はかる・ひろ・ひろし・ひろむ・みち・もろ・ゆき・ゆるす・よし
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす
《名付け》 くに・しのぶ・ただし・のぶ・のり・はかる・ひろ・ひろし・ひろむ・みち・もろ・ゆき・ゆるす・よし
《意味》
 {動・名}自分を思うのと同じように相手を思いやる。思いやり。「其恕乎、己所不欲勿施於人=ソレ恕カ、己ノ欲セザルトコロハ、人ニ施スコトナカレ」〔→論語〕
{動・名}自分を思うのと同じように相手を思いやる。思いやり。「其恕乎、己所不欲勿施於人=ソレ恕カ、己ノ欲セザルトコロハ、人ニ施スコトナカレ」〔→論語〕
 {動}ゆるす。自分に引き比べてみて、他人を寛大に扱う。また、同情して相手をとがめずにおく。「寛恕カンジョ」「宥恕ユウジョ」
《解字》
会意兼形声。如は、汝ジョ(自分とペアをなす相手)と同系のことば。自分と同じような対者という意味を含む。恕は「心+音符如ジョ」で、相手を自分と同じように見る心のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ゆるす。自分に引き比べてみて、他人を寛大に扱う。また、同情して相手をとがめずにおく。「寛恕カンジョ」「宥恕ユウジョ」
《解字》
会意兼形声。如は、汝ジョ(自分とペアをなす相手)と同系のことば。自分と同じような対者という意味を含む。恕は「心+音符如ジョ」で、相手を自分と同じように見る心のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
慢 ゆるい🔗⭐🔉
【慢】
 14画
14画  部 [常用漢字]
区点=4393 16進=4B7D シフトJIS=969D
《常用音訓》マン
《音読み》 マン
部 [常用漢字]
区点=4393 16進=4B7D シフトJIS=969D
《常用音訓》マン
《音読み》 マン /メン
/メン /バン
/バン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 おこたる/ゆるがせにする(ゆるがせにす)/あなどる/ゆるい(ゆるし)
《意味》
n〉
《訓読み》 おこたる/ゆるがせにする(ゆるがせにす)/あなどる/ゆるい(ゆるし)
《意味》
 {動・形}おこたる。ゆるがせにする(ユルガセニス)。行うべきことをけじめをつけず延引する。いいかげんにしておく。また、そのさま。だらしがないさま。「怠慢」「是上慢而残下也=コレ上慢リテ下ヲ残スルナリ」〔→孟子〕
{動・形}おこたる。ゆるがせにする(ユルガセニス)。行うべきことをけじめをつけず延引する。いいかげんにしておく。また、そのさま。だらしがないさま。「怠慢」「是上慢而残下也=コレ上慢リテ下ヲ残スルナリ」〔→孟子〕
 マンナリ{形・動}あなどる。いいかげんにあしらう。しまりがないさま。「慢心」「侮慢」「陛下慢而侮人=陛下、慢ニシテ人ヲ侮ル」〔→史記〕
マンナリ{形・動}あなどる。いいかげんにあしらう。しまりがないさま。「慢心」「侮慢」「陛下慢而侮人=陛下、慢ニシテ人ヲ侮ル」〔→史記〕
 {形}ゆるい(ユルシ)。ずるずると長びくさま。〈対語〉→急。「慢性」
{形}ゆるい(ユルシ)。ずるずると長びくさま。〈対語〉→急。「慢性」
 マンナリ{形}ゆるい(ユルシ)。ゆっくり。「慢歩(そぞろ歩き)」
《解字》
会意兼形声。曼マンとは、目をおおい隠すさま。長々とかぶさって広がる意を含む。慢は「心+音符曼」で、ずるずるとだらけて伸びる心のこと。
《単語家族》
幔マン(長く伸びる幕)
マンナリ{形}ゆるい(ユルシ)。ゆっくり。「慢歩(そぞろ歩き)」
《解字》
会意兼形声。曼マンとは、目をおおい隠すさま。長々とかぶさって広がる意を含む。慢は「心+音符曼」で、ずるずるとだらけて伸びる心のこと。
《単語家族》
幔マン(長く伸びる幕) 蔓マン(草がずるずると伸び広がる)
蔓マン(草がずるずると伸び広がる) 綿(長く伸びる糸)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
綿(長く伸びる糸)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 14画
14画  部 [常用漢字]
区点=4393 16進=4B7D シフトJIS=969D
《常用音訓》マン
《音読み》 マン
部 [常用漢字]
区点=4393 16進=4B7D シフトJIS=969D
《常用音訓》マン
《音読み》 マン /メン
/メン /バン
/バン 〈m
〈m n〉
《訓読み》 おこたる/ゆるがせにする(ゆるがせにす)/あなどる/ゆるい(ゆるし)
《意味》
n〉
《訓読み》 おこたる/ゆるがせにする(ゆるがせにす)/あなどる/ゆるい(ゆるし)
《意味》
 {動・形}おこたる。ゆるがせにする(ユルガセニス)。行うべきことをけじめをつけず延引する。いいかげんにしておく。また、そのさま。だらしがないさま。「怠慢」「是上慢而残下也=コレ上慢リテ下ヲ残スルナリ」〔→孟子〕
{動・形}おこたる。ゆるがせにする(ユルガセニス)。行うべきことをけじめをつけず延引する。いいかげんにしておく。また、そのさま。だらしがないさま。「怠慢」「是上慢而残下也=コレ上慢リテ下ヲ残スルナリ」〔→孟子〕
 マンナリ{形・動}あなどる。いいかげんにあしらう。しまりがないさま。「慢心」「侮慢」「陛下慢而侮人=陛下、慢ニシテ人ヲ侮ル」〔→史記〕
マンナリ{形・動}あなどる。いいかげんにあしらう。しまりがないさま。「慢心」「侮慢」「陛下慢而侮人=陛下、慢ニシテ人ヲ侮ル」〔→史記〕
 {形}ゆるい(ユルシ)。ずるずると長びくさま。〈対語〉→急。「慢性」
{形}ゆるい(ユルシ)。ずるずると長びくさま。〈対語〉→急。「慢性」
 マンナリ{形}ゆるい(ユルシ)。ゆっくり。「慢歩(そぞろ歩き)」
《解字》
会意兼形声。曼マンとは、目をおおい隠すさま。長々とかぶさって広がる意を含む。慢は「心+音符曼」で、ずるずるとだらけて伸びる心のこと。
《単語家族》
幔マン(長く伸びる幕)
マンナリ{形}ゆるい(ユルシ)。ゆっくり。「慢歩(そぞろ歩き)」
《解字》
会意兼形声。曼マンとは、目をおおい隠すさま。長々とかぶさって広がる意を含む。慢は「心+音符曼」で、ずるずるとだらけて伸びる心のこと。
《単語家族》
幔マン(長く伸びる幕) 蔓マン(草がずるずると伸び広がる)
蔓マン(草がずるずると伸び広がる) 綿(長く伸びる糸)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
綿(長く伸びる糸)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
抒 ゆるめる🔗⭐🔉
【抒】
 7画
7画  部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ
部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
 ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
 ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
 {動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける)
{動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける) 捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画
7画  部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ
部
区点=5719 16進=5933 シフトJIS=9D52
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のばす/とく/ゆるめる(ゆるむ)/くむ
《意味》
 ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
ジョス{動}のべる(ノブ)。のばす。心中の思いをおしのべて展開する。また、固まりを押し広げる。〈同義語〉→叙ジヨ(のべる)。「抒情ジョジョウ」「抒懐ジョカイ」
 ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
ジョス{動}とく。ゆるめる(ユルム)。固まりをほぐしてゆるめる。〈同義語〉→徐ジョ・→除ジョ。「抒念=念ヲ抒ス」
 {動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける)
{動}くむ。たまったものをくみ出す。
《解字》
会意兼形声。予ヨは、あるものを押し出してのばすさま。抒は「手+音符予」で、のばす動作を示す。→予
《単語家族》
除(押しのける) 捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨シャ(ゆるめる)と同系。また、叙(のべる)と最も近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
揺 ゆる🔗⭐🔉
【揺】
 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=4541 16進=4D49 シフトJIS=9768
【搖】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=4541 16進=4D49 シフトJIS=9768
【搖】旧字人名に使える旧字
 13画
13画  部
区点=5774 16進=596A シフトJIS=9D8A
《常用音訓》ヨウ/ゆ…さぶる/ゆ…すぶる/ゆ…する/ゆ…らぐ/ゆ…る/ゆ…るぐ/ゆ…れる
《音読み》 ヨウ(エウ)
部
区点=5774 16進=596A シフトJIS=9D8A
《常用音訓》ヨウ/ゆ…さぶる/ゆ…すぶる/ゆ…する/ゆ…らぐ/ゆ…る/ゆ…るぐ/ゆ…れる
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o〉
《訓読み》 ゆらぐ/ゆるぐ/ゆさぶる/ゆすぶる/ゆれる(ゆる)/ゆる/ゆるがす/ゆする
《意味》
{動}ゆれる(ユル)。ゆる。ゆるがす。ゆする。ゆらゆらと曲線をなして動く。また、そのように動かす。「動揺」「揺手=手ヲ揺ル」「揺其本=ソノ本ヲ揺ルガス」〔→柳宗元〕
《解字》
o〉
《訓読み》 ゆらぐ/ゆるぐ/ゆさぶる/ゆすぶる/ゆれる(ゆる)/ゆる/ゆるがす/ゆする
《意味》
{動}ゆれる(ユル)。ゆる。ゆるがす。ゆする。ゆらゆらと曲線をなして動く。また、そのように動かす。「動揺」「揺手=手ヲ揺ル」「揺其本=ソノ本ヲ揺ルガス」〔→柳宗元〕
《解字》
 形声。右側の字は「肉+缶(ほとぎ)」の会意文字で、肉をこねる器。ここでは音をあらわす。搖は、ゆらゆらと固定せず動くこと。游ユウ(ゆらゆら)と非常に近い。
《単語家族》
謠ヨウ(=謡。声を長くゆらせて歌う)
形声。右側の字は「肉+缶(ほとぎ)」の会意文字で、肉をこねる器。ここでは音をあらわす。搖は、ゆらゆらと固定せず動くこと。游ユウ(ゆらゆら)と非常に近い。
《単語家族》
謠ヨウ(=謡。声を長くゆらせて歌う) 遥ヨウ(=遥。はるかにゆらゆらと伸びる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遥ヨウ(=遥。はるかにゆらゆらと伸びる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=4541 16進=4D49 シフトJIS=9768
【搖】旧字人名に使える旧字
部 [常用漢字]
区点=4541 16進=4D49 シフトJIS=9768
【搖】旧字人名に使える旧字
 13画
13画  部
区点=5774 16進=596A シフトJIS=9D8A
《常用音訓》ヨウ/ゆ…さぶる/ゆ…すぶる/ゆ…する/ゆ…らぐ/ゆ…る/ゆ…るぐ/ゆ…れる
《音読み》 ヨウ(エウ)
部
区点=5774 16進=596A シフトJIS=9D8A
《常用音訓》ヨウ/ゆ…さぶる/ゆ…すぶる/ゆ…する/ゆ…らぐ/ゆ…る/ゆ…るぐ/ゆ…れる
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o〉
《訓読み》 ゆらぐ/ゆるぐ/ゆさぶる/ゆすぶる/ゆれる(ゆる)/ゆる/ゆるがす/ゆする
《意味》
{動}ゆれる(ユル)。ゆる。ゆるがす。ゆする。ゆらゆらと曲線をなして動く。また、そのように動かす。「動揺」「揺手=手ヲ揺ル」「揺其本=ソノ本ヲ揺ルガス」〔→柳宗元〕
《解字》
o〉
《訓読み》 ゆらぐ/ゆるぐ/ゆさぶる/ゆすぶる/ゆれる(ゆる)/ゆる/ゆるがす/ゆする
《意味》
{動}ゆれる(ユル)。ゆる。ゆるがす。ゆする。ゆらゆらと曲線をなして動く。また、そのように動かす。「動揺」「揺手=手ヲ揺ル」「揺其本=ソノ本ヲ揺ルガス」〔→柳宗元〕
《解字》
 形声。右側の字は「肉+缶(ほとぎ)」の会意文字で、肉をこねる器。ここでは音をあらわす。搖は、ゆらゆらと固定せず動くこと。游ユウ(ゆらゆら)と非常に近い。
《単語家族》
謠ヨウ(=謡。声を長くゆらせて歌う)
形声。右側の字は「肉+缶(ほとぎ)」の会意文字で、肉をこねる器。ここでは音をあらわす。搖は、ゆらゆらと固定せず動くこと。游ユウ(ゆらゆら)と非常に近い。
《単語家族》
謠ヨウ(=謡。声を長くゆらせて歌う) 遥ヨウ(=遥。はるかにゆらゆらと伸びる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遥ヨウ(=遥。はるかにゆらゆらと伸びる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
緩 ゆるい🔗⭐🔉
【緩】
 15画 糸部 [常用漢字]
区点=2043 16進=344B シフトJIS=8AC9
《常用音訓》カン/ゆる…い/ゆる…む/ゆる…める/ゆる…やか
《音読み》 カン(ク
15画 糸部 [常用漢字]
区点=2043 16進=344B シフトJIS=8AC9
《常用音訓》カン/ゆる…い/ゆる…む/ゆる…める/ゆる…やか
《音読み》 カン(ク ン)
ン) /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) 〈hu
〈hu n〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるい(ゆるし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるめる(ゆるむ)/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 のぶ・ひろ・ふさ・やす
《意味》
n〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるい(ゆるし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるめる(ゆるむ)/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 のぶ・ひろ・ふさ・やす
《意味》
 {形}ゆるい(ユルシ)。ゆるやか(ユルヤカナリ)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるさま。しめつけていない。ゆったり。ゆっくり。〈対語〉→急・→緊。「衣帯日已緩=衣帯日ニスデニ緩シ」〔→古詩十九首〕
{形}ゆるい(ユルシ)。ゆるやか(ユルヤカナリ)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるさま。しめつけていない。ゆったり。ゆっくり。〈対語〉→急・→緊。「衣帯日已緩=衣帯日ニスデニ緩シ」〔→古詩十九首〕
 カンニス{動}ゆるめる(ユルム)。ゆるくする(ユルクス)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるようにする。ゆるめる。ゆったりする。ゆっくりする。手をぬく。「緩刑=刑ヲ緩ニス」「君子以議獄緩死=君子ハモッテ獄ヲ議リ死ヲ緩クス」〔→易経〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符爰エン(間に仲介をはさむ、ゆとりをおく)」で、結びめの間にゆとりをあけること。
《単語家族》
換(するりと抜きとる)
カンニス{動}ゆるめる(ユルム)。ゆるくする(ユルクス)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるようにする。ゆるめる。ゆったりする。ゆっくりする。手をぬく。「緩刑=刑ヲ緩ニス」「君子以議獄緩死=君子ハモッテ獄ヲ議リ死ヲ緩クス」〔→易経〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符爰エン(間に仲介をはさむ、ゆとりをおく)」で、結びめの間にゆとりをあけること。
《単語家族》
換(するりと抜きとる) 寛(ゆとりがある)と同系。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
寛(ゆとりがある)と同系。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 糸部 [常用漢字]
区点=2043 16進=344B シフトJIS=8AC9
《常用音訓》カン/ゆる…い/ゆる…む/ゆる…める/ゆる…やか
《音読み》 カン(ク
15画 糸部 [常用漢字]
区点=2043 16進=344B シフトJIS=8AC9
《常用音訓》カン/ゆる…い/ゆる…む/ゆる…める/ゆる…やか
《音読み》 カン(ク ン)
ン) /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) 〈hu
〈hu n〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるい(ゆるし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるめる(ゆるむ)/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 のぶ・ひろ・ふさ・やす
《意味》
n〉
《訓読み》 ゆるむ/ゆるい(ゆるし)/ゆるやか(ゆるやかなり)/ゆるめる(ゆるむ)/ゆるくする(ゆるくす)
《名付け》 のぶ・ひろ・ふさ・やす
《意味》
 {形}ゆるい(ユルシ)。ゆるやか(ユルヤカナリ)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるさま。しめつけていない。ゆったり。ゆっくり。〈対語〉→急・→緊。「衣帯日已緩=衣帯日ニスデニ緩シ」〔→古詩十九首〕
{形}ゆるい(ユルシ)。ゆるやか(ユルヤカナリ)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるさま。しめつけていない。ゆったり。ゆっくり。〈対語〉→急・→緊。「衣帯日已緩=衣帯日ニスデニ緩シ」〔→古詩十九首〕
 カンニス{動}ゆるめる(ユルム)。ゆるくする(ユルクス)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるようにする。ゆるめる。ゆったりする。ゆっくりする。手をぬく。「緩刑=刑ヲ緩ニス」「君子以議獄緩死=君子ハモッテ獄ヲ議リ死ヲ緩クス」〔→易経〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符爰エン(間に仲介をはさむ、ゆとりをおく)」で、結びめの間にゆとりをあけること。
《単語家族》
換(するりと抜きとる)
カンニス{動}ゆるめる(ユルム)。ゆるくする(ユルクス)。空間的、時間的、精神的にゆとりのあるようにする。ゆるめる。ゆったりする。ゆっくりする。手をぬく。「緩刑=刑ヲ緩ニス」「君子以議獄緩死=君子ハモッテ獄ヲ議リ死ヲ緩クス」〔→易経〕
《解字》
会意兼形声。「糸+音符爰エン(間に仲介をはさむ、ゆとりをおく)」で、結びめの間にゆとりをあけること。
《単語家族》
換(するりと抜きとる) 寛(ゆとりがある)と同系。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
寛(ゆとりがある)と同系。
《類義》
→弛
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縦 ゆるす🔗⭐🔉
【縦】
 16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
 17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ
17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ /ショウ
/ショウ /シュ
/シュ 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
 {名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
 {形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
 {動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
16画 糸部 [六年]
区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63
【縱】旧字人名に使える旧字
 17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ
17画 糸部
区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373
《常用音訓》ジュウ/たて
《音読み》 ジュウ /ショウ
/ショウ /シュ
/シュ 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
ng〉
《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)
《名付け》 なお
《意味》
 {名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」
 {形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」
 {動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕
 {動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕
 {接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。
《類義》
→肆
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縵 ゆるい🔗⭐🔉
能 ゆるす🔗⭐🔉
【能】
 10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》
10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》  ノウ/ノ
ノウ/ノ /ドウ
/ドウ 〈n
〈n ng〉/
ng〉/ ダイ
ダイ /ナイ
/ナイ /タイ
/タイ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》

 {動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
 {名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
 {形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
 {動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕
{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

 {動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
 {名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
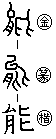 会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》
10画 肉部 [五年]
区点=3929 16進=473D シフトJIS=945C
《常用音訓》ノウ
《音読み》  ノウ/ノ
ノウ/ノ /ドウ
/ドウ 〈n
〈n ng〉/
ng〉/ ダイ
ダイ /ナイ
/ナイ /タイ
/タイ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 あたう(あたふ)/よくする(よくす)/よく/ゆるす/たえる(たふ)/のう
《名付け》 たか・ちから・とう・のり・ひさ・みち・むね・やす・よき・よし
《意味》

 {動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
{動・助動}あたう(アタフ)。よくする(ヨクス)。よく。物事をなしうる力や体力があってできる。たえうる。りっぱにたえて。しっかりと。「非不能也=能ハザルニアラザルナリ」〔→孟子〕「能近取譬=能ク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕
 {名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
{名}事をやりうる力。はたらき。「有能」「技能」「才能」
 {形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
{形}やりての。仕事たっしゃな。「能弁」「能者」
 {動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕
{動}ゆるす。やんわりとたえる。柔らかに接する。「柔遠能邇=遠キヲ柔ラゲ邇キヲ能ス」〔→詩経〕

 {動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
{動}たえる(タフ)。物事をなしうるだけの力がある。また、仕事をなしうる力があって任にたえる。〈同義語〉→耐タイ。「鳥獣毳毛其性能寒=鳥獣ノ毳毛ハソノ性、寒キニ能フ」〔→漢書〕
 {名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
{名}ねばり強いかめ。▽平声に読む。
〔国〕のう。能楽のこと。
《解字》
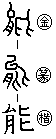 会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意兼形声。厶イ(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+音符厶」で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす。▽熊ユウ(ねばり強いくま)の字の上部と同じ。
《類義》
→耐
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
舒 ゆるい🔗⭐🔉
【舒】
 12画 舌部
区点=4816 16進=5030 シフトJIS=98AE
《音読み》 ジョ
12画 舌部
区点=4816 16進=5030 シフトJIS=98AE
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のびる(のぶ)/のばす/ゆるい(ゆるし)
《意味》
〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のびる(のぶ)/のばす/ゆるい(ゆるし)
《意味》
 {動}のべる(ノブ)。のびる(ノブ)。のばす。巻いたもの、かたまったものをのばし広げる。また、横にのびる。「展舒テンジョ(のばし広げる)」「舒眉=眉ヲ舒ス」「其本欲舒=ソノ本ハ舒ビント欲ス」〔→柳宗元〕
{動}のべる(ノブ)。のびる(ノブ)。のばす。巻いたもの、かたまったものをのばし広げる。また、横にのびる。「展舒テンジョ(のばし広げる)」「舒眉=眉ヲ舒ス」「其本欲舒=ソノ本ハ舒ビント欲ス」〔→柳宗元〕
 {形}ゆるい(ユルシ)。気持ちがのびのびしているさま。また、のんびりとしておそいさま。〈類義語〉→徐(のろい)。「舒緩ジョカン」「舒遅ジョチ」
{形}ゆるい(ユルシ)。気持ちがのびのびしているさま。また、のんびりとしておそいさま。〈類義語〉→徐(のろい)。「舒緩ジョカン」「舒遅ジョチ」
 {動}のべる(ノブ)。心中の思いをのべる。▽叙ジョに当てた用法。
{動}のべる(ノブ)。心中の思いをのべる。▽叙ジョに当てた用法。
 {名}春秋時代、華中にあった国の名。
{名}春秋時代、華中にあった国の名。
 「望舒ボウジョ」とは、月の神。また、月のこと。
《解字》
会意兼形声。予ヨの原字は、□印のものを下に引いてずらせたさまで、ずらせてのばすの意を含む。舎は手足をのばして休む所。舒は「舎+予」で、どちらを音符とみてもよい。
《単語家族》
徐(のんびりといく)
「望舒ボウジョ」とは、月の神。また、月のこと。
《解字》
会意兼形声。予ヨの原字は、□印のものを下に引いてずらせたさまで、ずらせてのばすの意を含む。舎は手足をのばして休む所。舒は「舎+予」で、どちらを音符とみてもよい。
《単語家族》
徐(のんびりといく) 余(ゆとりがある、ゆったりのびたさま)
余(ゆとりがある、ゆったりのびたさま) 豫(=予。ゆとりがある)などと同系。
《類義》
→伸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
豫(=予。ゆとりがある)などと同系。
《類義》
→伸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 舌部
区点=4816 16進=5030 シフトJIS=98AE
《音読み》 ジョ
12画 舌部
区点=4816 16進=5030 シフトJIS=98AE
《音読み》 ジョ /ショ
/ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のびる(のぶ)/のばす/ゆるい(ゆるし)
《意味》
〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のびる(のぶ)/のばす/ゆるい(ゆるし)
《意味》
 {動}のべる(ノブ)。のびる(ノブ)。のばす。巻いたもの、かたまったものをのばし広げる。また、横にのびる。「展舒テンジョ(のばし広げる)」「舒眉=眉ヲ舒ス」「其本欲舒=ソノ本ハ舒ビント欲ス」〔→柳宗元〕
{動}のべる(ノブ)。のびる(ノブ)。のばす。巻いたもの、かたまったものをのばし広げる。また、横にのびる。「展舒テンジョ(のばし広げる)」「舒眉=眉ヲ舒ス」「其本欲舒=ソノ本ハ舒ビント欲ス」〔→柳宗元〕
 {形}ゆるい(ユルシ)。気持ちがのびのびしているさま。また、のんびりとしておそいさま。〈類義語〉→徐(のろい)。「舒緩ジョカン」「舒遅ジョチ」
{形}ゆるい(ユルシ)。気持ちがのびのびしているさま。また、のんびりとしておそいさま。〈類義語〉→徐(のろい)。「舒緩ジョカン」「舒遅ジョチ」
 {動}のべる(ノブ)。心中の思いをのべる。▽叙ジョに当てた用法。
{動}のべる(ノブ)。心中の思いをのべる。▽叙ジョに当てた用法。
 {名}春秋時代、華中にあった国の名。
{名}春秋時代、華中にあった国の名。
 「望舒ボウジョ」とは、月の神。また、月のこと。
《解字》
会意兼形声。予ヨの原字は、□印のものを下に引いてずらせたさまで、ずらせてのばすの意を含む。舎は手足をのばして休む所。舒は「舎+予」で、どちらを音符とみてもよい。
《単語家族》
徐(のんびりといく)
「望舒ボウジョ」とは、月の神。また、月のこと。
《解字》
会意兼形声。予ヨの原字は、□印のものを下に引いてずらせたさまで、ずらせてのばすの意を含む。舎は手足をのばして休む所。舒は「舎+予」で、どちらを音符とみてもよい。
《単語家族》
徐(のんびりといく) 余(ゆとりがある、ゆったりのびたさま)
余(ゆとりがある、ゆったりのびたさま) 豫(=予。ゆとりがある)などと同系。
《類義》
→伸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
豫(=予。ゆとりがある)などと同系。
《類義》
→伸
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
許 ゆるす🔗⭐🔉
【許】
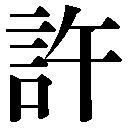 11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ
11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
 {動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
 {動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
 {名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
 {助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
 {名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
 {助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
 「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
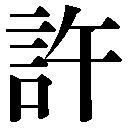 11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ
11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
 {動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
 {動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
 {名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
 {助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
 {名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
 {助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
 「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
貰 ゆるす🔗⭐🔉
【貰】
 12画 貝部
区点=4467 16進=4C63 シフトJIS=96E1
《音読み》 セイ
12画 貝部
区点=4467 16進=4C63 シフトJIS=96E1
《音読み》 セイ /セ
/セ /シャ
/シャ /ジャ
/ジャ 〈sh
〈sh 〉〈sh
〉〈sh 〉
《訓読み》 おきのる/ゆるす/もらう(もらふ)
《意味》
〉
《訓読み》 おきのる/ゆるす/もらう(もらふ)
《意味》
 セイス{動}おきのる。品物を先にやりとりして、支払いをのばす。かけ売りや、つけ買いをする。「貰買セイバイ(つけで買う)」「請貰宜陽一壺酒=請ヒテ貰ス宜陽一壺ノ酒」〔→李賀〕
セイス{動}おきのる。品物を先にやりとりして、支払いをのばす。かけ売りや、つけ買いをする。「貰買セイバイ(つけで買う)」「請貰宜陽一壺酒=請ヒテ貰ス宜陽一壺ノ酒」〔→李賀〕
 {動}ゆるす。処罰をのばして、とりあえずゆるしておく。「貰罪=罪ヲ貰ス」
〔国〕もらう(モラフ)。支払いをのばして品物を先にもらうことから、贈り物をうける。また、人の助けをうける。「賞品を貰う」「書いて貰う」
《解字》
会意兼形声。世セ・セイは、十印を三つあわせて、三十年(一世代)をあらわす会意文字で、長びくの意を含む。貰は「貝(財貨)+音符世」で、財貨の支払いを長びかせ、先にのばすこと。
《単語家族》
曳エイ
{動}ゆるす。処罰をのばして、とりあえずゆるしておく。「貰罪=罪ヲ貰ス」
〔国〕もらう(モラフ)。支払いをのばして品物を先にもらうことから、贈り物をうける。また、人の助けをうける。「賞品を貰う」「書いて貰う」
《解字》
会意兼形声。世セ・セイは、十印を三つあわせて、三十年(一世代)をあらわす会意文字で、長びくの意を含む。貰は「貝(財貨)+音符世」で、財貨の支払いを長びかせ、先にのばすこと。
《単語家族》
曳エイ 泄エイ(水が尾を引いてもれる)と同系。
《熟語》
→熟語
泄エイ(水が尾を引いてもれる)と同系。
《熟語》
→熟語
 12画 貝部
区点=4467 16進=4C63 シフトJIS=96E1
《音読み》 セイ
12画 貝部
区点=4467 16進=4C63 シフトJIS=96E1
《音読み》 セイ /セ
/セ /シャ
/シャ /ジャ
/ジャ 〈sh
〈sh 〉〈sh
〉〈sh 〉
《訓読み》 おきのる/ゆるす/もらう(もらふ)
《意味》
〉
《訓読み》 おきのる/ゆるす/もらう(もらふ)
《意味》
 セイス{動}おきのる。品物を先にやりとりして、支払いをのばす。かけ売りや、つけ買いをする。「貰買セイバイ(つけで買う)」「請貰宜陽一壺酒=請ヒテ貰ス宜陽一壺ノ酒」〔→李賀〕
セイス{動}おきのる。品物を先にやりとりして、支払いをのばす。かけ売りや、つけ買いをする。「貰買セイバイ(つけで買う)」「請貰宜陽一壺酒=請ヒテ貰ス宜陽一壺ノ酒」〔→李賀〕
 {動}ゆるす。処罰をのばして、とりあえずゆるしておく。「貰罪=罪ヲ貰ス」
〔国〕もらう(モラフ)。支払いをのばして品物を先にもらうことから、贈り物をうける。また、人の助けをうける。「賞品を貰う」「書いて貰う」
《解字》
会意兼形声。世セ・セイは、十印を三つあわせて、三十年(一世代)をあらわす会意文字で、長びくの意を含む。貰は「貝(財貨)+音符世」で、財貨の支払いを長びかせ、先にのばすこと。
《単語家族》
曳エイ
{動}ゆるす。処罰をのばして、とりあえずゆるしておく。「貰罪=罪ヲ貰ス」
〔国〕もらう(モラフ)。支払いをのばして品物を先にもらうことから、贈り物をうける。また、人の助けをうける。「賞品を貰う」「書いて貰う」
《解字》
会意兼形声。世セ・セイは、十印を三つあわせて、三十年(一世代)をあらわす会意文字で、長びくの意を含む。貰は「貝(財貨)+音符世」で、財貨の支払いを長びかせ、先にのばすこと。
《単語家族》
曳エイ 泄エイ(水が尾を引いてもれる)と同系。
《熟語》
→熟語
泄エイ(水が尾を引いてもれる)と同系。
《熟語》
→熟語
貸 ゆるす🔗⭐🔉
【貸】
 12画 貝部 [五年]
区点=3463 16進=425F シフトJIS=91DD
《常用音訓》タイ/か…す
《音読み》 タイ
12画 貝部 [五年]
区点=3463 16進=425F シフトJIS=91DD
《常用音訓》タイ/か…す
《音読み》 タイ
 〈d
〈d i〉
《訓読み》 かす/かし/ゆるす
《意味》
i〉
《訓読み》 かす/かし/ゆるす
《意味》
 {動・名}かす。かし。あとで返してもらう約束で、金品を人に与える。また、かし出した金品。▽まれに、かり入れるの意にも用いる。〈対語〉→借(かりる)。「賃貸チンタイ」
{動・名}かす。かし。あとで返してもらう約束で、金品を人に与える。また、かし出した金品。▽まれに、かり入れるの意にも用いる。〈対語〉→借(かりる)。「賃貸チンタイ」
 {動}ゆるす。ゆとりを与える。寛大に扱う。「貸宥タイユウ」「厳究不貸=厳究シテ貸サズ」
《解字》
会意兼形声。代は肩がわりすること。貸は「貝(財貨)+音符代」で、金品の所有を肩がわりすること。当人にひと息つくゆとりを与えることから、転じて、ゆとりを与えること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ゆるす。ゆとりを与える。寛大に扱う。「貸宥タイユウ」「厳究不貸=厳究シテ貸サズ」
《解字》
会意兼形声。代は肩がわりすること。貸は「貝(財貨)+音符代」で、金品の所有を肩がわりすること。当人にひと息つくゆとりを与えることから、転じて、ゆとりを与えること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 貝部 [五年]
区点=3463 16進=425F シフトJIS=91DD
《常用音訓》タイ/か…す
《音読み》 タイ
12画 貝部 [五年]
区点=3463 16進=425F シフトJIS=91DD
《常用音訓》タイ/か…す
《音読み》 タイ
 〈d
〈d i〉
《訓読み》 かす/かし/ゆるす
《意味》
i〉
《訓読み》 かす/かし/ゆるす
《意味》
 {動・名}かす。かし。あとで返してもらう約束で、金品を人に与える。また、かし出した金品。▽まれに、かり入れるの意にも用いる。〈対語〉→借(かりる)。「賃貸チンタイ」
{動・名}かす。かし。あとで返してもらう約束で、金品を人に与える。また、かし出した金品。▽まれに、かり入れるの意にも用いる。〈対語〉→借(かりる)。「賃貸チンタイ」
 {動}ゆるす。ゆとりを与える。寛大に扱う。「貸宥タイユウ」「厳究不貸=厳究シテ貸サズ」
《解字》
会意兼形声。代は肩がわりすること。貸は「貝(財貨)+音符代」で、金品の所有を肩がわりすること。当人にひと息つくゆとりを与えることから、転じて、ゆとりを与えること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}ゆるす。ゆとりを与える。寛大に扱う。「貸宥タイユウ」「厳究不貸=厳究シテ貸サズ」
《解字》
会意兼形声。代は肩がわりすること。貸は「貝(財貨)+音符代」で、金品の所有を肩がわりすること。当人にひと息つくゆとりを与えることから、転じて、ゆとりを与えること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
赦 ゆるし🔗⭐🔉
【赦】
 11画 赤部 [常用漢字]
区点=2847 16進=3C4F シフトJIS=8ECD
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
11画 赤部 [常用漢字]
区点=2847 16進=3C4F シフトJIS=8ECD
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 ゆるす/ゆるし
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/ゆるし
《意味》
 {動}ゆるす。大目にみる。いましめをとく。罪・あやまちをとがめない。「赦免」「君子以赦過宥罪=君子モッテ過チヲ赦シ、罪ヲ宥ム」〔→易経〕
{動}ゆるす。大目にみる。いましめをとく。罪・あやまちをとがめない。「赦免」「君子以赦過宥罪=君子モッテ過チヲ赦シ、罪ヲ宥ム」〔→易経〕
 {名}ゆるし。刑罰・罪をゆるすこと。「赦従重=赦ハ重キヨリス」〔→礼記〕
《解字》
形声。「攴(動詞の記号)+音符赤」で、赤(あか)には関係がない。ゆるむ、のびるの意味を含む。
《単語家族》
舒(ゆるくのびる)
{名}ゆるし。刑罰・罪をゆるすこと。「赦従重=赦ハ重キヨリス」〔→礼記〕
《解字》
形声。「攴(動詞の記号)+音符赤」で、赤(あか)には関係がない。ゆるむ、のびるの意味を含む。
《単語家族》
舒(ゆるくのびる) 捨(手を放して放置する)と同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨(手を放して放置する)と同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 赤部 [常用漢字]
区点=2847 16進=3C4F シフトJIS=8ECD
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
11画 赤部 [常用漢字]
区点=2847 16進=3C4F シフトJIS=8ECD
《常用音訓》シャ
《音読み》 シャ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 ゆるす/ゆるし
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/ゆるし
《意味》
 {動}ゆるす。大目にみる。いましめをとく。罪・あやまちをとがめない。「赦免」「君子以赦過宥罪=君子モッテ過チヲ赦シ、罪ヲ宥ム」〔→易経〕
{動}ゆるす。大目にみる。いましめをとく。罪・あやまちをとがめない。「赦免」「君子以赦過宥罪=君子モッテ過チヲ赦シ、罪ヲ宥ム」〔→易経〕
 {名}ゆるし。刑罰・罪をゆるすこと。「赦従重=赦ハ重キヨリス」〔→礼記〕
《解字》
形声。「攴(動詞の記号)+音符赤」で、赤(あか)には関係がない。ゆるむ、のびるの意味を含む。
《単語家族》
舒(ゆるくのびる)
{名}ゆるし。刑罰・罪をゆるすこと。「赦従重=赦ハ重キヨリス」〔→礼記〕
《解字》
形声。「攴(動詞の記号)+音符赤」で、赤(あか)には関係がない。ゆるむ、のびるの意味を含む。
《単語家族》
舒(ゆるくのびる) 捨(手を放して放置する)と同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
捨(手を放して放置する)と同系。
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
釈 ゆるす🔗⭐🔉
【釈】
 11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
 20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク
20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク /セキ
/セキ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
 {動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
{動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
 {動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
{動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
 {動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
{動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
 {名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す)
{名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す) 驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場)
驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場) 譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
11画 釆部 [常用漢字]
区点=2865 16進=3C61 シフトJIS=8EDF
【釋】旧字旧字
 20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク
20画 釆部
区点=7857 16進=6E59 シフトJIS=E7D7
《常用音訓》シャク
《音読み》 シャク /セキ
/セキ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
〉
《訓読み》 とく/とける(とく)/ゆるす/おく/すてる(すつ)
《名付け》 とき
《意味》
 {動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
{動・名}とく。とける(トク)。しめて固めたものを、一つ一つときほぐす。わからない部分やしこりをときほぐす。また、とけほぐれる。ときほぐした説明。「釈甲(よろいのひもをとく)」「氷釈(氷がとけるようにほぐれる)」「釈然(しこりがとけてさっぱりする)」「主人釈服=主人服ヲ釈ク」〔→儀礼〕「渙兮若氷之将釈=渙トシテ氷ノマサニ釈ケントスルガゴトシ」〔→老子〕
 {動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
{動}とく。ゆるす。いましめや束縛をとく。〈類義語〉→赦シャ。「保釈」「釈箕子之囚=箕子ノ囚ヲ釈ク」〔→史記〕
 {動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
{動}おく。すてる(スツ)。つかんだものを放しておく。〈類義語〉→捨・→舎。「釈奠セキテン(供物をおいてまつる→孔子をまつる祭り)」「堅持不釈=堅持シテ釈カズ」
 {名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す)
{名}「釈迦シャカ」の略。ほとけ。また、仏教。「釈氏」「釈門」「釈老(仏教と道教)」
《解字》
会意兼形声。釋の右側の字(音エキ)は「目+幸(刑具)」から成り、手かせをはめた罪人を、ひとりずつ並べて面通しをすること。釋はそれを音符とし、釆(ばらばらにわける)を加えた字で、しこりをばらばらにほぐし、一つずつわけて一本の線に連ねること。釈は、音符を尺にかえた略字。
《単語家族》
繹エキ(一つずつ連ねて引き出す) 驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場)
驛エキ(=駅。線上に一つ一つと連なった宿場) 譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
譯ヤク(=訳。ことばをほぐして連ねる)と同系。
《類義》
解は、ばらばらに分解すること。赦シャ・捨シャは、ゆるめること。説は、ときはなすこと。許は、上下にずれや幅をもたせてゆるすこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
闊 ゆるい🔗⭐🔉
【闊】
 17画 門部
区点=7972 16進=6F68 シフトJIS=E888
【濶】異体字異体字
17画 門部
区点=7972 16進=6F68 シフトJIS=E888
【濶】異体字異体字
 17画 水部
区点=7973 16進=6F69 シフトJIS=E889
《音読み》 カツ(ク
17画 水部
区点=7973 16進=6F69 シフトJIS=E889
《音読み》 カツ(ク ツ)
ツ) /カチ(ク
/カチ(ク チ)
チ) 〈ku
〈ku 〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/はるか(はるかなり)/ゆるい(ゆるし)/ゆるくする(ゆるくす)
《意味》
〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/はるか(はるかなり)/ゆるい(ゆるし)/ゆるくする(ゆるくす)
《意味》
 {形}ひろい(ヒロシ)。ひろびろとしている。また、人の度量が大きい。「快闊カイカツ」「水闊雲多客到稀=水闊ク雲多クシテ客到ルコト稀ナリ」〔→白居易〕
{形}ひろい(ヒロシ)。ひろびろとしている。また、人の度量が大きい。「快闊カイカツ」「水闊雲多客到稀=水闊ク雲多クシテ客到ルコト稀ナリ」〔→白居易〕
 {形}はるか(ハルカナリ)。間が広くあいているさま。まがぬけているさま。遠く離れているさま。また、疎遠であるさま。「久闊キュウカツ」「迂闊ウカツ」「于嗟闊兮、不我活兮=アア闊カナリ、我ト活キズ」〔→詩経〕
{形}はるか(ハルカナリ)。間が広くあいているさま。まがぬけているさま。遠く離れているさま。また、疎遠であるさま。「久闊キュウカツ」「迂闊ウカツ」「于嗟闊兮、不我活兮=アア闊カナリ、我ト活キズ」〔→詩経〕
 {形・動}ゆるい(ユルシ)。ゆるくする(ユルクス)。ゆとりがあるさま。ゆるめる。〈対語〉→狭・→迫。「闊其租賦=ソノ租賦ヲ闊クス」〔→漢書〕
{形・動}ゆるい(ユルシ)。ゆるくする(ユルクス)。ゆとりがあるさま。ゆるめる。〈対語〉→狭・→迫。「闊其租賦=ソノ租賦ヲ闊クス」〔→漢書〕
 {形}おおまかである。「闊達カッタツ」
《解字》
会意兼形声。活は、水が勢いよく流れること。ゆとりがあって、つかえない意を含む。闊は「門+音符活」。寛(ゆとりがある)の語尾がちぢまった形。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}おおまかである。「闊達カッタツ」
《解字》
会意兼形声。活は、水が勢いよく流れること。ゆとりがあって、つかえない意を含む。闊は「門+音符活」。寛(ゆとりがある)の語尾がちぢまった形。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 17画 門部
区点=7972 16進=6F68 シフトJIS=E888
【濶】異体字異体字
17画 門部
区点=7972 16進=6F68 シフトJIS=E888
【濶】異体字異体字
 17画 水部
区点=7973 16進=6F69 シフトJIS=E889
《音読み》 カツ(ク
17画 水部
区点=7973 16進=6F69 シフトJIS=E889
《音読み》 カツ(ク ツ)
ツ) /カチ(ク
/カチ(ク チ)
チ) 〈ku
〈ku 〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/はるか(はるかなり)/ゆるい(ゆるし)/ゆるくする(ゆるくす)
《意味》
〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/はるか(はるかなり)/ゆるい(ゆるし)/ゆるくする(ゆるくす)
《意味》
 {形}ひろい(ヒロシ)。ひろびろとしている。また、人の度量が大きい。「快闊カイカツ」「水闊雲多客到稀=水闊ク雲多クシテ客到ルコト稀ナリ」〔→白居易〕
{形}ひろい(ヒロシ)。ひろびろとしている。また、人の度量が大きい。「快闊カイカツ」「水闊雲多客到稀=水闊ク雲多クシテ客到ルコト稀ナリ」〔→白居易〕
 {形}はるか(ハルカナリ)。間が広くあいているさま。まがぬけているさま。遠く離れているさま。また、疎遠であるさま。「久闊キュウカツ」「迂闊ウカツ」「于嗟闊兮、不我活兮=アア闊カナリ、我ト活キズ」〔→詩経〕
{形}はるか(ハルカナリ)。間が広くあいているさま。まがぬけているさま。遠く離れているさま。また、疎遠であるさま。「久闊キュウカツ」「迂闊ウカツ」「于嗟闊兮、不我活兮=アア闊カナリ、我ト活キズ」〔→詩経〕
 {形・動}ゆるい(ユルシ)。ゆるくする(ユルクス)。ゆとりがあるさま。ゆるめる。〈対語〉→狭・→迫。「闊其租賦=ソノ租賦ヲ闊クス」〔→漢書〕
{形・動}ゆるい(ユルシ)。ゆるくする(ユルクス)。ゆとりがあるさま。ゆるめる。〈対語〉→狭・→迫。「闊其租賦=ソノ租賦ヲ闊クス」〔→漢書〕
 {形}おおまかである。「闊達カッタツ」
《解字》
会意兼形声。活は、水が勢いよく流れること。ゆとりがあって、つかえない意を含む。闊は「門+音符活」。寛(ゆとりがある)の語尾がちぢまった形。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}おおまかである。「闊達カッタツ」
《解字》
会意兼形声。活は、水が勢いよく流れること。ゆとりがあって、つかえない意を含む。闊は「門+音符活」。寛(ゆとりがある)の語尾がちぢまった形。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
饒 ゆるす🔗⭐🔉
【饒】
 21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ)
21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ) /ニョウ(ネウ)
/ニョウ(ネウ) 〈r
〈r o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
 {形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
 {動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
 {接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符
{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符 (大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる)
(大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる) 搦ニャク・ダク(まげる)
搦ニャク・ダク(まげる) 撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる)
撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる) 遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ)
21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ) /ニョウ(ネウ)
/ニョウ(ネウ) 〈r
〈r o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
 {形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
 {動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
 {接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符
{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符 (大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる)
(大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる) 搦ニャク・ダク(まげる)
搦ニャク・ダク(まげる) 撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる)
撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる) 遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「ゆる」で始まるの検索結果 1-27。
 17画 糸部
区点=6960 16進=655C シフトJIS=E37B
《音読み》
17画 糸部
区点=6960 16進=655C シフトJIS=E37B
《音読み》  18画 髟部
区点=8202 16進=7222 シフトJIS=E9A0
《音読み》 ショウ
18画 髟部
区点=8202 16進=7222 シフトJIS=E9A0
《音読み》 ショウ