複数辞典一括検索+![]()
![]()
丕 おおきい🔗⭐🔉
【丕】
 5画 一部
区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1
《音読み》 ヒ
5画 一部
区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1
《音読み》 ヒ
 〈p
〈p 〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)
《意味》
〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)
《意味》
 {形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。
{形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。
 {形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」
《解字》
{形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」
《解字》
 会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。
《単語家族》
胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ)
会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。
《単語家族》
胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ) 杯ハイ(まるくふくれたさかずき)
杯ハイ(まるくふくれたさかずき) 盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。
《熟語》
→熟語
盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。
《熟語》
→熟語
 5画 一部
区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1
《音読み》 ヒ
5画 一部
区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1
《音読み》 ヒ
 〈p
〈p 〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)
《意味》
〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)
《意味》
 {形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。
{形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。
 {形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」
《解字》
{形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」
《解字》
 会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。
《単語家族》
胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ)
会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。
《単語家族》
胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ) 杯ハイ(まるくふくれたさかずき)
杯ハイ(まるくふくれたさかずき) 盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。
《熟語》
→熟語
盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。
《熟語》
→熟語
巨 おおい🔗⭐🔉
【巨】
 5画 二部 [常用漢字]
区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90
《常用音訓》キョ
《音読み》 キョ
5画 二部 [常用漢字]
区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90
《常用音訓》キョ
《音読み》 キョ /ゴ
/ゴ /コ
/コ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ
《名付け》 お・おお・なお・まさ・み
《意味》
〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ
《名付け》 お・おお・なお・まさ・み
《意味》
 {形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕
{形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕
 {形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」
{形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」
 {名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。
{名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。
 {助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕
《解字》
{助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕
《解字》
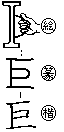 象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。
《単語家族》
距キョ(へだたる)
象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。
《単語家族》
距キョ(へだたる) 渠キョ(両側をへだてたみぞ)
渠キョ(両側をへだてたみぞ) 拒(押しへだてる)と同系。
《熟語》
→熟語
拒(押しへだてる)と同系。
《熟語》
→熟語
 5画 二部 [常用漢字]
区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90
《常用音訓》キョ
《音読み》 キョ
5画 二部 [常用漢字]
区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90
《常用音訓》キョ
《音読み》 キョ /ゴ
/ゴ /コ
/コ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ
《名付け》 お・おお・なお・まさ・み
《意味》
〉
《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ
《名付け》 お・おお・なお・まさ・み
《意味》
 {形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕
{形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕
 {形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」
{形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」
 {名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。
{名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。
 {助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕
《解字》
{助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕
《解字》
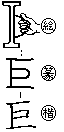 象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。
《単語家族》
距キョ(へだたる)
象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。
《単語家族》
距キョ(へだたる) 渠キョ(両側をへだてたみぞ)
渠キョ(両側をへだてたみぞ) 拒(押しへだてる)と同系。
《熟語》
→熟語
拒(押しへだてる)と同系。
《熟語》
→熟語
亶 おおい🔗⭐🔉
【亶】
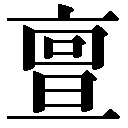 13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》
13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》  タン
タン
 〈d
〈d n〉/
n〉/ セン
セン /ゼン
/ゼン 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》
n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》

 {形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
 {接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
 {副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
 {形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
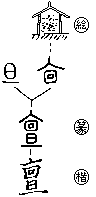 形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
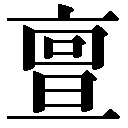 13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》
13画 亠部
区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7
《音読み》  タン
タン
 〈d
〈d n〉/
n〉/ セン
セン /ゼン
/ゼン 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》
n〉
《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに
《意味》

 {形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。
 {接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。
 {副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕
 {形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。
《解字》
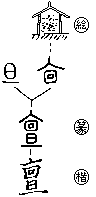 形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。
《熟語》
→主要人名
介 おおきい🔗⭐🔉
【介】
 4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ
4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》

 カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
 カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
 {動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
 {名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
 {形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
 {形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
 {名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。
{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。
四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
 会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界
会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界 堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ
4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》

 カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
 カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
 {動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
 {名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
 {形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
 {形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
 {名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。
{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。
四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
 会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界
会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界 堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
价 おおきい🔗⭐🔉
冖 おおう🔗⭐🔉
【冖】
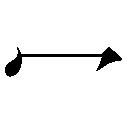 2画 冖部
区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B
《音読み》 ベキ
2画 冖部
区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B
《音読み》 ベキ /ミャク
/ミャク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)
《意味》
{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。
《解字》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)
《意味》
{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。
《解字》
 指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。
指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。
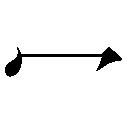 2画 冖部
区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B
《音読み》 ベキ
2画 冖部
区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B
《音読み》 ベキ /ミャク
/ミャク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)
《意味》
{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。
《解字》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)
《意味》
{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。
《解字》
 指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。
指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。
多 おおい🔗⭐🔉
【多】
 6画 夕部 [二年]
区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD
【夛】異体字異体字
6画 夕部 [二年]
区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD
【夛】異体字異体字
 6画 夕部
区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA
《常用音訓》タ/おお…い
《音読み》 タ
6画 夕部
区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA
《常用音訓》タ/おお…い
《音読み》 タ
 〈du
〈du 〉
《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに
《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる
《意味》
〉
《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに
《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる
《意味》
 {形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕
{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕
 タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕
タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕
 {副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕
《解字》
会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。
《単語家族》
亶タン(おおい)
{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕
《解字》
会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。
《単語家族》
亶タン(おおい) 侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 夕部 [二年]
区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD
【夛】異体字異体字
6画 夕部 [二年]
区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD
【夛】異体字異体字
 6画 夕部
区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA
《常用音訓》タ/おお…い
《音読み》 タ
6画 夕部
区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA
《常用音訓》タ/おお…い
《音読み》 タ
 〈du
〈du 〉
《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに
《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる
《意味》
〉
《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに
《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる
《意味》
 {形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕
{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕
 タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕
タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕
 {副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕
《解字》
会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。
《単語家族》
亶タン(おおい)
{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕
《解字》
会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。
《単語家族》
亶タン(おおい) 侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
大 おお🔗⭐🔉
【大】
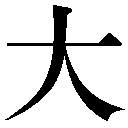 3画 大部 [一年]
区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5
《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい
《音読み》 ダイ
3画 大部 [一年]
区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5
《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい
《音読み》 ダイ /タイ
/タイ /タ
/タ /ダ
/ダ 〈d
〈d i〉〈d
i〉〈d 〉
《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ
《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか
《意味》
〉
《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ
《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか
《意味》
 ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
 {副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕
{副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕
 {副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕
{副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕
 {形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」
{形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」
 ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。
ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。
 {形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」
{形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」
 {数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。
《解字》
{数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。
《解字》
 象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。
《単語家族》
泰タイ・太と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。
《単語家族》
泰タイ・太と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
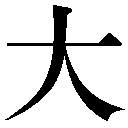 3画 大部 [一年]
区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5
《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい
《音読み》 ダイ
3画 大部 [一年]
区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5
《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい
《音読み》 ダイ /タイ
/タイ /タ
/タ /ダ
/ダ 〈d
〈d i〉〈d
i〉〈d 〉
《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ
《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか
《意味》
〉
《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ
《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか
《意味》
 ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕
 {副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕
{副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕
 {副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕
{副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕
 {形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」
{形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」
 ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。
ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。
 {形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」
{形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」
 {数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。
《解字》
{数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。
《解字》
 象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。
《単語家族》
泰タイ・太と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。
《単語家族》
泰タイ・太と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
大内 オオウチ🔗⭐🔉
【大内】
 ダイダイ・ダイナイ
ダイダイ・ダイナイ  天子の倉。
天子の倉。 天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。
天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。 オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』
オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』
 ダイダイ・ダイナイ
ダイダイ・ダイナイ  天子の倉。
天子の倉。 天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。
天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。 オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』
オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』
大法 オオカタ🔗⭐🔉
大江朝綱 オオエノアサツナ🔗⭐🔉
【大江朝綱】
オオエノアサツナ〔日〕〈人名〉886?〜957 平安時代中期の漢学者・書家。村上天皇の命により『新国史』『坤元録コンゲンロク』を撰した。
大江匡房 オオエノマサフサ🔗⭐🔉
【大江匡房】
オオエノマサフサ〔日〕〈人名〉1041〜1111 平安時代の貴族・学者。後三条・白河・堀河の三天皇の侍読。著に『本朝神仙伝』『江家ゴウケ次第』など、また、彼の談話を藤原実兼フジワラサネカネが筆録した『江談抄』がある。
奄 おおう🔗⭐🔉
【奄】
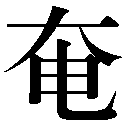 8画 大部
区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982
《音読み》 エン(エム)
8画 大部
区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982
《音読み》 エン(エム)
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる
《意味》
n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕
{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕
 {動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」
{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」
 {名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。
《解字》
{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。
《解字》
 会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。
《単語家族》
掩エン(おおう)
会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。
《単語家族》
掩エン(おおう) 淹エン(水につけておおう)
淹エン(水につけておおう) 庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
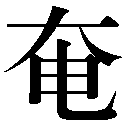 8画 大部
区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982
《音読み》 エン(エム)
8画 大部
区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982
《音読み》 エン(エム)
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる
《意味》
n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕
{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕
 {動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」
{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」
 {名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。
《解字》
{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。
《解字》
 会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。
《単語家族》
掩エン(おおう)
会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。
《単語家族》
掩エン(おおう) 淹エン(水につけておおう)
淹エン(水につけておおう) 庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
尾大不掉 オオオキクシテフレズ🔗⭐🔉
【尾大不掉】
ビダイナレバフレズ・オオオキクシテフレズ〈故事〉しっぽが大きすぎると自分の力では動かせない。臣下の力が大きすぎて君主の自由にならないことのたとえ。〔→左伝〕
屋 おおい🔗⭐🔉
【屋】
 9画 尸部 [三年]
区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE
《常用音訓》オク/や
《音読み》 オク(ヲク)
9画 尸部 [三年]
区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE
《常用音訓》オク/や
《音読み》 オク(ヲク)
 〈w
〈w 〉
《訓読み》 や/おおい(おほひ)
《名付け》 いえ・や
《意味》
〉
《訓読み》 や/おおい(おほひ)
《名付け》 いえ・や
《意味》
 {名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕
{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕
 {名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕
{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕
 {名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」
〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」
《解字》
{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」
〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」
《解字》
 会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至
《単語家族》
握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。
《類義》
→家
《異字同訓》
や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至
《単語家族》
握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。
《類義》
→家
《異字同訓》
や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 9画 尸部 [三年]
区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE
《常用音訓》オク/や
《音読み》 オク(ヲク)
9画 尸部 [三年]
区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE
《常用音訓》オク/や
《音読み》 オク(ヲク)
 〈w
〈w 〉
《訓読み》 や/おおい(おほひ)
《名付け》 いえ・や
《意味》
〉
《訓読み》 や/おおい(おほひ)
《名付け》 いえ・や
《意味》
 {名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕
{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕
 {名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕
{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕
 {名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」
〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」
《解字》
{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」
〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」
《解字》
 会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至
《単語家族》
握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。
《類義》
→家
《異字同訓》
や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至
《単語家族》
握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。
《類義》
→家
《異字同訓》
や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
庶 おおい🔗⭐🔉
【庶】
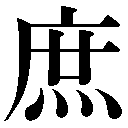 11画 广部 [常用漢字]
区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
11画 广部 [常用漢字]
区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)
《名付け》 ちか・もり・もろ
《意味》
〉
《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)
《名付け》 ちか・もり・もろ
《意味》
 {名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」
{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」
 {名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕
{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕
 {形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕
{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕
 「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。
「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。
 {形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕
{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕
 {動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」
{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」
 {副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。
《解字》
{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。
《解字》
 会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。
《単語家族》
煮(にる)
会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。
《単語家族》
煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
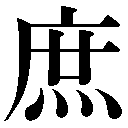 11画 广部 [常用漢字]
区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
11画 广部 [常用漢字]
区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)
《名付け》 ちか・もり・もろ
《意味》
〉
《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)
《名付け》 ちか・もり・もろ
《意味》
 {名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」
{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」
 {名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕
{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕
 {形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕
{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕
 「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。
「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。
 {形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕
{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕
 {動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」
{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」
 {副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。
《解字》
{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。
《解字》
 会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。
《単語家族》
煮(にる)
会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。
《単語家族》
煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
掩 おおう🔗⭐🔉
【掩】
 11画
11画  部
区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986
《音読み》 エン(エム)
部
区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986
《音読み》 エン(エム)
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす
《意味》
n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕
{動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕
 {動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」
{動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」
 {動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」
《解字》
会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄
《単語家族》
淹エン(水がおおう)
{動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」
《解字》
会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄
《単語家族》
淹エン(水がおおう) 庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画
11画  部
区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986
《音読み》 エン(エム)
部
区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986
《音読み》 エン(エム)
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす
《意味》
n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕
{動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕
 {動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」
{動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」
 {動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」
《解字》
会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄
《単語家族》
淹エン(水がおおう)
{動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」
《解字》
会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄
《単語家族》
淹エン(水がおおう) 庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
敝 おおう🔗⭐🔉
【敝】
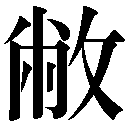 12画 攴部
区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7
《音読み》 ヘイ
12画 攴部
区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7
《音読み》 ヘイ /ベ
/ベ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)
《意味》
〉
《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)
《意味》
 {動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕
{動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕
 {動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕
{動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕
 {形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」
{形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」
 {動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。
《解字》
{動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。
《解字》
 会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。
《単語家族》
八(分ける)
会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。
《単語家族》
八(分ける) 別(分ける)
別(分ける) 貝バイ(二つに割れるかい)
貝バイ(二つに割れるかい) 敗(割れてだめになる)
敗(割れてだめになる) 廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
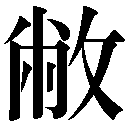 12画 攴部
区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7
《音読み》 ヘイ
12画 攴部
区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7
《音読み》 ヘイ /ベ
/ベ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)
《意味》
〉
《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)
《意味》
 {動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕
{動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕
 {動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕
{動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕
 {形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」
{形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」
 {動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。
《解字》
{動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。
《解字》
 会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。
《単語家族》
八(分ける)
会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。
《単語家族》
八(分ける) 別(分ける)
別(分ける) 貝バイ(二つに割れるかい)
貝バイ(二つに割れるかい) 敗(割れてだめになる)
敗(割れてだめになる) 廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
殷 おおい🔗⭐🔉
【殷】
 10画 殳部
区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75
《音読み》
10画 殳部
区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75
《音読み》  イン
イン /オン
/オン 〈y
〈y n〉/
n〉/ アン
アン /エン
/エン 〈y
〈y n〉/
n〉/ イン
イン /オン
/オン 《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)
《意味》
《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)
《意味》

 {形}充実して盛んなさま。
{形}充実して盛んなさま。
 {形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕
{形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕
 「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕
「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕
 {名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商
{名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商
 {形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。
{形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。
 {名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」
{名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」
 インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕
《解字》
インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕
《解字》
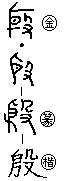 会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 殳部
区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75
《音読み》
10画 殳部
区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75
《音読み》  イン
イン /オン
/オン 〈y
〈y n〉/
n〉/ アン
アン /エン
/エン 〈y
〈y n〉/
n〉/ イン
イン /オン
/オン 《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)
《意味》
《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)
《意味》

 {形}充実して盛んなさま。
{形}充実して盛んなさま。
 {形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕
{形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕
 「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕
「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕
 {名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商
{名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商
 {形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。
{形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。
 {名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」
{名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」
 インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕
《解字》
インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕
《解字》
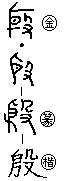 会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
泛 おおう🔗⭐🔉
【泛】
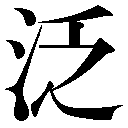 7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》
7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》  ハン(ハム)
ハン(ハム) /ボン(ボム)
/ボン(ボム) 〈f
〈f n〉/
n〉/ ホウ
ホウ /フウ
/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》
《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》

 {動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
 {動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
 {動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)
{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
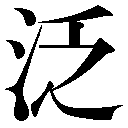 7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》
7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》  ハン(ハム)
ハン(ハム) /ボン(ボム)
/ボン(ボム) 〈f
〈f n〉/
n〉/ ホウ
ホウ /フウ
/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》
《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》

 {動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
 {動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
 {動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)
{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
洪 おおい🔗⭐🔉
【洪】
 9画 水部 [常用漢字]
区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E
《常用音訓》コウ
《音読み》 コウ
9画 水部 [常用漢字]
区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E
《常用音訓》コウ
《音読み》 コウ /グ
/グ 〈h
〈h ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 おお・ひろ・ひろし
《意味》
ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 おお・ひろ・ひろし
《意味》
 {名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕
{名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕
 {形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」
《解字》
会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共
《単語家族》
哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→主要人名
{形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」
《解字》
会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共
《単語家族》
哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→主要人名
 9画 水部 [常用漢字]
区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E
《常用音訓》コウ
《音読み》 コウ
9画 水部 [常用漢字]
区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E
《常用音訓》コウ
《音読み》 コウ /グ
/グ 〈h
〈h ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 おお・ひろ・ひろし
《意味》
ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 おお・ひろ・ひろし
《意味》
 {名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕
{名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕
 {形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」
《解字》
会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共
《単語家族》
哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→主要人名
{形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」
《解字》
会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共
《単語家族》
哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→主要人名
浩 おおい🔗⭐🔉
【浩】
 10画 水部 [人名漢字]
区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F
《音読み》 コウ(カウ)
10画 水部 [人名漢字]
区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F
《音読み》 コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)
/ゴウ(ガウ) 〈h
〈h o〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう
《意味》
o〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう
《意味》
 {形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。
{形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。
 {形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」
{形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」
 {形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」
{形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」
 {形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。
《解字》
形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。
《単語家族》
豪(おおきい)
{形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。
《解字》
形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。
《単語家族》
豪(おおきい) 厚(ぶあつい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
厚(ぶあつい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 水部 [人名漢字]
区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F
《音読み》 コウ(カウ)
10画 水部 [人名漢字]
区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F
《音読み》 コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)
/ゴウ(ガウ) 〈h
〈h o〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう
《意味》
o〉
《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう
《意味》
 {形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。
{形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。
 {形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」
{形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」
 {形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」
{形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」
 {形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。
《解字》
形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。
《単語家族》
豪(おおきい)
{形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。
《解字》
形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。
《単語家族》
豪(おおきい) 厚(ぶあつい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
厚(ぶあつい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
淹 おおう🔗⭐🔉
【淹】
 11画 水部
区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9
《音読み》 エン(エム)
11画 水部
区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9
《音読み》 エン(エム)
 /オン(オム)
/オン(オム) 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす
《意味》
n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」
{動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」
 {動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」
{動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」
 {形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」
《解字》
会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄
《単語家族》
掩エン(おおい隠す)
{形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」
《解字》
会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄
《単語家族》
掩エン(おおい隠す) 厭エン(上から封じこめる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
厭エン(上から封じこめる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 水部
区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9
《音読み》 エン(エム)
11画 水部
区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9
《音読み》 エン(エム)
 /オン(オム)
/オン(オム) 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす
《意味》
n〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」
{動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」
 {動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」
{動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」
 {形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」
《解字》
会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄
《単語家族》
掩エン(おおい隠す)
{形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」
《解字》
会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄
《単語家族》
掩エン(おおい隠す) 厭エン(上から封じこめる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
厭エン(上から封じこめる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
狼 おおかみ🔗⭐🔉
皇 おおい🔗⭐🔉
【皇】
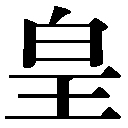 9画 白部 [六年]
区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63
《常用音訓》オウ/コウ
《音読み》 コウ(ク
9画 白部 [六年]
区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63
《常用音訓》オウ/コウ
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら
《名付け》 すべ・すめら
《意味》
ng〉
《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら
《名付け》 すべ・すめら
《意味》
 {名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕
{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕
 {名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」
{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」
 {形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕
{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕
 {形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」
{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」
 {形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」
{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」
 {形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」
{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」
 {形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕
〔国〕
{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕
〔国〕 すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。
すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。 すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」
《解字》
すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」
《解字》
 会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。
《単語家族》
広コウ(大きくひろがる)
会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。
《単語家族》
広コウ(大きくひろがる) 光(四方に広がるひかり)などと同系。
《類義》
→王
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
光(四方に広がるひかり)などと同系。
《類義》
→王
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
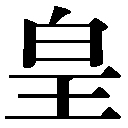 9画 白部 [六年]
区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63
《常用音訓》オウ/コウ
《音読み》 コウ(ク
9画 白部 [六年]
区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63
《常用音訓》オウ/コウ
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら
《名付け》 すべ・すめら
《意味》
ng〉
《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら
《名付け》 すべ・すめら
《意味》
 {名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕
{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕
 {名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」
{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」
 {形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕
{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕
 {形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」
{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」
 {形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」
{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」
 {形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」
{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」
 {形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕
〔国〕
{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕
〔国〕 すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。
すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。 すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」
《解字》
すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」
《解字》
 会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。
《単語家族》
広コウ(大きくひろがる)
会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。
《単語家族》
広コウ(大きくひろがる) 光(四方に広がるひかり)などと同系。
《類義》
→王
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
光(四方に広がるひかり)などと同系。
《類義》
→王
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
盍 おおう🔗⭐🔉
【盍】
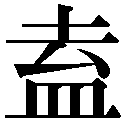 10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ)
10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) 〈h
〈h 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
 {動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
 {疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
 {疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ
{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
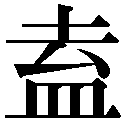 10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ)
10画 皿部
区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2
《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)
/ゴウ(ゴフ) 〈h
〈h 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ
《意味》
 {動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。
 {疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕
 {疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ
{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕
《解字》
会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。
《単語家族》
蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。
《熟語》
→熟語
冒 おおう🔗⭐🔉
【冒】
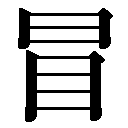 9画 目部 [常用漢字]
区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660
【冐】異体字異体字
9画 目部 [常用漢字]
区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660
【冐】異体字異体字
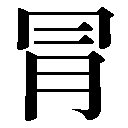 8画 肉部
区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC
《常用音訓》ボウ/おか…す
《音読み》 ボウ
8画 肉部
区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC
《常用音訓》ボウ/おか…す
《音読み》 ボウ /モウ
/モウ 〈m
〈m o〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)
《意味》
o〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕
{動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕
 {名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。
{名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。
 {動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕
{動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕
 {動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」
《解字》
{動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」
《解字》
 会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。
《単語家族》
帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。
《類義》
→犯
《異字同訓》
おかす。 →犯
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。
《単語家族》
帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。
《類義》
→犯
《異字同訓》
おかす。 →犯
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
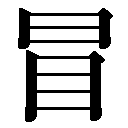 9画 目部 [常用漢字]
区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660
【冐】異体字異体字
9画 目部 [常用漢字]
区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660
【冐】異体字異体字
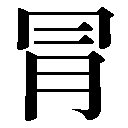 8画 肉部
区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC
《常用音訓》ボウ/おか…す
《音読み》 ボウ
8画 肉部
区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC
《常用音訓》ボウ/おか…す
《音読み》 ボウ /モウ
/モウ 〈m
〈m o〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)
《意味》
o〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)
《意味》
 {動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕
{動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕
 {名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。
{名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。
 {動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕
{動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕
 {動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」
《解字》
{動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」
《解字》
 会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。
《単語家族》
帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。
《類義》
→犯
《異字同訓》
おかす。 →犯
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。
《単語家族》
帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。
《類義》
→犯
《異字同訓》
おかす。 →犯
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
稠 おおい🔗⭐🔉
蒸 おおい🔗⭐🔉
【蒸】
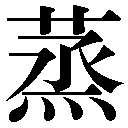 13画 艸部 [六年]
区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6
《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる
《音読み》 ジョウ
13画 艸部 [六年]
区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6
《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる
《音読み》 ジョウ /ショウ
/ショウ
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)
《名付け》 つぐ・つまき
《意味》
ng〉
《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)
《名付け》 つぐ・つまき
《意味》
 {動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」
{動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」
 {動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」
{動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」
 {名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」
{名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」
 ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。
ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。
 {形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕
{形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕
 {名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
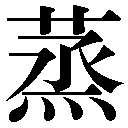 13画 艸部 [六年]
区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6
《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる
《音読み》 ジョウ
13画 艸部 [六年]
区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6
《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる
《音読み》 ジョウ /ショウ
/ショウ
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)
《名付け》 つぐ・つまき
《意味》
ng〉
《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)
《名付け》 つぐ・つまき
《意味》
 {動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」
{動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」
 {動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」
{動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」
 {名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」
{名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」
 ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。
ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。
 {形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕
{形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕
 {名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
蓋 おおう🔗⭐🔉
【蓋】
 13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
 12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
 11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》
11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》  ガイ
ガイ /カイ
/カイ
 〈g
〈g i〉/
i〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)
/ゴウ(ガフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》

 {動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
 {名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
 {単位}傘カサなどを数えることば。
{単位}傘カサなどを数えることば。
 {動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
 {動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
 {副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕
{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

 {名}草ぶきの屋根。とま。
{名}草ぶきの屋根。とま。
 {疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる)
{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57
【葢】異体字(A)異体字(A)
 12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
12画 艸部
区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2
【盖】異体字(B)異体字(B)
 11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》
11画 皿部
区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3
《音読み》  ガイ
ガイ /カイ
/カイ
 〈g
〈g i〉/
i〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)
/ゴウ(ガフ) 〈h
〈h ・g
・g 〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》
〉
《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる
《意味》

 {動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」
 {名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」
 {単位}傘カサなどを数えることば。
{単位}傘カサなどを数えることば。
 {動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。
 {動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」
 {副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕
{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

 {名}草ぶきの屋根。とま。
{名}草ぶきの屋根。とま。
 {疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる)
{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。
《解字》
会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。
《単語家族》
甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
蓑 おおう🔗⭐🔉
【蓑】
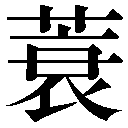 13画 艸部
区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA
【簑】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA
【簑】異体字(A)異体字(A)
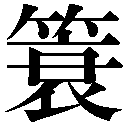 16画 竹部
区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0
【簔】異体字(B)異体字(B)
16画 竹部
区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0
【簔】異体字(B)異体字(B)
 17画 竹部
区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1
《音読み》 サイ
17画 竹部
区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1
《音読み》 サイ
 /サ
/サ
 〈su
〈su 〉
《訓読み》 みの/おおう(おほふ)
《意味》
〉
《訓読み》 みの/おおう(おほふ)
《意味》
 {名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。
{名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。
 {動}おおう(オホフ)。草でおおう。
{動}おおう(オホフ)。草でおおう。
 「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕
《解字》
会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕
《解字》
会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
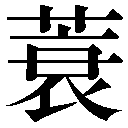 13画 艸部
区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA
【簑】異体字(A)異体字(A)
13画 艸部
区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA
【簑】異体字(A)異体字(A)
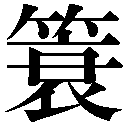 16画 竹部
区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0
【簔】異体字(B)異体字(B)
16画 竹部
区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0
【簔】異体字(B)異体字(B)
 17画 竹部
区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1
《音読み》 サイ
17画 竹部
区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1
《音読み》 サイ
 /サ
/サ
 〈su
〈su 〉
《訓読み》 みの/おおう(おほふ)
《意味》
〉
《訓読み》 みの/おおう(おほふ)
《意味》
 {名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。
{名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。
 {動}おおう(オホフ)。草でおおう。
{動}おおう(オホフ)。草でおおう。
 「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕
《解字》
会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕
《解字》
会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
蒙 おおう🔗⭐🔉
【蒙】
 13画 艸部
区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6
《音読み》 モウ
13画 艸部
区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6
《音読み》 モウ /ム
/ム /ボウ
/ボウ 〈m
〈m ng・m
ng・m ng・m
ng・m ng〉
《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)
《意味》
 {形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」
{形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」
 {形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」
{形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」
 {動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕
{動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕
 {動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」
{動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。
{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。
 {名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」
《解字》
{名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」
《解字》
 会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。
《単語家族》
冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす)
会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。
《単語家族》
冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす) 濛モウ(水気がおおう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
濛モウ(水気がおおう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 13画 艸部
区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6
《音読み》 モウ
13画 艸部
区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6
《音読み》 モウ /ム
/ム /ボウ
/ボウ 〈m
〈m ng・m
ng・m ng・m
ng・m ng〉
《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)
《意味》
 {形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」
{形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」
 {形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」
{形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」
 {動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕
{動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕
 {動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」
{動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」
 {名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。
{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。
 {名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」
《解字》
{名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」
《解字》
 会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。
《単語家族》
冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす)
会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。
《単語家族》
冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす) 濛モウ(水気がおおう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
濛モウ(水気がおおう)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
蔭 おおう🔗⭐🔉
蔀 おおい🔗⭐🔉
蔽 おおう🔗⭐🔉
【蔽】
 15画 艸部
区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1
《音読み》 ヘイ
15画 艸部
区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1
《音読み》 ヘイ /ヘ
/ヘ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)
《意味》
〉
《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)
《意味》
 {動}かくす。横にひろがってかくす。
{動}かくす。横にひろがってかくす。
 ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕
ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕
 ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕
ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕
 ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」
ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」
 {動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。
《単語家族》
幣(横にひろがる布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。
《単語家族》
幣(横にひろがる布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 艸部
区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1
《音読み》 ヘイ
15画 艸部
区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1
《音読み》 ヘイ /ヘ
/ヘ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)
《意味》
〉
《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)
《意味》
 {動}かくす。横にひろがってかくす。
{動}かくす。横にひろがってかくす。
 ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕
ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕
 ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕
ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕
 ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」
ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」
 {動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。
《単語家族》
幣(横にひろがる布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。
《単語家族》
幣(横にひろがる布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
衆 おおい🔗⭐🔉
【衆】
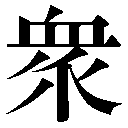 12画 血部 [六年]
区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F
《常用音訓》シュ/シュウ
《音読み》 シュウ
12画 血部 [六年]
区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F
《常用音訓》シュ/シュウ
《音読み》 シュウ /シュ/ス
/シュ/ス 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)
《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ
《意味》
ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)
《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ
《意味》
 {名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕
{名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕
 {形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」
{形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」
 {名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」
《解字》
{名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」
《解字》
 会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。
《単語家族》
充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる)
会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。
《単語家族》
充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる) 蓄(たくさんたまる)などと同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
蓄(たくさんたまる)などと同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
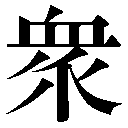 12画 血部 [六年]
区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F
《常用音訓》シュ/シュウ
《音読み》 シュウ
12画 血部 [六年]
区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F
《常用音訓》シュ/シュウ
《音読み》 シュウ /シュ/ス
/シュ/ス 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)
《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ
《意味》
ng〉
《訓読み》 おおい(おほし)
《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ
《意味》
 {名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕
{名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕
 {形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」
{形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」
 {名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」
《解字》
{名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」
《解字》
 会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。
《単語家族》
充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる)
会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。
《単語家族》
充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる) 蓄(たくさんたまる)などと同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
蓄(たくさんたまる)などと同系。
《類義》
→民
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
覆 おおう🔗⭐🔉
【覆】
 18画 襾部 [常用漢字]
区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2
《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る
《音読み》
18画 襾部 [常用漢字]
区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2
《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る
《音読み》  フク
フク
 〈f
〈f 〉/
〉/ フウ
フウ /フ
/フ /フク
/フク 〈f
〈f 〉/
〉/ ブ
ブ /フウ
/フウ /フク
/フク 〈f
〈f 〉
《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)
《意味》
〉
《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)
《意味》

 {動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」
{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」
 {動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」
{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」
 {動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」
{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」
 {動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕
{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕
 {名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。
《単語家族》
腹フク(はらわたを包んだはら)
{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。
《単語家族》
腹フク(はらわたを包んだはら) 孚フ(おおいかぶさる)
孚フ(おおいかぶさる) 伏(かぶさってふせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
伏(かぶさってふせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 18画 襾部 [常用漢字]
区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2
《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る
《音読み》
18画 襾部 [常用漢字]
区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2
《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る
《音読み》  フク
フク
 〈f
〈f 〉/
〉/ フウ
フウ /フ
/フ /フク
/フク 〈f
〈f 〉/
〉/ ブ
ブ /フウ
/フウ /フク
/フク 〈f
〈f 〉
《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)
《意味》
〉
《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)
《意味》

 {動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」
{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」
 {動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」
{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」
 {動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」
{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」
 {動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕
{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕
 {名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。
《単語家族》
腹フク(はらわたを包んだはら)
{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。
《単語家族》
腹フク(はらわたを包んだはら) 孚フ(おおいかぶさる)
孚フ(おおいかぶさる) 伏(かぶさってふせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
伏(かぶさってふせる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
那 おおい🔗⭐🔉
【那】
 7画 邑部 [人名漢字]
区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF
《音読み》 ナ
7画 邑部 [人名漢字]
区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF
《音読み》 ナ /ダ
/ダ 〈n
〈n ・n
・n ・n
・n ・n
・n i〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの
《名付け》 とも・ふゆ・やす
《意味》
i〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの
《名付け》 とも・ふゆ・やす
《意味》
 {形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕
{形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕
 ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕
ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕
 {前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕
{前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕
 {疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕
{疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕
 {助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕
{助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕
 {疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽
{疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽ 〜
〜 は、ふつうは上声。平声にも読む。
は、ふつうは上声。平声にも読む。
 {指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」
{指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」
 「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。
《解字》
会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。
《解字》
会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 邑部 [人名漢字]
区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF
《音読み》 ナ
7画 邑部 [人名漢字]
区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF
《音読み》 ナ /ダ
/ダ 〈n
〈n ・n
・n ・n
・n ・n
・n i〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの
《名付け》 とも・ふゆ・やす
《意味》
i〉
《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの
《名付け》 とも・ふゆ・やす
《意味》
 {形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕
{形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕
 ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕
ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕
 {前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕
{前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕
 {疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕
{疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕
 {助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕
{助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕
 {疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽
{疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽ 〜
〜 は、ふつうは上声。平声にも読む。
は、ふつうは上声。平声にも読む。
 {指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」
{指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」
 「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。
《解字》
会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。
《解字》
会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
阜 おおい🔗⭐🔉
【阜】
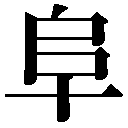 8画 阜部
区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C
《音読み》 フ
8画 阜部
区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C
《音読み》 フ /ブ
/ブ /フウ
/フウ 〈f
〈f 〉
《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《意味》
〉
《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《意味》
 {名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。
{名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。
 {形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。
{形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。
 {形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕
《解字》
{形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕
《解字》
 会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。
《単語家族》
腹(ふくれたはら)
会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。
《単語家族》
腹(ふくれたはら) 包(まるくつつむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
包(まるくつつむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
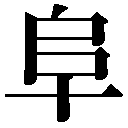 8画 阜部
区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C
《音読み》 フ
8画 阜部
区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C
《音読み》 フ /ブ
/ブ /フウ
/フウ 〈f
〈f 〉
《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《意味》
〉
《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)
《意味》
 {名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。
{名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。
 {形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。
{形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。
 {形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕
《解字》
{形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕
《解字》
 会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。
《単語家族》
腹(ふくれたはら)
会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。
《単語家族》
腹(ふくれたはら) 包(まるくつつむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
包(まるくつつむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
饒 おおい🔗⭐🔉
【饒】
 21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ)
21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ) /ニョウ(ネウ)
/ニョウ(ネウ) 〈r
〈r o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
 {形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
 {動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
 {接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符
{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符 (大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる)
(大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる) 搦ニャク・ダク(まげる)
搦ニャク・ダク(まげる) 撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる)
撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる) 遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ)
21画 食部
区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960
《音読み》 ジョウ(ゼウ) /ニョウ(ネウ)
/ニョウ(ネウ) 〈r
〈r o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
o〉
《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす
《意味》
 {形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕
 {動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」
 {接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符
{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。
《解字》
会意兼形声。「食+音符 (大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる)
(大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。
《単語家族》
弱(やわらかく曲がる) 搦ニャク・ダク(まげる)
搦ニャク・ダク(まげる) 撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる)
撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる) 遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鴻 おおがも🔗⭐🔉
【鴻】
 17画 鳥部 [人名漢字]
区点=2567 16進=3963 シフトJIS=8D83
《音読み》 コウ
17画 鳥部 [人名漢字]
区点=2567 16進=3963 シフトJIS=8D83
《音読み》 コウ /グ
/グ 〈h
〈h ng〉
《訓読み》 ひしくい(ひしくひ)/おおとり(おほとり)/おおがも(おほがも)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 とき・ひろ・ひろし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひしくい(ひしくひ)/おおとり(おほとり)/おおがも(おほがも)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 とき・ひろ・ひろし
《意味》
 {名}ひしくい(ヒシクヒ)。鳥の名。雁ガンの中で最も大きい。頭からくびにかけて、褐色カッショクで、羽は黒褐色。
{名}ひしくい(ヒシクヒ)。鳥の名。雁ガンの中で最も大きい。頭からくびにかけて、褐色カッショクで、羽は黒褐色。
 {名}おおとり(オホトリ)。おおがも(オホガモ)。鳥の名。黄鵠(はくちょう)のこと。
{名}おおとり(オホトリ)。おおがも(オホガモ)。鳥の名。黄鵠(はくちょう)のこと。
 {形}おおきい(オホイナリ)。広い。さかん。〈類義語〉→洪。「鴻業コウギョウ」「鴻徳コウトク」「鴻水コウスイ」
《解字》
形声。「鳥+音符江」で、大きい水鳥のこと。
《単語家族》
洪(大水)
{形}おおきい(オホイナリ)。広い。さかん。〈類義語〉→洪。「鴻業コウギョウ」「鴻徳コウトク」「鴻水コウスイ」
《解字》
形声。「鳥+音符江」で、大きい水鳥のこと。
《単語家族》
洪(大水) 哄(大声)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
哄(大声)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 17画 鳥部 [人名漢字]
区点=2567 16進=3963 シフトJIS=8D83
《音読み》 コウ
17画 鳥部 [人名漢字]
区点=2567 16進=3963 シフトJIS=8D83
《音読み》 コウ /グ
/グ 〈h
〈h ng〉
《訓読み》 ひしくい(ひしくひ)/おおとり(おほとり)/おおがも(おほがも)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 とき・ひろ・ひろし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ひしくい(ひしくひ)/おおとり(おほとり)/おおがも(おほがも)/おおきい(おほいなり)
《名付け》 とき・ひろ・ひろし
《意味》
 {名}ひしくい(ヒシクヒ)。鳥の名。雁ガンの中で最も大きい。頭からくびにかけて、褐色カッショクで、羽は黒褐色。
{名}ひしくい(ヒシクヒ)。鳥の名。雁ガンの中で最も大きい。頭からくびにかけて、褐色カッショクで、羽は黒褐色。
 {名}おおとり(オホトリ)。おおがも(オホガモ)。鳥の名。黄鵠(はくちょう)のこと。
{名}おおとり(オホトリ)。おおがも(オホガモ)。鳥の名。黄鵠(はくちょう)のこと。
 {形}おおきい(オホイナリ)。広い。さかん。〈類義語〉→洪。「鴻業コウギョウ」「鴻徳コウトク」「鴻水コウスイ」
《解字》
形声。「鳥+音符江」で、大きい水鳥のこと。
《単語家族》
洪(大水)
{形}おおきい(オホイナリ)。広い。さかん。〈類義語〉→洪。「鴻業コウギョウ」「鴻徳コウトク」「鴻水コウスイ」
《解字》
形声。「鳥+音符江」で、大きい水鳥のこと。
《単語家族》
洪(大水) 哄(大声)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
哄(大声)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「おお」で始まるの検索結果 1-43。もっと読み込む
 6画 人部
区点=4835 16進=5043 シフトJIS=98C1
《音読み》 カイ
6画 人部
区点=4835 16進=5043 シフトJIS=98C1
《音読み》 カイ おのおのその分を得て、かたよらないこと。〔
おのおのその分を得て、かたよらないこと。〔 大きな法則。『大法タイホウ』
大きな法則。『大法タイホウ』 正しい道。〔
正しい道。〔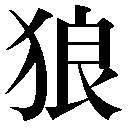 10画 犬部
区点=4721 16進=4F35 シフトJIS=9854
《音読み》 ロウ(ラウ)
10画 犬部
区点=4721 16進=4F35 シフトJIS=9854
《音読み》 ロウ(ラウ) 13画 禾部
区点=6739 16進=6347 シフトJIS=E266
《音読み》 チュウ(チウ)
13画 禾部
区点=6739 16進=6347 シフトJIS=E266
《音読み》 チュウ(チウ) 14画 艸部
区点=1694 16進=307E シフトJIS=88FC
《音読み》 イン(イム)
14画 艸部
区点=1694 16進=307E シフトJIS=88FC
《音読み》 イン(イム)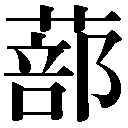 14画 艸部
区点=2835 16進=3C43 シフトJIS=8EC1
《音読み》 ホウ
14画 艸部
区点=2835 16進=3C43 シフトJIS=8EC1
《音読み》 ホウ 24画 黽部
区点=8371 16進=7367 シフトJIS=EA87
【鰲】異体字異体字
24画 黽部
区点=8371 16進=7367 シフトJIS=EA87
【鰲】異体字異体字
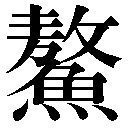 22画 魚部
区点=8266 16進=7262 シフトJIS=E9E0
《音読み》 ゴウ(ガウ)
22画 魚部
区点=8266 16進=7262 シフトJIS=E9E0
《音読み》 ゴウ(ガウ)