複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (51)
やま【山】🔗⭐🔉
やま【山】
①平地よりも高く隆起した地塊。谷と谷との間に挟まれた凸起部。古く、神が降下し領する所として信仰の対象とされた。万葉集17「すめ神の裾廻すそみの―の」。「―に登る」「富士は日本一の―」
②特に比叡山ひえいざん、また、そこにある延暦寺えんりゃくじの称。園城寺おんじょうじ(通称、三井寺)を寺というのに対していう。
③鉱山のこと。
④山陵。御陵ごりょう。
⑤猪・鹿などを捕らえるために仕掛ける落し穴。〈日葡辞書〉
⑥うず高く盛ったもの。山にまねて作ったもの。「塵の―」
⑦山形になった所。「ねじ―」
⑧山林。平地の林をもいう。
⑨山の形に盛り上げたものを数える語。「一―千円」
⑩物事の多く積み重なっていること。また、そのもの。「借金の―」
⑪物事の絶頂。最も肝要な部分。極点。とうげ。分岐点。「今日一日が―だ」「―を越す」
⑫(山師やましの仕事のように)万一の幸をねがってすること。やまごと。やまかん。「―が外れる」
⑬檀尻だんじりのこと。
⑭山鉾やまぼこの略。
⑮(名詞に冠して)同類のうちで、山野に自生するもの。また、恐ろしいもの。「―ゆり」「―桜」「―猫」
⇒山が当たる
⇒山が見える
⇒山から里へ
⇒山高きが故に貴からず
⇒山高く水長し
⇒山高ければ谷深し
⇒山と言えば川
⇒山に千年海に千年
⇒山眠る
⇒山のことは樵に聞け
⇒山粧う
⇒山笑う
⇒山を当てる
⇒山を鋳、海を煮る
⇒山を掛ける
⇒山をなす
⇒山を抜く力
⇒山を張る
やま‐あい【山間】‥アヒ🔗⭐🔉
やま‐あい【山間】‥アヒ
①山と山との間。やまかい。さんかん。
②馬の頭上の左右両耳の間。
やま‐あい【山藍】‥アヰ🔗⭐🔉
やま‐あい【山藍】‥アヰ
①トウダイグサ科の多年草。高さ約40センチメートル。山野の陰地に自生。葉は長楕円形。雌雄異株。春、上部の葉の付け根に緑白色の小花を穂状につける。昔は葉から汁をとって青色の染料にした。万葉集9「紅の赤裳裾引き―もち摺れる衣きぬ着て」
②リュウキュウアイの別称。
やま‐あがり【山上がり】🔗⭐🔉
やま‐あがり【山上がり】
対馬つしまで、家人が死んだ際、遺族が野辺に喪屋をつくって忌み籠りすること。伊豆新島では門屋かどやという。
やま‐あざみ【山薊】🔗⭐🔉
やま‐あざみ【山薊】
①数種のアザミ類の総称。倭名類聚鈔17「大葪、和名夜万阿佐美」
②モリアザミの別称。〈[季]秋〉
やま‐あし【山足】🔗⭐🔉
やま‐あし【山足】
スキーで、斜面の上側の足。↔谷足
やま‐あじさい【山紫陽花】‥アヂサヰ🔗⭐🔉
やま‐あじさい【山紫陽花】‥アヂサヰ
サワアジサイの別称。
やま‐あそび【山遊び】🔗⭐🔉
やま‐あそび【山遊び】
(主として春先に)野山に出て遊ぶこと。〈[季]春〉。→山磯遊び
やま‐あて【山当て】🔗⭐🔉
やま‐あて【山当て】
船舶が運航中に目当てとする陸の目標。山立て。
やま‐あらし【山荒らし・豪猪】🔗⭐🔉
やま‐あらし【山荒らし・豪猪】
ネズミ目ヤマアラシ科3属約11種とアメリカヤマアラシ科4属約10種の哺乳類の総称。体長30〜80センチメートルほど。毛色は黒褐色の種が多い。ヤマアラシ科はアフリカからヨーロッパ・南アジアに、アメリカヤマアラシ科は南北アメリカに広く分布。いずれも背から腰にとげのようになった剛毛を持ち、敵にあったとき、体を振って音を出したり、敵を刺したりする。昼は穴に隠れ、夜、球根や根のほか、動物質の食物をとる。
やまあらし
 ヤマアラシ
提供:東京動物園協会
ヤマアラシ
提供:東京動物園協会

 ヤマアラシ
提供:東京動物園協会
ヤマアラシ
提供:東京動物園協会

やま‐あらし【山嵐】🔗⭐🔉
やま‐あらし【山嵐】
①山に吹く嵐。山から吹いてくる嵐。
②柔道の手技の一つ。右手で相手の右襟えりをとらえ、左手で右袖そでを外部から順にとらえ、相手の浮き上がってくる時、吊り上げながら、その右くるぶしのやや上部に右足を当てて、相手の右前隅すみに大きく投げる。
やま‐あららぎ【山蘭】🔗⭐🔉
やま‐あららぎ【山蘭】
①コブシの別称。〈[季]春〉。〈本草和名〉
②ギョウジャニンニクの別称。
やま‐あり【山蟻】🔗⭐🔉
やま‐あり【山蟻】
アリ科ヤマアリ属の昆虫の総称。いずれも山地に多い中形のアリで、クロヤマアリ・アカヤマアリ・エゾアカヤマアリなどがある。〈[季]夏〉。新花つみ「―の覆道造る牡丹かな」
クロヤマアリ
撮影:海野和男
 アカヤマアリ
撮影:海野和男
アカヤマアリ
撮影:海野和男

 アカヤマアリ
撮影:海野和男
アカヤマアリ
撮影:海野和男

やま‐あるき【山歩き】🔗⭐🔉
やま‐あるき【山歩き】
運動または趣味として、山中を歩くこと。山踏み。
やまい【病】ヤマヒ🔗⭐🔉
やまい【病】ヤマヒ
①やむこと。病気。いたつき。南海寄帰内法伝平安後期点「疾ヤマヒを去さけむことを冀ねがうて」。「―に倒れる」
②よくない性癖。欠点。短所。きず。
③気がかり。苦労のたね。
④(中国の詩学でいう「詩八病」から)和歌・連歌などで修辞上嫌うべきこと。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いとところせう―去るべきところ多かりしかば」→うたのやまい→さりきらい。
⇒やまい‐け【病気】
⇒やまい‐だ【病田】
⇒やまい‐だおれ【病倒れ】
⇒やまい‐だれ【病垂】
⇒やまい‐はちまき【病鉢巻】
⇒やまい‐ばれ【病晴れ】
⇒やまい‐もの【病者】
⇒病革まる
⇒病膏肓に入る
⇒病治りて薬忘れる
⇒病は気から
⇒病は口より入り、禍は口より出づ
⇒病を養う
やま‐い【山井】‥ヰ🔗⭐🔉
やま‐い【山井】‥ヰ
山中の水のわき出るところ。やまのい。宇津保物語楼上下「楼の南なる―のしりひきたるに」
やま‐い【山居】‥ヰ🔗⭐🔉
やま‐い【山居】‥ヰ
山に住むこと。また、その居所。やまずみ。
やま‐い【山藍】‥ヰ🔗⭐🔉
やま‐い【山藍】‥ヰ
ヤマアイの約。しばしば「山井」にかけて用いる。貫之集「―もてすれる衣の赤紐の」
○病革まるやまいあらたまる
病気が危篤に陥る。
⇒やまい【病】
○病膏肓に入るやまいこうこうにいる🔗⭐🔉
○病膏肓に入るやまいこうこうにいる
[左伝成公10年](病が重くなった晋の景公の夢に、二人の子どもとなった病魔が名医の来ることを知って、肓の上、膏の下に隠れたという故事から)
①不治の病にかかる。また、病気が重くなってなおる見込みが立たないようになる。
②転じて、悪癖や弊害などが手のつけられないほどになる。また、物事に熱中してどうしようもないほどの状態になる。→膏肓→二豎にじゅ
⇒やまい【病】
やま‐いし【山石】
山から出る石。狂言、萩大名「あの石は海石か―か」
やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】
3月3日の節句に、野山や磯に出て遊び祝宴すること。
やまい‐だ【病田】ヤマヒ‥
その田で耕作すると病気やけがをすると伝えられている田。もとは禁忌を伴った聖地に発すると考えられる。
⇒やまい【病】
やまい‐だおれ【病倒れ】ヤマヒダフレ
病で倒れて死ぬこと。
⇒やまい【病】
やまい‐だれ【病垂】ヤマヒ‥
漢字の垂たれの一つ。「疾」「病」などの垂の「疒」の称。
⇒やまい【病】
やまい‐づ・く【病付く】ヤマヒ‥
〔自四〕
病気になる。やみつく。宇津保物語俊蔭「俄に母かくれぬ。それをなげく程に父―・きぬ」
やま‐いし【山石】🔗⭐🔉
やま‐いし【山石】
山から出る石。狂言、萩大名「あの石は海石か―か」
やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】🔗⭐🔉
やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】
3月3日の節句に、野山や磯に出て遊び祝宴すること。
やまい‐だ【病田】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐だ【病田】ヤマヒ‥
その田で耕作すると病気やけがをすると伝えられている田。もとは禁忌を伴った聖地に発すると考えられる。
⇒やまい【病】
やまい‐だおれ【病倒れ】ヤマヒダフレ🔗⭐🔉
やまい‐だおれ【病倒れ】ヤマヒダフレ
病で倒れて死ぬこと。
⇒やまい【病】
やまい‐だれ【病垂】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐だれ【病垂】ヤマヒ‥
漢字の垂たれの一つ。「疾」「病」などの垂の「疒」の称。
⇒やまい【病】
やまい‐づ・く【病付く】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐づ・く【病付く】ヤマヒ‥
〔自四〕
病気になる。やみつく。宇津保物語俊蔭「俄に母かくれぬ。それをなげく程に父―・きぬ」
○病治りて薬忘れるやまいなおりてくすりわすれる
ひとたび困難を乗り切ると、困難時に受けた恩義は忘れてしまうものだというたとえ。
⇒やまい【病】
やま‐いぬ【山犬・豺】🔗⭐🔉
やま‐いぬ【山犬・豺】
①日本産のオオカミの別称。〈[季]冬〉。名語記「おほかみ、如何。犲狼也。山犬といふ、これ也」→おおかみ1。
②山野にいる野犬の俗称。
やま‐いぬ【病犬】🔗⭐🔉
やま‐いぬ【病犬】
悪癖のある犬。また、狂犬。
○病は気からやまいはきから🔗⭐🔉
○病は気からやまいはきから
病気は気の持ち方一つで悪くもなり、良くもなる。
⇒やまい【病】
○病は口より入り、禍は口より出づやまいはくちよりいりわざわいはくちよりいず🔗⭐🔉
○病は口より入り、禍は口より出づやまいはくちよりいりわざわいはくちよりいず
[太平御覧人事部、口]病気は飲食物から起こり、災難は言語を慎まないことから起こる。軽率な発言を戒めた言葉。
⇒やまい【病】
やまい‐はちまき【病鉢巻】ヤマヒ‥
歌舞伎および人形劇で、男女ともに病人の役がする鉢巻のこと。左側に結ぶのがきまり。
⇒やまい【病】
やまい‐ばれ【病晴れ】ヤマヒ‥
気がかりがなくなること。狂言、法師が母「今日はざつとよい―をしたといふものぢや」
⇒やまい【病】
やま‐いも【山芋・薯蕷】
(→)「やまのいも」に同じ。〈[季]秋〉。新撰字鏡7「暑預、山伊母」
やまい‐もの【病者】ヤマヒ‥
病人。狂言、緡縄さしなわ「あのやうな、―をおこして、迷惑をさしやる事ぢや」
⇒やまい【病】
やまい‐よわ・い【病弱い】ヤマヒ‥
〔形〕
病気に堪える力が弱い。〈日葡辞書〉
やま‐いわい【山祝】‥イハヒ
(→)矢開やびらきに同じ。
やまい‐はちまき【病鉢巻】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐はちまき【病鉢巻】ヤマヒ‥
歌舞伎および人形劇で、男女ともに病人の役がする鉢巻のこと。左側に結ぶのがきまり。
⇒やまい【病】
やまい‐ばれ【病晴れ】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐ばれ【病晴れ】ヤマヒ‥
気がかりがなくなること。狂言、法師が母「今日はざつとよい―をしたといふものぢや」
⇒やまい【病】
やま‐いも【山芋・薯蕷】🔗⭐🔉
やま‐いも【山芋・薯蕷】
(→)「やまのいも」に同じ。〈[季]秋〉。新撰字鏡7「暑預、山伊母」
やまい‐もの【病者】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐もの【病者】ヤマヒ‥
病人。狂言、緡縄さしなわ「あのやうな、―をおこして、迷惑をさしやる事ぢや」
⇒やまい【病】
やまい‐よわ・い【病弱い】ヤマヒ‥🔗⭐🔉
やまい‐よわ・い【病弱い】ヤマヒ‥
〔形〕
病気に堪える力が弱い。〈日葡辞書〉
○病を養うやまいをやしなう🔗⭐🔉
○病を養うやまいをやしなう
療養する。
⇒やまい【病】
やまう【病】ヤマフ
やまい。平家物語3「漢の李夫人の、昭陽殿の―の床もかくやとおぼえ」
やま・う【病まふ】ヤマフ
〔自四〕
(病ムに接尾語フの付いた語とも、病ヒの動詞化した語ともいう)病気になる。わずらう。
やま‐うぐいす【山鶯】‥ウグヒス
①山にすむ鶯。野生の鶯。
②〔植〕ヤマルリソウの別称。
やま‐うさぎ【山兎】
山にいる兎。野生の兎。
やま‐うずら【山鶉】‥ウヅラ
キジ目キジ科の鳥。ウズラに似るが大きく、頭・胸は褐色、背に灰褐色に細かい黒横線があり、雄は腹面に蹄鉄形の大きな黒斑がある。シベリア南部から中国北部にかけて分布。
やまうち【山内】
(姓氏)
⇒やまのうち
やま‐うつぼ【山靫】
狩に用いる、粗末な靫。平家物語8「―竹箙たかえびらに矢ども少々さし」
やま‐うど【山人】
(ヤマビトの音便)木樵きこりなど山に働く人。やもうど。〈日葡辞書〉
やま‐うど【山独活】
山に生えているウド。野生のウド。〈[季]春〉
ヤマウド
撮影:関戸 勇
 やま‐うば【山姥】
深山に住み、怪力を発揮するなどと考えられている伝説的な女。山女。山に住む鬼女。やまんば。
⇒やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
(壱岐で)12月20日のこと。→果はての二十日
⇒やま‐うば【山姥】
やま‐うり【山売り】
①山を売ること。
②鉱山の売買を業とする人。
③いかさま物を売りつける人。山師。
④一山ひとやまいくらとまとめて売ること。山盛りにして売ること。
やま‐うるし【山漆】
①ウルシ科の落葉小高木。山野に自生。高さ約3メートル。葉は3〜7対の楕円形の小葉から成る羽状複葉で、葉柄は赤く、秋美しく紅葉する。6〜7月頃、黄緑色の小花を円錐花序に密生。花後、扁球形で毛の密生した小核果を結ぶ。果実から蝋を製する。ハゼノキ。ハニシ。
②ツタウルシの別称。
やま‐お【山尾・山峰】‥ヲ
山の峰つづき。山の稜線。
やま‐お【山緒】‥ヲ
鷹の捕らえた鳥を鳥柴としばなどに結びつける紐。葛かずら・籐とうなどを用いた。頼政集「―にたたむかづらだになし」
やまおか【山岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒やまおか‐げんりん【山岡元隣】
⇒やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】
やまおか‐げんりん【山岡元隣】‥ヲカ‥
江戸前期の仮名草子作者・俳人。名は新三郎。伊勢商人の流れをくむ京都の人。北村季吟に和歌・俳諧を学び、著には「宝蔵」などの俳書とともに、「徒然草増補鉄槌」など古典の注釈も多く、仮名草子に「他我身たがみの上」「小巵こさかずき」などがある。(1631〜1672)
⇒やまおか【山岡】
やまおか‐ずきん【山岡頭巾】‥ヲカヅ‥
①苧屑ほくそ頭巾の異称。
②形は苧屑頭巾に似せて、八丈絹やビロードで作った頭巾。また藺いでも作った。洒落本、辰巳之園「―を横ちよにかむり、日和下駄をはき」
やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】‥ヲカ‥シウ
幕末・明治の政治家。無刀流の創始者。前名、小野高歩たかゆき。通称、鉄太郎。江戸生れの幕臣。剣術にすぐれ、禅を修行、書をよくした。戊辰戦争の際、西郷隆盛を説き、勝海舟との会談を成立させた。のち明治天皇の侍従などをつとめる。子爵。(1836〜1888)
山岡鉄舟
提供:毎日新聞社
やま‐うば【山姥】
深山に住み、怪力を発揮するなどと考えられている伝説的な女。山女。山に住む鬼女。やまんば。
⇒やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
(壱岐で)12月20日のこと。→果はての二十日
⇒やま‐うば【山姥】
やま‐うり【山売り】
①山を売ること。
②鉱山の売買を業とする人。
③いかさま物を売りつける人。山師。
④一山ひとやまいくらとまとめて売ること。山盛りにして売ること。
やま‐うるし【山漆】
①ウルシ科の落葉小高木。山野に自生。高さ約3メートル。葉は3〜7対の楕円形の小葉から成る羽状複葉で、葉柄は赤く、秋美しく紅葉する。6〜7月頃、黄緑色の小花を円錐花序に密生。花後、扁球形で毛の密生した小核果を結ぶ。果実から蝋を製する。ハゼノキ。ハニシ。
②ツタウルシの別称。
やま‐お【山尾・山峰】‥ヲ
山の峰つづき。山の稜線。
やま‐お【山緒】‥ヲ
鷹の捕らえた鳥を鳥柴としばなどに結びつける紐。葛かずら・籐とうなどを用いた。頼政集「―にたたむかづらだになし」
やまおか【山岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒やまおか‐げんりん【山岡元隣】
⇒やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】
やまおか‐げんりん【山岡元隣】‥ヲカ‥
江戸前期の仮名草子作者・俳人。名は新三郎。伊勢商人の流れをくむ京都の人。北村季吟に和歌・俳諧を学び、著には「宝蔵」などの俳書とともに、「徒然草増補鉄槌」など古典の注釈も多く、仮名草子に「他我身たがみの上」「小巵こさかずき」などがある。(1631〜1672)
⇒やまおか【山岡】
やまおか‐ずきん【山岡頭巾】‥ヲカヅ‥
①苧屑ほくそ頭巾の異称。
②形は苧屑頭巾に似せて、八丈絹やビロードで作った頭巾。また藺いでも作った。洒落本、辰巳之園「―を横ちよにかむり、日和下駄をはき」
やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】‥ヲカ‥シウ
幕末・明治の政治家。無刀流の創始者。前名、小野高歩たかゆき。通称、鉄太郎。江戸生れの幕臣。剣術にすぐれ、禅を修行、書をよくした。戊辰戦争の際、西郷隆盛を説き、勝海舟との会談を成立させた。のち明治天皇の侍従などをつとめる。子爵。(1836〜1888)
山岡鉄舟
提供:毎日新聞社
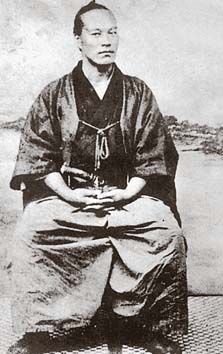 ⇒やまおか【山岡】
やま‐おく【山奥】
山の奥の方。山の深い所。「―の村」
やま‐おくり【山送り】
死骸を山に送り葬ること。のべおくり。今昔物語集22「葬送の夜、…―せむとありければ」
やま‐おこぜ【山鰧】‥ヲコゼ
狩人が山の神に供え、あるいはこれを秘蔵すると好猟があるとして携えるもの。「おこぜ」は普通海魚をいうが、カジカのような川魚や巻貝、あるいは鹿の耳などを指す地方もある。
やま‐おだまき【山苧環】‥ヲ‥
キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地草原に生える。太い主根があり、2回3出複葉で長柄のある根生葉を出す。茎の高さ30〜50センチメートル、3小葉の茎葉を互生。初夏に茎の上部が分かれて、クリーム色または紫褐色の大きな花を数個、下向きにつける。5片の萼片がくへんには長い管状の距がある。
やま‐おとこ【山男】‥ヲトコ
①山に住む男。山で仕事をする男。
②深山に住むという男の怪物。椿説弓張月前編「いまだかかる獣を見ず。こは世にいふ―ならんか」
③登山を趣味とし、その経験が深い男。
やま‐おやじ【山親爺】‥オヤヂ
(北海道で)ヒグマの俗称。
やま‐おり【山折り】‥ヲリ
紙などを折る時に、折れ目が外側に出るように折ること。↔谷折り
やま‐おろし【山颪】
①山から吹きおろす風。万葉集9「―の風な吹きそと」
②歌舞伎囃子の一つ。山中の場面に用い、大太鼓で風が吹きすさむ音に擬するもの。
⇒やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
(→)「やまおろし」1に同じ。
⇒やま‐おろし【山颪】
やま‐おんな【山女】‥ヲンナ
深山に住み、怪異をはたらくという伝説的な女。山姥やまうば。
やま‐が【山家】
山中や山里にある家。また、山里。
⇒やまが‐ずまい【山家住まい】
⇒やまが‐そだち【山家育ち】
やまが【山鹿】
熊本県北部の市。菊池川中流に位置し、山鹿盆地の中心都市。山鹿温泉がある。人口5万8千。
やまが【山鹿】
姓氏の一つ。
⇒やまが‐そこう【山鹿素行】
⇒やまが‐りゅう【山鹿流】
⇒やまおか【山岡】
やま‐おく【山奥】
山の奥の方。山の深い所。「―の村」
やま‐おくり【山送り】
死骸を山に送り葬ること。のべおくり。今昔物語集22「葬送の夜、…―せむとありければ」
やま‐おこぜ【山鰧】‥ヲコゼ
狩人が山の神に供え、あるいはこれを秘蔵すると好猟があるとして携えるもの。「おこぜ」は普通海魚をいうが、カジカのような川魚や巻貝、あるいは鹿の耳などを指す地方もある。
やま‐おだまき【山苧環】‥ヲ‥
キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地草原に生える。太い主根があり、2回3出複葉で長柄のある根生葉を出す。茎の高さ30〜50センチメートル、3小葉の茎葉を互生。初夏に茎の上部が分かれて、クリーム色または紫褐色の大きな花を数個、下向きにつける。5片の萼片がくへんには長い管状の距がある。
やま‐おとこ【山男】‥ヲトコ
①山に住む男。山で仕事をする男。
②深山に住むという男の怪物。椿説弓張月前編「いまだかかる獣を見ず。こは世にいふ―ならんか」
③登山を趣味とし、その経験が深い男。
やま‐おやじ【山親爺】‥オヤヂ
(北海道で)ヒグマの俗称。
やま‐おり【山折り】‥ヲリ
紙などを折る時に、折れ目が外側に出るように折ること。↔谷折り
やま‐おろし【山颪】
①山から吹きおろす風。万葉集9「―の風な吹きそと」
②歌舞伎囃子の一つ。山中の場面に用い、大太鼓で風が吹きすさむ音に擬するもの。
⇒やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
(→)「やまおろし」1に同じ。
⇒やま‐おろし【山颪】
やま‐おんな【山女】‥ヲンナ
深山に住み、怪異をはたらくという伝説的な女。山姥やまうば。
やま‐が【山家】
山中や山里にある家。また、山里。
⇒やまが‐ずまい【山家住まい】
⇒やまが‐そだち【山家育ち】
やまが【山鹿】
熊本県北部の市。菊池川中流に位置し、山鹿盆地の中心都市。山鹿温泉がある。人口5万8千。
やまが【山鹿】
姓氏の一つ。
⇒やまが‐そこう【山鹿素行】
⇒やまが‐りゅう【山鹿流】
 やま‐うば【山姥】
深山に住み、怪力を発揮するなどと考えられている伝説的な女。山女。山に住む鬼女。やまんば。
⇒やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
(壱岐で)12月20日のこと。→果はての二十日
⇒やま‐うば【山姥】
やま‐うり【山売り】
①山を売ること。
②鉱山の売買を業とする人。
③いかさま物を売りつける人。山師。
④一山ひとやまいくらとまとめて売ること。山盛りにして売ること。
やま‐うるし【山漆】
①ウルシ科の落葉小高木。山野に自生。高さ約3メートル。葉は3〜7対の楕円形の小葉から成る羽状複葉で、葉柄は赤く、秋美しく紅葉する。6〜7月頃、黄緑色の小花を円錐花序に密生。花後、扁球形で毛の密生した小核果を結ぶ。果実から蝋を製する。ハゼノキ。ハニシ。
②ツタウルシの別称。
やま‐お【山尾・山峰】‥ヲ
山の峰つづき。山の稜線。
やま‐お【山緒】‥ヲ
鷹の捕らえた鳥を鳥柴としばなどに結びつける紐。葛かずら・籐とうなどを用いた。頼政集「―にたたむかづらだになし」
やまおか【山岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒やまおか‐げんりん【山岡元隣】
⇒やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】
やまおか‐げんりん【山岡元隣】‥ヲカ‥
江戸前期の仮名草子作者・俳人。名は新三郎。伊勢商人の流れをくむ京都の人。北村季吟に和歌・俳諧を学び、著には「宝蔵」などの俳書とともに、「徒然草増補鉄槌」など古典の注釈も多く、仮名草子に「他我身たがみの上」「小巵こさかずき」などがある。(1631〜1672)
⇒やまおか【山岡】
やまおか‐ずきん【山岡頭巾】‥ヲカヅ‥
①苧屑ほくそ頭巾の異称。
②形は苧屑頭巾に似せて、八丈絹やビロードで作った頭巾。また藺いでも作った。洒落本、辰巳之園「―を横ちよにかむり、日和下駄をはき」
やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】‥ヲカ‥シウ
幕末・明治の政治家。無刀流の創始者。前名、小野高歩たかゆき。通称、鉄太郎。江戸生れの幕臣。剣術にすぐれ、禅を修行、書をよくした。戊辰戦争の際、西郷隆盛を説き、勝海舟との会談を成立させた。のち明治天皇の侍従などをつとめる。子爵。(1836〜1888)
山岡鉄舟
提供:毎日新聞社
やま‐うば【山姥】
深山に住み、怪力を発揮するなどと考えられている伝説的な女。山女。山に住む鬼女。やまんば。
⇒やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
(壱岐で)12月20日のこと。→果はての二十日
⇒やま‐うば【山姥】
やま‐うり【山売り】
①山を売ること。
②鉱山の売買を業とする人。
③いかさま物を売りつける人。山師。
④一山ひとやまいくらとまとめて売ること。山盛りにして売ること。
やま‐うるし【山漆】
①ウルシ科の落葉小高木。山野に自生。高さ約3メートル。葉は3〜7対の楕円形の小葉から成る羽状複葉で、葉柄は赤く、秋美しく紅葉する。6〜7月頃、黄緑色の小花を円錐花序に密生。花後、扁球形で毛の密生した小核果を結ぶ。果実から蝋を製する。ハゼノキ。ハニシ。
②ツタウルシの別称。
やま‐お【山尾・山峰】‥ヲ
山の峰つづき。山の稜線。
やま‐お【山緒】‥ヲ
鷹の捕らえた鳥を鳥柴としばなどに結びつける紐。葛かずら・籐とうなどを用いた。頼政集「―にたたむかづらだになし」
やまおか【山岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒やまおか‐げんりん【山岡元隣】
⇒やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】
やまおか‐げんりん【山岡元隣】‥ヲカ‥
江戸前期の仮名草子作者・俳人。名は新三郎。伊勢商人の流れをくむ京都の人。北村季吟に和歌・俳諧を学び、著には「宝蔵」などの俳書とともに、「徒然草増補鉄槌」など古典の注釈も多く、仮名草子に「他我身たがみの上」「小巵こさかずき」などがある。(1631〜1672)
⇒やまおか【山岡】
やまおか‐ずきん【山岡頭巾】‥ヲカヅ‥
①苧屑ほくそ頭巾の異称。
②形は苧屑頭巾に似せて、八丈絹やビロードで作った頭巾。また藺いでも作った。洒落本、辰巳之園「―を横ちよにかむり、日和下駄をはき」
やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】‥ヲカ‥シウ
幕末・明治の政治家。無刀流の創始者。前名、小野高歩たかゆき。通称、鉄太郎。江戸生れの幕臣。剣術にすぐれ、禅を修行、書をよくした。戊辰戦争の際、西郷隆盛を説き、勝海舟との会談を成立させた。のち明治天皇の侍従などをつとめる。子爵。(1836〜1888)
山岡鉄舟
提供:毎日新聞社
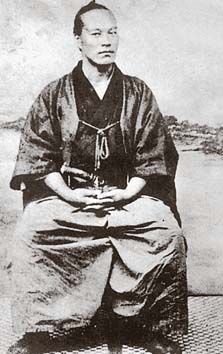 ⇒やまおか【山岡】
やま‐おく【山奥】
山の奥の方。山の深い所。「―の村」
やま‐おくり【山送り】
死骸を山に送り葬ること。のべおくり。今昔物語集22「葬送の夜、…―せむとありければ」
やま‐おこぜ【山鰧】‥ヲコゼ
狩人が山の神に供え、あるいはこれを秘蔵すると好猟があるとして携えるもの。「おこぜ」は普通海魚をいうが、カジカのような川魚や巻貝、あるいは鹿の耳などを指す地方もある。
やま‐おだまき【山苧環】‥ヲ‥
キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地草原に生える。太い主根があり、2回3出複葉で長柄のある根生葉を出す。茎の高さ30〜50センチメートル、3小葉の茎葉を互生。初夏に茎の上部が分かれて、クリーム色または紫褐色の大きな花を数個、下向きにつける。5片の萼片がくへんには長い管状の距がある。
やま‐おとこ【山男】‥ヲトコ
①山に住む男。山で仕事をする男。
②深山に住むという男の怪物。椿説弓張月前編「いまだかかる獣を見ず。こは世にいふ―ならんか」
③登山を趣味とし、その経験が深い男。
やま‐おやじ【山親爺】‥オヤヂ
(北海道で)ヒグマの俗称。
やま‐おり【山折り】‥ヲリ
紙などを折る時に、折れ目が外側に出るように折ること。↔谷折り
やま‐おろし【山颪】
①山から吹きおろす風。万葉集9「―の風な吹きそと」
②歌舞伎囃子の一つ。山中の場面に用い、大太鼓で風が吹きすさむ音に擬するもの。
⇒やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
(→)「やまおろし」1に同じ。
⇒やま‐おろし【山颪】
やま‐おんな【山女】‥ヲンナ
深山に住み、怪異をはたらくという伝説的な女。山姥やまうば。
やま‐が【山家】
山中や山里にある家。また、山里。
⇒やまが‐ずまい【山家住まい】
⇒やまが‐そだち【山家育ち】
やまが【山鹿】
熊本県北部の市。菊池川中流に位置し、山鹿盆地の中心都市。山鹿温泉がある。人口5万8千。
やまが【山鹿】
姓氏の一つ。
⇒やまが‐そこう【山鹿素行】
⇒やまが‐りゅう【山鹿流】
⇒やまおか【山岡】
やま‐おく【山奥】
山の奥の方。山の深い所。「―の村」
やま‐おくり【山送り】
死骸を山に送り葬ること。のべおくり。今昔物語集22「葬送の夜、…―せむとありければ」
やま‐おこぜ【山鰧】‥ヲコゼ
狩人が山の神に供え、あるいはこれを秘蔵すると好猟があるとして携えるもの。「おこぜ」は普通海魚をいうが、カジカのような川魚や巻貝、あるいは鹿の耳などを指す地方もある。
やま‐おだまき【山苧環】‥ヲ‥
キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地草原に生える。太い主根があり、2回3出複葉で長柄のある根生葉を出す。茎の高さ30〜50センチメートル、3小葉の茎葉を互生。初夏に茎の上部が分かれて、クリーム色または紫褐色の大きな花を数個、下向きにつける。5片の萼片がくへんには長い管状の距がある。
やま‐おとこ【山男】‥ヲトコ
①山に住む男。山で仕事をする男。
②深山に住むという男の怪物。椿説弓張月前編「いまだかかる獣を見ず。こは世にいふ―ならんか」
③登山を趣味とし、その経験が深い男。
やま‐おやじ【山親爺】‥オヤヂ
(北海道で)ヒグマの俗称。
やま‐おり【山折り】‥ヲリ
紙などを折る時に、折れ目が外側に出るように折ること。↔谷折り
やま‐おろし【山颪】
①山から吹きおろす風。万葉集9「―の風な吹きそと」
②歌舞伎囃子の一つ。山中の場面に用い、大太鼓で風が吹きすさむ音に擬するもの。
⇒やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
やまおろし‐の‐かぜ【山颪の風】
(→)「やまおろし」1に同じ。
⇒やま‐おろし【山颪】
やま‐おんな【山女】‥ヲンナ
深山に住み、怪異をはたらくという伝説的な女。山姥やまうば。
やま‐が【山家】
山中や山里にある家。また、山里。
⇒やまが‐ずまい【山家住まい】
⇒やまが‐そだち【山家育ち】
やまが【山鹿】
熊本県北部の市。菊池川中流に位置し、山鹿盆地の中心都市。山鹿温泉がある。人口5万8千。
やまが【山鹿】
姓氏の一つ。
⇒やまが‐そこう【山鹿素行】
⇒やまが‐りゅう【山鹿流】
やまう【病】ヤマフ🔗⭐🔉
やまう【病】ヤマフ
やまい。平家物語3「漢の李夫人の、昭陽殿の―の床もかくやとおぼえ」
やま・う【病まふ】ヤマフ🔗⭐🔉
やま・う【病まふ】ヤマフ
〔自四〕
(病ムに接尾語フの付いた語とも、病ヒの動詞化した語ともいう)病気になる。わずらう。
やま‐うぐいす【山鶯】‥ウグヒス🔗⭐🔉
やま‐うぐいす【山鶯】‥ウグヒス
①山にすむ鶯。野生の鶯。
②〔植〕ヤマルリソウの別称。
やま‐うさぎ【山兎】🔗⭐🔉
やま‐うさぎ【山兎】
山にいる兎。野生の兎。
やま‐うずら【山鶉】‥ウヅラ🔗⭐🔉
やま‐うずら【山鶉】‥ウヅラ
キジ目キジ科の鳥。ウズラに似るが大きく、頭・胸は褐色、背に灰褐色に細かい黒横線があり、雄は腹面に蹄鉄形の大きな黒斑がある。シベリア南部から中国北部にかけて分布。
やま‐うつぼ【山靫】🔗⭐🔉
やま‐うつぼ【山靫】
狩に用いる、粗末な靫。平家物語8「―竹箙たかえびらに矢ども少々さし」
やま‐うど【山人】🔗⭐🔉
やま‐うど【山人】
(ヤマビトの音便)木樵きこりなど山に働く人。やもうど。〈日葡辞書〉
やま‐うど【山独活】🔗⭐🔉
やま‐うど【山独活】
山に生えているウド。野生のウド。〈[季]春〉
ヤマウド
撮影:関戸 勇


大辞林の検索結果 (100)
やま【山】🔗⭐🔉
やま 【山】
■一■ [2] (名)
(1)周りの土地より著しく高くなった所。古くから信仰の対象となり,俗世間を離れた清浄の地とされた。
(2)鉱山。
(3){(1)}の形をしたもの。(ア)庭園などに小高く土を盛って作ったもの。築山。(イ)物をうず高く積み上げたもの。「書類の―」「―盛り」(ウ)数量がきわめて多いこと。「人の―」「借金の―」
(4)物の一部で,高くなっている所。「ねじの―」
(5)進行するに従って次第に高まり,やがて徐々におさまる物事の全体を{(1)}に見立てていう。(ア)最も重要なところ。絶頂。クライマックス。「―のない小説」(イ)成否を決定するような緊迫した場面。「病人は今夜が―だ」
(6)〔(2)の鉱脈を探し当てるのは,きわめて確率の低い賭(カ)けであったことから〕
万一の僥倖(ギヨウコウ)に賭けること。
(7)犯罪事件。警察や新聞記者などが用いる。「大きな―だ」
(8)山登り。「趣味は―だ」
(9)「山鉾(ヤマボコ)」に同じ。
(10)(園城寺(オンジヨウジ)を寺というのに対して)比叡山。延暦寺。「昨日―へ罷り登りにけり/源氏(夕顔)」
(11)高く,ゆるぎないもの。よりどころとすべきもの。「―と頼みし君をおきて/後撰(離別)」
(12)〔多く(1)にあったことから〕
墓。山陵。「御―に参り侍るを/源氏(須磨)」
(13)詐欺。また,もくろみ。「女郎の―で,…茶屋とぐるになつてしかけたところが/洒落本・蕩子筌枉解」
(14)動植物の名の上に付けて,同類のうちで野生のもの,あるいは山地に産するものであることを表す。「―ねこ」「―ぶどう」「―つつじ」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)盛り分けた物を数えるのに用いる。「みかん一―五百円」
(2)山,特に山林や鉱山を数えるのに用いる。
や-ま【矢間】🔗⭐🔉
や-ま [1] 【矢間】
(1)甲冑(カツチユウ)などで,矢の通る隙間。「甲冑をわり合はせわり合はせ―をたばひて振舞へば/盛衰記 35」
(2)「矢狭間(ヤザマ)」に同じ。
やま【夜摩】🔗⭐🔉
やま 【夜摩】
〔梵 Yama〕
⇒夜摩天(ヤマテン)
やま-あい【山間】🔗⭐🔉
やま-あい ―アヒ [0] 【山間】
山と山との間。山の中。「―の道」
やま-あい【山藍】🔗⭐🔉
やま-あい ―ア [3][0] 【山藍】
トウダイグサ科の多年草。山中の林内に生える。茎は四稜あり,高さ約40センチメートル。葉は対生し,卵状長楕円形。雌雄異株。春から夏,葉腋(ヨウエキ)に長い花穂をつける。古くは葉を藍染めの染料とした。
[3][0] 【山藍】
トウダイグサ科の多年草。山中の林内に生える。茎は四稜あり,高さ約40センチメートル。葉は対生し,卵状長楕円形。雌雄異株。春から夏,葉腋(ヨウエキ)に長い花穂をつける。古くは葉を藍染めの染料とした。
 [3][0] 【山藍】
トウダイグサ科の多年草。山中の林内に生える。茎は四稜あり,高さ約40センチメートル。葉は対生し,卵状長楕円形。雌雄異株。春から夏,葉腋(ヨウエキ)に長い花穂をつける。古くは葉を藍染めの染料とした。
[3][0] 【山藍】
トウダイグサ科の多年草。山中の林内に生える。茎は四稜あり,高さ約40センチメートル。葉は対生し,卵状長楕円形。雌雄異株。春から夏,葉腋(ヨウエキ)に長い花穂をつける。古くは葉を藍染めの染料とした。
やま-あざみ【山薊】🔗⭐🔉
やま-あざみ [3] 【山薊】
アザミの一種。西日本の山中に生える。茎は太く,高さ2メートルに達する。葉は密につき,羽状に中裂。秋,紅紫色の小頭花多数が穂状につく。
やま-あじさい【山紫陽花】🔗⭐🔉
やま-あじさい ―アヂサ [3] 【山紫陽花】
サワアジサイの別名。
[3] 【山紫陽花】
サワアジサイの別名。
 [3] 【山紫陽花】
サワアジサイの別名。
[3] 【山紫陽花】
サワアジサイの別名。
やま-あそび【山遊び】🔗⭐🔉
やま-あそび [3] 【山遊び】
三月三日の節句や卯月八日などに,野山に出て終日遊ぶこと。
やま-あたり【山中り】🔗⭐🔉
やま-あたり [3] 【山中り】
「山酔(ヤマヨ)い」に同じ。
やま-あらし【山荒・豪猪】🔗⭐🔉
やま-あらし [3] 【山荒・豪猪】
齧歯(ゲツシ)目のヤマアラシ科とアメリカヤマアラシ科の哺乳類の総称。頭胴長40〜90センチメートル。体と尾の上面にはとげ状に変化した硬い長毛があり,これで敵から身を守り,ときには攻撃に用いる。ヤマアラシ科の多くは尾が短く,木に登らない。アジア・ヨーロッパ・アフリカに分布。また,アメリカヤマアラシ科のものは尾が長く,普通,木の上で生活する。南北アメリカに分布。
山荒
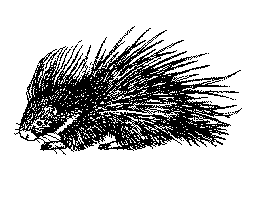 [図]
[図]
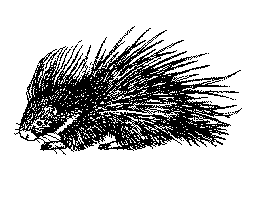 [図]
[図]
やま-あらし【山嵐】🔗⭐🔉
やま-あらし [3] 【山嵐】
(1)山から吹きおろす風。山に吹く嵐。「よし野の山の―も寒く/古今(雑体)」
(2)柔道の投げ技。相手の体を釣り上げながら,右くるぶしのやや上部に右足をあてて,相手の右前隅に大きく投げるもの。
やま-あららぎ【山蘭】🔗⭐🔉
やま-あららぎ 【山蘭】
植物コブシの別名。「妹(イモ)と我(アレ)といるさの山の―手な取り触れそや/催馬楽」
やま-あり【山蟻】🔗⭐🔉
やま-あり [2] 【山蟻】
ヤマアリ属のアリの総称。体長8ミリメートル前後。黒色または赤褐色。クロヤマアリ・アカヤマアリ・エゾアカヤマアリなどを含む。山地にすむものが多い。
やま-あるき【山歩き】🔗⭐🔉
やま-あるき [3] 【山歩き】 (名)スル
山を歩き楽しむこと。
やまい【山藍】🔗⭐🔉
やまい ヤマ 【山藍】
「やまあい」の転。歌では「山井」にかけて用いる。「あしひきの―にすれる衣をば/拾遺(雑秋)」
【山藍】
「やまあい」の転。歌では「山井」にかけて用いる。「あしひきの―にすれる衣をば/拾遺(雑秋)」
 【山藍】
「やまあい」の転。歌では「山井」にかけて用いる。「あしひきの―にすれる衣をば/拾遺(雑秋)」
【山藍】
「やまあい」の転。歌では「山井」にかけて用いる。「あしひきの―にすれる衣をば/拾遺(雑秋)」
やまい【病】🔗⭐🔉
やまい ヤマヒ [1] 【病】
(1)病気。「―の床につく」「―に冒される」
(2)悪い癖。欠点。特に,詩歌で気をつけて避けるべきことがら。「―さるべき心多かりしかば/源氏(玉鬘)」
(3)気がかり。苦労の種。「旦那の―になされた中国北国残らず売つて/浄瑠璃・五十年忌(中)」
やまい-け【病気】🔗⭐🔉
やまい-け ヤマヒ― [4] 【病気】
病気の気味。病気らしい気配。
やまい-だれ【病垂れ】🔗⭐🔉
やまい-だれ ヤマヒ― [0] 【病垂れ】
漢字の垂れの一。「病」「痛」などの「 」。
」。
 」。
」。
やまい-はちまき【病鉢巻】🔗⭐🔉
やまい-はちまき ヤマヒ― 【病鉢巻】
歌舞伎・人形浄瑠璃で,病人であることを示すために,象徴として結ぶ鉢巻。男女とも若い役では紫,老人役では黒の鉢巻を用い,頭の左側で結ぶ。
やま-い【山井】🔗⭐🔉
やま-い ― [2] 【山井】
「やまのい(山の井)」に同じ。「衣手の―の水にかげみえし/新古今(雑下)」
[2] 【山井】
「やまのい(山の井)」に同じ。「衣手の―の水にかげみえし/新古今(雑下)」
 [2] 【山井】
「やまのい(山の井)」に同じ。「衣手の―の水にかげみえし/新古今(雑下)」
[2] 【山井】
「やまのい(山の井)」に同じ。「衣手の―の水にかげみえし/新古今(雑下)」
やま-い【山居】🔗⭐🔉
やま-い ― [2] 【山居】
山に住むこと。また,その居所。やまずみ。
[2] 【山居】
山に住むこと。また,その居所。やまずみ。
 [2] 【山居】
山に住むこと。また,その居所。やまずみ。
[2] 【山居】
山に住むこと。また,その居所。やまずみ。
やま-いたち【山鼬】🔗⭐🔉
やま-いたち [3] 【山鼬】
オコジョの別名。
やまいぬ【病犬】🔗⭐🔉
やまいぬ [0] 【病犬】
〔「やまい犬」の転〕
悪いくせのある犬。また,狂犬。
やまいのそうし【病草紙】🔗⭐🔉
やまいのそうし ヤマヒノサウシ 【病草紙】
平安末期の絵巻。絵・詞書とも作者未詳。種々の奇病や治療法などを集めたもの。
やま-いも【山芋】🔗⭐🔉
やま-いも [0] 【山芋】
「山の芋」に同じ。
やまう【病まふ】🔗⭐🔉
やまう ヤマフ 【病まふ】
病気になること。やまい。「おもき御―をうけさせ給ひしかば/平家 1」
やま・う【病まふ】🔗⭐🔉
やま・う ヤマフ 【病まふ】 (動ハ四)
〔動詞「病(ヤ)む」に反復・継続の助動詞「ふ」の付いたものから〕
病気になる。病む。わずらう。「しられぬ恋に―・ふころかな/永久百首」
やま-うぐいす【山鶯】🔗⭐🔉
やま-うぐいす ―ウグヒス [4] 【山鶯】
山にすむウグイス。
やま-うさぎ【山兎】🔗⭐🔉
やま-うさぎ [3] 【山兎】
山にいる野生のウサギ。
やま-うずら【山鶉】🔗⭐🔉
やま-うずら ―ウヅラ [3] 【山鶉】
キジ目キジ科ヤマウズラ属の鳥の総称。ウズラに似るが大きく,全長25センチメートルほど。胸に馬蹄形の大きな斑紋がある。ユーラシアに三種がある。狩猟鳥。
〔古くは誤ってシャコと呼んだ〕
やま-うど【山独活】🔗⭐🔉
やま-うど [3][0] 【山独活】
山に生えている野生のウド。[季]春。《昼月や―を掌に匂はしめ/石田波郷》
やま-うば【山姥】🔗⭐🔉
やま-うば [2][0] 【山姥】
伝説や昔話で,奥深い山に住んでいる女の怪物。背が高く髪は長く,口は大きく目は光って鋭い。金時を育てた足柄山の山姥,瓜子姫説話の山姥など。やまんば。やまおんな。
→やまんば(山姥)
やま-うり【山売り】🔗⭐🔉
やま-うり [4] 【山売り】
(1)山林や鉱山を売ること。また,それを業とする人。
(2)山師のようなやり口で,人をだまして物を売りつける人。「博奕中間・―/浮世草子・永代蔵 4」
(3)一山(ヒトヤマ)を単位として売ること。山盛りで売ること。
やま-うるし【山漆】🔗⭐🔉
やま-うるし [3] 【山漆】
ウルシ科の落葉小高木。山野に自生。全体にウルシに似るが小さい。葉は枝先付近に互生し,大形の羽状複葉で,秋の紅葉が美しい。雌雄異株。初夏,開花。果実は小さく剛毛が密生する。
やま-お【山尾】🔗⭐🔉
やま-お ―ヲ 【山尾】
山の峰。山の稜線。「うごきなく絶ぬ例と貴船なる―河せに世を祈るかな/兼好集」
やまおか【山岡】🔗⭐🔉
やまおか ヤマヲカ 【山岡】
姓氏の一。
やまおか-げんりん【山岡元隣】🔗⭐🔉
やまおか-げんりん ヤマヲカ― 【山岡元隣】
(1631-1672) 江戸前期の仮名草子作者・俳人。字(アザナ)は徳甫。京の人。医を業とし,また,国学・和歌・俳諧を北村季吟に学ぶ。著に仮名草子「他我身之上」,俳書「宝蔵」,注釈書「徒然草増補鉄槌」など。
やまおか-そうはち【山岡荘八】🔗⭐🔉
やまおか-そうはち ヤマヲカサウハチ 【山岡荘八】
(1907-1978) 小説家。新潟県生まれ。本名,藤野庄蔵。「徳川家康」など時代小説を多作。ほかに「新太平記」「春の坂道」など。
やまおか-てっしゅう【山岡鉄舟】🔗⭐🔉
やまおか-てっしゅう ヤマヲカテツシウ 【山岡鉄舟】
(1836-1888) 幕末・明治の政治家・剣術家。江戸の人。通称,鉄太郎。千葉周作の門人,無刀流を創始。戊辰戦争の時,勝海舟の使者として,勝と西郷隆盛の会談を周旋,江戸開城に尽力。維新後,明治天皇の侍従。
やまおか-ずきん【山岡頭巾】🔗⭐🔉
やまおか-ずきん ヤマヲカヅキン [5][6] 【山岡頭巾】
(1)「苧屑(ホクソ)頭巾」に同じ。
(2)苧屑頭巾に似た長方形の布を二つ折りにして後頭部を縫い合わせたもの。のちにはくさび形の襠(マチ)のはいったものやボタン掛け・小鉤(コハゼ)掛けのものもできた。主に武士が黒・茶などの八丈絹やビロードで仕立てて用いた。
やま-おく【山奥】🔗⭐🔉
やま-おく [3] 【山奥】
山の奥の方。山の深い所。
やま-おくり【山送り】🔗⭐🔉
やま-おくり [3] 【山送り】
死者を山へ送って葬ること。野辺の送り。葬送。「最期の―して/撰集抄 6」
やま-おとこ【山男】🔗⭐🔉
やま-おとこ ―ヲトコ [3] 【山男】
(1)山に住んでいる男。山で働く男。
(2)登山の好きな男。登山歴のある男。
(3)山奥に住んでいると伝えられる怪物。
やま-おやじ【山親爺】🔗⭐🔉
やま-おやじ ―オヤヂ [3] 【山親爺】
(北海道などで)ヒグマのこと。おやじ。
やま-おり【山折(り)】🔗⭐🔉
やま-おり ―ヲリ [0] 【山折(り)】
折り目が外側に出るように,紙などを折ること。
⇔谷折り
やま-おろし【山颪】🔗⭐🔉
やま-おろし [3] 【山颪】
(1)山から吹き下ろす風。「―の風」
(2)下座音楽の一。山中の風が激しく木をゆさぶるさまを表したもので,大太鼓を長撥(バチ)で打つ。山中の場などの幕開き・幕切れなどに用いる。
やま-おんな【山女】🔗⭐🔉
やま-おんな ―ヲンナ [3] 【山女】
(1)「やまうば」に同じ。
(2)アケビの異名。
やま-が【山家】🔗⭐🔉
やま-が [0] 【山家】
山里にある家。
やまが-ずまい【山家住まい】🔗⭐🔉
やまが-ずまい ―ズマヒ [4] 【山家住まい】
山家に住むこと。また,その住居。
やまが-そだち【山家育ち】🔗⭐🔉
やまが-そだち [4] 【山家育ち】
山家に育ったこと。また,その人。
やまが-そば【山家蕎麦】🔗⭐🔉
やまが-そば [4] 【山家蕎麦】
⇒田舎蕎麦(イナカソバ)
やまが【山鹿】🔗⭐🔉
やまが 【山鹿】
熊本県北部の市。近世,宿場町・温泉地として発達。電機工業のほか,製糸・清酒醸造などが伝統産業。山鹿灯籠を特産。
やまが-おんせん【山鹿温泉】🔗⭐🔉
やまが-おんせん ―ヲン― 【山鹿温泉】
熊本県北部,山鹿市にある温泉。平安末期の発見という。炭酸アルカリ泉。
やまが【山鹿】🔗⭐🔉
やまが 【山鹿】
姓氏の一。
やまが-そこう【山鹿素行】🔗⭐🔉
やまが-そこう ―ソカウ 【山鹿素行】
(1622-1685) 江戸前期の儒学者・兵学者。会津の人。江戸に出て朱子学・甲州流軍学,歌学・神道などを学ぶ。武教的儒学によって諸大名らに支持されたが,朱子学を排斥し古代の道への復帰を説いた「聖教要録」の筆禍で赤穂に配流。配所で「中朝事実」を著した。他に著「武家事紀」「山鹿語類」など。
やま-かい【山峡】🔗⭐🔉
やま-かい ―カヒ [0] 【山峡】
山と山とに挟まれた狭い所。
やま-がえる【山蛙】🔗⭐🔉
やま-がえる ―ガヘル [3] 【山蛙】
アカガエルの別名。
やま-かがし【赤楝蛇・山楝蛇】🔗⭐🔉
やま-かがし [3][5] 【赤楝蛇・山楝蛇】
ヘビの一種。全長60〜120センチメートル。体色には変異が多いが普通,緑色を帯びた褐色ないし暗褐色で,黒・黄褐・赤色のまだら模様がある。有毒。水田の周辺に多く,カエルや小魚を食べる。本州以南と朝鮮半島・中国・台湾に分布。
やま-かがち【蟒蛇】🔗⭐🔉
やま-かがち 【蟒蛇】
うわばみ。大蛇。「―のねまり申したるやうな/仮名草子・東海道名所記」
やま-かがみ【山 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
やま-かがみ [3] 【山 】
ビャクレンの異名。[本草和名]
】
ビャクレンの異名。[本草和名]
 】
ビャクレンの異名。[本草和名]
】
ビャクレンの異名。[本草和名]
やま-がく・る【山隠る】🔗⭐🔉
やま-がく・る 【山隠る】
■一■ (動ラ四)
山の向こうにかくれる。山にさえぎられて見えなくなる。「明日よりはみ―・りて見えずかもあらむ/古事記(下)」
■二■ (動ラ下二)
{■一■}に同じ。「―・れ消えせぬ雪のわびしきは/後撰(恋六)」
やま-かけ【山掛(け)】🔗⭐🔉
やま-かけ [0] 【山掛(け)】
刺身・豆腐などの上にとろろ汁をかけた料理。薯掛(イモカケ)。
やまかけ-どうふ【山掛(け)豆腐】🔗⭐🔉
やまかけ-どうふ [5] 【山掛(け)豆腐】
とろろ汁をかけた八杯(ハチハイ)豆腐。いもかけどうふ。やまかけ。
やま-かげ【山陰】🔗⭐🔉
やま-かげ [0] 【山陰】
山にさえぎられて,光のささないこと。山のかげになること。また,その所。
やま-かげ【山影】🔗⭐🔉
やま-かげ [0] 【山影】
湖などに映る山の姿。
やま-かご【山駕籠】🔗⭐🔉
やま-かご [2][0] 【山駕籠】
山道などで用いる粗末な駕籠。竹で円く編んだ底を丸棒や丸竹からつるし,網代(アジロ)の屋根を掛けただけの,垂れも囲いもないもの。山輿(ヤマゴシ)。
山駕籠
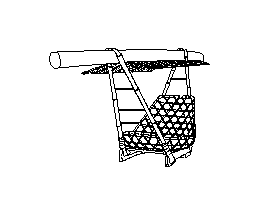 [図]
[図]
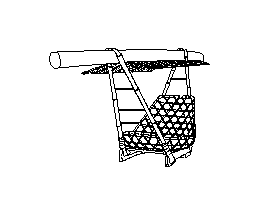 [図]
[図]
やま-がさ【山笠】🔗⭐🔉
やま-がさ [3] 【山笠】
(1)祭礼の時などに被る,飾りの付いた笠。
(2)七月一日から一五日までの,福岡市櫛田神社の例祭に出る山車(ダシ)。博多山笠。[季]夏。
やま-かじ【山火事】🔗⭐🔉
やま-かじ ―クワジ [0][3] 【山火事】
山林の火災。
やま-かずら【山蔓・山鬘】🔗⭐🔉
やま-かずら ―カヅラ [3] 【山蔓・山鬘】
(1)ヒカゲノカズラの別名。「あしひきの―の児今日行くと/万葉 3789」
(2){(1)}で作ったかずら。
(3)山の端にかかる暁の雲。「あら玉の年の明けゆく―/続千載(春上)」
やまかずら-かげ【山蔓陰】🔗⭐🔉
やまかずら-かげ ―カヅラ― 【山蔓陰】
ヒカゲノカズラの別名。「あしひきの―ましばにも/万葉 3573」
やま-かぜ【山風】🔗⭐🔉
やま-かぜ [2] 【山風】
(1)山中を吹く風。また,山の方から吹き下ろす風。「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ/古今(秋下)」
(2)夜,山岳の空気が冷えて山から谷に吹き下ろす風。
⇔谷風
やま-かせぎ【山稼ぎ】🔗⭐🔉
やま-かせぎ [3] 【山稼ぎ】
山で,木を切り出したり炭焼きや狩猟などに従事して生計を立てること。
やま-がた【山形・山型】🔗⭐🔉
やま-がた [0] 【山形・山型】
(1)山に似た形。中央が高く両側に低くなる形。
(2)灌仏会に飾る須弥山の形の作りもの。
(3)紋・符号などとして用いる の形。
(4)「吉原細見」で遊女の階級を示す
の形。
(4)「吉原細見」で遊女の階級を示す などの符号。「―の星結納へさしさはり/柳多留 9」
(5)的皮(マトカワ)の別名。
(6)馬具で,鞍の前輪・後輪(シズワ)の中央の高い所。
(7)折烏帽子(オリエボシ)の部分の名称。「ひなさき」の上。最もつき出たところ。
(8)歌舞伎の立回りの型の一。刀を上段から左に,ついで右に打ちおろすもの。
などの符号。「―の星結納へさしさはり/柳多留 9」
(5)的皮(マトカワ)の別名。
(6)馬具で,鞍の前輪・後輪(シズワ)の中央の高い所。
(7)折烏帽子(オリエボシ)の部分の名称。「ひなさき」の上。最もつき出たところ。
(8)歌舞伎の立回りの型の一。刀を上段から左に,ついで右に打ちおろすもの。
 の形。
(4)「吉原細見」で遊女の階級を示す
の形。
(4)「吉原細見」で遊女の階級を示す などの符号。「―の星結納へさしさはり/柳多留 9」
(5)的皮(マトカワ)の別名。
(6)馬具で,鞍の前輪・後輪(シズワ)の中央の高い所。
(7)折烏帽子(オリエボシ)の部分の名称。「ひなさき」の上。最もつき出たところ。
(8)歌舞伎の立回りの型の一。刀を上段から左に,ついで右に打ちおろすもの。
などの符号。「―の星結納へさしさはり/柳多留 9」
(5)的皮(マトカワ)の別名。
(6)馬具で,鞍の前輪・後輪(シズワ)の中央の高い所。
(7)折烏帽子(オリエボシ)の部分の名称。「ひなさき」の上。最もつき出たところ。
(8)歌舞伎の立回りの型の一。刀を上段から左に,ついで右に打ちおろすもの。
やまがた-こう【山形鋼】🔗⭐🔉
やまがた-こう ―カウ [0][4] 【山形鋼】
形鋼の一。横断面が山形{(3)}の鋼材。種々の構造物に利用。
やまがた-フライス【山形―】🔗⭐🔉
やまがた-フライス [6] 【山形―】
フライスの一種。軸に対して勾配角をもっているフライス。蟻溝(アリミゾ)など特殊な形の溝や歯車の歯を切るのに用いられ,種々の形状のものがある。山形カッター。
やまがた【山形】🔗⭐🔉
やまがた 【山形】
(1)東北地方南西部の県。かつての羽前国全域と羽後国の一部を占める。西は日本海に面して庄内平野がある。ほぼ中央を北流する最上川流域に米沢・山形・新庄の盆地があり,その東には奥羽山脈,西には飯豊・朝日山地がある。県庁所在地,山形市。
(2)山形県東部,山形盆地南部の市。県庁所在地。最上義光の城下町に起源を発し,近世は堀田・水野などの諸氏が領した。立石(リツシヤク)寺(山寺)・蔵王温泉がある。
やまがた-しんかんせん【山形新幹線】🔗⭐🔉
やまがた-しんかんせん 【山形新幹線】
JR 東日本の新幹線。東京・山形間,359.9キロメートル。1992年(平成4)全線開業。東京・福島間は東北新幹線,福島・山形間は奥羽本線を走る。
やまがた-だいがく【山形大学】🔗⭐🔉
やまがた-だいがく 【山形大学】
国立大学の一。1910年(明治43)創立の米沢高等工業(のち工専)と山形高校・県立農林専・師範系学校などが合併し,49年(昭和24)新制大学。本部は山形市。
やま-がた【山県】🔗⭐🔉
やま-がた 【山県】
山にある,あがた。山にある領地。また,山の畑。「―に蒔きしあたね舂(ツ)き/古事記(上)」
やまがた【山県】🔗⭐🔉
やまがた 【山県】
姓氏の一。
やまがた-ありとも【山県有朋】🔗⭐🔉
やまがた-ありとも 【山県有朋】
(1838-1922) 軍人・政治家。長州藩出身。維新後ヨーロッパの兵制を視察し,徴兵令の制定にあたり,陸軍の創設に活躍した。初代参謀本部長。のち陸相・内相を歴任。1889年(明治22),98年の二度組閣。典型的な藩閥政治家として明治政府を主導した。元帥。元老。
やまがた-だいに【山県大弐】🔗⭐🔉
やまがた-だいに 【山県大弐】
(1725-1767) 江戸中期の尊王論者。甲斐(カイ)の人。名は昌貞,号は柳荘。医師で儒学・仏教に通じ,江戸で兵学を講じた。「柳子新論」で尊王の大義を説き,幕政を批判。明和事件に連座して,処刑された。
やまがた【山片】🔗⭐🔉
やまがた 【山片】
姓氏の一。
やまがた-ばんとう【山片蟠桃】🔗⭐🔉
やまがた-ばんとう ―バンタウ 【山片蟠桃】
(1748-1821) 江戸後期の商人・学者。播磨の人。大坂の豪商升屋の経営に番頭として尽力する一方,懐徳堂で儒学,麻田剛立から天文学を学ぶ。主著「夢の代(シロ)」には,世界への広い関心と実用主義的な合理思想がうかがえる。
やま-がたな【山刀】🔗⭐🔉
やま-がたな [3] 【山刀】
山仕事をする人の用いる鉈(ナタ)のような形の刃物。
やま【山】(和英)🔗⭐🔉
やま【山】
(1) a mountain;→英和
a hill (小山);→英和
a peak (峰).→英和
(2)[鉱山]a mine.→英和
(3)[累積]a pile[heap].→英和
(4)[帽子の]the crown.→英和
(5)[小説・劇などの]the climax.→英和
〜の多い mountainous;→英和
hilly.→英和
〜のような mountainous;huge.→英和
〜が当たる make a lucky shot.
〜が見える The end is in sight.〜ほど(の) lots of.〜をかける take[try]one's chance.
〜の幸 mountain products.
やまあい【山間の】(和英)🔗⭐🔉
やまあい【山間の】
in a mountain.→英和
やまい【病】(和英)🔗⭐🔉
やまい【病】
⇒病気.
やまいぬ【山犬】(和英)🔗⭐🔉
やまいぬ【山犬】
a wild dog.
やまいも【山芋】(和英)🔗⭐🔉
やまいも【山芋】
a kind of yam.
やまおく【山奥に】(和英)🔗⭐🔉
やまおく【山奥に】
in the heart of a mountain.→英和
やまおとこ【山男】(和英)🔗⭐🔉
やまおとこ【山男】
a mountaineer (登山家);→英和
a wood(s)man (きこり).
やまおろし【山颪】(和英)🔗⭐🔉
やまおろし【山颪】
a mountain blast.
やまかがし(和英)🔗⭐🔉
やまかがし
[蛇]a grass[ring(ed)]snake.
やまかじ【山火事】(和英)🔗⭐🔉
やまかじ【山火事】
a forest[hill]fire.
やまがた【山形】(和英)🔗⭐🔉
やまがた【山形】
《紋》a chevron<∧,∨>.→英和
広辞苑+大辞林に「やま」で始まるの検索結果。もっと読み込む