複数辞典一括検索+![]()
![]()
世 よ🔗⭐🔉
【世】
 5画 一部 [三年]
区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2
【丗】異体字異体字
5画 一部 [三年]
区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2
【丗】異体字異体字
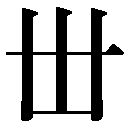 5画 十部
区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0
《常用音訓》セ/セイ/よ
《音読み》 セイ
5画 十部
区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0
《常用音訓》セ/セイ/よ
《音読み》 セイ /セ
/セ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 よ/よよ
《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ
《意味》
〉
《訓読み》 よ/よよ
《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ
《意味》
 {名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕
{名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕
 {名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」
{名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」
 {名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕
{名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕
 {副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕
{副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕
 {形}代々の。先祖からの。「世交」
《解字》
{形}代々の。先祖からの。「世交」
《解字》
 会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。
《単語家族》
泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる)
会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。
《単語家族》
泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる) 曳エイ(引きずる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
曳エイ(引きずる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 5画 一部 [三年]
区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2
【丗】異体字異体字
5画 一部 [三年]
区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2
【丗】異体字異体字
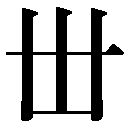 5画 十部
区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0
《常用音訓》セ/セイ/よ
《音読み》 セイ
5画 十部
区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0
《常用音訓》セ/セイ/よ
《音読み》 セイ /セ
/セ 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 よ/よよ
《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ
《意味》
〉
《訓読み》 よ/よよ
《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ
《意味》
 {名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕
{名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕
 {名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」
{名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」
 {名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕
{名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕
 {副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕
{副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕
 {形}代々の。先祖からの。「世交」
《解字》
{形}代々の。先祖からの。「世交」
《解字》
 会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。
《単語家族》
泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる)
会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。
《単語家族》
泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる) 曳エイ(引きずる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
曳エイ(引きずる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
代 よ🔗⭐🔉
【代】
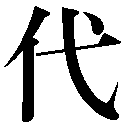 5画 人部 [三年]
区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3
《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ
《音読み》 ダイ
5画 人部 [三年]
区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3
《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ
《音読み》 ダイ /タイ
/タイ 〈d
〈d i〉
《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)
《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より
《意味》
i〉
《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)
《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より
《意味》
 {動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕
{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕
 {名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」
{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」
 {名}ある王朝の統治する期間。「唐代」
{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」
 {単位}世代や王朝の代を数えることば。
{単位}世代や王朝の代を数えることば。
 {副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。
{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。
 {副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。
《解字》
{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。
《解字》
 形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。
《単語家族》
貸タイ(持ち主が入れかわる)
形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。
《単語家族》
貸タイ(持ち主が入れかわる) 袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。
《類義》
化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。
《異字同訓》
かえる/かわる。→変
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。
《類義》
化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。
《異字同訓》
かえる/かわる。→変
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
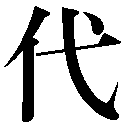 5画 人部 [三年]
区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3
《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ
《音読み》 ダイ
5画 人部 [三年]
区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3
《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ
《音読み》 ダイ /タイ
/タイ 〈d
〈d i〉
《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)
《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より
《意味》
i〉
《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)
《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より
《意味》
 {動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕
{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕
 {名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」
{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」
 {名}ある王朝の統治する期間。「唐代」
{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」
 {単位}世代や王朝の代を数えることば。
{単位}世代や王朝の代を数えることば。
 {副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。
{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。
 {副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。
《解字》
{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。
《解字》
 形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。
《単語家族》
貸タイ(持ち主が入れかわる)
形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。
《単語家族》
貸タイ(持ち主が入れかわる) 袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。
《類義》
化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。
《異字同訓》
かえる/かわる。→変
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。
《類義》
化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。
《異字同訓》
かえる/かわる。→変
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
令 よい🔗⭐🔉
【令】
 5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ
5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
 {名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
 {名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
 {形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
 {名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
 {名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
 レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
 {助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
 {助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
 「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
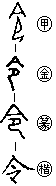 会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷)
会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)
玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)
伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ
5画 人部 [四年]
区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF
《常用音訓》レイ
《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)
/リョウ(リャウ) 〈l
〈l ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ
《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし
《意味》
 {名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」
 {名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」
 {形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」
 {名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」
 {名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」
 レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕
 {助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕
 {助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。
 「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。
《解字》
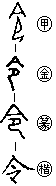 会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷)
会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。
《単語家族》
冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)
玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)
伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
价 よい🔗⭐🔉
余韻 ヨイン🔗⭐🔉
【余韻】
ヨイン  「余音」と同じ。
「余音」と同じ。 物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。
物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。
 「余音」と同じ。
「余音」と同じ。 物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。
物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。
佳 よい🔗⭐🔉
八 よう🔗⭐🔉
【八】
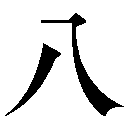 2画 八部 [一年]
区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA
《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう
《音読み》 ハチ
2画 八部 [一年]
区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA
《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう
《音読み》 ハチ /ハツ
/ハツ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ
《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ
《意味》
〉
《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ
《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ
《意味》
 {数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕
{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕
 {数}や。順番の八番め。「八月八日」
{数}や。順番の八番め。「八月八日」
 {副}やたび。八回。
{副}やたび。八回。
 {動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。
〔国〕
{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。
〔国〕 や。数の多いこと。「八千代」
や。数の多いこと。「八千代」 やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
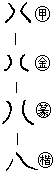 指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。
《単語家族》
別
指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。
《単語家族》
別 撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
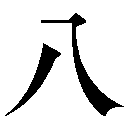 2画 八部 [一年]
区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA
《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう
《音読み》 ハチ
2画 八部 [一年]
区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA
《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう
《音読み》 ハチ /ハツ
/ハツ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ
《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ
《意味》
〉
《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ
《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ
《意味》
 {数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕
{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕
 {数}や。順番の八番め。「八月八日」
{数}や。順番の八番め。「八月八日」
 {副}やたび。八回。
{副}やたび。八回。
 {動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。
〔国〕
{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。
〔国〕 や。数の多いこと。「八千代」
や。数の多いこと。「八千代」 やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。
《解字》
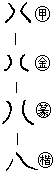 指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。
《単語家族》
別
指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。
《単語家族》
別 撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
吉 よい🔗⭐🔉
【吉】
 6画 口部 [常用漢字]
区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67
《常用音訓》キチ/キツ
《音読み》 キチ
6画 口部 [常用漢字]
区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67
《常用音訓》キチ/キツ
《音読み》 キチ /キツ
/キツ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし
《意味》
 キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕
キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕
 キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕
キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕
 「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。
《解字》
「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。
《解字》
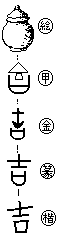 象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。
《単語家族》
壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける)
象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。
《単語家族》
壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける) 詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 6画 口部 [常用漢字]
区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67
《常用音訓》キチ/キツ
《音読み》 キチ
6画 口部 [常用漢字]
区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67
《常用音訓》キチ/キツ
《音読み》 キチ /キツ
/キツ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし
《意味》
 キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕
キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕
 キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕
キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕
 「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。
《解字》
「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。
《解字》
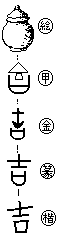 象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。
《単語家族》
壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける)
象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。
《単語家族》
壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける) 詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
善 よい🔗⭐🔉
【善】
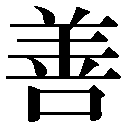 12画 口部 [六年]
区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150
【譱】異体字異体字
12画 口部 [六年]
区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150
【譱】異体字異体字
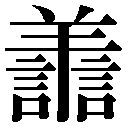 20画 言部
区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF
《常用音訓》ゼン/よ…い
《音読み》 ゼン
20画 言部
区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF
《常用音訓》ゼン/よ…い
《音読み》 ゼン /セン
/セン 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 さ・ただし・たる・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 さ・ただし・たる・よし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕
{形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕
 {名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕
{名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕
{形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」
{形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」
 {形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
{形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
 {動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕
《解字》
{動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕
《解字》
 会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。
《単語家族》
膳ゼン(みごとにそろった食べ物)
会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。
《単語家族》
膳ゼン(みごとにそろった食べ物) 亶タン(たっぷりとする)と同系。
《類義》
→良
《異字同訓》
よい。 →良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
亶タン(たっぷりとする)と同系。
《類義》
→良
《異字同訓》
よい。 →良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
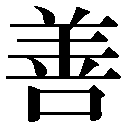 12画 口部 [六年]
区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150
【譱】異体字異体字
12画 口部 [六年]
区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150
【譱】異体字異体字
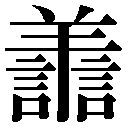 20画 言部
区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF
《常用音訓》ゼン/よ…い
《音読み》 ゼン
20画 言部
区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF
《常用音訓》ゼン/よ…い
《音読み》 ゼン /セン
/セン 〈sh
〈sh n〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 さ・ただし・たる・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 さ・ただし・たる・よし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕
{形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕
 {名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕
{名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕
{形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」
{形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」
 {形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
{形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
 {動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕
《解字》
{動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕
《解字》
 会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。
《単語家族》
膳ゼン(みごとにそろった食べ物)
会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。
《単語家族》
膳ゼン(みごとにそろった食べ物) 亶タン(たっぷりとする)と同系。
《類義》
→良
《異字同訓》
よい。 →良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
亶タン(たっぷりとする)と同系。
《類義》
→良
《異字同訓》
よい。 →良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
嘉 よい🔗⭐🔉
【嘉】
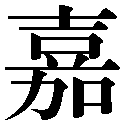 14画 口部 [人名漢字]
区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3
《音読み》 カ
14画 口部 [人名漢字]
区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3
《音読み》 カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」
{形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」
 {動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕
{動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕
 {名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」
《解字》
{名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」
《解字》
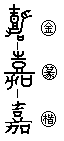 会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。
《単語家族》
賀(祝い)と同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。
《単語家族》
賀(祝い)と同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
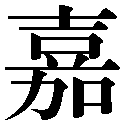 14画 口部 [人名漢字]
区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3
《音読み》 カ
14画 口部 [人名漢字]
区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3
《音読み》 カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)
《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」
{形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」
 {動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕
{動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕
 {名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」
《解字》
{名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」
《解字》
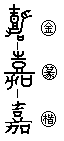 会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。
《単語家族》
賀(祝い)と同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。
《単語家族》
賀(祝い)と同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
四 よ🔗⭐🔉
【四】
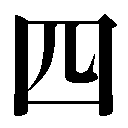 5画 囗部 [一年]
区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C
《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん
《音読み》 シ
5画 囗部 [一年]
区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C
《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに
《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ
《意味》
〉
《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに
《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ
《意味》
 {数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕
{数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕
 {数}よ。順番の四番め。「四月四日」
{数}よ。順番の四番め。「四月四日」
 {動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕
{動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕
 {副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕
〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」
《解字》
{副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕
〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」
《解字》
 会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。
《単語家族》
死(生気が分散し去る)
会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。
《単語家族》
死(生気が分散し去る) 西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
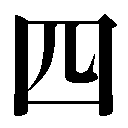 5画 囗部 [一年]
区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C
《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん
《音読み》 シ
5画 囗部 [一年]
区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C
《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん
《音読み》 シ
 〈s
〈s 〉
《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに
《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ
《意味》
〉
《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに
《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ
《意味》
 {数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕
{数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕
 {数}よ。順番の四番め。「四月四日」
{数}よ。順番の四番め。「四月四日」
 {動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕
{動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕
 {副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕
〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」
《解字》
{副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕
〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」
《解字》
 会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。
《単語家族》
死(生気が分散し去る)
会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。
《単語家族》
死(生気が分散し去る) 西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
壅遏 ヨウアツ🔗⭐🔉
【壅遏】
ヨウアツ 行動をさえぎりとどめる。わく内に押しこめる。
夜 よ🔗⭐🔉
【夜】
 8画 夕部 [二年]
区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9
《常用音訓》ヤ/よ/よる
《音読み》 ヤ
8画 夕部 [二年]
区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9
《常用音訓》ヤ/よ/よる
《音読み》 ヤ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)
《名付け》 やす・よ・よる
《意味》
〉
《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)
《名付け》 やす・よ・よる
《意味》
 {名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕
{名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕
 {副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕
《解字》
{副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕
《解字》
 会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。
《単語家族》
腋(からだの両わき)
会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。
《単語家族》
腋(からだの両わき) 掖エキ(わきをささえる)と同系。
《類義》
→暮
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
掖エキ(わきをささえる)と同系。
《類義》
→暮
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 8画 夕部 [二年]
区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9
《常用音訓》ヤ/よ/よる
《音読み》 ヤ
8画 夕部 [二年]
区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9
《常用音訓》ヤ/よ/よる
《音読み》 ヤ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)
《名付け》 やす・よ・よる
《意味》
〉
《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)
《名付け》 やす・よ・よる
《意味》
 {名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕
{名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕
 {副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕
《解字》
{副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕
《解字》
 会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。
《単語家族》
腋(からだの両わき)
会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。
《単語家族》
腋(からだの両わき) 掖エキ(わきをささえる)と同系。
《類義》
→暮
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
掖エキ(わきをささえる)と同系。
《類義》
→暮
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
好 よい🔗⭐🔉
【好】
 6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
 〈h
〈h o・h
o・h o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
 {動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
 {形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
 {形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
 {名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
 {動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
 {名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
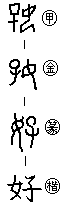 会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする)
会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)
畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
6画 女部 [四年]
区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44
《常用音訓》コウ/この…む/す…く
《音読み》 コウ(カウ)
 〈h
〈h o・h
o・h o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
o〉
《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ
《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ
《意味》
 {動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕
 {形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕
 {形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕
 {形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕
 {名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕
 {動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」
 {名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」
〔国〕このみ。趣味。
《解字》
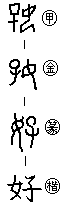 会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする)
会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。
《単語家族》
休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)
畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
孝(親をたいせつにする)などと同系。
《類義》
→良
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
宵 よ🔗⭐🔉
【宵】
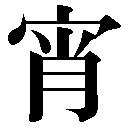 10画 宀部 [常用漢字]
区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA
《常用音訓》ショウ/よい
《音読み》 ショウ(セウ)
10画 宀部 [常用漢字]
区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA
《常用音訓》ショウ/よい
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ
《名付け》 よい
《意味》
o〉
《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ
《名付け》 よい
《意味》
 {名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
{名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
 {名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」
{名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」
 {形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」
《解字》
会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。
《単語家族》
消(水で火の勢いを小さくする)
{形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」
《解字》
会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。
《単語家族》
消(水で火の勢いを小さくする) 削(けずって小さくする)と同系。
《類義》
→晩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
削(けずって小さくする)と同系。
《類義》
→晩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
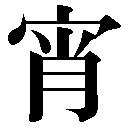 10画 宀部 [常用漢字]
区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA
《常用音訓》ショウ/よい
《音読み》 ショウ(セウ)
10画 宀部 [常用漢字]
区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA
《常用音訓》ショウ/よい
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ
《名付け》 よい
《意味》
o〉
《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ
《名付け》 よい
《意味》
 {名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
{名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
 {名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」
{名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」
 {形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」
《解字》
会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。
《単語家族》
消(水で火の勢いを小さくする)
{形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」
《解字》
会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。
《単語家族》
消(水で火の勢いを小さくする) 削(けずって小さくする)と同系。
《類義》
→晩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
削(けずって小さくする)と同系。
《類義》
→晩
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
容易 ヨウイ🔗⭐🔉
【容易】
ヨウイ 困難のないこと。ゆとりがあってしやすい。
庸医 ヨウイ🔗⭐🔉
【庸医】
ヨウイ 平凡な医者。やぶ医者。
徽 よい🔗⭐🔉
【徽】
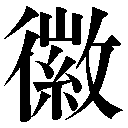 16画 彳部
区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A
《音読み》 キ(ク
16画 彳部
区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A
《音読み》 キ(ク )
) /ケ
/ケ 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)
《意味》
〉
《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)
《意味》
 {名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」
{名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」
 {形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」
{形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」
 {名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」
{名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」
 {名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。
《解字》
会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。
《解字》
会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
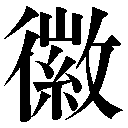 16画 彳部
区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A
《音読み》 キ(ク
16画 彳部
区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A
《音読み》 キ(ク )
) /ケ
/ケ 〈hu
〈hu 〉
《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)
《意味》
〉
《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)
《意味》
 {名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」
{名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」
 {形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」
{形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」
 {名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」
{名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」
 {名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。
《解字》
会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。
《解字》
会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
懿 よい🔗⭐🔉
曜威 ヨウイ🔗⭐🔉
【曜威】
ヨウイ  威光をかがやかせる。
威光をかがやかせる。 偉そうにいばる。
偉そうにいばる。
 威光をかがやかせる。
威光をかがやかせる。 偉そうにいばる。
偉そうにいばる。
洋夷 ヨウイ🔗⭐🔉
【洋夷】
ヨウイ 西洋人をいやしんでいうことば。▽「夷」は野蛮人の意。
淑 よい🔗⭐🔉
【淑】
 11画 水部 [常用漢字]
区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69
《常用音訓》シュク
《音読み》 シュク
11画 水部 [常用漢字]
区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69
《常用音訓》シュク
《音読み》 シュク /ジュク
/ジュク 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)
《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)
《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」
{形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」
 {動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」
《解字》
会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔
《単語家族》
叔(年齢の小さいほうのおじ)
{動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」
《解字》
会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔
《単語家族》
叔(年齢の小さいほうのおじ) 菽シュク(小さい豆)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
菽シュク(小さい豆)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 水部 [常用漢字]
区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69
《常用音訓》シュク
《音読み》 シュク
11画 水部 [常用漢字]
区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69
《常用音訓》シュク
《音読み》 シュク /ジュク
/ジュク 〈sh
〈sh 〉
《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)
《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)
《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」
{形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」
 {動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」
《解字》
会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔
《単語家族》
叔(年齢の小さいほうのおじ)
{動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」
《解字》
会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔
《単語家族》
叔(年齢の小さいほうのおじ) 菽シュク(小さい豆)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
菽シュク(小さい豆)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
用 よう🔗⭐🔉
【用】
 5画 用部 [二年]
区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770
《常用音訓》ヨウ/もち…いる
《音読み》 ヨウ
5画 用部 [二年]
区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770
《常用音訓》ヨウ/もち…いる
《音読み》 ヨウ /ユウ
/ユウ 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう
《名付け》 ちか・もち
《意味》
ng〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう
《名付け》 ちか・もち
《意味》
 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用
ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用 ルノ地」
ルノ地」
 {名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕
{名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕
 {名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」
{名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」
 {名}道具。「器用(道具や、うつわ)」
{名}道具。「器用(道具や、うつわ)」
 {動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕
〔国〕
{動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕
〔国〕 よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」
よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」 よう。大小便をする。「小用」
《解字》
よう。大小便をする。「小用」
《解字》
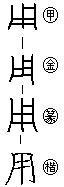 会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。
《単語家族》
庸(つき通す、ならす)
会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。
《単語家族》
庸(つき通す、ならす) 通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 5画 用部 [二年]
区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770
《常用音訓》ヨウ/もち…いる
《音読み》 ヨウ
5画 用部 [二年]
区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770
《常用音訓》ヨウ/もち…いる
《音読み》 ヨウ /ユウ
/ユウ 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう
《名付け》 ちか・もち
《意味》
ng〉
《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう
《名付け》 ちか・もち
《意味》
 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用
ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用 ルノ地」
ルノ地」
 {名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕
{名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕
 {名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」
{名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」
 {名}道具。「器用(道具や、うつわ)」
{名}道具。「器用(道具や、うつわ)」
 {動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕
〔国〕
{動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕
〔国〕 よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」
よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」 よう。大小便をする。「小用」
《解字》
よう。大小便をする。「小用」
《解字》
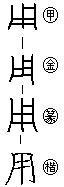 会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。
《単語家族》
庸(つき通す、ならす)
会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。
《単語家族》
庸(つき通す、ならす) 通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
用意 ヨウイ🔗⭐🔉
【用意】
ヨウイ  イヲモチウ心をつかう。
イヲモチウ心をつかう。 〔国〕注意。用心。
〔国〕注意。用心。 〔国〕つもり。準備。
〔国〕つもり。準備。
 イヲモチウ心をつかう。
イヲモチウ心をつかう。 〔国〕注意。用心。
〔国〕注意。用心。 〔国〕つもり。準備。
〔国〕つもり。準備。
穀 よい🔗⭐🔉
【穀】
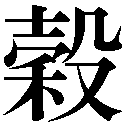 人名に使える旧字
人名に使える旧字
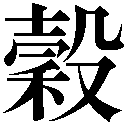 14画 禾部 [六年]
区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92
《常用音訓》コク
《音読み》 コク
14画 禾部 [六年]
区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92
《常用音訓》コク
《音読み》 コク
 〈g
〈g 〉
《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)
《名付け》 よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)
《名付け》 よし・より
《意味》
 {名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕
{名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕
 {動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に
{動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に の意という。
の意という。
 {動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕
{動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕
 {動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕
{動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕
 コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。
《単語家族》
角
コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。
《単語家族》
角 殼(=殻。から)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
殼(=殻。から)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
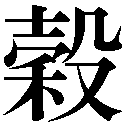 人名に使える旧字
人名に使える旧字
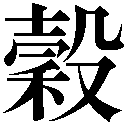 14画 禾部 [六年]
区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92
《常用音訓》コク
《音読み》 コク
14画 禾部 [六年]
区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92
《常用音訓》コク
《音読み》 コク
 〈g
〈g 〉
《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)
《名付け》 よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)
《名付け》 よし・より
《意味》
 {名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕
{名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕
 {動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に
{動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に の意という。
の意という。
 {動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕
{動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕
 {動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕
{動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕
 コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。
《単語家族》
角
コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。
《単語家族》
角 殼(=殻。から)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
殼(=殻。から)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
美 よい🔗⭐🔉
【美】
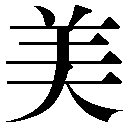 9画 羊部 [三年]
区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC
《常用音訓》ビ/うつく…しい
《音読み》 ビ
9画 羊部 [三年]
区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC
《常用音訓》ビ/うつく…しい
《音読み》 ビ /ミ
/ミ 〈m
〈m i〉
《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)
《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)
《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし
《意味》
 ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕
ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕
 ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」
ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」
 ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕
ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕
 {名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕
{名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕
 〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。
《解字》
会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。
《単語家族》
微ビ
〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。
《解字》
会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。
《単語家族》
微ビ 眉ビ(細いまゆげ)
眉ビ(細いまゆげ) 尾(細いおの毛)
尾(細いおの毛) 媚ビ(なまめかしい)などと同系。
《類義》
麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
媚ビ(なまめかしい)などと同系。
《類義》
麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
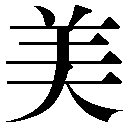 9画 羊部 [三年]
区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC
《常用音訓》ビ/うつく…しい
《音読み》 ビ
9画 羊部 [三年]
区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC
《常用音訓》ビ/うつく…しい
《音読み》 ビ /ミ
/ミ 〈m
〈m i〉
《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)
《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし
《意味》
i〉
《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)
《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし
《意味》
 ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕
ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕
 ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」
ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」
 ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕
ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕
 {名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕
{名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕
 〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。
《解字》
会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。
《単語家族》
微ビ
〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。
《解字》
会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。
《単語家族》
微ビ 眉ビ(細いまゆげ)
眉ビ(細いまゆげ) 尾(細いおの毛)
尾(細いおの毛) 媚ビ(なまめかしい)などと同系。
《類義》
麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
媚ビ(なまめかしい)などと同系。
《類義》
麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
義 よい🔗⭐🔉
【義】
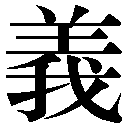 13画 羊部 [五年]
区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60
《常用音訓》ギ
《音読み》 ギ
13画 羊部 [五年]
区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60
《常用音訓》ギ
《音読み》 ギ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より
《意味》
 {名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕
{名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕
 {名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」
{名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」
 {名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」
{名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」
 {名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」
{名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」
 {名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」
{名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」
 {形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」
〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」
《解字》
{形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」
〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」
《解字》
 会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。
《単語家族》
峨ガ(かどめのたった山)
会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。
《単語家族》
峨ガ(かどめのたった山) 儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
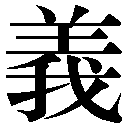 13画 羊部 [五年]
区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60
《常用音訓》ギ
《音読み》 ギ
13画 羊部 [五年]
区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60
《常用音訓》ギ
《音読み》 ギ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)
《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より
《意味》
 {名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕
{名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕
 {名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」
{名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」
 {名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」
{名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」
 {名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」
{名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」
 {名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」
{名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」
 {形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」
〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」
《解字》
{形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」
〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」
《解字》
 会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。
《単語家族》
峨ガ(かどめのたった山)
会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。
《単語家族》
峨ガ(かどめのたった山) 儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
腆 よい🔗⭐🔉
臧 よい🔗⭐🔉
【臧】
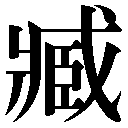 15画 臣部
区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468
《音読み》 ソウ(サウ)
15画 臣部
区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468
《音読み》 ソウ(サウ)
 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 よい(よし)
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕
{形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕
 {名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」
《解字》
会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。
《単語家族》
壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」
《解字》
会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。
《単語家族》
壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
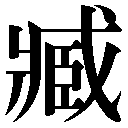 15画 臣部
区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468
《音読み》 ソウ(サウ)
15画 臣部
区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468
《音読み》 ソウ(サウ)
 〈z
〈z ng〉
《訓読み》 よい(よし)
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕
{形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕
 {名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」
《解字》
会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。
《単語家族》
壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」
《解字》
会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。
《単語家族》
壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
良 よい🔗⭐🔉
【良】
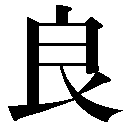 7画 艮部 [四年]
区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7
《常用音訓》リョウ/よ…い
《音読み》 リョウ(リヤウ)
7画 艮部 [四年]
区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7
《常用音訓》リョウ/よ…い
《音読み》 リョウ(リヤウ) /ロウ(ラウ)
/ロウ(ラウ) 〈li
〈li ng〉
《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや
《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや
《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕
{形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕
 {名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」
{名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」
 {副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ
{副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ 有ルナリ」〔→李白〕
有ルナリ」〔→李白〕
 {副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕
{副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕
 「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕
《解字》
「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕
《解字》
 会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。
《単語家族》
亮リョウ(けがれのない)
会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。
《単語家族》
亮リョウ(けがれのない) 涼リョウ(けがれのない)
涼リョウ(けがれのない) 諒リョウ(けがれのない)などと同系。
《類義》
善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。
《異字同訓》
よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
諒リョウ(けがれのない)などと同系。
《類義》
善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。
《異字同訓》
よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
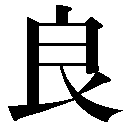 7画 艮部 [四年]
区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7
《常用音訓》リョウ/よ…い
《音読み》 リョウ(リヤウ)
7画 艮部 [四年]
区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7
《常用音訓》リョウ/よ…い
《音読み》 リョウ(リヤウ) /ロウ(ラウ)
/ロウ(ラウ) 〈li
〈li ng〉
《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや
《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう
《意味》
ng〉
《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや
《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕
{形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕
 {名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」
{名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」
 {副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ
{副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ 有ルナリ」〔→李白〕
有ルナリ」〔→李白〕
 {副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕
{副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕
 「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕
《解字》
「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕
《解字》
 会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。
《単語家族》
亮リョウ(けがれのない)
会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。
《単語家族》
亮リョウ(けがれのない) 涼リョウ(けがれのない)
涼リョウ(けがれのない) 諒リョウ(けがれのない)などと同系。
《類義》
善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。
《異字同訓》
よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
諒リョウ(けがれのない)などと同系。
《類義》
善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。
《異字同訓》
よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
茗 よう🔗⭐🔉
誼 よい🔗⭐🔉
【誼】
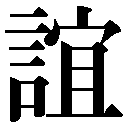 15画 言部 [人名漢字]
区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62
《音読み》 ギ
15画 言部 [人名漢字]
区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62
《音読み》 ギ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる
《名付け》 こと・よし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる
《名付け》 こと・よし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。
{形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。
 {名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。
{名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。
 {名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」
{名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」
 {名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」
{名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」
 {動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。
《解字》
会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。
《熟語》
→下付・中付語
{動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。
《解字》
会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。
《熟語》
→下付・中付語
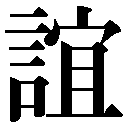 15画 言部 [人名漢字]
区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62
《音読み》 ギ
15画 言部 [人名漢字]
区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62
《音読み》 ギ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる
《名付け》 こと・よし
《意味》
〉
《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる
《名付け》 こと・よし
《意味》
 {形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。
{形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。
 {名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。
{名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。
 {名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」
{名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」
 {名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」
{名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」
 {動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。
《解字》
会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。
《熟語》
→下付・中付語
{動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。
《解字》
会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。
《熟語》
→下付・中付語
買酔 ヨイヲカウ🔗⭐🔉
【買酔】
バイスイ・ヨイヲカウ 酔いを買う。酒を買って酔うこと。
酔 よう🔗⭐🔉
【酔】
 11画 酉部 [常用漢字]
区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C
【醉】旧字人名に使える旧字
11画 酉部 [常用漢字]
区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C
【醉】旧字人名に使える旧字
 15画 酉部
区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB
《常用音訓》スイ/よ…う
《音読み》 スイ
15画 酉部
区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB
《常用音訓》スイ/よ…う
《音読み》 スイ
 〈zu
〈zu 〉
《訓読み》 よう(よふ)
《意味》
〉
《訓読み》 よう(よふ)
《意味》
 {動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕
{動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕
 {動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕
{動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕
 {形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」
〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」
《解字》
会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。
《単語家族》
碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。
《類義》
酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」
〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」
《解字》
会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。
《単語家族》
碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。
《類義》
酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 酉部 [常用漢字]
区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C
【醉】旧字人名に使える旧字
11画 酉部 [常用漢字]
区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C
【醉】旧字人名に使える旧字
 15画 酉部
区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB
《常用音訓》スイ/よ…う
《音読み》 スイ
15画 酉部
区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB
《常用音訓》スイ/よ…う
《音読み》 スイ
 〈zu
〈zu 〉
《訓読み》 よう(よふ)
《意味》
〉
《訓読み》 よう(よふ)
《意味》
 {動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕
{動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕
 {動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕
{動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕
 {形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」
〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」
《解字》
会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。
《単語家族》
碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。
《類義》
酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」
〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」
《解字》
会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。
《単語家族》
碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。
《類義》
酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
悪酔而強酒 ヨイヲニクミテサケヲシウ🔗⭐🔉
【悪酔而強酒】
ヨイヲニクミテサケヲシウ〈故事〉酒を飲んで酔うことをきらいながら、無理をして酒を飲む。意志と反対の行動をすること。〔→孟子〕
醺 よう🔗⭐🔉
雍遏 ヨウアツ🔗⭐🔉
【雍閼】
ヨウアツ ふさぎとどめる。物事をやめさせること。『雍遏ヨウアツ』
霄 よい🔗⭐🔉
養痾 ヨウア🔗⭐🔉
【養病】
ヨウヘイ・ヨウビョウ 病気の手当てをして病気をなおす。『養疾ヨウシツ・養痾ヨウア』
漢字源に「ヨ」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む
 6画 人部
区点=4835 16進=5043 シフトJIS=98C1
《音読み》 カイ
6画 人部
区点=4835 16進=5043 シフトJIS=98C1
《音読み》 カイ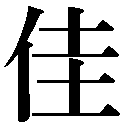 8画 人部 [常用漢字]
区点=1834 16進=3242 シフトJIS=89C0
《常用音訓》カ
《音読み》 カ
8画 人部 [常用漢字]
区点=1834 16進=3242 シフトJIS=89C0
《常用音訓》カ
《音読み》 カ /ケ
/ケ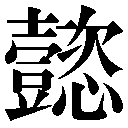 22画 心部
区点=5684 16進=5874 シフトJIS=9CF2
《音読み》 イ
22画 心部
区点=5684 16進=5874 シフトJIS=9CF2
《音読み》 イ 12画 肉部
区点=7102 16進=6722 シフトJIS=E441
《音読み》 テン
12画 肉部
区点=7102 16進=6722 シフトJIS=E441
《音読み》 テン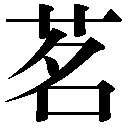 9画 艸部
区点=7212 16進=682C シフトJIS=E4AA
《音読み》 メイ
9画 艸部
区点=7212 16進=682C シフトJIS=E4AA
《音読み》 メイ 21画 酉部
区点=7853 16進=6E55 シフトJIS=E7D3
《音読み》 クン
21画 酉部
区点=7853 16進=6E55 シフトJIS=E7D3
《音読み》 クン 15画 雨部
区点=8028 16進=703C シフトJIS=E8BA
《音読み》 ショウ(セウ)
15画 雨部
区点=8028 16進=703C シフトJIS=E8BA
《音読み》 ショウ(セウ)