複数辞典一括検索+![]()
![]()
けつ‐あつ【血圧】🔗⭐🔉
けつ‐あつ【血圧】
血管壁に及ぼす血流の内圧。普通、動脈圧をいい、上腕動脈で測定する。血圧に影響するのは血液の粘度のほか、心臓の駆出力、動脈壁の弾力性、血流末梢の抵抗などで、心拍動に伴って収縮期に上昇し、拡張期に下降する波動を呈する。前者を収縮期血圧(最大・最高)、後者を拡張期血圧(最小・最低)といい、その差を脈圧という。人の最高血圧は平均水銀柱120ミリメートル、最低血圧は80ミリメートル前後であるが、年齢とともに高まる。病的に持続して血圧の高い状態を高血圧といい、低い状態を低血圧という。
⇒けつあつ‐けい【血圧計】
⇒けつあつ‐こうしん‐しょう【血圧亢進症】
けつあつ‐けい【血圧計】🔗⭐🔉
けつあつ‐けい【血圧計】
血圧を測定する装置。広く用いられるのは水銀血圧計で、上腕に圧迫帯を巻き、その遠位部の上腕動脈に聴診器を当て、圧迫帯の空気圧低下に伴う血管雑音を聴いて圧力計から間接的に血圧を測る。電子工学的な原理による空気血圧計あるいはアネロイド型血圧計を応用した自動血圧計もある。
⇒けつ‐あつ【血圧】
けつあつ‐こうしん‐しょう【血圧亢進症】‥カウ‥シヤウ🔗⭐🔉
けつあつ‐こうしん‐しょう【血圧亢進症】‥カウ‥シヤウ
血圧が異常にかつ慢性に亢進する病症。大循環系にみられる高血圧症と小循環系にみられる肺高血圧症とがある。
⇒けつ‐あつ【血圧】
けつ‐いん【血胤】🔗⭐🔉
けつ‐いん【血胤】
血すじ。血統をひいた子孫。
けつ‐えき【血液】🔗⭐🔉
けつ‐えき【血液】
動物体内を循環する体液の一種。脊椎動物では血球(赤血球・白血球・血小板)および血漿から成る。組織に酸素・栄養を供給し、二酸化炭素その他の代謝生成物を運び去る。白血球は食作用や抗体産生により、生体防御の役をする。血ち。
⇒けつえき‐がた【血液型】
⇒けつえきがた‐ふてきごう【血液型不適合】
⇒けつえき‐ぎょうこ【血液凝固】
⇒けつえきぎょうこ‐いんし【血液凝固因子】
⇒けつえき‐じゅんかん【血液循環】
⇒けつえき‐せいざい【血液製剤】
⇒けつえき‐センター【血液センター】
⇒けつえき‐ぞう【血液像】
⇒けつえき‐とうせき【血液透析】
⇒けつえき‐ドーピング【血液ドーピング】
けつえき‐がた【血液型】🔗⭐🔉
けつえき‐がた【血液型】
赤血球膜にふくまれる抗原の種類によって区別される血液の型。ふつう抗原抗体反応である血球凝集反応によって、その種類を分類する。血液型抗原は遺伝的に定まり多数の組合せが知られているが、ABO式、MN式、Rh式などが用いられ、輸血の適合性、親子関係の判定などに用いる。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえきがた‐ふてきごう【血液型不適合】‥ガフ🔗⭐🔉
けつえきがた‐ふてきごう【血液型不適合】‥ガフ
供血者と受血者の間で血液型が異なり輸血できないこと。誤って輸血するとアレルギー反応・ショック・腎不全などを起こす。また母子間に血液型不適合があると、胎児死亡、新生児の貧血・黄疸・肝脾腫・全身水腫(胎児性赤芽球症・先天性胎児性全身水腫)を来す。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐ぎょうこ【血液凝固】🔗⭐🔉
けつえき‐ぎょうこ【血液凝固】
血液がかたまること。血液は血管外に流れ出るとかたまり、その性質は止血のために重要。病的には血管内で凝固が起こることもある。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえきぎょうこ‐いんし【血液凝固因子】🔗⭐🔉
けつえきぎょうこ‐いんし【血液凝固因子】
血液が固まるのに関与する物質。ローマ数字でⅠ〜 (Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。
⇒けつ‐えき【血液】
(Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。
⇒けつ‐えき【血液】
 (Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。
⇒けつ‐えき【血液】
(Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐じゅんかん【血液循環】‥クワン🔗⭐🔉
けつえき‐じゅんかん【血液循環】‥クワン
動物体内での血のめぐり。普通は心臓または類似器官の拍動によって行われる。哺乳類では心臓→動脈→毛細血管→静脈→心臓→肺→心臓と循環する。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐せいざい【血液製剤】🔗⭐🔉
けつえき‐せいざい【血液製剤】
人の血液を材料としてつくる薬剤。血中有効成分を抽出したもの。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐センター【血液センター】🔗⭐🔉
けつえき‐センター【血液センター】
輸血に必要な血液を常に確保するため、献血を受け入れて保存管理し、必要に応じて迅速に供給することを業務とする施設。1936年シカゴに創立。日本では51年発足。現在、全国に77カ所の日本赤十字社血液センターがある。旧称、血液銀行。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐ぞう【血液像】‥ザウ🔗⭐🔉
けつえき‐ぞう【血液像】‥ザウ
血液の細胞成分の性状。赤血球の数・形・大きさ、白血球の数、種類別割合、形態異常の有無等の総称。疾病の種類により変化があるので診断に役立つ。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐とうせき【血液透析】🔗⭐🔉
けつえき‐とうせき【血液透析】
(→)人工透析に同じ。
⇒けつ‐えき【血液】
けつえき‐ドーピング【血液ドーピング】🔗⭐🔉
けつえき‐ドーピング【血液ドーピング】
スポーツ選手が運動能力向上のために、輸血により赤血球またはその産生に関連した物質を静脈内に投与すること。
⇒けつ‐えき【血液】
けつ‐えん【血縁】🔗⭐🔉
けつ‐えん【血縁】
①血すじ。血脈。血のつながり。
②血すじをひく親族。血族。けちえん。
↔地縁。
⇒けつえん‐かんけい【血縁関係】
⇒けつえん‐しゅうだん【血縁集団】
⇒けつえん‐とうた【血縁淘汰】
けつえん‐かんけい【血縁関係】‥クワン‥🔗⭐🔉
けつえん‐かんけい【血縁関係】‥クワン‥
親子関係と兄弟姉妹関係とを基本とし、さらにこの関係の連鎖で結ばれる関係。生物学的な血の関係だけでなく、共通の先祖をもつと信じあっている関係も含まれる。血族関係。
⇒けつ‐えん【血縁】
けつえん‐しゅうだん【血縁集団】‥シフ‥🔗⭐🔉
けつえん‐しゅうだん【血縁集団】‥シフ‥
血縁関係に基づいて成立した社会集団。最も一般的なものは親族集団。
⇒けつ‐えん【血縁】
けつえん‐とうた【血縁淘汰】‥タウ‥🔗⭐🔉
けつえん‐とうた【血縁淘汰】‥タウ‥
血縁のある個体間に有利に働く淘汰。利他的行動(例えば働き蜂)や子の保護は、この淘汰により進化してきたと考えられる。血縁選択。
⇒けつ‐えん【血縁】
けっ‐かい【血塊】‥クワイ🔗⭐🔉
けっ‐かい【血塊】‥クワイ
血液のかたまり。
けっ‐かん【血管】‥クワン🔗⭐🔉
けっ‐かん【血管】‥クワン
血液の通る管。脊椎動物では内腔が内皮で覆われ、壁の中層の平滑筋と弾性繊維が血管の径を変化させて血流を調節する。動脈・静脈および毛細血管の別がある。
⇒けっかん‐けい【血管系】
⇒けっかん‐しゅ【血管腫】
⇒けっかん‐ぞうえい【血管造影】
けっかん‐けい【血管系】‥クワン‥🔗⭐🔉
けっかん‐けい【血管系】‥クワン‥
血液の通路をなす脈管の系。心臓を含める場合もある。脊椎動物などの閉鎖血管系では、動脈系・静脈系・毛細血管系の別があり、心臓から発する動脈は走行の過程で無数の枝に分かれて毛細血管となり、これが再び合して静脈となり心臓に帰る。節足動物・軟体動物にみられる開放血管系では、毛細血管を欠き、動脈系・静脈系の末端は開放され、その間の血液は組織の空隙を流れる。→循環系。
⇒けっ‐かん【血管】
けっかん‐しゅ【血管腫】‥クワン‥🔗⭐🔉
けっかん‐しゅ【血管腫】‥クワン‥
血管の局所的増生巣。多くは良性腫瘍であるが、組織奇形と見られるものもある。毛細血管腫・血管内皮腫・血管周皮腫・海綿状血管腫・蔓状血管腫などの種類がある。→赤痣あかあざ。
⇒けっ‐かん【血管】
けっかん‐ぞうえい【血管造影】‥クワンザウ‥🔗⭐🔉
けっかん‐ぞうえい【血管造影】‥クワンザウ‥
血管の中にヨードを含む造影剤を注入し、X線撮影を行う方法。経皮的に直接穿刺する方法、カテーテル法、静脈性動脈造影法などがある。病変に伴う血管分布の異常から病変自体を診断し、血管の異常を調べる。
⇒けっ‐かん【血管】
けっ‐き【血気】🔗⭐🔉
けっ‐き【血気】
①血液と気力。生命を維持する身体の力。
②激しやすい意気。血の気け。客気かっき。「―にまかせる」「―盛ん」
⇒けっき‐ざかり【血気盛り】
⇒けっき‐の‐ゆう【血気の勇】
⇒けっき‐もの【血気者】
⇒血気に逸る
○血気に逸るけっきにはやる🔗⭐🔉
○血気に逸るけっきにはやる
(→)血気2にまかせて激しい行動に走ろうとする。「―若者をなだめる」
⇒けっ‐き【血気】
けっき‐の‐ゆう【血気の勇】
血気にまかせた一時の勇気。猪勇ちょゆう。
⇒けっ‐き【血気】
けっき‐もの【血気者】
血気盛んな人。
⇒けっ‐き【血気】
けっ‐きゅう【血球】‥キウ
(blood-corpuscle)血液の細胞成分。血漿けっしょう中に浮遊する。赤血球・白血球および血小板がある。白血球には顆粒球・単球・リンパ球の別があり、組織内に遊出する。
けっ‐きゅう【結球】‥キウ
キャベツ・白菜などの葉菜類で、葉が重なり合って球状をなすこと。また、そのもの。
げっ‐きゅう【月宮】
月の中にあるという宮殿。月宮殿。がっくう。
⇒げっきゅう‐でん【月宮殿】
げっ‐きゅう【月球】‥キウ
(形が球状であることから)月のこと。
⇒げっきゅう‐ぎ【月球儀】
げっ‐きゅう【月給】‥キフ
月単位に金額が定められた俸給。月俸。サラリー。正岡子規、仰臥漫録「中田氏新聞社ヨリノ―(四十円)ヲ携ヘ来ル」。「―だけでは足りない」
⇒げっきゅう‐とり【月給取り】
⇒げっきゅう‐どろぼう【月給泥棒】
げっきゅう‐ぎ【月球儀】‥キウ‥
月面の地形を球の表面に記した模型。地球儀に対する呼び名。
⇒げっ‐きゅう【月球】
げっきゅう‐でん【月宮殿】
①(→)月宮に同じ。謡曲、羽衣「―の有様…」
②能。(→)「鶴亀」に同じ。
③皇居。
④江戸吉原の遊里。
⇒げっ‐きゅう【月宮】
げっきゅう‐とり【月給取り】‥キフ‥
月給をもらって生活する人。俸給生活者。サラリーマン。
⇒げっ‐きゅう【月給】
げっきゅう‐どろぼう【月給泥棒】‥キフ‥バウ
十分な仕事をせずに給料だけは一人前にもらっている人。
⇒げっ‐きゅう【月給】
けっ‐きょ【穴居】
穴の中に住むこと。あなずまい。
けっ‐きょ【血虚】
漢方で、血の量が不足した病態。肌荒れ・脱毛・こむらがえり・視覚障害などの症状を現す。
けっ‐きょ【拮据】
⇒きっきょ
けっ‐きょう【結経】‥キヤウ
〔仏〕本経を説いた後に結論としてその要旨を述べた経。法華経に対する観普賢経の類。↔開経
けっ‐きょく【結局】
(囲碁を一局打ち終える意から)
①終りになること。結末。「―のところ」
②(副詞的に)あげくのはて。とどのつまり。せんずるところ。「―了承した」
けつぎ‐ろん【決疑論】
(casuistry)倫理の一般的規範を個々の事例に適用する仕方を、事例ごとに細かくタイプ分けして定めておくやり方。教父、中世のスコラ学で重視され、近世ではイエズス会が必携書をつくった。
けっ‐きん【欠勤】
つとめを休むこと。「会社を無断で―する」↔出勤
げっ‐きん【月琴】
(胴が満月のように円形で、音が琴に似るのでいう)中国・ベトナム・日本のリュート属の撥弦楽器。中国で阮咸げんかんから派生し、現在は3〜4弦で、13・14・17・24柱じのものがある。義甲で演奏する。日本では明清楽みんしんがくに用いる。明楽のは八角胴長棹(4弦15柱)、清楽のは円形胴短棹で4弦(2弦ずつ同音)8柱。→阮咸
月琴
 けっ‐く【結句】
[一]〔名〕
①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。
②一般に、詩歌の結びの句。
[二]〔副〕
①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」
②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」
け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ
①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。
②(→)グルーミングに同じ。
けつ‐げ【結夏】
〔仏〕
①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。
②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉
けつ‐げ【結解】
①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。
②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」
③当道座で、会計をつかさどる検校。
け‐づけ【毛付け】
(ケツケとも)
①馬の毛色。
②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。
③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」
④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」
⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。
げっ‐けい【月計】
1カ月の収支の会計。
げっ‐けい【月桂】
①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」
②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」
③月桂樹の略。
⇒げっけい‐かん【月桂冠】
⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】
げっ‐けい【月経】
(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。
⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】
⇒げっけい‐つう【月経痛】
⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
げっけい【月渓】
⇒まつむらげっけい(松村月渓)
げっ‐けい【月卿】
(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」
げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン
①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。
月桂冠
けっ‐く【結句】
[一]〔名〕
①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。
②一般に、詩歌の結びの句。
[二]〔副〕
①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」
②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」
け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ
①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。
②(→)グルーミングに同じ。
けつ‐げ【結夏】
〔仏〕
①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。
②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉
けつ‐げ【結解】
①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。
②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」
③当道座で、会計をつかさどる検校。
け‐づけ【毛付け】
(ケツケとも)
①馬の毛色。
②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。
③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」
④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」
⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。
げっ‐けい【月計】
1カ月の収支の会計。
げっ‐けい【月桂】
①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」
②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」
③月桂樹の略。
⇒げっけい‐かん【月桂冠】
⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】
げっ‐けい【月経】
(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。
⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】
⇒げっけい‐つう【月経痛】
⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
げっけい【月渓】
⇒まつむらげっけい(松村月渓)
げっ‐けい【月卿】
(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」
げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン
①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。
月桂冠
 ②転じて、最も名誉ある地位。
⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ
骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐じゅ【月桂樹】
クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。
げっけいじゅ
②転じて、最も名誉ある地位。
⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ
骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐じゅ【月桂樹】
クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。
げっけいじゅ
 ゲッケイジュ
提供:ネイチャー・プロダクション
ゲッケイジュ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐つう【月経痛】
月経に伴って下腹部に起こる疼痛。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。
⇒げっ‐けい【月経】
けっけい‐もじ【楔形文字】
⇒くさびがたもじ
けつ‐げき【穴隙】
あな。すきま。
⇒穴隙を鑽る
⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐つう【月経痛】
月経に伴って下腹部に起こる疼痛。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。
⇒げっ‐けい【月経】
けっけい‐もじ【楔形文字】
⇒くさびがたもじ
けつ‐げき【穴隙】
あな。すきま。
⇒穴隙を鑽る
 けっ‐く【結句】
[一]〔名〕
①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。
②一般に、詩歌の結びの句。
[二]〔副〕
①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」
②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」
け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ
①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。
②(→)グルーミングに同じ。
けつ‐げ【結夏】
〔仏〕
①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。
②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉
けつ‐げ【結解】
①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。
②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」
③当道座で、会計をつかさどる検校。
け‐づけ【毛付け】
(ケツケとも)
①馬の毛色。
②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。
③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」
④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」
⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。
げっ‐けい【月計】
1カ月の収支の会計。
げっ‐けい【月桂】
①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」
②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」
③月桂樹の略。
⇒げっけい‐かん【月桂冠】
⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】
げっ‐けい【月経】
(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。
⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】
⇒げっけい‐つう【月経痛】
⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
げっけい【月渓】
⇒まつむらげっけい(松村月渓)
げっ‐けい【月卿】
(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」
げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン
①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。
月桂冠
けっ‐く【結句】
[一]〔名〕
①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。
②一般に、詩歌の結びの句。
[二]〔副〕
①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」
②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」
け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ
①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。
②(→)グルーミングに同じ。
けつ‐げ【結夏】
〔仏〕
①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。
②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉
けつ‐げ【結解】
①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。
②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」
③当道座で、会計をつかさどる検校。
け‐づけ【毛付け】
(ケツケとも)
①馬の毛色。
②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。
③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」
④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」
⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。
げっ‐けい【月計】
1カ月の収支の会計。
げっ‐けい【月桂】
①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」
②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」
③月桂樹の略。
⇒げっけい‐かん【月桂冠】
⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】
げっ‐けい【月経】
(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。
⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】
⇒げっけい‐つう【月経痛】
⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
げっけい【月渓】
⇒まつむらげっけい(松村月渓)
げっ‐けい【月卿】
(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」
げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン
①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。
月桂冠
 ②転じて、最も名誉ある地位。
⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ
骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐じゅ【月桂樹】
クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。
げっけいじゅ
②転じて、最も名誉ある地位。
⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ
骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐じゅ【月桂樹】
クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。
げっけいじゅ
 ゲッケイジュ
提供:ネイチャー・プロダクション
ゲッケイジュ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐つう【月経痛】
月経に伴って下腹部に起こる疼痛。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。
⇒げっ‐けい【月経】
けっけい‐もじ【楔形文字】
⇒くさびがたもじ
けつ‐げき【穴隙】
あな。すきま。
⇒穴隙を鑽る
⇒げっ‐けい【月桂】
げっけい‐つう【月経痛】
月経に伴って下腹部に起こる疼痛。
⇒げっ‐けい【月経】
げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】
女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。
⇒げっ‐けい【月経】
けっけい‐もじ【楔形文字】
⇒くさびがたもじ
けつ‐げき【穴隙】
あな。すきま。
⇒穴隙を鑽る
けっき‐の‐ゆう【血気の勇】🔗⭐🔉
けっき‐の‐ゆう【血気の勇】
血気にまかせた一時の勇気。猪勇ちょゆう。
⇒けっ‐き【血気】
けっき‐もの【血気者】🔗⭐🔉
けっき‐もの【血気者】
血気盛んな人。
⇒けっ‐き【血気】
けっ‐きゅう【血球】‥キウ🔗⭐🔉
けっ‐きゅう【血球】‥キウ
(blood-corpuscle)血液の細胞成分。血漿けっしょう中に浮遊する。赤血球・白血球および血小板がある。白血球には顆粒球・単球・リンパ球の別があり、組織内に遊出する。
けっ‐きょ【血虚】🔗⭐🔉
けっ‐きょ【血虚】
漢方で、血の量が不足した病態。肌荒れ・脱毛・こむらがえり・視覚障害などの症状を現す。
ち【血】🔗⭐🔉
ち‐いみ【血忌】🔗⭐🔉
ち‐いみ【血忌】
①出産の忌。妻が出産した際の夫の忌ともいう。
②血忌日の略。
⇒ちいみ‐び【血忌日】
ちいみ‐び【血忌日】🔗⭐🔉
ちいみ‐び【血忌日】
暦注で、鍼灸しんきゅう・出血・狩猟などを忌むという日。ちこにち。
⇒ち‐いみ【血忌】
ち‐おろし【血下ろし】🔗⭐🔉
ち‐おろし【血下ろし】
子をおろすこと。堕胎だたい。ちおち。好色二代男「夜は男狂ひ、誰とも定めがたき―」
○血が通うちがかよう🔗⭐🔉
○血が通うちがかよう
事務的でなく、人間らしい暖かみがある。「血の通った処置」
⇒ち【血】
ち‐がき【血書】
誓紙などに血で文字を書くこと。また、その文書。けっしょ。
ちかき‐まもり【近衛】
⇒このえ。古今和歌集雑体「―の身なりしを」
⇒ちかきまもり‐の‐つかさ【近衛司】
ちかきまもり‐の‐つかさ【近衛司】
(→)近衛府このえふに同じ。宇津保物語国譲下「右の―のかみ藤原の仲忠」
⇒ちかき‐まもり【近衛】
ちかく【近く】
①近い所。近所。「―の町」
②(副詞的に)近い将来。「―外遊する予定だ」
③(接尾語的に)その数量にもう少しで達するさま。「一年―もかかった」
ち‐かく【地角】
①遠く隔たった土地のはて。「天涯―」
②岬みさき。地嘴ちし。
ち‐かく【地格】
〔言〕(→)所格に同じ。
ち‐かく【地核】
(→)核5に同じ。
ち‐かく【地殻】
地球の最外層。その下のマントルとはモホロヴィチッチ不連続面で境をなす。モホロヴィチッチ不連続面の深さは、大陸域で地表から30〜60キロメートル、海洋域で海底から約7キロメートル。地殻はマントルに比べて地震波の伝播が遅く、密度が小。海洋地殻は主に玄武岩質岩石から成り、大陸地殻の上部は主に花崗岩質岩石から成る。地皮。
⇒ちかく‐きんこう‐せつ【地殻均衡説】
⇒ちかく‐こうぞう【地殻構造】
⇒ちかく‐しゅうしゅく‐せつ【地殻収縮説】
⇒ちかく‐ねつりゅうりょう【地殻熱流量】
⇒ちかく‐へいこう‐せつ【地殻平衡説】
⇒ちかく‐へんどう【地殻変動】
ち‐かく【知覚】
①〔仏〕知り覚ること。分別すること。
②〔心〕(perception)感覚器官への刺激を通じてもたらされた情報をもとに、外界の対象の性質・形態・関係および身体内部の状態を把握するはたらき。→感覚→認知1
⇒ちかく‐しんけい【知覚神経】
⇒ちかく‐まひ【知覚麻痺】
ち‐がく【地学】
主に固体部分の地球とそれに関連する現象を扱う自然科学諸分野の総称。固体地球科学とほぼ同義。地形学・海洋学・古生物学・地質学・岩石学・鉱物学・地球化学・地球物理学などを含む。広義には、天文地学の略称として天文学・気象学なども含む。明治後半頃に地理学と同義にも使った。地球科学。
ちかく‐きんこう‐せつ【地殻均衡説】‥カウ‥
(→)アイソスタシーに同じ。
⇒ち‐かく【地殻】
ちかく‐こうぞう【地殻構造】‥ザウ
主として人工地震により観測された地震波の速度の不連続な面により、地殻をいくつかに区分したもの。多くは断面で示される。
⇒ち‐かく【地殻】
ちかく‐しゅうしゅく‐せつ【地殻収縮説】‥シウ‥
地球が次第に冷却・収縮するために褶曲しゅうきょくや地殻変動が起こると考える説。現在では顧みられない。
⇒ち‐かく【地殻】
ちかく‐しんけい【知覚神経】
(→)感覚神経に同じ。
⇒ち‐かく【知覚】
ちかく‐ねつりゅうりょう【地殻熱流量】‥リウリヤウ
地球内部から地表に向かって流れる熱量。地域・場所により異なるが、地球全体の平均は1平方メートル当り60〜70ミリワット。熱源は放射性元素の崩壊による熱およびマントルからの熱とされる。表面熱流量。
⇒ち‐かく【地殻】
ちかくのげんしょうがく【知覚の現象学】‥シヤウ‥
(Phénoménologie de la perception フランス)メルロ=ポンティの主著。1945年刊。世界を構成する主体を、意識ではなく知覚し運動する身体に求め、主知主義と経験主義をともに乗り越えることを目指す。
ちかく‐へいこう‐せつ【地殻平衡説】‥カウ‥
(→)アイソスタシーに同じ。
⇒ち‐かく【地殻】
ちかく‐へんどう【地殻変動】
①地球の内部力によって地殻に起こる運動。地殻運動。
②比喩的に、ある社会・組織内で、その深部から起こる構成員の力関係などの変化。「政界の―」
⇒ち‐かく【地殻】
ちかく‐まひ【知覚麻痺】
神経系統や精神作用の障害により知覚が麻痺すること。知覚鈍麻。
⇒ち‐かく【知覚】
ちか‐けい【地下茎】
植物の地中にある茎。地中を横行する根茎(ハスなど)、塊状をなす塊茎(ジャガイモなど)、球状をなす球茎(サトイモなど)、鱗状をなす鱗茎(ユリなど)などがある。↔地上茎
ちか‐けいざい【地下経済】
(→)アングラ経済に同じ。
ちか‐ケーブル【地下ケーブル】
地下に直接埋設したり地下管路中に敷設したりするケーブル。
ちか‐けつじつ【地下結実】
植物が地上で受精した後、地下において果実を結ぶこと。落花生らっかせいの類。
ちかげ‐りゅう【千蔭流】‥リウ
和様書道の一派。加藤千蔭を祖とするもの。
ちか‐けん【地下権】
他人の土地の地下に地下鉄や地下街など工作物を所有するため上下の範囲を定めて設定される地上権。→空中権
ちか‐こうじ‐せいど【地価公示制度】
国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1回、標準地の単位面積当りの正常な価格(公示価格)を判定して、官報で公示する制度。公共事業の用に供する土地収用や民間の一定面積以上の土地取引の価格の指標とされる。
ちか‐ごと【誓言】
誓いのことば。誓詞せいし。せいごん。源氏物語総角「仏の御前にて―も立て侍らむ」
⇒ちかごと‐ぶみ【誓言文】
ちかごと‐ぶみ【誓言文】
誓いのことばを記した文。誓紙せいし。馬内侍集「左大将―をおこせ給うて」
⇒ちか‐ごと【誓言】
ちか‐ごろ【近頃】
〔名・副〕
①近い過去から現在までを漠然とさす語。この頃。近来。古今著聞集20「―常陸国多賀郡に一人の上人ありけり」。「―の若い者」「―は物騒だ」
②(「近頃になく」の意から)たいそう。はなはだ。すこぶる。謡曲、鞍馬天狗「これは―狼藉なる者にて候」
③「近頃有り難いこと」「近頃満足なこと」の略。狂言、入間川「それは―で御座る」。毛詩抄「功成り名遂げてかへつたときに―したとあつて」
ちかごろかわらのたてひき【近頃河原達引】‥カハラ‥
浄瑠璃。為川宗輔ほか合作(一説)の世話物。1782年(天明2)初演。お俊・伝兵衛の心中情話に、四条河原の喧嘩と猿廻しの孝行譚とを加えて脚色。中の巻「堀川(猿廻し)」の段が有名。後に歌舞伎化。→お俊伝兵衛
ちがさき【茅ヶ崎】
神奈川県南部の相模湾に面した市。湘南の保養・住宅地。工場も進出。人口22万8千。
○血が騒ぐちがさわぐ🔗⭐🔉
○血が騒ぐちがさわぐ
興奮してじっとしていられない。心がおどる。血がわく。
⇒ち【血】
ちか・し【近し】
[一]〔形ク〕
⇒ちかい。
[二]〔形シク〕
⇒ちかしい
ちかし・い【近しい・親しい】
〔形〕[文]ちか・し(シク)
親密である。したしい。むつまじい。好色五人女2「烏丸からすまのほとりへ―・しき人有りて見舞ひしうちに」。「―・い関係」
⇒近しき仲にも垣を結え
⇒近しき仲に礼儀あり
○血が上るちがのぼる🔗⭐🔉
ち‐けむり【血煙】🔗⭐🔉
ち‐けむり【血煙】
人を斬った時に飛び散る血を煙に見立てていう語。ちけぶり。「―をあげる」
ちすい‐こうもり【血吸い蝙蝠】‥スヒカウモリ🔗⭐🔉
ちすい‐こうもり【血吸い蝙蝠】‥スヒカウモリ
チスイコウモリ科のコウモリの総称。3種ある。体長8センチメートルほど。門歯が鋭く、唾液中に血液凝固を防ぐ成分があり、家畜や鳥の皮膚を傷つけ、血をなめる。中南米産。吸血蝙蝠。バンパイア‐バット。
チスイコウモリ
撮影:小宮輝之
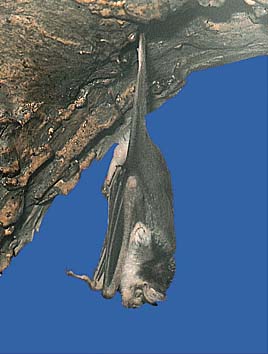
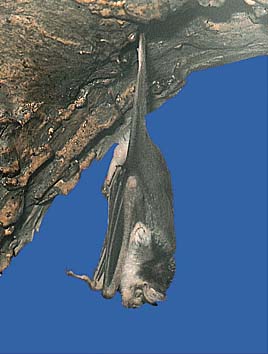
ちすい‐びる【血吸い蛭】‥スヒ‥🔗⭐🔉
ちすい‐びる【血吸い蛭】‥スヒ‥
アゴビル目のヒル。体は円柱形でやや扁平。体長3〜4センチメートル。背面は灰緑色で数条の縦線がある。水田・池沼などに生息。顎の歯で傷をつけてよく血を吸うので、古来医療に使用。医用蛭。水蛭。
ち‐すじ【血筋】‥スヂ🔗⭐🔉
ち‐すじ【血筋】‥スヂ
①血液が流れる脈絡。血管。
②先祖代々の血統。血のつながり。血縁。「―をひく」「―は争えない」
⇒ちすじ‐のり【血条苔・血筋苔】
ち‐そばえ【血戯え】‥ソバヘ🔗⭐🔉
ち‐そばえ【血戯え】‥ソバヘ
血を見ていよいよ興奮すること。義経記8「弁慶は血の出づればいとど―して、人をも人とも思はず」→ちえい(血酔)
ち‐だらけ【血だらけ】🔗⭐🔉
ち‐だらけ【血だらけ】
一面に血に染まること。ちまみれ。ちみどろ。
○血で血を洗うちでちをあらう🔗⭐🔉
○血で血を洗うちでちをあらう
①[旧唐書源休伝]殺傷に対し、殺傷をもって報復する。
②悪事に対して悪事で対処する。
③血族が相争う。同胞同士がたたかう。
⇒ち【血】
ち‐てん【地点】
地上のある1カ所。場所。位置。「折り返し―」
ち‐てん【治天】
天下を統治すること。国を治めること。じてん。
ち‐でん【治田】
古代、農民が自力で開墾した零細な墾田。はりた。百姓ひゃくせい治田。
ち‐でんりゅう【地電流】‥リウ
地中を流れる電流。地磁気変化によって誘導されるもののほか、雷、物質や温度の分布に伴う物理・化学的起電力によるもの、人為的なものなどが含まれる。
ち‐と【雉兎】
キジとウサギ。また、それを捕らえる人。猟師。「―芻蕘すうじょう」
ち‐と【些と・少と】
〔副〕
①すこし。ちょっと。いささか。建礼門院右京大夫集「おづおづ―見参らせしかば」。「これは―まずい」
②しばらく。暫時。宇治拾遺物語8「―まどろませ給ふともなきに」
○血と汗ちとあせ🔗⭐🔉
○血と汗ちとあせ
苦労し努力することのたとえ。「―の結晶」
⇒ち【血】
ち‐とう【池塘】‥タウ
①池のつつみ。
②高山や寒冷地の湿地の池。尾瀬沼など。
⇒池塘春草の夢
ち‐とう【池頭】
池のほとり。
ち‐とう【螭頭】
みずちの頭。また、その形をしたもの。太平記39「―の香炉に」
ち‐どう【地動】
①大地の動くこと。地震。
②地球の運動、すなわち地球の自転と公転。
⇒ちどう‐せつ【地動説】
ち‐どう【地道】‥ダウ
①大地にそなわる道理。↔天道。
②地下に造った道。地下道。トンネル。
ち‐どう【治道】‥ダウ
①国を治める方法。政治のしかた。
②伎楽面の一つ。鼻が極めて高い。→伎楽面(図)
ち‐どう【馳道】‥ダウ
天子や貴人の通路。輦路れんろ。
○血となり肉となるちとなりにくとなる🔗⭐🔉
○血となり肉となるちとなりにくとなる
見聞や経験が、のちの活動に役立つものとして、自分の中に十分とり入れられる。
⇒ち【血】
ち‐どめ【血止め】
①傷口の出血を止めること。また、その薬。止血。
②「ちどめぐさ」の略。
⇒ちどめ‐ぐさ【血止め草】
ちどめ‐ぐさ【血止め草】
(チトメグサとも)セリ科の多年草。小さな雑草で人家の付近に自生。細い茎は地上を這い、節から根を生じ、葉は円形で長柄。春から夏にかけ白色または帯紫色の微小花をつける。葉は血止めに効があるとされる。同属、近縁の数種がある。〈日葡辞書〉
ちどめぐさ
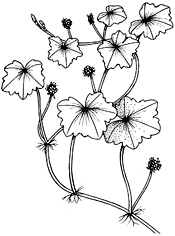 ⇒ち‐どめ【血止め】
ちと‐も【些も】
〔副〕
①少しも。いささかも。ちっとも。
②しばらくも。暫時も。
ち‐どり【千鳥・鵆】
①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」
②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」
こちどり
⇒ち‐どめ【血止め】
ちと‐も【些も】
〔副〕
①少しも。いささかも。ちっとも。
②しばらくも。暫時も。
ち‐どり【千鳥・鵆】
①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」
②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」
こちどり
 コチドリ
提供:OPO
コチドリ
提供:OPO
 シロチドリ
提供:OPO
シロチドリ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒ちどり‐あし【千鳥足】
⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】
⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】
⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】
⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】
⇒ちどり‐そう【千鳥草】
⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】
⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】
⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】
⇒ちどり‐やき【千鳥焼】
ちどり【千鳥】
狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。
ちどり‐あし【千鳥足】
①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」
②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐かがり【千鳥縢り】
(→)「ちどりがけ」に同じ。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐がけ【千鳥掛け】
①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。
②斜めに打ち違えた状態。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】
東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。
ちどり‐がま【千鳥鎌】
鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥
格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ
〔植〕
①(→)テガタチドリの別称。
②(→)ヒエンソウの別称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ
千鳥掛けに縫うこと。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥
宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐はふ【千鳥破風】
屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。
千鳥破風
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒ちどり‐あし【千鳥足】
⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】
⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】
⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】
⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】
⇒ちどり‐そう【千鳥草】
⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】
⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】
⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】
⇒ちどり‐やき【千鳥焼】
ちどり【千鳥】
狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。
ちどり‐あし【千鳥足】
①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」
②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐かがり【千鳥縢り】
(→)「ちどりがけ」に同じ。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐がけ【千鳥掛け】
①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。
②斜めに打ち違えた状態。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】
東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。
ちどり‐がま【千鳥鎌】
鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥
格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ
〔植〕
①(→)テガタチドリの別称。
②(→)ヒエンソウの別称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ
千鳥掛けに縫うこと。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥
宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐はふ【千鳥破風】
屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。
千鳥破風
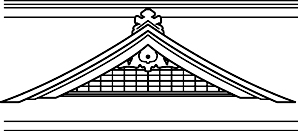 ⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐やき【千鳥焼】
蛤はまぐりの田楽でんがく。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ち‐どん【遅鈍】
遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」
ち‐どん【痴鈍】
おろかでにぶいこと。
ち‐な【千名】
いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」
ち‐ながし【血流し】
刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。
ち‐なき【ち鳴き】
(方言)(→)牡恋おごいに同じ。
ち‐なまぐさ・い【血腥い】
〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)
①鮮血のにおいがする。ちくさい。
②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」
ちなみ【因み】
(チナビ(道並)の転)
①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」
②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」
⇒ちなみ‐に【因みに】
ちなみ‐に【因みに】
〔接続〕
それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」
⇒ちなみ【因み】
ちな・む【因む】
〔自五〕
①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」
②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐やき【千鳥焼】
蛤はまぐりの田楽でんがく。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ち‐どん【遅鈍】
遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」
ち‐どん【痴鈍】
おろかでにぶいこと。
ち‐な【千名】
いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」
ち‐ながし【血流し】
刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。
ち‐なき【ち鳴き】
(方言)(→)牡恋おごいに同じ。
ち‐なまぐさ・い【血腥い】
〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)
①鮮血のにおいがする。ちくさい。
②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」
ちなみ【因み】
(チナビ(道並)の転)
①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」
②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」
⇒ちなみ‐に【因みに】
ちなみ‐に【因みに】
〔接続〕
それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」
⇒ちなみ【因み】
ちな・む【因む】
〔自五〕
①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」
②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」
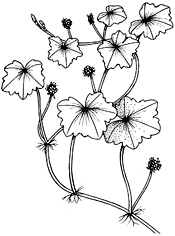 ⇒ち‐どめ【血止め】
ちと‐も【些も】
〔副〕
①少しも。いささかも。ちっとも。
②しばらくも。暫時も。
ち‐どり【千鳥・鵆】
①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」
②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」
こちどり
⇒ち‐どめ【血止め】
ちと‐も【些も】
〔副〕
①少しも。いささかも。ちっとも。
②しばらくも。暫時も。
ち‐どり【千鳥・鵆】
①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」
②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」
こちどり
 コチドリ
提供:OPO
コチドリ
提供:OPO
 シロチドリ
提供:OPO
シロチドリ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒ちどり‐あし【千鳥足】
⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】
⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】
⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】
⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】
⇒ちどり‐そう【千鳥草】
⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】
⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】
⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】
⇒ちどり‐やき【千鳥焼】
ちどり【千鳥】
狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。
ちどり‐あし【千鳥足】
①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」
②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐かがり【千鳥縢り】
(→)「ちどりがけ」に同じ。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐がけ【千鳥掛け】
①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。
②斜めに打ち違えた状態。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】
東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。
ちどり‐がま【千鳥鎌】
鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥
格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ
〔植〕
①(→)テガタチドリの別称。
②(→)ヒエンソウの別称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ
千鳥掛けに縫うこと。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥
宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐はふ【千鳥破風】
屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。
千鳥破風
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒ちどり‐あし【千鳥足】
⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】
⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】
⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】
⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】
⇒ちどり‐そう【千鳥草】
⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】
⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】
⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】
⇒ちどり‐やき【千鳥焼】
ちどり【千鳥】
狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。
ちどり‐あし【千鳥足】
①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」
②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐かがり【千鳥縢り】
(→)「ちどりがけ」に同じ。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐がけ【千鳥掛け】
①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。
②斜めに打ち違えた状態。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】
東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。
ちどり‐がま【千鳥鎌】
鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥
格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ
〔植〕
①(→)テガタチドリの別称。
②(→)ヒエンソウの別称。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ
千鳥掛けに縫うこと。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】
箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥
宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐はふ【千鳥破風】
屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。
千鳥破風
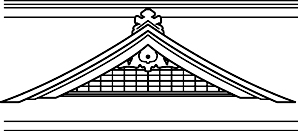 ⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐やき【千鳥焼】
蛤はまぐりの田楽でんがく。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ち‐どん【遅鈍】
遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」
ち‐どん【痴鈍】
おろかでにぶいこと。
ち‐な【千名】
いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」
ち‐ながし【血流し】
刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。
ち‐なき【ち鳴き】
(方言)(→)牡恋おごいに同じ。
ち‐なまぐさ・い【血腥い】
〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)
①鮮血のにおいがする。ちくさい。
②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」
ちなみ【因み】
(チナビ(道並)の転)
①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」
②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」
⇒ちなみ‐に【因みに】
ちなみ‐に【因みに】
〔接続〕
それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」
⇒ちなみ【因み】
ちな・む【因む】
〔自五〕
①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」
②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ちどり‐やき【千鳥焼】
蛤はまぐりの田楽でんがく。
⇒ち‐どり【千鳥・鵆】
ち‐どん【遅鈍】
遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」
ち‐どん【痴鈍】
おろかでにぶいこと。
ち‐な【千名】
いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」
ち‐ながし【血流し】
刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。
ち‐なき【ち鳴き】
(方言)(→)牡恋おごいに同じ。
ち‐なまぐさ・い【血腥い】
〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)
①鮮血のにおいがする。ちくさい。
②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」
ちなみ【因み】
(チナビ(道並)の転)
①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」
②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」
⇒ちなみ‐に【因みに】
ちなみ‐に【因みに】
〔接続〕
それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」
⇒ちなみ【因み】
ちな・む【因む】
〔自五〕
①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」
②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」
○血に飢えるちにうえる🔗⭐🔉
○血に飢えるちにうえる
人を殺傷したいというすさんだ気分になる。
⇒ち【血】
ち‐の‐あせ【血の汗】🔗⭐🔉
ち‐の‐あせ【血の汗】
苦しい努力をして流す汗。
ち‐の‐あまり【血の余り】🔗⭐🔉
ち‐の‐あまり【血の余り】
末子の異称。狂言、縄綯なわない「殿の―と見えまして、幼いを抱いて出られ」
ち‐の‐あめ【血の雨】🔗⭐🔉
ち‐の‐あめ【血の雨】
流血事件などで、死傷者を多く出すさまにいう。「―を降らす」
ち‐の‐いけ【血の池】🔗⭐🔉
ち‐の‐いけ【血の池】
地獄にあるという、血をたたえた池。
ち‐の‐うみ【血の海】🔗⭐🔉
ち‐の‐うみ【血の海】
血が流れ広がったさまを海にたとえていう語。「―と化す」
ち‐の‐け【血の気】🔗⭐🔉
ち‐の‐け【血の気】
①血の通っている様子。血色けっしょく。「―がさす」「―が引く」「―を失う」
②元気。生き生きした気力。血気けっき。「―の多い若者」
ち‐の‐すじ【血の筋】‥スヂ🔗⭐🔉
ち‐の‐すじ【血の筋】‥スヂ
血が続いていること。血縁。ちすじ。浄瑠璃、冥途飛脚「なう―は悲しい。中のよい他人より…親子の親しみは世の習ひ」
○血の出るようちのでるよう
非常に苦心し努力するさま。血のにじむよう。「―な努力」
⇒ち【血】
○血の出るようちのでるよう🔗⭐🔉
○血の出るようちのでるよう
非常に苦心し努力するさま。血のにじむよう。「―な努力」
⇒ち【血】
ち‐の‐なみだ【血の涙】
(「血涙けつるい」の訓読)涙が尽きて血の出るほど、はげしく泣き悲しむさまにいう語。伊勢物語「をとこ、―を流せども、とどむるよしなし」
ち‐の‐にちようび【血の日曜日】‥エウ‥
1905年1月22日(ロシア暦では9日)の日曜日に起こって、1905年革命の発端をなした事件。ペテルブルグで10万近い労働者とその家族が司祭ガポンの指導のもとに、自らの窮状を訴え、プラウダ(正義)の実現を求めて、冬宮へ向かって行進したのに対し、軍隊が発砲し、数百名の死者、千名以上の負傷者を出した。
軍隊発砲で死者千名以上 1905年1月22日
提供:毎日新聞社
 ち‐の‐ね【茅の根】
チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。
チノ‐パン【chino pants】
チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。
ち‐の‐ひと【乳の人】
うば。めのと。
ち‐のぼせ【血逆上】
のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。
ち‐の‐ま【乳の間】
釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)
ちの‐まさこ【茅野雅子】
明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)
⇒ちの【茅野】
ちのみ‐おや【乳飲み親】
乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。
ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】
乳をのむころの幼児。乳児。
ち‐の‐みち【血の道】
①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉
②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」
⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】
ちのみち‐もち【血の道持ち】
血の道を持病に持つこと。また、その人。
⇒ち‐の‐みち【血の道】
ち‐の‐め【乳の目】
乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。
ち‐の‐めぐり【血の巡り】
①血液の循環。
②頭脳のはたらき。「―が悪い人」
ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ
(→)「血の道」2に同じ。
ち‐のり【血糊】
血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。
ち‐の‐り【千箆入】
(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。
⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
ち‐の‐り【地の利】
①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」
②土地からあがる利益。
⇒地の利は人の和に如かず
ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」
⇒ち‐の‐り【千箆入】
ち‐の‐ね【茅の根】
チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。
チノ‐パン【chino pants】
チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。
ち‐の‐ひと【乳の人】
うば。めのと。
ち‐のぼせ【血逆上】
のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。
ち‐の‐ま【乳の間】
釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)
ちの‐まさこ【茅野雅子】
明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)
⇒ちの【茅野】
ちのみ‐おや【乳飲み親】
乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。
ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】
乳をのむころの幼児。乳児。
ち‐の‐みち【血の道】
①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉
②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」
⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】
ちのみち‐もち【血の道持ち】
血の道を持病に持つこと。また、その人。
⇒ち‐の‐みち【血の道】
ち‐の‐め【乳の目】
乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。
ち‐の‐めぐり【血の巡り】
①血液の循環。
②頭脳のはたらき。「―が悪い人」
ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ
(→)「血の道」2に同じ。
ち‐のり【血糊】
血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。
ち‐の‐り【千箆入】
(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。
⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
ち‐の‐り【地の利】
①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」
②土地からあがる利益。
⇒地の利は人の和に如かず
ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」
⇒ち‐の‐り【千箆入】
 ち‐の‐ね【茅の根】
チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。
チノ‐パン【chino pants】
チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。
ち‐の‐ひと【乳の人】
うば。めのと。
ち‐のぼせ【血逆上】
のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。
ち‐の‐ま【乳の間】
釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)
ちの‐まさこ【茅野雅子】
明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)
⇒ちの【茅野】
ちのみ‐おや【乳飲み親】
乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。
ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】
乳をのむころの幼児。乳児。
ち‐の‐みち【血の道】
①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉
②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」
⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】
ちのみち‐もち【血の道持ち】
血の道を持病に持つこと。また、その人。
⇒ち‐の‐みち【血の道】
ち‐の‐め【乳の目】
乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。
ち‐の‐めぐり【血の巡り】
①血液の循環。
②頭脳のはたらき。「―が悪い人」
ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ
(→)「血の道」2に同じ。
ち‐のり【血糊】
血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。
ち‐の‐り【千箆入】
(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。
⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
ち‐の‐り【地の利】
①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」
②土地からあがる利益。
⇒地の利は人の和に如かず
ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」
⇒ち‐の‐り【千箆入】
ち‐の‐ね【茅の根】
チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。
チノ‐パン【chino pants】
チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。
ち‐の‐ひと【乳の人】
うば。めのと。
ち‐のぼせ【血逆上】
のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。
ち‐の‐ま【乳の間】
釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)
ちの‐まさこ【茅野雅子】
明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)
⇒ちの【茅野】
ちのみ‐おや【乳飲み親】
乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。
ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】
乳をのむころの幼児。乳児。
ち‐の‐みち【血の道】
①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉
②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」
⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】
ちのみち‐もち【血の道持ち】
血の道を持病に持つこと。また、その人。
⇒ち‐の‐みち【血の道】
ち‐の‐め【乳の目】
乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。
ち‐の‐めぐり【血の巡り】
①血液の循環。
②頭脳のはたらき。「―が悪い人」
ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ
(→)「血の道」2に同じ。
ち‐のり【血糊】
血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。
ち‐の‐り【千箆入】
(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。
⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
ち‐の‐り【地の利】
①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」
②土地からあがる利益。
⇒地の利は人の和に如かず
ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】
多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」
⇒ち‐の‐り【千箆入】
ち‐の‐なみだ【血の涙】🔗⭐🔉
ち‐の‐なみだ【血の涙】
(「血涙けつるい」の訓読)涙が尽きて血の出るほど、はげしく泣き悲しむさまにいう語。伊勢物語「をとこ、―を流せども、とどむるよしなし」
ち‐の‐にちようび【血の日曜日】‥エウ‥🔗⭐🔉
ち‐の‐にちようび【血の日曜日】‥エウ‥
1905年1月22日(ロシア暦では9日)の日曜日に起こって、1905年革命の発端をなした事件。ペテルブルグで10万近い労働者とその家族が司祭ガポンの指導のもとに、自らの窮状を訴え、プラウダ(正義)の実現を求めて、冬宮へ向かって行進したのに対し、軍隊が発砲し、数百名の死者、千名以上の負傷者を出した。
軍隊発砲で死者千名以上 1905年1月22日
提供:毎日新聞社


ち‐のぼせ【血逆上】🔗⭐🔉
ち‐のぼせ【血逆上】
のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。
ち‐の‐みち【血の道】🔗⭐🔉
ち‐の‐みち【血の道】
①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉
②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」
⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】
ちのみち‐もち【血の道持ち】🔗⭐🔉
ちのみち‐もち【血の道持ち】
血の道を持病に持つこと。また、その人。
⇒ち‐の‐みち【血の道】
ち‐の‐めぐり【血の巡り】🔗⭐🔉
ち‐の‐めぐり【血の巡り】
①血液の循環。
②頭脳のはたらき。「―が悪い人」
ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ🔗⭐🔉
ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ
(→)「血の道」2に同じ。
○血は争えないちはあらそえない🔗⭐🔉
○血は争えないちはあらそえない
親から気質・性向を受け継いでいることは否定しようがない。血筋は争えない。
⇒ち【血】
ち‐はい【遅配】
配給・配達・支給などがおくれること。
ちは・う【幸ふ】チハフ
〔自四〕
(チは霊力の意)神の威力が働く。加護がある。万葉集9「女めの神も―・ひ給ひて」
ちば‐かめお【千葉亀雄】‥ヲ
文芸評論家。山形県生れ。早大中退。国民・時事・読売・東京日日各新聞の記者を歴任。文化学院・立教大教授。大正期の文学運動を推進し、大衆文学を育成。(1878〜1935)
⇒ちば【千葉】
ち‐ばかり【地測り】
水深測量具。網袋に石を入れ、糸をつけた簡単なしかけ。つず縄。
ちば・ける
〔自下一〕
(岡山・山口県などで)ふざける。
ちば‐しゅうさく【千葉周作】‥シウ‥
幕末の剣客。北辰一刀流の開祖。陸奥栗原郡の人。中西派一刀流などを学び、江戸に玄武館を開いて名を挙げ、のち、水戸弘道館に出張教授をして水戸藩士となる。(1794〜1855)
⇒ちば【千葉】
ち‐はしら【乳柱】
乳呑み児を乳離れさせる前に、飯を少しずつ与えること。また、離乳食。
ち‐ばし・る【血走る】
〔自五〕
血がほとばしる。また、血がにじんだり眼球が充血したりして赤くなる。浄瑠璃、平家女護島「縄目―・る弱腕よわかいな」。「―・った目」
ちば‐だいがく【千葉大学】
国立大学法人の一つ。旧制の千葉医大を中心に千葉農専・東京工専・千葉師範・同青年師範を母体として1949年設置。2004年法人化。千葉市。
○血は水よりも濃しちはみずよりもこし🔗⭐🔉
○血は水よりも濃しちはみずよりもこし
(西洋の諺から)血筋は争われず、他人よりも血縁の人とのつながりの方が強い。
⇒ち【血】
ち‐ば・む【血ばむ】
〔自五〕
血がにじむ。血を帯びる。
ちはや【襅】
①日本の原始衣。貫頭衣の類。
②小忌衣おみごろもの類。身二幅・袖一幅の、衽おくみのない白布の単衣で、打掛けの形をし、袖を縫わずに、紙捻こよりでくくったもの。山藍で水草・蝶・鳥などの模様を摺る。千早。今昔物語集28「宮々の御方の女官共の唐衣・―着て行あるき」
襅
 ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ
大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。
ちはや‐びと【千早人】
〔枕〕
(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。
ちはや・ぶ【千早ぶ】
〔自上二〕
(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」
ちはやふる【千早振る】
落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。
ちはや‐ぶる【千早振る】
〔枕〕
(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」
ち‐はら【茅原】
(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」
ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ
給与や代金などの支払いがおくれること。
ちばり‐よお
(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。
ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ
千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。
ち‐はん【池畔】
池のほとり。池辺。
ち‐ばん【血判】
(→)「けっぱん」に同じ。
ち‐ばん【地番】
土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」
ち‐はんじ【知藩事】
1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。
ち‐ひ【地皮】
(→)地殻ちかくに同じ。
ち‐ひ【地被】
地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」
ちび
からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」
ち‐びき【千引】
千人で引くほどの重さの物。
⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】
⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】
⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】
ち‐びき【血引】
沿岸魚、ハチビキの別称。
ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ
綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐つな【千引の綱】
千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ
(→)「千引の綱」に同じ。
⇒ち‐びき【千引】
ちび‐ちび
〔副〕
物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」
ち‐ひつ【遅筆】
文を書くのがおそいこと。
ちびっ‐こ【ちびっ子】
幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」
ちびっ‐ちょ
「ちび」を強めていう語。ちびっこ。
ち‐ひと【千人】
せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」
ち‐ひと【乳人】
乳母。めのと。ちのひと。
ちび‐ふで【禿筆】
毛さきのすりきれた筆。とくひつ。
ち‐ひょう【地表】‥ヘウ
地球の表面。土地の表面。
⇒ちひょう‐か【地表火】
⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】
⇒ちひょう‐すい【地表水】
ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ
門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。
ち‐びょう【稚苗】‥ベウ
葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗
ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ
燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥
越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥
地表にある水。河川・湖沼などの水。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちびり
〔副〕
すこし。いささか。
⇒ちびり‐ちびり
ちびり‐ちびり
少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」
⇒ちびり
ちび・る
〔他五〕
①小便などを少し漏らす。
②出し惜しむ。「費用を―・る」
③少しずつ飲む。
ち・びる【禿びる】
〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)
先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」
ち‐ひろ【千尋】
(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「
ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ
大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。
ちはや‐びと【千早人】
〔枕〕
(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。
ちはや・ぶ【千早ぶ】
〔自上二〕
(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」
ちはやふる【千早振る】
落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。
ちはや‐ぶる【千早振る】
〔枕〕
(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」
ち‐はら【茅原】
(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」
ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ
給与や代金などの支払いがおくれること。
ちばり‐よお
(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。
ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ
千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。
ち‐はん【池畔】
池のほとり。池辺。
ち‐ばん【血判】
(→)「けっぱん」に同じ。
ち‐ばん【地番】
土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」
ち‐はんじ【知藩事】
1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。
ち‐ひ【地皮】
(→)地殻ちかくに同じ。
ち‐ひ【地被】
地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」
ちび
からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」
ち‐びき【千引】
千人で引くほどの重さの物。
⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】
⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】
⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】
ち‐びき【血引】
沿岸魚、ハチビキの別称。
ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ
綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐つな【千引の綱】
千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ
(→)「千引の綱」に同じ。
⇒ち‐びき【千引】
ちび‐ちび
〔副〕
物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」
ち‐ひつ【遅筆】
文を書くのがおそいこと。
ちびっ‐こ【ちびっ子】
幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」
ちびっ‐ちょ
「ちび」を強めていう語。ちびっこ。
ち‐ひと【千人】
せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」
ち‐ひと【乳人】
乳母。めのと。ちのひと。
ちび‐ふで【禿筆】
毛さきのすりきれた筆。とくひつ。
ち‐ひょう【地表】‥ヘウ
地球の表面。土地の表面。
⇒ちひょう‐か【地表火】
⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】
⇒ちひょう‐すい【地表水】
ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ
門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。
ち‐びょう【稚苗】‥ベウ
葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗
ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ
燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥
越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥
地表にある水。河川・湖沼などの水。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちびり
〔副〕
すこし。いささか。
⇒ちびり‐ちびり
ちびり‐ちびり
少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」
⇒ちびり
ちび・る
〔他五〕
①小便などを少し漏らす。
②出し惜しむ。「費用を―・る」
③少しずつ飲む。
ち・びる【禿びる】
〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)
先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」
ち‐ひろ【千尋】
(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「 縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」
ち‐ふ【乳癰】
(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉
ち‐ふ【茅生】
チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」
ち‐ふ【地府】
①大地。地上。
②冥土めいど。冥界。
ち‐ふ【知府】
府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。
ち‐ふ【致富】
富を得ること。金持になること。「―譚たん」
ち‐ぶ【恥部】
①陰部。
②恥ずべき部分。「日本の―」
ち・ぶ【禿ぶ】
〔自上二〕
⇒ちびる(上一)
ち‐ぶくら【乳袋】
①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。
②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)
ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】
①乳房。
②(→)「ちぶくら」2に同じ。
ち‐ぶさ【乳房】
哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」
ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ
出産の忌をいう語。
チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」
⇒チフス‐きん【チフス菌】
チフス‐きん【チフス菌】
腸チフス菌の通称。
⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
ち‐ぶつ【地物】
地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。
ち‐ふね【千船】
多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」
ち‐ぶみ【血文】
血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」
ち‐ぶみ【地踏み】
力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。
ち‐ぶり【血鰤】
鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。
チフリス【Tiflis】
グルジア共和国の都市トビリシの旧称。
ちふり‐の‐かみ【道触の神】
陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」
ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ
①産後に血の道のため、体がふるえる病。
②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。
③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。
ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ
乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。
ち‐ぶん【地文】
⇒ちもん
ち‐ぶん【知分】
知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」
ち‐へい【地平】
①大地の平らな面。
②地平線。
③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」
⇒ちへい‐きょり【地平距離】
⇒ちへい‐せん【地平線】
⇒ちへい‐ふかく【地平俯角】
⇒ちへい‐めん【地平面】
⇒ちへい‐ゆうごう【地平融合】
ち‐へい【治平】
世の中が治まって平穏なこと。太平。
ち‐へい【治兵】
軍隊の兵員・装備をととのえること。
ちへい‐きょり【地平距離】
地球表面上、ある高さの所で、見通し得る最大距離。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐せん【地平線】
(horizon)
①海または平原が空と接する一線。自然地平。
②地上のある場所における鉛直線に垂直な平面が天球と交わる大円。視地平。→地心地平。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ふかく【地平俯角】
自然地平線(自然地平)と天文学的な地平線(視地平)とのなす微小な角。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐めん【地平面】
地球上のある地点において鉛直線に垂直な平面。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ゆうごう【地平融合】‥ガフ
(Horizontverschmelzung ドイツ)ガーダマーの哲学的解釈学の用語。テキストが属する過去の文化的地平と解釈者が属する現在の文化的地平とが相互に浸透し合うことによって、より大きな普遍性が獲得されること。
⇒ち‐へい【地平】
チベット【Tibet・西蔵】
中国四川省の西、インドの北、パミール高原の東に位置する高原地帯。7世紀には吐蕃が建国、18世紀以来、中国の宗主権下にあったが、20世紀に入りイギリスの実力による支配を受け、その保護下のダライ=ラマ自治国の観を呈した。第二次大戦後中華人民共和国が掌握、1965年チベット自治区となる。住民の約90パーセントはチベット族で、チベット語を用い、チベット仏教を信仰する。平均標高約4000メートルで、東部・南部の谷間では麦などの栽培、羊・ヤクなどの牧畜が行われる。面積約123万平方キロメートル。人口263万(2005)。区都ラサ(拉薩)。→中華人民共和国(図)。
⇒チベット‐ご【チベット語】
⇒チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】
⇒チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
⇒チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】
チベット‐ご【チベット語】
(Tibetan)中国チベット自治区を中心にパキスタンの一部、ネパールなどで用いられている言語。シナ‐チベット語族のチベット‐ビルマ語派に属する。文語と口語との区別が明瞭。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】‥ザウキヤウ
チベットで編集されたチベット語大蔵経。カンギュル(経律)とテンギュル(論書)とから成る。最も古いナルタン版やデルゲ版・北京版・ラサ版などがあり、インドの大乗仏教研究にも不可欠の資料。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
(Tibeto-Burman)シナ‐チベット語族の一語派。チベットからヒマラヤ・アッサム・中国南西部・ビルマ(ミャンマー)・タイにかけて分布。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】‥ケウ
仏教の一派。吐蕃王国時代にインドからチベットに伝わった大乗仏教と密教の混合形態。チベット大蔵経を用いる。のちモンゴル・旧満州(中国東北地方)・ネパール・ブータン・ラダックにも伝播した。主な宗派はニンマ派(紅教)・サキャ派・カギュー派・ゲルク派(黄教)の4派。俗称、ラマ教。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
ち‐へど【血反吐】
吐いて口から出す血。血の混じったへど。
ち‐べり【乳縁】
蚊帳かやなどで、乳ち3のついているへり。好色二代男「八畳づりの紋紗の蚊帳、―ひどんす」
ち‐へん【地変】
土地の変動。海岸線の移動、土地の陥没、火山の噴火または地震などの地殻変動。地異。「天災―」
ち‐へん【池辺】
池のほとり。池畔。
ち‐べん【知弁・智辨】
知恵があって、物を知りわける能力があること。
ち‐べん【知弁・智辯】
①才知のある弁舌。
②才知と弁舌。源平盛衰記1「顕密兼学の法灯、―無窮の秀才」
ち‐ほ【地歩】
自己のいる地位。活動する上での立場。立脚地。位置。「確乎たる―を占める」
ちぼ
(西日本で)すり。巾着切り。
ち‐ほう【地方】‥ハウ
①国内の一部分の土地。「関東―」
②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。
③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。
⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】
⇒ちほう‐かん【地方官】
⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】
⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】
⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】
⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】
⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】
⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】
⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】
⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】
⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】
⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】
⇒ちほう‐く【地方区】
⇒ちほう‐けい【地方型】
⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】
⇒ちほう‐けいば【地方競馬】
⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】
⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】
⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】
⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】
⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】
⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】
⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】
⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】
⇒ちほう‐さい【地方債】
⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】
⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】
⇒ちほう‐し【地方史】
⇒ちほう‐し【地方紙】
⇒ちほう‐じ【地方時】
⇒ちほう‐じち【地方自治】
⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】
⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】
⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】
⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】
⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】
⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】
⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】
⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】
⇒ちほう‐しょく【地方色】
⇒ちほう‐ぜい【地方税】
⇒ちほう‐せいど【地方制度】
⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】
⇒ちほう‐たい【地方隊】
⇒ちほう‐だんたい【地方団体】
⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】
⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】
⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】
⇒ちほう‐ばん【地方版】
⇒ちほう‐びょう【地方病】
⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】
⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】
⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】
⇒ちほう‐ほういん【地方法院】
⇒ちほう‐みんかい【地方民会】
⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】
⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】
ち‐ほう【治邦】‥ハウ
国を治めること。治まっている国。
ち‐ほう【痴呆】
いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態。ふつう感情面・意欲面の低下をも伴う。脳の腫瘍・炎症、中毒・血液循環障害また、加齢などに由来。アルツハイマー病の類。認知症。
ち‐ぼう【地貌】‥バウ
地表面の形状、すなわち高低・起伏・斜面などの状態。
ち‐ぼう【知謀・智謀】
ちえのあるはかりごと。巧みなはかりごと。太平記29「暫時の―事成りしかば」。「―をめぐらす」
ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥
日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン
明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥
明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ
その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ
地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きしょうだい【地方気象台】‥ハウ‥シヤウ‥
各府県に1カ所ずつと、北海道・沖縄では地理的に考慮された支庁に1カ所ずつ設置されている気象台。管区気象台の業務指導・予報指示を受け、区域内の測候所の管理業務を行う。国際空港には別に航空地方気象台がある。→管区気象台。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥
地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥
①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。
②国の地方行政官庁が行う国の行政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン
地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】‥ハウギヤウ‥クワンチヤウ
(→)地方官庁に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン
権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ
普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐く【地方区】‥ハウ‥
参議院議員選挙で、地方(都道府県など)を単位として設定された選挙区。1983年、比例代表制の導入により選挙区と改称。→全国区。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥
同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】‥ハウ‥ヰン
都道府県の職員である警察官。→地方警務官。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥
地方自治体などが主催する競馬。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン
国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】‥ハウ‥チヤウ
地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。→検察庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ
地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥
国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥
地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ
仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥
基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン
地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥
地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥
地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥
下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方史】‥ハウ‥
地域社会の歴史。過去における地域社会の発展を研究し、それが一国の歴史、世界の歴史の発展とどのような関係をもつかを明らかにし、地域社会が当面する諸問題について理解を深めようとするもの。→郷土史。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥
限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じ【地方時】‥ハウ‥
その地の子午線を基準として定めた時刻。→標準時。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥
地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥
地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じちたい【地方自治体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ
日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン
特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむしょ【地方事務所】‥ハウ‥
(→)支庁に同じ。沿革上名称を異にする。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ
各地を興行してまわること。巡業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥
都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥
国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥
その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥
地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥
地方行政の組織・権限などに関する制度。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せんきょ【地方選挙】‥ハウ‥
(→)一般選挙に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥
海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐だんたい【地方団体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン
明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ
一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐はいふぜい【地方配付税】‥ハウ‥
(→)配付税に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥
中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ
一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥
(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥
地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】‥ハウ‥
旧制で、いったん国税の形式によって課徴した地方税を一定の基準で地方団体に還元または配分交付した税。1948年廃止。→配付税。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン
旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ
明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥
防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】‥ハウラウ‥ヰヰンクワイ
都道府県に置かれる労働委員会。使用者・労働者・公益をそれぞれ代表する委員から成り、都道府県知事が任命する。略称、地労委。→労働委員会
⇒ち‐ほう【地方】
チボー【J. Thibaud】
⇒ティボー
チボーけのひとびと【チボー家の人々】
(Les Thibault フランス)マルタン=デュ=ガールの大河小説。1922〜40年刊。
チボーデ【Albert Thibaudet】
フランスの文芸批評家。マラルメとベルクソンの影響のもとに、該博な学識、精緻な分析、みずみずしい感性がとけあった批評を書いた。著「マラルメの詩」「ギュスタヴ=フロベール」「近代フランス文学史」など。(1874〜1936)
ちぼちぼ
①飛沫のとび散るさま、細雨の降るさま。また、小さな芽などの生ずるさま。〈日葡辞書〉
②小さなこと。日葡辞書「チボチボシタコト」
ちぼ・ゆ
〔自下二〕
小声でほえる。小声で鳴く。俚言集覧「ち吠ほゆる、奴詞也」
チマ【裳】
(朝鮮語ch‘ima)朝鮮の民族服。女性が用いる、スカートに似た胸からくるぶしまでの丈の裳も。上着のチョゴリと共に着用する。
チマーゼ【Zymase ドイツ】
糖類からアルコールと炭酸ガスとをつくる酵素系。1897年、アルコール発酵に関与する酵母中にドイツの生化学者ブフナーが発見・命名。
ちまうチマフ
動詞連用形につづく「…てしまう」の約。話し言葉で使う。「…でしまう」のときは「じまう」になる。「行っ―」「死んじまう」
ち‐まき【粽・茅巻】
①(古く茅ちがやの葉で巻いたからいう)端午の節句に食べる糯米もちごめ粉・粳米うるちまい粉・葛粉などで作った餅。長円錐形に固めて笹や真菰まこもなどの葉で巻き、藺草いぐさで縛って蒸したもの。中国では汨羅べきらに投身した屈原の忌日が5月5日なので、その姉が弟を弔うために、当日餅を江に投じて虬竜きゅうりょうを祀ったのに始まるという。〈[季]夏〉。伊勢物語「人のもとよりかざり―おこせたりする返事に」
②〔建〕柱の上下の、次第に円みをもってすぼまった部分。鎌倉時代より始まった禅宗建築に多い手法。粽形。
⇒ちまき‐うま【粽馬】
⇒ちまき‐がた【粽形】
⇒ちまき‐ざさ【粽笹】
ち‐まき【千巻】
織機の部分品で、織られた織物を巻き取るための木製の円棒。
ちまき‐うま【粽馬】
茅ちがやまたは菰こもを巻いて馬の形につくった玩具。端午に子供がもてあそんだ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐がた【粽形】
〔建〕(→)「ちまき」2に同じ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐ざさ【粽笹】
ササの一種。山地に自生。稈かんは高さ1.5メートル、まばらに分枝し、葉は広く大きく、短い柄で茎の先に5〜9片を掌状につける。葉は粽を包むのに用いる。クマイザサ。クスザサ。
チマキザサ
撮影:関戸 勇
縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」
ち‐ふ【乳癰】
(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉
ち‐ふ【茅生】
チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」
ち‐ふ【地府】
①大地。地上。
②冥土めいど。冥界。
ち‐ふ【知府】
府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。
ち‐ふ【致富】
富を得ること。金持になること。「―譚たん」
ち‐ぶ【恥部】
①陰部。
②恥ずべき部分。「日本の―」
ち・ぶ【禿ぶ】
〔自上二〕
⇒ちびる(上一)
ち‐ぶくら【乳袋】
①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。
②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)
ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】
①乳房。
②(→)「ちぶくら」2に同じ。
ち‐ぶさ【乳房】
哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」
ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ
出産の忌をいう語。
チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」
⇒チフス‐きん【チフス菌】
チフス‐きん【チフス菌】
腸チフス菌の通称。
⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
ち‐ぶつ【地物】
地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。
ち‐ふね【千船】
多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」
ち‐ぶみ【血文】
血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」
ち‐ぶみ【地踏み】
力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。
ち‐ぶり【血鰤】
鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。
チフリス【Tiflis】
グルジア共和国の都市トビリシの旧称。
ちふり‐の‐かみ【道触の神】
陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」
ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ
①産後に血の道のため、体がふるえる病。
②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。
③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。
ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ
乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。
ち‐ぶん【地文】
⇒ちもん
ち‐ぶん【知分】
知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」
ち‐へい【地平】
①大地の平らな面。
②地平線。
③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」
⇒ちへい‐きょり【地平距離】
⇒ちへい‐せん【地平線】
⇒ちへい‐ふかく【地平俯角】
⇒ちへい‐めん【地平面】
⇒ちへい‐ゆうごう【地平融合】
ち‐へい【治平】
世の中が治まって平穏なこと。太平。
ち‐へい【治兵】
軍隊の兵員・装備をととのえること。
ちへい‐きょり【地平距離】
地球表面上、ある高さの所で、見通し得る最大距離。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐せん【地平線】
(horizon)
①海または平原が空と接する一線。自然地平。
②地上のある場所における鉛直線に垂直な平面が天球と交わる大円。視地平。→地心地平。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ふかく【地平俯角】
自然地平線(自然地平)と天文学的な地平線(視地平)とのなす微小な角。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐めん【地平面】
地球上のある地点において鉛直線に垂直な平面。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ゆうごう【地平融合】‥ガフ
(Horizontverschmelzung ドイツ)ガーダマーの哲学的解釈学の用語。テキストが属する過去の文化的地平と解釈者が属する現在の文化的地平とが相互に浸透し合うことによって、より大きな普遍性が獲得されること。
⇒ち‐へい【地平】
チベット【Tibet・西蔵】
中国四川省の西、インドの北、パミール高原の東に位置する高原地帯。7世紀には吐蕃が建国、18世紀以来、中国の宗主権下にあったが、20世紀に入りイギリスの実力による支配を受け、その保護下のダライ=ラマ自治国の観を呈した。第二次大戦後中華人民共和国が掌握、1965年チベット自治区となる。住民の約90パーセントはチベット族で、チベット語を用い、チベット仏教を信仰する。平均標高約4000メートルで、東部・南部の谷間では麦などの栽培、羊・ヤクなどの牧畜が行われる。面積約123万平方キロメートル。人口263万(2005)。区都ラサ(拉薩)。→中華人民共和国(図)。
⇒チベット‐ご【チベット語】
⇒チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】
⇒チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
⇒チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】
チベット‐ご【チベット語】
(Tibetan)中国チベット自治区を中心にパキスタンの一部、ネパールなどで用いられている言語。シナ‐チベット語族のチベット‐ビルマ語派に属する。文語と口語との区別が明瞭。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】‥ザウキヤウ
チベットで編集されたチベット語大蔵経。カンギュル(経律)とテンギュル(論書)とから成る。最も古いナルタン版やデルゲ版・北京版・ラサ版などがあり、インドの大乗仏教研究にも不可欠の資料。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
(Tibeto-Burman)シナ‐チベット語族の一語派。チベットからヒマラヤ・アッサム・中国南西部・ビルマ(ミャンマー)・タイにかけて分布。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】‥ケウ
仏教の一派。吐蕃王国時代にインドからチベットに伝わった大乗仏教と密教の混合形態。チベット大蔵経を用いる。のちモンゴル・旧満州(中国東北地方)・ネパール・ブータン・ラダックにも伝播した。主な宗派はニンマ派(紅教)・サキャ派・カギュー派・ゲルク派(黄教)の4派。俗称、ラマ教。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
ち‐へど【血反吐】
吐いて口から出す血。血の混じったへど。
ち‐べり【乳縁】
蚊帳かやなどで、乳ち3のついているへり。好色二代男「八畳づりの紋紗の蚊帳、―ひどんす」
ち‐へん【地変】
土地の変動。海岸線の移動、土地の陥没、火山の噴火または地震などの地殻変動。地異。「天災―」
ち‐へん【池辺】
池のほとり。池畔。
ち‐べん【知弁・智辨】
知恵があって、物を知りわける能力があること。
ち‐べん【知弁・智辯】
①才知のある弁舌。
②才知と弁舌。源平盛衰記1「顕密兼学の法灯、―無窮の秀才」
ち‐ほ【地歩】
自己のいる地位。活動する上での立場。立脚地。位置。「確乎たる―を占める」
ちぼ
(西日本で)すり。巾着切り。
ち‐ほう【地方】‥ハウ
①国内の一部分の土地。「関東―」
②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。
③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。
⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】
⇒ちほう‐かん【地方官】
⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】
⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】
⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】
⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】
⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】
⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】
⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】
⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】
⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】
⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】
⇒ちほう‐く【地方区】
⇒ちほう‐けい【地方型】
⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】
⇒ちほう‐けいば【地方競馬】
⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】
⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】
⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】
⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】
⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】
⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】
⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】
⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】
⇒ちほう‐さい【地方債】
⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】
⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】
⇒ちほう‐し【地方史】
⇒ちほう‐し【地方紙】
⇒ちほう‐じ【地方時】
⇒ちほう‐じち【地方自治】
⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】
⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】
⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】
⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】
⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】
⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】
⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】
⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】
⇒ちほう‐しょく【地方色】
⇒ちほう‐ぜい【地方税】
⇒ちほう‐せいど【地方制度】
⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】
⇒ちほう‐たい【地方隊】
⇒ちほう‐だんたい【地方団体】
⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】
⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】
⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】
⇒ちほう‐ばん【地方版】
⇒ちほう‐びょう【地方病】
⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】
⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】
⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】
⇒ちほう‐ほういん【地方法院】
⇒ちほう‐みんかい【地方民会】
⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】
⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】
ち‐ほう【治邦】‥ハウ
国を治めること。治まっている国。
ち‐ほう【痴呆】
いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態。ふつう感情面・意欲面の低下をも伴う。脳の腫瘍・炎症、中毒・血液循環障害また、加齢などに由来。アルツハイマー病の類。認知症。
ち‐ぼう【地貌】‥バウ
地表面の形状、すなわち高低・起伏・斜面などの状態。
ち‐ぼう【知謀・智謀】
ちえのあるはかりごと。巧みなはかりごと。太平記29「暫時の―事成りしかば」。「―をめぐらす」
ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥
日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン
明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥
明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ
その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ
地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きしょうだい【地方気象台】‥ハウ‥シヤウ‥
各府県に1カ所ずつと、北海道・沖縄では地理的に考慮された支庁に1カ所ずつ設置されている気象台。管区気象台の業務指導・予報指示を受け、区域内の測候所の管理業務を行う。国際空港には別に航空地方気象台がある。→管区気象台。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥
地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥
①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。
②国の地方行政官庁が行う国の行政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン
地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】‥ハウギヤウ‥クワンチヤウ
(→)地方官庁に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン
権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ
普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐く【地方区】‥ハウ‥
参議院議員選挙で、地方(都道府県など)を単位として設定された選挙区。1983年、比例代表制の導入により選挙区と改称。→全国区。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥
同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】‥ハウ‥ヰン
都道府県の職員である警察官。→地方警務官。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥
地方自治体などが主催する競馬。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン
国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】‥ハウ‥チヤウ
地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。→検察庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ
地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥
国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥
地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ
仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥
基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン
地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥
地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥
地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥
下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方史】‥ハウ‥
地域社会の歴史。過去における地域社会の発展を研究し、それが一国の歴史、世界の歴史の発展とどのような関係をもつかを明らかにし、地域社会が当面する諸問題について理解を深めようとするもの。→郷土史。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥
限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じ【地方時】‥ハウ‥
その地の子午線を基準として定めた時刻。→標準時。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥
地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥
地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じちたい【地方自治体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ
日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン
特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむしょ【地方事務所】‥ハウ‥
(→)支庁に同じ。沿革上名称を異にする。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ
各地を興行してまわること。巡業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥
都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥
国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥
その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥
地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥
地方行政の組織・権限などに関する制度。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せんきょ【地方選挙】‥ハウ‥
(→)一般選挙に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥
海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐だんたい【地方団体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン
明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ
一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐はいふぜい【地方配付税】‥ハウ‥
(→)配付税に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥
中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ
一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥
(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥
地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】‥ハウ‥
旧制で、いったん国税の形式によって課徴した地方税を一定の基準で地方団体に還元または配分交付した税。1948年廃止。→配付税。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン
旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ
明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥
防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】‥ハウラウ‥ヰヰンクワイ
都道府県に置かれる労働委員会。使用者・労働者・公益をそれぞれ代表する委員から成り、都道府県知事が任命する。略称、地労委。→労働委員会
⇒ち‐ほう【地方】
チボー【J. Thibaud】
⇒ティボー
チボーけのひとびと【チボー家の人々】
(Les Thibault フランス)マルタン=デュ=ガールの大河小説。1922〜40年刊。
チボーデ【Albert Thibaudet】
フランスの文芸批評家。マラルメとベルクソンの影響のもとに、該博な学識、精緻な分析、みずみずしい感性がとけあった批評を書いた。著「マラルメの詩」「ギュスタヴ=フロベール」「近代フランス文学史」など。(1874〜1936)
ちぼちぼ
①飛沫のとび散るさま、細雨の降るさま。また、小さな芽などの生ずるさま。〈日葡辞書〉
②小さなこと。日葡辞書「チボチボシタコト」
ちぼ・ゆ
〔自下二〕
小声でほえる。小声で鳴く。俚言集覧「ち吠ほゆる、奴詞也」
チマ【裳】
(朝鮮語ch‘ima)朝鮮の民族服。女性が用いる、スカートに似た胸からくるぶしまでの丈の裳も。上着のチョゴリと共に着用する。
チマーゼ【Zymase ドイツ】
糖類からアルコールと炭酸ガスとをつくる酵素系。1897年、アルコール発酵に関与する酵母中にドイツの生化学者ブフナーが発見・命名。
ちまうチマフ
動詞連用形につづく「…てしまう」の約。話し言葉で使う。「…でしまう」のときは「じまう」になる。「行っ―」「死んじまう」
ち‐まき【粽・茅巻】
①(古く茅ちがやの葉で巻いたからいう)端午の節句に食べる糯米もちごめ粉・粳米うるちまい粉・葛粉などで作った餅。長円錐形に固めて笹や真菰まこもなどの葉で巻き、藺草いぐさで縛って蒸したもの。中国では汨羅べきらに投身した屈原の忌日が5月5日なので、その姉が弟を弔うために、当日餅を江に投じて虬竜きゅうりょうを祀ったのに始まるという。〈[季]夏〉。伊勢物語「人のもとよりかざり―おこせたりする返事に」
②〔建〕柱の上下の、次第に円みをもってすぼまった部分。鎌倉時代より始まった禅宗建築に多い手法。粽形。
⇒ちまき‐うま【粽馬】
⇒ちまき‐がた【粽形】
⇒ちまき‐ざさ【粽笹】
ち‐まき【千巻】
織機の部分品で、織られた織物を巻き取るための木製の円棒。
ちまき‐うま【粽馬】
茅ちがやまたは菰こもを巻いて馬の形につくった玩具。端午に子供がもてあそんだ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐がた【粽形】
〔建〕(→)「ちまき」2に同じ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐ざさ【粽笹】
ササの一種。山地に自生。稈かんは高さ1.5メートル、まばらに分枝し、葉は広く大きく、短い柄で茎の先に5〜9片を掌状につける。葉は粽を包むのに用いる。クマイザサ。クスザサ。
チマキザサ
撮影:関戸 勇
 ⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ち‐また【岐・巷・衢】
(「道股ちまた」の意)
①道の分かれる所。わかれみち。つじ。万葉集12「海石榴市つばいちの八十やその―に立ち平ならし」
②町の中の道路。街路。また、繁華な通り。今昔物語集7「門の内の南北に大きなる一つの―あり」
③ところ。場所。「修羅しゅらの―」
④世間。「―の声」
⇒ちまた‐の‐かみ【岐の神】
ちまた‐の‐かみ【岐の神】
①道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神。道祖神。さえのかみ。神代紀下「衢神ちまたのかみ」
②(天孫降臨の時、天の八衢やちまたに迎えて先導したからいう)猿田彦神の異称。
⇒ち‐また【岐・巷・衢】
ちまち‐だ【千町田】
(「千町もある田」の意)ひろい田。
ちま‐ちま
小さくまとまっているさま。ちんまり。こぢんまり。「―した家」「―とした顔」
ち‐まつり【血祭】
(昔中国で、出陣の際いけにえを殺し、その血をもって軍神を祀ったことから)
①戦場に臨む際に、縁起のため、間諜かんちょうまたは敵方の者などを殺すこと。また戦場などで、最初に敵を討ち取ること。〈日葡辞書〉。「―に上げる」
②狩人が猪や鹿を射とめたときに行う祭。→ふくまるまつり
ち‐まど・う【血惑ふ】‥マドフ
〔自四〕
取り乱す。逆上して狂乱の状態になる。血まよう。〈日葡辞書〉
ち‐まなこ【血眼】
①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」
②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」
チマブーエ【Giovanni Cimabue】
イタリアの画家。イタリア‐ビザンチン風の古い伝統様式を守った最後の人。ジョットの師。作「サンタ‐トリニタの荘厳の聖母」(フィレンツェ)など。(1240以後〜1302)
ち‐まぶれ【血塗れ】
(→)「ちまみれ」に同じ。南総里見八犬伝28「地上に樹たてたる小刀こだちを抜とり、閃ひらりと見せてとり直し―序ついでにこの刃で」
ち‐まみれ【血塗れ】
血にまみれること。一面に血で染まること。ちだらけ。ちみどろ。「―のシャツ」
ち‐まめ【血豆】
指などを強く挟んだり打ったりして圧迫した時にできる、豆状の血腫けっしゅ。
ち‐まよ・う【血迷う】‥マヨフ
〔自五〕
逆上して正常な判断力を失う。のぼせあがる。「何を―・っているのか」
ちま・る
〔自四〕
(上代東国方言)とまる。万葉集20「筑紫の崎に―・り居て」
チマローザ【Domenico Cimarosa】
イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。歌劇「秘密の結婚」など。(1749〜1801)
ち‐まん【遅慢】
おそいこと。のろいこと。
ち‐み【血身】
血族。ちみち。
ち‐み【地味】
①作物栽培についての、地質の良否の状態。「―が肥えている」
②土地に産する物。特に、米。じみ。
ち‐み【魑魅】
[史記五帝本紀](「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神)山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。
ち‐みち
(「ちみうち(血身内)」の略)血族。親類。
ち‐みち【血道】
血の通う道。血脈。
⇒血道をあげる
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ち‐また【岐・巷・衢】
(「道股ちまた」の意)
①道の分かれる所。わかれみち。つじ。万葉集12「海石榴市つばいちの八十やその―に立ち平ならし」
②町の中の道路。街路。また、繁華な通り。今昔物語集7「門の内の南北に大きなる一つの―あり」
③ところ。場所。「修羅しゅらの―」
④世間。「―の声」
⇒ちまた‐の‐かみ【岐の神】
ちまた‐の‐かみ【岐の神】
①道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神。道祖神。さえのかみ。神代紀下「衢神ちまたのかみ」
②(天孫降臨の時、天の八衢やちまたに迎えて先導したからいう)猿田彦神の異称。
⇒ち‐また【岐・巷・衢】
ちまち‐だ【千町田】
(「千町もある田」の意)ひろい田。
ちま‐ちま
小さくまとまっているさま。ちんまり。こぢんまり。「―した家」「―とした顔」
ち‐まつり【血祭】
(昔中国で、出陣の際いけにえを殺し、その血をもって軍神を祀ったことから)
①戦場に臨む際に、縁起のため、間諜かんちょうまたは敵方の者などを殺すこと。また戦場などで、最初に敵を討ち取ること。〈日葡辞書〉。「―に上げる」
②狩人が猪や鹿を射とめたときに行う祭。→ふくまるまつり
ち‐まど・う【血惑ふ】‥マドフ
〔自四〕
取り乱す。逆上して狂乱の状態になる。血まよう。〈日葡辞書〉
ち‐まなこ【血眼】
①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」
②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」
チマブーエ【Giovanni Cimabue】
イタリアの画家。イタリア‐ビザンチン風の古い伝統様式を守った最後の人。ジョットの師。作「サンタ‐トリニタの荘厳の聖母」(フィレンツェ)など。(1240以後〜1302)
ち‐まぶれ【血塗れ】
(→)「ちまみれ」に同じ。南総里見八犬伝28「地上に樹たてたる小刀こだちを抜とり、閃ひらりと見せてとり直し―序ついでにこの刃で」
ち‐まみれ【血塗れ】
血にまみれること。一面に血で染まること。ちだらけ。ちみどろ。「―のシャツ」
ち‐まめ【血豆】
指などを強く挟んだり打ったりして圧迫した時にできる、豆状の血腫けっしゅ。
ち‐まよ・う【血迷う】‥マヨフ
〔自五〕
逆上して正常な判断力を失う。のぼせあがる。「何を―・っているのか」
ちま・る
〔自四〕
(上代東国方言)とまる。万葉集20「筑紫の崎に―・り居て」
チマローザ【Domenico Cimarosa】
イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。歌劇「秘密の結婚」など。(1749〜1801)
ち‐まん【遅慢】
おそいこと。のろいこと。
ち‐み【血身】
血族。ちみち。
ち‐み【地味】
①作物栽培についての、地質の良否の状態。「―が肥えている」
②土地に産する物。特に、米。じみ。
ち‐み【魑魅】
[史記五帝本紀](「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神)山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。
ち‐みち
(「ちみうち(血身内)」の略)血族。親類。
ち‐みち【血道】
血の通う道。血脈。
⇒血道をあげる
 ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ
大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。
ちはや‐びと【千早人】
〔枕〕
(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。
ちはや・ぶ【千早ぶ】
〔自上二〕
(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」
ちはやふる【千早振る】
落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。
ちはや‐ぶる【千早振る】
〔枕〕
(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」
ち‐はら【茅原】
(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」
ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ
給与や代金などの支払いがおくれること。
ちばり‐よお
(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。
ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ
千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。
ち‐はん【池畔】
池のほとり。池辺。
ち‐ばん【血判】
(→)「けっぱん」に同じ。
ち‐ばん【地番】
土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」
ち‐はんじ【知藩事】
1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。
ち‐ひ【地皮】
(→)地殻ちかくに同じ。
ち‐ひ【地被】
地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」
ちび
からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」
ち‐びき【千引】
千人で引くほどの重さの物。
⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】
⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】
⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】
ち‐びき【血引】
沿岸魚、ハチビキの別称。
ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ
綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐つな【千引の綱】
千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ
(→)「千引の綱」に同じ。
⇒ち‐びき【千引】
ちび‐ちび
〔副〕
物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」
ち‐ひつ【遅筆】
文を書くのがおそいこと。
ちびっ‐こ【ちびっ子】
幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」
ちびっ‐ちょ
「ちび」を強めていう語。ちびっこ。
ち‐ひと【千人】
せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」
ち‐ひと【乳人】
乳母。めのと。ちのひと。
ちび‐ふで【禿筆】
毛さきのすりきれた筆。とくひつ。
ち‐ひょう【地表】‥ヘウ
地球の表面。土地の表面。
⇒ちひょう‐か【地表火】
⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】
⇒ちひょう‐すい【地表水】
ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ
門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。
ち‐びょう【稚苗】‥ベウ
葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗
ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ
燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥
越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥
地表にある水。河川・湖沼などの水。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちびり
〔副〕
すこし。いささか。
⇒ちびり‐ちびり
ちびり‐ちびり
少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」
⇒ちびり
ちび・る
〔他五〕
①小便などを少し漏らす。
②出し惜しむ。「費用を―・る」
③少しずつ飲む。
ち・びる【禿びる】
〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)
先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」
ち‐ひろ【千尋】
(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「
ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ
大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。
ちはや‐びと【千早人】
〔枕〕
(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。
ちはや・ぶ【千早ぶ】
〔自上二〕
(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」
ちはやふる【千早振る】
落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。
ちはや‐ぶる【千早振る】
〔枕〕
(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」
ち‐はら【茅原】
(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」
ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ
給与や代金などの支払いがおくれること。
ちばり‐よお
(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。
ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ
千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。
ち‐はん【池畔】
池のほとり。池辺。
ち‐ばん【血判】
(→)「けっぱん」に同じ。
ち‐ばん【地番】
土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」
ち‐はんじ【知藩事】
1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。
ち‐ひ【地皮】
(→)地殻ちかくに同じ。
ち‐ひ【地被】
地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」
ちび
からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」
ち‐びき【千引】
千人で引くほどの重さの物。
⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】
⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】
⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】
ち‐びき【血引】
沿岸魚、ハチビキの別称。
ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ
綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐つな【千引の綱】
千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」
⇒ち‐びき【千引】
ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ
(→)「千引の綱」に同じ。
⇒ち‐びき【千引】
ちび‐ちび
〔副〕
物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」
ち‐ひつ【遅筆】
文を書くのがおそいこと。
ちびっ‐こ【ちびっ子】
幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」
ちびっ‐ちょ
「ちび」を強めていう語。ちびっこ。
ち‐ひと【千人】
せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」
ち‐ひと【乳人】
乳母。めのと。ちのひと。
ちび‐ふで【禿筆】
毛さきのすりきれた筆。とくひつ。
ち‐ひょう【地表】‥ヘウ
地球の表面。土地の表面。
⇒ちひょう‐か【地表火】
⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】
⇒ちひょう‐すい【地表水】
ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ
門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。
ち‐びょう【稚苗】‥ベウ
葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗
ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ
燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥
越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥
地表にある水。河川・湖沼などの水。
⇒ち‐ひょう【地表】
ちびり
〔副〕
すこし。いささか。
⇒ちびり‐ちびり
ちびり‐ちびり
少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」
⇒ちびり
ちび・る
〔他五〕
①小便などを少し漏らす。
②出し惜しむ。「費用を―・る」
③少しずつ飲む。
ち・びる【禿びる】
〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)
先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」
ち‐ひろ【千尋】
(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「 縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」
ち‐ふ【乳癰】
(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉
ち‐ふ【茅生】
チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」
ち‐ふ【地府】
①大地。地上。
②冥土めいど。冥界。
ち‐ふ【知府】
府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。
ち‐ふ【致富】
富を得ること。金持になること。「―譚たん」
ち‐ぶ【恥部】
①陰部。
②恥ずべき部分。「日本の―」
ち・ぶ【禿ぶ】
〔自上二〕
⇒ちびる(上一)
ち‐ぶくら【乳袋】
①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。
②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)
ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】
①乳房。
②(→)「ちぶくら」2に同じ。
ち‐ぶさ【乳房】
哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」
ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ
出産の忌をいう語。
チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」
⇒チフス‐きん【チフス菌】
チフス‐きん【チフス菌】
腸チフス菌の通称。
⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
ち‐ぶつ【地物】
地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。
ち‐ふね【千船】
多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」
ち‐ぶみ【血文】
血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」
ち‐ぶみ【地踏み】
力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。
ち‐ぶり【血鰤】
鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。
チフリス【Tiflis】
グルジア共和国の都市トビリシの旧称。
ちふり‐の‐かみ【道触の神】
陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」
ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ
①産後に血の道のため、体がふるえる病。
②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。
③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。
ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ
乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。
ち‐ぶん【地文】
⇒ちもん
ち‐ぶん【知分】
知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」
ち‐へい【地平】
①大地の平らな面。
②地平線。
③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」
⇒ちへい‐きょり【地平距離】
⇒ちへい‐せん【地平線】
⇒ちへい‐ふかく【地平俯角】
⇒ちへい‐めん【地平面】
⇒ちへい‐ゆうごう【地平融合】
ち‐へい【治平】
世の中が治まって平穏なこと。太平。
ち‐へい【治兵】
軍隊の兵員・装備をととのえること。
ちへい‐きょり【地平距離】
地球表面上、ある高さの所で、見通し得る最大距離。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐せん【地平線】
(horizon)
①海または平原が空と接する一線。自然地平。
②地上のある場所における鉛直線に垂直な平面が天球と交わる大円。視地平。→地心地平。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ふかく【地平俯角】
自然地平線(自然地平)と天文学的な地平線(視地平)とのなす微小な角。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐めん【地平面】
地球上のある地点において鉛直線に垂直な平面。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ゆうごう【地平融合】‥ガフ
(Horizontverschmelzung ドイツ)ガーダマーの哲学的解釈学の用語。テキストが属する過去の文化的地平と解釈者が属する現在の文化的地平とが相互に浸透し合うことによって、より大きな普遍性が獲得されること。
⇒ち‐へい【地平】
チベット【Tibet・西蔵】
中国四川省の西、インドの北、パミール高原の東に位置する高原地帯。7世紀には吐蕃が建国、18世紀以来、中国の宗主権下にあったが、20世紀に入りイギリスの実力による支配を受け、その保護下のダライ=ラマ自治国の観を呈した。第二次大戦後中華人民共和国が掌握、1965年チベット自治区となる。住民の約90パーセントはチベット族で、チベット語を用い、チベット仏教を信仰する。平均標高約4000メートルで、東部・南部の谷間では麦などの栽培、羊・ヤクなどの牧畜が行われる。面積約123万平方キロメートル。人口263万(2005)。区都ラサ(拉薩)。→中華人民共和国(図)。
⇒チベット‐ご【チベット語】
⇒チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】
⇒チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
⇒チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】
チベット‐ご【チベット語】
(Tibetan)中国チベット自治区を中心にパキスタンの一部、ネパールなどで用いられている言語。シナ‐チベット語族のチベット‐ビルマ語派に属する。文語と口語との区別が明瞭。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】‥ザウキヤウ
チベットで編集されたチベット語大蔵経。カンギュル(経律)とテンギュル(論書)とから成る。最も古いナルタン版やデルゲ版・北京版・ラサ版などがあり、インドの大乗仏教研究にも不可欠の資料。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
(Tibeto-Burman)シナ‐チベット語族の一語派。チベットからヒマラヤ・アッサム・中国南西部・ビルマ(ミャンマー)・タイにかけて分布。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】‥ケウ
仏教の一派。吐蕃王国時代にインドからチベットに伝わった大乗仏教と密教の混合形態。チベット大蔵経を用いる。のちモンゴル・旧満州(中国東北地方)・ネパール・ブータン・ラダックにも伝播した。主な宗派はニンマ派(紅教)・サキャ派・カギュー派・ゲルク派(黄教)の4派。俗称、ラマ教。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
ち‐へど【血反吐】
吐いて口から出す血。血の混じったへど。
ち‐べり【乳縁】
蚊帳かやなどで、乳ち3のついているへり。好色二代男「八畳づりの紋紗の蚊帳、―ひどんす」
ち‐へん【地変】
土地の変動。海岸線の移動、土地の陥没、火山の噴火または地震などの地殻変動。地異。「天災―」
ち‐へん【池辺】
池のほとり。池畔。
ち‐べん【知弁・智辨】
知恵があって、物を知りわける能力があること。
ち‐べん【知弁・智辯】
①才知のある弁舌。
②才知と弁舌。源平盛衰記1「顕密兼学の法灯、―無窮の秀才」
ち‐ほ【地歩】
自己のいる地位。活動する上での立場。立脚地。位置。「確乎たる―を占める」
ちぼ
(西日本で)すり。巾着切り。
ち‐ほう【地方】‥ハウ
①国内の一部分の土地。「関東―」
②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。
③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。
⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】
⇒ちほう‐かん【地方官】
⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】
⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】
⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】
⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】
⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】
⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】
⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】
⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】
⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】
⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】
⇒ちほう‐く【地方区】
⇒ちほう‐けい【地方型】
⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】
⇒ちほう‐けいば【地方競馬】
⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】
⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】
⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】
⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】
⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】
⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】
⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】
⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】
⇒ちほう‐さい【地方債】
⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】
⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】
⇒ちほう‐し【地方史】
⇒ちほう‐し【地方紙】
⇒ちほう‐じ【地方時】
⇒ちほう‐じち【地方自治】
⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】
⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】
⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】
⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】
⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】
⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】
⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】
⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】
⇒ちほう‐しょく【地方色】
⇒ちほう‐ぜい【地方税】
⇒ちほう‐せいど【地方制度】
⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】
⇒ちほう‐たい【地方隊】
⇒ちほう‐だんたい【地方団体】
⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】
⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】
⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】
⇒ちほう‐ばん【地方版】
⇒ちほう‐びょう【地方病】
⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】
⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】
⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】
⇒ちほう‐ほういん【地方法院】
⇒ちほう‐みんかい【地方民会】
⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】
⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】
ち‐ほう【治邦】‥ハウ
国を治めること。治まっている国。
ち‐ほう【痴呆】
いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態。ふつう感情面・意欲面の低下をも伴う。脳の腫瘍・炎症、中毒・血液循環障害また、加齢などに由来。アルツハイマー病の類。認知症。
ち‐ぼう【地貌】‥バウ
地表面の形状、すなわち高低・起伏・斜面などの状態。
ち‐ぼう【知謀・智謀】
ちえのあるはかりごと。巧みなはかりごと。太平記29「暫時の―事成りしかば」。「―をめぐらす」
ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥
日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン
明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥
明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ
その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ
地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きしょうだい【地方気象台】‥ハウ‥シヤウ‥
各府県に1カ所ずつと、北海道・沖縄では地理的に考慮された支庁に1カ所ずつ設置されている気象台。管区気象台の業務指導・予報指示を受け、区域内の測候所の管理業務を行う。国際空港には別に航空地方気象台がある。→管区気象台。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥
地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥
①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。
②国の地方行政官庁が行う国の行政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン
地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】‥ハウギヤウ‥クワンチヤウ
(→)地方官庁に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン
権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ
普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐く【地方区】‥ハウ‥
参議院議員選挙で、地方(都道府県など)を単位として設定された選挙区。1983年、比例代表制の導入により選挙区と改称。→全国区。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥
同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】‥ハウ‥ヰン
都道府県の職員である警察官。→地方警務官。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥
地方自治体などが主催する競馬。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン
国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】‥ハウ‥チヤウ
地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。→検察庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ
地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥
国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥
地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ
仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥
基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン
地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥
地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥
地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥
下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方史】‥ハウ‥
地域社会の歴史。過去における地域社会の発展を研究し、それが一国の歴史、世界の歴史の発展とどのような関係をもつかを明らかにし、地域社会が当面する諸問題について理解を深めようとするもの。→郷土史。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥
限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じ【地方時】‥ハウ‥
その地の子午線を基準として定めた時刻。→標準時。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥
地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥
地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じちたい【地方自治体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ
日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン
特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむしょ【地方事務所】‥ハウ‥
(→)支庁に同じ。沿革上名称を異にする。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ
各地を興行してまわること。巡業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥
都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥
国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥
その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥
地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥
地方行政の組織・権限などに関する制度。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せんきょ【地方選挙】‥ハウ‥
(→)一般選挙に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥
海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐だんたい【地方団体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン
明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ
一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐はいふぜい【地方配付税】‥ハウ‥
(→)配付税に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥
中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ
一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥
(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥
地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】‥ハウ‥
旧制で、いったん国税の形式によって課徴した地方税を一定の基準で地方団体に還元または配分交付した税。1948年廃止。→配付税。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン
旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ
明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥
防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】‥ハウラウ‥ヰヰンクワイ
都道府県に置かれる労働委員会。使用者・労働者・公益をそれぞれ代表する委員から成り、都道府県知事が任命する。略称、地労委。→労働委員会
⇒ち‐ほう【地方】
チボー【J. Thibaud】
⇒ティボー
チボーけのひとびと【チボー家の人々】
(Les Thibault フランス)マルタン=デュ=ガールの大河小説。1922〜40年刊。
チボーデ【Albert Thibaudet】
フランスの文芸批評家。マラルメとベルクソンの影響のもとに、該博な学識、精緻な分析、みずみずしい感性がとけあった批評を書いた。著「マラルメの詩」「ギュスタヴ=フロベール」「近代フランス文学史」など。(1874〜1936)
ちぼちぼ
①飛沫のとび散るさま、細雨の降るさま。また、小さな芽などの生ずるさま。〈日葡辞書〉
②小さなこと。日葡辞書「チボチボシタコト」
ちぼ・ゆ
〔自下二〕
小声でほえる。小声で鳴く。俚言集覧「ち吠ほゆる、奴詞也」
チマ【裳】
(朝鮮語ch‘ima)朝鮮の民族服。女性が用いる、スカートに似た胸からくるぶしまでの丈の裳も。上着のチョゴリと共に着用する。
チマーゼ【Zymase ドイツ】
糖類からアルコールと炭酸ガスとをつくる酵素系。1897年、アルコール発酵に関与する酵母中にドイツの生化学者ブフナーが発見・命名。
ちまうチマフ
動詞連用形につづく「…てしまう」の約。話し言葉で使う。「…でしまう」のときは「じまう」になる。「行っ―」「死んじまう」
ち‐まき【粽・茅巻】
①(古く茅ちがやの葉で巻いたからいう)端午の節句に食べる糯米もちごめ粉・粳米うるちまい粉・葛粉などで作った餅。長円錐形に固めて笹や真菰まこもなどの葉で巻き、藺草いぐさで縛って蒸したもの。中国では汨羅べきらに投身した屈原の忌日が5月5日なので、その姉が弟を弔うために、当日餅を江に投じて虬竜きゅうりょうを祀ったのに始まるという。〈[季]夏〉。伊勢物語「人のもとよりかざり―おこせたりする返事に」
②〔建〕柱の上下の、次第に円みをもってすぼまった部分。鎌倉時代より始まった禅宗建築に多い手法。粽形。
⇒ちまき‐うま【粽馬】
⇒ちまき‐がた【粽形】
⇒ちまき‐ざさ【粽笹】
ち‐まき【千巻】
織機の部分品で、織られた織物を巻き取るための木製の円棒。
ちまき‐うま【粽馬】
茅ちがやまたは菰こもを巻いて馬の形につくった玩具。端午に子供がもてあそんだ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐がた【粽形】
〔建〕(→)「ちまき」2に同じ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐ざさ【粽笹】
ササの一種。山地に自生。稈かんは高さ1.5メートル、まばらに分枝し、葉は広く大きく、短い柄で茎の先に5〜9片を掌状につける。葉は粽を包むのに用いる。クマイザサ。クスザサ。
チマキザサ
撮影:関戸 勇
縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」
ち‐ふ【乳癰】
(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉
ち‐ふ【茅生】
チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」
ち‐ふ【地府】
①大地。地上。
②冥土めいど。冥界。
ち‐ふ【知府】
府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。
ち‐ふ【致富】
富を得ること。金持になること。「―譚たん」
ち‐ぶ【恥部】
①陰部。
②恥ずべき部分。「日本の―」
ち・ぶ【禿ぶ】
〔自上二〕
⇒ちびる(上一)
ち‐ぶくら【乳袋】
①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。
②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)
ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】
①乳房。
②(→)「ちぶくら」2に同じ。
ち‐ぶさ【乳房】
哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」
ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ
出産の忌をいう語。
チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」
⇒チフス‐きん【チフス菌】
チフス‐きん【チフス菌】
腸チフス菌の通称。
⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】
ち‐ぶつ【地物】
地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。
ち‐ふね【千船】
多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」
ち‐ぶみ【血文】
血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」
ち‐ぶみ【地踏み】
力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。
ち‐ぶり【血鰤】
鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。
チフリス【Tiflis】
グルジア共和国の都市トビリシの旧称。
ちふり‐の‐かみ【道触の神】
陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」
ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ
①産後に血の道のため、体がふるえる病。
②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。
③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。
ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ
乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。
ち‐ぶん【地文】
⇒ちもん
ち‐ぶん【知分】
知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」
ち‐へい【地平】
①大地の平らな面。
②地平線。
③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」
⇒ちへい‐きょり【地平距離】
⇒ちへい‐せん【地平線】
⇒ちへい‐ふかく【地平俯角】
⇒ちへい‐めん【地平面】
⇒ちへい‐ゆうごう【地平融合】
ち‐へい【治平】
世の中が治まって平穏なこと。太平。
ち‐へい【治兵】
軍隊の兵員・装備をととのえること。
ちへい‐きょり【地平距離】
地球表面上、ある高さの所で、見通し得る最大距離。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐せん【地平線】
(horizon)
①海または平原が空と接する一線。自然地平。
②地上のある場所における鉛直線に垂直な平面が天球と交わる大円。視地平。→地心地平。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ふかく【地平俯角】
自然地平線(自然地平)と天文学的な地平線(視地平)とのなす微小な角。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐めん【地平面】
地球上のある地点において鉛直線に垂直な平面。
⇒ち‐へい【地平】
ちへい‐ゆうごう【地平融合】‥ガフ
(Horizontverschmelzung ドイツ)ガーダマーの哲学的解釈学の用語。テキストが属する過去の文化的地平と解釈者が属する現在の文化的地平とが相互に浸透し合うことによって、より大きな普遍性が獲得されること。
⇒ち‐へい【地平】
チベット【Tibet・西蔵】
中国四川省の西、インドの北、パミール高原の東に位置する高原地帯。7世紀には吐蕃が建国、18世紀以来、中国の宗主権下にあったが、20世紀に入りイギリスの実力による支配を受け、その保護下のダライ=ラマ自治国の観を呈した。第二次大戦後中華人民共和国が掌握、1965年チベット自治区となる。住民の約90パーセントはチベット族で、チベット語を用い、チベット仏教を信仰する。平均標高約4000メートルで、東部・南部の谷間では麦などの栽培、羊・ヤクなどの牧畜が行われる。面積約123万平方キロメートル。人口263万(2005)。区都ラサ(拉薩)。→中華人民共和国(図)。
⇒チベット‐ご【チベット語】
⇒チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】
⇒チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
⇒チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】
チベット‐ご【チベット語】
(Tibetan)中国チベット自治区を中心にパキスタンの一部、ネパールなどで用いられている言語。シナ‐チベット語族のチベット‐ビルマ語派に属する。文語と口語との区別が明瞭。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】‥ザウキヤウ
チベットで編集されたチベット語大蔵経。カンギュル(経律)とテンギュル(論書)とから成る。最も古いナルタン版やデルゲ版・北京版・ラサ版などがあり、インドの大乗仏教研究にも不可欠の資料。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】
(Tibeto-Burman)シナ‐チベット語族の一語派。チベットからヒマラヤ・アッサム・中国南西部・ビルマ(ミャンマー)・タイにかけて分布。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】‥ケウ
仏教の一派。吐蕃王国時代にインドからチベットに伝わった大乗仏教と密教の混合形態。チベット大蔵経を用いる。のちモンゴル・旧満州(中国東北地方)・ネパール・ブータン・ラダックにも伝播した。主な宗派はニンマ派(紅教)・サキャ派・カギュー派・ゲルク派(黄教)の4派。俗称、ラマ教。
⇒チベット【Tibet・西蔵】
ち‐へど【血反吐】
吐いて口から出す血。血の混じったへど。
ち‐べり【乳縁】
蚊帳かやなどで、乳ち3のついているへり。好色二代男「八畳づりの紋紗の蚊帳、―ひどんす」
ち‐へん【地変】
土地の変動。海岸線の移動、土地の陥没、火山の噴火または地震などの地殻変動。地異。「天災―」
ち‐へん【池辺】
池のほとり。池畔。
ち‐べん【知弁・智辨】
知恵があって、物を知りわける能力があること。
ち‐べん【知弁・智辯】
①才知のある弁舌。
②才知と弁舌。源平盛衰記1「顕密兼学の法灯、―無窮の秀才」
ち‐ほ【地歩】
自己のいる地位。活動する上での立場。立脚地。位置。「確乎たる―を占める」
ちぼ
(西日本で)すり。巾着切り。
ち‐ほう【地方】‥ハウ
①国内の一部分の土地。「関東―」
②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。
③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。
⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】
⇒ちほう‐かん【地方官】
⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】
⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】
⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】
⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】
⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】
⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】
⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】
⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】
⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】
⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】
⇒ちほう‐く【地方区】
⇒ちほう‐けい【地方型】
⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】
⇒ちほう‐けいば【地方競馬】
⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】
⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】
⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】
⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】
⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】
⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】
⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】
⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】
⇒ちほう‐さい【地方債】
⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】
⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】
⇒ちほう‐し【地方史】
⇒ちほう‐し【地方紙】
⇒ちほう‐じ【地方時】
⇒ちほう‐じち【地方自治】
⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】
⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】
⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】
⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】
⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】
⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】
⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】
⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】
⇒ちほう‐しょく【地方色】
⇒ちほう‐ぜい【地方税】
⇒ちほう‐せいど【地方制度】
⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】
⇒ちほう‐たい【地方隊】
⇒ちほう‐だんたい【地方団体】
⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】
⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】
⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】
⇒ちほう‐ばん【地方版】
⇒ちほう‐びょう【地方病】
⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】
⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】
⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】
⇒ちほう‐ほういん【地方法院】
⇒ちほう‐みんかい【地方民会】
⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】
⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】
ち‐ほう【治邦】‥ハウ
国を治めること。治まっている国。
ち‐ほう【痴呆】
いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態。ふつう感情面・意欲面の低下をも伴う。脳の腫瘍・炎症、中毒・血液循環障害また、加齢などに由来。アルツハイマー病の類。認知症。
ち‐ぼう【地貌】‥バウ
地表面の形状、すなわち高低・起伏・斜面などの状態。
ち‐ぼう【知謀・智謀】
ちえのあるはかりごと。巧みなはかりごと。太平記29「暫時の―事成りしかば」。「―をめぐらす」
ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥
日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン
明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥
明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ
その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ
地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きしょうだい【地方気象台】‥ハウ‥シヤウ‥
各府県に1カ所ずつと、北海道・沖縄では地理的に考慮された支庁に1カ所ずつ設置されている気象台。管区気象台の業務指導・予報指示を受け、区域内の測候所の管理業務を行う。国際空港には別に航空地方気象台がある。→管区気象台。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥
地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥
①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。
②国の地方行政官庁が行う国の行政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン
地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】‥ハウギヤウ‥クワンチヤウ
(→)地方官庁に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン
権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ
普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐く【地方区】‥ハウ‥
参議院議員選挙で、地方(都道府県など)を単位として設定された選挙区。1983年、比例代表制の導入により選挙区と改称。→全国区。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥
同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】‥ハウ‥ヰン
都道府県の職員である警察官。→地方警務官。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥
地方自治体などが主催する競馬。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン
国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】‥ハウ‥チヤウ
地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。→検察庁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ
地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥
国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥
地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ
仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥
基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン
地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥
地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥
地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥
下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方史】‥ハウ‥
地域社会の歴史。過去における地域社会の発展を研究し、それが一国の歴史、世界の歴史の発展とどのような関係をもつかを明らかにし、地域社会が当面する諸問題について理解を深めようとするもの。→郷土史。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥
限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じ【地方時】‥ハウ‥
その地の子午線を基準として定めた時刻。→標準時。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥
地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥
地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じちたい【地方自治体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ
日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン
特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じむしょ【地方事務所】‥ハウ‥
(→)支庁に同じ。沿革上名称を異にする。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ
各地を興行してまわること。巡業。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥
都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥
国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥
その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥
地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥
地方行政の組織・権限などに関する制度。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐せんきょ【地方選挙】‥ハウ‥
(→)一般選挙に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥
海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐だんたい【地方団体】‥ハウ‥
(→)地方公共団体に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン
明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ
一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐はいふぜい【地方配付税】‥ハウ‥
(→)配付税に同じ。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥
中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ
一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥
(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥
地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】‥ハウ‥
旧制で、いったん国税の形式によって課徴した地方税を一定の基準で地方団体に還元または配分交付した税。1948年廃止。→配付税。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン
旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ
明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥
防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。
⇒ち‐ほう【地方】
ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】‥ハウラウ‥ヰヰンクワイ
都道府県に置かれる労働委員会。使用者・労働者・公益をそれぞれ代表する委員から成り、都道府県知事が任命する。略称、地労委。→労働委員会
⇒ち‐ほう【地方】
チボー【J. Thibaud】
⇒ティボー
チボーけのひとびと【チボー家の人々】
(Les Thibault フランス)マルタン=デュ=ガールの大河小説。1922〜40年刊。
チボーデ【Albert Thibaudet】
フランスの文芸批評家。マラルメとベルクソンの影響のもとに、該博な学識、精緻な分析、みずみずしい感性がとけあった批評を書いた。著「マラルメの詩」「ギュスタヴ=フロベール」「近代フランス文学史」など。(1874〜1936)
ちぼちぼ
①飛沫のとび散るさま、細雨の降るさま。また、小さな芽などの生ずるさま。〈日葡辞書〉
②小さなこと。日葡辞書「チボチボシタコト」
ちぼ・ゆ
〔自下二〕
小声でほえる。小声で鳴く。俚言集覧「ち吠ほゆる、奴詞也」
チマ【裳】
(朝鮮語ch‘ima)朝鮮の民族服。女性が用いる、スカートに似た胸からくるぶしまでの丈の裳も。上着のチョゴリと共に着用する。
チマーゼ【Zymase ドイツ】
糖類からアルコールと炭酸ガスとをつくる酵素系。1897年、アルコール発酵に関与する酵母中にドイツの生化学者ブフナーが発見・命名。
ちまうチマフ
動詞連用形につづく「…てしまう」の約。話し言葉で使う。「…でしまう」のときは「じまう」になる。「行っ―」「死んじまう」
ち‐まき【粽・茅巻】
①(古く茅ちがやの葉で巻いたからいう)端午の節句に食べる糯米もちごめ粉・粳米うるちまい粉・葛粉などで作った餅。長円錐形に固めて笹や真菰まこもなどの葉で巻き、藺草いぐさで縛って蒸したもの。中国では汨羅べきらに投身した屈原の忌日が5月5日なので、その姉が弟を弔うために、当日餅を江に投じて虬竜きゅうりょうを祀ったのに始まるという。〈[季]夏〉。伊勢物語「人のもとよりかざり―おこせたりする返事に」
②〔建〕柱の上下の、次第に円みをもってすぼまった部分。鎌倉時代より始まった禅宗建築に多い手法。粽形。
⇒ちまき‐うま【粽馬】
⇒ちまき‐がた【粽形】
⇒ちまき‐ざさ【粽笹】
ち‐まき【千巻】
織機の部分品で、織られた織物を巻き取るための木製の円棒。
ちまき‐うま【粽馬】
茅ちがやまたは菰こもを巻いて馬の形につくった玩具。端午に子供がもてあそんだ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐がた【粽形】
〔建〕(→)「ちまき」2に同じ。
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ちまき‐ざさ【粽笹】
ササの一種。山地に自生。稈かんは高さ1.5メートル、まばらに分枝し、葉は広く大きく、短い柄で茎の先に5〜9片を掌状につける。葉は粽を包むのに用いる。クマイザサ。クスザサ。
チマキザサ
撮影:関戸 勇
 ⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ち‐また【岐・巷・衢】
(「道股ちまた」の意)
①道の分かれる所。わかれみち。つじ。万葉集12「海石榴市つばいちの八十やその―に立ち平ならし」
②町の中の道路。街路。また、繁華な通り。今昔物語集7「門の内の南北に大きなる一つの―あり」
③ところ。場所。「修羅しゅらの―」
④世間。「―の声」
⇒ちまた‐の‐かみ【岐の神】
ちまた‐の‐かみ【岐の神】
①道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神。道祖神。さえのかみ。神代紀下「衢神ちまたのかみ」
②(天孫降臨の時、天の八衢やちまたに迎えて先導したからいう)猿田彦神の異称。
⇒ち‐また【岐・巷・衢】
ちまち‐だ【千町田】
(「千町もある田」の意)ひろい田。
ちま‐ちま
小さくまとまっているさま。ちんまり。こぢんまり。「―した家」「―とした顔」
ち‐まつり【血祭】
(昔中国で、出陣の際いけにえを殺し、その血をもって軍神を祀ったことから)
①戦場に臨む際に、縁起のため、間諜かんちょうまたは敵方の者などを殺すこと。また戦場などで、最初に敵を討ち取ること。〈日葡辞書〉。「―に上げる」
②狩人が猪や鹿を射とめたときに行う祭。→ふくまるまつり
ち‐まど・う【血惑ふ】‥マドフ
〔自四〕
取り乱す。逆上して狂乱の状態になる。血まよう。〈日葡辞書〉
ち‐まなこ【血眼】
①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」
②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」
チマブーエ【Giovanni Cimabue】
イタリアの画家。イタリア‐ビザンチン風の古い伝統様式を守った最後の人。ジョットの師。作「サンタ‐トリニタの荘厳の聖母」(フィレンツェ)など。(1240以後〜1302)
ち‐まぶれ【血塗れ】
(→)「ちまみれ」に同じ。南総里見八犬伝28「地上に樹たてたる小刀こだちを抜とり、閃ひらりと見せてとり直し―序ついでにこの刃で」
ち‐まみれ【血塗れ】
血にまみれること。一面に血で染まること。ちだらけ。ちみどろ。「―のシャツ」
ち‐まめ【血豆】
指などを強く挟んだり打ったりして圧迫した時にできる、豆状の血腫けっしゅ。
ち‐まよ・う【血迷う】‥マヨフ
〔自五〕
逆上して正常な判断力を失う。のぼせあがる。「何を―・っているのか」
ちま・る
〔自四〕
(上代東国方言)とまる。万葉集20「筑紫の崎に―・り居て」
チマローザ【Domenico Cimarosa】
イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。歌劇「秘密の結婚」など。(1749〜1801)
ち‐まん【遅慢】
おそいこと。のろいこと。
ち‐み【血身】
血族。ちみち。
ち‐み【地味】
①作物栽培についての、地質の良否の状態。「―が肥えている」
②土地に産する物。特に、米。じみ。
ち‐み【魑魅】
[史記五帝本紀](「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神)山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。
ち‐みち
(「ちみうち(血身内)」の略)血族。親類。
ち‐みち【血道】
血の通う道。血脈。
⇒血道をあげる
⇒ち‐まき【粽・茅巻】
ち‐また【岐・巷・衢】
(「道股ちまた」の意)
①道の分かれる所。わかれみち。つじ。万葉集12「海石榴市つばいちの八十やその―に立ち平ならし」
②町の中の道路。街路。また、繁華な通り。今昔物語集7「門の内の南北に大きなる一つの―あり」
③ところ。場所。「修羅しゅらの―」
④世間。「―の声」
⇒ちまた‐の‐かみ【岐の神】
ちまた‐の‐かみ【岐の神】
①道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神。道祖神。さえのかみ。神代紀下「衢神ちまたのかみ」
②(天孫降臨の時、天の八衢やちまたに迎えて先導したからいう)猿田彦神の異称。
⇒ち‐また【岐・巷・衢】
ちまち‐だ【千町田】
(「千町もある田」の意)ひろい田。
ちま‐ちま
小さくまとまっているさま。ちんまり。こぢんまり。「―した家」「―とした顔」
ち‐まつり【血祭】
(昔中国で、出陣の際いけにえを殺し、その血をもって軍神を祀ったことから)
①戦場に臨む際に、縁起のため、間諜かんちょうまたは敵方の者などを殺すこと。また戦場などで、最初に敵を討ち取ること。〈日葡辞書〉。「―に上げる」
②狩人が猪や鹿を射とめたときに行う祭。→ふくまるまつり
ち‐まど・う【血惑ふ】‥マドフ
〔自四〕
取り乱す。逆上して狂乱の状態になる。血まよう。〈日葡辞書〉
ち‐まなこ【血眼】
①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」
②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」
チマブーエ【Giovanni Cimabue】
イタリアの画家。イタリア‐ビザンチン風の古い伝統様式を守った最後の人。ジョットの師。作「サンタ‐トリニタの荘厳の聖母」(フィレンツェ)など。(1240以後〜1302)
ち‐まぶれ【血塗れ】
(→)「ちまみれ」に同じ。南総里見八犬伝28「地上に樹たてたる小刀こだちを抜とり、閃ひらりと見せてとり直し―序ついでにこの刃で」
ち‐まみれ【血塗れ】
血にまみれること。一面に血で染まること。ちだらけ。ちみどろ。「―のシャツ」
ち‐まめ【血豆】
指などを強く挟んだり打ったりして圧迫した時にできる、豆状の血腫けっしゅ。
ち‐まよ・う【血迷う】‥マヨフ
〔自五〕
逆上して正常な判断力を失う。のぼせあがる。「何を―・っているのか」
ちま・る
〔自四〕
(上代東国方言)とまる。万葉集20「筑紫の崎に―・り居て」
チマローザ【Domenico Cimarosa】
イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。歌劇「秘密の結婚」など。(1749〜1801)
ち‐まん【遅慢】
おそいこと。のろいこと。
ち‐み【血身】
血族。ちみち。
ち‐み【地味】
①作物栽培についての、地質の良否の状態。「―が肥えている」
②土地に産する物。特に、米。じみ。
ち‐み【魑魅】
[史記五帝本紀](「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神)山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。
ち‐みち
(「ちみうち(血身内)」の略)血族。親類。
ち‐みち【血道】
血の通う道。血脈。
⇒血道をあげる
ち‐ば・む【血ばむ】🔗⭐🔉
ち‐ば・む【血ばむ】
〔自五〕
血がにじむ。血を帯びる。
ち‐びき【血引】🔗⭐🔉
ち‐びき【血引】
沿岸魚、ハチビキの別称。
ち‐まなこ【血眼】🔗⭐🔉
ち‐まなこ【血眼】
①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」
②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」
ち‐みどろ【血みどろ】🔗⭐🔉
ち‐みどろ【血みどろ】
血まみれ。また、苦闘するさまのたとえ。「―の争い」
⇒ちみどろ‐ちんがい【血みどろちんがい】
ちみどろ‐ちんがい【血みどろちんがい】🔗⭐🔉
ちみどろ‐ちんがい【血みどろちんがい】
「ちみどろ」を強めていう語。浄瑠璃、博多小女郎波枕「耳殺ぐ鼻劓そぐ―追払ふ」
⇒ち‐みどろ【血みどろ】
ち‐め【血眼】🔗⭐🔉
ち‐め【血眼】
病気や逆上のため、充血した眼。今昔物語集23「目はすり赤めたるにやあらむ、―にみなして」
○血も涙もないちもなみだもない🔗⭐🔉
○血も涙もないちもなみだもない
人間味に欠けて冷酷である。「―仕打ち」
⇒ち【血】
ち‐もらい【乳貰い】‥モラヒ
(→)「ちちもらい」に同じ。
ち‐もり【道守】
①道路を守るもの。神代紀上「泉道守者よもつちもりびと」↔山守。
②道路をめぐって非違をいましめた人。敵の様子などをうかがいあるく人。〈倭名類聚鈔10〉
ち‐もり【地守】
⇒じもり
ち‐もん【地文】
(チブンとも)大地の模様。大地の状態。山川・丘陵・池沢など。
⇒ちもん‐がく【地文学】
⇒ちもん‐こうほう【地文航法】
ち‐もん【智門】
仏・菩薩の持つ徳のうち、菩提ぼだいを望み求める面。↔悲門
ちもん‐がく【地文学】
地球と他の天体との関係、地球を包む気圏・水圏および地球上に起こる諸現象などについて研究する学問。現在ではあまり使われない。↔天文学。
⇒ち‐もん【地文】
ちもん‐こうほう【地文航法】‥カウハフ
地上の物標によって船舶・航空機の位置を求めて行う航法。
⇒ち‐もん【地文】
ちゃ【茶】
(慣用音。漢音はタ、唐音はサ)
①ツバキ科の常緑低木。中国南西部の温・熱帯原産。葉は長楕円形で厚く表面に光沢があり、10月頃葉腋に白花を開く。多くの変種がある。果実は扁円形で、開花の翌秋に成熟し、通常3個の種子がある。木の芽。「茶の花」は〈[季]冬〉。「―を摘む」
ちゃ
 チャ(花)
撮影:関戸 勇
チャ(花)
撮影:関戸 勇
 チャ(実)
撮影:関戸 勇
チャ(実)
撮影:関戸 勇
 ②茶の若葉を採取して製した飲料。若葉を蒸しこれを冷却してさらに焙いって製する。若葉採取の時期は4月頃に始まるが、その遅速によって一番茶・二番茶・三番茶の別がある。湯を注いで用いるのを煎茶といい、粉にして湯にまぜて用いるのを抹茶または碾ひき茶という。なお、広義には焙ほうじ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称。茗。〈日葡辞書〉。「―を飲む」
③抹茶を立てること。点茶。茶の湯。「お―を習う」
④茶色の略。
⑤いいかげんなことを言うこと。からかうこと。ちゃかすこと。黄表紙、御存商売物「相応に―を言ふて置きけるゆゑ、絵そらごとといひ初めしなり」。「―を言う」
→御茶
⇒茶にする
⇒茶を立てる
ちゃあ
「ては」の約。話し言葉で使う。ちゃ。「泣いていてばかりい―、わからない」
チャージ【charge】
①充電。蓄電。
②自動車などに燃料油を入れること。
③料金。負担。「テーブル‐―」
④電荷。荷電。
⑤ラグビー・サッカーなどで、相手方の動きをおさえ、球を奪ったりする激しい動作。→チャージング。
⑥ゴルフで、先行する選手をはげしく追うこと。「首位に猛―をかける」
チャーシャワン【炸蝦丸】
(中国語)中国料理。えび団子のフライ。
チャーシュー【叉焼】
(広東音)下味をつけてから炉で焼いた豚肉。やきぶた。
⇒チャーシュー‐メン【叉焼麺】
チャーシュー‐メン【叉焼麺】
(広東音)スープを調味し、ゆでた中華麺を入れ、チャーシューの薄切りを具とした汁そば。
⇒チャーシュー【叉焼】
チャージング【charging】
バスケット‐ボール・アイス‐ホッケー・サッカーなどで、不当に相手方にぶつかったり跳びついたりすること。反則となる。チャージ。
チャーター【charter】
乗物を借りきること。「船を―する」「―契約」
チャーダーエフ【Petr Yakovlevich Chaadaev】
ロシアの急進的思想家・哲学者。主著「哲学書簡」で農奴制に鋭い批判を加えた。(1794〜1856)
チャーチ【church】
キリスト教の教会。教会堂。聖堂。
チャーチル【Winston Churchill】
イギリスの政治家。初め保守党ついで自由党に入り商相・内相を歴任、第一次大戦時の海相・軍需相、戦後陸相・植民相。のち保守党に復帰して蔵相。金本位制に復帰。第二次大戦には首相として指導力を発揮、連合国の勝利に貢献。戦後再び首相。著「世界の危機」「第二次大戦回顧録」など。ノーベル文学賞。(1874〜1965)
チャーチル
提供:ullstein bild/APL
②茶の若葉を採取して製した飲料。若葉を蒸しこれを冷却してさらに焙いって製する。若葉採取の時期は4月頃に始まるが、その遅速によって一番茶・二番茶・三番茶の別がある。湯を注いで用いるのを煎茶といい、粉にして湯にまぜて用いるのを抹茶または碾ひき茶という。なお、広義には焙ほうじ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称。茗。〈日葡辞書〉。「―を飲む」
③抹茶を立てること。点茶。茶の湯。「お―を習う」
④茶色の略。
⑤いいかげんなことを言うこと。からかうこと。ちゃかすこと。黄表紙、御存商売物「相応に―を言ふて置きけるゆゑ、絵そらごとといひ初めしなり」。「―を言う」
→御茶
⇒茶にする
⇒茶を立てる
ちゃあ
「ては」の約。話し言葉で使う。ちゃ。「泣いていてばかりい―、わからない」
チャージ【charge】
①充電。蓄電。
②自動車などに燃料油を入れること。
③料金。負担。「テーブル‐―」
④電荷。荷電。
⑤ラグビー・サッカーなどで、相手方の動きをおさえ、球を奪ったりする激しい動作。→チャージング。
⑥ゴルフで、先行する選手をはげしく追うこと。「首位に猛―をかける」
チャーシャワン【炸蝦丸】
(中国語)中国料理。えび団子のフライ。
チャーシュー【叉焼】
(広東音)下味をつけてから炉で焼いた豚肉。やきぶた。
⇒チャーシュー‐メン【叉焼麺】
チャーシュー‐メン【叉焼麺】
(広東音)スープを調味し、ゆでた中華麺を入れ、チャーシューの薄切りを具とした汁そば。
⇒チャーシュー【叉焼】
チャージング【charging】
バスケット‐ボール・アイス‐ホッケー・サッカーなどで、不当に相手方にぶつかったり跳びついたりすること。反則となる。チャージ。
チャーター【charter】
乗物を借りきること。「船を―する」「―契約」
チャーダーエフ【Petr Yakovlevich Chaadaev】
ロシアの急進的思想家・哲学者。主著「哲学書簡」で農奴制に鋭い批判を加えた。(1794〜1856)
チャーチ【church】
キリスト教の教会。教会堂。聖堂。
チャーチル【Winston Churchill】
イギリスの政治家。初め保守党ついで自由党に入り商相・内相を歴任、第一次大戦時の海相・軍需相、戦後陸相・植民相。のち保守党に復帰して蔵相。金本位制に復帰。第二次大戦には首相として指導力を発揮、連合国の勝利に貢献。戦後再び首相。著「世界の危機」「第二次大戦回顧録」など。ノーベル文学賞。(1874〜1965)
チャーチル
提供:ullstein bild/APL
 チャーティスト‐うんどう【チャーティスト運動】
(その綱領の宣言書「人民憲章」(People's Charter)に基づく)1836〜48年労働者階級を主体として行われたイギリスの政治運動。憲章に掲げた普通選挙権獲得を主な目的として大規模に展開したが、不成功。指導者はオコンナーやラヴェット(W. Lovett1800〜1877)ら。チャーティズム。
チャーティズム【Chartism】
チャーティスト運動のこと。
チャート【chart】
①海図。地図。天気図。
②図表。一覧表。「フロー‐―」
③ヒット‐チャートのこと。
チャート【chert】
珪質の堆積岩の一種。きめこまかで非常に固い。獣角状の光沢があり、赤褐色または薄黒いものが多い。層状チャートは、放散虫遺骸や珪質海綿の骨針が深海底に堆積し固結してできたもの。角岩。
チャート
撮影:斎藤靖二
チャーティスト‐うんどう【チャーティスト運動】
(その綱領の宣言書「人民憲章」(People's Charter)に基づく)1836〜48年労働者階級を主体として行われたイギリスの政治運動。憲章に掲げた普通選挙権獲得を主な目的として大規模に展開したが、不成功。指導者はオコンナーやラヴェット(W. Lovett1800〜1877)ら。チャーティズム。
チャーティズム【Chartism】
チャーティスト運動のこと。
チャート【chart】
①海図。地図。天気図。
②図表。一覧表。「フロー‐―」
③ヒット‐チャートのこと。
チャート【chert】
珪質の堆積岩の一種。きめこまかで非常に固い。獣角状の光沢があり、赤褐色または薄黒いものが多い。層状チャートは、放散虫遺骸や珪質海綿の骨針が深海底に堆積し固結してできたもの。角岩。
チャート
撮影:斎藤靖二
 チャーハン【炒飯】
(中国語)中国料理。米飯を油でいため、肉・卵・野菜などを混ぜあわせたもの。やきめし。
チャービル【chervil】
(フランス語ではセルフィーユ)セリ科の香草。パセリに似るがより繊細な風味を持つ。フランス料理で広く用いられる。
チャーミング【charming】
魅力のあるさま。人の心をひきつけるさま。魅力的。魅惑的。
チャーム【charm】
人の心をひきつけること。魅惑。
⇒チャーム‐ポイント
チャーム‐ポイント
(和製語charm point)人の心をひきつける魅力的なところ。「彼女の―は目だ」
⇒チャーム【charm】
チャールズ【Charles】
(英語の男子名。ドイツ語のカール、フランス語のシャルル、イタリア語のカルロ、スペイン語のカルロスに当たる)イギリス王。
①(1世)ジェームズ1世の子。議会としばしば抗争、1628年権利請願を受諾はしたが、以後11年間議会を召集せず、40年に長期議会と衝突、内乱となり、議会軍に敗れ、裁判の結果処刑。(1600〜1649)→清教徒革命。
②(2世)1の子。クロムウェル時代にフランスに亡命、1660年王政復古とともに即位。次第に専制に傾き、旧教の復活を図って議会と対立。名誉革命の一因を作った。(1630〜1685)
チャールストン【Charleston】
ダンスの一種。アメリカ南部の町チャールストンから起こり、第一次大戦後、流行。爪先を内側に向け、膝から下を側方に強く蹴って踊る。
チャイ【cāy ヒンディー・çay トルコ】
(「茶」の意)インド・中央アジア・中近東で飲む紅茶。水や牛乳で煮出し、香味料などを入れる。
チャイコフスキー【Petr Il'ich Chaikovskii】
ロシアの作曲家。作風はドイツ‐ロマン派音楽の系統をひくとともに、情熱・感傷・憂鬱などのスラヴ的特性を示す。交響曲「悲愴」、バレエ音楽「白鳥の湖」「くるみ割り人形」、歌劇「エヴゲニー=オネーギン」など。(1840〜1893)
チャイコフスキー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
チャーハン【炒飯】
(中国語)中国料理。米飯を油でいため、肉・卵・野菜などを混ぜあわせたもの。やきめし。
チャービル【chervil】
(フランス語ではセルフィーユ)セリ科の香草。パセリに似るがより繊細な風味を持つ。フランス料理で広く用いられる。
チャーミング【charming】
魅力のあるさま。人の心をひきつけるさま。魅力的。魅惑的。
チャーム【charm】
人の心をひきつけること。魅惑。
⇒チャーム‐ポイント
チャーム‐ポイント
(和製語charm point)人の心をひきつける魅力的なところ。「彼女の―は目だ」
⇒チャーム【charm】
チャールズ【Charles】
(英語の男子名。ドイツ語のカール、フランス語のシャルル、イタリア語のカルロ、スペイン語のカルロスに当たる)イギリス王。
①(1世)ジェームズ1世の子。議会としばしば抗争、1628年権利請願を受諾はしたが、以後11年間議会を召集せず、40年に長期議会と衝突、内乱となり、議会軍に敗れ、裁判の結果処刑。(1600〜1649)→清教徒革命。
②(2世)1の子。クロムウェル時代にフランスに亡命、1660年王政復古とともに即位。次第に専制に傾き、旧教の復活を図って議会と対立。名誉革命の一因を作った。(1630〜1685)
チャールストン【Charleston】
ダンスの一種。アメリカ南部の町チャールストンから起こり、第一次大戦後、流行。爪先を内側に向け、膝から下を側方に強く蹴って踊る。
チャイ【cāy ヒンディー・çay トルコ】
(「茶」の意)インド・中央アジア・中近東で飲む紅茶。水や牛乳で煮出し、香味料などを入れる。
チャイコフスキー【Petr Il'ich Chaikovskii】
ロシアの作曲家。作風はドイツ‐ロマン派音楽の系統をひくとともに、情熱・感傷・憂鬱などのスラヴ的特性を示す。交響曲「悲愴」、バレエ音楽「白鳥の湖」「くるみ割り人形」、歌劇「エヴゲニー=オネーギン」など。(1840〜1893)
チャイコフスキー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →交響曲第6番「悲愴」 第二楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→バレエ音楽「白鳥の湖」ワルツ 第一幕
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→ピアノ協奏曲 第1番 第一楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
チャイナ【China】
①中国。
②(china)磁器。
⇒チャイナ‐タウン【Chinatown】
⇒チャイナ‐ドレス
チャイナ‐タウン【Chinatown】
中国人が、本国以外で形成した街区。サン‐フランシスコ・横浜にあるものなどが著名。中華街。
⇒チャイナ【China】
チャイナ‐ドレス
(和製語China dress)立襟で裾に深いスリットの入った中国風のドレス。満州族の民族衣装を元にしたもの。→チーパオ
⇒チャイナ【China】
チャイニーズ【Chinese】
中国人。中国語。中国の。
⇒チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
(→)マンダリン‐カラーに同じ。
⇒チャイニーズ【Chinese】
チャイハネ【çayhane トルコ】
(チャイは「茶」、ハネは「家」の意)トルコの喫茶店。
チャイブ【chive】
ユリ科ネギ属の香草。アサツキに似るが、より細い。ソース・サラダ・スープに添える。シブレット。
チャイム【chime】
①音階を奏するように調子をそろえた一組の鐘。→カリヨン。
②玄関や時計につけたり学校・会社で使用したりする、1に似た音を出す装置。
チャイルド【child】
子供。幼児。
⇒チャイルド‐シート
⇒チャイルド‐ロック
チャイルド【Vere Gordon Childe】
イギリスの考古学者。オーストラリア生れ。古代オリエント文明の伝播によるヨーロッパ文明の成立、人類史上の革命としての新石器時代や都市の意義を説く。著「ヨーロッパ文明の黎明」「文明の起源」など。(1892〜1957)
チャイルド‐シート
(和製語child seat)幼児を自動車に乗せるとき、安全のため座席に固定させる装置。2000年より6歳未満の幼児への装着が義務付けられた。幼児用補助装置。
⇒チャイルド【child】
チャイルド‐ロック
(和製語child lock)自動車のドアや家電製品などで、幼い子供が手を触れても操作できないようにする装置。
⇒チャイルド【child】
ちゃ‐いれ【茶入】
茶を入れておく器。抹茶用は形が小さく、濃茶のは陶器、薄茶のは漆器・木地物を用い、棗なつめ・茄子なす・肩衝かたつきなど種々の名称がある。煎茶類には錫すずまたはブリキなどでつくる。
⇒ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
(→)仕服しふくに同じ。
⇒ちゃ‐いれ【茶入】
ちゃ‐いろ【茶色】
黒みを帯びた赤黄色。
Munsell color system: 5YR3.5/4
⇒ちゃいろ・い【茶色い】
ちゃいろ・い【茶色い】
〔形〕
茶色である。「川の水が―・く濁る」
⇒ちゃ‐いろ【茶色】
チャウ【茶宇】
茶宇縞の略。浄瑠璃、傾城反魂香「二つ重の白無垢白―に縫紋」
⇒チャウ‐じま【茶宇縞】
ちゃう
「…てしまう」の約。話し言葉で使う。ちまう。「あきれ―」→じゃう
ちゃ‐うけ【茶請け】
茶を飲む時に添えて食べる菓子・漬物など。茶の子。茶菓子。点心。口取。
チャウシェスク【Nicolae Ceauşescu】
ルーマニアの政治家。1974年以来大統領。ルーマニア共産党書記長・国家評議会議長を兼任。89年の民主化運動のなかで逮捕・処刑。(1918〜1989)
チャウ‐じま【茶宇縞】
インドのチャウル(Chaul)の産で、ポルトガル人が舶来した薄地琥珀こはく織の絹。精練絹糸を用いて織ったのを本練りという。袴はかま地に用いる。日本では天和(1681〜1684)年間に京都の織工が製出。
⇒チャウ【茶宇】
ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
葉茶を碾ひいて抹茶とするのに用いる石臼。古来、京都府宇治朝日山の石を賞用。
茶臼
→交響曲第6番「悲愴」 第二楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→バレエ音楽「白鳥の湖」ワルツ 第一幕
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→ピアノ協奏曲 第1番 第一楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
チャイナ【China】
①中国。
②(china)磁器。
⇒チャイナ‐タウン【Chinatown】
⇒チャイナ‐ドレス
チャイナ‐タウン【Chinatown】
中国人が、本国以外で形成した街区。サン‐フランシスコ・横浜にあるものなどが著名。中華街。
⇒チャイナ【China】
チャイナ‐ドレス
(和製語China dress)立襟で裾に深いスリットの入った中国風のドレス。満州族の民族衣装を元にしたもの。→チーパオ
⇒チャイナ【China】
チャイニーズ【Chinese】
中国人。中国語。中国の。
⇒チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
(→)マンダリン‐カラーに同じ。
⇒チャイニーズ【Chinese】
チャイハネ【çayhane トルコ】
(チャイは「茶」、ハネは「家」の意)トルコの喫茶店。
チャイブ【chive】
ユリ科ネギ属の香草。アサツキに似るが、より細い。ソース・サラダ・スープに添える。シブレット。
チャイム【chime】
①音階を奏するように調子をそろえた一組の鐘。→カリヨン。
②玄関や時計につけたり学校・会社で使用したりする、1に似た音を出す装置。
チャイルド【child】
子供。幼児。
⇒チャイルド‐シート
⇒チャイルド‐ロック
チャイルド【Vere Gordon Childe】
イギリスの考古学者。オーストラリア生れ。古代オリエント文明の伝播によるヨーロッパ文明の成立、人類史上の革命としての新石器時代や都市の意義を説く。著「ヨーロッパ文明の黎明」「文明の起源」など。(1892〜1957)
チャイルド‐シート
(和製語child seat)幼児を自動車に乗せるとき、安全のため座席に固定させる装置。2000年より6歳未満の幼児への装着が義務付けられた。幼児用補助装置。
⇒チャイルド【child】
チャイルド‐ロック
(和製語child lock)自動車のドアや家電製品などで、幼い子供が手を触れても操作できないようにする装置。
⇒チャイルド【child】
ちゃ‐いれ【茶入】
茶を入れておく器。抹茶用は形が小さく、濃茶のは陶器、薄茶のは漆器・木地物を用い、棗なつめ・茄子なす・肩衝かたつきなど種々の名称がある。煎茶類には錫すずまたはブリキなどでつくる。
⇒ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
(→)仕服しふくに同じ。
⇒ちゃ‐いれ【茶入】
ちゃ‐いろ【茶色】
黒みを帯びた赤黄色。
Munsell color system: 5YR3.5/4
⇒ちゃいろ・い【茶色い】
ちゃいろ・い【茶色い】
〔形〕
茶色である。「川の水が―・く濁る」
⇒ちゃ‐いろ【茶色】
チャウ【茶宇】
茶宇縞の略。浄瑠璃、傾城反魂香「二つ重の白無垢白―に縫紋」
⇒チャウ‐じま【茶宇縞】
ちゃう
「…てしまう」の約。話し言葉で使う。ちまう。「あきれ―」→じゃう
ちゃ‐うけ【茶請け】
茶を飲む時に添えて食べる菓子・漬物など。茶の子。茶菓子。点心。口取。
チャウシェスク【Nicolae Ceauşescu】
ルーマニアの政治家。1974年以来大統領。ルーマニア共産党書記長・国家評議会議長を兼任。89年の民主化運動のなかで逮捕・処刑。(1918〜1989)
チャウ‐じま【茶宇縞】
インドのチャウル(Chaul)の産で、ポルトガル人が舶来した薄地琥珀こはく織の絹。精練絹糸を用いて織ったのを本練りという。袴はかま地に用いる。日本では天和(1681〜1684)年間に京都の織工が製出。
⇒チャウ【茶宇】
ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
葉茶を碾ひいて抹茶とするのに用いる石臼。古来、京都府宇治朝日山の石を賞用。
茶臼
 茶臼・茶碾
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
茶臼・茶碾
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒ちゃうす‐げい【茶臼芸】
ちゃうす‐げい【茶臼芸】
①一芸にすぐれていること。
②(後に誤って)中途半端で一芸として通らないもの。表芸にならないもの。石臼芸。浮世床初「いはば―で一種ひといろも本業にならねへ」
⇒ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
ちゃうす‐やま【茶臼山】
大阪市天王寺区、天王寺公園の北東部、慶沢園内にある丘。昔の荒陵あらはかの地。1614年(慶長19)大坂冬の陣に徳川家康が本陣を置き、翌年の夏の陣に真田幸村がここで戦没。
茶臼山
撮影:的場 啓
⇒ちゃうす‐げい【茶臼芸】
ちゃうす‐げい【茶臼芸】
①一芸にすぐれていること。
②(後に誤って)中途半端で一芸として通らないもの。表芸にならないもの。石臼芸。浮世床初「いはば―で一種ひといろも本業にならねへ」
⇒ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
ちゃうす‐やま【茶臼山】
大阪市天王寺区、天王寺公園の北東部、慶沢園内にある丘。昔の荒陵あらはかの地。1614年(慶長19)大坂冬の陣に徳川家康が本陣を置き、翌年の夏の陣に真田幸村がここで戦没。
茶臼山
撮影:的場 啓
 チャウダー【chowder】
魚介類を主に野菜などを加えて煮込んだアメリカ風のスープ。「クラム‐―」
チャウ‐チャウ【chow-chow】
イヌの一品種。大形で、体高は40〜50センチメートル、毛色は黒から茶。耳は小さく顔は幅広く、毛が豊か。巻き尾。中国原産で、食肉とされた。イギリスで改良され、現在は愛玩用。
チャウチャウ
チャウダー【chowder】
魚介類を主に野菜などを加えて煮込んだアメリカ風のスープ。「クラム‐―」
チャウ‐チャウ【chow-chow】
イヌの一品種。大形で、体高は40〜50センチメートル、毛色は黒から茶。耳は小さく顔は幅広く、毛が豊か。巻き尾。中国原産で、食肉とされた。イギリスで改良され、現在は愛玩用。
チャウチャウ
 ちゃ‐えん【茶園】‥ヱン
①茶の木を栽培している園。ちゃばたけ。
②茶を売る店。
チャオ【炒】
(中国語)中国料理で、油でいためること。
チャオ【ciao イタリア】
(親しい間柄で用いる挨拶語)「おはよう」「こんにちは」「さようなら」などを兼ねる語。
チャオズ【餃子】
(中国語)
⇒ギョーザ
チャオ‐プラヤ【Chao Phraya】
メナムの正式名称。
ちゃおんど【茶音頭】
地歌・箏曲。京風手事物。菊岡検校作曲。八重崎検校箏手付。横井也有作詞の地歌「女手前」の文句をもとに、茶の湯の用語を綴って末永い仲を願う。茶の湯音頭。
ちゃ‐か【茶菓】‥クワ
茶と菓子。さか。
ちゃ‐か【茶課】‥クワ
中国で、宋・元・明代に行われた茶の販売税。
ちゃ‐かい【茶会】‥クワイ
客を招き、作法にのっとって茶を供する集まり。茶の会。茶事。茶の湯。さかい。
⇒ちゃかい‐き【茶会記】
ちゃかい‐き【茶会記】‥クワイ‥
茶会の記録。茶会の日時・場所・参会者・道具・懐石の料理・菓子に至るまで明細に記す。主催者側が記録する自会記と参会者が書き残す他会記とがある。
⇒ちゃ‐かい【茶会】
ちゃ‐かいせき【茶懐石】‥クワイ‥
(→)懐石に同じ。
ちゃ‐がえし【茶返し】‥ガヘシ
衣の表裏とも茶色であること。浮世風呂3「あひ着はずつと―の比翼で」
ちゃ‐がけ【茶掛】
(茶掛幅の略)茶席にかける掛物の称。
ちゃ‐かご【茶籠】
茶器を入れるかご。
ちゃ‐がし【茶菓子】‥グワ‥
茶に添えて出す菓子。茶うけの菓子。茶の子。
ちゃ‐かす【茶滓】
(→)茶殻ちゃがらに同じ。
ちゃ‐か・す
〔他五〕
(「茶化す」と当て字)
①冗談にしてしまう。ひやかす。からかう。茶にする。根無草後編「人を―・し」。「まじめな話を―・す」
②冗談のようにして、はぐらかす。ごまかす。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「十貫目といふ敷銀をあの女めに―・さりよか」。「うまく―・してその場をきりぬける」
ちゃ‐かた【茶方】
①茶の湯の方式。茶道。
②茶道にたずさわる人。茶道家。
チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ジンギス汗の次子。兄のジュチ、弟のオゴタイらとともに父に従って金国を討ち、さらにホラズムなど西域諸国を侵略、西遼(カラキタイ)の故地とアムール地方を領有。チャガタイ‐ハン国を建設。(在位1227〜1242)( 〜1242)
⇒チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
モンゴル四ハン国の一つ。チャガタイとその子孫の領国。都はアルマリク(阿力麻里)、所領はイリ河流域からチュー河流域に及ぶ。14世紀半ば東西両部に分裂。西部はティムール帝国に併呑され、東部は17世紀頃まで存続。チャガタイ‐ウルス。(1227〜 )→モンゴル帝国
⇒チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ちゃか‐ちゃか
①器械や金属片・陶片などが小刻みに動く音。「荷台の瓶が―と鳴る」
②動作や態度に落着きがなく軽率に見えるさま。「―と動き回る」「―した人」
ちゃ‐かっしょく【茶褐色】
やや黒みを帯びた茶色。とびいろ。
Munsell color system: 2.5YR3/4
ちゃかつ‐やく【茶褐薬】
(→)トリニトロ‐トルエンに同じ。
ちゃ‐がのこ【茶鹿の子】
茶色の鹿の子絞り。
ちゃ‐かぶき【茶香服・茶歌舞伎】
茶道の七事式の一つ。数種の茶を味わい、後で種類を言いあてる。
ちゃ‐がま【茶釜】
茶の湯または茶を煮出すのに用いる釜。上部がすぼまって口が狭く、鍔つばがある。鉄・真鍮しんちゅうなどで製する。
ちゃ‐がゆ【茶粥】
茶の煎じ汁または茶袋を入れて炊いた粥。入れ茶粥。
⇒ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
①茶粥をすすって間に合わせた腹。
②(朝食などに茶粥を多く用いるからいう)畿内の人をあざけっていう語。
⇒ちゃ‐がゆ【茶粥】
ちゃ‐がら【茶殻】
茶を煎じた残りかす。茶滓ちゃかす。
ちゃ‐がわり【茶代り】‥ガハリ
茶の代金。狂言、薩摩守「―を置いて行かしませ」
チャガン‐ド【慈江道】
(Chagang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年、平安北道から分離して設けられた。道都は江界。北は鴨緑江を隔てて中国と接する。大部分が山岳地帯で、主に畑作が行われる。→朝鮮(図)
ちゃ‐き【茶気】
①茶道の気。また、その心得。
②浮世ばなれした気質。変人の気質。
③人をちゃかす気質。茶目気。
ちゃ‐き【茶器】
広義には、茶の湯道具一般の総称。普通には、薄茶用の容器のこと。
ちゃ‐ぎ【茶技】
茶道の技術。
ちゃき‐ちゃき
(「嫡々ちゃくちゃく」の転)
①嫡流。正統。生粋きっすい。本場もの。「―の江戸っ子」
②仲間の中で、はぶりのよいもの。はばきき。「若手の中の―」
ちゃきょう【茶経】‥キヤウ
茶書。唐の陸羽の著。760年頃成立。3巻。茶の歴史・製法・器具について記述した最古の書。
ちゃ‐ぎょう【茶業】‥ゲフ
茶の製造または販売の業。
ちゃ‐きん【茶巾】
点茶の際、茶碗をぬぐうのに用いる麻の布。また、炭手前で釜をぬぐうのにも使う。
⇒ちゃきん‐いも【茶巾薯】
⇒ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
⇒ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
⇒ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
⇒ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
⇒ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
⇒ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
ちゃ‐ぎん【茶衣】
(熊本県で)婚礼の日に婿方で用意しておく嫁の晴着。
ちゃきん‐いも【茶巾薯】
蒸したサツマイモをすりつぶし、砂糖・塩などで味をつけ、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
茶の湯で、茶巾の扱い方。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
蒸したりゆでたりしてすりつぶした材料を、茶巾(または布巾)に包んで絞り、絞り目をつけたもの。サツマイモ・ユリネ・クリ・アズキなどを用いる。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
薄焼玉子で五目鮨を包み、干瓢かんぴょうなどでゆわえたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
茶巾を入れる筒。巾筒。陶磁器製・金属製・竹製などがある。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
砂金包さきんづつみの訛。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
蒸したユリネをつぶして調味し、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃく【笛】
ふえ。てき。沙石集6「簫、―、琴、箜篗くご」
ちゃく【着】
(呉音はジャク)
①ゆきつくこと。
②囲碁で石をうつこと。
③衣服を数える語。
④到着の順序を数える語。「3―まで入賞」
→ちょ(著)
ちゃく【嫡】
(呉音。漢音はテキ)
①本妻。正妻。
②本妻の生んだ子。あとつぎの子。
③正統。直系。
ちゃ‐ぐ【茶具】
茶道具。茶器。
ちゃく‐い【着衣】
衣服を着ること。また、着た衣服。ちゃくえ。
⇒ちゃくい‐えい【着衣泳】
⇒ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】
ちゃく‐い【着意】
①心をとどめること。気をつけること。
②心に思いついた考え。着想。
ちゃく・い
〔形〕
ずるい。こすい。
ちゃくい‐えい【着衣泳】
水難事故の際などに、衣服をつけたまま泳ぐこと。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】‥イハヒ
産児に初めてうぶぎを着せる祝い。うぶぎのいわい。ちゃくえ。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃく‐え【着衣】
①⇒ちゃくい。
②(→)「着衣ちゃくいの祝」に同じ。
ちゃく‐えき【着駅】
汽車・電車などの到着先の駅。「―払い」↔発駅
ちゃく‐か【嫡家】
⇒ちゃっけ
ちゃく‐がん【着岸】
岸に着くこと。
ちゃく‐がん【着眼】
物事をしたり考えたりするために、特定のところに目をつけること。その目のつけかた。また、目のつけどころ。着目。「いいところに―した」
⇒ちゃくがん‐てん【着眼点】
ちゃくがん‐てん【着眼点】
目のつけどころ。
⇒ちゃく‐がん【着眼】
ちゃく‐ぎょ【着御】
①天皇などが席または目的地につくことの尊敬語。↔発御はつぎょ。
②天皇などが衣服を着けることの尊敬語。お召しになること。
ちゃく‐ざ【着座】
①座につくこと。すわること。
②公卿が任官して、太政官庁・外記庁げきのちょうの座に着く儀式。
ちゃく‐さい【嫡妻】
本妻。正妻。嫡室。むかいめ。
ちゃく‐し【嫡子】
①嫡妻の子で家督を相続するもの。また一般に、跡つぎとなる子。よつぎ。
②嫡出の長子。嫡男。
③嫡出子。↔庶子
ちゃく‐し【嫡嗣】
嫡出の嗣子しし。
ちゃく‐じ【着時】
①到着の時刻。
②即時。すぐ。日葡辞書「チャクジニスル」
ちゃく‐しつ【嫡室】
嫡妻。本妻。正室。
ちゃく‐じつ【着実】
態度が、おちついて軽率でないこと。また、物事があぶなげなく行われること。「―な気風」「―に業績を伸ばす」
ちゃく‐しゅ【着手】
①手をつけること。とりかかること。しはじめ。「研究に―する」
②〔法〕(「著手」とも書く)犯罪の実行の開始、すなわち犯罪構成要件の一部分が実現されたこと。窃盗犯で、金品を物色する行為をはじめたときなど。実行の着手の有無により未遂と予備・陰謀とに区別される。
ちゃく‐しゅ【搩手・
ちゃ‐えん【茶園】‥ヱン
①茶の木を栽培している園。ちゃばたけ。
②茶を売る店。
チャオ【炒】
(中国語)中国料理で、油でいためること。
チャオ【ciao イタリア】
(親しい間柄で用いる挨拶語)「おはよう」「こんにちは」「さようなら」などを兼ねる語。
チャオズ【餃子】
(中国語)
⇒ギョーザ
チャオ‐プラヤ【Chao Phraya】
メナムの正式名称。
ちゃおんど【茶音頭】
地歌・箏曲。京風手事物。菊岡検校作曲。八重崎検校箏手付。横井也有作詞の地歌「女手前」の文句をもとに、茶の湯の用語を綴って末永い仲を願う。茶の湯音頭。
ちゃ‐か【茶菓】‥クワ
茶と菓子。さか。
ちゃ‐か【茶課】‥クワ
中国で、宋・元・明代に行われた茶の販売税。
ちゃ‐かい【茶会】‥クワイ
客を招き、作法にのっとって茶を供する集まり。茶の会。茶事。茶の湯。さかい。
⇒ちゃかい‐き【茶会記】
ちゃかい‐き【茶会記】‥クワイ‥
茶会の記録。茶会の日時・場所・参会者・道具・懐石の料理・菓子に至るまで明細に記す。主催者側が記録する自会記と参会者が書き残す他会記とがある。
⇒ちゃ‐かい【茶会】
ちゃ‐かいせき【茶懐石】‥クワイ‥
(→)懐石に同じ。
ちゃ‐がえし【茶返し】‥ガヘシ
衣の表裏とも茶色であること。浮世風呂3「あひ着はずつと―の比翼で」
ちゃ‐がけ【茶掛】
(茶掛幅の略)茶席にかける掛物の称。
ちゃ‐かご【茶籠】
茶器を入れるかご。
ちゃ‐がし【茶菓子】‥グワ‥
茶に添えて出す菓子。茶うけの菓子。茶の子。
ちゃ‐かす【茶滓】
(→)茶殻ちゃがらに同じ。
ちゃ‐か・す
〔他五〕
(「茶化す」と当て字)
①冗談にしてしまう。ひやかす。からかう。茶にする。根無草後編「人を―・し」。「まじめな話を―・す」
②冗談のようにして、はぐらかす。ごまかす。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「十貫目といふ敷銀をあの女めに―・さりよか」。「うまく―・してその場をきりぬける」
ちゃ‐かた【茶方】
①茶の湯の方式。茶道。
②茶道にたずさわる人。茶道家。
チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ジンギス汗の次子。兄のジュチ、弟のオゴタイらとともに父に従って金国を討ち、さらにホラズムなど西域諸国を侵略、西遼(カラキタイ)の故地とアムール地方を領有。チャガタイ‐ハン国を建設。(在位1227〜1242)( 〜1242)
⇒チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
モンゴル四ハン国の一つ。チャガタイとその子孫の領国。都はアルマリク(阿力麻里)、所領はイリ河流域からチュー河流域に及ぶ。14世紀半ば東西両部に分裂。西部はティムール帝国に併呑され、東部は17世紀頃まで存続。チャガタイ‐ウルス。(1227〜 )→モンゴル帝国
⇒チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ちゃか‐ちゃか
①器械や金属片・陶片などが小刻みに動く音。「荷台の瓶が―と鳴る」
②動作や態度に落着きがなく軽率に見えるさま。「―と動き回る」「―した人」
ちゃ‐かっしょく【茶褐色】
やや黒みを帯びた茶色。とびいろ。
Munsell color system: 2.5YR3/4
ちゃかつ‐やく【茶褐薬】
(→)トリニトロ‐トルエンに同じ。
ちゃ‐がのこ【茶鹿の子】
茶色の鹿の子絞り。
ちゃ‐かぶき【茶香服・茶歌舞伎】
茶道の七事式の一つ。数種の茶を味わい、後で種類を言いあてる。
ちゃ‐がま【茶釜】
茶の湯または茶を煮出すのに用いる釜。上部がすぼまって口が狭く、鍔つばがある。鉄・真鍮しんちゅうなどで製する。
ちゃ‐がゆ【茶粥】
茶の煎じ汁または茶袋を入れて炊いた粥。入れ茶粥。
⇒ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
①茶粥をすすって間に合わせた腹。
②(朝食などに茶粥を多く用いるからいう)畿内の人をあざけっていう語。
⇒ちゃ‐がゆ【茶粥】
ちゃ‐がら【茶殻】
茶を煎じた残りかす。茶滓ちゃかす。
ちゃ‐がわり【茶代り】‥ガハリ
茶の代金。狂言、薩摩守「―を置いて行かしませ」
チャガン‐ド【慈江道】
(Chagang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年、平安北道から分離して設けられた。道都は江界。北は鴨緑江を隔てて中国と接する。大部分が山岳地帯で、主に畑作が行われる。→朝鮮(図)
ちゃ‐き【茶気】
①茶道の気。また、その心得。
②浮世ばなれした気質。変人の気質。
③人をちゃかす気質。茶目気。
ちゃ‐き【茶器】
広義には、茶の湯道具一般の総称。普通には、薄茶用の容器のこと。
ちゃ‐ぎ【茶技】
茶道の技術。
ちゃき‐ちゃき
(「嫡々ちゃくちゃく」の転)
①嫡流。正統。生粋きっすい。本場もの。「―の江戸っ子」
②仲間の中で、はぶりのよいもの。はばきき。「若手の中の―」
ちゃきょう【茶経】‥キヤウ
茶書。唐の陸羽の著。760年頃成立。3巻。茶の歴史・製法・器具について記述した最古の書。
ちゃ‐ぎょう【茶業】‥ゲフ
茶の製造または販売の業。
ちゃ‐きん【茶巾】
点茶の際、茶碗をぬぐうのに用いる麻の布。また、炭手前で釜をぬぐうのにも使う。
⇒ちゃきん‐いも【茶巾薯】
⇒ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
⇒ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
⇒ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
⇒ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
⇒ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
⇒ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
ちゃ‐ぎん【茶衣】
(熊本県で)婚礼の日に婿方で用意しておく嫁の晴着。
ちゃきん‐いも【茶巾薯】
蒸したサツマイモをすりつぶし、砂糖・塩などで味をつけ、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
茶の湯で、茶巾の扱い方。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
蒸したりゆでたりしてすりつぶした材料を、茶巾(または布巾)に包んで絞り、絞り目をつけたもの。サツマイモ・ユリネ・クリ・アズキなどを用いる。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
薄焼玉子で五目鮨を包み、干瓢かんぴょうなどでゆわえたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
茶巾を入れる筒。巾筒。陶磁器製・金属製・竹製などがある。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
砂金包さきんづつみの訛。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
蒸したユリネをつぶして調味し、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃく【笛】
ふえ。てき。沙石集6「簫、―、琴、箜篗くご」
ちゃく【着】
(呉音はジャク)
①ゆきつくこと。
②囲碁で石をうつこと。
③衣服を数える語。
④到着の順序を数える語。「3―まで入賞」
→ちょ(著)
ちゃく【嫡】
(呉音。漢音はテキ)
①本妻。正妻。
②本妻の生んだ子。あとつぎの子。
③正統。直系。
ちゃ‐ぐ【茶具】
茶道具。茶器。
ちゃく‐い【着衣】
衣服を着ること。また、着た衣服。ちゃくえ。
⇒ちゃくい‐えい【着衣泳】
⇒ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】
ちゃく‐い【着意】
①心をとどめること。気をつけること。
②心に思いついた考え。着想。
ちゃく・い
〔形〕
ずるい。こすい。
ちゃくい‐えい【着衣泳】
水難事故の際などに、衣服をつけたまま泳ぐこと。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】‥イハヒ
産児に初めてうぶぎを着せる祝い。うぶぎのいわい。ちゃくえ。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃく‐え【着衣】
①⇒ちゃくい。
②(→)「着衣ちゃくいの祝」に同じ。
ちゃく‐えき【着駅】
汽車・電車などの到着先の駅。「―払い」↔発駅
ちゃく‐か【嫡家】
⇒ちゃっけ
ちゃく‐がん【着岸】
岸に着くこと。
ちゃく‐がん【着眼】
物事をしたり考えたりするために、特定のところに目をつけること。その目のつけかた。また、目のつけどころ。着目。「いいところに―した」
⇒ちゃくがん‐てん【着眼点】
ちゃくがん‐てん【着眼点】
目のつけどころ。
⇒ちゃく‐がん【着眼】
ちゃく‐ぎょ【着御】
①天皇などが席または目的地につくことの尊敬語。↔発御はつぎょ。
②天皇などが衣服を着けることの尊敬語。お召しになること。
ちゃく‐ざ【着座】
①座につくこと。すわること。
②公卿が任官して、太政官庁・外記庁げきのちょうの座に着く儀式。
ちゃく‐さい【嫡妻】
本妻。正妻。嫡室。むかいめ。
ちゃく‐し【嫡子】
①嫡妻の子で家督を相続するもの。また一般に、跡つぎとなる子。よつぎ。
②嫡出の長子。嫡男。
③嫡出子。↔庶子
ちゃく‐し【嫡嗣】
嫡出の嗣子しし。
ちゃく‐じ【着時】
①到着の時刻。
②即時。すぐ。日葡辞書「チャクジニスル」
ちゃく‐しつ【嫡室】
嫡妻。本妻。正室。
ちゃく‐じつ【着実】
態度が、おちついて軽率でないこと。また、物事があぶなげなく行われること。「―な気風」「―に業績を伸ばす」
ちゃく‐しゅ【着手】
①手をつけること。とりかかること。しはじめ。「研究に―する」
②〔法〕(「著手」とも書く)犯罪の実行の開始、すなわち犯罪構成要件の一部分が実現されたこと。窃盗犯で、金品を物色する行為をはじめたときなど。実行の着手の有無により未遂と予備・陰謀とに区別される。
ちゃく‐しゅ【搩手・ 手】
手の親指と中指をいっぱいに伸ばすこと。また、伸ばした長さ。仏像の高さをはかるのに用いる。1搩手は8寸(約24.5センチメートル)(異説もある)。平家物語1「一―半の薬師」
ちゃく‐しゅう【着臭】‥シウ
においを付けること。特に、無臭のガスなどににおいを付けて嗅ぎ取れるようにすること。
ちゃく‐しゅつ【嫡出】
正妻からの出生。法律上有効な婚姻をした夫婦間の出生。正出。↔庶出。
⇒ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
正妻から出生した子。法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子。
⇒ちゃく‐しゅつ【嫡出】
ちゃく‐じゅん【着順】
競走などで目標地点への到着順序。「―判定」
ちゃく‐しょ【嫡庶】
嫡出と庶出。また、嫡子と庶子。ちゃくそ。
ちゃく‐じょ【嫡女】‥ヂヨ
正妻の生んだ長女。
ちゃく‐しょう【着床】‥シヤウ
受精卵が子宮粘膜に定着すること。妊娠のはじまり。
⇒ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】
ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】‥シヤウ‥
体外受精によって得られた4細胞期または8細胞期の受精卵から1〜2個の割球を採取して行う染色体または遺伝子の診断。
⇒ちゃく‐しょう【着床】
ちゃく‐しょく【着色】
色をつけること。いろどり。彩色。「食品に―する」「人工―料」
⇒ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
⇒ちゃくしょく‐りょう【着色料】
ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
金属酸化物などを加えて着色したガラス。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃくしょく‐りょう【着色料】‥レウ
食品添加物の一種。食品に色をつけるために用いる。天然着色料と合成着色料とがある。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃく‐しん【着心】
執着する心。執心。執念。太平記35「人間に―の深かりし咎」
ちゃく‐しん【着信】
音信の到着すること。また、その音信。受信。「―局」
⇒ちゃくしん‐おん【着信音】
ちゃく‐じん【着陣】‥ヂン
①公卿が役所の列座する席(陣の座)につくこと。
②陣所に到着すること。
ちゃくしん‐おん【着信音】
携帯電話・電子メールなどで、着信を知らせるために出される音。着音。
⇒ちゃく‐しん【着信】
ちゃく‐すい【着水】
空中から水面につくこと。特に、水上飛行機などが水面に降りつくこと。↔離水
ちゃく・する【着する・著する】
[文]着す(サ変)
[一]〔自サ変〕
①ぴったりとつく。
②いたる。とどく。到着する。古今著聞集2「舟をになひて岸に―・しけり」
③執着する。「一事に―・する」→着じゃくす。
[二]〔他サ変〕
きる。着用する。また、身につける。持つ。
ちゃく‐せい【着生】
植物が樹木・岩石などの他物に付着して生育すること。
⇒ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
樹上・石上に付着して生活する植物の総称。寄生植物と異なり養分をその相手からは摂取しない。セッコク・シノブなど。樹上植物。気生植物。
⇒ちゃく‐せい【着生】
ちゃく‐せき【着席】
座席につくこと。着座。
ちゃく‐せつ【着雪】
雪が電線や木の枝などに付着する現象。
ちゃく‐せん【着船】
船が港につくこと。また、その船。
ちゃく‐そ【嫡庶】
⇒ちゃくしょ。〈日葡辞書〉
ちゃく‐そう【着相】‥サウ
執着する状態。太平記37「―を哀む」
ちゃく‐そう【着装】‥サウ
(→)装着そうちゃくに同じ。
ちゃく‐そう【着想】‥サウ
心に浮かんだ工夫。おもいつき。「奇抜な―だ」
ちゃく‐そう【嫡宗】
①同族中の総本家。宗家。
②正系。正統。
ちゃく‐そうそん【嫡曾孫】
嫡孫の嫡子。
ちゃく‐そん【嫡孫】
嫡子の嫡子。
⇒ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
嫡孫が直接に祖父の家督を継承すること。
⇒ちゃく‐そん【嫡孫】
ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
(「釱」「鈦」は鉄木かなきで、鉄製の足かせ)律令制で、徒役ずえき中の罪人に足かせをつけたこと。ちゃくたい。「―盤枷はんか」
⇒ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
ちゃく‐たい【着帯】
妊婦が妊娠5カ月目に腹帯(岩田帯)を締めること。また、その祝いの式。
ちゃく‐たい【着釱】
⇒ちゃくだ
ちゃく‐だつ【着脱】
身につけたり脱いだりすること。その部分につけたり、はずしたりすること。「―自由」
ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
平安時代、検非違使が陰暦5月・12月に日を選んで盗犯・私鋳銭などの犯人に着鈦し笞刑ちけいを加えた行事。
⇒ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
ちゃく‐だん【着弾】
銃砲から発射した弾丸が或る地点に到達すること。「―距離」
ちゃく‐ち【着地】
①着陸。また、着陸する場所。
②体操・スキー・跳躍競技などで、床・地面に降り立つこと。
ちゃく‐ちゃく【着着】
物事が順序を追ってはかどるさま。一歩一歩。「仕事が―と進む」
ちゃく‐ちゃく【嫡嫡】
嫡子から嫡子へと家を継いで行くこと。正統の血脈。嫡流。ちゃきちゃき。
ちゃぐちゃぐ‐うまこ【チャグチャグ馬こ】
岩手県の盛岡・花巻で作られる、首に鈴をつけた木製の馬の玩具。馬の息災延命を祈願した同名の行事に由来。「チャグチャグ」は鈴の音の擬音語。
ちゃく‐ちょう【着帳】‥チヤウ
その座に参会する者の姓名を記録すること。申楽談儀「将軍家御―自筆に先管領とあそばされしより」
ちゃく‐つ【着津】
港に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐てい【嫡弟】
嫡出の弟。
ちゃく‐でん【着電】
電信の到着すること。また、その電信。
ちゃく‐でん【嫡伝】
嫡々相伝えること。正統から正統に伝えること。正統の相伝。
ちゃく‐と
〔副〕
てばやくふるまうさま。す早く。ちゃっと。好色一代女2「帥すいとおもふと―言葉に色をつけて」
ちゃく‐とう【着到】‥タウ
①到着すること。
②役所に備えつけて出勤した吏員の姓名を記入する帳簿。古今著聞集16「弁―をとりよせて、寛快がつとめ日々に不参々々と書付てけり」
③出陣の命に応じて軍勢の参着したことを書き留めること。また、着到状の略。平家物語2「小松殿には盛国承つて―つけけり」
④着到和歌の略。
⑤歌舞伎儀式音楽の一つ。座頭ざがしら俳優が楽屋入りしたのをきっかけにはやす鳴物。能管・太鼓・大太鼓を用い、今は開演30分前にはやす。
⇒ちゃくとう‐じょう【着到状】
⇒ちゃくとう‐すずり【着到硯】
⇒ちゃくとう‐でん【着到殿】
⇒ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】
⇒ちゃくとう‐わか【着到和歌】
ちゃくとう‐じょう【着到状】‥タウジヤウ
中世、出陣の命を受け、あるいは自発的に参集した武士が、馳せ参じた旨を上申した文書。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐すずり【着到硯】‥タウ‥
着到をつける時に用いる硯。受付用の硯。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐でん【着到殿】‥タウ‥
神社で、祭使の上卿以下氏人らが着到して、その氏名を記す所。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】‥タウ‥
勢揃え・馬揃えなどを主将が見るために、本城大手門脇などに設けた櫓。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐わか【着到和歌】‥タウ‥
日数と人数を限り、毎日一定数の歌題を詠む方式。多くは百日にわたって百首を詠ずること。また、その和歌。鎌倉中期以降行われた。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃく‐なん【嫡男】
嫡出の長男。嫡出の男子。
ちゃく‐に【着荷】
荷物が到着すること。また、その荷物。ちゃっか。
ちゃく‐にょ【嫡女】
嫡出の長女。〈日葡辞書〉
ちゃく‐にん【着任】
任地に到着すること。また、任務につくこと。「4月1日付で―する」↔離任
ちゃく‐はつ【着発】
①到着と出発。発着。
②弾丸などが物に当たった瞬間に爆発すること。「―信管」
ちゃく‐ばらい【着払い】‥バラヒ
郵便物や品物などの代金・送料などを受取人が支払うこと。また、その制度。
ちゃく‐ひつ【着筆】
①筆をつけること。書き始めること。
②筆のつけよう。書きかた。
ちゃく‐ひょう【着氷】
①セ氏0度以下の物体に水が衝突して凍結する現象。過冷却の雲粒が飛行機に付着する場合、波のしぶきが船に付着する場合などがある。「船体―」
②スケート競技などで、氷面に降り立つこと。
ちゃく‐ふ【着府】
国府・城下町に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐ふく【着服】
①衣服を身につけること。
②(チャクブク・チャクボクとも)ごまかしてひそかにわが物とすること。東海道中膝栗毛5「手早くかの三百文を―して」。「公金を―する」
ちゃく‐ぼ【嫡母】
(庶子からの称)父の正妻。父の嫡妻。
ちゃく‐ぼう【着帽】
帽子をかぶること。↔脱帽↔無帽
ちゃく‐ぼく【着服】
「ちゃくふく」の訛。東海道中膝栗毛4「おのがふところへ―して」
ちゃ‐くみ【茶汲み】
茶を汲むこと。茶を汲んで供すること。また、その人。「お―」
ちゃく‐メロ【着メロ】
着信メロディーの略。着信音がメロディーになっているもの。
ちゃく‐もく【着目】
気をつけて見ること。特に目をつけること。着眼。「―に価する」
ちゃく‐よう【着用】
衣服をきること。身につけること。「―に及ぶ」「シート‐ベルトを―する」
ちゃ‐くらべ【茶競べ・茶較べ】
種々の茶を飲みわけてその良し悪しを品評し合う遊戯。狂言、止動方角しどうほうがく「けふは山一つあなたへ―に参りまするが」
ちゃく‐りく【着陸】
飛行中の航空機などが陸上に降りること。↔離陸。
⇒ちゃくりく‐そうち【着陸装置】
⇒ちゃくりく‐たい【着陸帯】
⇒ちゃくりく‐とう【着陸灯】
ちゃくりく‐そうち【着陸装置】‥サウ‥
(→)降着装置に同じ。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐たい【着陸帯】
航空機が安全に離着陸できるように設備した場所。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐とう【着陸灯】
夜間または悪天候時に着陸する際、前方を照射するために航空機に装備する灯火。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくり‐ちゃ‐と
〔副〕
すぐに。さっと。
ちゃく‐りゅう【嫡流】‥リウ
総本家の家筋。正統の流派。「清和源氏の―」↔庶流
ちゃく‐りょう【着料】‥レウ
①着るもの。また、その材料とするもの。衣料。
②衣服を給する代りに与える金銭。
③黄八丈の幅の狭いもの。
ちゃく‐れん【着輦】
高貴な人の乗物が目的地に着くこと。
ちゃ‐け【茶家】
茶道にたずさわる人。また点茶を業とする人。
チャケー【cha-khe タイ】
(鰐わにの意)タイのチター属の弦楽器。3弦で11個のフレットを持つ。象牙や骨の義甲で弦をはじいて演奏する。
チャコ
(チョークの訛)服地裁断の標付しるしつけに用いるチョーク。種々の色がある。
チャコ【Chaco】
南米パラグアイ川中流部の広大な草原地帯。パラグアイ領は無人地帯だが、アルゼンチン領は綿花地帯として発展。グラン‐チャコ。
ちゃ‐こう【茶講】‥カウ
茶を飲みに集まる人々の集会。〈日葡辞書〉
ちゃ‐ごう【茶合】‥ガフ
茶器の一つ。煎茶では二つ割にした竹で作り、茶を点ずるとき、茶を移し入れてその量を見はからう。抹茶では桜で椀形に作り、茶入れに茶を入れるとき、その量を計る。
チャコール【charcoal】
堅炭。木炭もくたん。
⇒チャコール‐グレー【charcoal grey】
チャコール‐グレー【charcoal grey】
黒に近い灰色。けしずみ色。
Munsell color system: 5P3/1
⇒チャコール【charcoal】
ちゃ‐こく【茶国】
色茶屋の勤め女。茶屋女。茶屋者。浄瑠璃、生玉心中「枝は木斛もっこく我が身は―」
ちゃ‐こし【茶漉し】
煎茶を漉す道具。
ちゃ‐こぼし【茶零し】
飲み残しの湯茶や滓かすを入れ捨てる容器。
ちゃ‐こもん【茶小紋】
茶色の小紋。
ちゃ‐ざい【茶剤】
熱湯に浸出して服用する、数種の生薬を調合した薬剤。
ちゃ‐さかもり【茶酒盛り】
酒の代りに茶を用いて、ともに飲食し興じること。男色大鑑「石すゑて土がまをかけ―をはじめ」
ちゃ‐さじ【茶匙】
①茶をすくうさじ。また、茶杓ちゃしゃく。ちゃしゃじ。
②小形のさじ。ティー‐スプーン。「―一杯の砂糖」
ちゃ‐ざしき【茶座敷】
茶をたてる座敷。茶席。茶室。
ちゃさんばい【茶子味梅・茶盞拝】
狂言。唐人の夫が日本人の妻の無情を嘆き、いったんは和解して楽を舞うが、やはり唐土を恋しがる。ちゃすあんばい。
ちゃ‐し【茶師】
抹茶または葉茶を製造する人。また、それを茶壺へ詰める人。おつめ。つめ。
ちゃ‐し【茶肆】
①抹茶または葉茶を販売する店。葉茶屋。茶舗。
②茶店。
チャシ
(アイヌ語)砦とりでの意。北海道および東北諸県に500を超える遺跡が残存。地形に恵まれた丘陵の突端の一部に壕をめぐらし、上を地ならししてあるものが多い。
ちゃ‐じ【茶事】
茶道に関すること。また、茶会。
⇒ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
ちゃ‐しき【茶式】
茶道の方式。室町時代、村田珠光を祖とし、武野紹鴎じょうおうを経て、千利休に至って大成。
ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
代表的な茶会の種類で、暁の茶事・朝の茶事・正午の茶事・夜咄よばなしの茶事・不時の茶事・飯後はんごの茶事・跡見あとみの茶事の7種をいう。
⇒ちゃ‐じ【茶事】
ちゃ‐しつ【茶室】
茶会に用いる室。古くは茶湯座敷・数寄屋・囲かこいなどといい、茶室と呼ぶようになったのは江戸時代以後。4畳半を基本とし、3畳・2畳、あるいは台目畳を用いて最小1畳台目まである。4畳半以下を小間、以上を広間といい、4畳半は両方を兼ねる。茶席。
茶室
手】
手の親指と中指をいっぱいに伸ばすこと。また、伸ばした長さ。仏像の高さをはかるのに用いる。1搩手は8寸(約24.5センチメートル)(異説もある)。平家物語1「一―半の薬師」
ちゃく‐しゅう【着臭】‥シウ
においを付けること。特に、無臭のガスなどににおいを付けて嗅ぎ取れるようにすること。
ちゃく‐しゅつ【嫡出】
正妻からの出生。法律上有効な婚姻をした夫婦間の出生。正出。↔庶出。
⇒ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
正妻から出生した子。法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子。
⇒ちゃく‐しゅつ【嫡出】
ちゃく‐じゅん【着順】
競走などで目標地点への到着順序。「―判定」
ちゃく‐しょ【嫡庶】
嫡出と庶出。また、嫡子と庶子。ちゃくそ。
ちゃく‐じょ【嫡女】‥ヂヨ
正妻の生んだ長女。
ちゃく‐しょう【着床】‥シヤウ
受精卵が子宮粘膜に定着すること。妊娠のはじまり。
⇒ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】
ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】‥シヤウ‥
体外受精によって得られた4細胞期または8細胞期の受精卵から1〜2個の割球を採取して行う染色体または遺伝子の診断。
⇒ちゃく‐しょう【着床】
ちゃく‐しょく【着色】
色をつけること。いろどり。彩色。「食品に―する」「人工―料」
⇒ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
⇒ちゃくしょく‐りょう【着色料】
ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
金属酸化物などを加えて着色したガラス。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃくしょく‐りょう【着色料】‥レウ
食品添加物の一種。食品に色をつけるために用いる。天然着色料と合成着色料とがある。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃく‐しん【着心】
執着する心。執心。執念。太平記35「人間に―の深かりし咎」
ちゃく‐しん【着信】
音信の到着すること。また、その音信。受信。「―局」
⇒ちゃくしん‐おん【着信音】
ちゃく‐じん【着陣】‥ヂン
①公卿が役所の列座する席(陣の座)につくこと。
②陣所に到着すること。
ちゃくしん‐おん【着信音】
携帯電話・電子メールなどで、着信を知らせるために出される音。着音。
⇒ちゃく‐しん【着信】
ちゃく‐すい【着水】
空中から水面につくこと。特に、水上飛行機などが水面に降りつくこと。↔離水
ちゃく・する【着する・著する】
[文]着す(サ変)
[一]〔自サ変〕
①ぴったりとつく。
②いたる。とどく。到着する。古今著聞集2「舟をになひて岸に―・しけり」
③執着する。「一事に―・する」→着じゃくす。
[二]〔他サ変〕
きる。着用する。また、身につける。持つ。
ちゃく‐せい【着生】
植物が樹木・岩石などの他物に付着して生育すること。
⇒ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
樹上・石上に付着して生活する植物の総称。寄生植物と異なり養分をその相手からは摂取しない。セッコク・シノブなど。樹上植物。気生植物。
⇒ちゃく‐せい【着生】
ちゃく‐せき【着席】
座席につくこと。着座。
ちゃく‐せつ【着雪】
雪が電線や木の枝などに付着する現象。
ちゃく‐せん【着船】
船が港につくこと。また、その船。
ちゃく‐そ【嫡庶】
⇒ちゃくしょ。〈日葡辞書〉
ちゃく‐そう【着相】‥サウ
執着する状態。太平記37「―を哀む」
ちゃく‐そう【着装】‥サウ
(→)装着そうちゃくに同じ。
ちゃく‐そう【着想】‥サウ
心に浮かんだ工夫。おもいつき。「奇抜な―だ」
ちゃく‐そう【嫡宗】
①同族中の総本家。宗家。
②正系。正統。
ちゃく‐そうそん【嫡曾孫】
嫡孫の嫡子。
ちゃく‐そん【嫡孫】
嫡子の嫡子。
⇒ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
嫡孫が直接に祖父の家督を継承すること。
⇒ちゃく‐そん【嫡孫】
ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
(「釱」「鈦」は鉄木かなきで、鉄製の足かせ)律令制で、徒役ずえき中の罪人に足かせをつけたこと。ちゃくたい。「―盤枷はんか」
⇒ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
ちゃく‐たい【着帯】
妊婦が妊娠5カ月目に腹帯(岩田帯)を締めること。また、その祝いの式。
ちゃく‐たい【着釱】
⇒ちゃくだ
ちゃく‐だつ【着脱】
身につけたり脱いだりすること。その部分につけたり、はずしたりすること。「―自由」
ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
平安時代、検非違使が陰暦5月・12月に日を選んで盗犯・私鋳銭などの犯人に着鈦し笞刑ちけいを加えた行事。
⇒ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
ちゃく‐だん【着弾】
銃砲から発射した弾丸が或る地点に到達すること。「―距離」
ちゃく‐ち【着地】
①着陸。また、着陸する場所。
②体操・スキー・跳躍競技などで、床・地面に降り立つこと。
ちゃく‐ちゃく【着着】
物事が順序を追ってはかどるさま。一歩一歩。「仕事が―と進む」
ちゃく‐ちゃく【嫡嫡】
嫡子から嫡子へと家を継いで行くこと。正統の血脈。嫡流。ちゃきちゃき。
ちゃぐちゃぐ‐うまこ【チャグチャグ馬こ】
岩手県の盛岡・花巻で作られる、首に鈴をつけた木製の馬の玩具。馬の息災延命を祈願した同名の行事に由来。「チャグチャグ」は鈴の音の擬音語。
ちゃく‐ちょう【着帳】‥チヤウ
その座に参会する者の姓名を記録すること。申楽談儀「将軍家御―自筆に先管領とあそばされしより」
ちゃく‐つ【着津】
港に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐てい【嫡弟】
嫡出の弟。
ちゃく‐でん【着電】
電信の到着すること。また、その電信。
ちゃく‐でん【嫡伝】
嫡々相伝えること。正統から正統に伝えること。正統の相伝。
ちゃく‐と
〔副〕
てばやくふるまうさま。す早く。ちゃっと。好色一代女2「帥すいとおもふと―言葉に色をつけて」
ちゃく‐とう【着到】‥タウ
①到着すること。
②役所に備えつけて出勤した吏員の姓名を記入する帳簿。古今著聞集16「弁―をとりよせて、寛快がつとめ日々に不参々々と書付てけり」
③出陣の命に応じて軍勢の参着したことを書き留めること。また、着到状の略。平家物語2「小松殿には盛国承つて―つけけり」
④着到和歌の略。
⑤歌舞伎儀式音楽の一つ。座頭ざがしら俳優が楽屋入りしたのをきっかけにはやす鳴物。能管・太鼓・大太鼓を用い、今は開演30分前にはやす。
⇒ちゃくとう‐じょう【着到状】
⇒ちゃくとう‐すずり【着到硯】
⇒ちゃくとう‐でん【着到殿】
⇒ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】
⇒ちゃくとう‐わか【着到和歌】
ちゃくとう‐じょう【着到状】‥タウジヤウ
中世、出陣の命を受け、あるいは自発的に参集した武士が、馳せ参じた旨を上申した文書。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐すずり【着到硯】‥タウ‥
着到をつける時に用いる硯。受付用の硯。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐でん【着到殿】‥タウ‥
神社で、祭使の上卿以下氏人らが着到して、その氏名を記す所。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】‥タウ‥
勢揃え・馬揃えなどを主将が見るために、本城大手門脇などに設けた櫓。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐わか【着到和歌】‥タウ‥
日数と人数を限り、毎日一定数の歌題を詠む方式。多くは百日にわたって百首を詠ずること。また、その和歌。鎌倉中期以降行われた。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃく‐なん【嫡男】
嫡出の長男。嫡出の男子。
ちゃく‐に【着荷】
荷物が到着すること。また、その荷物。ちゃっか。
ちゃく‐にょ【嫡女】
嫡出の長女。〈日葡辞書〉
ちゃく‐にん【着任】
任地に到着すること。また、任務につくこと。「4月1日付で―する」↔離任
ちゃく‐はつ【着発】
①到着と出発。発着。
②弾丸などが物に当たった瞬間に爆発すること。「―信管」
ちゃく‐ばらい【着払い】‥バラヒ
郵便物や品物などの代金・送料などを受取人が支払うこと。また、その制度。
ちゃく‐ひつ【着筆】
①筆をつけること。書き始めること。
②筆のつけよう。書きかた。
ちゃく‐ひょう【着氷】
①セ氏0度以下の物体に水が衝突して凍結する現象。過冷却の雲粒が飛行機に付着する場合、波のしぶきが船に付着する場合などがある。「船体―」
②スケート競技などで、氷面に降り立つこと。
ちゃく‐ふ【着府】
国府・城下町に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐ふく【着服】
①衣服を身につけること。
②(チャクブク・チャクボクとも)ごまかしてひそかにわが物とすること。東海道中膝栗毛5「手早くかの三百文を―して」。「公金を―する」
ちゃく‐ぼ【嫡母】
(庶子からの称)父の正妻。父の嫡妻。
ちゃく‐ぼう【着帽】
帽子をかぶること。↔脱帽↔無帽
ちゃく‐ぼく【着服】
「ちゃくふく」の訛。東海道中膝栗毛4「おのがふところへ―して」
ちゃ‐くみ【茶汲み】
茶を汲むこと。茶を汲んで供すること。また、その人。「お―」
ちゃく‐メロ【着メロ】
着信メロディーの略。着信音がメロディーになっているもの。
ちゃく‐もく【着目】
気をつけて見ること。特に目をつけること。着眼。「―に価する」
ちゃく‐よう【着用】
衣服をきること。身につけること。「―に及ぶ」「シート‐ベルトを―する」
ちゃ‐くらべ【茶競べ・茶較べ】
種々の茶を飲みわけてその良し悪しを品評し合う遊戯。狂言、止動方角しどうほうがく「けふは山一つあなたへ―に参りまするが」
ちゃく‐りく【着陸】
飛行中の航空機などが陸上に降りること。↔離陸。
⇒ちゃくりく‐そうち【着陸装置】
⇒ちゃくりく‐たい【着陸帯】
⇒ちゃくりく‐とう【着陸灯】
ちゃくりく‐そうち【着陸装置】‥サウ‥
(→)降着装置に同じ。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐たい【着陸帯】
航空機が安全に離着陸できるように設備した場所。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐とう【着陸灯】
夜間または悪天候時に着陸する際、前方を照射するために航空機に装備する灯火。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくり‐ちゃ‐と
〔副〕
すぐに。さっと。
ちゃく‐りゅう【嫡流】‥リウ
総本家の家筋。正統の流派。「清和源氏の―」↔庶流
ちゃく‐りょう【着料】‥レウ
①着るもの。また、その材料とするもの。衣料。
②衣服を給する代りに与える金銭。
③黄八丈の幅の狭いもの。
ちゃく‐れん【着輦】
高貴な人の乗物が目的地に着くこと。
ちゃ‐け【茶家】
茶道にたずさわる人。また点茶を業とする人。
チャケー【cha-khe タイ】
(鰐わにの意)タイのチター属の弦楽器。3弦で11個のフレットを持つ。象牙や骨の義甲で弦をはじいて演奏する。
チャコ
(チョークの訛)服地裁断の標付しるしつけに用いるチョーク。種々の色がある。
チャコ【Chaco】
南米パラグアイ川中流部の広大な草原地帯。パラグアイ領は無人地帯だが、アルゼンチン領は綿花地帯として発展。グラン‐チャコ。
ちゃ‐こう【茶講】‥カウ
茶を飲みに集まる人々の集会。〈日葡辞書〉
ちゃ‐ごう【茶合】‥ガフ
茶器の一つ。煎茶では二つ割にした竹で作り、茶を点ずるとき、茶を移し入れてその量を見はからう。抹茶では桜で椀形に作り、茶入れに茶を入れるとき、その量を計る。
チャコール【charcoal】
堅炭。木炭もくたん。
⇒チャコール‐グレー【charcoal grey】
チャコール‐グレー【charcoal grey】
黒に近い灰色。けしずみ色。
Munsell color system: 5P3/1
⇒チャコール【charcoal】
ちゃ‐こく【茶国】
色茶屋の勤め女。茶屋女。茶屋者。浄瑠璃、生玉心中「枝は木斛もっこく我が身は―」
ちゃ‐こし【茶漉し】
煎茶を漉す道具。
ちゃ‐こぼし【茶零し】
飲み残しの湯茶や滓かすを入れ捨てる容器。
ちゃ‐こもん【茶小紋】
茶色の小紋。
ちゃ‐ざい【茶剤】
熱湯に浸出して服用する、数種の生薬を調合した薬剤。
ちゃ‐さかもり【茶酒盛り】
酒の代りに茶を用いて、ともに飲食し興じること。男色大鑑「石すゑて土がまをかけ―をはじめ」
ちゃ‐さじ【茶匙】
①茶をすくうさじ。また、茶杓ちゃしゃく。ちゃしゃじ。
②小形のさじ。ティー‐スプーン。「―一杯の砂糖」
ちゃ‐ざしき【茶座敷】
茶をたてる座敷。茶席。茶室。
ちゃさんばい【茶子味梅・茶盞拝】
狂言。唐人の夫が日本人の妻の無情を嘆き、いったんは和解して楽を舞うが、やはり唐土を恋しがる。ちゃすあんばい。
ちゃ‐し【茶師】
抹茶または葉茶を製造する人。また、それを茶壺へ詰める人。おつめ。つめ。
ちゃ‐し【茶肆】
①抹茶または葉茶を販売する店。葉茶屋。茶舗。
②茶店。
チャシ
(アイヌ語)砦とりでの意。北海道および東北諸県に500を超える遺跡が残存。地形に恵まれた丘陵の突端の一部に壕をめぐらし、上を地ならししてあるものが多い。
ちゃ‐じ【茶事】
茶道に関すること。また、茶会。
⇒ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
ちゃ‐しき【茶式】
茶道の方式。室町時代、村田珠光を祖とし、武野紹鴎じょうおうを経て、千利休に至って大成。
ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
代表的な茶会の種類で、暁の茶事・朝の茶事・正午の茶事・夜咄よばなしの茶事・不時の茶事・飯後はんごの茶事・跡見あとみの茶事の7種をいう。
⇒ちゃ‐じ【茶事】
ちゃ‐しつ【茶室】
茶会に用いる室。古くは茶湯座敷・数寄屋・囲かこいなどといい、茶室と呼ぶようになったのは江戸時代以後。4畳半を基本とし、3畳・2畳、あるいは台目畳を用いて最小1畳台目まである。4畳半以下を小間、以上を広間といい、4畳半は両方を兼ねる。茶席。
茶室
 ちゃ‐しぶ【茶渋】
茶碗などに付着する、茶の煎じ汁のあか。
ちゃ‐しゃく【茶杓】
抹茶をすくい取るさじ。竹・象牙・金属・木地・塗物で作り、珠光形・利休形などがある。ちゃさじ。
茶杓
ちゃ‐しぶ【茶渋】
茶碗などに付着する、茶の煎じ汁のあか。
ちゃ‐しゃく【茶杓】
抹茶をすくい取るさじ。竹・象牙・金属・木地・塗物で作り、珠光形・利休形などがある。ちゃさじ。
茶杓
 ちゃ‐じゅ【茶寿】
(「茶」の字を分解すると、二つの十と八十八とになるとしていう)数え年108歳。また、その祝い。
ちゃ‐じゅす【茶繻子】
茶色のしゅす。
ちゃ‐じょく【茶職】
(→)茶坊主1に同じ。
ちゃ‐しん【茶神】
茶の神として祭る中国の陸羽の像。茶の神。→茶経ちゃきょう
ちゃ‐じん【茶人】
①茶の湯を好む人。茶道に通じた人。
②変わったことを好む人。一風かわった物好き。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「おらが若旦那にほれるとは…とんだ―だ」
ちゃすあんばい【茶子味梅】
⇒ちゃさんばい
ちゃ‐せき【茶席】
茶をたてる座席。茶座敷。茶室。また、茶会。
⇒ちゃせき‐がけ【茶席掛】
ちゃせき‐がけ【茶席掛】
(→)「ちゃがけ」に同じ。
⇒ちゃ‐せき【茶席】
ちゃせご
正月14日の晩の行事。宮城県で、厄年の人はこの日7軒から餅や銭を貰い集めると厄難をのがれるといって貰いに出る。させご。→かせどり
ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
①抹茶をたてる際、茶をかきまわして泡を立たせたり練ったりする具。白竹・青竹・胡麻竹・煤竹・紫竹などを用い、10センチメートル前後の竹筒の半分以下を細く割って穂とし、穂先の末端は内に曲げるが、直なものもある。数穂・中穂・荒穂などの種類がある。〈文明本節用集〉
茶筅
ちゃ‐じゅ【茶寿】
(「茶」の字を分解すると、二つの十と八十八とになるとしていう)数え年108歳。また、その祝い。
ちゃ‐じゅす【茶繻子】
茶色のしゅす。
ちゃ‐じょく【茶職】
(→)茶坊主1に同じ。
ちゃ‐しん【茶神】
茶の神として祭る中国の陸羽の像。茶の神。→茶経ちゃきょう
ちゃ‐じん【茶人】
①茶の湯を好む人。茶道に通じた人。
②変わったことを好む人。一風かわった物好き。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「おらが若旦那にほれるとは…とんだ―だ」
ちゃすあんばい【茶子味梅】
⇒ちゃさんばい
ちゃ‐せき【茶席】
茶をたてる座席。茶座敷。茶室。また、茶会。
⇒ちゃせき‐がけ【茶席掛】
ちゃせき‐がけ【茶席掛】
(→)「ちゃがけ」に同じ。
⇒ちゃ‐せき【茶席】
ちゃせご
正月14日の晩の行事。宮城県で、厄年の人はこの日7軒から餅や銭を貰い集めると厄難をのがれるといって貰いに出る。させご。→かせどり
ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
①抹茶をたてる際、茶をかきまわして泡を立たせたり練ったりする具。白竹・青竹・胡麻竹・煤竹・紫竹などを用い、10センチメートル前後の竹筒の半分以下を細く割って穂とし、穂先の末端は内に曲げるが、直なものもある。数穂・中穂・荒穂などの種類がある。〈文明本節用集〉
茶筅
 ②近世、茶筅1を行商し、賤民視された人々の称。
③茶筅髪の略。
⇒ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
⇒ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
⇒ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
⇒ちゃせん‐し【茶筅師】
⇒ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
⇒ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
⇒ちゃせん‐たて【茶筅立】
⇒ちゃせん‐とおし【茶筅通し】
⇒ちゃせん‐ぼう【茶筅坊】
ちゃ‐ぜん【茶禅】
茶道と禅道。
⇒ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
茶道の奥義と禅道とが一致するということ。
⇒ちゃ‐ぜん【茶禅】
ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
茶道の習事の一つ。水指の蓋の上に茶巾・茶筅・茶杓をのせ、前に茶碗の中に茶入を仕組んで飾っておいて行う点前。茶碗・茶入・茶杓・水指のいずれかに由緒や伝来があるか優品である場合に行う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
①男の髪の結い方。髪を頭の百会ひゃくえの所で束ね、もとどりを糸の組緒で巻き、先をほおけさせて茶筅の形にしたもの。
茶筅髪
②近世、茶筅1を行商し、賤民視された人々の称。
③茶筅髪の略。
⇒ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
⇒ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
⇒ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
⇒ちゃせん‐し【茶筅師】
⇒ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
⇒ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
⇒ちゃせん‐たて【茶筅立】
⇒ちゃせん‐とおし【茶筅通し】
⇒ちゃせん‐ぼう【茶筅坊】
ちゃ‐ぜん【茶禅】
茶道と禅道。
⇒ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
茶道の奥義と禅道とが一致するということ。
⇒ちゃ‐ぜん【茶禅】
ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
茶道の習事の一つ。水指の蓋の上に茶巾・茶筅・茶杓をのせ、前に茶碗の中に茶入を仕組んで飾っておいて行う点前。茶碗・茶入・茶杓・水指のいずれかに由緒や伝来があるか優品である場合に行う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
①男の髪の結い方。髪を頭の百会ひゃくえの所で束ね、もとどりを糸の組緒で巻き、先をほおけさせて茶筅の形にしたもの。
茶筅髪
 ②女の髪の結い方。後家島田などの刷毛先を散らして茶筅状にしたもの。未亡人が結う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
野菜の切り方の一つ。茄子なすの表面に縦に何本か切り込みを入れて、茶筅の形に似せたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ざ【茶煎座】
(岡山地方などで)鍋座なべざのこと。
ちゃせん‐し【茶筅師】
茶筅の製造を業とする人。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
チャセンシダ科の常緑シダの総称、また、その一種。葉は束生し、古い葉柄や全体の姿が茶筅に似る。世界の暖温帯に分布。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
袖垣の一形式。竹を筋違いに組み、その上部を竪たてに編み、上端を結束せずに茶筅状にしたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐たて【茶
②女の髪の結い方。後家島田などの刷毛先を散らして茶筅状にしたもの。未亡人が結う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
野菜の切り方の一つ。茄子なすの表面に縦に何本か切り込みを入れて、茶筅の形に似せたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ざ【茶煎座】
(岡山地方などで)鍋座なべざのこと。
ちゃせん‐し【茶筅師】
茶筅の製造を業とする人。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
チャセンシダ科の常緑シダの総称、また、その一種。葉は束生し、古い葉柄や全体の姿が茶筅に似る。世界の暖温帯に分布。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
袖垣の一形式。竹を筋違いに組み、その上部を竪たてに編み、上端を結束せずに茶筅状にしたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐たて【茶
 チャ(花)
撮影:関戸 勇
チャ(花)
撮影:関戸 勇
 チャ(実)
撮影:関戸 勇
チャ(実)
撮影:関戸 勇
 ②茶の若葉を採取して製した飲料。若葉を蒸しこれを冷却してさらに焙いって製する。若葉採取の時期は4月頃に始まるが、その遅速によって一番茶・二番茶・三番茶の別がある。湯を注いで用いるのを煎茶といい、粉にして湯にまぜて用いるのを抹茶または碾ひき茶という。なお、広義には焙ほうじ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称。茗。〈日葡辞書〉。「―を飲む」
③抹茶を立てること。点茶。茶の湯。「お―を習う」
④茶色の略。
⑤いいかげんなことを言うこと。からかうこと。ちゃかすこと。黄表紙、御存商売物「相応に―を言ふて置きけるゆゑ、絵そらごとといひ初めしなり」。「―を言う」
→御茶
⇒茶にする
⇒茶を立てる
ちゃあ
「ては」の約。話し言葉で使う。ちゃ。「泣いていてばかりい―、わからない」
チャージ【charge】
①充電。蓄電。
②自動車などに燃料油を入れること。
③料金。負担。「テーブル‐―」
④電荷。荷電。
⑤ラグビー・サッカーなどで、相手方の動きをおさえ、球を奪ったりする激しい動作。→チャージング。
⑥ゴルフで、先行する選手をはげしく追うこと。「首位に猛―をかける」
チャーシャワン【炸蝦丸】
(中国語)中国料理。えび団子のフライ。
チャーシュー【叉焼】
(広東音)下味をつけてから炉で焼いた豚肉。やきぶた。
⇒チャーシュー‐メン【叉焼麺】
チャーシュー‐メン【叉焼麺】
(広東音)スープを調味し、ゆでた中華麺を入れ、チャーシューの薄切りを具とした汁そば。
⇒チャーシュー【叉焼】
チャージング【charging】
バスケット‐ボール・アイス‐ホッケー・サッカーなどで、不当に相手方にぶつかったり跳びついたりすること。反則となる。チャージ。
チャーター【charter】
乗物を借りきること。「船を―する」「―契約」
チャーダーエフ【Petr Yakovlevich Chaadaev】
ロシアの急進的思想家・哲学者。主著「哲学書簡」で農奴制に鋭い批判を加えた。(1794〜1856)
チャーチ【church】
キリスト教の教会。教会堂。聖堂。
チャーチル【Winston Churchill】
イギリスの政治家。初め保守党ついで自由党に入り商相・内相を歴任、第一次大戦時の海相・軍需相、戦後陸相・植民相。のち保守党に復帰して蔵相。金本位制に復帰。第二次大戦には首相として指導力を発揮、連合国の勝利に貢献。戦後再び首相。著「世界の危機」「第二次大戦回顧録」など。ノーベル文学賞。(1874〜1965)
チャーチル
提供:ullstein bild/APL
②茶の若葉を採取して製した飲料。若葉を蒸しこれを冷却してさらに焙いって製する。若葉採取の時期は4月頃に始まるが、その遅速によって一番茶・二番茶・三番茶の別がある。湯を注いで用いるのを煎茶といい、粉にして湯にまぜて用いるのを抹茶または碾ひき茶という。なお、広義には焙ほうじ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称。茗。〈日葡辞書〉。「―を飲む」
③抹茶を立てること。点茶。茶の湯。「お―を習う」
④茶色の略。
⑤いいかげんなことを言うこと。からかうこと。ちゃかすこと。黄表紙、御存商売物「相応に―を言ふて置きけるゆゑ、絵そらごとといひ初めしなり」。「―を言う」
→御茶
⇒茶にする
⇒茶を立てる
ちゃあ
「ては」の約。話し言葉で使う。ちゃ。「泣いていてばかりい―、わからない」
チャージ【charge】
①充電。蓄電。
②自動車などに燃料油を入れること。
③料金。負担。「テーブル‐―」
④電荷。荷電。
⑤ラグビー・サッカーなどで、相手方の動きをおさえ、球を奪ったりする激しい動作。→チャージング。
⑥ゴルフで、先行する選手をはげしく追うこと。「首位に猛―をかける」
チャーシャワン【炸蝦丸】
(中国語)中国料理。えび団子のフライ。
チャーシュー【叉焼】
(広東音)下味をつけてから炉で焼いた豚肉。やきぶた。
⇒チャーシュー‐メン【叉焼麺】
チャーシュー‐メン【叉焼麺】
(広東音)スープを調味し、ゆでた中華麺を入れ、チャーシューの薄切りを具とした汁そば。
⇒チャーシュー【叉焼】
チャージング【charging】
バスケット‐ボール・アイス‐ホッケー・サッカーなどで、不当に相手方にぶつかったり跳びついたりすること。反則となる。チャージ。
チャーター【charter】
乗物を借りきること。「船を―する」「―契約」
チャーダーエフ【Petr Yakovlevich Chaadaev】
ロシアの急進的思想家・哲学者。主著「哲学書簡」で農奴制に鋭い批判を加えた。(1794〜1856)
チャーチ【church】
キリスト教の教会。教会堂。聖堂。
チャーチル【Winston Churchill】
イギリスの政治家。初め保守党ついで自由党に入り商相・内相を歴任、第一次大戦時の海相・軍需相、戦後陸相・植民相。のち保守党に復帰して蔵相。金本位制に復帰。第二次大戦には首相として指導力を発揮、連合国の勝利に貢献。戦後再び首相。著「世界の危機」「第二次大戦回顧録」など。ノーベル文学賞。(1874〜1965)
チャーチル
提供:ullstein bild/APL
 チャーティスト‐うんどう【チャーティスト運動】
(その綱領の宣言書「人民憲章」(People's Charter)に基づく)1836〜48年労働者階級を主体として行われたイギリスの政治運動。憲章に掲げた普通選挙権獲得を主な目的として大規模に展開したが、不成功。指導者はオコンナーやラヴェット(W. Lovett1800〜1877)ら。チャーティズム。
チャーティズム【Chartism】
チャーティスト運動のこと。
チャート【chart】
①海図。地図。天気図。
②図表。一覧表。「フロー‐―」
③ヒット‐チャートのこと。
チャート【chert】
珪質の堆積岩の一種。きめこまかで非常に固い。獣角状の光沢があり、赤褐色または薄黒いものが多い。層状チャートは、放散虫遺骸や珪質海綿の骨針が深海底に堆積し固結してできたもの。角岩。
チャート
撮影:斎藤靖二
チャーティスト‐うんどう【チャーティスト運動】
(その綱領の宣言書「人民憲章」(People's Charter)に基づく)1836〜48年労働者階級を主体として行われたイギリスの政治運動。憲章に掲げた普通選挙権獲得を主な目的として大規模に展開したが、不成功。指導者はオコンナーやラヴェット(W. Lovett1800〜1877)ら。チャーティズム。
チャーティズム【Chartism】
チャーティスト運動のこと。
チャート【chart】
①海図。地図。天気図。
②図表。一覧表。「フロー‐―」
③ヒット‐チャートのこと。
チャート【chert】
珪質の堆積岩の一種。きめこまかで非常に固い。獣角状の光沢があり、赤褐色または薄黒いものが多い。層状チャートは、放散虫遺骸や珪質海綿の骨針が深海底に堆積し固結してできたもの。角岩。
チャート
撮影:斎藤靖二
 チャーハン【炒飯】
(中国語)中国料理。米飯を油でいため、肉・卵・野菜などを混ぜあわせたもの。やきめし。
チャービル【chervil】
(フランス語ではセルフィーユ)セリ科の香草。パセリに似るがより繊細な風味を持つ。フランス料理で広く用いられる。
チャーミング【charming】
魅力のあるさま。人の心をひきつけるさま。魅力的。魅惑的。
チャーム【charm】
人の心をひきつけること。魅惑。
⇒チャーム‐ポイント
チャーム‐ポイント
(和製語charm point)人の心をひきつける魅力的なところ。「彼女の―は目だ」
⇒チャーム【charm】
チャールズ【Charles】
(英語の男子名。ドイツ語のカール、フランス語のシャルル、イタリア語のカルロ、スペイン語のカルロスに当たる)イギリス王。
①(1世)ジェームズ1世の子。議会としばしば抗争、1628年権利請願を受諾はしたが、以後11年間議会を召集せず、40年に長期議会と衝突、内乱となり、議会軍に敗れ、裁判の結果処刑。(1600〜1649)→清教徒革命。
②(2世)1の子。クロムウェル時代にフランスに亡命、1660年王政復古とともに即位。次第に専制に傾き、旧教の復活を図って議会と対立。名誉革命の一因を作った。(1630〜1685)
チャールストン【Charleston】
ダンスの一種。アメリカ南部の町チャールストンから起こり、第一次大戦後、流行。爪先を内側に向け、膝から下を側方に強く蹴って踊る。
チャイ【cāy ヒンディー・çay トルコ】
(「茶」の意)インド・中央アジア・中近東で飲む紅茶。水や牛乳で煮出し、香味料などを入れる。
チャイコフスキー【Petr Il'ich Chaikovskii】
ロシアの作曲家。作風はドイツ‐ロマン派音楽の系統をひくとともに、情熱・感傷・憂鬱などのスラヴ的特性を示す。交響曲「悲愴」、バレエ音楽「白鳥の湖」「くるみ割り人形」、歌劇「エヴゲニー=オネーギン」など。(1840〜1893)
チャイコフスキー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
チャーハン【炒飯】
(中国語)中国料理。米飯を油でいため、肉・卵・野菜などを混ぜあわせたもの。やきめし。
チャービル【chervil】
(フランス語ではセルフィーユ)セリ科の香草。パセリに似るがより繊細な風味を持つ。フランス料理で広く用いられる。
チャーミング【charming】
魅力のあるさま。人の心をひきつけるさま。魅力的。魅惑的。
チャーム【charm】
人の心をひきつけること。魅惑。
⇒チャーム‐ポイント
チャーム‐ポイント
(和製語charm point)人の心をひきつける魅力的なところ。「彼女の―は目だ」
⇒チャーム【charm】
チャールズ【Charles】
(英語の男子名。ドイツ語のカール、フランス語のシャルル、イタリア語のカルロ、スペイン語のカルロスに当たる)イギリス王。
①(1世)ジェームズ1世の子。議会としばしば抗争、1628年権利請願を受諾はしたが、以後11年間議会を召集せず、40年に長期議会と衝突、内乱となり、議会軍に敗れ、裁判の結果処刑。(1600〜1649)→清教徒革命。
②(2世)1の子。クロムウェル時代にフランスに亡命、1660年王政復古とともに即位。次第に専制に傾き、旧教の復活を図って議会と対立。名誉革命の一因を作った。(1630〜1685)
チャールストン【Charleston】
ダンスの一種。アメリカ南部の町チャールストンから起こり、第一次大戦後、流行。爪先を内側に向け、膝から下を側方に強く蹴って踊る。
チャイ【cāy ヒンディー・çay トルコ】
(「茶」の意)インド・中央アジア・中近東で飲む紅茶。水や牛乳で煮出し、香味料などを入れる。
チャイコフスキー【Petr Il'ich Chaikovskii】
ロシアの作曲家。作風はドイツ‐ロマン派音楽の系統をひくとともに、情熱・感傷・憂鬱などのスラヴ的特性を示す。交響曲「悲愴」、バレエ音楽「白鳥の湖」「くるみ割り人形」、歌劇「エヴゲニー=オネーギン」など。(1840〜1893)
チャイコフスキー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →交響曲第6番「悲愴」 第二楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→バレエ音楽「白鳥の湖」ワルツ 第一幕
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→ピアノ協奏曲 第1番 第一楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
チャイナ【China】
①中国。
②(china)磁器。
⇒チャイナ‐タウン【Chinatown】
⇒チャイナ‐ドレス
チャイナ‐タウン【Chinatown】
中国人が、本国以外で形成した街区。サン‐フランシスコ・横浜にあるものなどが著名。中華街。
⇒チャイナ【China】
チャイナ‐ドレス
(和製語China dress)立襟で裾に深いスリットの入った中国風のドレス。満州族の民族衣装を元にしたもの。→チーパオ
⇒チャイナ【China】
チャイニーズ【Chinese】
中国人。中国語。中国の。
⇒チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
(→)マンダリン‐カラーに同じ。
⇒チャイニーズ【Chinese】
チャイハネ【çayhane トルコ】
(チャイは「茶」、ハネは「家」の意)トルコの喫茶店。
チャイブ【chive】
ユリ科ネギ属の香草。アサツキに似るが、より細い。ソース・サラダ・スープに添える。シブレット。
チャイム【chime】
①音階を奏するように調子をそろえた一組の鐘。→カリヨン。
②玄関や時計につけたり学校・会社で使用したりする、1に似た音を出す装置。
チャイルド【child】
子供。幼児。
⇒チャイルド‐シート
⇒チャイルド‐ロック
チャイルド【Vere Gordon Childe】
イギリスの考古学者。オーストラリア生れ。古代オリエント文明の伝播によるヨーロッパ文明の成立、人類史上の革命としての新石器時代や都市の意義を説く。著「ヨーロッパ文明の黎明」「文明の起源」など。(1892〜1957)
チャイルド‐シート
(和製語child seat)幼児を自動車に乗せるとき、安全のため座席に固定させる装置。2000年より6歳未満の幼児への装着が義務付けられた。幼児用補助装置。
⇒チャイルド【child】
チャイルド‐ロック
(和製語child lock)自動車のドアや家電製品などで、幼い子供が手を触れても操作できないようにする装置。
⇒チャイルド【child】
ちゃ‐いれ【茶入】
茶を入れておく器。抹茶用は形が小さく、濃茶のは陶器、薄茶のは漆器・木地物を用い、棗なつめ・茄子なす・肩衝かたつきなど種々の名称がある。煎茶類には錫すずまたはブリキなどでつくる。
⇒ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
(→)仕服しふくに同じ。
⇒ちゃ‐いれ【茶入】
ちゃ‐いろ【茶色】
黒みを帯びた赤黄色。
Munsell color system: 5YR3.5/4
⇒ちゃいろ・い【茶色い】
ちゃいろ・い【茶色い】
〔形〕
茶色である。「川の水が―・く濁る」
⇒ちゃ‐いろ【茶色】
チャウ【茶宇】
茶宇縞の略。浄瑠璃、傾城反魂香「二つ重の白無垢白―に縫紋」
⇒チャウ‐じま【茶宇縞】
ちゃう
「…てしまう」の約。話し言葉で使う。ちまう。「あきれ―」→じゃう
ちゃ‐うけ【茶請け】
茶を飲む時に添えて食べる菓子・漬物など。茶の子。茶菓子。点心。口取。
チャウシェスク【Nicolae Ceauşescu】
ルーマニアの政治家。1974年以来大統領。ルーマニア共産党書記長・国家評議会議長を兼任。89年の民主化運動のなかで逮捕・処刑。(1918〜1989)
チャウ‐じま【茶宇縞】
インドのチャウル(Chaul)の産で、ポルトガル人が舶来した薄地琥珀こはく織の絹。精練絹糸を用いて織ったのを本練りという。袴はかま地に用いる。日本では天和(1681〜1684)年間に京都の織工が製出。
⇒チャウ【茶宇】
ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
葉茶を碾ひいて抹茶とするのに用いる石臼。古来、京都府宇治朝日山の石を賞用。
茶臼
→交響曲第6番「悲愴」 第二楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→バレエ音楽「白鳥の湖」ワルツ 第一幕
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
→ピアノ協奏曲 第1番 第一楽章
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
チャイナ【China】
①中国。
②(china)磁器。
⇒チャイナ‐タウン【Chinatown】
⇒チャイナ‐ドレス
チャイナ‐タウン【Chinatown】
中国人が、本国以外で形成した街区。サン‐フランシスコ・横浜にあるものなどが著名。中華街。
⇒チャイナ【China】
チャイナ‐ドレス
(和製語China dress)立襟で裾に深いスリットの入った中国風のドレス。満州族の民族衣装を元にしたもの。→チーパオ
⇒チャイナ【China】
チャイニーズ【Chinese】
中国人。中国語。中国の。
⇒チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
チャイニーズ‐カラー【Chinese collar】
(→)マンダリン‐カラーに同じ。
⇒チャイニーズ【Chinese】
チャイハネ【çayhane トルコ】
(チャイは「茶」、ハネは「家」の意)トルコの喫茶店。
チャイブ【chive】
ユリ科ネギ属の香草。アサツキに似るが、より細い。ソース・サラダ・スープに添える。シブレット。
チャイム【chime】
①音階を奏するように調子をそろえた一組の鐘。→カリヨン。
②玄関や時計につけたり学校・会社で使用したりする、1に似た音を出す装置。
チャイルド【child】
子供。幼児。
⇒チャイルド‐シート
⇒チャイルド‐ロック
チャイルド【Vere Gordon Childe】
イギリスの考古学者。オーストラリア生れ。古代オリエント文明の伝播によるヨーロッパ文明の成立、人類史上の革命としての新石器時代や都市の意義を説く。著「ヨーロッパ文明の黎明」「文明の起源」など。(1892〜1957)
チャイルド‐シート
(和製語child seat)幼児を自動車に乗せるとき、安全のため座席に固定させる装置。2000年より6歳未満の幼児への装着が義務付けられた。幼児用補助装置。
⇒チャイルド【child】
チャイルド‐ロック
(和製語child lock)自動車のドアや家電製品などで、幼い子供が手を触れても操作できないようにする装置。
⇒チャイルド【child】
ちゃ‐いれ【茶入】
茶を入れておく器。抹茶用は形が小さく、濃茶のは陶器、薄茶のは漆器・木地物を用い、棗なつめ・茄子なす・肩衝かたつきなど種々の名称がある。煎茶類には錫すずまたはブリキなどでつくる。
⇒ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
ちゃいれ‐ぶくろ【茶入袋】
(→)仕服しふくに同じ。
⇒ちゃ‐いれ【茶入】
ちゃ‐いろ【茶色】
黒みを帯びた赤黄色。
Munsell color system: 5YR3.5/4
⇒ちゃいろ・い【茶色い】
ちゃいろ・い【茶色い】
〔形〕
茶色である。「川の水が―・く濁る」
⇒ちゃ‐いろ【茶色】
チャウ【茶宇】
茶宇縞の略。浄瑠璃、傾城反魂香「二つ重の白無垢白―に縫紋」
⇒チャウ‐じま【茶宇縞】
ちゃう
「…てしまう」の約。話し言葉で使う。ちまう。「あきれ―」→じゃう
ちゃ‐うけ【茶請け】
茶を飲む時に添えて食べる菓子・漬物など。茶の子。茶菓子。点心。口取。
チャウシェスク【Nicolae Ceauşescu】
ルーマニアの政治家。1974年以来大統領。ルーマニア共産党書記長・国家評議会議長を兼任。89年の民主化運動のなかで逮捕・処刑。(1918〜1989)
チャウ‐じま【茶宇縞】
インドのチャウル(Chaul)の産で、ポルトガル人が舶来した薄地琥珀こはく織の絹。精練絹糸を用いて織ったのを本練りという。袴はかま地に用いる。日本では天和(1681〜1684)年間に京都の織工が製出。
⇒チャウ【茶宇】
ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
葉茶を碾ひいて抹茶とするのに用いる石臼。古来、京都府宇治朝日山の石を賞用。
茶臼
 茶臼・茶碾
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
茶臼・茶碾
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒ちゃうす‐げい【茶臼芸】
ちゃうす‐げい【茶臼芸】
①一芸にすぐれていること。
②(後に誤って)中途半端で一芸として通らないもの。表芸にならないもの。石臼芸。浮世床初「いはば―で一種ひといろも本業にならねへ」
⇒ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
ちゃうす‐やま【茶臼山】
大阪市天王寺区、天王寺公園の北東部、慶沢園内にある丘。昔の荒陵あらはかの地。1614年(慶長19)大坂冬の陣に徳川家康が本陣を置き、翌年の夏の陣に真田幸村がここで戦没。
茶臼山
撮影:的場 啓
⇒ちゃうす‐げい【茶臼芸】
ちゃうす‐げい【茶臼芸】
①一芸にすぐれていること。
②(後に誤って)中途半端で一芸として通らないもの。表芸にならないもの。石臼芸。浮世床初「いはば―で一種ひといろも本業にならねへ」
⇒ちゃ‐うす【茶臼・茶碾】
ちゃうす‐やま【茶臼山】
大阪市天王寺区、天王寺公園の北東部、慶沢園内にある丘。昔の荒陵あらはかの地。1614年(慶長19)大坂冬の陣に徳川家康が本陣を置き、翌年の夏の陣に真田幸村がここで戦没。
茶臼山
撮影:的場 啓
 チャウダー【chowder】
魚介類を主に野菜などを加えて煮込んだアメリカ風のスープ。「クラム‐―」
チャウ‐チャウ【chow-chow】
イヌの一品種。大形で、体高は40〜50センチメートル、毛色は黒から茶。耳は小さく顔は幅広く、毛が豊か。巻き尾。中国原産で、食肉とされた。イギリスで改良され、現在は愛玩用。
チャウチャウ
チャウダー【chowder】
魚介類を主に野菜などを加えて煮込んだアメリカ風のスープ。「クラム‐―」
チャウ‐チャウ【chow-chow】
イヌの一品種。大形で、体高は40〜50センチメートル、毛色は黒から茶。耳は小さく顔は幅広く、毛が豊か。巻き尾。中国原産で、食肉とされた。イギリスで改良され、現在は愛玩用。
チャウチャウ
 ちゃ‐えん【茶園】‥ヱン
①茶の木を栽培している園。ちゃばたけ。
②茶を売る店。
チャオ【炒】
(中国語)中国料理で、油でいためること。
チャオ【ciao イタリア】
(親しい間柄で用いる挨拶語)「おはよう」「こんにちは」「さようなら」などを兼ねる語。
チャオズ【餃子】
(中国語)
⇒ギョーザ
チャオ‐プラヤ【Chao Phraya】
メナムの正式名称。
ちゃおんど【茶音頭】
地歌・箏曲。京風手事物。菊岡検校作曲。八重崎検校箏手付。横井也有作詞の地歌「女手前」の文句をもとに、茶の湯の用語を綴って末永い仲を願う。茶の湯音頭。
ちゃ‐か【茶菓】‥クワ
茶と菓子。さか。
ちゃ‐か【茶課】‥クワ
中国で、宋・元・明代に行われた茶の販売税。
ちゃ‐かい【茶会】‥クワイ
客を招き、作法にのっとって茶を供する集まり。茶の会。茶事。茶の湯。さかい。
⇒ちゃかい‐き【茶会記】
ちゃかい‐き【茶会記】‥クワイ‥
茶会の記録。茶会の日時・場所・参会者・道具・懐石の料理・菓子に至るまで明細に記す。主催者側が記録する自会記と参会者が書き残す他会記とがある。
⇒ちゃ‐かい【茶会】
ちゃ‐かいせき【茶懐石】‥クワイ‥
(→)懐石に同じ。
ちゃ‐がえし【茶返し】‥ガヘシ
衣の表裏とも茶色であること。浮世風呂3「あひ着はずつと―の比翼で」
ちゃ‐がけ【茶掛】
(茶掛幅の略)茶席にかける掛物の称。
ちゃ‐かご【茶籠】
茶器を入れるかご。
ちゃ‐がし【茶菓子】‥グワ‥
茶に添えて出す菓子。茶うけの菓子。茶の子。
ちゃ‐かす【茶滓】
(→)茶殻ちゃがらに同じ。
ちゃ‐か・す
〔他五〕
(「茶化す」と当て字)
①冗談にしてしまう。ひやかす。からかう。茶にする。根無草後編「人を―・し」。「まじめな話を―・す」
②冗談のようにして、はぐらかす。ごまかす。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「十貫目といふ敷銀をあの女めに―・さりよか」。「うまく―・してその場をきりぬける」
ちゃ‐かた【茶方】
①茶の湯の方式。茶道。
②茶道にたずさわる人。茶道家。
チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ジンギス汗の次子。兄のジュチ、弟のオゴタイらとともに父に従って金国を討ち、さらにホラズムなど西域諸国を侵略、西遼(カラキタイ)の故地とアムール地方を領有。チャガタイ‐ハン国を建設。(在位1227〜1242)( 〜1242)
⇒チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
モンゴル四ハン国の一つ。チャガタイとその子孫の領国。都はアルマリク(阿力麻里)、所領はイリ河流域からチュー河流域に及ぶ。14世紀半ば東西両部に分裂。西部はティムール帝国に併呑され、東部は17世紀頃まで存続。チャガタイ‐ウルス。(1227〜 )→モンゴル帝国
⇒チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ちゃか‐ちゃか
①器械や金属片・陶片などが小刻みに動く音。「荷台の瓶が―と鳴る」
②動作や態度に落着きがなく軽率に見えるさま。「―と動き回る」「―した人」
ちゃ‐かっしょく【茶褐色】
やや黒みを帯びた茶色。とびいろ。
Munsell color system: 2.5YR3/4
ちゃかつ‐やく【茶褐薬】
(→)トリニトロ‐トルエンに同じ。
ちゃ‐がのこ【茶鹿の子】
茶色の鹿の子絞り。
ちゃ‐かぶき【茶香服・茶歌舞伎】
茶道の七事式の一つ。数種の茶を味わい、後で種類を言いあてる。
ちゃ‐がま【茶釜】
茶の湯または茶を煮出すのに用いる釜。上部がすぼまって口が狭く、鍔つばがある。鉄・真鍮しんちゅうなどで製する。
ちゃ‐がゆ【茶粥】
茶の煎じ汁または茶袋を入れて炊いた粥。入れ茶粥。
⇒ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
①茶粥をすすって間に合わせた腹。
②(朝食などに茶粥を多く用いるからいう)畿内の人をあざけっていう語。
⇒ちゃ‐がゆ【茶粥】
ちゃ‐がら【茶殻】
茶を煎じた残りかす。茶滓ちゃかす。
ちゃ‐がわり【茶代り】‥ガハリ
茶の代金。狂言、薩摩守「―を置いて行かしませ」
チャガン‐ド【慈江道】
(Chagang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年、平安北道から分離して設けられた。道都は江界。北は鴨緑江を隔てて中国と接する。大部分が山岳地帯で、主に畑作が行われる。→朝鮮(図)
ちゃ‐き【茶気】
①茶道の気。また、その心得。
②浮世ばなれした気質。変人の気質。
③人をちゃかす気質。茶目気。
ちゃ‐き【茶器】
広義には、茶の湯道具一般の総称。普通には、薄茶用の容器のこと。
ちゃ‐ぎ【茶技】
茶道の技術。
ちゃき‐ちゃき
(「嫡々ちゃくちゃく」の転)
①嫡流。正統。生粋きっすい。本場もの。「―の江戸っ子」
②仲間の中で、はぶりのよいもの。はばきき。「若手の中の―」
ちゃきょう【茶経】‥キヤウ
茶書。唐の陸羽の著。760年頃成立。3巻。茶の歴史・製法・器具について記述した最古の書。
ちゃ‐ぎょう【茶業】‥ゲフ
茶の製造または販売の業。
ちゃ‐きん【茶巾】
点茶の際、茶碗をぬぐうのに用いる麻の布。また、炭手前で釜をぬぐうのにも使う。
⇒ちゃきん‐いも【茶巾薯】
⇒ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
⇒ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
⇒ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
⇒ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
⇒ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
⇒ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
ちゃ‐ぎん【茶衣】
(熊本県で)婚礼の日に婿方で用意しておく嫁の晴着。
ちゃきん‐いも【茶巾薯】
蒸したサツマイモをすりつぶし、砂糖・塩などで味をつけ、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
茶の湯で、茶巾の扱い方。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
蒸したりゆでたりしてすりつぶした材料を、茶巾(または布巾)に包んで絞り、絞り目をつけたもの。サツマイモ・ユリネ・クリ・アズキなどを用いる。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
薄焼玉子で五目鮨を包み、干瓢かんぴょうなどでゆわえたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
茶巾を入れる筒。巾筒。陶磁器製・金属製・竹製などがある。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
砂金包さきんづつみの訛。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
蒸したユリネをつぶして調味し、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃく【笛】
ふえ。てき。沙石集6「簫、―、琴、箜篗くご」
ちゃく【着】
(呉音はジャク)
①ゆきつくこと。
②囲碁で石をうつこと。
③衣服を数える語。
④到着の順序を数える語。「3―まで入賞」
→ちょ(著)
ちゃく【嫡】
(呉音。漢音はテキ)
①本妻。正妻。
②本妻の生んだ子。あとつぎの子。
③正統。直系。
ちゃ‐ぐ【茶具】
茶道具。茶器。
ちゃく‐い【着衣】
衣服を着ること。また、着た衣服。ちゃくえ。
⇒ちゃくい‐えい【着衣泳】
⇒ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】
ちゃく‐い【着意】
①心をとどめること。気をつけること。
②心に思いついた考え。着想。
ちゃく・い
〔形〕
ずるい。こすい。
ちゃくい‐えい【着衣泳】
水難事故の際などに、衣服をつけたまま泳ぐこと。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】‥イハヒ
産児に初めてうぶぎを着せる祝い。うぶぎのいわい。ちゃくえ。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃく‐え【着衣】
①⇒ちゃくい。
②(→)「着衣ちゃくいの祝」に同じ。
ちゃく‐えき【着駅】
汽車・電車などの到着先の駅。「―払い」↔発駅
ちゃく‐か【嫡家】
⇒ちゃっけ
ちゃく‐がん【着岸】
岸に着くこと。
ちゃく‐がん【着眼】
物事をしたり考えたりするために、特定のところに目をつけること。その目のつけかた。また、目のつけどころ。着目。「いいところに―した」
⇒ちゃくがん‐てん【着眼点】
ちゃくがん‐てん【着眼点】
目のつけどころ。
⇒ちゃく‐がん【着眼】
ちゃく‐ぎょ【着御】
①天皇などが席または目的地につくことの尊敬語。↔発御はつぎょ。
②天皇などが衣服を着けることの尊敬語。お召しになること。
ちゃく‐ざ【着座】
①座につくこと。すわること。
②公卿が任官して、太政官庁・外記庁げきのちょうの座に着く儀式。
ちゃく‐さい【嫡妻】
本妻。正妻。嫡室。むかいめ。
ちゃく‐し【嫡子】
①嫡妻の子で家督を相続するもの。また一般に、跡つぎとなる子。よつぎ。
②嫡出の長子。嫡男。
③嫡出子。↔庶子
ちゃく‐し【嫡嗣】
嫡出の嗣子しし。
ちゃく‐じ【着時】
①到着の時刻。
②即時。すぐ。日葡辞書「チャクジニスル」
ちゃく‐しつ【嫡室】
嫡妻。本妻。正室。
ちゃく‐じつ【着実】
態度が、おちついて軽率でないこと。また、物事があぶなげなく行われること。「―な気風」「―に業績を伸ばす」
ちゃく‐しゅ【着手】
①手をつけること。とりかかること。しはじめ。「研究に―する」
②〔法〕(「著手」とも書く)犯罪の実行の開始、すなわち犯罪構成要件の一部分が実現されたこと。窃盗犯で、金品を物色する行為をはじめたときなど。実行の着手の有無により未遂と予備・陰謀とに区別される。
ちゃく‐しゅ【搩手・
ちゃ‐えん【茶園】‥ヱン
①茶の木を栽培している園。ちゃばたけ。
②茶を売る店。
チャオ【炒】
(中国語)中国料理で、油でいためること。
チャオ【ciao イタリア】
(親しい間柄で用いる挨拶語)「おはよう」「こんにちは」「さようなら」などを兼ねる語。
チャオズ【餃子】
(中国語)
⇒ギョーザ
チャオ‐プラヤ【Chao Phraya】
メナムの正式名称。
ちゃおんど【茶音頭】
地歌・箏曲。京風手事物。菊岡検校作曲。八重崎検校箏手付。横井也有作詞の地歌「女手前」の文句をもとに、茶の湯の用語を綴って末永い仲を願う。茶の湯音頭。
ちゃ‐か【茶菓】‥クワ
茶と菓子。さか。
ちゃ‐か【茶課】‥クワ
中国で、宋・元・明代に行われた茶の販売税。
ちゃ‐かい【茶会】‥クワイ
客を招き、作法にのっとって茶を供する集まり。茶の会。茶事。茶の湯。さかい。
⇒ちゃかい‐き【茶会記】
ちゃかい‐き【茶会記】‥クワイ‥
茶会の記録。茶会の日時・場所・参会者・道具・懐石の料理・菓子に至るまで明細に記す。主催者側が記録する自会記と参会者が書き残す他会記とがある。
⇒ちゃ‐かい【茶会】
ちゃ‐かいせき【茶懐石】‥クワイ‥
(→)懐石に同じ。
ちゃ‐がえし【茶返し】‥ガヘシ
衣の表裏とも茶色であること。浮世風呂3「あひ着はずつと―の比翼で」
ちゃ‐がけ【茶掛】
(茶掛幅の略)茶席にかける掛物の称。
ちゃ‐かご【茶籠】
茶器を入れるかご。
ちゃ‐がし【茶菓子】‥グワ‥
茶に添えて出す菓子。茶うけの菓子。茶の子。
ちゃ‐かす【茶滓】
(→)茶殻ちゃがらに同じ。
ちゃ‐か・す
〔他五〕
(「茶化す」と当て字)
①冗談にしてしまう。ひやかす。からかう。茶にする。根無草後編「人を―・し」。「まじめな話を―・す」
②冗談のようにして、はぐらかす。ごまかす。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「十貫目といふ敷銀をあの女めに―・さりよか」。「うまく―・してその場をきりぬける」
ちゃ‐かた【茶方】
①茶の湯の方式。茶道。
②茶道にたずさわる人。茶道家。
チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ジンギス汗の次子。兄のジュチ、弟のオゴタイらとともに父に従って金国を討ち、さらにホラズムなど西域諸国を侵略、西遼(カラキタイ)の故地とアムール地方を領有。チャガタイ‐ハン国を建設。(在位1227〜1242)( 〜1242)
⇒チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
チャガタイ‐ハンこく【チャガタイ汗国】
モンゴル四ハン国の一つ。チャガタイとその子孫の領国。都はアルマリク(阿力麻里)、所領はイリ河流域からチュー河流域に及ぶ。14世紀半ば東西両部に分裂。西部はティムール帝国に併呑され、東部は17世紀頃まで存続。チャガタイ‐ウルス。(1227〜 )→モンゴル帝国
⇒チャガタイ【Chaghatai・察合台】
ちゃか‐ちゃか
①器械や金属片・陶片などが小刻みに動く音。「荷台の瓶が―と鳴る」
②動作や態度に落着きがなく軽率に見えるさま。「―と動き回る」「―した人」
ちゃ‐かっしょく【茶褐色】
やや黒みを帯びた茶色。とびいろ。
Munsell color system: 2.5YR3/4
ちゃかつ‐やく【茶褐薬】
(→)トリニトロ‐トルエンに同じ。
ちゃ‐がのこ【茶鹿の子】
茶色の鹿の子絞り。
ちゃ‐かぶき【茶香服・茶歌舞伎】
茶道の七事式の一つ。数種の茶を味わい、後で種類を言いあてる。
ちゃ‐がま【茶釜】
茶の湯または茶を煮出すのに用いる釜。上部がすぼまって口が狭く、鍔つばがある。鉄・真鍮しんちゅうなどで製する。
ちゃ‐がゆ【茶粥】
茶の煎じ汁または茶袋を入れて炊いた粥。入れ茶粥。
⇒ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
ちゃがゆ‐ばら【茶粥腹】
①茶粥をすすって間に合わせた腹。
②(朝食などに茶粥を多く用いるからいう)畿内の人をあざけっていう語。
⇒ちゃ‐がゆ【茶粥】
ちゃ‐がら【茶殻】
茶を煎じた残りかす。茶滓ちゃかす。
ちゃ‐がわり【茶代り】‥ガハリ
茶の代金。狂言、薩摩守「―を置いて行かしませ」
チャガン‐ド【慈江道】
(Chagang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年、平安北道から分離して設けられた。道都は江界。北は鴨緑江を隔てて中国と接する。大部分が山岳地帯で、主に畑作が行われる。→朝鮮(図)
ちゃ‐き【茶気】
①茶道の気。また、その心得。
②浮世ばなれした気質。変人の気質。
③人をちゃかす気質。茶目気。
ちゃ‐き【茶器】
広義には、茶の湯道具一般の総称。普通には、薄茶用の容器のこと。
ちゃ‐ぎ【茶技】
茶道の技術。
ちゃき‐ちゃき
(「嫡々ちゃくちゃく」の転)
①嫡流。正統。生粋きっすい。本場もの。「―の江戸っ子」
②仲間の中で、はぶりのよいもの。はばきき。「若手の中の―」
ちゃきょう【茶経】‥キヤウ
茶書。唐の陸羽の著。760年頃成立。3巻。茶の歴史・製法・器具について記述した最古の書。
ちゃ‐ぎょう【茶業】‥ゲフ
茶の製造または販売の業。
ちゃ‐きん【茶巾】
点茶の際、茶碗をぬぐうのに用いる麻の布。また、炭手前で釜をぬぐうのにも使う。
⇒ちゃきん‐いも【茶巾薯】
⇒ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
⇒ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
⇒ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
⇒ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
⇒ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
⇒ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
ちゃ‐ぎん【茶衣】
(熊本県で)婚礼の日に婿方で用意しておく嫁の晴着。
ちゃきん‐いも【茶巾薯】
蒸したサツマイモをすりつぶし、砂糖・塩などで味をつけ、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐さばき【茶巾捌き】
茶の湯で、茶巾の扱い方。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐しぼり【茶巾絞り】
蒸したりゆでたりしてすりつぶした材料を、茶巾(または布巾)に包んで絞り、絞り目をつけたもの。サツマイモ・ユリネ・クリ・アズキなどを用いる。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ずし【茶巾鮨】
薄焼玉子で五目鮨を包み、干瓢かんぴょうなどでゆわえたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつ【茶巾筒】
茶巾を入れる筒。巾筒。陶磁器製・金属製・竹製などがある。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐づつみ【茶巾包】
砂金包さきんづつみの訛。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃきん‐ゆり【茶巾百合】
蒸したユリネをつぶして調味し、茶巾絞りにしたもの。
⇒ちゃ‐きん【茶巾】
ちゃく【笛】
ふえ。てき。沙石集6「簫、―、琴、箜篗くご」
ちゃく【着】
(呉音はジャク)
①ゆきつくこと。
②囲碁で石をうつこと。
③衣服を数える語。
④到着の順序を数える語。「3―まで入賞」
→ちょ(著)
ちゃく【嫡】
(呉音。漢音はテキ)
①本妻。正妻。
②本妻の生んだ子。あとつぎの子。
③正統。直系。
ちゃ‐ぐ【茶具】
茶道具。茶器。
ちゃく‐い【着衣】
衣服を着ること。また、着た衣服。ちゃくえ。
⇒ちゃくい‐えい【着衣泳】
⇒ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】
ちゃく‐い【着意】
①心をとどめること。気をつけること。
②心に思いついた考え。着想。
ちゃく・い
〔形〕
ずるい。こすい。
ちゃくい‐えい【着衣泳】
水難事故の際などに、衣服をつけたまま泳ぐこと。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃくい‐の‐いわい【着衣の祝】‥イハヒ
産児に初めてうぶぎを着せる祝い。うぶぎのいわい。ちゃくえ。
⇒ちゃく‐い【着衣】
ちゃく‐え【着衣】
①⇒ちゃくい。
②(→)「着衣ちゃくいの祝」に同じ。
ちゃく‐えき【着駅】
汽車・電車などの到着先の駅。「―払い」↔発駅
ちゃく‐か【嫡家】
⇒ちゃっけ
ちゃく‐がん【着岸】
岸に着くこと。
ちゃく‐がん【着眼】
物事をしたり考えたりするために、特定のところに目をつけること。その目のつけかた。また、目のつけどころ。着目。「いいところに―した」
⇒ちゃくがん‐てん【着眼点】
ちゃくがん‐てん【着眼点】
目のつけどころ。
⇒ちゃく‐がん【着眼】
ちゃく‐ぎょ【着御】
①天皇などが席または目的地につくことの尊敬語。↔発御はつぎょ。
②天皇などが衣服を着けることの尊敬語。お召しになること。
ちゃく‐ざ【着座】
①座につくこと。すわること。
②公卿が任官して、太政官庁・外記庁げきのちょうの座に着く儀式。
ちゃく‐さい【嫡妻】
本妻。正妻。嫡室。むかいめ。
ちゃく‐し【嫡子】
①嫡妻の子で家督を相続するもの。また一般に、跡つぎとなる子。よつぎ。
②嫡出の長子。嫡男。
③嫡出子。↔庶子
ちゃく‐し【嫡嗣】
嫡出の嗣子しし。
ちゃく‐じ【着時】
①到着の時刻。
②即時。すぐ。日葡辞書「チャクジニスル」
ちゃく‐しつ【嫡室】
嫡妻。本妻。正室。
ちゃく‐じつ【着実】
態度が、おちついて軽率でないこと。また、物事があぶなげなく行われること。「―な気風」「―に業績を伸ばす」
ちゃく‐しゅ【着手】
①手をつけること。とりかかること。しはじめ。「研究に―する」
②〔法〕(「著手」とも書く)犯罪の実行の開始、すなわち犯罪構成要件の一部分が実現されたこと。窃盗犯で、金品を物色する行為をはじめたときなど。実行の着手の有無により未遂と予備・陰謀とに区別される。
ちゃく‐しゅ【搩手・ 手】
手の親指と中指をいっぱいに伸ばすこと。また、伸ばした長さ。仏像の高さをはかるのに用いる。1搩手は8寸(約24.5センチメートル)(異説もある)。平家物語1「一―半の薬師」
ちゃく‐しゅう【着臭】‥シウ
においを付けること。特に、無臭のガスなどににおいを付けて嗅ぎ取れるようにすること。
ちゃく‐しゅつ【嫡出】
正妻からの出生。法律上有効な婚姻をした夫婦間の出生。正出。↔庶出。
⇒ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
正妻から出生した子。法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子。
⇒ちゃく‐しゅつ【嫡出】
ちゃく‐じゅん【着順】
競走などで目標地点への到着順序。「―判定」
ちゃく‐しょ【嫡庶】
嫡出と庶出。また、嫡子と庶子。ちゃくそ。
ちゃく‐じょ【嫡女】‥ヂヨ
正妻の生んだ長女。
ちゃく‐しょう【着床】‥シヤウ
受精卵が子宮粘膜に定着すること。妊娠のはじまり。
⇒ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】
ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】‥シヤウ‥
体外受精によって得られた4細胞期または8細胞期の受精卵から1〜2個の割球を採取して行う染色体または遺伝子の診断。
⇒ちゃく‐しょう【着床】
ちゃく‐しょく【着色】
色をつけること。いろどり。彩色。「食品に―する」「人工―料」
⇒ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
⇒ちゃくしょく‐りょう【着色料】
ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
金属酸化物などを加えて着色したガラス。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃくしょく‐りょう【着色料】‥レウ
食品添加物の一種。食品に色をつけるために用いる。天然着色料と合成着色料とがある。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃく‐しん【着心】
執着する心。執心。執念。太平記35「人間に―の深かりし咎」
ちゃく‐しん【着信】
音信の到着すること。また、その音信。受信。「―局」
⇒ちゃくしん‐おん【着信音】
ちゃく‐じん【着陣】‥ヂン
①公卿が役所の列座する席(陣の座)につくこと。
②陣所に到着すること。
ちゃくしん‐おん【着信音】
携帯電話・電子メールなどで、着信を知らせるために出される音。着音。
⇒ちゃく‐しん【着信】
ちゃく‐すい【着水】
空中から水面につくこと。特に、水上飛行機などが水面に降りつくこと。↔離水
ちゃく・する【着する・著する】
[文]着す(サ変)
[一]〔自サ変〕
①ぴったりとつく。
②いたる。とどく。到着する。古今著聞集2「舟をになひて岸に―・しけり」
③執着する。「一事に―・する」→着じゃくす。
[二]〔他サ変〕
きる。着用する。また、身につける。持つ。
ちゃく‐せい【着生】
植物が樹木・岩石などの他物に付着して生育すること。
⇒ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
樹上・石上に付着して生活する植物の総称。寄生植物と異なり養分をその相手からは摂取しない。セッコク・シノブなど。樹上植物。気生植物。
⇒ちゃく‐せい【着生】
ちゃく‐せき【着席】
座席につくこと。着座。
ちゃく‐せつ【着雪】
雪が電線や木の枝などに付着する現象。
ちゃく‐せん【着船】
船が港につくこと。また、その船。
ちゃく‐そ【嫡庶】
⇒ちゃくしょ。〈日葡辞書〉
ちゃく‐そう【着相】‥サウ
執着する状態。太平記37「―を哀む」
ちゃく‐そう【着装】‥サウ
(→)装着そうちゃくに同じ。
ちゃく‐そう【着想】‥サウ
心に浮かんだ工夫。おもいつき。「奇抜な―だ」
ちゃく‐そう【嫡宗】
①同族中の総本家。宗家。
②正系。正統。
ちゃく‐そうそん【嫡曾孫】
嫡孫の嫡子。
ちゃく‐そん【嫡孫】
嫡子の嫡子。
⇒ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
嫡孫が直接に祖父の家督を継承すること。
⇒ちゃく‐そん【嫡孫】
ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
(「釱」「鈦」は鉄木かなきで、鉄製の足かせ)律令制で、徒役ずえき中の罪人に足かせをつけたこと。ちゃくたい。「―盤枷はんか」
⇒ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
ちゃく‐たい【着帯】
妊婦が妊娠5カ月目に腹帯(岩田帯)を締めること。また、その祝いの式。
ちゃく‐たい【着釱】
⇒ちゃくだ
ちゃく‐だつ【着脱】
身につけたり脱いだりすること。その部分につけたり、はずしたりすること。「―自由」
ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
平安時代、検非違使が陰暦5月・12月に日を選んで盗犯・私鋳銭などの犯人に着鈦し笞刑ちけいを加えた行事。
⇒ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
ちゃく‐だん【着弾】
銃砲から発射した弾丸が或る地点に到達すること。「―距離」
ちゃく‐ち【着地】
①着陸。また、着陸する場所。
②体操・スキー・跳躍競技などで、床・地面に降り立つこと。
ちゃく‐ちゃく【着着】
物事が順序を追ってはかどるさま。一歩一歩。「仕事が―と進む」
ちゃく‐ちゃく【嫡嫡】
嫡子から嫡子へと家を継いで行くこと。正統の血脈。嫡流。ちゃきちゃき。
ちゃぐちゃぐ‐うまこ【チャグチャグ馬こ】
岩手県の盛岡・花巻で作られる、首に鈴をつけた木製の馬の玩具。馬の息災延命を祈願した同名の行事に由来。「チャグチャグ」は鈴の音の擬音語。
ちゃく‐ちょう【着帳】‥チヤウ
その座に参会する者の姓名を記録すること。申楽談儀「将軍家御―自筆に先管領とあそばされしより」
ちゃく‐つ【着津】
港に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐てい【嫡弟】
嫡出の弟。
ちゃく‐でん【着電】
電信の到着すること。また、その電信。
ちゃく‐でん【嫡伝】
嫡々相伝えること。正統から正統に伝えること。正統の相伝。
ちゃく‐と
〔副〕
てばやくふるまうさま。す早く。ちゃっと。好色一代女2「帥すいとおもふと―言葉に色をつけて」
ちゃく‐とう【着到】‥タウ
①到着すること。
②役所に備えつけて出勤した吏員の姓名を記入する帳簿。古今著聞集16「弁―をとりよせて、寛快がつとめ日々に不参々々と書付てけり」
③出陣の命に応じて軍勢の参着したことを書き留めること。また、着到状の略。平家物語2「小松殿には盛国承つて―つけけり」
④着到和歌の略。
⑤歌舞伎儀式音楽の一つ。座頭ざがしら俳優が楽屋入りしたのをきっかけにはやす鳴物。能管・太鼓・大太鼓を用い、今は開演30分前にはやす。
⇒ちゃくとう‐じょう【着到状】
⇒ちゃくとう‐すずり【着到硯】
⇒ちゃくとう‐でん【着到殿】
⇒ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】
⇒ちゃくとう‐わか【着到和歌】
ちゃくとう‐じょう【着到状】‥タウジヤウ
中世、出陣の命を受け、あるいは自発的に参集した武士が、馳せ参じた旨を上申した文書。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐すずり【着到硯】‥タウ‥
着到をつける時に用いる硯。受付用の硯。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐でん【着到殿】‥タウ‥
神社で、祭使の上卿以下氏人らが着到して、その氏名を記す所。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】‥タウ‥
勢揃え・馬揃えなどを主将が見るために、本城大手門脇などに設けた櫓。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐わか【着到和歌】‥タウ‥
日数と人数を限り、毎日一定数の歌題を詠む方式。多くは百日にわたって百首を詠ずること。また、その和歌。鎌倉中期以降行われた。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃく‐なん【嫡男】
嫡出の長男。嫡出の男子。
ちゃく‐に【着荷】
荷物が到着すること。また、その荷物。ちゃっか。
ちゃく‐にょ【嫡女】
嫡出の長女。〈日葡辞書〉
ちゃく‐にん【着任】
任地に到着すること。また、任務につくこと。「4月1日付で―する」↔離任
ちゃく‐はつ【着発】
①到着と出発。発着。
②弾丸などが物に当たった瞬間に爆発すること。「―信管」
ちゃく‐ばらい【着払い】‥バラヒ
郵便物や品物などの代金・送料などを受取人が支払うこと。また、その制度。
ちゃく‐ひつ【着筆】
①筆をつけること。書き始めること。
②筆のつけよう。書きかた。
ちゃく‐ひょう【着氷】
①セ氏0度以下の物体に水が衝突して凍結する現象。過冷却の雲粒が飛行機に付着する場合、波のしぶきが船に付着する場合などがある。「船体―」
②スケート競技などで、氷面に降り立つこと。
ちゃく‐ふ【着府】
国府・城下町に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐ふく【着服】
①衣服を身につけること。
②(チャクブク・チャクボクとも)ごまかしてひそかにわが物とすること。東海道中膝栗毛5「手早くかの三百文を―して」。「公金を―する」
ちゃく‐ぼ【嫡母】
(庶子からの称)父の正妻。父の嫡妻。
ちゃく‐ぼう【着帽】
帽子をかぶること。↔脱帽↔無帽
ちゃく‐ぼく【着服】
「ちゃくふく」の訛。東海道中膝栗毛4「おのがふところへ―して」
ちゃ‐くみ【茶汲み】
茶を汲むこと。茶を汲んで供すること。また、その人。「お―」
ちゃく‐メロ【着メロ】
着信メロディーの略。着信音がメロディーになっているもの。
ちゃく‐もく【着目】
気をつけて見ること。特に目をつけること。着眼。「―に価する」
ちゃく‐よう【着用】
衣服をきること。身につけること。「―に及ぶ」「シート‐ベルトを―する」
ちゃ‐くらべ【茶競べ・茶較べ】
種々の茶を飲みわけてその良し悪しを品評し合う遊戯。狂言、止動方角しどうほうがく「けふは山一つあなたへ―に参りまするが」
ちゃく‐りく【着陸】
飛行中の航空機などが陸上に降りること。↔離陸。
⇒ちゃくりく‐そうち【着陸装置】
⇒ちゃくりく‐たい【着陸帯】
⇒ちゃくりく‐とう【着陸灯】
ちゃくりく‐そうち【着陸装置】‥サウ‥
(→)降着装置に同じ。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐たい【着陸帯】
航空機が安全に離着陸できるように設備した場所。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐とう【着陸灯】
夜間または悪天候時に着陸する際、前方を照射するために航空機に装備する灯火。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくり‐ちゃ‐と
〔副〕
すぐに。さっと。
ちゃく‐りゅう【嫡流】‥リウ
総本家の家筋。正統の流派。「清和源氏の―」↔庶流
ちゃく‐りょう【着料】‥レウ
①着るもの。また、その材料とするもの。衣料。
②衣服を給する代りに与える金銭。
③黄八丈の幅の狭いもの。
ちゃく‐れん【着輦】
高貴な人の乗物が目的地に着くこと。
ちゃ‐け【茶家】
茶道にたずさわる人。また点茶を業とする人。
チャケー【cha-khe タイ】
(鰐わにの意)タイのチター属の弦楽器。3弦で11個のフレットを持つ。象牙や骨の義甲で弦をはじいて演奏する。
チャコ
(チョークの訛)服地裁断の標付しるしつけに用いるチョーク。種々の色がある。
チャコ【Chaco】
南米パラグアイ川中流部の広大な草原地帯。パラグアイ領は無人地帯だが、アルゼンチン領は綿花地帯として発展。グラン‐チャコ。
ちゃ‐こう【茶講】‥カウ
茶を飲みに集まる人々の集会。〈日葡辞書〉
ちゃ‐ごう【茶合】‥ガフ
茶器の一つ。煎茶では二つ割にした竹で作り、茶を点ずるとき、茶を移し入れてその量を見はからう。抹茶では桜で椀形に作り、茶入れに茶を入れるとき、その量を計る。
チャコール【charcoal】
堅炭。木炭もくたん。
⇒チャコール‐グレー【charcoal grey】
チャコール‐グレー【charcoal grey】
黒に近い灰色。けしずみ色。
Munsell color system: 5P3/1
⇒チャコール【charcoal】
ちゃ‐こく【茶国】
色茶屋の勤め女。茶屋女。茶屋者。浄瑠璃、生玉心中「枝は木斛もっこく我が身は―」
ちゃ‐こし【茶漉し】
煎茶を漉す道具。
ちゃ‐こぼし【茶零し】
飲み残しの湯茶や滓かすを入れ捨てる容器。
ちゃ‐こもん【茶小紋】
茶色の小紋。
ちゃ‐ざい【茶剤】
熱湯に浸出して服用する、数種の生薬を調合した薬剤。
ちゃ‐さかもり【茶酒盛り】
酒の代りに茶を用いて、ともに飲食し興じること。男色大鑑「石すゑて土がまをかけ―をはじめ」
ちゃ‐さじ【茶匙】
①茶をすくうさじ。また、茶杓ちゃしゃく。ちゃしゃじ。
②小形のさじ。ティー‐スプーン。「―一杯の砂糖」
ちゃ‐ざしき【茶座敷】
茶をたてる座敷。茶席。茶室。
ちゃさんばい【茶子味梅・茶盞拝】
狂言。唐人の夫が日本人の妻の無情を嘆き、いったんは和解して楽を舞うが、やはり唐土を恋しがる。ちゃすあんばい。
ちゃ‐し【茶師】
抹茶または葉茶を製造する人。また、それを茶壺へ詰める人。おつめ。つめ。
ちゃ‐し【茶肆】
①抹茶または葉茶を販売する店。葉茶屋。茶舗。
②茶店。
チャシ
(アイヌ語)砦とりでの意。北海道および東北諸県に500を超える遺跡が残存。地形に恵まれた丘陵の突端の一部に壕をめぐらし、上を地ならししてあるものが多い。
ちゃ‐じ【茶事】
茶道に関すること。また、茶会。
⇒ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
ちゃ‐しき【茶式】
茶道の方式。室町時代、村田珠光を祖とし、武野紹鴎じょうおうを経て、千利休に至って大成。
ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
代表的な茶会の種類で、暁の茶事・朝の茶事・正午の茶事・夜咄よばなしの茶事・不時の茶事・飯後はんごの茶事・跡見あとみの茶事の7種をいう。
⇒ちゃ‐じ【茶事】
ちゃ‐しつ【茶室】
茶会に用いる室。古くは茶湯座敷・数寄屋・囲かこいなどといい、茶室と呼ぶようになったのは江戸時代以後。4畳半を基本とし、3畳・2畳、あるいは台目畳を用いて最小1畳台目まである。4畳半以下を小間、以上を広間といい、4畳半は両方を兼ねる。茶席。
茶室
手】
手の親指と中指をいっぱいに伸ばすこと。また、伸ばした長さ。仏像の高さをはかるのに用いる。1搩手は8寸(約24.5センチメートル)(異説もある)。平家物語1「一―半の薬師」
ちゃく‐しゅう【着臭】‥シウ
においを付けること。特に、無臭のガスなどににおいを付けて嗅ぎ取れるようにすること。
ちゃく‐しゅつ【嫡出】
正妻からの出生。法律上有効な婚姻をした夫婦間の出生。正出。↔庶出。
⇒ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
ちゃくしゅつ‐し【嫡出子】
正妻から出生した子。法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子。
⇒ちゃく‐しゅつ【嫡出】
ちゃく‐じゅん【着順】
競走などで目標地点への到着順序。「―判定」
ちゃく‐しょ【嫡庶】
嫡出と庶出。また、嫡子と庶子。ちゃくそ。
ちゃく‐じょ【嫡女】‥ヂヨ
正妻の生んだ長女。
ちゃく‐しょう【着床】‥シヤウ
受精卵が子宮粘膜に定着すること。妊娠のはじまり。
⇒ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】
ちゃくしょうぜん‐しんだん【着床前診断】‥シヤウ‥
体外受精によって得られた4細胞期または8細胞期の受精卵から1〜2個の割球を採取して行う染色体または遺伝子の診断。
⇒ちゃく‐しょう【着床】
ちゃく‐しょく【着色】
色をつけること。いろどり。彩色。「食品に―する」「人工―料」
⇒ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
⇒ちゃくしょく‐りょう【着色料】
ちゃくしょく‐ガラス【着色硝子】
金属酸化物などを加えて着色したガラス。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃくしょく‐りょう【着色料】‥レウ
食品添加物の一種。食品に色をつけるために用いる。天然着色料と合成着色料とがある。
⇒ちゃく‐しょく【着色】
ちゃく‐しん【着心】
執着する心。執心。執念。太平記35「人間に―の深かりし咎」
ちゃく‐しん【着信】
音信の到着すること。また、その音信。受信。「―局」
⇒ちゃくしん‐おん【着信音】
ちゃく‐じん【着陣】‥ヂン
①公卿が役所の列座する席(陣の座)につくこと。
②陣所に到着すること。
ちゃくしん‐おん【着信音】
携帯電話・電子メールなどで、着信を知らせるために出される音。着音。
⇒ちゃく‐しん【着信】
ちゃく‐すい【着水】
空中から水面につくこと。特に、水上飛行機などが水面に降りつくこと。↔離水
ちゃく・する【着する・著する】
[文]着す(サ変)
[一]〔自サ変〕
①ぴったりとつく。
②いたる。とどく。到着する。古今著聞集2「舟をになひて岸に―・しけり」
③執着する。「一事に―・する」→着じゃくす。
[二]〔他サ変〕
きる。着用する。また、身につける。持つ。
ちゃく‐せい【着生】
植物が樹木・岩石などの他物に付着して生育すること。
⇒ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
ちゃくせい‐しょくぶつ【着生植物】
樹上・石上に付着して生活する植物の総称。寄生植物と異なり養分をその相手からは摂取しない。セッコク・シノブなど。樹上植物。気生植物。
⇒ちゃく‐せい【着生】
ちゃく‐せき【着席】
座席につくこと。着座。
ちゃく‐せつ【着雪】
雪が電線や木の枝などに付着する現象。
ちゃく‐せん【着船】
船が港につくこと。また、その船。
ちゃく‐そ【嫡庶】
⇒ちゃくしょ。〈日葡辞書〉
ちゃく‐そう【着相】‥サウ
執着する状態。太平記37「―を哀む」
ちゃく‐そう【着装】‥サウ
(→)装着そうちゃくに同じ。
ちゃく‐そう【着想】‥サウ
心に浮かんだ工夫。おもいつき。「奇抜な―だ」
ちゃく‐そう【嫡宗】
①同族中の総本家。宗家。
②正系。正統。
ちゃく‐そうそん【嫡曾孫】
嫡孫の嫡子。
ちゃく‐そん【嫡孫】
嫡子の嫡子。
⇒ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
ちゃくそん‐しょうそ【嫡孫承祖】
嫡孫が直接に祖父の家督を継承すること。
⇒ちゃく‐そん【嫡孫】
ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
(「釱」「鈦」は鉄木かなきで、鉄製の足かせ)律令制で、徒役ずえき中の罪人に足かせをつけたこと。ちゃくたい。「―盤枷はんか」
⇒ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
ちゃく‐たい【着帯】
妊婦が妊娠5カ月目に腹帯(岩田帯)を締めること。また、その祝いの式。
ちゃく‐たい【着釱】
⇒ちゃくだ
ちゃく‐だつ【着脱】
身につけたり脱いだりすること。その部分につけたり、はずしたりすること。「―自由」
ちゃくだ‐の‐まつりごと【着鈦の政】
平安時代、検非違使が陰暦5月・12月に日を選んで盗犯・私鋳銭などの犯人に着鈦し笞刑ちけいを加えた行事。
⇒ちゃく‐だ【着釱・着鈦】
ちゃく‐だん【着弾】
銃砲から発射した弾丸が或る地点に到達すること。「―距離」
ちゃく‐ち【着地】
①着陸。また、着陸する場所。
②体操・スキー・跳躍競技などで、床・地面に降り立つこと。
ちゃく‐ちゃく【着着】
物事が順序を追ってはかどるさま。一歩一歩。「仕事が―と進む」
ちゃく‐ちゃく【嫡嫡】
嫡子から嫡子へと家を継いで行くこと。正統の血脈。嫡流。ちゃきちゃき。
ちゃぐちゃぐ‐うまこ【チャグチャグ馬こ】
岩手県の盛岡・花巻で作られる、首に鈴をつけた木製の馬の玩具。馬の息災延命を祈願した同名の行事に由来。「チャグチャグ」は鈴の音の擬音語。
ちゃく‐ちょう【着帳】‥チヤウ
その座に参会する者の姓名を記録すること。申楽談儀「将軍家御―自筆に先管領とあそばされしより」
ちゃく‐つ【着津】
港に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐てい【嫡弟】
嫡出の弟。
ちゃく‐でん【着電】
電信の到着すること。また、その電信。
ちゃく‐でん【嫡伝】
嫡々相伝えること。正統から正統に伝えること。正統の相伝。
ちゃく‐と
〔副〕
てばやくふるまうさま。す早く。ちゃっと。好色一代女2「帥すいとおもふと―言葉に色をつけて」
ちゃく‐とう【着到】‥タウ
①到着すること。
②役所に備えつけて出勤した吏員の姓名を記入する帳簿。古今著聞集16「弁―をとりよせて、寛快がつとめ日々に不参々々と書付てけり」
③出陣の命に応じて軍勢の参着したことを書き留めること。また、着到状の略。平家物語2「小松殿には盛国承つて―つけけり」
④着到和歌の略。
⑤歌舞伎儀式音楽の一つ。座頭ざがしら俳優が楽屋入りしたのをきっかけにはやす鳴物。能管・太鼓・大太鼓を用い、今は開演30分前にはやす。
⇒ちゃくとう‐じょう【着到状】
⇒ちゃくとう‐すずり【着到硯】
⇒ちゃくとう‐でん【着到殿】
⇒ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】
⇒ちゃくとう‐わか【着到和歌】
ちゃくとう‐じょう【着到状】‥タウジヤウ
中世、出陣の命を受け、あるいは自発的に参集した武士が、馳せ参じた旨を上申した文書。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐すずり【着到硯】‥タウ‥
着到をつける時に用いる硯。受付用の硯。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐でん【着到殿】‥タウ‥
神社で、祭使の上卿以下氏人らが着到して、その氏名を記す所。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐やぐら【着到櫓】‥タウ‥
勢揃え・馬揃えなどを主将が見るために、本城大手門脇などに設けた櫓。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃくとう‐わか【着到和歌】‥タウ‥
日数と人数を限り、毎日一定数の歌題を詠む方式。多くは百日にわたって百首を詠ずること。また、その和歌。鎌倉中期以降行われた。
⇒ちゃく‐とう【着到】
ちゃく‐なん【嫡男】
嫡出の長男。嫡出の男子。
ちゃく‐に【着荷】
荷物が到着すること。また、その荷物。ちゃっか。
ちゃく‐にょ【嫡女】
嫡出の長女。〈日葡辞書〉
ちゃく‐にん【着任】
任地に到着すること。また、任務につくこと。「4月1日付で―する」↔離任
ちゃく‐はつ【着発】
①到着と出発。発着。
②弾丸などが物に当たった瞬間に爆発すること。「―信管」
ちゃく‐ばらい【着払い】‥バラヒ
郵便物や品物などの代金・送料などを受取人が支払うこと。また、その制度。
ちゃく‐ひつ【着筆】
①筆をつけること。書き始めること。
②筆のつけよう。書きかた。
ちゃく‐ひょう【着氷】
①セ氏0度以下の物体に水が衝突して凍結する現象。過冷却の雲粒が飛行機に付着する場合、波のしぶきが船に付着する場合などがある。「船体―」
②スケート競技などで、氷面に降り立つこと。
ちゃく‐ふ【着府】
国府・城下町に到着すること。〈日葡辞書〉
ちゃく‐ふく【着服】
①衣服を身につけること。
②(チャクブク・チャクボクとも)ごまかしてひそかにわが物とすること。東海道中膝栗毛5「手早くかの三百文を―して」。「公金を―する」
ちゃく‐ぼ【嫡母】
(庶子からの称)父の正妻。父の嫡妻。
ちゃく‐ぼう【着帽】
帽子をかぶること。↔脱帽↔無帽
ちゃく‐ぼく【着服】
「ちゃくふく」の訛。東海道中膝栗毛4「おのがふところへ―して」
ちゃ‐くみ【茶汲み】
茶を汲むこと。茶を汲んで供すること。また、その人。「お―」
ちゃく‐メロ【着メロ】
着信メロディーの略。着信音がメロディーになっているもの。
ちゃく‐もく【着目】
気をつけて見ること。特に目をつけること。着眼。「―に価する」
ちゃく‐よう【着用】
衣服をきること。身につけること。「―に及ぶ」「シート‐ベルトを―する」
ちゃ‐くらべ【茶競べ・茶較べ】
種々の茶を飲みわけてその良し悪しを品評し合う遊戯。狂言、止動方角しどうほうがく「けふは山一つあなたへ―に参りまするが」
ちゃく‐りく【着陸】
飛行中の航空機などが陸上に降りること。↔離陸。
⇒ちゃくりく‐そうち【着陸装置】
⇒ちゃくりく‐たい【着陸帯】
⇒ちゃくりく‐とう【着陸灯】
ちゃくりく‐そうち【着陸装置】‥サウ‥
(→)降着装置に同じ。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐たい【着陸帯】
航空機が安全に離着陸できるように設備した場所。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくりく‐とう【着陸灯】
夜間または悪天候時に着陸する際、前方を照射するために航空機に装備する灯火。
⇒ちゃく‐りく【着陸】
ちゃくり‐ちゃ‐と
〔副〕
すぐに。さっと。
ちゃく‐りゅう【嫡流】‥リウ
総本家の家筋。正統の流派。「清和源氏の―」↔庶流
ちゃく‐りょう【着料】‥レウ
①着るもの。また、その材料とするもの。衣料。
②衣服を給する代りに与える金銭。
③黄八丈の幅の狭いもの。
ちゃく‐れん【着輦】
高貴な人の乗物が目的地に着くこと。
ちゃ‐け【茶家】
茶道にたずさわる人。また点茶を業とする人。
チャケー【cha-khe タイ】
(鰐わにの意)タイのチター属の弦楽器。3弦で11個のフレットを持つ。象牙や骨の義甲で弦をはじいて演奏する。
チャコ
(チョークの訛)服地裁断の標付しるしつけに用いるチョーク。種々の色がある。
チャコ【Chaco】
南米パラグアイ川中流部の広大な草原地帯。パラグアイ領は無人地帯だが、アルゼンチン領は綿花地帯として発展。グラン‐チャコ。
ちゃ‐こう【茶講】‥カウ
茶を飲みに集まる人々の集会。〈日葡辞書〉
ちゃ‐ごう【茶合】‥ガフ
茶器の一つ。煎茶では二つ割にした竹で作り、茶を点ずるとき、茶を移し入れてその量を見はからう。抹茶では桜で椀形に作り、茶入れに茶を入れるとき、その量を計る。
チャコール【charcoal】
堅炭。木炭もくたん。
⇒チャコール‐グレー【charcoal grey】
チャコール‐グレー【charcoal grey】
黒に近い灰色。けしずみ色。
Munsell color system: 5P3/1
⇒チャコール【charcoal】
ちゃ‐こく【茶国】
色茶屋の勤め女。茶屋女。茶屋者。浄瑠璃、生玉心中「枝は木斛もっこく我が身は―」
ちゃ‐こし【茶漉し】
煎茶を漉す道具。
ちゃ‐こぼし【茶零し】
飲み残しの湯茶や滓かすを入れ捨てる容器。
ちゃ‐こもん【茶小紋】
茶色の小紋。
ちゃ‐ざい【茶剤】
熱湯に浸出して服用する、数種の生薬を調合した薬剤。
ちゃ‐さかもり【茶酒盛り】
酒の代りに茶を用いて、ともに飲食し興じること。男色大鑑「石すゑて土がまをかけ―をはじめ」
ちゃ‐さじ【茶匙】
①茶をすくうさじ。また、茶杓ちゃしゃく。ちゃしゃじ。
②小形のさじ。ティー‐スプーン。「―一杯の砂糖」
ちゃ‐ざしき【茶座敷】
茶をたてる座敷。茶席。茶室。
ちゃさんばい【茶子味梅・茶盞拝】
狂言。唐人の夫が日本人の妻の無情を嘆き、いったんは和解して楽を舞うが、やはり唐土を恋しがる。ちゃすあんばい。
ちゃ‐し【茶師】
抹茶または葉茶を製造する人。また、それを茶壺へ詰める人。おつめ。つめ。
ちゃ‐し【茶肆】
①抹茶または葉茶を販売する店。葉茶屋。茶舗。
②茶店。
チャシ
(アイヌ語)砦とりでの意。北海道および東北諸県に500を超える遺跡が残存。地形に恵まれた丘陵の突端の一部に壕をめぐらし、上を地ならししてあるものが多い。
ちゃ‐じ【茶事】
茶道に関すること。また、茶会。
⇒ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
ちゃ‐しき【茶式】
茶道の方式。室町時代、村田珠光を祖とし、武野紹鴎じょうおうを経て、千利休に至って大成。
ちゃじ‐しちしき【茶事七式】
代表的な茶会の種類で、暁の茶事・朝の茶事・正午の茶事・夜咄よばなしの茶事・不時の茶事・飯後はんごの茶事・跡見あとみの茶事の7種をいう。
⇒ちゃ‐じ【茶事】
ちゃ‐しつ【茶室】
茶会に用いる室。古くは茶湯座敷・数寄屋・囲かこいなどといい、茶室と呼ぶようになったのは江戸時代以後。4畳半を基本とし、3畳・2畳、あるいは台目畳を用いて最小1畳台目まである。4畳半以下を小間、以上を広間といい、4畳半は両方を兼ねる。茶席。
茶室
 ちゃ‐しぶ【茶渋】
茶碗などに付着する、茶の煎じ汁のあか。
ちゃ‐しゃく【茶杓】
抹茶をすくい取るさじ。竹・象牙・金属・木地・塗物で作り、珠光形・利休形などがある。ちゃさじ。
茶杓
ちゃ‐しぶ【茶渋】
茶碗などに付着する、茶の煎じ汁のあか。
ちゃ‐しゃく【茶杓】
抹茶をすくい取るさじ。竹・象牙・金属・木地・塗物で作り、珠光形・利休形などがある。ちゃさじ。
茶杓
 ちゃ‐じゅ【茶寿】
(「茶」の字を分解すると、二つの十と八十八とになるとしていう)数え年108歳。また、その祝い。
ちゃ‐じゅす【茶繻子】
茶色のしゅす。
ちゃ‐じょく【茶職】
(→)茶坊主1に同じ。
ちゃ‐しん【茶神】
茶の神として祭る中国の陸羽の像。茶の神。→茶経ちゃきょう
ちゃ‐じん【茶人】
①茶の湯を好む人。茶道に通じた人。
②変わったことを好む人。一風かわった物好き。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「おらが若旦那にほれるとは…とんだ―だ」
ちゃすあんばい【茶子味梅】
⇒ちゃさんばい
ちゃ‐せき【茶席】
茶をたてる座席。茶座敷。茶室。また、茶会。
⇒ちゃせき‐がけ【茶席掛】
ちゃせき‐がけ【茶席掛】
(→)「ちゃがけ」に同じ。
⇒ちゃ‐せき【茶席】
ちゃせご
正月14日の晩の行事。宮城県で、厄年の人はこの日7軒から餅や銭を貰い集めると厄難をのがれるといって貰いに出る。させご。→かせどり
ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
①抹茶をたてる際、茶をかきまわして泡を立たせたり練ったりする具。白竹・青竹・胡麻竹・煤竹・紫竹などを用い、10センチメートル前後の竹筒の半分以下を細く割って穂とし、穂先の末端は内に曲げるが、直なものもある。数穂・中穂・荒穂などの種類がある。〈文明本節用集〉
茶筅
ちゃ‐じゅ【茶寿】
(「茶」の字を分解すると、二つの十と八十八とになるとしていう)数え年108歳。また、その祝い。
ちゃ‐じゅす【茶繻子】
茶色のしゅす。
ちゃ‐じょく【茶職】
(→)茶坊主1に同じ。
ちゃ‐しん【茶神】
茶の神として祭る中国の陸羽の像。茶の神。→茶経ちゃきょう
ちゃ‐じん【茶人】
①茶の湯を好む人。茶道に通じた人。
②変わったことを好む人。一風かわった物好き。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「おらが若旦那にほれるとは…とんだ―だ」
ちゃすあんばい【茶子味梅】
⇒ちゃさんばい
ちゃ‐せき【茶席】
茶をたてる座席。茶座敷。茶室。また、茶会。
⇒ちゃせき‐がけ【茶席掛】
ちゃせき‐がけ【茶席掛】
(→)「ちゃがけ」に同じ。
⇒ちゃ‐せき【茶席】
ちゃせご
正月14日の晩の行事。宮城県で、厄年の人はこの日7軒から餅や銭を貰い集めると厄難をのがれるといって貰いに出る。させご。→かせどり
ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
①抹茶をたてる際、茶をかきまわして泡を立たせたり練ったりする具。白竹・青竹・胡麻竹・煤竹・紫竹などを用い、10センチメートル前後の竹筒の半分以下を細く割って穂とし、穂先の末端は内に曲げるが、直なものもある。数穂・中穂・荒穂などの種類がある。〈文明本節用集〉
茶筅
 ②近世、茶筅1を行商し、賤民視された人々の称。
③茶筅髪の略。
⇒ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
⇒ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
⇒ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
⇒ちゃせん‐し【茶筅師】
⇒ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
⇒ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
⇒ちゃせん‐たて【茶筅立】
⇒ちゃせん‐とおし【茶筅通し】
⇒ちゃせん‐ぼう【茶筅坊】
ちゃ‐ぜん【茶禅】
茶道と禅道。
⇒ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
茶道の奥義と禅道とが一致するということ。
⇒ちゃ‐ぜん【茶禅】
ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
茶道の習事の一つ。水指の蓋の上に茶巾・茶筅・茶杓をのせ、前に茶碗の中に茶入を仕組んで飾っておいて行う点前。茶碗・茶入・茶杓・水指のいずれかに由緒や伝来があるか優品である場合に行う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
①男の髪の結い方。髪を頭の百会ひゃくえの所で束ね、もとどりを糸の組緒で巻き、先をほおけさせて茶筅の形にしたもの。
茶筅髪
②近世、茶筅1を行商し、賤民視された人々の称。
③茶筅髪の略。
⇒ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
⇒ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
⇒ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
⇒ちゃせん‐し【茶筅師】
⇒ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
⇒ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
⇒ちゃせん‐たて【茶筅立】
⇒ちゃせん‐とおし【茶筅通し】
⇒ちゃせん‐ぼう【茶筅坊】
ちゃ‐ぜん【茶禅】
茶道と禅道。
⇒ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
ちゃぜん‐いっち【茶禅一致】
茶道の奥義と禅道とが一致するということ。
⇒ちゃ‐ぜん【茶禅】
ちゃせん‐かざり【茶筅飾・茶筌荘】
茶道の習事の一つ。水指の蓋の上に茶巾・茶筅・茶杓をのせ、前に茶碗の中に茶入を仕組んで飾っておいて行う点前。茶碗・茶入・茶杓・水指のいずれかに由緒や伝来があるか優品である場合に行う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐がみ【茶筅髪】
①男の髪の結い方。髪を頭の百会ひゃくえの所で束ね、もとどりを糸の組緒で巻き、先をほおけさせて茶筅の形にしたもの。
茶筅髪
 ②女の髪の結い方。後家島田などの刷毛先を散らして茶筅状にしたもの。未亡人が結う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
野菜の切り方の一つ。茄子なすの表面に縦に何本か切り込みを入れて、茶筅の形に似せたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ざ【茶煎座】
(岡山地方などで)鍋座なべざのこと。
ちゃせん‐し【茶筅師】
茶筅の製造を業とする人。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
チャセンシダ科の常緑シダの総称、また、その一種。葉は束生し、古い葉柄や全体の姿が茶筅に似る。世界の暖温帯に分布。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
袖垣の一形式。竹を筋違いに組み、その上部を竪たてに編み、上端を結束せずに茶筅状にしたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐たて【茶
②女の髪の結い方。後家島田などの刷毛先を散らして茶筅状にしたもの。未亡人が結う。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ぎり【茶筅切り】
野菜の切り方の一つ。茄子なすの表面に縦に何本か切り込みを入れて、茶筅の形に似せたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐ざ【茶煎座】
(岡山地方などで)鍋座なべざのこと。
ちゃせん‐し【茶筅師】
茶筅の製造を業とする人。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐しだ【茶筅羊歯】
チャセンシダ科の常緑シダの総称、また、その一種。葉は束生し、古い葉柄や全体の姿が茶筅に似る。世界の暖温帯に分布。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐そでがき【茶筅袖垣】
袖垣の一形式。竹を筋違いに組み、その上部を竪たてに編み、上端を結束せずに茶筅状にしたもの。
⇒ちゃ‐せん【茶筅・茶筌】
ちゃせん‐たて【茶○血を受けるちをうける🔗⭐🔉
○血を啜るちをすする🔗⭐🔉
○血を啜るちをすする
[礼記曲礼下](昔、中国で、盟ちかいに際して、いけにえを殺しその血をすすったことから)心から堅く誓う。
⇒ち【血】
○血を吐く思いちをはくおもい🔗⭐🔉
○血を吐く思いちをはくおもい
きわめてつらく苦しい思い。
⇒ち【血】
○血を分けたちをわけた🔗⭐🔉
○血を分けたちをわけた
親子・兄弟などの、血縁の間柄にある。
⇒ち【血】
ちん
①小さな金属製品を軽く打つときの音。
②(普通、チンと書く。初期の電子レンジの調理終了の合図の音から)電子レンジで加熱すること。「冷や飯を―して食べた」
③三味線の唱歌しょうがで、三の糸を押さえて、撥ばちで上から弾く音。
ちん【狆】
イヌの一品種。小形で体高約25センチメートル。顔は平たくしゃくれ、目は丸く大きい。体毛は絹糸状。黒と白、白と茶とのまだらが多い。中国からの品種をもとに、江戸時代に作出。愛玩用。ちんころ。
ちん【枕】
まくら。
ちん【亭】
(唐音)眺望または休憩のために庭園に設けた風雅な建物。あずまや。
ちん【珍】
①めずらしいこと。めずらしいもの。貴重。「―とするに足る」
②奇妙なこと。異様なもの。「―なことを言う」
ちん【陳】
中国の国名。
㋐春秋時代の国。嬀き姓の国。周の武王が舜の後裔を求めて陳(今の河南省淮陽県)に封じたという。前478年楚に滅ぼされた。
㋑南北朝時代の南朝最後の国。陳覇先(武帝)が梁の敬帝の禅譲を受けて創建。建康(南京)に都した。五代で隋の文帝に滅ぼされた。(557〜589)
ちん【椿】
「荘子」にみえる長寿の霊木。→大椿だいちゅん→つばき(椿)
ちん【賃】
使用料。報酬。代金。「借り―」
ちん【鴆】
①一種の毒鳥。その羽をひたした酒を飲めば死ぬという。
②(→)鴆酒に同じ。酖。
③(→)鴆毒に同じ。太平記12「―といふ恐しき毒を入れられたり」
ちん【鎮】
①中国で、
㋐北魏の頃、大軍を駐屯させた要地の称。
㋑宋代以後、県に所属する小都市の称。
㋒一地域を鎮安する軍隊またはその将。
②〔仏〕古代の諸大寺の僧職の一つ。大・中・小の別があり、三綱さんごうの上にあって庶務を処理したらしい。後に廃絶。
チン
(朝鮮語ching)韓国のゴング、鉦。
チン【chin】
下あご。あごさき。
チン【ching タイ】
タイの小型シンバル。
ちん【朕】
〔代〕
天子の自称。古く中国では一般に「われ」の意に用いたが、秦の始皇帝に至って天子に限定して用いるようになった。
ちん
〔接尾〕
人名や人を表す名詞に付けて親しみや軽い侮蔑を表す語。「やっ―」「でぶ―」「しぶ―」
ちん‐あ【沈痾】
久しくなおらない重い病。宿痾。沈痼ちんこ。万葉集5「―自哀の文」(山上憶良)
ちん‐あげ【賃上げ】
賃金の額・水準をあげること。増給。「―闘争」
ちん‐あつ【鎮圧】
①しずめおさえつけること。暴動などを威圧・鎮静すること。「暴徒を―する」
②耕地を鋤すき起こし、土を砕いてならし、地面をおさえつける作業。
⇒ちんあつ‐き【鎮圧器・鎮圧機】
⇒ちんあつ‐ばん【鎮圧板】
ちんあつ‐き【鎮圧器・鎮圧機】
①土壌を砕き地表を平坦にして固める機具。種子の発芽を促し、また、霜害を予防するために使用。
②物をおしつける器。おもし。
⇒ちん‐あつ【鎮圧】
ちんあつ‐ばん【鎮圧板】
木板を鎧戸式に連結し、これに乗って地表を摺りながら鎮圧する板。
⇒ちん‐あつ【鎮圧】
ちん‐い【珍異】
変わって珍しいこと。また、そのもの。
ちん‐いけい【沈惟敬】‥ヰ‥
⇒しんいけい
ちん‐うつ【沈鬱】
気分が沈みふさぐこと。「―な顔」
ちん‐うん【陳雲】
(Chen Yun)中国の政治家。旧名、廖陳雲・廖雲程。江蘇青浦出身。革命後、国務院副総理など、経済面の指導職を歴任。(1905〜1995)
ちん‐か【沈下】
しずみさがること。また、物をしずめること。「地盤―」
⇒ちんか‐きょう【沈下橋】
ちん‐か【珍花】‥クワ
形や色の珍しい花。また、季節初めの花。→盛花せいか→残花
ちん‐か【珍果】‥クワ
めずらしい果物。
ちん‐か【珍菓】‥クワ
めずらしい菓子。
ちん‐か【珍貨】‥クワ
めずらしい品物。
ちん‐か【鎮火】‥クワ
火事の消えて鎮まること。火事を消し鎮めること。
⇒ちんか‐さい【鎮火祭】
ちんがい‐ざい【鎮咳剤】
せきを鎮める薬剤。モルヒネ・リン酸コデインの類。
ちんか‐きょう【沈下橋】‥ケウ
河川が増水したとき水没することを想定して作られた橋。欄干が無く、水面からの高さも低い。潜水橋。潜没橋。沈没橋。
⇒ちん‐か【沈下】
ちん‐かく【珍客】
⇒ちんきゃく
ちん‐かこう【陳嘉庚】‥カウ
(Chen Jiageng)華僑の実業家。福建廈門アモイの人。長くシンガポールに住み、ゴム園経営に成功、故郷に廈門大学など多くの学校を建設。抗日民族統一戦線を支援し、1949年帰国後、人民共和国では要職を歴任。(1874〜1961)
ちんか‐さい【鎮火祭】‥クワ‥
陰暦6月・12月の晦日の夜、宮城の四方の隅で神を祭り、火災防止を祈った神事。延喜式に祝詞がある。今も各地の神社で行われる。ひしずめのまつり。ほしずめのまつり。
⇒ちん‐か【鎮火】
ちんか‐さい【鎮花祭】‥クワ‥
陰暦3月の落花の時期には疫病の流行が盛んで、これを鎮めるために行疫神ぎょうやくじんたる大神おおみわ・狭井さいの二神を祭った宮中の神事。神社でも行う。崇神天皇の時に始まるといい、平安時代に盛行。はなしずめのまつり。
ちん‐がし【賃貸し】
貸し賃を取って物を貸すこと。ちんたい。「部屋を―する」
ちん‐かせぎ【賃稼ぎ】
賃銭を取って労務に従うこと。
ちん‐カツ【賃カツ】
賃金カットの略。
ちん‐がら【珍柄】
織物などのめずらしい柄。
ちん‐からり
①金属が打ち合って響く音。
②内部に何物もないさま。からっぽ。浄瑠璃、心中天の網島「又引き出しても―、有たけこたけ引き出しても」
ちん‐からり【涼炉】
琉球から渡来した焜炉こんろの一種。略して「ちんから」とも。好色五人女5「賤の屋にありし―とやいへる物一つに、青き松葉を焼き捨て」
ちん‐がり【賃借り】
借り賃を出して物を借りること。ちんしゃく。
ちん‐がん【珍玩】‥グワン
①めずらしい玩具。
②めずらしがってもてあそぶこと。
ちん‐き【沈毅】
沈着で剛毅なこと。おちついて物事に動じないこと。沈着剛毅。「―な人格」
ちん‐き【珍奇】
めずらしく、奇妙なこと。「―な動物」
ちん‐き【珍稀】
めずらしく、まれなこと。
ちん‐き【珍貴】
めずらしく、貴重であること。
ちん‐き【珍器】
めずらしい器物。珍具。
ちん‐き【陳毅】
(Chen Yi)中国の軍人・政治家。四川楽至出身。1941年新四軍軍長代理となり、国民党のため壊滅した同軍の再建に成功。人民共和国では上海市長・国務院副総理・外交部長などを歴任。(1901〜1972)
チンキ【丁幾】
(tinctuur オランダに基づく)生薬をアルコールで浸出した液。また、化学薬品のアルコール溶液。
ちん‐きい【陳希夷】
五代・宋初の道士。名は摶たん、字は図南、号は扶揺子。河南の人。湖南の武当山で修行、のち宋の太宗に召され希夷先生と賜号。著「指玄篇」「還丹歌註」。( 〜989)
チンギス‐ハン
⇒ジンギスかん
ちん‐きゃく【珍客】
珍しい客。ちんかく。「―を迎える」
ちん‐きょう【聴叫】‥ケウ
(チンは唐音)禅寺で、住職の命令を諸寮に伝える童子。聴呼ちんこ。
ちんぎょ‐らくがん【沈魚落雁】
(「荘子」に、人間が見て美しいと思う人でも魚や鳥はこれを見て恐れて逃げるとあるのを、後世、魚や鳥も恥じらってかくれる意に転用して)美人の容貌のすぐれてあでやかなこと。→羞花閉月しゅうかへいげつ
ちん‐きん【沈金】
漆塗の面に模様を線彫し、その彫溝に漆を摺り込み金箔などを付着させる技法。室町時代に中国から伝来し、琉球で盛行。石川県輪島市などが産地として有名。沈金彫。→鎗金そうきん→輪島塗。
⇒ちんきん‐ぼり【沈金彫】
ちん‐きん【珍禽】
めずらしい鳥。
ちん‐きん【賃金】
①⇒ちんぎん。
②〔法〕民法上、(→)借賃に同じ。
ちん‐ぎん【沈吟】
①しずかに口ずさむこと。
②深く考えこむこと。うれえなげくこと。
ちん‐ぎん【沈銀】
沈金彫の一種。金箔の代りに銀箔を用いたもの。
ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
(wage)労働者が労働を提供することによって受け取る報酬。労働力の価値を貨幣で表したもの。労銀。賃銭。
⇒ちんぎん‐かくさ【賃金格差】
⇒ちんぎん‐カット【賃金カット】
⇒ちんぎん‐ききん‐せつ【賃金基金説】
⇒ちんぎん‐けいたい【賃金形態】
⇒ちんぎん‐しすう【賃金指数】
⇒ちんぎん‐すいじゅん【賃金水準】
⇒ちんぎん‐たいけい【賃金体系】
⇒ちんぎん‐てっそく【賃金鉄則】
⇒ちんぎん‐どれい【賃金奴隷】
⇒ちんぎん‐ベース【賃金ベース】
⇒ちんぎん‐ろうどう【賃金労働】
⇒ちんぎん‐ろうどうしゃ【賃金労働者】
ちんぎん‐かくさ【賃金格差】
職種・勤続年数・年齢・学歴・性別・産業・企業規模などの違いによる賃金の差。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐カット【賃金カット】
業績不振やストライキ中などの理由で賃金を差し引くこと。賃カツ。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐ききん‐せつ【賃金基金説】
イギリス古典学派、特にJ.S.ミルの唱えた賃金学説。ある社会で、労働者の賃金にあてられる基金は一定であり、労働者全体の受取総額は固定されているとするもの。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐けいたい【賃金形態】
賃金の支払形態。基本的な形態は時間賃金(時間給)と個数賃金(出来高給)。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐しすう【賃金指数】
賃金水準の変動を示すための指数。過去のある時期を基準とし、その時期の賃金を100として、他の時期の賃金がこれに比較して2倍ならば200というふうに表す。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐すいじゅん【賃金水準】
国・産業・職業・企業など一定の条件を具えた労働者の賃金の平均的な高さ。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐たいけい【賃金体系】
賃金を決定する諸要素の組合せ。基本給や諸手当を支払う基準、およびこれらの賃金諸項目の関係を総括するもの。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐てっそく【賃金鉄則】
リカードの賃金論のこと。1863年ラサールが名付けた。賃金の上昇・下落と人口との間には一定の関係があり、賃金水準は結局は労働者の最低生活水準で決まり、労働者は資本主義制度が続く限り悲惨と貧困とから免れ得ないとした。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐どれい【賃金奴隷】
(wage slave)資本主義下の賃金労働者を奴隷にたとえていった語。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐ベース【賃金ベース】
企業別または産業別・地域別に、賃金支払総額をそこに働く労働者の総数で割ったもの。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんきん‐ぼり【沈金彫】
(→)沈金に同じ。通言総籬つうげんそうまがき「―の机に」
⇒ちん‐きん【沈金】
ちんぎん‐ろうどう【賃金労働】‥ラウ‥
⇒ちんろうどう。
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちんぎん‐ろうどうしゃ【賃金労働者】‥ラウ‥
賃労働をする人。プロレタリア。→賃労働
⇒ちん‐ぎん【賃金・賃銀】
ちん‐く【珍句】
①めずらしい句。まれに見る句。
②奇異な句。珍妙な句。
ちん‐くしゃ【狆くしゃ】
狆がくしゃみをしたような顔。不美人の形容。
チンク‐ゆ【チンク油】
(zinc oxide oil)同量の酸化亜鉛と植物油(主にオリーブ油)とを混和したもの。収斂しゅうれん作用があり、皮膚の急性炎症に使う。
ちん‐ぐるま【稚児車】
(チゴグルマの転)バラ科の落葉小低木。代表的な高山植物。雪どけ後の湿地などに大群落を作る。高さ約10センチメートル。7〜8月頃、先端に白花を1個ずつつける。果実となっても花柱が残って長く延び、これが車輪状に多数集まる。
ちんぐるま
 チングルマ(花)
提供:OPO
チングルマ(花)
提供:OPO
 チングルマ(実)
提供:OPO
チングルマ(実)
提供:OPO
 ちんけ
(さいころばくちで一の目を「ちん」ということから)貧相なさま。器量の小さいさま。「―なことをするな」
ちん‐げい【珍芸】
めったに見られない珍しい芸。一風変わっていておもしろい芸。「―を披露する」
ちんけい‐ざい【鎮痙剤】
痙攣けいれんをしずめる薬剤。
ちん‐けいじゅ【陳継儒】
明代の文人。江蘇華亭(現在の上海)の人。字は仲醇、号は眉公。詩文書画にすぐれ、隠者として暮らす一方で、数多くの書物を編纂出版。(1558〜1639)
チンゲンサイ【青梗菜】
(中国語)中国野菜の一品種。パクチョイのうち、葉柄が緑色になるもの。
ちん‐げんぴん【陳元贇】
(本来はチンゲンインとよむ)明の詩人・陶工。字は義都、既白山人と号。1619年(元和5)乱を避けて来日、名古屋藩主徳川義直に仕える。僧元政と交わり、拳法にも秀でた。名古屋で没。(1587〜1671)→元贇焼
ちんこ
①体の非常に小さい人。こども。
②(幼児語)陰茎。ちんちん。ちんぼこ。
⇒ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
ちん‐ご【陳呉】
陳勝呉広ちんしょうごこうの略。
ちん‐ご【鎮護】
しずめまもること。乱を鎮め国を護ること。宴曲集2「―の道場頼みあり」
⇒ちんご‐こっか【鎮護国家】
ちん‐こう【沈降】‥カウ
①しずみくだること。沈下。
②よどむこと。沈殿。
⇒ちんこう‐かいがん【沈降海岸】
⇒ちんこう‐はんのう【沈降反応】
ちん‐こう【珍肴】‥カウ
めずらしいさかな。めずらしいごちそう。
ちんこう【鎮江】‥カウ
(Zhenjiang)中国、江蘇省南西部の都市。大運河と長江の交点に位置し、対岸の揚州と並んで江南地方の物資の集散地として繁栄。近年工業が盛ん。古称は朱方・京口。人口69万6千(2000)。
ちんこう‐かいがん【沈降海岸】‥カウ‥
地盤の沈降によって生じたと考えられる海岸。多くは海面の上昇によって生じたものとの判別が難しい。沈水海岸。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こうじゅ【陳洪綬】
明末の画家。字は章侯。号は老蓮。浙江諸曁しょきの人。仏画・人物画に優れ、デフォルメされた形態と描線が特徴。崔子忠と並び「南陳北崔」と称された。(1599〜1652)
ちん‐こうはく【陳公博】
(Chen Gongbo)中国の政治家。広東省南海生れ。北京大学・コロンビア大学に学ぶ。国民党・国民政府の要職を歴任。1940年汪兆銘を首班とする政権に加わり、第二次大戦後漢奸として逮捕・処刑。(1892〜1946)
ちんこう‐はんのう【沈降反応】‥カウ‥オウ
〔医〕試験管内で可溶性の抗原と抗体が結合して沈降物をつくる反応。特異性が高く、免疫の抗原や抗体の定性・定量に利用される。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こ‐きり【賃粉切】
手間賃を取って煙草の葉を刻むこと。また、その業者。洒落本、辰巳婦言「庖丁を引ツたくられた―か」
ちんご‐こっか【鎮護国家】‥コク‥
仏法によって国家を鎮定し守護すること。このために法華経・金光明経・仁王般若経などを読誦し、また種々の修法を行う。
⇒ちん‐ご【鎮護】
ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
江戸時代から明治初年まで行われた子供芝居。
⇒ちんこ
ちん‐こつ【砧骨】
⇒きぬたこつ
ちん‐ころ
①狆ちん。
②小犬。犬の子。
ちん‐こん【鎮魂】
①魂をおちつけしずめること。たましずめ。
②死者の魂をなぐさめしずめること。
⇒ちんこん‐か【鎮魂歌】
⇒ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
⇒ちんこん‐さい【鎮魂祭】
⇒ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
ちんこん‐か【鎮魂歌】
①死者の魂をなぐさめしずめるための歌。
②⇒たましずめのうた。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
精神をしずめて無念無想となり、一切をささげて神明に帰依すること。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐さい【鎮魂祭】
①⇒たましずめのまつり。
②神葬で、死者の魂を鎮める祭典。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
「レクイエム2」参照。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちん‐ざ【鎮座】
①神霊がその地に鎮まりいること。
②転じて、人や物がどっかりと座を占めることをからかっていう語。「団子鼻が顔のまんなかに―している」
ちん‐さい【鎮祭】
諸神を鎮め固めるための祭儀。
ちん‐さげ【賃下げ】
賃金の切り下げ。減給。
ちん‐ざしき【亭座敷】
あずまや風に作った座敷。
ちん‐さつ【鴆殺・酖殺】
鴆毒を飲ませて殺すこと。毒殺。
ちんざん【椿山】
⇒つばきちんざん(椿椿山)
ちん‐し【沈子】
釣針や網を沈めるのに用いる漁具部材。鉛・鉄・陶器などでつくる。おもり。しずみ。いわ。
ちん‐し【沈思】
おもいにしずむこと。深く考えこむこと。
⇒ちんし‐もっこう【沈思黙考】
ちん‐し【鎮子】
(チンジとも)室内の敷物・帷帳いちょうなどがあおられないように、おさえるおもし。軸物の風鎮もその一つ。ちんす。
ちん‐じ【珍事】
①珍しいこと。「前代未聞の―」
②おもいがけないできごと。一大事。椿事。
⇒ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】
ちん‐じ【椿事】
意外の出来事。非常の事件。珍事。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「如何なる―を惹起さうも知れぬと」
ちん‐しごと【賃仕事】
賃銭をとってする手仕事。
ちんじ‐さい【鎮地祭】‥ヂ‥
伊勢神宮で、式年造営前、大宮地の神に対して工程の無事完了を祈願する祭。
ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】‥エウ
(「珍事中庸」とも書く)
①非常な災難。義経記2「―にあふ事つねの事なり」
②珍しいこと。
⇒ちん‐じ【珍事】
ちん‐しどう【陳師道】‥ダウ
北宋の詩人。字は履常りじょう・無己。号は後山居士。彭城(江蘇省徐州)の人。詩は杜甫を尊重し、黄庭堅とともに江西詩派の祖とされる。著「後山居士文集」。(1053〜1101)
ちん‐しま【賃縞】
賃仕事として内職に織る木綿縞織物。
ちんし‐もっこう【沈思黙考】‥モクカウ
黙って深くじっくりと考えること。
⇒ちん‐し【沈思】
ちん‐しゃ【枕藉】
互いを枕にしてよりかかり、相重なって臥すこと。
ちん‐しゃ【陳謝】
①わけをのべてあやまること。「深く―致します」
②礼を言うこと。
チンジャオロース【青椒肉絲】
(中国語)中国料理の一つ。ピーマン・牛肉を細切りにして炒め、オイスター‐ソースなどで調味したもの。
ちん‐しゃく【賃借】
〔法〕賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をすること。
⇒ちんしゃく‐けん【賃借権】
⇒ちんしゃく‐にん【賃借人】
ちんしゃく‐けん【賃借権】
賃貸借契約に基づいて賃借人が有する債権、すなわち賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求しうる権利。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃく‐にん【賃借人】
賃貸借の当事者たる借り主。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃ‐ち【沈砂池】
(チンサチとも)水道・用水・発電などのために河川から水を取り入れる場合、流入した土砂を沈殿させるための人工池。
ちん‐しゅ【沈朱】
沈金彫の一種。金箔の代りに朱漆を用いたもの。
ちん‐しゅ【珍種】
珍しい種類。珍しい品種。「蘭の―」
ちん‐しゅ【鴆酒・酖酒】
鴆毒をまぜた酒。毒酒。
ちん‐じゅ【陳寿】
西晋の歴史家。字は承祚。四川安漢の人。中国正史の一つである「三国志」のほか、「益都耆旧伝」などの著がある。(233〜297)
ちん‐じゅ【椿寿】
[荘子逍遥遊「上古に大椿なる者有り、八千歳を以て春と為なし、八千歳を以て秋と為す」]長寿。長命。椿齢。→大椿だいちゅん。
⇒ちんじゅ‐き【椿寿忌】
ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
①兵士を駐在させて、その地を鎮め守ること。
②その地を鎮め守る神。また、その社。
⇒ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
⇒ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
⇒ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
⇒ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
⇒ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
⇒ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】
ちん‐しゅう【珍羞】‥シウ
(「羞」は食物をすすめる意)めずらしくてうまい食物。珍膳。
ちん‐じゅう【珍什】‥ジフ
めずらしい什器。珍器。
ちん‐じゅう【珍獣】‥ジウ
数が少なく、外見や生態が珍しいけもの。
ちんじゅ‐き【椿寿忌】
俳人高浜虚子の忌日。〈[季]春〉→虚子忌
⇒ちん‐じゅ【椿寿】
ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
仏寺の鎮守のために建てた神社。地主の神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐じゅつ【陳述】
①意見などを口頭で述べること。特に、訴訟当事者または訴訟関係人が、裁判所に対し、その係争事件について口頭または書面で述べること。
②言語表現において、個々の語の内容を統合し、具体的な表現として成り立たせる作用。山田孝雄の用語から一般化したが、学説により定義は異なる。
⇒ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
⇒ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
民事訴訟において、当事者本人または証人の言い分を書面にして裁判所に提出するもの。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
陳述に一定の意味の語が来るように作用する副詞。「決して(ない)」「たぶん(だろう)」「まるで(ようだ)」の類。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
一国・王城・院・城内・土地・寺院・邸宅・氏などを鎮護する神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
鎮守の社の境内にある森。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
土地の鎮守の神をまつった社。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
①古代、蝦夷えぞを鎮圧するために陸奥国むつのくにに置かれた官庁。初め多賀城に置き、後に胆沢いさわ城などに移した。
②明治以後、各海軍区の警備・防御、所管の出征準備に関することをつかさどり、所属部隊を指揮監督した海軍の機関。横須賀・呉・佐世保・舞鶴の各軍港に置いた。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】‥シヤウ‥
古代、鎮守府の長官。その下に、副将軍・権副将軍・将監(のち軍監)・将曹(のち軍曹)・弩師どし・医師・陰陽師各一人を置いた。鎮東将軍。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐しょ【珍書】
めずらしい書籍。珍本。
ちん‐しょ【砧杵】
きぬたとそれを打つ槌つち。きぬたを打つ槌、またはそれを打つ音。
ちん‐しょ【鎮所】
兵士がその土地をしずめ守るために駐在する所。鎮守府。
ちんじょ【陳書】
二十四史の一つ。南朝の陳の史書。唐の姚思廉ようしれんが太宗の勅命を奉じて撰し、636年成る。北宋の仁宗がこれを曾鞏そうきょうらに校訂させて刊行。本紀6巻、列伝30巻。
ちん‐しょう【沈床】‥シヤウ
木・コンクリートで枠を作り、その中に石を詰めて沈設した工作物。堤防や護岸工事などの基礎や根固めとして用いる。
ちん‐しょう【沈鐘】
淵や池や沼の底に沈んでいるという伝説の鐘。
⇒ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
ちん‐しょう【陳勝】
秦滅亡のきっかけをつくった反乱の指導者。字は渉。陽城(河南)の人。地主の雇い人であったが、前209年、呉広(陽夏(河南)の人、字は叔)と共に秦に叛し自立して楚王と称したが、秦軍に敗れ、呉広にあいつぎ部下に殺された。( 〜前209)
⇒ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】
ちん‐じょう【枕上】‥ジヤウ
①枕のほとり。まくらもと。
②枕をしている状態。
ちん‐じょう【陳状】‥ジヤウ
①意見などを述べた文書。
②中世、訴人(原告)の訴状に対して論人(被告)の提出した答弁書。
③歌合の判定についての不服を判者に申し立てる書状。
ちん‐じょう【陳情】‥ジヤウ
①実情を述べること。心事を述べること。
②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。「―団」
⇒ちんじょう‐ひょう【陳情表】
ちん‐しょうう【陳紹禹】‥セウ‥
(Chen Shaoyu)中国の政治家。安徽六安の人。別名、王明。モスクワ留学中に中国共産党に加入。1931年党総書記。親ソ派として終始毛沢東と対立、モスクワで死去。(1907〜1974)
ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】‥クワウ
(ともに兵を挙げて秦滅亡の端を開いたからいう)ある事のさきがけをすること。また、その人。陳呉。
⇒ちん‐しょう【陳勝】
ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
伝説の一類型。鐘を霊物とし、水界を支配する主と密接な関係を有すると考え、池沼・湖海などに多い。日本では諸所にある「鐘ヶ淵」は、普通にこの伝説を持っているが、俵藤太の竜宮の鐘を奪う伝説が最も著名。
⇒ちん‐しょう【沈鐘】
ちんじょう‐ひょう【陳情表】‥ジヤウヘウ
晋の李密の作。武帝が太子晋の洗馬(太子に奉仕する官名)に任じようとした時、祖母劉氏が90歳余で侍養する者がないために拝辞した上奏文。読む者を感泣させ、古く諸葛孔明の「出師表すいしのひょう」と並称。
⇒ちん‐じょう【陳情】
ちんじょう‐ようがん【枕状溶岩】‥ジヤウ‥
⇒まくらじょうようがん
ちん‐しょく【陳寔】
後漢の地方官。字は仲弓。潁川えいせん許(河南)の人。県吏となり、累進して太丘県長となり、徳をもって治める。盗賊が入って梁上に隠れた時、子弟を訓戒し、「梁上の君子を見よ」といって盗賊を悔悟させた逸話は有名。(104〜187)
ちん‐す【鎮子】
⇒ちんし
ちん・ず【鎮ず】
〔他サ変〕
騒ぎなどをしずめる。霊魂などをなぐさめ安らかにする。今昔物語集14「身を固め―・じて居たりけるに」
ちん‐すい【沈水】
①水に沈むこと。
②(堅く重くて水に沈むからいう)沈香じんこうの木。
⇒ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
⇒ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
⇒ちんすい‐よう【沈水葉】
ちん‐すい【沈酔】
酒に酔いつぶれること。古今著聞集18「康光すでに―に及べり」
ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
(→)沈降海岸に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
体の全部が水中にあり固着生活をする植物。フサモ・キンギョモなど。水中植物。→水生植物。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すいへん【陳水扁】
(Chen Shuibian; Ch‘ên Shui-pien)台湾の政治家。台南生れ。台湾大学卒業後、弁護士として活動。1994年初の民選台北市長、2000年中華民国総統。(1951〜)
ちんすい‐よう【沈水葉】‥エフ
(→)水葉に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すごう【陳子昂】‥ガウ
初唐の詩人。字は伯玉。梓州射洪(四川射洪)の人。質朴で慷慨の気に富む詩を作り、盛唐詩の先駆と評される。則天武后の時、右拾遺うしゅういとなる。著「陳伯玉文集」。(661?〜702?)
ちん・ずる【陳ずる】
〔他サ変〕[文]陳ず(サ変)
①口頭で述べる。
②言い張る。主張する。釈明する。
③嘘を言う。浄瑠璃、出世景清「真直に申せ、少しも―・ぜば拷問せん」
ちん‐せい【沈静】
おちついてしずかなこと。気勢がしずまること。「インフレが―する」
ちん‐せい【陳誠】
(Chen Cheng)中国の軍人。浙江青田の人。国民政府の軍政部長・参謀総長などを歴任。国共内戦で敗退後、台湾で行政院長・副総統。(1896〜1965)
ちん‐せい【鎮星】
五星の一つ。土星の漢名。填星てんせい。
ちん‐せい【鎮静】
騒ぎ・気持などがしずまってしずかなこと。また、しずめおちつかせること。「興奮を―する」
⇒ちんせい‐ざい【鎮静剤】
ちん‐ぜい【鎮西】
(743〜745年、大宰府を鎮西府と改称したからいう)九州の称。
⇒ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
⇒ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
⇒ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
⇒ちんぜい‐は【鎮西派】
⇒ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】
⇒ちんぜい‐ふ【鎮西府】
⇒ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】
ちんせい‐ざい【鎮静剤】
神経作用を鎮静するための薬剤。中枢抑制作用のあるバルビタールなど。かつては臭素剤・吉草根きっそうこんなどが用いられた。
⇒ちん‐せい【鎮静】
ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
(→)鎮西奉行に同じ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
鎌倉幕府の機関。蒙古襲来にそなえて九州御家人の関東への参訴を禁じたのに対応し、現地で訴訟を処理報告させるため博多に設置。1286年(弘安9)から鎮西探題発足まで存続。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
鎌倉幕府が博多に置いた統治機関。九州および壱岐・対馬二島の軍事・警察・裁判をつかさどり、辺海警備にあたった。1293年(永仁1)北条兼時を遣わしたのに始まる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐は【鎮西派】
浄土宗五流の一派。京都知恩院を総本山とし、念仏往生を正業とするとともに諸行往生をも認める。法然の弟子で九州に布教した聖光房弁長を祖とする。現在の浄土宗はこの流れをくむ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】‥ラウ
源為朝みなもとのためともの通称。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ふ【鎮西府】
743年(天平15)大宰府を改称した九州統督の府。将軍ほかの職員があった。745年大宰府復置により廃止。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】‥ギヤウ
鎌倉幕府が設けた統治機関。また、その長の呼称。1185年(文治1)天野遠景が初めてこれに任ぜられ、九州地方の管理・成敗をつかさどった。のち鎮西談議所の、ついで鎮西探題の一環となる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちん‐せき【沈積】
水中にある物質が水底に沈みつもること。堆積たいせき。
⇒ちんせき‐がん【沈積岩】
ちん‐せき【枕席】
(まくらとしきものの意)寝具。ねどこ。
⇒枕席に侍る
ちん‐せき【珍籍】
めずらしい書籍。珍書。
ちんせき‐がん【沈積岩】
(→)堆積岩に同じ。
⇒ちん‐せき【沈積】
ちんせき‐そうりゅう【枕石漱流】‥リウ
「石に枕し流れに漱くちすすぐ」に同じ。→石いし(成句)
ちんけ
(さいころばくちで一の目を「ちん」ということから)貧相なさま。器量の小さいさま。「―なことをするな」
ちん‐げい【珍芸】
めったに見られない珍しい芸。一風変わっていておもしろい芸。「―を披露する」
ちんけい‐ざい【鎮痙剤】
痙攣けいれんをしずめる薬剤。
ちん‐けいじゅ【陳継儒】
明代の文人。江蘇華亭(現在の上海)の人。字は仲醇、号は眉公。詩文書画にすぐれ、隠者として暮らす一方で、数多くの書物を編纂出版。(1558〜1639)
チンゲンサイ【青梗菜】
(中国語)中国野菜の一品種。パクチョイのうち、葉柄が緑色になるもの。
ちん‐げんぴん【陳元贇】
(本来はチンゲンインとよむ)明の詩人・陶工。字は義都、既白山人と号。1619年(元和5)乱を避けて来日、名古屋藩主徳川義直に仕える。僧元政と交わり、拳法にも秀でた。名古屋で没。(1587〜1671)→元贇焼
ちんこ
①体の非常に小さい人。こども。
②(幼児語)陰茎。ちんちん。ちんぼこ。
⇒ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
ちん‐ご【陳呉】
陳勝呉広ちんしょうごこうの略。
ちん‐ご【鎮護】
しずめまもること。乱を鎮め国を護ること。宴曲集2「―の道場頼みあり」
⇒ちんご‐こっか【鎮護国家】
ちん‐こう【沈降】‥カウ
①しずみくだること。沈下。
②よどむこと。沈殿。
⇒ちんこう‐かいがん【沈降海岸】
⇒ちんこう‐はんのう【沈降反応】
ちん‐こう【珍肴】‥カウ
めずらしいさかな。めずらしいごちそう。
ちんこう【鎮江】‥カウ
(Zhenjiang)中国、江蘇省南西部の都市。大運河と長江の交点に位置し、対岸の揚州と並んで江南地方の物資の集散地として繁栄。近年工業が盛ん。古称は朱方・京口。人口69万6千(2000)。
ちんこう‐かいがん【沈降海岸】‥カウ‥
地盤の沈降によって生じたと考えられる海岸。多くは海面の上昇によって生じたものとの判別が難しい。沈水海岸。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こうじゅ【陳洪綬】
明末の画家。字は章侯。号は老蓮。浙江諸曁しょきの人。仏画・人物画に優れ、デフォルメされた形態と描線が特徴。崔子忠と並び「南陳北崔」と称された。(1599〜1652)
ちん‐こうはく【陳公博】
(Chen Gongbo)中国の政治家。広東省南海生れ。北京大学・コロンビア大学に学ぶ。国民党・国民政府の要職を歴任。1940年汪兆銘を首班とする政権に加わり、第二次大戦後漢奸として逮捕・処刑。(1892〜1946)
ちんこう‐はんのう【沈降反応】‥カウ‥オウ
〔医〕試験管内で可溶性の抗原と抗体が結合して沈降物をつくる反応。特異性が高く、免疫の抗原や抗体の定性・定量に利用される。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こ‐きり【賃粉切】
手間賃を取って煙草の葉を刻むこと。また、その業者。洒落本、辰巳婦言「庖丁を引ツたくられた―か」
ちんご‐こっか【鎮護国家】‥コク‥
仏法によって国家を鎮定し守護すること。このために法華経・金光明経・仁王般若経などを読誦し、また種々の修法を行う。
⇒ちん‐ご【鎮護】
ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
江戸時代から明治初年まで行われた子供芝居。
⇒ちんこ
ちん‐こつ【砧骨】
⇒きぬたこつ
ちん‐ころ
①狆ちん。
②小犬。犬の子。
ちん‐こん【鎮魂】
①魂をおちつけしずめること。たましずめ。
②死者の魂をなぐさめしずめること。
⇒ちんこん‐か【鎮魂歌】
⇒ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
⇒ちんこん‐さい【鎮魂祭】
⇒ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
ちんこん‐か【鎮魂歌】
①死者の魂をなぐさめしずめるための歌。
②⇒たましずめのうた。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
精神をしずめて無念無想となり、一切をささげて神明に帰依すること。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐さい【鎮魂祭】
①⇒たましずめのまつり。
②神葬で、死者の魂を鎮める祭典。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
「レクイエム2」参照。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちん‐ざ【鎮座】
①神霊がその地に鎮まりいること。
②転じて、人や物がどっかりと座を占めることをからかっていう語。「団子鼻が顔のまんなかに―している」
ちん‐さい【鎮祭】
諸神を鎮め固めるための祭儀。
ちん‐さげ【賃下げ】
賃金の切り下げ。減給。
ちん‐ざしき【亭座敷】
あずまや風に作った座敷。
ちん‐さつ【鴆殺・酖殺】
鴆毒を飲ませて殺すこと。毒殺。
ちんざん【椿山】
⇒つばきちんざん(椿椿山)
ちん‐し【沈子】
釣針や網を沈めるのに用いる漁具部材。鉛・鉄・陶器などでつくる。おもり。しずみ。いわ。
ちん‐し【沈思】
おもいにしずむこと。深く考えこむこと。
⇒ちんし‐もっこう【沈思黙考】
ちん‐し【鎮子】
(チンジとも)室内の敷物・帷帳いちょうなどがあおられないように、おさえるおもし。軸物の風鎮もその一つ。ちんす。
ちん‐じ【珍事】
①珍しいこと。「前代未聞の―」
②おもいがけないできごと。一大事。椿事。
⇒ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】
ちん‐じ【椿事】
意外の出来事。非常の事件。珍事。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「如何なる―を惹起さうも知れぬと」
ちん‐しごと【賃仕事】
賃銭をとってする手仕事。
ちんじ‐さい【鎮地祭】‥ヂ‥
伊勢神宮で、式年造営前、大宮地の神に対して工程の無事完了を祈願する祭。
ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】‥エウ
(「珍事中庸」とも書く)
①非常な災難。義経記2「―にあふ事つねの事なり」
②珍しいこと。
⇒ちん‐じ【珍事】
ちん‐しどう【陳師道】‥ダウ
北宋の詩人。字は履常りじょう・無己。号は後山居士。彭城(江蘇省徐州)の人。詩は杜甫を尊重し、黄庭堅とともに江西詩派の祖とされる。著「後山居士文集」。(1053〜1101)
ちん‐しま【賃縞】
賃仕事として内職に織る木綿縞織物。
ちんし‐もっこう【沈思黙考】‥モクカウ
黙って深くじっくりと考えること。
⇒ちん‐し【沈思】
ちん‐しゃ【枕藉】
互いを枕にしてよりかかり、相重なって臥すこと。
ちん‐しゃ【陳謝】
①わけをのべてあやまること。「深く―致します」
②礼を言うこと。
チンジャオロース【青椒肉絲】
(中国語)中国料理の一つ。ピーマン・牛肉を細切りにして炒め、オイスター‐ソースなどで調味したもの。
ちん‐しゃく【賃借】
〔法〕賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をすること。
⇒ちんしゃく‐けん【賃借権】
⇒ちんしゃく‐にん【賃借人】
ちんしゃく‐けん【賃借権】
賃貸借契約に基づいて賃借人が有する債権、すなわち賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求しうる権利。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃく‐にん【賃借人】
賃貸借の当事者たる借り主。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃ‐ち【沈砂池】
(チンサチとも)水道・用水・発電などのために河川から水を取り入れる場合、流入した土砂を沈殿させるための人工池。
ちん‐しゅ【沈朱】
沈金彫の一種。金箔の代りに朱漆を用いたもの。
ちん‐しゅ【珍種】
珍しい種類。珍しい品種。「蘭の―」
ちん‐しゅ【鴆酒・酖酒】
鴆毒をまぜた酒。毒酒。
ちん‐じゅ【陳寿】
西晋の歴史家。字は承祚。四川安漢の人。中国正史の一つである「三国志」のほか、「益都耆旧伝」などの著がある。(233〜297)
ちん‐じゅ【椿寿】
[荘子逍遥遊「上古に大椿なる者有り、八千歳を以て春と為なし、八千歳を以て秋と為す」]長寿。長命。椿齢。→大椿だいちゅん。
⇒ちんじゅ‐き【椿寿忌】
ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
①兵士を駐在させて、その地を鎮め守ること。
②その地を鎮め守る神。また、その社。
⇒ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
⇒ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
⇒ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
⇒ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
⇒ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
⇒ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】
ちん‐しゅう【珍羞】‥シウ
(「羞」は食物をすすめる意)めずらしくてうまい食物。珍膳。
ちん‐じゅう【珍什】‥ジフ
めずらしい什器。珍器。
ちん‐じゅう【珍獣】‥ジウ
数が少なく、外見や生態が珍しいけもの。
ちんじゅ‐き【椿寿忌】
俳人高浜虚子の忌日。〈[季]春〉→虚子忌
⇒ちん‐じゅ【椿寿】
ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
仏寺の鎮守のために建てた神社。地主の神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐じゅつ【陳述】
①意見などを口頭で述べること。特に、訴訟当事者または訴訟関係人が、裁判所に対し、その係争事件について口頭または書面で述べること。
②言語表現において、個々の語の内容を統合し、具体的な表現として成り立たせる作用。山田孝雄の用語から一般化したが、学説により定義は異なる。
⇒ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
⇒ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
民事訴訟において、当事者本人または証人の言い分を書面にして裁判所に提出するもの。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
陳述に一定の意味の語が来るように作用する副詞。「決して(ない)」「たぶん(だろう)」「まるで(ようだ)」の類。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
一国・王城・院・城内・土地・寺院・邸宅・氏などを鎮護する神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
鎮守の社の境内にある森。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
土地の鎮守の神をまつった社。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
①古代、蝦夷えぞを鎮圧するために陸奥国むつのくにに置かれた官庁。初め多賀城に置き、後に胆沢いさわ城などに移した。
②明治以後、各海軍区の警備・防御、所管の出征準備に関することをつかさどり、所属部隊を指揮監督した海軍の機関。横須賀・呉・佐世保・舞鶴の各軍港に置いた。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】‥シヤウ‥
古代、鎮守府の長官。その下に、副将軍・権副将軍・将監(のち軍監)・将曹(のち軍曹)・弩師どし・医師・陰陽師各一人を置いた。鎮東将軍。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐しょ【珍書】
めずらしい書籍。珍本。
ちん‐しょ【砧杵】
きぬたとそれを打つ槌つち。きぬたを打つ槌、またはそれを打つ音。
ちん‐しょ【鎮所】
兵士がその土地をしずめ守るために駐在する所。鎮守府。
ちんじょ【陳書】
二十四史の一つ。南朝の陳の史書。唐の姚思廉ようしれんが太宗の勅命を奉じて撰し、636年成る。北宋の仁宗がこれを曾鞏そうきょうらに校訂させて刊行。本紀6巻、列伝30巻。
ちん‐しょう【沈床】‥シヤウ
木・コンクリートで枠を作り、その中に石を詰めて沈設した工作物。堤防や護岸工事などの基礎や根固めとして用いる。
ちん‐しょう【沈鐘】
淵や池や沼の底に沈んでいるという伝説の鐘。
⇒ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
ちん‐しょう【陳勝】
秦滅亡のきっかけをつくった反乱の指導者。字は渉。陽城(河南)の人。地主の雇い人であったが、前209年、呉広(陽夏(河南)の人、字は叔)と共に秦に叛し自立して楚王と称したが、秦軍に敗れ、呉広にあいつぎ部下に殺された。( 〜前209)
⇒ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】
ちん‐じょう【枕上】‥ジヤウ
①枕のほとり。まくらもと。
②枕をしている状態。
ちん‐じょう【陳状】‥ジヤウ
①意見などを述べた文書。
②中世、訴人(原告)の訴状に対して論人(被告)の提出した答弁書。
③歌合の判定についての不服を判者に申し立てる書状。
ちん‐じょう【陳情】‥ジヤウ
①実情を述べること。心事を述べること。
②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。「―団」
⇒ちんじょう‐ひょう【陳情表】
ちん‐しょうう【陳紹禹】‥セウ‥
(Chen Shaoyu)中国の政治家。安徽六安の人。別名、王明。モスクワ留学中に中国共産党に加入。1931年党総書記。親ソ派として終始毛沢東と対立、モスクワで死去。(1907〜1974)
ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】‥クワウ
(ともに兵を挙げて秦滅亡の端を開いたからいう)ある事のさきがけをすること。また、その人。陳呉。
⇒ちん‐しょう【陳勝】
ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
伝説の一類型。鐘を霊物とし、水界を支配する主と密接な関係を有すると考え、池沼・湖海などに多い。日本では諸所にある「鐘ヶ淵」は、普通にこの伝説を持っているが、俵藤太の竜宮の鐘を奪う伝説が最も著名。
⇒ちん‐しょう【沈鐘】
ちんじょう‐ひょう【陳情表】‥ジヤウヘウ
晋の李密の作。武帝が太子晋の洗馬(太子に奉仕する官名)に任じようとした時、祖母劉氏が90歳余で侍養する者がないために拝辞した上奏文。読む者を感泣させ、古く諸葛孔明の「出師表すいしのひょう」と並称。
⇒ちん‐じょう【陳情】
ちんじょう‐ようがん【枕状溶岩】‥ジヤウ‥
⇒まくらじょうようがん
ちん‐しょく【陳寔】
後漢の地方官。字は仲弓。潁川えいせん許(河南)の人。県吏となり、累進して太丘県長となり、徳をもって治める。盗賊が入って梁上に隠れた時、子弟を訓戒し、「梁上の君子を見よ」といって盗賊を悔悟させた逸話は有名。(104〜187)
ちん‐す【鎮子】
⇒ちんし
ちん・ず【鎮ず】
〔他サ変〕
騒ぎなどをしずめる。霊魂などをなぐさめ安らかにする。今昔物語集14「身を固め―・じて居たりけるに」
ちん‐すい【沈水】
①水に沈むこと。
②(堅く重くて水に沈むからいう)沈香じんこうの木。
⇒ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
⇒ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
⇒ちんすい‐よう【沈水葉】
ちん‐すい【沈酔】
酒に酔いつぶれること。古今著聞集18「康光すでに―に及べり」
ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
(→)沈降海岸に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
体の全部が水中にあり固着生活をする植物。フサモ・キンギョモなど。水中植物。→水生植物。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すいへん【陳水扁】
(Chen Shuibian; Ch‘ên Shui-pien)台湾の政治家。台南生れ。台湾大学卒業後、弁護士として活動。1994年初の民選台北市長、2000年中華民国総統。(1951〜)
ちんすい‐よう【沈水葉】‥エフ
(→)水葉に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すごう【陳子昂】‥ガウ
初唐の詩人。字は伯玉。梓州射洪(四川射洪)の人。質朴で慷慨の気に富む詩を作り、盛唐詩の先駆と評される。則天武后の時、右拾遺うしゅういとなる。著「陳伯玉文集」。(661?〜702?)
ちん・ずる【陳ずる】
〔他サ変〕[文]陳ず(サ変)
①口頭で述べる。
②言い張る。主張する。釈明する。
③嘘を言う。浄瑠璃、出世景清「真直に申せ、少しも―・ぜば拷問せん」
ちん‐せい【沈静】
おちついてしずかなこと。気勢がしずまること。「インフレが―する」
ちん‐せい【陳誠】
(Chen Cheng)中国の軍人。浙江青田の人。国民政府の軍政部長・参謀総長などを歴任。国共内戦で敗退後、台湾で行政院長・副総統。(1896〜1965)
ちん‐せい【鎮星】
五星の一つ。土星の漢名。填星てんせい。
ちん‐せい【鎮静】
騒ぎ・気持などがしずまってしずかなこと。また、しずめおちつかせること。「興奮を―する」
⇒ちんせい‐ざい【鎮静剤】
ちん‐ぜい【鎮西】
(743〜745年、大宰府を鎮西府と改称したからいう)九州の称。
⇒ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
⇒ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
⇒ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
⇒ちんぜい‐は【鎮西派】
⇒ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】
⇒ちんぜい‐ふ【鎮西府】
⇒ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】
ちんせい‐ざい【鎮静剤】
神経作用を鎮静するための薬剤。中枢抑制作用のあるバルビタールなど。かつては臭素剤・吉草根きっそうこんなどが用いられた。
⇒ちん‐せい【鎮静】
ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
(→)鎮西奉行に同じ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
鎌倉幕府の機関。蒙古襲来にそなえて九州御家人の関東への参訴を禁じたのに対応し、現地で訴訟を処理報告させるため博多に設置。1286年(弘安9)から鎮西探題発足まで存続。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
鎌倉幕府が博多に置いた統治機関。九州および壱岐・対馬二島の軍事・警察・裁判をつかさどり、辺海警備にあたった。1293年(永仁1)北条兼時を遣わしたのに始まる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐は【鎮西派】
浄土宗五流の一派。京都知恩院を総本山とし、念仏往生を正業とするとともに諸行往生をも認める。法然の弟子で九州に布教した聖光房弁長を祖とする。現在の浄土宗はこの流れをくむ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】‥ラウ
源為朝みなもとのためともの通称。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ふ【鎮西府】
743年(天平15)大宰府を改称した九州統督の府。将軍ほかの職員があった。745年大宰府復置により廃止。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】‥ギヤウ
鎌倉幕府が設けた統治機関。また、その長の呼称。1185年(文治1)天野遠景が初めてこれに任ぜられ、九州地方の管理・成敗をつかさどった。のち鎮西談議所の、ついで鎮西探題の一環となる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちん‐せき【沈積】
水中にある物質が水底に沈みつもること。堆積たいせき。
⇒ちんせき‐がん【沈積岩】
ちん‐せき【枕席】
(まくらとしきものの意)寝具。ねどこ。
⇒枕席に侍る
ちん‐せき【珍籍】
めずらしい書籍。珍書。
ちんせき‐がん【沈積岩】
(→)堆積岩に同じ。
⇒ちん‐せき【沈積】
ちんせき‐そうりゅう【枕石漱流】‥リウ
「石に枕し流れに漱くちすすぐ」に同じ。→石いし(成句)
 チングルマ(花)
提供:OPO
チングルマ(花)
提供:OPO
 チングルマ(実)
提供:OPO
チングルマ(実)
提供:OPO
 ちんけ
(さいころばくちで一の目を「ちん」ということから)貧相なさま。器量の小さいさま。「―なことをするな」
ちん‐げい【珍芸】
めったに見られない珍しい芸。一風変わっていておもしろい芸。「―を披露する」
ちんけい‐ざい【鎮痙剤】
痙攣けいれんをしずめる薬剤。
ちん‐けいじゅ【陳継儒】
明代の文人。江蘇華亭(現在の上海)の人。字は仲醇、号は眉公。詩文書画にすぐれ、隠者として暮らす一方で、数多くの書物を編纂出版。(1558〜1639)
チンゲンサイ【青梗菜】
(中国語)中国野菜の一品種。パクチョイのうち、葉柄が緑色になるもの。
ちん‐げんぴん【陳元贇】
(本来はチンゲンインとよむ)明の詩人・陶工。字は義都、既白山人と号。1619年(元和5)乱を避けて来日、名古屋藩主徳川義直に仕える。僧元政と交わり、拳法にも秀でた。名古屋で没。(1587〜1671)→元贇焼
ちんこ
①体の非常に小さい人。こども。
②(幼児語)陰茎。ちんちん。ちんぼこ。
⇒ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
ちん‐ご【陳呉】
陳勝呉広ちんしょうごこうの略。
ちん‐ご【鎮護】
しずめまもること。乱を鎮め国を護ること。宴曲集2「―の道場頼みあり」
⇒ちんご‐こっか【鎮護国家】
ちん‐こう【沈降】‥カウ
①しずみくだること。沈下。
②よどむこと。沈殿。
⇒ちんこう‐かいがん【沈降海岸】
⇒ちんこう‐はんのう【沈降反応】
ちん‐こう【珍肴】‥カウ
めずらしいさかな。めずらしいごちそう。
ちんこう【鎮江】‥カウ
(Zhenjiang)中国、江蘇省南西部の都市。大運河と長江の交点に位置し、対岸の揚州と並んで江南地方の物資の集散地として繁栄。近年工業が盛ん。古称は朱方・京口。人口69万6千(2000)。
ちんこう‐かいがん【沈降海岸】‥カウ‥
地盤の沈降によって生じたと考えられる海岸。多くは海面の上昇によって生じたものとの判別が難しい。沈水海岸。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こうじゅ【陳洪綬】
明末の画家。字は章侯。号は老蓮。浙江諸曁しょきの人。仏画・人物画に優れ、デフォルメされた形態と描線が特徴。崔子忠と並び「南陳北崔」と称された。(1599〜1652)
ちん‐こうはく【陳公博】
(Chen Gongbo)中国の政治家。広東省南海生れ。北京大学・コロンビア大学に学ぶ。国民党・国民政府の要職を歴任。1940年汪兆銘を首班とする政権に加わり、第二次大戦後漢奸として逮捕・処刑。(1892〜1946)
ちんこう‐はんのう【沈降反応】‥カウ‥オウ
〔医〕試験管内で可溶性の抗原と抗体が結合して沈降物をつくる反応。特異性が高く、免疫の抗原や抗体の定性・定量に利用される。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こ‐きり【賃粉切】
手間賃を取って煙草の葉を刻むこと。また、その業者。洒落本、辰巳婦言「庖丁を引ツたくられた―か」
ちんご‐こっか【鎮護国家】‥コク‥
仏法によって国家を鎮定し守護すること。このために法華経・金光明経・仁王般若経などを読誦し、また種々の修法を行う。
⇒ちん‐ご【鎮護】
ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
江戸時代から明治初年まで行われた子供芝居。
⇒ちんこ
ちん‐こつ【砧骨】
⇒きぬたこつ
ちん‐ころ
①狆ちん。
②小犬。犬の子。
ちん‐こん【鎮魂】
①魂をおちつけしずめること。たましずめ。
②死者の魂をなぐさめしずめること。
⇒ちんこん‐か【鎮魂歌】
⇒ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
⇒ちんこん‐さい【鎮魂祭】
⇒ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
ちんこん‐か【鎮魂歌】
①死者の魂をなぐさめしずめるための歌。
②⇒たましずめのうた。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
精神をしずめて無念無想となり、一切をささげて神明に帰依すること。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐さい【鎮魂祭】
①⇒たましずめのまつり。
②神葬で、死者の魂を鎮める祭典。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
「レクイエム2」参照。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちん‐ざ【鎮座】
①神霊がその地に鎮まりいること。
②転じて、人や物がどっかりと座を占めることをからかっていう語。「団子鼻が顔のまんなかに―している」
ちん‐さい【鎮祭】
諸神を鎮め固めるための祭儀。
ちん‐さげ【賃下げ】
賃金の切り下げ。減給。
ちん‐ざしき【亭座敷】
あずまや風に作った座敷。
ちん‐さつ【鴆殺・酖殺】
鴆毒を飲ませて殺すこと。毒殺。
ちんざん【椿山】
⇒つばきちんざん(椿椿山)
ちん‐し【沈子】
釣針や網を沈めるのに用いる漁具部材。鉛・鉄・陶器などでつくる。おもり。しずみ。いわ。
ちん‐し【沈思】
おもいにしずむこと。深く考えこむこと。
⇒ちんし‐もっこう【沈思黙考】
ちん‐し【鎮子】
(チンジとも)室内の敷物・帷帳いちょうなどがあおられないように、おさえるおもし。軸物の風鎮もその一つ。ちんす。
ちん‐じ【珍事】
①珍しいこと。「前代未聞の―」
②おもいがけないできごと。一大事。椿事。
⇒ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】
ちん‐じ【椿事】
意外の出来事。非常の事件。珍事。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「如何なる―を惹起さうも知れぬと」
ちん‐しごと【賃仕事】
賃銭をとってする手仕事。
ちんじ‐さい【鎮地祭】‥ヂ‥
伊勢神宮で、式年造営前、大宮地の神に対して工程の無事完了を祈願する祭。
ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】‥エウ
(「珍事中庸」とも書く)
①非常な災難。義経記2「―にあふ事つねの事なり」
②珍しいこと。
⇒ちん‐じ【珍事】
ちん‐しどう【陳師道】‥ダウ
北宋の詩人。字は履常りじょう・無己。号は後山居士。彭城(江蘇省徐州)の人。詩は杜甫を尊重し、黄庭堅とともに江西詩派の祖とされる。著「後山居士文集」。(1053〜1101)
ちん‐しま【賃縞】
賃仕事として内職に織る木綿縞織物。
ちんし‐もっこう【沈思黙考】‥モクカウ
黙って深くじっくりと考えること。
⇒ちん‐し【沈思】
ちん‐しゃ【枕藉】
互いを枕にしてよりかかり、相重なって臥すこと。
ちん‐しゃ【陳謝】
①わけをのべてあやまること。「深く―致します」
②礼を言うこと。
チンジャオロース【青椒肉絲】
(中国語)中国料理の一つ。ピーマン・牛肉を細切りにして炒め、オイスター‐ソースなどで調味したもの。
ちん‐しゃく【賃借】
〔法〕賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をすること。
⇒ちんしゃく‐けん【賃借権】
⇒ちんしゃく‐にん【賃借人】
ちんしゃく‐けん【賃借権】
賃貸借契約に基づいて賃借人が有する債権、すなわち賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求しうる権利。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃく‐にん【賃借人】
賃貸借の当事者たる借り主。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃ‐ち【沈砂池】
(チンサチとも)水道・用水・発電などのために河川から水を取り入れる場合、流入した土砂を沈殿させるための人工池。
ちん‐しゅ【沈朱】
沈金彫の一種。金箔の代りに朱漆を用いたもの。
ちん‐しゅ【珍種】
珍しい種類。珍しい品種。「蘭の―」
ちん‐しゅ【鴆酒・酖酒】
鴆毒をまぜた酒。毒酒。
ちん‐じゅ【陳寿】
西晋の歴史家。字は承祚。四川安漢の人。中国正史の一つである「三国志」のほか、「益都耆旧伝」などの著がある。(233〜297)
ちん‐じゅ【椿寿】
[荘子逍遥遊「上古に大椿なる者有り、八千歳を以て春と為なし、八千歳を以て秋と為す」]長寿。長命。椿齢。→大椿だいちゅん。
⇒ちんじゅ‐き【椿寿忌】
ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
①兵士を駐在させて、その地を鎮め守ること。
②その地を鎮め守る神。また、その社。
⇒ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
⇒ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
⇒ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
⇒ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
⇒ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
⇒ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】
ちん‐しゅう【珍羞】‥シウ
(「羞」は食物をすすめる意)めずらしくてうまい食物。珍膳。
ちん‐じゅう【珍什】‥ジフ
めずらしい什器。珍器。
ちん‐じゅう【珍獣】‥ジウ
数が少なく、外見や生態が珍しいけもの。
ちんじゅ‐き【椿寿忌】
俳人高浜虚子の忌日。〈[季]春〉→虚子忌
⇒ちん‐じゅ【椿寿】
ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
仏寺の鎮守のために建てた神社。地主の神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐じゅつ【陳述】
①意見などを口頭で述べること。特に、訴訟当事者または訴訟関係人が、裁判所に対し、その係争事件について口頭または書面で述べること。
②言語表現において、個々の語の内容を統合し、具体的な表現として成り立たせる作用。山田孝雄の用語から一般化したが、学説により定義は異なる。
⇒ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
⇒ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
民事訴訟において、当事者本人または証人の言い分を書面にして裁判所に提出するもの。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
陳述に一定の意味の語が来るように作用する副詞。「決して(ない)」「たぶん(だろう)」「まるで(ようだ)」の類。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
一国・王城・院・城内・土地・寺院・邸宅・氏などを鎮護する神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
鎮守の社の境内にある森。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
土地の鎮守の神をまつった社。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
①古代、蝦夷えぞを鎮圧するために陸奥国むつのくにに置かれた官庁。初め多賀城に置き、後に胆沢いさわ城などに移した。
②明治以後、各海軍区の警備・防御、所管の出征準備に関することをつかさどり、所属部隊を指揮監督した海軍の機関。横須賀・呉・佐世保・舞鶴の各軍港に置いた。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】‥シヤウ‥
古代、鎮守府の長官。その下に、副将軍・権副将軍・将監(のち軍監)・将曹(のち軍曹)・弩師どし・医師・陰陽師各一人を置いた。鎮東将軍。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐しょ【珍書】
めずらしい書籍。珍本。
ちん‐しょ【砧杵】
きぬたとそれを打つ槌つち。きぬたを打つ槌、またはそれを打つ音。
ちん‐しょ【鎮所】
兵士がその土地をしずめ守るために駐在する所。鎮守府。
ちんじょ【陳書】
二十四史の一つ。南朝の陳の史書。唐の姚思廉ようしれんが太宗の勅命を奉じて撰し、636年成る。北宋の仁宗がこれを曾鞏そうきょうらに校訂させて刊行。本紀6巻、列伝30巻。
ちん‐しょう【沈床】‥シヤウ
木・コンクリートで枠を作り、その中に石を詰めて沈設した工作物。堤防や護岸工事などの基礎や根固めとして用いる。
ちん‐しょう【沈鐘】
淵や池や沼の底に沈んでいるという伝説の鐘。
⇒ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
ちん‐しょう【陳勝】
秦滅亡のきっかけをつくった反乱の指導者。字は渉。陽城(河南)の人。地主の雇い人であったが、前209年、呉広(陽夏(河南)の人、字は叔)と共に秦に叛し自立して楚王と称したが、秦軍に敗れ、呉広にあいつぎ部下に殺された。( 〜前209)
⇒ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】
ちん‐じょう【枕上】‥ジヤウ
①枕のほとり。まくらもと。
②枕をしている状態。
ちん‐じょう【陳状】‥ジヤウ
①意見などを述べた文書。
②中世、訴人(原告)の訴状に対して論人(被告)の提出した答弁書。
③歌合の判定についての不服を判者に申し立てる書状。
ちん‐じょう【陳情】‥ジヤウ
①実情を述べること。心事を述べること。
②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。「―団」
⇒ちんじょう‐ひょう【陳情表】
ちん‐しょうう【陳紹禹】‥セウ‥
(Chen Shaoyu)中国の政治家。安徽六安の人。別名、王明。モスクワ留学中に中国共産党に加入。1931年党総書記。親ソ派として終始毛沢東と対立、モスクワで死去。(1907〜1974)
ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】‥クワウ
(ともに兵を挙げて秦滅亡の端を開いたからいう)ある事のさきがけをすること。また、その人。陳呉。
⇒ちん‐しょう【陳勝】
ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
伝説の一類型。鐘を霊物とし、水界を支配する主と密接な関係を有すると考え、池沼・湖海などに多い。日本では諸所にある「鐘ヶ淵」は、普通にこの伝説を持っているが、俵藤太の竜宮の鐘を奪う伝説が最も著名。
⇒ちん‐しょう【沈鐘】
ちんじょう‐ひょう【陳情表】‥ジヤウヘウ
晋の李密の作。武帝が太子晋の洗馬(太子に奉仕する官名)に任じようとした時、祖母劉氏が90歳余で侍養する者がないために拝辞した上奏文。読む者を感泣させ、古く諸葛孔明の「出師表すいしのひょう」と並称。
⇒ちん‐じょう【陳情】
ちんじょう‐ようがん【枕状溶岩】‥ジヤウ‥
⇒まくらじょうようがん
ちん‐しょく【陳寔】
後漢の地方官。字は仲弓。潁川えいせん許(河南)の人。県吏となり、累進して太丘県長となり、徳をもって治める。盗賊が入って梁上に隠れた時、子弟を訓戒し、「梁上の君子を見よ」といって盗賊を悔悟させた逸話は有名。(104〜187)
ちん‐す【鎮子】
⇒ちんし
ちん・ず【鎮ず】
〔他サ変〕
騒ぎなどをしずめる。霊魂などをなぐさめ安らかにする。今昔物語集14「身を固め―・じて居たりけるに」
ちん‐すい【沈水】
①水に沈むこと。
②(堅く重くて水に沈むからいう)沈香じんこうの木。
⇒ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
⇒ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
⇒ちんすい‐よう【沈水葉】
ちん‐すい【沈酔】
酒に酔いつぶれること。古今著聞集18「康光すでに―に及べり」
ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
(→)沈降海岸に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
体の全部が水中にあり固着生活をする植物。フサモ・キンギョモなど。水中植物。→水生植物。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すいへん【陳水扁】
(Chen Shuibian; Ch‘ên Shui-pien)台湾の政治家。台南生れ。台湾大学卒業後、弁護士として活動。1994年初の民選台北市長、2000年中華民国総統。(1951〜)
ちんすい‐よう【沈水葉】‥エフ
(→)水葉に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すごう【陳子昂】‥ガウ
初唐の詩人。字は伯玉。梓州射洪(四川射洪)の人。質朴で慷慨の気に富む詩を作り、盛唐詩の先駆と評される。則天武后の時、右拾遺うしゅういとなる。著「陳伯玉文集」。(661?〜702?)
ちん・ずる【陳ずる】
〔他サ変〕[文]陳ず(サ変)
①口頭で述べる。
②言い張る。主張する。釈明する。
③嘘を言う。浄瑠璃、出世景清「真直に申せ、少しも―・ぜば拷問せん」
ちん‐せい【沈静】
おちついてしずかなこと。気勢がしずまること。「インフレが―する」
ちん‐せい【陳誠】
(Chen Cheng)中国の軍人。浙江青田の人。国民政府の軍政部長・参謀総長などを歴任。国共内戦で敗退後、台湾で行政院長・副総統。(1896〜1965)
ちん‐せい【鎮星】
五星の一つ。土星の漢名。填星てんせい。
ちん‐せい【鎮静】
騒ぎ・気持などがしずまってしずかなこと。また、しずめおちつかせること。「興奮を―する」
⇒ちんせい‐ざい【鎮静剤】
ちん‐ぜい【鎮西】
(743〜745年、大宰府を鎮西府と改称したからいう)九州の称。
⇒ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
⇒ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
⇒ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
⇒ちんぜい‐は【鎮西派】
⇒ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】
⇒ちんぜい‐ふ【鎮西府】
⇒ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】
ちんせい‐ざい【鎮静剤】
神経作用を鎮静するための薬剤。中枢抑制作用のあるバルビタールなど。かつては臭素剤・吉草根きっそうこんなどが用いられた。
⇒ちん‐せい【鎮静】
ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
(→)鎮西奉行に同じ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
鎌倉幕府の機関。蒙古襲来にそなえて九州御家人の関東への参訴を禁じたのに対応し、現地で訴訟を処理報告させるため博多に設置。1286年(弘安9)から鎮西探題発足まで存続。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
鎌倉幕府が博多に置いた統治機関。九州および壱岐・対馬二島の軍事・警察・裁判をつかさどり、辺海警備にあたった。1293年(永仁1)北条兼時を遣わしたのに始まる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐は【鎮西派】
浄土宗五流の一派。京都知恩院を総本山とし、念仏往生を正業とするとともに諸行往生をも認める。法然の弟子で九州に布教した聖光房弁長を祖とする。現在の浄土宗はこの流れをくむ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】‥ラウ
源為朝みなもとのためともの通称。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ふ【鎮西府】
743年(天平15)大宰府を改称した九州統督の府。将軍ほかの職員があった。745年大宰府復置により廃止。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】‥ギヤウ
鎌倉幕府が設けた統治機関。また、その長の呼称。1185年(文治1)天野遠景が初めてこれに任ぜられ、九州地方の管理・成敗をつかさどった。のち鎮西談議所の、ついで鎮西探題の一環となる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちん‐せき【沈積】
水中にある物質が水底に沈みつもること。堆積たいせき。
⇒ちんせき‐がん【沈積岩】
ちん‐せき【枕席】
(まくらとしきものの意)寝具。ねどこ。
⇒枕席に侍る
ちん‐せき【珍籍】
めずらしい書籍。珍書。
ちんせき‐がん【沈積岩】
(→)堆積岩に同じ。
⇒ちん‐せき【沈積】
ちんせき‐そうりゅう【枕石漱流】‥リウ
「石に枕し流れに漱くちすすぐ」に同じ。→石いし(成句)
ちんけ
(さいころばくちで一の目を「ちん」ということから)貧相なさま。器量の小さいさま。「―なことをするな」
ちん‐げい【珍芸】
めったに見られない珍しい芸。一風変わっていておもしろい芸。「―を披露する」
ちんけい‐ざい【鎮痙剤】
痙攣けいれんをしずめる薬剤。
ちん‐けいじゅ【陳継儒】
明代の文人。江蘇華亭(現在の上海)の人。字は仲醇、号は眉公。詩文書画にすぐれ、隠者として暮らす一方で、数多くの書物を編纂出版。(1558〜1639)
チンゲンサイ【青梗菜】
(中国語)中国野菜の一品種。パクチョイのうち、葉柄が緑色になるもの。
ちん‐げんぴん【陳元贇】
(本来はチンゲンインとよむ)明の詩人・陶工。字は義都、既白山人と号。1619年(元和5)乱を避けて来日、名古屋藩主徳川義直に仕える。僧元政と交わり、拳法にも秀でた。名古屋で没。(1587〜1671)→元贇焼
ちんこ
①体の非常に小さい人。こども。
②(幼児語)陰茎。ちんちん。ちんぼこ。
⇒ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
ちん‐ご【陳呉】
陳勝呉広ちんしょうごこうの略。
ちん‐ご【鎮護】
しずめまもること。乱を鎮め国を護ること。宴曲集2「―の道場頼みあり」
⇒ちんご‐こっか【鎮護国家】
ちん‐こう【沈降】‥カウ
①しずみくだること。沈下。
②よどむこと。沈殿。
⇒ちんこう‐かいがん【沈降海岸】
⇒ちんこう‐はんのう【沈降反応】
ちん‐こう【珍肴】‥カウ
めずらしいさかな。めずらしいごちそう。
ちんこう【鎮江】‥カウ
(Zhenjiang)中国、江蘇省南西部の都市。大運河と長江の交点に位置し、対岸の揚州と並んで江南地方の物資の集散地として繁栄。近年工業が盛ん。古称は朱方・京口。人口69万6千(2000)。
ちんこう‐かいがん【沈降海岸】‥カウ‥
地盤の沈降によって生じたと考えられる海岸。多くは海面の上昇によって生じたものとの判別が難しい。沈水海岸。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こうじゅ【陳洪綬】
明末の画家。字は章侯。号は老蓮。浙江諸曁しょきの人。仏画・人物画に優れ、デフォルメされた形態と描線が特徴。崔子忠と並び「南陳北崔」と称された。(1599〜1652)
ちん‐こうはく【陳公博】
(Chen Gongbo)中国の政治家。広東省南海生れ。北京大学・コロンビア大学に学ぶ。国民党・国民政府の要職を歴任。1940年汪兆銘を首班とする政権に加わり、第二次大戦後漢奸として逮捕・処刑。(1892〜1946)
ちんこう‐はんのう【沈降反応】‥カウ‥オウ
〔医〕試験管内で可溶性の抗原と抗体が結合して沈降物をつくる反応。特異性が高く、免疫の抗原や抗体の定性・定量に利用される。
⇒ちん‐こう【沈降】
ちん‐こ‐きり【賃粉切】
手間賃を取って煙草の葉を刻むこと。また、その業者。洒落本、辰巳婦言「庖丁を引ツたくられた―か」
ちんご‐こっか【鎮護国家】‥コク‥
仏法によって国家を鎮定し守護すること。このために法華経・金光明経・仁王般若経などを読誦し、また種々の修法を行う。
⇒ちん‐ご【鎮護】
ちんこ‐しばい【ちんこ芝居】
江戸時代から明治初年まで行われた子供芝居。
⇒ちんこ
ちん‐こつ【砧骨】
⇒きぬたこつ
ちん‐ころ
①狆ちん。
②小犬。犬の子。
ちん‐こん【鎮魂】
①魂をおちつけしずめること。たましずめ。
②死者の魂をなぐさめしずめること。
⇒ちんこん‐か【鎮魂歌】
⇒ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
⇒ちんこん‐さい【鎮魂祭】
⇒ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
ちんこん‐か【鎮魂歌】
①死者の魂をなぐさめしずめるための歌。
②⇒たましずめのうた。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐きしん【鎮魂帰神】
精神をしずめて無念無想となり、一切をささげて神明に帰依すること。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐さい【鎮魂祭】
①⇒たましずめのまつり。
②神葬で、死者の魂を鎮める祭典。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちんこん‐ミサきょく【鎮魂ミサ曲】
「レクイエム2」参照。
⇒ちん‐こん【鎮魂】
ちん‐ざ【鎮座】
①神霊がその地に鎮まりいること。
②転じて、人や物がどっかりと座を占めることをからかっていう語。「団子鼻が顔のまんなかに―している」
ちん‐さい【鎮祭】
諸神を鎮め固めるための祭儀。
ちん‐さげ【賃下げ】
賃金の切り下げ。減給。
ちん‐ざしき【亭座敷】
あずまや風に作った座敷。
ちん‐さつ【鴆殺・酖殺】
鴆毒を飲ませて殺すこと。毒殺。
ちんざん【椿山】
⇒つばきちんざん(椿椿山)
ちん‐し【沈子】
釣針や網を沈めるのに用いる漁具部材。鉛・鉄・陶器などでつくる。おもり。しずみ。いわ。
ちん‐し【沈思】
おもいにしずむこと。深く考えこむこと。
⇒ちんし‐もっこう【沈思黙考】
ちん‐し【鎮子】
(チンジとも)室内の敷物・帷帳いちょうなどがあおられないように、おさえるおもし。軸物の風鎮もその一つ。ちんす。
ちん‐じ【珍事】
①珍しいこと。「前代未聞の―」
②おもいがけないできごと。一大事。椿事。
⇒ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】
ちん‐じ【椿事】
意外の出来事。非常の事件。珍事。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「如何なる―を惹起さうも知れぬと」
ちん‐しごと【賃仕事】
賃銭をとってする手仕事。
ちんじ‐さい【鎮地祭】‥ヂ‥
伊勢神宮で、式年造営前、大宮地の神に対して工程の無事完了を祈願する祭。
ちんじ‐ちゅうよう【珍事中夭】‥エウ
(「珍事中庸」とも書く)
①非常な災難。義経記2「―にあふ事つねの事なり」
②珍しいこと。
⇒ちん‐じ【珍事】
ちん‐しどう【陳師道】‥ダウ
北宋の詩人。字は履常りじょう・無己。号は後山居士。彭城(江蘇省徐州)の人。詩は杜甫を尊重し、黄庭堅とともに江西詩派の祖とされる。著「後山居士文集」。(1053〜1101)
ちん‐しま【賃縞】
賃仕事として内職に織る木綿縞織物。
ちんし‐もっこう【沈思黙考】‥モクカウ
黙って深くじっくりと考えること。
⇒ちん‐し【沈思】
ちん‐しゃ【枕藉】
互いを枕にしてよりかかり、相重なって臥すこと。
ちん‐しゃ【陳謝】
①わけをのべてあやまること。「深く―致します」
②礼を言うこと。
チンジャオロース【青椒肉絲】
(中国語)中国料理の一つ。ピーマン・牛肉を細切りにして炒め、オイスター‐ソースなどで調味したもの。
ちん‐しゃく【賃借】
〔法〕賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をすること。
⇒ちんしゃく‐けん【賃借権】
⇒ちんしゃく‐にん【賃借人】
ちんしゃく‐けん【賃借権】
賃貸借契約に基づいて賃借人が有する債権、すなわち賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求しうる権利。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃく‐にん【賃借人】
賃貸借の当事者たる借り主。
⇒ちん‐しゃく【賃借】
ちんしゃ‐ち【沈砂池】
(チンサチとも)水道・用水・発電などのために河川から水を取り入れる場合、流入した土砂を沈殿させるための人工池。
ちん‐しゅ【沈朱】
沈金彫の一種。金箔の代りに朱漆を用いたもの。
ちん‐しゅ【珍種】
珍しい種類。珍しい品種。「蘭の―」
ちん‐しゅ【鴆酒・酖酒】
鴆毒をまぜた酒。毒酒。
ちん‐じゅ【陳寿】
西晋の歴史家。字は承祚。四川安漢の人。中国正史の一つである「三国志」のほか、「益都耆旧伝」などの著がある。(233〜297)
ちん‐じゅ【椿寿】
[荘子逍遥遊「上古に大椿なる者有り、八千歳を以て春と為なし、八千歳を以て秋と為す」]長寿。長命。椿齢。→大椿だいちゅん。
⇒ちんじゅ‐き【椿寿忌】
ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
①兵士を駐在させて、その地を鎮め守ること。
②その地を鎮め守る神。また、その社。
⇒ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
⇒ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
⇒ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
⇒ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
⇒ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
⇒ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】
ちん‐しゅう【珍羞】‥シウ
(「羞」は食物をすすめる意)めずらしくてうまい食物。珍膳。
ちん‐じゅう【珍什】‥ジフ
めずらしい什器。珍器。
ちん‐じゅう【珍獣】‥ジウ
数が少なく、外見や生態が珍しいけもの。
ちんじゅ‐き【椿寿忌】
俳人高浜虚子の忌日。〈[季]春〉→虚子忌
⇒ちん‐じゅ【椿寿】
ちんじゅ‐しゃ【鎮守社】
仏寺の鎮守のために建てた神社。地主の神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐じゅつ【陳述】
①意見などを口頭で述べること。特に、訴訟当事者または訴訟関係人が、裁判所に対し、その係争事件について口頭または書面で述べること。
②言語表現において、個々の語の内容を統合し、具体的な表現として成り立たせる作用。山田孝雄の用語から一般化したが、学説により定義は異なる。
⇒ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
⇒ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
ちんじゅつ‐しょ【陳述書】
民事訴訟において、当事者本人または証人の言い分を書面にして裁判所に提出するもの。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅつ‐ふくし【陳述副詞】
陳述に一定の意味の語が来るように作用する副詞。「決して(ない)」「たぶん(だろう)」「まるで(ようだ)」の類。
⇒ちん‐じゅつ【陳述】
ちんじゅ‐の‐かみ【鎮守の神】
一国・王城・院・城内・土地・寺院・邸宅・氏などを鎮護する神。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐もり【鎮守の杜】
鎮守の社の境内にある森。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐の‐やしろ【鎮守の社】
土地の鎮守の神をまつった社。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅ‐ふ【鎮守府】
①古代、蝦夷えぞを鎮圧するために陸奥国むつのくにに置かれた官庁。初め多賀城に置き、後に胆沢いさわ城などに移した。
②明治以後、各海軍区の警備・防御、所管の出征準備に関することをつかさどり、所属部隊を指揮監督した海軍の機関。横須賀・呉・佐世保・舞鶴の各軍港に置いた。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちんじゅふ‐しょうぐん【鎮守府将軍】‥シヤウ‥
古代、鎮守府の長官。その下に、副将軍・権副将軍・将監(のち軍監)・将曹(のち軍曹)・弩師どし・医師・陰陽師各一人を置いた。鎮東将軍。
⇒ちん‐じゅ【鎮守・鎮主】
ちん‐しょ【珍書】
めずらしい書籍。珍本。
ちん‐しょ【砧杵】
きぬたとそれを打つ槌つち。きぬたを打つ槌、またはそれを打つ音。
ちん‐しょ【鎮所】
兵士がその土地をしずめ守るために駐在する所。鎮守府。
ちんじょ【陳書】
二十四史の一つ。南朝の陳の史書。唐の姚思廉ようしれんが太宗の勅命を奉じて撰し、636年成る。北宋の仁宗がこれを曾鞏そうきょうらに校訂させて刊行。本紀6巻、列伝30巻。
ちん‐しょう【沈床】‥シヤウ
木・コンクリートで枠を作り、その中に石を詰めて沈設した工作物。堤防や護岸工事などの基礎や根固めとして用いる。
ちん‐しょう【沈鐘】
淵や池や沼の底に沈んでいるという伝説の鐘。
⇒ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
ちん‐しょう【陳勝】
秦滅亡のきっかけをつくった反乱の指導者。字は渉。陽城(河南)の人。地主の雇い人であったが、前209年、呉広(陽夏(河南)の人、字は叔)と共に秦に叛し自立して楚王と称したが、秦軍に敗れ、呉広にあいつぎ部下に殺された。( 〜前209)
⇒ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】
ちん‐じょう【枕上】‥ジヤウ
①枕のほとり。まくらもと。
②枕をしている状態。
ちん‐じょう【陳状】‥ジヤウ
①意見などを述べた文書。
②中世、訴人(原告)の訴状に対して論人(被告)の提出した答弁書。
③歌合の判定についての不服を判者に申し立てる書状。
ちん‐じょう【陳情】‥ジヤウ
①実情を述べること。心事を述べること。
②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。「―団」
⇒ちんじょう‐ひょう【陳情表】
ちん‐しょうう【陳紹禹】‥セウ‥
(Chen Shaoyu)中国の政治家。安徽六安の人。別名、王明。モスクワ留学中に中国共産党に加入。1931年党総書記。親ソ派として終始毛沢東と対立、モスクワで死去。(1907〜1974)
ちんしょう‐ごこう【陳勝呉広】‥クワウ
(ともに兵を挙げて秦滅亡の端を開いたからいう)ある事のさきがけをすること。また、その人。陳呉。
⇒ちん‐しょう【陳勝】
ちんしょう‐でんせつ【沈鐘伝説】
伝説の一類型。鐘を霊物とし、水界を支配する主と密接な関係を有すると考え、池沼・湖海などに多い。日本では諸所にある「鐘ヶ淵」は、普通にこの伝説を持っているが、俵藤太の竜宮の鐘を奪う伝説が最も著名。
⇒ちん‐しょう【沈鐘】
ちんじょう‐ひょう【陳情表】‥ジヤウヘウ
晋の李密の作。武帝が太子晋の洗馬(太子に奉仕する官名)に任じようとした時、祖母劉氏が90歳余で侍養する者がないために拝辞した上奏文。読む者を感泣させ、古く諸葛孔明の「出師表すいしのひょう」と並称。
⇒ちん‐じょう【陳情】
ちんじょう‐ようがん【枕状溶岩】‥ジヤウ‥
⇒まくらじょうようがん
ちん‐しょく【陳寔】
後漢の地方官。字は仲弓。潁川えいせん許(河南)の人。県吏となり、累進して太丘県長となり、徳をもって治める。盗賊が入って梁上に隠れた時、子弟を訓戒し、「梁上の君子を見よ」といって盗賊を悔悟させた逸話は有名。(104〜187)
ちん‐す【鎮子】
⇒ちんし
ちん・ず【鎮ず】
〔他サ変〕
騒ぎなどをしずめる。霊魂などをなぐさめ安らかにする。今昔物語集14「身を固め―・じて居たりけるに」
ちん‐すい【沈水】
①水に沈むこと。
②(堅く重くて水に沈むからいう)沈香じんこうの木。
⇒ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
⇒ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
⇒ちんすい‐よう【沈水葉】
ちん‐すい【沈酔】
酒に酔いつぶれること。古今著聞集18「康光すでに―に及べり」
ちんすい‐かいがん【沈水海岸】
(→)沈降海岸に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちんすい‐しょくぶつ【沈水植物】
体の全部が水中にあり固着生活をする植物。フサモ・キンギョモなど。水中植物。→水生植物。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すいへん【陳水扁】
(Chen Shuibian; Ch‘ên Shui-pien)台湾の政治家。台南生れ。台湾大学卒業後、弁護士として活動。1994年初の民選台北市長、2000年中華民国総統。(1951〜)
ちんすい‐よう【沈水葉】‥エフ
(→)水葉に同じ。
⇒ちん‐すい【沈水】
ちん‐すごう【陳子昂】‥ガウ
初唐の詩人。字は伯玉。梓州射洪(四川射洪)の人。質朴で慷慨の気に富む詩を作り、盛唐詩の先駆と評される。則天武后の時、右拾遺うしゅういとなる。著「陳伯玉文集」。(661?〜702?)
ちん・ずる【陳ずる】
〔他サ変〕[文]陳ず(サ変)
①口頭で述べる。
②言い張る。主張する。釈明する。
③嘘を言う。浄瑠璃、出世景清「真直に申せ、少しも―・ぜば拷問せん」
ちん‐せい【沈静】
おちついてしずかなこと。気勢がしずまること。「インフレが―する」
ちん‐せい【陳誠】
(Chen Cheng)中国の軍人。浙江青田の人。国民政府の軍政部長・参謀総長などを歴任。国共内戦で敗退後、台湾で行政院長・副総統。(1896〜1965)
ちん‐せい【鎮星】
五星の一つ。土星の漢名。填星てんせい。
ちん‐せい【鎮静】
騒ぎ・気持などがしずまってしずかなこと。また、しずめおちつかせること。「興奮を―する」
⇒ちんせい‐ざい【鎮静剤】
ちん‐ぜい【鎮西】
(743〜745年、大宰府を鎮西府と改称したからいう)九州の称。
⇒ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
⇒ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
⇒ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
⇒ちんぜい‐は【鎮西派】
⇒ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】
⇒ちんぜい‐ふ【鎮西府】
⇒ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】
ちんせい‐ざい【鎮静剤】
神経作用を鎮静するための薬剤。中枢抑制作用のあるバルビタールなど。かつては臭素剤・吉草根きっそうこんなどが用いられた。
⇒ちん‐せい【鎮静】
ちんぜい‐しゅご【鎮西守護】
(→)鎮西奉行に同じ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐だんぎしょ【鎮西談議所】
鎌倉幕府の機関。蒙古襲来にそなえて九州御家人の関東への参訴を禁じたのに対応し、現地で訴訟を処理報告させるため博多に設置。1286年(弘安9)から鎮西探題発足まで存続。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐たんだい【鎮西探題】
鎌倉幕府が博多に置いた統治機関。九州および壱岐・対馬二島の軍事・警察・裁判をつかさどり、辺海警備にあたった。1293年(永仁1)北条兼時を遣わしたのに始まる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐は【鎮西派】
浄土宗五流の一派。京都知恩院を総本山とし、念仏往生を正業とするとともに諸行往生をも認める。法然の弟子で九州に布教した聖光房弁長を祖とする。現在の浄土宗はこの流れをくむ。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐はちろう【鎮西八郎】‥ラウ
源為朝みなもとのためともの通称。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ふ【鎮西府】
743年(天平15)大宰府を改称した九州統督の府。将軍ほかの職員があった。745年大宰府復置により廃止。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】‥ギヤウ
鎌倉幕府が設けた統治機関。また、その長の呼称。1185年(文治1)天野遠景が初めてこれに任ぜられ、九州地方の管理・成敗をつかさどった。のち鎮西談議所の、ついで鎮西探題の一環となる。
⇒ちん‐ぜい【鎮西】
ちん‐せき【沈積】
水中にある物質が水底に沈みつもること。堆積たいせき。
⇒ちんせき‐がん【沈積岩】
ちん‐せき【枕席】
(まくらとしきものの意)寝具。ねどこ。
⇒枕席に侍る
ちん‐せき【珍籍】
めずらしい書籍。珍書。
ちんせき‐がん【沈積岩】
(→)堆積岩に同じ。
⇒ちん‐せき【沈積】
ちんせき‐そうりゅう【枕石漱流】‥リウ
「石に枕し流れに漱くちすすぐ」に同じ。→石いし(成句)
[漢]血🔗⭐🔉
血 字形
 筆順
筆順
 〔血部0画/6画/教育/2376・376C〕
〔音〕ケツ(漢) ケチ(呉)
〔訓〕ち
[意味]
①ち。ちしお。「血液・血管・出血・流血・貧血」
②ちのつながり。ちすじ。身うち。「血族・血縁・血統・純血・血脈けちみゃく」
③もえたぎる生命力。「血気・熱血・心血」
④ちまみれ。「血路・血戦・無血革命」
[解字]
解字
〔血部0画/6画/教育/2376・376C〕
〔音〕ケツ(漢) ケチ(呉)
〔訓〕ち
[意味]
①ち。ちしお。「血液・血管・出血・流血・貧血」
②ちのつながり。ちすじ。身うち。「血族・血縁・血統・純血・血脈けちみゃく」
③もえたぎる生命力。「血気・熱血・心血」
④ちまみれ。「血路・血戦・無血革命」
[解字]
解字 神にささげるいけにえの血のかたまりを皿(=さら)に入れたさまを示す会意文字。
[下ツキ
溢血・鬱血・悪血・温血・壊血病・喀血・吸血・給血・供血・凝血・虚血・献血・膏血・混血・採血・止血・瀉血・充血・出血・純血・心血・鮮血・造血・多血・鉄血・吐血・熱血・脳溢血・敗血症・白血病・貧血・無血・輸血・流血・冷血
神にささげるいけにえの血のかたまりを皿(=さら)に入れたさまを示す会意文字。
[下ツキ
溢血・鬱血・悪血・温血・壊血病・喀血・吸血・給血・供血・凝血・虚血・献血・膏血・混血・採血・止血・瀉血・充血・出血・純血・心血・鮮血・造血・多血・鉄血・吐血・熱血・脳溢血・敗血症・白血病・貧血・無血・輸血・流血・冷血
 筆順
筆順
 〔血部0画/6画/教育/2376・376C〕
〔音〕ケツ(漢) ケチ(呉)
〔訓〕ち
[意味]
①ち。ちしお。「血液・血管・出血・流血・貧血」
②ちのつながり。ちすじ。身うち。「血族・血縁・血統・純血・血脈けちみゃく」
③もえたぎる生命力。「血気・熱血・心血」
④ちまみれ。「血路・血戦・無血革命」
[解字]
解字
〔血部0画/6画/教育/2376・376C〕
〔音〕ケツ(漢) ケチ(呉)
〔訓〕ち
[意味]
①ち。ちしお。「血液・血管・出血・流血・貧血」
②ちのつながり。ちすじ。身うち。「血族・血縁・血統・純血・血脈けちみゃく」
③もえたぎる生命力。「血気・熱血・心血」
④ちまみれ。「血路・血戦・無血革命」
[解字]
解字 神にささげるいけにえの血のかたまりを皿(=さら)に入れたさまを示す会意文字。
[下ツキ
溢血・鬱血・悪血・温血・壊血病・喀血・吸血・給血・供血・凝血・虚血・献血・膏血・混血・採血・止血・瀉血・充血・出血・純血・心血・鮮血・造血・多血・鉄血・吐血・熱血・脳溢血・敗血症・白血病・貧血・無血・輸血・流血・冷血
神にささげるいけにえの血のかたまりを皿(=さら)に入れたさまを示す会意文字。
[下ツキ
溢血・鬱血・悪血・温血・壊血病・喀血・吸血・給血・供血・凝血・虚血・献血・膏血・混血・採血・止血・瀉血・充血・出血・純血・心血・鮮血・造血・多血・鉄血・吐血・熱血・脳溢血・敗血症・白血病・貧血・無血・輸血・流血・冷血
広辞苑に「血」で始まるの検索結果 1-83。もっと読み込む