複数辞典一括検索+![]()
![]()
余 あます🔗⭐🔉
【余】
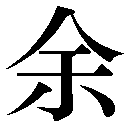 7画 人部 [五年]
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【余】旧字(A)旧字(A)
7画 人部 [五年]
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【余】旧字(A)旧字(A)
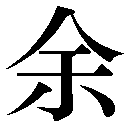 7画 人部
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【餘】旧字(B)旧字(B)
7画 人部
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【餘】旧字(B)旧字(B)
 16画 食部
区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950
《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る
《音読み》 ヨ
16画 食部
区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950
《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る
《音読み》 ヨ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる
《名付け》 われ
《意味》
(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕
(B)【餘】
〉
《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる
《名付け》 われ
《意味》
(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕
(B)【餘】 {名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕
{名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕
 {名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕
{名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕
 {名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕
{名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕
 {名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」
{名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」
 {動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」
《解字》
{動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」
《解字》
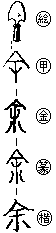 (A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。
《単語家族》
余
(A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。
《単語家族》
余 徐(ゆったり歩く)
徐(ゆったり歩く) 舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。
《類義》
→我
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。
《類義》
→我
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
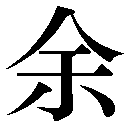 7画 人部 [五年]
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【余】旧字(A)旧字(A)
7画 人部 [五年]
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【余】旧字(A)旧字(A)
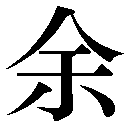 7画 人部
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【餘】旧字(B)旧字(B)
7画 人部
区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D
【餘】旧字(B)旧字(B)
 16画 食部
区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950
《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る
《音読み》 ヨ
16画 食部
区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950
《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る
《音読み》 ヨ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる
《名付け》 われ
《意味》
(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕
(B)【餘】
〉
《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる
《名付け》 われ
《意味》
(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕
(B)【餘】 {名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕
{名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕
 {名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕
{名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕
 {名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕
{名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕
 {名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」
{名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」
 {動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」
《解字》
{動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」
《解字》
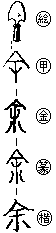 (A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。
《単語家族》
余
(A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。
《単語家族》
余 徐(ゆったり歩く)
徐(ゆったり歩く) 舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。
《類義》
→我
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。
《類義》
→我
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
冗 あまる🔗⭐🔉
【冗】
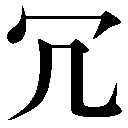 4画 冖部 [常用漢字]
区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ
4画 冖部 [常用漢字]
区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ /ニュウ
/ニュウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)
《意味》
 ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕
ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕
 {動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」
{動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」
 {動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」
《解字》
会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。
《単語家族》
怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ)
{動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」
《解字》
会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。
《単語家族》
怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ) 茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
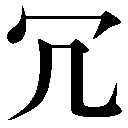 4画 冖部 [常用漢字]
区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ
4画 冖部 [常用漢字]
区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ /ニュウ
/ニュウ 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)
《意味》
 ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕
ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕
 {動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」
{動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」
 {動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」
《解字》
会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。
《単語家族》
怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ)
{動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」
《解字》
会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。
《単語家族》
怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ) 茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
剰 あます🔗⭐🔉
【剰】
 11画 リ部 [常用漢字]
区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8
【剩】旧字人名に使える旧字
11画 リ部 [常用漢字]
区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8
【剩】旧字人名に使える旧字
 12画 リ部
区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ
12画 リ部
区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ /ショウ
/ショウ 〈sh
〈sh ng〉
《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)
《名付け》 のり・ます
《意味》
ng〉
《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)
《名付け》 のり・ます
《意味》
 {名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」
{名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」
 {動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」
{動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」
 {副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。
《解字》
会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登
{副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。
《解字》
会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登 昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。
《類義》
→残
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。
《類義》
→残
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 リ部 [常用漢字]
区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8
【剩】旧字人名に使える旧字
11画 リ部 [常用漢字]
区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8
【剩】旧字人名に使える旧字
 12画 リ部
区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ
12画 リ部
区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994
《常用音訓》ジョウ
《音読み》 ジョウ /ショウ
/ショウ 〈sh
〈sh ng〉
《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)
《名付け》 のり・ます
《意味》
ng〉
《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)
《名付け》 のり・ます
《意味》
 {名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」
{名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」
 {動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」
{動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」
 {副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。
《解字》
会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登
{副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。
《解字》
会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登 昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。
《類義》
→残
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。
《類義》
→残
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
周 あまねし🔗⭐🔉
【周】
 8画 口部 [四年]
区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC
《常用音訓》シュウ/まわ…り
《音読み》 シュウ(シウ)
8画 口部 [四年]
区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC
《常用音訓》シュウ/まわ…り
《音読み》 シュウ(シウ) /シュ/ス
/シュ/ス 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる
《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと
《意味》
u〉
《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる
《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと
《意味》
 シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕
シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕
 シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕
シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕
 {名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕
{名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕
 {動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕
{動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕
 {名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。
{名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。
 {名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。
{名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。
 {名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。
{名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。
 {名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。
《解字》
{名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。
《解字》
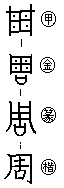 会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。
《単語家族》
州(まんべんなく取り巻いた砂地)
会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。
《単語家族》
州(まんべんなく取り巻いた砂地) 舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。
《異字同訓》
まわり。 →回
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。
《異字同訓》
まわり。 →回
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 8画 口部 [四年]
区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC
《常用音訓》シュウ/まわ…り
《音読み》 シュウ(シウ)
8画 口部 [四年]
区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC
《常用音訓》シュウ/まわ…り
《音読み》 シュウ(シウ) /シュ/ス
/シュ/ス 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる
《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと
《意味》
u〉
《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる
《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと
《意味》
 シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕
シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕
 シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕
シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕
 {名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕
{名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕
 {動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕
{動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕
 {名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。
{名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。
 {名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。
{名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。
 {名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。
{名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。
 {名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。
《解字》
{名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。
《解字》
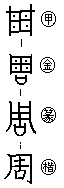 会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。
《単語家族》
州(まんべんなく取り巻いた砂地)
会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。
《単語家族》
州(まんべんなく取り巻いた砂地) 舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。
《異字同訓》
まわり。 →回
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。
《異字同訓》
まわり。 →回
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
天 あま🔗⭐🔉
【天】
 4画 大部 [一年]
区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356
《常用音訓》テン/あま/あめ
《音読み》 テン
4画 大部 [一年]
区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356
《常用音訓》テン/あま/あめ
《音読み》 テン
 〈ti
〈ti n〉
《訓読み》 あま/あめ
《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし
《意味》
n〉
《訓読み》 あま/あめ
《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし
《意味》
 {名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕
{名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕
 {名}天
{名}天 にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕
にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕
 {名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」
{名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」
 {名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕
{名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕
 {名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」
{名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」
 {名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。
{名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。
 {名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」
{名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」
 {名}キリスト教では、神のいる所。「天国」
{名}キリスト教では、神のいる所。「天国」
 {名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」
{名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」
 「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕
《解字》
「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕
《解字》
 指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
 4画 大部 [一年]
区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356
《常用音訓》テン/あま/あめ
《音読み》 テン
4画 大部 [一年]
区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356
《常用音訓》テン/あま/あめ
《音読み》 テン
 〈ti
〈ti n〉
《訓読み》 あま/あめ
《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし
《意味》
n〉
《訓読み》 あま/あめ
《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし
《意味》
 {名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕
{名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕
 {名}天
{名}天 にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕
にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕
 {名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」
{名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」
 {名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕
{名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕
 {名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」
{名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」
 {名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。
{名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。
 {名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」
{名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」
 {名}キリスト教では、神のいる所。「天国」
{名}キリスト教では、神のいる所。「天国」
 {名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」
{名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」
 「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕
《解字》
「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕
《解字》
 指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
天邪鬼 アマノジャク🔗⭐🔉
【天邪鬼】
アマノジャク  〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。
〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。 〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。
〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。
 〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。
〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。 〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。
〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。
宣 あまねし🔗⭐🔉
【宣】
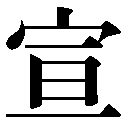 9画 宀部 [六年]
区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9
《常用音訓》セン
《音読み》 セン
9画 宀部 [六年]
区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9
《常用音訓》セン
《音読み》 セン
 〈xu
〈xu n〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)
《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)
《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし
《意味》
 センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕
センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕
 センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」
センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」
 {形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」
《解字》
{形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」
《解字》
 会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。
《単語家族》
旋(めぐる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。
《単語家族》
旋(めぐる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
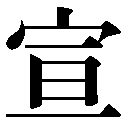 9画 宀部 [六年]
区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9
《常用音訓》セン
《音読み》 セン
9画 宀部 [六年]
区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9
《常用音訓》セン
《音読み》 セン
 〈xu
〈xu n〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)
《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)
《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし
《意味》
 センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕
センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕
 センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」
センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」
 {形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」
《解字》
{形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」
《解字》
 会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。
《単語家族》
旋(めぐる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。
《単語家族》
旋(めぐる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
尼 あま🔗⭐🔉
【尼】
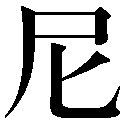 5画 尸部 [常用漢字]
区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2
《常用音訓》ニ/あま
《音読み》
5画 尸部 [常用漢字]
区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2
《常用音訓》ニ/あま
《音読み》  ニ
ニ /ジ(ヂ)
/ジ(ヂ) 〈n
〈n 〉/
〉/ ネイ
ネイ /デイ
/デイ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)
《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか
《意味》
〉
《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)
《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか
《意味》

 {名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。
{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。
 {動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。
{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。
 {動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕
《解字》
{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕
《解字》
 会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
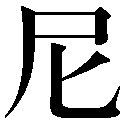 5画 尸部 [常用漢字]
区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2
《常用音訓》ニ/あま
《音読み》
5画 尸部 [常用漢字]
区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2
《常用音訓》ニ/あま
《音読み》  ニ
ニ /ジ(ヂ)
/ジ(ヂ) 〈n
〈n 〉/
〉/ ネイ
ネイ /デイ
/デイ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)
《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか
《意味》
〉
《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)
《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか
《意味》

 {名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。
{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。
 {動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。
{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。
 {動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕
《解字》
{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕
《解字》
 会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
弥 あまねし🔗⭐🔉
【弥】
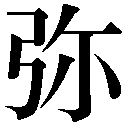 8画 弓部 [人名漢字]
区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED
【彌】旧字人名に使える旧字
8画 弓部 [人名漢字]
区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED
【彌】旧字人名に使える旧字
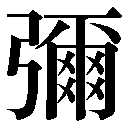 17画 弓部
区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C
《音読み》 ビ
17画 弓部
区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C
《音読み》 ビ /ミ
/ミ 〈m
〈m 〉
《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや
《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる
《意味》
〉
《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや
《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる
《意味》
 {動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕
{動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕
 {形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕
{形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕
 {形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」
{形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」
 {副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕
〔国〕いや。いよいよ。ますます。
《解字》
形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
{副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕
〔国〕いや。いよいよ。ますます。
《解字》
形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
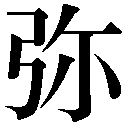 8画 弓部 [人名漢字]
区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED
【彌】旧字人名に使える旧字
8画 弓部 [人名漢字]
区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED
【彌】旧字人名に使える旧字
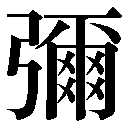 17画 弓部
区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C
《音読み》 ビ
17画 弓部
区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C
《音読み》 ビ /ミ
/ミ 〈m
〈m 〉
《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや
《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる
《意味》
〉
《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや
《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる
《意味》
 {動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕
{動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕
 {形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕
{形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕
 {形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」
{形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」
 {副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕
〔国〕いや。いよいよ。ますます。
《解字》
形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
{副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕
〔国〕いや。いよいよ。ますます。
《解字》
形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
徇 あまねし🔗⭐🔉
【徇】
 9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン
9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
 ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
 {動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
 {動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
 {形}あまねし。全部に行き渡っている。
{形}あまねし。全部に行き渡っている。
 {形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
 {助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン
9画 彳部
区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
n〉
《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ
《意味》
 ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕
 {動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。
 {動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕
 {形}あまねし。全部に行き渡っている。
{形}あまねし。全部に行き渡っている。
 {形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」
 {助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。
《解字》
会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬
《単語家族》
巡回の巡と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
敷 あまねし🔗⭐🔉
【敷】
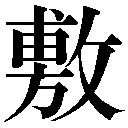 15画 攴部 [常用漢字]
区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E
《常用音訓》フ/し…く
《音読み》 フ
15画 攴部 [常用漢字]
区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E
《常用音訓》フ/し…く
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし
《名付け》 しき・のぶ・ひら
《意味》
〉
《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし
《名付け》 しき・のぶ・ひら
《意味》
 {動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」
{動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」
 {動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕
{動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕
 {形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」
{形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」
 「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。
《解字》
会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫
《単語家族》
普及の普(平らに広がる)
「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。
《解字》
会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫
《単語家族》
普及の普(平らに広がる) 布(平らにしくぬの)
布(平らにしくぬの) 膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
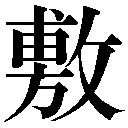 15画 攴部 [常用漢字]
区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E
《常用音訓》フ/し…く
《音読み》 フ
15画 攴部 [常用漢字]
区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E
《常用音訓》フ/し…く
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし
《名付け》 しき・のぶ・ひら
《意味》
〉
《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし
《名付け》 しき・のぶ・ひら
《意味》
 {動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」
{動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」
 {動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕
{動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕
 {形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」
{形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」
 「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。
《解字》
会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫
《単語家族》
普及の普(平らに広がる)
「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。
《解字》
会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫
《単語家族》
普及の普(平らに広がる) 布(平らにしくぬの)
布(平らにしくぬの) 膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
旁 あまねし🔗⭐🔉
【旁】
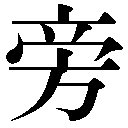 10画 方部
区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3
《音読み》
10画 方部
区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3
《音読み》  ボウ(バウ)
ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)
/ホウ(ハウ) 〈p
〈p ng〉/
ng〉/ ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ)
 〈b
〈b ng〉
ng〉 ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ)
 〈p
〈p ng〉
《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし
《意味》
ng〉
《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし
《意味》

 {名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」
{名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」
 {名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」
{名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」
 {名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」
{名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」
 {動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」
{動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」

 {動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」
{動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」
 {形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」
《解字》
{形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」
《解字》
 会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方
《単語家族》
傍(わき)
会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方
《単語家族》
傍(わき) 房(わき屋)
房(わき屋) 妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
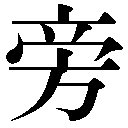 10画 方部
区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3
《音読み》
10画 方部
区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3
《音読み》  ボウ(バウ)
ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)
/ホウ(ハウ) 〈p
〈p ng〉/
ng〉/ ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ)
 〈b
〈b ng〉
ng〉 ホウ(ハウ)
ホウ(ハウ)
 〈p
〈p ng〉
《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし
《意味》
ng〉
《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし
《意味》

 {名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」
{名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」
 {名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」
{名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」
 {名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」
{名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」
 {動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」
{動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」

 {動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」
{動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」
 {形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」
《解字》
{形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」
《解字》
 会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方
《単語家族》
傍(わき)
会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方
《単語家族》
傍(わき) 房(わき屋)
房(わき屋) 妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
旬 あまねし🔗⭐🔉
【旬】
 6画 日部 [常用漢字]
区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン
6画 日部 [常用漢字]
区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 あまねし/しゅん
《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ
《意味》
n〉
《訓読み》 あまねし/しゅん
《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ
《意味》
 {名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕
{名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕
 {単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」
{単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」
 {動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。
〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」
《解字》
{動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。
〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」
《解字》
 会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。
《単語家族》
均(まるく全部に行き渡る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。
《単語家族》
均(まるく全部に行き渡る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 6画 日部 [常用漢字]
区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン
6画 日部 [常用漢字]
区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B
《常用音訓》ジュン
《音読み》 ジュン /シュン
/シュン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 あまねし/しゅん
《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ
《意味》
n〉
《訓読み》 あまねし/しゅん
《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ
《意味》
 {名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕
{名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕
 {単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」
{単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」
 {動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。
〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」
《解字》
{動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。
〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」
《解字》
 会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。
《単語家族》
均(まるく全部に行き渡る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。
《単語家族》
均(まるく全部に行き渡る)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
普 あまねし🔗⭐🔉
【普】
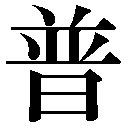 12画 日部 [常用漢字]
区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581
《常用音訓》フ
《音読み》 フ
12画 日部 [常用漢字]
区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581
《常用音訓》フ
《音読み》 フ /ホ
/ホ 〈p
〈p 〉
《訓読み》 あまねし
《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 あまねし
《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき
《意味》
 {動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕
{動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕
 {形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。
《解字》
会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。
《単語家族》
布(平らに敷きつめる)
{形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。
《解字》
会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。
《単語家族》
布(平らに敷きつめる) 敷(しく)
敷(しく) 博(広く行き渡る)などと同系。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
博(広く行き渡る)などと同系。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
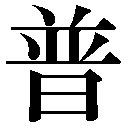 12画 日部 [常用漢字]
区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581
《常用音訓》フ
《音読み》 フ
12画 日部 [常用漢字]
区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581
《常用音訓》フ
《音読み》 フ /ホ
/ホ 〈p
〈p 〉
《訓読み》 あまねし
《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき
《意味》
〉
《訓読み》 あまねし
《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき
《意味》
 {動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕
{動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕
 {形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。
《解字》
会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。
《単語家族》
布(平らに敷きつめる)
{形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。
《解字》
会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。
《単語家族》
布(平らに敷きつめる) 敷(しく)
敷(しく) 博(広く行き渡る)などと同系。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
博(広く行き渡る)などと同系。
《類義》
→広
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
氾 あまねし🔗⭐🔉
【氾】
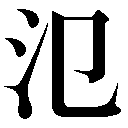 5画 水部
区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3
《音読み》 ハン(ハム)
5画 水部
区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3
《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)
/ホン(ホム) 〈f
〈f n〉
《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし
《意味》
n〉
《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし
《意味》
 {動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」
{動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」
 {形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。
〈同義語〉→汎ハン。
{形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。
〈同義語〉→汎ハン。
 {名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。
《解字》
{名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。
《単語家族》
範(車の外わく)
会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。
《単語家族》
範(車の外わく) 笵ハン(竹のわく)
笵ハン(竹のわく) 犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。
《熟語》
→熟語
犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。
《熟語》
→熟語
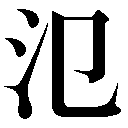 5画 水部
区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3
《音読み》 ハン(ハム)
5画 水部
区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3
《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)
/ホン(ホム) 〈f
〈f n〉
《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし
《意味》
n〉
《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし
《意味》
 {動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」
{動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」
 {形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。
〈同義語〉→汎ハン。
{形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。
〈同義語〉→汎ハン。
 {名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。
《解字》
{名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。
《解字》
 会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。
《単語家族》
範(車の外わく)
会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。
《単語家族》
範(車の外わく) 笵ハン(竹のわく)
笵ハン(竹のわく) 犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。
《熟語》
→熟語
犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。
《熟語》
→熟語
汎 あまねく🔗⭐🔉
【汎】
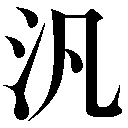 6画 水部
区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4
《音読み》 ハン(ハム)
6画 水部
区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4
《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)
/ホン(ホム) 〈f
〈f n〉
《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)
《意味》
n〉
《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)
《意味》
 ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕
ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕
 {形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕
{形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕
 {動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」
《解字》
会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。
《単語家族》
帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」
《解字》
会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。
《単語家族》
帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
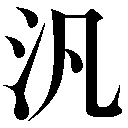 6画 水部
区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4
《音読み》 ハン(ハム)
6画 水部
区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4
《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)
/ホン(ホム) 〈f
〈f n〉
《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)
《意味》
n〉
《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)
《意味》
 ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕
ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕
 {形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕
{形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕
 {動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」
《解字》
会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。
《単語家族》
帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」
《解字》
会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。
《単語家族》
帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
泛 あまねし🔗⭐🔉
【泛】
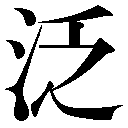 7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》
7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》  ハン(ハム)
ハン(ハム) /ボン(ボム)
/ボン(ボム) 〈f
〈f n〉/
n〉/ ホウ
ホウ /フウ
/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》
《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》

 {動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
 {動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
 {動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)
{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
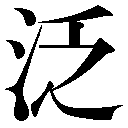 7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》
7画 水部
区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0
《音読み》  ハン(ハム)
ハン(ハム) /ボン(ボム)
/ボン(ボム) 〈f
〈f n〉/
n〉/ ホウ
ホウ /フウ
/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》
《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし
《意味》

 {動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕
 {動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」
 {動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)
{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。
《解字》
会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。
《単語家族》
貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。
《類義》
浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
海士 アマ🔗⭐🔉
【海人】
 カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』
カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。
アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。
 カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』
カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。
アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。
海女 アマ🔗⭐🔉
【海女】
 カイジョ 海神の娘。
カイジョ 海神の娘。 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。
アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。
 カイジョ 海神の娘。
カイジョ 海神の娘。 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。
アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。
洽 あまねし🔗⭐🔉
【洽】
 9画 水部
区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8
《音読み》
9画 水部
区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8
《音読み》  コウ(カフ)
コウ(カフ) /ギョウ(ゲフ)
/ギョウ(ゲフ) 〈xi
〈xi ・qi
・qi 〉/
〉/ ゴウ(ゴフ)
ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)
《意味》
《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)
《意味》

 {形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕
{形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕
 {動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕
{動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕
 {動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」
{動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」
 {名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。
《解字》
会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。
《解字》
会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 水部
区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8
《音読み》
9画 水部
区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8
《音読み》  コウ(カフ)
コウ(カフ) /ギョウ(ゲフ)
/ギョウ(ゲフ) 〈xi
〈xi ・qi
・qi 〉/
〉/ ゴウ(ゴフ)
ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)
/コウ(カフ) 《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)
《意味》
《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)
《意味》

 {形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕
{形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕
 {動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕
{動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕
 {動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」
{動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」
 {名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。
《解字》
会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。
《解字》
会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
溥 あまねし🔗⭐🔉
【溥】
 13画 水部
区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE
《音読み》 フ
13画 水部
区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE
《音読み》 フ /ホ
/ホ 〈p
〈p 〉
《訓読み》 あまねし
《意味》
〉
《訓読み》 あまねし
《意味》
 {動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕
{動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕
 {動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。
《単語家族》
博(四方にひろがる)
{動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。
《単語家族》
博(四方にひろがる) 普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→故事成語
普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→故事成語
 13画 水部
区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE
《音読み》 フ
13画 水部
区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE
《音読み》 フ /ホ
/ホ 〈p
〈p 〉
《訓読み》 あまねし
《意味》
〉
《訓読み》 あまねし
《意味》
 {動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕
{動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕
 {動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。
《単語家族》
博(四方にひろがる)
{動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕
《解字》
会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。
《単語家族》
博(四方にひろがる) 普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→故事成語
普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。
《熟語》
→熟語
→故事成語
甘 あまい🔗⭐🔉
【甘】
 5画 甘部 [常用漢字]
区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3
《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす
《音読み》 カン(カム)
5画 甘部 [常用漢字]
区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3
《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす
《音読み》 カン(カム)
 〈g
〈g n〉
《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて
《名付け》 あま・かい・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて
《名付け》 あま・かい・よし
《意味》
 {形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕
{形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕
 {形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕
{形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕
 {形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。
{形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。
 {動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢
{動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢 タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕
タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕
 {動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」
{動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」
 {副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。
〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」
《解字》
{副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。
〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」
《解字》
 会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。
《単語家族》
含(ふくむ)
会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。
《単語家族》
含(ふくむ) 柑カン(口中にふくんで味わうみかん)
柑カン(口中にふくんで味わうみかん) 拑カン(はさんで中にふくむ)
拑カン(はさんで中にふくむ) 鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。
《類義》
旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。
《類義》
旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 5画 甘部 [常用漢字]
区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3
《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす
《音読み》 カン(カム)
5画 甘部 [常用漢字]
区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3
《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす
《音読み》 カン(カム)
 〈g
〈g n〉
《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて
《名付け》 あま・かい・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて
《名付け》 あま・かい・よし
《意味》
 {形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕
{形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕
 {形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕
{形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕
 {形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。
{形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。
 {動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢
{動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢 タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕
タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕
 {動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」
{動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」
 {副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。
〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」
《解字》
{副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。
〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」
《解字》
 会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。
《単語家族》
含(ふくむ)
会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。
《単語家族》
含(ふくむ) 柑カン(口中にふくんで味わうみかん)
柑カン(口中にふくんで味わうみかん) 拑カン(はさんで中にふくむ)
拑カン(はさんで中にふくむ) 鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。
《類義》
旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。
《類義》
旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
甜 あまい🔗⭐🔉
羨 あまり🔗⭐🔉
【羨】
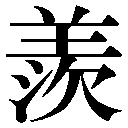 13画 羊部
区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141
《音読み》
13画 羊部
区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141
《音読み》  セン
セン /ゼン
/ゼン 〈xi
〈xi n〉/
n〉/ エン
エン
 /セン
/セン 《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる
《意味》
《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる
《意味》

 {動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕
{動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕
 {動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕
{動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕
 {動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。
{動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。
 {名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」
《解字》
会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。
《単語家族》
延(引きのばす)
{名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」
《解字》
会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。
《単語家族》
延(引きのばす) 涎セン(よだれ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
涎セン(よだれ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
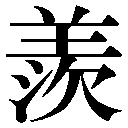 13画 羊部
区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141
《音読み》
13画 羊部
区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141
《音読み》  セン
セン /ゼン
/ゼン 〈xi
〈xi n〉/
n〉/ エン
エン
 /セン
/セン 《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる
《意味》
《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる
《意味》

 {動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕
{動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕
 {動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕
{動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕
 {動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。
{動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。
 {名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」
《解字》
会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。
《単語家族》
延(引きのばす)
{名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」
《解字》
会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。
《単語家族》
延(引きのばす) 涎セン(よだれ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
涎セン(よだれ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
蔗 あまい🔗⭐🔉
蜑 あま🔗⭐🔉
衍 あまる🔗⭐🔉
【衍】
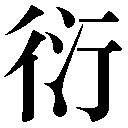 9画 行部
区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5
《音読み》 エン
9画 行部
区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5
《音読み》 エン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)
《意味》
n〉
《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)
《意味》
 {動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」
{動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」
 {動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕
{動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕
 {動}水が長くながれて海にそそぐ。
{動}水が長くながれて海にそそぐ。
 {動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。
{動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。
 {動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」
{動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」
 {形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。
《解字》
会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。
《単語家族》
演エン(ひきのばす)
{形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。
《解字》
会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。
《単語家族》
演エン(ひきのばす) 延エン(ひきのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
延エン(ひきのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
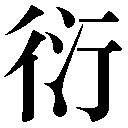 9画 行部
区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5
《音読み》 エン
9画 行部
区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5
《音読み》 エン
 〈y
〈y n〉
《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)
《意味》
n〉
《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)
《意味》
 {動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」
{動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」
 {動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕
{動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕
 {動}水が長くながれて海にそそぐ。
{動}水が長くながれて海にそそぐ。
 {動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。
{動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。
 {動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」
{動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」
 {形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。
《解字》
会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。
《単語家族》
演エン(ひきのばす)
{形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。
《解字》
会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。
《単語家族》
演エン(ひきのばす) 延エン(ひきのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
延エン(ひきのばす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
贏 あまり🔗⭐🔉
【贏】
 20画 貝部
区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5
《音読み》 エイ
20画 貝部
区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5
《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)
/ヨウ(ヤウ) 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 あまる/あまり/かつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 あまる/あまり/かつ
《意味》
 {動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」
{動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」
 {動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。
{動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。
 {動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」
{動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」
 {動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。
《解字》
会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。
《単語家族》
瀛エイ(大きい海)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。
《解字》
会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。
《単語家族》
瀛エイ(大きい海)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 20画 貝部
区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5
《音読み》 エイ
20画 貝部
区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5
《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)
/ヨウ(ヤウ) 〈y
〈y ng〉
《訓読み》 あまる/あまり/かつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 あまる/あまり/かつ
《意味》
 {動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」
{動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」
 {動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。
{動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。
 {動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」
{動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」
 {動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。
《解字》
会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。
《単語家族》
瀛エイ(大きい海)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。
《解字》
会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。
《単語家族》
瀛エイ(大きい海)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
遍 あまねし🔗⭐🔉
阿妹 アマイ🔗⭐🔉
【阿妹】
アマイ 妹を親しんでいうことば。
阿媽 アマ🔗⭐🔉
【阿媽】
 アボ〔俗〕母のこと。
アボ〔俗〕母のこと。 アマ〔俗〕女中・乳母のこと。
アマ〔俗〕女中・乳母のこと。
 アボ〔俗〕母のこと。
アボ〔俗〕母のこと。 アマ〔俗〕女中・乳母のこと。
アマ〔俗〕女中・乳母のこと。
雨 あま🔗⭐🔉
【雨】
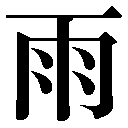 8画 雨部 [一年]
区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A
《常用音訓》ウ/あま/あめ
《音読み》 ウ
8画 雨部 [一年]
区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A
《常用音訓》ウ/あま/あめ
《音読み》 ウ
 〈y
〈y ・y
・y 〉
《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)
《名付け》 さめ・ふる
《意味》
〉
《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)
《名付け》 さめ・ふる
《意味》
 {名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕
{名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕 {動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕
{動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕
 {動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕
{動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕
 {動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。
《解字》
{動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。
《解字》
 象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。
《単語家族》
宇(大きくおおう屋根)
象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。
《単語家族》
宇(大きくおおう屋根) 羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
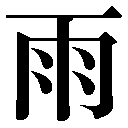 8画 雨部 [一年]
区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A
《常用音訓》ウ/あま/あめ
《音読み》 ウ
8画 雨部 [一年]
区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A
《常用音訓》ウ/あま/あめ
《音読み》 ウ
 〈y
〈y ・y
・y 〉
《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)
《名付け》 さめ・ふる
《意味》
〉
《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)
《名付け》 さめ・ふる
《意味》
 {名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕
{名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕 {動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕
{動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕
 {動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕
{動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕
 {動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。
《解字》
{動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。
《解字》
 象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。
《単語家族》
宇(大きくおおう屋根)
象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。
《単語家族》
宇(大きくおおう屋根) 羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
雨足 アマアシ🔗⭐🔉
【雨足】
 ウソク
ウソク  「雨脚
「雨脚 」と同じ。
」と同じ。 雨がじゅうぶんふる。
雨がじゅうぶんふる。 アマアシ〔国〕「雨脚
アマアシ〔国〕「雨脚 」と同じ。
」と同じ。
 ウソク
ウソク  「雨脚
「雨脚 」と同じ。
」と同じ。 雨がじゅうぶんふる。
雨がじゅうぶんふる。 アマアシ〔国〕「雨脚
アマアシ〔国〕「雨脚 」と同じ。
」と同じ。
雨足 アマアシ🔗⭐🔉
【雨脚】
 ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕
ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕 アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」
アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」
 ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕
ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕 アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」
アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」
塰 あま🔗⭐🔉
【塰】
 13画 土部 〔国〕
区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9
《訓読み》 あま
《意味》
あま。
13画 土部 〔国〕
区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9
《訓読み》 あま
《意味》
あま。 海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。
海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。 地名に使う。
地名に使う。
 13画 土部 〔国〕
区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9
《訓読み》 あま
《意味》
あま。
13画 土部 〔国〕
区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9
《訓読み》 あま
《意味》
あま。 海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。
海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。 地名に使う。
地名に使う。
漢字源に「アマ」で始まるの検索結果 1-35。もっと読み込む
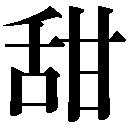 11画 甘部
区点=3728 16進=453C シフトJIS=935B
《音読み》 テン(テム)
11画 甘部
区点=3728 16進=453C シフトJIS=935B
《音読み》 テン(テム)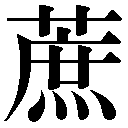 14画 艸部
区点=7284 16進=6874 シフトJIS=E4F2
《音読み》 シャ
14画 艸部
区点=7284 16進=6874 シフトJIS=E4F2
《音読み》 シャ 13画 虫部
区点=7373 16進=6969 シフトJIS=E589
《音読み》 タン
13画 虫部
区点=7373 16進=6969 シフトJIS=E589
《音読み》 タン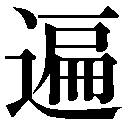 12画
12画  部 [常用漢字]
区点=4255 16進=4A57 シフトJIS=95D5
《常用音訓》ヘン
《音読み》 ヘン
部 [常用漢字]
区点=4255 16進=4A57 シフトJIS=95D5
《常用音訓》ヘン
《音読み》 ヘン