複数辞典一括検索+![]()
![]()
下落 カラク🔗⭐🔉
【下落】
 ゲラク
ゲラク  物価が下がる。
物価が下がる。 品質が悪くなる。
品質が悪くなる。 カラク〔俗〕
カラク〔俗〕 ゆくえ。所在。
ゆくえ。所在。 物事にきまりがついて終わること。
物事にきまりがついて終わること。
 ゲラク
ゲラク  物価が下がる。
物価が下がる。 品質が悪くなる。
品質が悪くなる。 カラク〔俗〕
カラク〔俗〕 ゆくえ。所在。
ゆくえ。所在。 物事にきまりがついて終わること。
物事にきまりがついて終わること。
体 からだ🔗⭐🔉
【体】
 7画 人部 [二年]
区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC
【體】旧字旧字
7画 人部 [二年]
区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC
【體】旧字旧字
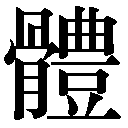 23画 骨部
区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993
【躰】異体字(A)異体字(A)
23画 骨部
区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993
【躰】異体字(A)異体字(A)
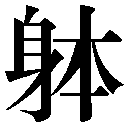 12画 身部
区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B
【軆】異体字(B)異体字(B)
12画 身部
区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B
【軆】異体字(B)異体字(B)
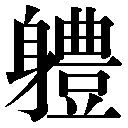 20画 身部
区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C
《常用音訓》タイ/テイ/からだ
《音読み》 タイ
20画 身部
区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C
《常用音訓》タイ/テイ/からだ
《音読み》 タイ /テイ
/テイ 〈t
〈t 〉
《訓読み》 からだ
《名付け》 なり・み・みる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 からだ
《名付け》 なり・み・みる・もと
《意味》
 {名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕
{名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕
 {名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」
{名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」
 {名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」
{名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」
 {名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」
{名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」
 {名}表面の姿。「体裁」
{名}表面の姿。「体裁」
 タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」
タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」
 {副}身につけて。みずから。「体得」
《解字》
〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}身につけて。みずから。「体得」
《解字》
〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 人部 [二年]
区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC
【體】旧字旧字
7画 人部 [二年]
区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC
【體】旧字旧字
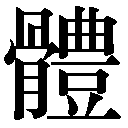 23画 骨部
区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993
【躰】異体字(A)異体字(A)
23画 骨部
区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993
【躰】異体字(A)異体字(A)
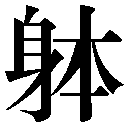 12画 身部
区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B
【軆】異体字(B)異体字(B)
12画 身部
区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B
【軆】異体字(B)異体字(B)
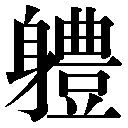 20画 身部
区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C
《常用音訓》タイ/テイ/からだ
《音読み》 タイ
20画 身部
区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C
《常用音訓》タイ/テイ/からだ
《音読み》 タイ /テイ
/テイ 〈t
〈t 〉
《訓読み》 からだ
《名付け》 なり・み・みる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 からだ
《名付け》 なり・み・みる・もと
《意味》
 {名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕
{名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕
 {名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」
{名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」
 {名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」
{名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」
 {名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」
{名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」
 {名}表面の姿。「体裁」
{名}表面の姿。「体裁」
 タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」
タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」
 {副}身につけて。みずから。「体得」
《解字》
〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}身につけて。みずから。「体得」
《解字》
〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
唐 から🔗⭐🔉
【唐】
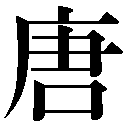 10画 口部 [常用漢字]
区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382
《常用音訓》トウ/から
《音読み》 トウ(タウ)
10画 口部 [常用漢字]
区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382
《常用音訓》トウ/から
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
ng〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
 {名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。
{名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。
 {名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。
{名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。
 {名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。
{名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。
 {名}上古の帝
{名}上古の帝 ギョウのこと。▽
ギョウのこと。▽ の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕
の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕
 {動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」
{動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」
 {名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」
{名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」
 {名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。
{名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。
 {動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」
《解字》
会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
{動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」
《解字》
会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
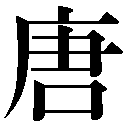 10画 口部 [常用漢字]
区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382
《常用音訓》トウ/から
《音読み》 トウ(タウ)
10画 口部 [常用漢字]
区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382
《常用音訓》トウ/から
《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)
/ドウ(ダウ) 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
ng〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
 {名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。
{名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。
 {名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。
{名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。
 {名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。
{名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。
 {名}上古の帝
{名}上古の帝 ギョウのこと。▽
ギョウのこと。▽ の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕
の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕
 {動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」
{動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」
 {名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」
{名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」
 {名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。
{名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。
 {動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」
《解字》
会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
{動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」
《解字》
会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
唐子 カラコ🔗⭐🔉
【唐子】
 トウシ
トウシ  あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕
あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕 山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。
山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。 カラコ〔国〕
カラコ〔国〕 中国ふうの姿・服装をした子ども。
中国ふうの姿・服装をした子ども。 「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。
「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。
 トウシ
トウシ  あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕
あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕 山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。
山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。 カラコ〔国〕
カラコ〔国〕 中国ふうの姿・服装をした子ども。
中国ふうの姿・服装をした子ども。 「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。
「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。
唐物 カラモノ🔗⭐🔉
【唐物】
カラモノ〔国〕 中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。
中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。 古道具。
古道具。
 中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。
中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。 古道具。
古道具。
唐草模様 カラクサモヨウ🔗⭐🔉
【唐草模様】
カラクサモヨウ〔国〕つる草がはいからまっているさまを描いた模様。
唐紙 カラカミ🔗⭐🔉
【唐紙】
カラカミ〔国〕 中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。
中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。 「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。
「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。
 中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。
中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。 「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。
「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。
奈 からなし🔗⭐🔉
【奈】
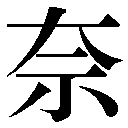 8画 大部 [人名漢字]
区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE
《音読み》 ナイ
8画 大部 [人名漢字]
区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE
《音読み》 ナイ /ダイ
/ダイ /ナ
/ナ /ダ
/ダ 〈n
〈n i〉〈n
i〉〈n 〉
《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば
《名付け》 なに
《意味》
〉
《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば
《名付け》 なに
《意味》
 {名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。
{名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。
 「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。
「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。
 {疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕
《解字》
会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕
《解字》
会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
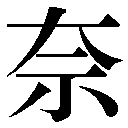 8画 大部 [人名漢字]
区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE
《音読み》 ナイ
8画 大部 [人名漢字]
区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE
《音読み》 ナイ /ダイ
/ダイ /ナ
/ナ /ダ
/ダ 〈n
〈n i〉〈n
i〉〈n 〉
《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば
《名付け》 なに
《意味》
〉
《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば
《名付け》 なに
《意味》
 {名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。
{名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。
 「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。
「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。
 {疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕
《解字》
会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕
《解字》
会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
揶 からかう🔗⭐🔉
【揶】
 12画
12画  部
区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88
《音読み》 ヤ
部
区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88
《音読み》 ヤ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 からかう(からかふ)
《意味》
{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」
《解字》
形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。
〉
《訓読み》 からかう(からかふ)
《意味》
{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」
《解字》
形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。
 12画
12画  部
区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88
《音読み》 ヤ
部
区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88
《音読み》 ヤ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 からかう(からかふ)
《意味》
{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」
《解字》
形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。
〉
《訓読み》 からかう(からかふ)
《意味》
{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」
《解字》
形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。
搦 からむ🔗⭐🔉
【搦】
 13画
13画  部
区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E
《音読み》 ニャク
部
区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E
《音読み》 ニャク /ダク
/ダク 〈nu
〈nu 〉
《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ
《意味》
〉
《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ
《意味》
 {動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。
{動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。
 {動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」
〔国〕
{動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」
〔国〕 からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」
からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」 「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。
《解字》
会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。
《単語家族》
若ジャク・ニャク(柔らかい)
「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。
《解字》
会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。
《単語家族》
若ジャク・ニャク(柔らかい) 蒻ニャク(柔らかい草)と同系。
蒻ニャク(柔らかい草)と同系。
 13画
13画  部
区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E
《音読み》 ニャク
部
区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E
《音読み》 ニャク /ダク
/ダク 〈nu
〈nu 〉
《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ
《意味》
〉
《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ
《意味》
 {動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。
{動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。
 {動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」
〔国〕
{動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」
〔国〕 からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」
からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」 「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。
《解字》
会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。
《単語家族》
若ジャク・ニャク(柔らかい)
「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。
《解字》
会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。
《単語家族》
若ジャク・ニャク(柔らかい) 蒻ニャク(柔らかい草)と同系。
蒻ニャク(柔らかい草)と同系。
撩 からげる🔗⭐🔉
【撩】
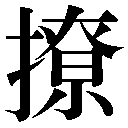 15画
15画  部
区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C
《音読み》 リョウ(レウ)
部
区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C
《音読み》 リョウ(レウ)
 〈li
〈li o・li
o・li o〉
《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)
《意味》
o〉
《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)
《意味》
 {動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」
{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」
 {動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」
{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」
 {動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」
{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」
 {動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。
《単語家族》
遼リョウ(長く続く)
{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。
《単語家族》
遼リョウ(長く続く) 了(けりをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
了(けりをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
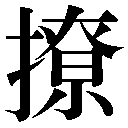 15画
15画  部
区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C
《音読み》 リョウ(レウ)
部
区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C
《音読み》 リョウ(レウ)
 〈li
〈li o・li
o・li o〉
《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)
《意味》
o〉
《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)
《意味》
 {動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」
{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」
 {動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」
{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」
 {動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」
{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」
 {動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。
《単語家族》
遼リョウ(長く続く)
{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」
《解字》
会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。
《単語家族》
遼リョウ(長く続く) 了(けりをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
了(けりをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
枷 からさお🔗⭐🔉
【枷】
 9画 木部
区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67
《音読み》 カ
9画 木部
区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67
《音読み》 カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 からさお(からさを)/かせ
《意味》
〉
《訓読み》 からさお(からさを)/かせ
《意味》
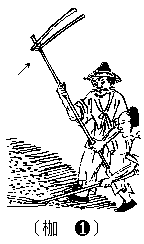
 {名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」
{名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」
 {名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。
{名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。
 カス{動}首かせをはめる。
カス{動}首かせをはめる。
 {名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。
《単語家族》
加(上にのせる)
{名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。
《単語家族》
加(上にのせる) 駕ガ(馬にくびきをのせる)
駕ガ(馬にくびきをのせる) 架(上にかけわたす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
架(上にかけわたす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 木部
区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67
《音読み》 カ
9画 木部
区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67
《音読み》 カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 からさお(からさを)/かせ
《意味》
〉
《訓読み》 からさお(からさを)/かせ
《意味》
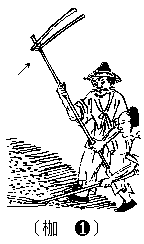
 {名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」
{名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」
 {名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。
{名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。
 カス{動}首かせをはめる。
カス{動}首かせをはめる。
 {名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。
《単語家族》
加(上にのせる)
{名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。
《単語家族》
加(上にのせる) 駕ガ(馬にくびきをのせる)
駕ガ(馬にくびきをのせる) 架(上にかけわたす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
架(上にかけわたす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枳 からたち🔗⭐🔉
枯 からす🔗⭐🔉
【枯】
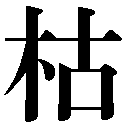 9画 木部 [常用漢字]
区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD
《常用音訓》コ/か…らす/か…れる
《音読み》 コ
9画 木部 [常用漢字]
区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD
《常用音訓》コ/か…らす/か…れる
《音読み》 コ /ク
/ク 〈k
〈k 〉
《訓読み》 からす/かれる(かる)
《意味》
〉
《訓読み》 からす/かれる(かる)
《意味》
 {動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」
{動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」
 {動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」
{動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」
 {動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」
{動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」
 {名}かれ木。
{名}かれ木。
 {形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」
《解字》
会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。
《単語家族》
固(かたい)
{形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」
《解字》
会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。
《単語家族》
固(かたい) 個(かたい個体)
個(かたい個体) 姑(ひからびた老女)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
姑(ひからびた老女)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
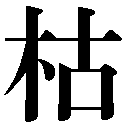 9画 木部 [常用漢字]
区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD
《常用音訓》コ/か…らす/か…れる
《音読み》 コ
9画 木部 [常用漢字]
区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD
《常用音訓》コ/か…らす/か…れる
《音読み》 コ /ク
/ク 〈k
〈k 〉
《訓読み》 からす/かれる(かる)
《意味》
〉
《訓読み》 からす/かれる(かる)
《意味》
 {動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」
{動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」
 {動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」
{動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」
 {動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」
{動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」
 {名}かれ木。
{名}かれ木。
 {形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」
《解字》
会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。
《単語家族》
固(かたい)
{形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」
《解字》
会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。
《単語家族》
固(かたい) 個(かたい個体)
個(かたい個体) 姑(ひからびた老女)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
姑(ひからびた老女)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
歌楽 カラク🔗⭐🔉
【歌楽】
 カガク 歌謡と音楽。
カガク 歌謡と音楽。 カラク
カラク  歌をうたって楽しむこと。
歌をうたって楽しむこと。 詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
 カガク 歌謡と音楽。
カガク 歌謡と音楽。 カラク
カラク  歌をうたって楽しむこと。
歌をうたって楽しむこと。 詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。
殻 から🔗⭐🔉
【殻】
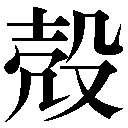 11画 殳部 [常用漢字]
区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B
【殼】旧字旧字
11画 殳部 [常用漢字]
区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B
【殼】旧字旧字
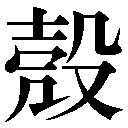 12画 殳部
区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76
《常用音訓》カク/から
《音読み》 カク
12画 殳部
区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76
《常用音訓》カク/から
《音読み》 カク /コク
/コク 〈k
〈k 〉〈qi
〉〈qi o〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
o〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
 {名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」
{名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」
 {動}かたい物をこつこつとたたく。
《解字》
会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かたい物をこつこつとたたく。
《解字》
会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
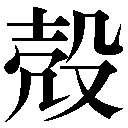 11画 殳部 [常用漢字]
区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B
【殼】旧字旧字
11画 殳部 [常用漢字]
区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B
【殼】旧字旧字
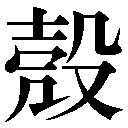 12画 殳部
区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76
《常用音訓》カク/から
《音読み》 カク
12画 殳部
区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76
《常用音訓》カク/から
《音読み》 カク /コク
/コク 〈k
〈k 〉〈qi
〉〈qi o〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
o〉
《訓読み》 から
《名付け》 から
《意味》
 {名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」
{名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」
 {動}かたい物をこつこつとたたく。
《解字》
会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}かたい物をこつこつとたたく。
《解字》
会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
涸 からす🔗⭐🔉
【涸】
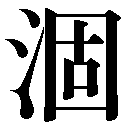 11画 水部
区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF
《音読み》 コ
11画 水部
区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF
《音読み》 コ /ガク
/ガク /カク
/カク 〈h
〈h 〉
《訓読み》 かれる(かる)/からす
《意味》
{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。
《単語家族》
故(かたくなった死人)
〉
《訓読み》 かれる(かる)/からす
《意味》
{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。
《単語家族》
故(かたくなった死人) 枯(草木がかれる)
枯(草木がかれる) 固(かたい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
固(かたい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
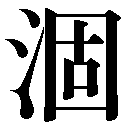 11画 水部
区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF
《音読み》 コ
11画 水部
区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF
《音読み》 コ /ガク
/ガク /カク
/カク 〈h
〈h 〉
《訓読み》 かれる(かる)/からす
《意味》
{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。
《単語家族》
故(かたくなった死人)
〉
《訓読み》 かれる(かる)/からす
《意味》
{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。
《単語家族》
故(かたくなった死人) 枯(草木がかれる)
枯(草木がかれる) 固(かたい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
固(かたい)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢 から🔗⭐🔉
【漢】
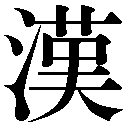 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 13画 水部 [三年]
区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF
《常用音訓》カン
《音読み》 カン
13画 水部 [三年]
区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF
《常用音訓》カン
《音読み》 カン
 〈h
〈h n〉
《訓読み》 から/あや
《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら
《意味》
n〉
《訓読み》 から/あや
《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら
《意味》
 {名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。
{名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。
 {名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」
{名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」
 {名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。
{名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。
 {名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」
{名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」
 {名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。
{名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。
 {名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」
{名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」
 {名}男。男に対する呼び名。「門外漢」
〔国〕から。あや。中国のこと。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
{名}男。男に対する呼び名。「門外漢」
〔国〕から。あや。中国のこと。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
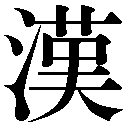 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 13画 水部 [三年]
区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF
《常用音訓》カン
《音読み》 カン
13画 水部 [三年]
区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF
《常用音訓》カン
《音読み》 カン
 〈h
〈h n〉
《訓読み》 から/あや
《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら
《意味》
n〉
《訓読み》 から/あや
《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら
《意味》
 {名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。
{名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。
 {名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」
{名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」
 {名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。
{名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。
 {名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」
{名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」
 {名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。
{名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。
 {名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」
{名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」
 {名}男。男に対する呼び名。「門外漢」
〔国〕から。あや。中国のこと。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
{名}男。男に対する呼び名。「門外漢」
〔国〕から。あや。中国のこと。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
烏 からす🔗⭐🔉
【烏】
 10画 火部
区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947
《音読み》 ウ
10画 火部
区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947
《音読み》 ウ /オ(ヲ)
/オ(ヲ) /ウ
/ウ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)
《意味》
〉
《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)
《意味》
 {名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕
{名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕
 {形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」
{形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」
 「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。
「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。
 {名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」
{名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」
 {副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕
《解字》
{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕
《解字》
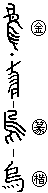 象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。
《単語家族》
鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。
《単語家族》
鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 10画 火部
区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947
《音読み》 ウ
10画 火部
区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947
《音読み》 ウ /オ(ヲ)
/オ(ヲ) /ウ
/ウ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)
《意味》
〉
《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)
《意味》
 {名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕
{名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕
 {形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」
{形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」
 「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。
「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。
 {名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」
{名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」
 {副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕
《解字》
{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕
《解字》
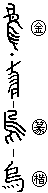 象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。
《単語家族》
鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。
《単語家族》
鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
烏有反哺之孝 カラスニハンポノコウアリ🔗⭐🔉
【烏有反哺之孝】
カラスニハンポノコウアリ〈故事〉からすでさえも、ひなのとき養われた恩返しに、口の中に含んだ食物を口づたえに親鳥に食べさせる孝行心がある。転じて、人は、なおさら孝行心をもたねばならないということ。〔梁武帝〕
犂 からすき🔗⭐🔉
【犂】
 12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
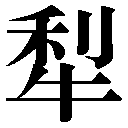 11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》
11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》  レイ
レイ /ライ
/ライ /
/ リ
リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
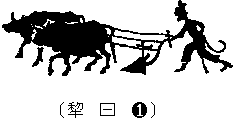

 {名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
 {動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕
{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

 {名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
 {形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
 {動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
12画 牛部
区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2
【犁】異体字異体字
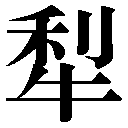 11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》
11画 牛部
区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3
《音読み》  レイ
レイ /ライ
/ライ /
/ リ
リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
〉
《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし
《意味》
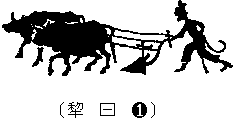

 {名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。
 {動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕
{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

 {名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」
 {形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。
 {動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕
《解字》
会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
空 から🔗⭐🔉
【空】
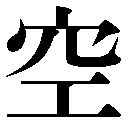 8画 穴部 [一年]
区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3
《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら
《音読み》 クウ
8画 穴部 [一年]
区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3
《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら
《音読み》 クウ /コウ
/コウ 〈k
〈k ng・k
ng・k ng〉
《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら
《名付け》 たか
《意味》
ng〉
《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら
《名付け》 たか
《意味》
 クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」
クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」
 クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕
クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕
 クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」
クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」
 {副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕
{副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕
 {名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕
{名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕
 {名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」
{名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」
 {名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕
《解字》
{名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕
《解字》
 会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。
《単語家族》
孔コウ(つきぬけたあな)
会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。
《単語家族》
孔コウ(つきぬけたあな) 腔コウ(のどのつきぬけたあな)
腔コウ(のどのつきぬけたあな) 肛コウ(しりのあな)
肛コウ(しりのあな) 攻(つきぬく)などと同系。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
攻(つきぬく)などと同系。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
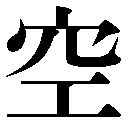 8画 穴部 [一年]
区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3
《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら
《音読み》 クウ
8画 穴部 [一年]
区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3
《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら
《音読み》 クウ /コウ
/コウ 〈k
〈k ng・k
ng・k ng〉
《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら
《名付け》 たか
《意味》
ng〉
《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら
《名付け》 たか
《意味》
 クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」
クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」
 クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕
クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕
 クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」
クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」
 {副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕
{副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕
 {名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕
{名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕
 {名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」
{名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」
 {名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕
《解字》
{名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕
《解字》
 会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。
《単語家族》
孔コウ(つきぬけたあな)
会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。
《単語家族》
孔コウ(つきぬけたあな) 腔コウ(のどのつきぬけたあな)
腔コウ(のどのつきぬけたあな) 肛コウ(しりのあな)
肛コウ(しりのあな) 攻(つきぬく)などと同系。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
攻(つきぬく)などと同系。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
空手 カラテ🔗⭐🔉
【空手】
 クウシュ「空拳クウケン」と同じ。
クウシュ「空拳クウケン」と同じ。 カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。
カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。 ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。
ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。
 クウシュ「空拳クウケン」と同じ。
クウシュ「空拳クウケン」と同じ。 カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。
カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。 ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。
ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。
絡 からます🔗⭐🔉
【絡】
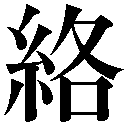 12画 糸部 [常用漢字]
区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D
《常用音訓》ラク/から…まる/から…む
《音読み》 ラク
12画 糸部 [常用漢字]
区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D
《常用音訓》ラク/から…まる/から…む
《音読み》 ラク
 〈lu
〈lu ・l
・l o〉
《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)
《名付け》 つら・なり
《意味》
o〉
《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)
《名付け》 つら・なり
《意味》
 ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」
ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」
 ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」
ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」
 {名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」
{名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」
 {名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」
{名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」
 {名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」
{名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」
 {名}果実の中の繊維。
{名}果実の中の繊維。
 {名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」
《解字》
形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。
《単語家族》
略(田の中の連絡みち)
{名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」
《解字》
形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。
《単語家族》
略(田の中の連絡みち) 路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
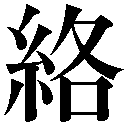 12画 糸部 [常用漢字]
区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D
《常用音訓》ラク/から…まる/から…む
《音読み》 ラク
12画 糸部 [常用漢字]
区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D
《常用音訓》ラク/から…まる/から…む
《音読み》 ラク
 〈lu
〈lu ・l
・l o〉
《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)
《名付け》 つら・なり
《意味》
o〉
《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)
《名付け》 つら・なり
《意味》
 ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」
ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」
 ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」
ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」
 {名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」
{名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」
 {名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」
{名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」
 {名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」
{名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」
 {名}果実の中の繊維。
{名}果実の中の繊維。
 {名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」
《解字》
形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。
《単語家族》
略(田の中の連絡みち)
{名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」
《解字》
形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。
《単語家族》
略(田の中の連絡みち) 路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
縢 からげる🔗⭐🔉
【縢】
 16画 糸部
区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377
《音読み》 トウ
16画 糸部
区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377
《音読み》 トウ /ドウ
/ドウ 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき
《意味》
ng〉
《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき
《意味》
 {名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕
{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕
 {動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。
{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。
 {名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」
《解字》
形声。糸を除いた部分が音をあらわす。
《単語家族》
藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」
《解字》
形声。糸を除いた部分が音をあらわす。
《単語家族》
藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
 16画 糸部
区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377
《音読み》 トウ
16画 糸部
区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377
《音読み》 トウ /ドウ
/ドウ 〈t
〈t ng〉
《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき
《意味》
ng〉
《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき
《意味》
 {名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕
{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕
 {動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。
{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。
 {名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」
《解字》
形声。糸を除いた部分が音をあらわす。
《単語家族》
藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」
《解字》
形声。糸を除いた部分が音をあらわす。
《単語家族》
藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
芥 からし🔗⭐🔉
【芥】
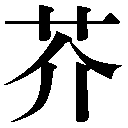 7画 艸部
区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48
《音読み》 カイ
7画 艸部
区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji ・g
・g i〉
《訓読み》 からしな/からし/あくた
《意味》
i〉
《訓読み》 からしな/からし/あくた
《意味》
 {名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。
{名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。
 {名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。
{名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。
 {名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕
{名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕
 {名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
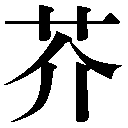 7画 艸部
区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48
《音読み》 カイ
7画 艸部
区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji ・g
・g i〉
《訓読み》 からしな/からし/あくた
《意味》
i〉
《訓読み》 からしな/からし/あくた
《意味》
 {名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。
{名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。
 {名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。
{名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。
 {名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕
{名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕
 {名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
苛 からい🔗⭐🔉
【苛】
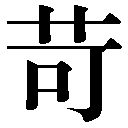 8画 艸部
区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5
《音読み》 カ
8画 艸部
区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5
《音読み》 カ /ガ
/ガ 〈k
〈k 〉
《訓読み》 からい(からし)
《意味》
〉
《訓読み》 からい(からし)
《意味》
 {形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕
{形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕
 {動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」
《解字》
会意兼形声。可は「
{動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」
《解字》
会意兼形声。可は「 印+口」からなり、
印+口」からなり、 型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。
《単語家族》
河(
型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。
《単語家族》
河( 型に曲がる黄河)
型に曲がる黄河) 呵カ(のどをかすらせる)
呵カ(のどをかすらせる) 歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
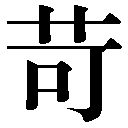 8画 艸部
区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5
《音読み》 カ
8画 艸部
区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5
《音読み》 カ /ガ
/ガ 〈k
〈k 〉
《訓読み》 からい(からし)
《意味》
〉
《訓読み》 からい(からし)
《意味》
 {形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕
{形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕
 {動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」
《解字》
会意兼形声。可は「
{動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」
《解字》
会意兼形声。可は「 印+口」からなり、
印+口」からなり、 型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。
《単語家族》
河(
型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。
《単語家族》
河( 型に曲がる黄河)
型に曲がる黄河) 呵カ(のどをかすらせる)
呵カ(のどをかすらせる) 歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
苧 からむし🔗⭐🔉
華洛 カラク🔗⭐🔉
【華洛】
カラク  花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』
花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』 〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。
〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。
 花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』
花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』 〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。
〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。
誂 からかう🔗⭐🔉
【誂】
 13画 言部
区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F
《音読み》 チョウ(テウ)
13画 言部
区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F
《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈di
〈di o〉
《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)
《意味》
o〉
《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)
《意味》
 {動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。
{動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。
 {動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」
〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。
《解字》
会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。
《単語家族》
挑と同系。
{動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」
〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。
《解字》
会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。
《単語家族》
挑と同系。
 13画 言部
区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F
《音読み》 チョウ(テウ)
13画 言部
区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F
《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)
/ジョウ(デウ) 〈di
〈di o〉
《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)
《意味》
o〉
《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)
《意味》
 {動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。
{動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。
 {動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」
〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。
《解字》
会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。
《単語家族》
挑と同系。
{動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」
〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。
《解字》
会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。
《単語家族》
挑と同系。
躯 からだ🔗⭐🔉
辛 からい🔗⭐🔉
【辛】
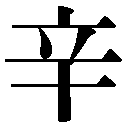 7画 辛部 [常用漢字]
区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068
《常用音訓》シン/から…い
《音読み》 シン
7画 辛部 [常用漢字]
区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068
《常用音訓》シン/から…い
《音読み》 シン
 〈x
〈x n〉
《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし
《名付け》 かのと・からし
《意味》
n〉
《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし
《名付け》 かのと・からし
《意味》
 {名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」
{名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」
 {名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」
{名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」
 {名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」
〔国〕
{名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」
〔国〕 からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」
からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」 からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」
からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」 「辛うじて」とは、やっとの意。
《解字》
「辛うじて」とは、やっとの意。
《解字》
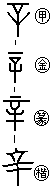 象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。
《単語家族》
新(切りたて、なま)
象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。
《単語家族》
新(切りたて、なま) 薪(切りたてのまき)と同系。
《類義》
鹹カンは、しおからい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
薪(切りたてのまき)と同系。
《類義》
鹹カンは、しおからい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
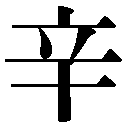 7画 辛部 [常用漢字]
区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068
《常用音訓》シン/から…い
《音読み》 シン
7画 辛部 [常用漢字]
区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068
《常用音訓》シン/から…い
《音読み》 シン
 〈x
〈x n〉
《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし
《名付け》 かのと・からし
《意味》
n〉
《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし
《名付け》 かのと・からし
《意味》
 {名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」
{名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」
 {名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」
{名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」
 {名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」
〔国〕
{名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」
〔国〕 からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」
からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」 からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」
からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」 「辛うじて」とは、やっとの意。
《解字》
「辛うじて」とは、やっとの意。
《解字》
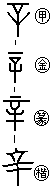 象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。
《単語家族》
新(切りたて、なま)
象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。
《単語家族》
新(切りたて、なま) 薪(切りたてのまき)と同系。
《類義》
鹹カンは、しおからい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
薪(切りたてのまき)と同系。
《類義》
鹹カンは、しおからい。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
雅 からす🔗⭐🔉
【雅】
 13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》
13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》  ガ
ガ /ゲ
/ゲ 〈y
〈y 〉/
〉/ エ
エ /ア
/ア 〈y
〈y 〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》
〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》

 {形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
 {名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
 {名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
 {形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
 {名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
 {形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
 {副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
 {名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす)
{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす) 午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》
13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》  ガ
ガ /ゲ
/ゲ 〈y
〈y 〉/
〉/ エ
エ /ア
/ア 〈y
〈y 〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》
〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》

 {形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
 {名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
 {名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
 {形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
 {名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
 {形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
 {副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
 {名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす)
{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす) 午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
韓 から🔗⭐🔉
養体 カラダヲヤシナウ🔗⭐🔉
【養体】
ヨウタイ・カラダヲヤシナウ 肉体をやしない育てる。健康に注意して、からだをじょうぶにすること。養身。〔→呂覧〕
鴉 からす🔗⭐🔉
漢字源に「から」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む
 9画 木部
区点=5944 16進=5B4C シフトJIS=9E6B
《音読み》 シ
9画 木部
区点=5944 16進=5B4C シフトJIS=9E6B
《音読み》 シ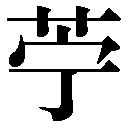 8画 艸部
区点=3587 16進=4377 シフトJIS=9297
《音読み》 チョ
8画 艸部
区点=3587 16進=4377 シフトJIS=9297
《音読み》 チョ 〉
《訓読み》 からむし/お
《意味》
{名}からむし。草の名。麻の一種。山野に自生。栽培もする。茎の皮の繊維で布を織る。〈同義語〉
〉
《訓読み》 からむし/お
《意味》
{名}からむし。草の名。麻の一種。山野に自生。栽培もする。茎の皮の繊維で布を織る。〈同義語〉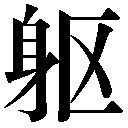 11画 身部
区点=2277 16進=366D シフトJIS=8BEB
《音読み》 ク
11画 身部
区点=2277 16進=366D シフトJIS=8BEB
《音読み》 ク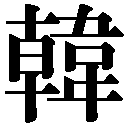 17画 韋部
区点=2058 16進=345A シフトJIS=8AD8
《音読み》 カン
17画 韋部
区点=2058 16進=345A シフトJIS=8AD8
《音読み》 カン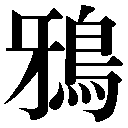 15画 鳥部
区点=8277 16進=726D シフトJIS=E9EB
《音読み》 ア
15画 鳥部
区点=8277 16進=726D シフトJIS=E9EB
《音読み》 ア 20画 鹵部
区点=8336 16進=7344 シフトJIS=EA63
《音読み》 カン(カム)
20画 鹵部
区点=8336 16進=7344 シフトJIS=EA63
《音読み》 カン(カム)