複数辞典一括検索+![]()
![]()
さん【山】🔗⭐🔉
さん【山】
①やま。また、やまを数える語。「出羽三―」
②寺院に添える語。山号。
③寺院。特に、比叡山延暦寺。
さん‐いん【山陰】🔗⭐🔉
さん‐いん【山陰】
(サンノン・センインとも)
①山の北側。山のかげ。↔山陽。
②山陰道・山陰地方の略。
⇒さんいんかいがん‐こくりつこうえん【山陰海岸国立公園】
⇒さんいん‐ちほう【山陰地方】
⇒さんいん‐どう【山陰道】
⇒さんいん‐ほんせん【山陰本線】
さんいんかいがん‐こくりつこうえん【山陰海岸国立公園】‥ヱン🔗⭐🔉
さんいんかいがん‐こくりつこうえん【山陰海岸国立公園】‥ヱン
京都府・兵庫県・鳥取県にまたがる海岸の国立公園。大部分は海食海岸であって、有名な鳥取砂丘・城崎温泉などを含む。
⇒さん‐いん【山陰】
さんいん‐ちほう【山陰地方】‥ハウ🔗⭐🔉
さんいん‐ちほう【山陰地方】‥ハウ
中国地方の北部、脊梁山脈北側の区域。鳥取県・島根県および山口県日本海側を指す。兵庫県・京都府の日本海側を含める場合もある。古代の山陰道。
⇒さん‐いん【山陰】
さんいん‐どう【山陰道】‥ダウ🔗⭐🔉
さんいん‐どう【山陰道】‥ダウ
五畿七道の一つ。丹波・丹後・但馬たじま・因幡いなば・伯耆ほうき・出雲いずも・石見いわみ・隠岐おきの8カ国。現在の中国地方・近畿地方の日本海側。また、これらの各地を通ずる街道。せんいんどう。古称、そとものみち。
⇒さん‐いん【山陰】
さんいん‐ほんせん【山陰本線】🔗⭐🔉
さんいん‐ほんせん【山陰本線】
山陰地方を縦貫するJR線。京都から福知山・鳥取・松江を経て下関市の幡生はたぶに至る。全長676.0キロメートル。
⇒さん‐いん【山陰】
さん‐う【山雨】🔗⭐🔉
さん‐う【山雨】
山から降りくる雨。山中の雨。
⇒山雨来らんと欲して風楼に満つ
○山雨来らんと欲して風楼に満つさんうきたらんとほっしてかぜろうにみつ🔗⭐🔉
○山雨来らんと欲して風楼に満つさんうきたらんとほっしてかぜろうにみつ
[許渾、咸陽城東楼詩]山雨の来る前に、高楼へ風のさっと吹き来る意。転じて、事の起ころうとする前の何となく形勢のおだやかでないさまをいう。
⇒さん‐う【山雨】
さん‐うつ【散鬱】
気鬱をはらすこと。きばらし。きさんじ。
さん‐うん【桟雲】
①雲に分け入るような高い山道。
②桟道の辺にかかっている雲。
ざん‐うん【残雲】
残っている雲。
さん‐え【三会】‥ヱ
(サンネとも)〔仏〕
①仏が成道の後、衆生済度のために行うことになっている3度の大説法会。→竜華りゅうげ三会。
②(三大会とも)
㋐南京なんきょう三会。興福寺の維摩会ゆいまえと薬師寺の最勝会と大極殿の御斎会ごさいえ。
㋑北京ほっきょう三会。法勝寺の大乗会と円宗寺の法華会および最勝会。
③禅寺で、鐘・鼓を36打つのを1会といい、3会は108打つことをいう。
さん‐え【三衣】
(サンネとも)〔仏〕僧尼の着る3種の衣、すなわち袈裟けさ。大衣の僧伽梨そうかりと七条の鬱多羅僧うったらそうと五条の安陀会あんだえ。
⇒さんえ‐いっぱつ【三衣一鉢】
⇒さんえ‐ばこ【三衣匣】
⇒さんえ‐ぶくろ【三衣袋】
さん‐え【三慧】‥ヱ
(サンネとも)〔仏〕修行の段階に従って分類した聞・思・修の三種の智慧。経典の教えを聞くことによって得られる聞慧と、真理を思惟することによって得られる思慧と、禅定を修することによって得られる修慧。
さん‐え【産穢】‥ヱ
出産の時、産児の父母の身にこうむるというけがれ。江戸時代の制では、父は7日間、母は35日間慎んだ。→触穢しょくえ
さん‐えい【山影】
山の姿。また、物にうつった山のかげ。
ざん‐えい【残英】
散り残った花。残花。
ざん‐えい【残映】
①夕映え。夕焼け。残照。
②転じて、かつては華やかであったものの名残。「明治文化の―」「―をとどめる」
ざん‐えい【残影】
おもかげ。「―を偲ぶ」
さんえ‐いっぱつ【三衣一鉢】
三衣と一個の鉄鉢。共に僧侶の携えるべきもの。
⇒さん‐え【三衣】
さん‐えき【三易】
夏・殷いん・周3代の易。夏の易は連山、殷の易は帰蔵、周の易は周易という。今伝わるものは周易のみ。
さん‐えき【山駅】
山中にある宿駅。今昔物語集14「播磨国赤穂の郡の―に住しき」
さん‐えきゆう【三益友】‥イウ
①[論語季氏「益者三友、損者三友、直きを友とし、諒まことを友とし、多聞を友とす、益なるかな」]交わって利益となる3種の友人。すなわち正直な友、誠ある友、博識な友。益者三友。↔三損友。
②[蘇軾、賛文与可梅石竹「梅寒而秀、竹痩而寿、石醜而文、是為三益之友」]風流なものとして、梅・竹・石をいう。画題ともなる。
さん‐えつ【三越】‥ヱツ
北越の3国、越前(加賀・能登を含む)・越中・越後の称。昔の越こしの国。
さん‐えつ【参謁】
参上して謁見すること。
さんえ‐ばこ【三衣匣】
三衣袋を容れる箱。居箱すえばこ。
⇒さん‐え【三衣】
さんえ‐ぶくろ【三衣袋】
三衣を入れて持ち歩く袋。
三衣袋
 ⇒さん‐え【三衣】
さん‐えん【三猿】‥ヱン
三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。
三猿(日光東照宮)
撮影:関戸 勇
⇒さん‐え【三衣】
さん‐えん【三猿】‥ヱン
三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。
三猿(日光東照宮)
撮影:関戸 勇
 さん‐えん【三遠】‥ヱン
〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭
さん‐えん【三遠】‥ヱン
〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭 かくきが提唱し、以後永く尊重された。
さん‐えん【三縁】
〔仏〕
①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。
②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。
さん‐えん【山猿】‥ヱン
山にすむ猿。やまざる。
さん‐えん【山塩】
(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩
ざん‐えん【残炎】
のこりの暑さ。残暑。
ざん‐えん【残煙】
消え残る煙。
さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥
(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。
さん‐えんき‐さん【三塩基酸】
1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。
さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】
水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。
サン‐オイル
(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。
さん‐おう【三王】‥ワウ
⇒さんのう
さん‐おう【山鶯】‥アウ
山にいるウグイス。〈日葡辞書〉
ざん‐おう【残桜】‥アウ
春過ぎてなお咲き残っている桜。
ざん‐おう【残鶯】‥アウ
春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉
さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ
大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。
さん‐おき【算置】
算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」
さん‐おん【三音】
茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。
さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ
黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。
さん‐か【三化】‥クワ
昆虫などが、1年に3世代を経過すること。
⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】
⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】
さん‐か【三夏】
夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。
さん‐か【三過】‥クワ
〔仏〕身と口と意との過ち。
さん‐か【山下】
山のもと。ふもと。→さんげ
さん‐か【山果・山菓】‥クワ
山中でみのった果物。
さん‐か【山河】
(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」
⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】
さん‐か【山家】
①山中にある家。やまが。
②⇒さんげ
さん‐か【山窩】‥クワ
(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。
さん‐か【参加】
①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」
②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。
⇒さんか‐しょう【参加賞】
さん‐か【蚕架】
四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。
さん‐か【惨禍】‥クワ
いたましいわざわい。「戦争の―」
さん‐か【産科】‥クワ
妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。
さん‐か【傘下】
中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」
さん‐か【酸化】‥クワ
(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。
⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】
⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】
⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】
⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】
⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】
⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】
⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】
⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】
⇒さんか‐クロム【酸化クロム】
⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】
⇒さんか‐ざい【酸化剤】
⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】
⇒さんか‐すう【酸化数】
⇒さんか‐すず【酸化錫】
⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】
⇒さんか‐たい【酸化帯】
⇒さんか‐チタン【酸化チタン】
⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】
⇒さんか‐てつ【酸化鉄】
⇒さんか‐どう【酸化銅】
⇒さんか‐なまり【酸化鉛】
⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】
⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】
⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】
⇒さんか‐ぶつ【酸化物】
⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】
⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】
⇒さんか‐りん【酸化燐】
さん‐か【餐霞】
(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」
さん‐か【讃歌・賛歌】
讃美の意を表した歌。「青春―」
さんが
鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。
さん‐が【参賀】
参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉
さん‐が【蚕蛾】
⇒かいこが
さん‐が【算賀】
長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。
サンガ【saṃgha 梵】
(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。
ざん‐か【残火】‥クワ
①残りの火。のこり火。
②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。
ざん‐か【残花】‥クワ
散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか
サンガー【Frederick Sanger】
イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)
サンガー【Margaret Sanger】
アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)
さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥
化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。
⇒さん‐か【酸化】
さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥
化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。
⇒さん‐か【酸化】
さん‐かい【三戒】
①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。
②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。
さん‐かい【三魁】‥クワイ
宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。
さん‐かい【三槐】‥クワイ
[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位
さん‐かい【山海】
山と海。
⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】
⇒さんかい‐へんど【山海辺土】
さん‐かい【山塊】‥クワイ
断層で周囲を限られた山地。「六甲―」
さん‐かい【参会】‥クワイ
①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」
②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」
③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」
さん‐かい【散会】‥クワイ
①会合が終わって出席者が解散すること。
②「延会1」参照。
さん‐かい【散開】
①散らばること。
②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」
⇒さんかい‐せいだん【散開星団】
さん‐がい【三界】
①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」
②(→)三世に同じ。
③(接尾語的に)
㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」
㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」
⇒さんがい‐かたく【三界火宅】
⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】
⇒さんがい‐ぼう【三界坊】
⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】
⇒さんがい‐るてん【三界流転】
⇒三界に家無し
さん‐がい【三階】
①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。
②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。
⇒さんがい‐ぶし【三階節】
さん‐がい【三蓋】
3層に重ねたこと。みつがさね。
⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】
⇒さんがい‐びし【三蓋菱】
⇒さんがい‐まつ【三蓋松】
さん‐がい【三懸・三繋・三掛】
三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。
さん‐がい【山外】‥グワイ
〔仏〕「山家さんげ1」参照。
さん‐がい【惨害】
いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」
ざん‐かい【残壊】‥クワイ
そこないやぶること。残毀。
ざん‐かい【慚悔】‥クワイ
恥じ悔いること。慚愧ざんき。
ざん‐がい【残害】
そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」
ざん‐がい【残骸】
①捨て置かれた死骸。
②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」
さんがい‐がさ【三蓋笠】
①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。
三蓋笠
かくきが提唱し、以後永く尊重された。
さん‐えん【三縁】
〔仏〕
①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。
②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。
さん‐えん【山猿】‥ヱン
山にすむ猿。やまざる。
さん‐えん【山塩】
(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩
ざん‐えん【残炎】
のこりの暑さ。残暑。
ざん‐えん【残煙】
消え残る煙。
さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥
(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。
さん‐えんき‐さん【三塩基酸】
1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。
さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】
水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。
サン‐オイル
(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。
さん‐おう【三王】‥ワウ
⇒さんのう
さん‐おう【山鶯】‥アウ
山にいるウグイス。〈日葡辞書〉
ざん‐おう【残桜】‥アウ
春過ぎてなお咲き残っている桜。
ざん‐おう【残鶯】‥アウ
春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉
さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ
大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。
さん‐おき【算置】
算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」
さん‐おん【三音】
茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。
さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ
黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。
さん‐か【三化】‥クワ
昆虫などが、1年に3世代を経過すること。
⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】
⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】
さん‐か【三夏】
夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。
さん‐か【三過】‥クワ
〔仏〕身と口と意との過ち。
さん‐か【山下】
山のもと。ふもと。→さんげ
さん‐か【山果・山菓】‥クワ
山中でみのった果物。
さん‐か【山河】
(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」
⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】
さん‐か【山家】
①山中にある家。やまが。
②⇒さんげ
さん‐か【山窩】‥クワ
(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。
さん‐か【参加】
①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」
②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。
⇒さんか‐しょう【参加賞】
さん‐か【蚕架】
四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。
さん‐か【惨禍】‥クワ
いたましいわざわい。「戦争の―」
さん‐か【産科】‥クワ
妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。
さん‐か【傘下】
中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」
さん‐か【酸化】‥クワ
(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。
⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】
⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】
⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】
⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】
⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】
⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】
⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】
⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】
⇒さんか‐クロム【酸化クロム】
⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】
⇒さんか‐ざい【酸化剤】
⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】
⇒さんか‐すう【酸化数】
⇒さんか‐すず【酸化錫】
⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】
⇒さんか‐たい【酸化帯】
⇒さんか‐チタン【酸化チタン】
⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】
⇒さんか‐てつ【酸化鉄】
⇒さんか‐どう【酸化銅】
⇒さんか‐なまり【酸化鉛】
⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】
⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】
⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】
⇒さんか‐ぶつ【酸化物】
⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】
⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】
⇒さんか‐りん【酸化燐】
さん‐か【餐霞】
(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」
さん‐か【讃歌・賛歌】
讃美の意を表した歌。「青春―」
さんが
鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。
さん‐が【参賀】
参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉
さん‐が【蚕蛾】
⇒かいこが
さん‐が【算賀】
長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。
サンガ【saṃgha 梵】
(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。
ざん‐か【残火】‥クワ
①残りの火。のこり火。
②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。
ざん‐か【残花】‥クワ
散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか
サンガー【Frederick Sanger】
イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)
サンガー【Margaret Sanger】
アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)
さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥
化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。
⇒さん‐か【酸化】
さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥
化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。
⇒さん‐か【酸化】
さん‐かい【三戒】
①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。
②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。
さん‐かい【三魁】‥クワイ
宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。
さん‐かい【三槐】‥クワイ
[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位
さん‐かい【山海】
山と海。
⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】
⇒さんかい‐へんど【山海辺土】
さん‐かい【山塊】‥クワイ
断層で周囲を限られた山地。「六甲―」
さん‐かい【参会】‥クワイ
①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」
②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」
③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」
さん‐かい【散会】‥クワイ
①会合が終わって出席者が解散すること。
②「延会1」参照。
さん‐かい【散開】
①散らばること。
②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」
⇒さんかい‐せいだん【散開星団】
さん‐がい【三界】
①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」
②(→)三世に同じ。
③(接尾語的に)
㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」
㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」
⇒さんがい‐かたく【三界火宅】
⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】
⇒さんがい‐ぼう【三界坊】
⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】
⇒さんがい‐るてん【三界流転】
⇒三界に家無し
さん‐がい【三階】
①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。
②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。
⇒さんがい‐ぶし【三階節】
さん‐がい【三蓋】
3層に重ねたこと。みつがさね。
⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】
⇒さんがい‐びし【三蓋菱】
⇒さんがい‐まつ【三蓋松】
さん‐がい【三懸・三繋・三掛】
三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。
さん‐がい【山外】‥グワイ
〔仏〕「山家さんげ1」参照。
さん‐がい【惨害】
いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」
ざん‐かい【残壊】‥クワイ
そこないやぶること。残毀。
ざん‐かい【慚悔】‥クワイ
恥じ悔いること。慚愧ざんき。
ざん‐がい【残害】
そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」
ざん‐がい【残骸】
①捨て置かれた死骸。
②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」
さんがい‐がさ【三蓋笠】
①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。
三蓋笠
 ②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。
⇒さん‐がい【三蓋】
さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥
〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。
⇒さん‐がい【三界】
さんかいかん【山海関】‥クワン
(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。
さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥
人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。
さんかいき【山槐記】‥クワイ‥
(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。
さんかいきょう【山海経】‥キヤウ
⇒せんがいきょう
さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ
〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。
さんがい‐しょてん【三界諸天】
〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。
⇒さん‐がい【三界】
さんかい‐せいだん【散開星団】
〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団
⇒さん‐かい【散開】
さん‐かいだん【三戒壇】
聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇
②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。
⇒さん‐がい【三蓋】
さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥
〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。
⇒さん‐がい【三界】
さんかいかん【山海関】‥クワン
(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。
さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥
人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。
さんかいき【山槐記】‥クワイ‥
(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。
さんかいきょう【山海経】‥キヤウ
⇒せんがいきょう
さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ
〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。
さんがい‐しょてん【三界諸天】
〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。
⇒さん‐がい【三界】
さんかい‐せいだん【散開星団】
〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団
⇒さん‐かい【散開】
さん‐かいだん【三戒壇】
聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇
 ⇒さん‐え【三衣】
さん‐えん【三猿】‥ヱン
三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。
三猿(日光東照宮)
撮影:関戸 勇
⇒さん‐え【三衣】
さん‐えん【三猿】‥ヱン
三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。
三猿(日光東照宮)
撮影:関戸 勇
 さん‐えん【三遠】‥ヱン
〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭
さん‐えん【三遠】‥ヱン
〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭 かくきが提唱し、以後永く尊重された。
さん‐えん【三縁】
〔仏〕
①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。
②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。
さん‐えん【山猿】‥ヱン
山にすむ猿。やまざる。
さん‐えん【山塩】
(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩
ざん‐えん【残炎】
のこりの暑さ。残暑。
ざん‐えん【残煙】
消え残る煙。
さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥
(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。
さん‐えんき‐さん【三塩基酸】
1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。
さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】
水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。
サン‐オイル
(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。
さん‐おう【三王】‥ワウ
⇒さんのう
さん‐おう【山鶯】‥アウ
山にいるウグイス。〈日葡辞書〉
ざん‐おう【残桜】‥アウ
春過ぎてなお咲き残っている桜。
ざん‐おう【残鶯】‥アウ
春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉
さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ
大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。
さん‐おき【算置】
算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」
さん‐おん【三音】
茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。
さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ
黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。
さん‐か【三化】‥クワ
昆虫などが、1年に3世代を経過すること。
⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】
⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】
さん‐か【三夏】
夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。
さん‐か【三過】‥クワ
〔仏〕身と口と意との過ち。
さん‐か【山下】
山のもと。ふもと。→さんげ
さん‐か【山果・山菓】‥クワ
山中でみのった果物。
さん‐か【山河】
(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」
⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】
さん‐か【山家】
①山中にある家。やまが。
②⇒さんげ
さん‐か【山窩】‥クワ
(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。
さん‐か【参加】
①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」
②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。
⇒さんか‐しょう【参加賞】
さん‐か【蚕架】
四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。
さん‐か【惨禍】‥クワ
いたましいわざわい。「戦争の―」
さん‐か【産科】‥クワ
妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。
さん‐か【傘下】
中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」
さん‐か【酸化】‥クワ
(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。
⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】
⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】
⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】
⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】
⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】
⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】
⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】
⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】
⇒さんか‐クロム【酸化クロム】
⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】
⇒さんか‐ざい【酸化剤】
⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】
⇒さんか‐すう【酸化数】
⇒さんか‐すず【酸化錫】
⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】
⇒さんか‐たい【酸化帯】
⇒さんか‐チタン【酸化チタン】
⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】
⇒さんか‐てつ【酸化鉄】
⇒さんか‐どう【酸化銅】
⇒さんか‐なまり【酸化鉛】
⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】
⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】
⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】
⇒さんか‐ぶつ【酸化物】
⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】
⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】
⇒さんか‐りん【酸化燐】
さん‐か【餐霞】
(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」
さん‐か【讃歌・賛歌】
讃美の意を表した歌。「青春―」
さんが
鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。
さん‐が【参賀】
参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉
さん‐が【蚕蛾】
⇒かいこが
さん‐が【算賀】
長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。
サンガ【saṃgha 梵】
(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。
ざん‐か【残火】‥クワ
①残りの火。のこり火。
②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。
ざん‐か【残花】‥クワ
散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか
サンガー【Frederick Sanger】
イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)
サンガー【Margaret Sanger】
アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)
さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥
化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。
⇒さん‐か【酸化】
さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥
化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。
⇒さん‐か【酸化】
さん‐かい【三戒】
①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。
②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。
さん‐かい【三魁】‥クワイ
宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。
さん‐かい【三槐】‥クワイ
[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位
さん‐かい【山海】
山と海。
⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】
⇒さんかい‐へんど【山海辺土】
さん‐かい【山塊】‥クワイ
断層で周囲を限られた山地。「六甲―」
さん‐かい【参会】‥クワイ
①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」
②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」
③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」
さん‐かい【散会】‥クワイ
①会合が終わって出席者が解散すること。
②「延会1」参照。
さん‐かい【散開】
①散らばること。
②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」
⇒さんかい‐せいだん【散開星団】
さん‐がい【三界】
①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」
②(→)三世に同じ。
③(接尾語的に)
㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」
㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」
⇒さんがい‐かたく【三界火宅】
⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】
⇒さんがい‐ぼう【三界坊】
⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】
⇒さんがい‐るてん【三界流転】
⇒三界に家無し
さん‐がい【三階】
①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。
②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。
⇒さんがい‐ぶし【三階節】
さん‐がい【三蓋】
3層に重ねたこと。みつがさね。
⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】
⇒さんがい‐びし【三蓋菱】
⇒さんがい‐まつ【三蓋松】
さん‐がい【三懸・三繋・三掛】
三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。
さん‐がい【山外】‥グワイ
〔仏〕「山家さんげ1」参照。
さん‐がい【惨害】
いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」
ざん‐かい【残壊】‥クワイ
そこないやぶること。残毀。
ざん‐かい【慚悔】‥クワイ
恥じ悔いること。慚愧ざんき。
ざん‐がい【残害】
そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」
ざん‐がい【残骸】
①捨て置かれた死骸。
②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」
さんがい‐がさ【三蓋笠】
①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。
三蓋笠
かくきが提唱し、以後永く尊重された。
さん‐えん【三縁】
〔仏〕
①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。
②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。
さん‐えん【山猿】‥ヱン
山にすむ猿。やまざる。
さん‐えん【山塩】
(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩
ざん‐えん【残炎】
のこりの暑さ。残暑。
ざん‐えん【残煙】
消え残る煙。
さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥
(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。
さん‐えんき‐さん【三塩基酸】
1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。
さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】
水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。
サン‐オイル
(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。
さん‐おう【三王】‥ワウ
⇒さんのう
さん‐おう【山鶯】‥アウ
山にいるウグイス。〈日葡辞書〉
ざん‐おう【残桜】‥アウ
春過ぎてなお咲き残っている桜。
ざん‐おう【残鶯】‥アウ
春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉
さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ
大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。
さん‐おき【算置】
算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」
さん‐おん【三音】
茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。
さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ
黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。
さん‐か【三化】‥クワ
昆虫などが、1年に3世代を経過すること。
⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】
⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】
さん‐か【三夏】
夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。
さん‐か【三過】‥クワ
〔仏〕身と口と意との過ち。
さん‐か【山下】
山のもと。ふもと。→さんげ
さん‐か【山果・山菓】‥クワ
山中でみのった果物。
さん‐か【山河】
(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」
⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】
さん‐か【山家】
①山中にある家。やまが。
②⇒さんげ
さん‐か【山窩】‥クワ
(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。
さん‐か【参加】
①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」
②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。
⇒さんか‐しょう【参加賞】
さん‐か【蚕架】
四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。
さん‐か【惨禍】‥クワ
いたましいわざわい。「戦争の―」
さん‐か【産科】‥クワ
妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。
さん‐か【傘下】
中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」
さん‐か【酸化】‥クワ
(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。
⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】
⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】
⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】
⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】
⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】
⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】
⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】
⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】
⇒さんか‐クロム【酸化クロム】
⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】
⇒さんか‐ざい【酸化剤】
⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】
⇒さんか‐すう【酸化数】
⇒さんか‐すず【酸化錫】
⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】
⇒さんか‐たい【酸化帯】
⇒さんか‐チタン【酸化チタン】
⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】
⇒さんか‐てつ【酸化鉄】
⇒さんか‐どう【酸化銅】
⇒さんか‐なまり【酸化鉛】
⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】
⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】
⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】
⇒さんか‐ぶつ【酸化物】
⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】
⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】
⇒さんか‐りん【酸化燐】
さん‐か【餐霞】
(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」
さん‐か【讃歌・賛歌】
讃美の意を表した歌。「青春―」
さんが
鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。
さん‐が【参賀】
参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉
さん‐が【蚕蛾】
⇒かいこが
さん‐が【算賀】
長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。
サンガ【saṃgha 梵】
(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。
ざん‐か【残火】‥クワ
①残りの火。のこり火。
②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。
ざん‐か【残花】‥クワ
散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか
サンガー【Frederick Sanger】
イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)
サンガー【Margaret Sanger】
アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)
さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥
化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。
⇒さん‐か【酸化】
さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥
化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。
⇒さん‐か【酸化】
さん‐かい【三戒】
①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。
②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。
さん‐かい【三魁】‥クワイ
宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。
さん‐かい【三槐】‥クワイ
[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位
さん‐かい【山海】
山と海。
⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】
⇒さんかい‐へんど【山海辺土】
さん‐かい【山塊】‥クワイ
断層で周囲を限られた山地。「六甲―」
さん‐かい【参会】‥クワイ
①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」
②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」
③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」
さん‐かい【散会】‥クワイ
①会合が終わって出席者が解散すること。
②「延会1」参照。
さん‐かい【散開】
①散らばること。
②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」
⇒さんかい‐せいだん【散開星団】
さん‐がい【三界】
①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」
②(→)三世に同じ。
③(接尾語的に)
㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」
㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」
⇒さんがい‐かたく【三界火宅】
⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】
⇒さんがい‐ぼう【三界坊】
⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】
⇒さんがい‐るてん【三界流転】
⇒三界に家無し
さん‐がい【三階】
①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。
②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。
⇒さんがい‐ぶし【三階節】
さん‐がい【三蓋】
3層に重ねたこと。みつがさね。
⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】
⇒さんがい‐びし【三蓋菱】
⇒さんがい‐まつ【三蓋松】
さん‐がい【三懸・三繋・三掛】
三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。
さん‐がい【山外】‥グワイ
〔仏〕「山家さんげ1」参照。
さん‐がい【惨害】
いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」
ざん‐かい【残壊】‥クワイ
そこないやぶること。残毀。
ざん‐かい【慚悔】‥クワイ
恥じ悔いること。慚愧ざんき。
ざん‐がい【残害】
そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」
ざん‐がい【残骸】
①捨て置かれた死骸。
②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」
さんがい‐がさ【三蓋笠】
①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。
三蓋笠
 ②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。
⇒さん‐がい【三蓋】
さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥
〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。
⇒さん‐がい【三界】
さんかいかん【山海関】‥クワン
(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。
さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥
人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。
さんかいき【山槐記】‥クワイ‥
(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。
さんかいきょう【山海経】‥キヤウ
⇒せんがいきょう
さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ
〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。
さんがい‐しょてん【三界諸天】
〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。
⇒さん‐がい【三界】
さんかい‐せいだん【散開星団】
〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団
⇒さん‐かい【散開】
さん‐かいだん【三戒壇】
聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇
②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。
⇒さん‐がい【三蓋】
さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥
〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。
⇒さん‐がい【三界】
さんかいかん【山海関】‥クワン
(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。
さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥
人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。
さんかいき【山槐記】‥クワイ‥
(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。
さんかいきょう【山海経】‥キヤウ
⇒せんがいきょう
さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ
〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。
さんがい‐しょてん【三界諸天】
〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。
⇒さん‐がい【三界】
さんかい‐せいだん【散開星団】
〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団
⇒さん‐かい【散開】
さん‐かいだん【三戒壇】
聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇
さん‐えい【山影】🔗⭐🔉
さん‐えい【山影】
山の姿。また、物にうつった山のかげ。
さん‐えき【山駅】🔗⭐🔉
さん‐えき【山駅】
山中にある宿駅。今昔物語集14「播磨国赤穂の郡の―に住しき」
そとも‐の‐みち【山陰道】🔗⭐🔉
そとも‐の‐みち【山陰道】
山陰道さんいんどうの古称。天武紀下「山陰そとものみち」
⇒そと‐も【背面】
むれ【山】🔗⭐🔉
むれ【山】
(朝鮮語からか)やま。斉明紀「今城なる小お―が上に」
やま【山】🔗⭐🔉
やま【山】
①平地よりも高く隆起した地塊。谷と谷との間に挟まれた凸起部。古く、神が降下し領する所として信仰の対象とされた。万葉集17「すめ神の裾廻すそみの―の」。「―に登る」「富士は日本一の―」
②特に比叡山ひえいざん、また、そこにある延暦寺えんりゃくじの称。園城寺おんじょうじ(通称、三井寺)を寺というのに対していう。
③鉱山のこと。
④山陵。御陵ごりょう。
⑤猪・鹿などを捕らえるために仕掛ける落し穴。〈日葡辞書〉
⑥うず高く盛ったもの。山にまねて作ったもの。「塵の―」
⑦山形になった所。「ねじ―」
⑧山林。平地の林をもいう。
⑨山の形に盛り上げたものを数える語。「一―千円」
⑩物事の多く積み重なっていること。また、そのもの。「借金の―」
⑪物事の絶頂。最も肝要な部分。極点。とうげ。分岐点。「今日一日が―だ」「―を越す」
⑫(山師やましの仕事のように)万一の幸をねがってすること。やまごと。やまかん。「―が外れる」
⑬檀尻だんじりのこと。
⑭山鉾やまぼこの略。
⑮(名詞に冠して)同類のうちで、山野に自生するもの。また、恐ろしいもの。「―ゆり」「―桜」「―猫」
⇒山が当たる
⇒山が見える
⇒山から里へ
⇒山高きが故に貴からず
⇒山高く水長し
⇒山高ければ谷深し
⇒山と言えば川
⇒山に千年海に千年
⇒山眠る
⇒山のことは樵に聞け
⇒山粧う
⇒山笑う
⇒山を当てる
⇒山を鋳、海を煮る
⇒山を掛ける
⇒山をなす
⇒山を抜く力
⇒山を張る
やま‐い【山井】‥ヰ🔗⭐🔉
やま‐い【山井】‥ヰ
山中の水のわき出るところ。やまのい。宇津保物語楼上下「楼の南なる―のしりひきたるに」
やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】🔗⭐🔉
やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】
3月3日の節句に、野山や磯に出て遊び祝宴すること。
やま‐いも【山芋・薯蕷】🔗⭐🔉
やま‐いも【山芋・薯蕷】
(→)「やまのいも」に同じ。〈[季]秋〉。新撰字鏡7「暑預、山伊母」
やま‐うば【山姥】🔗⭐🔉
やま‐うば【山姥】
深山に住み、怪力を発揮するなどと考えられている伝説的な女。山女。山に住む鬼女。やまんば。
⇒やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】🔗⭐🔉
やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】
(壱岐で)12月20日のこと。→果はての二十日
⇒やま‐うば【山姥】
○山が当たるやまがあたる🔗⭐🔉
○山が当たるやまがあたる
万一の幸運を期待した見当が適中する。試験などの予想が当たる。↔山が外れる
⇒やま【山】
やま‐かい【山峡】‥カヒ
(古くはヤマガイ)山と山との間。やまあい。万葉集17「―に咲ける桜を」
やま‐がえり【山回り・山帰り】‥ガヘリ
①年を越えて山で羽毛をかえた鷹。山家集「巣鷹渡る…なほ木に帰る―かな」
②山から帰ること。特に大山参りから帰ること。誹風柳多留15「―あたり近所は笛だらけ」
やま‐がえる【山蛙】‥ガヘル
アカガエルの別称。
やま‐かがし【赤楝蛇・山楝蛇】
ヘビの一種。全長約70〜120センチメートル、水辺に普通で、カエルなどを捕食する。背面はオリーブ色、黒斑が多く、体側には紅色の斑点がある。上顎の奥と頸部に毒腺がある。奥歯は長く、毒牙の機能をもち、深く咬まれると、腫れることや血が止まらないこともあり、時に致命的。本州以南、朝鮮半島南部・中国・台湾に分布。〈[季]夏〉
ヤマカガシ
提供:東京動物園協会
 やま‐かがち【蟒蛇】
うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉
やま‐がく・る【山隠る】
〔自四・下二〕
山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」
やま‐がくれ【山隠れ】
山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」
やま‐かけ【山掛け】
①高く積むこと。
②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。
⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
やま‐かげ【山陰】
山裾で陰になること。また、その場所。
やま‐かげ【山影】
山の姿。山の形。
やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。
⇒やま‐かけ【山掛け】
やま‐かご【山駕籠】
竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。
やま‐がさ【山笠】
①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。
②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉
やま‐かじ【山火事】‥クワ‥
山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉
やま‐がしゅう【山何首烏】
ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。
やま‐がしら【山頭】
田植作業の指揮者、また世話役。
やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ
山家に住んでいること。また、そのすまい。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ
①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」
②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」
やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥
〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」
やま‐かぜ【山風】
①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」
②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風
やま‐かせぎ【山稼ぎ】
山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。
やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ
江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)
→著作:『配所残筆』
→著作:『聖教要録』
⇒やまが【山鹿】
やまが‐そだち【山家育ち】
山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かた【山方】
山の方向。山の地方。
やまがた【山片】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】
やま‐がた【山形・山型】
①山に似た形。
②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉
③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。
④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。
⇒やまがた‐カッター【山形カッター】
⇒やまがた‐こう【山型鋼】
やまがた【山形】
①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。
→花笠音頭
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。
⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
⇒やまがた‐だいがく【山形大学】
やま‐がた【山県】
山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」
やまがた【山県】
岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。
やまがた【山県】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】
⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】
⇒やまがた‐だいに【山県大弐】
やまがた‐ありとも【山県有朋】
軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)
山県有朋
提供:毎日新聞社
やま‐かがち【蟒蛇】
うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉
やま‐がく・る【山隠る】
〔自四・下二〕
山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」
やま‐がくれ【山隠れ】
山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」
やま‐かけ【山掛け】
①高く積むこと。
②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。
⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
やま‐かげ【山陰】
山裾で陰になること。また、その場所。
やま‐かげ【山影】
山の姿。山の形。
やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。
⇒やま‐かけ【山掛け】
やま‐かご【山駕籠】
竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。
やま‐がさ【山笠】
①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。
②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉
やま‐かじ【山火事】‥クワ‥
山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉
やま‐がしゅう【山何首烏】
ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。
やま‐がしら【山頭】
田植作業の指揮者、また世話役。
やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ
山家に住んでいること。また、そのすまい。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ
①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」
②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」
やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥
〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」
やま‐かぜ【山風】
①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」
②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風
やま‐かせぎ【山稼ぎ】
山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。
やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ
江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)
→著作:『配所残筆』
→著作:『聖教要録』
⇒やまが【山鹿】
やまが‐そだち【山家育ち】
山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かた【山方】
山の方向。山の地方。
やまがた【山片】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】
やま‐がた【山形・山型】
①山に似た形。
②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉
③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。
④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。
⇒やまがた‐カッター【山形カッター】
⇒やまがた‐こう【山型鋼】
やまがた【山形】
①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。
→花笠音頭
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。
⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
⇒やまがた‐だいがく【山形大学】
やま‐がた【山県】
山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」
やまがた【山県】
岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。
やまがた【山県】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】
⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】
⇒やまがた‐だいに【山県大弐】
やまがた‐ありとも【山県有朋】
軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)
山県有朋
提供:毎日新聞社
 ⇒やまがた【山県】
やまがた‐カッター【山形カッター】
(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。
山形カッター
⇒やまがた【山県】
やまがた‐カッター【山形カッター】
(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。
山形カッター
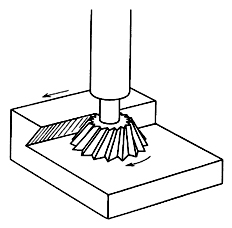 ⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ
型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。
山型鋼
⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ
型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。
山型鋼
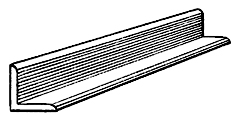 ⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥
江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)
⇒やまがた【山県】
やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
「ミニ新幹線」参照。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいがく【山形大学】
国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいに【山県大弐】
江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件
→資料:『柳子新論』
⇒やまがた【山県】
やま‐がたな【山刀】
きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。
やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ
江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)
→著作:『夢の代』
⇒やまがた【山片】
やま‐がつ【山賤】
①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」
②人をあざけっていう語。
③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」
やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥
括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。
やま‐がに【山蟹】
山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉
やま‐がね【山金】
山から掘り出したままの銅。
やま‐かます【山叺】
ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。
やま‐がみ【山神】
山を守る神。山をつかさどる神。
⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥
江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)
⇒やまがた【山県】
やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
「ミニ新幹線」参照。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいがく【山形大学】
国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいに【山県大弐】
江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件
→資料:『柳子新論』
⇒やまがた【山県】
やま‐がたな【山刀】
きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。
やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ
江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)
→著作:『夢の代』
⇒やまがた【山片】
やま‐がつ【山賤】
①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」
②人をあざけっていう語。
③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」
やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥
括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。
やま‐がに【山蟹】
山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉
やま‐がね【山金】
山から掘り出したままの銅。
やま‐かます【山叺】
ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。
やま‐がみ【山神】
山を守る神。山をつかさどる神。
 やま‐かがち【蟒蛇】
うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉
やま‐がく・る【山隠る】
〔自四・下二〕
山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」
やま‐がくれ【山隠れ】
山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」
やま‐かけ【山掛け】
①高く積むこと。
②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。
⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
やま‐かげ【山陰】
山裾で陰になること。また、その場所。
やま‐かげ【山影】
山の姿。山の形。
やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。
⇒やま‐かけ【山掛け】
やま‐かご【山駕籠】
竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。
やま‐がさ【山笠】
①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。
②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉
やま‐かじ【山火事】‥クワ‥
山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉
やま‐がしゅう【山何首烏】
ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。
やま‐がしら【山頭】
田植作業の指揮者、また世話役。
やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ
山家に住んでいること。また、そのすまい。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ
①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」
②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」
やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥
〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」
やま‐かぜ【山風】
①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」
②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風
やま‐かせぎ【山稼ぎ】
山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。
やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ
江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)
→著作:『配所残筆』
→著作:『聖教要録』
⇒やまが【山鹿】
やまが‐そだち【山家育ち】
山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かた【山方】
山の方向。山の地方。
やまがた【山片】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】
やま‐がた【山形・山型】
①山に似た形。
②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉
③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。
④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。
⇒やまがた‐カッター【山形カッター】
⇒やまがた‐こう【山型鋼】
やまがた【山形】
①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。
→花笠音頭
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。
⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
⇒やまがた‐だいがく【山形大学】
やま‐がた【山県】
山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」
やまがた【山県】
岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。
やまがた【山県】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】
⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】
⇒やまがた‐だいに【山県大弐】
やまがた‐ありとも【山県有朋】
軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)
山県有朋
提供:毎日新聞社
やま‐かがち【蟒蛇】
うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉
やま‐がく・る【山隠る】
〔自四・下二〕
山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」
やま‐がくれ【山隠れ】
山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」
やま‐かけ【山掛け】
①高く積むこと。
②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。
⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
やま‐かげ【山陰】
山裾で陰になること。また、その場所。
やま‐かげ【山影】
山の姿。山の形。
やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】
八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。
⇒やま‐かけ【山掛け】
やま‐かご【山駕籠】
竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。
やま‐がさ【山笠】
①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。
②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉
やま‐かじ【山火事】‥クワ‥
山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉
やま‐がしゅう【山何首烏】
ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。
やま‐がしら【山頭】
田植作業の指揮者、また世話役。
やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ
山家に住んでいること。また、そのすまい。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ
①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」
②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」
やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥
〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」
やま‐かぜ【山風】
①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」
②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風
やま‐かせぎ【山稼ぎ】
山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。
やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ
江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)
→著作:『配所残筆』
→著作:『聖教要録』
⇒やまが【山鹿】
やまが‐そだち【山家育ち】
山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。
⇒やま‐が【山家】
やま‐かた【山方】
山の方向。山の地方。
やまがた【山片】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】
やま‐がた【山形・山型】
①山に似た形。
②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉
③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。
④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。
⇒やまがた‐カッター【山形カッター】
⇒やまがた‐こう【山型鋼】
やまがた【山形】
①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。
→花笠音頭
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。
⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
⇒やまがた‐だいがく【山形大学】
やま‐がた【山県】
山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」
やまがた【山県】
岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。
やまがた【山県】
姓氏の一つ。
⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】
⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】
⇒やまがた‐だいに【山県大弐】
やまがた‐ありとも【山県有朋】
軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)
山県有朋
提供:毎日新聞社
 ⇒やまがた【山県】
やまがた‐カッター【山形カッター】
(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。
山形カッター
⇒やまがた【山県】
やまがた‐カッター【山形カッター】
(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。
山形カッター
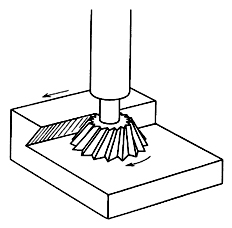 ⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ
型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。
山型鋼
⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ
型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。
山型鋼
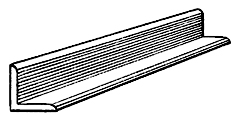 ⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥
江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)
⇒やまがた【山県】
やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
「ミニ新幹線」参照。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいがく【山形大学】
国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいに【山県大弐】
江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件
→資料:『柳子新論』
⇒やまがた【山県】
やま‐がたな【山刀】
きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。
やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ
江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)
→著作:『夢の代』
⇒やまがた【山片】
やま‐がつ【山賤】
①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」
②人をあざけっていう語。
③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」
やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥
括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。
やま‐がに【山蟹】
山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉
やま‐がね【山金】
山から掘り出したままの銅。
やま‐かます【山叺】
ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。
やま‐がみ【山神】
山を守る神。山をつかさどる神。
⇒やま‐がた【山形・山型】
やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥
江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)
⇒やまがた【山県】
やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】
「ミニ新幹線」参照。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいがく【山形大学】
国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。
⇒やまがた【山形】
やまがた‐だいに【山県大弐】
江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件
→資料:『柳子新論』
⇒やまがた【山県】
やま‐がたな【山刀】
きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。
やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ
江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)
→著作:『夢の代』
⇒やまがた【山片】
やま‐がつ【山賤】
①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」
②人をあざけっていう語。
③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」
やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥
括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。
やま‐がに【山蟹】
山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉
やま‐がね【山金】
山から掘り出したままの銅。
やま‐かます【山叺】
ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。
やま‐がみ【山神】
山を守る神。山をつかさどる神。
やま‐がく・る【山隠る】🔗⭐🔉
やま‐がく・る【山隠る】
〔自四・下二〕
山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」
やま‐がくれ【山隠れ】🔗⭐🔉
やま‐がくれ【山隠れ】
山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」
やま‐かげ【山陰】🔗⭐🔉
やま‐かげ【山陰】
山裾で陰になること。また、その場所。
やま‐かげ【山影】🔗⭐🔉
やま‐かげ【山影】
山の姿。山の形。
○山が見えるやまがみえる🔗⭐🔉
○山が見えるやまがみえる
前途の見込みが立つ。困難な事業などの完成が近づいたことにいう。
⇒やま【山】
やま‐から【山柄】
山の品格。万葉集3「み吉野の吉野の宮は―し貴くあるらし」
やま‐がら【山雀】
スズメ目シジュウカラ科の鳥。頭上・咽喉のどは黒色。額から頸にかけて黄白色。背の上部と胸・腹は栗色。翼・尾羽は灰青色。日本各地の山林にすみ、昆虫などを食う。敏捷・怜悧で、籠鳥として愛玩、神社などでおみくじを引く鳥としても親しまれた。やまがらめ。〈[季]夏〉
やまがら
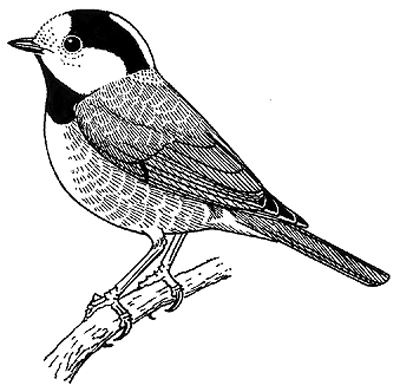 ヤマガラ
提供:OPO
ヤマガラ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒やまがら‐りこん【山雀利根】
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒やまがら‐りこん【山雀利根】
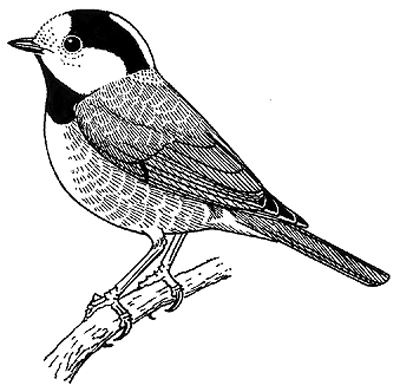 ヤマガラ
提供:OPO
ヤマガラ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒やまがら‐りこん【山雀利根】
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒やまがら‐りこん【山雀利根】
○山から里へやまからさとへ🔗⭐🔉
○山から里へやまからさとへ
(「山」は寺の意。普通は里の檀家が寺へ物を贈る)物事があべこべであることのたとえ。寺から里へ。
⇒やま【山】
やま‐がらす【山烏】
①山にすむ烏。
②ハシブトガラスの別称。
③ミヤマガラスの別称。
④色の黒い人をあざけっていう語。
やまがら‐りこん【山雀利根】
(山雀が、おみくじを引く芸しかできないとして)一つのことは分かっているが、それを一般に応用できないこと。また、その人。小才を侮あなどっていう。
⇒やま‐がら【山雀】
やま‐がり【山狩】
①山で鳥獣を狩ること。
②犯罪者などが山へ逃げこんだのを大勢で捜索すること。
やまが‐りゅう【山鹿流】‥リウ
兵学の一派。北条流を学んだ山鹿素行が独立してからのもの。「―の陣太鼓」
⇒やまが【山鹿】
やま‐かわ【山川】‥カハ
①山と川。
②山の神と川の神。山の精と川の精。万葉集1「―もよりて仕ふる神の御代かも」
③山川酒の略。
⇒やまかわ‐ざけ【山川酒】
やまかわ【山川】‥カハ
姓氏の一つ。
⇒やまかわ‐きくえ【山川菊栄】
⇒やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】
⇒やまかわ‐ひとし【山川均】
やま‐がわ【山川】‥ガハ
山中を流れる川。山から流れる川。万葉集10「雨ふればたぎつ―岩に触れ」
やま‐がわ【山側】‥ガハ
山に沿った方。
やまかわ‐きくえ【山川菊栄】‥カハ‥
女性運動家。東京生れ。女子英学塾卒。山川均と結婚、伊藤野枝らと赤瀾せきらん会を結成し、女性解放運動で活躍。第二次大戦後、日本社会党に属し、新設の労働省婦人少年局長となる。(1890〜1980)
山川菊栄
提供:岩波書店
 山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
 ⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ
物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)
⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥
白酒の異称。山川白酒。
⇒やま‐かわ【山川】
やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥
社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)
山川均
撮影:田村 茂
⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ
物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)
⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥
白酒の異称。山川白酒。
⇒やま‐かわ【山川】
やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥
社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)
山川均
撮影:田村 茂
 山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
 ⇒やまかわ【山川】
やま‐かん【山勘】
①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。
②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」
やま‐かんむり【山冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。
や‐まき【八巻】
八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」
やまき【山木】
姓氏の一つ。
⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】
やま‐き【山気】
(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」
やま‐ぎ【山木】
山に生えている木。
やまき‐かねたか【山木兼隆】
平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)
⇒やまき【山木】
やま‐ぎし【山岸】
山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」
やま‐きず【山傷・山疵】
石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。
やま‐ぎり【山桐】
〔植〕
①アブラギリの別称。〈[季]夏〉
②ハリギリの別称。
③サワグルミの別称。
やま‐ぎり【山霧】
山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」
やまぎわ【山極】‥ギハ
姓氏の一つ。
⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】
やま‐ぎわ【山際】‥ギハ
山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」
やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ
病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)
⇒やまぎわ【山極】
やま‐きん【山金】
鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金
やま‐くさ【山草】
①山に生えている草。
②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」
やま‐くじ【山公事】
山林または鉱山に関する訴訟。
やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ
猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉
やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ
急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。
やま‐ぐち【山口】
①山への入り口。
②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。
③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」
⇒やまぐち‐さい【山口祭】
やまぐち【山口】
①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。
→男なら
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。
⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】
やまぐち【山口】
姓氏の一つ。
⇒やまぐち‐かおる【山口薫】
⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】
⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】
⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】
⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】
⇒やまぐち‐たけお【山口長男】
⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル
洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)
山口薫
撮影:田沼武能
⇒やまかわ【山川】
やま‐かん【山勘】
①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。
②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」
やま‐かんむり【山冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。
や‐まき【八巻】
八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」
やまき【山木】
姓氏の一つ。
⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】
やま‐き【山気】
(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」
やま‐ぎ【山木】
山に生えている木。
やまき‐かねたか【山木兼隆】
平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)
⇒やまき【山木】
やま‐ぎし【山岸】
山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」
やま‐きず【山傷・山疵】
石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。
やま‐ぎり【山桐】
〔植〕
①アブラギリの別称。〈[季]夏〉
②ハリギリの別称。
③サワグルミの別称。
やま‐ぎり【山霧】
山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」
やまぎわ【山極】‥ギハ
姓氏の一つ。
⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】
やま‐ぎわ【山際】‥ギハ
山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」
やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ
病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)
⇒やまぎわ【山極】
やま‐きん【山金】
鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金
やま‐くさ【山草】
①山に生えている草。
②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」
やま‐くじ【山公事】
山林または鉱山に関する訴訟。
やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ
猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉
やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ
急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。
やま‐ぐち【山口】
①山への入り口。
②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。
③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」
⇒やまぐち‐さい【山口祭】
やまぐち【山口】
①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。
→男なら
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。
⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】
やまぐち【山口】
姓氏の一つ。
⇒やまぐち‐かおる【山口薫】
⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】
⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】
⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】
⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】
⇒やまぐち‐たけお【山口長男】
⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル
洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)
山口薫
撮影:田沼武能
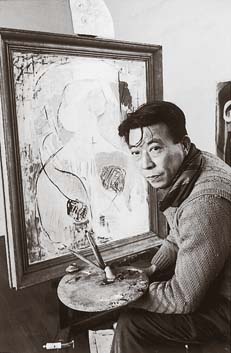 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ
日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)
山口華楊
撮影:田沼武能
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ
日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)
山口華楊
撮影:田沼武能
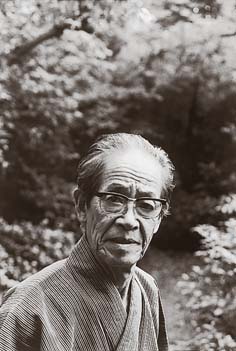 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐さい【山口祭】
伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。
⇒やま‐ぐち【山口】
やまぐち‐せいし【山口誓子】
俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)
山口誓子
提供:毎日新聞社
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐さい【山口祭】
伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。
⇒やま‐ぐち【山口】
やまぐち‐せいし【山口誓子】
俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)
山口誓子
提供:毎日新聞社
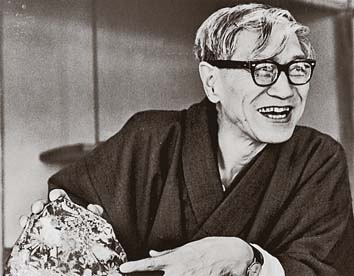 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐せいそん【山口青邨】
俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)
山口青邨
提供:毎日新聞社
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐せいそん【山口青邨】
俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)
山口青邨
提供:毎日新聞社
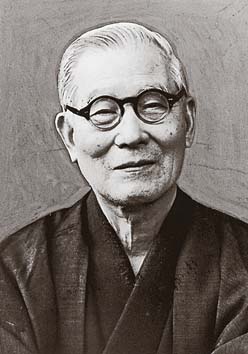 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ
江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐だいがく【山口大学】
国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ
画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】
狭山湖の別名。
やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ
語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。
やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)
山口蓬春
撮影:田沼武能
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ
江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐だいがく【山口大学】
国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ
画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】
狭山湖の別名。
やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ
語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。
やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)
山口蓬春
撮影:田沼武能
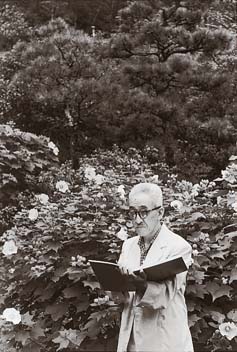 ⇒やまぐち【山口】
やま‐くどき【山口説】
江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」
やま‐ぐに【山国】
山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」
やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ
大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。
やま‐ぐま【山隈】
山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。
やま‐ぐも【山雲】
山にたちこめている雲。山に起こる雲。
やま‐ぐり【山栗】
山地に自生する栗。〈[季]秋〉
やま‐ぐるま【山車】
ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。
やま‐ぐわ【山桑】‥グハ
①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。
②ヤマボウシの別称。
やま‐け【山気】
⇒やまき
やま‐げた【山下駄】
杉などで作った粗末な下駄。
やま‐げら【山啄木鳥】
キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。
やま‐こ【山子】
①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉
②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。
やま‐ご【山子】
木樵きこりなど山仕事をする者の総称。
やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ
クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。
やま‐ごえ【山肥】
緑肥りょくひのこと。
やま‐ごえ【山越え】
①山を越えること。また、その所。山越し。
②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。
⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。
⇒やま‐ごえ【山越え】
やま‐こかし【山こかし】
①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」
②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。
やま‐ごけ【山苔】
細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。
やま‐ごころ【山心】
①(→)「のごころ」に同じ。
②山気やまき。
やま‐ごし【山越し】
①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。
②山を越したむこう側。山のむこう。
やま‐ごと【山事】
投機的または冒険的な事業。
やま‐ことば【山言葉・山詞】
猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。
やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ
①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。
ヤマゴボウ
提供:OPO
⇒やまぐち【山口】
やま‐くどき【山口説】
江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」
やま‐ぐに【山国】
山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」
やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ
大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。
やま‐ぐま【山隈】
山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。
やま‐ぐも【山雲】
山にたちこめている雲。山に起こる雲。
やま‐ぐり【山栗】
山地に自生する栗。〈[季]秋〉
やま‐ぐるま【山車】
ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。
やま‐ぐわ【山桑】‥グハ
①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。
②ヤマボウシの別称。
やま‐け【山気】
⇒やまき
やま‐げた【山下駄】
杉などで作った粗末な下駄。
やま‐げら【山啄木鳥】
キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。
やま‐こ【山子】
①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉
②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。
やま‐ご【山子】
木樵きこりなど山仕事をする者の総称。
やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ
クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。
やま‐ごえ【山肥】
緑肥りょくひのこと。
やま‐ごえ【山越え】
①山を越えること。また、その所。山越し。
②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。
⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。
⇒やま‐ごえ【山越え】
やま‐こかし【山こかし】
①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」
②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。
やま‐ごけ【山苔】
細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。
やま‐ごころ【山心】
①(→)「のごころ」に同じ。
②山気やまき。
やま‐ごし【山越し】
①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。
②山を越したむこう側。山のむこう。
やま‐ごと【山事】
投機的または冒険的な事業。
やま‐ことば【山言葉・山詞】
猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。
やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ
①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。
ヤマゴボウ
提供:OPO
 ②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉
やま‐ごもり【山籠り】
山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」
やま‐ごや【山小屋】
登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。
やまごろ‐いんもち【山五郎家持】
作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。
やま‐さか【山坂】
①山と坂。
②(ヤマザカとも)山の中にある坂。
やま‐さか【山険】
山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」
やまざき【山崎】
京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。
⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】
やまざき【山崎】
(ヤマサキとも)姓氏の一つ。
⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】
⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】
⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】
やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ
(→)垂加神道に同じ。
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥
木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)
山崎朝雲
撮影:田沼武能
②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉
やま‐ごもり【山籠り】
山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」
やま‐ごや【山小屋】
登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。
やまごろ‐いんもち【山五郎家持】
作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。
やま‐さか【山坂】
①山と坂。
②(ヤマザカとも)山の中にある坂。
やま‐さか【山険】
山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」
やまざき【山崎】
京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。
⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】
やまざき【山崎】
(ヤマサキとも)姓氏の一つ。
⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】
⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】
⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】
やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ
(→)垂加神道に同じ。
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥
木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)
山崎朝雲
撮影:田沼武能
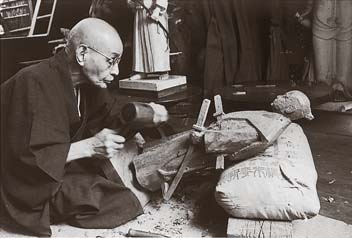 ⇒やまざき【山崎】
やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥
地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ
1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。
⇒やまざき【山崎】
やま‐ざくら【山桜】
①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。
②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉
ヤマザクラ
撮影:関戸 勇
⇒やまざき【山崎】
やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥
地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ
1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。
⇒やまざき【山崎】
やま‐ざくら【山桜】
①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。
②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉
ヤマザクラ
撮影:関戸 勇
 ⇒やまざくら‐ど【山桜戸】
やまざくら‐ど【山桜戸】
①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」
②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」
⇒やま‐ざくら【山桜】
やま‐さち【山幸】
①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」
②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。
③「海幸山幸」参照。
やま‐さつ【山猟師】
(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」
やま‐ざと【山里】
①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」
②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」
⇒やまざと‐びと【山里人】
⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】
やまざと‐びと【山里人】
山里に住む人。やまびと。
⇒やま‐ざと【山里】
やまざと・ぶ【山里ぶ】
〔自上二〕
山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」
⇒やま‐ざと【山里】
やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ
山にある野生のサネカズラ。
やま‐さ・ぶ【山さぶ】
〔自上二〕
山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」
やま‐ざる【山猿】
①山にすむ猿。
②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。
やま‐さわ【山沢】‥サハ
①山と沢。また、山間の沢。
②多いこと。たくさん。さわやま。
⇒やまさわ‐びと【山沢人】
やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥
山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」
⇒やま‐さわ【山沢】
やま‐さん【山様】
江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。
やまし【知母】
⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉
やま‐し【山師】
①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。
②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。
⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】
やま‐じ【山路】‥ヂ
山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」
やまじ【山路】‥ヂ
姓氏の一つ。
⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】
やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥
ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)
⇒やまじ【山路】
やまし・い【疾しい・疚しい】
〔形〕[文]やま・し(シク)
(「病む」の形容詞化)
①病気の感じである。気分がすぐれない。
②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。
③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」
やま‐じお【山塩】‥ジホ
山からとる塩。岩塩がんえん。
やまじ‐かぜ【やまじ風】
愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。
やま‐しぎ【山鷸・山鴫】
シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉
やましぎ
⇒やまざくら‐ど【山桜戸】
やまざくら‐ど【山桜戸】
①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」
②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」
⇒やま‐ざくら【山桜】
やま‐さち【山幸】
①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」
②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。
③「海幸山幸」参照。
やま‐さつ【山猟師】
(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」
やま‐ざと【山里】
①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」
②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」
⇒やまざと‐びと【山里人】
⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】
やまざと‐びと【山里人】
山里に住む人。やまびと。
⇒やま‐ざと【山里】
やまざと・ぶ【山里ぶ】
〔自上二〕
山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」
⇒やま‐ざと【山里】
やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ
山にある野生のサネカズラ。
やま‐さ・ぶ【山さぶ】
〔自上二〕
山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」
やま‐ざる【山猿】
①山にすむ猿。
②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。
やま‐さわ【山沢】‥サハ
①山と沢。また、山間の沢。
②多いこと。たくさん。さわやま。
⇒やまさわ‐びと【山沢人】
やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥
山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」
⇒やま‐さわ【山沢】
やま‐さん【山様】
江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。
やまし【知母】
⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉
やま‐し【山師】
①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。
②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。
⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】
やま‐じ【山路】‥ヂ
山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」
やまじ【山路】‥ヂ
姓氏の一つ。
⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】
やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥
ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)
⇒やまじ【山路】
やまし・い【疾しい・疚しい】
〔形〕[文]やま・し(シク)
(「病む」の形容詞化)
①病気の感じである。気分がすぐれない。
②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。
③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」
やま‐じお【山塩】‥ジホ
山からとる塩。岩塩がんえん。
やまじ‐かぜ【やまじ風】
愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。
やま‐しぎ【山鷸・山鴫】
シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉
やましぎ
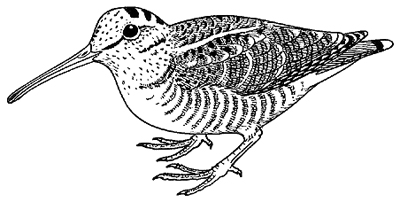 ヤマシギ
提供:OPO
ヤマシギ
提供:OPO
 やま‐しごと【山仕事】
①山でする仕事。
②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。
やま‐しず【山賤】‥シヅ
(→)「やまがつ」に同じ。
やま‐じそ【山紫蘇】
シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。
やま‐した【山下】
山のした。山のふもと。山もと。
⇒やました‐かげ【山下陰】
⇒やました‐かぜ【山下風】
⇒やました‐つゆ【山下露】
⇒やました‐の【山下の】
⇒やました‐みず【山下水】
やました【山下】
姓氏の一つ。
⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】
やました‐かげ【山下陰】
山の麓の陰となる所。
⇒やま‐した【山下】
やました‐かぜ【山下風】
山から吹きおろす風。山おろし。
⇒やま‐した【山下】
やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)
山下新太郎
撮影:田沼武能
やま‐しごと【山仕事】
①山でする仕事。
②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。
やま‐しず【山賤】‥シヅ
(→)「やまがつ」に同じ。
やま‐じそ【山紫蘇】
シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。
やま‐した【山下】
山のした。山のふもと。山もと。
⇒やました‐かげ【山下陰】
⇒やました‐かぜ【山下風】
⇒やました‐つゆ【山下露】
⇒やました‐の【山下の】
⇒やました‐みず【山下水】
やました【山下】
姓氏の一つ。
⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】
やました‐かげ【山下陰】
山の麓の陰となる所。
⇒やま‐した【山下】
やました‐かぜ【山下風】
山から吹きおろす風。山おろし。
⇒やま‐した【山下】
やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)
山下新太郎
撮影:田沼武能
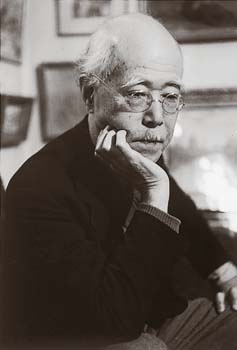 ⇒やました【山下】
やました‐つゆ【山下露】
山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。
⇒やま‐した【山下】
やました‐の【山下の】
山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」
⇒やま‐した【山下】
やました‐みず【山下水】‥ミヅ
山のふもとを流れる水。
⇒やま‐した【山下】
やましな【山科・山階】
京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。
山科 天智天皇陵
撮影:的場 啓
⇒やました【山下】
やました‐つゆ【山下露】
山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。
⇒やま‐した【山下】
やました‐の【山下の】
山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」
⇒やま‐した【山下】
やました‐みず【山下水】‥ミヅ
山のふもとを流れる水。
⇒やま‐した【山下】
やましな【山科・山階】
京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。
山科 天智天皇陵
撮影:的場 啓
 ▷行政区名は「山科区」と書く。
⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】
⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】
⇒やましな‐でら【山階寺】
⇒やましな‐どうり【山階道理】
⇒やましな‐べついん【山科別院】
やましな【山科】
姓氏の一つ。藤原北家四条流。
⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】
⇒やましな‐りゅう【山科流】
やましな‐かんきょ【山科閑居】
浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ
(→)山科別院に同じ。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐でら【山階寺】
興福寺の旧称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥
(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ときつぐ【山科言継】
戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)
⇒やましな【山科】
やましな‐の‐みや【山階宮】
旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。
やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン
京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐りゅう【山科流】‥リウ
公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流
⇒やましな【山科】
やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン
山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。
⇒やま‐し【山師】
やま‐しば【山柴】
山にある柴。山から採って来た柴。
やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ
(愛知県三河地方で)火葬すること。
やま‐しみず【山清水】‥シミヅ
山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」
やま‐じゃり【山砂利】
河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。
やま‐しゅ【山衆】
(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」
やま‐じるし【山印】
①(→)木印きじるしに同じ。
②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。
やま‐しるべ【山導】
山の案内。また、その人。
やましろ【山城・山背】
旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。
⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
⇒やましろ‐もの【山城物】
やま‐じろ【山城】
山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ
やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥
石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。
やま‐しろぎく【山白菊】
キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。
やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ
聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)
やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。
⇒やましろ【山城・山背】
やましろ‐ばんし【山代半紙】
周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。
やましろ‐もの【山城物】
山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶
⇒やましろ【山城・山背】
やましろや‐じけん【山城屋事件】
1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。
やま・す
〔他サ変〕
打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」
やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ
アノアのこと。
やま‐すが【山菅】
⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」
やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥
山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。
やま‐すげ【山菅】
山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」
⇒やますげ‐うら【山菅占】
⇒やますげ‐がさ【山菅笠】
⇒やますげ‐の【山菅の】
やますげ‐うら【山菅占】
山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐がさ【山菅笠】
山菅で編んだ笠。
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐の【山菅の】
〔枕〕
「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。
⇒やま‐すげ【山菅】
やま‐すそ【山裾】
山のふもと。
やま‐ずみ【山住み】
山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」
やま‐せ【山背】
(山背風の略)
①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。
②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉
⇒やませ‐かぜ【山背風】
やませ【山勢】
山田流箏曲の家柄の一つ。
⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】
やませ‐かぜ【山背風】
①(→)山背に同じ。
②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。
⇒やま‐せ【山背】
やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン
(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)
⇒やませ【山勢】
やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】
カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉
やませみ
▷行政区名は「山科区」と書く。
⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】
⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】
⇒やましな‐でら【山階寺】
⇒やましな‐どうり【山階道理】
⇒やましな‐べついん【山科別院】
やましな【山科】
姓氏の一つ。藤原北家四条流。
⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】
⇒やましな‐りゅう【山科流】
やましな‐かんきょ【山科閑居】
浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ
(→)山科別院に同じ。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐でら【山階寺】
興福寺の旧称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥
(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ときつぐ【山科言継】
戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)
⇒やましな【山科】
やましな‐の‐みや【山階宮】
旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。
やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン
京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐りゅう【山科流】‥リウ
公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流
⇒やましな【山科】
やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン
山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。
⇒やま‐し【山師】
やま‐しば【山柴】
山にある柴。山から採って来た柴。
やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ
(愛知県三河地方で)火葬すること。
やま‐しみず【山清水】‥シミヅ
山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」
やま‐じゃり【山砂利】
河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。
やま‐しゅ【山衆】
(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」
やま‐じるし【山印】
①(→)木印きじるしに同じ。
②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。
やま‐しるべ【山導】
山の案内。また、その人。
やましろ【山城・山背】
旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。
⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
⇒やましろ‐もの【山城物】
やま‐じろ【山城】
山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ
やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥
石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。
やま‐しろぎく【山白菊】
キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。
やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ
聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)
やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。
⇒やましろ【山城・山背】
やましろ‐ばんし【山代半紙】
周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。
やましろ‐もの【山城物】
山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶
⇒やましろ【山城・山背】
やましろや‐じけん【山城屋事件】
1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。
やま・す
〔他サ変〕
打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」
やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ
アノアのこと。
やま‐すが【山菅】
⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」
やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥
山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。
やま‐すげ【山菅】
山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」
⇒やますげ‐うら【山菅占】
⇒やますげ‐がさ【山菅笠】
⇒やますげ‐の【山菅の】
やますげ‐うら【山菅占】
山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐がさ【山菅笠】
山菅で編んだ笠。
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐の【山菅の】
〔枕〕
「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。
⇒やま‐すげ【山菅】
やま‐すそ【山裾】
山のふもと。
やま‐ずみ【山住み】
山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」
やま‐せ【山背】
(山背風の略)
①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。
②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉
⇒やませ‐かぜ【山背風】
やませ【山勢】
山田流箏曲の家柄の一つ。
⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】
やませ‐かぜ【山背風】
①(→)山背に同じ。
②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。
⇒やま‐せ【山背】
やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン
(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)
⇒やませ【山勢】
やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】
カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉
やませみ
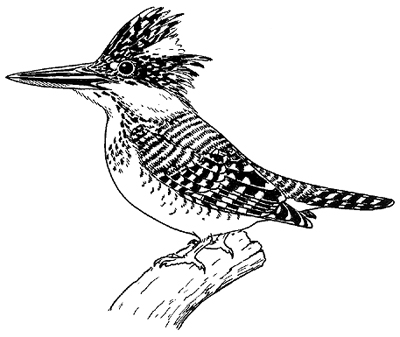 ヤマセミ
提供:OPO
ヤマセミ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
やま‐ぜみ【山蝉】
クマゼミの別称。
やま‐ぜり【山芹】
セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。
やま‐せん【山千】
山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千
やま‐そ【山苧】
〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。
やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ
山にそうこと。また、その場所。
やま‐そだち【山育ち】
山に育つこと。また、その人。やまがそだち。
やま‐そわ【山岨】‥ソハ
山のがけ。山のきりぎし。
やま‐だ【山田】
山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」
⇒やまだ‐もり【山田守】
やまだ【山田】
①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。
②⇒うじやまだ(宇治山田)。
⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】
⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】
やまだ【山田】
姓氏の一つ。
⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】
⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】
⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】
⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】
⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】
⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】
⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】
⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】
⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】
⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】
⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】
⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】
⇒やまだ‐りゅう【山田流】
やまだ‐あきよし【山田顕義】
軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)
⇒やまだ【山田】
やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥
江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。
⇒やまだ【山田】
やま‐だい【山台】
歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん
やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】
「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。
→資料:『魏志倭人伝』
やま‐たか【山高】
①中ほどが山形に高くなっていること。中高。
②山高帽子の略。
⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】
やま‐だか【山高】
江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
やま‐ぜみ【山蝉】
クマゼミの別称。
やま‐ぜり【山芹】
セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。
やま‐せん【山千】
山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千
やま‐そ【山苧】
〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。
やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ
山にそうこと。また、その場所。
やま‐そだち【山育ち】
山に育つこと。また、その人。やまがそだち。
やま‐そわ【山岨】‥ソハ
山のがけ。山のきりぎし。
やま‐だ【山田】
山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」
⇒やまだ‐もり【山田守】
やまだ【山田】
①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。
②⇒うじやまだ(宇治山田)。
⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】
⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】
やまだ【山田】
姓氏の一つ。
⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】
⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】
⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】
⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】
⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】
⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】
⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】
⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】
⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】
⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】
⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】
⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】
⇒やまだ‐りゅう【山田流】
やまだ‐あきよし【山田顕義】
軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)
⇒やまだ【山田】
やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥
江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。
⇒やまだ【山田】
やま‐だい【山台】
歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん
やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】
「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。
→資料:『魏志倭人伝』
やま‐たか【山高】
①中ほどが山形に高くなっていること。中高。
②山高帽子の略。
⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】
やま‐だか【山高】
江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。
 山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
 ⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ
物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)
⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥
白酒の異称。山川白酒。
⇒やま‐かわ【山川】
やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥
社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)
山川均
撮影:田村 茂
⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ
物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)
⇒やまかわ【山川】
やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥
白酒の異称。山川白酒。
⇒やま‐かわ【山川】
やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥
社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)
山川均
撮影:田村 茂
 山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
山川均・菊栄
撮影:木村伊兵衛
 ⇒やまかわ【山川】
やま‐かん【山勘】
①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。
②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」
やま‐かんむり【山冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。
や‐まき【八巻】
八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」
やまき【山木】
姓氏の一つ。
⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】
やま‐き【山気】
(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」
やま‐ぎ【山木】
山に生えている木。
やまき‐かねたか【山木兼隆】
平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)
⇒やまき【山木】
やま‐ぎし【山岸】
山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」
やま‐きず【山傷・山疵】
石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。
やま‐ぎり【山桐】
〔植〕
①アブラギリの別称。〈[季]夏〉
②ハリギリの別称。
③サワグルミの別称。
やま‐ぎり【山霧】
山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」
やまぎわ【山極】‥ギハ
姓氏の一つ。
⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】
やま‐ぎわ【山際】‥ギハ
山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」
やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ
病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)
⇒やまぎわ【山極】
やま‐きん【山金】
鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金
やま‐くさ【山草】
①山に生えている草。
②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」
やま‐くじ【山公事】
山林または鉱山に関する訴訟。
やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ
猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉
やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ
急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。
やま‐ぐち【山口】
①山への入り口。
②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。
③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」
⇒やまぐち‐さい【山口祭】
やまぐち【山口】
①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。
→男なら
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。
⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】
やまぐち【山口】
姓氏の一つ。
⇒やまぐち‐かおる【山口薫】
⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】
⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】
⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】
⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】
⇒やまぐち‐たけお【山口長男】
⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル
洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)
山口薫
撮影:田沼武能
⇒やまかわ【山川】
やま‐かん【山勘】
①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。
②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」
やま‐かんむり【山冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。
や‐まき【八巻】
八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」
やまき【山木】
姓氏の一つ。
⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】
やま‐き【山気】
(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」
やま‐ぎ【山木】
山に生えている木。
やまき‐かねたか【山木兼隆】
平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)
⇒やまき【山木】
やま‐ぎし【山岸】
山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」
やま‐きず【山傷・山疵】
石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。
やま‐ぎり【山桐】
〔植〕
①アブラギリの別称。〈[季]夏〉
②ハリギリの別称。
③サワグルミの別称。
やま‐ぎり【山霧】
山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」
やまぎわ【山極】‥ギハ
姓氏の一つ。
⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】
やま‐ぎわ【山際】‥ギハ
山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」
やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ
病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)
⇒やまぎわ【山極】
やま‐きん【山金】
鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金
やま‐くさ【山草】
①山に生えている草。
②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」
やま‐くじ【山公事】
山林または鉱山に関する訴訟。
やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ
猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉
やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ
急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。
やま‐ぐち【山口】
①山への入り口。
②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。
③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」
⇒やまぐち‐さい【山口祭】
やまぐち【山口】
①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。
→男なら
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。
⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】
やまぐち【山口】
姓氏の一つ。
⇒やまぐち‐かおる【山口薫】
⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】
⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】
⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】
⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】
⇒やまぐち‐たけお【山口長男】
⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル
洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)
山口薫
撮影:田沼武能
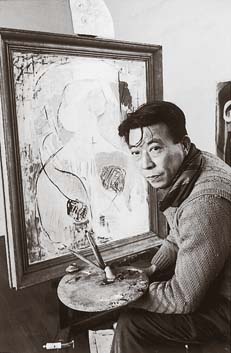 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ
日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)
山口華楊
撮影:田沼武能
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ
日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)
山口華楊
撮影:田沼武能
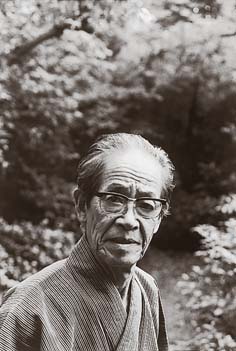 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐さい【山口祭】
伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。
⇒やま‐ぐち【山口】
やまぐち‐せいし【山口誓子】
俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)
山口誓子
提供:毎日新聞社
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐さい【山口祭】
伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。
⇒やま‐ぐち【山口】
やまぐち‐せいし【山口誓子】
俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)
山口誓子
提供:毎日新聞社
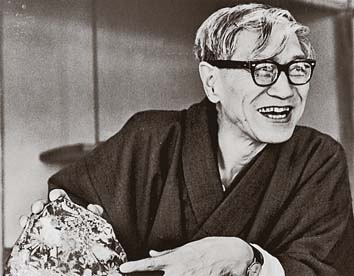 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐せいそん【山口青邨】
俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)
山口青邨
提供:毎日新聞社
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐せいそん【山口青邨】
俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)
山口青邨
提供:毎日新聞社
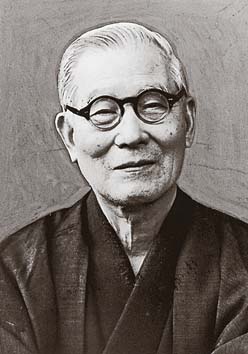 ⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ
江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐だいがく【山口大学】
国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ
画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】
狭山湖の別名。
やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ
語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。
やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)
山口蓬春
撮影:田沼武能
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ
江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐だいがく【山口大学】
国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ
画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)
⇒やまぐち【山口】
やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】
狭山湖の別名。
やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ
語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。
やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】
日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)
山口蓬春
撮影:田沼武能
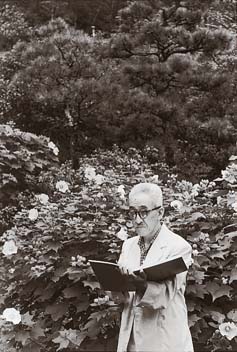 ⇒やまぐち【山口】
やま‐くどき【山口説】
江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」
やま‐ぐに【山国】
山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」
やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ
大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。
やま‐ぐま【山隈】
山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。
やま‐ぐも【山雲】
山にたちこめている雲。山に起こる雲。
やま‐ぐり【山栗】
山地に自生する栗。〈[季]秋〉
やま‐ぐるま【山車】
ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。
やま‐ぐわ【山桑】‥グハ
①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。
②ヤマボウシの別称。
やま‐け【山気】
⇒やまき
やま‐げた【山下駄】
杉などで作った粗末な下駄。
やま‐げら【山啄木鳥】
キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。
やま‐こ【山子】
①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉
②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。
やま‐ご【山子】
木樵きこりなど山仕事をする者の総称。
やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ
クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。
やま‐ごえ【山肥】
緑肥りょくひのこと。
やま‐ごえ【山越え】
①山を越えること。また、その所。山越し。
②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。
⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。
⇒やま‐ごえ【山越え】
やま‐こかし【山こかし】
①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」
②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。
やま‐ごけ【山苔】
細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。
やま‐ごころ【山心】
①(→)「のごころ」に同じ。
②山気やまき。
やま‐ごし【山越し】
①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。
②山を越したむこう側。山のむこう。
やま‐ごと【山事】
投機的または冒険的な事業。
やま‐ことば【山言葉・山詞】
猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。
やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ
①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。
ヤマゴボウ
提供:OPO
⇒やまぐち【山口】
やま‐くどき【山口説】
江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」
やま‐ぐに【山国】
山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」
やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ
大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。
やま‐ぐま【山隈】
山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。
やま‐ぐも【山雲】
山にたちこめている雲。山に起こる雲。
やま‐ぐり【山栗】
山地に自生する栗。〈[季]秋〉
やま‐ぐるま【山車】
ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。
やま‐ぐわ【山桑】‥グハ
①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。
②ヤマボウシの別称。
やま‐け【山気】
⇒やまき
やま‐げた【山下駄】
杉などで作った粗末な下駄。
やま‐げら【山啄木鳥】
キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。
やま‐こ【山子】
①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉
②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。
やま‐ご【山子】
木樵きこりなど山仕事をする者の総称。
やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ
クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。
やま‐ごえ【山肥】
緑肥りょくひのこと。
やま‐ごえ【山越え】
①山を越えること。また、その所。山越し。
②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。
⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。
⇒やま‐ごえ【山越え】
やま‐こかし【山こかし】
①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」
②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。
やま‐ごけ【山苔】
細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。
やま‐ごころ【山心】
①(→)「のごころ」に同じ。
②山気やまき。
やま‐ごし【山越し】
①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。
②山を越したむこう側。山のむこう。
やま‐ごと【山事】
投機的または冒険的な事業。
やま‐ことば【山言葉・山詞】
猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。
やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ
①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。
ヤマゴボウ
提供:OPO
 ②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉
やま‐ごもり【山籠り】
山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」
やま‐ごや【山小屋】
登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。
やまごろ‐いんもち【山五郎家持】
作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。
やま‐さか【山坂】
①山と坂。
②(ヤマザカとも)山の中にある坂。
やま‐さか【山険】
山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」
やまざき【山崎】
京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。
⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】
やまざき【山崎】
(ヤマサキとも)姓氏の一つ。
⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】
⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】
⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】
やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ
(→)垂加神道に同じ。
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥
木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)
山崎朝雲
撮影:田沼武能
②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉
やま‐ごもり【山籠り】
山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」
やま‐ごや【山小屋】
登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。
やまごろ‐いんもち【山五郎家持】
作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。
やま‐さか【山坂】
①山と坂。
②(ヤマザカとも)山の中にある坂。
やま‐さか【山険】
山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」
やまざき【山崎】
京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。
⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】
やまざき【山崎】
(ヤマサキとも)姓氏の一つ。
⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】
⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】
⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】
やまざき‐あんさい【山崎闇斎】
江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ
(→)垂加神道に同じ。
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】
室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥
木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)
山崎朝雲
撮影:田沼武能
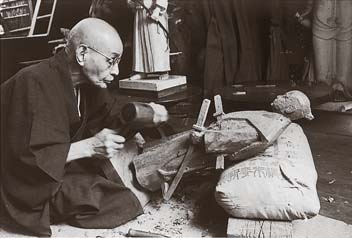 ⇒やまざき【山崎】
やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥
地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ
1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。
⇒やまざき【山崎】
やま‐ざくら【山桜】
①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。
②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉
ヤマザクラ
撮影:関戸 勇
⇒やまざき【山崎】
やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥
地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)
⇒やまざき【山崎】
やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ
1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。
⇒やまざき【山崎】
やま‐ざくら【山桜】
①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。
②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉
ヤマザクラ
撮影:関戸 勇
 ⇒やまざくら‐ど【山桜戸】
やまざくら‐ど【山桜戸】
①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」
②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」
⇒やま‐ざくら【山桜】
やま‐さち【山幸】
①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」
②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。
③「海幸山幸」参照。
やま‐さつ【山猟師】
(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」
やま‐ざと【山里】
①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」
②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」
⇒やまざと‐びと【山里人】
⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】
やまざと‐びと【山里人】
山里に住む人。やまびと。
⇒やま‐ざと【山里】
やまざと・ぶ【山里ぶ】
〔自上二〕
山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」
⇒やま‐ざと【山里】
やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ
山にある野生のサネカズラ。
やま‐さ・ぶ【山さぶ】
〔自上二〕
山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」
やま‐ざる【山猿】
①山にすむ猿。
②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。
やま‐さわ【山沢】‥サハ
①山と沢。また、山間の沢。
②多いこと。たくさん。さわやま。
⇒やまさわ‐びと【山沢人】
やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥
山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」
⇒やま‐さわ【山沢】
やま‐さん【山様】
江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。
やまし【知母】
⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉
やま‐し【山師】
①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。
②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。
⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】
やま‐じ【山路】‥ヂ
山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」
やまじ【山路】‥ヂ
姓氏の一つ。
⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】
やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥
ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)
⇒やまじ【山路】
やまし・い【疾しい・疚しい】
〔形〕[文]やま・し(シク)
(「病む」の形容詞化)
①病気の感じである。気分がすぐれない。
②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。
③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」
やま‐じお【山塩】‥ジホ
山からとる塩。岩塩がんえん。
やまじ‐かぜ【やまじ風】
愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。
やま‐しぎ【山鷸・山鴫】
シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉
やましぎ
⇒やまざくら‐ど【山桜戸】
やまざくら‐ど【山桜戸】
①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」
②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」
⇒やま‐ざくら【山桜】
やま‐さち【山幸】
①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」
②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。
③「海幸山幸」参照。
やま‐さつ【山猟師】
(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」
やま‐ざと【山里】
①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」
②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」
⇒やまざと‐びと【山里人】
⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】
やまざと‐びと【山里人】
山里に住む人。やまびと。
⇒やま‐ざと【山里】
やまざと・ぶ【山里ぶ】
〔自上二〕
山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」
⇒やま‐ざと【山里】
やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ
山にある野生のサネカズラ。
やま‐さ・ぶ【山さぶ】
〔自上二〕
山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」
やま‐ざる【山猿】
①山にすむ猿。
②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。
やま‐さわ【山沢】‥サハ
①山と沢。また、山間の沢。
②多いこと。たくさん。さわやま。
⇒やまさわ‐びと【山沢人】
やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥
山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」
⇒やま‐さわ【山沢】
やま‐さん【山様】
江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。
やまし【知母】
⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉
やま‐し【山師】
①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。
②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。
⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】
やま‐じ【山路】‥ヂ
山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」
やまじ【山路】‥ヂ
姓氏の一つ。
⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】
やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥
ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)
⇒やまじ【山路】
やまし・い【疾しい・疚しい】
〔形〕[文]やま・し(シク)
(「病む」の形容詞化)
①病気の感じである。気分がすぐれない。
②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。
③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」
やま‐じお【山塩】‥ジホ
山からとる塩。岩塩がんえん。
やまじ‐かぜ【やまじ風】
愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。
やま‐しぎ【山鷸・山鴫】
シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉
やましぎ
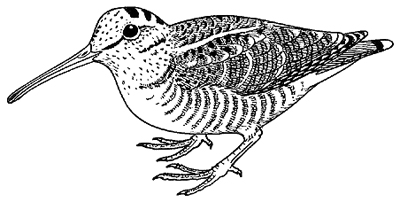 ヤマシギ
提供:OPO
ヤマシギ
提供:OPO
 やま‐しごと【山仕事】
①山でする仕事。
②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。
やま‐しず【山賤】‥シヅ
(→)「やまがつ」に同じ。
やま‐じそ【山紫蘇】
シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。
やま‐した【山下】
山のした。山のふもと。山もと。
⇒やました‐かげ【山下陰】
⇒やました‐かぜ【山下風】
⇒やました‐つゆ【山下露】
⇒やました‐の【山下の】
⇒やました‐みず【山下水】
やました【山下】
姓氏の一つ。
⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】
やました‐かげ【山下陰】
山の麓の陰となる所。
⇒やま‐した【山下】
やました‐かぜ【山下風】
山から吹きおろす風。山おろし。
⇒やま‐した【山下】
やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)
山下新太郎
撮影:田沼武能
やま‐しごと【山仕事】
①山でする仕事。
②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。
やま‐しず【山賤】‥シヅ
(→)「やまがつ」に同じ。
やま‐じそ【山紫蘇】
シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。
やま‐した【山下】
山のした。山のふもと。山もと。
⇒やました‐かげ【山下陰】
⇒やました‐かぜ【山下風】
⇒やました‐つゆ【山下露】
⇒やました‐の【山下の】
⇒やました‐みず【山下水】
やました【山下】
姓氏の一つ。
⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】
やました‐かげ【山下陰】
山の麓の陰となる所。
⇒やま‐した【山下】
やました‐かぜ【山下風】
山から吹きおろす風。山おろし。
⇒やま‐した【山下】
やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)
山下新太郎
撮影:田沼武能
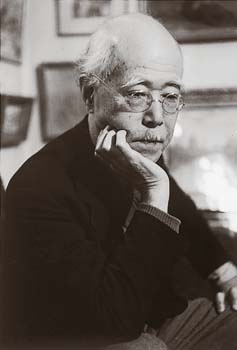 ⇒やました【山下】
やました‐つゆ【山下露】
山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。
⇒やま‐した【山下】
やました‐の【山下の】
山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」
⇒やま‐した【山下】
やました‐みず【山下水】‥ミヅ
山のふもとを流れる水。
⇒やま‐した【山下】
やましな【山科・山階】
京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。
山科 天智天皇陵
撮影:的場 啓
⇒やました【山下】
やました‐つゆ【山下露】
山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。
⇒やま‐した【山下】
やました‐の【山下の】
山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」
⇒やま‐した【山下】
やました‐みず【山下水】‥ミヅ
山のふもとを流れる水。
⇒やま‐した【山下】
やましな【山科・山階】
京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。
山科 天智天皇陵
撮影:的場 啓
 ▷行政区名は「山科区」と書く。
⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】
⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】
⇒やましな‐でら【山階寺】
⇒やましな‐どうり【山階道理】
⇒やましな‐べついん【山科別院】
やましな【山科】
姓氏の一つ。藤原北家四条流。
⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】
⇒やましな‐りゅう【山科流】
やましな‐かんきょ【山科閑居】
浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ
(→)山科別院に同じ。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐でら【山階寺】
興福寺の旧称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥
(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ときつぐ【山科言継】
戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)
⇒やましな【山科】
やましな‐の‐みや【山階宮】
旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。
やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン
京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐りゅう【山科流】‥リウ
公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流
⇒やましな【山科】
やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン
山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。
⇒やま‐し【山師】
やま‐しば【山柴】
山にある柴。山から採って来た柴。
やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ
(愛知県三河地方で)火葬すること。
やま‐しみず【山清水】‥シミヅ
山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」
やま‐じゃり【山砂利】
河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。
やま‐しゅ【山衆】
(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」
やま‐じるし【山印】
①(→)木印きじるしに同じ。
②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。
やま‐しるべ【山導】
山の案内。また、その人。
やましろ【山城・山背】
旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。
⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
⇒やましろ‐もの【山城物】
やま‐じろ【山城】
山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ
やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥
石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。
やま‐しろぎく【山白菊】
キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。
やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ
聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)
やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。
⇒やましろ【山城・山背】
やましろ‐ばんし【山代半紙】
周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。
やましろ‐もの【山城物】
山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶
⇒やましろ【山城・山背】
やましろや‐じけん【山城屋事件】
1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。
やま・す
〔他サ変〕
打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」
やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ
アノアのこと。
やま‐すが【山菅】
⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」
やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥
山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。
やま‐すげ【山菅】
山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」
⇒やますげ‐うら【山菅占】
⇒やますげ‐がさ【山菅笠】
⇒やますげ‐の【山菅の】
やますげ‐うら【山菅占】
山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐がさ【山菅笠】
山菅で編んだ笠。
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐の【山菅の】
〔枕〕
「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。
⇒やま‐すげ【山菅】
やま‐すそ【山裾】
山のふもと。
やま‐ずみ【山住み】
山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」
やま‐せ【山背】
(山背風の略)
①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。
②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉
⇒やませ‐かぜ【山背風】
やませ【山勢】
山田流箏曲の家柄の一つ。
⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】
やませ‐かぜ【山背風】
①(→)山背に同じ。
②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。
⇒やま‐せ【山背】
やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン
(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)
⇒やませ【山勢】
やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】
カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉
やませみ
▷行政区名は「山科区」と書く。
⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】
⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】
⇒やましな‐でら【山階寺】
⇒やましな‐どうり【山階道理】
⇒やましな‐べついん【山科別院】
やましな【山科】
姓氏の一つ。藤原北家四条流。
⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】
⇒やましな‐りゅう【山科流】
やましな‐かんきょ【山科閑居】
浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ
(→)山科別院に同じ。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐でら【山階寺】
興福寺の旧称。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥
(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐ときつぐ【山科言継】
戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)
⇒やましな【山科】
やましな‐の‐みや【山階宮】
旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。
やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン
京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。
⇒やましな【山科・山階】
やましな‐りゅう【山科流】‥リウ
公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流
⇒やましな【山科】
やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン
山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。
⇒やま‐し【山師】
やま‐しば【山柴】
山にある柴。山から採って来た柴。
やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ
(愛知県三河地方で)火葬すること。
やま‐しみず【山清水】‥シミヅ
山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」
やま‐じゃり【山砂利】
河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。
やま‐しゅ【山衆】
(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」
やま‐じるし【山印】
①(→)木印きじるしに同じ。
②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。
やま‐しるべ【山導】
山の案内。また、その人。
やましろ【山城・山背】
旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。
⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
⇒やましろ‐もの【山城物】
やま‐じろ【山城】
山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ
やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥
石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。
やま‐しろぎく【山白菊】
キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。
やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ
聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)
やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】
1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。
⇒やましろ【山城・山背】
やましろ‐ばんし【山代半紙】
周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。
やましろ‐もの【山城物】
山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶
⇒やましろ【山城・山背】
やましろや‐じけん【山城屋事件】
1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。
やま・す
〔他サ変〕
打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」
やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ
アノアのこと。
やま‐すが【山菅】
⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」
やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥
山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。
やま‐すげ【山菅】
山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」
⇒やますげ‐うら【山菅占】
⇒やますげ‐がさ【山菅笠】
⇒やますげ‐の【山菅の】
やますげ‐うら【山菅占】
山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐がさ【山菅笠】
山菅で編んだ笠。
⇒やま‐すげ【山菅】
やますげ‐の【山菅の】
〔枕〕
「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。
⇒やま‐すげ【山菅】
やま‐すそ【山裾】
山のふもと。
やま‐ずみ【山住み】
山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」
やま‐せ【山背】
(山背風の略)
①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。
②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉
⇒やませ‐かぜ【山背風】
やませ【山勢】
山田流箏曲の家柄の一つ。
⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】
やませ‐かぜ【山背風】
①(→)山背に同じ。
②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。
⇒やま‐せ【山背】
やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン
(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)
⇒やませ【山勢】
やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】
カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉
やませみ
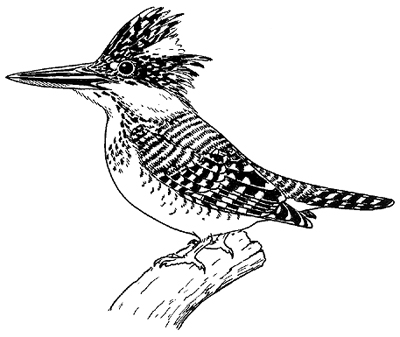 ヤマセミ
提供:OPO
ヤマセミ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
やま‐ぜみ【山蝉】
クマゼミの別称。
やま‐ぜり【山芹】
セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。
やま‐せん【山千】
山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千
やま‐そ【山苧】
〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。
やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ
山にそうこと。また、その場所。
やま‐そだち【山育ち】
山に育つこと。また、その人。やまがそだち。
やま‐そわ【山岨】‥ソハ
山のがけ。山のきりぎし。
やま‐だ【山田】
山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」
⇒やまだ‐もり【山田守】
やまだ【山田】
①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。
②⇒うじやまだ(宇治山田)。
⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】
⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】
やまだ【山田】
姓氏の一つ。
⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】
⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】
⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】
⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】
⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】
⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】
⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】
⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】
⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】
⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】
⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】
⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】
⇒やまだ‐りゅう【山田流】
やまだ‐あきよし【山田顕義】
軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)
⇒やまだ【山田】
やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥
江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。
⇒やまだ【山田】
やま‐だい【山台】
歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん
やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】
「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。
→資料:『魏志倭人伝』
やま‐たか【山高】
①中ほどが山形に高くなっていること。中高。
②山高帽子の略。
⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】
やま‐だか【山高】
江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
やま‐ぜみ【山蝉】
クマゼミの別称。
やま‐ぜり【山芹】
セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。
やま‐せん【山千】
山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千
やま‐そ【山苧】
〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。
やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ
山にそうこと。また、その場所。
やま‐そだち【山育ち】
山に育つこと。また、その人。やまがそだち。
やま‐そわ【山岨】‥ソハ
山のがけ。山のきりぎし。
やま‐だ【山田】
山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」
⇒やまだ‐もり【山田守】
やまだ【山田】
①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。
②⇒うじやまだ(宇治山田)。
⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】
⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】
やまだ【山田】
姓氏の一つ。
⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】
⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】
⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】
⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】
⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】
⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】
⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】
⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】
⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】
⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】
⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】
⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】
⇒やまだ‐りゅう【山田流】
やまだ‐あきよし【山田顕義】
軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)
⇒やまだ【山田】
やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥
江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。
⇒やまだ【山田】
やま‐だい【山台】
歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん
やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】
「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。
→資料:『魏志倭人伝』
やま‐たか【山高】
①中ほどが山形に高くなっていること。中高。
②山高帽子の略。
⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】
やま‐だか【山高】
江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。
やま‐がらす【山烏】🔗⭐🔉
やま‐がらす【山烏】
①山にすむ烏。
②ハシブトガラスの別称。
③ミヤマガラスの別称。
④色の黒い人をあざけっていう語。
やま‐ぐも【山雲】🔗⭐🔉
やま‐ぐも【山雲】
山にたちこめている雲。山に起こる雲。
やま‐ごえ【山越え】🔗⭐🔉
やま‐ごえ【山越え】
①山を越えること。また、その所。山越し。
②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。
⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】🔗⭐🔉
やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】
(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。
⇒やま‐ごえ【山越え】
やま‐こかし【山こかし】🔗⭐🔉
やま‐こかし【山こかし】
①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」
②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。
やま‐ごし【山越し】🔗⭐🔉
やま‐ごし【山越し】
①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。
②山を越したむこう側。山のむこう。
やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ🔗⭐🔉
やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ
山にある野生のサネカズラ。
やま‐さ・ぶ【山さぶ】🔗⭐🔉
やま‐さ・ぶ【山さぶ】
〔自上二〕
山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」
やま‐じるし【山印】🔗⭐🔉
やま‐じるし【山印】
①(→)木印きじるしに同じ。
②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。
やま‐そだち【山育ち】🔗⭐🔉
やま‐そだち【山育ち】
山に育つこと。また、その人。やまがそだち。
やま‐たず【山たづ】‥タヅ🔗⭐🔉
やま‐たず【山たづ】‥タヅ
〔植〕接骨木にわとこの古名。
⇒やまたず‐の【山たづの】
やまたず‐の【山たづの】‥タヅ‥🔗⭐🔉
やまたず‐の【山たづの】‥タヅ‥
〔枕〕
(ニワトコの枝葉は相対して生ずるから)「むかへ」にかかる。古事記下「―迎へを行かむ待つには待たじ」
⇒やま‐たず【山たづ】
やまっ‐け【山っ気】🔗⭐🔉
やまっ‐け【山っ気】
⇒やまき
○山と言えば川やまといえばかわ🔗⭐🔉
○山と言えば川やまといえばかわ
人のことばに殊更に反対することのたとえ。「右と言えば左」という類。
⇒やま【山】
やまと‐いも【大和芋】
ナガイモの一品種。芋は手のひら形など不規則な塊状で良質。栽培して「とろろ」などとして食用。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐いわな【大和岩魚】‥イハ‥
イワナ類の一地方群(亜種)。関東地方以南に産。ニッコウイワナに似るが、体の淡色点は朱紅色で、体背半にも分布。全長25センチメートル。紀伊半島の個体群は特にキリクチと呼ばれる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐うた【大和歌・倭歌】
①日本固有の文学である和歌。やまとことのは。古今和歌集序「―は人の心を種として」↔唐歌からうた。
②昔の、大和地方の風俗歌ふぞくうた。大和舞に用いる歌。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐うち【大和打】
塀などの板を1枚ずつ交互に重ね合わせて横木の内側と外側とに打ち付けること。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐うつぼ【大和靫】
木または竹で編み、黒く塗って毛皮をつけないうつぼ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐え【大和絵・倭絵】‥ヱ
①日本の事物を描いた絵。中国の事物を描いた唐絵と区別していう。鎌倉時代までの用語。権記長保元年10月30日「書―四尺屏風色紙形」
②平安時代、唐朝画の様式を国風化した日本的情趣に富む世俗画およびその伝統による絵画の総称。鎌倉時代以後、宋元系絵画、特に水墨画を唐絵・漢画と呼ぶのに対していう。14世紀後半、宮廷絵師の家系として土佐家が成立し大和絵を標榜してからは、流派を含めた語ともなった。
③(→)浮世絵うきよえ1に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐えし【大和絵師】‥ヱ‥
①大和絵を描く人。
②日本の画家。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐おおじ【大和大路】‥オホヂ
京都市東山区祇園の四条通から南へ向かう通り。京都と奈良を結ぶ大和街道の一部。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐おり【大和織】
敷物用織物の一つ。太い木綿糸を経たてとし、太い黄麻糸を緯よことして平織にした厚い織物。また、輪奈織わなおりで鞄かばん類の生地に使用したものもこの名で呼ばれた。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かいれい【大和海嶺】
日本海中央部に東北東‐西南西方向に長さ130キロメートル、幅20キロメートルでのびる海底の高まり。比高約2000メートル。頂部は水深300メートルの平坦面で岩盤が露出する。日本列島が大陸から分離し、日本海が形成された時の大陸地塊の残存物と考えられている。大和堆。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐がかり【大和掛】
(→)下掛しもがかり1に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かき【大和掻】
下地窓の竹に藤蔓ふじづるなどを蛇のまといついたように巻きつかせること。また、そのもの。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐がき【大和柿】
御所柿ごしょがきの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐がく【大和楽】
三味線音楽の一種。1933年(昭和8)に一中節都派家元大倉喜七郎(1882〜1963)が、各種の三味線音楽の特色を融合して創始。従来の流派により固定した旋律の終り方を用いず、声部を複数にするなどの工夫がある。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐がすり【大和絣】
大和国南葛城・北葛城・磯城しき・高市の諸郡から産出する木綿絣。古来、白絣で有名。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かたかなはんせつぎげ【倭片仮字反切義解】
語学書。1巻。耕雲著。室町中期に成る。五十音図の伝来、反切法、仮名の起源・沿革を説く。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】
鎌倉中期に成立した両部神道書・修験道書。行基の著に仮託される。葛城山をめぐる秘説を説くもの。両部・伊勢神道の著作に大きな影響を与えた。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐がな【大和仮名】
①(→)「かたかな」に同じ。
②(→)「ひらがな」に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かぬち【倭鍛冶】
「鍛冶部かぬちべ」参照。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐がわ【大和川】‥ガハ
奈良県北西部から大阪府の中央を経て、堺市で大阪湾に流入する川。笠置山地に発源する。長さ68キロメートル。
大和川
撮影:的場 啓
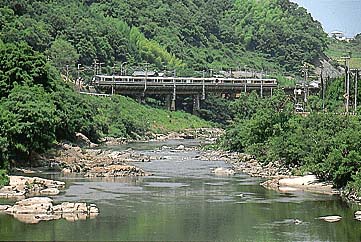 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】‥カハチ‥
(大和を東、河内を西と表記する)それぞれ阿知使主あちのおみ・王仁わにの子孫と称し、史の姓かばねを賜って朝廷の記録や外交文書をつかさどった氏。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐさ【大和草】
ヤマトグサ科の多年草。山地に自生。高さ約20センチメートル。葉は卵形。全体はハコベに似る。4〜5月頃、淡緑色の小さな単性花を開く。雄花では白い多数の雄しべが細長く垂れる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】
飾り鞍の一種。唐様の鞍に対して和様化した鞍。わぐら。↔唐鞍からくら。
大和鞍
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】‥カハチ‥
(大和を東、河内を西と表記する)それぞれ阿知使主あちのおみ・王仁わにの子孫と称し、史の姓かばねを賜って朝廷の記録や外交文書をつかさどった氏。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐさ【大和草】
ヤマトグサ科の多年草。山地に自生。高さ約20センチメートル。葉は卵形。全体はハコベに似る。4〜5月頃、淡緑色の小さな単性花を開く。雄花では白い多数の雄しべが細長く垂れる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】
飾り鞍の一種。唐様の鞍に対して和様化した鞍。わぐら。↔唐鞍からくら。
大和鞍
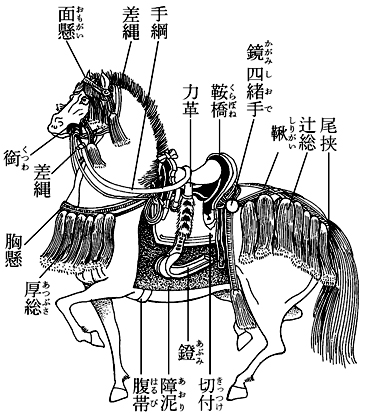 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐けんぎょう【山登検校】‥ゲウ
(初世)江戸後期の箏曲家・平曲家。山登派の家元。江戸生れ。名は松和一しょうわいち。本名、高木清吉。山田検校の筆頭弟子で、その没後は山田流の指導的立場にあった。作「春日詣かすがもうで」「新七草」など。(1782〜1863)
⇒やまと【山登】
やまと‐ごえ【倭音・和音】‥ゴヱ
(→)呉音ごおんに同じ。漢音を「からごえ」というのに対していう。わおん。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こおりやま【大和郡山】‥コホリ‥
奈良県北部の市。もと柳沢氏15万石の城下町。近世以降、金魚の養殖で有名。人口9万2千。
大和郡山 金魚の養殖
撮影:的場 啓
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐けんぎょう【山登検校】‥ゲウ
(初世)江戸後期の箏曲家・平曲家。山登派の家元。江戸生れ。名は松和一しょうわいち。本名、高木清吉。山田検校の筆頭弟子で、その没後は山田流の指導的立場にあった。作「春日詣かすがもうで」「新七草」など。(1782〜1863)
⇒やまと【山登】
やまと‐ごえ【倭音・和音】‥ゴヱ
(→)呉音ごおんに同じ。漢音を「からごえ」というのに対していう。わおん。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こおりやま【大和郡山】‥コホリ‥
奈良県北部の市。もと柳沢氏15万石の城下町。近世以降、金魚の養殖で有名。人口9万2千。
大和郡山 金魚の養殖
撮影:的場 啓
 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】
ゴキブリ科の一種。体長2〜3センチメートル。体は栗色、雌の成虫は翅はねが短い。家住性ゴキブリのうち唯一の在来種で、東北から近畿地方に分布。一般家屋内に多いやや大形のクロゴキブリに似るが、胸部背面が平滑でない。
ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】
ゴキブリ科の一種。体長2〜3センチメートル。体は栗色、雌の成虫は翅はねが短い。家住性ゴキブリのうち唯一の在来種で、東北から近畿地方に分布。一般家屋内に多いやや大形のクロゴキブリに似るが、胸部背面が平滑でない。
ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごころ【大和心】
①(→)「やまとだましい」1に同じ。大鏡道隆「大弐殿、弓矢の本末もとすえも知り給はねば、いかがとおぼしけれど、―かしこくおはする人にて」↔漢心からごころ。
②日本人の持つ、やさしく、やわらいだ心情。石上稿(本居宣長)「しきしまの―を人問はば朝日に匂ふ山桜花」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごたつ【大和火燵】
(→)置おき火燵に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こっか【大和国家】‥コク‥
畿内を中心とする古代国家。成立は、邪馬台国大和説を採れば3世紀前半以前、九州説を採れば3世紀後半以後となる。4世紀後半には畿内から西日本まで統一して朝鮮と交流、5世紀には東北地方を除く東日本を征服し、7世紀半ばの大化改新により律令国家に変質。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごと【大和琴・倭琴】
和琴わごんの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことのは【大和言の葉】
(→)「やまとことば」に同じ。源氏物語桐壺「伊勢、貫之に詠ませ給へる―をも、もろこしの歌をも」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことば【山人言葉】
狩人が山で使う言葉。山言葉。
⇒やま‐と【山人】
やまと‐ことば【大和言葉】
①日本固有の言語。日本語。和語。やまとことのは。
②和歌。やまとうた。源氏物語東屋「―だにつきなく習ひにければ」
③日本の雅言。主に平安時代の語。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さるがく【大和猿楽】
室町時代、大和国に住し、春日神社の神事に従事した結崎ゆうざき・外山とび・円満井えんまい・坂戸さかどの4座の猿楽。後にそれぞれ観世・宝生・金春こんぱる・金剛の4座となった。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さんざん【大和三山】
奈良盆地南部にある三つの山。古代の藤原京を囲み、北に耳成みみなし山、東に香具かぐ山、西に畝傍うねび山がある。
大和三山
撮影:的場 啓
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごころ【大和心】
①(→)「やまとだましい」1に同じ。大鏡道隆「大弐殿、弓矢の本末もとすえも知り給はねば、いかがとおぼしけれど、―かしこくおはする人にて」↔漢心からごころ。
②日本人の持つ、やさしく、やわらいだ心情。石上稿(本居宣長)「しきしまの―を人問はば朝日に匂ふ山桜花」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごたつ【大和火燵】
(→)置おき火燵に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こっか【大和国家】‥コク‥
畿内を中心とする古代国家。成立は、邪馬台国大和説を採れば3世紀前半以前、九州説を採れば3世紀後半以後となる。4世紀後半には畿内から西日本まで統一して朝鮮と交流、5世紀には東北地方を除く東日本を征服し、7世紀半ばの大化改新により律令国家に変質。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごと【大和琴・倭琴】
和琴わごんの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことのは【大和言の葉】
(→)「やまとことば」に同じ。源氏物語桐壺「伊勢、貫之に詠ませ給へる―をも、もろこしの歌をも」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことば【山人言葉】
狩人が山で使う言葉。山言葉。
⇒やま‐と【山人】
やまと‐ことば【大和言葉】
①日本固有の言語。日本語。和語。やまとことのは。
②和歌。やまとうた。源氏物語東屋「―だにつきなく習ひにければ」
③日本の雅言。主に平安時代の語。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さるがく【大和猿楽】
室町時代、大和国に住し、春日神社の神事に従事した結崎ゆうざき・外山とび・円満井えんまい・坂戸さかどの4座の猿楽。後にそれぞれ観世・宝生・金春こんぱる・金剛の4座となった。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さんざん【大和三山】
奈良盆地南部にある三つの山。古代の藤原京を囲み、北に耳成みみなし山、東に香具かぐ山、西に畝傍うねび山がある。
大和三山
撮影:的場 啓
 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じ【大和路】‥ヂ
①大和へ向かう道。万葉集6「―の吉備の児島を過ぎて行かば」
②京都の五条口から伏見・木津を通り大和に至る道。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐しじみ【大和蜆】
シジミガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で、殻長3センチメートル。黒褐色で、幼若期は黄褐色の放射状色帯をもつ。卵生。日本全国の河口域にすみ、宍道湖・十三湖・利根川が主要産地。市場のシジミのほとんどが本種。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じだい【大和時代】
日本史の時代区分の一つ。大和または大和を中心とする畿内地方に大王(のちに天皇)の政権のあった時代。律令時代の前で、考古学上の古墳時代とほぼ一致する。→大和政権。
⇒やまと【大和・倭】
やまとじ‐ぶし【大和路節】‥ヂ‥
浄瑠璃の一流派。宝暦(1751〜1764)頃、宮古路豊後掾の上方の門弟、大和路仲太夫が創始。やがて廃絶。広義の豊後節に属する。仲太夫節。
やまと‐しまね【大和島根】
①日本国の別称。万葉集20「天地の固めし国そ―は」
②大和国の称。万葉集3「千重に隠りぬ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐せいけん【大和政権】
大和を中心とする畿内地方の古代政権。諸豪族が連合して大王、後には天皇という称号の君主を擁立し、4〜5世紀までに東北地方以遠を除く日本本土の大半を統一した。統一時代の君主は軍事的英雄であったと見る説もあるが、6世紀には世襲的王制が確立し、諸豪族は臣おみ・連むらじなどの姓かばねによって階層的に秩序づけられて、氏姓制度が成立した。飛鳥時代から氏姓より個人の才能・努力を重んずる官司制度が発達し、7世紀半ばの大化改新後、律令制の朝廷に変質した。大和朝廷。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐そう【大和相】‥サウ
日本風の観相。源氏物語桐壺「―をおほせておぼし寄りにける筋なれば」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぞっくん【大和俗訓】‥ゾク‥
貝原益軒著の通俗教訓書。「益軒十訓」の一つ。儒教的倫理観から修身・礼儀・作法などを平易な和文で記す。8巻。1708年(宝永5)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐たかだ【大和高田】
奈良県北西部の市。奈良盆地の南西部に位置し、靴下製造などの繊維工業が盛ん。人口7万1千。
⇒やまと【大和・倭】
やまとたける‐の‐みこと【日本武尊・倭建命】
古代伝説上の英雄。景行天皇の皇子で、本名は小碓命おうすのみこと。別名、日本童男やまとおぐな。天皇の命を奉じて熊襲くまそを討ち、のち東国を鎮定。往途、駿河で草薙剣くさなぎのつるぎによって野火の難を払い、走水はしりみずの海では妃弟橘媛おとたちばなひめの犠牲によって海上の難を免れた。帰途、近江伊吹山の神を討とうとして病を得、伊勢の能褒野のぼので没したという。
やまと‐だましい【大和魂】‥ダマシヒ
①漢才かんざい・からざえすなわち学問(漢学)上の知識に対して、実生活上の知恵・才能。和魂わこん。源氏物語少女「才を本としてこそ、―の世に用ひらるる方も」→漢才。
②日本民族固有の精神。勇猛で潔いのが特性とされる。椿説弓張月後編「事に迫りて死を軽んずるは、―なれど多くは慮おもいはかりの浅きに似て、学ばざるの悞あやまちなり」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ちょうてい【大和朝廷】‥テウ‥
「大和政権」参照。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐つかい【大和使】‥ツカヒ
遣唐使のこと。夫木和歌抄35「今の世にありとは聞かずもろこしのふみ学ぶてふ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐でん【大和伝】
大和の刀工の系統。また、その作風。→大和物。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐とじ【大和綴じ】‥トヂ
和装本の綴じ方の一つ。本文料紙は綴葉装てっちょうそうまたは袋綴じと同様の綴じ方で下綴じした上で、表紙を加え、紐などで上下2カ所(計4穴)結んで綴じる。近代以降も写真帳などに用いられる。結び綴じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐な【大和名】
日本風の名。日本名。和名。源氏物語順集「―にいひにくき事をこそそへてはよめ」↔唐名からな。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐なでしこ【大和撫子】
①ナデシコの異称。〈[季]秋〉
②日本女性の美称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐に【大和煮】
牛肉などを醤油・砂糖・生薑しょうがなどで煮たもの。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐にしき【大和錦】
①日本で織った錦。↔唐錦。
②主として2色の緯糸よこいとを一越ひとこし交替に扱い、地と文様もともに緯六枚綾の組織とした錦。糸錦。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ねこ【倭根子】
詔勅などに歴代天皇の用いた通号。孝徳紀「明神あきつみかみと御宇あめのしたしらす―の天皇…詔のたまはく」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】‥アタヒ
古代の渡来系氏族。阿知使主あちのおみの子孫と称し、朝廷の記録や外交文書をつかさどった。5世紀ごろ渡来した朝鮮の漢民族の子孫と見られ、大和を本拠とした。7世紀には政治的・軍事的に有力となり、姓かばねは直あたいから忌寸いみきや宿祢すくねに昇格。東漢氏やまとのあやうじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
垂仁天皇の皇女といわれる伝説上の人物。天照大神あまてらすおおみかみの祠を大和の笠縫邑かさぬいのむらから伊勢の五十鈴川上に遷す。景行天皇の時、甥の日本武尊やまとたけるのみことの東国征討に際して草薙剣くさなぎのつるぎを授けたという。
⇒やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
神道五部書の一つ。1巻。神宮の古伝承に加筆して古人の編に仮託し、鎌倉中期頃成立したもの。天地開闢から雄略天皇朝の外宮鎮座に至る神祇関係事項、倭姫命の事跡、宮中の諸神などを説く。
⇒やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
やまと‐ひょうぐ【大和表具】‥ヘウ‥
日本の正式の掛物の表具。上・下・中回ちゅうまわし・一文字・風帯から成り、一文字と風帯は共裂ともぎれで、金襴などを用い、上・下と中回は材料を異にし、変化をつける。
大和表具
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じ【大和路】‥ヂ
①大和へ向かう道。万葉集6「―の吉備の児島を過ぎて行かば」
②京都の五条口から伏見・木津を通り大和に至る道。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐しじみ【大和蜆】
シジミガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で、殻長3センチメートル。黒褐色で、幼若期は黄褐色の放射状色帯をもつ。卵生。日本全国の河口域にすみ、宍道湖・十三湖・利根川が主要産地。市場のシジミのほとんどが本種。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じだい【大和時代】
日本史の時代区分の一つ。大和または大和を中心とする畿内地方に大王(のちに天皇)の政権のあった時代。律令時代の前で、考古学上の古墳時代とほぼ一致する。→大和政権。
⇒やまと【大和・倭】
やまとじ‐ぶし【大和路節】‥ヂ‥
浄瑠璃の一流派。宝暦(1751〜1764)頃、宮古路豊後掾の上方の門弟、大和路仲太夫が創始。やがて廃絶。広義の豊後節に属する。仲太夫節。
やまと‐しまね【大和島根】
①日本国の別称。万葉集20「天地の固めし国そ―は」
②大和国の称。万葉集3「千重に隠りぬ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐せいけん【大和政権】
大和を中心とする畿内地方の古代政権。諸豪族が連合して大王、後には天皇という称号の君主を擁立し、4〜5世紀までに東北地方以遠を除く日本本土の大半を統一した。統一時代の君主は軍事的英雄であったと見る説もあるが、6世紀には世襲的王制が確立し、諸豪族は臣おみ・連むらじなどの姓かばねによって階層的に秩序づけられて、氏姓制度が成立した。飛鳥時代から氏姓より個人の才能・努力を重んずる官司制度が発達し、7世紀半ばの大化改新後、律令制の朝廷に変質した。大和朝廷。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐そう【大和相】‥サウ
日本風の観相。源氏物語桐壺「―をおほせておぼし寄りにける筋なれば」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぞっくん【大和俗訓】‥ゾク‥
貝原益軒著の通俗教訓書。「益軒十訓」の一つ。儒教的倫理観から修身・礼儀・作法などを平易な和文で記す。8巻。1708年(宝永5)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐たかだ【大和高田】
奈良県北西部の市。奈良盆地の南西部に位置し、靴下製造などの繊維工業が盛ん。人口7万1千。
⇒やまと【大和・倭】
やまとたける‐の‐みこと【日本武尊・倭建命】
古代伝説上の英雄。景行天皇の皇子で、本名は小碓命おうすのみこと。別名、日本童男やまとおぐな。天皇の命を奉じて熊襲くまそを討ち、のち東国を鎮定。往途、駿河で草薙剣くさなぎのつるぎによって野火の難を払い、走水はしりみずの海では妃弟橘媛おとたちばなひめの犠牲によって海上の難を免れた。帰途、近江伊吹山の神を討とうとして病を得、伊勢の能褒野のぼので没したという。
やまと‐だましい【大和魂】‥ダマシヒ
①漢才かんざい・からざえすなわち学問(漢学)上の知識に対して、実生活上の知恵・才能。和魂わこん。源氏物語少女「才を本としてこそ、―の世に用ひらるる方も」→漢才。
②日本民族固有の精神。勇猛で潔いのが特性とされる。椿説弓張月後編「事に迫りて死を軽んずるは、―なれど多くは慮おもいはかりの浅きに似て、学ばざるの悞あやまちなり」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ちょうてい【大和朝廷】‥テウ‥
「大和政権」参照。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐つかい【大和使】‥ツカヒ
遣唐使のこと。夫木和歌抄35「今の世にありとは聞かずもろこしのふみ学ぶてふ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐でん【大和伝】
大和の刀工の系統。また、その作風。→大和物。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐とじ【大和綴じ】‥トヂ
和装本の綴じ方の一つ。本文料紙は綴葉装てっちょうそうまたは袋綴じと同様の綴じ方で下綴じした上で、表紙を加え、紐などで上下2カ所(計4穴)結んで綴じる。近代以降も写真帳などに用いられる。結び綴じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐な【大和名】
日本風の名。日本名。和名。源氏物語順集「―にいひにくき事をこそそへてはよめ」↔唐名からな。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐なでしこ【大和撫子】
①ナデシコの異称。〈[季]秋〉
②日本女性の美称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐に【大和煮】
牛肉などを醤油・砂糖・生薑しょうがなどで煮たもの。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐にしき【大和錦】
①日本で織った錦。↔唐錦。
②主として2色の緯糸よこいとを一越ひとこし交替に扱い、地と文様もともに緯六枚綾の組織とした錦。糸錦。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ねこ【倭根子】
詔勅などに歴代天皇の用いた通号。孝徳紀「明神あきつみかみと御宇あめのしたしらす―の天皇…詔のたまはく」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】‥アタヒ
古代の渡来系氏族。阿知使主あちのおみの子孫と称し、朝廷の記録や外交文書をつかさどった。5世紀ごろ渡来した朝鮮の漢民族の子孫と見られ、大和を本拠とした。7世紀には政治的・軍事的に有力となり、姓かばねは直あたいから忌寸いみきや宿祢すくねに昇格。東漢氏やまとのあやうじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
垂仁天皇の皇女といわれる伝説上の人物。天照大神あまてらすおおみかみの祠を大和の笠縫邑かさぬいのむらから伊勢の五十鈴川上に遷す。景行天皇の時、甥の日本武尊やまとたけるのみことの東国征討に際して草薙剣くさなぎのつるぎを授けたという。
⇒やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
神道五部書の一つ。1巻。神宮の古伝承に加筆して古人の編に仮託し、鎌倉中期頃成立したもの。天地開闢から雄略天皇朝の外宮鎮座に至る神祇関係事項、倭姫命の事跡、宮中の諸神などを説く。
⇒やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
やまと‐ひょうぐ【大和表具】‥ヘウ‥
日本の正式の掛物の表具。上・下・中回ちゅうまわし・一文字・風帯から成り、一文字と風帯は共裂ともぎれで、金襴などを用い、上・下と中回は材料を異にし、変化をつける。
大和表具
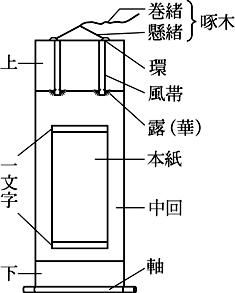 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ひょうそう【大和表装】‥ヘウサウ
(→)大和表具に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】
神楽笛かぐらぶえの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶき【大和葺】
板葺の一種。各板を同一平面に並べず、1枚おきに同一平面に置き、その相隣接する端を重ねるように並べた葺き方のもの。
大和葺
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ひょうそう【大和表装】‥ヘウサウ
(→)大和表具に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】
神楽笛かぐらぶえの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶき【大和葺】
板葺の一種。各板を同一平面に並べず、1枚おきに同一平面に置き、その相隣接する端を重ねるように並べた葺き方のもの。
大和葺
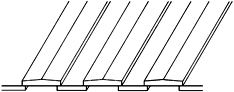 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶみ【大和文】
①日本の文章。和文。日本文。国文。
②日本語で書いた書籍。和書。国書。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶろ【大和風炉】
土製の粗末な鉢形の風炉。火鉢にも代用する。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐べい【大和塀】
①数寄屋すきやの庭などに用いる塀。地長押じなげしから笠木の間に杉皮を竪たてに張り、晒竹を押縁として打ちつけたもの。
②大和葺の要領で板を打ちつけて造った塀。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ほんぞう【大和本草】‥ザウ
和漢の本草1362種を収録・分類し、解説した書。貝原益軒著。日本で最初の本格的な本草書。16巻・付録2巻・諸品図3巻。1709年(宝永6)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まい【大和舞・倭舞】‥マヒ
①雅楽の国風歌舞くにぶりのうたまいの一種。初めは大和地方の歌舞であったものが採り入れられ、倭歌やまとうたを歌詞とし、歌方数人(一人は笏拍子を持つ)・竜笛りゅうてき一人・篳篥ひちりき一人の伴奏により舞人四人が舞う。宮中の大嘗会だいじょうえのほか、神社の神事などで行われる。都舞。
②神楽2の一つ。奈良の春日大社・伊勢神宮など諸社の神事で行われるが芸態はそれぞれ異なる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まど【大和窓】
突上げの障子がある天窓てんまど。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みこと【大和御言】
「やまとことば」の美称。千載和歌集序「―歌は、ちはやぶる神代より始まりて」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みんぞく【大和民族】
日本民族に同じ。→日本人。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐むね【大和棟】
大和を中心として河内・伊賀の地方で多く造られた民家の一形式。中央の大屋根を急勾配の茅かや葺きとし、その両妻に近い部分を瓦葺きとし、両妻面は大壁、左右または片方に台所などの緩勾配の屋根を1段低く設けた屋根形。高塀造たかへづくり。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐め【大和目】
薬種に用いた量目。1斤きんを180匁もんめとする。古く中国から伝来。中世に宋の秤目が伝えられて以後、一般には用いなくなった。→唐目とうめ→輪目わめ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どめ【山止め】
山に入ることや山の産物などを採取することを禁ずること。
やま‐どめ【山留め】
鉱山で土砂の崩壊を防ぐこと。また、そのための防御物。
やまと‐もじ【大和文字】
仮名の別称。↔唐文字からもじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐もの【大和物】
大和の刀工が製作した刀の総称。伝説的な天国あまくにらに始まり、鎌倉時代頃から千手院・当麻たいま・手掻てがい・保昌ほうしょう・尻懸しっかけなどの系統がある。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ものがたり【大和物語】
平安時代の物語。作者未詳。951年(天暦5)頃成立、以後増補か。170段余の小説話から成り、前半は伊勢物語の系統をひいた歌物語、後半約40段は歌に結びついた伝説的説話の集成。
→文献資料[大和物語]
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐や【大和屋】
①歌舞伎俳優岩井半四郎・坂東三津五郎とその一門の屋号。
②(俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ)大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。
③大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よざ【大和四座】
大和猿楽の四座。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よみ【大和訓】
漢字を大和言葉で訓むこと。また、そのよみ方。和訓。訓よみ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どり【山取り】
①山に陣取ること。山中に砦などを築くこと。日葡辞書「ヤマドリヲスル」
②植物などを、山の自生地で採集すること。
やま‐どり【山鳥】
①山にすむ鳥。
②キジ目キジ科の鳥。キジに似るが、全体光沢のある赤銅しゃくどう色で、背・胸・腹に黒白の斑がある。尾羽はきわめて長く、竹節状の横帯がある。顔の大部分は裸で赤色。雌は雄にくらべて地味で、尾羽は短い。日本特産種で本州・四国・九州の山林にすむ。雄は翼で胸をうち「どどど」と音を出し、これを「ほろを打つ」という。〈[季]春〉。万葉集8「あしひきの―こそは峰向おむかいに妻問ひすといへ」
やまどり(雄)
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶみ【大和文】
①日本の文章。和文。日本文。国文。
②日本語で書いた書籍。和書。国書。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶろ【大和風炉】
土製の粗末な鉢形の風炉。火鉢にも代用する。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐べい【大和塀】
①数寄屋すきやの庭などに用いる塀。地長押じなげしから笠木の間に杉皮を竪たてに張り、晒竹を押縁として打ちつけたもの。
②大和葺の要領で板を打ちつけて造った塀。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ほんぞう【大和本草】‥ザウ
和漢の本草1362種を収録・分類し、解説した書。貝原益軒著。日本で最初の本格的な本草書。16巻・付録2巻・諸品図3巻。1709年(宝永6)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まい【大和舞・倭舞】‥マヒ
①雅楽の国風歌舞くにぶりのうたまいの一種。初めは大和地方の歌舞であったものが採り入れられ、倭歌やまとうたを歌詞とし、歌方数人(一人は笏拍子を持つ)・竜笛りゅうてき一人・篳篥ひちりき一人の伴奏により舞人四人が舞う。宮中の大嘗会だいじょうえのほか、神社の神事などで行われる。都舞。
②神楽2の一つ。奈良の春日大社・伊勢神宮など諸社の神事で行われるが芸態はそれぞれ異なる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まど【大和窓】
突上げの障子がある天窓てんまど。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みこと【大和御言】
「やまとことば」の美称。千載和歌集序「―歌は、ちはやぶる神代より始まりて」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みんぞく【大和民族】
日本民族に同じ。→日本人。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐むね【大和棟】
大和を中心として河内・伊賀の地方で多く造られた民家の一形式。中央の大屋根を急勾配の茅かや葺きとし、その両妻に近い部分を瓦葺きとし、両妻面は大壁、左右または片方に台所などの緩勾配の屋根を1段低く設けた屋根形。高塀造たかへづくり。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐め【大和目】
薬種に用いた量目。1斤きんを180匁もんめとする。古く中国から伝来。中世に宋の秤目が伝えられて以後、一般には用いなくなった。→唐目とうめ→輪目わめ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どめ【山止め】
山に入ることや山の産物などを採取することを禁ずること。
やま‐どめ【山留め】
鉱山で土砂の崩壊を防ぐこと。また、そのための防御物。
やまと‐もじ【大和文字】
仮名の別称。↔唐文字からもじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐もの【大和物】
大和の刀工が製作した刀の総称。伝説的な天国あまくにらに始まり、鎌倉時代頃から千手院・当麻たいま・手掻てがい・保昌ほうしょう・尻懸しっかけなどの系統がある。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ものがたり【大和物語】
平安時代の物語。作者未詳。951年(天暦5)頃成立、以後増補か。170段余の小説話から成り、前半は伊勢物語の系統をひいた歌物語、後半約40段は歌に結びついた伝説的説話の集成。
→文献資料[大和物語]
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐や【大和屋】
①歌舞伎俳優岩井半四郎・坂東三津五郎とその一門の屋号。
②(俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ)大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。
③大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よざ【大和四座】
大和猿楽の四座。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よみ【大和訓】
漢字を大和言葉で訓むこと。また、そのよみ方。和訓。訓よみ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どり【山取り】
①山に陣取ること。山中に砦などを築くこと。日葡辞書「ヤマドリヲスル」
②植物などを、山の自生地で採集すること。
やま‐どり【山鳥】
①山にすむ鳥。
②キジ目キジ科の鳥。キジに似るが、全体光沢のある赤銅しゃくどう色で、背・胸・腹に黒白の斑がある。尾羽はきわめて長く、竹節状の横帯がある。顔の大部分は裸で赤色。雌は雄にくらべて地味で、尾羽は短い。日本特産種で本州・四国・九州の山林にすむ。雄は翼で胸をうち「どどど」と音を出し、これを「ほろを打つ」という。〈[季]春〉。万葉集8「あしひきの―こそは峰向おむかいに妻問ひすといへ」
やまどり(雄)
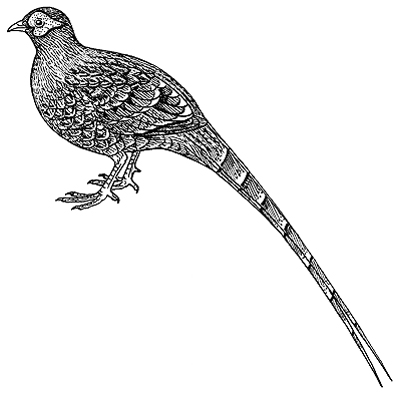 ヤマドリ
提供:OPO
ヤマドリ
提供:OPO
 ③2の雌雄は峰をへだてて寝ると言い伝えられ、古くから「ひとり寝」の例に引かれる。また、その尾が長いことから「山鳥の尾の」と続けて「長し」「尾」などを起こす序詞として用いる。万葉集11「あしひきの―の尾の長きこの夜を」
④エゾライチョウの別称。
⇒やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
⇒やまどり‐たけ【山鳥茸】
やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
ゼンマイ科の多年性シダ。中部以北の山地の湿原に群生。羽状再複葉で直立。若い葉柄を食用にする。胞子葉は別葉で、夏に生ずる。ヤマドリシダ。
やまどりぜんまい
③2の雌雄は峰をへだてて寝ると言い伝えられ、古くから「ひとり寝」の例に引かれる。また、その尾が長いことから「山鳥の尾の」と続けて「長し」「尾」などを起こす序詞として用いる。万葉集11「あしひきの―の尾の長きこの夜を」
④エゾライチョウの別称。
⇒やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
⇒やまどり‐たけ【山鳥茸】
やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
ゼンマイ科の多年性シダ。中部以北の山地の湿原に群生。羽状再複葉で直立。若い葉柄を食用にする。胞子葉は別葉で、夏に生ずる。ヤマドリシダ。
やまどりぜんまい
 ⇒やま‐どり【山鳥】
やまどり‐たけ【山鳥茸】
担子菌類のきのこ。夏・秋に、主にブナ林中に生ずる。直径15センチメートル以上。全体に黄褐色。傘は饅頭笠まんじゅうがさ状で厚く、裏面は初め鮮黄色、のち黄褐色で、多数の細孔がある。美味で食用とする。従来、ヤマドリタケとされた菌は正しくはヤマドリタケモドキであると考えられる。
⇒やま‐どり【山鳥】
やまとんちゅ
(「大和の人」の意)沖縄語で、本土の人。↔うちなんちゅ
やまな【山名】
姓氏の一つ。新田氏の支族。室町幕府四職ししきの一家。
⇒やまな‐うじきよ【山名氏清】
⇒やまな‐そうぜん【山名宗全】
やま‐ない【止まない・已まない】
(動詞連用形にテを添えた形に続けて)いつまでも…する。大いに…する。「期待して―」
やまな‐うじきよ【山名氏清】‥ウヂ‥
南北朝時代の武将。陸奥守。足利義満に仕えて戦功をたて、和泉・丹波などの守護となるが、山名一族の強大化を恐れた義満の計略により反乱、敗北して討たれる(明徳の乱)。(1344〜1391)
⇒やまな【山名】
やま‐なか【山中】
山のなか。山間。さんちゅう。
やまなか【山中】
石川県加賀市、大聖寺川中流の黒谷川渓谷にある温泉地。加賀温泉郷の一つ。硫酸塩泉。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか‐ぬり【山中塗】
⇒やまなか‐ぶし【山中節】
やまなか【山中】
姓氏の一つ。
⇒やまなか‐さだお【山中貞雄】
⇒やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
⇒やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】
やまなか‐こ【山中湖】
富士五湖の一つ。山梨県南東部にあって、五湖の東端に位置する。面積は五湖中最大で、6.8平方キロメートル。湖面標高981メートル。最大深度13メートル。湖畔は避暑・観光の好適地。
山中湖
撮影:山梨勝弘
⇒やま‐どり【山鳥】
やまどり‐たけ【山鳥茸】
担子菌類のきのこ。夏・秋に、主にブナ林中に生ずる。直径15センチメートル以上。全体に黄褐色。傘は饅頭笠まんじゅうがさ状で厚く、裏面は初め鮮黄色、のち黄褐色で、多数の細孔がある。美味で食用とする。従来、ヤマドリタケとされた菌は正しくはヤマドリタケモドキであると考えられる。
⇒やま‐どり【山鳥】
やまとんちゅ
(「大和の人」の意)沖縄語で、本土の人。↔うちなんちゅ
やまな【山名】
姓氏の一つ。新田氏の支族。室町幕府四職ししきの一家。
⇒やまな‐うじきよ【山名氏清】
⇒やまな‐そうぜん【山名宗全】
やま‐ない【止まない・已まない】
(動詞連用形にテを添えた形に続けて)いつまでも…する。大いに…する。「期待して―」
やまな‐うじきよ【山名氏清】‥ウヂ‥
南北朝時代の武将。陸奥守。足利義満に仕えて戦功をたて、和泉・丹波などの守護となるが、山名一族の強大化を恐れた義満の計略により反乱、敗北して討たれる(明徳の乱)。(1344〜1391)
⇒やまな【山名】
やま‐なか【山中】
山のなか。山間。さんちゅう。
やまなか【山中】
石川県加賀市、大聖寺川中流の黒谷川渓谷にある温泉地。加賀温泉郷の一つ。硫酸塩泉。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか‐ぬり【山中塗】
⇒やまなか‐ぶし【山中節】
やまなか【山中】
姓氏の一つ。
⇒やまなか‐さだお【山中貞雄】
⇒やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
⇒やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】
やまなか‐こ【山中湖】
富士五湖の一つ。山梨県南東部にあって、五湖の東端に位置する。面積は五湖中最大で、6.8平方キロメートル。湖面標高981メートル。最大深度13メートル。湖畔は避暑・観光の好適地。
山中湖
撮影:山梨勝弘
 やまなか‐さだお【山中貞雄】‥ヲ
映画監督・脚本家。京都生れ。作「丹下左膳余話 百万両の壺」「河内山宗俊」「人情紙風船」など。(1909〜1938)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
戦国時代の武将。名は幸盛ゆきもり。出雲の人。尼子義久に仕える。1566年(永禄9)義久が毛利氏に降ったので、尼子勝久を擁して戦ったが、のち播磨上月こうづき城で毛利方に攻められ、捕らえられて斬。( 〜1578)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぬり【山中塗】
石川県加賀市の山中温泉地区に産する漆器。天正(1573〜1592)年間に越前の挽物師が来て業を始めたという。糸目椀(千筋)などの挽物を主とし、溜塗ためぬりに優れる。
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぶし【山中節】
山中温泉を中心に歌われる民謡。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】‥ラウ
小説家・児童文学作家。本姓、馬淵。大阪府生れ。陸軍大学校卒。児童向けの軍事冒険小説で活躍。作「敵中横断三百里」など。(1885〜1966)
⇒やまなか【山中】
やま‐なし【山梨】
バラ科の落葉高木。西日本から中国大陸に分布。葉は卵形。5月頃、新枝の先に白花を開く。果実は秋に熟し、直径約2センチメートル、黄色または紅色で梨に似、外皮に小斑点が散在。〈[季]秋〉。源氏物語総角「かかる御すまひのかひなき、―の花ぞのがれん方なかりける」
やまなし【山梨】
①中部地方南東部、内陸の県。甲斐国を管轄。県庁所在地は甲府市。面積4465平方キロメートル。人口88万5千。全13市。
→えんこ節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山梨県中北部の市。笛吹川上流域にあり、ブドウ栽培が盛ん。人口3万9千。
⇒やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】
⇒やまなし‐だいがく【山梨大学】
やまなし【山梨】
姓氏の一つ。
⇒やまなし‐とうせん【山梨稲川】
やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】‥クワ‥
もと国立大学の一つ。1978年設立。2002年山梨大学に統合され、同大医学部となる。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐だいがく【山梨大学】
国立大学法人の一つ。1795年(寛政7)設立の甲府学問所徽典館を起源とする山梨師範学校、同青年師範、1924年(大正13)創立の山梨高等工業学校(のち山梨工専)が合併し、49年新制大学となる。2002年山梨医学大学を統合。04年法人化。本部は甲府市。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐とうせん【山梨稲川】‥タウ‥
江戸後期の漢学者・音韻学者。名は治憲。通称、東平。駿河の人。本居宣長らが古音を論ずるのに刺激されて「説文せつもん」を音韻的に研究した。著「文緯」「古声譜」「諧声図」「稲川文草」など。(1771〜1826)
⇒やまなし【山梨】
やまな‐そうぜん【山名宗全】
室町中期の武将。名は持豊。嘉吉かきつの乱に赤松満祐を討ち、その旧領を得て一族で山陰・山陽9カ国の守護職を併す。後に細川勝元と結託して畠山氏に当たったが、将軍義政の妻富子がその子義尚を託したことから、足利義視を擁する勝元と対抗し応仁の乱を起こした。西軍の主将。戦乱半ばにして陣中に没。(1404〜1473)
⇒やまな【山名】
やま‐なみ【山並・山脈】
山が並んでいること。また、そのさま。また、その山。連山。万葉集6「―のよろしき国と」
山並
撮影:関戸 勇
やまなか‐さだお【山中貞雄】‥ヲ
映画監督・脚本家。京都生れ。作「丹下左膳余話 百万両の壺」「河内山宗俊」「人情紙風船」など。(1909〜1938)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
戦国時代の武将。名は幸盛ゆきもり。出雲の人。尼子義久に仕える。1566年(永禄9)義久が毛利氏に降ったので、尼子勝久を擁して戦ったが、のち播磨上月こうづき城で毛利方に攻められ、捕らえられて斬。( 〜1578)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぬり【山中塗】
石川県加賀市の山中温泉地区に産する漆器。天正(1573〜1592)年間に越前の挽物師が来て業を始めたという。糸目椀(千筋)などの挽物を主とし、溜塗ためぬりに優れる。
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぶし【山中節】
山中温泉を中心に歌われる民謡。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】‥ラウ
小説家・児童文学作家。本姓、馬淵。大阪府生れ。陸軍大学校卒。児童向けの軍事冒険小説で活躍。作「敵中横断三百里」など。(1885〜1966)
⇒やまなか【山中】
やま‐なし【山梨】
バラ科の落葉高木。西日本から中国大陸に分布。葉は卵形。5月頃、新枝の先に白花を開く。果実は秋に熟し、直径約2センチメートル、黄色または紅色で梨に似、外皮に小斑点が散在。〈[季]秋〉。源氏物語総角「かかる御すまひのかひなき、―の花ぞのがれん方なかりける」
やまなし【山梨】
①中部地方南東部、内陸の県。甲斐国を管轄。県庁所在地は甲府市。面積4465平方キロメートル。人口88万5千。全13市。
→えんこ節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山梨県中北部の市。笛吹川上流域にあり、ブドウ栽培が盛ん。人口3万9千。
⇒やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】
⇒やまなし‐だいがく【山梨大学】
やまなし【山梨】
姓氏の一つ。
⇒やまなし‐とうせん【山梨稲川】
やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】‥クワ‥
もと国立大学の一つ。1978年設立。2002年山梨大学に統合され、同大医学部となる。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐だいがく【山梨大学】
国立大学法人の一つ。1795年(寛政7)設立の甲府学問所徽典館を起源とする山梨師範学校、同青年師範、1924年(大正13)創立の山梨高等工業学校(のち山梨工専)が合併し、49年新制大学となる。2002年山梨医学大学を統合。04年法人化。本部は甲府市。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐とうせん【山梨稲川】‥タウ‥
江戸後期の漢学者・音韻学者。名は治憲。通称、東平。駿河の人。本居宣長らが古音を論ずるのに刺激されて「説文せつもん」を音韻的に研究した。著「文緯」「古声譜」「諧声図」「稲川文草」など。(1771〜1826)
⇒やまなし【山梨】
やまな‐そうぜん【山名宗全】
室町中期の武将。名は持豊。嘉吉かきつの乱に赤松満祐を討ち、その旧領を得て一族で山陰・山陽9カ国の守護職を併す。後に細川勝元と結託して畠山氏に当たったが、将軍義政の妻富子がその子義尚を託したことから、足利義視を擁する勝元と対抗し応仁の乱を起こした。西軍の主将。戦乱半ばにして陣中に没。(1404〜1473)
⇒やまな【山名】
やま‐なみ【山並・山脈】
山が並んでいること。また、そのさま。また、その山。連山。万葉集6「―のよろしき国と」
山並
撮影:関戸 勇
 やま‐ならし【山鳴らし】
〔植〕(風にゆれて葉が鳴るからいう)ハコヤナギの別称。
やま‐なり【山形】
山のような曲線をえがくこと。また、その形。「―の超スローボール」
やま‐なり【山鳴り】
山が鳴動すること。また、その音。
やま‐ならし【山鳴らし】
〔植〕(風にゆれて葉が鳴るからいう)ハコヤナギの別称。
やま‐なり【山形】
山のような曲線をえがくこと。また、その形。「―の超スローボール」
やま‐なり【山鳴り】
山が鳴動すること。また、その音。
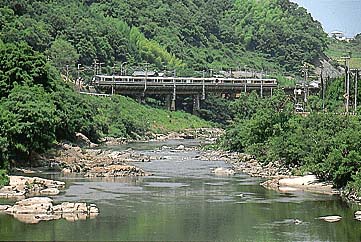 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】‥カハチ‥
(大和を東、河内を西と表記する)それぞれ阿知使主あちのおみ・王仁わにの子孫と称し、史の姓かばねを賜って朝廷の記録や外交文書をつかさどった氏。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐさ【大和草】
ヤマトグサ科の多年草。山地に自生。高さ約20センチメートル。葉は卵形。全体はハコベに似る。4〜5月頃、淡緑色の小さな単性花を開く。雄花では白い多数の雄しべが細長く垂れる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】
飾り鞍の一種。唐様の鞍に対して和様化した鞍。わぐら。↔唐鞍からくら。
大和鞍
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】‥カハチ‥
(大和を東、河内を西と表記する)それぞれ阿知使主あちのおみ・王仁わにの子孫と称し、史の姓かばねを賜って朝廷の記録や外交文書をつかさどった氏。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐさ【大和草】
ヤマトグサ科の多年草。山地に自生。高さ約20センチメートル。葉は卵形。全体はハコベに似る。4〜5月頃、淡緑色の小さな単性花を開く。雄花では白い多数の雄しべが細長く垂れる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】
飾り鞍の一種。唐様の鞍に対して和様化した鞍。わぐら。↔唐鞍からくら。
大和鞍
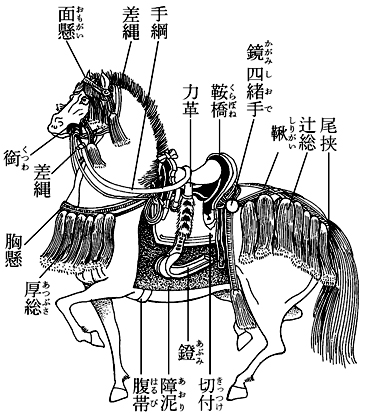 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐けんぎょう【山登検校】‥ゲウ
(初世)江戸後期の箏曲家・平曲家。山登派の家元。江戸生れ。名は松和一しょうわいち。本名、高木清吉。山田検校の筆頭弟子で、その没後は山田流の指導的立場にあった。作「春日詣かすがもうで」「新七草」など。(1782〜1863)
⇒やまと【山登】
やまと‐ごえ【倭音・和音】‥ゴヱ
(→)呉音ごおんに同じ。漢音を「からごえ」というのに対していう。わおん。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こおりやま【大和郡山】‥コホリ‥
奈良県北部の市。もと柳沢氏15万石の城下町。近世以降、金魚の養殖で有名。人口9万2千。
大和郡山 金魚の養殖
撮影:的場 啓
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐けんぎょう【山登検校】‥ゲウ
(初世)江戸後期の箏曲家・平曲家。山登派の家元。江戸生れ。名は松和一しょうわいち。本名、高木清吉。山田検校の筆頭弟子で、その没後は山田流の指導的立場にあった。作「春日詣かすがもうで」「新七草」など。(1782〜1863)
⇒やまと【山登】
やまと‐ごえ【倭音・和音】‥ゴヱ
(→)呉音ごおんに同じ。漢音を「からごえ」というのに対していう。わおん。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こおりやま【大和郡山】‥コホリ‥
奈良県北部の市。もと柳沢氏15万石の城下町。近世以降、金魚の養殖で有名。人口9万2千。
大和郡山 金魚の養殖
撮影:的場 啓
 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】
ゴキブリ科の一種。体長2〜3センチメートル。体は栗色、雌の成虫は翅はねが短い。家住性ゴキブリのうち唯一の在来種で、東北から近畿地方に分布。一般家屋内に多いやや大形のクロゴキブリに似るが、胸部背面が平滑でない。
ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】
ゴキブリ科の一種。体長2〜3センチメートル。体は栗色、雌の成虫は翅はねが短い。家住性ゴキブリのうち唯一の在来種で、東北から近畿地方に分布。一般家屋内に多いやや大形のクロゴキブリに似るが、胸部背面が平滑でない。
ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごころ【大和心】
①(→)「やまとだましい」1に同じ。大鏡道隆「大弐殿、弓矢の本末もとすえも知り給はねば、いかがとおぼしけれど、―かしこくおはする人にて」↔漢心からごころ。
②日本人の持つ、やさしく、やわらいだ心情。石上稿(本居宣長)「しきしまの―を人問はば朝日に匂ふ山桜花」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごたつ【大和火燵】
(→)置おき火燵に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こっか【大和国家】‥コク‥
畿内を中心とする古代国家。成立は、邪馬台国大和説を採れば3世紀前半以前、九州説を採れば3世紀後半以後となる。4世紀後半には畿内から西日本まで統一して朝鮮と交流、5世紀には東北地方を除く東日本を征服し、7世紀半ばの大化改新により律令国家に変質。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごと【大和琴・倭琴】
和琴わごんの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことのは【大和言の葉】
(→)「やまとことば」に同じ。源氏物語桐壺「伊勢、貫之に詠ませ給へる―をも、もろこしの歌をも」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことば【山人言葉】
狩人が山で使う言葉。山言葉。
⇒やま‐と【山人】
やまと‐ことば【大和言葉】
①日本固有の言語。日本語。和語。やまとことのは。
②和歌。やまとうた。源氏物語東屋「―だにつきなく習ひにければ」
③日本の雅言。主に平安時代の語。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さるがく【大和猿楽】
室町時代、大和国に住し、春日神社の神事に従事した結崎ゆうざき・外山とび・円満井えんまい・坂戸さかどの4座の猿楽。後にそれぞれ観世・宝生・金春こんぱる・金剛の4座となった。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さんざん【大和三山】
奈良盆地南部にある三つの山。古代の藤原京を囲み、北に耳成みみなし山、東に香具かぐ山、西に畝傍うねび山がある。
大和三山
撮影:的場 啓
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごころ【大和心】
①(→)「やまとだましい」1に同じ。大鏡道隆「大弐殿、弓矢の本末もとすえも知り給はねば、いかがとおぼしけれど、―かしこくおはする人にて」↔漢心からごころ。
②日本人の持つ、やさしく、やわらいだ心情。石上稿(本居宣長)「しきしまの―を人問はば朝日に匂ふ山桜花」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごたつ【大和火燵】
(→)置おき火燵に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐こっか【大和国家】‥コク‥
畿内を中心とする古代国家。成立は、邪馬台国大和説を採れば3世紀前半以前、九州説を採れば3世紀後半以後となる。4世紀後半には畿内から西日本まで統一して朝鮮と交流、5世紀には東北地方を除く東日本を征服し、7世紀半ばの大化改新により律令国家に変質。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ごと【大和琴・倭琴】
和琴わごんの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことのは【大和言の葉】
(→)「やまとことば」に同じ。源氏物語桐壺「伊勢、貫之に詠ませ給へる―をも、もろこしの歌をも」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ことば【山人言葉】
狩人が山で使う言葉。山言葉。
⇒やま‐と【山人】
やまと‐ことば【大和言葉】
①日本固有の言語。日本語。和語。やまとことのは。
②和歌。やまとうた。源氏物語東屋「―だにつきなく習ひにければ」
③日本の雅言。主に平安時代の語。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さるがく【大和猿楽】
室町時代、大和国に住し、春日神社の神事に従事した結崎ゆうざき・外山とび・円満井えんまい・坂戸さかどの4座の猿楽。後にそれぞれ観世・宝生・金春こんぱる・金剛の4座となった。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐さんざん【大和三山】
奈良盆地南部にある三つの山。古代の藤原京を囲み、北に耳成みみなし山、東に香具かぐ山、西に畝傍うねび山がある。
大和三山
撮影:的場 啓
 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じ【大和路】‥ヂ
①大和へ向かう道。万葉集6「―の吉備の児島を過ぎて行かば」
②京都の五条口から伏見・木津を通り大和に至る道。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐しじみ【大和蜆】
シジミガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で、殻長3センチメートル。黒褐色で、幼若期は黄褐色の放射状色帯をもつ。卵生。日本全国の河口域にすみ、宍道湖・十三湖・利根川が主要産地。市場のシジミのほとんどが本種。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じだい【大和時代】
日本史の時代区分の一つ。大和または大和を中心とする畿内地方に大王(のちに天皇)の政権のあった時代。律令時代の前で、考古学上の古墳時代とほぼ一致する。→大和政権。
⇒やまと【大和・倭】
やまとじ‐ぶし【大和路節】‥ヂ‥
浄瑠璃の一流派。宝暦(1751〜1764)頃、宮古路豊後掾の上方の門弟、大和路仲太夫が創始。やがて廃絶。広義の豊後節に属する。仲太夫節。
やまと‐しまね【大和島根】
①日本国の別称。万葉集20「天地の固めし国そ―は」
②大和国の称。万葉集3「千重に隠りぬ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐せいけん【大和政権】
大和を中心とする畿内地方の古代政権。諸豪族が連合して大王、後には天皇という称号の君主を擁立し、4〜5世紀までに東北地方以遠を除く日本本土の大半を統一した。統一時代の君主は軍事的英雄であったと見る説もあるが、6世紀には世襲的王制が確立し、諸豪族は臣おみ・連むらじなどの姓かばねによって階層的に秩序づけられて、氏姓制度が成立した。飛鳥時代から氏姓より個人の才能・努力を重んずる官司制度が発達し、7世紀半ばの大化改新後、律令制の朝廷に変質した。大和朝廷。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐そう【大和相】‥サウ
日本風の観相。源氏物語桐壺「―をおほせておぼし寄りにける筋なれば」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぞっくん【大和俗訓】‥ゾク‥
貝原益軒著の通俗教訓書。「益軒十訓」の一つ。儒教的倫理観から修身・礼儀・作法などを平易な和文で記す。8巻。1708年(宝永5)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐たかだ【大和高田】
奈良県北西部の市。奈良盆地の南西部に位置し、靴下製造などの繊維工業が盛ん。人口7万1千。
⇒やまと【大和・倭】
やまとたける‐の‐みこと【日本武尊・倭建命】
古代伝説上の英雄。景行天皇の皇子で、本名は小碓命おうすのみこと。別名、日本童男やまとおぐな。天皇の命を奉じて熊襲くまそを討ち、のち東国を鎮定。往途、駿河で草薙剣くさなぎのつるぎによって野火の難を払い、走水はしりみずの海では妃弟橘媛おとたちばなひめの犠牲によって海上の難を免れた。帰途、近江伊吹山の神を討とうとして病を得、伊勢の能褒野のぼので没したという。
やまと‐だましい【大和魂】‥ダマシヒ
①漢才かんざい・からざえすなわち学問(漢学)上の知識に対して、実生活上の知恵・才能。和魂わこん。源氏物語少女「才を本としてこそ、―の世に用ひらるる方も」→漢才。
②日本民族固有の精神。勇猛で潔いのが特性とされる。椿説弓張月後編「事に迫りて死を軽んずるは、―なれど多くは慮おもいはかりの浅きに似て、学ばざるの悞あやまちなり」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ちょうてい【大和朝廷】‥テウ‥
「大和政権」参照。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐つかい【大和使】‥ツカヒ
遣唐使のこと。夫木和歌抄35「今の世にありとは聞かずもろこしのふみ学ぶてふ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐でん【大和伝】
大和の刀工の系統。また、その作風。→大和物。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐とじ【大和綴じ】‥トヂ
和装本の綴じ方の一つ。本文料紙は綴葉装てっちょうそうまたは袋綴じと同様の綴じ方で下綴じした上で、表紙を加え、紐などで上下2カ所(計4穴)結んで綴じる。近代以降も写真帳などに用いられる。結び綴じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐な【大和名】
日本風の名。日本名。和名。源氏物語順集「―にいひにくき事をこそそへてはよめ」↔唐名からな。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐なでしこ【大和撫子】
①ナデシコの異称。〈[季]秋〉
②日本女性の美称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐に【大和煮】
牛肉などを醤油・砂糖・生薑しょうがなどで煮たもの。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐にしき【大和錦】
①日本で織った錦。↔唐錦。
②主として2色の緯糸よこいとを一越ひとこし交替に扱い、地と文様もともに緯六枚綾の組織とした錦。糸錦。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ねこ【倭根子】
詔勅などに歴代天皇の用いた通号。孝徳紀「明神あきつみかみと御宇あめのしたしらす―の天皇…詔のたまはく」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】‥アタヒ
古代の渡来系氏族。阿知使主あちのおみの子孫と称し、朝廷の記録や外交文書をつかさどった。5世紀ごろ渡来した朝鮮の漢民族の子孫と見られ、大和を本拠とした。7世紀には政治的・軍事的に有力となり、姓かばねは直あたいから忌寸いみきや宿祢すくねに昇格。東漢氏やまとのあやうじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
垂仁天皇の皇女といわれる伝説上の人物。天照大神あまてらすおおみかみの祠を大和の笠縫邑かさぬいのむらから伊勢の五十鈴川上に遷す。景行天皇の時、甥の日本武尊やまとたけるのみことの東国征討に際して草薙剣くさなぎのつるぎを授けたという。
⇒やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
神道五部書の一つ。1巻。神宮の古伝承に加筆して古人の編に仮託し、鎌倉中期頃成立したもの。天地開闢から雄略天皇朝の外宮鎮座に至る神祇関係事項、倭姫命の事跡、宮中の諸神などを説く。
⇒やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
やまと‐ひょうぐ【大和表具】‥ヘウ‥
日本の正式の掛物の表具。上・下・中回ちゅうまわし・一文字・風帯から成り、一文字と風帯は共裂ともぎれで、金襴などを用い、上・下と中回は材料を異にし、変化をつける。
大和表具
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じ【大和路】‥ヂ
①大和へ向かう道。万葉集6「―の吉備の児島を過ぎて行かば」
②京都の五条口から伏見・木津を通り大和に至る道。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐しじみ【大和蜆】
シジミガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で、殻長3センチメートル。黒褐色で、幼若期は黄褐色の放射状色帯をもつ。卵生。日本全国の河口域にすみ、宍道湖・十三湖・利根川が主要産地。市場のシジミのほとんどが本種。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐じだい【大和時代】
日本史の時代区分の一つ。大和または大和を中心とする畿内地方に大王(のちに天皇)の政権のあった時代。律令時代の前で、考古学上の古墳時代とほぼ一致する。→大和政権。
⇒やまと【大和・倭】
やまとじ‐ぶし【大和路節】‥ヂ‥
浄瑠璃の一流派。宝暦(1751〜1764)頃、宮古路豊後掾の上方の門弟、大和路仲太夫が創始。やがて廃絶。広義の豊後節に属する。仲太夫節。
やまと‐しまね【大和島根】
①日本国の別称。万葉集20「天地の固めし国そ―は」
②大和国の称。万葉集3「千重に隠りぬ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐せいけん【大和政権】
大和を中心とする畿内地方の古代政権。諸豪族が連合して大王、後には天皇という称号の君主を擁立し、4〜5世紀までに東北地方以遠を除く日本本土の大半を統一した。統一時代の君主は軍事的英雄であったと見る説もあるが、6世紀には世襲的王制が確立し、諸豪族は臣おみ・連むらじなどの姓かばねによって階層的に秩序づけられて、氏姓制度が成立した。飛鳥時代から氏姓より個人の才能・努力を重んずる官司制度が発達し、7世紀半ばの大化改新後、律令制の朝廷に変質した。大和朝廷。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐そう【大和相】‥サウ
日本風の観相。源氏物語桐壺「―をおほせておぼし寄りにける筋なれば」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぞっくん【大和俗訓】‥ゾク‥
貝原益軒著の通俗教訓書。「益軒十訓」の一つ。儒教的倫理観から修身・礼儀・作法などを平易な和文で記す。8巻。1708年(宝永5)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐たかだ【大和高田】
奈良県北西部の市。奈良盆地の南西部に位置し、靴下製造などの繊維工業が盛ん。人口7万1千。
⇒やまと【大和・倭】
やまとたける‐の‐みこと【日本武尊・倭建命】
古代伝説上の英雄。景行天皇の皇子で、本名は小碓命おうすのみこと。別名、日本童男やまとおぐな。天皇の命を奉じて熊襲くまそを討ち、のち東国を鎮定。往途、駿河で草薙剣くさなぎのつるぎによって野火の難を払い、走水はしりみずの海では妃弟橘媛おとたちばなひめの犠牲によって海上の難を免れた。帰途、近江伊吹山の神を討とうとして病を得、伊勢の能褒野のぼので没したという。
やまと‐だましい【大和魂】‥ダマシヒ
①漢才かんざい・からざえすなわち学問(漢学)上の知識に対して、実生活上の知恵・才能。和魂わこん。源氏物語少女「才を本としてこそ、―の世に用ひらるる方も」→漢才。
②日本民族固有の精神。勇猛で潔いのが特性とされる。椿説弓張月後編「事に迫りて死を軽んずるは、―なれど多くは慮おもいはかりの浅きに似て、学ばざるの悞あやまちなり」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ちょうてい【大和朝廷】‥テウ‥
「大和政権」参照。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐つかい【大和使】‥ツカヒ
遣唐使のこと。夫木和歌抄35「今の世にありとは聞かずもろこしのふみ学ぶてふ―は」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐でん【大和伝】
大和の刀工の系統。また、その作風。→大和物。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐とじ【大和綴じ】‥トヂ
和装本の綴じ方の一つ。本文料紙は綴葉装てっちょうそうまたは袋綴じと同様の綴じ方で下綴じした上で、表紙を加え、紐などで上下2カ所(計4穴)結んで綴じる。近代以降も写真帳などに用いられる。結び綴じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐な【大和名】
日本風の名。日本名。和名。源氏物語順集「―にいひにくき事をこそそへてはよめ」↔唐名からな。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐なでしこ【大和撫子】
①ナデシコの異称。〈[季]秋〉
②日本女性の美称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐に【大和煮】
牛肉などを醤油・砂糖・生薑しょうがなどで煮たもの。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐にしき【大和錦】
①日本で織った錦。↔唐錦。
②主として2色の緯糸よこいとを一越ひとこし交替に扱い、地と文様もともに緯六枚綾の組織とした錦。糸錦。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ねこ【倭根子】
詔勅などに歴代天皇の用いた通号。孝徳紀「明神あきつみかみと御宇あめのしたしらす―の天皇…詔のたまはく」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】‥アタヒ
古代の渡来系氏族。阿知使主あちのおみの子孫と称し、朝廷の記録や外交文書をつかさどった。5世紀ごろ渡来した朝鮮の漢民族の子孫と見られ、大和を本拠とした。7世紀には政治的・軍事的に有力となり、姓かばねは直あたいから忌寸いみきや宿祢すくねに昇格。東漢氏やまとのあやうじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
垂仁天皇の皇女といわれる伝説上の人物。天照大神あまてらすおおみかみの祠を大和の笠縫邑かさぬいのむらから伊勢の五十鈴川上に遷す。景行天皇の時、甥の日本武尊やまとたけるのみことの東国征討に際して草薙剣くさなぎのつるぎを授けたという。
⇒やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
やまとひめのみこと‐せいき【倭姫命世記】
神道五部書の一つ。1巻。神宮の古伝承に加筆して古人の編に仮託し、鎌倉中期頃成立したもの。天地開闢から雄略天皇朝の外宮鎮座に至る神祇関係事項、倭姫命の事跡、宮中の諸神などを説く。
⇒やまとひめ‐の‐みこと【倭姫命】
やまと‐ひょうぐ【大和表具】‥ヘウ‥
日本の正式の掛物の表具。上・下・中回ちゅうまわし・一文字・風帯から成り、一文字と風帯は共裂ともぎれで、金襴などを用い、上・下と中回は材料を異にし、変化をつける。
大和表具
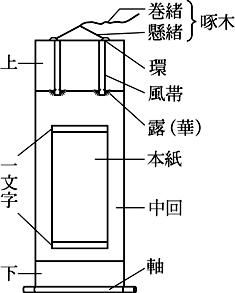 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ひょうそう【大和表装】‥ヘウサウ
(→)大和表具に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】
神楽笛かぐらぶえの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶき【大和葺】
板葺の一種。各板を同一平面に並べず、1枚おきに同一平面に置き、その相隣接する端を重ねるように並べた葺き方のもの。
大和葺
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ひょうそう【大和表装】‥ヘウサウ
(→)大和表具に同じ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】
神楽笛かぐらぶえの別称。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶき【大和葺】
板葺の一種。各板を同一平面に並べず、1枚おきに同一平面に置き、その相隣接する端を重ねるように並べた葺き方のもの。
大和葺
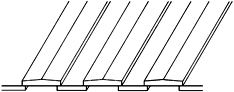 ⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶみ【大和文】
①日本の文章。和文。日本文。国文。
②日本語で書いた書籍。和書。国書。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶろ【大和風炉】
土製の粗末な鉢形の風炉。火鉢にも代用する。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐べい【大和塀】
①数寄屋すきやの庭などに用いる塀。地長押じなげしから笠木の間に杉皮を竪たてに張り、晒竹を押縁として打ちつけたもの。
②大和葺の要領で板を打ちつけて造った塀。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ほんぞう【大和本草】‥ザウ
和漢の本草1362種を収録・分類し、解説した書。貝原益軒著。日本で最初の本格的な本草書。16巻・付録2巻・諸品図3巻。1709年(宝永6)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まい【大和舞・倭舞】‥マヒ
①雅楽の国風歌舞くにぶりのうたまいの一種。初めは大和地方の歌舞であったものが採り入れられ、倭歌やまとうたを歌詞とし、歌方数人(一人は笏拍子を持つ)・竜笛りゅうてき一人・篳篥ひちりき一人の伴奏により舞人四人が舞う。宮中の大嘗会だいじょうえのほか、神社の神事などで行われる。都舞。
②神楽2の一つ。奈良の春日大社・伊勢神宮など諸社の神事で行われるが芸態はそれぞれ異なる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まど【大和窓】
突上げの障子がある天窓てんまど。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みこと【大和御言】
「やまとことば」の美称。千載和歌集序「―歌は、ちはやぶる神代より始まりて」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みんぞく【大和民族】
日本民族に同じ。→日本人。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐むね【大和棟】
大和を中心として河内・伊賀の地方で多く造られた民家の一形式。中央の大屋根を急勾配の茅かや葺きとし、その両妻に近い部分を瓦葺きとし、両妻面は大壁、左右または片方に台所などの緩勾配の屋根を1段低く設けた屋根形。高塀造たかへづくり。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐め【大和目】
薬種に用いた量目。1斤きんを180匁もんめとする。古く中国から伝来。中世に宋の秤目が伝えられて以後、一般には用いなくなった。→唐目とうめ→輪目わめ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どめ【山止め】
山に入ることや山の産物などを採取することを禁ずること。
やま‐どめ【山留め】
鉱山で土砂の崩壊を防ぐこと。また、そのための防御物。
やまと‐もじ【大和文字】
仮名の別称。↔唐文字からもじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐もの【大和物】
大和の刀工が製作した刀の総称。伝説的な天国あまくにらに始まり、鎌倉時代頃から千手院・当麻たいま・手掻てがい・保昌ほうしょう・尻懸しっかけなどの系統がある。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ものがたり【大和物語】
平安時代の物語。作者未詳。951年(天暦5)頃成立、以後増補か。170段余の小説話から成り、前半は伊勢物語の系統をひいた歌物語、後半約40段は歌に結びついた伝説的説話の集成。
→文献資料[大和物語]
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐や【大和屋】
①歌舞伎俳優岩井半四郎・坂東三津五郎とその一門の屋号。
②(俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ)大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。
③大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よざ【大和四座】
大和猿楽の四座。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よみ【大和訓】
漢字を大和言葉で訓むこと。また、そのよみ方。和訓。訓よみ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どり【山取り】
①山に陣取ること。山中に砦などを築くこと。日葡辞書「ヤマドリヲスル」
②植物などを、山の自生地で採集すること。
やま‐どり【山鳥】
①山にすむ鳥。
②キジ目キジ科の鳥。キジに似るが、全体光沢のある赤銅しゃくどう色で、背・胸・腹に黒白の斑がある。尾羽はきわめて長く、竹節状の横帯がある。顔の大部分は裸で赤色。雌は雄にくらべて地味で、尾羽は短い。日本特産種で本州・四国・九州の山林にすむ。雄は翼で胸をうち「どどど」と音を出し、これを「ほろを打つ」という。〈[季]春〉。万葉集8「あしひきの―こそは峰向おむかいに妻問ひすといへ」
やまどり(雄)
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶみ【大和文】
①日本の文章。和文。日本文。国文。
②日本語で書いた書籍。和書。国書。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ぶろ【大和風炉】
土製の粗末な鉢形の風炉。火鉢にも代用する。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐べい【大和塀】
①数寄屋すきやの庭などに用いる塀。地長押じなげしから笠木の間に杉皮を竪たてに張り、晒竹を押縁として打ちつけたもの。
②大和葺の要領で板を打ちつけて造った塀。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ほんぞう【大和本草】‥ザウ
和漢の本草1362種を収録・分類し、解説した書。貝原益軒著。日本で最初の本格的な本草書。16巻・付録2巻・諸品図3巻。1709年(宝永6)刊。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まい【大和舞・倭舞】‥マヒ
①雅楽の国風歌舞くにぶりのうたまいの一種。初めは大和地方の歌舞であったものが採り入れられ、倭歌やまとうたを歌詞とし、歌方数人(一人は笏拍子を持つ)・竜笛りゅうてき一人・篳篥ひちりき一人の伴奏により舞人四人が舞う。宮中の大嘗会だいじょうえのほか、神社の神事などで行われる。都舞。
②神楽2の一つ。奈良の春日大社・伊勢神宮など諸社の神事で行われるが芸態はそれぞれ異なる。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐まど【大和窓】
突上げの障子がある天窓てんまど。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みこと【大和御言】
「やまとことば」の美称。千載和歌集序「―歌は、ちはやぶる神代より始まりて」
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐みんぞく【大和民族】
日本民族に同じ。→日本人。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐むね【大和棟】
大和を中心として河内・伊賀の地方で多く造られた民家の一形式。中央の大屋根を急勾配の茅かや葺きとし、その両妻に近い部分を瓦葺きとし、両妻面は大壁、左右または片方に台所などの緩勾配の屋根を1段低く設けた屋根形。高塀造たかへづくり。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐め【大和目】
薬種に用いた量目。1斤きんを180匁もんめとする。古く中国から伝来。中世に宋の秤目が伝えられて以後、一般には用いなくなった。→唐目とうめ→輪目わめ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どめ【山止め】
山に入ることや山の産物などを採取することを禁ずること。
やま‐どめ【山留め】
鉱山で土砂の崩壊を防ぐこと。また、そのための防御物。
やまと‐もじ【大和文字】
仮名の別称。↔唐文字からもじ。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐もの【大和物】
大和の刀工が製作した刀の総称。伝説的な天国あまくにらに始まり、鎌倉時代頃から千手院・当麻たいま・手掻てがい・保昌ほうしょう・尻懸しっかけなどの系統がある。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐ものがたり【大和物語】
平安時代の物語。作者未詳。951年(天暦5)頃成立、以後増補か。170段余の小説話から成り、前半は伊勢物語の系統をひいた歌物語、後半約40段は歌に結びついた伝説的説話の集成。
→文献資料[大和物語]
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐や【大和屋】
①歌舞伎俳優岩井半四郎・坂東三津五郎とその一門の屋号。
②(俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ)大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。
③大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よざ【大和四座】
大和猿楽の四座。
⇒やまと【大和・倭】
やまと‐よみ【大和訓】
漢字を大和言葉で訓むこと。また、そのよみ方。和訓。訓よみ。
⇒やまと【大和・倭】
やま‐どり【山取り】
①山に陣取ること。山中に砦などを築くこと。日葡辞書「ヤマドリヲスル」
②植物などを、山の自生地で採集すること。
やま‐どり【山鳥】
①山にすむ鳥。
②キジ目キジ科の鳥。キジに似るが、全体光沢のある赤銅しゃくどう色で、背・胸・腹に黒白の斑がある。尾羽はきわめて長く、竹節状の横帯がある。顔の大部分は裸で赤色。雌は雄にくらべて地味で、尾羽は短い。日本特産種で本州・四国・九州の山林にすむ。雄は翼で胸をうち「どどど」と音を出し、これを「ほろを打つ」という。〈[季]春〉。万葉集8「あしひきの―こそは峰向おむかいに妻問ひすといへ」
やまどり(雄)
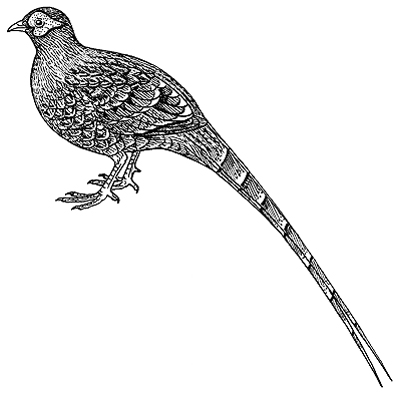 ヤマドリ
提供:OPO
ヤマドリ
提供:OPO
 ③2の雌雄は峰をへだてて寝ると言い伝えられ、古くから「ひとり寝」の例に引かれる。また、その尾が長いことから「山鳥の尾の」と続けて「長し」「尾」などを起こす序詞として用いる。万葉集11「あしひきの―の尾の長きこの夜を」
④エゾライチョウの別称。
⇒やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
⇒やまどり‐たけ【山鳥茸】
やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
ゼンマイ科の多年性シダ。中部以北の山地の湿原に群生。羽状再複葉で直立。若い葉柄を食用にする。胞子葉は別葉で、夏に生ずる。ヤマドリシダ。
やまどりぜんまい
③2の雌雄は峰をへだてて寝ると言い伝えられ、古くから「ひとり寝」の例に引かれる。また、その尾が長いことから「山鳥の尾の」と続けて「長し」「尾」などを起こす序詞として用いる。万葉集11「あしひきの―の尾の長きこの夜を」
④エゾライチョウの別称。
⇒やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
⇒やまどり‐たけ【山鳥茸】
やまどり‐ぜんまい【山鳥薇】
ゼンマイ科の多年性シダ。中部以北の山地の湿原に群生。羽状再複葉で直立。若い葉柄を食用にする。胞子葉は別葉で、夏に生ずる。ヤマドリシダ。
やまどりぜんまい
 ⇒やま‐どり【山鳥】
やまどり‐たけ【山鳥茸】
担子菌類のきのこ。夏・秋に、主にブナ林中に生ずる。直径15センチメートル以上。全体に黄褐色。傘は饅頭笠まんじゅうがさ状で厚く、裏面は初め鮮黄色、のち黄褐色で、多数の細孔がある。美味で食用とする。従来、ヤマドリタケとされた菌は正しくはヤマドリタケモドキであると考えられる。
⇒やま‐どり【山鳥】
やまとんちゅ
(「大和の人」の意)沖縄語で、本土の人。↔うちなんちゅ
やまな【山名】
姓氏の一つ。新田氏の支族。室町幕府四職ししきの一家。
⇒やまな‐うじきよ【山名氏清】
⇒やまな‐そうぜん【山名宗全】
やま‐ない【止まない・已まない】
(動詞連用形にテを添えた形に続けて)いつまでも…する。大いに…する。「期待して―」
やまな‐うじきよ【山名氏清】‥ウヂ‥
南北朝時代の武将。陸奥守。足利義満に仕えて戦功をたて、和泉・丹波などの守護となるが、山名一族の強大化を恐れた義満の計略により反乱、敗北して討たれる(明徳の乱)。(1344〜1391)
⇒やまな【山名】
やま‐なか【山中】
山のなか。山間。さんちゅう。
やまなか【山中】
石川県加賀市、大聖寺川中流の黒谷川渓谷にある温泉地。加賀温泉郷の一つ。硫酸塩泉。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか‐ぬり【山中塗】
⇒やまなか‐ぶし【山中節】
やまなか【山中】
姓氏の一つ。
⇒やまなか‐さだお【山中貞雄】
⇒やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
⇒やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】
やまなか‐こ【山中湖】
富士五湖の一つ。山梨県南東部にあって、五湖の東端に位置する。面積は五湖中最大で、6.8平方キロメートル。湖面標高981メートル。最大深度13メートル。湖畔は避暑・観光の好適地。
山中湖
撮影:山梨勝弘
⇒やま‐どり【山鳥】
やまどり‐たけ【山鳥茸】
担子菌類のきのこ。夏・秋に、主にブナ林中に生ずる。直径15センチメートル以上。全体に黄褐色。傘は饅頭笠まんじゅうがさ状で厚く、裏面は初め鮮黄色、のち黄褐色で、多数の細孔がある。美味で食用とする。従来、ヤマドリタケとされた菌は正しくはヤマドリタケモドキであると考えられる。
⇒やま‐どり【山鳥】
やまとんちゅ
(「大和の人」の意)沖縄語で、本土の人。↔うちなんちゅ
やまな【山名】
姓氏の一つ。新田氏の支族。室町幕府四職ししきの一家。
⇒やまな‐うじきよ【山名氏清】
⇒やまな‐そうぜん【山名宗全】
やま‐ない【止まない・已まない】
(動詞連用形にテを添えた形に続けて)いつまでも…する。大いに…する。「期待して―」
やまな‐うじきよ【山名氏清】‥ウヂ‥
南北朝時代の武将。陸奥守。足利義満に仕えて戦功をたて、和泉・丹波などの守護となるが、山名一族の強大化を恐れた義満の計略により反乱、敗北して討たれる(明徳の乱)。(1344〜1391)
⇒やまな【山名】
やま‐なか【山中】
山のなか。山間。さんちゅう。
やまなか【山中】
石川県加賀市、大聖寺川中流の黒谷川渓谷にある温泉地。加賀温泉郷の一つ。硫酸塩泉。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか‐ぬり【山中塗】
⇒やまなか‐ぶし【山中節】
やまなか【山中】
姓氏の一つ。
⇒やまなか‐さだお【山中貞雄】
⇒やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
⇒やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】
やまなか‐こ【山中湖】
富士五湖の一つ。山梨県南東部にあって、五湖の東端に位置する。面積は五湖中最大で、6.8平方キロメートル。湖面標高981メートル。最大深度13メートル。湖畔は避暑・観光の好適地。
山中湖
撮影:山梨勝弘
 やまなか‐さだお【山中貞雄】‥ヲ
映画監督・脚本家。京都生れ。作「丹下左膳余話 百万両の壺」「河内山宗俊」「人情紙風船」など。(1909〜1938)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
戦国時代の武将。名は幸盛ゆきもり。出雲の人。尼子義久に仕える。1566年(永禄9)義久が毛利氏に降ったので、尼子勝久を擁して戦ったが、のち播磨上月こうづき城で毛利方に攻められ、捕らえられて斬。( 〜1578)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぬり【山中塗】
石川県加賀市の山中温泉地区に産する漆器。天正(1573〜1592)年間に越前の挽物師が来て業を始めたという。糸目椀(千筋)などの挽物を主とし、溜塗ためぬりに優れる。
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぶし【山中節】
山中温泉を中心に歌われる民謡。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】‥ラウ
小説家・児童文学作家。本姓、馬淵。大阪府生れ。陸軍大学校卒。児童向けの軍事冒険小説で活躍。作「敵中横断三百里」など。(1885〜1966)
⇒やまなか【山中】
やま‐なし【山梨】
バラ科の落葉高木。西日本から中国大陸に分布。葉は卵形。5月頃、新枝の先に白花を開く。果実は秋に熟し、直径約2センチメートル、黄色または紅色で梨に似、外皮に小斑点が散在。〈[季]秋〉。源氏物語総角「かかる御すまひのかひなき、―の花ぞのがれん方なかりける」
やまなし【山梨】
①中部地方南東部、内陸の県。甲斐国を管轄。県庁所在地は甲府市。面積4465平方キロメートル。人口88万5千。全13市。
→えんこ節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山梨県中北部の市。笛吹川上流域にあり、ブドウ栽培が盛ん。人口3万9千。
⇒やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】
⇒やまなし‐だいがく【山梨大学】
やまなし【山梨】
姓氏の一つ。
⇒やまなし‐とうせん【山梨稲川】
やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】‥クワ‥
もと国立大学の一つ。1978年設立。2002年山梨大学に統合され、同大医学部となる。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐だいがく【山梨大学】
国立大学法人の一つ。1795年(寛政7)設立の甲府学問所徽典館を起源とする山梨師範学校、同青年師範、1924年(大正13)創立の山梨高等工業学校(のち山梨工専)が合併し、49年新制大学となる。2002年山梨医学大学を統合。04年法人化。本部は甲府市。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐とうせん【山梨稲川】‥タウ‥
江戸後期の漢学者・音韻学者。名は治憲。通称、東平。駿河の人。本居宣長らが古音を論ずるのに刺激されて「説文せつもん」を音韻的に研究した。著「文緯」「古声譜」「諧声図」「稲川文草」など。(1771〜1826)
⇒やまなし【山梨】
やまな‐そうぜん【山名宗全】
室町中期の武将。名は持豊。嘉吉かきつの乱に赤松満祐を討ち、その旧領を得て一族で山陰・山陽9カ国の守護職を併す。後に細川勝元と結託して畠山氏に当たったが、将軍義政の妻富子がその子義尚を託したことから、足利義視を擁する勝元と対抗し応仁の乱を起こした。西軍の主将。戦乱半ばにして陣中に没。(1404〜1473)
⇒やまな【山名】
やま‐なみ【山並・山脈】
山が並んでいること。また、そのさま。また、その山。連山。万葉集6「―のよろしき国と」
山並
撮影:関戸 勇
やまなか‐さだお【山中貞雄】‥ヲ
映画監督・脚本家。京都生れ。作「丹下左膳余話 百万両の壺」「河内山宗俊」「人情紙風船」など。(1909〜1938)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐しかのすけ【山中鹿介】
戦国時代の武将。名は幸盛ゆきもり。出雲の人。尼子義久に仕える。1566年(永禄9)義久が毛利氏に降ったので、尼子勝久を擁して戦ったが、のち播磨上月こうづき城で毛利方に攻められ、捕らえられて斬。( 〜1578)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぬり【山中塗】
石川県加賀市の山中温泉地区に産する漆器。天正(1573〜1592)年間に越前の挽物師が来て業を始めたという。糸目椀(千筋)などの挽物を主とし、溜塗ためぬりに優れる。
⇒やまなか【山中】
やまなか‐ぶし【山中節】
山中温泉を中心に歌われる民謡。
→山中節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
⇒やまなか【山中】
やまなか‐みねたろう【山中峯太郎】‥ラウ
小説家・児童文学作家。本姓、馬淵。大阪府生れ。陸軍大学校卒。児童向けの軍事冒険小説で活躍。作「敵中横断三百里」など。(1885〜1966)
⇒やまなか【山中】
やま‐なし【山梨】
バラ科の落葉高木。西日本から中国大陸に分布。葉は卵形。5月頃、新枝の先に白花を開く。果実は秋に熟し、直径約2センチメートル、黄色または紅色で梨に似、外皮に小斑点が散在。〈[季]秋〉。源氏物語総角「かかる御すまひのかひなき、―の花ぞのがれん方なかりける」
やまなし【山梨】
①中部地方南東部、内陸の県。甲斐国を管轄。県庁所在地は甲府市。面積4465平方キロメートル。人口88万5千。全13市。
→えんこ節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②山梨県中北部の市。笛吹川上流域にあり、ブドウ栽培が盛ん。人口3万9千。
⇒やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】
⇒やまなし‐だいがく【山梨大学】
やまなし【山梨】
姓氏の一つ。
⇒やまなし‐とうせん【山梨稲川】
やまなし‐いか‐だいがく【山梨医科大学】‥クワ‥
もと国立大学の一つ。1978年設立。2002年山梨大学に統合され、同大医学部となる。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐だいがく【山梨大学】
国立大学法人の一つ。1795年(寛政7)設立の甲府学問所徽典館を起源とする山梨師範学校、同青年師範、1924年(大正13)創立の山梨高等工業学校(のち山梨工専)が合併し、49年新制大学となる。2002年山梨医学大学を統合。04年法人化。本部は甲府市。
⇒やまなし【山梨】
やまなし‐とうせん【山梨稲川】‥タウ‥
江戸後期の漢学者・音韻学者。名は治憲。通称、東平。駿河の人。本居宣長らが古音を論ずるのに刺激されて「説文せつもん」を音韻的に研究した。著「文緯」「古声譜」「諧声図」「稲川文草」など。(1771〜1826)
⇒やまなし【山梨】
やまな‐そうぜん【山名宗全】
室町中期の武将。名は持豊。嘉吉かきつの乱に赤松満祐を討ち、その旧領を得て一族で山陰・山陽9カ国の守護職を併す。後に細川勝元と結託して畠山氏に当たったが、将軍義政の妻富子がその子義尚を託したことから、足利義視を擁する勝元と対抗し応仁の乱を起こした。西軍の主将。戦乱半ばにして陣中に没。(1404〜1473)
⇒やまな【山名】
やま‐なみ【山並・山脈】
山が並んでいること。また、そのさま。また、その山。連山。万葉集6「―のよろしき国と」
山並
撮影:関戸 勇
 やま‐ならし【山鳴らし】
〔植〕(風にゆれて葉が鳴るからいう)ハコヤナギの別称。
やま‐なり【山形】
山のような曲線をえがくこと。また、その形。「―の超スローボール」
やま‐なり【山鳴り】
山が鳴動すること。また、その音。
やま‐ならし【山鳴らし】
〔植〕(風にゆれて葉が鳴るからいう)ハコヤナギの別称。
やま‐なり【山形】
山のような曲線をえがくこと。また、その形。「―の超スローボール」
やま‐なり【山鳴り】
山が鳴動すること。また、その音。
○山に千年海に千年やまにせんねんうみにせんねん🔗⭐🔉
○山に千年海に千年やまにせんねんうみにせんねん
「海に千年山に千年」に同じ。→海千山千うみせんやません
⇒やま【山】
やま‐ぬけ【山抜け】
山腹の一部の土砂が時として崩れて落ちること。
やま‐ぬし【山主】
①山の所有主。山のあるじ。
②鉱山の経営者。山師。
やま‐ぬすびと【山盗人】
山賊。〈元和本下学集〉
やま‐ね【山鼠・冬眠鼠】
ネズミ目ヤマネ科の哺乳類。1属1種。体長約8センチメートル。毛色は褐色で、背に1条の黒線がある。四肢は短く、耳も小さい。北海道を除く各地の森林にすみ、冬眠する。日本特産で、天然記念物。
やまね
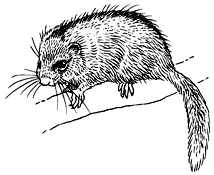 ヤマネ
提供:東京動物園協会
ヤマネ
提供:東京動物園協会
 やま‐ねこ【山猫】
①ネコ科のうち、小形の野生種の総称。ツシマヤマネコ・イリオモテヤマネコ・ヨーロッパヤマネコなど。
ツシマヤマネコ
提供:東京動物園協会
やま‐ねこ【山猫】
①ネコ科のうち、小形の野生種の総称。ツシマヤマネコ・イリオモテヤマネコ・ヨーロッパヤマネコなど。
ツシマヤマネコ
提供:東京動物園協会
 ②山野にすむ猫。野猫。
③江戸市中の寺社付近にいた淫売婦の称。
④京都東山の芸妓の異称。
(書名別項)
⇒やまねこ‐ざ【山猫座】
⇒やまねこ‐スト【山猫スト】
やまねこ【山猫】
(Il Gattopardo イタリア)イタリアの作家トマージ=ディ=ランペドゥーサ(Giuseppe Tomasi di Lampedusa1896〜1957)の小説。滅びゆくシチリア貴族の姿を描く。1958年刊。ヴィスコンティにより63年映画化。
やまねこ‐ざ【山猫座】
(Lynx ラテン)北天の星座。大熊座と馭者ぎょしゃ座の間にあり、輝星に乏しい。
⇒やま‐ねこ【山猫】
やまねこ‐スト【山猫スト】
(wildcat strike)労働組合員の一部が、指導部の承認を得ないで突発的あるいは散発的にストライキを行うこと。また、そのストライキ。
⇒やま‐ねこ【山猫】
②山野にすむ猫。野猫。
③江戸市中の寺社付近にいた淫売婦の称。
④京都東山の芸妓の異称。
(書名別項)
⇒やまねこ‐ざ【山猫座】
⇒やまねこ‐スト【山猫スト】
やまねこ【山猫】
(Il Gattopardo イタリア)イタリアの作家トマージ=ディ=ランペドゥーサ(Giuseppe Tomasi di Lampedusa1896〜1957)の小説。滅びゆくシチリア貴族の姿を描く。1958年刊。ヴィスコンティにより63年映画化。
やまねこ‐ざ【山猫座】
(Lynx ラテン)北天の星座。大熊座と馭者ぎょしゃ座の間にあり、輝星に乏しい。
⇒やま‐ねこ【山猫】
やまねこ‐スト【山猫スト】
(wildcat strike)労働組合員の一部が、指導部の承認を得ないで突発的あるいは散発的にストライキを行うこと。また、そのストライキ。
⇒やま‐ねこ【山猫】
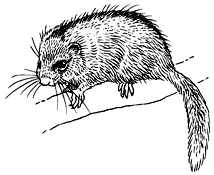 ヤマネ
提供:東京動物園協会
ヤマネ
提供:東京動物園協会
 やま‐ねこ【山猫】
①ネコ科のうち、小形の野生種の総称。ツシマヤマネコ・イリオモテヤマネコ・ヨーロッパヤマネコなど。
ツシマヤマネコ
提供:東京動物園協会
やま‐ねこ【山猫】
①ネコ科のうち、小形の野生種の総称。ツシマヤマネコ・イリオモテヤマネコ・ヨーロッパヤマネコなど。
ツシマヤマネコ
提供:東京動物園協会
 ②山野にすむ猫。野猫。
③江戸市中の寺社付近にいた淫売婦の称。
④京都東山の芸妓の異称。
(書名別項)
⇒やまねこ‐ざ【山猫座】
⇒やまねこ‐スト【山猫スト】
やまねこ【山猫】
(Il Gattopardo イタリア)イタリアの作家トマージ=ディ=ランペドゥーサ(Giuseppe Tomasi di Lampedusa1896〜1957)の小説。滅びゆくシチリア貴族の姿を描く。1958年刊。ヴィスコンティにより63年映画化。
やまねこ‐ざ【山猫座】
(Lynx ラテン)北天の星座。大熊座と馭者ぎょしゃ座の間にあり、輝星に乏しい。
⇒やま‐ねこ【山猫】
やまねこ‐スト【山猫スト】
(wildcat strike)労働組合員の一部が、指導部の承認を得ないで突発的あるいは散発的にストライキを行うこと。また、そのストライキ。
⇒やま‐ねこ【山猫】
②山野にすむ猫。野猫。
③江戸市中の寺社付近にいた淫売婦の称。
④京都東山の芸妓の異称。
(書名別項)
⇒やまねこ‐ざ【山猫座】
⇒やまねこ‐スト【山猫スト】
やまねこ【山猫】
(Il Gattopardo イタリア)イタリアの作家トマージ=ディ=ランペドゥーサ(Giuseppe Tomasi di Lampedusa1896〜1957)の小説。滅びゆくシチリア貴族の姿を描く。1958年刊。ヴィスコンティにより63年映画化。
やまねこ‐ざ【山猫座】
(Lynx ラテン)北天の星座。大熊座と馭者ぎょしゃ座の間にあり、輝星に乏しい。
⇒やま‐ねこ【山猫】
やまねこ‐スト【山猫スト】
(wildcat strike)労働組合員の一部が、指導部の承認を得ないで突発的あるいは散発的にストライキを行うこと。また、そのストライキ。
⇒やま‐ねこ【山猫】
やま‐の‐い【山の井】‥ヰ🔗⭐🔉
やま‐の‐い【山の井】‥ヰ
山の岩間などから水のわき出るところ。山の泉。やまい。万葉集16「安積山あさかやま影さへ見ゆる―の浅き心をわが思はなくに」
やま‐の‐いえ【山の家】‥イヘ🔗⭐🔉
やま‐の‐いえ【山の家】‥イヘ
避暑・登山・スキーなどの際の宿泊用に山や高原に建てられた家。
やま‐の‐いも【山芋・薯蕷】🔗⭐🔉
やま‐の‐いも【山芋・薯蕷】
ヤマノイモ科の蔓性多年草。日本各地の山野に自生。塊根は長い円柱形。茎は細長く左巻き。雌雄異株。葉は対生し長心臓形。夏、白色の小花を穂状につけ、3稜翼をもつ果実を結ぶ。「むかご」という珠芽を葉のつけ根に生じ、これでもふえる。塊根と「むかご」を食用。ジネンジョウ。ヤマイモ。ヤマツイモ。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔17〉
ヤマノイモ
撮影:関戸 勇
 ⇒やまのいも‐か【薯蕷科】
⇒山芋が鰻になる
⇒やまのいも‐か【薯蕷科】
⇒山芋が鰻になる
 ⇒やまのいも‐か【薯蕷科】
⇒山芋が鰻になる
⇒やまのいも‐か【薯蕷科】
⇒山芋が鰻になる
○山芋が鰻になるやまのいもがうなぎになる🔗⭐🔉
○山芋が鰻になるやまのいもがうなぎになる
物事が急に意外なものに変わることのたとえ。また、身分の低い者が急に成り上がることのたとえ。狂言、成上り「―とは定じょうぢやと申しましてござる」
⇒やま‐の‐いも【山芋・薯蕷】
やまのうえ【山上】‥ウヘ
姓氏の一つ。
⇒やまのうえ‐の‐おくら【山上憶良】
やまのうえ‐の‐おくら【山上憶良】‥ウヘ‥
万葉歌人。山上臣。702年(大宝2)遣唐録事として入唐、707年(慶雲4)頃帰国。従五位下・伯耆守・東宮侍講、後に筑前守。豊かな学識を有し、「子等を思ふ歌」「貧窮問答歌」など現実的な人生社会を詠じた切実・真率な作が多い。「類聚歌林」を編む。(660〜733頃)
→作品:『貧窮問答歌』[貧窮問答歌(山上憶良)]
⇒やまのうえ【山上】
やまのうち【山内】
(ヤマウチとも)姓氏の一つ。近世の大名。藤原秀郷の後裔首藤資清すどうすけきよの曾孫俊通が相州山内やまのうち荘を領したのに始まるという。
⇒やまのうち‐かずとよ【山内一豊】
⇒やまのうち‐すがお【山内清男】
⇒やまのうち‐ようどう【山内容堂】
やまのうち‐かずとよ【山内一豊】
安土桃山時代の武将。土佐藩祖。初め織田信長、後に豊臣秀吉に仕えた。秀吉没後、徳川家康に仕え、上杉征伐・関ヶ原の戦に功をたて、土佐に封。その妻は、信長の馬揃えのとき鏡匣かがみばこから黄金10両を出して一豊に名馬を買わせ、夫の立身の基を作ったという逸話で知られる。(1546〜1605)
⇒やまのうち【山内】
やまのうち‐すがお【山内清男】‥ヲ
考古学者。東京生れ。東大講師、成城大教授。縄文土器と縄文文化研究の基礎を確立。著「日本遠古之文化」「日本先史土器図譜」など。(1902〜1970)
⇒やまのうち【山内】
やまのうち‐ようどう【山内容堂】‥ダウ
幕末の土佐藩主。名は豊信とよしげ。分家の出。藩政を改革。公武合体に尽力、後藤象二郎の建策を容れて将軍徳川慶喜に大政奉還を建白。維新後、議定ぎじょう。酒を好み、鯨海酔侯と自称。(1827〜1872)
⇒やまのうち【山内】
やま‐の‐かみ【山の神】
①山を守り、山をつかさどる神。また、山の精。民間信仰では、秋の収穫後は近くの山に居り、春になると下って田の神となるという。法華経(竜光院本)平安後期点「魑ヤマノカミ魅さわのかみ」。今昔物語集27「さやうならむ歌などをば深き山中などにては詠うたふべからず。―の此れを聞きてめづる程に留むるなり」
②自分の妻の卑称。かかあ。狂言、花子「―が少しの間も離さぬに依て」
③〔動〕
㋐カジカ科の淡水産の硬骨魚。カジカに似る。全長約15センチメートル。有明海流入河川、朝鮮半島および中国に産。
㋑ミノカサゴ・カジカ類の魚の方言。→やまおこぜ。
⇒やまのかみ‐まつり【山の神祭】
やまのかみ‐まつり【山の神祭】
山に生業を持つ猟師・林業者・木地師などが山の神を崇め、仕事を休んで祭ること。〈[季]冬〉
⇒やま‐の‐かみ【山の神】
やま‐の‐くちあけ【山の口明け】
共有山野の草木・果実などの採取を解禁すること。禁止することを「山の鎌止め」という。
やま‐の‐かみ【山の神】🔗⭐🔉
やま‐の‐かみ【山の神】
①山を守り、山をつかさどる神。また、山の精。民間信仰では、秋の収穫後は近くの山に居り、春になると下って田の神となるという。法華経(竜光院本)平安後期点「魑ヤマノカミ魅さわのかみ」。今昔物語集27「さやうならむ歌などをば深き山中などにては詠うたふべからず。―の此れを聞きてめづる程に留むるなり」
②自分の妻の卑称。かかあ。狂言、花子「―が少しの間も離さぬに依て」
③〔動〕
㋐カジカ科の淡水産の硬骨魚。カジカに似る。全長約15センチメートル。有明海流入河川、朝鮮半島および中国に産。
㋑ミノカサゴ・カジカ類の魚の方言。→やまおこぜ。
⇒やまのかみ‐まつり【山の神祭】
やまのかみ‐まつり【山の神祭】🔗⭐🔉
やまのかみ‐まつり【山の神祭】
山に生業を持つ猟師・林業者・木地師などが山の神を崇め、仕事を休んで祭ること。〈[季]冬〉
⇒やま‐の‐かみ【山の神】
やま‐の‐くちあけ【山の口明け】🔗⭐🔉
やま‐の‐くちあけ【山の口明け】
共有山野の草木・果実などの採取を解禁すること。禁止することを「山の鎌止め」という。
○山のことは樵に聞けやまのことはきこりにきけ
何かを尋ねるには専門家が一番よいということ。
⇒やま【山】
○山のことは樵に聞けやまのことはきこりにきけ🔗⭐🔉
○山のことは樵に聞けやまのことはきこりにきけ
何かを尋ねるには専門家が一番よいということ。
⇒やま【山】
やまのこ‐まつり【山の講祭】
山の神の祭。中部山岳地方では初春・初冬の2度、信者が集団で祭る。
やま‐の‐さき【山の崎】
山の突き出たところ。尾根の先端。やまのはな。万葉集14「さ衣の小筑波嶺ろの―」
やま‐の‐さち【山の幸】
⇒やまさち2。↔海の幸
やま‐の‐しずく【山の雫】‥シヅク
山で、木などから落ちるしずく。万葉集2「吾立ちぬれぬ―に」
やま‐の‐すえ【山の末】‥スヱ
山の奥。山頂。
やまのだん【山の段】
浄瑠璃「妹背山婦女庭訓いもせやまおんなていきん」3段目後半の通称。歌舞伎では「吉野川」と通称。
→文献資料[妹背山婦女庭訓]
やま‐の‐つかさ【山の司】
①山の峰。頂上。
②山をつかさどる人。また、狩人。
やま‐の‐て【山の手】
①山に近い方。やまて。
②高台の土地。東京では文京・新宿区あたり一帯の高台地域の称。↔下町したまち。
⇒やまのて‐ことば【山の手言葉】
⇒やまのて‐せん【山手線】
⇒やまのて‐やっこ【山の手奴】
やまのて‐ことば【山の手言葉】
江戸時代、武家屋敷が並んだ江戸城北方から西方の台地で話された言葉。明治以降、学校教育の場で使われ、現代日本語の共通語の母体となる。→下町言葉。
⇒やま‐の‐て【山の手】
やまのて‐せん【山手線】
品川から新宿・池袋を経て田端に至るJR線。田端・東京・品川間も含めた環状電車線をもいう。1972年までは「やまてせん」と読んだ。
⇒やま‐の‐て【山の手】
やまのて‐やっこ【山の手奴】
江戸時代、江戸山の手の大名・旗本に仕えた奴。赤坂奴。
⇒やま‐の‐て【山の手】
やま‐の‐とね【山の刀祢】
(「刀祢」は山賊の長を戯れていう語)山賊のかしら。
やま‐の‐ねんぶつ【山の念仏】
旧暦8月11日から7日間、延暦寺常行三昧堂で行われた、節ふしをつけた念仏。9世紀中葉に円仁が中国五台山から伝えた。
やま‐の‐は【山の端】
山を遠くから眺めたときの稜線。また、そのすぐ下の部分。万葉集6「―にいさよふ月の出でむかと」
やま‐の‐はな【山の端・山の鼻】
山の尾根の突き出たところ。山の崎。やまばな。
やま‐の‐べ【山の辺】
(古くは清音)山のあたり。やまべ。万葉集10「―にい行く猟男さつおは多かれど」
やまのべ‐の‐みち【山辺の道】
奈良市から奈良盆地の東縁を初瀬はせ街道まで南北に通ずる約35キロメートルの古道。
山辺の道
撮影:的場 啓
 やま‐のぼり【山登り】
山に登ること。登山。
やま‐ば【山場】
物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」
やま‐はい【山廃】
日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」
やま‐ばかま【山袴】
仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。
山袴(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
やま‐のぼり【山登り】
山に登ること。登山。
やま‐ば【山場】
物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」
やま‐はい【山廃】
日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」
やま‐ばかま【山袴】
仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。
山袴(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 やま‐はぎ【山萩】
マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉
やまはぎ
やま‐はぎ【山萩】
マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉
やまはぎ
 やま‐はた【山畑】
山にある畑。山間の畑。↔野畑
やま‐はだ【山肌・山膚】
山の表面。
やま‐ばち【山蜂】
スズメバチの類の俗称。
やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥
シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。
やま‐ばと【山鳩】
山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。
⇒やまばと‐いろ【山鳩色】
やまばと‐いろ【山鳩色】
青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。
Munsell color system: 5GY5/1.5
⇒やま‐ばと【山鳩】
やま‐はね【山跳ね】
坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。
やまば‐はぐるま【山歯歯車】
ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)
やま‐ははこ【山母子】
キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。
やま‐ばん【山番】
山の番人。山守。
やま‐ばんし【山半紙】
武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」
やま‐はんのき【山榛】
カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。
やま‐び【山傍】
山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」
やま‐びこ【山彦】
①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」
②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」
やま‐ひだ【山襞】
山がひだのように波打って見えるところ。
やま‐びと【山人】
①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」
②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」
③仙人。〈日葡辞書〉
④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。
やま‐ひめ【山姫】
①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」
②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉
やま‐びらき【山開き】
①山をきりひらいて新たに路を設けること。
②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」
③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。
やま‐びる【山蛭】
顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉
やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ
アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。
やま‐ぶか・い【山深い】
〔形〕
山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」
やま‐ぶき【山吹・款冬】
①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」
ヤマブキ
撮影:関戸 勇
やま‐はた【山畑】
山にある畑。山間の畑。↔野畑
やま‐はだ【山肌・山膚】
山の表面。
やま‐ばち【山蜂】
スズメバチの類の俗称。
やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥
シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。
やま‐ばと【山鳩】
山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。
⇒やまばと‐いろ【山鳩色】
やまばと‐いろ【山鳩色】
青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。
Munsell color system: 5GY5/1.5
⇒やま‐ばと【山鳩】
やま‐はね【山跳ね】
坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。
やまば‐はぐるま【山歯歯車】
ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)
やま‐ははこ【山母子】
キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。
やま‐ばん【山番】
山の番人。山守。
やま‐ばんし【山半紙】
武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」
やま‐はんのき【山榛】
カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。
やま‐び【山傍】
山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」
やま‐びこ【山彦】
①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」
②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」
やま‐ひだ【山襞】
山がひだのように波打って見えるところ。
やま‐びと【山人】
①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」
②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」
③仙人。〈日葡辞書〉
④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。
やま‐ひめ【山姫】
①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」
②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉
やま‐びらき【山開き】
①山をきりひらいて新たに路を設けること。
②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」
③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。
やま‐びる【山蛭】
顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉
やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ
アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。
やま‐ぶか・い【山深い】
〔形〕
山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」
やま‐ぶき【山吹・款冬】
①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」
ヤマブキ
撮影:関戸 勇
 ②山吹色の略。
③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。
④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。
⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉
⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉
⇒やまぶき‐いろ【山吹色】
⇒やまぶき‐おり【山吹織】
⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】
⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
⇒やまぶき‐そう【山吹草】
⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】
⇒やまぶき‐におい【山吹匂】
やま‐ぶき【山蕗】
①山間に生える蕗。
②ツワブキの別称。
やまぶき‐いろ【山吹色】
①やや赤味のある黄色。こがねいろ。
Munsell color system: 10YR7.5/13
②大判・小判など、金貨の異称。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐おり【山吹織】
経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐がさね【山吹襲】
襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ
ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ
玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ
女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やま‐ふじ【山藤】‥フヂ
マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉
ヤマフジ
撮影:関戸 勇
②山吹色の略。
③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。
④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。
⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉
⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉
⇒やまぶき‐いろ【山吹色】
⇒やまぶき‐おり【山吹織】
⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】
⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
⇒やまぶき‐そう【山吹草】
⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】
⇒やまぶき‐におい【山吹匂】
やま‐ぶき【山蕗】
①山間に生える蕗。
②ツワブキの別称。
やまぶき‐いろ【山吹色】
①やや赤味のある黄色。こがねいろ。
Munsell color system: 10YR7.5/13
②大判・小判など、金貨の異称。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐おり【山吹織】
経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐がさね【山吹襲】
襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ
ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ
玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ
女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やま‐ふじ【山藤】‥フヂ
マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉
ヤマフジ
撮影:関戸 勇
 やま‐ぶし【山伏・山臥】
①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」
②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」
③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」
⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】
⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】
⇒やまぶし‐どう【山伏道】
やまぶし‐ごころ【山伏心】
山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐たけ【山伏茸】
担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ
修験道しゅげんどうの別称。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ
ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉
ヤマブドウ
撮影:関戸 勇
やま‐ぶし【山伏・山臥】
①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」
②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」
③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」
⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】
⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】
⇒やまぶし‐どう【山伏道】
やまぶし‐ごころ【山伏心】
山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐たけ【山伏茸】
担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ
修験道しゅげんどうの別称。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ
ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉
ヤマブドウ
撮影:関戸 勇
 ヤマブドウ(実)
撮影:関戸 勇
ヤマブドウ(実)
撮影:関戸 勇
 やま‐ふところ【山懐】
山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」
やま‐ふふき【槖吾】
ツワブキの古名。〈本草和名〉
やま‐ぶみ【山踏み】
山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」
やまべ
(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉
やま‐べ【山辺】
(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」
やま‐べ【山部】
大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」
やまべ【山部】
姓氏の一つ。
⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。
⇒やまべ【山部】
やま‐へん【山偏】
漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。
やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥
比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師
やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥
(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。
ヤマボウシ(実)
撮影:関戸 勇
やま‐ふところ【山懐】
山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」
やま‐ふふき【槖吾】
ツワブキの古名。〈本草和名〉
やま‐ぶみ【山踏み】
山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」
やまべ
(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉
やま‐べ【山辺】
(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」
やま‐べ【山部】
大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」
やまべ【山部】
姓氏の一つ。
⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。
⇒やまべ【山部】
やま‐へん【山偏】
漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。
やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥
比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師
やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥
(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。
ヤマボウシ(実)
撮影:関戸 勇
 ヤマボウシ(花)
撮影:関戸 勇
ヤマボウシ(花)
撮影:関戸 勇
 やま‐ぼくち【山火口】
キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。
やま‐ぼこ【山鉾】
山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉
やま‐ほど【山程】
積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」
やま‐ほととぎす【山杜鵑】
①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」
②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。
ヤマホトトギス
撮影:関戸 勇
やま‐ぼくち【山火口】
キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。
やま‐ぼこ【山鉾】
山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉
やま‐ほど【山程】
積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」
やま‐ほととぎす【山杜鵑】
①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」
②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。
ヤマホトトギス
撮影:関戸 勇
 やま‐ほめ【山誉め】
正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。
やま‐ま【山間】
山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」
やま‐まく【山幕】
歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。
やま‐まつ【山松】
山に生えている松。野生の松。
やま‐まつり【山祭】
山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。
やま‐まど【山窓】
①山家やまがのまど。さんそう。
②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉
やま‐まゆ【山眉】
山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)
やま‐まゆ【山繭・天蚕】
ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉
ヤママユ(繭)
撮影:海野和男
やま‐ほめ【山誉め】
正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。
やま‐ま【山間】
山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」
やま‐まく【山幕】
歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。
やま‐まつ【山松】
山に生えている松。野生の松。
やま‐まつり【山祭】
山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。
やま‐まど【山窓】
①山家やまがのまど。さんそう。
②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉
やま‐まゆ【山眉】
山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)
やま‐まゆ【山繭・天蚕】
ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉
ヤママユ(繭)
撮影:海野和男
 ⇒やままゆ‐いと【山繭糸】
⇒やままゆ‐おり【山繭織】
⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
やままゆ‐いと【山繭糸】
山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐おり【山繭織】
山繭糸を交ぜて織った織物。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
山繭糸を用いて織った紬。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ
(→)「山酔い」に同じ。
やま‐み【山見】
①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。
②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。
やま‐みず【山水】‥ミヅ
①山と水。
②山から出る水。
③山と水との見える景色。
やま‐みち【山道】
①山中の道。やまじ。
②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。
③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」
やま‐むけ【山向け】
神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。
やま‐むすめ【山娘】
スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。
やまむら【山村】
姓氏の一つ。
⇒やまむら‐ざ【山村座】
⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】
⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】
⇒やまむら‐りゅう【山村流】
やまむら‐ざ【山村座】
歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。
⇒やまむら【山村】
やまむら‐さいすけ【山村才助】
江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ
詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ
上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。
⇒やまむら【山村】
やまむろ【山室】
姓氏の一つ。
⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)
⇒やまむろ【山室】
やま‐め【鰥・寡】
(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」
やま‐め【山女】
サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。
やまめ
⇒やままゆ‐いと【山繭糸】
⇒やままゆ‐おり【山繭織】
⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
やままゆ‐いと【山繭糸】
山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐おり【山繭織】
山繭糸を交ぜて織った織物。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
山繭糸を用いて織った紬。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ
(→)「山酔い」に同じ。
やま‐み【山見】
①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。
②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。
やま‐みず【山水】‥ミヅ
①山と水。
②山から出る水。
③山と水との見える景色。
やま‐みち【山道】
①山中の道。やまじ。
②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。
③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」
やま‐むけ【山向け】
神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。
やま‐むすめ【山娘】
スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。
やまむら【山村】
姓氏の一つ。
⇒やまむら‐ざ【山村座】
⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】
⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】
⇒やまむら‐りゅう【山村流】
やまむら‐ざ【山村座】
歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。
⇒やまむら【山村】
やまむら‐さいすけ【山村才助】
江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ
詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ
上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。
⇒やまむら【山村】
やまむろ【山室】
姓氏の一つ。
⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)
⇒やまむろ【山室】
やま‐め【鰥・寡】
(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」
やま‐め【山女】
サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。
やまめ
 ヤマメ
提供:東京動物園協会
ヤマメ
提供:東京動物園協会
 やま‐め【水蠆】
〔動〕(→)「やご」の別称。
やま‐めぐり【山巡り・山回り】
①山々をめぐること。
②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」
やま‐もえ【山燃え】
山に火災の起こること。山火事。
やま‐もがし【山もがし】
ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。
やま‐もち【山持ち】
山または鉱山を所有すること。また、その人。
やま‐もと【山下・山本・山元】
①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」
②(「山元」と書く)
㋐山の持主。また、鉱山の経営者。
㋑山や鉱山・炭坑のある所。
やまもと【山本】
姓氏の一つ。
⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】
⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】
⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】
⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】
⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】
⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】
⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】
⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】
⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】
⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】
⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】
⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】
⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】
⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】
⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】
⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】
⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】
⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】
⇒やまもと‐やすえ【山本安英】
⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】
⇒やまもと‐りょう【山本亮】
やまもと‐いそろく【山本五十六】
軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)
山本五十六
提供:毎日新聞社
やま‐め【水蠆】
〔動〕(→)「やご」の別称。
やま‐めぐり【山巡り・山回り】
①山々をめぐること。
②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」
やま‐もえ【山燃え】
山に火災の起こること。山火事。
やま‐もがし【山もがし】
ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。
やま‐もち【山持ち】
山または鉱山を所有すること。また、その人。
やま‐もと【山下・山本・山元】
①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」
②(「山元」と書く)
㋐山の持主。また、鉱山の経営者。
㋑山や鉱山・炭坑のある所。
やまもと【山本】
姓氏の一つ。
⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】
⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】
⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】
⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】
⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】
⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】
⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】
⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】
⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】
⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】
⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】
⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】
⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】
⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】
⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】
⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】
⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】
⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】
⇒やまもと‐やすえ【山本安英】
⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】
⇒やまもと‐りょう【山本亮】
やまもと‐いそろく【山本五十六】
軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)
山本五十六
提供:毎日新聞社
 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐かけい【山本荷兮】
江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)
→作品抜粋(阿羅野)
→抜粋:『春の日』
→抜粋:『冬の日』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ
映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ
洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かんすけ【山本勘助】
戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥
日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)
山本丘人
撮影:田沼武能
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かけい【山本荷兮】
江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)
→作品抜粋(阿羅野)
→抜粋:『春の日』
→抜粋:『冬の日』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ
映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ
洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かんすけ【山本勘助】
戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥
日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)
山本丘人
撮影:田沼武能
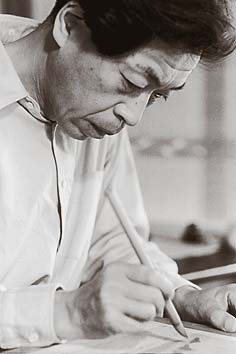 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐けんきち【山本健吉】
文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)
山本健吉
撮影:田沼武能
⇒やまもと【山本】
やまもと‐けんきち【山本健吉】
文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)
山本健吉
撮影:田沼武能
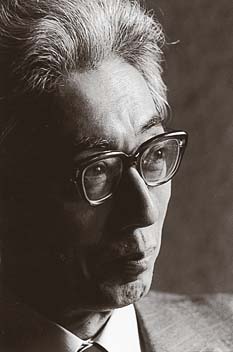 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ
軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)
山本権兵衛
提供:毎日新聞社
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ
軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)
山本権兵衛
提供:毎日新聞社
 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ
映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)
山本薩夫
撮影:田村 茂
⇒やまもと【山本】
やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ
映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)
山本薩夫
撮影:田村 茂
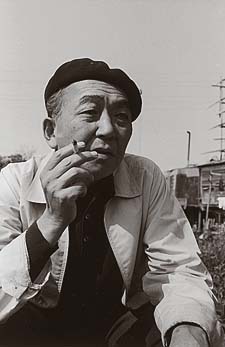 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐さねひこ【山本実彦】
出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ
小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)
山本周五郎
撮影:林 忠彦
⇒やまもと【山本】
やまもと‐さねひこ【山本実彦】
出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ
小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)
山本周五郎
撮影:林 忠彦
 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ
生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ
東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ
(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ
狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。
①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)
②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とよいち【山本豊市】
彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐は【山元派】
浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。
やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥
洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ほくざん【山本北山】
江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐やすえ【山本安英】
新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ
小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)
山本有三
撮影:田沼武能
⇒やまもと【山本】
やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ
生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ
東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ
(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ
狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。
①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)
②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とよいち【山本豊市】
彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐は【山元派】
浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。
やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥
洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ほくざん【山本北山】
江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐やすえ【山本安英】
新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ
小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)
山本有三
撮影:田沼武能
 →作品:『路傍の石』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ
農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)
⇒やまもと【山本】
やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ
カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。
やま‐もも【山桃】
ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉
やまもも
→作品:『路傍の石』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ
農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)
⇒やまもと【山本】
やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ
カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。
やま‐もも【山桃】
ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉
やまもも
 ヤマモモ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
ヤマモモ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 やま‐もり【山守】
山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり
やま‐もり【山盛り】
山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」
やま‐やき【山焼き】
春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉
やま‐やく【山役】
「山年貢やまねんぐ」参照。
やま‐やけ【山焼け】
山が焼けること。山火事。
やまや‐どうふ【山屋豆腐】
江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」
やま‐やま【山山】
①あの山この山。多くの山。
②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」
③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」
④せいぜい。限度。「5000円が―だ」
やまやま‐いり【山山入】
「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。
やま‐ゆき【山雪】
日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。
やま‐ゆり【山百合】
ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉
ヤマユリ
撮影:関戸 勇
やま‐もり【山守】
山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり
やま‐もり【山盛り】
山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」
やま‐やき【山焼き】
春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉
やま‐やく【山役】
「山年貢やまねんぐ」参照。
やま‐やけ【山焼け】
山が焼けること。山火事。
やまや‐どうふ【山屋豆腐】
江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」
やま‐やま【山山】
①あの山この山。多くの山。
②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」
③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」
④せいぜい。限度。「5000円が―だ」
やまやま‐いり【山山入】
「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。
やま‐ゆき【山雪】
日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。
やま‐ゆり【山百合】
ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉
ヤマユリ
撮影:関戸 勇
 やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ
高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。
やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ
高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。
 やま‐のぼり【山登り】
山に登ること。登山。
やま‐ば【山場】
物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」
やま‐はい【山廃】
日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」
やま‐ばかま【山袴】
仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。
山袴(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
やま‐のぼり【山登り】
山に登ること。登山。
やま‐ば【山場】
物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」
やま‐はい【山廃】
日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」
やま‐ばかま【山袴】
仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。
山袴(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 やま‐はぎ【山萩】
マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉
やまはぎ
やま‐はぎ【山萩】
マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉
やまはぎ
 やま‐はた【山畑】
山にある畑。山間の畑。↔野畑
やま‐はだ【山肌・山膚】
山の表面。
やま‐ばち【山蜂】
スズメバチの類の俗称。
やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥
シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。
やま‐ばと【山鳩】
山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。
⇒やまばと‐いろ【山鳩色】
やまばと‐いろ【山鳩色】
青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。
Munsell color system: 5GY5/1.5
⇒やま‐ばと【山鳩】
やま‐はね【山跳ね】
坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。
やまば‐はぐるま【山歯歯車】
ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)
やま‐ははこ【山母子】
キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。
やま‐ばん【山番】
山の番人。山守。
やま‐ばんし【山半紙】
武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」
やま‐はんのき【山榛】
カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。
やま‐び【山傍】
山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」
やま‐びこ【山彦】
①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」
②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」
やま‐ひだ【山襞】
山がひだのように波打って見えるところ。
やま‐びと【山人】
①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」
②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」
③仙人。〈日葡辞書〉
④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。
やま‐ひめ【山姫】
①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」
②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉
やま‐びらき【山開き】
①山をきりひらいて新たに路を設けること。
②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」
③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。
やま‐びる【山蛭】
顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉
やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ
アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。
やま‐ぶか・い【山深い】
〔形〕
山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」
やま‐ぶき【山吹・款冬】
①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」
ヤマブキ
撮影:関戸 勇
やま‐はた【山畑】
山にある畑。山間の畑。↔野畑
やま‐はだ【山肌・山膚】
山の表面。
やま‐ばち【山蜂】
スズメバチの類の俗称。
やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥
シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。
やま‐ばと【山鳩】
山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。
⇒やまばと‐いろ【山鳩色】
やまばと‐いろ【山鳩色】
青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。
Munsell color system: 5GY5/1.5
⇒やま‐ばと【山鳩】
やま‐はね【山跳ね】
坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。
やまば‐はぐるま【山歯歯車】
ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)
やま‐ははこ【山母子】
キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。
やま‐ばん【山番】
山の番人。山守。
やま‐ばんし【山半紙】
武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」
やま‐はんのき【山榛】
カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。
やま‐び【山傍】
山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」
やま‐びこ【山彦】
①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」
②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」
やま‐ひだ【山襞】
山がひだのように波打って見えるところ。
やま‐びと【山人】
①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」
②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」
③仙人。〈日葡辞書〉
④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。
やま‐ひめ【山姫】
①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」
②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉
やま‐びらき【山開き】
①山をきりひらいて新たに路を設けること。
②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」
③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。
やま‐びる【山蛭】
顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉
やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ
アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。
やま‐ぶか・い【山深い】
〔形〕
山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」
やま‐ぶき【山吹・款冬】
①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」
ヤマブキ
撮影:関戸 勇
 ②山吹色の略。
③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。
④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。
⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉
⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉
⇒やまぶき‐いろ【山吹色】
⇒やまぶき‐おり【山吹織】
⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】
⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
⇒やまぶき‐そう【山吹草】
⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】
⇒やまぶき‐におい【山吹匂】
やま‐ぶき【山蕗】
①山間に生える蕗。
②ツワブキの別称。
やまぶき‐いろ【山吹色】
①やや赤味のある黄色。こがねいろ。
Munsell color system: 10YR7.5/13
②大判・小判など、金貨の異称。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐おり【山吹織】
経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐がさね【山吹襲】
襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ
ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ
玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ
女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やま‐ふじ【山藤】‥フヂ
マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉
ヤマフジ
撮影:関戸 勇
②山吹色の略。
③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。
④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。
⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉
⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉
⇒やまぶき‐いろ【山吹色】
⇒やまぶき‐おり【山吹織】
⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】
⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
⇒やまぶき‐そう【山吹草】
⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】
⇒やまぶき‐におい【山吹匂】
やま‐ぶき【山蕗】
①山間に生える蕗。
②ツワブキの別称。
やまぶき‐いろ【山吹色】
①やや赤味のある黄色。こがねいろ。
Munsell color system: 10YR7.5/13
②大判・小判など、金貨の異称。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐おり【山吹織】
経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐がさね【山吹襲】
襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐しょうま【山吹升麻】
バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ
ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ
玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ
女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。
⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】
やま‐ふじ【山藤】‥フヂ
マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉
ヤマフジ
撮影:関戸 勇
 やま‐ぶし【山伏・山臥】
①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」
②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」
③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」
⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】
⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】
⇒やまぶし‐どう【山伏道】
やまぶし‐ごころ【山伏心】
山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐たけ【山伏茸】
担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ
修験道しゅげんどうの別称。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ
ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉
ヤマブドウ
撮影:関戸 勇
やま‐ぶし【山伏・山臥】
①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」
②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」
③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」
⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】
⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】
⇒やまぶし‐どう【山伏道】
やまぶし‐ごころ【山伏心】
山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐たけ【山伏茸】
担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ
修験道しゅげんどうの別称。
⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】
やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ
ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉
ヤマブドウ
撮影:関戸 勇
 ヤマブドウ(実)
撮影:関戸 勇
ヤマブドウ(実)
撮影:関戸 勇
 やま‐ふところ【山懐】
山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」
やま‐ふふき【槖吾】
ツワブキの古名。〈本草和名〉
やま‐ぶみ【山踏み】
山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」
やまべ
(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉
やま‐べ【山辺】
(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」
やま‐べ【山部】
大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」
やまべ【山部】
姓氏の一つ。
⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。
⇒やまべ【山部】
やま‐へん【山偏】
漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。
やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥
比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師
やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥
(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。
ヤマボウシ(実)
撮影:関戸 勇
やま‐ふところ【山懐】
山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」
やま‐ふふき【槖吾】
ツワブキの古名。〈本草和名〉
やま‐ぶみ【山踏み】
山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」
やまべ
(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉
やま‐べ【山辺】
(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」
やま‐べ【山部】
大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」
やまべ【山部】
姓氏の一つ。
⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】
奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。
⇒やまべ【山部】
やま‐へん【山偏】
漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。
やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥
比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師
やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥
(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。
ヤマボウシ(実)
撮影:関戸 勇
 ヤマボウシ(花)
撮影:関戸 勇
ヤマボウシ(花)
撮影:関戸 勇
 やま‐ぼくち【山火口】
キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。
やま‐ぼこ【山鉾】
山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉
やま‐ほど【山程】
積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」
やま‐ほととぎす【山杜鵑】
①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」
②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。
ヤマホトトギス
撮影:関戸 勇
やま‐ぼくち【山火口】
キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。
やま‐ぼこ【山鉾】
山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉
やま‐ほど【山程】
積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」
やま‐ほととぎす【山杜鵑】
①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」
②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。
ヤマホトトギス
撮影:関戸 勇
 やま‐ほめ【山誉め】
正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。
やま‐ま【山間】
山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」
やま‐まく【山幕】
歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。
やま‐まつ【山松】
山に生えている松。野生の松。
やま‐まつり【山祭】
山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。
やま‐まど【山窓】
①山家やまがのまど。さんそう。
②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉
やま‐まゆ【山眉】
山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)
やま‐まゆ【山繭・天蚕】
ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉
ヤママユ(繭)
撮影:海野和男
やま‐ほめ【山誉め】
正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。
やま‐ま【山間】
山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」
やま‐まく【山幕】
歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。
やま‐まつ【山松】
山に生えている松。野生の松。
やま‐まつり【山祭】
山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。
やま‐まど【山窓】
①山家やまがのまど。さんそう。
②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉
やま‐まゆ【山眉】
山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)
やま‐まゆ【山繭・天蚕】
ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉
ヤママユ(繭)
撮影:海野和男
 ⇒やままゆ‐いと【山繭糸】
⇒やままゆ‐おり【山繭織】
⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
やままゆ‐いと【山繭糸】
山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐おり【山繭織】
山繭糸を交ぜて織った織物。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
山繭糸を用いて織った紬。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ
(→)「山酔い」に同じ。
やま‐み【山見】
①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。
②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。
やま‐みず【山水】‥ミヅ
①山と水。
②山から出る水。
③山と水との見える景色。
やま‐みち【山道】
①山中の道。やまじ。
②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。
③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」
やま‐むけ【山向け】
神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。
やま‐むすめ【山娘】
スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。
やまむら【山村】
姓氏の一つ。
⇒やまむら‐ざ【山村座】
⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】
⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】
⇒やまむら‐りゅう【山村流】
やまむら‐ざ【山村座】
歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。
⇒やまむら【山村】
やまむら‐さいすけ【山村才助】
江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ
詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ
上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。
⇒やまむら【山村】
やまむろ【山室】
姓氏の一つ。
⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)
⇒やまむろ【山室】
やま‐め【鰥・寡】
(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」
やま‐め【山女】
サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。
やまめ
⇒やままゆ‐いと【山繭糸】
⇒やままゆ‐おり【山繭織】
⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
やままゆ‐いと【山繭糸】
山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐おり【山繭織】
山繭糸を交ぜて織った織物。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やままゆ‐つむぎ【山繭紬】
山繭糸を用いて織った紬。
⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】
やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ
(→)「山酔い」に同じ。
やま‐み【山見】
①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。
②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。
やま‐みず【山水】‥ミヅ
①山と水。
②山から出る水。
③山と水との見える景色。
やま‐みち【山道】
①山中の道。やまじ。
②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。
③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」
やま‐むけ【山向け】
神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。
やま‐むすめ【山娘】
スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。
やまむら【山村】
姓氏の一つ。
⇒やまむら‐ざ【山村座】
⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】
⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】
⇒やまむら‐りゅう【山村流】
やまむら‐ざ【山村座】
歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。
⇒やまむら【山村】
やまむら‐さいすけ【山村才助】
江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ
詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)
⇒やまむら【山村】
やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ
上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。
⇒やまむら【山村】
やまむろ【山室】
姓氏の一つ。
⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】
宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)
⇒やまむろ【山室】
やま‐め【鰥・寡】
(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」
やま‐め【山女】
サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。
やまめ
 ヤマメ
提供:東京動物園協会
ヤマメ
提供:東京動物園協会
 やま‐め【水蠆】
〔動〕(→)「やご」の別称。
やま‐めぐり【山巡り・山回り】
①山々をめぐること。
②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」
やま‐もえ【山燃え】
山に火災の起こること。山火事。
やま‐もがし【山もがし】
ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。
やま‐もち【山持ち】
山または鉱山を所有すること。また、その人。
やま‐もと【山下・山本・山元】
①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」
②(「山元」と書く)
㋐山の持主。また、鉱山の経営者。
㋑山や鉱山・炭坑のある所。
やまもと【山本】
姓氏の一つ。
⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】
⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】
⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】
⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】
⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】
⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】
⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】
⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】
⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】
⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】
⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】
⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】
⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】
⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】
⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】
⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】
⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】
⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】
⇒やまもと‐やすえ【山本安英】
⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】
⇒やまもと‐りょう【山本亮】
やまもと‐いそろく【山本五十六】
軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)
山本五十六
提供:毎日新聞社
やま‐め【水蠆】
〔動〕(→)「やご」の別称。
やま‐めぐり【山巡り・山回り】
①山々をめぐること。
②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」
やま‐もえ【山燃え】
山に火災の起こること。山火事。
やま‐もがし【山もがし】
ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。
やま‐もち【山持ち】
山または鉱山を所有すること。また、その人。
やま‐もと【山下・山本・山元】
①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」
②(「山元」と書く)
㋐山の持主。また、鉱山の経営者。
㋑山や鉱山・炭坑のある所。
やまもと【山本】
姓氏の一つ。
⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】
⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】
⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】
⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】
⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】
⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】
⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】
⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】
⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】
⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】
⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】
⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】
⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】
⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】
⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】
⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】
⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】
⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】
⇒やまもと‐やすえ【山本安英】
⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】
⇒やまもと‐りょう【山本亮】
やまもと‐いそろく【山本五十六】
軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)
山本五十六
提供:毎日新聞社
 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐かけい【山本荷兮】
江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)
→作品抜粋(阿羅野)
→抜粋:『春の日』
→抜粋:『冬の日』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ
映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ
洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かんすけ【山本勘助】
戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥
日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)
山本丘人
撮影:田沼武能
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かけい【山本荷兮】
江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)
→作品抜粋(阿羅野)
→抜粋:『春の日』
→抜粋:『冬の日』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ
映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ
洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐かんすけ【山本勘助】
戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥
日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)
山本丘人
撮影:田沼武能
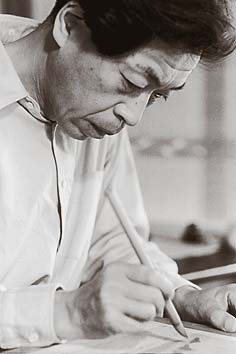 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐けんきち【山本健吉】
文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)
山本健吉
撮影:田沼武能
⇒やまもと【山本】
やまもと‐けんきち【山本健吉】
文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)
山本健吉
撮影:田沼武能
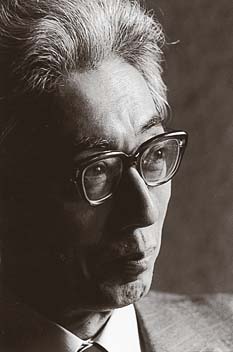 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ
軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)
山本権兵衛
提供:毎日新聞社
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ
軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)
山本権兵衛
提供:毎日新聞社
 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ
映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)
山本薩夫
撮影:田村 茂
⇒やまもと【山本】
やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ
映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)
山本薩夫
撮影:田村 茂
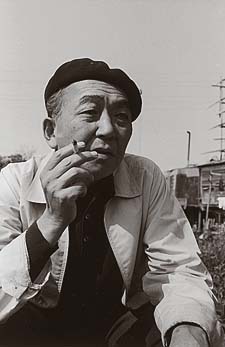 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐さねひこ【山本実彦】
出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ
小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)
山本周五郎
撮影:林 忠彦
⇒やまもと【山本】
やまもと‐さねひこ【山本実彦】
出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ
小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)
山本周五郎
撮影:林 忠彦
 ⇒やまもと【山本】
やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ
生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ
東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ
(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ
狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。
①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)
②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とよいち【山本豊市】
彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐は【山元派】
浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。
やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥
洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ほくざん【山本北山】
江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐やすえ【山本安英】
新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ
小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)
山本有三
撮影:田沼武能
⇒やまもと【山本】
やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ
生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】
社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ
東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ
(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ
狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。
①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)
②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐とよいち【山本豊市】
彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐は【山元派】
浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。
やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥
洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ほくざん【山本北山】
江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐やすえ【山本安英】
新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)
⇒やまもと【山本】
やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ
小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)
山本有三
撮影:田沼武能
 →作品:『路傍の石』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ
農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)
⇒やまもと【山本】
やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ
カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。
やま‐もも【山桃】
ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉
やまもも
→作品:『路傍の石』
⇒やまもと【山本】
やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ
農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)
⇒やまもと【山本】
やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ
カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。
やま‐もも【山桃】
ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉
やまもも
 ヤマモモ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
ヤマモモ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 やま‐もり【山守】
山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり
やま‐もり【山盛り】
山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」
やま‐やき【山焼き】
春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉
やま‐やく【山役】
「山年貢やまねんぐ」参照。
やま‐やけ【山焼け】
山が焼けること。山火事。
やまや‐どうふ【山屋豆腐】
江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」
やま‐やま【山山】
①あの山この山。多くの山。
②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」
③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」
④せいぜい。限度。「5000円が―だ」
やまやま‐いり【山山入】
「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。
やま‐ゆき【山雪】
日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。
やま‐ゆり【山百合】
ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉
ヤマユリ
撮影:関戸 勇
やま‐もり【山守】
山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり
やま‐もり【山盛り】
山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」
やま‐やき【山焼き】
春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉
やま‐やく【山役】
「山年貢やまねんぐ」参照。
やま‐やけ【山焼け】
山が焼けること。山火事。
やまや‐どうふ【山屋豆腐】
江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」
やま‐やま【山山】
①あの山この山。多くの山。
②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」
③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」
④せいぜい。限度。「5000円が―だ」
やまやま‐いり【山山入】
「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。
やま‐ゆき【山雪】
日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。
やま‐ゆり【山百合】
ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉
ヤマユリ
撮影:関戸 勇
 やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ
高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。
やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ
高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。
やまのこ‐まつり【山の講祭】🔗⭐🔉
やまのこ‐まつり【山の講祭】
山の神の祭。中部山岳地方では初春・初冬の2度、信者が集団で祭る。
やま‐の‐さき【山の崎】🔗⭐🔉
やま‐の‐さき【山の崎】
山の突き出たところ。尾根の先端。やまのはな。万葉集14「さ衣の小筑波嶺ろの―」
やま‐の‐さち【山の幸】🔗⭐🔉
やま‐の‐さち【山の幸】
⇒やまさち2。↔海の幸
やま‐の‐しずく【山の雫】‥シヅク🔗⭐🔉
やま‐の‐しずく【山の雫】‥シヅク
山で、木などから落ちるしずく。万葉集2「吾立ちぬれぬ―に」
やま‐の‐すえ【山の末】‥スヱ🔗⭐🔉
やま‐の‐すえ【山の末】‥スヱ
山の奥。山頂。
やまのだん【山の段】🔗⭐🔉
やまのだん【山の段】
浄瑠璃「妹背山婦女庭訓いもせやまおんなていきん」3段目後半の通称。歌舞伎では「吉野川」と通称。
→文献資料[妹背山婦女庭訓]
やま‐の‐つかさ【山の司】🔗⭐🔉
やま‐の‐つかさ【山の司】
①山の峰。頂上。
②山をつかさどる人。また、狩人。
やま‐の‐て【山の手】🔗⭐🔉
やま‐の‐て【山の手】
①山に近い方。やまて。
②高台の土地。東京では文京・新宿区あたり一帯の高台地域の称。↔下町したまち。
⇒やまのて‐ことば【山の手言葉】
⇒やまのて‐せん【山手線】
⇒やまのて‐やっこ【山の手奴】
やまのて‐ことば【山の手言葉】🔗⭐🔉
やまのて‐ことば【山の手言葉】
江戸時代、武家屋敷が並んだ江戸城北方から西方の台地で話された言葉。明治以降、学校教育の場で使われ、現代日本語の共通語の母体となる。→下町言葉。
⇒やま‐の‐て【山の手】
やまのて‐やっこ【山の手奴】🔗⭐🔉
やまのて‐やっこ【山の手奴】
江戸時代、江戸山の手の大名・旗本に仕えた奴。赤坂奴。
⇒やま‐の‐て【山の手】
やま‐の‐とね【山の刀祢】🔗⭐🔉
やま‐の‐とね【山の刀祢】
(「刀祢」は山賊の長を戯れていう語)山賊のかしら。
やま‐の‐ねんぶつ【山の念仏】🔗⭐🔉
やま‐の‐ねんぶつ【山の念仏】
旧暦8月11日から7日間、延暦寺常行三昧堂で行われた、節ふしをつけた念仏。9世紀中葉に円仁が中国五台山から伝えた。
やま‐の‐は【山の端】🔗⭐🔉
やま‐の‐は【山の端】
山を遠くから眺めたときの稜線。また、そのすぐ下の部分。万葉集6「―にいさよふ月の出でむかと」
やま‐の‐はな【山の端・山の鼻】🔗⭐🔉
やま‐の‐はな【山の端・山の鼻】
山の尾根の突き出たところ。山の崎。やまばな。
やま‐の‐べ【山の辺】🔗⭐🔉
やま‐の‐べ【山の辺】
(古くは清音)山のあたり。やまべ。万葉集10「―にい行く猟男さつおは多かれど」
やま‐もがし【山もがし】🔗⭐🔉
やま‐もがし【山もがし】
ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。
やま‐やま【山山】🔗⭐🔉
やま‐やま【山山】
①あの山この山。多くの山。
②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」
③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」
④せいぜい。限度。「5000円が―だ」
やまやま‐いり【山山入】🔗⭐🔉
やまやま‐いり【山山入】
「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。
○山を当てるやまをあてる🔗⭐🔉
○山を当てるやまをあてる
鉱脈を掘り当てる。転じて、少ない可能性のものをうまく当てる。
⇒やま【山】
○山を鋳、海を煮るやまをいうみをにる🔗⭐🔉
○山を鋳、海を煮るやまをいうみをにる
[史記呉王濞伝](「山を鋳る」は山から金銅を採掘して金属を鋳る、「海を煮る」は海水を煮て塩を得る意)国中に物産の豊富なことをいう。
⇒やま【山】
○山を掛けるやまをかける🔗⭐🔉
○山を掛けるやまをかける
万一の僥倖ぎょうこうを望んで事をする。試験などで、受験者が問題に出そうな箇所を推定することなどにもいう。山を張る。
⇒やま【山】
○山をなすやまをなす🔗⭐🔉
○山をなすやまをなす
山のような形をなす。うずたかく積みあげられている。たくさんたまっている。山積する。「未解決の問題が山をなしている」
⇒やま【山】
○山を抜く力やまをぬくちから🔗⭐🔉
○山を抜く力やまをぬくちから
[史記項羽本紀「力は山を抜き気は世を蓋おおう」]山を抜き通すほどの強大な力。抜山蓋世ばつざんがいせい。
⇒やま【山】
○山を張るやまをはる🔗⭐🔉
○山を張るやまをはる
(→)「山を掛ける」に同じ。
⇒やま【山】
やまんば【山姥】
⇒やまうば
やまんば【山姥】
(ヤマウバの音便)
①能。世阿弥作。山姥の曲舞くせまいを歌って有名となった百ま山姥という都の遊女が、善光寺に詣でる途次、山中で山姥に逢う。
山姥
撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)
 ②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
やみ【止み】
やむこと。とまり。終止。「雨―」「小―」
やみ【病み】
病むこと。やまい。病気。また、その病人。「目―」「―あがり」
やみ【闇】
①暗いこと。くらやみ。光のないこと。万葉集4「照らす日を―に見なして」。「無明の―」
②夜の暗いこと。夜陰。万葉集8「―ならば宜うべも来まさじ梅の花咲ける月夜つくよに」
③思慮・分別のないこと。心が乱れて迷うこと。後撰和歌集雑「人の親の心は―にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな」。「心の―」
④字が読めないこと。文盲。醒睡笑「其の余の文字は―なる男」
⑤世が乱れて治まらないことのたとえ。
⑥先の見通しがつかないこと、絶望的であることのたとえ。「一寸先は―」
⑦(陰暦の30日は闇夜であるところから)3、30、300など、3のつく値段を表す符丁。江戸時代の馬子や駕籠舁かごかきが用いた。→闇半。
⑧世人の目にふれないところ。世間の目をはばかること。「―に葬る」
⑨㋐闇相場やみそうばの略。
㋑闇取引やみとりひきの略。「米を―で買う」「―商人」
⇒闇から牛を引き出す
⇒闇から闇に葬る
⇒闇に烏
⇒闇に暮れる
⇒闇に咲く花
⇒闇に惑う
や‐み【矢見】
的矢まとやの当りの状態を調査する人。
やみ‐あがり【病み上り】
病後まだ体力が十分に回復しないこと。また、その時、その人。病気あがり。「―の体で無理がきかない」
やみ‐あきない【闇商い】‥アキナヒ
闇取引でする商売。
やみ‐あげく【病み挙句】
病後であること。また、その時期。やみあがり。
やみ‐いち【闇市】
闇取引の品物を売る店が集まっているところ。闇市場。ブラック‐マーケット。
やみ‐うち【闇討】
①暗闇にまぎれて人を不意に討つこと。暗夜に乗じて人を討ち取ること。平家物語1「今夜―にせられ給べき由承り候あひだ」
②不意を襲うこと。「―を食わせる」
やみ‐かえし【病み返し】‥カヘシ
いったん快方に向かった病気がまた悪くなること。ぶりかえし。
やみ‐かえ・る【病み返る】‥カヘル
〔自四〕
病気が再発する。ぶり返す。〈日葡辞書〉
やみ‐がすり【闇絣】
黒地に小さい乱れ絣を織り込んだ木綿絣。
やみ‐がた【止み方】
①止もうとすること。また、止む頃。「雨の―」
②病気がなおりかけること。また、回復期。
やみ‐がた・い【止み難い】
〔形〕[文]やみがた・し(ク)
感情などを、抑えることがむずかしい。「―・い悲しみ」
②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
やみ【止み】
やむこと。とまり。終止。「雨―」「小―」
やみ【病み】
病むこと。やまい。病気。また、その病人。「目―」「―あがり」
やみ【闇】
①暗いこと。くらやみ。光のないこと。万葉集4「照らす日を―に見なして」。「無明の―」
②夜の暗いこと。夜陰。万葉集8「―ならば宜うべも来まさじ梅の花咲ける月夜つくよに」
③思慮・分別のないこと。心が乱れて迷うこと。後撰和歌集雑「人の親の心は―にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな」。「心の―」
④字が読めないこと。文盲。醒睡笑「其の余の文字は―なる男」
⑤世が乱れて治まらないことのたとえ。
⑥先の見通しがつかないこと、絶望的であることのたとえ。「一寸先は―」
⑦(陰暦の30日は闇夜であるところから)3、30、300など、3のつく値段を表す符丁。江戸時代の馬子や駕籠舁かごかきが用いた。→闇半。
⑧世人の目にふれないところ。世間の目をはばかること。「―に葬る」
⑨㋐闇相場やみそうばの略。
㋑闇取引やみとりひきの略。「米を―で買う」「―商人」
⇒闇から牛を引き出す
⇒闇から闇に葬る
⇒闇に烏
⇒闇に暮れる
⇒闇に咲く花
⇒闇に惑う
や‐み【矢見】
的矢まとやの当りの状態を調査する人。
やみ‐あがり【病み上り】
病後まだ体力が十分に回復しないこと。また、その時、その人。病気あがり。「―の体で無理がきかない」
やみ‐あきない【闇商い】‥アキナヒ
闇取引でする商売。
やみ‐あげく【病み挙句】
病後であること。また、その時期。やみあがり。
やみ‐いち【闇市】
闇取引の品物を売る店が集まっているところ。闇市場。ブラック‐マーケット。
やみ‐うち【闇討】
①暗闇にまぎれて人を不意に討つこと。暗夜に乗じて人を討ち取ること。平家物語1「今夜―にせられ給べき由承り候あひだ」
②不意を襲うこと。「―を食わせる」
やみ‐かえし【病み返し】‥カヘシ
いったん快方に向かった病気がまた悪くなること。ぶりかえし。
やみ‐かえ・る【病み返る】‥カヘル
〔自四〕
病気が再発する。ぶり返す。〈日葡辞書〉
やみ‐がすり【闇絣】
黒地に小さい乱れ絣を織り込んだ木綿絣。
やみ‐がた【止み方】
①止もうとすること。また、止む頃。「雨の―」
②病気がなおりかけること。また、回復期。
やみ‐がた・い【止み難い】
〔形〕[文]やみがた・し(ク)
感情などを、抑えることがむずかしい。「―・い悲しみ」
 ②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
やみ【止み】
やむこと。とまり。終止。「雨―」「小―」
やみ【病み】
病むこと。やまい。病気。また、その病人。「目―」「―あがり」
やみ【闇】
①暗いこと。くらやみ。光のないこと。万葉集4「照らす日を―に見なして」。「無明の―」
②夜の暗いこと。夜陰。万葉集8「―ならば宜うべも来まさじ梅の花咲ける月夜つくよに」
③思慮・分別のないこと。心が乱れて迷うこと。後撰和歌集雑「人の親の心は―にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな」。「心の―」
④字が読めないこと。文盲。醒睡笑「其の余の文字は―なる男」
⑤世が乱れて治まらないことのたとえ。
⑥先の見通しがつかないこと、絶望的であることのたとえ。「一寸先は―」
⑦(陰暦の30日は闇夜であるところから)3、30、300など、3のつく値段を表す符丁。江戸時代の馬子や駕籠舁かごかきが用いた。→闇半。
⑧世人の目にふれないところ。世間の目をはばかること。「―に葬る」
⑨㋐闇相場やみそうばの略。
㋑闇取引やみとりひきの略。「米を―で買う」「―商人」
⇒闇から牛を引き出す
⇒闇から闇に葬る
⇒闇に烏
⇒闇に暮れる
⇒闇に咲く花
⇒闇に惑う
や‐み【矢見】
的矢まとやの当りの状態を調査する人。
やみ‐あがり【病み上り】
病後まだ体力が十分に回復しないこと。また、その時、その人。病気あがり。「―の体で無理がきかない」
やみ‐あきない【闇商い】‥アキナヒ
闇取引でする商売。
やみ‐あげく【病み挙句】
病後であること。また、その時期。やみあがり。
やみ‐いち【闇市】
闇取引の品物を売る店が集まっているところ。闇市場。ブラック‐マーケット。
やみ‐うち【闇討】
①暗闇にまぎれて人を不意に討つこと。暗夜に乗じて人を討ち取ること。平家物語1「今夜―にせられ給べき由承り候あひだ」
②不意を襲うこと。「―を食わせる」
やみ‐かえし【病み返し】‥カヘシ
いったん快方に向かった病気がまた悪くなること。ぶりかえし。
やみ‐かえ・る【病み返る】‥カヘル
〔自四〕
病気が再発する。ぶり返す。〈日葡辞書〉
やみ‐がすり【闇絣】
黒地に小さい乱れ絣を織り込んだ木綿絣。
やみ‐がた【止み方】
①止もうとすること。また、止む頃。「雨の―」
②病気がなおりかけること。また、回復期。
やみ‐がた・い【止み難い】
〔形〕[文]やみがた・し(ク)
感情などを、抑えることがむずかしい。「―・い悲しみ」
②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
やみ【止み】
やむこと。とまり。終止。「雨―」「小―」
やみ【病み】
病むこと。やまい。病気。また、その病人。「目―」「―あがり」
やみ【闇】
①暗いこと。くらやみ。光のないこと。万葉集4「照らす日を―に見なして」。「無明の―」
②夜の暗いこと。夜陰。万葉集8「―ならば宜うべも来まさじ梅の花咲ける月夜つくよに」
③思慮・分別のないこと。心が乱れて迷うこと。後撰和歌集雑「人の親の心は―にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな」。「心の―」
④字が読めないこと。文盲。醒睡笑「其の余の文字は―なる男」
⑤世が乱れて治まらないことのたとえ。
⑥先の見通しがつかないこと、絶望的であることのたとえ。「一寸先は―」
⑦(陰暦の30日は闇夜であるところから)3、30、300など、3のつく値段を表す符丁。江戸時代の馬子や駕籠舁かごかきが用いた。→闇半。
⑧世人の目にふれないところ。世間の目をはばかること。「―に葬る」
⑨㋐闇相場やみそうばの略。
㋑闇取引やみとりひきの略。「米を―で買う」「―商人」
⇒闇から牛を引き出す
⇒闇から闇に葬る
⇒闇に烏
⇒闇に暮れる
⇒闇に咲く花
⇒闇に惑う
や‐み【矢見】
的矢まとやの当りの状態を調査する人。
やみ‐あがり【病み上り】
病後まだ体力が十分に回復しないこと。また、その時、その人。病気あがり。「―の体で無理がきかない」
やみ‐あきない【闇商い】‥アキナヒ
闇取引でする商売。
やみ‐あげく【病み挙句】
病後であること。また、その時期。やみあがり。
やみ‐いち【闇市】
闇取引の品物を売る店が集まっているところ。闇市場。ブラック‐マーケット。
やみ‐うち【闇討】
①暗闇にまぎれて人を不意に討つこと。暗夜に乗じて人を討ち取ること。平家物語1「今夜―にせられ給べき由承り候あひだ」
②不意を襲うこと。「―を食わせる」
やみ‐かえし【病み返し】‥カヘシ
いったん快方に向かった病気がまた悪くなること。ぶりかえし。
やみ‐かえ・る【病み返る】‥カヘル
〔自四〕
病気が再発する。ぶり返す。〈日葡辞書〉
やみ‐がすり【闇絣】
黒地に小さい乱れ絣を織り込んだ木綿絣。
やみ‐がた【止み方】
①止もうとすること。また、止む頃。「雨の―」
②病気がなおりかけること。また、回復期。
やみ‐がた・い【止み難い】
〔形〕[文]やみがた・し(ク)
感情などを、抑えることがむずかしい。「―・い悲しみ」
やまんば【山姥】(作品名)🔗⭐🔉
やまんば【山姥】
(ヤマウバの音便)
①能。世阿弥作。山姥の曲舞くせまいを歌って有名となった百ま山姥という都の遊女が、善光寺に詣でる途次、山中で山姥に逢う。
山姥
撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)
 ②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
 ②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
②1に関連する邦楽曲。地歌。沢野九郎兵衛作曲、紀海音作詞。常磐津節。初世鳥羽屋里長作曲、初世瀬川如皐作詞。「古山姥」とも。富本節・清元節など。
わさび【山葵】🔗⭐🔉
わさび【山葵】
アブラナ科の多年草。日本原産で、渓流のほとりに自生し、また多く流水地に栽培する。地下茎は肥厚した円柱状で、葉柄とともに強い辛味を有し、根出葉は心臓形、春に白色4弁の小花を開く。根を香辛料、また、葉と共にわさび漬とする。〈[季]春〉。〈本草和名〉
わさび
 山葵田(安曇野)
撮影:佐藤 尚
山葵田(安曇野)
撮影:佐藤 尚
 ⇒わさび‐おろし【山葵卸し】
⇒わさび‐じょうゆ【山葵醤油】
⇒わさび‐すまし【山葵清汁】
⇒わさび‐だいこん【山葵大根】
⇒わさび‐づけ【山葵漬】
⇒わさび‐の‐き【山葵の木】
⇒わさび‐もち【山葵餅】
⇒山葵を利かす
⇒わさび‐おろし【山葵卸し】
⇒わさび‐じょうゆ【山葵醤油】
⇒わさび‐すまし【山葵清汁】
⇒わさび‐だいこん【山葵大根】
⇒わさび‐づけ【山葵漬】
⇒わさび‐の‐き【山葵の木】
⇒わさび‐もち【山葵餅】
⇒山葵を利かす
 山葵田(安曇野)
撮影:佐藤 尚
山葵田(安曇野)
撮影:佐藤 尚
 ⇒わさび‐おろし【山葵卸し】
⇒わさび‐じょうゆ【山葵醤油】
⇒わさび‐すまし【山葵清汁】
⇒わさび‐だいこん【山葵大根】
⇒わさび‐づけ【山葵漬】
⇒わさび‐の‐き【山葵の木】
⇒わさび‐もち【山葵餅】
⇒山葵を利かす
⇒わさび‐おろし【山葵卸し】
⇒わさび‐じょうゆ【山葵醤油】
⇒わさび‐すまし【山葵清汁】
⇒わさび‐だいこん【山葵大根】
⇒わさび‐づけ【山葵漬】
⇒わさび‐の‐き【山葵の木】
⇒わさび‐もち【山葵餅】
⇒山葵を利かす
わさび‐おろし【山葵卸し】🔗⭐🔉
わさび‐おろし【山葵卸し】
①金属製・陶製またはサメの皮製の、小突起の目があって山葵・生薑しょうがなどをすりおろす道具。また、それですりおろした山葵。
②(その履いている袴のさまざまの菖蒲革しょうぶがわの模様が1に似ていたので)若党・中間ちゅうげんの異称。
⇒わさび【山葵】
わさび‐じょうゆ【山葵醤油】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
わさび‐じょうゆ【山葵醤油】‥ジヤウ‥
山葵をすりおろして加えた醤油。刺身などを食べる際に用いる。
⇒わさび【山葵】
わさび‐すまし【山葵清汁】🔗⭐🔉
わさび‐すまし【山葵清汁】
清まし汁の中に山葵の絞り汁を加えた料理。
⇒わさび【山葵】
わさび‐だいこん【山葵大根】🔗⭐🔉
わさび‐だいこん【山葵大根】
アブラナ科の多年生根菜。ヨーロッパ原産とされ、栽培は新しい。日本には明治初めに導入。根は太くて長く、芳香・辛味を有し、香辛料・健胃剤とする。西洋わさび。ホース‐ラディッシュ。
⇒わさび【山葵】
わさび‐づけ【山葵漬】🔗⭐🔉
わさび‐づけ【山葵漬】
山葵の葉・根・茎を細かに刻んで塩漬けにし、砂糖などを加えて練った酒粕に漬けた食品。静岡の名産。〈[季]春〉
⇒わさび【山葵】
わさび‐の‐き【山葵の木】🔗⭐🔉
わさび‐の‐き【山葵の木】
ワサビノキ科の落葉小高木。インド原産。葉は大きく3回羽状複葉。花は蝶形花に似て白色。果実は棒状で長さ30〜60センチメートル。若葉・花および未熟の莢さやを食用。全体に辛味があり、根は山葵の代用。樹皮の分泌物からトラガカント‐ゴムを作る。種子から採る油(モリンガ油)は最高級の時計用油とされる。
⇒わさび【山葵】
わさび‐もち【山葵餅】🔗⭐🔉
○山葵を利かすわさびをきかす🔗⭐🔉
○山葵を利かすわさびをきかす
①山葵の辛い味が十分にあらわれるようにする。
②ぴりっと引きしまったものを感じさせる言動をする。さびを利かす。
⇒わさび【山葵】
わさ‐ほ【早稲穂】
早稲わせの穂。万葉集8「秋の田の―のかづら見れど飽かぬかも」
わざ‐まえ【業前】‥マヘ
うでまえ。てなみ。技量。
わさ‐みの【早稲蓑】
早稲わせのわらを編んでつくった蓑。堀河百首恋「真菅よき笠のかりでの―を」
わさ‐もの【早物】
米麦・野菜などの、季節に先だって出るもの。はしりもの。〈日葡辞書〉
わざ‐もの【業物】
①名工が鍛えた、切れ味のよい刀剣。わざよし。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「只一刀に大の男、七つに切つたる―」
②なすべきわざの多い曲。風姿花伝「木樵・汐汲の―などの翁形をしよせぬれば」
わざ‐よし【業良し】
切れ味のよいこと。また、その刀剣。業物わざもの。狂言、入間川「重代―でもない物を、これもそなたへ進ずるでもおりないぞ」
わざわい【禍・災い】ワザハヒ
(ワザは鬼神のなす業わざ、ハヒはその状さまをあらわす)傷害・疾病・天変地異・難儀などをこうむること。悪いできごと。不幸なできごと。まがごと。災難。法華経(竜光院本)平安後期点「其の殃ワザハヒに罹かからむ」。「―を招く」「口は―の門」
⇒禍も三年
⇒禍を転じて福となす
わざわい・する【災いする】ワザハヒ‥
〔自サ変〕[文]わざはひ・す(サ変)
悪い結果をもたらす。「才気が―・した」
[漢]山🔗⭐🔉
山 字形
 筆順
筆順
 〔山部0画/3画/教育/2719・3B33〕
〔音〕サン(漢) セン(呉)
〔訓〕やま
[意味]
①地表の高くもり上がっている所。やま。「山河・山地・山積・深山・火山・登山・須弥山しゅみせん」
②寺院の名に添える語。「山号・比叡ひえい山延暦寺・金竜山浅草寺」。寺院。「開山・山門」
[解字]
解字
〔山部0画/3画/教育/2719・3B33〕
〔音〕サン(漢) セン(呉)
〔訓〕やま
[意味]
①地表の高くもり上がっている所。やま。「山河・山地・山積・深山・火山・登山・須弥山しゅみせん」
②寺院の名に添える語。「山号・比叡ひえい山延暦寺・金竜山浅草寺」。寺院。「開山・山門」
[解字]
解字 解字
解字 やまの形を描いた象形文字。
[下ツキ
叡山・遠山・開山・火山・帰山・仰山・金山・銀山・群山・下山・剣山・鉱山・高山・故山・五山・深山・青山・千山万岳・大山・泰山・太山・沢山・他山・治山・鉄山・天王山・天目山・当山・銅山・登山・抜山蓋世・氷山・巫山・本山・満山・名山・遊山・霊山・連山
[難読]
山梔子くちなし・山茶花さざんか・山樝子さんざし・山査子さんざし・山車だし・山毛欅ぶな・山羊やぎ・山賤やまがつ・山雀やまがら・山祇やまつみ・山女魚やまめ・山葵わさび
やまの形を描いた象形文字。
[下ツキ
叡山・遠山・開山・火山・帰山・仰山・金山・銀山・群山・下山・剣山・鉱山・高山・故山・五山・深山・青山・千山万岳・大山・泰山・太山・沢山・他山・治山・鉄山・天王山・天目山・当山・銅山・登山・抜山蓋世・氷山・巫山・本山・満山・名山・遊山・霊山・連山
[難読]
山梔子くちなし・山茶花さざんか・山樝子さんざし・山査子さんざし・山車だし・山毛欅ぶな・山羊やぎ・山賤やまがつ・山雀やまがら・山祇やまつみ・山女魚やまめ・山葵わさび
 筆順
筆順
 〔山部0画/3画/教育/2719・3B33〕
〔音〕サン(漢) セン(呉)
〔訓〕やま
[意味]
①地表の高くもり上がっている所。やま。「山河・山地・山積・深山・火山・登山・須弥山しゅみせん」
②寺院の名に添える語。「山号・比叡ひえい山延暦寺・金竜山浅草寺」。寺院。「開山・山門」
[解字]
解字
〔山部0画/3画/教育/2719・3B33〕
〔音〕サン(漢) セン(呉)
〔訓〕やま
[意味]
①地表の高くもり上がっている所。やま。「山河・山地・山積・深山・火山・登山・須弥山しゅみせん」
②寺院の名に添える語。「山号・比叡ひえい山延暦寺・金竜山浅草寺」。寺院。「開山・山門」
[解字]
解字 解字
解字 やまの形を描いた象形文字。
[下ツキ
叡山・遠山・開山・火山・帰山・仰山・金山・銀山・群山・下山・剣山・鉱山・高山・故山・五山・深山・青山・千山万岳・大山・泰山・太山・沢山・他山・治山・鉄山・天王山・天目山・当山・銅山・登山・抜山蓋世・氷山・巫山・本山・満山・名山・遊山・霊山・連山
[難読]
山梔子くちなし・山茶花さざんか・山樝子さんざし・山査子さんざし・山車だし・山毛欅ぶな・山羊やぎ・山賤やまがつ・山雀やまがら・山祇やまつみ・山女魚やまめ・山葵わさび
やまの形を描いた象形文字。
[下ツキ
叡山・遠山・開山・火山・帰山・仰山・金山・銀山・群山・下山・剣山・鉱山・高山・故山・五山・深山・青山・千山万岳・大山・泰山・太山・沢山・他山・治山・鉄山・天王山・天目山・当山・銅山・登山・抜山蓋世・氷山・巫山・本山・満山・名山・遊山・霊山・連山
[難読]
山梔子くちなし・山茶花さざんか・山樝子さんざし・山査子さんざし・山車だし・山毛欅ぶな・山羊やぎ・山賤やまがつ・山雀やまがら・山祇やまつみ・山女魚やまめ・山葵わさび
広辞苑に「山」で始まるの検索結果 1-84。もっと読み込む