複数辞典一括検索+![]()
![]()
な【名】🔗⭐🔉
な【名】
➊有形・無形の事物を、他の事物と区別して、言語で表した呼び方。
①事物(の概念)を代表する呼称。万葉集3「酒の―を聖とおほせし」。「花の―」
②特に人や人に準ずるものに付けた呼び名。姓・氏など家名に対して実名・通称など個人名を指し、また姓氏と併せたものをも指す。万葉集2「妹が―呼びて袖そ振りつる」。宇津保物語俊蔭「―をば仲忠といふ」。「無礼者、―を言え」「会社の―」
③実質が伴わないただの名目。万葉集15「家島は―にこそありけれ」。「春とは―ばかりの今日この頃」
④その事を言い立てて口実とするところのもの。「正義の―のもとに兵を動かす」
➋人・家の名に伴う聞え。
①上古、家に世襲の職業や人の業績について負った名称。万葉集20「大伴の氏と―に負へるますらをの伴」
②他人の口にのぼって、立つ評判。うわさ。万葉集11「妹が―もわが―も立たば惜しみこそ」。「―のある詩人」「―が立つ」
③名誉。「男の―が立たない」
➌名によって表された、人倫上の分際。名分。
➍「名残なごりの折」の略。
⇒名有り
⇒名有りて実無し
⇒名が売れる
⇒名が通る
⇒名に負う
⇒名に聞く
⇒名にし負う
⇒名に背く
⇒名に立つ
⇒名に流る
⇒名に旧る
⇒名の無い星は宵から出る
⇒名は実の賓
⇒名は体を表す
⇒名もない
⇒名を揚げる
⇒名を埋む
⇒名を売る
⇒名を得る
⇒名を惜しむ
⇒名を折る
⇒名を借りる
⇒名を腐す
⇒名を汚す
⇒名を沈む
⇒名を雪ぐ
⇒名を捨てて実を取る
⇒名を正す
⇒名を立てる
⇒名を保つ
⇒名を竹帛に垂る
⇒名を散らす
⇒名を釣る
⇒名を遂げる
⇒名を留める
⇒名を取る
⇒名を流す
⇒名を成す
⇒名を偸む
⇒名を残す
⇒名を辱める
⇒名を馳せる
⇒名を振るう
な‐あて【名宛】🔗⭐🔉
な‐あて【名宛】
①名前をあげて遊女などを指定すること。名ざし。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「輪留井思庵わるいしあんが―にて、浮名を揚げ詰めに」
②手紙などで、指定した人の名。あてな。
⇒なあて‐にん【名宛人】
なあて‐にん【名宛人】🔗⭐🔉
なあて‐にん【名宛人】
①書類や荷物の受取人に指定された人。
②証券などで、特定人を指定して作成された場合に、その指定された人。約束手形の受取人の類。
⇒な‐あて【名宛】
な‐うて【名うて】🔗⭐🔉
な‐うて【名うて】
名高いこと。評判の高いこと。名代なだい。浮世風呂4「おちやつぴいと―の子もり」
○名が売れるながうれる🔗⭐🔉
○名が売れるながうれる
名前が世間に広く知られるようになる。有名になる。「作曲家として―」
⇒な【名】
なかえ【中江】
姓氏の一つ。
⇒なかえ‐うしきち【中江丑吉】
⇒なかえ‐ちょうみん【中江兆民】
⇒なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】
なか‐え【中重】‥ヘ
(→)中陪なかべに同じ。
な‐がえ【名替】‥ガヘ
年給(年官・年爵)で諸国の掾じょう・目さかんなどに任命された人が、赴任を望まない旨を申請した時、その任国に他人を改めて任ずること。
なが‐え【轅】
(長柄の意)牛車ぎっしゃ・馬車などの前に長く平行に出した2本の棒。その前端に軛くびきを渡し、牛馬に引かせる。→牛車(図)
なが‐え【長柄】
柄の長い道具または武具。長道具。
⇒ながえ‐がたな【長柄刀】
⇒ながえ‐ぐみ【長柄組】
⇒ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】
⇒ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】
⇒ながえ‐の‐ま【長柄の間】
⇒ながえ‐の‐やり【長柄の槍】
⇒ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】
⇒ながえ‐ぶね【長柄船】
⇒ながえ‐もち【長柄持】
なかえ‐うしきち【中江丑吉】
中国学者。兆民の長男。大阪生れ。東大卒。北京に在住30年。主著「中国古代政治思想」「公羊伝くようでんの研究」。(1889〜1942)
⇒なかえ【中江】
ながえ‐がたな【長柄刀】
両手で握って使用するために柄を長くした刀。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぐみ【長柄組】
武家の職名。戦時に長柄の槍を持って出陣した騎馬あるいは徒歩の一隊。道具衆。
⇒なが‐え【長柄】
なかえ‐ちょうみん【中江兆民】‥テウ‥
思想家。名は篤介。土佐の人。1871年(明治4)渡仏、帰国後仏学塾を開き民権論を提唱、自由党の創設に参画、同党機関紙「自由新聞」の主筆。第1回総選挙に代議士当選。ルソー「民約論」、ヴェロン「維氏美学」を翻訳。著「一年有半」「続一年有半」「三酔人経綸問答」など。(1847〜1901)
中江兆民
提供:毎日新聞社
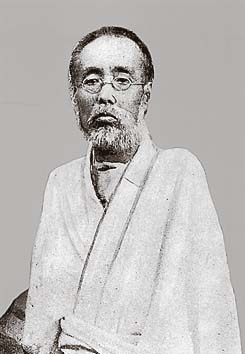 →資料:『三酔人経綸問答』
⇒なかえ【中江】
なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】
江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)
→著作:『翁問答』
⇒なかえ【中江】
ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】
馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥
柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ま【長柄の間】
槍・長刀などを飾りつけて置く室。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐やり【長柄の槍】
長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ
槍奉行。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶね【長柄船】
長柄組の乗る船。
⇒なが‐え【長柄】
なが‐えぼし【長烏帽子】
立烏帽子の丈の長いもの。
ながえ‐もち【長柄持】
長柄の傘を持って従う者。
⇒なが‐え【長柄】
なかお【中尾】‥ヲ
姓氏の一つ。
⇒なかお‐とざん【中尾都山】
なか‐お【中緒】‥ヲ
①中ほどについている緒・紐。
②(→)「中の緒」に同じ。
③茶入の袋につける緒。
ながお【長尾】‥ヲ
姓氏の一つ。上杉氏の家宰。
⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】
なが‐おい【長追い】‥オヒ
逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。
なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥
牛の貸借の仲介人。
なかおか【中岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】
ながおか【長岡】‥ヲカ
新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。
⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】
ながおか【長岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】
ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥
国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。
⇒ながおか【長岡】
ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ
①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。
②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。
ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥
上杉謙信の初名。
⇒ながお【長尾】
なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ
幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)
中岡慎太郎
提供:毎日新聞社
→資料:『三酔人経綸問答』
⇒なかえ【中江】
なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】
江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)
→著作:『翁問答』
⇒なかえ【中江】
ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】
馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥
柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ま【長柄の間】
槍・長刀などを飾りつけて置く室。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐やり【長柄の槍】
長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ
槍奉行。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶね【長柄船】
長柄組の乗る船。
⇒なが‐え【長柄】
なが‐えぼし【長烏帽子】
立烏帽子の丈の長いもの。
ながえ‐もち【長柄持】
長柄の傘を持って従う者。
⇒なが‐え【長柄】
なかお【中尾】‥ヲ
姓氏の一つ。
⇒なかお‐とざん【中尾都山】
なか‐お【中緒】‥ヲ
①中ほどについている緒・紐。
②(→)「中の緒」に同じ。
③茶入の袋につける緒。
ながお【長尾】‥ヲ
姓氏の一つ。上杉氏の家宰。
⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】
なが‐おい【長追い】‥オヒ
逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。
なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥
牛の貸借の仲介人。
なかおか【中岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】
ながおか【長岡】‥ヲカ
新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。
⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】
ながおか【長岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】
ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥
国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。
⇒ながおか【長岡】
ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ
①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。
②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。
ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥
上杉謙信の初名。
⇒ながお【長尾】
なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ
幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)
中岡慎太郎
提供:毎日新聞社
 ⇒なかおか【中岡】
ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ
物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)
長岡半太郎
撮影:田村 茂
⇒なかおか【中岡】
ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ
物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)
長岡半太郎
撮影:田村 茂
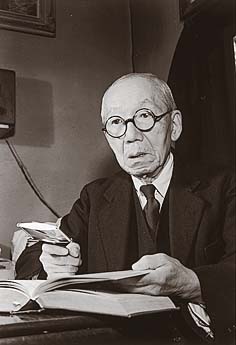 ⇒ながおか【長岡】
なが‐おき【長起き】
夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」
なか‐おく【中奥】
江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく
なか‐おし【中押】
(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)
⇒ちゅうおし
なか‐おち【中落ち】
魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。
なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥
(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)
⇒なかお【中尾】
ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥
⇒ちょうびけい
なか‐おび【中帯】
上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。
なか‐おもて【中表】
布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」
なか‐おり【中折り】‥ヲリ
①中ほどから折ること。
②中折紙の略。
⇒なかおり‐がみ【中折紙】
なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥
①紙の真ん中を二つに折ったもの。
②半紙の一種。鼻紙などに用いる。
③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙
⇒なか‐おり【中折り】
なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ
①中央で折れかえり、また、くぼむこと。
②「中折れ下駄」の略。
③「中折れ帽子」の略。
⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】
⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】
なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥
台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。
中折れ下駄
⇒ながおか【長岡】
なが‐おき【長起き】
夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」
なか‐おく【中奥】
江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく
なか‐おし【中押】
(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)
⇒ちゅうおし
なか‐おち【中落ち】
魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。
なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥
(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)
⇒なかお【中尾】
ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥
⇒ちょうびけい
なか‐おび【中帯】
上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。
なか‐おもて【中表】
布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」
なか‐おり【中折り】‥ヲリ
①中ほどから折ること。
②中折紙の略。
⇒なかおり‐がみ【中折紙】
なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥
①紙の真ん中を二つに折ったもの。
②半紙の一種。鼻紙などに用いる。
③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙
⇒なか‐おり【中折り】
なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ
①中央で折れかえり、また、くぼむこと。
②「中折れ下駄」の略。
③「中折れ帽子」の略。
⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】
⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】
なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥
台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。
中折れ下駄
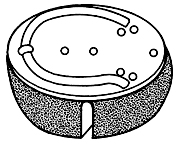 ⇒なか‐おれ【中折れ】
なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥
頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。
⇒なか‐おれ【中折れ】
なか‐がい【仲買】‥ガヒ
問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」
なか‐がき【中垣】
両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」
なが‐かけ【長掛】
(略して「なが」とも)
①打掛うちかけの長いもの。
②長い髢かもじ。
なか‐がさ【中蓋】
①中椀のふた。ちゅうがさ。
②中形の盃。
なが‐がたな【長刀】
刀身の長い刀。
なが‐ガッパ【長合羽】
丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。
長合羽
⇒なか‐おれ【中折れ】
なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥
頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。
⇒なか‐おれ【中折れ】
なか‐がい【仲買】‥ガヒ
問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」
なか‐がき【中垣】
両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」
なが‐かけ【長掛】
(略して「なが」とも)
①打掛うちかけの長いもの。
②長い髢かもじ。
なか‐がさ【中蓋】
①中椀のふた。ちゅうがさ。
②中形の盃。
なが‐がたな【長刀】
刀身の長い刀。
なが‐ガッパ【長合羽】
丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。
長合羽
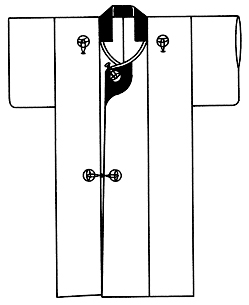 なか‐がみ【天一神】
暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」
なかがみ【中上】
姓氏の一つ。
⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】
なかがみ‐けんじ【中上健次】
小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)
⇒なかがみ【中上】
なが‐がみしも【長上下】
江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下
長上下
なか‐がみ【天一神】
暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」
なかがみ【中上】
姓氏の一つ。
⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】
なかがみ‐けんじ【中上健次】
小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)
⇒なかがみ【中上】
なが‐がみしも【長上下】
江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下
長上下
 なが‐かもじ【長髢】
毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。
なかがわ【中川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】
⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】
⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】
なかがわ【中河】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐よいち【中河与一】
なか‐がわ【那珂川】‥ガハ
関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。
那珂川
撮影:関戸 勇
なが‐かもじ【長髢】
毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。
なかがわ【中川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】
⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】
⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】
なかがわ【中河】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐よいち【中河与一】
なか‐がわ【那珂川】‥ガハ
関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。
那珂川
撮影:関戸 勇
 なか‐がわ【那賀川】‥ガハ
徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。
なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ
江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼
なか‐がわ【那賀川】‥ガハ
徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。
なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ
江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼 りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥
洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)
中川一政(1)
撮影:石井幸之助
りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥
洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)
中川一政(1)
撮影:石井幸之助
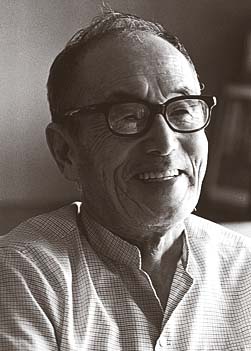 中川一政(2)
撮影:石井幸之助
中川一政(2)
撮影:石井幸之助
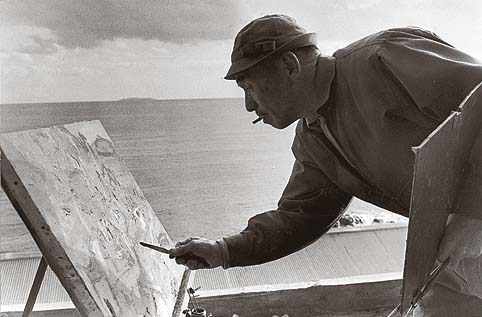 ⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥
江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥
「朝彦親王あさひこしんのう」参照。
なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥
小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)
⇒なかがわ【中河】
なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥
鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。
なか‐かんすけ【中勘助】
小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)
中勘助
提供:岩波書店
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥
江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥
「朝彦親王あさひこしんのう」参照。
なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥
小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)
⇒なかがわ【中河】
なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥
鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。
なか‐かんすけ【中勘助】
小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)
中勘助
提供:岩波書店
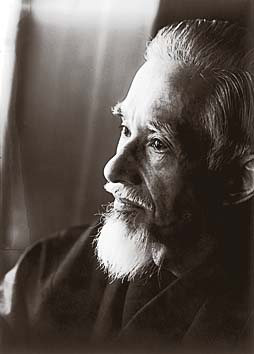 →作品:『銀の匙』
⇒なか【中】
なか‐がんな【中鉋】
荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな
なか‐ぎ【中着】
襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」
な‐がき【名書き】
名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。
なが‐ぎ【長着】
足首のあたりまである丈の長い着物。
なが‐ぎぬ【長衣】
丈の長い衣服。
ながき‐ねぶり【長き眠り】
①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」
②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」
ながき‐ひ【永き日】
ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)
なが‐きゃく【長客】
長居する客。長逗留する客。
ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ
いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」
ながき‐よ【長き夜】
①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」
②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」
⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ
①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。
②京都市の区名。
ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」
⇒ながき‐よ【長き夜】
なか‐ぎり【中限】
(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり
ながき‐わかれ【長き別れ】
①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」
②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」
なか‐くぎ【中釘】
茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。
なか‐くぐり【中潜り】
茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。
な‐がくし【名隠し】
①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」
②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。
なが‐ぐそく【長具足】
(→)長道具に同じ。
なか‐ぐち【中口】
①中央にある入口。
②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。
なが‐ぐつ【長靴】
革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴
ながくて【長久手・長湫】
名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。
なか‐くぼ【中窪】
中央がくぼんでいること。なかびく。
ながくぼ【長久保】
姓氏の一つ。
⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)
⇒ながくぼ【長久保】
なか‐くみ【中汲】
濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。
なが‐くみわ【長組輪】
(→)長小結ながこゆいに同じ。
なが‐くら【長倉】
(→)長殿ながとのに同じ。
なかぐり‐ばん【中刳り盤】
孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)
なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ
濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。
なか‐ぐろ【中黒】
①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。
②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。
③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」
ながけ【長け】
形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」
なが‐け・し【長けし】
〔形ク〕
(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」
なか‐けしむらさき【中滅紫】
滅紫色の濃淡の中間のもの。
なか‐こ【仲子】
(→)「中つ子」に同じ。
なか‐ご【中子・中心】
①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉
②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。
③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。
④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」
⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。
⑥入れ子づくりで、中に入るもの。
⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。
⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。
⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。
⇒なかご‐うけ【中子受】
⇒なかご‐おさえ【中子抑え】
⇒なかご‐さき【中子先】
⇒なかご‐ぼし【心宿】
なかご‐うけ【中子受】
鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ
長々とものを言うこと。
なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ
鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なかご‐さき【中子先】
(→)根緒懸ねおかけに同じ。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごし【長腰】
①腰に帯びる長太刀。
②長尻。長居。
なか‐ごしょ【中御所】
将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。
なか‐ごと【中言】
中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」
なが‐ごと【長言】
長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」
なが‐ごと【長事】
長々しい事柄。
なかご‐ぼし【心宿】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごもり【長籠り】
長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」
なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ
折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。
なか‐ごろ【中頃】
①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」
②あまり遠くない昔。中世。
③なかほどのところ。中途。「―で切る」
なが‐こんぶ【長昆布】
コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。
ながこんぶ
→作品:『銀の匙』
⇒なか【中】
なか‐がんな【中鉋】
荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな
なか‐ぎ【中着】
襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」
な‐がき【名書き】
名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。
なが‐ぎ【長着】
足首のあたりまである丈の長い着物。
なが‐ぎぬ【長衣】
丈の長い衣服。
ながき‐ねぶり【長き眠り】
①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」
②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」
ながき‐ひ【永き日】
ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)
なが‐きゃく【長客】
長居する客。長逗留する客。
ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ
いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」
ながき‐よ【長き夜】
①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」
②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」
⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ
①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。
②京都市の区名。
ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」
⇒ながき‐よ【長き夜】
なか‐ぎり【中限】
(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり
ながき‐わかれ【長き別れ】
①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」
②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」
なか‐くぎ【中釘】
茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。
なか‐くぐり【中潜り】
茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。
な‐がくし【名隠し】
①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」
②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。
なが‐ぐそく【長具足】
(→)長道具に同じ。
なか‐ぐち【中口】
①中央にある入口。
②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。
なが‐ぐつ【長靴】
革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴
ながくて【長久手・長湫】
名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。
なか‐くぼ【中窪】
中央がくぼんでいること。なかびく。
ながくぼ【長久保】
姓氏の一つ。
⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)
⇒ながくぼ【長久保】
なか‐くみ【中汲】
濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。
なが‐くみわ【長組輪】
(→)長小結ながこゆいに同じ。
なが‐くら【長倉】
(→)長殿ながとのに同じ。
なかぐり‐ばん【中刳り盤】
孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)
なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ
濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。
なか‐ぐろ【中黒】
①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。
②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。
③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」
ながけ【長け】
形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」
なが‐け・し【長けし】
〔形ク〕
(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」
なか‐けしむらさき【中滅紫】
滅紫色の濃淡の中間のもの。
なか‐こ【仲子】
(→)「中つ子」に同じ。
なか‐ご【中子・中心】
①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉
②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。
③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。
④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」
⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。
⑥入れ子づくりで、中に入るもの。
⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。
⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。
⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。
⇒なかご‐うけ【中子受】
⇒なかご‐おさえ【中子抑え】
⇒なかご‐さき【中子先】
⇒なかご‐ぼし【心宿】
なかご‐うけ【中子受】
鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ
長々とものを言うこと。
なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ
鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なかご‐さき【中子先】
(→)根緒懸ねおかけに同じ。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごし【長腰】
①腰に帯びる長太刀。
②長尻。長居。
なか‐ごしょ【中御所】
将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。
なか‐ごと【中言】
中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」
なが‐ごと【長言】
長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」
なが‐ごと【長事】
長々しい事柄。
なかご‐ぼし【心宿】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごもり【長籠り】
長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」
なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ
折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。
なか‐ごろ【中頃】
①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」
②あまり遠くない昔。中世。
③なかほどのところ。中途。「―で切る」
なが‐こんぶ【長昆布】
コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。
ながこんぶ
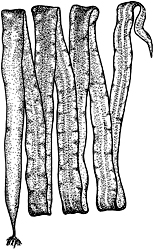 なか‐ざ【中座】
①中央の座席。
②途中で座を立つこと。ちゅうざ。
③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。
④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。
なが‐さ【長さ】
①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」
②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」
なが‐ざ【長座】
長くそこにいること。長居。ちょうざ。
なが‐さお【長棹】‥サヲ
①長い棹。
②(女房詞)長持。
③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」
ながさき【長崎】
①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。
→ぶらぶら節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。
長崎夜景
撮影:山梨勝弘
なか‐ざ【中座】
①中央の座席。
②途中で座を立つこと。ちゅうざ。
③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。
④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。
なが‐さ【長さ】
①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」
②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」
なが‐ざ【長座】
長くそこにいること。長居。ちょうざ。
なが‐さお【長棹】‥サヲ
①長い棹。
②(女房詞)長持。
③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」
ながさき【長崎】
①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。
→ぶらぶら節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。
長崎夜景
撮影:山梨勝弘
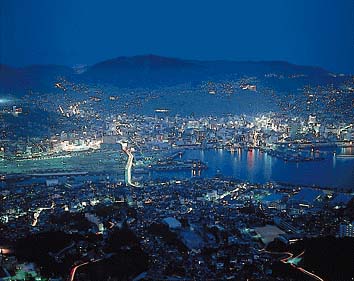 きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)
撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館
きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)
撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館
 城山国民学校
撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館
城山国民学校
撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館
 爆心地西側(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
爆心地西側(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
 道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
 長崎原爆投下
提供:平和博物館を創る会
原子爆弾
⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】
⇒ながさき‐え【長崎絵】
⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】
⇒ながさき‐けん【長崎拳】
⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】
⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】
⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】
⇒ながさき‐は【長崎派】
⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】
⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】
⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】
ながさき【長崎】
姓氏の一つ。
⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】
⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】
⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】
ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ
江戸幕府が長崎会所に課した税金。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ
江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。
長崎絵
長崎原爆投下
提供:平和博物館を創る会
原子爆弾
⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】
⇒ながさき‐え【長崎絵】
⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】
⇒ながさき‐けん【長崎拳】
⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】
⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】
⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】
⇒ながさき‐は【長崎派】
⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】
⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】
⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】
ながさき【長崎】
姓氏の一つ。
⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】
⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】
⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】
ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ
江戸幕府が長崎会所に課した税金。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ
江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。
長崎絵
 ⇒ながさき【長崎】
ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥
江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐けん【長崎拳】
(→)本拳ほんけんの異称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ
長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐しんれい【長崎新例】
(→)正徳しょうとく新例に同じ。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐だいがく【長崎大学】
国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかすけ【長崎高資】
鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかつな【長崎高綱】
鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐は【長崎派】
江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。
①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。
②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。
③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。
④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。
⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ほんせん【長崎本線】
鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥
江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥
戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。
⇒ながさき【長崎】
なが‐ささげ【長豇豆】
〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。
なか‐ざし【中差・中指】
箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。
なか‐ざし【中挿】
女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。
なが‐ざし【長差】
(→)長尺ながじゃくに同じ。
なが‐ざしき【長座敷】
その座敷に長居すること。長座。
なか‐さだ【中さだ】
(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」
なかざと【中里】
姓氏の一つ。
⇒なかざと‐かいざん【中里介山】
なかざと‐かいざん【中里介山】
小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)
中里介山
提供:毎日新聞社
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥
江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐けん【長崎拳】
(→)本拳ほんけんの異称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ
長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐しんれい【長崎新例】
(→)正徳しょうとく新例に同じ。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐だいがく【長崎大学】
国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかすけ【長崎高資】
鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかつな【長崎高綱】
鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐は【長崎派】
江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。
①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。
②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。
③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。
④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。
⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ほんせん【長崎本線】
鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥
江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥
戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。
⇒ながさき【長崎】
なが‐ささげ【長豇豆】
〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。
なか‐ざし【中差・中指】
箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。
なか‐ざし【中挿】
女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。
なが‐ざし【長差】
(→)長尺ながじゃくに同じ。
なが‐ざしき【長座敷】
その座敷に長居すること。長座。
なか‐さだ【中さだ】
(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」
なかざと【中里】
姓氏の一つ。
⇒なかざと‐かいざん【中里介山】
なかざと‐かいざん【中里介山】
小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)
中里介山
提供:毎日新聞社
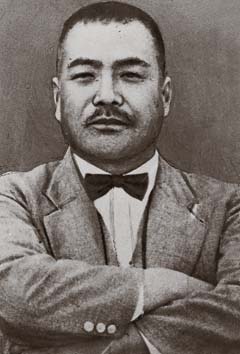 ⇒なかざと【中里】
なが‐さま【長様】
長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」
なかさ・れる【泣かされる】
〔自下一〕
①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」
②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」
なかざわ【中沢】‥ザハ
姓氏の一つ。
⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】
⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】
⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】
ながさわ【長沢】‥サハ
姓氏の一つ。
⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】
なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥
江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥
文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)
⇒なかざわ【中沢】
ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥
江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)
⇒ながさわ【長沢】
なか‐し【仲仕】
荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」
ながし【流し】
①ながすこと。ながすもの。
②流罪。島流し。
③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。
④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」
⑤生花で、流し枝のこと。
⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」
⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。
⑧物事に構わず、やり過ごすこと。
⑨(九州・四国で)梅雨。
⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。
⇒ながし‐あみ【流し網】
⇒ながし‐いた【流し板】
⇒ながし‐うち【流し打ち】
⇒ながし‐えだ【流し枝】
⇒ながし‐かじ【流し舵】
⇒ながし‐ぎ【流し木】
⇒ながし‐さく【流し作】
⇒ながし‐さくば【流し作場】
⇒ながし‐しがらみ【流し柵】
⇒ながし‐ずき【流し漉き】
⇒ながし‐そうめん【流し索麺】
⇒ながし‐だい【流し台】
⇒ながし‐づり【流し釣り】
⇒ながし‐どり【流し撮り】
⇒ながし‐ば【流し場】
⇒ながし‐ばこ【流し箱】
⇒ながし‐びな【流し雛】
⇒ながし‐ぶみ【流し文】
⇒ながし‐め【流し目】
⇒ながし‐もち【流し黐】
⇒ながし‐もと【流し元】
⇒ながし‐もの【流し者】
⇒ながし‐よみ【流し読み】
なが・し【長し・永し】
〔形ク〕
⇒ながい
なが‐じ【長道・長路】‥ヂ
(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」
ながし‐あみ【流し網】
刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。
⇒ながし【流し】
ながし‐いた【流し板】
①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。
②竪張りにした屋根板。
⇒ながし【流し】
ながし‐うち【流し打ち】
野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。
⇒ながし【流し】
ながし‐えだ【流し枝】
立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。
⇒ながし【流し】
なか‐しお【中潮】‥シホ
干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。
なが‐しお【長潮】‥シホ
小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。
なが‐しかく【長四角】
長方形のこと。
ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ
和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。
⇒ながし【流し】
なか‐じき【中敷】
中に敷くこと。また、そのもの。
ながし‐ぎ【流し木】
山から伐り出して川に流し下ろす木材。
⇒ながし【流し】
なか‐じきい【中敷居】‥ヰ
押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。
なか‐じきり【中仕切】
部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」
なか‐じく【中軸】‥ヂク
歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。
なか‐しこ【中仕子・中鉋】
(→)「なかがんな」に同じ。
ながし‐こ・む【流し込む】
〔他五〕
①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」
②茶漬飯などを急いで食う。
ながし‐さく【流し作】
「流し作場」の略。
⇒ながし【流し】
ながし‐さくば【流し作場】
川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。
⇒ながし【流し】
ながし‐しがらみ【流し柵】
昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐ずき【流し漉き】
和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。
⇒ながし【流し】
ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥
樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐だい【流し台】
台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。
⇒ながし【流し】
ながし‐づり【流し釣り】
①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。
②トローリング。
⇒ながし【流し】
ながし‐どり【流し撮り】
被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。
⇒ながし【流し】
ながしの【長篠】
愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。
ながし‐ば【流し場】
湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。
⇒ながし【流し】
ながし‐ばこ【流し箱】
箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。
⇒ながし【流し】
ながし‐びな【流し雛】
3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。
流し雛(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
⇒なかざと【中里】
なが‐さま【長様】
長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」
なかさ・れる【泣かされる】
〔自下一〕
①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」
②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」
なかざわ【中沢】‥ザハ
姓氏の一つ。
⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】
⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】
⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】
ながさわ【長沢】‥サハ
姓氏の一つ。
⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】
なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥
江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥
文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)
⇒なかざわ【中沢】
ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥
江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)
⇒ながさわ【長沢】
なか‐し【仲仕】
荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」
ながし【流し】
①ながすこと。ながすもの。
②流罪。島流し。
③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。
④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」
⑤生花で、流し枝のこと。
⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」
⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。
⑧物事に構わず、やり過ごすこと。
⑨(九州・四国で)梅雨。
⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。
⇒ながし‐あみ【流し網】
⇒ながし‐いた【流し板】
⇒ながし‐うち【流し打ち】
⇒ながし‐えだ【流し枝】
⇒ながし‐かじ【流し舵】
⇒ながし‐ぎ【流し木】
⇒ながし‐さく【流し作】
⇒ながし‐さくば【流し作場】
⇒ながし‐しがらみ【流し柵】
⇒ながし‐ずき【流し漉き】
⇒ながし‐そうめん【流し索麺】
⇒ながし‐だい【流し台】
⇒ながし‐づり【流し釣り】
⇒ながし‐どり【流し撮り】
⇒ながし‐ば【流し場】
⇒ながし‐ばこ【流し箱】
⇒ながし‐びな【流し雛】
⇒ながし‐ぶみ【流し文】
⇒ながし‐め【流し目】
⇒ながし‐もち【流し黐】
⇒ながし‐もと【流し元】
⇒ながし‐もの【流し者】
⇒ながし‐よみ【流し読み】
なが・し【長し・永し】
〔形ク〕
⇒ながい
なが‐じ【長道・長路】‥ヂ
(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」
ながし‐あみ【流し網】
刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。
⇒ながし【流し】
ながし‐いた【流し板】
①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。
②竪張りにした屋根板。
⇒ながし【流し】
ながし‐うち【流し打ち】
野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。
⇒ながし【流し】
ながし‐えだ【流し枝】
立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。
⇒ながし【流し】
なか‐しお【中潮】‥シホ
干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。
なが‐しお【長潮】‥シホ
小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。
なが‐しかく【長四角】
長方形のこと。
ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ
和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。
⇒ながし【流し】
なか‐じき【中敷】
中に敷くこと。また、そのもの。
ながし‐ぎ【流し木】
山から伐り出して川に流し下ろす木材。
⇒ながし【流し】
なか‐じきい【中敷居】‥ヰ
押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。
なか‐じきり【中仕切】
部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」
なか‐じく【中軸】‥ヂク
歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。
なか‐しこ【中仕子・中鉋】
(→)「なかがんな」に同じ。
ながし‐こ・む【流し込む】
〔他五〕
①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」
②茶漬飯などを急いで食う。
ながし‐さく【流し作】
「流し作場」の略。
⇒ながし【流し】
ながし‐さくば【流し作場】
川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。
⇒ながし【流し】
ながし‐しがらみ【流し柵】
昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐ずき【流し漉き】
和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。
⇒ながし【流し】
ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥
樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐だい【流し台】
台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。
⇒ながし【流し】
ながし‐づり【流し釣り】
①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。
②トローリング。
⇒ながし【流し】
ながし‐どり【流し撮り】
被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。
⇒ながし【流し】
ながしの【長篠】
愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。
ながし‐ば【流し場】
湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。
⇒ながし【流し】
ながし‐ばこ【流し箱】
箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。
⇒ながし【流し】
ながし‐びな【流し雛】
3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。
流し雛(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 流し雛(和歌山)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
流し雛(和歌山)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒ながし【流し】
ながし‐ぶみ【流し文】
入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。
⇒ながし【流し】
なか‐じま【中島】
池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」
なかじま【中島】
姓氏の一つ。
⇒なかじま‐あつし【中島敦】
⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】
⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】
⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】
⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】
⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】
ながしま【長島】
三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。
長島
撮影:的場 啓
⇒ながし【流し】
ながし‐ぶみ【流し文】
入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。
⇒ながし【流し】
なか‐じま【中島】
池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」
なかじま【中島】
姓氏の一つ。
⇒なかじま‐あつし【中島敦】
⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】
⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】
⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】
⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】
⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】
ながしま【長島】
三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。
長島
撮影:的場 啓
 長島の水屋
撮影:的場 啓
長島の水屋
撮影:的場 啓
 ⇒ながしま‐いっき【長島一揆】
なかじま‐あつし【中島敦】
小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)
中島敦
提供:毎日新聞社
⇒ながしま‐いっき【長島一揆】
なかじま‐あつし【中島敦】
小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)
中島敦
提供:毎日新聞社
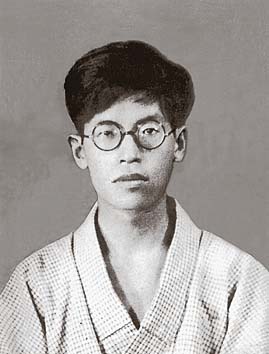 ⇒なかじま【中島】
ながしま‐いっき【長島一揆】
伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。
⇒ながしま【長島】
なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ
評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)
中島健蔵
撮影:石井幸之助
⇒なかじま【中島】
ながしま‐いっき【長島一揆】
伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。
⇒ながしま【長島】
なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ
評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)
中島健蔵
撮影:石井幸之助
 ⇒なかじま【中島】
なかじま‐そういん【中島棕隠】
江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨
⇒なかじま【中島】
なかじま‐そういん【中島棕隠】
江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨
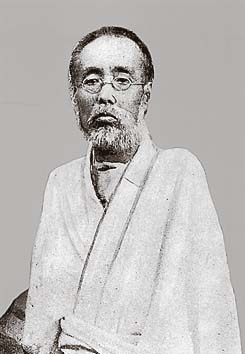 →資料:『三酔人経綸問答』
⇒なかえ【中江】
なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】
江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)
→著作:『翁問答』
⇒なかえ【中江】
ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】
馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥
柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ま【長柄の間】
槍・長刀などを飾りつけて置く室。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐やり【長柄の槍】
長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ
槍奉行。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶね【長柄船】
長柄組の乗る船。
⇒なが‐え【長柄】
なが‐えぼし【長烏帽子】
立烏帽子の丈の長いもの。
ながえ‐もち【長柄持】
長柄の傘を持って従う者。
⇒なが‐え【長柄】
なかお【中尾】‥ヲ
姓氏の一つ。
⇒なかお‐とざん【中尾都山】
なか‐お【中緒】‥ヲ
①中ほどについている緒・紐。
②(→)「中の緒」に同じ。
③茶入の袋につける緒。
ながお【長尾】‥ヲ
姓氏の一つ。上杉氏の家宰。
⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】
なが‐おい【長追い】‥オヒ
逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。
なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥
牛の貸借の仲介人。
なかおか【中岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】
ながおか【長岡】‥ヲカ
新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。
⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】
ながおか【長岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】
ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥
国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。
⇒ながおか【長岡】
ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ
①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。
②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。
ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥
上杉謙信の初名。
⇒ながお【長尾】
なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ
幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)
中岡慎太郎
提供:毎日新聞社
→資料:『三酔人経綸問答』
⇒なかえ【中江】
なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】
江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)
→著作:『翁問答』
⇒なかえ【中江】
ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】
馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥
柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐ま【長柄の間】
槍・長刀などを飾りつけて置く室。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐の‐やり【長柄の槍】
長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ
槍奉行。
⇒なが‐え【長柄】
ながえ‐ぶね【長柄船】
長柄組の乗る船。
⇒なが‐え【長柄】
なが‐えぼし【長烏帽子】
立烏帽子の丈の長いもの。
ながえ‐もち【長柄持】
長柄の傘を持って従う者。
⇒なが‐え【長柄】
なかお【中尾】‥ヲ
姓氏の一つ。
⇒なかお‐とざん【中尾都山】
なか‐お【中緒】‥ヲ
①中ほどについている緒・紐。
②(→)「中の緒」に同じ。
③茶入の袋につける緒。
ながお【長尾】‥ヲ
姓氏の一つ。上杉氏の家宰。
⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】
なが‐おい【長追い】‥オヒ
逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。
なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥
牛の貸借の仲介人。
なかおか【中岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】
ながおか【長岡】‥ヲカ
新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。
⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】
ながおか【長岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】
ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥
国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。
⇒ながおか【長岡】
ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ
①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。
②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。
ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥
上杉謙信の初名。
⇒ながお【長尾】
なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ
幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)
中岡慎太郎
提供:毎日新聞社
 ⇒なかおか【中岡】
ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ
物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)
長岡半太郎
撮影:田村 茂
⇒なかおか【中岡】
ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ
物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)
長岡半太郎
撮影:田村 茂
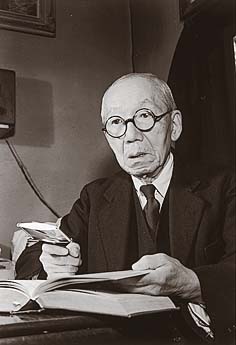 ⇒ながおか【長岡】
なが‐おき【長起き】
夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」
なか‐おく【中奥】
江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく
なか‐おし【中押】
(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)
⇒ちゅうおし
なか‐おち【中落ち】
魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。
なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥
(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)
⇒なかお【中尾】
ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥
⇒ちょうびけい
なか‐おび【中帯】
上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。
なか‐おもて【中表】
布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」
なか‐おり【中折り】‥ヲリ
①中ほどから折ること。
②中折紙の略。
⇒なかおり‐がみ【中折紙】
なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥
①紙の真ん中を二つに折ったもの。
②半紙の一種。鼻紙などに用いる。
③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙
⇒なか‐おり【中折り】
なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ
①中央で折れかえり、また、くぼむこと。
②「中折れ下駄」の略。
③「中折れ帽子」の略。
⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】
⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】
なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥
台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。
中折れ下駄
⇒ながおか【長岡】
なが‐おき【長起き】
夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」
なか‐おく【中奥】
江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく
なか‐おし【中押】
(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)
⇒ちゅうおし
なか‐おち【中落ち】
魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。
なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥
(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)
⇒なかお【中尾】
ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥
⇒ちょうびけい
なか‐おび【中帯】
上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。
なか‐おもて【中表】
布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」
なか‐おり【中折り】‥ヲリ
①中ほどから折ること。
②中折紙の略。
⇒なかおり‐がみ【中折紙】
なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥
①紙の真ん中を二つに折ったもの。
②半紙の一種。鼻紙などに用いる。
③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙
⇒なか‐おり【中折り】
なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ
①中央で折れかえり、また、くぼむこと。
②「中折れ下駄」の略。
③「中折れ帽子」の略。
⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】
⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】
なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥
台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。
中折れ下駄
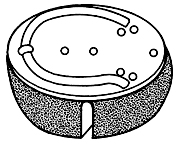 ⇒なか‐おれ【中折れ】
なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥
頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。
⇒なか‐おれ【中折れ】
なか‐がい【仲買】‥ガヒ
問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」
なか‐がき【中垣】
両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」
なが‐かけ【長掛】
(略して「なが」とも)
①打掛うちかけの長いもの。
②長い髢かもじ。
なか‐がさ【中蓋】
①中椀のふた。ちゅうがさ。
②中形の盃。
なが‐がたな【長刀】
刀身の長い刀。
なが‐ガッパ【長合羽】
丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。
長合羽
⇒なか‐おれ【中折れ】
なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥
頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。
⇒なか‐おれ【中折れ】
なか‐がい【仲買】‥ガヒ
問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」
なか‐がき【中垣】
両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」
なが‐かけ【長掛】
(略して「なが」とも)
①打掛うちかけの長いもの。
②長い髢かもじ。
なか‐がさ【中蓋】
①中椀のふた。ちゅうがさ。
②中形の盃。
なが‐がたな【長刀】
刀身の長い刀。
なが‐ガッパ【長合羽】
丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。
長合羽
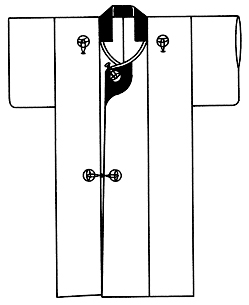 なか‐がみ【天一神】
暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」
なかがみ【中上】
姓氏の一つ。
⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】
なかがみ‐けんじ【中上健次】
小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)
⇒なかがみ【中上】
なが‐がみしも【長上下】
江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下
長上下
なか‐がみ【天一神】
暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」
なかがみ【中上】
姓氏の一つ。
⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】
なかがみ‐けんじ【中上健次】
小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)
⇒なかがみ【中上】
なが‐がみしも【長上下】
江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下
長上下
 なが‐かもじ【長髢】
毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。
なかがわ【中川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】
⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】
⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】
なかがわ【中河】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐よいち【中河与一】
なか‐がわ【那珂川】‥ガハ
関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。
那珂川
撮影:関戸 勇
なが‐かもじ【長髢】
毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。
なかがわ【中川】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】
⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】
⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】
なかがわ【中河】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐よいち【中河与一】
なか‐がわ【那珂川】‥ガハ
関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。
那珂川
撮影:関戸 勇
 なか‐がわ【那賀川】‥ガハ
徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。
なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ
江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼
なか‐がわ【那賀川】‥ガハ
徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。
なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ
江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼 りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥
洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)
中川一政(1)
撮影:石井幸之助
りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥
洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)
中川一政(1)
撮影:石井幸之助
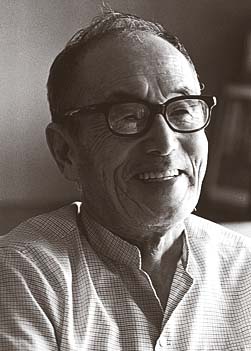 中川一政(2)
撮影:石井幸之助
中川一政(2)
撮影:石井幸之助
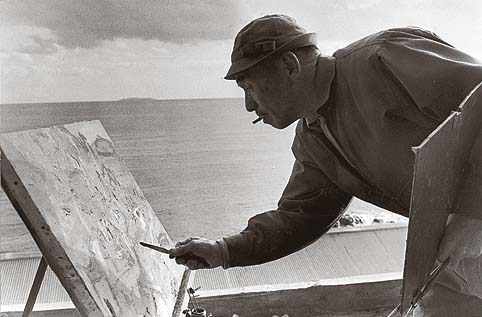 ⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥
江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥
「朝彦親王あさひこしんのう」参照。
なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥
小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)
⇒なかがわ【中河】
なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥
鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。
なか‐かんすけ【中勘助】
小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)
中勘助
提供:岩波書店
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥
江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)
⇒なかがわ【中川】
なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥
「朝彦親王あさひこしんのう」参照。
なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥
小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)
⇒なかがわ【中河】
なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥
鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。
なか‐かんすけ【中勘助】
小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)
中勘助
提供:岩波書店
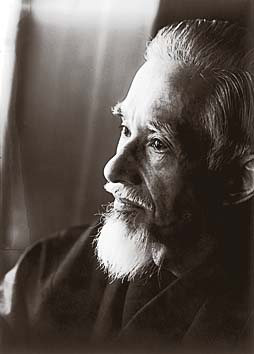 →作品:『銀の匙』
⇒なか【中】
なか‐がんな【中鉋】
荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな
なか‐ぎ【中着】
襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」
な‐がき【名書き】
名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。
なが‐ぎ【長着】
足首のあたりまである丈の長い着物。
なが‐ぎぬ【長衣】
丈の長い衣服。
ながき‐ねぶり【長き眠り】
①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」
②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」
ながき‐ひ【永き日】
ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)
なが‐きゃく【長客】
長居する客。長逗留する客。
ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ
いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」
ながき‐よ【長き夜】
①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」
②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」
⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ
①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。
②京都市の区名。
ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」
⇒ながき‐よ【長き夜】
なか‐ぎり【中限】
(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり
ながき‐わかれ【長き別れ】
①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」
②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」
なか‐くぎ【中釘】
茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。
なか‐くぐり【中潜り】
茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。
な‐がくし【名隠し】
①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」
②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。
なが‐ぐそく【長具足】
(→)長道具に同じ。
なか‐ぐち【中口】
①中央にある入口。
②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。
なが‐ぐつ【長靴】
革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴
ながくて【長久手・長湫】
名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。
なか‐くぼ【中窪】
中央がくぼんでいること。なかびく。
ながくぼ【長久保】
姓氏の一つ。
⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)
⇒ながくぼ【長久保】
なか‐くみ【中汲】
濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。
なが‐くみわ【長組輪】
(→)長小結ながこゆいに同じ。
なが‐くら【長倉】
(→)長殿ながとのに同じ。
なかぐり‐ばん【中刳り盤】
孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)
なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ
濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。
なか‐ぐろ【中黒】
①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。
②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。
③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」
ながけ【長け】
形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」
なが‐け・し【長けし】
〔形ク〕
(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」
なか‐けしむらさき【中滅紫】
滅紫色の濃淡の中間のもの。
なか‐こ【仲子】
(→)「中つ子」に同じ。
なか‐ご【中子・中心】
①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉
②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。
③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。
④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」
⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。
⑥入れ子づくりで、中に入るもの。
⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。
⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。
⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。
⇒なかご‐うけ【中子受】
⇒なかご‐おさえ【中子抑え】
⇒なかご‐さき【中子先】
⇒なかご‐ぼし【心宿】
なかご‐うけ【中子受】
鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ
長々とものを言うこと。
なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ
鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なかご‐さき【中子先】
(→)根緒懸ねおかけに同じ。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごし【長腰】
①腰に帯びる長太刀。
②長尻。長居。
なか‐ごしょ【中御所】
将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。
なか‐ごと【中言】
中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」
なが‐ごと【長言】
長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」
なが‐ごと【長事】
長々しい事柄。
なかご‐ぼし【心宿】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごもり【長籠り】
長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」
なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ
折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。
なか‐ごろ【中頃】
①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」
②あまり遠くない昔。中世。
③なかほどのところ。中途。「―で切る」
なが‐こんぶ【長昆布】
コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。
ながこんぶ
→作品:『銀の匙』
⇒なか【中】
なか‐がんな【中鉋】
荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな
なか‐ぎ【中着】
襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」
な‐がき【名書き】
名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。
なが‐ぎ【長着】
足首のあたりまである丈の長い着物。
なが‐ぎぬ【長衣】
丈の長い衣服。
ながき‐ねぶり【長き眠り】
①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」
②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」
ながき‐ひ【永き日】
ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)
なが‐きゃく【長客】
長居する客。長逗留する客。
ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ
いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」
ながき‐よ【長き夜】
①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」
②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」
⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ
①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。
②京都市の区名。
ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】
凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」
⇒ながき‐よ【長き夜】
なか‐ぎり【中限】
(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり
ながき‐わかれ【長き別れ】
①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」
②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」
なか‐くぎ【中釘】
茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。
なか‐くぐり【中潜り】
茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。
な‐がくし【名隠し】
①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」
②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。
なが‐ぐそく【長具足】
(→)長道具に同じ。
なか‐ぐち【中口】
①中央にある入口。
②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。
なが‐ぐつ【長靴】
革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴
ながくて【長久手・長湫】
名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。
なか‐くぼ【中窪】
中央がくぼんでいること。なかびく。
ながくぼ【長久保】
姓氏の一つ。
⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】
江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)
⇒ながくぼ【長久保】
なか‐くみ【中汲】
濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。
なが‐くみわ【長組輪】
(→)長小結ながこゆいに同じ。
なが‐くら【長倉】
(→)長殿ながとのに同じ。
なかぐり‐ばん【中刳り盤】
孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)
なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ
濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。
なか‐ぐろ【中黒】
①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。
②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。
③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」
ながけ【長け】
形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」
なが‐け・し【長けし】
〔形ク〕
(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」
なか‐けしむらさき【中滅紫】
滅紫色の濃淡の中間のもの。
なか‐こ【仲子】
(→)「中つ子」に同じ。
なか‐ご【中子・中心】
①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉
②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。
③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。
④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」
⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。
⑥入れ子づくりで、中に入るもの。
⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。
⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。
⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。
⇒なかご‐うけ【中子受】
⇒なかご‐おさえ【中子抑え】
⇒なかご‐さき【中子先】
⇒なかご‐ぼし【心宿】
なかご‐うけ【中子受】
鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ
長々とものを言うこと。
なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ
鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なかご‐さき【中子先】
(→)根緒懸ねおかけに同じ。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごし【長腰】
①腰に帯びる長太刀。
②長尻。長居。
なか‐ごしょ【中御所】
将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。
なか‐ごと【中言】
中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」
なが‐ごと【長言】
長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」
なが‐ごと【長事】
長々しい事柄。
なかご‐ぼし【心宿】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。
⇒なか‐ご【中子・中心】
なが‐ごもり【長籠り】
長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」
なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ
折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。
なか‐ごろ【中頃】
①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」
②あまり遠くない昔。中世。
③なかほどのところ。中途。「―で切る」
なが‐こんぶ【長昆布】
コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。
ながこんぶ
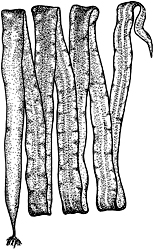 なか‐ざ【中座】
①中央の座席。
②途中で座を立つこと。ちゅうざ。
③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。
④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。
なが‐さ【長さ】
①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」
②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」
なが‐ざ【長座】
長くそこにいること。長居。ちょうざ。
なが‐さお【長棹】‥サヲ
①長い棹。
②(女房詞)長持。
③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」
ながさき【長崎】
①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。
→ぶらぶら節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。
長崎夜景
撮影:山梨勝弘
なか‐ざ【中座】
①中央の座席。
②途中で座を立つこと。ちゅうざ。
③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。
④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。
なが‐さ【長さ】
①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」
②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」
なが‐ざ【長座】
長くそこにいること。長居。ちょうざ。
なが‐さお【長棹】‥サヲ
①長い棹。
②(女房詞)長持。
③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」
ながさき【長崎】
①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。
→ぶらぶら節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。
長崎夜景
撮影:山梨勝弘
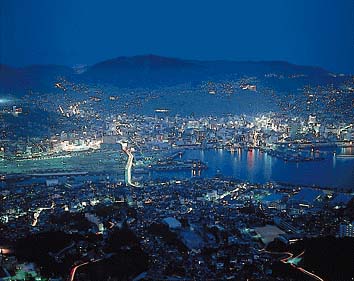 きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)
撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館
きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)
撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館
 城山国民学校
撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館
城山国民学校
撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館
 爆心地西側(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
爆心地西側(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
 道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)
撮影:山端庸介
 長崎原爆投下
提供:平和博物館を創る会
原子爆弾
⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】
⇒ながさき‐え【長崎絵】
⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】
⇒ながさき‐けん【長崎拳】
⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】
⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】
⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】
⇒ながさき‐は【長崎派】
⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】
⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】
⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】
ながさき【長崎】
姓氏の一つ。
⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】
⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】
⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】
ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ
江戸幕府が長崎会所に課した税金。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ
江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。
長崎絵
長崎原爆投下
提供:平和博物館を創る会
原子爆弾
⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】
⇒ながさき‐え【長崎絵】
⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】
⇒ながさき‐けん【長崎拳】
⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】
⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】
⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】
⇒ながさき‐は【長崎派】
⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】
⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】
⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】
ながさき【長崎】
姓氏の一つ。
⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】
⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】
⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】
ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ
江戸幕府が長崎会所に課した税金。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ
江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。
長崎絵
 ⇒ながさき【長崎】
ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥
江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐けん【長崎拳】
(→)本拳ほんけんの異称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ
長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐しんれい【長崎新例】
(→)正徳しょうとく新例に同じ。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐だいがく【長崎大学】
国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかすけ【長崎高資】
鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかつな【長崎高綱】
鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐は【長崎派】
江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。
①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。
②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。
③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。
④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。
⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ほんせん【長崎本線】
鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥
江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥
戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。
⇒ながさき【長崎】
なが‐ささげ【長豇豆】
〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。
なか‐ざし【中差・中指】
箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。
なか‐ざし【中挿】
女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。
なが‐ざし【長差】
(→)長尺ながじゃくに同じ。
なが‐ざしき【長座敷】
その座敷に長居すること。長座。
なか‐さだ【中さだ】
(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」
なかざと【中里】
姓氏の一つ。
⇒なかざと‐かいざん【中里介山】
なかざと‐かいざん【中里介山】
小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)
中里介山
提供:毎日新聞社
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥
江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐けん【長崎拳】
(→)本拳ほんけんの異称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ
長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐しんれい【長崎新例】
(→)正徳しょうとく新例に同じ。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐だいがく【長崎大学】
国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかすけ【長崎高資】
鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐たかつな【長崎高綱】
鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐は【長崎派】
江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。
①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。
②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。
③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。
④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。
⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】
江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐ほんせん【長崎本線】
鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥
江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」
⇒ながさき【長崎】
ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥
戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。
⇒ながさき【長崎】
なが‐ささげ【長豇豆】
〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。
なか‐ざし【中差・中指】
箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。
なか‐ざし【中挿】
女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。
なが‐ざし【長差】
(→)長尺ながじゃくに同じ。
なが‐ざしき【長座敷】
その座敷に長居すること。長座。
なか‐さだ【中さだ】
(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」
なかざと【中里】
姓氏の一つ。
⇒なかざと‐かいざん【中里介山】
なかざと‐かいざん【中里介山】
小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)
中里介山
提供:毎日新聞社
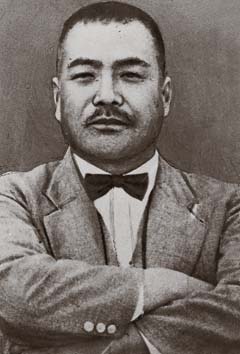 ⇒なかざと【中里】
なが‐さま【長様】
長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」
なかさ・れる【泣かされる】
〔自下一〕
①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」
②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」
なかざわ【中沢】‥ザハ
姓氏の一つ。
⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】
⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】
⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】
ながさわ【長沢】‥サハ
姓氏の一つ。
⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】
なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥
江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥
文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)
⇒なかざわ【中沢】
ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥
江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)
⇒ながさわ【長沢】
なか‐し【仲仕】
荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」
ながし【流し】
①ながすこと。ながすもの。
②流罪。島流し。
③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。
④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」
⑤生花で、流し枝のこと。
⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」
⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。
⑧物事に構わず、やり過ごすこと。
⑨(九州・四国で)梅雨。
⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。
⇒ながし‐あみ【流し網】
⇒ながし‐いた【流し板】
⇒ながし‐うち【流し打ち】
⇒ながし‐えだ【流し枝】
⇒ながし‐かじ【流し舵】
⇒ながし‐ぎ【流し木】
⇒ながし‐さく【流し作】
⇒ながし‐さくば【流し作場】
⇒ながし‐しがらみ【流し柵】
⇒ながし‐ずき【流し漉き】
⇒ながし‐そうめん【流し索麺】
⇒ながし‐だい【流し台】
⇒ながし‐づり【流し釣り】
⇒ながし‐どり【流し撮り】
⇒ながし‐ば【流し場】
⇒ながし‐ばこ【流し箱】
⇒ながし‐びな【流し雛】
⇒ながし‐ぶみ【流し文】
⇒ながし‐め【流し目】
⇒ながし‐もち【流し黐】
⇒ながし‐もと【流し元】
⇒ながし‐もの【流し者】
⇒ながし‐よみ【流し読み】
なが・し【長し・永し】
〔形ク〕
⇒ながい
なが‐じ【長道・長路】‥ヂ
(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」
ながし‐あみ【流し網】
刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。
⇒ながし【流し】
ながし‐いた【流し板】
①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。
②竪張りにした屋根板。
⇒ながし【流し】
ながし‐うち【流し打ち】
野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。
⇒ながし【流し】
ながし‐えだ【流し枝】
立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。
⇒ながし【流し】
なか‐しお【中潮】‥シホ
干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。
なが‐しお【長潮】‥シホ
小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。
なが‐しかく【長四角】
長方形のこと。
ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ
和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。
⇒ながし【流し】
なか‐じき【中敷】
中に敷くこと。また、そのもの。
ながし‐ぎ【流し木】
山から伐り出して川に流し下ろす木材。
⇒ながし【流し】
なか‐じきい【中敷居】‥ヰ
押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。
なか‐じきり【中仕切】
部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」
なか‐じく【中軸】‥ヂク
歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。
なか‐しこ【中仕子・中鉋】
(→)「なかがんな」に同じ。
ながし‐こ・む【流し込む】
〔他五〕
①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」
②茶漬飯などを急いで食う。
ながし‐さく【流し作】
「流し作場」の略。
⇒ながし【流し】
ながし‐さくば【流し作場】
川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。
⇒ながし【流し】
ながし‐しがらみ【流し柵】
昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐ずき【流し漉き】
和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。
⇒ながし【流し】
ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥
樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐だい【流し台】
台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。
⇒ながし【流し】
ながし‐づり【流し釣り】
①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。
②トローリング。
⇒ながし【流し】
ながし‐どり【流し撮り】
被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。
⇒ながし【流し】
ながしの【長篠】
愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。
ながし‐ば【流し場】
湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。
⇒ながし【流し】
ながし‐ばこ【流し箱】
箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。
⇒ながし【流し】
ながし‐びな【流し雛】
3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。
流し雛(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
⇒なかざと【中里】
なが‐さま【長様】
長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」
なかさ・れる【泣かされる】
〔自下一〕
①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」
②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」
なかざわ【中沢】‥ザハ
姓氏の一つ。
⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】
⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】
⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】
ながさわ【長沢】‥サハ
姓氏の一つ。
⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】
なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥
江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥
洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)
⇒なかざわ【中沢】
なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥
文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)
⇒なかざわ【中沢】
ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥
江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)
⇒ながさわ【長沢】
なか‐し【仲仕】
荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」
ながし【流し】
①ながすこと。ながすもの。
②流罪。島流し。
③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。
④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」
⑤生花で、流し枝のこと。
⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」
⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。
⑧物事に構わず、やり過ごすこと。
⑨(九州・四国で)梅雨。
⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。
⇒ながし‐あみ【流し網】
⇒ながし‐いた【流し板】
⇒ながし‐うち【流し打ち】
⇒ながし‐えだ【流し枝】
⇒ながし‐かじ【流し舵】
⇒ながし‐ぎ【流し木】
⇒ながし‐さく【流し作】
⇒ながし‐さくば【流し作場】
⇒ながし‐しがらみ【流し柵】
⇒ながし‐ずき【流し漉き】
⇒ながし‐そうめん【流し索麺】
⇒ながし‐だい【流し台】
⇒ながし‐づり【流し釣り】
⇒ながし‐どり【流し撮り】
⇒ながし‐ば【流し場】
⇒ながし‐ばこ【流し箱】
⇒ながし‐びな【流し雛】
⇒ながし‐ぶみ【流し文】
⇒ながし‐め【流し目】
⇒ながし‐もち【流し黐】
⇒ながし‐もと【流し元】
⇒ながし‐もの【流し者】
⇒ながし‐よみ【流し読み】
なが・し【長し・永し】
〔形ク〕
⇒ながい
なが‐じ【長道・長路】‥ヂ
(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」
ながし‐あみ【流し網】
刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。
⇒ながし【流し】
ながし‐いた【流し板】
①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。
②竪張りにした屋根板。
⇒ながし【流し】
ながし‐うち【流し打ち】
野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。
⇒ながし【流し】
ながし‐えだ【流し枝】
立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。
⇒ながし【流し】
なか‐しお【中潮】‥シホ
干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。
なが‐しお【長潮】‥シホ
小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。
なが‐しかく【長四角】
長方形のこと。
ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ
和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。
⇒ながし【流し】
なか‐じき【中敷】
中に敷くこと。また、そのもの。
ながし‐ぎ【流し木】
山から伐り出して川に流し下ろす木材。
⇒ながし【流し】
なか‐じきい【中敷居】‥ヰ
押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。
なか‐じきり【中仕切】
部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」
なか‐じく【中軸】‥ヂク
歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。
なか‐しこ【中仕子・中鉋】
(→)「なかがんな」に同じ。
ながし‐こ・む【流し込む】
〔他五〕
①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」
②茶漬飯などを急いで食う。
ながし‐さく【流し作】
「流し作場」の略。
⇒ながし【流し】
ながし‐さくば【流し作場】
川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。
⇒ながし【流し】
ながし‐しがらみ【流し柵】
昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐ずき【流し漉き】
和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。
⇒ながし【流し】
ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥
樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。
⇒ながし【流し】
ながし‐だい【流し台】
台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。
⇒ながし【流し】
ながし‐づり【流し釣り】
①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。
②トローリング。
⇒ながし【流し】
ながし‐どり【流し撮り】
被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。
⇒ながし【流し】
ながしの【長篠】
愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。
ながし‐ば【流し場】
湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。
⇒ながし【流し】
ながし‐ばこ【流し箱】
箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。
⇒ながし【流し】
ながし‐びな【流し雛】
3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。
流し雛(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 流し雛(和歌山)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
流し雛(和歌山)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒ながし【流し】
ながし‐ぶみ【流し文】
入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。
⇒ながし【流し】
なか‐じま【中島】
池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」
なかじま【中島】
姓氏の一つ。
⇒なかじま‐あつし【中島敦】
⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】
⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】
⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】
⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】
⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】
ながしま【長島】
三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。
長島
撮影:的場 啓
⇒ながし【流し】
ながし‐ぶみ【流し文】
入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。
⇒ながし【流し】
なか‐じま【中島】
池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」
なかじま【中島】
姓氏の一つ。
⇒なかじま‐あつし【中島敦】
⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】
⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】
⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】
⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】
⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】
ながしま【長島】
三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。
長島
撮影:的場 啓
 長島の水屋
撮影:的場 啓
長島の水屋
撮影:的場 啓
 ⇒ながしま‐いっき【長島一揆】
なかじま‐あつし【中島敦】
小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)
中島敦
提供:毎日新聞社
⇒ながしま‐いっき【長島一揆】
なかじま‐あつし【中島敦】
小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)
中島敦
提供:毎日新聞社
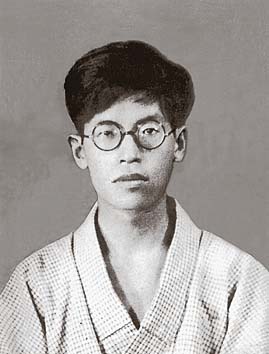 ⇒なかじま【中島】
ながしま‐いっき【長島一揆】
伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。
⇒ながしま【長島】
なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ
評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)
中島健蔵
撮影:石井幸之助
⇒なかじま【中島】
ながしま‐いっき【長島一揆】
伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。
⇒ながしま【長島】
なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ
評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)
中島健蔵
撮影:石井幸之助
 ⇒なかじま【中島】
なかじま‐そういん【中島棕隠】
江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨
⇒なかじま【中島】
なかじま‐そういん【中島棕隠】
江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨な‐がくし【名隠し】🔗⭐🔉
な‐がくし【名隠し】
①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」
②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。
○名が通るながとおる🔗⭐🔉
○名が通るながとおる
有名になる。世間によく知られる。「世界的に名の通った人」
⇒な【名】
なが‐ときん【長頭巾】
頭巾の長く垂れ下がったもの。
なが‐とこ【長床】
①寺院などで、板敷の上に一段高く畳を敷いたところ。栄華物語本雫「寺房の―のやうに」
②神社の拝殿または拝殿の脇にある建物。村の会所に使用。
なか‐とじ【中綴じ】‥トヂ
仮製本の一種。本文と表紙を一緒に丁合いし、真ん中の折り目の所を針金や糸で綴じ、3方を化粧裁ちする。週刊誌その他ページ数の少ない絵本・雑誌などに用いられる。
ながと‐たんだい【長門探題】
鎌倉幕府が長門に置いた統治機関。元の来襲に備えて長門守護に北条一門を任じ、権限を強化したもの。長門周防探題。→中国探題。
⇒ながと【長門】
なが‐との【長殿】
古代の倉庫の一種。数戸の倉庫を一棟に長く続けて造ったもの。特に大蔵省のものを指し、諸国からの貢納物を収めた。ながくら。→大内裏(図)
なが‐とのい【長宿直】‥トノヰ
幾日も続いて宿直すること。
なが‐とば【長苫】
(関東・静岡地方で)漁夫が陸で着る長着物。転じて、漁夫が病気などで長く休むこと。
なか‐とびら【中扉】
本の中仕切りの扉。特に洋装本で、おのおの独立している数編の本文を一冊本に仕立てる場合、各編の前に区切りとして付ける扉。
なかとみ【中臣】
古代の氏族。天児屋根命あまのこやねのみことの子孫と称し、朝廷の祭祀を担当。はじめ中臣連むらじ、後に中臣朝臣、さらに大中臣朝臣となる。なお、中臣鎌足は藤原と賜姓され、その子孫は中臣氏と分かれて藤原氏となった。
⇒なかとみ‐の‐かまこ【中臣鎌子】
⇒なかとみ‐の‐はらえ【中臣の祓】
⇒なかとみのはらえ‐くんかい【中臣祓訓解】
⇒なかとみ‐の‐よごと【中臣寿詞】
なかとみ‐の‐かまこ【中臣鎌子】
藤原鎌足ふじわらのかまたりの初名。
⇒なかとみ【中臣】
なかとみ‐の‐はらえ【中臣の祓】‥ハラヘ
(大祓おおはらえの儀は中臣氏が中心となって奉仕したからいう)(→)大祓に同じ。
⇒なかとみ【中臣】
なかとみのはらえ‐くんかい【中臣祓訓解】‥ハラヘ‥
平安末期頃に作られた神道書。1巻。空海に仮託される。中臣の祓(大祓詞)に両部神道の立場で注釈を加えたもの。
⇒なかとみ【中臣】
なかとみ‐の‐よごと【中臣寿詞】
天皇践祚せんそまたは大嘗祭だいじょうさいに、中臣氏が上奏した祝詞。天神寿詞あまつかみのよごと。
⇒なかとみ【中臣】
なか‐とり【中取り】
「中取り案つくえ」の略。食器を載せ、または綿などを積む台。宇津保物語俊蔭「蘇芳の脚つけたる―三つに東絹つみて」
なか‐どり【中取り】
①双方の間にいて横どりすること。中に立って手数料などをとること。浄瑠璃、生玉心中「―したと思はれては出入りがならぬ」
②女髪結いの助手で、下梳したすきよりは上のもの。
ながとろ【長瀞】
埼玉県秩父郡北東部の名勝地。荒川の渓谷に沿い、灰緑色の結晶片岩の板状節理が水食によってあらわれ、独特の峡谷美を形成。
長瀞
撮影:山梨勝弘
 なが‐な【長縄】
延縄はえなわのこと。
なか‐なおし【中直し】‥ナホシ
①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」
②(→)上美濃に同じ。
なか‐なおり【中直り】‥ナホリ
①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。
②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。
なか‐なか【中中】
[一]〔名・副〕
①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」
②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」
③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」
④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」
⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」
[二]〔感〕
(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」
⇒中中でもない
なが‐なが【長長】
①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」
②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」
ながなが‐し・い【長長しい】
〔形〕[文]ながなが・し(シク)
非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」
なが‐な【長縄】
延縄はえなわのこと。
なか‐なおし【中直し】‥ナホシ
①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」
②(→)上美濃に同じ。
なか‐なおり【中直り】‥ナホリ
①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。
②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。
なか‐なか【中中】
[一]〔名・副〕
①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」
②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」
③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」
④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」
⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」
[二]〔感〕
(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」
⇒中中でもない
なが‐なが【長長】
①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」
②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」
ながなが‐し・い【長長しい】
〔形〕[文]ながなが・し(シク)
非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」
 なが‐な【長縄】
延縄はえなわのこと。
なか‐なおし【中直し】‥ナホシ
①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」
②(→)上美濃に同じ。
なか‐なおり【中直り】‥ナホリ
①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。
②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。
なか‐なか【中中】
[一]〔名・副〕
①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」
②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」
③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」
④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」
⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」
[二]〔感〕
(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」
⇒中中でもない
なが‐なが【長長】
①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」
②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」
ながなが‐し・い【長長しい】
〔形〕[文]ながなが・し(シク)
非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」
なが‐な【長縄】
延縄はえなわのこと。
なか‐なおし【中直し】‥ナホシ
①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」
②(→)上美濃に同じ。
なか‐なおり【中直り】‥ナホリ
①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。
②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。
なか‐なか【中中】
[一]〔名・副〕
①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」
②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」
③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」
④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」
⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」
[二]〔感〕
(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」
⇒中中でもない
なが‐なが【長長】
①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」
②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」
ながなが‐し・い【長長しい】
〔形〕[文]ながなが・し(シク)
非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」
なごえ‐りゅう【名越流】‥リウ🔗⭐🔉
なごえ‐りゅう【名越流】‥リウ
浄土宗鎮西派六流の一つ。良忠の門下の尊観(1239〜1316)を流祖とし、鎌倉名越の善導寺に住して教えを弘めたからいう。善導寺流。
な‐ごし【夏越・名越】🔗⭐🔉
な‐ごし【夏越・名越】
「夏越の祓」の略。〈[季]夏〉。忠見集「みな月の―はらふるかみのごと」
⇒なごし‐の‐かぐら【夏越の神楽】
⇒なごし‐の‐せっく【夏越の節供】
⇒なごし‐の‐つき【夏越の月】
⇒なごし‐の‐はらえ【夏越の祓】
⇒なごし‐の‐みそぎ【夏越の御禊】
な‐さか【名さか】🔗⭐🔉
な‐さか【名さか】
汚名。悪評。多く、「―の立つ」の形で用いられる。浄瑠璃、桂川連理柵「お半女郎と二人の―立たぬ様にと」
な‐だいめん【名対面・名謁】🔗⭐🔉
な‐だいめん【名対面・名謁】
①供奉ぐぶ・宿直の官人がその名を問われて名乗ること。特に禁中で、夜の亥いの刻に、宿直勤番の殿上人・滝口などが点呼のため氏名を問われて名乗ること。なだめし。みょうえつ。宿直奏とのいもうし。問籍もんじゃく。枕草子56「殿上の―こそなほをかしけれ」
②戦場で互いに名乗り合うこと。源平盛衰記41「互ひに―して散々に射死ころしぬる者もあり」
な‐だめし【名謁】🔗⭐🔉
な‐だめし【名謁】
(→)名対面なだいめん1に同じ。
○名に負うなにおう🔗⭐🔉
○名に負うなにおう
①名として負い持っている。古事記下「かくのごと名に負はむとそらみつ大和の国を蜻蛉島あきずしまとふ」
②かねて聞いているところと違わない。名前どおりである。古今和歌集雑「かんな月しぐれふりおける楢の葉の―宮のふるごとぞこれ」
③名高い。有名である。万葉集1「紀路にありとふ―背の山」
⇒な【名】
なに‐か【何彼】
何やかや。あれこれ。宇治拾遺物語6「顔よりはじめ、着たる物・馬、―にいたるまで」
⇒なにか‐と【何彼と】
⇒なにか‐なし【何彼無し】
⇒何彼につけ
なに‐か【何か】
①(代名詞的に)
㋐内容が不定・未知の物事を指すのに用いる語。万葉集5「明日は来なむを―障さやれる」。「―がある」「―欲しい」
㋑不定の多くのものを指すのに用いる語。
②(副詞的に)
㋐(原因・理由を疑う)なぜ…か。万葉集8「ほととぎす…―来鳴かぬ」
㋑(自責・詰問の意を含む)どうして…か。万葉集10「かくしあらば―植ゑけむ」
㋒(反語の意を表す)どうして…か。万葉集4「風をだに来むとし待たば―嘆かむ」
㋓(理由や程度の不明を表す)どうしてか。なぜか。「―悲しい」
③(感動詞的に)前に語られた内容と反対のことを言う語。いやいや。どうしてどうして。源氏物語帚木「心にくくおしはからるるなり。されど―。…心に及ばずいとゆかしきこともなしや」
⇒何かせむ
⇒何かと言えば
なに‐が【何が】
①(下に推量の語句を伴い、疑問・反語の意を表す)何も…ない。「―惜しかろう」
②(「何がさて」の略)何しろ。狂言、素襖落「―大盃で突つかけ突つかけ下されてござれば」
なにがかのじょをそうさせたか【何が彼女をさうさせたか】‥ヂヨ‥サウ‥
藤森成吉作の戯曲。1927年発表。同年検閲により「彼女」と改題し、土方与志演出・山本安英主演により築地小劇場で上演。
なに‐が‐さて【何がさて】
①(他をさしおき、これだけはと強調する)何はともあれ。とにかく。狂言、附子ぶす「―ゆるりとゐて話さうとも」
②(相手の言葉をうけ、ある事柄を強く主張する)いかにも。もちろん。狂言、末広がり「都にはあらうか。―広い都でござるによつて、都にはござりませう」
なに‐がし【某・何某】
〔代〕
①人または物事・場所などの名および数量がはっきりしないか、または、わざとぼんやりという時に用いる語。源氏物語夕顔「―の阿闍梨あじゃり」。「小川―」「―かの金銭」
②(一人称)おのれ。それがし。男性がへりくだっていう。源氏物語帚木「―よりはじめて」
⇒なにがし‐かがし【何某彼某】
⇒なにがし‐くれがし【何某呉某】
⇒なにがし‐それがし【何某某】
なにがし‐かがし【何某彼某】
(→)「なにがしくれがし」に同じ。→かがし。
⇒なに‐がし【某・何某】
なにがし‐くれがし【何某呉某】
だれそれ。なにがしそれがし。源氏物語夕顔「―とかぞへしは頭中将の随身」
⇒なに‐がし【某・何某】
なにがし‐それがし【何某某】
(→)「なにがしくれがし」に同じ。
⇒なに‐がし【某・何某】
なに‐か‐しら【何か知ら】
(「何か知らん(ぬ)」の略)
①何かわからない、あること。なにか。「―考え込んでいる」
②(副詞的に)何かわからないが。どことなく。「―うさんくさい」
○名に聞くなにきく🔗⭐🔉
○名に聞くなにきく
うわさに聞く。音にきく。土佐日記「まことにて―ところ羽根ならば飛ぶがごとくに都へもがな」
⇒な【名】
なに‐くそ【何糞】
〔感〕
自分の気持を奮い立たせる時に発する語。「―、負けてたまるか」
なに‐くれ【何くれ】
(人や事物を明示せずに、列挙する場合にいう)だれかれ。何やかや。あれこれ。源氏物語葵「山の座主、―やむ事なき僧ども」。「―と面倒をみる」
⇒なにくれ‐と‐なく【何くれと無く】
なにくれ‐と‐なく【何くれと無く】
何と定まったこともなく、いろいろと。なにやかやと。「―世話をやく」
⇒なに‐くれ【何くれ】
なに‐くわぬ‐かお【何食わぬ顔】‥クハヌカホ
何も知らないといった顔。そしらぬ顔。「―で嘘うそをつく」
なにげ‐な・い【何気無い】
〔形〕[文]なにげな・し(ク)
これといった特別の意図もない。特に注意せず、関心を示さない。さりげない。「―・く空を仰ぐ」「―・い風ふうをよそおう」
なにげ‐に【何気に】
「何気無い」の連用修飾の形として「何気無く」「何気無しに」というところを、1980年代から、誤って使われ始めた語形。
なに‐ごこち【何心地】
①どんな気持。古今和歌集別「惜しむから恋しきものを白雲の立ちなむのちは―せむ」
②どんな病気。源氏物語東屋「―ともおぼえ侍らず、ただいと苦しく侍り」
なに‐ごころ【何心】
どういう心。どういう考え。源氏物語若紫「―ありて海の底まで深う思ひ入るらむ」
⇒なにごころ‐な・い【何心無い】
なにごころ‐な・い【何心無い】
〔形〕[文]なにごころな・し(ク)
何の気もない。無心だ。なにげない。源氏物語空蝉「若き人は―・くいとようまどろみたるべし」
⇒なに‐ごころ【何心】
なに‐ごと【何事】
①何ということがら。どんなことがら。万葉集10「妹と吾と―あれそ紐解かずあらむ」。「―が起こったか」
②あらゆることがら。何もかも。万事。源氏物語桐壺「―の儀式をももてなし給ひけれど」。「―も我慢が大事」
③とがめる気持などにいう。なんとしたこと。源氏物語若紫「―ぞや、わらはべと腹だち給へるか」。「その醜態は―だ」
④(不定のことがらを指していう)なになに。徒然草「―の式といふことは後嵯峨の御代までは言はざりけるを」
なに‐さ【何さ】
〔感〕
相手の言動に反発して言う語。主に女性が用いる。「―、言い訳ばかりして」
なに‐さま【何様】
[一]〔名〕
①どういうふう。どのよう。太平記10「傍輩―腹切討死してみゆるか」
②(多くの皮肉や反語に用いる)たれそれ様といった高貴な人。名門の出。「―ではあるまいし」
[二]〔副〕
いかにも。なるほど。まったく。義経記5「音声の聞き事かな。―只人にてはなし」。「―かなわぬ」
なに‐ざま【何方】
どういう方面。源氏物語末摘花「―の事ぞ」
○名にし負うなにしおう🔗⭐🔉
○名にし負うなにしおう
(シは強めの助詞)「名に負う」を強めたもの。古今和歌集旅「名にし負はばいざこととはむ都鳥」
⇒な【名】
な‐に‐し‐おう【名にし負う】‥オフ
⇒な(名)(成句)
なに‐し‐か【何しか】
(シは強めの助詞)どうして…か。万葉集12「今更に―思はむ」
⇒なにしか‐も【何しかも】
なにしか‐も【何しかも】
どうしてまあ…なのか。万葉集8「―ここだく恋ふる」
⇒なに‐し‐か【何しか】
なに‐し‐に【何為に】
①何をするために。何用で。源氏物語若菜下「―参りつらむ」
②何ゆえに。なぜ。落窪物語2「―部屋におしこめて」
③(反語の意)何としてか。どうしてか。竹取物語「―悲しきに見送り奉らむ」
なに‐しろ【何しろ】
〔副〕
(シロはス(為)ルの命令形。他のことは一応別にして、これだけは強調したいという気持を表す)なんにしても。なににせよ。とにかく。「―忙しいので休む暇がない」
な‐に‐し‐おう【名にし負う】‥オフ🔗⭐🔉
な‐に‐し‐おう【名にし負う】‥オフ
⇒な(名)(成句)
○名に背くなにそむく🔗⭐🔉
○名に背くなにそむく
名声に反した行いをする。「名門の―」
⇒な【名】
○名に立つなにたつ🔗⭐🔉
○名に立つなにたつ
うわさに立つ。有名になる。古今和歌集春「あだなりと名にこそ立てれ桜花」
⇒な【名】
なに‐と【何と】
①(副詞的に)
㋐なにとて。なぜ。続古今和歌集雑「―憂き世にむすぼほるらむ」
㋑どのように。いかが。狂言、烏帽子折「出仕にあがらうと思ふが―あらうぞ」
②(感動詞的に)
㋐(念をおして問いかえす時にいう語)なんだと。なに。謡曲、烏帽子折「えい―、―」
㋑(言いかけて相談する時に用いる)いかに。どうじゃ。狂言、烏帽子折「やい、して―」
③(助詞的に)など。なりと。土佐日記「これかれ酒―もて」→など
なに‐と‐か‐して【何とかして】
①何としてか。どうしたわけか。狂言、膏薬煉「―取り放ちけむ」
②何とか手を尽くして。どうにかして。なんとかして。
なに‐と‐かは【何とかは】
①(疑問の意)どのように…か。源氏物語椎本「松の雪をも―見る」
②(反語の意)どうして…か。源氏物語初音「つれなき人の御心をば―見たてまつりとがめむ」
なに‐と‐かも【何とかも】
どうしてかまあ。孝徳紀「―愛うつくし妹がまた咲き出で来ぬ」
なに‐どき【何時】
いつ。いつごろ。なんどき。和泉式部続集「鳥のねに驚かされし時は―」
なに‐と‐した【何とした】
どうした。どうしたらよい。狂言、佐渡狐「合点の行かぬ顔つきであつたが、―ものであらうぞ」
なに‐と‐して【何として】
①どのような具合に。続古今和歌集雑「―心のとまる月になるらむ」
②どうして。なぜ。新後撰和歌集雑「―うき身ひとつの残るらむ」
③なんのために。謡曲、七騎落「此の者をば、―召し連れられて候ふぞ」
④どういう方法で。どうやって。狂言、武悪「道具もないが―取るぞ」
⑤(反語の意)どうしてどうして。狂言、鬼の継子「身共が為にもまま子ぢや物を―喰ふ物ぢや」
なに‐と‐ぞ【何卒】
〔副〕
①何とかして。どうにかして。狂言、枕物狂「相談致し―ならう事ならばかなへて進ぜうと存ずる」
②相手に強く願う気持を表す語。どうか。どうぞ。ぜひ。「―よろしく」
なに‐と‐て【何とて】
何として。どうして。なぜ。更級日記「闇にくれたる姨捨に―こよひ尋ねきつらむ」
なに‐と‐なし【何と無し】
①なぜということもない。どこともない。枕草子5「何となくすずろにをかしきに」
②何と取り立てていう程のことはない。平凡である。能因本枕草子木の花は「卯の花は品劣りて何となけれど」
③何と定まったことがない。何につけてもである。太平記1「天下の事何となく関東の計らひとして」
④何という目的もない。何とない。狂言、土産の鏡「何となく鏡を見れば」
なに‐と‐には‐なし【何とには無し】
なんということはない。たいしたことでない。
なに‐と‐は‐なし【何とは無し】
(→)「なにとにはなし」に同じ。源氏物語鈴虫「何とはなけれど過ぐる齢にそへて忘れぬ昔の御物語などうけたまはり」
なに‐とも【何とも】
〔副〕
①何のものとも。物の数とも。なんとも。源氏物語若紫「今日あすになりぬる命をば―おぼしたらで」
②どうとも。一向に。更に。宇治拾遺物語12「衆中にてかくいふことを―答へざらむも口をし」
③何分にも。はやどうも。狂言、貰聟「婿入を致さぬによつて―参りにくうござる」
④あらゆる方法で。どうやっても。三道「―風体を巧みて」
なに‐と‐や‐らむ【何とやらむ】
①なんであろうか。平家物語(延慶本)「漫々たる海上に―はたらく物あり」
②なんとなく。謡曲、船弁慶「―今の時節然るべからず存じ候」
○名に流るなにながる🔗⭐🔉
○名に流るなにながる
その名で世の中に知られる。名高くなる。後撰和歌集雑「うつろはぬ名に流れたる川竹の」
⇒な【名】
なに‐なに【何何】
[一]〔代〕
列挙する事物が不明な時、また、具体的に挙げる必要のない時にいう語。何と何。どれそれ。「必要なものは―ですか」
[二]〔感〕
①(文を読みはじめる時や、相手の言葉に問いかける時に発する語)何事か。何だ何だ。狂言、地蔵舞「―、往来の者に宿貸すこと禁制」
②特にとりあげるほどのことではないと否定する思いで発する語。「―、心配はいらない」
なに‐なら‐ず【何ならず】
①なんというほどでもない。取るに足りない。源氏物語夕顔「なにならぬ御名のりを聞え給はむ」
②何にもならない。役に立たない。平家物語4「かかるめでたき聖跡なれども、今は―」
なに‐に【何に】
何のために。源氏物語末摘花「―のこりなう見あらはしつらん」
○名に旧るなにふる🔗⭐🔉
○名に旧るなにふる
古くからその名が聞こえる。続後撰和歌集秋「秋の行く山は手向けの名にふりて」
⇒な【名】
なに‐ぶん【何分】
[一]〔名〕
いくらか。なんらか。「―の寄付」「―の処置」
[二]〔副〕
①どうも。何といっても。「―年寄りなので」
②なにとぞ。どうか。「―よろしく」
⇒なにぶん‐にも【何分にも】
なにぶん‐にも【何分にも】
〔副〕
(「何分」を強めたいい方)何といっても。「―まだ子供ですから」
⇒なに‐ぶん【何分】
なに‐へん‐とも‐なし【何へんとも無し】
どうということもない。とりたてていうほどもない。醒睡笑「何へんともなき者ども、三人つれだち清水へ参り」
なに‐ほど【何程】
①どれほど。どのくらい。いかほど。狂言、鐘の音「鐘のねをきいてきたか―するぞ」
②どんなに。いかに。「―欲しがっても」
③(否定・反語の表現に用いて)程度が問題にならない、取るに足りない意を表す。「―のことがあろうか」
なにも【汝妹】
(ナノイモの約。ナは我の意)男から女を親しんでいう語。古事記上「愛うつくしき我が―の命」↔なせ
なに‐も【何も】
①㋐どういう物事も。何でも。みな。平家物語8「―あたらしき物を無塩といふと心得て」
㋑(打消を伴って)少しも。全く。「―見えない」
㋒(「…も―」の形で)なにもかも。それを含めてみんな。「ノートも―忘れてきた」
②(打消の語を伴って)どういう事が原因であるにしろ。取り立てて。「―そんなに泣かなくてもよかろう」
なに‐も‐か‐も【何も彼も】
何事も。すべて。今昔物語集30「―残さず」。「―うまくいった」
なに‐もの【何物】
どういう物。何という物。なに。「厄介以外の―でもない」「芸術の―なるかを解さない」
なに‐もの【何者】
どういう人。何という人。なにびと。
なに‐や‐か‐や【何や彼や】
あれやこれや。いろいろさまざま。「―用事があって忙しい」
なに‐やつ【何奴】
どういうやつ。どいつ。
なに‐やら【何やら】
①何であろうか。狂言、末広がり「田舎者とみえて―わつぱと申す」
②なんとなく。なんだか。野ざらし紀行「山路来て―ゆかしすみれ草」(芭蕉)
なに‐ゆえ【何故】‥ユヱ
どういうわけ。なんのため。なぜ。「―失敗したのか」
なに‐より【何より】
①どんなものよりも。いかなる物事よりも。「お目にかかれて―うれしい」
②何よりよいこと。何よりすぐれていること。「―の品」「無事で―だ」
なに‐ら【何等】
〔副〕
①どのような。どういう。「―のことを知らんと欲するか」
②少しも。なんら。
なにわ【難波・浪速・浪花】ナニハ
(一説に「魚な庭にわ」の意という)大阪市およびその付近の古称。
⇒なにわ‐え【難波江】
⇒なにわ‐おどり【浪花踊】
⇒なにわ‐がた【難波潟】
⇒なにわ‐ぐさ【難波草】
⇒なにわ‐じょうるり【難波浄瑠璃】
⇒なにわ‐すががさ【難波菅笠】
⇒なにわ‐づ【難波津】
⇒なにわ‐でら【難波寺】
⇒なにわ‐と【難波門】
⇒なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】
⇒なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】
⇒なにわ‐の‐みや【難波宮】
⇒なにわ‐ばし【難波橋】
⇒なにわ‐ぶし【浪花節】
⇒なにわぶし‐しばい【浪花節芝居】
⇒なにわぶし‐てき【浪花節的】
⇒なにわ‐やき【難波焼】
⇒難波の葦は伊勢の浜荻
なにわ‐え【難波江】ナニハ‥
大阪市付近の海面の古称。難波潟。
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐おどり【浪花踊】ナニハヲドリ
大阪の芸者が演ずる春の踊り。曾根崎新地の北陽浪速踊(明治15年創始)と新町の浪花踊(明治41年創始)とがある。
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐がた【難波潟】ナニハ‥
(→)難波江に同じ。万葉集2「―潮干ありそね」
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐ぐさ【難波草】ナニハ‥
(「難波の葦あしは伊勢の浜荻」のたとえから)葦の異称。日葡辞書「ナニワグサ…即ち、アシ」
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なに‐わざ【何業】
どういうわざ。どんなこと。源氏物語槿「取り立てて―をもし給はむは」
なにわ‐じょうるり【難波浄瑠璃】ナニハジヤウ‥
大坂地方に起こって流行した浄瑠璃節。井上播磨掾はりまのじょうの起こした播磨節をはじめ、文弥節などがあり、竹本義太夫の始めた義太夫節に至って最も盛んに行われた。→江戸浄瑠璃→京浄瑠璃。
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐すががさ【難波菅笠】ナニハ‥
難波産のスゲで作った笠。
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐づ【難波津】ナニハ‥
①難波江の要津。古代には、今の大阪城付近まで海が入りこんでいたので、各所に船瀬ふなせを造り、瀬戸内海へ出る港としていた。
②古今集仮名序に手習の初めに学ぶとある歌。すなわち「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」をいう。王仁わにの作という伝説があり、奈良時代にすでに手習に用いられていた。
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐でら【難波寺】ナニハ‥
大阪の四天王寺の別称。
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
なにわ‐と【難波門】ナニハ‥
難波の港。万葉集20「―を漕ぎ出て見れば」
⇒なにわ【難波・浪速・浪花】
な‐の‐あそん【名の朝臣】🔗⭐🔉
な‐の‐あそん【名の朝臣】
上卿が五位を召す時、その人の名を、朝臣を付けて「藤原朝臣某」のように呼んだこと。
な‐の‐かたみ【名の形見】🔗⭐🔉
な‐の‐かたみ【名の形見】
名声が形見として後世に残ること。謡曲、源氏供養「亡き跡までの筆のすさび―とはなりたれども」
な‐の‐き【名の木】🔗⭐🔉
な‐の‐き【名の木】
①名のある香木。名木めいぼく。
②俳諧で、楓・柳などの名高い木の称。
○名の無い星は宵から出るなのないほしはよいからでる🔗⭐🔉
○名の無い星は宵から出るなのないほしはよいからでる
つまらないものが先に出ることのたとえ。
⇒な【名】
な‐の‐はな【菜の花】
アブラナの花。また、アブラナ。〈[季]春〉。続明烏「―や月は東に日は西に」(蕪村)。「―畑」
な‐の‐ふう【名の封】
文書の上紙などの封じ目に差出人の名を記すこと。源氏物語橋姫「彼の御―つきたり」
なのめ【斜め】
①(→)「ななめ」に同じ。
②際立たないこと。ありふれていること。普通。源氏物語浮舟「人のもどきあるまじく、―にてこそ良からめ」
③通り一遍。枕草子262「世を―に書き流したることばのにくきこそ」
④(→)「なのめならず」に同じ。謡曲、烏帽子折「帝―に思し召し」
⇒斜めならず
な‐の‐ふう【名の封】🔗⭐🔉
な‐の‐ふう【名の封】
文書の上紙などの封じ目に差出人の名を記すこと。源氏物語橋姫「彼の御―つきたり」
な‐の‐ろく【名の禄】🔗⭐🔉
な‐の‐ろく【名の禄】
律令制で、妃ひ・夫人・嬪ひんなどの名号に応じて支給された季禄。号禄。
○名は実の賓なはじつのひん🔗⭐🔉
○名は実の賓なはじつのひん
[荘子逍遥遊]実際の徳が主で名誉は従であること。実際の徳があってはじめて名誉がこれに伴う。
⇒な【名】
○名は体を表すなはたいをあらわす🔗⭐🔉
○名は体を表すなはたいをあらわす
名はその実体がどのような物かを示している。名と実体とはうまく合っている。
⇒な【名】
なばたけ‐いせき【菜畑遺跡】‥ヰ‥
佐賀県唐津市にある縄文時代から弥生時代の遺跡。縄文晩期後半の水田跡・炭化米・農耕具などが1980年代に発見され、水田稲作開始の論議をよんだ。
な‐ばな【菜花】
食用にするアブラナの葉やつぼみ。かき菜。
なばり【隠】
なばること。かくれること。万葉集1「暮よいにあひて朝あした面おも無み―(地名「名張」にかける)にか」
なばり【名張】
①伊賀国の旧郡名。伊勢・大和に接する。天武紀上「夜半に及いたりて隠郡なばりのこおりに到りて」
②三重県西部、上野盆地の南部にある市。上代より街道の宿駅として栄える。名勝赤目四十八滝がある。人口8万2千。
なはる
〔助動〕
(活用は四段型)「なさる」の転。「お上がりなはれ」
なば・る【隠る】
〔自四〕
かくれる。
な‐はん【名判】
①氏名と印判。
②かきはん。花押かおう。
なはん
〔助詞〕
(終助詞。岩手県で)ね。「かわいそうだ―」
な‐び【儺火】
小正月の1月15日に、正月の飾り物を焼き、邪気を払った行事。左義長さぎちょうはこの名残りかという。蜻蛉日記下「十五日―あり」
ナビ
ナビゲーター・ナビゲーションの略。
なびか・う【靡かふ】ナビカフ
〔自四〕
(ナビクに接尾語フの付いた語)しきりになびく。なびき続ける。万葉集2「玉藻なすか寄りかく寄り―・ひし」
なびか・す【靡かす】
〔他五〕
①なびくようにする。万葉集15「玉藻―・し漕ぎ出なむ君がみ船を」
②服従させる。討ち平らげる。源氏物語賢木「天の下を―・し給へるさま」。太平記5「逆徒の大軍をば―・しぬるぞ」
なびき【靡き】
①なびくこと。なびいたこと。万葉集2「捧げたる旗の―は」
②風になびいて反ったような形の旗指物はたさしもの。
⇒なびき‐がお【靡き顔】
⇒なびき‐ざま【靡き様】
⇒なびき‐ば【靡き葉】
⇒なびき‐も【靡き藻】
⇒なびき‐やす【靡き易】
なびき‐がお【靡き顔】‥ガホ
他人の意に従うような様子。源氏物語行幸「人の御言に―にて許してむとおぼす」
⇒なびき【靡き】
なびき‐ざま【靡き様】
なびく様子。源氏物語総角「木草の―も殊に見なされて」
⇒なびき【靡き】
なびき・ぬ【靡き寝】
〔自下二〕
寄り添って寝る。共寝する。万葉集2「玉藻なす―・ねし児を」
なびき‐ば【靡き葉】
風などになびいている葉。夫木和歌抄9「池の蓮の―に露ふきわたす風ぞ涼しき」
⇒なびき【靡き】
なびき‐も【靡き藻】
水のままに靡く藻。万葉集11「紫の名高の浦の―の」
⇒なびき【靡き】
なびき‐やす【靡き易】
従いやすい有様。源氏物語椎本「心軽うて―なるなど」
⇒なびき【靡き】
なび・く【靡く】
[一]〔自五〕
①風・水などに押されて横に伏す。万葉集2「妹が門見む―・けこの山」。万葉集12「浪の共むた―・く珠藻の」。源氏物語明石「藻塩焼くけぶりは同じ方に―・かむ」。「旗が風に―・く」
②他人の威力・意志などに従う。魅力にひかれて、心を移す。万葉集11「さ寝ぬがには誰とも寝めど沖つ藻の―・きし君が言待つ我を」。源氏物語帚木「上は下に助けられ、下は上に―・きて」。「強い方に―・く」
[二]〔他下二〕
①風・水などの勢いに従って横に伏すようにする。なびかせる。万葉集9「響矢なりやもち鹿か取り―・けし坂の上にそある」
②従わせる。服従させる。太平記6「和泉・河内の両国を―・けて」。好色一代女3「それよりしのびしのびに旦那を―・けて」
ナビゲーション【navigation】
①航海。航空。また、航海術。航空術。
②自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向を指示すること。
ナビゲーター【navigator】
①航海士。航空士。
②(→)ラリー3などで、運転者に道筋や速度などの指示を出す同乗者。
③案内役。進行役。
④航空機やミサイルの進路を自動調整する装置。
な‐びと【汝人】
〔代〕
(ナヒトとも)なんじ。お前。允恭紀「能く そのを作るや、―」→な(己・汝)
ナビ‐は【ナビ派】
(les Nabis フランス 預言者の意のヘブライ語に由来)19世紀末、フランスの画派の一つ。セリュジエ(P. Sérusier1864〜1927)・ドニ・ボナールらがゴーガンの影響を受けて結成。神秘的・象徴的・装飾的画風を示す。ポスター・デザインなどにも活躍。
なび‐やか
しなやか。なよやか。なびらか。散木奇歌集「草のはがひも末―に」。六条宰相家歌合「言葉使ひなど―ならず」
なびやか・し
〔形シク〕
なびやかである。しなやかである。
なび‐らか
(→)「なびやか」に同じ。毎月抄「ふとみほそみもなく―に聞きにくからぬやうによみなすがきはめて重事にて侍るなり」
な‐びらき【名開き】
赤子の命名の儀礼。普通は生まれて7日目に行う。名付け親をとり、名を紙に書いて床の間・神棚に掲げ、祝宴を張る。
な‐びろう【名披露】
(→)「なびろめ」に同じ。
な‐びろめ【名広め・名披露目】
芸人が芸名を得た時、または商人が開店の時、その名を世間に披露すること。
な・ぶ【並ぶ】
〔他下二〕
ならべる。つらねる。古事記中「日々かが―・べて夜には九夜ここのよ日には十日を」
な・ぶ【靡ぶ】
〔他下二〕
なびかせる。万葉集1「旗すすき小竹しのをおし―・べ」
ナフキン
ナプキンの訛。
ナプキン【napkin】
①食事時に胸や膝にかけたり口や手を拭ったりする布巾。紙製もある。
②生理用品の一つ。
ナフサ【naphtha】
原油を蒸留するとき、ガソリンの沸点範囲であるセ氏25〜200度で留出する部分。沸点100度以下の軽質ナフサと80〜200度の重質ナフサとに分ける。軽質ナフサは熱分解によりエチレン・プロピレンなどの石油化学原料が得られ、重質ナフサは接触改質によりガソリンが製造される。
なふさ‐なふさ
〔副〕
⇒のうさのうさ
ナプス【NAPS】
(Numerical Analysis and Prediction System)数値解析予報システム。気象庁に設置するスーパー‐コンピューターを主軸として数値解析と数値予報を行うコンピューター‐システムで、気象予報以外に海洋に関する諸計算も行う。→コスメッツ→アデス
ナフタ【NAFTA】
(North American Free Trade Agreement)北米自由貿易協定。アメリカ・カナダ・メキシコの3国間で相互に市場を開放するための協定。1992年調印、94年発効。
な‐ふだ【名札】
名を記したふだ。また名刺。福地桜痴、もしや草紙「乗客は衣嚢ポッケットから名刺なふだを出し、御在宅なら御目に掛らうと申込む」。「胸に―をつける」
ナフダトゥル‐ウラマー【Nahdatul Ulama】
(「イスラム指導者の覚醒」の意)インドネシア最大のイスラム団体・政治組織。1926年結成。伝統的スンニ派イスラムを標榜。NU
ナフタリン【Naphthalin ドイツ】
(→)ナフタレンに同じ。
ナフタレン【naphthalene】
分子式C10H8 芳香族炭化水素の一つ。コールタールから分離される白色板状の結晶。石油の分解混合物中に含まれるアルキル‐ナフタレンの脱アルキルによっても製造される。常温で昇華し、特異の臭気がある。合成化学工業上の重要な原料。また、樟脳しょうのうの代用品として防虫・防臭用。ナフタリン。
ナフテン【naphthene】
原油の成分として含まれる飽和環式炭化水素(シクロ‐パラフィン)の総称。一般式CnH2n
ナフトール【Naphthol ドイツ】
分子式C10H7OH フェノール類の一つ。無色の針状結晶。フェノールに類似し、防腐剤として用いるほか、染料製造などの原料。「―染め」
な‐ぶら
(ナムラの訛)遊泳する魚の群れ。
なぶり【嬲り】
なぶること。もてあそぶこと。万葉集15「人―のみ好みたるらむ」
⇒なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
⇒なぶり‐だて【嬲り立て】
⇒なぶり‐もの【嬲り者】
なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
なぶって殺すこと。すぐに殺さずに苦しめ、もてあそんで殺すこと。
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐だて【嬲り立て】
なぶるさまをすること。出しゃばってからかうこと。狂言、蟹山伏「―しおつてはさまれおつて、あのなりは」
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐もの【嬲り者】
なぶる対象になるもの。なぶられるもの。
⇒なぶり【嬲り】
なぶ・る【嬲る】
〔他五〕
①責めさいなむ。いじめる。日本霊異記中「壮おとこ強ひて入り―・る」
②からかい、ひやかす。ばかにする。謡曲、橋弁慶「牛若彼を―・つてみんと」。「人前で―・られる」
③手でもてあそぶ。いじる。好色五人女4「くらまぎれに前髪を―・りて」
な‐へ
(ナはノの意の格助詞。ヘはウヘ(上)の約。活用語の連体形に付き、その状態と下に来る状態が並行することを表す)…と共に。…につれて。なへに。万葉集7「山河の瀬のなる―に弓月が岳に雲立ち渡る」。万葉集10「秋風の寒く吹く―吾が屋前やどの浅茅がもとに蟋蟀こおろぎ鳴くも」
なべ【鍋】
①(ナは肴、ヘは瓮の意)食物を煮たりいためたりする器。金属製または石製・陶製で、底が比較的浅く口が開き、蓋・把手・つるなどを付ける。〈新撰字鏡6〉
②鍋料理。鍋物。「寄せ―」「―をつつく」
③下女の通名。おなべ。
なべ‐がえし【鍋返し】‥ガヘシ
煮物の途中で鍋をふって材料の上下を入れ替え、味が行き渡るようにすること。
なべ‐がね【鍋鉄】
(鍋などを鋳るのに用いることから)銑鉄や鋳鉄の俗称。ずくてつ。
なべ‐かぶり【鍋被り】
①(→)筑摩祭つくままつりに同じ。〈[季]夏〉
②江戸中期頃の悪性の流行病の一つ。鼻から上が黒くなるもの。
③〔動〕ヒガラの異称。
なべ‐かま【鍋釜】
鍋と釜。炊事道具の代表。しばしば、生活に必要な最低限の道具の意に用いる。「―売っても嚊かか売るな」
⇒鍋釜が賑わう
そのを作るや、―」→な(己・汝)
ナビ‐は【ナビ派】
(les Nabis フランス 預言者の意のヘブライ語に由来)19世紀末、フランスの画派の一つ。セリュジエ(P. Sérusier1864〜1927)・ドニ・ボナールらがゴーガンの影響を受けて結成。神秘的・象徴的・装飾的画風を示す。ポスター・デザインなどにも活躍。
なび‐やか
しなやか。なよやか。なびらか。散木奇歌集「草のはがひも末―に」。六条宰相家歌合「言葉使ひなど―ならず」
なびやか・し
〔形シク〕
なびやかである。しなやかである。
なび‐らか
(→)「なびやか」に同じ。毎月抄「ふとみほそみもなく―に聞きにくからぬやうによみなすがきはめて重事にて侍るなり」
な‐びらき【名開き】
赤子の命名の儀礼。普通は生まれて7日目に行う。名付け親をとり、名を紙に書いて床の間・神棚に掲げ、祝宴を張る。
な‐びろう【名披露】
(→)「なびろめ」に同じ。
な‐びろめ【名広め・名披露目】
芸人が芸名を得た時、または商人が開店の時、その名を世間に披露すること。
な・ぶ【並ぶ】
〔他下二〕
ならべる。つらねる。古事記中「日々かが―・べて夜には九夜ここのよ日には十日を」
な・ぶ【靡ぶ】
〔他下二〕
なびかせる。万葉集1「旗すすき小竹しのをおし―・べ」
ナフキン
ナプキンの訛。
ナプキン【napkin】
①食事時に胸や膝にかけたり口や手を拭ったりする布巾。紙製もある。
②生理用品の一つ。
ナフサ【naphtha】
原油を蒸留するとき、ガソリンの沸点範囲であるセ氏25〜200度で留出する部分。沸点100度以下の軽質ナフサと80〜200度の重質ナフサとに分ける。軽質ナフサは熱分解によりエチレン・プロピレンなどの石油化学原料が得られ、重質ナフサは接触改質によりガソリンが製造される。
なふさ‐なふさ
〔副〕
⇒のうさのうさ
ナプス【NAPS】
(Numerical Analysis and Prediction System)数値解析予報システム。気象庁に設置するスーパー‐コンピューターを主軸として数値解析と数値予報を行うコンピューター‐システムで、気象予報以外に海洋に関する諸計算も行う。→コスメッツ→アデス
ナフタ【NAFTA】
(North American Free Trade Agreement)北米自由貿易協定。アメリカ・カナダ・メキシコの3国間で相互に市場を開放するための協定。1992年調印、94年発効。
な‐ふだ【名札】
名を記したふだ。また名刺。福地桜痴、もしや草紙「乗客は衣嚢ポッケットから名刺なふだを出し、御在宅なら御目に掛らうと申込む」。「胸に―をつける」
ナフダトゥル‐ウラマー【Nahdatul Ulama】
(「イスラム指導者の覚醒」の意)インドネシア最大のイスラム団体・政治組織。1926年結成。伝統的スンニ派イスラムを標榜。NU
ナフタリン【Naphthalin ドイツ】
(→)ナフタレンに同じ。
ナフタレン【naphthalene】
分子式C10H8 芳香族炭化水素の一つ。コールタールから分離される白色板状の結晶。石油の分解混合物中に含まれるアルキル‐ナフタレンの脱アルキルによっても製造される。常温で昇華し、特異の臭気がある。合成化学工業上の重要な原料。また、樟脳しょうのうの代用品として防虫・防臭用。ナフタリン。
ナフテン【naphthene】
原油の成分として含まれる飽和環式炭化水素(シクロ‐パラフィン)の総称。一般式CnH2n
ナフトール【Naphthol ドイツ】
分子式C10H7OH フェノール類の一つ。無色の針状結晶。フェノールに類似し、防腐剤として用いるほか、染料製造などの原料。「―染め」
な‐ぶら
(ナムラの訛)遊泳する魚の群れ。
なぶり【嬲り】
なぶること。もてあそぶこと。万葉集15「人―のみ好みたるらむ」
⇒なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
⇒なぶり‐だて【嬲り立て】
⇒なぶり‐もの【嬲り者】
なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
なぶって殺すこと。すぐに殺さずに苦しめ、もてあそんで殺すこと。
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐だて【嬲り立て】
なぶるさまをすること。出しゃばってからかうこと。狂言、蟹山伏「―しおつてはさまれおつて、あのなりは」
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐もの【嬲り者】
なぶる対象になるもの。なぶられるもの。
⇒なぶり【嬲り】
なぶ・る【嬲る】
〔他五〕
①責めさいなむ。いじめる。日本霊異記中「壮おとこ強ひて入り―・る」
②からかい、ひやかす。ばかにする。謡曲、橋弁慶「牛若彼を―・つてみんと」。「人前で―・られる」
③手でもてあそぶ。いじる。好色五人女4「くらまぎれに前髪を―・りて」
な‐へ
(ナはノの意の格助詞。ヘはウヘ(上)の約。活用語の連体形に付き、その状態と下に来る状態が並行することを表す)…と共に。…につれて。なへに。万葉集7「山河の瀬のなる―に弓月が岳に雲立ち渡る」。万葉集10「秋風の寒く吹く―吾が屋前やどの浅茅がもとに蟋蟀こおろぎ鳴くも」
なべ【鍋】
①(ナは肴、ヘは瓮の意)食物を煮たりいためたりする器。金属製または石製・陶製で、底が比較的浅く口が開き、蓋・把手・つるなどを付ける。〈新撰字鏡6〉
②鍋料理。鍋物。「寄せ―」「―をつつく」
③下女の通名。おなべ。
なべ‐がえし【鍋返し】‥ガヘシ
煮物の途中で鍋をふって材料の上下を入れ替え、味が行き渡るようにすること。
なべ‐がね【鍋鉄】
(鍋などを鋳るのに用いることから)銑鉄や鋳鉄の俗称。ずくてつ。
なべ‐かぶり【鍋被り】
①(→)筑摩祭つくままつりに同じ。〈[季]夏〉
②江戸中期頃の悪性の流行病の一つ。鼻から上が黒くなるもの。
③〔動〕ヒガラの異称。
なべ‐かま【鍋釜】
鍋と釜。炊事道具の代表。しばしば、生活に必要な最低限の道具の意に用いる。「―売っても嚊かか売るな」
⇒鍋釜が賑わう
 そのを作るや、―」→な(己・汝)
ナビ‐は【ナビ派】
(les Nabis フランス 預言者の意のヘブライ語に由来)19世紀末、フランスの画派の一つ。セリュジエ(P. Sérusier1864〜1927)・ドニ・ボナールらがゴーガンの影響を受けて結成。神秘的・象徴的・装飾的画風を示す。ポスター・デザインなどにも活躍。
なび‐やか
しなやか。なよやか。なびらか。散木奇歌集「草のはがひも末―に」。六条宰相家歌合「言葉使ひなど―ならず」
なびやか・し
〔形シク〕
なびやかである。しなやかである。
なび‐らか
(→)「なびやか」に同じ。毎月抄「ふとみほそみもなく―に聞きにくからぬやうによみなすがきはめて重事にて侍るなり」
な‐びらき【名開き】
赤子の命名の儀礼。普通は生まれて7日目に行う。名付け親をとり、名を紙に書いて床の間・神棚に掲げ、祝宴を張る。
な‐びろう【名披露】
(→)「なびろめ」に同じ。
な‐びろめ【名広め・名披露目】
芸人が芸名を得た時、または商人が開店の時、その名を世間に披露すること。
な・ぶ【並ぶ】
〔他下二〕
ならべる。つらねる。古事記中「日々かが―・べて夜には九夜ここのよ日には十日を」
な・ぶ【靡ぶ】
〔他下二〕
なびかせる。万葉集1「旗すすき小竹しのをおし―・べ」
ナフキン
ナプキンの訛。
ナプキン【napkin】
①食事時に胸や膝にかけたり口や手を拭ったりする布巾。紙製もある。
②生理用品の一つ。
ナフサ【naphtha】
原油を蒸留するとき、ガソリンの沸点範囲であるセ氏25〜200度で留出する部分。沸点100度以下の軽質ナフサと80〜200度の重質ナフサとに分ける。軽質ナフサは熱分解によりエチレン・プロピレンなどの石油化学原料が得られ、重質ナフサは接触改質によりガソリンが製造される。
なふさ‐なふさ
〔副〕
⇒のうさのうさ
ナプス【NAPS】
(Numerical Analysis and Prediction System)数値解析予報システム。気象庁に設置するスーパー‐コンピューターを主軸として数値解析と数値予報を行うコンピューター‐システムで、気象予報以外に海洋に関する諸計算も行う。→コスメッツ→アデス
ナフタ【NAFTA】
(North American Free Trade Agreement)北米自由貿易協定。アメリカ・カナダ・メキシコの3国間で相互に市場を開放するための協定。1992年調印、94年発効。
な‐ふだ【名札】
名を記したふだ。また名刺。福地桜痴、もしや草紙「乗客は衣嚢ポッケットから名刺なふだを出し、御在宅なら御目に掛らうと申込む」。「胸に―をつける」
ナフダトゥル‐ウラマー【Nahdatul Ulama】
(「イスラム指導者の覚醒」の意)インドネシア最大のイスラム団体・政治組織。1926年結成。伝統的スンニ派イスラムを標榜。NU
ナフタリン【Naphthalin ドイツ】
(→)ナフタレンに同じ。
ナフタレン【naphthalene】
分子式C10H8 芳香族炭化水素の一つ。コールタールから分離される白色板状の結晶。石油の分解混合物中に含まれるアルキル‐ナフタレンの脱アルキルによっても製造される。常温で昇華し、特異の臭気がある。合成化学工業上の重要な原料。また、樟脳しょうのうの代用品として防虫・防臭用。ナフタリン。
ナフテン【naphthene】
原油の成分として含まれる飽和環式炭化水素(シクロ‐パラフィン)の総称。一般式CnH2n
ナフトール【Naphthol ドイツ】
分子式C10H7OH フェノール類の一つ。無色の針状結晶。フェノールに類似し、防腐剤として用いるほか、染料製造などの原料。「―染め」
な‐ぶら
(ナムラの訛)遊泳する魚の群れ。
なぶり【嬲り】
なぶること。もてあそぶこと。万葉集15「人―のみ好みたるらむ」
⇒なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
⇒なぶり‐だて【嬲り立て】
⇒なぶり‐もの【嬲り者】
なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
なぶって殺すこと。すぐに殺さずに苦しめ、もてあそんで殺すこと。
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐だて【嬲り立て】
なぶるさまをすること。出しゃばってからかうこと。狂言、蟹山伏「―しおつてはさまれおつて、あのなりは」
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐もの【嬲り者】
なぶる対象になるもの。なぶられるもの。
⇒なぶり【嬲り】
なぶ・る【嬲る】
〔他五〕
①責めさいなむ。いじめる。日本霊異記中「壮おとこ強ひて入り―・る」
②からかい、ひやかす。ばかにする。謡曲、橋弁慶「牛若彼を―・つてみんと」。「人前で―・られる」
③手でもてあそぶ。いじる。好色五人女4「くらまぎれに前髪を―・りて」
な‐へ
(ナはノの意の格助詞。ヘはウヘ(上)の約。活用語の連体形に付き、その状態と下に来る状態が並行することを表す)…と共に。…につれて。なへに。万葉集7「山河の瀬のなる―に弓月が岳に雲立ち渡る」。万葉集10「秋風の寒く吹く―吾が屋前やどの浅茅がもとに蟋蟀こおろぎ鳴くも」
なべ【鍋】
①(ナは肴、ヘは瓮の意)食物を煮たりいためたりする器。金属製または石製・陶製で、底が比較的浅く口が開き、蓋・把手・つるなどを付ける。〈新撰字鏡6〉
②鍋料理。鍋物。「寄せ―」「―をつつく」
③下女の通名。おなべ。
なべ‐がえし【鍋返し】‥ガヘシ
煮物の途中で鍋をふって材料の上下を入れ替え、味が行き渡るようにすること。
なべ‐がね【鍋鉄】
(鍋などを鋳るのに用いることから)銑鉄や鋳鉄の俗称。ずくてつ。
なべ‐かぶり【鍋被り】
①(→)筑摩祭つくままつりに同じ。〈[季]夏〉
②江戸中期頃の悪性の流行病の一つ。鼻から上が黒くなるもの。
③〔動〕ヒガラの異称。
なべ‐かま【鍋釜】
鍋と釜。炊事道具の代表。しばしば、生活に必要な最低限の道具の意に用いる。「―売っても嚊かか売るな」
⇒鍋釜が賑わう
そのを作るや、―」→な(己・汝)
ナビ‐は【ナビ派】
(les Nabis フランス 預言者の意のヘブライ語に由来)19世紀末、フランスの画派の一つ。セリュジエ(P. Sérusier1864〜1927)・ドニ・ボナールらがゴーガンの影響を受けて結成。神秘的・象徴的・装飾的画風を示す。ポスター・デザインなどにも活躍。
なび‐やか
しなやか。なよやか。なびらか。散木奇歌集「草のはがひも末―に」。六条宰相家歌合「言葉使ひなど―ならず」
なびやか・し
〔形シク〕
なびやかである。しなやかである。
なび‐らか
(→)「なびやか」に同じ。毎月抄「ふとみほそみもなく―に聞きにくからぬやうによみなすがきはめて重事にて侍るなり」
な‐びらき【名開き】
赤子の命名の儀礼。普通は生まれて7日目に行う。名付け親をとり、名を紙に書いて床の間・神棚に掲げ、祝宴を張る。
な‐びろう【名披露】
(→)「なびろめ」に同じ。
な‐びろめ【名広め・名披露目】
芸人が芸名を得た時、または商人が開店の時、その名を世間に披露すること。
な・ぶ【並ぶ】
〔他下二〕
ならべる。つらねる。古事記中「日々かが―・べて夜には九夜ここのよ日には十日を」
な・ぶ【靡ぶ】
〔他下二〕
なびかせる。万葉集1「旗すすき小竹しのをおし―・べ」
ナフキン
ナプキンの訛。
ナプキン【napkin】
①食事時に胸や膝にかけたり口や手を拭ったりする布巾。紙製もある。
②生理用品の一つ。
ナフサ【naphtha】
原油を蒸留するとき、ガソリンの沸点範囲であるセ氏25〜200度で留出する部分。沸点100度以下の軽質ナフサと80〜200度の重質ナフサとに分ける。軽質ナフサは熱分解によりエチレン・プロピレンなどの石油化学原料が得られ、重質ナフサは接触改質によりガソリンが製造される。
なふさ‐なふさ
〔副〕
⇒のうさのうさ
ナプス【NAPS】
(Numerical Analysis and Prediction System)数値解析予報システム。気象庁に設置するスーパー‐コンピューターを主軸として数値解析と数値予報を行うコンピューター‐システムで、気象予報以外に海洋に関する諸計算も行う。→コスメッツ→アデス
ナフタ【NAFTA】
(North American Free Trade Agreement)北米自由貿易協定。アメリカ・カナダ・メキシコの3国間で相互に市場を開放するための協定。1992年調印、94年発効。
な‐ふだ【名札】
名を記したふだ。また名刺。福地桜痴、もしや草紙「乗客は衣嚢ポッケットから名刺なふだを出し、御在宅なら御目に掛らうと申込む」。「胸に―をつける」
ナフダトゥル‐ウラマー【Nahdatul Ulama】
(「イスラム指導者の覚醒」の意)インドネシア最大のイスラム団体・政治組織。1926年結成。伝統的スンニ派イスラムを標榜。NU
ナフタリン【Naphthalin ドイツ】
(→)ナフタレンに同じ。
ナフタレン【naphthalene】
分子式C10H8 芳香族炭化水素の一つ。コールタールから分離される白色板状の結晶。石油の分解混合物中に含まれるアルキル‐ナフタレンの脱アルキルによっても製造される。常温で昇華し、特異の臭気がある。合成化学工業上の重要な原料。また、樟脳しょうのうの代用品として防虫・防臭用。ナフタリン。
ナフテン【naphthene】
原油の成分として含まれる飽和環式炭化水素(シクロ‐パラフィン)の総称。一般式CnH2n
ナフトール【Naphthol ドイツ】
分子式C10H7OH フェノール類の一つ。無色の針状結晶。フェノールに類似し、防腐剤として用いるほか、染料製造などの原料。「―染め」
な‐ぶら
(ナムラの訛)遊泳する魚の群れ。
なぶり【嬲り】
なぶること。もてあそぶこと。万葉集15「人―のみ好みたるらむ」
⇒なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
⇒なぶり‐だて【嬲り立て】
⇒なぶり‐もの【嬲り者】
なぶり‐ごろし【嬲り殺し】
なぶって殺すこと。すぐに殺さずに苦しめ、もてあそんで殺すこと。
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐だて【嬲り立て】
なぶるさまをすること。出しゃばってからかうこと。狂言、蟹山伏「―しおつてはさまれおつて、あのなりは」
⇒なぶり【嬲り】
なぶり‐もの【嬲り者】
なぶる対象になるもの。なぶられるもの。
⇒なぶり【嬲り】
なぶ・る【嬲る】
〔他五〕
①責めさいなむ。いじめる。日本霊異記中「壮おとこ強ひて入り―・る」
②からかい、ひやかす。ばかにする。謡曲、橋弁慶「牛若彼を―・つてみんと」。「人前で―・られる」
③手でもてあそぶ。いじる。好色五人女4「くらまぎれに前髪を―・りて」
な‐へ
(ナはノの意の格助詞。ヘはウヘ(上)の約。活用語の連体形に付き、その状態と下に来る状態が並行することを表す)…と共に。…につれて。なへに。万葉集7「山河の瀬のなる―に弓月が岳に雲立ち渡る」。万葉集10「秋風の寒く吹く―吾が屋前やどの浅茅がもとに蟋蟀こおろぎ鳴くも」
なべ【鍋】
①(ナは肴、ヘは瓮の意)食物を煮たりいためたりする器。金属製または石製・陶製で、底が比較的浅く口が開き、蓋・把手・つるなどを付ける。〈新撰字鏡6〉
②鍋料理。鍋物。「寄せ―」「―をつつく」
③下女の通名。おなべ。
なべ‐がえし【鍋返し】‥ガヘシ
煮物の途中で鍋をふって材料の上下を入れ替え、味が行き渡るようにすること。
なべ‐がね【鍋鉄】
(鍋などを鋳るのに用いることから)銑鉄や鋳鉄の俗称。ずくてつ。
なべ‐かぶり【鍋被り】
①(→)筑摩祭つくままつりに同じ。〈[季]夏〉
②江戸中期頃の悪性の流行病の一つ。鼻から上が黒くなるもの。
③〔動〕ヒガラの異称。
なべ‐かま【鍋釜】
鍋と釜。炊事道具の代表。しばしば、生活に必要な最低限の道具の意に用いる。「―売っても嚊かか売るな」
⇒鍋釜が賑わう
な‐びらき【名開き】🔗⭐🔉
な‐びらき【名開き】
赤子の命名の儀礼。普通は生まれて7日目に行う。名付け親をとり、名を紙に書いて床の間・神棚に掲げ、祝宴を張る。
○名もないなもない🔗⭐🔉
○名もないなもない
人があまり関心を示さず、名前の知られていない。ごく普通の。無名の。「―花」
⇒な【名】
なもみ
火にあたりすぎて、腕や脚などにできる斑。不精者の象徴とされる。
なも‐ろ
(上代東国方言。ロは間投助詞)…ているだろうよ。万葉集14「真人言まひとごと思ほす―我が思もほのすも」
な‐や【納屋】
①中世、主として海岸に設けた商業用の倉庫。→納屋衆。
②江戸時代、流通過程にある商品を取り扱う倉庫。→納屋物。
③(農家などで)物を納めておく小屋。ものおき。
④(漁業地で)網元の小部屋。若者を起居させる室。
⑤(→)飯場はんばに同じ。
な‐や【魚屋】
魚を商う家。さかなや。
なや‐うや【否諾】
いやかおうか。いやおうの返辞。
なや‐しゅう【納屋衆】
室町時代、納屋すなわち海岸の倉庫を有した豪商。堺ではその中から選ばれた36名が会合えごう衆として市政をとった。
なや・す【萎す】
〔他五〕
①なえるようにする。やわらかにする。蜻蛉日記上「着―・したる、ものの色もあらぬやうに見ゆ」
②ぐったりさせる。平家物語12「太刀のみね長刀の柄にてうち―・してからめとり」
③鉄などをうちきたえる。ねやす。ねる。〈類聚名義抄〉
なや‐せいど【納屋制度】
(→)飯場はんば制度に同じ。
なや‐まい【納屋米】
「納屋物なやもの」参照。
なやまし・い【悩ましい】
〔形〕[文]なやま・し(シク)
①なやみを感ずる。難儀である。くるしい。顕宗紀「吾が父の先王は、是れ天皇の子たりと雖も、迍邅なやましきに遭遇あひて、天位に登りたまはず」。「―・い問題を突きつけられる」
②病気などのために気分がわるい。源氏物語帚木「いと―・しきにとて大殿ごもれり」
③官能が刺激されて心が乱れる。「―・い視線」
なやまし‐が・る【悩ましがる】
〔自四〕
病気などのため気分悪がる。源氏物語胡蝶「―・りてふし給へれど」
なやまし‐げ【悩ましげ】
悩ましいさま。気分が悪い様子。源氏物語胡蝶「御ここち―に見え給ふ」
なやま・す【悩ます】
〔他五〕
悩ませる。苦しませる。困らせる。万葉集19「安眠やすい寝しめず君を―・せ」。「頭を―・す」
なやみ【悩み】
①なやむこと。くるしみ。思いわずらい。「―がつきない」「―多き年ごろ」
②やまい。病気。わずらい。源氏物語明石「御目の―さへ、この頃重くならせ給ひて」
なや・む【悩む】
[一]〔自五〕
①いたみ苦しむ。病む。源氏物語賢木「例ならず時々―・ませ給へば」。天草本平家物語「中宮御懐妊あつて、もつてのほか―・ませられたによつて」。「神経痛に―・む」
②苦しむ。こまる。思いわずらう。万葉集15「安けくもなく―・みきて」。「恋に―・む」
③とやかく非難する。栄華物語花山「安からぬことに世の人―・み申して」
④(他の動詞の連用形に付いて)…に難儀する。…しかねる。源氏物語槿「石間の水は行き―・み」。「若手がのび―・む」
[二]〔他四〕
①苦しめる。なやます。好色五人女4「暮方の障子をひらき、身を―・みおはしけるを」
②取り扱う。いじる。浄瑠璃、鎌倉三代記「手荒う―・むな、つい破われるぞ」
なや・める【悩める】
〔他下一〕[文]なや・む(下二)
苦しめる。なやます。狂言、悪坊「いかう路次で出家をとらまへて―・めたが」。「民を―・める」「主の御心を―・める」
なや‐もの【納屋物】
江戸時代、諸藩の蔵屋敷などを経て販売する蔵物くらものに対し、民間商人が産地で買い入れ、大坂などに送って直接売買する米・商品。米ならば納屋米なやまいという。荷積問屋・荷受問屋・仲買・小売を経て消費者にわたる。
なや‐やか
なよなよしているさま。なよやか。
な‐やらい【追儺】‥ヤラヒ
おにやらい。ついな。〈[季]冬〉。紫式部日記「滝口も―果てけるままに」
な‐やら・う【追儺ふ】‥ヤラフ
〔自四〕
追儺なやらいを行う。源氏物語紅葉賀「―・ふとて、犬君がこれをこぼち侍りにければ」
な・ゆ【萎ゆ】
〔自下二〕
⇒なえる(下一)
なゆた【那由他・那由多】
①〔仏〕(梵語nayuta)古代インドの数の単位。極めて大きな数量。千万または千億に当たるなど、諸説がある。
②数の単位。10の60乗。一説に10の72乗。(塵劫記)
なゆ‐たけ【弱竹】
ナヨタケの転。
⇒なゆたけ‐の【弱竹の】
なゆたけ‐の【弱竹の】
〔枕〕
「とを(撓)」にかかる。
⇒なゆ‐たけ【弱竹】
な‐ゆみ【棝斗】
鼠を捕らえるのに用いる仕掛け。ねずみおとし。ますおとし。〈倭名類聚鈔15〉
な‐よし【名吉・鯔】
ボラまたはイナの異称。みょうぎち。土佐日記「―の頭、ひひらぎら、いかにぞ」
な‐よせ【名寄せ】
①いろいろな名称を寄せ集めること。また、それを書きしるしたもの。「名所―」「美人―」
②複数の場に現れる同一の名称をまとめること。「預金口座を―する」
⇒なよせ‐ちょう【名寄帳】
なよせ‐ちょう【名寄帳】‥チヤウ
①中世、検注の結果をもとに作成された帳簿のうち、名みょう別・百姓別に集計したもの。→検注帳→取帳。
②江戸時代、各村の田畑・屋敷の各筆の年貢高・面積を所持者(名請なうけ人)ごとにまとめた土地台帳。年貢割付けの基礎となるもの。田畑名寄帳。
⇒な‐よせ【名寄せ】
なよたけ
加藤道夫(1918〜1953)作の戯曲。1946年発表、51年尾上菊五郎劇団が初演。「竹取物語」に拠って詩人の誕生を語る。作者の出征に際して遺書として書いたもの。
なよ‐たけ【弱竹】
細くしなやかな竹。若竹。なゆたけ。また、女竹めだけ。宇津保物語田鶴群鳥「―の茂れる宿にまとゐして」
⇒なよたけ‐の【弱竹の】
なよたけ‐の【弱竹の】
〔枕〕
「とを(撓)」「おきふし」「よ(夜・世)」「ふし(節)」にかかる。万葉集2「―とをよる子らは」
⇒なよ‐たけ【弱竹】
なよ‐なよ
(多く助詞「と」を伴って用いる)しなやかなさま。たおやかなさま。なえたさま。枕草子67「萩…―とひろごり伏したる」。「―した男」
なよび‐か
①しなやかなさま。なよやか。源氏物語総角「白き御衣どもの―なるに」
②上品であるさま。優美であるさま。源氏物語帚木「―にをかしきことはなくて」
なよび‐すがた【なよび姿】
なよなよとなまめかしい姿。源氏物語柏木「―はた、いたうたをやぎけるをや」
なよ・ぶ
〔自上二〕
①衣服などがしなやかである。ごわごわしないようになる。源氏物語夕霧「―・びたる御衣どもを脱い給うて」
②なよなよとしている。柔和である。源氏物語賢木「御心―・びたる方に過ぎて」
③風流めく。源氏物語若菜上「いたく―・びよしめくほどに、重き方おくれて」
なよ‐やか
しなやかなさま。物やわらかなさま。なよよか。好色一代女1「かほばせ―にうまれ付きしとて」。「―な手つき」
なよ‐よか
しなやかなさま。なよらか。源氏物語帚木「白き御衣どもの―なるに」
なよ‐らか
(→)「なよよか」に同じ。
な‐よ・る【馴寄る】
〔自四〕
なれてよる。親しくなって近寄る。後鳥羽院集「なよ竹の―・りあひてもいく世へぬらん」
なよろ【名寄】
北海道北部、名寄盆地の中心をなす市。周辺は米作の北限。人口3万2千。
なら【楢・柞・枹】
①コナラ(ナラ)・ミズナラなどの総称。カシと同属だが常緑でないものをいう。
②コナラの別称。古名、ははそ。古今和歌集雑「神無月時雨降りおける―の葉の名におふ宮の古言ぞこれ」
なら【奈良】
①近畿地方の中央部、内陸の県。大和国を管轄。北部の奈良盆地は大和政権の宮殿・都城が置かれた地、南部の吉野も古代の離宮や南北朝時代の南朝の根拠地の置かれた地で、史跡に富む。面積3690平方キロメートル。人口142万1千。全12市。
→吉野木挽唄
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
②奈良県北部、奈良盆地の北東部の市。県庁所在地。古く「那羅」「平城」「寧楽」とも書き、奈良時代の平城京の地で、現在の中心市街は古都の北東郊外にあたる。社寺・史跡に富む。人口37万。→南都
古都奈良の文化財
提供:NHK
なら【奈良】
姓氏の一つ。
⇒なら‐としなが【奈良利寿】
なら
〔助動〕
(指定の助動詞ダの仮定形)…であったら。「明日おひま―お出かけ下さい」
▷「―帰りなさい」のように接続詞としても使う。
なら
〔助詞〕
(助動詞「なり」の未然形から)並列の意を表す。でも。なり。…といい。好色一代女4「大節季に、一門中から寄る餅―肴物―」
ならいナラヒ
冬、陸や山に沿って吹く強い風。三陸から熊野灘まで、方位は地域により異なる。〈[季]冬〉。三遊亭円朝、文七元結「空は一面に曇つて雪模様、風は少し―が強く」
⇒ならい‐かぜ【ならい風】
ならい【慣・習い・倣い】ナラヒ
①なれること。しきたり。習慣。源氏物語夕霧「例もあつしうのみ聞き侍りつる―に」
②世の常。きまり。方丈記「朝に死に夕に生るる―、ただ水の泡にぞ似たりける」。「世の―」
③ならうこと。学ぶこと。学習。練習。狂言、料理聟「―に参りました」
④口授されて学ぶべき秘事など。「口伝くでんの―」
⇒ならい‐ごと【習い事】
⇒ならい‐しょう【習い性】
⇒ならい‐せんばん【倣い旋盤】
⇒ならい‐もの【習い物】
⇒習い性と成る
ならい【奈良井】‥ヰ
長野県塩尻市の地名。中山道の宿駅で、景観保存地区。南西に鳥居峠がある。
ならい‐おぼ・える【習い覚える】ナラヒ‥
〔他下一〕[文]ならひおぼ・ゆ(下二)
知識や技能などを習って身につける。また、見聞きするうちに自然に習得する。
ならい‐かぜ【ならい風】ナラヒ‥
(→)「ならい」に同じ。好色五人女4「―はげしく」
⇒ならい
ならい‐ごと【習い事】ナラヒ‥
師から習う事柄。稽古事。ならいもの。
⇒ならい【慣・習い・倣い】
ならい‐こ・む【習い込む】ナラヒ‥
〔他五〕
習って十分に覚える。習ってよく熟練する。
ならい‐しょう【習い性】ナラヒシヤウ
(「習い性せいとなる」から)その人にしみついた習慣的な行動様式。習性しゅうせい。
⇒ならい【慣・習い・倣い】
な‐よし【名吉・鯔】🔗⭐🔉
な‐よし【名吉・鯔】
ボラまたはイナの異称。みょうぎち。土佐日記「―の頭、ひひらぎら、いかにぞ」
な‐よせ【名寄せ】🔗⭐🔉
な‐よせ【名寄せ】
①いろいろな名称を寄せ集めること。また、それを書きしるしたもの。「名所―」「美人―」
②複数の場に現れる同一の名称をまとめること。「預金口座を―する」
⇒なよせ‐ちょう【名寄帳】
なよせ‐ちょう【名寄帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
なよせ‐ちょう【名寄帳】‥チヤウ
①中世、検注の結果をもとに作成された帳簿のうち、名みょう別・百姓別に集計したもの。→検注帳→取帳。
②江戸時代、各村の田畑・屋敷の各筆の年貢高・面積を所持者(名請なうけ人)ごとにまとめた土地台帳。年貢割付けの基礎となるもの。田畑名寄帳。
⇒な‐よせ【名寄せ】
なよろ【名寄】🔗⭐🔉
なよろ【名寄】
北海道北部、名寄盆地の中心をなす市。周辺は米作の北限。人口3万2千。
○名を揚げるなをあげる🔗⭐🔉
○名を揚げるなをあげる
名声を世にあらわす。有名になる。「身を立て―」
⇒な【名】
○名を埋むなをうずむ🔗⭐🔉
○名を埋むなをうずむ
[漢書翟方進伝]名を知られないようにする。名を残さない。
⇒な【名】
○名を惜しむなをおしむ🔗⭐🔉
○名を惜しむなをおしむ
名前や名声が汚れるのを残念に思う。万葉集12「名を惜しみ人に知らえず恋ひ渡るかも」
⇒な【名】
○名を借りるなをかりる🔗⭐🔉
○名を借りるなをかりる
①他人の名義を用いる。
②自分の行為を正当化するための口実とする。「視察に名を借りた慰安旅行」
⇒な【名】
○名を腐すなをくたす🔗⭐🔉
○名を腐すなをくたす
名誉をけがす。評判をおとす。源氏物語絵合「業平が名をやくたすべき」
⇒な【名】
○名を汚すなをけがす🔗⭐🔉
○名を汚すなをけがす
名誉・名声に反する行いをして、評判をおとす。「母校の―」
⇒な【名】
○名を沈むなをしずむ🔗⭐🔉
○名を沈むなをしずむ
(→)「名を腐くたす」に同じ。源氏物語絵合「伊勢をの海士あまの名をや沈めむ」
⇒な【名】
○名を雪ぐなをすすぐ🔗⭐🔉
○名を雪ぐなをすすぐ
汚名をすすぐ。名誉を回復する。「名をそそぐ」とも。
⇒な【名】
○名を捨てて実を取るなをすててじつをとる🔗⭐🔉
○名を捨てて実を取るなをすててじつをとる
名声よりも実利をえらぶ。体面や名目については譲っても実質を得る方がよいということ。
⇒な【名】
○名を正すなをただす🔗⭐🔉
○名を正すなをただす
①正邪を判断する。源氏物語須磨「名をばただすの神にまかせて」
②[論語子路]君臣・父子などの名分を正しくする。
⇒な【名】
○名を立てるなをたてる🔗⭐🔉
○名を立てるなをたてる
①名声を揚げる。万葉集19「ますらをは名をし立つべし」
②評判を立てる。源氏物語柏木「あるまじき名をも立ち、我も人も安からぬ乱れ出でくるやうも」
⇒な【名】
○名を保つなをたもつ🔗⭐🔉
○名を保つなをたもつ
名声を保持する。千載和歌集釈教「嬉しくぞ―だに仇ならぬみのりの花に実を結びける」
⇒な【名】
○名を竹帛に垂るなをちくはくにたる🔗⭐🔉
○名を竹帛に垂るなをちくはくにたる
[後漢書鄧禹伝](竹帛は書物、転じて歴史)名を史上に留めて永く後世に伝える。歴史に残るような功績を立てる。功名を竹帛に垂る。
⇒な【名】
○名を散らすなをちらす🔗⭐🔉
○名を散らすなをちらす
名声を世に知らせる。また、浮き名を立てる。源氏物語紅梅「花もえならぬ名をや散らさむ」
⇒な【名】
○名を遂げるなをとげる🔗⭐🔉
○名を遂げるなをとげる
名声を十分にあげる。新撰六帖2「名を遂げてこそ入りこもるなれ」
⇒な【名】
○名を留めるなをとどめる🔗⭐🔉
○名を流すなをながす🔗⭐🔉
○名を流すなをながす
名声を世に伝わらせる。評判を立てる。竹取物語「汝らが君の使と名を流しつ」
⇒な【名】
○名を偸むなをぬすむ🔗⭐🔉
○名を偸むなをぬすむ
実力がないのに、名声を得る。
⇒な【名】
○名を残すなをのこす🔗⭐🔉
○名を残すなをのこす
歴史に残るような功績を立てる。名をとどめる。源氏物語絵合「名を残しける古き心をいふに」。「末代に―」
⇒な【名】
○名を辱めるなをはずかしめる🔗⭐🔉
○名を辱めるなをはずかしめる
名声をきずつける。「親の―」
⇒な【名】
○名を馳せるなをはせる🔗⭐🔉
○名を馳せるなをはせる
名が広く知られる。「画壇の奇才として名を馳せた」
⇒な【名】
○名を振るうなをふるう🔗⭐🔉
○名を振るうなをふるう
名声をひびかせる。賀茂保憲女集「かしこき鷹と名をふるひ」
⇒な【名】
なん【男】
(呉音)むすこの順番を示したり、数えるときに用いる語。「三―坊」「2―をもうける」→だん(男)
なん【南】
方角の一つ。みなみ。
なん【軟】
やわらかいこと。よわいこと。おだやかなこと。「―エックス線」↔硬
なん【難】
①むずかしいこと。「―に当たる」↔易。
②わざわい。「―をまぬかれる」「水火の―」
③責めるべきところ。きず。欠点。源氏物語帚木「これをはじめの―とすべし」。「―をつける」
④なじること。日葡辞書「ナンヲイウ」
⇒難に臨んで遽かに兵を鋳る
⇒難を構える
ナン【naan ヒンディー】
インド・西アジア・中央アジアなどの平焼きパン。小麦粉を水でこねて発酵させ、薄く伸ばして壺形のかまどの内側にはりつけて焼いたもの。ナーン。
なん【何】
[一]〔代〕
「なに」の音便。
[二]〔接頭〕
どれくらい。どういう。「―回」「―百」「何人なんぴと」
⇒何にせよ
な‐ん
⇒なむ
なん
〔助詞〕
⇒なむ
なん‐ア【南ア】
南みなみアフリカの略称。南阿。
⇒なんア‐せんそう【南ア戦争】
⇒なんア‐れんぽう【南ア連邦】
なんア‐せんそう【南ア戦争】‥サウ
1899〜1902年、トランスヴァール共和国およびオレンジ自由国に対して、金などの資源獲得のためにイギリスが行なった植民地拡張戦争。イギリスは辛勝した後、両国を併合、1910年南ア連邦を建設。ブーア戦争。南アフリカ戦争。
⇒なん‐ア【南ア】
なんア‐れんぽう【南ア連邦】‥パウ
南アフリカ共和国の旧称。
⇒なん‐ア【南ア】
なん‐い【南緯】‥ヰ
赤道から南へ測った緯度。
なん‐い【難易】
むずかしいこととやさしいこと。
⇒なんい‐ど【難易度】
なん‐いち【南一】
(江戸後期の通称)南鐐なんりょう1枚。銀2朱にあたる。
なんい‐ど【難易度】
むずかしさの度合。「―が高い」「―に差がある」
⇒なん‐い【難易】
なん‐えつ【南越】‥ヱツ
①漢代の国名。秦末、趙佗ちょうだが建国。今の広東・広西地方にあり、番禹(今の広州)に都したが、前漢の武帝に5世で滅ぼされた。(前207〜前111)
②越前えちぜんの別称。「―温故集」
なん‐エックス‐せん【軟X線】
(soft X-rays)比較的波長の長いX線。透過力が小さい。波長が数百ピコメートル以上のものをいう。
なん‐えん【南燕】
中国、五胡十六国の一つ。鮮卑の慕容徳が滑台(河南省滑県)に建国。2世で東晋の将の劉裕に滅ぼされた。(398〜410)
なん‐えんどう【南円堂】‥ヱンダウ
奈良興福寺の南西隅にある八角円堂。813年(弘仁4)藤原冬嗣の建立で、摂関家氏寺信仰の中心。西国三十三所第9番の札所。
なん‐えんぶだい【南閻浮提】
(須弥山しゅみせんの南部にあるからいう)閻浮提の別称。
なん‐おう【南欧】
ヨーロッパの南部。イタリア・フランス南部・スペイン・ポルトガル・ギリシアなど。↔北欧
なん‐おん【軟音】
〔言〕(lenis)
①調音器官の緊張を伴わずに発音する子音。〔b〕〔d〕〔g〕などの有声閉鎖音は一般に軟音となる。
②スラヴ語学で、口蓋化を伴う子音のこと。軟子音。
↔硬音
なん‐か【南下】
南の方へ進むこと。「―政策」↔北上
なん‐か【南瓜】‥クワ
カボチャの異称。
なん‐か【南柯】
南にさし出た枝。南枝。
⇒なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】
なん‐か【南華】‥クワ
①「南華真経」の略称。
②(「荘子」に寓言が多いからいう)うそつき。変人。
③(遊里語)ばか。愚者。野暮天。
⇒なんか‐しんきょう【南華真経】
⇒なんか‐しんじん【南華真人】
なん‐か【軟化】‥クワ
①かたい物がやわらかになること。また、やわらかにすること。
②強硬だった主張や態度がおだやかになること。
③(取引用語)相場が安くなること。
↔硬化。
⇒なんか‐さいばい【軟化栽培】
⇒なんか‐びょう【軟化病】
なん‐か【軟貨】‥クワ
①鋳造貨幣以外の通貨。紙幣。
②他国通貨または金への交換性を有しない通貨。
↔硬貨
なん‐か【何か】
(ナニカの音便)何事か。何ものか。「―ちょうだい」
なんか
〔助詞〕
(代名詞ナニに助詞カの付いたものの転)
①一つの例として示す。「こちらの品―いかがですか」
②望ましくないもの、価値の低いものとしてあげる。…など。「おまえ―に負けない」「嘘―つかない」
なん‐が【南画】‥グワ
①南宗画なんしゅうがの略。
②日本の文人画。南宗画に由来し、江戸時代に独自の様式が大成。
なん‐かい【南海】
①南方の海。
②東洋史上、南方諸国を指していう称。
③南海道の略。
⇒なんかい‐しょとう【南海諸島】
⇒なんかい‐でんしゃ【南海電車】
⇒なんかい‐どう【南海道】
⇒なんかいどう‐じしん【南海道地震】
⇒なんかい‐トラフ【南海トラフ】
なん‐かい【南階】
①南向きの階段。
②特に、紫宸殿の南面のきざはし。
なん‐かい【難解】
解釈しにくいこと。分かりにくいこと。「―な文章」
なんかいききないほうでん【南海寄帰内法伝】‥ホフ‥
唐代の僧義浄の著した旅行記。4巻。インドへ求法ぐほうの旅に上った際に集めた話、中国との風習の違い、インドでの修学のあり方などを記し、691年に長安に送る。
なんかい‐しょとう【南海諸島】‥タウ
南シナ海に散在する諸島。約200の島・岩礁から成り、東沙・西沙(ホアンサ)・中沙・南沙(スプラトリー)の4群島と黄岩島などに分かれる。周辺諸国間に領有権をめぐる確執がある。→スプラトリー諸島。
⇒なん‐かい【南海】
なん‐かいじん【南懐仁】‥クワイ‥
フェルビーストの漢名。
なんかい‐でんしゃ【南海電車】
大阪府と和歌山県で営業する大手私鉄の一つ。難波(大阪)・和歌山市間の本線、汐見橋・極楽橋間の高野線などがある。
⇒なん‐かい【南海】
なんかい‐どう【南海道】‥ダウ
五畿七道の一つ。紀伊・淡路・阿波・讃岐・伊予・土佐の6カ国の称。畿内・山陽道の南方にあるからいう。
⇒なん‐かい【南海】
なんかいどう‐じしん【南海道地震】‥ダウヂ‥
四国沖から紀伊半島沖にかけて起こる巨大地震。最近では1707年(宝永4)、1854年(安政1)、1946年に発生し、特に最後のものを指すことが多い。震源の断層はプレート境界にほぼ一致。地震時に太平洋側の半島の先端部は隆起、付け根の地域は沈降する。南海地震。
高知市日の出町一文字橋付近の堤防亀裂 1946年12月
提供:毎日新聞社
 ⇒なん‐かい【南海】
なんかい‐トラフ【南海トラフ】
伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。
⇒なん‐かい【南海】
なん‐がく【南学】
朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。
なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥
ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。
⇒なん‐か【軟化】
なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ
(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。
⇒なん‐か【南華】
なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥
唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。
⇒なん‐か【南華】
なんかたいしゅでん【南柯太守伝】
唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢
なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】
[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。
⇒なん‐か【南柯】
ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】
ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。
ナンガパルバット(1)
提供:オフィス史朗
⇒なん‐かい【南海】
なんかい‐トラフ【南海トラフ】
伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。
⇒なん‐かい【南海】
なん‐がく【南学】
朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。
なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥
ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。
⇒なん‐か【軟化】
なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ
(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。
⇒なん‐か【南華】
なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥
唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。
⇒なん‐か【南華】
なんかたいしゅでん【南柯太守伝】
唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢
なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】
[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。
⇒なん‐か【南柯】
ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】
ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。
ナンガパルバット(1)
提供:オフィス史朗
 ナンガパルバット(2)
提供:オフィス史朗
ナンガパルバット(2)
提供:オフィス史朗
 なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ
体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。
⇒なん‐か【軟化】
なん‐かん【難関】‥クワン
①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。
②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」
なん‐かん【難艱】
(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」
なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】
九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。
なん‐き【南紀】
①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」
②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。
なん‐ぎ【難義】
分かりにくい意義。また、その語。
なん‐ぎ【難儀】
①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」
②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」
③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」
④貧窮。貧乏。
なん‐きつ【難詰】
欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」
なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥
[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。
なんき‐ぶんこ【南葵文庫】
(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。
なん‐きゅう【軟球】‥キウ
比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球
なん‐きょう【南京】‥キヤウ
(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。
⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】
なん‐きょう【難境】‥キヤウ
困難な境遇。
なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ
極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。
⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】
⇒なんぎょう‐どう【難行道】
なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ
困難な事業。
なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ
種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。
⇒なん‐ぎょう【難行】
なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ
〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。
⇒なん‐きょう【南京】
なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ
他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道
⇒なん‐ぎょう【難行】
なん‐きょく【南曲】
中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。
なん‐きょく【南極】
①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。
②南極圏の内部。また、南極大陸の略。
南極
なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ
体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。
⇒なん‐か【軟化】
なん‐かん【難関】‥クワン
①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。
②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」
なん‐かん【難艱】
(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」
なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】
九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。
なん‐き【南紀】
①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」
②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。
なん‐ぎ【難義】
分かりにくい意義。また、その語。
なん‐ぎ【難儀】
①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」
②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」
③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」
④貧窮。貧乏。
なん‐きつ【難詰】
欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」
なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥
[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。
なんき‐ぶんこ【南葵文庫】
(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。
なん‐きゅう【軟球】‥キウ
比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球
なん‐きょう【南京】‥キヤウ
(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。
⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】
なん‐きょう【難境】‥キヤウ
困難な境遇。
なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ
極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。
⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】
⇒なんぎょう‐どう【難行道】
なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ
困難な事業。
なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ
種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。
⇒なん‐ぎょう【難行】
なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ
〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。
⇒なん‐きょう【南京】
なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ
他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道
⇒なん‐ぎょう【難行】
なん‐きょく【南曲】
中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。
なん‐きょく【南極】
①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。
②南極圏の内部。また、南極大陸の略。
南極
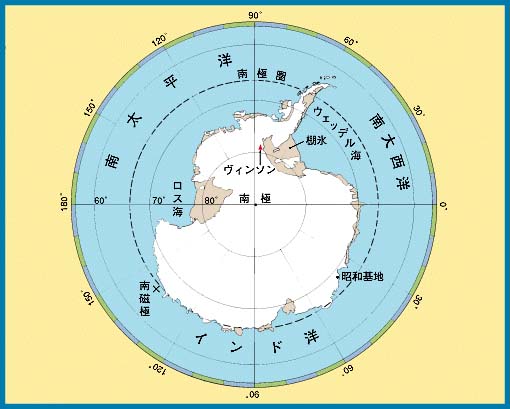 ③天の南極。地軸が天球と交わる南端。
④磁石の南方を指す極。指南極。S極。
⑤地磁気の南の極。南磁極。
⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
⇒なんきょく‐かい【南極海】
⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】
⇒なんきょく‐きだん【南極気団】
⇒なんきょく‐けん【南極圏】
⇒なんきょく‐しゅう【南極州】
⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】
⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】
⇒なんきょく‐せい【南極星】
⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】
⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】
⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】
⇒なんきょく‐てん【南極点】
⇒なんきょく‐よう【南極洋】
⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】
なん‐きょく【難曲】
演奏するのに高度の技術を要する楽曲。
なん‐きょく【難局】
処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」
なん‐ぎょく【軟玉】
玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。
なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かい【南極海】
南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥
国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐きだん【南極気団】
南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐けん【南極圏】
地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ
南極大陸および付近の島々の称。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥
南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥
南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。
→文献資料[南極条約]
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐せい【南極星】
竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たいりく【南極大陸】
南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たんけん【南極探検】
南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ
南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐てん【南極点】
地軸の南端。南緯90度の地点。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ
(→)南極海に同じ。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥
①(→)南極星のこと。
②(→)寿老人じゅろうじんの異称。
⇒なん‐きょく【南極】
なん‐きん【軟禁】
監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。
ナンキン【南京】
①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。
②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。
③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。
④カボチャの異称。
⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】
⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】
⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
⇒ナンキン‐じけん【南京事件】
⇒ナンキン‐したみ【南京下見】
⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】
⇒ナンキン‐じょう【南京錠】
⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】
⇒ナンキン‐じん【南京人】
⇒ナンキン‐せん【南京銭】
⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
⇒ナンキン‐だま【南京玉】
⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】
⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
⇒ナンキン‐まい【南京米】
⇒ナンキン‐まめ【南京豆】
⇒ナンキン‐むし【南京虫】
⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】
⇒ナンキン‐やき【南京焼】
⇒ナンキン‐ろ【南京路】
ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ
中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐あやつり【南京操り】
(→)「糸操り」の異称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じけん【南京事件】
①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。
②南京大虐殺。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐したみ【南京下見】
下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。
ナンキンシャモ
撮影:小宮輝之
③天の南極。地軸が天球と交わる南端。
④磁石の南方を指す極。指南極。S極。
⑤地磁気の南の極。南磁極。
⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
⇒なんきょく‐かい【南極海】
⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】
⇒なんきょく‐きだん【南極気団】
⇒なんきょく‐けん【南極圏】
⇒なんきょく‐しゅう【南極州】
⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】
⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】
⇒なんきょく‐せい【南極星】
⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】
⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】
⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】
⇒なんきょく‐てん【南極点】
⇒なんきょく‐よう【南極洋】
⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】
なん‐きょく【難曲】
演奏するのに高度の技術を要する楽曲。
なん‐きょく【難局】
処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」
なん‐ぎょく【軟玉】
玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。
なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かい【南極海】
南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥
国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐きだん【南極気団】
南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐けん【南極圏】
地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ
南極大陸および付近の島々の称。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥
南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥
南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。
→文献資料[南極条約]
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐せい【南極星】
竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たいりく【南極大陸】
南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たんけん【南極探検】
南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ
南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐てん【南極点】
地軸の南端。南緯90度の地点。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ
(→)南極海に同じ。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥
①(→)南極星のこと。
②(→)寿老人じゅろうじんの異称。
⇒なん‐きょく【南極】
なん‐きん【軟禁】
監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。
ナンキン【南京】
①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。
②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。
③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。
④カボチャの異称。
⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】
⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】
⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
⇒ナンキン‐じけん【南京事件】
⇒ナンキン‐したみ【南京下見】
⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】
⇒ナンキン‐じょう【南京錠】
⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】
⇒ナンキン‐じん【南京人】
⇒ナンキン‐せん【南京銭】
⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
⇒ナンキン‐だま【南京玉】
⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】
⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
⇒ナンキン‐まい【南京米】
⇒ナンキン‐まめ【南京豆】
⇒ナンキン‐むし【南京虫】
⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】
⇒ナンキン‐やき【南京焼】
⇒ナンキン‐ろ【南京路】
ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ
中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐あやつり【南京操り】
(→)「糸操り」の異称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じけん【南京事件】
①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。
②南京大虐殺。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐したみ【南京下見】
下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。
ナンキンシャモ
撮影:小宮輝之
 ⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じゅす【南京繻子】
経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ
巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥
阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じん【南京人】
昔、日本で中国人を呼んだ俗称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐せん【南京銭】
①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。
②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
中華門城壁爆破 1937年
提供:毎日新聞社
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じゅす【南京繻子】
経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ
巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥
阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じん【南京人】
昔、日本で中国人を呼んだ俗称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐せん【南京銭】
①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。
②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
中華門城壁爆破 1937年
提供:毎日新聞社
 ⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だま【南京玉】
陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ばと【南京鳩】
ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まい【南京米】
インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まめ【南京豆】
(→)落花生の別称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐むし【南京虫】
①(→)トコジラミの別称。
②俗に、小形の女性用金側腕時計。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐もめん【南京木綿】
帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐やき【南京焼】
江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ろ【南京路】
(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。
⇒ナンキン【南京】
なん‐く【難句】
①むずかしい句。わかりにくい文句。
②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」
なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】
岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。
なん‐くせ【難癖】
非難すべき点。欠点。
⇒難癖を付ける
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だま【南京玉】
陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ばと【南京鳩】
ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まい【南京米】
インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まめ【南京豆】
(→)落花生の別称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐むし【南京虫】
①(→)トコジラミの別称。
②俗に、小形の女性用金側腕時計。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐もめん【南京木綿】
帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐やき【南京焼】
江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ろ【南京路】
(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。
⇒ナンキン【南京】
なん‐く【難句】
①むずかしい句。わかりにくい文句。
②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」
なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】
岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。
なん‐くせ【難癖】
非難すべき点。欠点。
⇒難癖を付ける
 ⇒なん‐かい【南海】
なんかい‐トラフ【南海トラフ】
伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。
⇒なん‐かい【南海】
なん‐がく【南学】
朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。
なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥
ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。
⇒なん‐か【軟化】
なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ
(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。
⇒なん‐か【南華】
なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥
唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。
⇒なん‐か【南華】
なんかたいしゅでん【南柯太守伝】
唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢
なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】
[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。
⇒なん‐か【南柯】
ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】
ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。
ナンガパルバット(1)
提供:オフィス史朗
⇒なん‐かい【南海】
なんかい‐トラフ【南海トラフ】
伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。
⇒なん‐かい【南海】
なん‐がく【南学】
朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。
なんか‐さいばい【軟化栽培】‥クワ‥
ウド・フキ・ネギ・アスパラガスなどの野菜類で、日光の当たるのを防ぎ茎葉を白く軟らかくする栽培法。軟白栽培。
⇒なん‐か【軟化】
なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ
(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。
⇒なん‐か【南華】
なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥
唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。
⇒なん‐か【南華】
なんかたいしゅでん【南柯太守伝】
唐代の小説。中唐の李公佐の作。淳于棼じゅんうふんが夢の中で南柯太守となって栄達する。→南柯の夢
なんか‐の‐ゆめ【南柯の夢】
[李公佐、南柯太守伝](淳于棼じゅんうふんが酔って古い槐かい樹の下で眠り、夢の中で大槐安国に至り、王命によって南柯郡守に封ぜられ、20年間栄華をきわめた。夢からさめて槐樹の下を見ると、二つの穴があり、一つの穴には大蟻が王として住み、他の穴は南枝に通じそれが南柯郡であったという故事による)夢のこと。また、はかないことのたとえにいう。槐夢。槐安の夢。
⇒なん‐か【南柯】
ナンガ‐パルバット【Nanga Parbat】
ヒマラヤ山脈の西端、カシミール地方にある高峰。ラーワルピンディーの北東に位置する。標高8125メートル。1953年ドイツ‐オーストリア隊のH.ブールが初登頂。
ナンガパルバット(1)
提供:オフィス史朗
 ナンガパルバット(2)
提供:オフィス史朗
ナンガパルバット(2)
提供:オフィス史朗
 なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ
体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。
⇒なん‐か【軟化】
なん‐かん【難関】‥クワン
①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。
②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」
なん‐かん【難艱】
(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」
なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】
九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。
なん‐き【南紀】
①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」
②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。
なん‐ぎ【難義】
分かりにくい意義。また、その語。
なん‐ぎ【難儀】
①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」
②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」
③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」
④貧窮。貧乏。
なん‐きつ【難詰】
欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」
なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥
[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。
なんき‐ぶんこ【南葵文庫】
(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。
なん‐きゅう【軟球】‥キウ
比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球
なん‐きょう【南京】‥キヤウ
(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。
⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】
なん‐きょう【難境】‥キヤウ
困難な境遇。
なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ
極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。
⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】
⇒なんぎょう‐どう【難行道】
なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ
困難な事業。
なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ
種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。
⇒なん‐ぎょう【難行】
なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ
〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。
⇒なん‐きょう【南京】
なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ
他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道
⇒なん‐ぎょう【難行】
なん‐きょく【南曲】
中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。
なん‐きょく【南極】
①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。
②南極圏の内部。また、南極大陸の略。
南極
なんか‐びょう【軟化病】‥クワビヤウ
体が軟弱となって死ぬ蚕病の総称。空頭病・起縮おきちぢみ病・縮小病など。ウイルスや細菌による感染、生理的原因などによる。
⇒なん‐か【軟化】
なん‐かん【難関】‥クワン
①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。
②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」
なん‐かん【難艱】
(ナンガンとも)くるしみ。苦労。艱難。平治物語「―のあまりにありのままに申しける」
なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】
九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。
なん‐き【南紀】
①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」
②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。
なん‐ぎ【難義】
分かりにくい意義。また、その語。
なん‐ぎ【難儀】
①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」
②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」
③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」
④貧窮。貧乏。
なん‐きつ【難詰】
欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」
なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥
[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。
なんき‐ぶんこ【南葵文庫】
(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。
なん‐きゅう【軟球】‥キウ
比較的やわらかく、軽い球。軟式のテニス・野球などに使用。↔硬球
なん‐きょう【南京】‥キヤウ
(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。
⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】
なん‐きょう【難境】‥キヤウ
困難な境遇。
なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ
極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。
⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】
⇒なんぎょう‐どう【難行道】
なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ
困難な事業。
なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ
種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。
⇒なん‐ぎょう【難行】
なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ
〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。
⇒なん‐きょう【南京】
なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ
他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道
⇒なん‐ぎょう【難行】
なん‐きょく【南曲】
中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。
なん‐きょく【南極】
①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。
②南極圏の内部。また、南極大陸の略。
南極
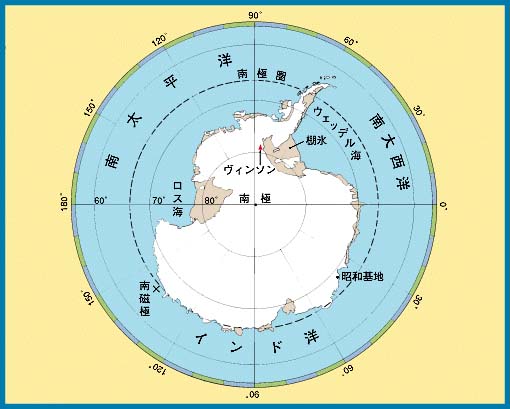 ③天の南極。地軸が天球と交わる南端。
④磁石の南方を指す極。指南極。S極。
⑤地磁気の南の極。南磁極。
⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
⇒なんきょく‐かい【南極海】
⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】
⇒なんきょく‐きだん【南極気団】
⇒なんきょく‐けん【南極圏】
⇒なんきょく‐しゅう【南極州】
⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】
⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】
⇒なんきょく‐せい【南極星】
⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】
⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】
⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】
⇒なんきょく‐てん【南極点】
⇒なんきょく‐よう【南極洋】
⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】
なん‐きょく【難曲】
演奏するのに高度の技術を要する楽曲。
なん‐きょく【難局】
処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」
なん‐ぎょく【軟玉】
玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。
なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かい【南極海】
南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥
国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐きだん【南極気団】
南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐けん【南極圏】
地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ
南極大陸および付近の島々の称。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥
南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥
南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。
→文献資料[南極条約]
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐せい【南極星】
竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たいりく【南極大陸】
南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たんけん【南極探検】
南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ
南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐てん【南極点】
地軸の南端。南緯90度の地点。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ
(→)南極海に同じ。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥
①(→)南極星のこと。
②(→)寿老人じゅろうじんの異称。
⇒なん‐きょく【南極】
なん‐きん【軟禁】
監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。
ナンキン【南京】
①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。
②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。
③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。
④カボチャの異称。
⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】
⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】
⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
⇒ナンキン‐じけん【南京事件】
⇒ナンキン‐したみ【南京下見】
⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】
⇒ナンキン‐じょう【南京錠】
⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】
⇒ナンキン‐じん【南京人】
⇒ナンキン‐せん【南京銭】
⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
⇒ナンキン‐だま【南京玉】
⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】
⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
⇒ナンキン‐まい【南京米】
⇒ナンキン‐まめ【南京豆】
⇒ナンキン‐むし【南京虫】
⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】
⇒ナンキン‐やき【南京焼】
⇒ナンキン‐ろ【南京路】
ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ
中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐あやつり【南京操り】
(→)「糸操り」の異称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じけん【南京事件】
①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。
②南京大虐殺。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐したみ【南京下見】
下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。
ナンキンシャモ
撮影:小宮輝之
③天の南極。地軸が天球と交わる南端。
④磁石の南方を指す極。指南極。S極。
⑤地磁気の南の極。南磁極。
⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
⇒なんきょく‐かい【南極海】
⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】
⇒なんきょく‐きだん【南極気団】
⇒なんきょく‐けん【南極圏】
⇒なんきょく‐しゅう【南極州】
⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】
⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】
⇒なんきょく‐せい【南極星】
⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】
⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】
⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】
⇒なんきょく‐てん【南極点】
⇒なんきょく‐よう【南極洋】
⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】
なん‐きょく【難曲】
演奏するのに高度の技術を要する楽曲。
なん‐きょく【難局】
処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」
なん‐ぎょく【軟玉】
玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。
なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】
オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かい【南極海】
南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥
国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐きだん【南極気団】
南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐けん【南極圏】
地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ
南極大陸および付近の島々の称。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥
南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥
南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。
→文献資料[南極条約]
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐せい【南極星】
竜骨座の首星カノープスの漢名。中国古代の天文説で、人の寿命をつかさどるとされる。また、あらわれれば治安、あらわれなければ戦乱があるという。老人星。南極老人。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たいりく【南極大陸】
南極を中心とする広大な大陸。ニュー‐ジーランド南方のロス海と大西洋南方のウェッデル海の湾入により、東大陸と西大陸とに分けられる。東大陸は古期の岩石より成るアフリカ式高原、西大陸は南米大陸より続く若い褶曲山脈で、大陸氷が海にまでのびる。気候寒冷で、永住的な居住者はなく、各国の観測基地がある。陸上および周辺の動物はペンギン・アザラシ・鯨など、植物は地衣類のほかは生育しない。推定面積1360万平方キロメートル。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐たんけん【南極探検】
南極大陸の調査・研究を目的とする探検。1772〜75年のイギリス人クックの探検航海を最初とし、1911年12月ノルウェー人アムンゼン、12年1月イギリス人スコットが南極点に到達。同年に日本人白瀬矗のぶ、また1929年より3回にわたりアメリカ人バードらが上陸探検を行なった。南極観測基地を起点とし、各国探検隊が相次いで極点に到達(日本隊は1968年)。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ちほう【南極地方】‥ハウ
南極収束線から南の海域と南極大陸および付近の島々の称。南極地域。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐てん【南極点】
地軸の南端。南緯90度の地点。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐よう【南極洋】‥ヤウ
(→)南極海に同じ。
⇒なん‐きょく【南極】
なんきょく‐ろうじん【南極老人】‥ラウ‥
①(→)南極星のこと。
②(→)寿老人じゅろうじんの異称。
⇒なん‐きょく【南極】
なん‐きん【軟禁】
監禁の程度のゆるいもの。身体の自由は束縛しないが、外部との一般的な接触は禁じあるいは制限し、行動の自由をある程度束縛するもの。
ナンキン【南京】
①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。
②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。
③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。
④カボチャの異称。
⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】
⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】
⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
⇒ナンキン‐じけん【南京事件】
⇒ナンキン‐したみ【南京下見】
⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】
⇒ナンキン‐じょう【南京錠】
⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】
⇒ナンキン‐じん【南京人】
⇒ナンキン‐せん【南京銭】
⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
⇒ナンキン‐だま【南京玉】
⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】
⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
⇒ナンキン‐まい【南京米】
⇒ナンキン‐まめ【南京豆】
⇒ナンキン‐むし【南京虫】
⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】
⇒ナンキン‐やき【南京焼】
⇒ナンキン‐ろ【南京路】
ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ
中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐あやつり【南京操り】
(→)「糸操り」の異称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】
広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じけん【南京事件】
①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。
②南京大虐殺。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐したみ【南京下見】
下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】
シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。
ナンキンシャモ
撮影:小宮輝之
 ⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じゅす【南京繻子】
経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ
巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥
阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じん【南京人】
昔、日本で中国人を呼んだ俗称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐せん【南京銭】
①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。
②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
中華門城壁爆破 1937年
提供:毎日新聞社
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じゅす【南京繻子】
経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ
巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥
阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐じん【南京人】
昔、日本で中国人を呼んだ俗称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐せん【南京銭】
①明代に南京付近で鋳造した私鋳銭で日本に輸入され、流通した銭貨。悪質の銭。→京銭きんせん。
②江戸末期、中国から横浜に輸入された中国製の粗悪な天保当百銭。→天保銭。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
中華門城壁爆破 1937年
提供:毎日新聞社
 ⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だま【南京玉】
陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ばと【南京鳩】
ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まい【南京米】
インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まめ【南京豆】
(→)落花生の別称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐むし【南京虫】
①(→)トコジラミの別称。
②俗に、小形の女性用金側腕時計。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐もめん【南京木綿】
帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐やき【南京焼】
江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ろ【南京路】
(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。
⇒ナンキン【南京】
なん‐く【難句】
①むずかしい句。わかりにくい文句。
②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」
なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】
岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。
なん‐くせ【難癖】
非難すべき点。欠点。
⇒難癖を付ける
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐だま【南京玉】
陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ねずみ【南京鼠】
ハツカネズミの飼養変種。かつて中国からもたらされたという。→舞鼠まいねずみ。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】
トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ばと【南京鳩】
ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ぶくろ【南京袋】
麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まい【南京米】
インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐まめ【南京豆】
(→)落花生の別称。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐むし【南京虫】
①(→)トコジラミの別称。
②俗に、小形の女性用金側腕時計。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐もめん【南京木綿】
帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐やき【南京焼】
江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。
⇒ナンキン【南京】
ナンキン‐ろ【南京路】
(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。
⇒ナンキン【南京】
なん‐く【難句】
①むずかしい句。わかりにくい文句。
②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」
なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】
岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。
なん‐くせ【難癖】
非難すべき点。欠点。
⇒難癖を付ける
みょう【名】ミヤウ🔗⭐🔉
みょう‐えつ【名謁】ミヤウ‥🔗⭐🔉
みょう‐えつ【名謁】ミヤウ‥
(→)名対面なだいめん1に同じ。
みょうぎしょう【名義抄】ミヤウ‥セウ🔗⭐🔉
みょうぎしょう【名義抄】ミヤウ‥セウ
(→)類聚るいじゅう名義抄の略称。
みょう‐ぎち【名吉】ミヤウ‥🔗⭐🔉
みょう‐ぎち【名吉】ミヤウ‥
(「名吉なよし」の音読)ボラまたはイナの異称。謡曲、河水「夕波に海豚も―参らんと」
めい‐あん【名案】🔗⭐🔉
めい‐あん【名案】
よい思いつき。「それは―だ」「―が浮かぶ」
めい‐い【名医】🔗⭐🔉
めい‐い【名医】
名高い医者。すぐれた医師。
めい‐えつ【名謁】🔗⭐🔉
めい‐えつ【名謁】
(→)名対面なだいめんに同じ。
めい‐えん【名園・名苑】‥ヱン🔗⭐🔉
めい‐えん【名園・名苑】‥ヱン
名高い庭園。すぐれた庭園。
めい‐えん【名演】🔗⭐🔉
めい‐えん【名演】
すばらしい演技・演奏。「しばし―に聞きほれる」
めい‐おう【名王】‥ワウ🔗⭐🔉
めい‐おう【名王】‥ワウ
名高い君主。すぐれた君主。
めい‐か【名花】‥クワ🔗⭐🔉
めい‐か【名花】‥クワ
名高く美しい花。美女の形容。
⇒めいか‐じゅうにかく【名花十二客】
⇒めいか‐じゅうゆう【名花十友】
めい‐か【名家】🔗⭐🔉
めい‐か【名家】
①名望のある家柄。名門。「地方の―」
②その道に秀でた人。名人。
③公卿くぎょうの家格の一つ。羽林家うりんけの下。文筆を主とし、大納言まで昇進できる家柄。日野・広橋・烏丸など。太平記13「或いは清華の家是を妬ねたみ、或いは―の輩是を猜そねんで」
④中国、春秋戦国時代の諸子百家の一つ。名(言葉)と実(実体)との関係を明らかにしようとする論理学派。公孫竜・恵施はその代表者。
めい‐か【名菓】‥クワ🔗⭐🔉
めい‐か【名菓】‥クワ
名のある菓子。すぐれた菓子。
めい‐か【名歌】🔗⭐🔉
めい‐か【名歌】
名高い歌。すぐれた歌。「古今の―」
めい‐が【名画】‥グワ🔗⭐🔉
めい‐が【名画】‥グワ
①名高い絵。すぐれた絵。「泰西―」
②有名な映画。すぐれた映画。「往年の―を上映する」
めいか‐じゅうにかく【名花十二客】‥クワジフ‥🔗⭐🔉
めいか‐じゅうにかく【名花十二客】‥クワジフ‥
(画題)宋の張景修が十二種の名花を選んで客になぞらえたもの。牡丹を貴客、梅を清客、菊を寿客、瑞香じんちょうげを佳客、丁香ちょうじを素客、蘭を幽客、蓮を静客、荼蘼どび(ときんいばら)を雅客、桂かつらを仙客、薔薇を野客、茉莉まつりを遠客、芍薬しゃくやくを近客とする。
⇒めい‐か【名花】
めいか‐じゅうゆう【名花十友】‥クワジフイウ🔗⭐🔉
めいか‐じゅうゆう【名花十友】‥クワジフイウ
(画題)宋の曾端伯が草木の花十種を選び、友になぞらえたもの。荼蘼どびを韻友、茉莉まつりを雅友、瑞香じんちょうげを殊友、荷花はすを浄友、桂かつらを仙友、海棠かいどうを名友、菊花を佳友、芍薬しゃくやくを艶友、梅を清友、梔子くちなしを禅友とする。茉莉・芍薬を省き、蘭(芳友)・蝋梅(奇友)を加える説もある。
⇒めい‐か【名花】
めい‐かん【名鑑】🔗⭐🔉
めい‐かん【名鑑】
人や物の名を集めて分類した名簿。人名録。
めい‐き【名器】🔗⭐🔉
めい‐き【名器】
名高い器物や楽器。すぐれた器物や楽器。「バイオリンの―」「茶道の―」
めい‐ぎ【名妓】🔗⭐🔉
めい‐ぎ【名妓】
有名な芸妓。すぐれた芸妓。
めい‐ぎ【名義】🔗⭐🔉
めい‐ぎ【名義】
①なまえ。名号。
②(→)名分めいぶんに同じ。
③表面上の名前。「―を借りる」「―上の所有者」「―書換え」
⇒めいぎ‐にん【名義人】
めいぎ‐にん【名義人】🔗⭐🔉
めいぎ‐にん【名義人】
公の書類などに正式に名前を表している人。名前人。
⇒めい‐ぎ【名義】
めい‐きょう【名教】‥ケウ🔗⭐🔉
めい‐きょう【名教】‥ケウ
人として守るべき道を明らかにする教え。儒教。
めい‐きょく【名局】🔗⭐🔉
めい‐きょく【名局】
囲碁や将棋で、後々まで語りつがれるような、すばらしい対局。
めい‐コンビ【名コンビ】🔗⭐🔉
めい‐コンビ【名コンビ】
すぐれた組合せ。よく息の合った二人組。
[漢]名🔗⭐🔉
名 字形
 筆順
筆順
 〔口部3画/6画/教育/4430・4C3E〕
〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉)
〔訓〕な・なづける
[意味]
①人のなまえ。事物のよびな。な。「姓名・命名・地名・社名・戒名かいみょう・名詞・名代みょうだい・名称」
②なづける。言いあらわす。「名状」
③名①が知られている。すぐれていて、なだかい。ほまれ。(うわべの)評判。「名物・名声・名士・著名・高名こうめい・こうみょう・虚名・有名無実・名存実亡」
④ミョウ「名田」の略。「名主・大名」
⑤人数を数える語。「若干名・数名」
[解字]
会意。「夕」+「口」。夕暮れの薄暗い中で自分の存在を告げる意。
[下ツキ
悪名・一名・異名・威名・英名・汚名・戒名・改名・学名・下名・家名・画名・雅名・仮名・記名・偽名・嬌名・驍名・虚名・御名・空名・刑名・芸名・件名・原名・功名・高名・合名・失名・実名・指名・氏名・綽名・襲名・醜名・唱名・小名・称名・署名・除名・人名・垂名・声名・姓名・盛名・俗名・賊名・尊名・大名・題名・地名・知名・著名・通名・唐名・同名・匿名・俳名・売名・筆名・美名・病名・仏名・武名・文名・別名・変名・法名・芳名・本名・無名・命名・訳名・唯名・勇名・有名・幼名・雷名・令名・連名・倭名・和名
[難読]
名残なごり
〔口部3画/6画/教育/4430・4C3E〕
〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉)
〔訓〕な・なづける
[意味]
①人のなまえ。事物のよびな。な。「姓名・命名・地名・社名・戒名かいみょう・名詞・名代みょうだい・名称」
②なづける。言いあらわす。「名状」
③名①が知られている。すぐれていて、なだかい。ほまれ。(うわべの)評判。「名物・名声・名士・著名・高名こうめい・こうみょう・虚名・有名無実・名存実亡」
④ミョウ「名田」の略。「名主・大名」
⑤人数を数える語。「若干名・数名」
[解字]
会意。「夕」+「口」。夕暮れの薄暗い中で自分の存在を告げる意。
[下ツキ
悪名・一名・異名・威名・英名・汚名・戒名・改名・学名・下名・家名・画名・雅名・仮名・記名・偽名・嬌名・驍名・虚名・御名・空名・刑名・芸名・件名・原名・功名・高名・合名・失名・実名・指名・氏名・綽名・襲名・醜名・唱名・小名・称名・署名・除名・人名・垂名・声名・姓名・盛名・俗名・賊名・尊名・大名・題名・地名・知名・著名・通名・唐名・同名・匿名・俳名・売名・筆名・美名・病名・仏名・武名・文名・別名・変名・法名・芳名・本名・無名・命名・訳名・唯名・勇名・有名・幼名・雷名・令名・連名・倭名・和名
[難読]
名残なごり
 筆順
筆順
 〔口部3画/6画/教育/4430・4C3E〕
〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉)
〔訓〕な・なづける
[意味]
①人のなまえ。事物のよびな。な。「姓名・命名・地名・社名・戒名かいみょう・名詞・名代みょうだい・名称」
②なづける。言いあらわす。「名状」
③名①が知られている。すぐれていて、なだかい。ほまれ。(うわべの)評判。「名物・名声・名士・著名・高名こうめい・こうみょう・虚名・有名無実・名存実亡」
④ミョウ「名田」の略。「名主・大名」
⑤人数を数える語。「若干名・数名」
[解字]
会意。「夕」+「口」。夕暮れの薄暗い中で自分の存在を告げる意。
[下ツキ
悪名・一名・異名・威名・英名・汚名・戒名・改名・学名・下名・家名・画名・雅名・仮名・記名・偽名・嬌名・驍名・虚名・御名・空名・刑名・芸名・件名・原名・功名・高名・合名・失名・実名・指名・氏名・綽名・襲名・醜名・唱名・小名・称名・署名・除名・人名・垂名・声名・姓名・盛名・俗名・賊名・尊名・大名・題名・地名・知名・著名・通名・唐名・同名・匿名・俳名・売名・筆名・美名・病名・仏名・武名・文名・別名・変名・法名・芳名・本名・無名・命名・訳名・唯名・勇名・有名・幼名・雷名・令名・連名・倭名・和名
[難読]
名残なごり
〔口部3画/6画/教育/4430・4C3E〕
〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉)
〔訓〕な・なづける
[意味]
①人のなまえ。事物のよびな。な。「姓名・命名・地名・社名・戒名かいみょう・名詞・名代みょうだい・名称」
②なづける。言いあらわす。「名状」
③名①が知られている。すぐれていて、なだかい。ほまれ。(うわべの)評判。「名物・名声・名士・著名・高名こうめい・こうみょう・虚名・有名無実・名存実亡」
④ミョウ「名田」の略。「名主・大名」
⑤人数を数える語。「若干名・数名」
[解字]
会意。「夕」+「口」。夕暮れの薄暗い中で自分の存在を告げる意。
[下ツキ
悪名・一名・異名・威名・英名・汚名・戒名・改名・学名・下名・家名・画名・雅名・仮名・記名・偽名・嬌名・驍名・虚名・御名・空名・刑名・芸名・件名・原名・功名・高名・合名・失名・実名・指名・氏名・綽名・襲名・醜名・唱名・小名・称名・署名・除名・人名・垂名・声名・姓名・盛名・俗名・賊名・尊名・大名・題名・地名・知名・著名・通名・唐名・同名・匿名・俳名・売名・筆名・美名・病名・仏名・武名・文名・別名・変名・法名・芳名・本名・無名・命名・訳名・唯名・勇名・有名・幼名・雷名・令名・連名・倭名・和名
[難読]
名残なごり
広辞苑に「名」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む