複数辞典一括検索+![]()
![]()
下 もと🔗⭐🔉
【下】
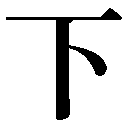 3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ
3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ /ゲ
/ゲ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
 {名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
 {名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
 {名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
 {名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
 {動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
 {動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
 {動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
 {動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
 {動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
 {助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
 {助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
 {形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
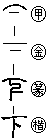 指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す)
指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す) 仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
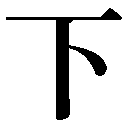 3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ
3画 一部 [一年]
区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA
《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと
《音読み》 カ /ゲ
/ゲ 〈xi
〈xi 〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす
《名付け》 し・じ・した・しも・もと
《意味》
 {名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」
 {名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」
 {名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」
 {名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕
 {動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」
 {動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」
 {動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕
 {動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」
 {動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」
 {助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」
 {助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」
 {形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」
〔国〕あらかじめすること。「下調べ」
《解字》
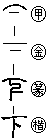 指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す)
指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。
《単語家族》
家カ(屋根をおおって下のものを隠す) 仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。
《類義》
→降
《異字同訓》
さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
乖 もとる🔗⭐🔉
【乖】
 8画 丿部
区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8
《音読み》 カイ(ク
8画 丿部
区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8
《音読み》 カイ(ク イ)
イ) /ケ
/ケ 〈gu
〈gu i〉
《訓読み》 そむく/もとる
《意味》
i〉
《訓読み》 そむく/もとる
《意味》
 {動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕
{動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕
 {動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕
{動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕
 {形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク
{形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク イチァオ」
《解字》
イチァオ」
《解字》
 会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。
《単語家族》
掛カイ(左右に振りわけてかける)
会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。
《単語家族》
掛カイ(左右に振りわけてかける) 畦ケイ(田畑をわけるあぜ道)
畦ケイ(田畑をわけるあぜ道) 劃カク(区切ってわける)などと同系。
《類義》
背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
劃カク(区切ってわける)などと同系。
《類義》
背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 丿部
区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8
《音読み》 カイ(ク
8画 丿部
区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8
《音読み》 カイ(ク イ)
イ) /ケ
/ケ 〈gu
〈gu i〉
《訓読み》 そむく/もとる
《意味》
i〉
《訓読み》 そむく/もとる
《意味》
 {動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕
{動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕
 {動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕
{動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕
 {形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク
{形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク イチァオ」
《解字》
イチァオ」
《解字》
 会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。
《単語家族》
掛カイ(左右に振りわけてかける)
会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。
《単語家族》
掛カイ(左右に振りわけてかける) 畦ケイ(田畑をわけるあぜ道)
畦ケイ(田畑をわけるあぜ道) 劃カク(区切ってわける)などと同系。
《類義》
背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
劃カク(区切ってわける)などと同系。
《類義》
背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
元 もと🔗⭐🔉
【元】
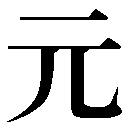 4画 儿部 [二年]
区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3
《常用音訓》ガン/ゲン/もと
《音読み》 ゲン
4画 儿部 [二年]
区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3
《常用音訓》ガン/ゲン/もと
《音読み》 ゲン /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) /ゴン
/ゴン 〈yu
〈yu n〉
《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと
《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと
《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし
《意味》
 {名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕
{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕
 「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕
「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕
 {名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」
{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」
 {名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」
{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」
 {形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」
{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」
 {名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」
{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」
 {名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。
{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。
 {単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。
《解字》
{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。
《解字》
 象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。
《単語家族》
頑ガン(まるい頭)と同系。
《類義》
→始・→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。
《単語家族》
頑ガン(まるい頭)と同系。
《類義》
→始・→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
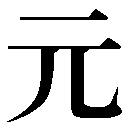 4画 儿部 [二年]
区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3
《常用音訓》ガン/ゲン/もと
《音読み》 ゲン
4画 儿部 [二年]
区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3
《常用音訓》ガン/ゲン/もと
《音読み》 ゲン /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) /ゴン
/ゴン 〈yu
〈yu n〉
《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと
《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし
《意味》
n〉
《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと
《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし
《意味》
 {名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕
{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕
 「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕
「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕
 {名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」
{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」
 {名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」
{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」
 {形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」
{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」
 {名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」
{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」
 {名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。
{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。
 {単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。
《解字》
{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。
《解字》
 象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。
《単語家族》
頑ガン(まるい頭)と同系。
《類義》
→始・→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。
《単語家族》
頑ガン(まるい頭)と同系。
《類義》
→始・→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
剌 もとる🔗⭐🔉
【剌】
 9画 リ部
区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F
《音読み》 ラツ
9画 リ部
区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F
《音読み》 ラツ /ラチ
/ラチ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)
《意味》
〉
《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)
《意味》
 {動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」
{動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」
 {動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。
{動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。
 「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。
《解字》
会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。
《単語家族》
戻レイ(もとる、はね返る)
「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。
《解字》
会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。
《単語家族》
戻レイ(もとる、はね返る) 辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する)
辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する) 瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 リ部
区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F
《音読み》 ラツ
9画 リ部
区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F
《音読み》 ラツ /ラチ
/ラチ 〈l
〈l 〉
《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)
《意味》
〉
《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)
《意味》
 {動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」
{動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」
 {動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。
{動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。
 「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。
《解字》
会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。
《単語家族》
戻レイ(もとる、はね返る)
「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。
《解字》
会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。
《単語家族》
戻レイ(もとる、はね返る) 辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する)
辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する) 瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
原 もと🔗⭐🔉
【原】
 10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン
10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン /ゴン
/ゴン /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) 〈yu
〈yu n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
 {名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
 {名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
 {名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
 {副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
 {動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
 {形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
 {動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
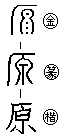 会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)
会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン
10画 厂部 [二年]
区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4
《常用音訓》ゲン/はら
《音読み》 ゲン /ゴン
/ゴン /ガン(グ
/ガン(グ ン)
ン) 〈yu
〈yu n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
n〉
《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす
《名付け》 おか・はじめ・はら・もと
《意味》
 {名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕
 {名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕
 {名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕
 {副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕
 {動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕
 {形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕
 {動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕
《解字》
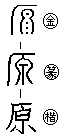 会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)
会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
《類義》
→始
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
固 もとより🔗⭐🔉
【固】
 8画 囗部 [四年]
区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5
《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める
《音読み》 コ
8画 囗部 [四年]
区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5
《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める
《音読み》 コ /ク
/ク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより
《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと
《意味》
〉
《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより
《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと
《意味》
 {形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕
{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕
 {副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕
{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕
 コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕
コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕
 {動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕
{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕
 {副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。
《単語家族》
枯(かたく乾いた木)
{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。
《単語家族》
枯(かたく乾いた木) 各(かたくつかえる石)
各(かたくつかえる石) 個(かたい物)などと同系。
《類義》
→堅
《異字同訓》
かたい。 →堅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
個(かたい物)などと同系。
《類義》
→堅
《異字同訓》
かたい。 →堅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 囗部 [四年]
区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5
《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める
《音読み》 コ
8画 囗部 [四年]
区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5
《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める
《音読み》 コ /ク
/ク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより
《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと
《意味》
〉
《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより
《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと
《意味》
 {形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕
{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕
 {副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕
{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕
 コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕
コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕
 {動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕
{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕
 {副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。
《単語家族》
枯(かたく乾いた木)
{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕
《解字》
会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。
《単語家族》
枯(かたく乾いた木) 各(かたくつかえる石)
各(かたくつかえる石) 個(かたい物)などと同系。
《類義》
→堅
《異字同訓》
かたい。 →堅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
個(かたい物)などと同系。
《類義》
→堅
《異字同訓》
かたい。 →堅
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
固然 モトヨリシカリ🔗⭐🔉
基 もと🔗⭐🔉
【基】
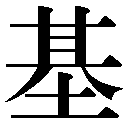 11画 土部 [五年]
区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE
《常用音訓》キ/もと/もとい
《音読み》 キ
11画 土部 [五年]
区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE
《常用音訓》キ/もと/もとい
《音読み》 キ /コ
/コ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく
《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい
《意味》
〉
《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく
《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい
《意味》
 {名}もとい(モト
{名}もとい(モト )。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」
)。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」
 {名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕
{名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕
 {動}もとづく。それをよりどころとする。
{動}もとづく。それをよりどころとする。
 {名}刃の四角いすき。
《解字》
会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其
《単語家族》
旗(四角いはた)
{名}刃の四角いすき。
《解字》
会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其
《単語家族》
旗(四角いはた) 碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。
《類義》
亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。
《異字同訓》
もと。 →下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。
《類義》
亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。
《異字同訓》
もと。 →下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
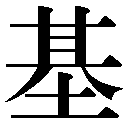 11画 土部 [五年]
区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE
《常用音訓》キ/もと/もとい
《音読み》 キ
11画 土部 [五年]
区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE
《常用音訓》キ/もと/もとい
《音読み》 キ /コ
/コ 〈j
〈j 〉
《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく
《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい
《意味》
〉
《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく
《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい
《意味》
 {名}もとい(モト
{名}もとい(モト )。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」
)。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」
 {名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕
{名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕
 {動}もとづく。それをよりどころとする。
{動}もとづく。それをよりどころとする。
 {名}刃の四角いすき。
《解字》
会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其
《単語家族》
旗(四角いはた)
{名}刃の四角いすき。
《解字》
会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其
《単語家族》
旗(四角いはた) 碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。
《類義》
亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。
《異字同訓》
もと。 →下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。
《類義》
亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。
《異字同訓》
もと。 →下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
報本反始 モトニムクイハジメニカエル🔗⭐🔉
【報本反始】
ホウホンハンシ・モトニムクイハジメニカエル〈故事〉天地の神や祖先の霊をまつり、それらの恩功にむくいること。〔→礼記〕
干 もとめる🔗⭐🔉
【干】
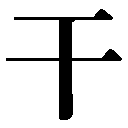 3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
 〈g
〈g n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
 {動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
 {動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
 {名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
 {名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
 {動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
 {動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
 カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
 {動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
 「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
 「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
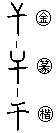 象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
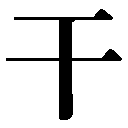 3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
 〈g
〈g n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
 {動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
 {動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
 {名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
 {名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
 {動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
 {動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
 カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
 {動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
 「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
 「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
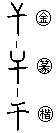 象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
弗 もとる🔗⭐🔉
【弗】
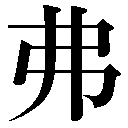 5画 弓部
区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4
《音読み》 フツ
5画 弓部
区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4
《音読み》 フツ /ホチ
/ホチ 〈f
〈f 〉
《訓読み》 ず/もとる/ドル
《意味》
〉
《訓読み》 ず/もとる/ドル
《意味》
 {副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕
{副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕
 {動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。
〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」
《解字》
{動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。
〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」
《解字》
 会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。
《単語家族》
拂(=払。左右に払いのける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。
《単語家族》
拂(=払。左右に払いのける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
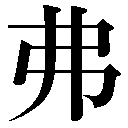 5画 弓部
区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4
《音読み》 フツ
5画 弓部
区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4
《音読み》 フツ /ホチ
/ホチ 〈f
〈f 〉
《訓読み》 ず/もとる/ドル
《意味》
〉
《訓読み》 ず/もとる/ドル
《意味》
 {副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕
{副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕
 {動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。
〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」
《解字》
{動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。
〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」
《解字》
 会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。
《単語家族》
拂(=払。左右に払いのける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。
《単語家族》
拂(=払。左右に払いのける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
征 もとめる🔗⭐🔉
【征】
 8画 彳部 [常用漢字]
区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA
《常用音訓》セイ
《音読み》 セイ
8画 彳部 [常用漢字]
区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA
《常用音訓》セイ
《音読み》 セイ /ショウ(シヤウ)
/ショウ(シヤウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる
《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく
《意味》
ng〉
《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる
《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく
《意味》
 {動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕
{動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕
 セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」
セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」
 セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕
セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕
 {名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。
{名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。
 {動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正
《単語家族》
挺テイ(まっすぐ)
{動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正
《単語家族》
挺テイ(まっすぐ) 整(まっすぐにする)と同系。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
整(まっすぐにする)と同系。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 彳部 [常用漢字]
区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA
《常用音訓》セイ
《音読み》 セイ
8画 彳部 [常用漢字]
区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA
《常用音訓》セイ
《音読み》 セイ /ショウ(シヤウ)
/ショウ(シヤウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる
《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく
《意味》
ng〉
《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる
《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく
《意味》
 {動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕
{動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕
 セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」
セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」
 セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕
セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕
 {名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。
{名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。
 {動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正
《単語家族》
挺テイ(まっすぐ)
{動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正
《単語家族》
挺テイ(まっすぐ) 整(まっすぐにする)と同系。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
整(まっすぐにする)と同系。
《類義》
→往
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
很 もとる🔗⭐🔉
【很】
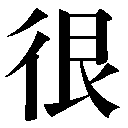 9画 彳部
区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B
《音読み》 コン
9画 彳部
区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B
《音読み》 コン /ゴン
/ゴン 〈h
〈h n〉
《訓読み》 もとる
《意味》
n〉
《訓読み》 もとる
《意味》
 {動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕
{動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕
 コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」
コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」
 {副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。
《単語家族》
根(ひと所にねを下ろして動かない木のね)
{副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。
《単語家族》
根(ひと所にねを下ろして動かない木のね) 恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
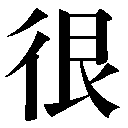 9画 彳部
区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B
《音読み》 コン
9画 彳部
区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B
《音読み》 コン /ゴン
/ゴン 〈h
〈h n〉
《訓読み》 もとる
《意味》
n〉
《訓読み》 もとる
《意味》
 {動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕
{動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕
 コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」
コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」
 {副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。
《単語家族》
根(ひと所にねを下ろして動かない木のね)
{副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。
《単語家族》
根(ひと所にねを下ろして動かない木のね) 恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
徴 もとめる🔗⭐🔉
【徴】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 彳部 [常用漢字]
区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5
《常用音訓》チョウ
《音読み》
14画 彳部 [常用漢字]
区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5
《常用音訓》チョウ
《音読み》  チョウ
チョウ
 〈zh
〈zh ng〉/
ng〉/ チ
チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし
《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし
《意味》
〉
《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし
《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし
《意味》

 チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕
チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕
 チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕
チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕
 チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕
チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕
 {動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕
{動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕
 {名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」
{名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」
 {名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。
《解字》
会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。
《単語家族》
チョウは登
{名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。
《解字》
会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。
《単語家族》
チョウは登 昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 14画 彳部 [常用漢字]
区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5
《常用音訓》チョウ
《音読み》
14画 彳部 [常用漢字]
区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5
《常用音訓》チョウ
《音読み》  チョウ
チョウ
 〈zh
〈zh ng〉/
ng〉/ チ
チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし
《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし
《意味》
〉
《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし
《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし
《意味》

 チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕
チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕
 チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕
チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕
 チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕
チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕
 {動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕
{動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕
 {名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」
{名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」
 {名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。
《解字》
会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。
《単語家族》
チョウは登
{名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。
《解字》
会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。
《単語家族》
チョウは登 昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
徼 もとめる🔗⭐🔉
【徼】
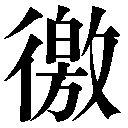 16画 彳部
区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74
《音読み》 キョウ(ケウ)
16画 彳部
区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74
《音読み》 キョウ(ケウ)
 /ギョウ(ゲウ)
/ギョウ(ゲウ) 〈ji
〈ji o・ji
o・ji o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)
《意味》
 {動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」
{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」
 キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕
キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕
 {動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」
{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」
 {動}出口をしぼって追いつめる。
{動}出口をしぼって追いつめる。
 {動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」
{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」
 {名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕
《解字》
形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。
《単語家族》
絞コウ(細く引き絞る)
{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕
《解字》
形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。
《単語家族》
絞コウ(細く引き絞る) 覈カク(締め上げて調べる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
覈カク(締め上げて調べる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
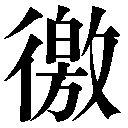 16画 彳部
区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74
《音読み》 キョウ(ケウ)
16画 彳部
区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74
《音読み》 キョウ(ケウ)
 /ギョウ(ゲウ)
/ギョウ(ゲウ) 〈ji
〈ji o・ji
o・ji o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)
《意味》
 {動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」
{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」
 キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕
キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕
 {動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」
{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」
 {動}出口をしぼって追いつめる。
{動}出口をしぼって追いつめる。
 {動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」
{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」
 {名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕
《解字》
形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。
《単語家族》
絞コウ(細く引き絞る)
{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕
《解字》
形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。
《単語家族》
絞コウ(細く引き絞る) 覈カク(締め上げて調べる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
覈カク(締め上げて調べる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
懋 もとめる🔗⭐🔉
【懋】
 17画 心部
区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA
《音読み》 ボウ
17画 心部
区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA
《音読み》 ボウ /ム/モ
/ム/モ 〈m
〈m o〉
《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる
《意味》
o〉
《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる
《意味》
 {動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕
{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕
 {動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」
{動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」
 {動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。
《解字》
会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。
《単語家族》
務
{動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。
《解字》
会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。
《単語家族》
務 貿
貿 謀(はかりもとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
謀(はかりもとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
 17画 心部
区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA
《音読み》 ボウ
17画 心部
区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA
《音読み》 ボウ /ム/モ
/ム/モ 〈m
〈m o〉
《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる
《意味》
o〉
《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる
《意味》
 {動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕
{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕
 {動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」
{動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」
 {動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。
《解字》
会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。
《単語家族》
務
{動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。
《解字》
会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。
《単語家族》
務 貿
貿 謀(はかりもとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
謀(はかりもとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
忤 もとる🔗⭐🔉
【忤】
 7画
7画  部
区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77
《音読み》 ゴ
部
区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77
《音読み》 ゴ /グ
/グ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる
《意味》
{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕
《解字》
会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。
《単語家族》
互ゴ(食い違う)
〉
《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる
《意味》
{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕
《解字》
会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。
《単語家族》
互ゴ(食い違う) 禦ギョ(抵抗して防ぐ)
禦ギョ(抵抗して防ぐ) 逆(さからう)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
逆(さからう)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画
7画  部
区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77
《音読み》 ゴ
部
区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77
《音読み》 ゴ /グ
/グ 〈w
〈w 〉
《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる
《意味》
{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕
《解字》
会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。
《単語家族》
互ゴ(食い違う)
〉
《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる
《意味》
{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕
《解字》
会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。
《単語家族》
互ゴ(食い違う) 禦ギョ(抵抗して防ぐ)
禦ギョ(抵抗して防ぐ) 逆(さからう)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
逆(さからう)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
悖 もとる🔗⭐🔉
【悖】
 10画
10画  部
区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1
《音読み》
部
区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1
《音読み》  ハイ
ハイ /バイ
/バイ 〈b
〈b i〉/
i〉/ ホツ
ホツ /ボチ/ボツ
/ボチ/ボツ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 もとる
《意味》
〉
《訓読み》 もとる
《意味》
 {動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕
{動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕
 {動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画
10画  部
区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1
《音読み》
部
区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1
《音読み》  ハイ
ハイ /バイ
/バイ 〈b
〈b i〉/
i〉/ ホツ
ホツ /ボチ/ボツ
/ボチ/ボツ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 もとる
《意味》
〉
《訓読み》 もとる
《意味》
 {動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕
{動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕
 {動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。
《解字》
会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
故 もと🔗⭐🔉
【故】
 9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ
9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ /ク
/ク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
 {名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
 {形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
 {名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
 {名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
 {名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
 {動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
 {名}ゆえ(ユ
{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
 {接続}ゆえに(ユ
{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
 「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
 {副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい)
{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ
9画 攴部 [五年]
区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC
《常用音訓》コ/ゆえ
《音読み》 コ /ク
/ク 〈g
〈g 〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに
《名付け》 ひさ・ふる・もと
《意味》
 {名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕
 {形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕
 {名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕
 {名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕
 {名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕
 {動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」
 {名}ゆえ(ユ
{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕
 {接続}ゆえに(ユ
{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕
 「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕
 {副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい)
{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕
〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」
《解字》
会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古
《単語家族》
固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
個(かたまった物体)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
旧 もと🔗⭐🔉
【旧】
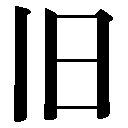 5画 日部 [五年]
区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C
【舊】旧字旧字
5画 日部 [五年]
区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C
【舊】旧字旧字
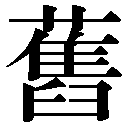 17画 艸部
区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470
《常用音訓》キュウ
《音読み》 キュウ(キウ)
17画 艸部
区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470
《常用音訓》キュウ
《音読み》 キュウ(キウ) /グ
/グ /ク
/ク 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)
《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)
《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと
《意味》
 {形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕
{形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕
 {名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」
{名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」
 {名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕
〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」
《解字》
形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった)
{名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕
〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」
《解字》
形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった) 朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。
《類義》
→古
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。
《類義》
→古
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
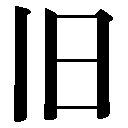 5画 日部 [五年]
区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C
【舊】旧字旧字
5画 日部 [五年]
区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C
【舊】旧字旧字
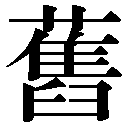 17画 艸部
区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470
《常用音訓》キュウ
《音読み》 キュウ(キウ)
17画 艸部
区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470
《常用音訓》キュウ
《音読み》 キュウ(キウ) /グ
/グ /ク
/ク 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)
《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと
《意味》
〉
《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)
《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと
《意味》
 {形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕
{形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕
 {名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」
{名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」
 {名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕
〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」
《解字》
形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった)
{名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕
〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」
《解字》
形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった) 朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。
《類義》
→古
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。
《類義》
→古
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
本 もと🔗⭐🔉
【本】
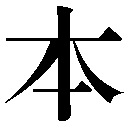 5画 木部 [一年]
区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B
《常用音訓》ホン/もと
《音読み》 ホン
5画 木部 [一年]
区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B
《常用音訓》ホン/もと
《音読み》 ホン
 〈b
〈b n〉
《訓読み》 もと/はじめ
《名付け》 なり・はじめ・もと
《意味》
n〉
《訓読み》 もと/はじめ
《名付け》 なり・はじめ・もと
《意味》
 {名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕
{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕
 {名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」
{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」
 {名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」
{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」
 {形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」
{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」
 {形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」
{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」
 {副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」
{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」
 {単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。
{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。
 {名}上奏文。「題本(上奏文)」
{名}上奏文。「題本(上奏文)」
 {名}書物。「善本」
《解字》
指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。
《単語家族》
笨ホン(太い竹)
{名}書物。「善本」
《解字》
指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。
《単語家族》
笨ホン(太い竹) 墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。
《類義》
→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。
《類義》
→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
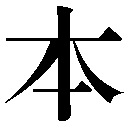 5画 木部 [一年]
区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B
《常用音訓》ホン/もと
《音読み》 ホン
5画 木部 [一年]
区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B
《常用音訓》ホン/もと
《音読み》 ホン
 〈b
〈b n〉
《訓読み》 もと/はじめ
《名付け》 なり・はじめ・もと
《意味》
n〉
《訓読み》 もと/はじめ
《名付け》 なり・はじめ・もと
《意味》
 {名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕
{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕
 {名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」
{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」
 {名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」
{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」
 {形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」
{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」
 {形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」
{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」
 {副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」
{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」
 {単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。
{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。
 {名}上奏文。「題本(上奏文)」
{名}上奏文。「題本(上奏文)」
 {名}書物。「善本」
《解字》
指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。
《単語家族》
笨ホン(太い竹)
{名}書物。「善本」
《解字》
指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。
《単語家族》
笨ホン(太い竹) 墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。
《類義》
→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。
《類義》
→基
《異字同訓》
もと。→下
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
本立而道生 モトタチテミチショウズ🔗⭐🔉
【本立而道生】
モトタチテミチショウズ〈故事〉物事の根本が定まってはじめて、実行のしかたが生ずる。〔→論語〕
模搨 モトウ🔗⭐🔉
【模拓】
モタク =摸拓。石碑などに書かれた文字を紙に写すこと。『模搨モトウ』
求 もとめる🔗⭐🔉
【求】
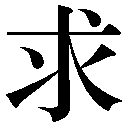 7画 水部 [四年]
区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81
《常用音訓》キュウ/もと…める
《音読み》 キュウ(キウ)
7画 水部 [四年]
区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81
《常用音訓》キュウ/もと…める
《音読み》 キュウ(キウ) /グ
/グ 〈qi
〈qi 〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)
《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす
《意味》
〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)
《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす
《意味》
 {動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕
{動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕
 {動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」
〔国〕もとめる(モトム)。買う。
《解字》
{動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」
〔国〕もとめる(モトム)。買う。
《解字》
 象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。
《単語家族》
糾キュウ(引き締める)
象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。
《単語家族》
糾キュウ(引き締める) 救キュウ(引き止める)
救キュウ(引き止める) 球(中心に引き締まった形のたま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
球(中心に引き締まった形のたま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
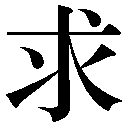 7画 水部 [四年]
区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81
《常用音訓》キュウ/もと…める
《音読み》 キュウ(キウ)
7画 水部 [四年]
区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81
《常用音訓》キュウ/もと…める
《音読み》 キュウ(キウ) /グ
/グ 〈qi
〈qi 〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)
《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす
《意味》
〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)
《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす
《意味》
 {動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕
{動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕
 {動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」
〔国〕もとめる(モトム)。買う。
《解字》
{動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」
〔国〕もとめる(モトム)。買う。
《解字》
 象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。
《単語家族》
糾キュウ(引き締める)
象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。
《単語家族》
糾キュウ(引き締める) 救キュウ(引き止める)
救キュウ(引き止める) 球(中心に引き締まった形のたま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
球(中心に引き締まった形のたま)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
牟 もとめる🔗⭐🔉
索 もとめる🔗⭐🔉
【索】
 10画 糸部 [常用漢字]
区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5
《常用音訓》サク
《音読み》 サク
10画 糸部 [常用漢字]
区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5
《常用音訓》サク
《音読み》 サク
 /シャク
/シャク 〈su
〈su 〉
《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)
《名付け》 もと
《意味》
〉
《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)
《名付け》 もと
《意味》
 {名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」
{名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」
 {名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」
{名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」
 {動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
{動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
 {動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕
{動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕
 {動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」
{動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」
 〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。
《解字》
〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。
《解字》
 会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。
《単語家族》
素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。
《類義》
縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。
《単語家族》
素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。
《類義》
縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 糸部 [常用漢字]
区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5
《常用音訓》サク
《音読み》 サク
10画 糸部 [常用漢字]
区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5
《常用音訓》サク
《音読み》 サク
 /シャク
/シャク 〈su
〈su 〉
《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)
《名付け》 もと
《意味》
〉
《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)
《名付け》 もと
《意味》
 {名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」
{名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」
 {名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」
{名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」
 {動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
{動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕
 {動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕
{動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕
 {動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」
{動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」
 〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。
《解字》
〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。
《解字》
 会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。
《単語家族》
素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。
《類義》
縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。
《単語家族》
素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。
《類義》
縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
素 もと🔗⭐🔉
【素】
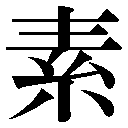 10画 糸部 [五年]
区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166
《常用音訓》ス/ソ
《音読み》 ソ
10画 糸部 [五年]
区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166
《常用音訓》ス/ソ
《音読み》 ソ /ス
/ス 〈s
〈s 〉
《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく
《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく
《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと
《意味》
 {名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。
{名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。
 {名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」
{名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」
 {名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」
{名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」
 {形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕
{形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕
 {名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」
{名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」
 {形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」
{形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」
 {副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
{副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
 ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕
ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕
 {名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」
〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」
《解字》
{名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」
〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」
《解字》
 会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。
《単語家族》
疏ソ(一つずつ離れる)
会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。
《単語家族》
疏ソ(一つずつ離れる) 索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
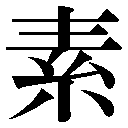 10画 糸部 [五年]
区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166
《常用音訓》ス/ソ
《音読み》 ソ
10画 糸部 [五年]
区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166
《常用音訓》ス/ソ
《音読み》 ソ /ス
/ス 〈s
〈s 〉
《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく
《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく
《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと
《意味》
 {名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。
{名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。
 {名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」
{名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」
 {名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」
{名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」
 {形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕
{形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕
 {名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」
{名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」
 {形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」
{形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」
 {副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
{副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕
 ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕
ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕
 {名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」
〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」
《解字》
{名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」
〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」
《解字》
 会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。
《単語家族》
疏ソ(一つずつ離れる)
会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。
《単語家族》
疏ソ(一つずつ離れる) 索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。
《類義》
→基
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
→主要人名
職 もとより🔗⭐🔉
【職】
 18画 耳部 [五年]
区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045
《常用音訓》ショク
《音読み》 ショク
18画 耳部 [五年]
区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045
《常用音訓》ショク
《音読み》 ショク /シキ
/シキ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより
《名付け》 つね・もと・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより
《名付け》 つね・もと・よし・より
《意味》
 {名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」
{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」
 {名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」
{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」
 {名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕
{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕
 {動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕
{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕
 ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」
《解字》
会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。
《単語家族》
幟シ(識別する目じるしの旗)
ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」
《解字》
会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。
《単語家族》
幟シ(識別する目じるしの旗) 識シキ(ことばでみわける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
識シキ(ことばでみわける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 18画 耳部 [五年]
区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045
《常用音訓》ショク
《音読み》 ショク
18画 耳部 [五年]
区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045
《常用音訓》ショク
《音読み》 ショク /シキ
/シキ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより
《名付け》 つね・もと・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより
《名付け》 つね・もと・よし・より
《意味》
 {名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」
{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」
 {名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」
{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」
 {名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕
{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕
 {動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕
{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕
 ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」
《解字》
会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。
《単語家族》
幟シ(識別する目じるしの旗)
ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」
《解字》
会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。
《単語家族》
幟シ(識別する目じるしの旗) 識シキ(ことばでみわける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
識シキ(ことばでみわける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
要 もとめる🔗⭐🔉
【要】
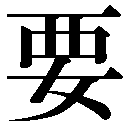 9画 襾部 [四年]
区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776
《常用音訓》ヨウ/い…る
《音読み》 ヨウ(エウ)
9画 襾部 [四年]
区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776
《常用音訓》ヨウ/い…る
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o・y
o・y o〉
《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ
《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす
《意味》
o〉
《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ
《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす
《意味》
 {名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」
{名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」
 {名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」
{名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」
 ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」
ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」
 {接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕
{接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕
 {動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕
{動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕
 ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕
ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕
 ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」
ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」
 〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」
〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」
 〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。
《解字》
〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。
《解字》
 会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。
《単語家族》
腰
会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。
《単語家族》
腰 竅キョウ(細くしまった穴)
竅キョウ(細くしまった穴) 約ヤク(しめくくる)などと同系。
《異字同訓》
いる。 →入
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
約ヤク(しめくくる)などと同系。
《異字同訓》
いる。 →入
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
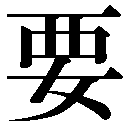 9画 襾部 [四年]
区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776
《常用音訓》ヨウ/い…る
《音読み》 ヨウ(エウ)
9画 襾部 [四年]
区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776
《常用音訓》ヨウ/い…る
《音読み》 ヨウ(エウ)
 〈y
〈y o・y
o・y o〉
《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ
《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす
《意味》
o〉
《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ
《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす
《意味》
 {名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」
{名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」
 {名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」
{名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」
 ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」
ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」
 {接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕
{接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕
 {動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕
{動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕
 ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕
ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕
 ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」
ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」
 〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」
〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」
 〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。
《解字》
〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。
《解字》
 会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。
《単語家族》
腰
会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。
《単語家族》
腰 竅キョウ(細くしまった穴)
竅キョウ(細くしまった穴) 約ヤク(しめくくる)などと同系。
《異字同訓》
いる。 →入
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
約ヤク(しめくくる)などと同系。
《異字同訓》
いる。 →入
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
覓 もとめる🔗⭐🔉
討 もとめる🔗⭐🔉
【討】
 10画 言部 [六年]
区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2
《常用音訓》トウ/う…つ
《音読み》 トウ(タウ)
10画 言部 [六年]
区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2
《常用音訓》トウ/う…つ
《音読み》 トウ(タウ)
 〈t
〈t o〉
《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)
《意味》
o〉
《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)
《意味》
 {動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕
{動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕
 {動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕
{動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕
 {動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」
《解字》
形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。
《単語家族》
搗トウ(すみずみまでつく)
{動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」
《解字》
形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。
《単語家族》
搗トウ(すみずみまでつく) 掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。
《類義》
伐は、武器で切ること。
《異字同訓》
うつ。 →打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。
《類義》
伐は、武器で切ること。
《異字同訓》
うつ。 →打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 10画 言部 [六年]
区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2
《常用音訓》トウ/う…つ
《音読み》 トウ(タウ)
10画 言部 [六年]
区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2
《常用音訓》トウ/う…つ
《音読み》 トウ(タウ)
 〈t
〈t o〉
《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)
《意味》
o〉
《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)
《意味》
 {動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕
{動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕
 {動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕
{動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕
 {動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」
《解字》
形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。
《単語家族》
搗トウ(すみずみまでつく)
{動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」
《解字》
形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。
《単語家族》
搗トウ(すみずみまでつく) 掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。
《類義》
伐は、武器で切ること。
《異字同訓》
うつ。 →打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。
《類義》
伐は、武器で切ること。
《異字同訓》
うつ。 →打
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
許 もと🔗⭐🔉
【許】
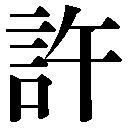 11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ
11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
 {動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
 {動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
 {名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
 {助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
 {名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
 {助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
 「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
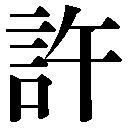 11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ
11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
 {動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
 {動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
 {名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
 {助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
 {名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
 {助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
 「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
謀 もとめる🔗⭐🔉
【謀】
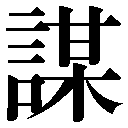 16画 言部 [常用漢字]
区点=4337 16進=4B45 シフトJIS=9664
《常用音訓》ボウ/ム/はか…る
《音読み》 ボウ
16画 言部 [常用漢字]
区点=4337 16進=4B45 シフトJIS=9664
《常用音訓》ボウ/ム/はか…る
《音読み》 ボウ /ム
/ム 〈m
〈m u〉
《訓読み》 はかる/はかりごと/もとめる(もとむ)
《名付け》 こと・のぶ・はかる
《意味》
u〉
《訓読み》 はかる/はかりごと/もとめる(もとむ)
《名付け》 こと・のぶ・はかる
《意味》
 {動・名}はかる。はかりごと。わからない先のことをどうするか考える。うつ手をさぐる。また、その計画。「共謀」「謀議」「謀於長者=長者ニ謀ル」〔→礼記〕
{動・名}はかる。はかりごと。わからない先のことをどうするか考える。うつ手をさぐる。また、その計画。「共謀」「謀議」「謀於長者=長者ニ謀ル」〔→礼記〕
 {動・名}はかる。はかりごと。悪事をたくらむ。また、害しようとたくらむ。たくらみ。「謀害」「謀反ボウハン」「陰謀」「謀晋故也=晋ヲ謀ルガ故ナリ」〔→左伝〕
{動・名}はかる。はかりごと。悪事をたくらむ。また、害しようとたくらむ。たくらみ。「謀害」「謀反ボウハン」「陰謀」「謀晋故也=晋ヲ謀ルガ故ナリ」〔→左伝〕
 {動}もとめる(モトム)。さぐりもとめる。「謀生=生ヲ謀ム」「謀面(いちど会いたいと望むこと)」
《解字》
会意兼形声。某ボウは、楳(=梅)の原字で、もと、うめのことであるが、暗くてよくわからない、の意に転用される。謀は「言+音符某」で、よくわからない先のことをことばで相談すること。
《単語家族》
煤バイ(黒くてよく見えないすす)
{動}もとめる(モトム)。さぐりもとめる。「謀生=生ヲ謀ム」「謀面(いちど会いたいと望むこと)」
《解字》
会意兼形声。某ボウは、楳(=梅)の原字で、もと、うめのことであるが、暗くてよくわからない、の意に転用される。謀は「言+音符某」で、よくわからない先のことをことばで相談すること。
《単語家族》
煤バイ(黒くてよく見えないすす) 媒バイ(よく知らない相手どうしをもとめる)などと同系。
《類義》
→計
《異字同訓》
はかる。 →図
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
媒バイ(よく知らない相手どうしをもとめる)などと同系。
《類義》
→計
《異字同訓》
はかる。 →図
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
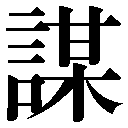 16画 言部 [常用漢字]
区点=4337 16進=4B45 シフトJIS=9664
《常用音訓》ボウ/ム/はか…る
《音読み》 ボウ
16画 言部 [常用漢字]
区点=4337 16進=4B45 シフトJIS=9664
《常用音訓》ボウ/ム/はか…る
《音読み》 ボウ /ム
/ム 〈m
〈m u〉
《訓読み》 はかる/はかりごと/もとめる(もとむ)
《名付け》 こと・のぶ・はかる
《意味》
u〉
《訓読み》 はかる/はかりごと/もとめる(もとむ)
《名付け》 こと・のぶ・はかる
《意味》
 {動・名}はかる。はかりごと。わからない先のことをどうするか考える。うつ手をさぐる。また、その計画。「共謀」「謀議」「謀於長者=長者ニ謀ル」〔→礼記〕
{動・名}はかる。はかりごと。わからない先のことをどうするか考える。うつ手をさぐる。また、その計画。「共謀」「謀議」「謀於長者=長者ニ謀ル」〔→礼記〕
 {動・名}はかる。はかりごと。悪事をたくらむ。また、害しようとたくらむ。たくらみ。「謀害」「謀反ボウハン」「陰謀」「謀晋故也=晋ヲ謀ルガ故ナリ」〔→左伝〕
{動・名}はかる。はかりごと。悪事をたくらむ。また、害しようとたくらむ。たくらみ。「謀害」「謀反ボウハン」「陰謀」「謀晋故也=晋ヲ謀ルガ故ナリ」〔→左伝〕
 {動}もとめる(モトム)。さぐりもとめる。「謀生=生ヲ謀ム」「謀面(いちど会いたいと望むこと)」
《解字》
会意兼形声。某ボウは、楳(=梅)の原字で、もと、うめのことであるが、暗くてよくわからない、の意に転用される。謀は「言+音符某」で、よくわからない先のことをことばで相談すること。
《単語家族》
煤バイ(黒くてよく見えないすす)
{動}もとめる(モトム)。さぐりもとめる。「謀生=生ヲ謀ム」「謀面(いちど会いたいと望むこと)」
《解字》
会意兼形声。某ボウは、楳(=梅)の原字で、もと、うめのことであるが、暗くてよくわからない、の意に転用される。謀は「言+音符某」で、よくわからない先のことをことばで相談すること。
《単語家族》
煤バイ(黒くてよく見えないすす) 媒バイ(よく知らない相手どうしをもとめる)などと同系。
《類義》
→計
《異字同訓》
はかる。 →図
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
媒バイ(よく知らない相手どうしをもとめる)などと同系。
《類義》
→計
《異字同訓》
はかる。 →図
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
貿 もとめる🔗⭐🔉
【貿】
 12画 貝部 [五年]
区点=4339 16進=4B47 シフトJIS=9666
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ
12画 貝部 [五年]
区点=4339 16進=4B47 シフトJIS=9666
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ /ム/モ
/ム/モ 〈m
〈m o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/あきなう(あきなふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/あきなう(あきなふ)
《意味》
 {形}もとめる(モトム)。あきなう(アキナフ)。金品を交換してもうけをもとめる。互いにとりひきして利益をはかる。また、金品を渡して品物を得る。「貿易」
{形}もとめる(モトム)。あきなう(アキナフ)。金品を交換してもうけをもとめる。互いにとりひきして利益をはかる。また、金品を渡して品物を得る。「貿易」
 {形}目がみえない。「貿然ボウゼン」「貿貿」
《解字》
会意兼形声。卯ボウは、むりに窓をこじあけて、中のものをもとめるさま。貿は「貝(財貨)+音符卯」で、相手の手のうちをむりにおしあけて、利益をもとめること。
《単語家族》
謀ボウ(もとめはかる)
{形}目がみえない。「貿然ボウゼン」「貿貿」
《解字》
会意兼形声。卯ボウは、むりに窓をこじあけて、中のものをもとめるさま。貿は「貝(財貨)+音符卯」で、相手の手のうちをむりにおしあけて、利益をもとめること。
《単語家族》
謀ボウ(もとめはかる) 冒ボウ(むりにもとめる)
冒ボウ(むりにもとめる) 務ム(むりをしてつとめる)などと同系。
《類義》
易エキは、とりかえること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
務ム(むりをしてつとめる)などと同系。
《類義》
易エキは、とりかえること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 12画 貝部 [五年]
区点=4339 16進=4B47 シフトJIS=9666
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ
12画 貝部 [五年]
区点=4339 16進=4B47 シフトJIS=9666
《常用音訓》ボウ
《音読み》 ボウ /ム/モ
/ム/モ 〈m
〈m o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/あきなう(あきなふ)
《意味》
o〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/あきなう(あきなふ)
《意味》
 {形}もとめる(モトム)。あきなう(アキナフ)。金品を交換してもうけをもとめる。互いにとりひきして利益をはかる。また、金品を渡して品物を得る。「貿易」
{形}もとめる(モトム)。あきなう(アキナフ)。金品を交換してもうけをもとめる。互いにとりひきして利益をはかる。また、金品を渡して品物を得る。「貿易」
 {形}目がみえない。「貿然ボウゼン」「貿貿」
《解字》
会意兼形声。卯ボウは、むりに窓をこじあけて、中のものをもとめるさま。貿は「貝(財貨)+音符卯」で、相手の手のうちをむりにおしあけて、利益をもとめること。
《単語家族》
謀ボウ(もとめはかる)
{形}目がみえない。「貿然ボウゼン」「貿貿」
《解字》
会意兼形声。卯ボウは、むりに窓をこじあけて、中のものをもとめるさま。貿は「貝(財貨)+音符卯」で、相手の手のうちをむりにおしあけて、利益をもとめること。
《単語家族》
謀ボウ(もとめはかる) 冒ボウ(むりにもとめる)
冒ボウ(むりにもとめる) 務ム(むりをしてつとめる)などと同系。
《類義》
易エキは、とりかえること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
務ム(むりをしてつとめる)などと同系。
《類義》
易エキは、とりかえること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
資 もと🔗⭐🔉
【資】
 13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
 {名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
 {名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
 {名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
 シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
 シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ)
シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ) 茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
13画 貝部 [五年]
区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
 〈z
〈z 〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
〉
《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる
《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より
《意味》
 {名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」
 {名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」
 {名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」
 シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕
 シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ)
シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕
《解字》
会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次
《単語家族》
姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ) 茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
質 もと🔗⭐🔉
【質】
 15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
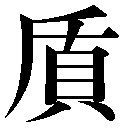 11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》
11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》  シツ
シツ /シチ
/シチ 〈zh
〈zh 〉/
〉/ チ
チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》

 {名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
 {名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
 {名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
 シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕
シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

 {名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
 チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ)
チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ) 緻チ(きめ細かくなかみがつまる)
緻チ(きめ細かくなかみがつまる) 室シツ(つまったへや)
室シツ(つまったへや) 窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
15画 貝部 [五年]
区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF
【貭】異体字異体字
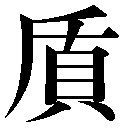 11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》
11画 貝部
区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2
《常用音訓》シチ/シツ/チ
《音読み》  シツ
シツ /シチ
/シチ 〈zh
〈zh 〉/
〉/ チ
チ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》
〉
《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす
《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと
《意味》

 {名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕
 {名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」
 {名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕
 シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕
シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

 {名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」
 チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ)
チス{動}人質にする。抵当に入れる。
《解字》
会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。
《単語家族》
実ジツ(なかみ) 緻チ(きめ細かくなかみがつまる)
緻チ(きめ細かくなかみがつまる) 室シツ(つまったへや)
室シツ(つまったへや) 窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
邀 もとめる🔗⭐🔉
【邀】
 17画
17画  部
区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1
《音読み》 ヨウ(
部
区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1
《音読み》 ヨウ( ウ)
ウ)
 〈y
〈y o〉/キョウ(ケウ)
o〉/キョウ(ケウ)
 《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)
《意味》
《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)
《意味》
 {動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕
{動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕
 {動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。
{動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。
 {動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。
《単語家族》
要(しめつける、もとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。
《単語家族》
要(しめつける、もとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 17画
17画  部
区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1
《音読み》 ヨウ(
部
区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1
《音読み》 ヨウ( ウ)
ウ)
 〈y
〈y o〉/キョウ(ケウ)
o〉/キョウ(ケウ)
 《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)
《意味》
《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)
《意味》
 {動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕
{動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕
 {動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。
{動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。
 {動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。
《単語家族》
要(しめつける、もとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。
《単語家族》
要(しめつける、もとめる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
雅 もとより🔗⭐🔉
【雅】
 13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》
13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》  ガ
ガ /ゲ
/ゲ 〈y
〈y 〉/
〉/ エ
エ /ア
/ア 〈y
〈y 〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》
〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》

 {形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
 {名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
 {名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
 {形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
 {名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
 {形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
 {副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
 {名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす)
{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす) 午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》
13画 隹部 [常用漢字]
区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB
《常用音訓》ガ
《音読み》  ガ
ガ /ゲ
/ゲ 〈y
〈y 〉/
〉/ エ
エ /ア
/ア 〈y
〈y 〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》
〉
《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす
《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと
《意味》

 {形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」
 {名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」
 {名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。
 {形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」
 {名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」
 {形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕
 {副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕
 {名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす)
{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。
《解字》
形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。
《単語家族》
御(ならす) 午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
需 もとめ🔗⭐🔉
【需】
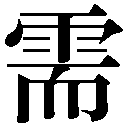 14画 雨部 [常用漢字]
区点=2891 16進=3C7B シフトJIS=8EF9
《常用音訓》ジュ
《音読み》 ジュ
14画 雨部 [常用漢字]
区点=2891 16進=3C7B シフトJIS=8EF9
《常用音訓》ジュ
《音読み》 ジュ /シュ
/シュ /ス
/ス 〈x
〈x 〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/もとめ/まつ/よわい(よわし)
《名付け》 まち・みつ・もと・もとむ・もとめ
《意味》
〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/もとめ/まつ/よわい(よわし)
《名付け》 まち・みつ・もと・もとむ・もとめ
《意味》
 {動}もとめる(モトム)。あれがあったらと、まちもとめる。また、あてにしてまつ。〈同義語〉→須。〈対語〉→給。「必需(=必須)」「需要」「相需=アヒ需ム」
{動}もとめる(モトム)。あれがあったらと、まちもとめる。また、あてにしてまつ。〈同義語〉→須。〈対語〉→給。「必需(=必須)」「需要」「相需=アヒ需ム」
 {名}もとめ。あてにしてまちもとめるもの。〈対語〉→給。「需給」「供需(もとめに応じて提供する)」
{名}もとめ。あてにしてまちもとめるもの。〈対語〉→給。「需給」「供需(もとめに応じて提供する)」
 {動}まつ。何かをあてにしてためらう。〈類義語〉→疑。「需事之下也=需ツハ事ノ下ナリ」〔→左伝〕
{動}まつ。何かをあてにしてためらう。〈類義語〉→疑。「需事之下也=需ツハ事ノ下ナリ」〔→左伝〕
 {名}周易の六十四卦カの一つ。乾下坎上ケンカカンショウの形で、下が強く表面が弱いことをあらわす。また、困難に出あって、むりをせず、好機をまつとの意を示す。
{名}周易の六十四卦カの一つ。乾下坎上ケンカカンショウの形で、下が強く表面が弱いことをあらわす。また、困難に出あって、むりをせず、好機をまつとの意を示す。
 {形}よわい(ヨワシ)。しっとりとして柔らかい。▽儒ジュ(柔弱)や懦ダ(しぶる)に当てた用法。「其需弱者来使=ソノ需弱ナル者来使ス」〔→国策〕
{形}よわい(ヨワシ)。しっとりとして柔らかい。▽儒ジュ(柔弱)や懦ダ(しぶる)に当てた用法。「其需弱者来使=ソノ需弱ナル者来使ス」〔→国策〕
 {形}しっとりぬれて、動きがにぶるさま。▽濡ジュに当てた用法。
《解字》
会意。而は、柔らかなひげ(または、ひも)の垂れたさまを描いた象形文字。需は「雨+而(柔らか)」で、雨水にしっとりぬれて柔らかくなり、動きがにぶること。しっとりとぬれて動かず、何かをあてにしてまつ意。
《単語家族》
濡(ぬれる)
{形}しっとりぬれて、動きがにぶるさま。▽濡ジュに当てた用法。
《解字》
会意。而は、柔らかなひげ(または、ひも)の垂れたさまを描いた象形文字。需は「雨+而(柔らか)」で、雨水にしっとりぬれて柔らかくなり、動きがにぶること。しっとりとぬれて動かず、何かをあてにしてまつ意。
《単語家族》
濡(ぬれる) 襦ジュ(柔らかい下着)
襦ジュ(柔らかい下着) 孺ジュ(からだの柔らかい子ども)などと同系。また、須シュ(柔らかいひげ)とまったく同じことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
孺ジュ(からだの柔らかい子ども)などと同系。また、須シュ(柔らかいひげ)とまったく同じことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
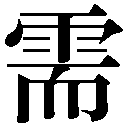 14画 雨部 [常用漢字]
区点=2891 16進=3C7B シフトJIS=8EF9
《常用音訓》ジュ
《音読み》 ジュ
14画 雨部 [常用漢字]
区点=2891 16進=3C7B シフトJIS=8EF9
《常用音訓》ジュ
《音読み》 ジュ /シュ
/シュ /ス
/ス 〈x
〈x 〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/もとめ/まつ/よわい(よわし)
《名付け》 まち・みつ・もと・もとむ・もとめ
《意味》
〉
《訓読み》 もとめる(もとむ)/もとめ/まつ/よわい(よわし)
《名付け》 まち・みつ・もと・もとむ・もとめ
《意味》
 {動}もとめる(モトム)。あれがあったらと、まちもとめる。また、あてにしてまつ。〈同義語〉→須。〈対語〉→給。「必需(=必須)」「需要」「相需=アヒ需ム」
{動}もとめる(モトム)。あれがあったらと、まちもとめる。また、あてにしてまつ。〈同義語〉→須。〈対語〉→給。「必需(=必須)」「需要」「相需=アヒ需ム」
 {名}もとめ。あてにしてまちもとめるもの。〈対語〉→給。「需給」「供需(もとめに応じて提供する)」
{名}もとめ。あてにしてまちもとめるもの。〈対語〉→給。「需給」「供需(もとめに応じて提供する)」
 {動}まつ。何かをあてにしてためらう。〈類義語〉→疑。「需事之下也=需ツハ事ノ下ナリ」〔→左伝〕
{動}まつ。何かをあてにしてためらう。〈類義語〉→疑。「需事之下也=需ツハ事ノ下ナリ」〔→左伝〕
 {名}周易の六十四卦カの一つ。乾下坎上ケンカカンショウの形で、下が強く表面が弱いことをあらわす。また、困難に出あって、むりをせず、好機をまつとの意を示す。
{名}周易の六十四卦カの一つ。乾下坎上ケンカカンショウの形で、下が強く表面が弱いことをあらわす。また、困難に出あって、むりをせず、好機をまつとの意を示す。
 {形}よわい(ヨワシ)。しっとりとして柔らかい。▽儒ジュ(柔弱)や懦ダ(しぶる)に当てた用法。「其需弱者来使=ソノ需弱ナル者来使ス」〔→国策〕
{形}よわい(ヨワシ)。しっとりとして柔らかい。▽儒ジュ(柔弱)や懦ダ(しぶる)に当てた用法。「其需弱者来使=ソノ需弱ナル者来使ス」〔→国策〕
 {形}しっとりぬれて、動きがにぶるさま。▽濡ジュに当てた用法。
《解字》
会意。而は、柔らかなひげ(または、ひも)の垂れたさまを描いた象形文字。需は「雨+而(柔らか)」で、雨水にしっとりぬれて柔らかくなり、動きがにぶること。しっとりとぬれて動かず、何かをあてにしてまつ意。
《単語家族》
濡(ぬれる)
{形}しっとりぬれて、動きがにぶるさま。▽濡ジュに当てた用法。
《解字》
会意。而は、柔らかなひげ(または、ひも)の垂れたさまを描いた象形文字。需は「雨+而(柔らか)」で、雨水にしっとりぬれて柔らかくなり、動きがにぶること。しっとりとぬれて動かず、何かをあてにしてまつ意。
《単語家族》
濡(ぬれる) 襦ジュ(柔らかい下着)
襦ジュ(柔らかい下着) 孺ジュ(からだの柔らかい子ども)などと同系。また、須シュ(柔らかいひげ)とまったく同じことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
孺ジュ(からだの柔らかい子ども)などと同系。また、須シュ(柔らかいひげ)とまったく同じことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
須 もとめ🔗⭐🔉
【須】
 12画 頁部 [人名漢字]
区点=3160 16進=3F5C シフトJIS=907B
《音読み》 シュ
12画 頁部 [人名漢字]
区点=3160 16進=3F5C シフトJIS=907B
《音読み》 シュ /ス
/ス 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ひげ/もちいる(もちゐる・もちふ)/もとめる(もとむ)/まつ/もとめ/すべからく…すべし
《名付け》 まつ・もち・もとむ
《意味》
〉
《訓読み》 ひげ/もちいる(もちゐる・もちふ)/もとめる(もとむ)/まつ/もとめ/すべからく…すべし
《名付け》 まつ・もち・もとむ
《意味》
 {名}ひげ。柔らかいひげ。とくに、あごひげ。〈同義語〉→鬚シュ。「竜須リュウシュ(竜のひげ)」「須髯シュゼン」
{名}ひげ。柔らかいひげ。とくに、あごひげ。〈同義語〉→鬚シュ。「竜須リュウシュ(竜のひげ)」「須髯シュゼン」
 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。もとめる(モトム)。他の何物かにたよろうとしてまちうける。ぜひ必要とする。ぜひにと期待する。〈類義語〉→需シュ/ジュ。「必須ヒッス/ヒッシュ」「急須キュウシュ(さし迫って必要とする。日本では急いで湯をわかすきゅうすのこと)」「何須…=ナンゾ…スルヲ須
ル・モチフ)。もとめる(モトム)。他の何物かにたよろうとしてまちうける。ぜひ必要とする。ぜひにと期待する。〈類義語〉→需シュ/ジュ。「必須ヒッス/ヒッシュ」「急須キュウシュ(さし迫って必要とする。日本では急いで湯をわかすきゅうすのこと)」「何須…=ナンゾ…スルヲ須 ンヤ」「不須…=…スルヲ須
ンヤ」「不須…=…スルヲ須 ズ」
ズ」
 {動}まつ。こちらが動かず、相手の動きをまち望む。その機会をまちうける。〈類義語〉→待。「須待シュタイ」「相須甚切=アヒ須ツコトハナハダ切ナリ」「須其成列而後撃之=ソノ列ヲ成スヲ須チテ後コレヲ撃ツ」〔→穀梁〕
{動}まつ。こちらが動かず、相手の動きをまち望む。その機会をまちうける。〈類義語〉→待。「須待シュタイ」「相須甚切=アヒ須ツコトハナハダ切ナリ」「須其成列而後撃之=ソノ列ヲ成スヲ須チテ後コレヲ撃ツ」〔→穀梁〕
 {名}もとめ。要求。需要。〈同義語〉→需。「不給使君須=使君ノ須ヲ給セズ」〔→李賀〕
{名}もとめ。要求。需要。〈同義語〉→需。「不給使君須=使君ノ須ヲ給セズ」〔→李賀〕
 {助動}すべからく…すべし。動詞の前につけ、ぜひ…する必要がある、の意をあらわす。「須知=須ラク知ルベシ」▽「応須」というかたちで用いたときは、「まさにすべからく…すべし」と読み、当然…する必要がある、の意。
{助動}すべからく…すべし。動詞の前につけ、ぜひ…する必要がある、の意をあらわす。「須知=須ラク知ルベシ」▽「応須」というかたちで用いたときは、「まさにすべからく…すべし」と読み、当然…する必要がある、の意。
 「須臾シュユ」とは、ほんの短い間、ごくわずかの時間がたって、の意。▽「須」は、細いひげ。「臾」は、細く抜き出すこと。いずれも細く小さいの意を含む。「不可須臾離也=須臾モ離ルベカラザルナリ」〔→中庸〕
《解字》
「須臾シュユ」とは、ほんの短い間、ごくわずかの時間がたって、の意。▽「須」は、細いひげ。「臾」は、細く抜き出すこと。いずれも細く小さいの意を含む。「不可須臾離也=須臾モ離ルベカラザルナリ」〔→中庸〕
《解字》
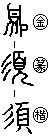 会意。もと、あごひげの垂れた老人を描いた象形文字。のち「彡(ひげ)+頁(あたま)」で、しっとりとしたひげのこと。柔らかくしめって、きびきびと動かぬ意から、しぶる、じっとたってまつの意となり、他者を頼りにして期待する、必要としてまちうけるなどの意となった。需も同じ経過をたどって必需の意となり、須と通用する。
《単語家族》
需(柔らかい)
会意。もと、あごひげの垂れた老人を描いた象形文字。のち「彡(ひげ)+頁(あたま)」で、しっとりとしたひげのこと。柔らかくしめって、きびきびと動かぬ意から、しぶる、じっとたってまつの意となり、他者を頼りにして期待する、必要としてまちうけるなどの意となった。需も同じ経過をたどって必需の意となり、須と通用する。
《単語家族》
需(柔らかい) 濡(しっとり)
濡(しっとり) 乳(ねっとり)などと同系。
《類義》
→可・→必・→胡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
乳(ねっとり)などと同系。
《類義》
→可・→必・→胡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 12画 頁部 [人名漢字]
区点=3160 16進=3F5C シフトJIS=907B
《音読み》 シュ
12画 頁部 [人名漢字]
区点=3160 16進=3F5C シフトJIS=907B
《音読み》 シュ /ス
/ス 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ひげ/もちいる(もちゐる・もちふ)/もとめる(もとむ)/まつ/もとめ/すべからく…すべし
《名付け》 まつ・もち・もとむ
《意味》
〉
《訓読み》 ひげ/もちいる(もちゐる・もちふ)/もとめる(もとむ)/まつ/もとめ/すべからく…すべし
《名付け》 まつ・もち・もとむ
《意味》
 {名}ひげ。柔らかいひげ。とくに、あごひげ。〈同義語〉→鬚シュ。「竜須リュウシュ(竜のひげ)」「須髯シュゼン」
{名}ひげ。柔らかいひげ。とくに、あごひげ。〈同義語〉→鬚シュ。「竜須リュウシュ(竜のひげ)」「須髯シュゼン」
 {動}もちいる(モチ
{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。もとめる(モトム)。他の何物かにたよろうとしてまちうける。ぜひ必要とする。ぜひにと期待する。〈類義語〉→需シュ/ジュ。「必須ヒッス/ヒッシュ」「急須キュウシュ(さし迫って必要とする。日本では急いで湯をわかすきゅうすのこと)」「何須…=ナンゾ…スルヲ須
ル・モチフ)。もとめる(モトム)。他の何物かにたよろうとしてまちうける。ぜひ必要とする。ぜひにと期待する。〈類義語〉→需シュ/ジュ。「必須ヒッス/ヒッシュ」「急須キュウシュ(さし迫って必要とする。日本では急いで湯をわかすきゅうすのこと)」「何須…=ナンゾ…スルヲ須 ンヤ」「不須…=…スルヲ須
ンヤ」「不須…=…スルヲ須 ズ」
ズ」
 {動}まつ。こちらが動かず、相手の動きをまち望む。その機会をまちうける。〈類義語〉→待。「須待シュタイ」「相須甚切=アヒ須ツコトハナハダ切ナリ」「須其成列而後撃之=ソノ列ヲ成スヲ須チテ後コレヲ撃ツ」〔→穀梁〕
{動}まつ。こちらが動かず、相手の動きをまち望む。その機会をまちうける。〈類義語〉→待。「須待シュタイ」「相須甚切=アヒ須ツコトハナハダ切ナリ」「須其成列而後撃之=ソノ列ヲ成スヲ須チテ後コレヲ撃ツ」〔→穀梁〕
 {名}もとめ。要求。需要。〈同義語〉→需。「不給使君須=使君ノ須ヲ給セズ」〔→李賀〕
{名}もとめ。要求。需要。〈同義語〉→需。「不給使君須=使君ノ須ヲ給セズ」〔→李賀〕
 {助動}すべからく…すべし。動詞の前につけ、ぜひ…する必要がある、の意をあらわす。「須知=須ラク知ルベシ」▽「応須」というかたちで用いたときは、「まさにすべからく…すべし」と読み、当然…する必要がある、の意。
{助動}すべからく…すべし。動詞の前につけ、ぜひ…する必要がある、の意をあらわす。「須知=須ラク知ルベシ」▽「応須」というかたちで用いたときは、「まさにすべからく…すべし」と読み、当然…する必要がある、の意。
 「須臾シュユ」とは、ほんの短い間、ごくわずかの時間がたって、の意。▽「須」は、細いひげ。「臾」は、細く抜き出すこと。いずれも細く小さいの意を含む。「不可須臾離也=須臾モ離ルベカラザルナリ」〔→中庸〕
《解字》
「須臾シュユ」とは、ほんの短い間、ごくわずかの時間がたって、の意。▽「須」は、細いひげ。「臾」は、細く抜き出すこと。いずれも細く小さいの意を含む。「不可須臾離也=須臾モ離ルベカラザルナリ」〔→中庸〕
《解字》
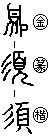 会意。もと、あごひげの垂れた老人を描いた象形文字。のち「彡(ひげ)+頁(あたま)」で、しっとりとしたひげのこと。柔らかくしめって、きびきびと動かぬ意から、しぶる、じっとたってまつの意となり、他者を頼りにして期待する、必要としてまちうけるなどの意となった。需も同じ経過をたどって必需の意となり、須と通用する。
《単語家族》
需(柔らかい)
会意。もと、あごひげの垂れた老人を描いた象形文字。のち「彡(ひげ)+頁(あたま)」で、しっとりとしたひげのこと。柔らかくしめって、きびきびと動かぬ意から、しぶる、じっとたってまつの意となり、他者を頼りにして期待する、必要としてまちうけるなどの意となった。需も同じ経過をたどって必需の意となり、須と通用する。
《単語家族》
需(柔らかい) 濡(しっとり)
濡(しっとり) 乳(ねっとり)などと同系。
《類義》
→可・→必・→胡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
乳(ねっとり)などと同系。
《類義》
→可・→必・→胡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
漢字源に「もと」で始まるの検索結果 1-43。もっと読み込む
 本来の姿・基本となるものなどにたちかえる。
本来の姿・基本となるものなどにたちかえる。 うまれ出たもとのもの、父母や天のことを思う。「人窮則反本=人窮スレバスナハチ本ニ反ル」〔
うまれ出たもとのもの、父母や天のことを思う。「人窮則反本=人窮スレバスナハチ本ニ反ル」〔 6画 牛部
区点=4422 16進=4C36 シフトJIS=96B4
《音読み》 ボウ
6画 牛部
区点=4422 16進=4C36 シフトJIS=96B4
《音読み》 ボウ 11画 見部
区点=7512 16進=6B2C シフトJIS=E64B
《音読み》 ベキ
11画 見部
区点=7512 16進=6B2C シフトJIS=E64B
《音読み》 ベキ 16画 髟部
区点=8201 16進=7221 シフトJIS=E99F
《音読み》
16画 髟部
区点=8201 16進=7221 シフトJIS=E99F
《音読み》